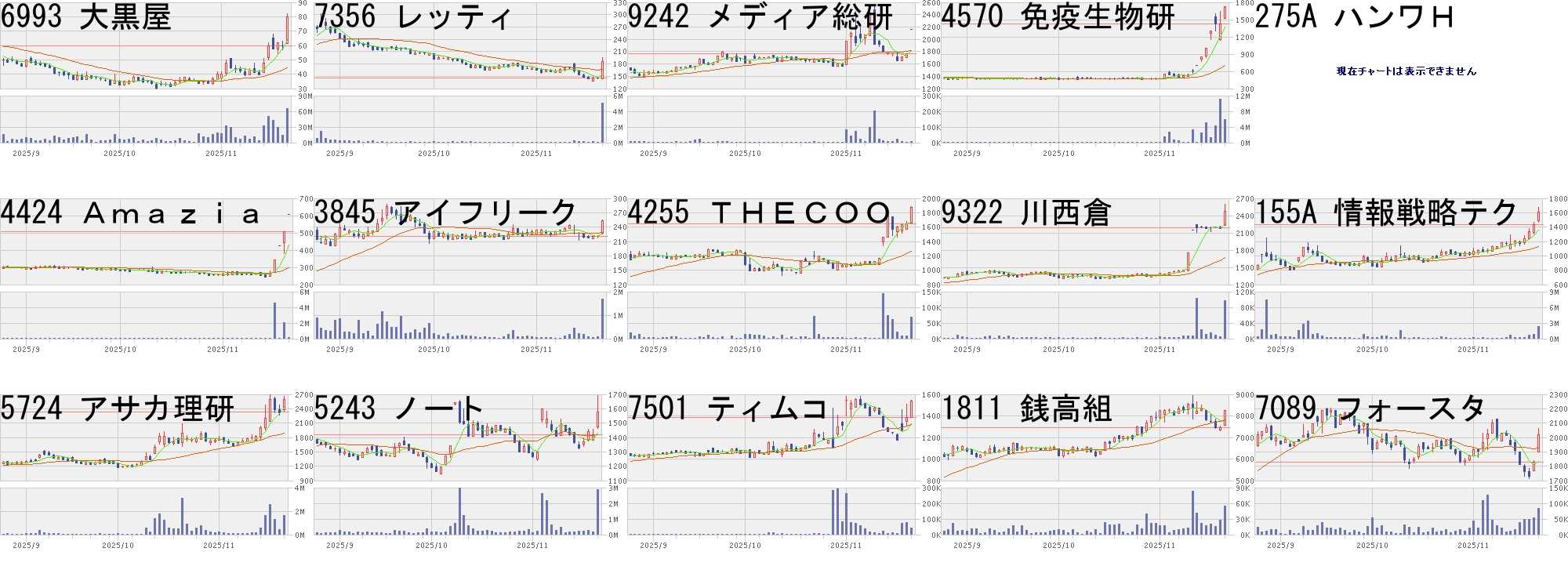2020年09月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-

サルコペニアⅥ まとめ
ホタテ塩焼き イカリング生きくらげ と しし唐のごま油炒め生まれて初めて生きくらげを食べた 「とろん」としてるね!言ったところ 洋子さんによれば「鮮度が落ちてるから」らしいまとめサルコペニア対策の必要性筋肉=細胞なのでサルコペニアを「細胞の量と質の低下」に言葉を入れ替える細胞レベルでエラーやミスが増え弱い生き物になるという事は、その生命は常に危険で有る十分な栄養=生命を保つための材料 が必須条件で有るのと同時に、備わった機能は惜しみなく使うという事が重要になる現場で見えるのは物理的な温度や重力など環境に対応できないだけでなく、生物として弱いものは他の生物、ウイルスや細菌などに侵食されるポイント①細胞数は色んな原因で減ってしまうが、細胞の質は年齢に関係なく維持向上ができる負荷がなく細胞分裂を繰り返すとストレスに弱くなった細胞に育つまた自ら動くとは重力に逆らうエネルギーが必要なこと、身体の働きは様々な物質が使われており不足すればトラブルになる多かれ少なかれサルコぺ二の症状は誰にも等しく起こりうり、物理的、化学的反応によって発症する生活習慣が大きく影響し、油断すれば老いとは関係なく衰えていく事になる人には、知識と技術で寿命を全うできる能力が有るのだから使えばよいだけの話なのだけれど、人の意思は弱い社会性や地域性で問題を共有し声を掛け合う環境が大切になるつまり、人々が少しでも意識する事から始まる②サルコペニア対策は比較的プラス効果が出やすい因果関係が複雑だという事は、他の問題にも共通し効率が良いと期待できる食事では意識を高め摂食機構を働かせ、必要量を取る事で胃腸を動かし排泄機構を働かせる睡眠機構を上手く働かせるにも体内物質が必要に応じて作用できる環境でないと乱れてしまう筋肉は骨の可動域に十分対応できるよう意識していれば柔軟性と強さが備わる脳は思考する意識が大切で「興味を持つ」「好奇心が強い」などが上げられるこれらには、人生観が大切だという事が見えてくる投げ出すか全うするか?人の発想は大きく割れてしまう病気やケガの後遺症は本人にも分かりやすいが、日常生活での運動不足で出来ないことが多くなる事で起きてしまうサルコペニアは自覚しにくいので、ある日「あれっ?」と思う事が多い年齢は一つの理由付けになるので、多くの人は老化だと勘違いしてしまい「もう、年だから」と思い込んでしまうその時、人生の残り時間を計算し「今さら」と思ってしまえば、衰えは加速する「命を全うし、生き抜く」と言う考え方が根底にないと「どうせ」とか「どうでも良い」と投げやりになる脳も含め細胞の質や体の仕組みは、バランスさえ取れていれば力を何とか発揮できる体内のバランスが崩れて問題が起きてしまう状態を病気と言う③もともと持っている能力を目覚めさせる使わないことでスキルを発揮できなくなっただけなので、使うことから始める単純で簡単な事が多く、手始めとして「まずは意識する」ことから始める例えば、麻痺の方でも改善できることは沢山あるのに「動かせない・役に立たない」と決めつけている場合が多い動かない手足だとしても体温が有り重さがあり「生きている」限り役割は有る能力とは、全く動けなかった赤ちゃんが動けるようになると言う根本的な事なので誰でもできる事になる支援介護やリハビリにおいて大切な発想になり、動かせない足でもしっかりと床を踏み、自身の一部として置き去りにしないように心がけるだけで違ってくる人は自らの意思を持ち細胞が元気になれるようコントロールできるなのでサルコペニアは何とかできる状態の一つ難病であるパーキンソン病も進行を抑える事ができるようになった現代何もしないと言う選択は無いと思えるが、絶望感や認知症状によって良い選択ができなくなってしまえば、その個体は弱体化が加速し自ら終止符を打つことになる
2020/09/23
コメント(0)
-

サルコペニアⅤ 家庭内介護 サルコペニアの対応
野菜で肉を食べる もちろん肉はフライパンで直焼きオクラとニラはボイル トマトと玉ねぎのスライスサルコペニアⅤ 家庭内介護 サルコペニアの対応Q「何をする?」 A,リセットするA1筋肉バランス縮んでいる筋肉のせいで伸ばされている筋肉の関係は支配と従属常習犯が脳の場合は本人にとっては無意識なので自己修正は非常に難しい筋肉の委縮の場合は、その筋肉の緊張をほぐす支援をするまず筋肉のバランス(働き)を均一にすると考え、縮みたがる筋肉には伸びてもらい、伸ばされている方には縮んでもらう重要ポイント1{今から何をするか}本人と脳に宣言する(自分で行う場合も) 2「一緒に動かす」つもりになってもらう全く動かないとしても「いいよ!いいねぇ!動かして」と声掛けをする言葉が理解できない場合は動かす部位を軽く叩くなど予動作を加える上手くできないと逆効果で更に緊張させ、噛みつかれたり抓られたりしてしまう硬直や委縮が強く補正や改善が難しい場合は、潔く寝てしまい重力との関係を変える事でリセットするA2可動域の確保{骨の異常がない場合}サルコペニアが進行すると可動に影響が出てくる筋肉だけでなく恐怖心や用心深さから動きを制御してしまう事も多い習慣化してしまうと劣化が始まる{それなりの筋肉の動きに収まってしまい、それなりの筋肉に置き換えられていく}①大きく動かす 関節が柔らかい これは口語で実際は筋肉が柔らかいか?例えば、「舌を大きく動かして」「指を大きく開いて」「肩を大きく回して」など関節に関わる小さな筋肉から、すべての筋肉を大きく動かすこれだけで筋力がつき、質が向上する②小さく動かす 可動制限が極端に強い場合関節が固い 実際は筋肉が固い(委縮や硬直など)関節が柔らかい場合も含め、自分で動かし始めて止まったところから1cm更に動かす他人が動かすときは、痛みが発生したところで一度止めて1mm更に動かす実際は、そんな微調整はできず、それ以上に動かしているこれを繰り返して可動範囲を広げていくと「簡単で楽に結果が出る」心理と脳へのアプローチが効果を上げる関節と筋肉の関係骨格筋の殆どは繊維の束が集まり筋膜で覆われている基本的にはゴムボールの様に変幻自在で、骨格に従って人を形作り、骨の可動域に制御されて二足歩行や座っての作業を可能にしている筋肉は骨がバラバラになったり擦れないよう接合し、接合部は繊維性が変わり腱と言われている筋肉が柔軟性を失うと動きが悪くなり、無理をすると痛みが発生する骨の可動域に沿った捻りの動作は食事や服の着脱、オシリを拭くなど人間独自の動きを可能にしている様々な場面においての身の交わし方も捻りが重要になる筋肉と筋肉の関係対の関係であり基本的には前後と左右で均衡を図っている筋肉の均衡とは同等の力ではなく働きによる関係で、どちらも柔軟性が重要になる例えば、屈伸運動で辛くなる場所は体が固いほど広範囲になる神経経路を含み筋肉は繋がっていて関連しているので影響を及ぼし合っている関節が一つの節目になって動作に現れてくるつまり、良いことも悪い事も連鎖するサルコペニアで考える場合、臓器も筋肉なので適度な運動は臓器の働きに影響することを忘れてはいけない関連痛支援介護では痛みの訴えが付き物だが、痛むんだから「そこが悪い」と言うのは通用しないと考えておく一般的な腰痛は腰が悪いのではなく多くは骨盤の歪みや首が原因更に範囲を広げると腕や足の指までに及ぶ丈夫な腰の筋肉を痛めることは滅多に無い大事件で、逆に原因も分かりやすい本当の悪い原因箇所は押さえないと分からないので自覚するのが難しい首が悪いのに違う場所の腰に出ている痛みを関連通と言うこの場合、首の状態を改善しなければ腰の痛みは永遠に続く臓器も同じく関連通で悪いところが分かり放散痛と言うつまり、悪いところとは別の場所に痛みが出ていると考える事が出来なければ沢山の事を見落としてしまう事になる上級編A3動作環境と柔軟性 捻り人の骨格は他動物より複雑な動きができるその骨格で人の形を保ち、自由に動かすのは筋肉服を着たり、靴を履いたり、料理を作ったり、物を操り、おしりを拭く筋肉のトラブルが重症化すれば、そう言ったことが出来なくなる柔軟だけではグニャグニャしてしまい強いだけではギクシャクして繊細な動きができない素早さ(反応速度)も緻密さも筋肉の質が悪いと発揮できない捻りを邪魔するもの首・肩・手首・腰・膝・足首など左右の傾きや前後の曲がり首では顎の突き出し肩が前に出ている・左右の上り下がり手首は手のひらをテーブルに返して親指がつかない腰は左右の上り下がり・骨盤の開きと立ち膝の曲がりと膝小僧の向き足首の曲がりと向き・指の浮き筋肉は繋がっていて影響し合うので単独で症状はでない捻ったまま、捻りが困難、返しが上手くできないなど動作に問題が起きてくる※捻りの改善は危険なので専門家に相談しアドバイスをしてもらう簡単にできること座る位置を変える座った時の足の置き方物の配置、位置や高さを変える例えば枕や、よく使うもの利き腕を使わない一日一回からOK筋力やバランス感覚があれば、ぶら下がりやその場での軽いジャンプは効果も効率も良い体力・心臓、呼吸系など問題、骨粗鬆症が有れば、最強なのは貧乏ゆすりや体の至る所をブラブラ揺するなど揺するときは拠点(支点)があって固定、揺らされる方は脱力しないとブラブラしない覚醒しているとき筋肉を意図的に弛緩させることは意外に難しいこの様な動作はサルコペニアや認知症で更に困難になるので目安になる筋肉に休日はない寝返りは物理的な悪影響から体を守るのに必要な動きで、健康体で有れば一晩で平均睡眠8時間辺りなら20回近く無意識で行われているつまり、20~30分に1回ペースで体を動かしている事になる筋肉を使う⇔弛緩させる スイッチのON/OFFが上手くできないと良い睡眠は取れない起きている時は尚更で、ON/OFFができないとストレスを溜めてしまう手を上げて背伸ばしをするのはOFFにする下準備と言える緊張・収縮で溜めた縮みストレスを伸ばして開放しリセットしている寝起きで行うと良いと言われるのは寝ている時も頻繁に体を動かしているからで、一日のスタートを筋肉目線でリセットしているこの時、異常が無ければ快感物質が働き脳は喜び、痛みなど問題が有れば不快物質の働きで脳は嫌がる
2020/09/08
コメント(0)
-

サルコペニア Ⅳ 家庭内介護 サルコペニアを見る
春菊をあんかけで食べるあんはカリフラワー、ニンジン、ブタ肉、玉ねぎ青空を見ると元気がでるサルコペニア Ⅳ 家庭内介護 サルコペニアを見る相手を心配し気使う心も、間違った見解をしてしまうと空振りになってしまう「要らぬ世話」や「有難迷惑」も含めて多少なりのエビデンスを持っておかないと相手も自分も傷つける事になるし怪我をすることも有るなので、相手を見たときに「どんな状態に有るのか?」感情抜きで分析できる{もう一人の自分}を持っておいた方が良い例えると「おかあさんに会いに行く」と決めた瞬間から始まっている同居なら朝起きた瞬間から母親のことを何かしら思うだろう大切なのは顔を見る直前までにリセットをする事認知バイアスを外して、ありのままを見て受け止めるこの作業は難しく、思い込みや勘違いを修正する事で過去を書き変えなければ出来ない自分が見てきた母親の像が変われば、家族関係を見直す必要も起きてくる「知らない方が良かった」と思ってしまう人は、主観的で現実をゆがめてしまう人かも知れないので自覚する機会になる母親で有る前に女性であり、女性で有る前に人間である最終的には、人間で有る前に動物であることを認め身体や心理状態を見るサルコペニアを見る Q & AQ1,家庭や施設では「何を見る?」 A、姿勢 頭の天辺から足の先までの位置関係A1寝ている どちらを向いていることが多いか?個体には癖が有り、癖は自覚できていないものが多く、脳が勝手に支持している仰向けでは膝を立てないと(折る)寝苦しいのは背中の筋肉が原因猫背や円パイでオシリが布団から浮いてしまうと重力で荷重され腰痛や息苦しさの原因になる肘を折りたたみ腕を内側にいれてしまう場合は柔軟運動をした方が良い最終的には肘を伸ばせなくなり、さらに進行すると手のひらを開けなくなる何もしていない状態なのに筋肉が固くなっているところが有れば、反射的な緊張が有るか筋委縮だと考えることができる進行に伴い痺れや痛みが走るようになると、寝返りも辛くなり起きるのも一苦労手伝うにも知識と技術がなければ、より痛い思いをさせるだけでなく骨折させることも有るA2座っている例えば、背もたれや肘置きを一日の大半使っているとかヘソが上を向いているようであれば、真っすぐ座っているのが辛いんだと脳が嫌がっている疲れたからヘソを上にして座ろうと考えた人は居ないはず少なくとも体幹筋、大胸筋、広背筋のバランスの問題や弱体化を見ていることになる首の筋肉は姿勢の悪さから視界を捉えるため頭の位置を確保しようとし余分なストレスを感じている慢性的な肩(首)コリや腰痛になると寝ていても目が覚める常に同じ方向に傾いたり、手や足を変な位置に置いていたり、そうさせている原因が有る大雑把に運動障害や筋肉バランスの崩れなどを捉えておくこれも本人には意味が分からず不安や恐怖を感じているつまり、本人には修正はできないし、いちいち意識しての体制ではないので、声掛けではイントネーションが大切になる「またか!」「行儀悪い」等と怒ったりするのは相手を闇雲に攻撃している事になるA3立っている体の折れや曲がり具合脳がバランス補正をするために取った苦肉の策を見ている事になる足の開きや床への吸い付きで安定感が分かるので歩き方と問題が分かるどこから始まっているか?は病歴や手術で見当が着く一か所で異変が起きると連鎖して大きく3か所が折れてくる(屈曲)首・腰・膝で骨盤を起こせなくなると立てなくなってしまう歩幅が狭くなる・踵が上がらくなる・視界が限られてくる・動きが遅くなる更にバランス感覚が悪くなると小走りするような歩き方になる左右の傾きは運動障害や筋肉バランスの問題脳は自分なりのバランス感覚で均衡を保とうとするので、奇妙な動作が物理的に間違っているとは言えないただ、常に事故のリスクが高く、速く動けず対応に遅れる負荷が片寄り局部浪費しているので故障の原因にもなる出来るだけ本来の体の仕組みと正しい姿勢に近づけていかないと、悪化してしまい手遅れになると元に戻れなくなってしまう※サルコペニアの症状は、難病パーキンソン病と同じ症状で、放っておけば同じように進行するなのでパーキンソン症候群と書かれる事が多い
2020/09/03
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1