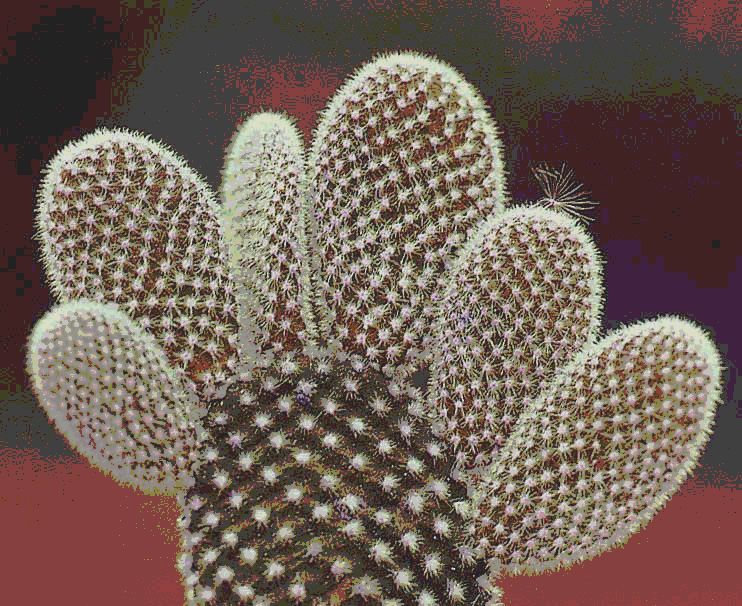テーマ: 短歌(1718)
カテゴリ: 游歌
♪ 泣きもせず笑いもせずに井の中を一歩も出ない自己顕示欲
本も読まず、自己を見つめる事もなく苦手なものを遠ざけて、感動も挫折も知らずに生きている。
人が笑えば気に入らず人が悲しめばざまあみろと、己の心の空洞を満たす素材は他人の不幸。
何をすればいいのか何をしなければいけないのかを考えようとはせず、ただ自分の存在を認めてほしいばっかりに不平・反論を並べ立てる。
人の心の痛みや悲しみにはまったく思いが至らず、ただ自分の満たされぬ心を知ってほしい気持ちばかりが先行する。それが分らぬ輩には敵対意識が増すばかり。
自立などとは程遠く甘えの中の自己欺瞞。都合の悪い事柄には眼をそらし、自己主張だけは怠らない。
1960年から70年代に活躍した寺山修司。
現代の青年達は「淡々として、平和で無事に生きてきわめて健康で、しかし友人も自己認識もなく(不安も恍惚感もなく)生きている」のだ。
「こんな時代の青年たちを、どうして私たちは仲間だと思うことが出来るだろうか?」「希望」という病気に罹るために、「冷淡な健康よりは、やさしい病弱さを」と。寺山は言う。
「目を醒まして、歌え・・・ドラマには終わりがあるが、人生には終わりがないのです」
青年が罹る病気にも罹ったという意識もなく(意識さえ持たず)、淡々と仕事に身を任せて気がつけば定年。仕事に逃げて自己をだまし続け、自分の居場所を仕事そのものの中にしか見出せない。
仕事がなくなることへの不安と焦燥感に苛まれ、それから逃れるために唯一時間をつぶせる釣行という名の逃避行。
それでもなを生きねばならない身を持て余し、家族のために働いた、自分を殺して働いたと、ただそれだけが勲章の日々。そんな私に誰がした、誰のおかげで生きてこられた誰のお陰で大きくなった、と自己犠牲を標榜する。
夢もなく希望も無く生きる意味も見いだせないまま、家族はどんどん前へ行く。取り残されていく疎外感。
無い無い尽くしのこの自分、誰もわかってくれないこの不幸。自分はこの世で一番に不幸な存在であると、ただただ悲嘆に暮れる毎日が過ぎてゆく。
これから先、まだまだ長い人生を無目的に生きることは、地獄に落ちるも同然の辛くて悲しいこと。青春時代に、「挫折と虚無と無頼と浪費」を体験せずに過ごしてきたクソまじめ人間に訪れた、人生の最後の空しい試練。
始めよければ終わり良し、終わりよければ全て良し。
如何に終わりを有意義に楽しいものにしていくか、そのことだけを考えて人の非難を顧みずただ生き抜いていく覚悟があるか。
あなたに残されたものは「人はどこから来て、どこへ向かうのか」ではなく、「自分とは一体何なのか」を問い続けること。
生きてきて良かったと思うための、自分自身の心に灯る「光明」を探すことだ。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[游歌] カテゴリの最新記事
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カレンダー
キーワードサーチ
▼キーワード検索
サイド自由欄
◆2006年5月8日よりスタートした「日歌」が千首を超えたのを機に、「游歌」とタイトルを変えて、2009年2月中旬より再スタートしました。
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
「アーカイブ」
◎ Ⅰ 短歌
◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編
◎ Ⅲ 興味深いこと
◎ Ⅳ 興味深いこと パート2
◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など
◆2011年1月2日からは、楽歌「TNK31」と改題しました。
◆2014年10月23日から「一日一首」と改題しました。
◆2016年5月8日より「気まぐれ短歌」と改題しました。
◆2017年10月10日より つれずれにつづる「みそひともじ」と心のさんぽに改題しました。
◆2019年6月6日より 「歌とこころと心のさんぽ」に改題しました。
★ 「ジグソーパズル」 自作短歌百選(2006年5月~2009年2月)
「アーカイブ」
◎ Ⅰ 短歌
◎ Ⅱ 知っていて損はない話 健康と生活編
◎ Ⅲ 興味深いこと
◎ Ⅳ 興味深いこと パート2
◎ Ⅴ 自然界 地球 異常気象など
コメント新着
© Rakuten Group, Inc.