2019年05月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

eラーニング講義『教師に求められる発達障害の理解と支援』2
eラーニング講義の続きを観ました。▼前回はこちら2時間以上続けて観ると、さすがに疲れました。自宅学習だと、時間がある時は連続で視聴することもできますが、やはり休憩は必要ですね。(^^;)今回は、小林玄(しずか)先生と、上野一彦先生。始語や始歩はおよそ1歳~1歳6ヶ月、というのは、以前習ったのですが、忘れていたので、もう1度覚え直します。特別支援教育の講義の中で一番ありがたく感じる内容は、具体的な事例。上野先生の講義では、LD(学習障害)の子どもが実際に通常学級の中で受けている支援例として、まずiPadで黒板を写し、次にそのiPadを見てノートに写している子を写真付きで示していただきました。上野先生は、実際に出会われた子どもたちの話を笑顔で話されるのが、とても素敵です。また、「障害と健常は連続する」「障害は特徴ある個性と考えるべき」という、大変重要なメッセージも話してくださいました。小林先生の講義では、「学力の指導」のところで、これも大変具体的な指導内容を教えていただきました。・○○○の言葉を1文字換えて別の言葉にする、等の音韻認識のトレーニング・単語カードと単語カードを並べて文を作る際に、間に入る助詞を選ばせる「統語」のトレーニング・意味のある言葉のまとまりを探す「ことばさがし」・教科書のテキストデータを使って、1つの単語が行をまたがらないように改行する 読み支援等々・・・。一番印象に残ったのは、漢字を覚える指導例で、「転」を、「車にムかって転ぶと危険!」というイラストで覚えるもの。車へんが、本当に車になっていたりなど、楽しいイラストで、インパクトがありました。
2019.05.26
コメント(0)
-

eラーニング講義『教師に求められる発達障害の理解と支援』1
5月のはじめのブログで、eラーニングのことを書きました。▼教員免許更新講習を eラーニングで受講する!せっかくなので、eラーニングの講義で学んだことを、こちらのブログに残していきたいと思います。本日が講義初視聴。一番のおめあてだった、上野一彦先生の発達障害についての講義から視聴。タイトルは、『教師に求められる発達障害の理解と支援』です。放送大学のときのビデオ講義とは違って、スライドも同時に映し出されるので大変分かりやすかったです。資料としてダウンロード資料(PDF)が示されていましたが、手元にダウンロードしておかなくても、同時上映されるので大丈夫でした。ただ、講義のウインドウの横にまだスペースがあるので、僕の場合は資料PDFを別ウインドウで開いて、講義の真横に平行して表示させました。そうすることで、今現在のスライド以外も表示させられるので、便利でした。1つの講義動画は、上野先生のUnit1が、20分弱。Unit2が30分弱。これぐらいの時間だと、忙しい中でもちょっとずつ見ていくことができそうです。僕は特別支援教育の勉強は今までしてきているので、知識としては知っていることは多かったですが、今までの知識を体系的に整理し直すことができました。Unit1「発達障害のある子供たちを取り巻く環境」で興味深かったのは、「障害分類」の国際比較です。アメリカの場合は、数の多い順(支援の多さ順)、イギリスの場合はニーズによる分類、というのが特徴的でした。日本の障害分類も今後変わっていきそうな可能性を感じました。Unit2「発達障害について」では、「脳は様々な情報のタンスのようなもの」という分かりやすい比喩のもと、LDやADHD、ASDについての定義をもう一度勉強し直すことができました。上野先生のご説明は本当におすすめで、ADHDの説明の場面でも、「ADHDをもつ子供の力」というのがいくつも示され、とても説得力がありました。弱みを強みとして理解するリフレーミングのしかたがとても素晴らしい、と感じました。▼『教師に求められる発達障害の理解と支援』(eラーニング講義) https://www.sainou.or.jp/e-learning/course_5.php
2019.05.25
コメント(0)
-

辻秀一『上達する人 長続きする人』
わが家には、本棚があちこちにあります。その中の一角が「とてもよかったので、いつかブログで紹介する本」の一角です。今日はそこから1冊取り出した、こちらの本を紹介します。『上達する人・長続きする人』(辻秀一、ヤマハミュージックメディア、2006,1400円)本のタイトルに「音楽を最高に楽しむためのセルフコーチ力」と副題がついています。しかし、音楽をやる人だけに限らない、かなり有効なやり方が具体的に書かれています。ちょっと紹介しますね。=============================『上達する人・長続きする人』 ・セロトニン系の喜びは 結果ではなく過程を大事にすることで生まれます。 「クリスマスプレゼント、あの人に何をあげたら喜ぶかなぁ」と考えているだけでセロトニンは発生しているのです。 (p27より)幸せホルモンと言われることもある、セロトニン。 こんなふうにカンタンに出すことができるのですね。 子どもの頃幸せだったのは、こんなふうに「こうなるかなあ、ああなるかなあ」とニヤニヤしていたことが多かったからかもしれません。 さあ、あなたも、今からニヤニヤしましょう!・暗い表情を意識的に明るい表情に変えることです。 口の端を上げることだけでも表情は変わりますよね。 感情は伴わなくても笑顔を作るのです。 そうすると脳が錯覚を起こします。 「あれ!? 楽しいのかな」と脳が錯覚することで身体にいい影響を与えるホルモンが出てくるのです。 (p46より)楽しくなくても、笑顔を作る。 そうすると、楽しくなる。 他の本でも何度も読んだのですが、忘れてました。(^^;) これを読んで、あわてて笑顔を作りました。 ちょうど楽しくなくなっていたときだったので、よかったです。・「今ヘタな自分だとしても、続けていくうちに曲の良さを味わうように演奏できて、その時の自分はまるでおいしいお料理を食べたときのようにシアワセな気持ちだろうな」といったセロトニン系の楽しみを味わっている自分像が描けたならどうでしょう? やんわりと気持ちが高揚してきますね。 (p74より)・3ヶ月後の自分のビジョンを何かひとつでも描ければいいのです。 (p75より)しなければいけないことがあったとして、今はそれが上手にできなかったとしても。 「3ヶ月後」「半年後」「1年後」 うまくいったときのこと、達成したときのこと、そういう状況をありありと思い描いて、楽しく取り組みたいものです。 いやいややるのか、楽しんでやるのか。 大きな、違いです。=============================音楽をやる人意外にも通用する本書ですが、音楽をやる人なら、よけいに当てはまることが書いてあると思います。本書の中には音楽に関係することがいっぱい出てきます。僕はこの本の「あなたが音楽をやっていて楽しいことは何ですか?」の質問のところに、いっぱい書き込みをしていました。そういった自分が答えた「楽しいこと」の中身を改めて読み返すだけでも、ワクワク・ニヤニヤの気持ちを取り戻すために役立つ気がします。
2019.05.20
コメント(0)
-

小学校市販テストの合理的配慮等(正進社のパンフレットより)
先週の土曜日に、民間教育サークルの特別支援教育セミナーに行ってきました。そこで配られた「正進社 教材カタログ 2019年度版」を見て、びっくり。発達障害の子どもたちなど、必要な子どもたちに向けた様々な工夫を取り入れて改善されていることが分かりました。小学校市販テストの合理的配慮については、以前に「ルビうちテスト」が増えてきたことなどを、このブログで書きました。▼業者テストの「ルビうち」が標準対応に! (2017年06月10日の日記)今は、さらにそのほかの工夫もどんどん導入されているんですね!「正進社 教材カタログ 2019年度版」から、少し紹介したいと思います。このカタログの中では「合理的配慮」という言葉が頻繁に使われていて、なんでもかんでも「合理的配慮」扱いになっているような気はしますが、それでも、こういった教材の工夫で救われる子どもたちもいると思うので、大変有意義なことだなーと思います。(1) マス目式解答欄解答文字数がはっきり分かるというのは、実はかなり大きな支援になります。( )という枠だと、思いっきり枠からはみ出してしまう子がいます。答えもその中に含んではいるんだけれど、どこまでが必要なのかの判断ができずに、長く書きすぎてしまうのです。(逆に、短く書きすぎてしまう子もいます。)そういった子どもたちに、このマス目式解答欄、とてもいいですね!(2)漢字採点シート漢字の採点基準が複数の先生でバラバラ・・・ということはわりとよくあることのように思います。「合理的配慮」という意味で、書字障害の子どもの漢字の採点で大目に見る、といったこともされています。この教師用付録の画期的なところは、文化庁の出している表を載せているところ。文化庁は、簡単に言うと、「これも、あれも、OK」ということを言っています。その漢字だと分かれば、トメ・ハネ等の細かいところで減点したり、間違いと見なす必要はないのです。ともあれ、新出漢字の指導の時には正しい書き方を細かく教えることが一般的であるため、そういった指導とテストの採点基準と、こういった文化庁指針のあいだで、ズレが生じるわけです。必ずしも文化庁指針のとおりに採点しなければならないわけではありませんが、そういった報告が出ていることをご存じない先生方も多数おられるわけで・・・正進社さんのこの指導資料は、先生方への情報提供という点でも、非常に有意義だと思います。▼常用漢字表の字体・字形に関する指針(報告)について - 文化庁なお、上のPDFの中でも、以下のような記載がされています。========================実際の教育現場では,使用する教科書や,それに基づく教材等に示された字形以外の字形は誤りとする評価が行われることがある。(略)「字体についての解説」についての理解そのものが十分に広がっておらず,その内容が知られないまま,指導した字形に沿った評価が行われる場合があるとの指摘もなされた。========================知られていない「字体についての解説」を教師に知らせる役割を教材会社が担ってくださるのは、ありがたいです。なお、この件については、マチポンブログさんの記事が、かなりわかりやすいので、よければ合わせてお読みください。▼文化庁指針(漢字のとめ・はねなど)への誤解と早とちり②(3)筆算方眼これも、支援を要するお子さんの場合、有効だと思います。筆算を練習させるノートには、マス目がありますものね。テストの時も、マス目があったほうが、いい。他社の業者テストでも、これは、見たことがあります。中学・高校と進んで行くにつれて、マス目なしでも書ける力は必要になってくる気もしますが。習いたての頃は、マス目ありで、いいんじゃないでしょうか。(4)フォーカス・テスト特別支援学級の学習指導では、問題が多すぎると、1枚あたりの問題数を少なくして、たくさんのプリントに分ける、といったことをされているところがわりとあります。これを業者がやってくれるとは、なかなかすごい。「全国学力学習状況調査」のように、問題が冊子になっていて複数のページに分かれていると対応できない、という子の場合にも、あらかじめこういう形式の問題をさせておくと、いい気がします。なお、この「フォーカス・テスト」については、LD学会でもポスター発表されたそうで、そのときの発表内容も記載されています。(4)QRコードで動画閲覧最近はQRコードをいろいろなところで見かけるようになってきました。こちらのパンフレットにもQRコードが載っていて、目的の動画をすぐに見ることができます。子どもたちにとっても、先生たちにとっても、有効な支援になると思います。
2019.05.19
コメント(0)
-
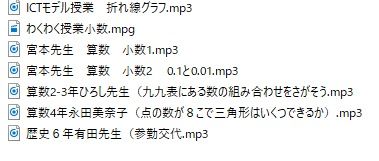
名人の授業は、子どもと同じ目線で話す!
かなり以前にNHKの教育テレビで、実際の授業の録画を放送していたことがありました。それらの録画は、パソコン上で音声ファイルにしてあります。昨日、超久しぶりに、通勤のクルマの中でそれらを聴いてみました。そして、「授業がうまい先生というのは、ある共通の特徴を持っている」ということに気付きました。どの先生も、みんな、子どもと同じ目線で、子どもたちと話をされているのです。「授業がうまい」というのは、教える中身、コンテンツのことでは、決してありません。先生が子どもに対する時の、空気というか、考え方というか、態度というか、それらがすべて、子どもと同じところに立っているのです。録音だけを聴くと、声の調子が、子どもたちと楽しくお話をしている雰囲気に満ちあふれています。上の者が下の者に教える、という類いの印象は、全くありません。子どもたちに向けて話される言葉の中には、「い~い?」などの、子どもたちに確認をする言葉が大変多いです。先生だけが勝手にしゃべって、子どもたちを置き去りにすることは、ありません。子どもたちの意見を聞いたり、今の話題についてきているか確認したり、常に「子どもたちと共に」ということを意識されていることが分かります。10年ぶりくらいに、「名人の授業」の音声を聞いて、そんな発見をしました。自分もこうありたい、という思いを持ちました。教材研究も子ども目線でするから、子どもたちが食いついてくる面白い授業になります。教師が教師役ではなく、子ども役をするから、先生と関わることが子ども同士で学ぶことと同じになっています。教師と子どもの学びが、子ども同士の学び合いに、もろにつながっています。連続した一直線上の学びになっています。授業の名人であろうとするなら、教師は子どもにならねばなりません。
2019.05.11
コメント(0)
-

教員免許更新講習を eラーニングで受講する!
教員免許更新講習の2巡目がまわってきました。僕は教員免許更新講習が義務化された最初のグループに該当しており、約10年前に第1回目の更新講習を受けました。あれから10年・・・。教員免許更新講習、再び!(笑)同じ職場の方は、近くの大学に受けに行くことが多いようですが、僕は第1回のときにeラーニングを選んだので、今回もそれで行こうと思っていました。eラーニングとは、ネットを通じて講義を視聴するものです。PC環境があれば、基本的には自宅で受講でき、大学に行って話を聞くのと同じように、単位認定されます。自宅で家族と過ごす時間を大事にしたい方や、事情があって外に出にくい方にとっては、かなりメリットがあると思います。講義の視聴にあたって、僕が重視したのは、講義内容と講師。いろいろ調べた結果、僕が話を聞きたい先生のお名前があったところに、決めました。公益財団法人 才能開発教育研究財団主催の「文部科学省認定 教員免許状eラーニング講習」です。https://www.sainou.or.jp/e-learning/index.phpおめあての先生は、学習障害の分野での第一人者、上野一彦先生。なかなかこの先生のお話を聞ける機会はありません。発達障害に関して勉強してみたいと思っておられる方であれば、他の方にも、強くおすすめしたい先生です。なお、本日申し込みをしたのですが、講師の方にはほかにも著名な方がおられました。NHK「プロフェッショナル 仕事の流儀」に出られていた、院内学級の先生、副島賢和先生。「いのちの教育」についての著書を日野原重明先生監修のもと出版されている菊田文夫先生。そのほかにも著名な方が講師として講義を受け持たれていました。ネット試聴であっても、直接お話を聞くのであっても、やはり自分が興味のある分野の、「この先生のお話が聞きたい!」と強く思えるものを主体的に選んで受講したいものだと思っています。僕と同じような考え方の人は、ぜひ、近くで受講可能な大学での開講講座だけでなく、ネットで受けられるものも含めて、いろいろ調べてみた上で、教員免許更新講習を受けられてみては、と思います。(eラーニングを受けられるところはいろいろあります。 僕は第1回目の時は、KAGACでした。) ▼KAGAC eラーニング教員免許状更新講習推進機構なお、自分の教員免許更新講習をいつまでに受けないといけないかは、次のサイトをご覧ください。修了確認期限(文部科学省のサイト)http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/003/index1.htmちなみに、受講費用はどこも同じようなものだと思っていますが、もしかすると違いがあるかもしれません。僕が今回申し込んだ才能開発教育研究財団主催のものは、必要単位分をすべて申し込むと、33000円でした。(5時間×6講義=30時間分です。高いとみるか、安いとみるか?)『みらいへの教科書 きみと・友だちと・よのなかと』(著者:菊田文夫、監修:日野原重明)【電子書籍版】
2019.05.04
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-
-

- 子供服ってキリがない!
- ウルラブバスパウダー半額
- (2025-11-22 20:20:04)
-
-
-

- 大学生母の日記
- 美濃吉「京の旬彩 丹波若どりの味噌…
- (2025-11-18 10:44:22)
-
-
-
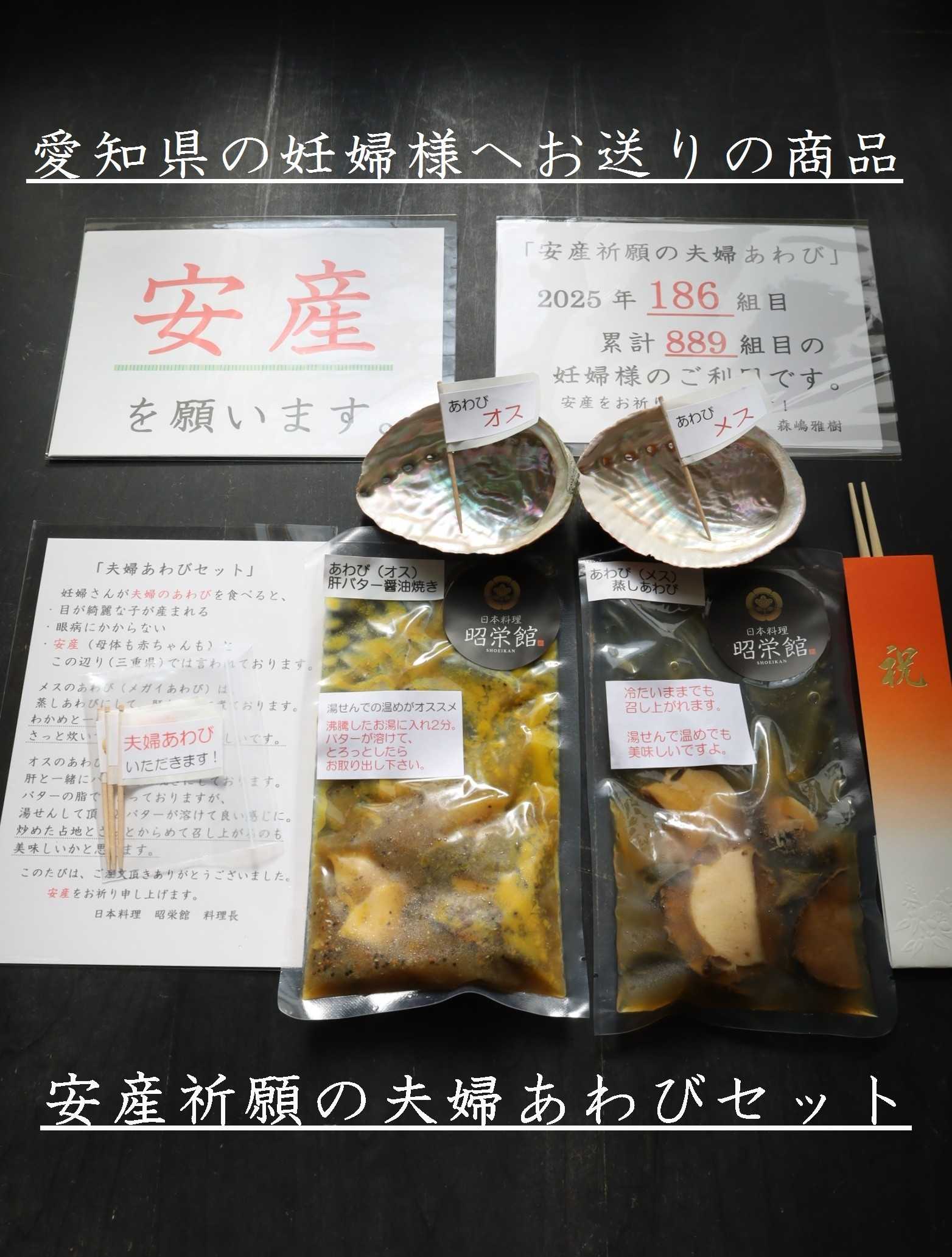
- 妊婦さん集まれ~!!
- 娘の腹帯祝いに夫婦鮑を探していまし…
- (2025-11-22 06:19:53)
-


