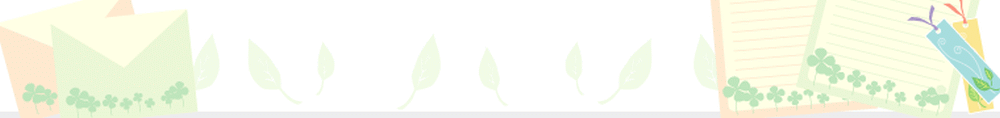PR
X
カレンダー
カテゴリ: 演劇
本日は、国立文楽劇場の新春公演の初日でした。第一部開演前には、劇場玄関前にて振る舞い酒が振る舞われ、私も升をいただきました。ロビーには黒門市場から贈呈されたにらみ鯛と、壺阪寺住職による「亥」の文字の揮毫が飾られ、普段とは異なる新春らしい風情にみちあふれていました。
第一部は、補助席が出るほどの盛況で、さすがに新春初日の第一部らしい賑やかさ。「花競四季寿」の「万才」は、文楽に興味を抱くきっかけとなった思い出の曲。「八瀬女(やしょめ)八瀬女」の詞にのせた舞の初春らしい賑々しさが、懐かしくも新鮮でした。
圧巻だったのは、文雀の「関寺小町」。生者必衰の理をこれほどの無常感をもって演じられる人形遣いさんは、今はこの人をおいて他にはいないと思います。
続く「鷺娘」は勘十郎。実は、この鷺娘といい第二部の忠兵衛といい、この人の芸が、以前よりもひとまわり大きく、華のあるものになってきたことが、今回の一連の公演を通じて最も楽しい驚きでした。舞台を圧する気力に満ち、説得力のある表現力と、役に応じたこぼれるような色気が強い印象を残してくれました。まさしく、主役を演ずるにふさわしい貫録が備わってきたように思います。
第一部は、弁慶上使と壺坂で、どちらも涙なくしては見られない作品ばかり。特に、今まで時代物の印象が強かった十九大夫ですが、あの美声に深い情がこめられていて、すばらしい出来栄えでした。
第二部は、廓を舞台にした作品が集められ、花街のもつ艶やかさと機微、そして悲哀を、異なる性格をもつ作品で見事に表現していたところが心憎い演出だと感じました。近松は、やはりそのドラマ性が際立っていましたし、そのドラマに共感させるだけの説得力を持たせた紋寿と勘十郎の梅川・忠兵衛に新鮮な感動を覚えたのも事実です。
吉田玉男さんの姿を舞台上で見られない寂しさはもちろんありましたが、次代を担う人々が着実に芸を深めているさまを目のあたりにして、何か感慨深いものを感じた今回の新春公演でした。
第一部は、補助席が出るほどの盛況で、さすがに新春初日の第一部らしい賑やかさ。「花競四季寿」の「万才」は、文楽に興味を抱くきっかけとなった思い出の曲。「八瀬女(やしょめ)八瀬女」の詞にのせた舞の初春らしい賑々しさが、懐かしくも新鮮でした。
圧巻だったのは、文雀の「関寺小町」。生者必衰の理をこれほどの無常感をもって演じられる人形遣いさんは、今はこの人をおいて他にはいないと思います。
続く「鷺娘」は勘十郎。実は、この鷺娘といい第二部の忠兵衛といい、この人の芸が、以前よりもひとまわり大きく、華のあるものになってきたことが、今回の一連の公演を通じて最も楽しい驚きでした。舞台を圧する気力に満ち、説得力のある表現力と、役に応じたこぼれるような色気が強い印象を残してくれました。まさしく、主役を演ずるにふさわしい貫録が備わってきたように思います。
第一部は、弁慶上使と壺坂で、どちらも涙なくしては見られない作品ばかり。特に、今まで時代物の印象が強かった十九大夫ですが、あの美声に深い情がこめられていて、すばらしい出来栄えでした。
第二部は、廓を舞台にした作品が集められ、花街のもつ艶やかさと機微、そして悲哀を、異なる性格をもつ作品で見事に表現していたところが心憎い演出だと感じました。近松は、やはりそのドラマ性が際立っていましたし、そのドラマに共感させるだけの説得力を持たせた紋寿と勘十郎の梅川・忠兵衛に新鮮な感動を覚えたのも事実です。
吉田玉男さんの姿を舞台上で見られない寂しさはもちろんありましたが、次代を担う人々が着実に芸を深めているさまを目のあたりにして、何か感慨深いものを感じた今回の新春公演でした。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年01月03日 21時31分05秒
[演劇] カテゴリの最新記事
-
ハンブルク・バレエの「人魚姫」 2009年03月01日
-
観劇再開 2008年03月30日
-
観劇週間第4日 文楽四月公演 2007年04月30日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.