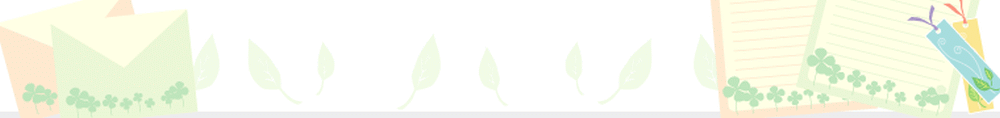全113件 (113件中 1-50件目)
-
法務担当経験者としてはモヤモヤ感が残るドラマ ― またまた書いてしまった「初恋DOGs」の風変わりな感想
7月からTBS系列で放映されていたドラマ「初恋DOGs」も、先般最終回を迎えました。「ドラマの感想は?」と聞かれたら、私はこう答えると思います。《一般向け感想》青春群像劇として、最終的には視聴者の納得を得られるエンディングだったのではないでしょうか。爽やかで心温まるストーリーだったと思います。個人的には、主役2名の恋愛模様にはあまり興味は持てず、むしろ、動物たちの賞賛に値する演技や、圧倒的な存在感を放っていた韓国人俳優ナ・イヌのカリスマ性、そういったものの方が印象に残りました。《法務担当経験者としての感想》法務担当経験者としては、やはり残念なポイントが満載だったとしか言いようがありません。そして、世間でどう思われようと、弁護士としての花村愛子さんは未熟であるとしか言いようがなく、私だったら独立した彼女に仕事を依頼しようとは思いません。大手の看板がなくなったからではなく、弁護士としての経験や力量等に疑問があるからです。これが、ドラマという虚構の世界の話でつくづく良かったです。「そんな小難しいこと言わなくてもいいじゃないの」と自分でも思うのですが、「心温まるハッピーエンドだったわよね」と思う一方で、どうにもモヤモヤしたものが残ってしまうので、そこはここで吐き出しておこうかなと思います。風変わりな感想になりますが、どうぞご容赦下さい。【最初に訴えられた訴訟はどこへ?】第8回の放送で、確か訴状の送達が獣医師の白崎さんのところにあったはずですね。訴状も画面上にチラッと見えていました。原告の名前は「湯本昇」(←ドラマにも出てきた怪しげなあの人!)、訴訟代理人名前は「九条夕貴」、送達場所は「草野・九条法律事務所」でした。ちなみに、訴状の日付は、令和7年8月15日になっていました。前回の記事でも書きましたが、基本応訴しなければならないはずです。なぜなら、訴状を無視して放置すれば、原告=湯本昇の主張がそのまま認められてしまうからです。私は、この訴訟こそスラップ訴訟(←最終回でこの言葉がセリフに出てきました!)のようなものだと思っていましたし、当然反訴はありかな、と思っていたのですが、あにはからんや、最終回を見る限り、この訴訟については全く触れられることなく終わっているようです。本当にスルーされている感じ。というのも、最終回で放映された訴訟は、上述の訴訟とは異なり、新たに提起された訴訟(別訴)のようです。原告が白崎さん、被告が相楽さんと湯本さんで、訴訟代理人も本澤さんでしたから。確かに、訴えられた場合、反訴という選択肢をとらずに、訴えられた訴訟の対応も進めつつ、新たな訴訟提起を行って対応する、というやり方はありますけれどね。ドラマの尺の関係で、最初の訴訟についてはオール割愛、ということにしたのかもしれませんが、訴訟に慣れていない多くの視聴者に対して、何か誤解を与えてしまいそうで、モヤモヤ感が残りますね。【夏期休廷期間もあるので訴訟が終わるのはまだまだ先の話ですよね?】訴状の日付が放送日近辺に設定されるのは、ドラマでは「あるある」なのでしょうが、それで思い出しました。裁判所には夏期休廷期間というものがあります。つまり、8月中に口頭弁論等の期日が設定されることはまずない、ということです。訴訟に関わる者なら皆知っている話です。通常、第一回の口頭弁論期日は、訴状が提出されてから1ヶ月後あたりに設定されますが、休廷期間が挟まれると、さらに後ろ倒しになりがち。上述の最初に提起された訴訟(8月15日の日付があるもの)であっても、どんなに早くても、令和7年の9月の下旬か10月のはじめ頃に、第一回口頭弁論期日が設定されるのではないでしょうか。言うまでもなく、新たに提起した訴訟の第一回口頭弁論期日は、もう結構寒くなる頃でしょうね。え…もうドラマ終わってるって…。【訴訟代理人がいるなら原告本人や被告本人は第一回の口頭弁論には普通出席しない】ちなみに、訴訟代理人を選任しているときは、第一回の口頭弁論期日はもちろん、他の期日であっても、原告本人や被告本人は出席しないのが普通です。かつ、被告側は、期日の一週間前までに争う旨の答弁書を出しておき、被告代理人も含めて初回期日を欠席するのが普通ですね。ですから、ああいった第一回の口頭弁論の場面は、いわばドラマ仕様なわけです(←手続き的に間違っているわけではないですが)。【証拠の後出しは必ずしも得策ではない】準備書面や証拠(書証等)は、期日の一週間前に裁判所前に出しておくのが基本ルールです。ところが、どうやら「不意打ち」が好きそうな愛子さんは、期日当日に新しい証拠を提出していますね。もちろん、最終回のケースでは、さすがに「時機に後れて提出した攻撃又は防御の方法」にはならないでしょうが、裁判官からするとあまりいい印象ではないでしょうね。でも、その方が演出効果が高いからなのか、こういうところもドラマ仕様になってしまっているようです。【証人尋問もね…】最終回では、証人尋問の場面がありましたが、これは、訴え提起から相当時間が経過した段階で行われるのが普通です。なぜなら、当事者の主張と書証が出尽くされ、争点整理が行われた後、ようやく実施されるのが証人尋問手続だからです。夏期休廷期間もあっての話ですし、そうですね、今年中に尋問期日にまで到達するとは考えにくいです。下手すると来年の終わり頃かも。え…このドラマ来年まで続くわけないじゃないし…。それから、これも法曹関係者では常識レベルの話として…。人証(証人尋問)よりも書証がしっかりしていることの方がよほど重要です。人間の記憶は曖昧ですし、だんだん記憶は変化していきます。しかも、法廷で証言すること自体、それこそ一生のうちで一度あるかどうかというような場面、証言者は緊張を強いられるのが普通ですから。また、この段階では、既に裁判官の心証はある程度決まっているのが普通です。実際問題、「証人尋問なんて当事者のガス抜きのためあるようなものだ」と言う法曹関係者も少なくありません。つまり、証人尋問が主戦場ではないのです。でも、ドラマ演出上、訴訟の山場のように描かれがちなのでしょう。【このセリフはいただけない ― 「ソハさんの力をあてにして仕事のチャンスをもらうより、自分の手でつかむ」】愛子さんの「ソハさんの力をあてにして仕事のチャンスをもらうより、自分の手でつかむ」というセリフ、「カッコイイ」ということになっていますが、私に言わせると、愛子さん少し勘違いしていないかなと思いますね。ビジネスはご縁です。ご縁を大切に出来ないと、いい仕事は出来ません。仕事のオファーがあるということは、とてもありがたいことであり、貴重な勉強の機会をいただけるわけですから、大いに感謝すべきことなのです。そこが抜けている印象でした。実際、企業法務の現場は、生きた学びの宝庫です。企業法務に求められるスキルは、訴訟対応だけではありません。契約業務、ガバナンス対応、業法対応、会社法対応、人事労務対応等、分野も多岐にわたります。そして、何よりも、多くの人と人が関わり合いを持つことで生じるいろいろな事象に適切に対応していくことが求められますので、本当の意味での「人間力」が要ります。もちろん、オファーを断る自由はあります。正直なところ、まだ駆け出しの新米にしか見えない愛子さんには、ソハさんが提案している仕事は、「時期尚早レベル」で「かなり高いハードル」だと思った方がいいでしょう。ですから、「貴重な機会をいただけるのは大変ありがたいのですが、未熟な私には荷が重く」と断るならまだしも、「あなたの力なんて借りないわ」という感覚はちょっといただけない。結局、人の好意を素直に受け取れないのは、こじらせ女子のこじらせ女子たるゆえんなのでしょう。ま、若いってことなのでしょうかね。#初恋DOGs
2025年09月03日
-
ドラマはツッコミどころ満載 ― 続・ドラマ「初恋DOGs」の風変わりな感想
先般、たまたま視聴していたドラマ「初恋DOGs」について、企業法務を長年経験した者からすると、ヒロイン花村愛子=敏腕弁護士という設定にどうも疑問符がついてしまうという記事をアップロードしました。このドラマに限った話ではありませんが、「それってやっぱりちょっと違うよね~」という違和感はドラマにはつきもの。例えば、戦前戦後を生きてきた私の親世代などは、戦前戦後のドラマが放映される度に、「やっぱりちょっと感覚的に違うと思うのよね、男の人の髪型とか、違和感あるのよ~」とテレビ画面に向けて文句をぶつけています。私の場合も、一応、学生時代歴史学を学び、古文書学も履修していますから、時代劇で出てくる毛筆の書体を見るたびに、「その時代の書体(スタイル)ではない」といつも文句を言ってしまいます。近世(江戸時代)の文字のスタイル、戦国期の文字のスタイル、平安期の女房奉書の文字のスタイル、全部ダメ出ししたくなります。確かに、厳密にその時代の文字を再現するとなると、画面に映し出された文字をほとんどの人が読めないでしょうし、致し方ないというところかもしれません。もちろん、制作サイドの方たちは、いろいろ細かいところまで調べて段取りされているとは思いますが、いろいろな事情で限界もあるのでしょう。さて、世の中には、医療ドラマや法廷ドラマ等、いろいろなタイプの作品が存在しますが、その道のプロの方が見ると、案外「おいおいおい!」とツッコミたくなる箇所多数なのではないでしょうか。正直なところ、それはそれとして、「違うでしょ~」とツッコミつつも、「結局ドラマなのだから」と割り切って楽しむ方がこの際精神衛生上良さそうです。それこそ「初恋DOGs」なんて、本来胸キュンドラマなのですから、心優しい獣医さんなり、王子様級の御曹司お坊ちゃまなりを見ながら、「この二人の組合せも眼福よね~」と愛でていればそれでいいのかな、と思ったりしています。…と書いたところで、それでもやっぱり、元企業法務担当者から見ると、「初恋DOGs」はツッコミどころ満載なので、そこだけちょっと書いておきますね。●いきなり「訴状」という展開って…ケース・バイ・ケースとはいえ、企業法務を長くやっていた感覚からすると、訴え提起は最後の手段であり、それまでにいくつものプロセスがあるのが普通ではないかと思うのですね。もちろん、いきなり訴訟という戦略もないわけではないですが、かなり稀だと思います。勝訴判決があれば債務名義が獲得できる=強制執行が可能、というメリットはあるにしても、訴訟となればさして複雑な事案でなくても相当に時間がかかるうえに、弁護士費用も含めて出費もかなりのもの、どうせ裁判所は和解勧試するだろうし(←裁判官だって判決書くより和解調書書く方が楽だし…)、等々考慮すると、「よほどのことがない限り訴訟以外の方法をまずは探れ」というのが鉄則だと思うのです。ま、ドラマですからね!このドラマの場合、雰囲気的にどうも「嫌がらせ」目的の訴訟提起に見えますね。いわゆるスラップ訴訟という感じでしょうか。勝つことを目的にしない訴訟ですかね。ということは、不当訴訟の可能性もあるわけで(←ただしその主張が認められるのはかなり限定的な場面でしょうが)、普通に考えて、訴えられた側は、反訴は必須なのだろうなと思います。●裁判所から呼出しが来たということは「応訴」しなければならないってことですよ反訴という言葉が出てきたところで、そもそも、獣医の白崎さん、訴状を受け取ったのですよね。訴状には「口頭弁論期日呼出及び答弁書催告状」が同封されていましたよね。つまり、訴えられた以上、最低限応訴しなければならないはずです。答弁書一つとっても、獣医さんご自身で書くのは難しいでしょうから、訴訟代理人の弁護士を選任するところから始めなければなりません。訴訟委任手続きとか、避けては通れない手続きが存在することをまずは認識する必要があります。第9話に至っても「裁判なんて」とか「訴えるつもりはありません」とかいった白崎さんのセリフがありましたが、白崎さんにとって、この段階で訴訟に背を向けるという選択肢はないのです。ま、ドラマですからね!それにしても、弁護士の花村さんはちゃんと説明したのでしょうか?「訴えられた以上、応訴は必要」「こちらに非がないのであれば、反訴も必要」という話が先にあり、そのうえで「刑事告訴も視野に入れて」の話になるわけですよ、花村さん。確かに、花村さんのセリフに法律的な間違いは見られません。が、ちゃんと説明できていないのでは?という印象がどうしても拭えない…。●刑事告訴されるようなことにそもそも手を出すかな?大手の法律事務所なら、刑事告訴をされるようなことにそもそも手を出しますかね、という基本的な疑問がありますね。あるいは、問題の獣医(相楽)さんだって、獣医師資格喪失の危機リスクを負ってまで悪事に手を染めるかしらね~。それに、世界中どこの企業グループも、ガバナンスの問題には非常に気をつかっているはず。不祥事は企業活動の命とりになりますから。という具合に考えてくると、やっぱり荒唐無稽な話にしか見えてこないですね~。ま、ドラマですからね!そう、ドラマですから。それに、時々「事実は小説より奇なり」ということが起こるのがこの世の中。だから、「あり得ない」などとムキになるのもナンセンスな話。それより、最後まで楽しく視聴することにいたしましょう。巷では、獣医さん派か御曹司派か、という話題で盛り上がっているのでしょうか?ちなみに、私は●●派ですよ。そんなこと聞かれてない?さぁ最終回どうなりますことやら。#初恋DOGs
2025年08月29日
-
元企業法務担当者による弁護士花村愛子評 ― ドラマ「初恋DOGs」の風変わりな感想
最近ともすれば「ドラマ・ブログ」になってしまうきらいがありますが、今回は、現在TBS系列で放映中の「初恋DOGs」の話題。巷では、動物たちの演技や日韓合作ドラマといったことでも話題になっているようですが、私が今回言及したい話題は、元企業法務経験者として、さまざまな事案を弁護士たちとともに仕事をしてきた私から見た「弁護士花村愛子評」です。これから書こうとすることは、残念ながら、花村愛子の仕事ぶりに対する「そこそこ辛口なコメント」になりそうです。もっとも、そのことをもって、このドラマの出来が悪いなどということを言うつもりはありません。ドラマを制作するにあたり、現場業務に精通している専門家による法律監修もしっかりなされているはずですし、むしろ、これから列挙するようなことも十分認識したうえで、ドラマのプロット構成や人物造形がなされているだろう、と思うからです。かつ、限られた話数の中で、どの部分によりスポットを当てるかという問題もあろうとか思いますから、場合によっては、割愛された要素もあるのかもしれません。なお、一部ネタバレも含まれるでしょうが、詳しいあらすじ等は、公式ページや配信サービスをご参照下さい。また、この記事を書いている時点では、第5話までの放映が終わっており、今後の展開には未知な要素がかなり含まれているという前提でお読みいただけると幸いです。正直なところ、主人公の弁護士花村愛子は、公式サイトでは「敏腕弁護士」という人物紹介がなされていましたが、私の独断と偏見によれば、このドラマで拝見する限り、未熟でそれなりに教育的指導が必要そうな新米レベルの弁護士という印象です。実際の女優さんの年齢についてはこの際不問にするとしても、役における位置づけを想像するに、司法試験が終わり、司法修習生が終わって、まだそれほど実務の経験を積んでいない若手の駆け出しなのかな、というのが正直な印象です。もちろん、業務を進めるにあたって、業務上求められることと自らの良心・正義感との狭間で葛藤している主人公は、いたって大真面目なのだと思いますし、何と言っても生身の人間なのですから、理屈と本音が異なるのは当たり前のことです。そうだとしても、仕事の進め方にかなり問題が多そうだな、と思いましたので、そのあたりを以下列挙しますね。【上司や利害関係者の同意なき不意打ちを二度行ってしまった件】まず、最も問題が大きいと思われるのは、事前に上司や利害関係者の一人であるウ・ソハの同意を得ることなく、異なる利害関係者が一同に会している席上で、「不意打ち」を食らわせてしまう件です。しかも二度も。これは、仕事の進め方としては、お世辞にも褒められない話ですね。一度目(第2話)の段階では、「重要な事実を伏せたまま話をまとめると我々の信用問題にもなる」というような巧妙な理屈を述べておりましたが、「重要な事実」であるのなら、まずクライアントと上司との間で、十分に事実確認を行い、そのうえで方向性についてクライアントや上司と合意形成を行ってから、相手方との話し合いの席につくべきことでしょう。それでも、私も、第2話の段階では、「そこまで目くじらを立てなくても、もともと癒しのドラマなんだから、寛容に見なくちゃね」と思っていたのですが、第5話のオンライン会議の場面で、再び上司とウ・ソハをいわば「出し抜く」形になったとき、これには、私も主人公に対して「厳重注意が必要だな」と思ったのであります。実際、上司役は怒っていたようですが、私が上司でも、相当厳しく指導するだろうな、と思います。法廷では、場合によっては、法廷戦術のようなものを使うこともあります。が、少なくとも、依頼人や上司との間のコミュニケーション不足のまま、ある意味取り返しのつかない方法で「不意打ち」を食らわせるような行動をとるのは、いかがなものかと思いますね。根底に友情や愛情といった美しい感情があったとしても、その美しい感情に従うことと、仕事の場で「不意打ち」を食らわせることとは同義ではありません。【そもそもクライアントが誰でクライアントの利益がどういうものなのか整理されていない】第5話まで見進めてきて、気になったのが、主人公花村愛子が、クライアントが誰で、そのクライアントの利益が一体どういうものであるのか、という根本的なところの整理をしないまま、気持ちだけで仕事を進めてしまっていることです。少なくとも、最初の段階では、依頼人はウ・ソハだったのではないでしょうか。もっとも、その背後にある企業グループ全体をクライアントとみなすようになっていったことが厄介さの根源であったことは致し方ありません。そうなると、実は、ウロア・グループの中でも、利害が対立していたわけです。ですから、そこを整理したうえで、どう調整していくか、というプロセスがどうしても必要なはずでした。が、そのあたり、しっかりした議論もなされないまま、グループ外の人(白崎快)も含めた話し合いの席を持ってしまっていることについては、上司含めお粗末としか言いようがありません。一番呆れたのは、最初の依頼人であるはずのウ・ソハが、ずっと腹案のように持っていた主張について、花村愛子という人は、全く確認することなく「遺産と犬の管理権を分ける」という提案に及んだことでした。結果、当初の依頼人であったはずのウ・ソハには、一文も遺産が残らないという本末転倒な結果を惹起することになってしまいました。もしかしたら、花村愛子は、ウ・ソハのことを「わかったつもり」だったのでしょうか。そういえば、第2話で、白崎快から「花村さんが俺の何を知ってるっていうんですか」と注意されていましたね。確かに、「能ある鷹は爪を隠す」を地で行っていたウ・ソハは、第4話以降、慎重に自分の本当の意図を隠しながら行動していました。なお、第5話で明かされた「ウ・ソハが500億ウォンの相続権を獲得することを諦めていない」という主張は、考えようによっては、最善の策だったのかもしれません。ウ・ソハだけではなく、白崎快にとっても。さすがに、ウ・ソハは、主人公花村愛子に対して、「あなたのおかげでお金がなくなりました」と釘を刺していましたから、余程の愚か者でない限り、愛子は自分のしてしまった過ちに気づくでしょうが、弁護士としてはかなりお粗末と言わざるを得ません。【未確認事項が多すぎる】それから、遺産整理の事案なのに、故人の意思が本当はどういうものであったのか、そこが棚上げになってしまっているあたりからして、主人公は仕事の基本を見失っていると感じます。主人公花村愛子自身、「遺産と犬の管理権を分ける」というアイディアが気に入ってしまったのでしょう。その事情は十分理解できますが、そもそも、故人がなぜ「負担付遺贈」という建付けを選んだのか、というあたりをすっ飛ばしてしまっているあたりは、やはり仕事の進め方としては、稚拙と言わざるを得ません。考えてみれば、500億ウォン(50億円)という金額規模は、企業グループの時価総額レベルからすれば、かなりささやかなものです。ひょっとすると、故人(ソハの亡き祖母)としては、企業グループの後継者になるつもりがなさそうな末の孫に、彼の才覚で自由に生きていけるだけの独立資金を渡すつもりで、あのような遺言に及んだのかもしれませんし。さらに、実行犯は逮捕されたとはいえ、犬の誘拐事件(+ソハへの暴行事件)の黒幕が明らかにされていないまま、「遺産と犬の管理権を分ける」という、あろうことかその黒幕かもしれない人を利する可能性がある提案をしてしまうとは、かなり迂闊な話ではないでしょうか。こう書いてくると、そこそこどころか、激烈辛口コメントになってしまったかもしれません。そうだとしても、あくまでもドラマの話ですし、悩み多き若者たちの成長物語なのでしょうから、これでも私自身、できるだけ温かい目で見守るつもりで視聴しています。若いときは、いろいろ失敗して当たり前ですからね。それに、かわいい動物たちから沢山の癒しをもらっています。何より、演技者たちは、非常に頑張っているな、と感じます。特に、異国の地で、おそらく第二か第三の外国語であろう日本語のセリフを大量にこなしつつ、ネイティブではないその日本語でもしっかりと感情を伝えることができる韓国人俳優ナ・イヌの演技力の高さには、惜しみない拍手を送りたいと感じています。#初恋DOGs
2025年07月30日
-
(続)「傷ついた心」「生きづらさ」を真正面からとりあげるドラマ ― 「モーテル・カリフォルニア」
先日、韓国ドラマ「モーテル・カリフォルニア」について、実は「深刻な心の傷を負った主人公の生きづらさ、そして、大きな痛みを伴いながら過去と向き合っていく自己統合の過程が赤裸々に描かれている」ドラマであると言及しました。過去の記事はこちら。「心の傷」 ― 最近でこそそれなりにいろいろなところでとりあげられる話題ではありますが、そうだとしても、まだまだ周囲の理解が得られにくい分野ではないでしょうか。ある心理士さんが、「トラウマを抱えている人は、トラウマ症状そのものでも苦しんでいるが、周囲の人になかなか理解してもらえないがゆえに、生きづらさが増幅される。周囲には、性格が悪いとか、本人が悪いとか決めつける人も多いので」と仰っていましたが、このドラマについても、虚構の話ながら、ヒロインに対して、そういう風当りのようなものが発生している可能性があるかもしれないな、と感じています。いえ、それだけ、ヒロインを演じた女優さんの演技が素晴らしいということでもあるのですが。さて。前回は、ドラマで提示されていた心の傷が、どのようなものであるのか、思うところを書いてみたわけですが、今回は、トラウマからの回復過程について、少し言及したいと思います。実は、このドラマ、キャストとして精神科医や心理士は登場しないものの、男性主人公(獣医師さんという設定でした)が恋人であると同時に「医師」のマインドを持っていたことが功を奏したのでしょうか、結構有効な対処を行っていた場面が随所に見られたように感じましたので、そのあたり少しだけ言及してみたいと思います。まず、ヒロインのトラウマに対して、男性主人公が実質的にナラティブ精神療法的なアプローチになるようにサポートしていた点はさすがだな、と思って見ておりました。トラウマ経験に対する断片化された記憶は、必ずしも過去のファクトを正しく反映しているとは限らないところもあるのですが、トラウマと向き合いつつ再構築し、過去のできごとや経験を新しい視点から見直し新しい意味を与える、というまさにトラウマ対処の王道を行っていました。あるいは、多くの方がお気づきになったと思いますが、インナーチャイルドを癒す文脈がしっかり映像化されていた点、お見事だったと思います。そろそろ最終回を迎えるということらしいのですが、最後に少しだけ。やはり、仮に今回のドラマのような状況であれば、精神科医・心理士・薬剤師・家族がチームを組んで、粘り強く適切に対処する経過を辿る方が本当は望ましかった、と思いますね。そういう適切な処置を経ることによって、トラウマを克服する力を得た人は、魅力的な人物へと変容していくことが可能なのです。…と書いてみたところで、あくまでドラマでのお話ですから、という話になるでしょうかね。それにしてもこのドラマ、ある意味「問題作」と言ってもいいのかもしれません。少なくとも、ドラマで繰り広げられたようなことは、全くの絵空事ではなく、現実の世界でも普通に起こりうる事象であることを明確に人々に提示した、というべきでしょう。
2025年02月15日
-
「傷ついた心」「生きづらさ」を真正面からとりあげるドラマ ― 「モーテル・カリフォルニア」
長い間放置していたこのブログですが、唐突に「書いてみよう」というトピックが浮かびあがってきました。おつきあいいただける方は、ご笑覧下さい。 韓国ドラマについては、それほど多く視聴するわけではないのですが、たまたまふと気になって視聴を始めた「モーテル・カリフォルニア」で扱われるテーマの重さに、驚きを隠せません。現時点では、最終回の放映はまだなされていませんが、それでも「これは…」と思うこと多々、ちょっと書き留めておきたいと思った次第です。当初『田舎のモーテルを背景に、モーテルで生まれてモーテルで育ったヒロインが、12年前に逃げ出した故郷で初恋の人と再会することで経験する、紆余曲折の初恋リモデリングロマンスドラマ』という触れ込みだったのですが、なんのなんの、深刻な心の傷を負った主人公(主人公たちといった方が正確かもしれません)の生きづらさ、そして、大きな痛みを伴いながら過去と向き合っていく自己統合の過程が赤裸々に描かれているのです。まるで臨床心理学の分野でとりあげられる「臨床事例」でも見ているかのようです。私自身、これでもカウンセリングや認知行動療法の単位も取得していますから、それなりに興味関心の分野ということもあって、「なるほど」と思いながらドラマを追うことができますが、人によっては「ヒロインに共感できない」と思う方も相当数存在するだろうな、と思ったりするわけです。そういった事情をちょっとひも解いていきたいと思います。ここでは、いわゆる「ネタバレ」を積極的に行うつもりはありません。あくまで、私自身が思うところを書いていこうと思います。このドラマでは、臨床心理学的観点から、注目に値する要素が山のように見つかります。物語の序盤から、ヒロインには何らかの愛着の問題が存在すること、自己肯定感が低いこと、感情の起伏が激しいこと、人間関係を築くのが難しいこと等の特徴的要素をはっきり見てとることができます。そして、最も自分に愛情を注いでくれる対象(このドラマでは男性主人公)に対して、しがみついたかと思うと突き放して振り回す行動が繰り返されます。いわゆる試し行動も多くみられます。当初、このヒロインについては、「愛着障害か、はたまた境界性パーソナリティー障害か、そんな想定もできるかもしれないな」と思いながら見ていました。なお、鑑別を行うのは、私の役目ではありません。それは、臨床医の行うことです。が、説明の便宜上、そういう想定もできるかもしれない、と記載しておきますので、そうご承知置き下さいませ。ところが、物語が進むにしたがって、ヒロインの「生きづらさ」の正体は、「いわゆる複雑性PTSDのような状況かもしれない」ということが明らかになってきます。繰り返しますが、鑑別を行うことが目的ではありませんし、臨床医によっては異なる鑑別の可能性も十分あるだろう、という前提で書いておりますので、そこはご理解ください。それはともかく、ヒロインも(そして男性の主人公も)トラウマと呼ぶにふさわしいほどの凄絶な体験を子供の頃にしていたことが、ドラマの後半になって明らかになってきます。このヒロインの場合、長い間その体験に関する記憶がなくなっていたところ、フラッシュバックにより断片化された記憶がよみがえってくるというものでした。こうした断片化された記憶については、『こころの情報サイト』に詳しく説明がありますが、端的に状況が解説されているように思いますので、一部引用しておきます。あまりにも強い恐怖やショックを感じたために、その体験を落ち着いて整理することができません。そのために、非常に良く覚えている部分と、覚えていない部分が混じり合ったり、体験したこと、感じたこと、考えたことの関係が混乱したり、時間的な順序や、何が原因で結果なのかといったつながりも分からなくなります。これを記憶の断片化と呼びます。そのような記憶は、「いつ、どこで、どのように、なぜ起こったのか、その結果はどうなったのか」という枠組みができていませんので、大変に不安定な状態となっています。そのために、ふとしたことで、あるいは突然に、記憶が意識の中に侵入し、フラッシュバックや悪夢を生じます。トラウマ体験の記憶は断片化していて、その一部を思い出すと、他の色々な断片的なイメージが次々に思い出されたり、辛い感情や考えが出てきます。あたかも常に被害が生じているように感じられますので、不安や緊張が消えることがありません。時にはこうした辛さから心を守るために、現実感がなくなり、ぼんやりとしたり、記憶の一部が飛んでしまうこともあります。また落ち着いて記憶をふりかえって考えることができませんので、必要以上に自分を責めたり、自信を失ったり、周りの人に不信感を向けたりもします。極端な場合には、世の中に安全な場所などないとか、自分には何も良いところがないと思い詰めたりもします。過去の体験についての恐怖が強くなりすぎると、過去の被害を思い出すことで、もう一度現実に被害を受けているかのように感じられます。確かに、このヒロインのケースでは、複雑性PTSDの場合によくみられる「回避」「否定的自己」「感情調整困難」「対人関係障害」という典型的症状(といって差し支えないと思います)を呈しているように見えます。ドラマですので、あくまでも虚構の物語なのでしょうが、本来であれば、専門的知見を持った経験豊富な臨床医・心理士・薬剤師等がチームを組み、適切な治療方針のもと丁寧に取り組んでいくべきレベルの状況です。という具合に、ヒロインの状況がかなり危機的状況であるのは言うまでもないのですが、ヒロインと傷を共有し、心理的共振状態にあった男性主人公にも、実はそれなりに課題があったように思います。「助けるという方法でしか愛情を表現できないと思い込みすぎていた」こと、そして「罪悪感ゆえに償いと称する補償行為を繰り返しどこか他人軸で生き続けてきた」ことあたりでしょう。ただ、幸いなことに、ドラマ中盤から、自分の状況を認識し、罪悪感を手放し、自分軸で生きることにコミットする、という望ましい方向性を辿っていたあたりは、視聴者にもそれなりに安心感を与えたのではないかと思います。その他、心理的課題の世代的連鎖の問題等、見るべきポイントはいろいろあるように思いますが、ドラマの視聴者としては、何とか心安らぐラストが欲しいところでしょう。幸いなことに、とても困難な道のりを辿ることにはなるのですが、トラウマを克服することは可能であるとされています。トラウマを抱える者にとって、回避行動が一番問題解決を遅らせることになってしまいます。むしろ、とても辛い時間を過ごすことにはなりますが、トラウマとなった出来事に向き合い、言語化し、新たな意味づけを自ら行い、整理し直すことが特に重要ポイントだとされています。このときに重要なのが、トラウマを再体験する際、安全が確保され、深い共感とともに受容されるかどうか、というあたりでしょう。なお、トラウマの克服は、トラウマそのものを消滅させることではなく、傷ついても立ち上がれる力を手に入れることに他なりません。今後、ヒロインがどのような経過を辿っていくのか、そのあたりはまだこれからの話ということでしょうが、仮にヒロインが紆余曲折を経てホンモノのアイデンティティを獲得できるようになった暁には、怒りが感謝に変わるプロセスが見られるのかもしれません。そして、多くの苦しみの過程で背負ってきたものが、その人にとっての大きな生きる力へと変容していくとき、本当の意味で癒しの瞬間が訪れるのかもしれません。いずれにしても、お茶の間のドラマに、「心の傷」を真正面からとりあげるものが登場するようになったことは、「生きづらさ」がもはや他人事ではなくなってきた、ということの表れなのでしょう。もっとも、「生きづらい」のは、ときとして「理解してほしいのになかなか理解が得られない」から。それゆえ、爆発的な人気ドラマにはなりにくい要素を持っているともいえるでしょう。そうだとしても、「心の傷」というものをこれほどじっくり映像で見せる試みに、私としてはやはり驚嘆を禁じ得ないのでした。#モーテル・カリフォルニア#MotelCalifornia
2025年02月10日
-
臨床法務のすすめ
企業法務の世界でよく耳にする語として、「戦略法務」・「予防法務」・「臨床法務」という表現があります。世の中でよく言われているのが、「従来の日本の企業法務は臨床法務に終始していたが、これからは紛争予防と損害を回避するための予防法務や、積極的な経営戦略のための法務活動にシフトしていくべきである」という意見です。もちろん、健康管理と同じで、治療よりも予防の方がはるかに身体に与えるダメージは小さく、コスト・ミニマムですから、今さら予防法務・戦略法務の重要性に疑問符を付けるつもりはありません。契約締結時のリスク評価や取引開始前の秘密保持契約締結等は、企業活動の基本中の基本ですし、リスクマネジメントに関わる事項のマニュアル化も日常の経営の場面では不可避な事項といえるでしょう。今や企業統治におけるコンプライアンスは常識であり、コンプライアンスに基づく企業統治の失敗は、文字通り「命とり」になることは言うまでもありません。とはいえ、それでもあえて私が申し上げたいのは、「それでも臨床経験なくして企業法務はつとまらない」ということです。よく「契約書の雛型を作って下さい」とか、「マニュアル化して下さい」とかいった要請を受けることもあるのですが、その度に私は口を酸っぱくして「雛型は参考であって、万能ではないし、雛型の罠に陥ることは危険である」と強調するようにしています。例えば、次のような事例はどうでしょうか。営業担当者から契約書案をのチェック・添削依頼があったとしましょう。文面だけを見ていたらほぼ雛型通りだし、何の問題もなさそうな内容だったから、そのままOKの返事を出す、これは法務初心者のすることです。こういう場合よくあるのが、契約書案文面には登場していない厄介な問題が隠れている、というケースです。熟練の法務担当者なら、念のため担当者を呼んで、どういう理由でこの契約書を締結することになったのか、経緯や内容を確認するものです。そのうえで、本来条件交渉すべき事象が、全く不問のまま放置されていないか、契約書の内容が取引の事情上に即応しているか、この契約が締結されることによる経営へのインパクトはどの程度か、といったあたりを判断していくのです。ある外科医の方が、「手術で開腹してみてびっくり、などということは日常茶飯事、教科書通りに進むと思ったら大間違い」と仰っていたのを聞いたことがありますが、企業法務の世界でも全く同じことです。企業法務の現場で起こっていることは、さまざまな条件の複雑な組み合わせによって惹き起こされるものであり、型どおりの答えで済ませられない問題も非常に多いのです。ですから、「民法は得意だが、不正競争防止法は専門外」とか、「会社法は学習したが、いわゆる業法の類はわからない」とかいった態度は、臨床法務の現場ではご法度です。企業法務の現場では、刻一刻の判断が経営に大きな影響を与えることも多く、かつ、判断すべき事象は、単なる法的評価に止まらないことも多いです。会計・税務・労務、あらゆる要素を瞬時に判断していく力は、残念ながら経験を積まないと、一朝一夕では身につきません。資格人間・マニュアル人間が増えている昨今、私はあえて声を大きくして言いたいです。「臨床経験なくして語るべからず」と。
2014年02月09日
-
小学校とコミュニティ
もう10年以上前、ホームページを細々作っていた頃、別途掲載しているような駄文を書いていたことがありました。あれからさらに小学校の統廃合は進み、コミュニティとしての学区の概念と実際の小学校の校区との乖離は大きくなる一方です。もっとも、世の中、それでも伝統は継承されていくもののようで、今でもしっかり学区がコミュニティの単位になっているから驚きです。http://www.city.kyoto.lg.jp/kamigyo/page/0000029004.htmlそういえば、大阪も船場(東横堀川・西横堀川・土佐堀川・長堀川で囲まれる地域)あたりでは、とっくに統廃合で消えてしまった小学校の名前が町会の名前に残っているようです。先日、三休橋筋のとあるお店に貼られていた地図に「愛日・集英連合振興町会」と書かれているのを見つけ、船場の町の人たちの地域の拠点がやはり昔の小学校にあったことを知った次第です。そういえば、船場もいわゆる通りを挟んで同じ町名を冠する両側町でしたね。http://osakacommunity.jp/chuo/chosei_kaigi/chiiki/chokai_shokai.htmlということで、10年以上前の駄文を別途掲載させていただきます。
2013年05月03日
-
花火3発・金魚2匹
「花火3発・金魚2匹」-夏の風物詩のようですが、これは先日私が聞きに行ったピアノの会で遭遇した今年ならではの事象。ドビュッシー・イヤーですからね。普通の演奏会で、花火が3回も演奏されたり、金色の魚(金魚と言ってしまうと大和郡山の金魚になってしまいますかね…)が2回も演奏されたりなどということは普通は考えられないわけです。ドビュッシーについては、そういえばあまり人前で弾いたこともないですし(小学生のとき弾いた「亜麻色の髪のおとめ」は別として)、あまりさらったこともないですね。たまには挑戦してみてもいいかもしれません。
2012年08月26日
-
ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウの訃報
お昼のニュースで、バリトンのディートリヒ・フィッシャー=ディースカウの訃報を耳にしました。数日前、久しぶりに通勤時に彼のシューベルトの歌曲を聞きながら、「彼も相当高齢になっただろうなあ」と思っていた矢先のことでした。私にとって、ディートリヒ・フィッシャー=ディースカウは特別な歌手です。その昔、N響定期の学生会員だった頃、たったの千円で聞いた「ドイツ・レクイエム」の衝撃が忘れられません。「世の中にこんなに上手い神様のような歌手が存在するのか」という驚きのあまり、その日の晩は興奮して眠れなかった程です。その後しばらく彼の歌うドイツ歌曲の世界にどっぷり浸かっておりました。特に、R・シュトラウスとヴォルフの歌曲集を、何度も何度も繰り返し聞いたものです。もちろん、1992年秋に来日したときのシューベルト歌曲の演奏会にも出かけました。「小人(Der Zwerg)」や「星(Die Sterne)」といった、普段の演奏会ではあまり聞く機会の少ない曲で構成されたプログラムの面白さ・奥深さが印象に残っています。息のあったサヴァリッシュとの共演は、それはもう「珠玉」としかいいようのない至福の時間でした。その直後、彼は突如引退を表明、二度とステージでの演奏に触れることができなくなってしまいました。そういえば、1992年来日時には、ルチア・ポップとの「ドイツ・レクイエム」もあったように記憶しておりますが、彼女もその直後に故人になってしまったのでしたね。それもかなり衝撃でした。本当に寂しい限りです。
2012年05月19日
-
真っ黒な楽譜
フォーレのバラードの楽譜がようやく届きました。本当に3ヶ月程度かかってしまいました。ここのところ、フォーレの初期の作品を弾くことが多く、それならばバラードの譜読みをしてみようかと思って、楽譜を取り寄せた次第ですが、何だか真っ黒な楽譜です。調性から#や♭が多いことは予想がついておりましたが、先日弾いていた夜想曲以上に、音が重なっているようで、これは譜読みに時間がかかるかもしれません。
2011年09月02日
-
フォーレ3題
フォーレの夜想曲第5番にまつわるこぼれ話を3題。★本屋の立ち読みがきっかけで現在練習中のフォーレ夜想曲第5番、ここ数年舟歌第1番・第2番やヴァルス・カプリス第1番といったフォーレ初期を手がけてきたとはいえ、練習をはじめたきっかけは意外なところにありました。ことの次第は、阪急沿線でチェーン展開している某書店のBGMで流れているのを偶然耳にしたことに始まったわけです。ちなみに、その某書店では、「またなぜこんな曲が…」と思うようなBGMがよく流れており、先日もフランクの「プレリュード、フーガと変奏曲」のピアノ編曲版(バウアー編か?)が聞こえてきて、一瞬わが耳を疑ってしまったほどです。フォーレの夜想曲第5番に至っては、少なくとも2度ほど聞いた覚えがあり(2度というのも驚きです!)、最初に聞いたとき「これ何番だったかしら…」とすぐには思い出せなかったわけで、そんなこんなで譜読みを始めた私でありました。★ジェルメーヌ・ティッサン=ヴァランタン譜読みにあたっては、藤井一興氏による運指版の他に、アメル社から出ているジェルメーヌ・ティッサン=ヴァランタンによる運指版を参照しました。先日、お世話になっている先生のレッスン時に両方の版を持参したところ、ジェルメーヌ・ティッサン=ヴァランタン女史の話題になり、先生の師匠であったアンリエット・ピュイグ=ロジェ女史による興味深いティッサン=ヴァランタン評を聞くことができました(お二方は「ドリー」で共演していますし…)。そして、「貴方(=私のこと)きっと気に入ると思うわよ」という先生の予言通り、ティッサン=ヴァランタンの録音は、まさに「私好みのストラークゾーンどんぴしゃり!」の演奏、その気品と深みのある演奏スタイルの虜になってしまったのでした。★クセモノ~ソステヌート・ペダル~フォーレがソステヌート・ペダルを前提としてこの夜想曲を作曲したか否かは定かではありませんが、少なくともフォーレの作品でダンパーを濫用するのは御法度だと思いますし、むしろ積極的にソステヌート・ペダルを使っていくべきではないかと思っております。ただ、人前で弾くときに、この「難儀な真ん中のペダル」を上手く操作できるか…ということについては、相当程度リスクを伴う問題だと言わざるを得ません。ソステヌート・ペダルを踏み損なって不発に終わってしまったときの悲惨さといったら…、これは間抜け以外の何ものでもありませんから。
2011年07月18日
-
ルプーその後
京都公演を皮切りに始まるはずだった今回のルプー来日ツアー、なんと京都公演の後に予定されている公演については、ご本人の急病によりキャンセルになってしまったのだとか。なんとも驚きです。京都のときも、きっと体調は最悪だったのでしょうね。前半のベートーヴェンは確かに迫力がなく、やや精彩を欠いた感がありましたが、そのためだったのかもしれません。しかし、それにしても驚異なのが、驚くべきあのシューベルトの美しさです。聴いている私も確かに最悪の体調でしたが、全てが洗われるような癒しに満ちた演奏だったのですから。プロとはそういうものなのでしょうか。演奏会を楽しみにしていらっしゃった方には気の毒な限りですが、今は一日も早い回復をお祈りしたいところです。
2010年10月17日
-
心地よい響きの漂泊 ~ ルプーのシューベルト
秋に入り、今までの元気はどこへやら、風邪に端を発し、咳喘息と片頭痛の再発にすっかり低調な日々を過ごしておりましたが、ルーマニア出身のラドゥ・ルプーが、随分久しぶりに来日するとのこと、しかも今回は京都で演奏会を開くということで、久しぶりにピアノの演奏会に出かけました。ルプーのピアニッシモの美しさについては、ブラームスの晩年の小品集やシューベルトのソナタ等、既に幾つか持っているディスクでも十分味わっていたつもりでしたが、やはり生演奏は予想をはるかに超えたものでした。特に、今回のプログラムの後半に配されたシューベルトのピアノ・ソナタ変ロ長調(D.960)では、空間に放たれたまろやかな響きが実に心地よく、いつまでもいつまでも、そのゆらゆらふわふわととした心地よさに身を任せていたいと感じさせるほどの至福の時間でした。心の奥にまで染み入るようなピアニッシモが、微妙に変化を見せながら、美しい響きが連綿と漂っていくさまは、まさに「さすらい」のシューベルトに相応しいものだったと思います。正直なところ、体力に自信がない状態でしたから、あの長大なシューベルトを聴くことができるのだろうか、と少し不安に思っていたのですが、実際には快適なソファーにも座ってお部屋で寛いでいるような気分になり、コンサートホールにいることすら忘れてしまうほど、リラックスすることができました。多分、どんな薬よりも心身の疲れに効いたのではないでしょうか。
2010年10月16日
-
本当に視力回復?
この年になると毎年の健康診断が憂鬱の種。検査項目も増えますし、すっきり「異常なし」というわけにもいきません。やれ胃カメラだの視野検査だのと、追加の検査を指定され、身体の経年劣化を否応なく思い知らされます。そんな中で、今年ちょっと気分のいい結果が出たのが視力検査。もともと軽度とはいえ近視(+乱視)で、運転免許も「眼鏡等」の条件つき、プロジェクタを用いたプレゼンテーションや観劇時には眼鏡は欠かせませんでした。ただ、ここのところ、裸眼で過ごす時間が増えましたし、先日の旅行でも、眼鏡を持たずに出かけてさして不自由を感じませんでした。内心「軽い老眼かな」と思い込んでいたのです。健康診断の視力検査では、左=1.0で右=0.9という結果。しかも「近い距離も両眼=1.5ですから、老眼じゃないですよ」との看護士のコメントにびっくり仰天してしまいました。「自分では理由が思い当たらない」と看護士にたずねたところ、「ヨガをやっているということだから、その影響じゃないですかね、血流がよくなると視力がよくなるという話も聞きますよ」という返答。これにまたまたびっくりしてしまいました。その後、視野検査のために病院の眼科で再び視力検査を受けましたが、やはり結果は同じでした。職場の仲間にこの話をしたところ、「『視力回復ヨガ』というのがあるらしいですよ」という話を聞いて、驚きは増すばかり。確かに、ヨガを始めたことで基礎代謝と筋肉量が上がり、高校生の頃の体型を維持できるようになったのは事実ですが、視力回復という予期せぬ副産物まであったのだとしたら、これは本当に嬉しいことですね。ヨガも、やり方を間違えれば怪我をすることもありますし(事実ときどき首やかかとを痛めたりしています)、無理は禁物なのでしょうが、適度に継続していくと何となく効用はありそうで、「当分やめられないな」と思う今日この頃です。
2010年05月29日
-
写真をいくつかアップロード
旅行の写真は膨大な量に及び、まだまだ整理には時間がかかりそうですが、取り急ぎ気に入ったものをいくつかアップロードしてみました。こちらに入れております。http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=58318&key=1861803&m=0 画像からムービーを作る機能があるそうで、DVDで再生できるムービー作りでもしてみようかと考えているところです。
2010年05月09日
-
路線バスのすすめ
今回の旅では、自分なりにいくつかの目標を掲げていたわけですが、そのうちの一つに「パリの路線バスを乗りこなす」というものがありました。事前に、パリの路線バスに関するテレビ番組を見ていたこともそのきっかけだったのですが、行ってみた結論として、やはり「パリ市内を移動するなら断然路線バスがおすすめ」です。乗客数に比して運行本数が少なく、大混雑・大渋滞の京都の路線バスに、普段から辟易としている私ですが、バス専用レーンが整備され、運行本数も多く、比較的清潔なパリの路線バスは、うってかわって非常に快適です。メトロやRERは、何といっても暗いし、旧型車のドアは重いし、いつも混雑気味、少し治安にも不安のあるイメージですが、路線バスにはその心配は一切不要。よく見ると地元のお嬢様方が好んで利用している感じでした。カルネやモビリスといったチケット類や、路線図を手に入れ、あとはちょっとしたコツさえつかめば、これほど小回りのきく移動手段はありません。景色を見ているのも楽しいし、すっかりバス・ファンになって帰ってまいりました。パリだけではなく、ロンドンでもほとんど路線バスを利用しておりました。以前訪問したときと比べると、ワンマン・カーが増えているようで、車掌さんがいない車内に一抹の寂しさはありましたが、ダブル・デッカーの車窓からの眺めはやはり最高ですね。こちらも大のお気に入りです。
2010年05月09日
-
乱高下する気温について行けず
今年の春はとりわけ寒暖の差が激しかったように思いますが、出張先→海外旅行中にも気温が「乱高下」し、身体が悲鳴をあげてしまいました。久しぶりに風邪をひき、声が出なくなりましたが、この土日でどうにか回復しそうです。4月の最終週は、出張で札幌・真駒内に行った後、そのまま休暇に入り、パリ→ロンドン→パリを旅行しておりました。札幌はまだ真冬の寒さだったのですが、出国してみたらいきなり真夏の暑さ、ベルサイユでは暑さに参ってヘロヘロになってしまいました。その後、パリの街中がお休みになる5月1日を有効に過ごそうと、鉄道でロンドンに脱出したところまではよかったのですが、こちらは真冬の寒さに逆戻り、パリに舞い戻ってみたら、こちらもあの暑さはどこへ行ってしまったのだろうと思うほどの寒さで、とうとう風邪をひいてしまいました。帰りの飛行機では、マスク等の自衛策に出ましたが、その甲斐むなしく症状はひどくなるばかり。そして帰国してみたら、いきなり「真夏日」というではないですか!さすがの私も、ダウンしてしまいました。撮ってきた写真やお土産の整理もまだ終わっていない状態ですが、記憶が薄れないうちに、少しでも記録をとっておきたいなと思う次第です。
2010年05月09日
-
心に残る除夜の鐘 ~ 謹賀新年
明けましておめでとうございます。本年も、よろしくお願い申し上げます。昨年もいろいろなことがございましたが、終わりよければ全てよし、とは本当にその通りで、最高の大晦日を過ごすことができ、我ながら満足しております。大晦日といえば除夜の鐘ですが、今回なんと自分で鐘をつく体験をいたしました。とあるお寺(世界遺産にも登録された誰でも知っている近所の有名寺院)の関係者のはからいで、何人かで交替で鐘をつくというもの。最近では住職さんがいらっしゃらないので、お寺を管理する関係者とその知人で除夜の鐘を鳴らすことになっているのだそうです。関係者の方曰く、「昨年は108ちゃんと数えていなかったから、今年は真面目に数えようね…」だとか、「一人5回はいけるかな…」とか、まあ、とても●●寺の除夜の鐘とはとても言い難いきわめてアバウトなもの。とはいえ、その寺院よりも古くから伝わるという鐘(某家伝来の鐘で鎌倉時代のものとのこと)の音はとても美しく、年の終わりにとても清々しい気分になりました。その後、平野神社にて新年を迎え、その足で北野天満宮にも参拝、ひと眠りしてお昼からは今宮神社と下鴨神社にも初詣に出かけました。お餅を美味しくいただくには、全て徒歩で詣でるというのが基本!昨晩から本日にかけての歩行距離は、計13.1キロでした。新しい年が、みなさまにとって幸多きものになりますように。
2010年01月01日
-
早朝の鹿苑寺
天気予報によると朝一番晴れるらしいということでしたので、すぐに行ける近いところで撮影してまいりました。他所は、まだ本格的な色づきではないようですが、ここはそろそろ見頃を迎えつつあるようです。早朝の光に照らし出された紅葉を撮影するのは、気分がいいものです。境内では、お掃除の人や搬入作業中の土産業者さんが忙しくされていて、やや申し訳ない気もしたのですが、この時間だから撮れるありがたさを味わってまいりました。最近忙しくて未整理だった写真も一緒にアップロードしています。北鎌倉の明月院と三井寺の写真もこちらに入れておきました。http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=58318&key=1861803&m=0
2009年11月15日
-
思いのほか豪華な休日
しばらく続いた雨模様でしたが、願いが天に通じたのか、この週末は絶好の行楽日和でした。コスモスが見たくなって、気軽に行ける亀岡まで足を伸ばしました。電車と湯の花温泉の送迎バスで、お手軽に済ませるはずが…、終わってみると豪勢な休日になってしまいました。烟河では自家農園野菜や地元野菜を中心とした里山ランチバイキング、亀岡駅前の広大なコスモス園では花の撮影、そして帰路は船で保津川下り…。保津川下り、実は、生まれてはじめての経験でした。地元民とはそんなものです。落合の岩場や保津峡駅から船に向けて手を振ったり、国道9号線でトラックを使って亀岡まで船を運ぶのを見たり(3隻重ねてトラックで運ぶのです!)、電車で亀岡に戻る船頭さんを見たり…。それが私にとっての普段の保津川下りでしたから、実に楽しかったですね。見慣れた景色とはいえ、ゆったりとした川の流れ、時折飛び散る水しぶき、ひんやりとした川風、本当に新鮮でした。それにしても、船頭さん、重労働ですね。あれを日に何回もやるとしたら、とんでもないことです。写真はコスモス園で撮影したものです。それにしても、今日はどこもいつも比較的すいていましたね。人ごみに慣れすぎてしまったせいか、保津川下りも(待ち時間ほとんどなし!)嵐山界隈も、びっくりするほど人が少なく、少々拍子抜けでした。天竜寺近くにお店を出している知り合いのお漬物屋さんも、「今日はお月見のせいか昼間は人が少なかったわ…夜の大覚寺は混むかもしれんけど…」とのことでしたから。やはり、みなさん紅葉の頃を狙っているのでしょうかね。
2009年10月04日
-
美しい青空に誘われて
連休に入り、毎日抜けるような青い空が広がっています。仕事が忙しかったため、予定が立てられず、連休中の宿泊旅行は断念したのですが、家でゴロゴロするにはもったいない程の美しい青空に誘われて、ついフラフラとその辺りを散策しております。昨日は、墓参の後、静原・大原まで足を伸ばし、彼岸花と咲き始めたコスモスを見ながら、里の休日を満喫。大原に行くときにいつも利用している駐車場のおじさんから、もぎたてのミニトマトや富有柿をいただいたり、里の駅でつきたてのお餅を焼いてもらったりして、のんびりとした時を過ごしました。たまには体を動かさないと、ということで、音無の滝まで歩きましたが、運動不足解消には少々距離が足りなかったかも…。今日は、新しく買ったカメラの撮影練習ということで、ご近所でいろいろ試し撮り。上の写真もその一つ、妙心寺境内で撮影したものです。
2009年09月20日
-
お気に入りの画家 クロード・ロラン
お気に入りの画家を一名挙げよ、と言われたら、実は「クロード・ロラン」の名前を真っ先に挙げることでしょう。今回のルーブル美術館展(京都市美術館)に、彼の作品が含まれていると知って、久しぶりにとれた週末の休み、混雑覚悟で出かけてみました。混雑の原因は、ひょっとするとフェルメールゆえだったのかもしれませんが(最近フェルメールを何点見たでしょうか…多分生きているうちに全部見終わるのではないかというほどよく来ますね…)、私のお目当ては断然(!)逆光の画家クロード・ロランでした。もともと、クロード・ロランという画家に注目するようになったのは、ロンドンのナショナル・ギャラリーで見た「アモルの宮殿の前のプシュケ」の魅力にとりつかれたことから。誰にも真似できない乳白色の光の表現。今回の展覧会で出品されていた「クリュセイスを父親のもとに帰すオデュッセウス」にも遺憾なく発揮されていました。ミュージアムショップでこの作品のお土産を買おうと思ったのですが、あの何ともいえない淡い光にみちた色彩は、生でなければ味わえない、と思ってしまい、断念しました。まだ会期終了まで間があります。もう一回見に行こうかしら…。
2009年08月02日
-
パワー・ヨーガの効用?
仕事が忙しかったことや、精神的に辛い状況が続いたこともあって、みるみるうちに体重が減り、気がつくと大学1年生頃の体格に戻っておりました。そうなると、人間欲が出てしまうもの。きっかけはともあれ、せっかく痩せたわけですから、ここは健康的な体重維持を心がけようと思い、パワー・ヨーガなるものを始めてみました。近所のフィットネス・クラブのレッスンに時々通ったり、市販のDVDも利用したりして、楽しく続けております。その効用でしょうか、いくつか嬉しい状況が!寝付きがよくなったこと、片頭痛に見舞われなくなったこと、生理痛がなくなったこと、風邪をひきにくくなったこと、お腹をこわしくにくくなったこと等々。若くはないので、怪我に注意しながら、無理しない程度に続けてみようかな…と思っております。
2009年08月02日
-
やはり花見は欠かせない~紅しだれ~
新年度を迎え、最も忙しくなる季節がやってまいりました。紅しだれが最高に美しいときなのに、青空が広がる気持ちのよい快晴なのに、今日は休日出勤をしなければならなかったのでした。しかし、どんなことがあろうとも、花見だけは欠かせない…、ということで、出勤前に上賀茂神社に寄りました。見事な斎王桜の美しさに酔ったまま、職場に向かうのも悪くないものです。
2009年04月11日
-
桜だより
今年も、桜の季節がめぐってまいりました。残念なことに、4月以降仕事が忙しくなりそうな見込みですが、「桜の期間は案外長い」ものですから、今のうちに楽しむことにしようと心に決めました。平野神社で、こんな愛らしい花を見つけました。「陽光」という桜だそうです。他の写真は、例によって、以下のサイトに掲載しています。http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=58318&key=1861803&m=0
2009年03月29日
-
ハンブルク・バレエの「人魚姫」
ジョン・ノイマイヤー率いるハンブルク・バレエの来日公演に出かけてまいりました。前回来日時の「ニジンスキー」の衝撃以来(そのときの記事はこちら)、すっかりノイマイヤーの世界の虜になっている私ですが、今回の「人魚姫」で、いよいよ彼の才能の豊かさの前にひれ伏してしまいました。何よりも心揺さぶられたのは、その濃密で演劇的な演出です。舞台上のダンサーはもはやダンサーというよりもアクターであると言ってよいでしょう。今回の「人魚姫」を演じたシルヴィア・アッツォーニは、人間ばなれした魚の感覚と、少女のような可愛らしさを余すところなく表現していて圧巻の一言。人間の世界を西洋的な様式美で描く一方、人魚姫の属する海の世界は東洋的な様式美をとりいれる工夫(日本の歌舞伎・文楽からの着想だとか)もなかなかなもの。空間演出も、曲線を活かした海の世界と、鋭い直線で構成された人間界といった対比が見られて、興味深いものがありました。照明・美術・衣装、どれをとっても、隅々に至るまでノイマイヤーの知性と美意識が貫かれており、その天才的な総合芸術家ぶりに圧倒されてしまいました。
2009年03月01日
-
今週の北野天満宮
ほとんど毎週のように北野天満宮に出かけておりますが、見るたびに異なる花が咲く今の季節は、本当に飽くことがありません。枝垂梅も咲き始めましたし、まさに今が盛りというべきでしょう。
2009年02月15日
-
鹿苑寺方丈
現在公開中の鹿苑寺方丈に行ってまいりました。こちらの方丈のすばらしいところは、手前に広がる枯山水の向こう側に、有名な鏡湖池を望むことができるところ。趣の異なる庭を同時に目の前にする贅沢さに圧倒されます。写真は方丈南側の枯山水。この西側に、鏡湖池が広がっております。方丈の西側には起伏に飛んだ庭が、北側には陸舟の松と称される見事な松がありました。身近なところに、こんな見事な風景があったのかと、感嘆することしきりでした。
2009年02月15日
-
本日の散歩道
うらうらとあたたかい春の日差しに包まれた今日の午後、週末恒例の散歩に出かけました。とはいえ、月曜日から仕事が忙しくなりそうなので、今日は近所で済ませました。行き先はこちら。画面右端にヒントがありそうですね。
2009年02月15日
-
梅香に酔う
立春を過ぎ、光の色が少しずつ変わってきていることを感じます。そして、北野天満宮はいよいよ梅本番。今日はゆっくり梅香に酔ってまいりました。本日のお気に入りは白梅。鮮やかで華麗な紅梅もすばらしいですが、何といっても白梅の凛とした清楚な美しさは、筆舌に尽くしがたいです。
2009年02月08日
-
北野天満宮の蝋梅
冬型の気圧配置が強まり、今朝は随分と冷え込みました。こんな寒さ厳しい季節にけなげに咲く花が蝋梅。北野天満宮境内に見事な蝋梅の木があり、毎年その凛とした美しさと芳香を楽しんでおりますが、実はこの花、魅力的に撮影することはとても難しいと感じています。今年こそは、と思って今日もがんばってシャッターを押しておりましたが、この花の魅力を表現するところまでは到底達することができませんでした。比較的気に入った2枚を以下のページにアップロードしました。多少花の質感が感じられる写真になったかしら、とは思っているのですが、いかがでしょうか。http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=58318&key=1861803&m=0
2009年01月24日
-
初春の花(2)
こちらは、平野神社の境内で見つけたものです。本当に小さくて可憐な花です。
2009年01月04日
-
初春の花(1)
こちらは、北野天満宮境内で撮ったものです。まだ大半が蕾ですが、ちらほら咲き始めました。
2009年01月04日
-
今年の初詣
今年のお正月は、冷え込みも厳しく、どんより曇天、時雨もあったりと、お天気には恵まれませんでしたので、いつもの年よりは多少近いところでの初詣となりました。今年は、岡寺にまず参拝、近くの石舞台古墳にも足をのばしましたが、とにかく寒いので、飛鳥散策はそこで打ち切り、本格的な飛鳥めぐりは後日にしようと、下見気分でバスにゆられておりました。位置関係はざっと把握できましたので、日差しが厳しくならない程度に暖かくなった頃にでも、今度は徒歩ないしサイクリングでまわろうと思っています。橿原神宮に着いた頃には、雨が霰に変わってきて、寒さとのたたかいになってまいりましたが、これで帰るのはいかにももったいないので、久しぶりに西の京に寄り道することに。唐招提寺と薬師寺に寄りましたが、悪天候の正月の夕方だと、人出もさほどではなく、京都では見られない白鳳・奈良時代の文化財を堪能することができました。薬師三尊像は、遠征(!)から戻ったばかりだからなのでしょうか、お風呂上がりのように磨かれているなあという印象でした。お正月だと、秘仏の吉祥天像も公開されているとのことで、かなり得した気分になりました。とても美しい天女さまでした。それにしても笑えたのは、薬師寺から帰宅して24時間以内に、「まじめに復習しなさい」と言わんばかりに、「薬師寺~白鳳伽藍の一年~」が放映されたことでした。おかげで、みっちり復習させていただきました。
2009年01月02日
-
年の瀬
慌ただしく今年も過ぎゆこうとしています。北野天満宮と平野神社の境内を通り抜けて、お気に入りのフランスパンを買いに出かけました。神社の境内は、どこもお正月の準備で大忙し。真新しい注連縄、蕾が膨らみはじめた梅の枝に「おみくじを結ばないように」と注意喚起する短冊。大人たち十人ほどが、かけ声も高らかに可動式の建屋を設置していましたが、初詣客に御神酒をふるまうためのものでしょうか。ふと見まわしてみると、先日訪れたときよりも、どの梅も蕾が膨らんでいて、新しい年がすぐそこまで到来していることを告げるかのようでした。梅よりも早く開花する蝋梅の蕾、こちらはもうかなり大きく膨らんでいて、まだ黄色い葉が枝に沢山残っているのに、一輪二輪綻びはじめていました。決して派手ではないけれど、「寒空に一足先に花を咲かせ、芳香を漂わせる姿がいじらしい」と評した人の言の如く、花言葉は「先導」「慈愛」なのだそうです。平野神社の境内では、十月桜や寒桜が寒風にも負けず、小さな花弁を開かせていました。小さいけれど、開きはじめた花の美しさはえもいわれぬものがありました。景気も冷え込んでしまった年の瀬ですが、花木たちに少し元気をもらいました。新しい年に希望を託しつつ。
2008年12月28日
-
西宮での休日 ベルリン・フィルハーモニー来日公演
紅葉三昧の昨日に続いて、本日は西宮でこれまたしっかり遊んでまいりました。オープンしたばかりの西宮ガーデンズでショッピングを楽しんだ後、来日中のベルリン・フィルハーモニーの演奏会に酔いしれてまいりました。余談ですが、西宮北口駅前の高松町のあたりは、震災復旧時の担当エリアの一つでした。あの界隈の被災状況を身をもって知っているだけに、次々と建設される諸施設を見る度に、ある種の感慨のようなものを覚えます。さて。今年の秋の目玉と思っていたベルリン・フィルハーモニーの来日公演ですが、生まれてはじめてオーケストラの演奏を大らかな気持ちで楽しむことができました。オーケストラの演奏会に出かけると、心の中でいつもどこかしら『ダメ出し』を出している自分がいるのですが、今日は全くそんな気持ちを抱くこともなく、ただひたすら、響きの美しさと豊かな表現力に感動しておりました。どの一瞬をとっても、音楽の響きと流れの中で、構成員の一人一人が、音楽における自らの役割を見事に演じていく ―あるときは溶け込み、あるときは対峙し、またあるときは呼応する― これがフィルハーモニーの極意なのか、と実感できたひとときでした。そして、意外にも、世界のスーパースターが集まる交響楽団というよりは、正しく欧州の美を体現する伝統的な音楽集団であると解した方がしっくりくることも知ったのでした。ラトルとのコンビということについても、なかなか面白いものを見せていただいた、という思いが強いです。ラトルも、オーケストラに任せるところは思い切って任せているようでしたし、ラトルが演奏中に何らかの合図を出すと、必ずそのパートが意味のある音色で応えてくるあたり、これが一流ということなのかと思った次第です。楽曲(本日はブラームスの交響曲の第1番&第2番)の印象ですが、流麗な第1番、エモーショナルな第2番といったところでしょうか。重厚長大で劇的イメージの強い第1番において、ブラームスの音楽はかくも麗しいものかと思い知らされたのも驚きでしたし(安永さんのソロで落涙!)、続く交響曲第2番では、多彩な音色と感情のうねりの見事さに我を忘れてしまいました。
2008年11月30日
-
秘策は徒歩
紅葉を愛でたいけれども、京都市内の人ごみは恐ろしいものがありますし、今年は松磯山荘も含めてどうも今ひとつかな、と思っていたのですが、バスの定期券を買いに行くついでもありましたし、日頃の運動不足解消も兼ねて紅葉狩の散歩に出かけてまいりました。驚くなかれ以下の事実!スタート:正午・JR東福寺駅自宅着:17時10分交通費:140円(京都-東福寺)本日の「通過」箇所東福寺・蓮華王院南門・養源院・智積院・妙法院門跡・大谷本廟・清水寺・法観寺・長楽館・円山公園・大谷祖廟・知恩院・青蓮院門跡・平安神宮・南禅寺・永観堂・金戒光明寺・真如堂・吉田神社・知恩寺・糺の森・相国寺こんな短い時間でこれだけまわれるの? - ええ、まわれますとも。人ごみは? - 多少混雑したところもありますが、さほどでも。秘策は? - 全行程徒歩だから。早足で歩くことがポイント。今日は、あくまでも「運動不足解消」が目的でしたので、庭園鑑賞等はしませんでしたが、撮影枚数114枚に及びましたし、燃えるような紅葉を堪能いたしました。それにしても不思議なもので、百万遍のあたりから少し疲労を覚え始め、相国寺を抜けた頃から、どっと疲れが出てしまいました。不審菴の場所を聞かれた頃には、すでにヨレヨレになっていて、あまり上手く説明できませんでした。ごめんなさいね。きちんと小川通り上ると教えてあげればよかった、と後悔してみたりして…。やはり、自宅が近いと思うと、気が緩むのでしょうか。本日の写真、少しだけ以下にアップロードしております。http://www.photohighway.co.jp/AlbumPage.asp?un=58318&key=1861803&m=0帰宅後、地図上で歩行距離を測ったところ、16.9kmでした。やはり、私の場合、12kmを超えると急に疲れるものらしいです。
2008年11月29日
-
小倉山から渡月橋を望む
小倉山 峰のもみぢ葉 心あらばいまひとたびの みゆきまたなむ写真は、百人一首のこの歌でも有名な小倉山からの眺めです。サイズを圧縮しておりますので、わかりにくいかもしれませんが、渡月橋は「人また人」で恐ろしいことになっております。
2008年11月22日
-
天の声が聞こえる瞬間
セザール・フランクの作品を聴きたいと思うとき、それは決まって自分自身が苦しみの淵にあるとき。「ヴァイオリン・ソナタ」にしても、「前奏曲、アリアと終曲」にしても、彼の作品には、身の引き締まるような厳しさの中に、深い祈りの世界があるような気がします。何より、彼の作品の中には、必ず「天の声が聞こえる瞬間」があります。一筋の光明を見出して思わず涙する…。それは、心の垢が涙とともに洗い流される瞬間ではないでしょうか。
2008年11月07日
-
プーランク弾きのつぶやき
とにかく音が多い平易なメロディなのにもかかわらずよくよく見ると内声に音が多い伴奏もかなり複雑な譜面になっている指づかいにも苦労するでも難しそうに見えないし聞こえないショパンの協奏曲の方がずっと譜面は単純だ悔しいが誰もショパンの方が簡単だなんて思わないだろう譜面通りに音を保持しようとすると指がちぎれそうになるきっとプーランクという人は手がやたら大きかったに違いない日本人女性の手には酷な作品だプーランクという人はやんちゃなお坊ちゃまだったらしいだから突如ぶっきらぼうな場面があらわれるでもさすがは根っからのパリジャンだ何より都会的でセンス抜群魅惑に満ちた旋律が次から次へとわいてでるメランコリックなメロディをかかせたらもう絶品だがそのメロディは長続きせず突然破られるどんなに悩ましげな部分でもルバートはご法度だ多少揺らいだとしてもそれはカッコつきのルバートそもそもルバートはダサいのだプーランクという人は自身相当の弾き手だったらしいそのせいか速度指定は容赦なく早いメトロノームの指定もかなり早いだが誰かさんのようにメトロノーム指示を無視してもいいということはないらしい冗長という言葉はプーランクには無縁であるだから大抵の曲の演奏時間はかなり短いきれいなメロディもだらだらとは続かないフレーズの終わりもズバっと途切れる途切れるだけじゃなく休符までついてくるこの休符で息継ぎができるのはありがたい休符の後は脈絡なく新しい要素に移ってしまうその実結構気まぐれだしかもときどき計画性のない迷ったようなコーダを書くしかもコーダの途中で「もうやーめた」と言わんばかりに曲が終わるプーランクという人の作品は実に不思議だだが間違いなくユニークでお洒落だそこがたまらない(とある演奏会のプログラムノートに寄稿したものです)
2008年09月07日
-
秋の気配
五山の送り火が終わったら夏休みもあと少し、急に秋の気配が訪れる…。これが、子供の頃からの実感です。今年はいつになく酷暑だったとは思いますが、それでも送り火が終わると、空には秋の雲が広がるようになるから不思議です。日が暮れた今、気がつくと虫の音が聞こえています。今日の京都は、きびしい日差しは残っているものの、空気は澄み渡り、風も心地よく、そぞろ歩きたくなるような気候でした。日差しを避けるにはどこがよいか、明日からの一週間を考えて手軽に散歩できるところはどこか、と考えて選んだのが竜安寺でした。ここは木陰がとても多く、夏の日曜日の午後を過ごすには最高の選択でした。
2008年08月17日
-
下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐる旅(3)
【唐津】充実感いっぱいではありましたが、とにかく先を急いだため、慌ただしく太宰府を後にして、向かった先は、眺望と唐津焼で知られる城下町唐津でした。唐津に行くことにしたのは、以前何度か出張で福岡へ行った折、唐津へのアクセスが案外簡単であることを知ったからだったのです。地下鉄空港線からそのままJR筑肥線へと続くこの路線、地上を走るようになってからというもの、車窓からは博多湾に能古島、唐津湾に虹の松原と次々と美しい風景が続き、お天気にも恵まれて本当に目で楽しむ旅になりました。夕方4時頃に唐津駅にたどりつきましたが、最終の市内循環バスが5時過ぎであることを知り、これに乗らないと宿のある東唐津に行くのが大変になりそうでしたので、唐津城下を大汗をかきながらまるで競歩のような足取りで歩きまわりました。とはいえ、さして広い城下町でもありませんでしたから、市内循環バスまでの間に、唐津くんちの曳山展示場をはじめ、唐津神社・埋門ノ館・時の太鼓・旧唐津銀行本店・西の浜をチェックする時間はなんとか確保できました。宿へ入ってからも、松浦橋から唐津城を眺めたり(もれなく火力発電所も見えてしまうことには苦笑を禁じえなかったですが)、高島を望む浜辺で貝殻を拾って遊んだりする時間は十分ありました。文政年間以降唐津神社の氏子たちが奉納したという、漆の一閑張で作られた色鮮やかな14台の曳山は、豪壮華麗でありながら、どれもどこかユーモラスな表情が可愛らしかったです。鯛の目も獅子の目も、まるでアニメキャラクターのような親しみやすさにあふれ、心和むものがあります。翌朝、虹の松原を少しだけ散策した後、藤の見事な唐津城へ。唐津城からの眺望は、東西南北どちらもなかなかのもので、特に玄界灘にぽっかり浮かぶ島々が本当に美しかったです。宝当神社があるという高島に渡ることも考えましたが、定期船の便数が案外少なく、旅程の関係もあって今回は天守閣からの眺めを楽しむだけに終わってしまいました。【福岡】出張等で何度かこの町に来る機会があったのですが、観光となると櫛田神社や旧日本生命九州支店(昨年夏の記事はこちら)にちらっと寄った程度で、いわゆる筑前黒田52万石の威容について触れたのは今回がはじめてのことでした。今までの出張では、那珂川の東側にある港湾商業都市「博多」のイメージが強かったですが、巨大な大堀(現在の大濠公園)に、福岡城址のあまりに巨大な城郭に驚いた(むしろ「驚き呆れた」)というのが正直なところです。近代に入って陸軍第12師団が置かれたり、国民体育大会による運動施設が設置されたりと、いろいろな時代を経てきたようですが、ようやくこの史跡が史跡らしく認知されるようになってきたのでしょう、筑紫の鴻臚館跡(平和台球場のあったところ)では着々と発掘が進んでいるようでした。この鴻臚館ですが、他の平安京や難波についてはあまり詳しいことが分かっていないようですし、唯一遺構がはっきりと遺されている史跡なのですから、今後の発掘の成果に大いに期待したいところです。
2008年05月05日
-
下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐる旅(2)
【太宰府】下関を後にした私は、夜博多の町に入り一泊、翌朝ラッシュ・アワーの勤め人達を尻目に(そんな私は有給休暇中!)、念願の太宰府詣でに出かけました。お正月に道明寺天満宮に参拝したわけですが、結局太宰府よりも道明寺詣でが先になったことは、先日ここで書いた通りです(そのときの記事はこちら)。菅原伝授手習鑑でおなじみの天拝山の位置関係も確認でき、すっかり心は菅公伝説の世界に浸りきっておりました。西鉄太宰府駅から天満宮に至る参道は、梅が枝餅を食べさせるお土産屋さんが軒をつらねていて、北野よりも道明寺よりもさらに賑やかな門前と感じました。心字池に架かる太鼓橋・平橋・太鼓橋がこれまた見事で、まだ参拝客の少ない朝の境内でひたすらシャッターを切り続けていた私でした。小早川隆景が造営したという本殿も、北野同様(こちらは豊臣秀頼造営)桃山様式ですが、見慣れた北野の社殿とはまた異なる豪壮華麗な建築がひときわ印象的でした。山に抱かれた緑の多い地域、歩きながら一瞬大和の山の辺の道に入り込んだのかという錯覚にとらわれることもありました。太宰府は、確かに大和の佇まいとどこか通じるものがあるような気がします。特に、観世音寺・戒壇院・太宰府政庁跡の周囲は、古代の息吹に満ち満ちていて、この地に大宰府が置かれたのも頷けると思うことしきりでした。天智天皇の発願によるという観世音寺、東大寺・下野の薬師寺とともに知られている戒壇院、いずれも静寂のなかにときを超えてそこに立つ歴史の重みがあり、はるばるここまで足をのばしてよかったと何度思ったことでしょう。写真は、戒壇院の門前です。我ながら、いかにも春らしい光景が撮れたと思う1枚です。他の写真は、以下にアップロードしています。 ↓http://www.photohighway.co.jp/AlbumTop.asp?key=1861803&un=58318&m=0あと、旅の復習にもってこいのページを見つけました。九州国立博物館(今回こちらに寄る時間はありませんでしたが…)による太宰府紹介のページです。http://www.kyuhaku-db.jp/dazaifu/historic/index.html
2008年05月04日
-
下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐる旅(1)
大型連休も後半に入り、気温もぐんぐん上昇してまいりました。連休前半、2泊3日で下関・門司・太宰府・唐津・福岡をめぐってまいりました。今日あたり、博多どんたくで福岡あたりは恐ろしい人出でしょうが、連休前半はさしたる人ごみにも巻き込まれることもなく、ゆったりとした気分で、しかし(捻挫した足首にも頓着せず)旺盛に、ひたすら歩きまわってまいりました。写真を20枚ほどピックアップして、こちらにアップロードいたしましたので、よろしければご覧下さい。http://www.photohighway.co.jp/AlbumTop.asp?key=1861803&un=58318&m=0【下関・門司】まずは、さまざまな表情を持つ下関へ。朝一番落ち着いた佇まいの城下町長府へ寄りました。これほど情緒と清潔感あふれた城下町はなかなかないと思います。長府藩侍屋敷長屋・忌宮神社・菅家長屋門・古江小路・長府毛利邸・功山寺を歩いてひとまわり。人通りもまばらで、どこも訪れる人も少なく、「人だらけの京都から逃れて正解」と実感できたひとときでした。功山寺山門前では美しい新緑の写真を撮ることができてすっかり満足。また、最古の禅寺様式を持つという国宝の功山寺仏殿は、造りがとても面白かったのですが、近くに送電線があったりして、なかなか思うような撮影ができなかったのが少し残念でした。そういえば、世界遺産登録されている宇治上神社も、社殿のすぐ傍に送電鉄塔が立っていますが、文化財と社会インフラ、どちらが大切と一概には言い切れないだけに、複雑なものがありますね。次に訪れたのは、唐戸地区。途中たまたま乗った路線バスが、かつてロンドン市内を走っていたというあの赤い2階建てバス。旧下関英国領事館内では、ロンドンバス路線化記念ということで、英国政府発行の観光ガイドブックが配布されていましたので、そちらもちゃっかりいただいてまいりました(重かったですが…)。向いの唐戸市場だけは、新鮮な海産物めあての家族連れも多く、人また人の賑わい。しかし、人だらけの京都で「百戦錬磨」の私には、その程度の人ごみに物怖じなどいたしません。しっかり美味しいものをたらふくいただきました。唐戸市場の人ごみにひきかえ、日清講和記念館、旧秋田商会ビルあたりは、訪れる人も案外少なく、静かそのもの。落ち着いて史跡めぐりをすることができました。中でも、個人的に興味深かったのは、李鴻章道と赤間神宮内にあった能登守教経の墓所でしょうか。海岸沿いの国道を歩くのは、車の音もうるさく日差しも厳しいと感じたことから、丘沿いのコースを歩いていたところ、偶然見つけてしまったのが李鴻章道。日清戦争の講和条約の清国全権大使であった李鴻章が、危難を避けるために通ったとされるこの道は、徒歩の旅だからこそ見つけられた細い細い小径でした。壇之浦古戦場には、八艘飛びの源義経像とともに、碇をかついだ平知盛像が置かれていますが、赤間神宮の平家一門の墓所の中央に一際大きな墓石で祀られているのは、「見るべきことは見はてつ」と言い残して果てた新中納言知盛ではなく、安芸兄弟を左右の脇にはさんで「おのれら死出の山の供せよ」と入水した猛将能登守教経でした。子供の頃親しんだ平家物語の中で、敦盛最期とともに鮮やかな印象となって残っている能登殿最期のくだりを、しばし思い出しました。義経・知盛像と長州砲展示のある御裳川は、関ヶ原同様歴史上重ねて戦場になった場所のようですが、今は関門トンネル人道の下関側出入口になっているとのこと。ここから、歩いて関門海峡を渡り門司へ入りました。和布刈神社・門司関址・平家一杯水を経て、門司港レトロ地区へとひたすら強烈な日差しの下歩き続けたのでした。門司関は、海峡を往来する人や船を監視したり太宰府と都とを行き来する役人の世話をする拠点だったようで、恐ろしく古い史跡なのにもかかわらず、あまり宣伝もされているようでもなく、その辺の児童公園内にあっけらかんと石碑だけが残されているのが、やや妙な感じでした。むしろ、門司=バナナの叩き売り発祥の地ということなのでしょうか(笑)。旧門司税関・旧門司三井倶楽部・旧大阪商船といった洋館群も、現在では門司港駅以外すべて用途を変え、若者向けのおしゃれなスポットになっているようでしたが、賑やかさの中に、どこか時代の移り変わりを感じ、一抹の寂しさを感じた瞬間でした。門司港桟橋から船で再度唐戸へ渡る頃には、すっかり夕刻となっていました。平家物語に早鞆とうたわれた潮の流れも、頻繁に行き来するタンカー類も何のその、門司⇔唐戸定期船の舵をとるのは、威勢のよさそうなお嬢さん達。時間切れで、満珠・干珠も巌流島も陸からちらっと見るだけに終わりましたが、素晴らしい景観の中に歴史の息吹を感じさせるこの地域は、汲めども尽きぬ魅力にあふれていると思いました。
2008年05月03日
-
西陣の名桜(2)
こちらも西陣の名桜といって差支えないでしょう、私が知る限り、最も立派な御衣黄だと思います。この桜、とても大切にされているらしく、本当に木に力があって、花も素晴らしいです。来週あたり、黄色が抜けて色が変わって来ることでしょう。
2008年04月13日
-
西陣の名桜(1)
今週は本日のみの週休一日でしたが、幸い夕方までは雨も降らず、近所の名桜を愛でることができました。写真の普賢象、以前は知る人ぞ知る桜花だったのですが、最近ではきっとガイドブックにでも載っているのでしょうね、私が見ているほんのわずかな間にも、次々と観光客が訪れていました。普賢象という桜は、本当にかわいらしく、八重桜の中でも、最も好きな品種です。
2008年04月13日
-
捻挫しつつも花見だけは
先週末右足首を捻挫、月曜日にはかなりよくなったと思ったのですが、そこから先がなかなか治らず、まだ階段の昇降に痛みを感じています。しかし、花の季節は今だけですから、無理をしない程度に散歩に出かけることにしました。写真は、半木の道の紅しだれです。ここも有名になってきたようで、恐ろしい人出でした。
2008年04月05日
-
観劇再開
転勤して、あの悪夢のような激務から解放されたので、少しずつ趣味を復活させつつあります。といっても、年度決算確定から取締役会・株主総会までの期間、恐ろしく忙しくなることは見えているので、遊んでいられるのは今のうちなのですが…。まずは、3月はじめ兵庫県立芸術文化センターにて、「ペテン師と詐欺師」の再演を観てまいりました。実は、この作品、前回の初演も観ているのですが、キャストに若干不満があったため、あまり良い印象はなかったのです。しかし、今回は全体に舞台の質が上がり、見事にお口直しができました。喜劇というのは、観ている方は楽しいですが、演じるのはとても難しいのだと思います。今回、お腹の底から笑うことができましたが、それだけ演じている人たちの熟練の技があったということなのでしょう。それにしても残念なのが、この舞台ではお元気そうだった愛華みれさんのリンパ腫による降板が報道されたこと。早く快癒されることを祈るばかりです。3月下旬には、妹と一緒にシアタードラマシティにおける星組公演を楽しんでまいりました。スタンダールの『赤と黒』、私にとっては中学2年生の頃から何度も繰り返し読んだ小説の舞台化ということで、自分の中にある作品の印象と舞台との間にかなりギャップがあるかもしれないと思っていたのですが、さすがに主役のジュリアン・ソレルを演じた安蘭けいの人物造形の確かさには感心しました。原作もかなり読みこんでいるように見えました。少し残念だったのは、マチルド役の演技でしょうか。体当たりな演技には好感も持てましたが、やはりこの小説の後半は、いわゆる「心理戦」なのですから、そのあたりのきめの細かさが欲しかったですね。
2008年03月30日
-
天王山めぐり
運動不足解消と花見を兼ねて、大山崎まで散歩に出かけてまいりました。春休みゆえか、親子連れのハイカーも多かった気がします。子供のうちから山道に親しんでおくことはとてもいいことですね。毎日天王山の前を電車で通り過ぎていますが(大抵熟睡していますが)、身近な通勤ルートにも実は見所は満載、駅前に唐突に存在する妙喜庵(かの有名な国宝の待庵のあるところ)、油祖像のある離宮八幡宮や天王山中腹の自玉手祭来酒解神社(酒解神社)、やたらカラフルな陶板絵図(やはり天下分け目の天王山ですから)等、目をひくものが多いスポットでした。最後に訪れた山崎聖天は、ひっそりとした桜の名所で、すっかりご満悦だった私ですが、花に浮かれて石段下にさらに溝があったことに気づかず、足をとられて転んでしまいました。しばらく動けなかったときには、さすがに焦りましたが、とりあえず足を引き摺りながらもなんとか帰ることができました。しかし、明日からの通勤、この足で通えるのでしょうか?梅田の乗り換えや大阪環状線の乗り降り、考えると少しこわいものがあります。
2008年03月30日
-
年々花見客が増える京都御苑
私がHPで近衛の糸桜を紹介していた頃は、京都御苑も「知る人ぞ知る名所」だったような気がしますが、この頃はすっかり有名になってしまったようで、年々花見客が増えているようです。もう京都市内に「穴場」は存在しないかもしれませんね。あとは、自分で桜を所有するしか…。ということで、来週には松磯山荘の桜を確認に行かなければ、と思うのですが、右足首の捻挫、果たして行けるのでしょうか…?
2008年03月30日
全113件 (113件中 1-50件目)