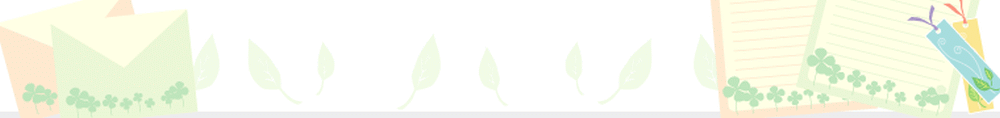PR
カレンダー
お正月に続き、文楽四月公演に出かけてまいりました。文楽に出かけるときは、通し狂言であれみどり狂言であれ、第一部と第二部を続けて鑑賞するようにしております。気がつくと文楽に通い始めて十年以上になりますが、それだけ観客としてのキャリア(?)を積んだからこそできることなのかもしれません。もっとも、終演後は満足感・充実感とともに、かなりの疲労感も味わうものです。疲れているときは、公演中も時々集中力が途切れてしまったり...ということもあります。事実、今回も何度かありました。
今回の演目は、文楽の生舞台で接するのははじめてという演目が多く、何か新鮮な発見が出来るのではないかという期待感がありました。以下、上演順に少しずつ。
第一部の『玉藻前曦袂』は、玉藻前というからには、謡曲『殺生石』を素材にした作品だろうという予想があったのですが、なるほど『殺生石』を思わせる要素が随所にふんだんに散りばめられており、観ている方としては、そういう要素を発見する楽しさがありました。解説書によれば、近世後期の作であるとのことで、なるほど人形浄瑠璃のスタイルが既に確立されていた時期の作品らしく、作劇上の定石、とりわけ時代物の鉄則を踏まえた凝った作りになっていたと思います。さすがに、鑑賞歴も十年選手になりますと、伏線の段階から「ははーん、どんでん返しはこう来るだろうなぁ」という予想はつくもので、その通りに筋が運ぶと内心なかなか痛快でしたね。
続く『心中宵庚申』は、いかにもそのドラマツルギーが近松らしいと感じさせる作品。お正月に続き、ここでも会心の演技を見せたのが勘十郎。この人が演じる世話物の色男には、何というか抗いがたい色気があって、「馬鹿男とはわかっていても、それでも惚れてしまう」のがなぜか納得できてしまいます。そうです、登場人物の女性に共感できてしまうのです。「上田村の段」は、決して大仰に騒ぐことなく、ただ静かに深い情と諦念が表現出来なければ成り立たない難しい演目で、今の住大夫でなければ表現し得なかっただろうと思われます。続く「八百屋の段」における嶋大夫の艶のある声といったら...。
第二部は、これまた妖艶な花ますの勘十郎の演技が見ものの『粂仙人吉野花王』。未亡人なのに(?)、いえ未亡人だから(?)こんなにもなまめかしいのでしょうか?
最後は、これぞ天下の大物悪役「岩藤」を、これまた憎々しげに演じた十九大夫&富助&玉女トリオの印象が強い『加賀見山旧錦絵』。悪役は悪ければ悪いほど、大物であれば大物であるほど、芝居が楽しくなるというものです。悪役万歳!!!
-
ハンブルク・バレエの「人魚姫」 2009年03月01日
-
観劇再開 2008年03月30日
-
観劇週間第3日 座付作者と主演者の不思… 2007年04月30日