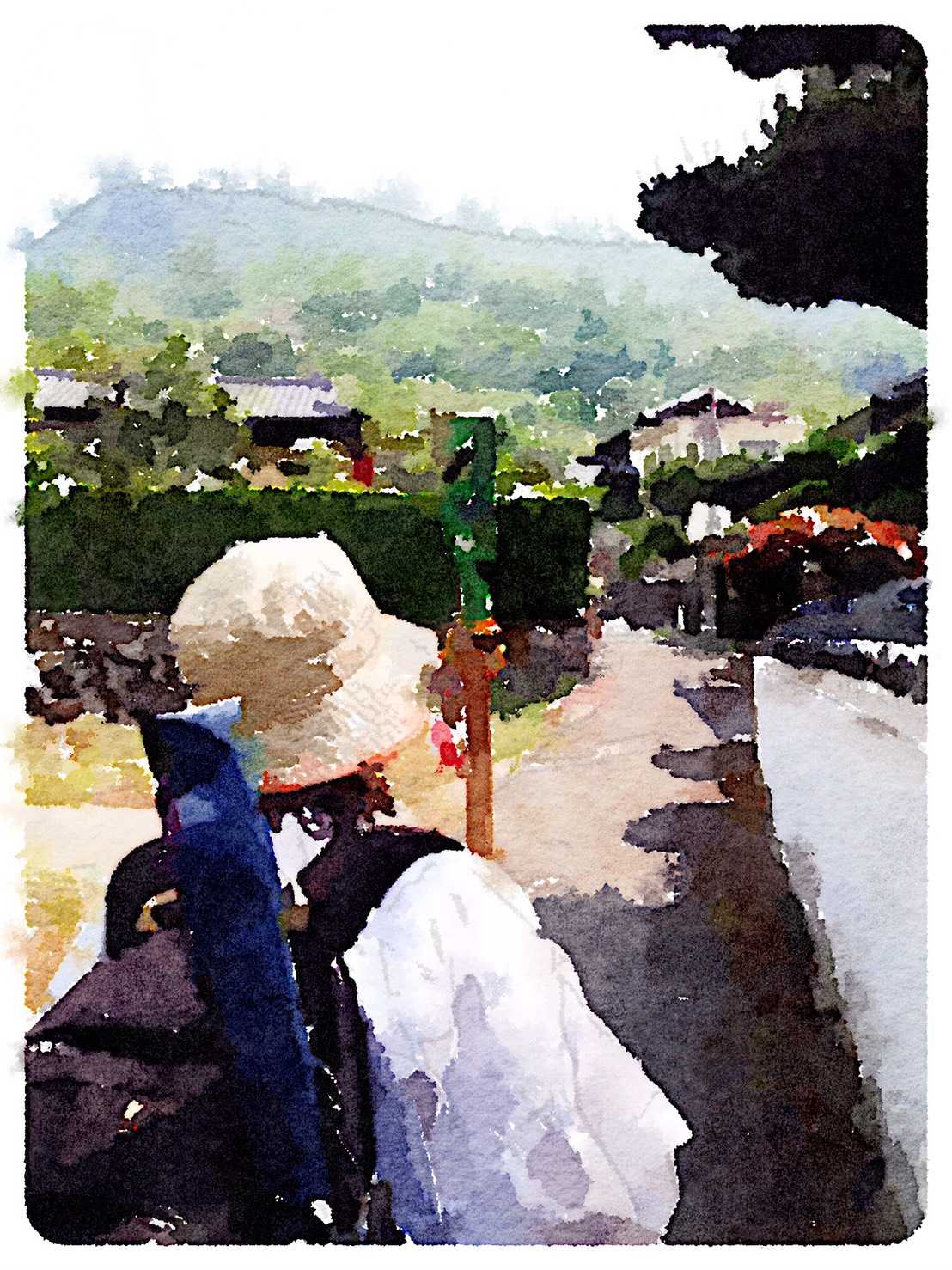コメント新着
カレンダー
 New!
細魚*hoso-uo*さん
New!
細魚*hoso-uo*さん梅宮大社 キシシマ… お散歩うさぎさんさん
エンドウ豆の花
 春の小川7768さん
春の小川7768さん牡丹の花 すずめのじゅんじゅんさん
午後のひとりごと 雪桃7216さん
不思議の国・四国歩… 柊(ひいらぎ)さん
ウォーキング時々へ… 湖山町民さん
龍神さまが住むと信仰されてきた室生山
室生寺は 奈良時代末期に勅命によって 国家の為に創建されました
国宝や重要文化財に指定された貴重な品がた~くさん^^
仏像フアンにはたまらない お寺さんです

~ 風流な表門 ~
奥深い山の中にお寺と門前屋が肩を寄せ合う様に佇んでいます
室生川を渡ると本坊に通じる 小さいけど味のある門のお出迎え
朝晩が冷え込むせいでしょうか
奈良市内のモミジより 枯れモミジです
2日間で どれだけのもみじを見たことでしょう 瞳の中に赤い☆が輝いてます♪
(訪れたのは12月初旬です...)

~ 真言宗 室生寺派 本山 ~
同じ真言宗の 高野山 が かつて厳しく女人を禁止してきたのに対して
女性の済度もはかる道場として参詣を許していたことから
<女人高野> と親しまれてきました

~ 仁王門 裏側 ~
室生寺のシャクナゲ 、 長谷寺のボタン 春の観光名所です
この階段脇が 花々で賑わうようですが、紅葉の秋もなっかなか^^
石段を登ったところに見えるのは 平安時代に建てられた金堂です

~ 鎧坂 ~
段になった石垣の上に建ち、 正面に出入り口がない、 めずらしい御堂だ(相方曰く)
♪平安時代初期の 山岳密教仏堂 で、仏像の為の建物という考え方。僧侶も滅多に入らなかったので正面に出入り口は無く、仏様の為の扉が横(左側)にある
秋の特別拝観中 こんな機会は滅多にない^^☆
内陣に上がり(¥400) モ~ッと近くからお姿拝見

~ 金堂 国宝 ~
御堂の中央には 一木作りの釈迦如来像(国宝)
その背後にある大きな板壁には 帝釈天曼荼羅図(国宝) が描かれている
左側に 文殊菩薩像・ 十一面観音菩薩像(国宝) 右側に 薬師如来像・地蔵菩薩像
横一列に並んだ5像の前には 運慶の作と伝わる 十二神将像 が
勇ましく愛らしく並ぶ

~ 弥勒堂 ~
本尊の 逗子入り阿弥陀菩薩像 と 釈迦如来像(国宝) の前に座って
静かに 般若心経を唱える
お四国を廻っているお蔭で 暗唱が出来るようになりましたよ^^♪
室生寺さんでは 門 と 奥の院 で御朱印が頂けますが
なんと^^; 弥勒堂でも 3タイプの菩薩様の御朱印 がありました
全部頂くと・ ・・¥300x5種類x2人分= ^^;

~ 五重塔 国宝 ~
平安時代初期の建立 屋外にある塔では日本で一番小さい
でも、法隆寺の塔に 次いで古い つまり ~日本で二番目に古い塔 です
一番上の相輪が
ふつう九輪の上は水煙だが 宝瓶をのせて 宝鐸を吊りめぐらせて 天蓋を作ってある
・・・そうな。専門的でよく解んないけど 珍しいんだって (汗;)

~ 奥の院へ ~
塔の横から奥の院に向かう石段が始まります
原生林に囲まれたかなりの坂 です・・・がぁ~この位は慣れたものよ
息が切れた亀 みたいだけど、 オバハンは確実に登る 事ができるのだ(ガガーリンさん風)

~ かなりのもんだ ~
観光気分の方は 手ごわい坂に驚いています
こんな坂を毎日登る御朱印係りさんは きっと若者だよなぁ~ なんて言いながら
やっとこさ登ると 静かな奥の院に到着
こんな思いをしてきたのだから 私はここの御朱印に決めた!!
(ご朱印係りは 結構 年配のおじさまでした^^*)

~ 舞台造り ~
西国三十三ヶ寺を歩いてまわっているのかしら?
リュックを背負った 青年が 御堂に上がり 静かに鎮座しています
いいお姿

~ 奥の院 位牌堂 ~
お寺にきて お経を上げている人の姿がなかったので チョッと淋しかった
仏像の前では 鑑賞 したらスル~スル~する人が多くて、
手を合わせてお参りする姿も少なくて 空しかった

~ 空 ~
4時を過ぎると 山あいのお寺は急に薄暗くなり みんな足早に坂を下りて行きます
室生寺へは道路が出来て便利になったけど、
昔は 東西南北にあるのお寺を 四門 と呼んでこの内側を聖域として
それぞれの寺から山や谷を越えて室生寺をめざしたそうだ。
青年は奥の院の裏側の木戸から 行ってしまった
歩き道があるのだろうか・・・
-
思い切って、整形受診 August 20, 2024 コメント(6)
-
知らず知らずの〜うちに…骨折? August 13, 2024 コメント(6)
PR