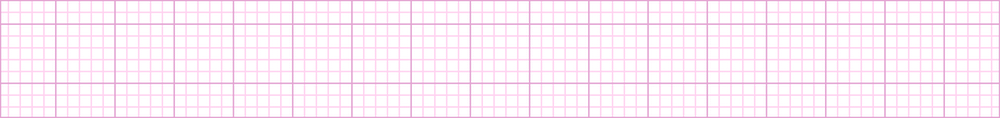PR
Calendar
Comments
Keyword Search
Freepage List
昨日お伝えした通り、今日は「効率のよい勉強法」をご紹介いたします。この方法はある有名な精神科医(誰でも一度は名前を聞いた事があると思います)の方が著書の中で紹介したものを、私が実際に学生時代に使用する中でより実践的にアレンジしたものです。
一言で言えば、ズバリ「復習の仕方」です。(「そんな月並みなことか」とあなどらずにまずは読んでみてください。)
「いつ」「どれほどの時間をかけて」「何を」復習するのがもっとも効率的か。
「いつ」について 。まずは最初の学習(学校の授業や塾の授業や参考書での自主学習)を終える。次に9~14時間後に一回目の復習(この「9~14時間後」が真夜中などになってしまう場合には「翌日」でよい)。最後に1週間後に二回目の復習。
「どれほどの時間をかけて」 について。9~14時間後に行なう「一回目の復習」では、最初の学習の3分の1から4分の1くらいの時間をかける。1週間後の「二回目の復習」では「一回目の復習」の半分くらいの時間をかける。例えば、最初に授業などで1時間学んだ内容は、翌日に15~20分の復習をし、1週間後に10分ほどの復習をする。つまり、3回の学習でだんだんと時間を短縮していくことになります。
「何を」について 。だんだんと時間が減っていくわけですから、当然全く同じことを繰り返すわけではありません(たまにこのような復習の仕方をする生徒がいますが、時間ばかりが掛かりすぎて、学習内容が先に進まず、結果手薄な箇所が出現し、復習どころではなくなります)。 大切な事は、「一度できた問題は二度は解かずサラっと見直す程度」というサジ加減 です。つまり、できなかった問題の解説をよく読み、できなかったその問題だけにもう一度チャレンジして、正解を得たらそこで完了とするのです。実践すればわかりますが、前日に出来た問題は翌日もできます。翌日にできた問題は1週間後もできます。そして1週間後にできなかった問題(つまり最後までできなかった問題)には特別な印をつけておいて、特別にもう一度解答を読んでさらにその翌日にチャレンジする。それでもできないようであれば、もうこれは相性の悪い問題なので、間違える原因を先生に聞くことです。
「以前できなかった」問題が「できる」ようになる、このときにこそ得点は伸びていることになります。たいていの中学生は(高校生にも少なからず当てはまるのですが)復習をしたがりません。その理由は、「自己満足したいから」です。学習内容が先へ先へ進むことが彼らの充実感を満たします。「俺(私)は今日こんなに進んだorこんなにたくさんの量を勉強した」と満足したいのです。復習では「ページ数」が先へは進みません。だからばかばかしくなる。
それにしても、1ヶ月後に復習するのではいけないのか?という疑問もよく聞かれるのですが、答えは「いけません」です。1ヶ月後の復習では復習そのものに時間がかかりすぎます。 1ヶ月間ほったらかしになっていた事柄は、定着していないので、1ヵ月後に復習すると内容を思い出すのだけで非常に時間が掛かりすぎ、初見の内容と同じくらいの学習時間を必要とします 。1ヶ月前に出来た問題ができなくなっていたりします。
最後に、上記の復習法を端的な言葉でまとめます。 「復習は大き目のを1つではなく、小さいのを2つ」 が鉄則です。