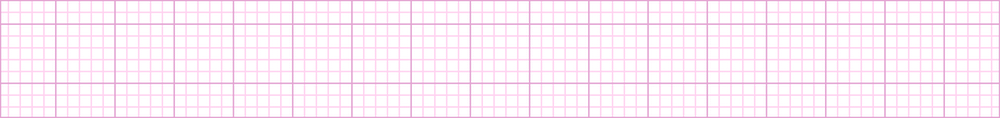全48件 (48件中 1-48件目)
1
-
こぶたさんしております
また、独り言から始めます。今まで当ブログをご贔屓になさってくださった方々には非常に申し訳なく思っています。 軽度の鬱(自己診断 笑)で何となくボワーんとして過ごしていました。更新にも精神力が必要なわけで。。。 32のオヤジにもなるとやはり思春期の子(特に女子)の心理が読めなくなってきます。爆笑していたかと思えば3分後にはスネていたりする。もう訳分からん。。。と、まだ14・15歳の多感な人々に翻弄される毎日なのであります。多感な生徒たちの気まぐれな表情や刹那の態度が気に掛かって、夜も目がパッチリ。自分はクヨクヨするタチなのでそういうのが何日も瞼の裏から離れません。もう、足掛け10年も教えているのに。。。この調子では身が持ちませんね。才能ないのかな、などと知り合いに相談する始末なのでありました。 先ごろ他塾で高校3年生を担当していたのですが、やはり高3ともなるとちょっとは大人っぽい対応をして見せてくれ、社交辞令とはわかっていながらも気持ちよく会話ができました。まぁ、生徒に気を遣わせている時点で失格に近いんですが。。。 年齢とともに気持ちって鈍くなるのですね。相手の心理状態を瞬時に察知してそれに即した言動をとることが昔より難しくなったように思います。その最たるものが老人的な自己中心的言動なのかな。平たく言えばKYってやつですね。 会話をする、授業をする際には「愛情」を忘れないようにしないと。。。 つまらない日記でした。瞑想します。読んでくれてありがとうございました。 mailto: wakakichinimoyuru@yahoo.co.jpご意見お待ちしております。
2008.06.19
コメント(93)
-
さて。
F先生という力のある先生とさっきまで飲んでた。話によると当ブログ、意外にもまじめに読んでくれていた人もいらっしゃったようなので地味~に更新していきたいと思います。F先生、T村さんありがとね。地味~に続けていきたいと思います。ほったらかしの期間中、直前の記事にいろーんなトラックバックやコメントが溜まってしまいましたがいちいち消すのが面倒なのでそっとしておこうと思います。それにしても恥ずかしいな~。
2008.04.29
コメント(0)
-
大概は。。。
大概は、逆説の接続詞でもない限り、連続した英文は「順接」か「理由」を表すんだけどなぁ。だから、傍線部分の理由なり補足説明はその前後にはっきりと述べられているってのは常識じゃん。。。はぁ。。。
2008.01.04
コメント(0)
-
おすすめブログ
受験について真剣に悩んでいる方は左を見てください。「お気に入りブログ」の中に「受験コンサル」という方のブログがあります。受験に関して非常に造詣が深く、為になる内容となっていますので、ぜひ!最近。。。やっぱり自分の経験だけでは受験は語りきれないことがはっきりと自覚され、いろいろなプロの意見を聞き、多くのものの見方を学んでいる最中です。また錆びついてきた自らの英語力に磨きをかけるため、隙間時間を見つけては英語の勉強をしています。初心に還り、主にオーバーラッピングとシャドウイングを毎日こそこそと2時間ほど。。。
2007.12.20
コメント(1)
-
駿台フロンティアJrのすごいところ
駿台の中学部(駿台フロンティアJr)のすごいところは、何と言っても、その場限りの知識で終わらせないところ。私はある校舎で英語を担当しているが、単なる受験知識を超えて汎用の利く基本的な考え方を身に付けることができるようテキストが作られている。 私は大手塾を過去2つ経験したが、駿台の特徴は集約すれば上記のようなことだ。 その分、生徒への負担が大きいのも事実だが、中学を卒業して、高校生になった生徒たちが口を揃えて言うのが「高校で英語が一気に伸びた」という一言。これはもう確実に口にする。下地を叩き込まれているので、高校でバラバラに教わるような知識でも元塾生にとっては一貫した基礎知識の発展形に過ぎない。大原則はちょっと色をつければ、多種多様な表現に発展していくことを高校になってから学ぶ。中学生のうちは、「こんなに単純な事をなぜクドクドと説明するのだろうか」と不思議に思う生徒も少なくない。中学生には、それが後にどれほどの威力を発揮するのかが理解できない。 もっともシンプルな例を挙げれば、「one→an→a」という歴史的派生を1つ覚えておくだけでも、one dayが「ある日」ならば、in a villageが「ある村に」という派生だって当然導ける。中学生がこれを習っている最中は「oneなんて知ってるよ。anもaも知ってるに決まってるじゃん、バカにすんな」くらいの気持ちだろう。目先のことだけに囚われると将来的な利益を損ないやすい。あるいは、Speaking English is difficult for me.とTo speak English is difficult for me.のニュアンスの違いも将来的な英語力を左右するほどの威力がある。 こういった統一的な知識がテンコ盛りなテキストは市販では一切お目にかかれない。特に中高一貫用のテキストはこれを目標に編まれている。一見の価値はある。英語を嫌というほど勉強して全国偏差値105をとったことのある私ですら「へ~、そういうことだったのか」と舌を巻くことがある。そんな時、「俺これらをバラバラに苦労して覚えたな~、このテキストの考え方知ってればもっと楽だったのに」などと自分の過去の境遇を恨んでしまう。急がば回れ?原則論はジレったいが、その分破壊力は抜群だ。
2007.12.07
コメント(2)
-
中2~3年の英文法、間違えやすい
気になっている方もいらっしゃるかもしれませんので念のため。 I don't like both Ken and Tom.は「私は、ケンとトムの両方を好きだというわけではない」の部分否定ですね。 「否定+100%」は「100%なんじゃないんだよ」という意味。すると I don't like all of you. 俺はお前らみんなが嫌いだ(×) 俺はお前らみんなを好きなのではない(○) I don't always cheat in the exam 僕はカンニングをいつもしない(×) 僕はカンニングをいつもするわけではない(○) その延長上に、I don't like apples very much. 私はリンゴがとても嫌いだ(×) 私はリンゴがそんなに好きではない(○) 1つ1つ覚えていって、気付いたら確かにそうだ、ってのが王道なんですが、結局受験生たちには入試までの時間が少ない。そこで、一網打尽の(「否定+100%」みたいな)近道を教えてやるってのが塾業界ですね。ちなみに「私は、ケンもトムも両方とも好きではない」(全部否定)ってどういう表現しますか?通常は2種類ありますね。
2007.12.04
コメント(2)
-
中学生のリスニング
「あいぷろんまいこうたとうむ、ばらっすくーぉ、あいてきろーふ」 I put on my coat at home, but at school I take it off.ちょっと速いとこんな読まれ方しちゃうんですよね。試しにこの間生徒たちに、読んでやった。ディクテーションさせると、I prone my coat at home, barassco I tekiroff. こんなんなっちゃう。 ちょっと遅くして、rになってしまっている音をtでちゃんと発音してみる。「あいぷとんまいこうとぅあっとうむ、ばたっとすくーぅ、あいてきとーふ」すると、I put on my coat at home, batat school I tekitohff.うんうん、近づいた。 tがrで発音されやすいこと、子音字と母音は合体すること、前置詞などの機能語はほとんどフェイドアウトしてしまうことこの3点を説明抜きで教える事ができた。それにしても3年間学校でどんな訓練をしてきたのか。。。
2007.11.29
コメント(4)
-
パンフの役割
詳しくは忘れてしまったけれど。。。Much people read in newspapers is only one aspect of matters.みたいな文が、うちの塾のパンフに載ってて、「これちゃんと読めないとマズい」っぽい文面だった。中2生へ向けたメッセージだった。確かにこういうのちゃんと読めないと大学に入ってから苦労するけれど、中2にはちょっと早すぎるような気がした。せめて中3でしょー・・・。うちの塾はちょっと勇み足。。。で、英語科の他の先生の意見も伺ってみた。すると「うちの塾生はこのくらい読めないと恥ずかしい」と。パンフって塾生が読むものだっけ?校外生を集めるためのツールだと思うんだけど。。。それにしても挑戦的すぎる。。。
2007.11.18
コメント(5)
-
文型
「He is watching TV.の文型はやっぱりSVOだ。」開成中くらいになると、この解釈がシックリこない人もいるわけです。どうでもいいことですね。おやすみ。
2007.11.01
コメント(0)
-
嘘を教える
例えば。。。 複数のSを中1に教えます。いつも困る(といか迷う)事柄があります。付け方は大別して6種類あります。1.普通の付け方。desk→desks2.語尾s/o/x/ch/sh。tomato→tomatoes3.語尾子音字+y。city→cities4.語尾発音が[f]。wolf→wolves5.単複同形。fish→fish6.不規則変化。child→childrenですが、いつも困るのが、2・4・5なんです。先生によって教えにくいところは違うと思いますが、私はこれら3つが嫌いです。2については、「ソックスチッシュ(soxchsh)」は「es」だから、くっつけて「ソックスチッシーズ」だね。で、なんとか覚えてくれはします。しかーし、「pianosとかphotosとかstudiosはどうすんの?」となる。pianoなど外来語の語尾oの場合には「es」ではなく「s」をつけますが、ぶっちゃけこのあたりの経緯や理由を説明している暇がない。よって、「pianoのように人工物のoはsをつけ、自然物(生き物)のoにはesだぞ」という「嘘」というか「飛躍」で方便説いています。一応、これでheroもpotatoもbuffaloも説明がつくんですが。。。まずいな、と思いつつしかし塾だから、と諦める。4については、例外がねー。roofs があったりbeliefsだったりと、これはもう説明できません。なんでだろう。。。知りません。しかもroofsは読み方だけは「ヴズ」なんだよなー。いつも「roofは例外だからねー。」などと、およそ「教えている」にふさわしくない表現を使うしかない。この記事書き終わったら調べてみます(案外すぐに判明しちゃったりして。。)5に関しては、生徒がよく質問に来るので困る。もちろん暗記すればいいということになりますが、どうも「単複同形」っていうのが気に食わないらしく「そうなる理由」が欲しいらしいのです。一応、「集団で暮らし、逃げるときにカタマリで逃げる動物」という定義を与え、「カタマリで逃げるから、一匹に見える」だからたくさんいても単数形だと。別にこれは私が勝手に考えたわけではなくある偉い先生が言っていたのでそのままマネしているわけですが、こじ付けっぽいし、どうも例外が多すぎる。。。「fishはわかる。sheepはわかる。JapaneseやChineseやPortugueseやVietnameseはちょっとあやしいな。deerはホントかよ?」ですね。逆に集団で暮らしカタマリで逃げるのならsparrowはどうなんだよ!となる。我々の世代では、理屈ぬきにガリ勉して覚えたという思い出があるけどなー。「とにかく全部覚えろ!来週までに覚えてこなかったら100回書く!」とかいうやり方もありなんですが、部活や行事で疲弊している生徒に対してあまり訓練主義を導入したくないな。「嘘でも理屈を」というのは、教え方として間違っているのか??
2007.10.31
コメント(5)
-
「知っている」≠「理解している」
最近じゃあ、I don't have enough money to buy the car with.の最後のwithは省くことが多いらしいですね。 じゃあ、なんで以下の3つは前置詞が必要なの?となる。I have no house to live in.I have no friends to play with.I have a pen to write with.だってさー、不定詞で後置修飾される場合、修飾される名詞は後ろの修飾語句から飛び出して前に出たって考えるでしょ。buy the car with moneyだからwithは必要じゃん!そこでこの間、ライトハウス英和辞典を執筆なさっているFさんに尋ねた。すると「本来、不定詞によって後置修飾される名詞は、直後の不定詞句から抜け出て前に来ていると考えられるので、逆に、その名詞は不定詞句中にそのまま戻せなければならない。」つまり、a book to readはread a bookから倒置された形、a pen to write withはwrite with a penから倒置された形だということ。したがって、write a pen とは言わないようにa pen to writeとは言わないということだ。 Fさんの説明は続く。「そうなるとbuy the car with moneyになるためにはmoney to buy the car withというようにwithが必要になりそうだけど、これは必要ない。なぜかというと、この例の場合、buyの目的語がthe carとはっきりと示されているので、間違ってもmoneyがbuyの目的語だとは勘違いされないから、こういう場合は原則省くんだ」と。うーん、明快。。。かつpracticalな分析だ!さすがは辞書執筆者!a house to live inはin がないとダメ、a pen to write withはwithがないとダメなのね。でもa pen to write some wordsはOKなのね。time to study math.でOK。a chance to meet her.でOK.the way to study math.でいいというのは、そういう意思が外国人の頭で働いてたからなのね。な~んだそういうことだったのか。「不定詞句の中に目的語があれば前置詞を補う必要がなくなる」ってことなのね。「知っている」≠「理解している」のよい例だった
2007.10.30
コメント(0)
-
格差社会。。。と俗物
「勝ち組・負け組」、「上流・下流」、「一流・三流」。。。今年の流行語大賞にでもなりそうな勢いである。無論、これらのありふれた語句は今に始まったことではないが、ここ数年で一気に使用頻度を増したようである。私の場合、他人を蹴散らしたい時にはよく使う、いじわるな「隠語」である。 これらが象徴する一元的価値基準による評価方法は、近年取り沙汰されている「格差社会」への過度な意識・注目を助長する。この尺度でいくと、私の人生は、「高校は六流、大学は二流、会社は五流、人生は今のところ七流(八流中)」となり、およそ「生きていても価値のないレベル」ということとなる。 今日は少し暇があったので、書店のいわゆる「岩波文庫コーナー」の前に突っ立ってこのあたりを思索した。左から題名ばかりを目で追う。自殺について、いきの構造、判断力批判・・・ロビンソンクルーソー、デミアン、罪と罰、・・・羅生門、坊ちゃん、山羊の歌、・・・。ルバイヤート、般若心経・・・などと呆然と目を這わせる。そう。学生時代だ。 高校の時に早熟なやつが3人いた。あくまで私の主観(に決まっている)だが、目の閃光・考え方が凡人とはまるで違う。卒業後、1人は単身アメリカのスラムへ、1人は自殺、1人は大学生となった(が現在消息不明)。価値観が違ったんだな、とわかったのは私が大学生となり、その中で準「世捨て人」となった後半3年間だった。その3年間、私は尊敬するMという人物とともに歩んだ、そして哲学・文学について口頭で教わる。実際に熟読する。討議する。とはいっても「ハゲるとなぜモテないのか」とか「なぜ目は目を見ることができないのか」などといった現世利益とは無縁の議題だ。ここでは主に逆説的な世界観を学んだ。こうしている間に出世欲とも無縁な人間に成り果てた。 豊かな人生とはなんだろうか。個人の価値観でそれはいかようにもなりそうだ。しかし、少なくとも六本木通りを時代の寵児風吹かせて闊歩するsnobbishな下衆野郎どもには一生かかっても理解し得ない価値観てもんがありそうだ。具体的にはどういった価値観だろうか。今後30年くらいかけて突き止めたい。 俗物には清談が理解できない。 などという長い夢を見ていたらいつのまにか3時になってしまった。
2007.10.25
コメント(6)
-
やばい先生
先週も今週も、授業にお偉いさんが入って授業見学。やりにくかったなー。いわゆる評価査定だ。別に媚びを売った授業をするわけではないけれど、やっぱり気になる。なにせ来年度の生活がかかっていますから。 講師の実力や授業スキルは塾によって非常に差がある。もちろん、同一の塾内でも個人差はあるが、それよりもなによりも塾自体にレベルがある、というか。。。6年ほど前まで勤めていた大手のある塾はその点、レベルが低くかったなぁ。そんな塾も学校の授業より断然わかりやすいと評価は良かった。その塾での話。集団授業経験者だった私も、勤め始めの頃はやはり先輩達の授業を見学する事になっていたのだが、内心「レベル低っ!」と思いながら、さも得るものがたくさんあるかのように振舞っていた。その後、「じゃあ、次回は君が授業研修ね」となり、後日、私が見せる番が来た。被研修者は私1人、対して研修者は6人。黒板にタイトルを書いた瞬間、皆の目が変わった。「ざま~みろい」って思いましたね。。。超快感でした。前職で死ぬほど研修を受けてきた私にしか成し得ないスムーズで「(頭に)落とす」授業。分かってます。自画自賛。でもね、黒板や色の使い方から発問のタイミング、指示出し、目線、声の大きさ、メリハリ、落とし方。。授業は経験が長ければうまくなるなんてものじゃないんだよ。。。問題意識を持って特訓しなきゃ。何から何まで彼らを超越していました。恐らく、彼らの見たこともないレベルだったと思います。研修者たちからは思いっきり褒められまくりで、その後はいきなり最難関のクラスをもち、期待にこたえて難関校実績も全120校舎中1番をとりましたよ。で、1年ちょっとで辞めました、その塾。上司も好きではなかったし、なによりレベル低すぎて成長できなさそうだったから。 でも。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。今は。。。。。。。。。。。。。。。。今の塾(駿台)でわぁ。。。。。。褒められたことがない。。。。。。。。。。。。。私の授業自体レベルが下がったわけではない。周りが恐ろしくうまい。私は高校受験部&中高一貫である。駿台予備学校(大学受験部)の講師たちと空間を一にすることも多いが、そっちはもっとやばい。授業の神があちこちにいる。時折教室に残っている他の先生の消し残しの板書。やべー。羽衣(チョークのブランド名)のフルタッチチョークはこう使って、ペンギンのカルシウムチョークはこう使って、羽衣の蛍光は囲みに使って、蛍光で文字を書くときはペンギンかー、雨の日はこの素材を使って~。。。みたいなあり得ないマニアックなこだわりを学んでいます。黒板に常に背を向けた状態で板書しつつ同時に生徒の目を見て解説する先生。。。まるで世界が違う。。。しかもあり得ない速さで授業が進行し、確認テスト平均点が9割とか。。。だめだ。。。吐きそうだ。。。世界ビックリ大賞だよ。オーソドックスな先生でも「落としどころ」がうまい。窓から見ると、まるで催眠術に掛かったかのように生徒たちが思わず頷きまくってる。授業終了後に中1の生徒たちが「ん~、勧誘の表現はえ~、Let's~ Shall we~ How about~ing Why don't we~ What do you say to ~ingで違いは・・・」なんて会話してる。。。どうやったら割り振り5分でそこまで教えられるの?? 早く、超人になりたい。
2007.10.20
コメント(5)
-
必要悪
いわゆる「西麻布の交差点」にはいまだに大きな灰皿が置いてある。タバコをやめた3週間前まで、私が毎日お世話になっていた灰皿だ。信号待ちの間一服するための?灰皿。 今思えば周りに多大な迷惑を掛けていた。私は禁煙者でこそあれ嫌煙家ではないし、受動喫煙も特に気にならないが、交差点で他人の煙が服につくのがとても気になる。 「六本木の交差点」でもアマンドの前とUFJの前に大きな灰皿がある。そこはほとんど喫煙所と化していて、「信号待ちの」とかいう生易しいものではなく、常に何人かが暇つぶしや待ち合わせで吸っている。そこから灰皿をなくしたらどうなるかと考えてみた。愛煙家だった私からいわせると、喫煙者は必ずどこかしらで吸わないと苦しくなる。そういった場所があるほうが喫煙者も安心して吸うことができる。そして歩きタバコも減る。ポイ捨ても減る。どこもかしこも禁煙地帯ということになれば、隠れポイ捨てが横行することは目に見えている。規制は強化しすぎるとかえって弊害を生むことが多い。問題は「その場所」が交差点に設置されているということだ。読んで字のごとく無差別に「交差」する地点。したがって本来ならば、それがあってはならない場所かもしれない。しかし、「その場所」がひと気のない目立たない場所にありかつ喫煙者がstrangerだったりすると、どこに喫煙所があるのかわからず、我慢も限界に差し掛かった時には仕方なく道端で吸うしかなくなってしまう。つまり、喫煙所として理想の場所は、「禁煙者が避けて通れ、かつ目立つ場所」ということなのか。なかなか難しい。渋谷ハチ公前のバカでかい喫煙所は、渋谷の美化に一役買っている。常に20名くらいの喫煙者が気晴らしをしている。もし、あれがなくなったら、渋谷には吸殻があちこちに散在するという結果を招くだろう。禁煙してからいろいろな視点が養われつつある。これからは双方に耳を傾けられる人間になりたい。
2007.10.17
コメント(3)
-
禁煙!禁煙!禁煙!ブログ趣旨変わってらー。。。
禁煙10日目 一仕事終えた後の一服。食後の一服。確かに気分はよかったけれども、タバコを吸う事自体に何のメリットがあったのだろう?単なる惰性で吸っていた?やめられないから吸っていた?なけなしの300円はオニギリではなくタバコに使っていた学生時代。 よくもまあ、10日間も吸わずにいられるなあ、と我ながら不思議に思います。と同時に先々の不安もあり、禁煙に成功した人を私は心の底から尊敬します。 禁煙の定義はかなり難しいと思います。1年我慢したけどまた戻っちゃった、という話を聞いたとき、愕然としました。「えーーーーっ、1年も我慢??」この苦しみを1年も耐える??この間までは、1ヶ月タバコを吸わなければ禁煙成功だと思っていました。1ヶ月経てば吸いたい気持ちもなくなるだろうと。禁煙生活で学んだ事は、「吸いたい欲求」の存続期間には個人差が大きいということです。5日くらいでおさまる人もいるようですし、私が調べた中でもっとも長かったのが、4年です。そう、4年後に誘惑に負けたっていう人です。おそらく「禁煙」の定義は「吸いたいと思わなくなれる」ってことでしょうか。 その意味では私はまだ「禁煙成功」とは言えない。だってすっごく吸いたいから。とりあえず、現在の禁断症状は頭痛、めまい、鼻血、くしゃみです。手足のしびれは収まりました禁断症状なのかは定かではないのですが、タバコをやめてからこれらは起こりはじめました。これもまあ、体が正常化するプロセスなのだと思います。体の中で黒い物質が代謝により反応を起こしているのだと勝手に解釈しておきます。だから、もっと反応すればいいなくらいに考えています。 そして、中でも「めまい」に関して言えば、これは特に振り返った瞬間や視線を移動させた瞬間に起こるのですが、タバコを久々に吸った時のあの「ラリる」瞬間と同じ感覚なのでこれを楽しんでいます。もっともっとめまいには活躍してもらいたいです。今も頭がボワーンとしてクラクラするので気持ちがいいです。禁断症状を楽しんで禁煙生活をエンジョイしていきたいと思います。
2007.10.10
コメント(4)
-
タバコ、やめました。というより奮闘中。
禁煙生活(とりあえず)1週間 9月30日を以ってタバコをやめました。いや、正確には「やめている最中」、という変な表現になりますが。それまでは1日20本吸っていました。「なぜ止めようと思ったか」という質問に対する答えは、月並みなものです。止めたほうがいいからです。アハハ。18の時から吸っていたので実に13年間の喫煙生活でした。 と明るく振り返りますが、個人差があるといわれる「禁断症状」について言えば、実はまだ真っ只中。今日も苦しくて苦しくて気が狂いそうになりながら、震える手でミント味のキャンディーを頬張りながら「こりゃ重症だ」と苦笑する私がいます。 興味のない方がほとんどと思いますが、今日までの私の禁煙経過を時系列に報告します。思い立ったのは9月の上旬。親友と「やってみようか」となる。 〈ステップ1〉9月上旬~中旬今までの経験で「本数を徐々に減らす」というやり方では失敗することが明白だったので、今回は「まずいタバコを吸ってみよう」という計画を実行。まずいタバコは本数が少しだけ減る。自動販売機でできるだけまずそうなタバコ(私の場合経験でCというやつだった)を買い、それしか買わない。とにかく自動販売機の前で一瞬がんばるだけで本数が減るのだ。9月15日くらいまでに本数が半分になった。(もちろん、「減らそう」という意志は持ち続けた結果です)。禁断症状はゼロ。 〈ステップ2〉9月中旬~下旬薬局でネオシーダー(タバコのように火をつけるタイプのノドの医薬品。擬似タバコとして)を購入。いつものまずいタバコの箱の中に混入させ、ネオシーダー(ハズレ)を引いてしまったら仕方なくネオシーダーを吸うことにする。日を追うごとにネオシーダー(ハズレ)の割合を増やしていく。9月20日くらいにはすでにネオシーダーだけで生きられるようになった。禁断症状は少しあった。タバコ独特のあの毒々しいニコチンの「引っかかり」を体が求めるが、ネオシーダーで満足できなければ禁煙など到底できないと強く言い聞かせた。(後に調べた結果ネオシーダーにも若干のニコチンと多量のタールが含まれていることが判明。ただし、習慣性のあるニコチンが微量なのでタバコをやめるよりは楽です。しかし、発がん性のあるタールが25mgも入っているので、万一ネオシーダーがやめられなくなるとタバコよりも危険みたいですので、ネオシーダーの箱に記載の通り「禁煙目的で使用しない」というのを守るべきだと今になって思いました。) 〈ステップ3〉9月下旬~終盤ネオシーダーの本数を減らす。ネオシーダー自体にもニコチンがほんの微量含まれているが、ほとんど空気レベルなので習慣性はタバコに比べれば月とスッポンの差。したがってここまでくればあとは心理的な戦いだ。1日10本吸っていたネオシーダーをいきなり2本に落とす(というより、最初から2本と決めていたわけではなく、「0本にしよう」と決めたが自分に負けて結果として2本くらい吸う感じになってしまった)。3日間くらい2本生活が続いた。禁断症状はあった。指の先がピリピリとしびれているのがわかり、気持ちよかった。 〈ステップ4〉10月1日~タバコもネオシーダーも吸わない。(友達と飲みに行った日、その一日だけネオシーダーを吸ってしまった。)ミント系のキャンディーや実際のペパーミントの葉やスペアミントの葉を買って噛んだりしている。あと体に良さげなスナック菓子(成城石井や明治屋とかで売っている感じのやつ)を買って吸いたくなったらバリバリやる。禁断症状はかなり実感。指先の痺れに加え、私の場合は(今もそうだが)強烈な偏頭痛(前頭葉)、めまい。なににも増して強烈なのが「吸いたい」という誘惑。吸いたくなったら、私の場合は「シャケトバ食べてぇ!」とすり替えています。スルメでもよさそう。すると本当にそれが食べたくなる。ムニムニ食べたくなる。とにかく「スパスパ」を止めて、「バリバリ」「ムニムニ」をイメージした。 今日は仕事が休みだったので、気晴らしに、六本木のドンキまで散歩。六本木ドンキの出入り口は全体が喫煙所になっているので、試練の場としては最高だと思ったからです。時間にして約15分でしたが、このたった15分の散歩中に1つ発見がありました。 タバコを吸うといわゆる「ラリる」という一種の陶酔状態(多幸感)になることがあるが、私は吸っていない状態で「ラリ」りました。というのも、ものは言いようで、先ほど挙げた禁断症状に「めまい」と書きましたが、これこそが「ラリ」っているのとほとんど同じ状態なのだと気付いてしまったのです。結構気持ちいいんです。禁断症状でフラフラする。頭が回らない。手足の力が抜ける、しびれる。名づけて「逆ラリリ」。禁断症状大歓迎!超気持ちいいー。 外を歩くと実感できます。今日は空を見上げながら散歩したので、それがコツなのかな。美しい夕焼けを仰ぎながら思った。やはり煙(タバ子)への未練はあるものの、この新しい「ラリリん」を新しい彼女だと思って愛していきたい。タバ子ってドブ臭い名前だしね。
2007.10.08
コメント(5)
-
英語 長文読解テクニック その壱
テクニック編。 He mentioned that he was a teacher.(A)He remarked that sushi was his favorite.(B)He stated me that he was an American.(C)I suppose that he will not come.(D)I suspect that he is a thief.(E)We figured that the world would be more dangerous.(F)これらのピンクの動詞はだいたい英検で言うと準1級か2級レベルですね。私立高校の入試長文では、このくらいの動詞なら注釈なしで読まされます。こうなると「知らない単語だから、読み飛ばした」とかいうpassiveな中学生が多いのですが、もったいないなぁー。眠いので結論。上記の英文のように、「主語+知らない動詞+that節~」の形を使っている文ならば、応急処置として「知らない動詞」をsayかthinkに置き換えて読んでいい。大概、say(言う)かthink(思う)の類義語だから。A~Cはsayに、D~Fはthinkに置き換えても意味は大して変わりません。英語の場数を踏んでいれば無意識にできますが、中学生は意識してやることにより解釈レベルもグッと上がります。I believe that he is kind. なんかもそうですね。英字新聞を読むときとかでも役に立ちますよ。それではっ!zzz・・・
2007.10.01
コメント(6)
-
郵政民営化記念切手を買い占める??
郵政民営化記念切手が今日10月1日発売されます。 さてと、どれほど希少価値が出るだろう。。。と昼間考えて、「1シート800円だから、100シートくらい買い込んで暴利を貪ってやろうか」などとたくらんでいました。 結論からいって期待できないらしいですね。今どき高値で取引されることはないそうです。切手収集自体かなり下火の様相で、昔みたいに血眼になるコレクターが少ないのだそうです。まあ、本当に切手を愛しているならば、希少価値うんぬんは関係ないのでしょうが。。。今回は150万シートの発売だそうですし、最初からオークション目的で買い占める人もいらっしゃるそうですから、そのかた達に任せておきましょう。 価値が確実に上がるモノの見分け方を本で読んだ事があります。その本にはクドクドと書いてありましたが、要するに「有限なもの」だそうです。当たり前ですが。。。(汗)例えば、古いですが、同じテレカでも「年号の入っているもの」などはその年にしか発行できないものなので確実に「有限発行」です。或いは、いかなるものでも「初版」も有限。或いは、芸能人の若い頃(ぷぷっ)。 いずれも、需要さえ一定(上がらなくてもよい)ならば、しだいに品薄になるはずですから、必然的に価値が上がるということでした。そういう意味では、今回の記念切手に期待するより、むしろ今までの切手のほうが有限性が高くなるのかもしれませんね、もう発行されないという意味で。ただ、今までの切手は、民営化に伴い有価証券としての価値がなくなってしまうのかななんて、どうでもいいことを考えてますが。調べるのも面倒くさいからやめた。 この間、古本屋で、「古銭買取相場一覧本」なるものを発見、目をギラギラさせて立ち読みしてしまいました。なんとそこいらへんで見かけるあのギザ10(ギザギザの10円)昭和27年モノが○○円に跳ね上がっているなんて!興味のある人は調べてみてもいいかもしれませんね。 一昔前、携帯会社ド○モのコマーシャルに広○涼○さんが出演なさっていましたが、その1カットがテレカになりました。私は当時の彼女からタダで譲り受けました。同じ物が1年後に2万円で金券屋に並んでいました。使わなきゃよかった。
2007.09.30
コメント(5)
-
孔子さんは次のように言った。
生徒の作文をたまたま見てしまった。 孔子の言葉を引用していたが「孔子さんは~と言った」と書いてあった。 なんだか、孔子をばかにしているような文だなと思った。失礼だな、と思った。 著名人の名は、敬称を略さなければ陳腐に(というか馴れ馴れしく)なり、かえってバカにしているようにも取れる。私も昔「九鬼周造さん」と引用して、先生に注意されたことがある。 敬称を略すべき時とそうでない時との境界線はどのあたりなのだろう?感覚的なものかな。「河合隼雄さん」も変だな。 公人だからか?芸能人にもあまりつけないな。 森本哲朗の本(たしか「日本語表と裏」だったか)に「日本人はなんにでも『さん』をつけたがる。おさるさん、お月さん、おいなりさん、お人形さん・・・」というような内容があったが、(彼自身の結論は忘れたが)「親しみ」を込めたいという意識が働いているのだろうか?
2007.09.29
コメント(0)
-
公立中学の先生ってホント大変だと思う。
公立中学の先生ってホント大変だと思う。どんなに苦手な生徒にも得意な生徒にも、同じことを限られた時間内で教えなければならないから。とにかく生徒の能力の差はいかんともしがたいものがある。 英語で言えば、かたや帰国子女、かたやABCから、といったクラスを十羽一からげにしなければならない。いや、これならまだ「経験の差」なのでなんとかなるといえばなんとかなる。つまり情報量を増やしてやればたいていの子が満足できる。一番厄介なのは、冒頭でも述べた、「能力の差」。きれい事抜きにこればっかりは認めざるを得ない。特に顕著なのは「視認力(見る力)」と「論理への集中力」だ。「視認力」の例を挙げると、「bとdを書き間違える」。間違えない人は生まれてから死ぬまで一生間違えない。間違える人は高校生でも間違える。これって、単なるケアレスミスじゃないと思う。だって、間違えない人はそもそも「ケア(注意)」すらしないから。視覚における統覚作用が関係していると思う。私の経験だが、この業界に入って初めて「bとdの書き間違え」というものに遭遇し、驚いた。しかも、これは中学生においてはよくある間違いなのだ。徐々に改善する生徒もいる。タイプは3つ。夢にも間違えることのない生徒。徐々に改善する生徒。改善しない生徒。塾においてさえそうなのだから、公立の中学では全体の3分の1くらいは間違えたりするんじゃないか?そして、この「bとd」で間違える生徒は間違えない生徒に比べ、英語全般においてスペリングがなかなか覚えらず英語が苦手になる傾向がある。スペリングにおいては人一倍の労力を費やすべき生徒だ。アルファベットを教える際に「左手も右手も両方とも、OKのサイン出してみて。すると左手がbの形だね、右手がdの形だね。bとdは間違えるから注意だぞ」と言った1分後に間違え始める。あくまで一例だが、こんな初歩の段階ですでに差が出てくる。よく「頭のいい人はうまく教えられないことが多い」と言われるが、まさに本人は「bとd」なんて間違えた事がないから教えずに放っておく。すると生徒が間違えまくる。 「論理への集中力」でいえば、例えば「修飾関係」がわかるか否かって試金石だと思う。「公園を走っている少年はVinceだ。」の「少年」を修飾(「修飾」という言葉は普通英語授業では「詳しく」という語で代替する教師が多い)している部分に下線引けない。そうなると、The boy running in the park is Vince.でもThe boy is running in the park is Vince.でもよくなっちゃう。「修飾」という「意味」からのアプローチが無理ならば、今度は形容詞句とか後置修飾とか「形」からのアプローチを試みるも、所詮、「意味からのアプローチ」に失敗する子にとっては「形からのアプローチ」はなおハードルが高い。 こうなるとあとは「慣れ」で、なんとなくわかってくるまでとことん正しい文を書くしかない。「記憶力」にも個人差が大きいですけどね。上記はほんの一例です。よく「頭のいい人はうまく教えられない事が多い」と言われますが、まさに本人は「bとd」なんて注意すらしたことがないので教えない(教える事すら考え付かない)、あるいは「修飾」という用語をポンポン使って生徒がついていけない、などと日常的に起こっています。 できるだけ工夫した後は、「その子なりに伸ばす」、という楽観でよいかもね。
2007.09.27
コメント(0)
-
文法って英語学習に必要なのかな。。。人によりますね。目指す所に。
HI' Yuo will be visit America October ,2007. I am very welcome yuo con stay My Home (Vegas)yuo like, I am sent you Email &sam pitchers from 2006 travel in Europe, abut 3 Hour ago but retruned. Mybe the pitchers was tomuch. I will sent yuo by mail. Hop see yuo soon.ラスベガスに約30年在住の私の○○○(血がつながっているので言えない)の文章です。先日私に宛てたメールの内容です。一字一句違わずに完璧に写しました。日常会話は英語です。文法は習わなかったそうです。どう感じますか、この英語。方言とかなまりでええじゃないか、って言いますか?Would you be willing to speak or read or write English without grammar?「楽しく学ぼう英会話」みたいな低い次元での英語はさておき。現地の人でも小さい頃、teach-taught-taught(ちゃんとこの順番で)とがんばって暗記するし、現在進行形だって「in the middle of an actionなんだな、それをbe- ingで表すんだな」と意識的に文の形に反映しています。 過去完了(the past perfect)なんかもその使用法を覚えて、had and PPと暗記して、ちゃんと意識的に使っているんです。 カナダ人のMr. Kに聞いたところ、ride-rode-riddenなど不規則変化は学校で習ってまじめに暗記したと言っていましたし、had PPとて意識して間違えないように使っていると言っていました。ネイティブの元通訳の同僚も同じ事を言っていた(彼女も「低い次元での話はさておき」と言っていたが)し、元フライトアテンダントの同僚も同じ事を言っていた。ついでに私も同じ事を考えます。ちなみに私は中学3年生の英語は低い次元だとは思いません。「受験英語は実用性が低い」を「英文法は必要ない」と履き違えてはならない。この考え方は非常に危険で、海外に住んでいてもこの記事の最初にお見せした文章(実物)しか書けないようなおばちゃんの予備軍になります。100歩譲って受験英語は実用性が低いと認めたとしても、それだからといって英文法は必要ないなんて絶対に言えない。あいさつ表現や慣用句は必ずしも文法だけではまかないきれない。しかし、あいさつ表現や慣用句だけで英語をマスターした気になっている人が多い。文法を抜きにして英語は語れません。あいさつ表現も覚える、慣用句も覚える、文法も覚える。どれか一つ抜けても完全な英語力にはならないと思います。文法を抜きにして英語を語る資格のある人は、「ネイティブでかつ、現地でもその辺にいるおばちゃんレベルの会話しか必要ない」という人。あるいはシュリーマンほどの天才にでもなればそれでもいいかなと思います(あれも嘘っぽいですけどね。。。)。私の知り合い(といっても私よりずーっと年上です。私の高校時代からお付き合いがある)に誰でも一度はその名を聞いたことのある(と思われる)有名な学者(日本よりもアメリカやドイツでの方が有名かも知れませんが)Mr. Mがいます。英語に関しても学者の中でも誰もが一目置く存在ですが、彼の昔話を聞きますとやっぱり「死ぬかと思うくらい、英語は勉強した」って言ってました。「勉強した」という表現しますよ。当時まだ高校2年生だった私は大学受験の勉強(穴埋め問題とか並べ替え問題などのいわゆる受験英語)をやっており、Mr. Mにも入試問題を解いてもらってみたのだけれども、びっくりするくらい解けなかった(汗)。そこでわかったのは、彼が昔訓練したものは確かに英文法の暗記と習得(当たり前だが暗記と習得は別物)+typical sentenceの暗記の2本立てだったが、いわゆる受験英語における独特のクセのある英語(問題作成者の意図を受験生が汲むような問題群)とはちょっと違う物なんだな、ということ。東大恒例の要約させる英語に「象と一秒はどちらが大きいか」という題材の文章が出ていましたが、Mr. Mは「この問題は非常に難しい」と内容の吟味に入ってしまった。私は笑いを堪えられませんでしたが、そのくらい受験というものが分かっていらっしゃらなかった。でも「think-thought-thought」と暗記して現在完了を暗記して練習してtypical sentenceを暗記して、っていう勉強を続けて彼は「(彼いわく)イギリス人よりもきれいな英語」をマスターしたのであります。 まあ、はっきり言うと、単に「バランスの問題」なんですけどね。文法だけではダメってことですね、本来英語は。かといって文法を全否定する冒頭のようなおばちゃんスピーカーとは深い話は英語では出来かねますね(^-^:A
2007.09.26
コメント(0)
-
入試が近づくにつれ、手につかなくなってきた
入試を目前にして、焦り始めている生徒たちも多いと思います。現に私の周りにも(毎年のように)だんだんとトルモノテニツカズといった様子の子が増え始めています。ここから急激に成績を伸ばしていく子がいます。2年ほど前に、個人的に分析してみました。それまで徐々たる向上だったのが、正月を境に一気に急上昇or急降下、というサンプルが多くありました。秋に諦めずに着実に身に付けていった子が一気に伸びることが多いです。 この時期から過去問をわんさか解いていくことになりますが、単に数多くの問題に当たるだけでは絶対にいけません。この時期の過去問は「傾向を押さえる」などという呑気なことをするためのものではありません。そんなことは受験勉強を始めた当初にすでにある程度つかんでいるはずです。今ある知識を個別の問題へと的確に当てはめる力を養う「応用力育成期間」と考えてください。「応用」というと「知識」のようなニオイはしませんが、「応用」だってゆくゆくは応用ではなくなります。言葉は悪いですが、「惰性的な知識」となるのです。したがって、「応用力育成期間」=「応用知識暗記期間」と言いってしまってもいい。そしてその応用知識をさらに汎用が利くようにブワっと広げてくれるのが先生です。キレイごと抜きに実際そうだから。そうやって入試に成功していくから。実際、入試会場で、持っている知識を応用して初見の発展問題に当てはめるってのは困難なことです。解答できるケースのほとんどの場合、初見のように見えて実は以前に類題をやったことがあるというほどのものです。「『着実』って何?精神論じゃん!」 とんでもない、着実というのは「広く灰色(たくさんのことがなんとなく分かっている状態)」よりも「狭く黒色(知っている事に関しては確実に解ける)」を意味します。 過去問を進めていく際、「次に出会ったときに確実に解けるのか」をロクに検証しないで次の問題へと突き進むのはほとんど時間の無駄です。かえって自信を失い、問題に対して懐疑的になることにより今までよりも実力を失う事すらあります。 例えばここに100問あるとしましょう。最高の理想が、100問全部が黒、という状態。次に50問黒色で残りの50問は全く白。次に100問全部なんとなくわかっている状態。傾向として、得点につながるのは上位校になればなるほど、「完全な知識」の応用なので、なんとなくわかっている程度の知識ではなにも解けません。 別に一般論を偉そうに言っているわけではないです。目の前の生徒が現にそうだからです。 例えば簡単な例ですが、「受け入れる」という単語を穴埋めする問題。Aくんは何も書けず空白のまま提出。Bくんは「あー、あれだよ、えっとアクセプト」と言って「acsept」と書いて提出。そして両者ともその部分は0点。Bくんはこのテストで全問こんな調子で結局は30点しか取れず、一方Aくんはacceptは全く知らなかったが、知っている単語については確実に書けたので50点取れた。なんてことがすごく多い。一番言いたい事。それは、「今だからこそ、前日の復習を!」です。生徒も親も「先へ先へ」と焦りがちですが、「身につける」ということが学習です。結構前の記事の『復習の仕方』で書いたように、「1時間の勉強に対し、翌日15分から20分程度の解き直し」が記憶の王道です。そしてまた間違えたら、今度は1週間後の解き直しです。Slow and steady wins the race! (急がば回れ!)slowである必要はないので、Steady wins the race!(確実が勝ち!)と言い換えておきます0(^-^)0
2007.09.25
コメント(0)
-
英語 長文読解のコツ 第5弾
今回は英語長文読解のコツ最後として、「先の形の予測」を説明します。全国のどこかに1人でも「読んでよかった」と思える人がいれば幸いです。さて、当たり前ですが英語は中学生も私もイギリス人も皆、左から読みます。したがって、視界に入る語句は必ず、左から右へと情報を与えてくれます。それに加えて今回の「先の形の予測」をすれば、英文の構造を効率よく把握できます。例えば、I gave という2語が視界に飛び込んできたとしましょう。まずは意味を考えてみる。「私はあげた」です。「あげる」ってどんな動作?あげる相手がいても、あげる品物がなければ成り立たないし、逆にあげる品物があってもあげる相手がいなければgiveという動作はできません。そう、giveを見た瞬間、後ろには「相手+品物」がほぼ確実に置かれるってことが予測できるわけです。こういう動詞を授与動詞といいますが、ちょっと難しいですが、第四文型を作りやすいのです。直後に「人+物」が置かれる。teachだって教える内容と相手の2つが必要。sendもそうでしょ?showだって。動詞の意味を自分で考えれば、その後にどんな語句が置かれるのかは予測できます。わざとらしくわかりにくく書いてみますが、こんないじわるな文でもわかるんです。I gave the girl whom I like the best a present. gaveの後には「人+物」が来る事を知っていれば。まあ、この文のように「人」が長い場合には、I gave a present to the girl whom I like the best.というように「物to 人」にして、かっこよくしますが。In the parkを文頭に見つけたら、次にどんな語句が待ち受けているのかはまず予想できます。そう、「S+V」です。このin the parkは前置詞のカタマリなので、主語にはなれない。じゃあ、もっと後に主語があるんだな、と主語探しにうずうずしながら読んでいくんです。先の形を考えながら読むってことですね。In the park the girl with blue eyes spoke to me.あるいはWhen I came back home, を見た瞬間home,の後にはさらに大きなS+Vが待ち構えていると考えながら読む。だって「私が家に帰ったとき」だけで終わる文なんてありえないから。だから「私が家に帰ったとき、誰が(S)どうした(V)んだ?」と問題意識をもって読む。そうすれば、接続詞のカタマリがどんなに長くなっても、いつかは大きなSVが出てくるんだなというように、英文全体の把握がしやすくなるんです。接続詞を見つけたら、小さなSVの後に大きなSVが必ず置かれてると意識しておこう。Though our team defeated the opponent in soccer game by the score of 3to 1, our manager told us to practice harder.Thoughのカタマリがどんなに長くても、必ずその後に大きな「誰がどうする」が来ると知っていれば安心して読める。あるいはThere is を見たら??そうThere is 何が+どこに の順番で語句が置かれることがほとんど。そりゃそうだよね?「ある」っていうのだから、「何が」あるのか、そしてそれは「どこに」あるのかも普通はくっついてくるじゃん。There was an unkind woman on the other side of the lake.何が(誰が)どこに の形、確認できますか?ちょっと疲れてしまったので、ここまでにします。これまで5回にわたって長文読解のコツを簡単ではありますが、紹介してきました。今日初めて読んでくれた方は、以前の記事をご覧になり、5回のうちの1つでも身につけてください。長文がだいぶ楽になるはずです。今後は、長文読解がどうしてもできない方用に、完璧には読めなくても問題は解けてしまうといういわゆる解法のテクニック(邪道)をいくつか紹介していきます。でも本当は邪道じゃないんだよ♪
2007.09.23
コメント(3)
-
「逆児(さかご)」を端的に説明しなさい!
骨休め。 小学生のころ、保健(?)の授業で「妊娠」について教わった。「女性の中にある卵子は、男性の中にある精子と結びつくと、分裂を始め・・・だんだんと赤ん坊へと成長するんだよ」というように先生が教えてくれた。 訳がわからず、家に帰り、「なんで女性の中にある卵子が、精子と結びつくことができるんだ?だって精子は男性の体の中にしかないんでしょ?」と問い詰めて、両親を困らせた想い出がある。その答えを知ったのはいつだったろう?しかしながら、今ではある程度知っているのでこの件についてはまずは安泰といったところか。 しかし、これまた保健だが、中学の時に私に「逆児(サカゴ)」について教えてくれた先生を私は今でもちょっと恨んでいる。「サカゴは、足から産まれてくることが多いんだよ~」と教えてくれた。 これまた、タマげて家に帰り、両親に「足から産まれてくる子なんているの!?」と問い詰めた所、返答は「いる」。 「ス、スゲーっ!!」。。。お腹からじゃなくて足から産まれちゃう子もいるんだ~。すげ~。この感動を胸に大学2年生まで過ごした。腹部ではなく脚部に子をみごもっている女性など経験として見たことがなかったのに。どこかにそういうスゲー人もいるんだと知識として覚えておいた。結局はその誤解をサークルの部室(5~6人はいたかな?)で解くことになってしまったが。恥ずかしかったな~。 確かに言葉としては間違ってはいない。「サカゴは、足から産まれてくることが多い」。確かに。「足から産まれてくる子なんているの!?→いる」。確かに。言葉としてはどこにも間違いは見当たらない。まあ、勘違いってやつですか。 問題はサカゴの「定義」を教わらなかったことに起因する。加えて「逆児」という文字を見て「逆(さかさま)」をイメージできなかった私のマヌケさにも起因する。 結局何が言いたいのかというと、「ちゃんと教わらなかったこと」とか「定義を知らないこと」は危険だということだ。小さい頃はまだまだ辞書で調べても、書いてある内容が難しすぎて「未知」のスパイラルに陥ることがある。そこで、「教える人」が登場するわけだが、大人は子どもに、誤解のないような的確な表現で教えなければいけない。ともすれば、「真実を知った時が赤っ恥」とか「日常生活に支障をきたした」とか「一生誤解のまま死んでいく」というようにもなりかねない。こういったことは、中学生を教えると日常的に出てくる。気を付けて教えていきたいものだ。
2007.09.22
コメント(0)
-
前置詞ってよく分かってない人が多いです。単なる修飾語句の棟梁なんだけど。
お話したい内容が多すぎて、ブログに打ちこむのがもどかしい気持ちです。「なら、ブログなんてやめちゃえばいいじゃん。」との忠告もあるでしょうが、私の生徒も何人か読んでくれているようなので書き続けます。また、ある一定の常連さんたち(小中学生のご父兄)にとっても、このブログが後のち少しでもお役に立てればと思っています。あと、虚栄心も手伝っていることも事実です。「虚栄心が喋らせない時、人は寡黙になる。」(ラ・ロシュフコー)。というわけで、バンバンお話しします。 えっと、今日もまた、英語の長文読解のコツ(第4弾)です。全部で第5弾までです。今回は「前置詞の働きに注意すると、読みやすくなる」ってことです。 まず、前置詞ってなんだ?ってことですが、「直後に名詞を導いて・・・」といった抽象的な定義を覚えるより、30コくらい覚えちゃった方が早いです。例えばat in for on of with withoutなどなどです。 でもって、前置詞の働きは?というと、簡単に言うと「修飾語のカタマリ」を作る、と言えます。言い換えれば、「形容詞や副詞のカタマリ」を作る、とも言えます。さらに言い換えると「名詞・動詞・形容詞・副詞を詳しくする」と言えます。名詞・動詞・形容詞・副詞のどれを詳しくしているのかは、文の前後関係で判断しなければならないことが多いです。 ここから先は精読のできる方のみどうぞ。文法用語が得意でない方はここまでにしておいてください。 ※形容詞的用法 He looked at the book on the desk.・・・A Aの英文では、on the deskという前置詞のカタマリが直前のbookを「どんな本か」と詳しくしています(昨日の記事内で、名詞の後置修飾の1つとして前置詞を挙げました)。book(名詞)を詳しくしているのだから、on the deskは形容詞のカタマリと言えます。「彼は机の上の本を見ました。」が標準的な日本語訳でしょう。 ※副詞的用法(動詞修飾) He was sleeping on the desk.・・・B Bの英文中にもon the deskというカタマリがあります。が、今回は形容詞の働きではありません。なぜなら、直前に詳しくされたい名詞がないからです。こうなると、副詞の働き確定です。on the deskはwas sleepingという述語動詞を「どこで寝ていたのか」と詳しくしています。「彼は机の上で寝ていた。」になります。 ※副詞的用法(形容詞修飾) He is the tallest in his class.・・・C Cの文中in his classも前置詞のカタマリですね。今回はtallestという形容詞を「どの範囲でもっとも背が高いのか」と詳しくしています。形容詞を詳しくしているのだから、今回も副詞の働きですね。「彼はクラスの中でもっとも背が高い。」という日本語訳です。 ※副詞的用法(副詞修飾) He runs fastest in his class.・・・D Dの文中にもCと(見た目が)同じin his classがありますが、今回はfastest(「もっとも速く」)という副詞を「どの範囲でもっとも速くなのか」と詳しくしています。副詞を詳しくしているのだから、今回も副詞の働きですね。 「彼はクラスの中でもっとも速く走る。」です。 というわけで、よくわからない人もいらっしゃるかも知れませんが、とにかく、「前置詞のカタマリは何かを詳しくしているんだ」ということを覚えておいて、今後10月後半くらいまでは、前置詞のカタマリに出くわしたら詳しくされている語に向けて矢印を引っ張ってみる訓練をしておきましょう。
2007.09.19
コメント(0)
-
英語の長文が苦手な中学生へ。
今回は第3弾。andです。and なんてフツー習わないですよね?でも、私はandに青筋を立てます。長文読解の時の文法は、いわゆる文法問題の文法と違うってことがこのあたりでわかるものです。 He tried to eat sushi and vomit.・・・A He tried to eat sushi and vomited.・・・B注)vomit 吐く故意に、ちょっとだけわかりにくく英作文してみました。Aはすごく嫌なヤツですね。性根か腐ってる。Bは仕方がない。「彼は寿司を食べようとし、かつ吐こうとした。」・・・A「彼は寿司を食べようとして、吐いてしまった。」・・・B 日本語訳を見ておわかりいただけると思いますが、Aの人物は「食べる」動作と「吐く」動作の両方にトライしたということになります。Bの人物は「食べる」動作だけにトライしたら、あまりの生臭さに「ボヘっ」と吐いてしまった、ということになります。 Aのand はeatとvomitという2つ原形を結んでおり、Bのand はtriedとvomited いう2つの過去形を結んでいます。 はい、結論。「andは同じ品詞しか結べない」。さらに、「できるだけ似た形をとっているもの(原形と原形、過去形と過去形、ingとingなど)を結ぶ」。 頭では上記の原則が分かっていても実際の英文になると発揮できず、何となく意味を取ってしまった結果、文中で述べている実態がつかめないという困難があります。ここでテクニックですが、まだ慣れないうちは「まずandの直後の単語に下線を引け!そしてandの前の方からそれと同じ品詞(の同じ形)を探して下線を引け!」ってことになります。つまり、長文の苦手な人がandを正確に捉えたいなら、「先に後ろを見ろ」ってことです。試しにわざわざややこしく作った下のムカつくような英文をandに気をつけて精読してみましょう。He liked to see something new and strange and know the things that he hadn’t known since then. So he went to dangerous and unknown places and into the buildings into which nobody was allowed to go. He often said that he had a love of adventure and exploration and that there were still a lot of places to go and see and were few places that weren’t worth visiting and exploring. 最後の緑色のand達がそれぞれ何と何を結んでいるか正確に把握できるようであれば、完璧だと思います。 ふぅ~、おやすみなさい。。。(あと2回かかるなぁ~)
2007.09.18
コメント(1)
-
最近思う事。ちょっと道草です(^-^;A
毎度ご訪問ありがとうございます。只今、英語の長文の読み方を書き連ねている本ブログですが、堅苦しい話ばかりなので、少しだけ道草を食おうと思います。 最近思う事。訪問してくださる方々の中には非常に親切な方が多いということです。訪問者履歴でたどっていくと「ネットだけで月30万円稼ぐ方法」を案内してくれていたり、「無料で異性と出会う方法」を伝授してくださっていたりします。仮に私がそういった立場で、ネットだけで30万円稼ぐ事ができるようであっても、こんなおいしい話は他人に教えようとは思わないし、異性とバンバン出会う方法も絶対に秘密にして自分ひとりで得をしようと思うでしょう。 他の人を思いやる気持ち。これに勝るものはないと思います!しかしながら、こんなに心の広い人々がネット上にはいるというのに、ついぞ実生活の中ではこんな親切な人々には出会ったことがございません。そういった天使のような人たちと実際に会って話したいと考える昨今です。 などととぼけてみたりもしますが、実際問題、そういった天使たち(迷惑メールの送信者やこういったわけの分からない俗物たち)は、もうちょっと頭を使って稼いだ方がいいんじゃないかなと思います。人をだまそうとするならばもう少しうまい方法はないのか、一緒に考えてやりたいくらいです。頭の中が透けて見えてしまうので面白くもなんともありません。そういう甘い考えがまかり通るわけがない、と実生活の中で学習してこなかった人たちは、学習能力がないor温室育ちのどちらかでしょう。 こういった人々は別に人をバカにしてやっているわけではないと思いますが、正直世の中こういったものが通用するくらいに思っているその浅ましさ加減に厭世観を助長せられ、知性のかけらも見られないクズたちが、よりによってこの私をだまくらかそうとしていることに憤懣やるかたない気分で一杯になります(笑)。 大衆雑誌に載っている出会い系広告。「半信半疑で登録しました。そしたらすぐにセレブからメールが入り、恐る恐る待ち合わせの場所に行ってみました。すると一見おとなしい人妻。速攻でホテルに入ると、豹変。あんなことやこんなことをして楽しく過ごしました。さらに帰り際にお小遣いまでもらって一石二鳥!超ラッキー。もう病みつきになりそうです。」 そんなバカな話があるかっ!と独りで憤るとともに、笑いすら覚えてしまうのは私だけでしょうか。あー、もうなんか嫌になっちゃいますね。 愚痴でした。
2007.09.17
コメント(0)
-
長文が苦手な人の克服法
長文の読み方。前回はSVを的確に捉えることに焦点をあてました。「Sは絶対に名詞(句)」ということを念頭に置くということで。 さて、今回は予告どおり、「名詞の後置修飾」についてです。長文が苦手で本当にどうにかしたいという人は、面倒くさがらずにしっかりと読んでください。名詞を後ろから詳しく説明(後置修飾)する方法は大別して5つあります。1.関係代名詞2.分詞3.前置詞4.不定詞5.形容詞この分類に関して諸説ある(分詞はすならち形容詞じゃないか!など)と思いますが、このブログではできるだけ一般的な考え方に従おうと思います。※Look at the boy.1.Look at the boy who is running over there.2.Look at the boy running over there.3.Look at the boy on the sofa.4.He is the first boy to climb the mountain.5.Matthew is the boy taller than you.(高校入試の英文で使われることは稀)※の英文はかなりシンプルですね。 上記英文の文頭の数字はさらに上の数字に対応しています。ご覧になってわかるかと思いますが、それぞれのboyはすべて後ろから詳しくされていて、長い名詞のカタマリになっています。英文の一文一文を長くする決定的な原因がコレです。つまり名詞が大きくなってしまっていて、1つのカタマリとは見えづらくなっていることです。考え方としては、「修飾語句なんて所詮はコバンザメに過ぎないのだから、( )でくくってしまおう」という楽観的な考え方が功を奏すことが多いです。1.を例にすればLook at the boy (who is running over there).こんな記号をつけてみると読みやすくなります。骨格はとにかく「少年を見なさい。」で、その後、「ちなみにその少年はどんな少年か」と説明しているに過ぎない。 大人が考えれば「こんなことはしなくたって。」とか「こんなことをしているようではなかなか読み進められな。」となりますが、日本人の中学生はこんな些細なことでずっとつまずいていて、「長文が嫌い」→勉強しない、という悪循環に陥っているんです。まずは補助輪をつけるのは英文読解も同じ。最初から理想は求められません。名詞が後置修飾されるきっかけを上記で5つ挙げましたが、これら5つは完全に覚えておく必要があります。少なくともそれらに出会ったら「ああ、後置修飾されているのだから、所詮は名詞の大きなカタマリだな」と自分で言えるようにならなければなりません。知らなかった方は、5つを暗記してください。 Yesterday I went to the park. In the park a boy running very fast stopped in front of me and said, “Look. Do you know? What is the object flying in the sky?” I looked up at the sky. And I saw a glittering object there. But I had no idea what it was. So I said nothing to the boy. Then he got angry with me and threw a stone at me. The stone he threw hit me.
2007.09.17
コメント(0)
-
文法問題は解けるのに、長文がダメという人、一緒に乗り越えよう!
皆様ご無沙汰しています。更新怠っていました。夏期講習も終わり、ブログ更新の季節がまたやってまいりました。私の不在の間に、コメントいただいた方々ありがとうございます。 さて、毎度のことなのですが、夏期講習中には「長文が苦手で」という常套句をよく耳にしますので、今回からはいわゆる英語の長文読解問題への具体的な対策を3度くらいに分けてお話しようと思います。文法では得点できるのに長文はなぜ読めないのか。そこには、端的に言って「長文を読む際には文法問題とはまた別の、文法に対する巨視的な(鳥瞰的な)把握が必要」ということを「意識」しなくてはならないという難しい課題が待っています。じゃあ、具体的に。。。1度でお話できませんので、まずはその「難しい課題」を一気に5つ挙げてしまいます。後3回にわたってそれら1つ1つについて具体的にお話したいと考えます。もしも長文が読めなくて困っていたなんて方が、読者の中にいらっしゃったら、非常に幸運ですよ。(自分で言うのもなんですが(^-^;A) ※文法問題は解けるのに、長文が読めない原因 1.SV(主語・動詞)をいちいち把握する癖がない。 2.後置修飾に対する意識が低い。(名詞のカタマリという観点がない) 3.等位接続詞(andなど)に対する意識が低い。 4.前置詞句の働きに関する知識と注意が足りない。 5.先の予測(内容ではなく形の予測)をしようとしていない。 上記5つをクリアーすれば怖いものなんてなくなります。この5つのMissionを1つ1つ潰していく。そんなに時間はかかりません。1つの長文で1つづつクリアしていけば20時間くらいで身につきます。(今回の夏期講習で実践済み) 今回はこの中の1.「SVをいちいち把握する癖がない」についての解決策。簡単な例を。He played tennis in the park yesterday.・・・AYesterday he played tennis in the park.・・・BIn the park he played tennis yesterday.・・・C 上記3つの文で出来事の実態はかわりません。(内容がほぼ同じ)。しかし、Aが簡単に捉えられる生徒もBCでつまづくことがあるようです。「ふつう、英文はSV(誰がどうする)から始まる」ということを念頭におかなければなりません。 そしてその次に、「主語は必ず(代)名詞(句)」ということも忘れてはなりません。 (ここで「そんなのあったりまえじゃーん!」と突っ込んでいては読めるようになりません) Aはなぜ簡単なのか。それはSVから始まる「ふつう」の文だからです。 Bの考え方は。。。英語における「時」を表す単語が「副詞」だと知っていれば、「ああ、主語は名詞なはずだから、yesterdayは主語じゃないな。次のheが主語」といえる。 Cの考え方。。。前置詞句(前置詞のかたまり)が形容詞か副詞の働きをするものだと知っていれば、「ああ、主語は名詞なはずだから、in the parkは主語じゃないな。次のheが・・・」といえる。もっと簡単に言えば「inがついているから主語じゃない」。 非常にシンプルなことを言っているのですが、日本語でこう説明するとややこしく見えますね。「こんなこといちいち考えながら読んでられっか!」とつっこみたくもなります。しかしながら、初めのうちはいちいちこのように文法的に考えるのです。会話とかそういったレベルじゃなくて論説文などきっちりと文構造を把握しなければ、その文の持つ論理構造(記号)を把握できません。けれども、慣れればいちいち考えなくても(意識しなくても)、主語として捉えようとしてしまっている語句が名詞でなかった場合には、頭のどこかで「違和感を伝える統覚作用」みたいなものが働くようになってくれますので安心してください。 別に論説文でなくても、田吾作や権兵衛が登場するような物語文ですらこれを応用した知識が必要になることもあります。例えば、 In a village lived an honest man.なんていうのはいかがでしょうか。物語文の第一文目としていとも簡単に出てきそうな文です。まずはSVの発見です。 さっきも述べましたとおり、In a villageは前置詞句なので主語じゃない。ならば主語は?そうその次に出てくる名詞(句)なはずだからlivedを通り越してan honest manです。じゃあ述語動詞は?もちろん、動詞はlived1つだけ。そう、自然と「倒置」がわかってしまいます。 文構造としてはMVSという特殊な形をしているのです。 最後の例は大学入試で主となるので中学生の方はわからなくてもいいかも知れません、まずはHe played tennis in the park yesterday.の例をしっかりと頭に叩き込んでおきましょう。今後10月半ばくらいまでは必ず英文にSVをつけてみてね! 次回は後置修飾いきます。これで失敗している人が大半です。またね!
2007.09.12
コメント(0)
-
教育は資格でしょ!失格とは資格を失うあるいは失っていること。
今日こそは、かなりシビアに「ほんたうの」自分で意見します。 私事。だいぶ前の話だが、10年以上前に付き合っていた彼女が10年ほど前に教員になった。公立中学校の国語。大学生の時代にドイツ語は私が教え、レポートのゴーストライターも私だった。国文科にしろ、何を知っていてどんな苦労をして教員になったのか。親からの仕送りで暮らし、好きな洋服を買って大学生活を無難に過ごし、教員となりおおせた。児童心理学も単位さえ取得できればいいわけで、要は大学の単位の1つに過ぎない。カントもニーチェもベルグソンの名前すら知らなかった。少なくとも国語の授業には哲学にしろ倫理学にしろ詩学にしろそのあたりからのアプローチが必須なはずだろ。 思うに、現行の教科書はその出典はいいとは思うが、教える側がそれについていけているのかという問題が大きい。 今は国語の教科書にあるか不明だが、たとえば宮沢賢治の「わたくしという現象は~」という句を1つとっても「なぜ『わたくしという存在は』じゃないのか」、説明するには現象学とか実存主義とか、もろに哲学にかかわってくる宮沢賢治の考え方のコアな部分(っていうか「イキザマ」っていう一番大事な部分)を知らなければ不可能。哲学だけじゃない。物理学だって生物学だってかかわってくる。単なる童話作家みたいな紹介のされかたじゃ、出典の意図に反していると思う。「銀河鉄道の夜」だって「なぜみかんじゃなくてりんごなのか」とか深い部分での考察なんて私は中学では教わらなかった。実際中学生のころは「宮沢賢治ってあのメルヘンチックな作風がいいな~」などと呑気に読み返していたからな。 あ~、メルヘンで思い出した。その教科書には中原中也の「1つのメルヘン」も載ってたっけ。中学校の先生が仰せになっていたことは「冒頭部分とクライマックスでは時間的にだいぶズレがある」ということだったっけ。「だから何?」とずっと突っ込んでたよ。ああ、私、いい教育受けてこなかったな。中也の「山羊のうた」だの無刊詩だの読んでから語れって言いたい。「みちこ」とか「修羅街挽歌」とかを読んだ上で、中也独特の「破壊的な語呂」などにも触れてほしかったな。 卑しくも「学校は受験のためにあるわけじゃない」と言うならばそれこそ「ほんたうのこと」を教えてやれと言いたい。それができないなら何も教えていないに等しい。それを抜きにして、上っ面で甘っちょろい、月並みな指導で教育だの道徳だのと御託をならべるようならば自宅で中公新書だの岩波文庫だのを多読させたほうが子供のためだ。 別に別れた彼女だからとかいうわけでなく、内実をよく知っているからこのように批判めいてしまうのだけれど、どうも考えれば考えるほど不条理極まりない。 以前、桜蔭中学の生徒が国語の質問に来た。先生から与えられた課題に取り組んでいたのだが、非常に文学的な課題で「いい教育受けているんだな」と思った。「これぞ国語」だと思った。その生徒の国語の先生については名前すら知らないのだが、尊敬する。桜蔭は入学する生徒たちのポテンシャルもさることながら、教員がいい授業(教育といえる授業)しているな~と実感した。少なくとも私が今まで出会ってきた桜蔭中学の生徒たちは芯がしっかりとしていて、やると決めたらやる。強いし、人のせいにしないし、他人のミスも大人のようにフォローする。家に電話を掛けても「わざわざお電話いただきまして、恐縮です。」などと8流の大人顔負けの対応。しかも約4分の1が東大生になる。大事なのはここからで、学校では一切順位をつけていないというから驚く。生徒たちは競争によって学力を伸ばしているのではなく、自ら絶対的な基準に基づいて学力を伸ばしているのだ。塾で働く私が言うのもなんだが、「ほんたうの」教育をすれば自ずと大学入試にも成功するということだろうか。このあたりが興味深い。
2007.08.10
コメント(6)
-
教え方を教えてください。
Please teach me the best way to teach students the grammer of infinitive! 夏期講習の前期が終わり、一息つく間もなく今度は後期分の予習に明け暮れています。私の場合、1時間の授業に対し1時間半から2時間くらいの予習時間をとってプリントを作成したり、クラスの実情に合わせた授業展開の仕方を練ります。前もってやっておかないと1日9時間の授業ともなると睡眠がとれない状況になってしまうので、怠慢な私でもさすがにお盆ですらほとんど休みません。 後期の授業は不定詞から始まるのですが、私のもっとも嫌いな分野。教えにくいったらありゃしません。それこそTo know is one thing and to teach is another.の世界でして、私的には不定詞は非常に使い勝手のあるいろいろな局面で使える文法分野なのですが、中学生にとってはそれが仇となり、多種多様な使い方で混乱してしまうらしいのです。これはもう9年間も教えているのに解決されません。あ~どうしよう。 特に副詞的用法はつらい。たいていの生徒が、「副詞」ってものがどんな働きをするのか、日本語レベルで知らない。「英語ではね、副詞はね、動詞・形容詞・副詞を修飾するんだから~」で始めても何がなんだかわからない、ってことです。さらに、副詞的用法自体がさらに5種類に分かれるので、「もうだめだ」ってことになるんです。 He went to the airport to see his uncle off.から始まり、次にはHe was surprised to hear the news.さらにHe is kind to help me with my homework.次にThis chair is comfortable to sit on. とどめに、My grandmother lived to be 80 years old. 以上はすべて副詞的用法なのにもかかわらず、日本語にするとまったく違う表現になり、教える側としてはほんとにお手上げ状態になってしまいます。自分が生徒だったら投げ出しますから。原義をたどればどれも同じことなのに。 どなたか、うまい教え方を私に伝授してくれませんか?
2007.08.10
コメント(0)
-
数学は苦手。でも点数は取れますね。
皆さまお久しぶりです。やっと少しだけブログを更新する時間ができました(^0^)/最近は塾の夏期講習で手一杯なのに加えて、事業を興し始めたものですから、非常に忙しいです。(日本人の風潮として「忙しい」を「名誉」だと考える方も多いですが、私は決してそうは思いません。) そういえば最近は、「数学は才能じゃない」ということでお話を進めていたような気がします(^0^;A端的に言って、「数学は暗記」というスタンスです。この間は早稲田大理工の方の意見を紹介させていただきました。しかも、このブログに関して彼からのコメントもいただきましたので、この日記の一番下に貼り付けておきます。特に数学に悩みを抱えている方、ぜひご一読ください。 中学生(特に女子)はいずれ数学のどこかしらでつまずきますので、そんな時に彼ら理系のエキスパートがどんな風に数学を身につけていったのか、その勉強方法(少し前の記事で紹介しました)をマネしてみるのもいいのかと思います。私は文系でしたが、実は結局は彼と同じやりかたで最後の最後までバケの皮ははがれませんでした。というより、「自分の頭で考えて何とかして解こうとする」ということこそ、いつかバケの皮がはがれてしまうことが多いですね。 理系の人や数学を得点源とする学生は、少なからずどこかでつまずきやがては最良の方法(結局は「解法の暗記とそれらの組み合わせ」)へと自ら模索の後にたどり着くことが多いようです(数学の才能のある一部の天才を除いては。)以下、念のため、例の理工学部卒でメーカー勤務の思いっきり理系の方の生のコメントを貼り付けておきます。 私の意見をブログに書いていただいてありがとうございます。今回はこの件に関して追加コメントさせていただきます。現在私は某メーカーで「生産管理」という仕事をしております。もちろん自分の仕事内容を紹介してそれで終わりってことはないので安心して最後まで読んでいただけたらと思います。この仕事をはじめて実はまだ1年も経っていませんが、次のようなことがわかりました。自分の前に難題(生産トラブルで出荷できない場合の対処など)や奇問(今回の新潟地震での生産影響など)が時々現れますが、基本的に一見そのように見えるだけで《以前やったようなことが組み合わさってたり形を変えてるだけ》なんです。碌な知識もない上でそんな問題に出合ったとき当然の如く対処できません。しかし、今となっては基本的な問題はここ1年ぐらいの間に何度も対処しましたし、そんな慌てることなく対処できていると自覚しています。なぜなら《以前やったようなことが組み合わさってたり形を変えてるだけ》だからです。数学だって同じです。合否を決めるような難題も実はそんな難しくもなく、そう見えてるだけなんですよ。だから今の私がそうであるようにわからなかったら先生や解説(私の場合は先輩や上司ですが・・・)をじっくり読んで理解し自分の物にしてください。一度は理解したつもりが、次回できなかったらもう一度読んで理解してください。基本的な知識(解答方法)を暗記してください。それだけで充分なんです。それだけで数学の才能がある人にだって充分対処できるので安心してください。皆さんがんばってくださいね。私も引き続き頑張ります。また機会があったら書き込みさせてください。それでは・・・(2007年07月27日 21時08分31秒)
2007.07.29
コメント(0)
-
もうすぐ夏休みだ!受験生、自らの怠慢と戦い打ち勝て!自律克己!
もうすぐ夏休みですね。「夏は受験の天王山」とよく言われますが、正直意味がよくわかりません。要するに「大事だ」ってことなのでしょうか(^-^;Aしかし、たしかに長期休暇後には学力の差が出やすいです。その理由は、自由時間が長いからです。普段は学校という束縛があるために、毎日の時間がある程度均一化されています。一方、夏休みなどの長期休暇は1日6~8時間勉強する子もいれば、1時間も勉強しない子もいます。夏休みは約40日間あるわけですから、その差は夏休みだけで200時間~280時間にもなります。この恐ろしい差を普段学校のある日に埋め合わせようとしてもなかなか簡単にはいきません。200時間あったら何ができるでしょうか。数学の苦手分野が20コあったとしても1つにつき10時間かけてすべて克服できてしまいます。英語の文法でも新出だとしてもやはり完全に20項目はマスターできます。1日は24時間ですから、6~8時間の勉強といっても実際には24分の6~8時間。つまり1日の3分の1にも満たないのです。無論、生活の基本となる衣食住や睡眠にかける時間もあるでしょう。しかし、6~8時間勉強したくらいで「灰色の夏休みだった」などとはまだまだ言えないはず。ぜひぜひ精一杯はりきって夏を勝ちきってください。
2007.07.14
コメント(0)
-
数学のエキスパート?からのお墨付き勉強法 (^0^/
今回は、いわゆる「ケアレスミス」(うっかりミス)の防ぎ方をお伝えしようと考え、原稿は既に出来上がっているのですが、7月2日の記事に関して、早稲田大学理工学部卒・同大学大学院で基礎工学(?)を修了し現在大手メーカーに勤務する、理系のエキスパートのK・Wくんから、生のコメントを頂きましたので、その概略を以下に記します。ケアレスミスの防ぎ方は次回載せますね。正直、7月2日の記事はバリバリ文系で数学が苦手だった私が提唱する「数学の勉強法」なので説得力に欠けました。以下Kくんの言葉。「確かにそうですね(年下なので敬語)。僕も実は高校生の時は文系的な人間だったんです。数学は、結局にっしー(実際にこう呼ばれています)のブログのやり方でしたね。やっぱり、数学のできる、発想力のある生徒は僕の学校にもいましたけど、数学の得点は僕の方が上でしたね(Kくんは早大実戦模試で数学は全国10位に入ったこともありますし、慶應経済学部の本番の入試では《本人いわくですが》恐らくほぼ満点だったらしい。)しかし、ただ単に解き方を暗記するって感じじゃなかったです。まずは自分で解けるかどうかやってみて、できそうもないなと見切りがついたらすぐに解説を読み始めて、理解できたら次にはだいたい解けるようになってましたね。解説が理解できたらそれが暗記につながってたって感じっすね。(実はまさにこのことをブログで書いたんですが・・・)。数学の先生は、とことん考えることが大事だと言ってましたけど、そんな時間はなかったですから。」以上が理系トップ集団の生の声です。バリバリ理系のK・Wくんも同じ考えだったとは結構意外でした。世の中の事象に対して、数学的なメスを入れて分析する力を彼は持っています。したがって、モロに理系で私とは対極にいる存在なのです。もともと数学的な発想に長けている人なのだと思っていました。「俺のブログ、読んでみて」から始まり、読んでもらった結果、以上のようなありがたい言葉をもらいました。Special Thanks to Kくん!書き込み待ってるぜ!
2007.07.13
コメント(1)
-
数学が苦手ならば…勉強の仕方を変える!
数学の「解き方を暗記する」というと誤解を生む可能性があります。なぜなら、「暗記」は頭を使わない、と考える人が多いからです。 しかし、数学における「暗記」は「理解」とほぼ同意です。解答を見て「ああ、なるほど。」と思えたら「暗記」はほど成功していると考えられます。「ああ、なるほど。」と思えたときにその問題をもう一度解いてみて解けたら確実です。次に同じ問題に出くわした時には既に解けるようになっていることがほとんどです。なぜなら理解を伴った記憶だからです。 確かに長い時間解答を見ずに問題と向き合っている時間は中学生にとって有効な時間かもしれません。そしてなにより自分自身で難問が解けた快感は勉強の起爆剤になります。しかし、長いこと一人で考え込んだ結果、結局違う事を考えてしまったり数学が苦手な人など、ともすれば面倒くさくなってしまいそのまま寝てしまうなど、非効率なことが多いです。最終的には解答解説を読んで「なるほど」と思い、解答解説こそが再び出会った時の「こやし」あるいは「経験値」になっていく。徒手空拳で難問と向き合って得られる知恵はそんなに多くはないですよね。 このあたりは「読書」と同じ理屈だと思います。大人は子どもに「本を読め」と言います。これは一人で考え込んでも結論が出ない時に、偉大な先人達の知恵を拝借し、ひいてはこれを自らのものとして賢く生きていくためのメソッドだと考えます。この「読書」という作業に対して否定的である大人はいないと思います。(哲学者ショーペンハウエルは「読書について」という著書の中でこれすらも否定してしまっていますが。。。)ひとりで考え込んでもロクなことを考えないことも日常的に多いですし(^-^;A結論は出ないことが多いですし。「クマと出会ったら死んだフリをし、イノシシに追いかけられたら横に逃げる」という(俗説かもしれませんが)知恵を一人で考えた末に導き出せる人などこの世にいるのでしょうか?身近なひとや読書に頼ることは多いですね。同じじゃないでしょうか、数学の解答解説も。問題はどこで自分の考えに見切りをつけるか、だと思います。解答解説を読むタイミングですよね。 問題文を読んで、考えもせずに解答解説を読み始めるのは私とて反対ですが、少なくとも中学生の問題で30分も考え込むようでは要領が悪いと思いませんか。とりあえず時間を決めて自分の頭で考えて、解法が思いつかなかったら「解答解説という先生」に聞いて「知恵」を授かった方が効率がいいと思うのですが。 若干31歳で人生について偉そうなことを述べる資格などなさそうですが、少なくとも「読書」によって人生の処世術や哲学などを学ぶことも経験値up術だと思いますし、同じく数学において解答解説を読んで次の局面に備えることも経験値upという意味で全く同じだと思います。(英語教師なのでなんとなく自信のない言い方になってしまいますが、数学が苦手だという立場だからこそ言えることもあります(^-^;A)数学が苦手でも、数学で学校順位5位に入ることくらいは必ずできます!それこそ「やればできる」の世界です。諦めずたゆまず継続してやれば必ず結果はついてきます。解答解説を読んだ後に「ちゃんともう一度解いてみる」ことを心がければ!(←すっごく力入っています!) 「解答解説が充実している問題集を選べ」とは昔からよく言われます。その理由はこのあたりにあるのではないでしょうか。
2007.07.02
コメント(0)
-
誠に申し訳ありません
このブログを読んでくれている方、ほんとうにごめんなさい。昨日も今日も時間がなさ過ぎです。記事書けません。前回の記事の続きは来週中にお伝えします。
2007.06.30
コメント(0)
-
問題集の活用
こんにちは!私は英語担当なので数学の勉強方法について語る資格はあまりないと思いますが、数学の成績がドーンとあがった生徒の談があります。その生徒いわく、「問題集の解答を読むタイミングを早くした」と言っていました。やはり!別の言い方をすれば、「うんぬん考える時間を短くした、或いは見切りを早くつけるようにした」かな?なんか最後の方は、「問題を読んで解答をその次に読む」という「読み物」になっていたと笑いました。この生徒のやり方って結構抵抗があるんですよね。数学は思考力を鍛えなければならない、と「数学の」先生方は言いますから。しかし、苦手な子にとってこれほど意味不明な御託もないです。私は以前の日記で書いたとおり、数学がすっごく苦手で(実力でやったらだいたい50点中20点くらい)解き方を単語カードで覚えてテストを凌いでいた不届き者でした。中学生の時代には、できる友達を見て「どうしたらあんな解き方を思いつくんだよ!」と思っていました。はっきり言って今でも「思いつけ」と言われても思いつくことはできないと思います。ただ、思いつかないかわりに「やり方を知っている」ので解けます。第一、私はいまだに「一次関数の交点を求める場合には、2つの直線の式を連立させる」理由がわかりませんから。それでも解けて得点できてしまうのは覚えているからなんですよね!!(^-^;A。それでも中学の数学と大学入試の文系の数学は解けてしまうんですよね。明日の記事でもっと詳しく書きます。(今日は時間が無いので)
2007.06.28
コメント(0)
-
中学生の「中だるみ」回避術
昨年と一昨年、私は高校受験クラスと中高一貫クラスの両者を掛け持ちしていました。両者を比較すると、「中だるみ」の時期がずれています。高校受験クラスは主に、中2において中だるみします。高校受験クラスの中2はやはり、授業を受け持ってみると明らかに中1・3と比べて「たるんだ」というか「殺伐とした(或いは「疲れた」)」雰囲気が伝わってきます。 一方、中高一貫クラスでは主に中2の後半から中3の後半にかけて長い中だるみの時期に入ります。同じ中だるみでもこちらは高校受験クラスとは違って「妙ににぎやかな」というか「落ち着きがない」雰囲気になります。なんだか青春を謳歌していて勉強どころではないという感じです。塾にゲームを持ってくるのも中高一貫クラスの中3の特徴です。 ここでは「なぜ、高校受験クラスと中高一貫クラスでは、『中だるみ』の質に違いが見られるのか」を考えるよりも、まずは「その『勉強を怠ける時期』たる中だるみの時期を、いかにうまく回避する(させる)か」に焦点を絞りたいと思います。 結論から言います。勉強に関してある種の「刺激」を与えてやれば軽傷で済むケースが多いです。やはりある程度の中だるみは覚悟しておいて、それをできるだけ抑制するという考え方でいいと思います。いくら中だるみの生徒たちでも、学校の定期テストの得点や順位には結構こだわります。定期テストはある種の「刺激」と考えていいでしょう。したがって、定期テスト直前にはいつもとは違った奮闘ぶりを見せます。しかし、ひとたび定期テストが終わってしまうと、一目散にゲームにマンガと道楽三昧です。 これではせっかくがんばって身に付きつつある学力もまさに「付け焼刃」で、高校入試や大学入試まで持っていける「実力」とはならず、入試当日に憂き目を見る結果となることは容易に予測できます。したがって、定期テスト以外の「刺激」を与える必要があります。 一言で言ってしまえば、「英検」「漢検」「数検」などの各種の検定試験や「駿台模試」などの各種の模試です。 学校の定期テストに加え、検定試験、模試の2つを組み合わせれば休む間もなくテスト三昧となります。これでは疲れてしまい返って逆効果というケースも見られましたので、優先順位をつけます。それぞれの「刺激」には魅力があります。検定試験は一生の資格ですので本人にとってやりがいもありますし、小さな合格祝いをして家族で喜ぶ事もできます。模試も、普段では味わえない「合格可能性」や「全国偏差値」を見ることができ、自分の実力を「肌で」感じる事ができます。 上記のような「刺激の機会」をお子さんにうまく与える事ができれば、「中だるみ」は軽傷で済む事例が多いです。
2007.06.26
コメント(0)
-
勉強をやる気になれない人へ
勉強がやる気にならない人は勉強の部屋の環境を変えてみてはいかがでしょうか。ここでは勉強するのが面倒くさいとか勉強が嫌いだという中学生を前提にして紹介します。 嫌いな勉強はやる気が起きない。でもやらなければ成績が落ちる。勉強部屋を非常にストイックな雰囲気(例えば学習机以外のものを撤去するなど)にし仕立てる親や本人がよくいるようですが、やる気が起きないときは余計にその部屋へ行きたくなくなります。 おすすめは、勉強する時に、勉強机の端(か前方)にポットに入ったジュースとお菓子などを置いておき、「この問題が終わったら食べる。食べ終わったらこの問題をやる。」と短期的な目標を目の前に掲げて取り組んでみると結構ハマります。(食べながらでもいいと思いますが。)ポットに入れる理由は、時間が経つとぬるくなってしまうからです。氷と一緒にポットにオレンジジュースでも入れておきましょう。注意点といえば、お菓子を食べるときに横になったりテレビを見たりしないことです。あと食べ過ぎると眠くなることでしょうか。 まるで、学習机が自分の秘密基地というかテリトリーのようにそこから離れたくなくなります。あるいはその他のやり方としては、常に飴・ガム・ハイチューなど口に含みながら勉強するというやり方です。口を動かしながら勉強すると予想外にはかどります。まずは実践してみましょう。クチャクチャやりながら、飴やガムと同じくらい粘り強く取り組んでみるのです。1人でサービス残業をしている状況に似ているかもしれません。学校とは違ってジュースを飲みながら、菓子を食べながら、自分のペースでずっとできます。 これを読んでいらっしゃるご父兄の方の中には「けしからん、そんなふしだらな態度は勉強に対する冒涜だ」とおっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんし、こんなやり方は聞いたこともないかもしれません。まずは、勉強と友達になると考えてみてください。そのうち、お菓子やジュースや飴がなくても、自然と粘り強く勉強ががんばれるようになってきます。 勉強の時間を「楽しく、充実した空間」にしてみるのです。なにごとも「段階」とか「順序」が大切なのだと思います。最初から、ストイックに完璧を求めるよりも、まず、第一に勉強するクセをつけなければ、そのうちまったく勉強しなくなります。最初のハードルは低めに、そしてだんだんと自主的に高みへと昇っていくのが中学生だと考えます。ご父兄の方、お子さんにちょっとだけ協力してやってみてください。最初は勉強しているときに「これ、食うか?」などと差し入れするところから始めてみては?
2007.06.23
コメント(2)
-
例の「単語の覚え方」実践結果
今日は嬉しいことが1つありました。私の教えている塾では毎回25点満点の英熟語テストがあります。今日のクラスはお世辞にも英語が得意とはいえません。塾の中では最も易しいクラスです。毎回の英熟語テストでは25点中10点取れば良い方で中には2点とか1点という生徒もいます。 そこで先々週、クラス全体に例の(たしか3回くらい前にブログに書いたかな?)「単語の覚え方」を教えて実際に単語カードも配ってその場で少し実践させてみました。反響はよかったものの、家でやってみると面倒くさくなってしまったのか、次回の英熟語テストは普段とさほど変わらない平均点でした。 しかし、今日、やっとクラスのうちの1人が家でも実践してくれまして、25点中22点取りました。本人も「やり方を変えたら得点が変わった」とあの方法の威力を実感してくれたようでした。私から見れば、当然といえば当然なのですが、中学生は往々にしてこの「当然」とか「因果関係」を理解しません。そのあたりはいくら理屈で教えても納得しないので、実際に自分で実感してもらわなければなりません。ここが難しいところですよね。勉強の方法の効果を、本人に実感させるためだからといって無理やり強制することはできませんから。あくまでアドバイスとして、「行き詰まったらやってみ」というレベルにとどまります。私のクラスに関して言えば、今回のケースでは「みんな勉強したくないよな?じゃあ、勉強時間増やさずに得点を伸ばすにはどうすればいい?「効率」だよな?」といって、おもむろに単語カードを出す。 こんなやり方でした。これでもなかなかやってくれません。(実際に今回は1人だけでしたし。ですが、今回はその子をみんなの前で褒めたので、周囲にまた波及効果がでると思います。) 実践すれば出来る子ばかりなのに。。。もったいない!中学生の可能性!
2007.06.22
コメント(0)
-
「国私立高校」と十羽一からげにしてもいいの?
国立(こくりつ)高校に合格するのは非常に難しい。私立高校も難関高校となると非常に難しい。合格するには両者とも特別な訓練が必要になります。関東では、たとえばもっともハイレベルな受験パターンとして、筑波大学附属駒場高校と開成高校を受験するパターンがあります。 しかしながら(これは大学受験におけるトップレベルの国立大学と早慶の受験にもある程度当てはまるのですが)入試問題の傾向がハッキリと異なります。 一般的に国立高校(都県立でも日比谷・西・船橋などの独自入試を行う高校を含み)の傾向はいわば「基礎の応用」と表現できます。難解な単語や複雑な文法は使わない代わりに、公立中学で習う範囲の知識を非常に応用させた問題を出題します。簡単な知識を使って思考力を試す試験です。 たとえば、筑波大附属高校の過去問で次のようなものが出題されました。「今度あなたの町に遊びに行きます。私があなたの町に行ったら、町の中を案内してください」(たしかこんな内容でした)英作文。。。大抵の中学生は「行ったら」を見た瞬間、「if I visit」とためらいもなく書いてしまうところです。正解は「when I visit」ですね。行くことが予め確定しているので「時間の問題」ですよね。 一方私立難関高校の傾向は、一般的には「発展の基礎」です。思考力はさして問題としない代わりに難解な単語や塾に通っていないと絶対に習わないような文法を使うことがあります。早稲田大学高等学院なんかだと長文の中に仮定法を使った文が4~5文くらい含まれていることもあります。思考力を試す私立高校ももちろんありますので(例えば桐朋高校など)、あとは個別具体的に研究することをお勧めします。 そろそろ志望校に向けた個別の対策に目を向けていく時期ですので、傾向は夏前までに押さえておきましょう。過去問の練習素材としては、国立高校と都県立の独自入試はある程度似ているといってもよいので、互いに参考にしてみてもいいかと思います。私立には多種多様な傾向があるのでなんともいえませんが、一般的にほぼ同じくらいの偏差値の学校であれば傾向もだいたい似ています。
2007.06.21
コメント(0)
-
教師の口癖:「家で見とけー」。なんじゃそりゃ?
「ここ大事だけど、今日は時間がないから各自、家で見とけー。」と言う先生をよく見かけます(汗)。例文だとか熟語・慣用句などを目の前にして、「見とけー。」は私も昔よく使っていました。教える立場だと時間の関係からつい使ってしまうセリフの1つです。しかし、よく考えてみると、この「見とけー。」はすごく不親切で無責任な言葉だと思いませんか?「覚えておけー」ならまだ少しは指示の具体性があります。 「どこがどのように大事だから、どのくらいの時間をかけてどのように覚えるといいのか」まで説明するのが面倒くさいとか時間がないとかいう場合にこの「見とけー」を使っていたと思います。少なくとも「これは大事だから家で覚えておけー」であれば許容だと思えますが。 実際私がまだまだ青二才だったころ授業の研修をしてくださった偉い先生でも「見とけー」を普通に使っていました。「見とけーって何?意味不明...」と思うのは私だけでしょうか。「本当に見るだけでいいの?それとも覚えろということ?」と突っ込みたくなります。なぜなら、「見とけー」には先生や状況によって温度差があり、本当に見ておけばいい時もあれば、暗記して欲しい場合もあるからです。実は学校の先生や塾の先生が「見とけー」と言った場合、ある種の面倒くささからこう口にする事が多いです。或いは生徒の自主性を信じている(or過信している)のでしょうか。 本当に見ておくだけでいいもの(例えばテキストの端のほうにあるコラム的なものなど)もありますが、「見とけー」で済む内容はそんなに多くはないので、このセリフを多用する先生はちょっと気をつけたほうがいいですね。授業放棄ですよね?「見とけー」の内容がテストで出てしまったら詐欺師ですね。先生が「見とけー」という時にはその先生はかなり弱気になっています。中学生の皆さんは、先生が「見とけー」と言ったら次のように言い換えましょう。「ここはテストに出るかもしれないから、一応教えた事にしておくぞ」です。「見とけー」の箇所が例えば慣用句だとかいった場合結構重要だったりしますので実は「見とけー」と流されたところは要チェックです(^-^;A。少なくとも「差」のつく学習内容に違いありませんね。Top10の生徒とTop30の生徒の差は案外こういうところにあります。。。
2007.06.19
コメント(0)
-
とても恥ずかしい英語
唐突ですが、やっぱり英語って難しいですね。中学生に英語を教えている私がいうのもなんですが、ネイティブのようにニュアンスの違いに気付かずに話している事があるということですね。今日、ある外国人とお話しました。「今日はすることがない」という英語。これは中2くらいで言えるようにはなるのですが、私は今日、"I have to do nothing today.と言ってしまい失笑を買いました。とっさにこう言ってしまうものですね。私たちは日本人なので頭の中で文法を組み立てて、"I don't have to do anything."=I have to do nothing."つまり「否定文+any=no」という回路を機械的に口に出してしまいます。「nothingって難しいですね」という旨を伝えたら、「意味を考えるよりもnothing自体の使い方をパターンで覚えた方がいい」と言われました。そのパターンとは1、文頭に置く。Nothing is wrong with my car.2、Be動詞かhaveの直後に置く。I have nothing to do today.の2通りだそうです。それ以外は「否定文+any」が無難だということです。日々勉強の私でした(恥)(^-^:A侮れないものです、Nothing!「私にはすることがない」(I don't have to do anything.か I don't have anything to do. か I have nothing to do.)であります。
2007.06.18
コメント(0)
-
英単語の効果的な覚え方(負荷を掛けるからこそ覚える)
今日は効果的な単語の覚え方をご紹介します。もちろん私がここに紹介する覚え方が最高かどうかはわかりません。しかし、分析的にも実践上も、かなり効果はありますし、効率もよいです。リスクはありませんし、一度やってみて効果がないと思ったらやめればいいだけのことですから、まずは一度試してみてくださいませ。 単語カードを使います。(理由は、なるべく「問題形式」にしたほうが効果があるからです。よく、「単語集の左側を隠して、1つ1つ下にずらしながら覚えていく」という方法をとる生徒がいますが、これでは書いてある順番や場所で覚えてしまい、覚えたようで覚えていないという事態がよく起こります。)手順1.覚えたい単語を、単語カードに写します。(表面に日本語、裏面に英語、そして何より、ボールペンで丁寧に写してください。ここが一番たいへんです。本気で覚えたいならば気合いで乗り切るんだ!)手順2.覚えたい単語を全て写してしまったら、「英語→日本語」すなわち「和訳」の訓練です。(知らない単語をカード化しているわけですから、めくるたびに「わからない」となります。この時点では、30枚のカードのうち、5枚わかればマシなほうです。わからなかったからといって、ここで「漢字の練習」のように何十回と書き取って練習してはいけません。まずは、「目に焼き付ける」ようなイメージで裏と表を2~3回見比べてください。「覚えよう」という気で20秒くらい。出来れば発音もしながら。そうしてすぐに次の単語へと移ってしまってください。これをやっていって最後の単語までたどりついたら、また最初の単語から同じ事をやってください。今度は2度目ですからおそらく10コくらいは言えます。そして2度目も最後までたどりついたら、また最初からやります。すべてスラスラと「英語→日本語」が言えるようになるまで続けてください。たぶん6回くらい回せば30コなら覚えるはずです。)手順3.次に「日本語→英語」すなわち「英訳」の訓練です。手順2と同じ要領でやってみてください。手順2がスラスラならばこの手順3は4回くらいでマスターできます。(やはり言えなかったからといってその場で何十回も書き取りをするのだけはやめてください。)手順4.最後に「日本語→英語の書き取り」です。日本語を見て、その日本語を英語で書いてみよう。見事正解ならば次の単語へ進む。答えと違っていたら、その場で「3回」(絶対覚えるぞ、と思いながら)練習する。やはり、ここでも何十回と書き取り練習するのだけはやめてください。そして次の単語に取り掛かる。またわからなかったらその単語も「3回」書き取る。そして最後の単語までいったらまた最初から同じようにやる。以上の4手順で単語は比較的スピーディーに、しかもいつまでも忘れない「強い記憶」(こっちのほうが大事)になります。 「こんな手順踏むのは面倒くさい」という人のために簡略バージョンがあります。手順2と3はやらずに、「手順1の次にいきなり手順4へととぶ」やり方。中1以外ならばこの「簡略バージョン」でもいいでしょう。(ただし、最初からすごい負荷が掛かりますので「根性」が必要です)。今日のお話の要点をひとことでまとめます。「30回書き取り×1セット」よりも「3回書き取り×10セット」の方が覚える。(大きいのを1回よりも小さいのを何回かに分ける!)
2007.06.16
コメント(2)
-
記憶力up術紹介!(嘘っぽいけどホントです)
記憶力up術…暗記が嫌いな方はぜひ次の訓練で記憶力のある脳を作りましょう。(なんだか胡散くさいですが、実際に効果のあった訓練です。ノーリスクですのでやってみる価値ありです。蛇足ですが、子どもはこういう情報はかなり喜びますので、親御様はぜひ子どもに勧めてみてください(^0^/ )1.就寝時明かりを消して目をつむる。2.次に、眠りに落ちるまで、「その日にあった出来事」を逆から思い出していく。たったこれだけのことを2週間続けてみてください。これはある著書(大脳生理学系)の中で紹介されていた方法で、私は実際に高校生のときに実践していました。(「記憶」には3段階あり、それぞれ「記録」「保持」「再生」です。我々がテストで試されるのは最後の「再生」です。頭のどこかに保持されているものを「引き出す」能力です。上に書いた方法はこの「再生」のステップを強くしてくれます。というか、結構有名な方法ですが)。2週間後くらいで、物覚えがよくなったと実感しました(単なるプラシーボみたいなものかも知れなかったのですが)。このころ私は1日に70~80コ位の新出単語を覚える事はできるようになっていました。ただし、昨日私が書いた「復習の仕方」とセットにしなければ覚えた単語も片っ端から忘れますので必ず昨日の復習法とセットでやってみてください。(単語にもやはり「効率がよく、確実な覚え方」があります。来週中にお届けします。) 上記の「記憶力up術」において気をつけるべき点は1点。とにかくなるべく細かく詳しく思い出そうと努力する事。どうしても思い出せないならば、それは捨ててその前にあった出来事へと進んでもいいのですが、「なるべく細かく」を合言葉に! 例えば私の場合、こんな感じです。「さて、寝ようか。えっと、今明かりを消した。その前はトイレで小便をしてたな。トイレの芳香剤が干からびてたな。手はどこで洗ったっけ?あ、そうそう洗面所だ。その前は洗面所で歯を磨いたな。少しだけ歯から血が出たな。うがいは何回したっけ?う~ん、思い出せない。じゃあ、その前は…コンタクトをはずして…」という感じです。これを眠りに落ちるまで行ないます。2週間!がんばってみてください。途中で邪念が邪魔しますが、打ち勝ってください。(邪念とは…例えば好きな子のことを考えたり妄想したり、ゲームのボスキャラの倒し方を考えたり…)などです。面倒くさくても2週間続けてみてください。ちなみに、プロフィールにある「偏差値21上がった子」はこの訓練を実践してました。
2007.06.14
コメント(0)
-
勉強の効率は復習の仕方にあり!
同じ時間勉強しているのに、ある子は90点、ある子は60点・・・。正直に言いますが、「才能」の結果とも言えるでしょう(あ~耳が痛い!)。しかし実もフタもないことを言っても始まりません。私たちの課題は結局、「限られた才能の中で最大限の効果を発揮する」勉強の仕方です。 昨日お伝えした通り、今日は「効率のよい勉強法」をご紹介いたします。この方法はある有名な精神科医(誰でも一度は名前を聞いた事があると思います)の方が著書の中で紹介したものを、私が実際に学生時代に使用する中でより実践的にアレンジしたものです。一言で言えば、ズバリ「復習の仕方」です。(「そんな月並みなことか」とあなどらずにまずは読んでみてください。)「いつ」「どれほどの時間をかけて」「何を」復習するのがもっとも効率的か。「いつ」について。まずは最初の学習(学校の授業や塾の授業や参考書での自主学習)を終える。次に9~14時間後に一回目の復習(この「9~14時間後」が真夜中などになってしまう場合には「翌日」でよい)。最後に1週間後に二回目の復習。 「どれほどの時間をかけて」について。9~14時間後に行なう「一回目の復習」では、最初の学習の3分の1から4分の1くらいの時間をかける。1週間後の「二回目の復習」では「一回目の復習」の半分くらいの時間をかける。例えば、最初に授業などで1時間学んだ内容は、翌日に15~20分の復習をし、1週間後に10分ほどの復習をする。つまり、3回の学習でだんだんと時間を短縮していくことになります。 「何を」について。だんだんと時間が減っていくわけですから、当然全く同じことを繰り返すわけではありません(たまにこのような復習の仕方をする生徒がいますが、時間ばかりが掛かりすぎて、学習内容が先に進まず、結果手薄な箇所が出現し、復習どころではなくなります)。大切な事は、「一度できた問題は二度は解かずサラっと見直す程度」というサジ加減です。つまり、できなかった問題の解説をよく読み、できなかったその問題だけにもう一度チャレンジして、正解を得たらそこで完了とするのです。実践すればわかりますが、前日に出来た問題は翌日もできます。翌日にできた問題は1週間後もできます。そして1週間後にできなかった問題(つまり最後までできなかった問題)には特別な印をつけておいて、特別にもう一度解答を読んでさらにその翌日にチャレンジする。それでもできないようであれば、もうこれは相性の悪い問題なので、間違える原因を先生に聞くことです。 「以前できなかった」問題が「できる」ようになる、このときにこそ得点は伸びていることになります。たいていの中学生は(高校生にも少なからず当てはまるのですが)復習をしたがりません。その理由は、「自己満足したいから」です。学習内容が先へ先へ進むことが彼らの充実感を満たします。「俺(私)は今日こんなに進んだorこんなにたくさんの量を勉強した」と満足したいのです。復習では「ページ数」が先へは進みません。だからばかばかしくなる。 それにしても、1ヶ月後に復習するのではいけないのか?という疑問もよく聞かれるのですが、答えは「いけません」です。1ヶ月後の復習では復習そのものに時間がかかりすぎます。1ヶ月間ほったらかしになっていた事柄は、定着していないので、1ヵ月後に復習すると内容を思い出すのだけで非常に時間が掛かりすぎ、初見の内容と同じくらいの学習時間を必要とします。1ヶ月前に出来た問題ができなくなっていたりします。 最後に、上記の復習法を端的な言葉でまとめます。「復習は大き目のを1つではなく、小さいのを2つ」が鉄則です。
2007.06.13
コメント(1)
-
中学生にとって無駄な勉強
中学生に「勉強したいか」と尋ねると「いいえ」と答え、「志望校に受かりたいか」と尋ねると「はい」と返ってきます。 要するに「勉強はしたくないが、志望校には受かりたい」と考えているという事になります。これが大人の世界では「そんな虫のいい話があるか!」と叱られてしまいますが、我々大人が中学生に対して「つべこべ言わずにとにかく勉強しろ!」と言っても問題は解決しない事の方が多いようです。むしろ、中学生からは「この大人は物事を効率的に達成する能力のない人だ」と見下されるか反感を買い、言う事を聞くような事はほとんどないです(経験上)。 上記のような、大人から見れば「虫のいい」願いは、より正確に表現すれば「出来る限り無駄を抑え、最小限の努力で最大の成果を得たい」、すなわちこのケースでは「無駄な勉強はしたくない。効率のよい勉強法があれば知りたい」と換言できるのではないでしょうか。 ここで、昔かたぎの大人の中には「勉強に無駄なんてない!効率や要領ばかり追ってもそれによって身につけた知識などすぐにはがれてしまう。遠回りでもがむしゃらにがんばれ!」などとおっしゃる方も多数いらっしゃいます。この場合の「無駄」には2種類ありますね。1つ目は「学習内容」の無駄。2つ目は「勉強の仕方」の無駄。いずれにしても私は「無駄」だと考えます。少し乱暴な言い方になってしまいましたが、学習内容にも勉強の仕方にも無駄は確実に存在します。(偉そうな言い方をしますが)日本人には今も根強く「訓練主義」に対する美徳の観念があるように思えます。わざわざ辛い方、遠回りな方を選ぶクセ?を日々感じます。 仮にこの昔かたぎの大人たちの言う事、つまり効率性を無視した訓練主義を実践しようものなら、それこそ中学生は寝ても覚めても勉強勉強で、部活をやる時間も、友達とお話する時間も、考え事をする時間もetc いろいろな「青春固有の貴重な時間」が一転「勉強ばかりの灰色の青春」と化すに違いありません。中学生らしくあるためにこそ、「効率のよい勉強の仕方」は身につけておくべきだと私は考えます。では「効率のよい勉強法」とはいったいどんなものなのでしょうか。私の一押し(私も実践していました)の方法があります。明日の日記でご紹介いたします。またお待ちしております。
2007.06.12
コメント(0)
-
今日こそは、単語・熟語テストでいい点取ってくれ!才能VS努力
本日土曜日は都内のとある校舎への出講です。ここで私が担当するクラスの生徒たちは、知識に貪欲で授業を非常に熱心に聞いてくれます。まず、雰囲気が良いです。笑うべき時に笑い、悩んでもらいたい時に首をかしげる。生徒と講師の呼吸がピッタリ合っていると実感出来ます。 こういうクラスの生徒たちはまず間違いなく伸びます。。。ある条件をクリアーしていれば。。。その条件とは1.指定された宿題を必ずやる事。2.毎回行なわれる単・熟語など小テストで8割以上をキープし続けること。の2点です。「8割以上をキープし続ける」と簡単に言いましたが、実際に8割をキープすることは、小テストではそれほど難しい事ではありません。「単・熟語などの小テストは苦労と得点がほぼ比例する」と言っても過言ではないと思います。嘘はつきたくないので正直言いますが、実際に小テストですら「苦労と得点の割合」での個人差は出てしまいます。しかし、8割を下回った場合、まずは才能うんぬんよりも「それにかけた時間と苦労」の少なさを疑うべきです。「じゃあ、時間がない人はどうすればいいの?」・・・このあたりについても解決策はあります。来週中に綴りたいと思っています。 「才能」・・・私自身も含めほとんどの人にとって耳が痛い言葉です。本当は避けて通りたい話題です。私も中学・高校時代には数学が本当に苦手でした。中学生のころから「俺は数学的センスは無いな」と分かっていました。しかし、少なくとも小テストなんかでは絶対に8割は下回りませんでした。どんなに嫌いで才能がないと自分で分かっている教科でも小テストくらいなら「苦労と根性」でなんとかなるものです。実際、私は数学を英単語のように「単語カード」で覚えていたくらいです(普通ありえないですよね?)。そこまでしないと数学で得点できなかったのです。大き目の単語カードの表面に問題文を書き、裏面に解き方の手順を3手順くらいでまとめておき、そらで言えるまで何回も練習しました(汗)。考えても分からないのでとにかく暗記してました(こんなこと数学の先生たちに言わせればナンセンス以外の何者でもないですよね。。)。こんな数学オンチな私は中学最初のテストで数学は50点満点で17点でした。平均点は忘れましたが恐らく平均の半分位の得点でしょうか。しかし既に中1の3学期の段階で数学は50点中40点はとれるようになっていました。何も自慢なんてしたいわけじゃありません。伝えたいことは次のことです。「やはり実際に才能の差はあると思う。でも精一杯やってみれば、その人なりに成果は必ず出る!」ということです。 中学生の時に陸上部の顧問の先生が言っていました。「男子の100mは努力をすれば誰でも12秒台まではいける。その先は、『才能』だな」と。これを聞いて私は喜びました。なぜなら、12秒といえばいわゆる「あいつ運動神経いい!」と言われるくらいの速さじゃないですか!そこまでいければ十分と考えました。実際勉強においてもほぼ同じ事がいえます。この「100m12秒」が「テストの8割」と同じ加減なのです。 実際、私の数学はそれ以上にはなりませんでした。しかし、単語カードであそこまで才能の無さを隠しおおすことができ、高校入試でも十分通用したことは「その人なりに伸びる」という証明ではないでしょうか。 なんだか最初から私の経験ばかりだし堅苦しくて辛い話になってしまいましたが、このブログでは「面白おかしい話」よりも「得をする話、有益な話」を主に私の9年間の教壇生活から引っ張ってきて(押し付けがましいようですが)読者のみなさんにご提供できたらと考えております。できるだけ毎日書き綴っていきます。特にムダのない勉強の仕方、暗記の方法など実践的な得点アップ術を出来る限りご提供したいと考えております。今後ともよろしくお願いします(^0^)/
2007.06.09
コメント(0)
全48件 (48件中 1-48件目)
1
-
-

- 楽天アフィリエイト
- 【楽天ROOM 始めやすいジャンルのご…
- (2025-06-15 15:14:58)
-
-
-

- 働きながらの子育て色々
- 美味しいごはん
- (2025-11-16 23:15:19)
-
-
-

- 軽度発達障害と向き合おう!
- 【書評】『小児・成人・高齢者の発達…
- (2025-11-17 06:15:32)
-