2005年12月の記事
全26件 (26件中 1-26件目)
1
-

柚子(ゆず)をとむらう
昨日、掃除をしていたら(゜ロ゜*)わっ!!果物を盛った器の底で柚子がぐじゅぐじゅに柔らかくなっていた!!この柚子、冬至の後、スーパーで見つけ、今年最後の風呂に浮かべようと買ったもの。スーパーで見つけた時、すでに元気がなかった。だから、私が買わないと捨てられると思って(それに安かったから)買ったのに、使わないで捨てることに・・・。牛肉、豚肉、魚、貝、タコ、イカ・・・。それに米に野菜に果物・・・。この一年、私が生きるために、どれだけの生物が犠牲になったことか・・・。自分が生きるためなら仕方が無いけれど、このように、使わないで腐らせるということが、何回あったことか・・・。そう思いながら、卵のパックに土を入れ、その中に取り出した柚子の種を蒔いた。柚子をとむらうように・・・。 +++++●今年も後数時間で終わりです。リンクしていただいて、ご紹介いただいて、コメントをいただいて、人気blogランキングや日記才人のボタンをクリックしていただいてそして読んでいただいてありがとうございました。m(_ _)m「人気blogランキング」には、「環境問題」で登録していますが、毎日環境問題について書いているわけではありません。柚子を腐らせるような、もったいないことをしながらも「エコロジー」、「ロハス」について考えています。2006年が、皆様にとってよいお年でありますように・・・。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月31日*ショウガツゴ* UP
2005.12.31
コメント(2)
-

♪山人(やまど)は戻るし・・・ああ、忙しい!!
♪山人(やまど)は戻るし、赤子は泣くし、かまどは煮えて、しゃくしも見えず、やれ、尻、かいや。・・・・・・・山からとうちゃんは、戻って来るし、背中にしょった赤子は泣くし、竈は、吹いてるのにしゃもじのある場所が・・・。おまけに、お尻がかい~。というこのユーモラスな歌、忙しい時に、父がよく歌ってました( ̄▽ ̄) ただ今、私もそんな状態。正月用の買い物にも行かないといけないし、掃除だって完全には終わっていない。年末で面白いテレビをやってるから見たいし、日記も書かねば・・・。そんなことより、年賀状・・・ 。_| ̄|○嗚呼、忙しい!!!11月に大掃除をやって、年賀状を書いておけばよかった・・・。毎年、後悔をするのですが、みんなが正月というカウントダウンに向かって頑張る、年末のこの忙しさ、ちょっと好きです。後、一日とちょっと。さあ、頑張ろう!! 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月29日*◎民具:もろぶた◎の語源* UP
2005.12.30
コメント(0)
-

12月のおしゃれ手紙
はるなです。年末も押し詰まったとです。12月は、なんだか体調がすぐれず、日記を書かなかった日もあったとです。なのに、今月も、またリンクしてくれた人がいるとです。☆★☆★12月のリンクしていただいたblog★☆★☆★★気になる最新求人情報 影武者さん★ MY SOURCE 豊かさを愉しむ幸せアーティスト♪かなカナさんありがたかとです(ノД`)12月、書けなかったこと、書きたかったことを、メモしとくとです。★少子化問題★天皇問題★「負け犬の遠吠え」★30年代のこと★テレビドラマ★会社のこと★エコ生活などなど・・・。今年は、 人気blogランキングに登録したとです。おかげでいろんな方の日記が読めるとです。来年は、そんな日記も紹介するとです。(^-^)☆★☆★リンクしていただいたblog★☆★☆★11月の「おしゃれ手紙」 10月の「おしゃれ手紙」 9月の「おしゃれ手紙」 8月の「おしゃれ手紙」 7月の「おしゃれ手紙」 6月の「おしゃれ手紙」 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月29日*◎民具:もろぶた◎の語源* UP
2005.12.29
コメント(2)
-

大阪しぐれ:医者の車引き
「医者の車引きや」と隣の席のお局が言った。「はっ?なにそれ??」と私が聞くまでもなく、「あっちでも、こっちでも、行くとこ、行くとこ悪いとこばっかりや」とお局は言う。ものごとが悪い方にばかりいくことを「医者の車引き」と言う。私も仕事を机ごと取られるという肩たたき、いや肩蹴りにあったが、お局も長年やった仕事を失い、がっかりしている。「なんか、美味しいもんで食べて元気を出そう」と女3人で、イタリアンレストランでランチ♪「来年の今頃、どうなっているやろ、私達」と私が言う。「わからんわー」とお局。去年の今頃、こんな会話をするとは思ってもいなかった・・・。来年のことは分からないけれど、今年の仕事は終わった。来年は、来年の風が吹く。・・・・・・・・・・●大阪しぐれは私が大阪で知った「へえー!!」や「( ̄▽ ̄) 」なことを書いています。●イラストは「波に千鳥」。とり年ですから。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月28日*おつりはマッチ * UP
2005.12.28
コメント(0)
-

町屋と町屋風
友人と今年の10月20日に、大阪の梅田に出来た、ファッションビル「Nu cyayamachi(ぬー ちゃやまち)」に。ちょうど、お昼時だったので、「冶之助(じのすけ)」に入る。「わー、いい感じ! ( ゚∀゚)人(゚∀゚ )」と友人と私は声を上げた。店の中に入ると石畳になっている。(路地風)靴を脱いで上に上がると、着物の布で作ったと思われる、かわいい座布団。窓越しに廊下を見ると、昔の絵の入ったガラス戸がはめてある。電気の笠も昭和20年代の映画に出てくるような、レトロでシックなもの。梅田という繁華街のビルの8階にあるのに、京都の町屋にいるみたい。私の大好きなノスタルジックな雰囲気にうっとりとしてしまう。古いもの大好き、町屋大好きの私が、ここでちょっと考える。これは、古く見えるだけで、古いものではない。私は、古いものを残し、それを活用することに大賛成。けれども、以前からあった路地や町屋を潰して、ビルを建て、町屋ブームだからといって、ビルの中に路地のある町屋風な場所を作る・・・。これって、自然を壊して、自然に似た*「ビオトープ」*を作ることに似てる・・・。いかにも日本的な発想だ。路地と路地風。町屋と町屋風・・・。「風」がついただけで大違い。まあ、「冶之助(じのすけ)」は、素敵だったから、また行きますが・・・。この辺が、私のミーハーなとこ _| ̄|○**ビオトープ**(Bio生物の生息環境を意味する生物学の用語。また人工的に作られた生態系を指す言葉。言葉はラテン語とギリシア語からの造語で、「bio(いのち)+topos(場所)」。学校の池をビオトープにするのもいいけれど、田んぼをむやみに潰してはならないなど自然を守ることも忘れてはいけない。◆イラストは、鶴の香合。(とり年ですから) 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月27日*父の麦わら帽子:遠い故郷/◎民具:もろぶた◎* UP
2005.12.27
コメント(4)
-

昔語り:不思議な贈り物
歳末助け合い運動の赤い羽根は、私に、「貧しい人に愛の手を」という鉛筆をくれた。それ以外にも貰った物がある。貧しい農家が、まがりなりにも、年を越せたのは、いくばくかのお金が手に入ったから。赤い羽根のおかげと感謝しなければ・・・。その他にも、「?」という不思議な贈り物が、あった。それは、長方形の黄みを帯びた白いものだった。私たち家族は、額を寄せ合って考えた。「なんだろう??」考えても、考えても分らなかった。クセのあるにおいがした。「消しゴムにしては大きいな」父は笑いながら言った。食べるものなのかもしれないが、食べ方が分らない。仕方がないから、放っておいたら、その四角いものに、青いカビが生えてきた。もう、この辺で、勘のいい方は、お気づきでしょう。答は、はい、「チーズ」。それは、今から40数年前の贈り物。その頃は、クリスマスプレゼントというより、年越しの贈り物だった。家族で思い出しては、笑っていたのに、その中の一人、父は、今年はいない。。★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★☆★毎月26日は昔の思い出を書いています。★これは父の死んだ2002年の12月に書いたものを再度アップしたものです。★参考 ◎父の麦わら帽子◎ 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月25日*クリスマスケーキを初めて食べた日* UP
2005.12.26
コメント(4)
-

賢者の贈り物:貧しくとも心豊かに・・。
愛し合う貧しい夫婦がいた。夫は妻の美しい髪を飾る櫛を買いたいと思った。妻は、夫が大切にしている懐中時計の鎖を買いたいと思った。あるクリスマスの日、夫は、大切にしている懐中時計を売って妻に髪飾りを買い、妻は、自慢の髪を売って、夫の懐中時計の鎖を買った。O・ヘンリーの「賢者の贈り物」という物語。お互いの贈り物は、無駄になったけれど、この夫婦は幸せなクリスマスをおくったに違いない。★☆。。。★☆。。。★☆。。。★☆。。。★☆今年の夏、友人が東京から来たので京都で待ち合わせた。約束の時間に京都駅に着いた私は、友人に電話した。「今、JRの京都駅に着いたよ。」すると友人が言った。「えっ!!JRで来たの?京阪電車で来ると思ったから、JR京都駅から京阪の駅に来たよ。」お互いに、お互いの都合がいいようにと思ってしたことが裏目にでた。そのために、数十分遅れたけれど、私達は楽しい、一日を過ごした。リストラの嵐が吹こうが、けっこう楽しくやっていられるのは、きっと友人に恵まれているからかもしれな。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月24日*ヤドリギの下でキスを・・・。* UP
2005.12.25
コメント(6)
-

昭和30年代の灯り:「若いおまわりさん」
「若いおまわりさん」(1956 /昭和31年)もしもしベンチでささやくお二人さん早くお帰り夜が更ける野暮な説教するんじゃないがここらは、近頃ぶっそうだ話の続きは明日にしたらそろそろ広場の灯も消える♪♪♪♪♪♪友人と大阪は梅田界隈をうろつく。クリスマスセールでどの店も活気がある。道路の並木道には、針金がギリギリと巻きつけられ、まるでキリストのいばらの冠のよう。夜ともなれば、光のシャワーが降り注ぐ。都会の夜は、光輝いている。+++昭和30年代には夜は暗かった。私の家は、田舎にあったので、月と星の明かりが頼りだった。街でも、ある一定の時間が過ぎれば真っ暗になった。昭和31年のヒット曲「若いおまわりさん」では、広場で遅くまで話し込む「アベック」に「♪そろそろ広場の灯も消える」から帰るようにと、いっている。この頃、小学生だった私は、ベンチという言葉を知らず「♪もしもしベンチでささやくお二人さん」を「♪もしもし元気でささやくお二人さん」と元気よく歌っていました。( ̄▽ ̄) 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月23日*月待ち・「二十三夜講」* UP
2005.12.24
コメント(0)
-

*節季払い*
私が子どもだった頃、家には現金収入がありませんでした。今のように簡単に現金が手に入らない時代でした。だから、買い物は、いつも「ツケ」にしてもらっていました。支払いは、年二回の「節季払い」。八月と十二月、つまり「盆暮れ」。六月と十二月というところもあったようですが、どちらにしろ、暮れは支払いの月。母はお金をどうやって工面してきたのか、支払いをしていました。支払ったらもらえるのが、暦や餅を焼く金網。暦も金網も大切に使いました。この年二回支払いの「節季払い」制度は、江戸時代からのものだそうです。買う方もきちんとルールを守ったから続いた信用取引です。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月22日*正月準備:年の箸 * UP
2005.12.23
コメント(2)
-

トリビアの井戸:カボチャの語源
今日は冬至。冬至とは24節気のひとつで、昼が最も短く、夜が長い日になります。太陽の光が弱まり、その日を堺に日照時間が長くなる事の節目として、古くから信仰や行事が行われたと伝えられています。昔から冬至の日に、カボチャ(なんきん)を食べると風邪をひかないいって食べる風習があります。本来カボチャは、夏野菜。冷蔵庫などがなかった時代、夏野菜を冬に食べられるということだけでも、ありがたいことだったのかも・・・。カボチャは、ポルトガル人によってカンボジア経由で持ち込まれました。よって、カンボジア→カンボジャ→カボチャとなったそうです。へええ~!!冷蔵庫を使わなくてもいいものを食べる。これも、◎えこ◎です。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月21日*「松迎え」* UP
2005.12.22
コメント(6)
-

間違いない!:市民会館は、誰のもの。
「 第九」を聴きに行った会場は、コンサートホール、図書館、広場、会議室などがある地域の「文化会館」。コンサートホールに入ってびっくりした。正面に大きなパイプオルガンがある。年間、何回使うのだろう。人口10万あまりの小さな市にパイプオルガンが果たして必要なのだろうか。「第九」が始まる前に、パイプオルガンの演奏があった。夫「ボクは、パイプオルガンは、どうもなぁ~。」私「このパイプオルガン、無駄にしていませんよと使っているんやわ。間違いない!(長井秀和風)」本当に文化的な市をと思うなら、もっと違ったやり方があったはず。例えば、隣の市と協力して、駅に近い一等地に作り、内容のあるものにするとか市民の要請があれば、合唱の練習のための場所を確保するとか、講師を紹介するとか・・・。里山を保全するための会議場を確保するために、毎回四苦八苦した私は、そんなことを思った。パイプオルガンどころか、このコンサートホールが本当に必要なのだろうか。これは、市民のためのものというより、業者を儲けさせるためのものだ!間違いない!*(長井秀和風)*。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月18日*火の用心* UP
2005.12.19
コメント(6)
-

新歳時記:師走に「第九」を聞く
後10日あまりで、お正月。大掃除をしなければならないし、年賀状も書かなければならない。障子を張り替えたりもしなければならない・・・。正しいお正月を迎えるためには、やらなければならないことがいっぱいあるはず。でも、そんなことは、何もしないで、今日は、オッチャン(続柄・夫)と「第九」を聞きに行った。オッチャンは、クラッシック音楽が大好き。特にベートーベンが好き。毎年、12月になると「第九」を聴きに行く。「第九」とは、ベートーベンの交響曲第九番のこと。今年も、先週の日曜日に娘のミナと行ったばかり。年末には、全国各地でベートーベンの「第九」が演奏されます。これは日本だけの現象で、その起源には、その昔、楽団員の越年資金を稼ごうと始まったものだとか。いわば「餅代稼ぎ」。餅つき、障子の張替えなど新年を迎えるための用意が次々に消えていくなかで、師走に「第九」を聴くというのは、今や新しい歳時記になったようだ。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月18日*火の用心* UP
2005.12.18
コメント(4)
-

時代の歌:「リンゴ村から」
戦後10年を過ぎた「ALWAYS 三丁目の夕日」の時代、昭和30年代は、各地に、まだ美しい里山の風景が残っていました。私も、田植えや稲刈りなどの農作業を手伝ったり、川で洗濯をしたり、山に薪をとりに行ったり・・・。昔話の「桃太郎」たちと同じような生活が昭和30年代まで続いていたのです。ところが、この頃から、「ALWAYS 三丁目の夕日」の中に出てくる、集団就職の少年少女のように、少しずつ、都会に行く人たちが増えてきました。故郷を捨て、家族を捨て、恋人を捨て・・・。その頃、大ヒットしたのが「リンゴ村から」。「リンゴ村から」(音に注意)1 おぼえているかい 故郷の村を 便りも途絶(とだ)えて 幾年(いくとせ)すぎた 都へ積み出す 真赤なリンゴ 見るたび つらいよ 俺らのナ 俺らの胸が2 おぼえているかい 別れたあの夜 泣き泣き走った 小雨のホーム 上りの夜汽車の にじんだ汽笛 せつなく ゆするよ 俺らのナ 俺らの胸を 3 おぼえているかい 子供の頃に 二人であそんだ あの山 小川 昔とちっとも 変わっちゃいない 帰って おくれよ 俺らのナ 俺らの胸に・・・・・・・・・故郷の村、途絶えた便り 都と呼ぶにふさわしい遠い街東京、 真赤なリンゴ泣き泣き走った 小雨のホーム、 上りの夜汽車の にじんだ汽笛 二人であそんだ昔と変わらぬ山 小川・・・。歌謡曲にピッタリの哀しみのフレーズ・・・。テレビを買うために、お金を稼ぐために、帰れない故郷・・・。私達が故郷の岡山を捨てたのは、昭和37年でした。父母は、晩年を岡山で過ごしたけれど、私は、二度と岡山に住むことはありませんでした。たまに「行く」故郷の人の手が加わらない山は荒れて、三面コンクリートで、人の手を加えすぎた川は、細い水を心もとなげに流れています。昭和30年代の自然は、もう願っても戻らないのでしょうか・・・。「リンゴ村から」は、昭和30年代を象徴する名曲です。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月17日*哀しみの赤い羽根* UP
2005.12.17
コメント(2)
-

■魂呼び■二人使い/亡くなった人。
■魂呼び■臨終になると屋根にあがって「○○さん、もどらんせ、こっちじゃ」と死んだ人の名前を呼んだ。(兵庫県佐用郡佐用町)死者の名を表に出て屋根の方に向いて呼んだり、屋根の上で杓でもどって来いと招いた。(兵庫県・宍粟郡千種)棟にまたがって、一升瓶の底を叩いて死んだ人の名を呼んだ。(兵庫県・朝来郡旧上生野)■二人使い■死の通知は親戚、ジゲ(地下)、お寺へなされる。その時には、一人で行くと死人がひっぱるといって必ず二人で行った。他所へ住む子どもや、郡内の親戚へのヒキャクも二人で行った。魔おどしといって鎌など腰にさし、提灯をつけて行った。使いを受けた家では、食事を出すことになっていた。そしてヒキャクが帰ってしまった後、用意をして出かけた。(朝来郡生野町)「日本の民俗<兵庫>」和田邦平・・・・・・●プロ野球の近鉄とオリックスで監督を務めた仰木彬(おおぎ・あきら)さんが15日、福岡県内の病院で死去したというニュースにびっくりした。70歳って若すぎる。この間まで、ユニホームを着ていたので、ほんとうにショック。●本田美奈子さん、白血病で死去。今日、テレビで、その闘病生活を見た。38歳という若さで、悔しかったと思うと涙が出た。健康で生きているって、本当にありがたいことなんだなって思う。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月16日*父の麦わら帽子:涙の蜜柑* UP
2005.12.16
コメント(6)
-

大阪しぐれ:死んだら地獄の一(いち)の客
会社に元取引先のKちゃん(68歳・・・何歳でもちゃん付けで呼ぶ)が来た。彼女は、年齢の割りに古い言葉や諺を使うので、私は、仕事をしながらも、しっかり、耳はそっちにいっている。「悪いやつがいるもんやな」とKちゃんは言う。「地震が来たらつぶれるマンションを作って、どないすんねん。」「そや、そや」と私達。「それに、どうや、次から次に、*ころも*が殺されて・・・」ため息混じりに、Kちゃんは言う。「死んだら地獄の一の客ばっかりや。」いやはや、地獄は、一番乗りを目指す客でひしめき合っている。**ころも**子どものこと。河内弁では、こどもは、ころもになり、「さざんかの宿」は「さらんかのやろ」となる 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月14日*事始め・・・煤払い/「サランカのやろ」 * UP
2005.12.15
コメント(0)
-
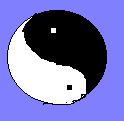
肩たたき?いや肩蹴り
本社から月、水、金の三回、S氏が来て、これまで私達がやっていたことを全てやる。ということは聞いていた。来年からということだった。しかし、来年を待たずに、S氏がやって来ることになった。空いている机が2箇所あったが、どこに座ってもらうか・・・。「社長にS氏の席を決めてもらおう」とみんなで言っていた。月曜の朝、社長がやってきて、「Sは、ここに座らす」と言って指差したのは、私の机だった。一同、呆然。私は、あわてて、他の席に移った。これって、肩たたきって言うより、思いっきり、肩蹴りじゃない。仕事を机ごと、とられたのは、2回目だ。へそ曲がりな私は、イヤガラセをやられると、辞めてやるもんかという気になる。S氏も同じ被害者と思うので、憎む気にはなれないし、いつもどうり、にこやかに、なにもなかったように過ごした。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月12日*まわしこ* UP
2005.12.14
コメント(6)
-

ロハス度チェック
*「ロハス」*って言葉をご存知ですか?読むたびにいつも納得してしまう、「サステナ・ラボ」さんのブログから、ロハスチェックをやってみました。*****ロハスチェックリスト*****1. 自然を愛し、自然破壊を大いに憂慮している。2. 地球全体の諸問題(地球温暖化、熱帯雨林破壊、人口問題、持続可能性に欠ける生態系、貧しい国における労働搾取)を明確に認識し、経済成長を制限するといった行動が必要であると思う。3. 環境の浄化や地球温暖化防止のために自分が支払った金が使われるのなら、もっと税金を払ったり商品が高くても購入する。4. 人間関係を広めたり維持することを重視する。5. 他人を助け、その独自な才能を発揮させることを重視する。6. 1つ以上のボランティア活動に従事している。7. 自分の心と魂を成長させたいと思う。8. 精神性あるいは宗教は自分の人生の中で重要だが、宗教右翼の政治の世界における行動には懸念している。9. 職場において女性はもっと平等に扱われるべきだし、ビジネスや政界に女性の指導者がもっと必要だと思う。10. 世界中の女性や子供への暴力や虐待を憂慮している。11. とくに子供の教育と幸福、地域社会の再建、生態学的に持続可能な未来を構築するために、政府はもっと金を出すべきだと思う。12. 政治の右翼でも左翼でもなく、また、どっちつかずの中道でもない新たな道を見出したい。13. われわれの未来には楽観的な見方をしており、メディアが伝えるような皮相的で悲観的な見方を信じることはできない。14. 自分の国によりよい新たな暮らし方をつくり出すことに関わりたいと思う。15. 利益を上げるという大義名分を掲げて大企業が行っている人員削減、環境問題、貧しい国での搾取を懸念している。16. ローンと支出は収入内におさまっており、収入以上にお金を使う心配はない。17. 成功すること、金を儲けて使うこと、富や贅沢品を重要視する今日的な文化は嫌いだ。18. 異国情緒ある外国の人や場所が好きで、自分とは異なる暮らし方を体験したり学ぶのが好きだ。 ******************** 18のうち10以上に該当すれば、ローハスをしている「生活創造者(cultural creatives)」だそうです。私が、×だったのが、6と13。6. 1つ以上のボランティア活動に従事している。病気になってから、里山保全の活動に参加をしていません。(ノД`)13. われわれの未来には楽観的な見方をしており、メディアが伝えるような皮相的で悲観的な見方を信じることはできない。年々地球環境は悪くなる一方。悲観的です。+++私が昭和30年代にこだわるのも、シンプルライフを目指すのも、ジャンクなモノを集めるのも、きっとロハスな暮らしを求めているんだろうと思う。**ロハス**健康で持続可能な社会を考えたライフスタイルのこと。アメリカの社会学者ポール・レイと心理学者シェリー・アンダーソンが提唱した「Lifestyle Of Health And Sustainability」の頭文字をとってLOHAS。ローハスともいう。サステナ・ラボさんのサステナもSustainabilityからつけられたもの。■参考■地球を救う127の方法 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月11日*お正月に読みたい本「焚き火大全」* UP
2005.12.11
コメント(13)
-

売るべきか、残すべきか・・・。シンプルライフ。
シンプルライフを目指す私は、今まで大事にとっておいた、お気に入りの骨董品やジャンクな食器を売ってしまう決心をしたのだった。次女のレイが来たので、一緒に食事。「この食器も売るんだから、今のうちにしっかり使ってね」と私。「(゚∇゚ ;)エッ!?売るん?もったいない~。そんなんやったら、私にちょうだい」とレイ。そこで私の決心が揺れる。私だって、本当は売りたくない。持っていたい。白洲正子には、およびもしないけでど、自分の気に入って集めた食器たちへの愛着は、なみなみならぬものがある。+++10月に一緒に白洲邸に行った友人。彼女が大阪から東京に引っ越す時、いろんなものを処分した。そんな彼女が、白洲邸から帰って「また、愛するモノに囲まれた生活がしたい」と言っていたのを思い出した。やっぱり、売らないでおこうかな・・・。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月9日*「ジャンク・スタイル」* UP
2005.12.09
コメント(4)
-

「コトの日」針供養
日本人は、物にも霊魂が宿っているものと考えた。その物を一年間酷使し、また暮れには捨去ることも多い。そうしたときに物に宿った霊魂が怒って妖怪となって人々を脅かすと考えた。そうした人々の観念は、室町時代に描かれた「付喪神(つくもがみ)草紙」がよく物語っている。そこで事納めのさいにはそれらの霊魂を慰めまつる風が生まれた。その一つに「針供養」がある。二月八日と同じく、十二月八日に針を休ませるために、この日針を使うことを忌み、豆腐やコンニャクなどに古針をさして川や海に流したりするのである。いずれにしても、この日は忌籠りをして、慎み深い生活をし、来るべき正月を迎えるため心の準備をする日であった。「民具の歳時記」 河出書房新書・・・・・・・・・・・・・昔はモノを大切にしていたんだな~。12月8日は2月8日と対照される「コトの日」で、両者とも「事八日」という。12月8日を「事始め」とした場合、2月8日は「事納め」。12月8日を「事納め」とした場合、2月8日は「事始め」となる。来るべき正月を迎える準備をするどころか、今度の土曜日からくる孫のちゅん太を迎えること準備をしなければ・・・。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月8日*七月(ななつき)の投げ座(ずわ)り* UP
2005.12.08
コメント(2)
-

「ALWAYS 三丁目の夕日」の◎えこ◎な暮らし
感動の涙を流しに、再び映画「ALWAYS 三丁目の夕日」を見に・・・。2回目だとストーリーがわかっているから、細かい部分まで見えます。目についたのが◎えこ◎な暮らし。昭和30年は、今のようにモノがなく、誰もが簡単にエコロジーな暮らしが出来ました。■路面電車東京でも、車の数は少なく、乗用車に乗るのは、一部の限られた人のみ。自動車修理工場を営む、鈴木オートにも、乗用車はありません。「スマートやな~、ミゼット」と言うCMで大人気の「ミゼット」と呼ばれるかわいい三輪自動車があるのみ。その代わり、路面電車がスイスイ。今、外国でも環境に優しい路面電車のよさが見直されているのですが、日本も是非、復活して欲しいもの。■地道=舗装されていない道。雨が降れば、ぬかるんで大変。けれども、舗装されていない道=地道は、雨を染み込ませる。各地で名水が枯れたというニュースが聞こえますが、それは、日本中隅から隅まで舗装したり、家を建てたりしたから。でも、雨の時のぬかるみは困るという現代人に「透水舗装」という雨水を染み込ませる舗装が開発されています。■繕う。昭和30年代は、繕い物は、みんながやっていました。テレビ、洗濯機、電気冷蔵庫の「三種の神器」を持つ、比較的恵まれた、鈴木家でも、息子の一平のセーターの肘に当て布をする、お母さん(薬師丸ひろ子)。今のパッチワークのように趣味でするのではなく、あたりまえとして暮らしの中にツギあてがありました。■冷暖房。映画は「春夏秋冬」と場面が移っていきます。夏は、一家に扇風機が一台あればいい方。みんなうちわでパタパタを涼をとります。冬には炬燵と火鉢が主なる暖房器具。冷房や暖房のある暮らしなど、思いもよらなかったのです。+++他にも、納豆売りや富山の薬売り、行商の人たちも皆、車でなく人力。地球温暖化など、思いもよらなかったあの頃、岡山でも冬になると、雪を見ました。*****参考*****「昭和30年代の写真日記」◎日本ちょっと昔話◎ 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月7日*花ふきん* UP
2005.12.07
コメント(2)
-

昭和30年代のりんご
「ALWAYS 三丁目の夕日」の中に出てくる、東北から東京に集団就職してきた、ロクちゃん。彼女のお土産は、籠に入ったりんごだった。今でこそ、りんごは年中食べられる、身近な果物だけれど昭和33年、「ALWAYS 三丁目の夕日」の時代には、めったに口に入らなかった。だからこそ、ロクちゃんは、りんごを田舎のお土産として、持ってきたのだった。私の育った岡山の田舎では特に珍しく、たまに見ることはあっても、それは遠い国の果物のようだった。それゆえに、りんごに対する憧れにもにた気持ちがあった。歌われている歌詞の中で、りんごは、遠い北の国のものというイメージが強い。♪私は真赤(まっか)な りんごです/お国は寒い 北の国・・・「りんごのひとりごと」♪りんごの ふるさとは/北国の果て・・・「津軽のふるさと」なんてったって、「お国は、寒い北の国」で「北国の果て」なのですから・・・。+++昨日、娘のレイが来たので、「りんご、持って帰る?」と言うと「いらん」ですって・・・。嗚呼、憧れだった、りんごも、今やこのありさま・・・。とはいえ、♪りんご畑のお月さんこんばんわ。・・・「お月さんこんばんわ」♪りんごの花びらが風に散ったよな・・・「りんご追分」の歌詞の「りんご」の部分を他の果物にしたら、やっぱり変。りんごって、やっぱりかわいくて、絵になる・・・。 「リンゴの歌」 赤いりんごに 唇寄せて 黙って見ている 青い空 りんごはなんにも言わないけれど りんごの気持ちは 良くわかる りんご可愛いや 可愛いやりんご 歌うは、椎名林檎!! 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月6日*父の麦わら帽子余滴:お泊まりメニュー(年末年始)* UP
2005.12.06
コメント(2)
-

黒猫は走る
会社に宅配便が届きました。「ご苦労さま!」と言って受け取りながら、「朝早くから、大変ですね、何時から配達してるんですか?」とお局が声をかけた。「朝は8時からです。」と黒猫氏。「早いですね、終わるのは?」とお局。「日付が変わっています。昨日も、配達が終わったのが、夜中の1時でした」と黒猫氏。「うわー・・・!」とそこにいた人が皆一斉に声を出した。いつでも、どこでも、どこからでも、どこよりも早く、どこよりも安く・・・。わがままな、消費者のために朝から夜中まで働く黒猫やカンガルー、象・・・。郵政民営化になったら、この傾向は、もっと強くなる・・・。殺人、リストラ、詐欺・・・。ますます悪くなる世の中・・・。来年になれば、よくなる・・・。昔は、そんなを信じてがんばれたけれど、今は、来年が信じられない。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月4日*守護聖女バルブの日の小麦* UP
2005.12.05
コメント(4)
-

植物のチカラ「宮廷女官 チャングムの誓い」
朝鮮王朝時代に生きた歴史上の実在の人物、チャングムの波乱万丈の生涯を描いた物語、「宮廷女官 チャングムの誓い」を楽しみに見ています。■ストーリー■時は朝鮮王朝時代。チャングム(イ・ヨンエ)は、両親を亡くしたのを期に、10歳にして宮廷に入ることになりました。宮廷であたえられた仕事は、かつて母親がしていたのと同じスラッカン(料理部門)。好奇心旺盛で友達思いのチャングムは、いろいろな事件に巻き込まれる。たびたび、王宮(職場)を追放されそうになりながらも、その機転で難を逃れる。原題の『大長今(テジャングム)』とは、「偉大なるチャングム(長今)」の意。 ・・・・・・・・前回も小麦粉を盗まれてしまうという、不運に遇うチャングム。課題料理は、饅頭。小麦粉で、饅頭を作らねばならないのに・・・。( ̄□ ̄;)!!しかし、当時、小麦粉は、めったに手に入らない貴重な食材。小麦粉のない饅頭なんて・・・と普通なら思うが、そこは、あっぱれチャングム。小麦粉の代わりに菜園で採った夕顔を皮にして饅頭を作るのです!!・・・・・・・・このドラマでは、植物のチカラが多いに発揮しています。例えば、ネギは喉にいいとか、前出の夕顔は、胃に優しいとか・・・。食物は、美味しい薬。一緒に採ることで、作用が倍増したり副作用が出たり・・・。+++私はかつて、麦の入ったお餅を食べ、胃が痛くなった経験があります。一緒に食べた人も同じ症状。実は、麦は、消化が悪く、それを助けるのがトロロ。「麦とろ」は、先人が考えた偉大なるメニューだったのですね。好きなものを好きなときに、好きなだけ食べられる現代。チャングムの作る料理に、植物のチカラをほんの少し知って、「食い合わせ」を思い出したり・・・。「食」について考えさせられるドラマです。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月3日*切干大根を作る* UP
2005.12.04
コメント(4)
-

暮らしの中の義経*「勧進帳」
兄、源頼朝(中井貴一)さまの追手をかわしながら奥州平泉を目指す義経さま主従は、加賀国に到着しておりました。その義経さま主従の行く手には、安宅の関という難関が待ち構えていたのでございます。鎌倉の意向は、この地まで届いており、主従は役人の厳しい詮議を受けることになったのでございます。まさに関を通ろうとしたその時、義経さまたちは、現れた関守の富樫泰家(石橋蓮司)に呼び止めらました。弁慶(松平健)は東大寺大仏殿再建の勧進をしながら羽黒山に向かう山伏一行だと偽り、その場を切り抜けようといたしました。しかし、先を急ぐ一行を不審に思った関守は、ならば勧進帳を見せろと弁慶に迫ったのでございます・・・。第47回「義経・安宅の関」(11月27日放送)お徳、白石加代子風( ̄m ̄*)+++勧進帳を見せろとせまる関守。勧進帳(寄付ノート)などありもしないのに白紙の巻物を広げ、さも書いてあるように、朗々と読み上げる弁慶・・・。「義経」の後半最大の見所のひとつ。再放送を見ました。結果はわかっていても、ドキドキなシーンです。+++実生活でも、ありもしないことをつらつらと言うことを「勧進帳を読む」と言います。知り合いのAさんは、小学生の頃、「朝顔を育て、毎日記録すること」を夏休みの宿題にを出されたそうです。ところが、遊ぶのが大好きなAさんは、8月の終わりになって、なんにもしていないことに気がつきました。そこで、一晩で、あたかも、育てたように「朝顔日記」を書いたそうです。そして、それを持って登校。その文章があまりに素晴らしく、全校生徒の前で披露されたそうです。Aさんは、嬉しいような、困ったような、複雑な心境だったとか・・・。「勧進帳を読んだ」Aさんは、その後、東大文学部に入られました。栴檀は双葉より芳しい!!今から50年以上前の実際にあったお話です。「勧進帳 」のシーンは 今も歌舞伎で演じられています。 人気blogランキングへ・・・・・・・・・・・・・・・暮らしの中の義経:ひらかた菊人形、義経を最後に95年の歴史に幕 暮らしの中の義経:源平の合戦:紅白歌合戦暮らしの中の義経:那須与一(なすのよいち)暮しの中の義経:♪哀れ白拍子、花の命~暮らしの中の義経:CMおけいはん義経と清原弁慶 ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月2日*トリビアの井戸:てしょう* UP
2005.12.03
コメント(2)
-

「ALWAYS 三丁目の夕日」★昭和30年代グラフティ
ミゼット、駄菓子屋、ちゃぶ台、力道山、街頭テレビ、汽車、フラフープ、舗装されていない道路、広場、子どもたちの歓声、タバコ屋のおばあさん、戦争の傷あと、東京タワー、「別れの一本杉」、「ダイアナ」、ロカビリー・・・。映画「ALWAYS 三丁目の夕日」には、そんな懐かしいものがいっぱい。「もはや戦後では無い」と言われた昭和30年。それから3年後の昭和33年の東京の下町が舞台。そのせいか、お客さんの年齢層が高い(「NANA」は殆ど若者でした。)古きよき時代を実際に体験して来た人達が、昔を懐かしむ為にこの映画を観る。私もそのひとり。私は、この頃、この映画に出てくる子ども、一平や淳之介たちと同じくらい。■ストーリー■ 昭和33年、東京タワーが完成するこの年、東京下町の夕日町3丁目には、人情味あふれる住民達が賑やかに暮らしていた。ある日、自動車修理工場・鈴木オート(堤 真一)に集団就職で上京した六子(堀北真希)がやってくる。立派な会社を期待していた六子は、がっかりした様子だった・・・。一方、しがない小説家の茶川竜之介(吉岡秀隆)は、飲み屋のおかみ・ヒロミ(小雪)から頼まれ、身寄りのない少年・古行淳之介の世話をすることになってしまった・・・ 。なんでもない話なのである。けれども、戦後10数年、高度成長期にある日本で、誰もが幸せに向かって、誰もが幸せを信じて疑わず生きることが出来た昭和33年。毎日が、新鮮な驚きの昭和33年には、普通の生活でもドラマがある。例えば、鈴木オートにテレビが来たといって町中が大騒ぎ。「お祝い」と言ってお酒が届けられ、町中の人がテレビを見るために集まる。テレビにうつる力道山の空手チョップに、大人も子どもも一緒になって声を枯らした。私も子ども時代には、映画の中に出てくる人たちと同じように、村でテレビを持つただ一軒の家に行っていた。+++豊かではないから、ツギのあたったセーターを着た、一平。でも今の子どもより、輝いた笑顔に涙がこぼれる。親に捨てられた淳之介少年や、空襲で家族を失った宅間先生(三浦友和)・・・。暖かくて、おかしくて、悲しくて、懐かしくて・・・。いとしい日々昭和30年代を思って涙の止まらない映画でした。「携帯もパソコンもTVもなかったのに、どうしてあんなに楽しかったのだろう」 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月1日*おとごの朔日(さくじつ)* UP
2005.12.02
コメント(6)
-

「園芸家12ヶ月:12月の園芸家」*待てばバラの花咲く季節もある。
待てばバラの花咲く季節もある、という諺がある。(待てば海路の日和、と日本ではいう。)(略)私は数本のシラカバを植えて、心の中で思った。いまここがシラカバの森になるだろう。そして、あそこの隅に百歳の樹齢を経たカシワの巨木がにょきっと一本そびえるのだ、と。私はカシワの木を一本植えた。ところが、もう二年たつが、樹齢百歳の巨木にはまだならないし、キラカバもニンフが踊りをおどるような百歳の森には、まだなかなかならない。もちろん、まだ数年わたしは待つつもりだ。われわれ園芸家は根気がいい。*「園芸家12ヶ月」 カレル・チャペック*・・・・・・・・・・・・・来年からは、出勤日数が減る。いくら待っても「バラの花咲く季節」も「海路の日和」もなさそう。(ノД`)まあ、そこは気持ちを切り替えて、花や野菜を作ったりお金の許す範囲で旅行をしたり・・・。web日記も時間がとれる・・・。+++「園芸家12ヶ月」をネタに書いていたら、いつの間にか12ヶ月、一年がたってしまいました。来年はどの本を書いていこうかな( ̄ー ̄)**「園芸家12ヶ月」 カレル・チャペック**チェコの生んだ最も著名な作家カレル・チャペックは、こよなく園芸を愛した。彼は、人々の心まで耕して、緑の木々を茂らせ、花々を咲かせる。その絶妙のユーモアは、園芸に興味のない人を園芸マニアにおちいらせ、園芸マニアをますます重症にしてしまう。無類に愉快な本。●今月で「とり年」も終わりということで、イラストは鳥。 人気blogランキングへ ・・・・・・・・・・・・・・・◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★12月1日*おとごの朔日(さくじつ)* UP
2005.12.01
コメント(0)
全26件 (26件中 1-26件目)
1









