2011年08月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

8月のおしゃれ手紙:夏服
夏も終わりだ。ここ数年、痩せていたのに、今年は、数キロ肥った。健康的にはこれでいいのだが、若い人向けの細い夏服が多かったので、今年は、新しくブラウスを2枚買った。でも、イマイチだ。欲しいのは、ウーロン茶?のCMの若い女の子が着ているようなワンピース。■この■夏服もかわいい。これに似た、生地を探して、妹に作ってもらおう。イラストは、娘のレイのワンピース。■8月に見た映画■*小川の辺■8.4*父と暮らせば■8.6*太陽がいっぱい■8.6*リメンバー・ミー■8.23*ワン・ヴォイス■8.24■過去の書き残したネタ■*江戸風ガーデニング*ファーストレディ*浜寺の水練所*電力会社のやらせ*節電・・・自動販売機*「小石川の家」*大型店の開店*あさぶら*小説「アーレンガート」*椅子*ラパン・アジル*チューブとメトロ*メトロのすり*二つの風車*ヨーロッパの家はなぜきれい?*「北極星」*アルミ缶エコ*江戸時代、和歌山の防災意識*子供と春の花と桜*ケチな近鉄・・・吉野の桜*「ゲゲゲの女房」昭和30年代。貸本屋、方言*瀬田の町で見つけた小さな川*インテリアのページ*近所で見つけた古いものたち*冬のオリンピック(フィギアスケートの採点)・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月31日*「菊次郎とさき」:戦争の跡/昭和恋々:行水/「よーじや」の名前の由来/植物物語:椋(むく) *・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.31
コメント(0)
-

島田紳助、引退
小気味良い毒舌にいつも感心しながらテレビを見ていた私は、島田紳助の突然の引退にショックを受けた。8月24日に会った妹も一緒に食事をしながら発した言葉が「紳助、やめたな・・・」だった。数年前、鬱病を病んだ友人は「今は又バカ言ってるくらいに思って笑ってるけど、不眠症が最悪の頃はずいぶんそのバカ話しに救われた。自殺願望が出た時は泣きながら、面白い話にふと笑って…救われた。もう私はお笑いのテレビがなくても大丈夫だけど私のように笑いをもらった人いっぱいいるやろと思って・・・」という。 もちろん、島田紳助の嫌な面も知っている。2004年には吉本興業の女性社員を殴ってけがをさせたとして略式起訴され、罰金30万円の略式命令を受けた。この事件で3カ月近くタレント活動を自粛した。それ以後も2009年10月3日放送の『オールスター感謝祭』(TBSテレビ)では、シルク・ドゥ・ソレイユのショーの最中に司会の島田紳助が「東京03」というコントグループに詰め寄るるシーンが放送された。芸能界でのさばっていたのだろう。その勢力は誰も止められないくらい強大だったのだろう。暴力団とかかわる原因になったのは、テレビで右翼を批判し、そのため右翼に妨害されたからだそうだ。それを暴力団が中に入って「解決」したのだそうだ。どんな風に批判したのかは知らないが、その時、吉本興業や警察は守ってくれなかったのだろうか?リーゼントにつなぎ服姿でしゃべる「ツッパリ漫才」の時代から見ていた私は、その才能が断たれたことが残念でたまらない。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月29日*地蔵盆今昔/雨の名前:盆の雨/父の麦わら帽子:目次/ゆかたの一生*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.29
コメント(0)
-

ワン・ヴォイス★ハワイ語
■ワン・ヴォイス:あらすじ■この瞬間は未来のために。いま奏でられる、ひとつの歌声・・・。ハワイ、オアフ島で創立120年を誇る伝統校“カメハメハ・スクール”。ハワイアンの血を引く子どもたちが通うこの名門校では、毎年3月に“ハワイアン・スクール・ソング・コンテスト”という合唱コンクールが開催される。9~12年生の約2,000人もの生徒が学年ごとに分かれ、課題曲はすべてハワイ語で歌い、そのハーモニーを競いあうのだ。本作は学年ごとにリーダーとして選ばれた生徒たちとその家族を中心に、指導者である教師やミュージシャンらのインタビューも交えながら、1年がかりで猛練習に励む姿を追った愛と感動に満ちた物語である。 カメハメハ王直系の子孫の寄付により1887年に創設されたカメハメハ・スクールは、ネイティブ・ハワイアンを祖先に持つ子を対象にした教育機関。だが創設直後の1888年、カメハメハ・スクールはハワイ語の使用を禁止され、1896年にはハワイの公立校でも“イングリッシュ・オンリー”の法律によってその使用が禁じられた。ハワイの言葉が正式にハワイ州の公用語として認められるのは、それから80年も経った1987年のことである。現在ではハワイ語の復活を目指す多くの活動や研究が進められ、ハワイアンとしてのアイデンティティや文化とより強く深いつながりを実感できるような環境づくりが行われている。このコンテストも、その意識が色濃く反映されたものであり、大切に継承され続けている。 そうだ、ハワイにはハワイの言葉があったのだ。ハワイには、かつて王朝があって、その王朝が無くなる時に王女が作ったのが「アロハ・オエ」という歌。「アロハ!」という挨拶も知っていたのに、この映画を見てあらためて、ハワイには、英語ではなくハワイ語があったことを認識した。アメリカがハワイの言葉を使わせないようにして、長い間がたった。ハワイの言葉は、完全に忘れさられたが、歌の中で生きていた。ハワイの言葉を取り戻すため、学校では、ハワイ語を習わせる。“ハワイアン・スクール・ソング・コンテスト”もそのひとつ。また、ハワイ語しか使ってはいけないという合宿もある。この映画を見ながら、アイヌや沖縄を思う。アイヌの言葉はなくなってしまったが、沖縄の言葉は、歌の中で残っている。涙がぼろぼろこぼれ落ちるという意味の「涙(なだ)そうそう」など、よく知られている。映画の中で「涙(なだ)そうそう」をハワイの言葉で歌っていた。沖縄の歌でありながら、ぴったり。この映画に出ている高校生たちのしっかししていること。その中のひとりは、アメリカ本土では、あまりハワイの現状を知らないと嘆いていた。ケイタイをいじったり、化粧に余念のない日本のコギャルと大違いで骨太な頼もしさ。フラダンスよウクレレを習っている妹と一緒に見た映画。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月23日*サルビア歳時記:8月の三箇条/ 器歳時記:金魚の絵皿*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.27
コメント(0)
-

昔語り:朝顔の思い出
子どもの頃の夏休みの思い出は、いろいろあるが、そのひとつにラジオ体操がある。そして、ラジオ体操からの帰り道に咲いていた朝顔がある。農業を営む私の家も他の家と同じく米や野菜を作っていたが花は育てていなかった。そんな中、村に一軒だけ、毎年、朝顔を育てている家があった。その家は、たった一間だけの小さな小屋だった。田畑はもちろん、他の家のように、家の前の「カド」とよばれる空間もなかった。だから縦に育つ朝顔しか育てることが出来なかったのだ。私は、ラジオ体操の帰りにその粗末な家を通りながら、きれいに咲いた朝顔をちぎっていた。この家の家族は、戦時中に大阪から疎開してきたと父は言っていた。皆が田植えをする時、稲刈りをする時、道普請、寄り合い、祭、葬式・・・。村で行う行事は沢山あったけれど、その家は、どれにも参加していなかったと思う。稲作の共同作業から生まれた村の行事に田畑を持たない人は、入る必要もないし、入れないのだ。それは、どんなに寂しいことだったろうか・・・。その家の人たちは私が中学生になった頃、気がつくといなくなっていた。今、東北の3.11の震災で疎開している人が沢山いる。彼らは寂しい思いをしていないだろうか・・・。彼らの夏に朝顔は、咲いているだろうか・・・。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月23日*サルビア歳時記:8月の三箇条/ 器歳時記:金魚の絵皿*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.26
コメント(0)
-

リメンバー・ミー★NY
■リメンバー・ミー:あらすじ■きみに会えて よかった。舞台はニューヨーク。6年前の兄の死をきっかけに両親は離婚、弁護士の父親との溝が広がるばかりの青年・タイラー(ロバート・パティンソン)は孤独と虚無の日々を送っていた。そんなある日、タイラーはアリーという女性に出会い、恋に落ちた。初めて感じる本気の愛、生きる悦び。やがて、彼女自身も同じ傷を抱えていることを知ったとき、家族の再生がゆるやかに訪れる…。傷つき閉ざされた心が愛で解けてゆく。生きる悦びを取り戻した忘れられない夏。『トワイライト』シリーズで人気を博したロバート・パティンソン主演で贈るラブストーリー。 私もそうだったけど、22歳って本当に悩む年頃だ。タイラーは、愛する兄の死から、心は死んでいる。■『トワイライト』■シリーズで人気を博したロバート・パティンソンは、そんな役にぴったりだった。無名の脚本家が書いたのをロバート・パティンソンが気にいって製作総指揮をしたそうだ。まだ20代と若いのに「トワイライト」シリーズ3本のヒットでそういう権限が与えられるって、さすが、ハリウッドの大スターはスゴイ。22歳でガンジーは3人の子供を持ち、モーツァルトは交響曲を作りバディ・ホリーは死んだ。兄さん、俺はもうすぐ22歳になる。劇中でタイラーはそうつぶやく。まるで、22歳が人生の最後のごときつぶやき。はじまりから終わりまで、死がまとわりつく。予期せぬラスト。この終わり方でよかったのかな?・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月23日*サルビア歳時記:8月の三箇条/ 器歳時記:金魚の絵皿*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.25
コメント(0)
-

ツバメの巣、邪魔ですか?
先日、眼科からの帰りに寄ったスーパーの軒先に傘が数本、さかさまに開いて吊るしてあった。みると、ツバメの巣がある。スーパーは、ツバメの糞が客に当たらないようにとの配慮に傘を吊っているのだった。しかし、張り紙を見て、がっかりした。 ツバメの巣があります。子育て中です。鳥獣保護法により撤去できません。ご理解のほど宜しくお願いします。********客は、ツバメの巣があると言って怒るのだろうか?鳥獣保護法がなければ、撤去するのだろうか?以前にも書いてのだが、「山村の四季」という本にツバメのことがあった。***6月4日***昨日は家のツバメの卵がむけた。取次(とりつぎ=玄関の間)の天井とダイドコの天井と、ニ処に巣を「くった」が、ダイドコのは、もとからの古い巣へ入り込み取次のはふたつの古い巣を嫌って、電線の碍子(がいし)へ新しく巣を造った。危なっかしいので下に板を当ててやったが、この板は縦目にしないと嫌がって巣を造らないという。ダイドコの方はまだだが、取次の四つの卵がむけて、ピヨピヨと雛の声が賑やかだ。今朝起きたら、二つに割れた卵の殻が畳の上に落ちているので、祖母に見せると、「ああ、そりゃ、ツバメの宿賃だんて、おエベスさまの、お棚に上げず」と言った。「ツバメのお礼」だといって恵比寿様に上げることは、川中島平でもしているし、またこれを細かに砕いて水に入れたものは目薬になるという。「山村の四季」宇都宮貞子ここでは、ツバメが安全なように巣の下に板をひいたり、卵がかえり、割れた卵を「ツバメの宿賃」といって、神棚に祀った。いつから日本人は、こういう優しさをなくしたのだろう・・・。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月23日*八朔(はっさく)/サルビア歳時記:8月の季語*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.23
コメント(2)
-

こんなものいらない!:「24時間テレビ」
■ 「24時間テレビ」って本当に必要ですか?今年は、原発事故のために皆が節電しているのに、なんでやるの?「愛は地球を救う!」というなら、出演者が皆、愛をもって被災地で活動するのが、普通だと思うけど。「24時間テレビ」のスタッフも震災2ヵ月後の5月11日の段階では、「浜岡の停止でいよいよ分からなくなってきました。24時間テレビメイン会場の日本武道館は千代田区ということもあり、計画停電対象地域からは外れるでしょうが…。東日本震災チャリティーなので中止はありえないですが、館内照明を24時間つけっぱなしの放送では、3月にプロ野球の東京ドーム開催を延期しなければならなかったときのような世論になってしまうと、どうすることもできない」と言ってたそうだが、5ヵ月も過ぎると、結局やってしまった。24時間、開いてるコンビニがあって、24時間営業の自動販売機がある。放射性物質を含んだ原発のごみは、こんな、なんでもありの浪費が作ったのだ。来年こそ、是非やめて欲しい、「24時間テレビ」。私の推理では、テレビ局の社員の夏休み対策ではないかと思う。なら、いっそ、各テレビ局が夏の間、1週間休みというのはどうだろう。社員もゆっくりできるし、電気代の節約、すなわち、エコになる。やめる勇気こそ、地球を救うかも?!■こんなものいらない!■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月21日*サルビア歳時記:8月の三箇条/ 器歳時記:金魚の絵皿*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.21
コメント(6)
-
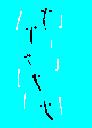
大阪の都心に人工ビーチ登場
♪大阪には川がぎょうさんあるんやで。堂島川、土佐堀川、道頓堀大阪には、まだまだ川があるんやで。淀川、大川、欲の皮。なんでやねん。(by はるな)というように、大阪には、沢山の川がある。しかし、たんに水が流れているという感じ。水に親しむという川は少ない。そんな中、砂浜のある水辺が出来た。「水都大阪」を目指す大阪府が、大阪の都心を流れる大川沿い(大阪市都島区)に、約7千平方メートルの砂浜「大阪ふれあいの水辺」をつくった。18日以降、無料開放する。 生物の生息に配慮して、同じ水系の淀川の砂1万5千立方メートルを運び入れた。イベントに参加した橋下徹知事は、「大阪のど真ん中で水辺に触れ合う空間ができた。南の島と言ってもおかしくない」。 ただ大川の深さは満潮時で3メートルを超すため、府は安全のため泳がないよう呼びかけている。■毎日8/18■ 三面コンクリート張りの川を嘆いていた私は、もろ手を挙げて喜んだ♪\(^∇^)/1億3000万円を投じて市内を流れる大川におよそ140mにわたるビーチを完成させたもの。税金も、こういう風に使うんだったら、大賛成。まず、市民が川に親しむことが、川を大事にする第一歩。脱原発を言ったり、こういうことをするから、橋元知事に疑問を感じても嫌いになれないのだ。下の写真は、京都。鴨川では、夏になると普通に川で楽しんでいる。大阪も早くこうなるといいな・・・。 ・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月19日*鐘楼舟の葡萄でひと儲け/「◎日本ちょっと昔話◎」始まります!! *・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.19
コメント(0)
-

明石海峡大橋って必要か?
8月11日■広島からの帰りに■明石海峡大橋に寄った。明石海峡大橋は、兵庫県神戸市垂水区東舞子町と淡路市岩屋とを結ぶ、明石海峡を横断して架けられた世界最長の吊り橋である。明石海峡大橋の主塔の高さは海面上298.3mであり、国内では東京スカイツリー(634.0m ※2012年竣工時の高さ)、東京タワー(333.0m)に次ぎ、横浜ランドマークタワー(296.3m、海抜は300mで同じ高さとなる)を超える高さの構造物である。その日本有数の高さの主塔に登るというツアーに参加したのだ。3000円也。しかも主塔までは、車が走っている下の関係者のみが使う橋を関係者の案内で歩いて渡るのだ。通路は格子状になっていて、海がまるみえ。なにかのひょうしに、ケイタイなどを落としても、海に消えてしまう。それどころか、運悪く船が通っていて、人にでも当たると、ケガをさせかねない。というので、ケイタイやカメラは、全て、首からかけるようにと言われた。足場の悪い所を歩いて行ったり、高い所や狭い所があって、参加者は30人ほどだったが、ほとんど20代から30代だった。私は、人間がこんな巨大なものを作っていいのかといつも思う。理由は下のとおりだ。●毎日のメンテナンス。橋を吊っている金属のロープがさびないように、上の写真の装置で電気で風を送り続けている。●建設費約5,000億円という巨費。●橋という障害物が出来たことで、船で通りにくい。●大工事による、漁場への影響。●明石と淡路島を結ぶフェリー・ボートの影響。■たこフェリー■は運航を休止した。車のみが利用する、しかも料金の高い橋。もし、何年、何十年か後、巨大地震で橋が落ちたら、船さえも通れなくなる。世界で一番長い橋といわれる、明石大橋。しかし、その座が脅かされたことがある。それは、イタリアとシシリー島を結ぶ橋の案があった時だ。しかし、イタリアは、賢明にも巨大な橋をつくらなかった。 この黒い管は、明石から、淡路島に水を送る水道管だそうだ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月17日*あの頃はよかったね。/なぜ、お盆に墓参りなのか? *・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.17
コメント(0)
-

被災地の松、二転三転
東日本大震災の津波でなぎ倒された岩手県陸前高田市の松でできた薪(まき)を、京都の大文字送り火で燃やす計画が中止になった問題で、五山送り火の各保存会で組織する「京都五山送り火連合会」(京都市)は9日、現地から別の薪を受け入れることを決めた。京都市が500本を取り寄せ、送り火で燃やされるという。しかし、その松からセシウムが出て 一転使用中止となった。京都市は12日、市が取り寄せた薪500本について放射能検査をした結果、放射性セシウムが検出されたと発表した。市は記者会見で「科学的根拠に基づき、誠に残念だが断念せざるを得ない」と説明。16日の五山送り火で燃やすことを中止するという。 市によると、薪の表皮から1キログラムあたりセシウム137が588ベクレル、セシウム134が542ベクレルの放射性セシウムがそれぞれ検出されたという。 最初に、「大文字保存会」が被災地の松は使わないと決めた時、全国各地から、「被災地差別だ。」「もう、京都には、観光に行かない」という抗議があったと言う。京都市長も、「京都市民として恥ずかしい」と発言。被災地の松を使わないのは、悪だとばかりの雰囲気。再度、被災地の松を京都に持ってきた。2度目に持ってきた薪から、放射性物質、検出。薪の表皮から 検出されたのは、「人体に影響がない」そうだ。しかし、それがわずかであっても、燃やしてしまうと、凝縮してしまう。京都から琵琶湖はすぐそこ。近畿の水がめとも言われている琵琶湖に、たとえ、害がないといっても、放射性物質を入れる危険性は、避けて欲しい。関西では、これでいいという意見だが、被災地は複雑だろう。悪いのは、被災地でも、被災地の松でもなく、原発だということを私たちは、よく分かっている。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月15日*竹八月/迎え盆*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.15
コメント(0)
-

がんばるブルーベリーの木
8月10日~11日にかけて、岡山県に近い広島県の■帝釈峡■に行ってきた。行く途中でブルーベリー摘み。この季節、夫は、必ず、ブルーベリー摘みに行きたがる。最近、視力が衰えてきたから、「目にいい」というブルーベリーで視力回復ということらしい。今回行ってみると、いたるところで、木の枝が折れている。聞いてみると、今年の冬は雪が多く、雪の重みに耐えかねて枝が折れたとか。そういえば、私も■寒い。寒いよパトラッシュ。(略)■とつぶやいていたし、めったに雪の降らない大阪でも数回降った。雪の降ったうちのまわりの様子を写真でイギリスに暮らす次女のレイに送ると、「イギリスよりも寒そう」と言われたことを思い出す。ポッキリと折れた枝は、赤いテープでグルグル巻きにされている。わずかにくっついている部分から水分が補給されるのか、実もたわわだ。傷ついても、がんばっているブルーベリーの木。植物って偉い!・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月13日*八月のやり/ヨウネンコウ*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.13
コメント(0)
-
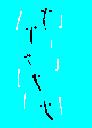
おしゃれ手紙34◆ビオトープ
■天地 はるな様■お元気そうで何よりです。はるなさんのガーデニング熱、上昇中だとか。こういう熱なら地球も喜ぶでしょう。おっしゃるとうり、コンクリートは暑い。ホント暑い。私の実家は屋根がなく、コンクリートの屋上ですが、めちゃ暑!夏はクーラーがないと倒れてしまいそう。以前、私にできるヒートアイランド退治方は何ぞや?と頭を悩ませた結果、屋上庭園なるものを作ってやろうと計画を企てたのですが・・・。土を乗せるだけの荷重に耐えられるように作られていないとのことで父が猛反対。泣く泣く、諦めたのですが、某企業が土の代わりにヤシの実の繊維で作った、マットのようなものを開発したとのこと。それやったら、ええやんと思ったのもつかの間。お値段が高すぎました。でもクーラーに使う電気代のことを思えば・・・。とりあえず、壁をツタに這っていただいて、それからまた考えるとしましょう。なにごともチープが肝心だもの。 はるなさんから譲り受けたバラもすこぶるつきの元気。工事現場で朽ち果てる運命にあった、バラと葡萄の木。バラは私が、葡萄がは、はるなさんが育てることに。工事現場ばかり目に付き、田んぼや里山が荒れ果て、消えて行くこの頃。なんともやるせない気持ちになってしまいます。田んぼだけでなく、山も消える今日この頃。そこに住む生き物たちを追いやって、人間だけがはびこるご時世。 かと思えば、先日、大阪・鶴見緑地に「里山」を再現するゾーンができたとか。「*ビオトープ*…生き物が生活できる環境を復活しよう」という活動を展開するとか。まあ、それはそれで、ええんやけれど、わざわざお金を払って田んぼの土を運ばんでも、今ある田んぼをそのまま使ったらええのに。ビオトープと言えば、私もこの夏始めてみました。私の方はただ、古い小さな水槽を畑に埋め込んだだけのものですが、これが面白いのなんのって。 最初は私の成金趣味で、金魚を入れたのだけど、ツユクサの根にからまって昇天。ドジョウだけになったのも束の間、いつしかカエルのサロンとなり多いときには6匹も。今ではタニシも加わって、なかなか賑やかな水槽、いやいやサロン。湿地大好きな私は、これだけでは飽きたらず、お次は田んぼをそのまま切り取って。古い火鉢やお茶碗に入れて眺めたり・・・。うーん、オリエンタル! ヘルマン・ヘッセが「庭仕事は瞑想である」とうたっていましたが、私も土関係のものに触れている時が至福の時。「個人」が慈しんで楽しむビオトープをいろんな人に感染させたいものです。 浜辺 遥(はるか)追伸:命拾いいたバラに名前をつけていただけませんか?**ビオトープ**生き物の生息空間・場所という造語。かつては、石垣の間や田んぼ、川、家の屋根裏、などを棲家とする小動物がたくさんいました。小動物の生息する空間や場所を大切にしようとする、世界的な動きがあります。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月11日*ふるさとは近くにありてつくるもの/停電今昔*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.11
コメント(0)
-

太陽がいっぱい★アラン・ドロン
■太陽がいっぱい:あらすじ■悪友フィリップ(モーリス・ロネ)を、彼の父親の頼みで連れ戻しに来た貧乏な若者トム(アラン・ドロン)。しかし放蕩息子であるフィリップは父の元へ戻る気はなく、親の金で遊び回っていた。トムはフィリップの金目当てに彼と行動を共にするが、トムやフィリップの恋人マルジュ(マリー・ラフォレ)に対してフィリップが時折見せる傍若無人な態度に怒り、フィリップを殺害してしまう。死体を海に捨てた後、トムはフィリップになりすまして彼の財産を手に入れようと画策し、計画を実行していく。 アラン・ドロンの代表作といわれている「太陽がいっぱい」。皆が口をそろえて、「世紀の二枚目」というアラン・ドロン。しかし、ただ二枚目というだけでなく、野卑な顔でもある。それが、貧しいけれど、成り上がりたいという役柄にピッタリだったからではないだろうか。 リメイクで「リプリー」という作品があるが、「太陽がいっぱい」といえば、あまりにアラン・ドロンが有名なだけに、あんまり話題にならなかった。しかし、ジュード・ロウが悪友を無邪気に気品たっぷりに演じたというので見てみたい。「太陽がいっぱい」が作られたのは、1960年。随所に時代を感じる。例えば、冒頭の目の悪い人をからかうシーン。あれなど、今は考えられないのだが、当時は、あれが冗談ととれたのだろうか。しかし、全編に流れるテーマ曲は、怖さと哀愁を感じる名曲で作品を盛り上げる。■1960年(.カラー カラー作品 )■上映時間 119分 ■サイズ ヨーロッパ ビスタ ■監督 ルネ・クレマン ■午前十時の映画祭■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月9日*七日盆の髪洗い/北国(ほっこく)の雷*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.09
コメント(0)
-
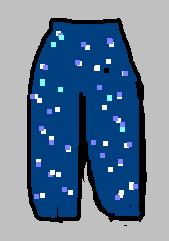
父と暮らせば★原爆
■父と暮らせば:あらすじ■おとったん、ありがとありました。終戦から3年後の広島。図書館に勤める美津江(宮沢りえ)は、たった一人の家族だった父親を原爆で喪い、生き残った自分に負い目を感じながら暮らしていた。ある日、原爆の資料を探しに図書館を訪れた青年(浅野忠信)と出会い、互いに惹かれ合うが、美津江は「うちは幸せになってはいけんのじゃ」と自分の心を塞ぎ、青年の誘いを断ろうとする。そんな娘を見かねたのか、その晩から美津江の前に父・竹造(原田芳雄)の幽霊が現れ始める。“恋の応援団長”を名乗る竹造は、あの手この手で娘の心を開かせようとするが…。 いやー、宮沢りえ、きれいだったー!!勤め先から帰って来た時の白いブラウス。普通に襟のついたもので、袖はフレンチ。何も足さない、何も引かないというシンプルな美。家に帰って着替えたのは、白い開襟シャツにモンペ。他にも、こんな服が欲しかったというような服ばかり。 監督は、戦争をテーマに市井の人の姿を描いてきた、黒木和夫。原作は、かの井上ひさしとくれば、面白くないわけがない。父親に先日、亡くなった原田芳雄、娘が宮沢りえ。ストーリーは、ほとんど、このたった二人だけで進む。舞台のほとんどが、広島で半焼した、親子の家。これの作品は、1994年、「こまつ座」で初演されたものだ。原爆で死んでいった友人たちを思い、自分だけ生き残っていいのかという思いになる美津江。また、彼女は、被爆者として、発病するのではないかという不安もあった。テレビで同じようなことを東北の人が言っていた。町ごとなくなってしまい、運よく、生き残った人は、自分だけが生き残ったと言っていた。福島の原発事故で、将来、ちゃんと子どもが産めるのかという人もいた。戦争と地震という違いがあっても、同じ思いに違いない。そんな重いテーマを井上ひさしは、笑いを織り交ぜながら進めている。広島に原爆が落とされた8月6日にみられたことがは意味あることだと思う。毎年、上映してもらいたいものだ。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月7日*父の麦わら帽子:ふるさと遠く/七日盆*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.07
コメント(2)
-

小川の辺★残したい日本の美しいもの
■小川の辺(ほとり):あらすじ■藩命か。愛か。海坂(うなさか)藩から江戸へ百里の旅。藩から上意討ちの命を受けた戌井朔之助(いぬい さくのすけ)。狙う相手・佐久間森衛の妻が妹・田鶴だったことから、朔之助は肉親の情愛と藩命の間で苦悩する。田鶴自身が剣術遣いでもあり、もし刃向かえば彼は妹を斬らなくてはいけない…。その朔之助が佐久間を探す道中に付き従うのは、戌井家に仕える若党の新蔵。彼は朔之助や田鶴とは兄弟同然に育った仲で、田鶴には主従関係以上の思いを抱いていた。妹を思う朔之助と、愛する人を死なせたくない新蔵。二人の男の心情は、田鶴との再会によって臨界点を迎える――。 妹の夫を討つよう藩から命じられ、使用人の新蔵と旅する朔之助。朔之助の妹と新蔵は、秘めた恋仲でもある。そんな辛いストーリーなのに、観終わった後、なぜかさわやかだ。朔之助と新蔵の旅がほとんどだが、江戸時代の旅は、なんというエコなのだろう。江戸まで10日もかかり、そこからまだいつ終わるともしれない旅なのに、持って行くものは、背の小さな荷物ただ一つ。しかも、二人でひとつなのだ。 頭には、スゲという植物から作った菅笠(すげがさ)。腰には竹で作った水筒。途中で、水を補給する。足元は、わらじ。もちろん、藁で作っているので、履きつぶしたら、燃料や、肥料になる。豊かな水量の川を舟で下る。食事は、おにぎりのみ。 極限のシンプルライフは、もちろん、ごみなど出さない。また、狭い道をゆずったり、動かなくなった荷車を押したり・・・。二人の旅の景色と行動、立ち居振る舞いの美しいこと。かつての日本は、こんなに美しかったのか・・・。どうしてこんな国になってしまったのか・・・?この映画は、ロードムービーだ。そこには、残したい日本の美しいものがあった。・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月5日*トリビアの井戸:淡路島/「竹八月」というけれど・・・。*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.05
コメント(0)
-

サンパチェンスのトリビア
『サンパチェンス』シリーズは、鮮やかな色合いをもち、真夏の暑さや強い日ざしに耐え、たくさんの花を咲かせる草花です。またそれだけではなく、おもに自動車などの排気ガスに含まれる環境汚染物質の二酸化窒素(NO2)や、シックハウス症候群の原因物質であるホルムアルデヒド(HCHO)、地球温暖化の原因とされる二酸化炭素(CO2)できわめて高い吸収能力を発揮し、 大気汚染の軽減効果のある「環境浄化植物」として注目されています。さらに、『サンパチェンス』の表面温度を測定したところ、従来の園芸植物よりも3.0~4.5℃低い結果となり、気温よりも2.5℃、地面の温度よりも10℃以上低く「打ち水」効果による温度降下能力も備えていることがわかっています。『サンパチェンス』は、品種名の由来でもある「サン(Sun)=太陽+ペイシェンス(Patience)=忍耐」という特性により、暑さや強い日ざしに耐え夏でもたくさんの花を次々に咲かせます。 サンパチェンスは、通勤の途中でもよく見かける。派手な花だな、私好みではないわといつも、冷たく見ていたけど、ホルムアルデヒドや二酸化炭素(CO2)を吸ってくれるわ、気温を下げてくれるわとスゴイ役に立っている。サンパチェンス様、これまで、冷たくして、すみません。m(_ _)m熱い中、これからも、頑張ってください。暑中おみまい申し上げます!・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月3日*遊び唄:さよならサンカク・・・/「くわばら、くわばら」*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.03
コメント(0)
-

里山の旬だより:お天気話
■ハチが巣を下に作る年ゃあ、よぉ台風が来る。台風が来てもええように、ハチは準備しょうるんかのう。■雨の降る前にゃあ、木の葉が裏返るんで。雨の降る前には、風が吹き始め、葉が裏返るんじゃと。■雷が鳴ったら桑の木に逃げんさい。桑の木には、熱や電気を通さない特性をもっとるんよ。よう言うがね「クワバラ、クワバラ」って。 広島県の庄原という所に行った時、「道の駅」で偶然見つけた、「しょうばら里山の旬だより」という小冊子に紹介されていた。伝統の食事や諺の数々・・・。 鉢の巣を見たり、木の葉を見たり・・・。天気予報を自然で感じていた昔の人たちの知恵を忘れて、私たちは、テレビから流れる天気予報を聞いて明日の天気を知る。地震は予知出来なくても、明日の天気くらいは、自分で分かりたいものだ。「クワバラ、クワバラ」という雷の呪文は、下記の意味とも言われる。「菅原道真をめぐる伝説に由来するらしい。左遷されて、九州で悶死(もんし)した道真が雷神になって京都に襲来。次々と復讐するが、彼の領地、桑原は落雷を免れた。その「桑原」にあやかった呪文だという説である。」03/9月朝日新聞「天声人語」より■里山の旬だより■・・・・・・・・・・・・・ ◎自然と人間が仲良く暮らしていたころの話です。★2011年8月1日*三尺流れて水清し*・・・・・・・・・・・・・・
2011.08.01
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-
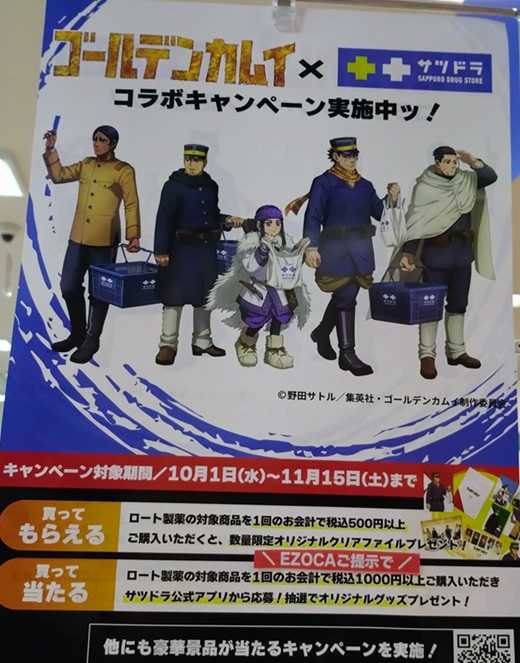
- 【楽天ブログ公式】お買い物マラソン…
- お買物マラソンお疲れ様でした&ゴー…
- (2025-11-15 17:02:59)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- 楽天お買い物マラソンで目が疲れて限…
- (2025-11-15 20:30:04)
-
-
-

- 今日のこと★☆
- 「王寺ミルキーウェイ2025」のボ…
- (2025-11-15 21:48:42)
-






