-
1

『西村賢太殺人事件』に驚愕
なんか、風邪ひいたっぽい。急に寒くなったからかしら? それでイマイチ、気力充実せず、今日は一日、モゾモゾと本を読んでおりました。読んでいたのは『西村賢太殺人事件』なる本。 以下、ネタバレ注意なんですけど、この本、1章から9章までは割と普通の本で、私小説家・西村賢太の内縁の妻だった人が書いた思い出の記なんですわ。で、生前の西村さんというのは、そういう人の立場から見るとこういう感じの人だったんだ、というのがよく分かる。西村賢太ファンからすれば、必読の本なのではないかと。 ところが。 第10章に入って、何だか様子がおかしくなる。 ご存じの通り、西村賢太は心臓発作か何かでまだ若いうちに急逝するんだけど、著者によると、あれは大がかりな組織による陰謀殺人であったと。で、著者自身も、その組織に追い詰められていると。 で、著者が西村さんと別れた後、彼女のバイト先の人たちや、住んでいたアパートの住人達、近所の子供まで、そういうのが全部グルで、寄ってたかって彼女に嫌がらせをし、自宅侵入を繰り返し、彼女を追い詰め、西村賢太を殺害したと。本書第10章は、その過程を事細かに明らかにしていく。そういう内容なのよ。 もう、ビックリ。お口あんぐり。これはもはやアレじゃない――令和日本版『ねじの回転』だわ。そもそも、本当にこの人は西村賢太氏の内縁の妻だったのか? それもひょっとしてすべて妄想だったのか・・・? これ、ワタクシが読むべき本ではなかったかもね。少なくとも体調が悪い時に読む本ではなかった。今夜あたり悪夢を見そう・・・。やばかったわ~。西村賢太殺人事件 [ 小林麻衣子 ]
November 21, 2025
閲覧総数 1128
-
2

話題の『ジェイムズ』を読む
昨年、斯界で大きな話題となったパーシヴァル・エヴェレットの『ジェイムズ』という小説を読んでみました。以下、ネタバレ注意ということで。これこれ! ↓ジェイムズ [ パーシヴァル・エヴェレット ] 本作はマーク・トウェインの傑作『ハックルベリー・フィンの冒険』のスピンオフというか、トウェインの作品がハックの視点で書かれているのを、ハックと行動を共にする黒人奴隷のジム(=ジェイムズ)の視点から語り直すという趣向。もっとも後半に至ると、元ネタを逸脱していくんですけどね。 で、全米図書賞だとかピューリッツァー賞とか、主要な賞を総ナメにしたというね。だから、まあ、一応はまだアメリカ文学者の端くれという立場からして、読んでおかないといかんのかなと思ったわけよ。 で、どうだったかって? それ、ワタクシに聞く? 大抵の人が「素晴らしかった!」と感心しまくる作品をワタクシがどう評価するか、敢えて聞く? 聞くなら答えるけど、まあ、大したことはないね(爆!)。 面白くなくはないです。噂に聞いた「ページ・ターナー」というのは確かにその通り。読み始めたら、すぐ読み終わっちゃうからね。だけど、じゃあ、これが『ハックルベリー・フィンの冒険』と同様の傑作かって言われたら、とてもとても。 なんかね、あちこち中途半端なのよ。たとえばジェイムズが「書くこと」に執着することとかね。ノートや鉛筆に執着していることはわかるのだけど、その結果、どうなったの? それが書いてない。まさかこの小説自体がジェイムズの作品とか? それならそれでいいけど、そう窺わせるようには書いてない。 あと、逃亡奴隷としてジェイムズが受ける様々な悲惨な事件にしても、なんかリアリティがないんだよね! たとえばジェイムズに鉛筆を渡すために、奴隷主から鉛筆を盗んだ奴隷が奴隷主に殺されるという場面とか。だって奴隷って、タダじゃないのよ。奴隷主にとってはひと財産だ。それを、たかがちびた鉛筆一本盗んだために殺すとか、そんなことありえない。悲惨さを演出するためにあり得ない作り話をしているところが興ざめもいいところ。むしろ「この奴隷、値段が高かったんだから長く使おう」という白人奴隷主の心根こそリアルであり、そっちのリアルさを批判すべきなのにね。 で、そんな風にあり得ない悲惨さをずっと描いていたのに、最後の最後になってジェイムズはいとも簡単に悪い白人を皆殺しにし、あっさり妻子を助け出して北部への脱出成功なんて、どんだけ都合がいいんだと。 あと、ジェイムズがハックの父親だったなんて、もう、あり得ないを通り越して噴飯ものよ。 なんつーの? さっきの「書くこと」にしても、ジェイムズが使い分ける言葉遣いの件にしても、あちこちで描かれる「パッシング」の事例にしても、ミンストレル・ショーのくだりにしても、ジェイムズの空想の中でのジョン・ロックやらヴォルテールやらとの会話にしても、作者のエヴェレットが研究者受けしそうな主題の餌をあちこちにバラまいているような感じがするじゃないの。そんな、これ見よがしに「拾え」と言われているものなんか、ワタクシは拾わないよ。 でも、そういうのを拾いまくって、研究発表する研究者とか、今後、やたらに出るんだろうな。「ジェイムズは、自ら語る/自ら書く主体となることで、白人支配の構図を鮮やかに逆転してみせたのだ」とかなんとか。やだねえ、そういう頭でっかちな結論。作者の思うつぼじゃないの。 っつーわけで、この小説、ワタクシにはあまり響かなかったのでした。同じ「ジェイムズ」なら、ワタクシはビリー・ジョエルの名曲の方を推すな。こっちはちゃんと「小説」してるからね。これこれ! ↓ビリー・ジョエル「ジェイムズ」
November 25, 2025
閲覧総数 248
-
3

井上拓真 vs 那須川天心戦
昨日行われた井上拓真 vs 那須川天心戦、観ちゃった。 第1ラウンド、第2ラウンドあたり、那須川選手の方が断然有利で、一発、かなりいい奴をくらって拓真選手がグラッとするシーンもあったりして、あれ、これは案外、早い決着になるのかなと。 とにかくね、リーチの差が数字以上にあるというか。リーチの長い那須川選手に対し、リーチの短い拓真選手が圧倒的に不利で、拓真選手のパンチが全然届かないのよ。 ところが第3・第4ラウンドで若干、拓真選手が盛り返してきた。私の見立てでは、それでもまだ那須川選手が有利と思っていましたが、第4ラウンド終わった時点での採点では両者まったくの互角。おそらくこの採点を見て、拓真選手は「行ける」と思ったのではないでしょうか。 で、その後は拓真選手が至近距離からのアッパーの連打もあったりして、結構、有利に試合を運び、両者の点差は拓真選手有利に振れていく。で、そのまま、那須川選手が挽回することなく、最後まで行っちゃったと。 ワタクシの戦前の予想では、両者ともKOするだけのパンチがないので、判定勝負になるだろうなとは思っていて、判定になった場合、無敗神話という追い風もあるし、何事につけ派手な那須川選手の方に分があるだろうと思っていたのですが、その予想はいい意味で外れちゃった。 まあ、いいんじゃないの? 井上拓真選手はたたき上げのボクサーだしね。キックから転向してきてまだ2、3年とかの人に負けるわけにはいかないでしょう。ボクシング好きの玄人ファンは皆、井上拓真選手推しだっただろうし。 で、思うのは、那須川選手のこと。 なんだろう、本人は大真面目に精進しているのだろうけれど、いざ表に出るとなると、天性のビッグマウスというか、ちょっと外連味があり過ぎる。 彼は何かと言うと「シン・ボクシングを見せる」とか大口を叩くわけで、キックボクシング・ファンと那須川ファンにはそういうのも受けるだろうけど、生粋のボクシング・ファンからしたら「しゃらくさい」と思っちゃうのよ、どうしても。 だから、今後、那須川選手が、生粋のボクシング・ファンからも愛されたいのであれば、ああいうビッグ・マウスは慎んだ方がいいと思うし、控室でのボクシングを舐めたような動きや、派手な入場とかも慎んだ方がいいと思う。 今の那須川選手の立ち居振る舞いを見ていると、柔道の講道館杯に、覆面プロレスラーがテーマソングかけて入場してきたような感じに映る。このままだと、そういう「色物」のまま終わるよ。その才能を花開かせたいなら、周囲の人間も、参謀として、彼の振る舞いを変えてあげないと。余計なお世話だけど、ついそう思ってしまいますわ。
November 25, 2025
閲覧総数 219
-
4

おめでとう、安青錦!
かつては熱狂的な好角家、でもモンゴル力士全盛時代に興味を失い、この二十年ほどほとんど相撲を見なくなったワタクシ。今もほとんど見ないのですが、今日はたまたま午後のコーヒー・ブレイクに相撲の時間が重なった上、千秋楽だったこともあって、結局、優勝決定戦まで見ちゃった。 で、安青錦の初優勝を目撃したというね。 最初にテレビをつけた時、たまたま安青錦と琴桜の一番をやっていたのよ。で、安青錦が勝ったのですが、ワタクシが驚いたのはその勝ち方。両者低く当たってこれ以上ないというくらい低く構え、膠着状態に入ったまさにその時、安青錦が内無双を切ったのよ。それで琴桜が前に落ち、勝負あり。 えーー。あの状況で無双を切るの?! 素晴らしい。さすが安治川親方のところの弟子だけのことはあるわ。安治川親方は現役時代、技能賞をやたらに取った技巧派だからね。 あの内無双ですっかり気に入った安青錦。それが次に優勝決定戦に出るということで、これは興味津々。 で、対横綱戦。やる気満々の豊昇龍に対し、ガチコンと当たって一歩も引かず、逆に横綱を押し込んで相手が引くのに乗じて横に回り込み、そのまま押しつぶして勝負あり。 外国人力士の通例とは異なり、安青錦はむしろ小兵と言っていいくらいの体格。それで横綱の突進に一歩も下がらなかったんだから、体幹が強いんでしょうな。小さい割に馬力もあるし。そして業師なんだから面白い。 ウクライナ出身というところも、ちょっと応援したくなるしね。 ということで、今日は思いもかけず、好角家だった昔に戻って、ついつい相撲に熱中してしまったワタクシ。まあ、そういうこともありますわ。 でも、安青錦は良かったね。弱冠21歳、来場所は大関だそうですが、果たしてこのまま横綱まで突っ走れるか。ちょっと楽しみですな。
November 23, 2025
閲覧総数 389
-
5

その自己啓発思想に、神はいるのか?
頼まれている新書本執筆が滞っておりまして。こういうことは、ワタクシには珍しいのですが。 滞ると、当然、執筆がおっくうになる。執筆がおっくうになると、さらに滞る。これを悪循環という。ワタクシは今、まさにその悪循環にはまっているわけですな。 だけど、ここ数日、試行錯誤しつつ筆を進めているうちに、結局、これをやらないといかんのだろうな、というのが見えてきた。 見えてきたのは、今朝。眠りから覚めて、まだウトウトしている時。ワタクシの場合、この状態の時にアイディアがひらめくことが多いんですが、今日もそのパターン。 ずばり、言いましょう。なぜ、日本では自己啓発本に対して批判的な人が多いのか。 答え。それは日本人が自己啓発本の根本にあるキリスト教的発想を踏まえていないから。 結局、これだなと。だから、このことを書かないと、永久に日本人は自己啓発本の世界を完全に理解できないままになってしまう。 日本人は、アメリカから自己啓発思想が入って来た時に、それを儒教の立身出世主義に接ぎ木する形で理解しちゃったのよ。つまり神のない自己啓発思想として理解してしまった。 だけど、本来の自己啓発思想のポイントはキリスト教的世界観だから、それを儒教の発想で理解すると、最終的には誤解が生じる。この誤解こそが、日本人の自己啓発思想嫌悪の元なのだと。 だから、本当の意味で自己啓発思想を理解するためには、「神のいる世界」というものをベースにしないとダメよと。そしてそこを理解すれば、自己啓発思想に対する日本人の誤解は氷解するよと。 たとえば、アメリカの自己啓発思想では、直観を信じろ、という話がよく出てくる。 これ、日本人には理解できないわけよ。論理を突き詰めた結論よりも、パッと思い浮かんだ直観を上に置くって、どういうこと? そんなの非論理的じゃない?! というわけ。 だけど、違うのよね。そうじゃない。 本来の自己啓発思想では、そもそも宇宙の中心に神がいて、人間の中にも神の一部が埋め込まれているという想定があるのよ。つまり、人間は神から直通トランシーバーを手渡されているようなものなわけ。直観というのは、だから、そのトランシーバーを使って神が人間に「こうしなさい」と教えてくれているのと同意なの。 だから、人間が論理的に突き詰めた結論よりも、直観を重視するというのは、論理的なわけ。だって、神の論理の方が人間の論理よりも上だから。神と人間とどちらが優れているかを考えれば、直観の方が上だ、というのはまさに論理的な帰結なのよ。 そういうのが呑み込めていないと、自己啓発思想の本当のところはわかりません。 だから、新書ではそこを書けばいいのだ・・・・と、ひらめいたわけ。これもまあ、いわば、直観だよね! 神様がワタクシに「こうしなさい」と教えてくれたのだから。 ということで、当面はその方向で書き進めてみよう。何しろ、ワタクシには神様がついているのだからね。成功するかどうかわからないし、この先も詰まるかもしれないけど、その時はまたその時で、神がワタクシに方向を示してくれることでしょう。
November 24, 2025
閲覧総数 339
-
6

年賀状、出すべきか、出さざるべきか・・・
11月も後半に入って、そろそろあちこちから喪中はがきが届くようになりました。なんだか矛盾するようだけど、喪中はがきが届くようになると、そろそろ年賀状、用意しないとな、という気分にさせられます。 年賀状ねえ・・・。 最近、喪中ではないけれど、年賀状じまいをする、という人が周りにも増えてきました。家内なんか、何年か前からそうしているし。 一方、ワタクシは相変わらず年賀状を出し続けて入るのですが、最近、さすがのワタクシも、それってどうなのかなと思うようになりまして。 特に、昔の親しい教え子との年賀状のやり取りね。 教え子だって、ワタクシから年賀状をもらえば返さないわけにはいかない。ひょっとして既に年賀状じまいをしているのに、ワタクシに対しては出さなければと思って、面倒な思いをしているのかもしれないなと。 どうしようかな。今年あたりから、もう、出す相手を厳選して、出す量を半分くらいに減らそうかな。 とはいえ、さすがに全廃というわけにもいくまい。 まあ、とりあえず年長者に対しては今まで通りにし、年下の人に対しては、向こうから来れば返す、というスタンスにしておいて、年賀状をやりとりを続けるか止めるかの決定権を相手に渡す、というのがいいのかもね。 それにしても、とにかくそろそろ年賀状を買わなくては。週明けにでも、通勤途中に買っていきますかね。
November 22, 2025
閲覧総数 495
-
7

白山神社の御利益? マスコミへの露出キターーー!
先週、家の近くの白山神社に詣でて、「マスコミへの露出が増えますように!」ってお祈りしておいたのだけど、お賽銭をはずんだ成果がいきなり出ました! まずね、『Forbes Japan』の最新号に記事が載りました。まあ、これは掲載されることになっていたんだから、不思議はないのだけど。 で、次に驚いたのが、某在京ラジオ局の某番組への出演が決まったこと。前にNHKラジオに出た時はアナウンサーさんと喋ったんだけど、今回は芸人さんとのからみだって。面白いねえ。週末は収録に行かなくちゃ! そして、あれあれと思っている間に、突然、6年前に出した本のキンドル版が再び売れ出したこと。多分、どなたか影響力の強い方がコメントしたんだと思う。これこれ! ↓ハーレクイン・ロマンス【電子書籍】[ 尾崎俊介 ] いやはや、こうも続けざまにいいことが起こると、怖くなるねえ・・・。 とにかく、こうなってくると近いうち、白山神社にお礼参りにいかないとまずいな。またまたお賽銭はずんじゃおう!
November 26, 2025
閲覧総数 130
-
8

半纏の季節
急に寒くなりましたなあ。 で、そんな話を家内としていた時、そう言えば子供の頃、寒くなると半纏を着させられたという話になり。 ああ! そう言えばそうだった。我が家でも中学生とか高校生の頃、家では冬に半纏を着ていましたわ。 ああいう半纏は、一体どこで買ったのか。なんか当時としては、スーパーの衣料部とかではなく、商店街にある呉服屋だか布団屋だか、そういうところの店先で、1500円くらいの安い値段で売っていたのではなかったかと。あいまいな記憶だけどね。 ほんと、そういうのを、カッコいいとか悪いとか、そういう判断なしに、寒いから着る、みたいな感じで着ていたなあ。自分だけでなく、たとえばテレビ・コマーシャルとかでも、受験生といえば半纏に鉢巻、みたいなのがこの季節の定番だったような。 懐かしいな。父母の膝下にいてなんの不安もなく過ごしていた頃、冬に着ていた半纏。 そんなことを考えていたら、なんだか、そういうのをまた着たくなってきた。 今、そういうのって、どこに行けば売っているのだろう? イオンに行けばいいのか? いや、楽天で買えばいいのか。これこれ! ↓久留米 半纏 メンズ はんてん 綿入り 半天 袢纏 男性用 どてら 日本製 丹前 冬 暖かい 部屋着 誕生日 ギフト 冬 ちゃんちゃんこ 男性フリーサイズ どんぶく 誕生日 プレゼント ギフト でもなんか、通販で買うのは面白くない。どこか旅先で、シブい商店街の店先でゲットするとか、そういうドラマ性が欲しいな。ちょっとヒマになったら、半纏探しの旅にでも出るか?
November 21, 2025
閲覧総数 561
-
9

『「成功哲学」を体系化した男 ナポレオン・ヒル』を読む
マイケル・リット・ジュニアとカーク・ランダースの共著になる『「成功哲学」を体系化した男 ナポレオン・ヒル』(原題:A Lifetime of Riches, 1995)という本を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 っていうか、これ、再読なんですけど、前には心覚えをつけておかなかったので、改めまして。 ナポレオン・ヒルは、泣く子も黙る自己啓発本の王者『思考は現実化する』の著者なんですが、その割に伝記が無かった。まあ、自己啓発本の著者なんて、文学史的には馬鹿にされていますから、それも珍しいことではないのですけど、ヒルの場合は、ナポレオン・ヒル財団というのが作られているので、そこがこの伝記を企画し、ようやく一応は伝記的なものが書かれたと。 ただ、そういうものとして、結局、お手盛りの伝記になっているわけですよ。悪いことは書かない。っていうか、書けない。だから、ここに書いてあることを、100%真実だと見做すのはちょっと、っていうところがある。話半分で読まないといかんわけ。 まあ、それはそうとして、ざっと見ていきます。〇ナポレオン・ヒルの実母サラは、ヒルが9歳の時に他界。そのため、ヒル少年は近所でも評判の悪ガキに。(29)〇サラの死から1年後、ナポレオンの父ジェームズは再婚。この再婚相手のマーサがいい人で、彼女のお陰でヒルは真っ当に育つことに。(31)〇ヒルが12歳の時、マーサは、銃と交換する条件で、ヒルにタイプライターを買い与え、これがヒルの文筆業を志すきっかけとなった。(34)〇ヒルは、一時期弟と共にロースクールに通うが、その際、Bob Taylor's Magazine という立身出世雑誌を出していたロバート・L・テイラーという人物の元でフリーランスのライターのバイトをする。その後ロースクールでの学習に飽き、法曹の道は断念。(56)〇結局、1908年、25歳の時に、先の雑誌会社に勤めることになり、産業界の名士にインタビューする仕事に就く。そこでインタビューすることになったのが、アンドリュー・カーネギーだった。(59)〇同じ1908年、ヒルはフローレンス・エリザベス・ホーナーと結婚。(77)〇結婚した13カ月後に、ヘンリー・フォードにインタビュー。その場でT型フォードを680ドルで購入。フローレンスの顰蹙を買う。(84)〇1912年11月11日、次男ブレア誕生。ブレアは耳の障害を抱えていた。(90)〇1913年冬、家族を置いて単身シカゴに出たヒルは、ラサール・エクステンション大学の宣伝・販売部門に就職。ここで「人に教える」ことについての自分の才能に気づく。(93)〇その後、1915年に「ベッツィ・ロス・キャンデー・カンパニー」なる菓子製造業を起こすが失敗。企業よりも教育が自分の天性であると悟り、1916年、通信教育コース「ジョージ・ワシントン・インスティテュート」を設立。(-102)〇1917年、アメリカは第1次世界大戦に参戦。ヒルは既知の間柄であったウッドロー・ウィルソン大統領に手紙を書き、何らかの貢献を志願。その結果、ウィルソン大統領からプロパガンダ資料作成の仕事をオファーされる。ヒルはこの申し出を無給を条件に受ける。(106)〇1918年11月、休戦を申し出るドイツに対し、カイザーの退位を条件にすることをウィルソン大統領に進言。(110)〇1918年11月11日、終戦の日、黄金法則に基づく資本主義の再編というアイディアを思いついたヒルは、その思いを文章にし、シカゴの印刷業者ジョージ・ウィリアムズに見せたところ、同意を得ることに成功する。(-117)〇1919年1月、『Hill's Golden Rule』なる雑誌創刊。そこそこの成功。 「この成功は、ナポレオン・ヒルの才能、忍耐力、そして彼のユニークな編集コンセプトの証明であった。 当時、アメリカには数え切れないほどの宗教関連雑誌があった。おそらく、ビジネスに関する雑誌の数はさらに多かっただろう。しかし、"Hill's Golden Rules" は、この二つの分野を統合したユニークなものだった。それは倫理的ガイダンスと成功の秘訣を統合させた、前例のない雑誌だったのだ。」(120-121)〇「すべてのストーリー、人物描写、意見は人生における二つの真実を読者に教えていた。一つは、「自分がしてほしいと思うことは、なによりもまず他人にそうしてあげることだ」という黄金律こそが、ビジネスと人生における成功の切符であるということ。もう一つは、ゴールを定め、障害物や失望をものともせず、それを追求する人物が成功するということであった」(122)●「狂乱の一九二〇年代は、ナポレオン・ヒルにとって新しい時代の到来を意味した。彼は自分のことを、成功した雑誌をつくり出した才能ある文筆家兼哲学者ととらえていた。(中略) ”Hill's Golden Rule” の誌面は毎月、ビジネスの世界で成功するよう、労働組合や社会主義といったアメリカ社会における反競争的要素と闘うよう、読者に勧める何万もの単語によって埋め尽くされていた。 当時の伝統的保守主義者たちとは違い、ヒルは資本主義の行き過ぎを正当化したりはしなかった。彼は理解しやすい哲学を構築し、放任資本主義を一般人にとってずっと魅力的で身近なものとした。それは「高い身分には道義的な義務が伴う」という、古くからあるヨーロッパの概念に二〇世紀のアメリカ独特のひねりを加えたものであった。 このヨーロッパ産に概念は、貴族には富と権力を支配する権利があるが、同時にそれらを公正に賢く運用する義務もあるというものである。「すべての人間には、成功を手に入れるだけでなく、手に入れたなら、人生と財産のある部分を他人が同じゴールに到達するのを手助けするために捧げる義務がある」とヒルは説いた。 ナポレオン・ヒルの哲学は、物質主義と道徳を、そして資本主義とヒューマニズムを統合していた。 何千人何万人ものアメリカ人にとって、彼の説明は説得力があった。彼の哲学は、苦しい状況を乗り越えようとしている人々に希望を与え、厳しい労使対立をやわらげた。彼は野心を抱く労働者に、ストライキをやめ、自由の国アメリカで彼らが見いだすことができる無限の可能性の中から、もっといい機会を見つけるよう説いたのである。」(124-125)〇Hill's Golden Rule の表紙絵あり。「A Business Magazine of a different kind」の文字あり。(127)〇この雑誌はそこそこの成功を収めたが、ジョージ・ウィリアムズと不和になり、ヒルはこの雑誌から手を引く。(127)〇1921年4月、新雑誌『Napoleon Hill's Magazine』創刊。『Hill's Golden Rule』より判型を大きくし、目立たせた。(128)〇「加えて、新雑誌は毎号、インスピレーションを与えることを目的としたフル・ページ・メッセージで彩られていた。実際に大きな活字で組まれたこれらのメッセージは額縁に入れるのに最適であった。これらの「ページ・エッセイ」は、他の雑誌における全面広告と同じ効果を生み出していた。それはグラフィックと編集の両面で、記事と意見のページに緩衝地帯を生み出していたのである。」(130)〇1921年夏、ヒルは文筆業よりも講演業に力を入れていた。 「当時、彼は二つの講演シリーズに基づいてスピーチを行っていた。 一つは”Magic Ladder of Success”と『呼ばれ、ビジネス団体を対象としたものであった。これは、ヒルが成功の基盤であると信じていた十五の原則を網羅したもので、黄金律の哲学に忠実に、ヒルが最も大切にした理想を織り込んだ。それは友好的な協力、そして人種的、宗教的不寛容、憎しみ、ねたみの追放であった。 彼のもう一つの講演シリーズ”The End of The Rainbow"は、純粋にインスピレーションの喚起を目的としたもので、市民グループや宗教団体を対象としていた。 これはヒルが「私の人生における、七つの主要なターニング・ポイント」と呼んだものに基づいていた。彼は自分の個人的、そして仕事上の成功と失敗、そしてその両方から、彼が学んだ教訓について話した。ヒルは、こうした自分が得た教訓を、人生を乗り切る上での指針としてほしいと願い、聴衆に伝授したのである。」(133)〇「ヒルの、影響力を持つ話し方をフルに活かすため、このコースには教科書一〇冊だけでなく、六枚のレコードがつけられた」(134)〇1922年、火事でそれまでのすべての記録を失う。(142)〇1926年、『カントン・デイリーニューズ』の発行者ドン・メレットと共同で、USスティールの会長の庇護の下、「成功哲学」を説いた本の出版に向けて計画を進めるが、ドン・メレットがギャングに殺害され、計画が反故になり、ヒルも隠遁生活を強いられる。(147⁻150)〇1927年、カーネギーとの約束からほぼ20年が経ち、いよいよ成果を出すことを決意。1500ページ、8分冊の成功哲学書の刊行を計画。コネティカット州の印刷業者アンドリュー・ペルトンに対し、外連味たっぷりのセールスを行い、この本の出版を引き受けさせる。それまでヒルがアプローチした出版社は、すべて文学系出版社だったが、ペルトンの出版社は自己啓発本の出版社だったことが幸いした。(-162)〇リライトは1927年の暮れから1928年3月末まで続き、その結果、完成したのが『Law of Success』。8冊の分冊で販売され、一冊4ドルでバラ売り。全巻揃えると30ドルだが、1929年当時、30ドルあれば一家四人が一か月生活できたという。それでもバラ売りの効果か、それなりに売れた。(166)〇『成功哲学』で説かれていたのは理論ではなく、事実と証拠であり、「個人のための資本主義の福音」であって、こういう種類の本が出されたのは初めてのこと。(167)〇小売り業にとって、『成功哲学』は現在の「シリーズもの出版物」の先駆け。第一巻を買った人は、第二巻、第三巻・・・と繰り返し買って行くので、書店にとってはありがたいものだった。(167⁻168)〇『成功哲学』の第一巻の主要レッスンは、「マスターマインド」。この法則は、「二人で考えるほうが一人で悩むより良い」という古来の格言を実用的に発展させたもの。ユニークではないが、ヒルはこの法則をビジネスに応用した、という点で独創的だった。マスターマインドを組むことで、ビジネス上の協力関係にある人々の間の軋轢を取り除き、すべてのエネルギーを市場にそそぐことができる点で、大きなメリットがあった。事実、当時26歳だったクレメント・ストーンは、マスターマインドの考え方を自社と自分の家庭に応用し、効果を上げていた。(168⁻169)〇また第一巻には、振動する流体である「エーテル」に関する抽象的な議論も展開している。人間の思考の波はエーテル中で永遠に振動し続ける、的な。ゆえに、この本は「狂人の戯言」とみなされても仕方ない類のものでもあった。(169⁻170)〇『成功哲学』の好評により、1929年夏、ヒルと妻は、一時的な裕福さを味わう。そしてニューヨーク州キャッツキル山脈のふもとに、成功哲学を教える学校を作らんと、夢を見た。(174⁻)〇1929年の年末、ヒルは次の作品『The Magic Ladder to Success』の執筆に入っていたが、ここで世界大恐慌勃発。(183-)〇『Magic Ladder』は恐慌のために売れず、1930年10月には、ヒル一家は再びどん底へ。(186)〇1931年4月、ワシントンDCに移ったヒルは、「Mental Dynamite」と題した講演シリーズのプロモーションを開始。その他、貧困を脱出する様々な企てを立てるが、すべて失敗に終わる。(187-)〇1933年、50歳の誕生日を迎える直前、ヒルはルーズベルト政権からアプローチされ、国家再建本部のスタッフになる。ウッドロー・ウィルソン政権の時と同じく今回も無報酬を申し出る。ルーズベルトの「私たちは、恐怖そのもの以外、何も恐れるものはない」というフレーズは、実はヒルが考案したものだった。(189⁻190)〇ルーズベルト政権が大恐慌から国を立て直すことに成功したのも、ヒルのマスターマインドの考え方を政権が取り入れ、国を挙げて不況克服のゴールに集中することが出来たからである。(196)〇1935年、多忙により齟齬の大きくなったこともあり、フローレンスと離婚。(198)〇1936年年末、ローザ・リー・ビーランドと出会い、「情欲を掻き立てられ」結婚。(200⁻201)〇しかし、ローザ・リーは、後に書いた本の中で、「金のために結婚するのは、他の動機と同じく立派なことだ」と主張していたように、ヒルを金づると見ていた。(202)〇ヒルはこの頃、『The Thirteen Steps to Riches』という本の原稿を書いていたが、ローザ・リーはこれを励まし、自らタイプを打って三回に及ぶ書き直し作業を手伝った。(203)〇ヒルの出版を担当していたアンドリュー・ペルトンは、当初、難色を示したが、ローザ・リーに押し切られる形で出版に同意、タイトルを魅力的にすることが条件となり、『Think and Grow Rich』というタイトルで出版された。当初、一冊2.5ドルで5000部だった。そして、不況下であるにもかかわらず、本書は飛ぶように売れた。(204)〇本書の成功は、理論的に『成功哲学』に基づいていたこと、カーネギーとのエピソードのユニークさ、そしてローザ・リーが本書の明確さ・簡潔さに貢献したことなどが挙げられる。性衝動をビジネスに活かすことなど、初期にはなかったものも入っていた。想像力がビジネスに重要であることを指摘していたことも、この本が初めてだった。(206)〇クレメント・ストーンは、1938年にこの本に出会い、実際に彼の会社は、この本に基づいて大きく成長した。(208⁻209)〇1940年には、ヒルの財産は100万ドルを超えていた。この年、ローザ・リーは『How to Attract Men and Money』を出版。この後、両者の関係は悪化し、裁判の末、1941年3月に離婚成立。(212)〇その後、失意のヒルは、サウスカロライナ州クリントンで織物業の広報を担当していたオーアム・プラマー・ジェーコブズに招かれ、この地で労使関係を改善するために手を貸す、という仕事をもらう。(214⁻215)〇ここでヒルは『Mental Dynamite』の改稿・執筆をしていたが、同時にアニー・ルー・ノーマンという女性と出会い、ゆっくりと二人の交際が進むことになる。(220)〇1941年末、『Mental Dynamite』出版。(228)〇しかし、この頃、第二次大戦が勃発。紙が配給になり、出版事業には痛手となる。(228)〇ところが、軍事物資の生産をしていた地元の業者ルトゥルノーに、労使関係改善のアドバイスを求められ、この分野で再び活躍。(230)〇1943年、ヒル、アニー・ルーと結婚。(240)〇ラジオ番組で、成功哲学を説くようになり、評判になる。(242)〇1949年、65歳でセミリタイア宣言。(243)〇1951年、シカゴで講演をしたヒルは、知人の紹介でクレメント・ストーンに会い、ここからヒルの晩年の活動の扉が開かれる。(248)〇1952年8月、「ナポレオン・ヒル・アソシエイツ」結成。(251)〇1953年、ヒルとストーンとの共著『Science of Success』(後の『PMA Science of Success』)の最初の一巻が出る。これは例の17の成功法則の自習紙上講座。(254)〇1953年、ヒルとストーンは『How to Raise Your Own Salary』を出版。アンドリュー・カーネギーとの対話形式で、成功原則を語るという趣向。本書は、ヒルの文才を、ストーンの販売力で売る、という形式のパワーが存分に発揮され、ストーンは様々な媒体を使ってこの本の販促を行なった。なかでもラジオ/テレビ・パーソナリティーとして活躍していたアール・ナイチンゲールがヒルの信奉者だったことから、ナイチンゲールも熱心にこの販促に協力した。(255⁻256)〇アソシエイツの発展には、デール・カーネギーやノーマン・ヴィンセント・ピールも協力。(267)〇1959(1960?)、ヒルとストーンは共著として『Success Through a Positive Mental Attitude』(『心構えが奇跡を生む』)を出版。ほとんどはストーンが書いていた。〇1961年、78歳になったヒルは、アソシエイツのフランチャイズ化を企画。これはあまりにも無茶であるということで、ストーンはアソシエイツ事業をヒルに委託して、自らは手を引いた。(271)〇1962年8月、ヒルとアニー・ルーは「ナポレオン・ヒル財団」を設立。(276)その目的は、『アンドリュー・カーネギーの協力による、ナポレオン・ヒル博士の生涯をかけた研究、著作、教義を永遠のものにすること」。(277)〇1970年11月8日、ヒルは87歳にて永眠。(287) ・・・というような感じかな。 さて、一巻を通じて学んだのは、黄金律の重要性。 黄金律はキリスト教徒にとっては非常に重要な概念であるけれども、ヒルはこれをビジネスの極意として位置付けた。これによって、キリスト教徒のビジネスマン化に貢献したということ。 それから、彼のマスターマインドという考え方が、彼の生きた時代には大きな問題であった労使関係の改善に用いられ、効果を発揮した、ということ。つまり、アメリカが嫌悪する社会主義的な発想を廃して、それでもなお労使が力をあわせることで、労使の間にウィンウィンの関係が築けることを実証したこと。これも大きかった。この意味で、実際にヒルが二つの政権に協力したかどうかは別としても、彼の思想が、政権にとっては非常に受け入れやすいものであったことは事実。だから、彼が自分の思想の政治的活用を夢想したとしても、それは納得できる。 そして、分冊方式での本の販売や、オーディオ・ブックの販売、メディア・コングロメリットによる本の販促といった、革新的なマーケットを試みた、という点も評価できる。 これらのことが納得できたことだけども、本書を読んだ甲斐はありましたね。 それにしても二番目の奥さんのローザ・リーは、したたかな女だなあ・・・。これこれ! ↓成功哲学を体系化した男ナポレオン・ヒル/バーゲンブック{マイケル・リット・ジュニア 他 きこ書房 ビジネス 経済 ビジネス読み物 経営者評伝 評伝 哲学 読み物 経営}
March 26, 2024
閲覧総数 577
-
10

「すわえ」って何?
皆さん、「すわえ」って言葉、ご存知? これね、木の枝や幹から細く長く伸びた若い小枝のこと。漢字で書くと「楚」となります。あるいは「木へん」に「若」、あるいは「木へん」に「少」という字を書くと、それぞれ「すわえ」と読むらしい。木へんに若いとか少ないとか、「峠」と同じく明らかに日本製の漢字でしょうけど、そんな字に出会ったことがないですな。っていうか、そもそも「すわえ」という言葉自体、知らなかった。 なんで「すわえ」の話題になったかと申しますと、実家の庭に梅の木があり、「梅切らぬバカ」で剪定しないものですから、若い枝がすんすんと夏空に突き出すように伸びている。それを「すわえ」というのだ、と母が教えてくれたもので、いや〜、そんな言葉しらなかったなあ、という話になったわけ。 で、「すわえ」を辞書でひいてみると、確かにそういう言葉がありますなあ。 で、この年齢になっても、まだまだ知らない日本語があるわい、と思ってそのまま辞書を読んでいると、これがまた面白くて。 たとえば「すわえ」の近くに「すわこそ」という言葉がある。これは「すわ」を「こそ」で強調した言葉で、要するに「さあ、大変!」という意味。これは何となく判りますが、日常的に「すわこそ!」って言ったことないなあ。 その下は「スワジランド」。南ア共和国とモザンビークに挟まれた王国だそうで。首都はムババネ。知らなかった・・・。 その下には「すわすわ」という擬態語がある。これは物の軽く打ち当たる様だそうで、宇治拾遺物語からの引用で、「毛の中より松茸の大きやかなる物の腹にすわすわとうちつけたり」とある。何だ、この引用は? ちなみに「ずわずわ」となると、これは現代語の「ずばずば」と同意とのこと。「あの人の占いはずわずわ当たるね!」で、使い方あってる? そのちょっと下へ行くと、「諏訪八幡も照覧あれ」という項目がある。これは「決して偽らない」という意味なんだとか。いいね、これ。今度、使ってみよう。「うそじゃねーよ、諏訪八幡も照覧あれだよ」とか。 とまあ、知らないと言葉を探し出したらキリがない。日本語は語彙が豊富だなあと思いつつ、現代人はそのうちの何割を使って生活しているのだろう、と、反省してしまいました。 昔の偉い学者さんの話なんかを読むと、『言海』を何度か読破した、なんてツワモノが沢山いますけど、私も少し国語辞書を読んでみましょうかね。だけど、私だけ読んで語彙を豊富にしたところで、周りの人も一緒に語彙を豊富にしてくれないと、通じない理屈ですよね。 「伸びた梅のすわえが家の壁にあたってすわすわするので、思い切ってずわずわ切っちゃった。ホントだよ、諏訪八幡も照覧あれ」。これが通じる日本に、ならないだろうなあ・・・。
August 18, 2013
閲覧総数 1495
-
11

映画『暴力脱獄』を観た
昨夜、NHKの衛星映画劇場でポール・ニューマン主演の『暴力脱獄』(1967年)をやっていたので、久々に見直してしまいました。 この映画を最初に観たのは、もう正確には覚えていないほど昔のことで、多分私が小学生の高学年とか、せいぜい中学生とか、そのくらいの時だったのではないかと。で、その時、面白かった、という印象が強かったので、もう一度見ちゃおう、という気になったわけですな。 ところが・・・。 やっぱり、子供時代の目線というのは我ながら幼いというか、つたないというか。最初に観た時の印象は、とにかくポール・ニューマン演じるルークという名の囚人が、それこそ不屈の精神で何度失敗しても脱獄を繰り返す、そのガッツに感動! というもので、まあ、そこしか観てなかったと。 しかし、今回改めて見直してみたら、あんまり実のない映画だなと。私の個人的な評価は大下降でございます。 要するに、こう、あざとい感じがするんですよね。1967年っつーと、『卒業』とか『俺たちに明日はない』などが上映された年、そしてもう2年もすると『イージー・ライダー』でしょう? アメリカ文学的にいえば、ケン・キージーが『カッコーの巣の上で』を書いたのが1962年。つまり1960年代ってのは、文学界・映画界では反抗もの/反体制ものがどどっと出てくる時代なわけですよ。だからまあ、「抑圧的な実社会」を「規則の厳しい刑務所」に移し替え、その規則に反抗して何度でも脱獄を試みる一人の囚人をヒーローとして描くなんていうのは、いわば時代の常套句だったところがあるわけですよ。その意味で、テーマ的に新味はない、と。 で、テーマに新味がないのは、私としては別に構わないんです。でも、それなら細部に凝って欲しい。しかし、この映画の場合、そこがいまいちなんだなあ。 という意味はですね、雑に作ってある、ということではなく、逆に作り手の意図がちょっと見えすぎだ、ということなんですけどね。例えば抑圧的な刑務所を象徴する人物として「サングラスの男」を用意し、彼が最終的にルークを射殺するところとか。その上で、彼のサングラスが最後に壊されるところを映して、体制に対するささやかな反撃を演出するところとか。なんか、こう、あまりにも陳腐過ぎる。 それからルークという男の造形が実に曖昧。戦争のヒーローであった彼がなぜ「酔っぱらってパーキング・メーターを破壊した」などというつまらない罪で刑務所に入らなければならないのか。また刑務所に面会に来た母親との会話で、彼が母親から贔屓されて育った母親っ子であったことは分るとして、その母の死(および、それに対する刑務所側の仕打ち)に反応して最初の脱獄を図るくらいなら、どうして娑婆にいるときからもっとまともな生き方をしなかったのか。その辺の事情がまったく描かれてない。 要するに、ただ「大した罪でもないのに不当に刑務所に入れられ、しかもそこで不当にひどい仕打ちを受ける人物」という設定だけが欲しかったんだな、ということがバレバレなんだなあ。 しかも、ますますルークの人物像を分らなくするのは、映画中に繰り返されるキリスト教的ニュアンスです。「ルーク」という名前からしても「ルカ伝」を偲ばせますが、有名な「卵食い」のシーンで、50個の卵を食べて伸びちゃったルークの姿を、キリストの磔刑図そっくりに演出するところとか、「雷のシーン」や「最後の脱獄のシーン」で彼が神に「old man」と呼びかけるところなど、ルークを「人々に神の子と期待されつつ、その期待を一度裏切り、死んだ後に人々(の心)に蘇って希望の光となる」キリストになぞらえていることが見え過ぎ。その割に、ルークと神の関係についてはまったく描かれていないという・・・。 つまり、ここでも「ルークをキリストのように描く」という意図だけで作られた映画、ということが見え見えなんですよね。 でね、ワタクシ、こういう感じで「製作意図」だけの映画ってまったく評価しないんだなあ。製作意図があるのはいいんですけど、それならそれを裏付けるだけのリアルな設定が欲しい。もしこういう映画を作るのであれば、例えば「ルークはもともとすごく宗教的な男だったのだけど、何か彼の信仰をゆるがせるようなことがあって、それで自暴自棄になって刑務所に入った」とか、そういう事情をちゃんと描いて欲しいわけ。観客を納得させるような筋書きで。 だから、もしこの映画が最初からルークを完全な「愛すべき反社会的人物」として描き、とにかく子供の頃から反抗、反抗。結果、刑務所に入れられても反抗、反抗。で、どんなひどい目にあってもとにかく脱獄を試みる、というような徹底的な反抗的人物として描いてくれたなら、ワタクシはそれで満足したと思うのですが。多分、子供の頃の私は、この映画をそういう映画だと思って見ていたので、「すごく面白い」と思ったのでしょう。しかし、大人になってから見直すと、この映画の製作者たちがこの映画に妙な意味づけをしよう、しようとしているところが見えるようになってしまって、それがどうにも鼻についてしまった、というところなんでしょうな。 で、それだったら、同じタフな脱獄囚を描いた『パピヨン』(1973)の方がいいかな、なんて思ったりして。でも、私が『パピヨン』を見たのも子供の頃だったしなあ。今見たら、ガッカリするかも・・・。見直してみたいような、子供の頃の「面白かった」という印象を壊したくないような。 ま、それはともかく『暴力脱獄』、見直したことによって、逆に私の中では評価を下げてしまったのでした。残念! ちなみに、一応この映画の筋書きを確認しようと思って、「goo映画」を見たんですが、どうもここに書かれている筋書き、随分、実際と違うのではないかと。あれはどなたが編集しているのか、知りませんが、書き直した方がいいのではないかと言っておきましょう。
January 13, 2010
閲覧総数 328
-
12

マラベル・モーガン著『トータル・ウーマン』に驚愕
マラベル・モーガンという人の書いた『トータル・ウーマン』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 この本、1973年に弱小出版社から出版されるや、すぐに50万部が売れ、1974年にアメリカで一番売れたノンフィクション本となったベストセラーでございます。 で、1973年とか74年なんつったら、ウーマン・リブ運動の真っ只中と言ってもいい時期。それで『トータル・ウーマン』と来たら、こりゃすごいフェミニズム本だと思うでしょ? ところが、さにあらず。フェミニズムとかウーマン・リブとか、その類いの運動の180度対極にある本よ。 で、この本の内容ですが、冒頭、マラベルさんご自身がご主人となるチャーリーさんからプロポーズされた時の思い出から語り始められます。当然、甘ーい話ですわなあ。 ところが甘かったのも束の間、世の大抵のご夫婦同然(?)、その甘さはあっという間に消え去り、さらに7年後に生まれた娘が4歳になる頃にはマラベルさんとチャーリーさんの仲は冷えきっていたと。 しかし、このままじゃ後10年もしないうちに,夫婦互いに憎み合うようになるぞと思ったマラベルさん、夫婦関係の改善に乗り出します。まず結婚関係について専門家の書いた本を何冊も貪り読み、セミナーにも出、さらに信仰深いマラベルさんとしては聖書も研究し、戦略を練ったと。 で、その戦略を実際にチャーリーさんに適用してみたら、あーら不思議、チャーリーさんのマラベルさんを見る目が劇的に変わり、二人の関係は新婚当初のようにラブラブなものに! かくしてマラベルさんはご自身の成功を元に、単なる主婦ではなく、いつまでも夫から愛され、子ども達から信頼される家の光、すなわち「トータル・ウーマン」になるためのセミナーを起ち上げ、さらにはこの本も書いて、悩めるアメリカ中の主婦たちに自分の後に続けと獅子吼しているのでありまーす。 つまり、冷えきった夫婦関係を元に戻し、最高の家庭の幸福を作り上げるのは一家の主婦たるあなた! そうあなたの仕事なんです! っていう本なの。「トータル・ウーマン」とは「完璧な主婦」の謂いであり、世の女性達よ、完璧な主婦となって、女の幸せを突き詰めろ! っていう本。この前このブログで扱ったベティ・フリーダンの『女らしさの神話』が、女たちよ、主婦なんてつまらない身分はかなぐり捨てて、社会に出て自己実現するのよ! と獅子吼していたのとはまったく逆の本なのね。この対照、ある意味、すごくない? っていうか、ひょっとしてこの本はベティ・フリーダンの『女らしさの神話』に対する、主婦の側の反論なのかもね。「主婦の何が悪いっていうの!? 聖書にだって女の役目は夫を助けることだって書いてあるじゃない。あんたら、偉そうなこと言ったって、しょせん女の幸せの何たるかも知らない哀れな連中でしょ。そんなに男に伍して働きたかったら働くけばいい。その代わり、夫に愛想つかされて離縁されるのがおち。フリーダンとやらも離婚したんでしょ。フェミニストなんぞ、みんな一人寂しく惨めに死になさい! 完璧な主婦たる私たちは、夫の愛に包まれ、子ども達の笑顔に囲まれた最高の幸せの中で充実した人生を歩むのよ!」っていうね。 とはいえ、単なる主婦からトータル・ウーマンになるには、それなりの修行が要ります。 では、マラベル流・完璧な主婦になるにはどうすればいいのか? という話になってくるわけですけれども、結構すごいこと書いてあるよ! 少なくとも私はちょっとビックリ。 マラベル曰く、まずね、とにもかくにも「家の主は夫である」ということを認めろ、と。あなたが今住んでいる家は夫の城であって、その城の王様はあなたの夫なのだから、すべての舵取りは夫の仕事、妻たるものは、差し出がましい口は挟まず、ひたすら夫の言うなりになれと。 ひょえ〜〜〜!! すげー! 1973年という時代にそんなこと言っちゃうマラベルすげー!! でもね、マラベルさんの観察によれば、世の失敗した結婚の例(っていうか、大抵の結婚はそうなんだけど)を見ると、大抵、この点で女は間違うと。つまり、自分が家を切り盛りしている気になって、夫を自分のいいなりにしようとする妻が多過ぎる。だけど、それをやって結婚生活が成功しているのを見たことがないとマラベルさんは言うわけ。 逆に、結婚生活が成功しているのは、夫唱婦随を徹底しているカップルの場合だと。だから、結婚生活をうまく回して行きたいなら、夫唱婦随になればいい。マラベルさんの主張はそういうことですな。たとえ、夫がへまばっかりしているように思えても、そこはぐっと我慢して、「あなた、最高よ! あなたの考えに賛成! 私はいつもあなたの味方! あなたの行く方向に私もついて行くわ!」と言うだけで、万事うまく行く。 と、ここまで話を聞くと、何と言う時代錯誤! 封建社会じゃあるまいし、なんで女が男の後に従わなきゃいけないのよ! と思うでしょ? だけど、マラベルさんのこの先の説明を聞くと、なるほどと思うところもあります。 つまりね、男と女は違う、とマラベルさんは言うんですな。女が欲しいのは愛。だけど男が欲しいのは愛じゃない。賞賛だと。 で、世の(この場合、アメリカ中の)殿方は、賞賛という面では空っぽのグラスみたいなものだと、マラベルさんは言います。空なの。で、空のグラスを傾けても何も出て来ないように、賞賛を受けていない男性をどう動かしたって、そこから女の欲しい愛なんて出て来ない。 だから、女性の皆さん、もし夫の愛が欲しくば、先ずは夫の空っぽのグラスを満たしなさいとマラベルさんは指摘するわけ。 えーーー。だって、私の夫に賞賛すべきところなんて一つもないもん。そう思ったあなた。だけど、あなたの隣に居る男性は、かつてあなたが恋し、結婚したいと思った人なわけでしょ? 夫だって、あなたを愛し、あなたと結婚したいと思ったから結婚したのであって。だから、もし今の夫に賞賛すべきところがないように見えても、そこは恋愛時代・新婚時代のことを思い出して、とにかく夫を褒めなさいと。あなたのこういう所,好きよ。あなた、まだまだカッコいいわ。あなたならきっと今回の仕事、うまくやり遂げられるわ、だってあなたいつも立派に仕事をこなしてきたじゃない。私、いつもすごいなあって、感心していたんですもの・・・。こんな言葉を一言掛けてあげれば、あなたの夫は、俄然、あなたのことを見つめ直し、あなたへのプレゼントを手に、いそいそと家に帰ってくるようになりますよ、と。 マラベルさんのアドバイスをまとめると、もし今の冷えきった夫婦関係を改善したいなら、夫を変えようとしないで、まず自分が変わりなさいと。そしてとにかく先に与える。夫は妻からの賞賛を欲しがっているのだから、その欲しがっているものを与える。そうしたら、夫はあなたにその何倍もの愛を返してくれて、白馬の王子様に変わりますよ、と、まあそういうことですな。 つまり、マラベルさんのアドバイスの中には、「世界を変えたいなら、まず自分が変われ」「受け取りたいと思ったら、まず与えよ」という、自己啓発思想の二大テーゼがちゃーんと入っているんですな。だから,この本は自己啓発本、それも女性向け自己啓発本と言えるんです。 だからね、妻は夫に従うべし、という点だけ見ると、なんだか時代錯誤に見えますけど、その内容をしっかり見れば、主導権を握っているのは女だ、ということでもあるんです。こうやれば、自分の思う通りの夫に仕立てられますよ、夫を自分の手のひらの上で転がせますよと言っているようなもんですからね。男は馬鹿なんだから、それを認めて、頭のいい女がうまく操縦すればいいじゃんと。 私見ですが、マラベルさんの言っていることは、かなり当たっているんじゃないかな。特に、女が欲しいのは愛、男が欲しいのは賞賛、っていうところは卓見のような気がします。 で、このあと、トータル・ウーマンはセックス面でも活発! 誘惑されるばかりじゃなく、夫を誘惑しちゃえ! 的なノウハウが書いてあったり、あと、子育ての面で、いい親になるにはどうすればいいか、的なノウハウが書いてあったりもして、その部分もなかなか読ませます。 で、最後の方になって、マラベルさんの宗教観が語られるセクションが来る。ま、それ以前に書いてあることからして、マラベルさんが保守派であることは分かり切っていますが、結構、マジな感じで神とつながった実感を得た時の事なんかを語ったりしております。本書全般、聖書からの引用も多いですしね。 とまあ、本書の内容はこんな感じ。 ちなみに、マラベルさんは「トータル・ウーマン」のセミナーを各地で実施してきたのですが、アメフトの「マイアミ・ドルフィンズ」の本拠地近くで実施した際、ドルフィンズのメンバーの奥さんが結構沢山、セミナーに参加したそうで。それでマラベルさんのセミナー受けて、その奥さんたちがトータル・ウーマン、すなわち完璧な良妻に変身したせいか、次のシーズンでドルフィンズは全勝、スーパー・ボウルでも勝って全米ナンバー1になったとか。いやあ、マラベルさんの影響は、そんなところまで及んでいたのね・・・。 まあ、なかなか面白い本ではありました。っていうか、家内にも是非読ませたい! これこれ! ↓【中古】 トータル・ウーマン / 板橋 好枝 / 講談社 [文庫]【メール便送料無料】【あす楽対応】 ところでこの本、最初のうち訳がぎこちなくて、なんだか読みにくいんですわ。読み進めて行くと,段々気にならなくなるのですが。 で、読み始めた当初、「誰だよ、この下手っぴーな訳をしているのは・・・」とか思って訳者の名前を確認してビックリ。津田塾大の板橋好枝先生じゃあーりませんか。ひゃー、お見それしました〜。 しかし、板橋先生って・・・フェミニスト、なのかと思っていましたが、違ったんでしたっけ? フェミニストがこの本訳すってのも変な話ですが。 しかもこの本(私が読んだのは講談社文庫版)、巻末に曾野綾子氏と渡部昇一氏による推薦文が付いているんですけど、まずその人選がすごいよね。曾野綾子と渡部昇一。 特に渡部昇一氏の推薦文はすごいよ。「ウーマン・リブの風潮に断乎として目もくれず、『主婦こそ完全なる女性』と宣言したのがこの本である。女の幸せとは,夫があって子供があり、しかも夫を幸福にし、子どもを幸福にしている女性に見出されるという『古き良き時代』のテーゼをかざしてこの著者は揺ぐことがない。そういう女性が『トータル・ウーマン』というわけである。/結婚している女性も、これからしようとしている女性も、必ず一度は読むべき本である! そしてこの著者と意見を異にする時は『自分は結婚する資格があるのかどうか』と一度考えてみるとよい」なーんて書いてある。 板橋先生〜! これで良かったのでしょうか? 先生の女性観って「女たるもの、主婦になって幸せになれい!」でしたっけ? 意外〜!
August 18, 2018
閲覧総数 1116
-
13

アゼルバイジャンのvlogに驚愕
料理系YouTube を見るのが好きなせいか、そっち系のおススメ動画が上がってくるのですが、先日、そんなおススメ動画を見たところ、これがまた驚愕の内容でして。 その動画というのは「Country Life vlog」というもので、アゼルバイジャンのとある農家のお母さんが、何らかの料理を作る動画なのよ。まあ、百聞は一見に如かずなので、こちらを見てもらいたいのですが。これこれ! ↓アゼルバイジャンのカントリー・ライフ もうね、どの動画を見ても、画面が変わる度におもわず「え?」と声が出てしまう。もう、ほとんど目が離せない状態です。 第一、お母さんが作る料理の分量が半端ない。「これ、20人前でしょ?」というような分量の料理を、お母さん一人で、それも電動の道具を使わず、人力だけで黙々と作るわけ。例えば、洗面器というか、盥みたいにでかい器に、4リッターくらいクリームを入れ、それを人力で泡立ててホイップクリームを作るとか。50センチくらいはあろうかという、鯉みたいな魚を10匹くらい一度に調理するとか。直系80センチくらいの焼き型を4個も5個も使って巨大なキャロット・ケーキみたいなのを焼くとか。 しかも、料理を作る合間に挿入される映像が「え?」の連続で。たとえば「え? どうして野生のカラスが家の中に遊びに来て、平然と猫の隣で寝ているの?」とか。とにかく、目が点になる事ばっかりが起こるのよ。 まあ、しかし、ともかく、とんでもなく昔ながらで、とんでもなく豊かな暮らしがそこにある。驚愕につぐ驚愕よ。 で、さらに驚くのは、再生回数ね。普通に600万再生とか、そういう感じ。世界中の人が、このお母さんの一挙手一投足に釘付けになっているのだろうな、というのがわかる。 とにかく、すごい動画です。皆様も是非、ご覧いただいて、ワタクシと一緒に「え?」を連発してみてください。
March 17, 2024
閲覧総数 3780
-
14

頭の中に大きな絵を描く
このところ、明治維新以降の日本の自己啓発思想の流れについて、様々な本や論文を読破しております。私の専門はアメリカ文学だから、この辺の日本の歴史については無知以外の何物でもない。でも、アメリカの自己啓発思想の日本への伝播とそのプロセスを考えるためには、日本のことも知っておかなくてはならないのよ。 で、遅まきながら色々な資料を読んでいるんだけど、やっぱり知ることは面白いことであって、段々頭の中に、大きな絵ができてきた。 そう、ここで重要なのは、頭の中に大きな絵を描くことなのよね。大雑把に、大柄に、様々な事柄の流れを把握すること。 たとえば明治維新以前にも儒教的な自己啓発思想ってのはあって、勤勉といった美徳を重視する通俗道徳があった。 じゃあ、そういう通俗道徳と、明治維新以降の立身出世主義とはどう違うのか? 結局ね、職業がポイントなのね。 維新以前の通俗道徳だと、職業ということがあまり問題視されてない。なぜなら、それぞれが従事している職業は当たり前のことだったからね。士農工商制があるから、農民には農業という職業しかないし、商人には商業という職業しかない。だから、通俗道徳における勤勉とは、各々の仕事を一生懸命やれ、ということになる。 ところが維新後は、そうじゃないんだなあ。特に士族階級にとって、状況がガラリと変わる。 だって、維新によって、士族は職業を失うんだもん。無職化よ。そうなると、通俗道徳でいう、各々の仕事に精を出せと言われたところで、職が無くなっちゃったんだから、士族階級の連中にとってはまるで意味をなさない。 しかし、そうこうしているうちに学校なるものができ、学校を卒業すると官僚になれるという道ができた。この制度は、士族以外の人々にとって、特に豪農にとっては意味があったけれど、それ以上に士族にとって意味があったのよね。だって、無職の彼らには、この道を使うしかないんだから。 で、明治以降、この教育システムが出世の鍵となるんだけど・・・なにせ人はいっぱいいるのに、教育システムに乗れる人の数は限られている。このシステムに乗れなかった人が大量に出てくると。 そこで絶望して煩悶青年になっちゃう人が大勢出てきたんだけど、そこで出てくるのが、官僚にならなくてもいいじゃん?という発想。実業主義ですな。 そこでそれまで姦商とか言われて、すごく軽蔑されていた実業界の連中がクローズアップされてくると。で、そういう連中が、煩悶青年たちを実業界に引っ張る策略を始めるのだけど・・・ ま、そんな感じで、今、私の頭の中で明治時代の大きな絵が作られている真っ最中。この大きな絵が、段々、細密になって行った時、本が書けるという自信が出てくるわけだけど、まあ、そう先を急がず、今のところはできるだけ大きな絵を描くよう、頑張りましょうかね。
November 18, 2025
閲覧総数 733
-
15

興味津々! 白髪をなくす技
YouTube 見ていたら、なんだか面白そうなのを見つけました。白髪を根本的になくす技、というのですが。これこれ! ↓白髪をなくす簡単な技 なんかね、スパイスの「クローブ」と「ベイリーフ」の抽出物、それにインスタントコーヒーを混ぜて作った液体を髪と地肌にかけ、2時間ほどおいて洗い流すだけ、というのですが、本当にこれで白髪が無くなるんですかね?? まあ、クローブにしてもベイリーフにしても、それほど値段の張るものではないし、ましてやインスタントコーヒーなんて安いものですから、実際に作って試してみようかな、なんて。 染めるのではなく、根本的に白髪が無くなるというのは本当なのか? もし時間があったら、ゴールデンウィーク後半にでも、試してみようかな!
May 5, 2022
閲覧総数 2423
-
16

野崎訳 vs 村上訳 さて軍配はどちらに?!
サリンジャーの『ライ麦畑でつかまえて』には今でも白水社から2つの異なる日本語訳が出版されていて、一方は野崎孝訳で、これは1964年のもの(ただし1984年に廉価版の「Uブックス」が出た時に若干手を入れている)。で、もう一方は2003年に出た村上春樹訳。こちらにも廉価版が出たので、読者としては野崎訳を選ぶか、村上訳を選ぶかの二択が許されているわけ。 まあ、稀有な状況ですな。一つの小説について同じ出版社から2つの訳が出ていて、しかも同じ値段(950円)で買えるなんて、そんなこと普通ではありえない。 で、一つ言っておくと、私はもちろん、野崎孝訳世代なわけですよ。最初に『ライ麦畑』を読んだのは野崎訳だった。原書を読んだのはその後だから、とにかくこの作品への入り口が野崎訳だったわけ。で、2003年に鳴り物入りで村上春樹訳が出た時、一応、私もその訳書を買いましたが、読みはしなかった。野崎訳で読み、原書で読んでいるんだから、その必要が無かったんですな。 だけど、今回、サリンジャーについての連載をするにあたって、一応、両者の違いをチェックしておこうかなと。まあ、そんな風に思って村上訳を初めて読んでみたわけ。 で? どうだったかって? うーむ。言っちゃっていい? 言っちゃうよ。 野崎訳の圧勝だね。 ま、多分、これは世間の見方の逆を行っているんだと思います。私はいつもそうだからね。私の意見ってのは、大抵、世間の逆だから。世間は、多分、「野崎訳は古いしダサい。村上訳になってようやくこの小説もアップデートされた」と思っているのだろうと思います。 だけど、私から見ると、もうその差は歴然と言っていいくらい、野崎訳の方が『ライ麦畑』を日本語で再現していると思います。村上訳はね、あれはサリンジャーの小説じゃなくて、サリンジャーの小説の真似をした村上さんの小説みたいにしか見えない。村上節炸裂って感じだもの。それが気になって、気になって、もう読んでられない。 まずね、目に見えて嫌なのは、村上訳が妙にアメリカかぶれ(英語かぶれ?)なところ。 例えば小説冒頭のホールデンとスペンサー先生の会話のところで、村上訳はスペンサー先生のセリフに「あーむ」って入れるんだよね: 「そこに座りなさい、あーむ」とスペンサー先生は言った。ベッドに座れということだった。僕はそこに腰を下ろした。「流感の具合はいかがですか、先生?」 「あーむ、もっと良くなったら医者を呼ばんとな」とスペンサー先生は言った。 なに、この「あーむ」って。これ、普通訳すかね。むしろ野崎訳のように無視するか(最初の奴)、あるいは「いやどうも」(2番目の奴)などと訳した方がよほど自然だと思う。 この手のアメリカかぶれ・英語かぶれってのは村上訳には他にも沢山あって、「ジーザス・クライスト」とか、その手の間投詞をそのまま訳してあったりする。あと普通に「アントリーニ先生」と訳せばいいのに、「ミスタ・アントリーニ」と訳すとか。こういうのもすごく嫌。 あと、村上訳独自の言い回しってのがあって、例えば人の名前にスポットライトを当てる時に「くん」を付けるのよ。「フィービーくん」とか「ギャッツビーくん」とか。そういうのも気になるし、あるいは形容詞でいうと「うらぶれた」なんて言い方を何度も使われるとすごく違和感がある。 あと、最後の方でフィービーとホールデンが会話するシーンで、妹で10歳のフィービーが、高校生の兄ホールデンに「あなた」って呼びかけるんだよね。これもすごく不自然だと思う。私には妹は居ないけど、10歳の妹に「あなた」なんて呼びかけられたら、本当に嫌。ちなみに、野崎訳では普通に「兄さん」と訳されているんですけどね。 つまり、野崎訳がどこまでも「普通」に訳しているのに対し、村上訳はどこか色がついているというか、突出しちゃっているわけね。それが気になり出すと、すごく気になる。 あ、それから村上訳には日本語の言葉遣いにもおかしいところがある。167ページにキリストが12弟子を選んだことについて「でも彼(イエス)はきっとわりに見ずてんで選んだんだよ」と書いてあって、「見ずてん」のところにわざわざ傍点まで振ってあるんですわ。多分、「見ずてんで」ということばを「選り好みしないで」の意味で使ったのだろうと思うけれど、「みずてん」という言葉は漢字で書けば「不見転」と書いて、芸者が金次第でどんな相手とでも寝ることを言う言葉ですよ。元来、すごく下品な言葉。それをイエスに当てはめるなんて、日本語を知らないにもほどがあるんじゃないかい? だけど、上に述べたような細かいことだけじゃないのよ。実際には上に述べたようなことは瑣末なことで、問題はむしろそうじゃない部分の訳なのね。 訳として間違ってないんだけれども、野崎訳に比べ、村上訳は「切れ」が悪い。それは全体を通してそう。 例えばホールデンが母親から送られたスケート靴についてコメントするシーンを比べると・・・〈野崎訳〉 おふくろは見当違いのスケート靴を買ってよこしたんだけどさーー僕は競走用のスケートがほしかったのに、おふくろはホッケー用のを買ってよこしたんだーーしかし、それにしてもやっぱり悲しくなっちまった。僕はひとから贈物をもらうと、しまいには、そのためにたいてい悲しい思いをさせられることになる。〈村上訳〉 もっとも母が送ってくれたのは間違ったスケート靴だった。ほしかったのはレース用のシューズなのに、送ってきたのはホッケー用のやつだった。でもどっちにしても、けっこう哀しい気持ちになった。誰かに何かをプレゼントされると、ほぼ間違いなく最後には哀しい気持ちになっちゃうんだよね。 問題はね、最後の文の終わりね。野崎訳が「させられることになる」でピシッと切れるのに対し、村上訳は「なっちゃうんだよね」となっていて、なんだかずっこけちゃって、悲しみが伝わってこないわけ。野崎訳だと、この話をした時のホールデンの,一瞬、暗くうつむいた姿、目の奥の暗がりが見えるのに、村上訳だと「なっちゃうんだよね〜! ちゃんちゃん!」というイメージが出て来てしまって、どうにも締まらない。 要するにね、そういうことですよ。村上訳だと、あるセリフの言葉遣いと、それを言っている時のホールデンの姿とが、合っていないと(私には)思えるところが多過ぎる。本当に細かいところなんだけど、こういうのが積み重なって行って、私にとってのホールデンのイメージが、村上訳によって崩されてしまうんですな。だから、いちいち「ちげーよ」って言いたくなる。 野崎訳にはそういうところはないんだなあ。それから、もう一つ言わせてもらえれば、野崎訳より前の橋本福夫訳にもそういう不自然なところはない。この二人は学者だからね、訳すとなったら黒子に徹するところがある。 だけど村上さんは小説家だからねえ。やっぱり自分も書く人だから、筆が滑るんじゃないかなあ。 というわけで、異論・反論がたーくさんありそうですけれども、少なくとも私にとって『ライ麦畑』の訳は、やっぱり野崎訳にトドメを刺すと。そういうことですな。ライ麦畑でつかまえて/J.D.サリンジャー/野崎孝【1000円以上送料無料】キャッチャー・イン・ザ・ライ ペーパーバック・エディション/J.D.サリンジャー/村上春樹【1000円以上送料無料】
December 30, 2018
閲覧総数 23598
-
17

満州、そして二宮尊徳
日本の自己啓発本の研究していると、へえ~っと思うことがしばしばで、それはまあ、私があまりに日本史の知識がないからなんだけど、それにしても今更ながらなるほどと思わされることが多いですわ。 たとえば満州のこととか。 ワタクシは前々から、ある年代の人の中に「満州生まれです」という人が結構いる(たとえば池田満寿夫なんかもそうだけど)のはなぜなのか、どうして日本はあの時期、満州にそんなに執着したのか、不思議で仕方なかったんですけど、自己啓発本の研究をしていて、明治の後半、日本の就職事情が極端に悪化して、高等教育機関を出ても全然就職できないという時代があったことを知り、その絶望的な就職難を解決するための方策が満州進出だったんだ、ということが分かった。なるほど、そういうことだったのね! 今更納得! あと、二宮尊徳のことなんだけど、私は薪を背負って本を読んだ人、としてしか知らなかった。だけど、あの人は結局、荒廃農村の立て直し屋、凄腕のコストカッターだったのね。かつて日産を一時的に立て直したカルロス・ゴーンみたいな。 じゃあ、江戸時代、なんで地方の農村が荒廃したかっつーと、それは重税を課した幕府と、税金を支払えなくて困っている農村の弱みに付け込んだ高利貸による収奪だったと。で、もう食い詰めた村民は、村を捨てて行方をくらましたり、働くのをやめ、博打などに手を出すようになっちゃった。だから、農村の荒廃は、本当は社会システム上の欠陥が原因なんだけど、そこに二宮尊徳登場! 俺が来たからにはこの村を立て直す! だから俺の言うことは絶対聞け! とか言って、残っていた村民の生活態度の改善から取り組み、倹約・勤勉を強いて借金を数年のうちに返済させ、なんとか村の運営を正常に戻したと。 だから、社会システム上の欠陥を、個人個人の意識改革(=自己啓発!)によって乗り越えたのね。それがいいことだったのか、悪いことだったのかは措くとして。 二宮尊徳の剛腕コストカッターぶりを見ると、なるほど自己啓発思想というのは、大昔から社会悪には目をつぶり、個人の自己啓発を促すことだったのね、ということがよく分かる。 勉強になるわ~。 ということで、勉強すると、日々発見があるなと。そんなことを実感しているワタクシなのであります。
November 19, 2025
閲覧総数 632
-
18

研究室宛て郵便物、正しい書き方は?
学会の資料室なるものを引き受けている関係で、大学の私の研究室宛てで沢山の郵便物が届くのですが、その宛名の書き方について私には前から一つ疑問がありまして。 もちろん、学会のHPでは、会員の皆様に対し、本などを出版された場合は、その一部を資料室宛て、すなわち「○○大学 釈迦楽研究室宛て」でご恵送下さい、みたいなことを促しているわけですよ。それはそれでいい。 だけど、それをそのまま真に受けて、と言いますか、本当に「釈迦楽研究室」と郵便物の上に書いて送ってこられると、あれ? それでいいんだっけ? と思ってしまうわけ。受け取る側とすると、何だか呼び捨てにされたような気がしてね。 私だったらこういう場合、「○○研究室」とは書かず、「○○先生研究室」と書くんだなあ。 実際ね、私のところに届く郵便物の中にも、「釈迦楽先生研究室」と書かれているものもたまにあるんです。そういうのがあると、ちょっとホッとする。 だけど、ネットとかで調べても、こういう場合の正しい宛名の書き方って書いてないんですな。例えば「物理学研究室」とか、そういう例はあるんですけど、「研究室」の前に人名が来る場合の書き方が、ネット上でもなかなかない。 ひょっとすると、「人名呼び捨て+研究室」でいいのかも知れませんが、なんかね、ちょっとね、気になるんですわ。 「研究室」がついてなくて、ただ「田中宛て、ご送付ください」と書いてあった場合、「田中へ」とは書かないでしょ。「田中様」とか書くでしょ。だったら、やっぱり「○○先生研究室」と書いた方がいいんじゃないかなと。 ま、よく分かりません。どなたか、こういう時の礼儀について詳しい方、ご教示いただければ幸いです。
October 19, 2016
閲覧総数 13191
-
19

ロマンス小説史(第24回) 『ブリジット・ジョーンズの日記』を読む
前回のところで私は、「ロマンス小説とは、パターンの文学である」というようなことを言いました。ロマンス小説と呼ばれる文学ジャンルには、守るべきルールというか、構成原理が確固としてある。そういう非常に特殊な文学ジャンルだ、と述べたわけです。 しかし、そんなふうにルールがガチガチに決まっていたら、どのロマンス小説も基本的に同じようなストーリー展開のものばかりになってしまうのではないかと、そう思われる方がいるかも知れません。そうです。ロマンス小説というのは、マンネリの文学なのです。過去の作品の焼き直しがいくらでもできる、そういう特殊な文学ジャンル、それがロマンス小説の世界なのです。今日はその辺のことについて、面白い例を挙げて論じてみましょう。 もうかれこれ10年ほど前のことになりますが、ヘレン・フィールディングというイギリスの女性作家の書いた『ブリジット・ジョーンズの日記』(1996)という本が、日本でも評判になりました。出版社勤務の30代のOLがつけた日記の体裁を取りながら、この年代の女性の悩みやトキメキを赤裸々に綴るというような小説です。結婚適齢期を微妙に通り越してしまい、そのことも少しは気になるけれど、まだまだ一人の男に自分の人生を託す気もないし、もう少しキャリアを積みたいという野心もある。おいしいものを食べながら友達と騒ぐのも好きだが、体重の増加も気になる。煙草は止めた方がいいとは分かっているが、ついついまた吸ってしまう。そんな微妙な女心の綾が同年代の女性たちの共感を得たためか、イギリスでも日本でも大変なベストセラーになったことはまだ記憶に新しいところですね。ルネー・ゼルウィガーが主役に抜擢された映画版の方も評判になりました。 ところで、小説の方でも映画の方でもいいのですが、この『日記』を読んだり見たりした方は、この作品が純然たるロマンスであることはご存じでしょう。何しろこの作品、主人公たるブリジット・ジョーンズが、いかにしてマーク・ダーシーなる恋人を得るに到ったか、ということを描いたものなのですから。しかし、彼女は最初からダーシーに惹かれたわけではありません。それどころか無骨なところあるダーシーのことを、ブリジットは最初のうち、あまりよくは思っていなかった。むしろ彼女が最初に惹かれるのは、勤務先の上司ダニエル・クリーヴァーなんです。 しかし、クリーヴァーとの付き合いが深まっていくうちに、次第に彼の誠実さのメッキははがれ落ちていきます。彼には、ブリジットとは別に付き合っていた女性がいたんですね。でも、そうやって不誠実な男に振り回されたおかげで、もっと一途に彼女のことを見守ってくれていたダーシーという誠実な男性を、彼女は発見するわけ。ブリジットは、見かけでは分からない男の価値というものに気付き、今までどちらかと言うと胡散臭い目で見てきたダーシーを、自分の真の恋人として意識するようになるんですね。で、色々あった1年間を振り返るように、ブリジットは彼女の日記の最後のページに次のように記します。「やっと、男性と幸せになる秘訣がわかった」と。メデタシ、メデタシ・・・。 さて、で、この小説から私は何が言いたいのかと言いますと・・・この小説もまたまぎれもないマンネリの産物だ、ということなんです。実は『ブリジット・ジョーンズの日記』という作品、19世紀前半に書かれたイギリス文学の傑作であるジェイン・オースティンの『高慢と偏見』(1813)のパロディ、と言いますか、焼き直しなんですね。 では『ブリジット・ジョーンズの日記』が依って立つ『高慢と偏見』とはそもそもどういう小説か、と言うことですが、さすがに文学史に名を残す名作だけあって、その筋書きは複雑なものであり、簡単にはまとめられません。それでも敢えて主筋だけを身も蓋もなく要約するならば、自分には教育も才能も資産もあるし、別に結婚なんて目じゃないわ、と思っていた主人公エリザベス・ベネットが、すったもんだの末に、自分にふさわしい相手を見つけて結婚する、という話です。しかも彼女が選んだのは、第一印象からして「嫌な奴」だと思っていたフィッツウィリアム・ダーシー氏。つまり種々の偏見によって正しい判断力を失っていたエリザベスが、恋愛を通じて人間的に成長し、ダーシー氏の真価を見抜けるようになるまでを描いたロマンス、というわけ。 ところで、このように『ブリジット・ジョーンズの日記』と『高慢と偏見』を並べてみますと、当然、ヒロインが最終的に選ぶ男性の名前が共に「ダーシー」であることに気付きます。これは明らかに意図的なもので、そのことは著者のヘレン・フィールディングも認めている。が、二つの小説がパラレルであることについてはもっと明確な証拠があります。『ブリジット・ジョーンズの日記』が書かれる1年前の1995年、イギリス放送協会(BBC)が『高慢と偏見』をテレビドラマ化して放映してすごい視聴率をとったことがあるのですが、この時にダーシーを演じて一躍人気俳優となったコリン・ファースが、映画版の『ブリジット・ジョーンズの日記』でも、やはりダーシー役を務めているんですね。ですからBBCテレビの『高慢と偏見』を見、かつ映画版の『ブリジット・ジョーンズの日記』を見た人であれば誰でも、ああ、『日記』は『高慢と偏見』の現代版なんだな、ということが即座に分かるようになっていたんです。 もちろん、『ブリジット・ジョーンズの日記』と『高慢と偏見』の共通点は、ヒーローの名前や、演じた役者の一致ばかりではありません。たとえば、『ブリジット・ジョーンズの日記』でヒロインが最初からダーシーに好意を抱いていたわけではなく、むしろ「嫌な奴」というふうに思っていたというところも、『高慢と偏見』の筋書きと共通します。また『ブリジット・ジョーンズの日記』にはダニエル・クリーヴァーという、表面的にはダーシーよりもカッコいい優男がいて、ブリジットは最初こちらの方に惹かれるわけですけれど、この辺のプロットもその原型は『高慢と偏見』にあって、こちらの場合にはジョージ・ウィカムというハンサムな男が、ベネット家の娘たち目当ての優男として登場します。で、どちらの場合もそれらの優男たちはヒロインの気を惹くため、ダーシーに対するいわれのない中傷を彼女の耳に注ぎ込むんですね。ま、『ブリジット・ジョーンズの日記』の場合、原作にはそういう場面はないのですが、映画版ではクリーヴァーがダーシーの悪口をブリジットに聞かせる場面がちゃんとある。 で、こうしたいわれなき中傷のためもあって、当初ダーシーはヒロインの目には醜い「蛙」として、あるいは「野獣」として映るわけです。要するにクリーヴァーだのウィカムだのというのは、ヒロインを害する魔法使いの役どころなんですな。しかしどちらのヒロインも、魔法によって醜い姿に変えられていたダーシーの真価を見抜くことで、彼を本来の王子様の姿に戻すことになる。どちらの小説も、ほぼ同じ形でロマンス小説に必須の「蛙の王様・美女と野獣」の要素を押さえているんです。 またロマンス小説における必須の条件として、「シンデレラ」の要素、すなわち「結婚によるヒロインの身分の上昇」という要素が、二つの小説の中でどのように扱われているか、という点について見ていきますと、『高慢と偏見』の場合、ダーシー家というのは、ヒロインの属するベネット家よりも明らかに上の階級という設定です。ダーシーがエリザベスを娶るに当たって悩んだのはまさにここ。彼は「高慢」であったがゆえに、下賤な家から嫁をもらうのはちょっと嫌だな、と思っていたんです。ですから、ヒーローもまたエリザベスとの恋愛を通じて自らの高慢さから抜け出し、人間的に成長するというところがある。ま、それはともかく、結果から言えばこの小説のヒロインのエリザベスは、ダーシーとの結婚によって一つ上の階級にステップアップすることになります。そういう形で、この小説はロマンス小説の条件を満たしているわけですね。 で、それなら『ブリジット・ジョーンズの日記』の中で、「結婚によるヒロインの身分の上昇」という要素がどのように描かれているかというと、さすがに現代イギリスの話ですから、家柄がどうの、身分がどうのという話にはなりません。そこで著者のヘレン・フィールディングは、ダーシーを一種のマザコン男に描くことにしたんですな。彼には母親という理想の女性像がある。つまりこの小説では、「理想の女性像としての母親」という高いハードルが、ヒーローとヒロインの間の階級差を象徴しているのです。ダーシーの母親とは似ても似つかぬ、ということはつまり「身分の低い」ブリジットは、それでもダーシーに恋人として選ばれることで、ダーシー家の女に、つまり「身分の高い」女になれた、ということになり、そこに象徴的な意味での「身分の上昇」が見られるわけ。というと、何だかこじつけみたいですが、要するに『高慢と偏見』の中でダーシーが「家柄」に固執するように、『ブリジット・ジョーンズの日記』におけるダーシーもまた「母親(=つまり自分の出身)」に固執するわけですよ。で、どちらの小説でも、最終的には、ヒーローのダーシーも、この点に関してはヒロインに妥協する。そういうことです。 とまあ、そんな感じで、『ブリジット・ジョーンズの日記』がはっきりと『高慢と偏見』を踏まえて書かれており、少なくともメインプロットに関して言えばどちらの小説もほぼ同じストーリー展開を示すということがお分かりいただけたのではないかと思います。つまり、推理小説のような文学ジャンルとは異なって、ロマンス小説のジャンルでは、大昔に使われたトリックを意識的に繰り返しても何ら差し支えないどころか、むしろそれが受ける、ということです。そしてそのことこそ、私がこの文の冒頭で述べたこと、すなわち、「ロマンス小説という文学ジャンルはマンネリでいいんだ」ということの、一つの証になっているのではないかと思うのです。『ブリジット・ジョーンズの日記』は、ロマンス小説の系譜という点から見ると、『高慢と偏見』という文学史上の傑作を踏まえた「正統派」、なんですね。 ちなみに、その「ロマンス小説の正統派」という点から見ますと、『ブリジット・ジョーンズの日記』には、もう一つ、面白いところがあります。実はこの小説の著者であるヘレン・フィールディングは、ヘンリー・フィールディングの末裔なんです。ヘンリー・フィールディング(1707-1754)というのはイギリスの小説家で、かのロマンス小説の祖たる『パミラ』をパロディにした小説、『シャミラ』を著した作家として知られている。どうもフィールディング家というのは、歴史に名だたるロマンス小説をパロディにしたり、焼き直したりするのが好きな家系らしいんですな。ちなみに、ヘンリー・フィールディングの代表作のタイトルは『トム・ジョーンズ』です。ヘレン・フィールディングの小説のヒロインであるブリジットの苗字がなぜ「ジョーンズ」なのかは、これで何となく分かりますよね。 とまあ、以上のようなことから考えてましても、ロマンス小説というのが偉大なるマンネリの産物であり、それゆえに、現代の作品が過去の作品と密接な関係を持つことが頻繁に行なわれている、ということが分かるのではないかと思います。 で、だからこそロマンス小説というのは、個々の作品を論じるより、ロマンス小説全体として捉え、相互の作品の中にあるその密接な関係性を論じていった方が面白いのだ、と、私は思うのですよ。私がロマンス小説史を書こうと思っている理由はそこにあります。 なーんて、ちょっと大風呂敷を広げてしまいましたが、『高慢と偏見』で19世紀初頭を、前回の『ジェイン・エア』で19世紀半ばを見てきましたので、次回は19世紀末から20世紀前半あたりにかけてのロマンス小説の方向性について考えていきたいと思います。乞うご期待です。 「お気楽日記」はまた夜更新しますね!
October 3, 2005
閲覧総数 756
-
20

多井学著『大学教授こそこそ日記』を読む
多井学さんが書かれた『大学教授こそこそ日記』なる本を読了しましたので、ちょいと心覚えを。 これ、『交通誘導員ヨレヨレ日記』をはじめとする三五館シンシャから出ている一連のシリーズの一環として出ているもので、色々な職業の人の実体験から、外部からはなかなか見えないその職業の裏側というか、苦労話を暴露的に書くという本。私も前に『出版翻訳家なんてなるんじゃなかった日記』というのを読んだことがあって、それはそれで結構面白かった。で、今回の『大学教授こそこそ日記』ですが、これは先輩同僚のアニキことK教授からおススメされ、はい、と手渡されたもの。アニキに手渡されちゃったら読むしかないんでね。これこれ! ↓大学教授こそこそ日記 (日記シリーズ) [ 多井 学 ] さて、著者の多井学さんですが、これはもちろん身分バレを隠すためのペンネームであって、本名は別。上智大を出て、アメリカとカナダの大学・大学院を出た国際関係論の先生で、長野県のS短大に就職したのを始め、そこから国立の徳島大に移籍、さらにそこから関西学院大学に移籍して今日に至る、という経歴。ここまでわかれば、ちょっと調べれば本名はすぐに分かります。本もそれなりに出されている人ですね。専門書もあるけど、「大学教授になる方法」的な本もある。どの道、この手の本が書きたい人なんですな。 で、3つの大学、それも弱小私立短大、地方国立大、メジャー私立4大と、それぞれ異なるタイプの大学に勤めたことがあるというのがいわば強みで、それぞれの大学に勤めていた時期に経験したことを、面白おかしく書いている。それを読むと、それぞれの大学に特徴というか、くせがあって、そういう癖のある職場に適応しながら生きる大学教員の生態がよく分かります。 特に、私自身が国立大学に勤めているので、多井さんが徳島大学に勤めていた時の話はすごくよく分かる。となると、弱小私立大学に勤めている人、メジャー私立大学に勤めている人、それぞれ、この本を読むと「ある、ある!」となることでしょう。同業の人間からすれば「ある、ある!」だし、大学というところに関係がない人が読めば、「へえ、大学教授って、そういう職業なんだ」というのが分かるかも知れない。 ま、そんな感じで、「ある、ある!」と思いながら、軽くさらっと読んじゃった。 もっとも、最後のところで、多井さんが奥さんを亡くした経緯と、その後の辛い生活のことがちらっと書かれていて、愛妻家が妻を亡くすとこうなるんだ、というところがあり、そこはちょっと可哀想。私も愛妻家の一人として、奥さんには自分より長生きしてもらわないといかんなと、あらためて思った次第。 ということで、読んで特にためになるという類の本ではないけれど、大学教授の方、あるいは大学の先生になりたいなと思っている方には面白い本かもしれません。その程度のものとして、おすすめ、と言っておきましょうかね。大学教授こそこそ日記 当年62歳、学生諸君、そろそろ私語はやめてください/多井学【1000円以上送料無料】
January 19, 2024
閲覧総数 4727
-
21

C・H・ブルックス&エミール・クーエ著『自己暗示』を読む
金曜日に父の本の入稿を済ませたし、土曜は土曜で、9月末締め切りの書評を書きあげて送ってしまった(私にしてはすごくね?!)し、昨日の日曜日は久しぶりにのんびり自分の仕事ができる一日となりました。 ってなわけで、エミール・クーエの『暗示で心と体を癒しなさい!』という本と、C・H・ブルックス&エミール・クーエ著『自己暗示』という本の2冊を読了~。でも後から分かったのですが、『暗示で心と体を癒しなさい!』は、『自己暗示』の後半部分と同じものでした。だから、要するに『自己暗示』一冊読めばいいわけ。 ちなみに、『自己暗示』という本は、法政大学出版局から出ているからね。自己啓発本というと、ちょっとインチキ臭いような(失礼!)出版社から出ていることが往々にしてあるんですけど、これはもうあの法政大学出版局だから、由緒正しいっていう意味ではめちゃくちゃ由緒正しいよ! さて、この本の主役を演じるエミール・クーエという人は、1857年生まれの1926年没といった時代の人。言ってみれば、私より100年ちょい前に生まれた人というくらいのもんですな。で、職業的に言うと、もともとは薬局を経営していた薬剤師。で、後に催眠療法に興味を持ち、アメリカの通信教育でしばし学んだ後、自分の薬局に診療所を付設して治療を始めたところ、病人がどんどん良くなるものだから評判が高くなって、さらにフランスの心理学者シャルル・ボードゥアン博士とか、イギリスの名医モニア・ウィリアムズ博士なんかが持ち上げたおかげで、ヨーロッパやイギリスやアメリカにまで名が知られるようになったという経歴の持ち主。 で、彼の治療法は、「自己暗示法」って奴。 もともとは催眠療法をやっていて、患者に催眠術をかけてから治療していたのだけれども、患者の中には催眠術にかけられること自体にストレスや恐怖を感じてしまって、治療にならないケースが結構あったんですな。で、催眠術なしでやってみたら、むしろその方が治療効果も高まることが分かり、最終的には催眠術はやめて、覚醒している患者に対して、暗示(=自己暗示)をかける方法に切り替えたと。 で、ならばその「自己暗示療法」っていうのはどういうものかと申しますと、理論的にはですね、人間には意識と無意識があると。で、意識よりもはるかに広大な領域を無意識が司っている。例えば体に関することはほとんどすべて無意識がコントロールしているので、何かを食べて、それを消化する、なんてことを一つ取ってみても、それは人間が意識的にやっていることではなく、無意識にやっているわけですな。意志の力で胃液を出したりしているわけではないわけだし。 で、意識の層と無意識の層は互いに連携を取り合い、意識的に考えたことなどはいったん無意識の方に送られて、そこで検討され、再び意識の層に返答を返してくる。 で、この両者がうまく連携していると、人間ってのは健やかにいられるのですけれども、この両者に齟齬が生じると、それは何らかの形でアレルギー反応を起こす。例えばストレスだったり、体の不調だったりを引き起こすと。 ま、これが人間の仕組みだ、というのが大前提ね。 じゃ、一つ例を出しましょう。舞台はゴルフの大きなトーナメント。次のホールでバーディ取ればあなたが優勝というシーン。だけど、難しいホールで、そこここにバンカーの罠がある。さあ、あなたが打つ番でーす。 意識の層、すなわち「意志」は、「よーし、何がなんでもグリーンに乗せたる」と思い、「そのために死ぬ思いで練習してきたんじゃないか! 絶対成功するぞ!」と思う。ところが、無意識の層では、「絶対にバンカーにつかまって、優勝どころか大恥だ。お前はいつだって大舞台で失敗ばかりしていたじゃないか。今度も絶対失敗するぞ。ボールは見事バンカーのど真ん中に飛んでいくに決まっている」という結論を出す。 で、クーエ理論の第一テーゼは「意志と想像力が喧嘩した場合、必ず想像力が勝つ」ですから、この場合、無意識の層が勝ちます。で、体を司る全神経が一致協力して彼の身体とクラブを操り、その結果、ボールは絶妙の軌道を描いて、想像していた通り、バンカーのど真ん中に飛んでいく。それは見事に。 同じことは、逆の方向でも実現します。例えば、嵐に翻弄される船の中で、屈強の船乗りに向かって「顔色が悪いですね。船酔いじゃないですか?」って言っても、船乗りは全然影響を受けません。それはその船乗りの無意識層が「俺は船に酔わない」という答えを用意しているからで、そこへ意識的に働きかけても無駄なわけ。ところが、同じ船にのって青い顔をしている乗客に同じことを言うと、言われたことと無意識層の理解が同じなので、とたんに船酔いしてしまう。 だからね、意識層と無意識層が一致しなければ、意識的にしようとしたことは絶対に実現しないし、逆に両者が一致しているときには、すべてが実現しちゃうの。 で、病気とか体の不調とか、そういうのも全部これ式なわけ。たとえば「吃音」にしても、意志の力でなんとか吃音を止めようとしても、無意識の層で「絶対どもるぞ」と判断している限り、意志とか努力とかはまったく無力。それどころか、意志と努力で「止めよう」とすること自体が無意識層を活性化させ、「ほら、やっぱりダメだ! ますますダメだ!」となるので、さらに止まらなくなると。 じゃあ、この堂々巡りをどうやって止めればいいかというと、そこで登場するのが「自己暗示」でーす。 意志の力で無意識層を押さえつけるのは無理なので、無意識層が一番不活発な時、すなわち心身ともにリラックスしているとか、一番いいのは、睡眠前と睡眠直後のぼんやりとした時間。この、いわば無意識層がノーガードな状態の時に、「大丈夫、すべてはうまく行くから」と自己暗示をかける。すると、抵抗なく無意識層に入り込んだこの言葉によって無意識層に変化が起こり、次の意識層からの問いかけに肯定的な返事を出す。「ボールはグリーンにオンできるだろうか→きっとできるよ」、「吃音は止まるだろうか→きっと止まるよ」と。これによって、意識層と無意識層が協働して働きだすので、結果、望んだ通りにことが進むようになると。 えーーー、ほんとーーーー?! ほんとです。 例えばさ、「明日の朝は6時15分に絶対起きなきゃ」と思って寝るとするじゃん? すると、6時14分にハッと目が覚めて、目覚まし時計が鳴る前にそれをオフにする、なんてこと、経験あるでしょ? 眠っているはずなのに、どうしてそんな芸当ができるの? 無意識層がコントロールしているからでーす! だから無意識層の働きって、すごいのよ。 ちなみに、我々が意識的に「自己暗示」をかけなくとも、我々が社会生活を営んでいる限り、常に「暗示」にさらされています。新聞、本、人から聞いた話、ラジオ、テレビ、インターネット、そういったものが常に我々の無意識層にメッセージを送っており、また無意識層は我々が気づかないうちにそのメッセージを受け取って、次の判断の材料にしている。 人間が、なかなか思い通りに生きられないのは、知らぬ間に無意識の中にたまった様々な暗示によって、無意識層の返答の仕方にバイアスがかかっていて、それで意識層から問い合わせがあったときに、それに従って否定的な返事を出すからなんですな。だから、そういう方向性のない「暗示」を、建設的な「自己暗示」にすり替えれば、物事はうまく行くと。 これがクーエの理論なのでありまーす。 で、この理論を応用する形で、クーエの診療所ではジャンジャン人を治しちゃうの。 と言っても、誤解無きように言っておくと、クーエは別に医学的な治療を否定しているわけではありません。なにせ彼は薬剤師だからね。 だけど、医学的治療にもクーエ理論というのは応用できるのであって、例えば医者が患者に薬を出す時、黙って渡した場合と、「この薬は効くんだよ。実によく効く。あなたと同じ病気の人で、この薬で救われた人を何人も見てきたよ」って言いながら渡した場合、薬の効き方が違うと。プラシーボ効果に、さらに本物の薬の薬効が加わるわけだから、そりゃあ、効くでしょうね。 さて、クーエは、薬剤師であり、治療師だから、主に病気を治す方法としてこの理論を活用したので、ついつい「自己暗示」というのは「治療法」なんだと思われがちですけど、実は必ずしもそうではない。 つまり、体の不調があるから、クーエ理論で治す、というのではなく、そもそもクーエ理論を使って無意識層を活用することで、人間が本来の能力を最大限使って、十全に生きることが重要なんですな。その意味で、クーエ理論とは治療法ではなく、人生修養と考えた方がいい。 で、その観点からクーエは我々に一つの万能薬を処方してくれています。 それは何かと言いますと、毎日、夜寝る前など無意識層が油断している時を狙って、「私は毎日あらゆる面でますます良くなっている」と20回つぶやくというもの。英語ですと、「Day by day, in every way, I'm getting better and better.」ですな。 ちなみに、この魔法の呪文は、あまりにも漠然としているように見えますが、このままがいいみたいです。というのは、無意識層というのは万能なので、この言葉をつぶやいた人にとって何を改善するのが一番いいのか、ちゃんとわかっているから。だから、変に特殊なものに変えて「私は毎日頭が良くなっている」とか、「健康が良くなっている」とか「性格が良くなっている」といったようにしない方がいいみたい。あくまでも漠然と「あらゆる面でますます・・・」と言うべきなんだそうな。 とにかく、この魔法の呪文を毎日つぶやくことで、あなたの人生は良い方に激変する、かも。 ところで、このクーエの「自己暗示」が、現代の自己啓発にすごく大きな影響を与えているというのは、すぐわかるよね! まず、努力しちゃいけない、という側面。寝ながら魔法の呪文を唱えればすべてうまく行く、という即効的かつ安易な方法論。クーエが想定した無意識層を「宇宙」と読み替えるだけで、「宇宙に頼んだことはすべて目の前に現れる」的な引き寄せ理論になるし。 だから、引き寄せの法則をくだらない、偽物だ、というのは簡単なのだけど、その裏に例えばクーエの理論を置いてみると、そう簡単には否定できないのではないかと。 実際、「意志の力で努力したことはほとんど成功しない」というのは、かなりな程度、普遍的な事実なわけで。 だからクーエが「努力するな」と言うとき、それは努力という美徳を否定しているわけではなく、「それをやると、意識層と無意識層が喧嘩するから、まずは『これは簡単なことで、自分にはそれをやり遂げる能力があるし、やっているうちに楽しくなってくる』という自己暗示をかけなさい」ということなわけよ。 で、自己啓発も、結局、同じことを言っているわけ。そこを理解できるかどうかで、自己啓発の世界が分かるか分からないかが決まってくると思うんだなあ。 ということで、この本、本気で自己啓発のなんたるかを理解するためには、非常に面白い本だと思います。教授のおすすめ! と言っておきましょう。自己暗示新装版 [ C.H.ブルックス ]価格:2052円(税込、送料無料)
June 13, 2016
閲覧総数 1840
-
22

リチャード・バック著『イリュージョン』を読む
昨日読んだ『セラピー文化の社会学』の101-2ページに「歴史的な規範を無効化し、自己の内側にすべての源泉があると考え、自己は選択により何にでもなれるのだとする発想は、アメリカ文化に流れるひとつの世界観でもあり、リチャード・バックの小説『イリュージョン』(Bach 1977)などにも典型的に表されている。」とあって、リチャード・バックの小説に言及されている箇所があるのですが、実は前にもこの小説のことを自己啓発本として紹介している本がありまして、興味はあったんですわ。 ということで、とりあえず読んでみたと。 まあ、ごくごく短い小説・・・というか、中編くらいですかね、長さ的に。 主人公はリチャードという、本作の著者リチャード・バックと同じ名前の男でして、古い複葉機フリートで旅をしながら、ところどころで町に降りて、10分間3ドルの値段を取って人を乗せて飛ぶという商売(?)をしているんですな。 で、そんなことをしている時に、たまたま「トラベル・エア4000」という機種の複葉機が原っぱに止まっているのを見かけるわけ。で、リチャードはちょっと気になって着陸してみたところ、そのトラベル・エア4000の持ち主はドン(=ドナルド)・シモダという奴で、どうもリチャードと同様、ところどころで人を乗せてお金を取る商売をしているらしい。要するに、同業者だったんですな。 だけど、それだけではなかった。実は、ドンは同業者であると同時に、救世主だったと。キリストみたいな感じの。だから、トラベル・エア4000は、どんなに飛んでも虫の死骸などはつかず、新品のままだし、そもそも燃料も要らないんですな。ドンがそう願いさえすれば、自動的に満タンになるので。それに、複葉機なのに、ほとんどヘリコプターみたいにふわっと着陸することもできる。なにせドンは救世主なので、どんな奇跡でもおこせるわけ。 はい、この時点で、この前提を受け入れられる人とそうでない人が分かれまーす。 とりあえず受け入れたということにして、話を先に進めましょう。 でまあ、救世主ってのは、どうも資格試験みたいなものがあるそうで、ドンもちゃんと専用の「入門書」を勉強して救世主になったんですな。で、そんな感じのふわっとした話の流れから、リチャードはドンの弟子ということになり、その入門書も譲り受けて、ちょっとずつ救世主になる勉強を始めるわけ。 ま、勉強といってもそんな熱心なものではなく、ドンと一緒に旅をしながら、ちょっとずつ彼からノウハウというか、救世主の心得的なものを学んでいったり、例の入門書に書かれていることを読んで、あれこれ納得していくと。 で、ある時、ちょっとこう、視野の狭いというか、堅苦しい町に滞在していた時に、ある話の流れからドンがラジオのインタビューを受けることになり、そこで「なんでもやりたいことをやればいい」みたいなことを言っちゃうんですな。ところがこれが町の住民の反感を買う。みんなやりたくないことをやって、一生懸命に生きているのに、何を不埒なことを、というわけ。 で、ちょうどイエス様のように、同胞から非難の雨あられを受けた後、町を後にしようとするのですが、飛行機に乗り込んだところで銃で撃たれてドンは敢え無く死んでしまう。もちろん、死なないようにすることもできたのですが、ドンはわざと撃たれて死んじゃうんですな。 で、ここまで来れば当然、予想されることですが、ドンは死んだあと、リチャードの元をまた訪れます。そりゃ救世主ですから、3日もすれば復活するわけね。で、リチャードに後を託して去ると。で、託されたリチャードも、大分、救世主パワーがついてきたらしく、もう、飛行機で飛んでも虫の死骸ひとつつかないくらいには上達しましたとさ、と。 で、本書全体を通してドンが伝えたかったことは、この世はすべてイリュージョンであって、自分のやりたいことをやりたいようにやれば、すべてうまく行くようにできていると。空を飛びたいと思えば、飛行機に乗らなくても、人間の形そのままで飛ぶこともできますよと。だって世界はイリュージョンなんだから、物理の法則なんか軽々と超えられるので。 ・・・というね。そういう本。 ま、『かもめのジョナサン』も、ジョナサンがかもめの限界を超える話であるわけで、リチャード・バックの言いたいことってのは、『イリュージョン』も同じなんですな。好きなことをやって、フローを得れば、何でもできるよと。つまり引き寄せの法則と、チクセントミハイ的なフロー概念を足して2で割ったような哲学。 ちなみに、私が読んだ集英社文庫版(村上龍訳・・・村上龍??)は1981年第1刷で、1997年には第33刷ですから、16年で32回刷り増している。年2回のペースで増刷していると。まあ、売れているわけですなあ。 まあ、文学的に言ってまったく取るところのないこの本が、これだけ売れているってんだから、すごいよね。逆に言うと、ダメダメな作家は、自作に自己啓発思想をぶち込めばいいんだ。そうすれば売れる本にはなるんだから。 ということで、期せずしてこのタイミングで読んでしまいましたが、まあ、仕事上、いつかは読まなくてはならなかったのでしょうから、よかったかな。これこれ! ↓『中古』イリュージョン—悩める救世主の不思議な体験 (集英社文庫)
August 12, 2020
閲覧総数 683
-
23

ジャズ喫茶「グッドベイト」マスター・神谷年幸さんの生涯
先日、地元ケーブルテレビ「キャッチ」の方からお電話をいただきまして。何かと思ったら、知立市にある有名なジャズ喫茶「グッドベイト」のマスター、神谷年幸さんのドキュメンタリーを制作したので、視聴して欲しいとのこと。 実は「アメリカ文化史」の授業でジャズの歴史を講じているワタクシ、毎年最後の授業のトピックとして「ジャズ喫茶」の話題を取り上げ、宿題として「グッドベイト」でコーヒーを飲んでくることを課していたんですわ。そんなこともあって、神谷年幸さんとも知り合いであったことから、そういう話が飛び込んできたと。 で、送っていただいた番組のDVDを視聴したのですが、これがねえ、なかなかよく出来たドキュメンタリーだったのよ。 番組では、神谷さんがGISという特殊なガンを患い、最後の闘病生活から亡くなるまでを描いているのですが、体調が悪いはずの神谷さんも、ジャズの話になると病気のことを忘れたように元気になるので、重病人を扱ったドキュメンタリーのようには全然見えない。 むしろ人生の最後の最後までこよなくジャズを愛し尽くし、そして仲良しの奥様と二人三脚でジャズ喫茶を経営してきた、その一途で底抜けに楽しい人生の航跡が描かれているわけ。 私は、神谷さんが亡くなるほんの2週間前にグッドベイトを訪れていたのですが、ドキュメンタリーもそのあたりのことを映像化しているので、結構、個人的にも感慨がありました。 それにしても、ただ純粋にジャズが好きだというだけで、別に取り立てて裕福でもない神谷さんが、あれほどのジャズアルバムのコレクションを作り上げるんだから、人の執念ってのはスゴイものだなと。無駄なことにお金を使わず、ただ好きなジャズだけに専心すると、日本でも有数のコレクターになれるし、またそのことを通じて色々な人と出会うことができるわけだからね・・・。 いま、そういう形で文学をやっている人間がどれほどいるか。お仕事としてではなく、ただ好きで好きでっていうだけで文学研究している人がどれほどいるか。自分のことも含め、なかなか神谷さんに叶う人って、いないんじゃないかな。 でまた、神谷さんと奥様の関係が、とてもいいんだよね。理解のある奥様で。またその奥様が大好きな神谷さんで。 というわけで、この番組、非常に優れた人間ドキュメンタリーになっていたのでした。今年も後期にジャズの授業をやりますが、その際、どこかでこの番組を学生に見せようかな。これこれ! ↓ジャズ喫茶「グッドベイト」マスター、神谷年幸:自分らしい人生の終い方
April 24, 2022
閲覧総数 1750
-
24

悲報! らくだ書店東郷店、閉店・・・
ひゃー、押坂忍さんも亡くなられたか・・・。また一つ、昭和の灯が消えた・・・。 いや、それも悲報ですけど、今日はもう一つ、悲報が・・・。 愛知県で何店舗が経営されている「らくだ書店」の東郷店が6月30日をもって閉店しておりました。 いやあ、結構大きい書店で、自宅と大学の丁度中間点にあるもので、時々寄って本や雑誌を買ったりしていたんですわ。それが、ついに・・・。 リアル書店が次々と姿を消していくとは聞いておりましたが、身近な本屋さんにそれが起こると、さすがに堪えます。 昔は本屋なんて、そうそうつぶれるもんでもなかったですけどねえ。売れない本は、出版社に返してしまえばいいんだから。でも今はそうも言っていられないくらい、本が売れないんですかねえ・・・。 愛知県で言えば、「ちくさ正文館」という名店も昨年くらいにつぶれたし、もうだめだな。本はもう、ビジネスにはならんのだな。 本を読むことを商売にしている私なんぞからすれば、なんだか自分の職業も風前の灯なのかな、なんて思ったりして。 それにしても、馴染みの本屋がつぶれるというのは、悲しいもんですなあ。
July 8, 2024
閲覧総数 3159
-
25

『DUO 3.0』は英単語集の傑作だ!
このところ母の具合が悪く、やれめまいがする、心臓の動悸が激しい、首筋が攣るようだ、血圧が高い、などと怖いことを言うのに加え、昨日は一日ほとんどものを食べていないので、これは何か問題があるのではないか、脳梗塞とかクモ膜下出血の前兆なのではないかと、私としては超不安。 で、今日は朝から市の「休日診療所」ってところに連れて行ってみたのですが、ここは風邪とか腹痛とか、その程度の診療しかしておらず、脳の検査など出来ませんと断られ、別な大病院にもちらっと行ってみたものの、救急医療班は手がいっぱいで、自分で歩ける人なんか見ている余裕ありませんと門前払い。 ま、そりゃそうなんだろうけど、もしこれで母がクモ膜下出血か何かで倒れて不帰の人にでもなったら、あーた、わたしゃ恨むよ、あんたらのことを。 さてさて、そんな調子ですから、あまり気合いを入れた勉強には身が入らず、昨日は一日、英語の勉強をしておりました。 使ったのは『DUO 3.0』という割と有名な、そして評判のいい英単語集なんですけど、これね、実際に使ってみたら、確かにすごくいいものだったんです。大学受験の時以来、英単語集で単語を覚えていて「面白い!」と思ったことなんか今まで一度もないですけど、この本は面白いの。そう、英単語集なのに、すっごく面白いんです。 この単語集には特長があって、覚えるべき英単語(1600語)と英熟語(1000語)を、重複なしで(この重複なしで、というところがまずスゴい)560個の例文として提示してあり、これらの例文を例文ごと覚えることで、トータル2600もの英単語・英熟語をマスターできると。 しかし、まあ、例文を使って単語や熟語を覚えさせるというだけであれば、類書が山とあるでしょう。 だけど、その先がすごいのよ。 今、560個の例文が挙げられていると言いましたが、この560個の例文に、なんとなくストーリーがあるんです。前の例文と、その次の例文の間に、なんとなくストーリーがあるの。だから、まったく関連性のない例文を560個覚えるのではなく、なんとなく関連性のある、つまりストーリーのある例文を覚えるので、例文にバックグラウンドが生じるわけね。だから、まったく関連性のない例文を覚えるのと違って、頭の中に入り易いんですわ。 例えば、「Whenever I go abroad, I suffer from jet lag and diarrhea.」(外国へ行くと、いつも時差ボケと下痢に悩まされる)という例文の後に、「I feel sort of dizzy and I feel like throwing up.」(めまいがするし、吐き気がする)という例文がくる。そしてその次の例文は「Take some aspirin. It will cure you of your headache in no time.」(アスピリンを飲みなさい、そうすれば頭痛なんてすぐ治まるよ)という例文が来て、さらに次の例文は「I'm afraid I'm coming down with something.」(なんか病気をうつされたようだ)ってな例文が来て、このあたりはずっと病気関係の例文が続くわけですな。 しかし,その次の例文は「Some of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.」(この飲み物に含まれる成分には有害なものがある,特に妊娠中の人にとっては)という例文が来て、さらにその次には「Good nutrition is vital for an infant's growth.」(十分な栄養摂取は幼児の発育にとって極めて重要だ)とあるので、話題が「病気」のことから「妊娠・乳幼児」系の方面に少しズレたことが分かります。 こんな感じで、例文間に何らかの関連があるのだけど、それが少しずつズレて行きながら、どんどん違う話題に移って行くという。だから覚え易いと同時に、飽きないんですな。 で、そういう飽きない例文を辿りながら重要単語・重要熟語をさらっていくことが出来るわけですが、特にこの本の最後の方になると、人間関係の話題になっていて、色々な人名が登場してくるんです。 で、そういう人名の登場してくる例文を読んでいると、個々の人名(っていうか、その名前を持った人物)には、どうやら特定のキャラクターが備わっているんだというのが分かってくるわけ。 例えばボブ。 ボブの出てくる例文を見ると、「Bob felt embarrassed when he was teased in front of some girls.」(女の子の前でからかわれて,ボブが恥ずかしかった)とあり,その次の例文では「His ambiguous reply made her all the more irritated.」(彼の曖昧な返事は、なおさら彼女をいらだたせた)とあって、さらに「Bob is very timid and blushes when chatting with girls. 」(ボブは臆病で、女の子と話をすると赤面してしまう)なんてありますから、あれ、ひょっとしてボブ君は奥手で、優柔不断な「もてない君」なのかなと想像がつく。 で、ちょっと後の方でボブが再登場したと思ったら、「Bob derives pleasure from observing insects.」(ボブは昆虫の観察に楽しみを見いだす)とあって、あらあら、とうとうボブは女の子と付き合うのを諦めて、虫の方に行っちゃったよ・・・と。 そうかと思うと、「After making sure she was sound asleep, he crept out of the room and set off.」(彼女がぐっすり眠っているのを確かめた後、彼は部屋を抜け出し、外へ出た)なんていう例文があり、その後に「Between you and me, Lisa, I came across Nick passionately embracing a woman.」(リサ,ここだけの話だけど、ニックが女の人と熱い抱擁を交わしているのを見ちゃったんだけど)、なんて例文が来て、どうやらリサとニックの夫婦には、何か危機的な状況が生じている様子。さらにそのちょっと後には「Once in a while, I think of divorcing him.」(時々、離婚のことを考える)なんて例文が来ますから、二人の決別はかなり決定的な様子。 で、そうこうしているうちに、本書でも指折りの性悪女、ジェニファーが登場してくる。 「Jennifer deceived me! / You should have known better than to trust her.」(ジェニファーに裏切られた!/彼女を信じたあなたが馬鹿なのよ)という例文で登場するジェニファーですが、その後「Jennifer left me for another guy.」(ジェニファーが俺をふって他の男のところに行きやがった)とか、「"Living here all by myself is torture!" he sobbed.」(ここで自分一人で暮らして行くなんて、拷問だ、と彼はすすり泣いた)などの例文が来ますから、いかにこの女が男を泣かせて来たかが分かります。しかしジェニファーの腹黒さってのは底知らずで、「Speaking of Jennifer, she got engaged to a businessman. / I'm at a loss for words! I hope she won't break it off.」(ジェニファーと言えば、彼女、実業家と婚約したんだよ/あきれてものが言えないわ。破談にならなきゃいいけど)という例文の後、「These days, the motives for marriage are not necessarily pure. Take Jennifer for example.」(近頃では、結婚の動機は必ずしも純粋なものとは限らない。例えばジェニファーを見てご覧よ)という例文が来る。もうジェニファー、どこまで腹黒いんだっ!! とまあ、そんな感じで色々な人物間の恋愛事情が例文の中から浮かび上がってくるのですが、それを踏まえた上で、この本の最後の最後にくる3つの例文がまたいいのよ。 「Go easy on Bob. You know, he's been going through a rough period recently.」(ボブには優しくしてあげて。だってほら、彼最近、辛いことがあったでしょう)と来て,その次に「By the way, do you have the time? / Let's see. . .It's a quarter to eight.」(ところで、今何時?/えーと、8時15分前)と来て、そして本書一番最後の例文が「Let's call it a day, Bob. I'm starved. / Yep. I'll buy you dinner.」(もう今日はこの辺にしましょうよ,ボブ /そうだね。今日は僕が夕食をおごるよ)となっている。 つまり、ニックと離婚したリサと、ジェニファーみたいな性悪女に翻弄され続けた奥手のボブが、どうもちょっといい感じになって来たんじゃないの? というところで本書が終わるわけ。もちろん、明確には書いてないですよ。だけど、何となくそういうことなんじゃないの? というほのめかしで終わる。 この、よくわからないけど、なんとなくそうなんじゃないの? という、ゆるーいほのめかしが最高に良いのよ!! 最後の方なんて、もう、面白過ぎて、あたかも上手に書かれた小説を読むかのように英単語集を読んでしまったという。一言で言って、堪能しました。先にも言いましたが、英単語集・英熟語集を読んでいて、こういう面白さを味わう経験って、いまだかつてなかったわ・・・。 で、肝心の英語のお勉強ですが、本書で扱われる単語・熟語のレベルから言って、大人の勉強に十分耐えます。大学生はもちろん、英語のスキルアップを狙っている社会人に最適。 というわけで、世評が高いのも納得のこの一冊、教授の熱烈おすすめ!です。DUO 3.0 [ 鈴木陽一 ]
May 5, 2018
閲覧総数 1430
-
26

大学授業「半期15回」の愚
今日は本来なら研究日で自宅研修なんですが、所属大学では今日は「月曜日スケジュール」で動くので、仕方なく月曜日の授業をやってきました。 ま、月曜日は連休の関係で潰れることが多く、「半期15回」の授業をしなければならない現在の大学事情からして、どこかで埋め合わせをしなくてはならないんですな。で、学期末に近くなると、他の曜日を月曜日に振り替えるようなことをする羽目になると。 しかし、こういうことも結局、「大学は、半期に15回の授業をしなくてはならない」という規則を厳密執行せよという、このところの文科省の愚かしいご命令から来るのであって、下らないの一語でございます。まさに愚の骨頂。 大体ね、大学っつーところは小学校から高校までとは違って、「ここからここまで教えなければいけない」なんて規則は初めからないのでありまして、個々の教員が個々のやり方で教えりゃーいいんですよ。 もちろん、大学の単位について、規則はありますよ。「一コマ2時間、これを15週行って計30時間。この30時間をもって『単位』と認める」、という規則は昔からある。しかし、規則は規則、運用は運用なのであってね。 昔はですね、そういう規則はあるけれども、大雑把に運用されていたもんです。さすがに半期10回の授業で済ますとなるとちょっと気が引けるところはありましたが、まあ、12回くらい授業をやれば大手を振ってキャンパスを歩けた。つまり、規則が厳密に運用されていなくとも、その辺は任されていたわけです。大体「一コマ2時間」という規則だって、実際には120分ではなく90分で行われているわけで、しかしそれに文句を言う人なんかいないんですから。 ところが今は、15回ばっちりやらないとダメというわけ。 それで思い出すのですが、昔、折口信夫が慶応大学で教えていた頃、劇作家にして俳人の久保田万太郎が非常勤講師で教えに来ていた。ところが、久保万さんは忙しい人でしたから、毎週毎週、三田まで教えに来られない。で、段々休講が多くなり、また久保万さんが演出している舞台の見学などで授業の代わりとする、なんてことも増えてきたんですな。 そしたら、学生側から文句が出た。 で、それに対して折口さんは「近頃の学生は馬鹿だ。久保田万太郎の話を年に数回聞けるだけだって勉強になるのに・・・」と嘆いたというのですな。 これはまったく折口信夫の言う通りで、大学なんてそういうところであったっていいし、むしろそうあるべきだと思うんです。要は、学生が大学での授業の中で何か知的な刺激を受け、それをきっかけに自分で勉強すりゃーいいので、その意味では、半期にたった一回授業をするだけだっていいのよ。その一回で、学生が刺激を受けるのであれば。 それをねえ、何でもかんでも一律に「15回やれ」とは・・・。文科省の見識を疑うね。ちなみに、「15回やれ」は今年度までで、来年度からは「15回授業をやって、16週目に試験をしろ」ということなので、都合半期16週にわたって拘束されることになります。それだけ、夏休み、冬休み、春休みが削られるということですな。 しかし、これらの休みの期間こそ、大学の先生方は研究に打ち込むんですよ。それを奪ったら、研究なんか進まず、その結果、新しいことなんか教えられなくなるじゃないですか! 文科省は、規則の厳密な執行を押しつけることで、大学をますます活気のないところにしようとしているわけです。これを「愚」と言わずして何と言いましょうや。 はあ~。やれやれ・・・。情けなくって、ため息しか出ないね。
January 21, 2011
閲覧総数 2549
-
27

話題の「レミパン」、優れモノです!
先日、買ってしまいましたよ、話題の「ドゥ! レミパン」! ま、男性の中にはご存じない方も多いかと思いますが、これ、タレントの平野レミさんが開発した新種のフライパンなんですな。なーんだ、そんなもの、と思うなかれ、これがなかなか優れモノなんです。ちなみに我が家が買ったのは大きさが24センチ、蒸し台つきのもので、色はグレーの奴。 レミパンというのは、基本的にはフライパンですから、焼いたり炒めたりが出来るのは当たり前。ところが普通のフライパンよりよほど深く作ってあるので、シチューや煮物を作ることも出来るし、揚げ物もできる。それから附属の蒸し台を使えば、蒸し器として使うこともできるんです。こうした多様な使い方ができることに加え、大きさが手頃で、しかもがっしり作ってある割には軽いところもいい。それから把手の反対側にもちょっと出っ張りがあるので、「鍋掴み」を使えば両手で鍋を持つことができるところも安心です。 それから鍋に附属する蓋がまた優れモノで、自立するんですよ。料理をしている最中、鍋の蓋って案外置き場に困ることが多いのですが、レミパンなら蓋自体に自立する仕組みがあるのでとても便利。しかもその蓋には細工がしてあって、餃子を焼く時など、蓋を完全に開けずに差し水をすることができる。この機能も、使ってみると結構重宝します。 というわけで、この「レミパン」を買って以来、家内はその使い易さを絶賛しています。事実、今日から数日のうちの我が家の夕食のメニュー(お好み焼き・ビーフシチュー・ギョーザ・骨つきチキンの酢煮・・・)も、すべてこのレミパンで作ると豪語していますから、その入れ込みようはすごい! 家内に言わせると、今まで料理毎に鍋を替えていたのだけれど、レミパンが一つあれば、他の鍋は必要ないとのこと。1万円かそこらでそんなに喜んでくれるなら、私もこのレミパンを家内に買ってあげた甲斐があるというものです。 ちなみに、レミパンを買った自慢話(?)をすると、家内の友人である主婦の皆さんは「ホントにいいの?!」と身を乗り出して聞いてくるそうです。つまり、皆、この鍋に興味はあるのだけど、ちょっと値段が高いので、実際に買うところまで踏み切れないみたいなんですな。でもねー、この鍋、ホントにいいですよー! 「教授(とその奥さん)のおすすめ!」です。 それにしてもこの鍋を開発した平野レミさんって、頭いいなあ。料理好きの主婦の立場から、「こういう鍋が使い易い」っていうものを形にして、見事販売に成功したんですからね。大したもんだ。 というわけで、今日は「教授のキッチンウェア」でも販売しているレミパンを、自信を持ってアフィリエイトしてしまいます。ぜひ、お買い求め下さい。後悔はさせませんゾ!ここをクリック! ↓セットでお買い上げの方が断然お得♪【ドゥ!レミ・パン 24cm イエロー&専用蒸し台セット】...
August 24, 2005
閲覧総数 605
-
28

渡辺和子著『置かれた場所で咲きなさい』を読む
渡辺和子さんの『置かれた場所で咲きなさい』を読みましたので、心覚えをつけておきましょう。 これ、先日家の近くの本屋さんの古書部門で見つけて100円で買って来たんですけど、なにせ200万部のベストセラーとなった自己啓発本ですからね。自己啓発本研究者としては読まざるをえないでしょうってことで。 ちなみに、この本を読んで知ったのですけれども、渡辺和子さんというのは「二・二六事件」で若い将校たちに惨殺された陸軍教育総監・渡辺錠太郎のお嬢さんなのね。ビックリ。 で、二・二六事件当日、和子さんは9歳だったそうですが、三十数名の将校たちが自宅に踏み込んできた時、とっさにお父さんが彼女のことを座卓の陰に隠してくれたんですと。で、その連中がお父さんに機関銃の銃弾を撃ち込んだ時も、間近でそれを見ていたと。 で、その時のことを回想して和子さんの曰く、父が死ぬ時、一人でなくて良かった、私がそばにいて良かったと。 うーん、すごい話ですな・・・。 で、長じた和子さんは、30歳の手前で修道会に入ったのですが、その後、修道会から修行のためにアメリカに行かされ、帰国したら今度は岡山のノートルダム清心女子大に派遣されたのですが、そこに派遣された直後に当時の学長さんが急逝されたもので、弱冠36歳にして同大学の学長になるという数奇な運命を負わされたんですと。 で、それまでその大学では二代続けて高齢の外国人が学長を務めていたもので、そこへもってきて36歳の小娘が新学長になったものだから、当然、いじめられるわけですよ。でもそこで彼女は頑張った。 まあ、それがいわば「置かれた場所で咲きなさい」っていうことの意味なんですな。運命によって不本意な役割を負わせられて苦しんでいた時に、ある人からこの言葉をかけてもらい、それで和子さんは立ち直ったんですと。だから、この言葉は和子さんにとっては非常に意味のある言葉だった。だから同じような苦しみを味わっている人たちを救うために、本に書いて人々に知らせようと。 いつも言いますが、自己啓発本っていうのは、内容がどうのというよりも、誰がそれを書いたかが重要なのね。だから、お父さんが惨殺されるのを間近で見るという経験をした後、若くして大学の学長になってしまって散々苦労した人が書いたものだから、この本には価値があるわけ。 そうじゃなかったら、うーん、まあ、本書の内容自体は、いわば「相田みつお的」な感じ? もちろん相田みつおはとってもいいことばっかり言っていると思いますけど、そうそういいことを言われると「またか」ってなるじゃん? そういう感じ。 もうちょっと具体的に言うと、例えば「人はありがたいものは両手で受け取るけれども、それだったら辛い試練だって神様から与えられた宿題だと思って大切に、両手で受け取りなさい」みたいな。 あるいは「人生、辛いことも一杯あるけれども、神様はその人に耐えられないほどの試練は絶対与えません」みたいな。 はたまた「苦しいことがあったら、「今、とても苦しい。だからもうちょっと生きてみる」という風に考えてごらんなさい」みたいな。 あるいは、「あなたがそこにいるだけで、その場の空気が明るくなる。あなたがそこにいるだけで、みんなの心がやすらぐ。そんなあなたに私もなりたい」みたいな。 ウソ、ウソ。最後の奴は相田みつおの詩ね。ま、傾向としては大体同じでしょ? 人間だもの。 とにかく、こういう相田みつお的な散文を小さな本にして952円で売ると200万部が売れる。幻冬舎の見城徹の思う壷だな・・・。 ま、日本人はこういうのが好きなんですな。 もちろん、悪い本じゃないですよ〜。悪いことは一つも書いてないですから。元気の無い時にこういう本を読んでちょっと元気になる。ビタミン剤みたいなもんです。体に良いものでこそあれ、悪いものではない。 ま、自己啓発本って、もともとビタミン剤みたいなもんですからね。そういう意味で、典型的なビタミン剤系自己啓発本とご紹介しておきましょう。【中古】置かれた場所で咲きなさい / 渡辺和子 / 幻冬舎
March 28, 2019
閲覧総数 566
-
29

イアン・スティーヴンソン著『前世を記憶する子どもたち』を読む(1)
イアン・スティーヴンソンという人の書いた『前世を記憶する子どもたち』(原題:Children Who Remember Previous Lives, 1987)という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 イアン・スティーブンソンという人は、ヴァージニア大学精神科の主任教授だった人ですが、一言で言いまして、学者として本格派。本ブログでは、臨死体験の研究者として、レイモンド・ムーディー・ジュニアとかケネス・リングなどの著書についても報告してきましたが、そんな連中の「研究」なるものが児戯に見えてくるほど、この本は本格的でございます。 「生まれ変わりの研究」などというと、眉唾な超常現象を扱った「トンデモ本」なんじゃないかと推測される向きもあろうかと思いますが、これは違う。要するに、これはアレですよ、本格的な文化人類学の本だと思えばいい。「生まれ変わり」という現象が世界各地で報告されているのだから、その実態を現地で詳細に調べ上げ、1ケースごとに厳密に検討し、信憑性のあるものとないものにふるい分けした上で、信憑性のあるものがあるのならば、それは一体どういうことなのかを考察する。その調査と思考の産物がこの本なのであって、ケネス・リングのオカルト本とは天と地の差でございます。 まあね、そうは言っても主題が「生まれ変わり」ですからね。信じるか信じないかは人によるし、信じない人はこの本を手にとりさえしないでしょう。それはもう、どんなに厳密な証拠を提示しても信じない人ってのはいるわけですよ。本書にも書いてあるのですが、ある田舎に住むアメリカ人の農夫が、友人に無理強いされて動物園に行ったと。で、そこでラクダを初めて見たんですが、しばらくジーっとラクダを見たあと、くるりと背を向けて、「こんな動物いるわけない」と言ったとか(339)。つまり、頑なな信念は直接の経験をも打ち破る可能性があるわけ。 しかし、かのドクター・ジョンソンが「仮に人影が現れて、『お前は悪いことばかりしているから悔い改めよ』と言ったとしたら、それは自分の良心から出た幻影である可能性が高い。しかし、どこからともなく『誰それがどこでどうして死んだ』というような声が聞こえてきて、そのことをまったく予期してもおらず、またそれを知るすべもないのに、しかも後で確認して状況が全くその通りだったと判明したら、超自然的な知的存在の実在を信じざるを得ない」とボズウェルに語った(406)ごとく、生まれ変わり現象の実在を証明する事象に出くわしたら、少なくともその可能性を検討せざるを得ない、というのがスティーヴンソンの立場でありまして、それは科学者の態度として(私は)納得できる。逆に、明らかに生まれ変わったとしか思えないような事象を前にして、「そんなことあるわけないじゃん!」と、端から検討すらしようとしないとしたら、それこそ科学者としてどうなんだと。昔、ガリレオ・ガリレイが「地球が太陽の周りを回っている」と言い出した時に、多くの科学者たちは「そんなことあるわけないじゃん!」と言ったのでしょうが、それと同じことなわけであってね。 さて、本書によると、そもそも「前世を記憶している人がいる」という話は、古代からあって、「ピタゴラスとアポロニオスの例」という二例があるけれども、これはあまり信憑性がない。一方、哲学的な考察から生まれ変わりの存在を確信するに至った一連の哲学者もいて、例えばプラトン、ショーペンハウエル、マクタガート、ブロード、デュカッスなどがその例(55)。しかし、これは考察ですからね。本当に生まれ変わり現象というものがあるのかどうかを検討する材料になるものではない。 では、大昔の伝説とか、哲学的思考の帰結とか、そういうのではなく、もっと現代的な意味での「生まれ変わり」現象の報告の中で信頼性の高いものとしては、ムガール帝国の皇帝アウランジーブが18世紀初頭に調査したインドの事例が最初なのだとか。で、その次に19世紀初頭の日本の勝五郎の例(ラフカディオ・ハーンの報告)が続く。その後は1898年にビルマで採取された事例6例まで長いブランクがあった。その後1900年から1960年までの60年間に、インドの生まれ変わり事例が心霊主義関係の雑誌などで報告されたんですと。 で、本書の著者スティーヴンソンは1950年代にこの現象を知り、興味を抱いて、それまでに発表されていた事例報告を集め、その比較検討を始めたところ、信憑性のある事例が44例見つかったと。で、1960年にこれらの中から7例を挙げた短い考察を論文にまとめたんですな。 で、これが呼び水となったのか、翌1961年、研究助成が出て(生々しい!)スティーヴンソンはインドに飛んで現地調査することができるようになったと。で、やり始めて見たら、あーた、見つかるわ、みつかるわ、予想外に「生まれ変わり」が普通に起こっていることが判明した。先ほど述べた44例は、35年間かけて集められたものだそうですが、スティーヴンソンが現地に行って5週間もしないうちに25例が見つかった。つまり、生まれ変わり現象というのは、数が少なかったのではなくて、報告が少なかっただけだったと(196-200)。で、以後25年間にわたってスティーヴンソンは研究チームを組んで研究を続け、インドのみならず世界各地(8文化圏)で事例を採取し、2000例を越すデータを集めることに成功するんですな。 ちなみに、一般に西洋人は「生まれ変わり」などというアホなことを信じているのは、文化の遅れた東南アジアの(ヒンドゥー教及び仏教を信仰する)諸民族だけだろうと思っているわけですけれども、実際に調べて見ると、生まれ変わり現象(信仰)を持つ民族というのは世界各地にある。 例えば北インド(チベット)、スリランカ、ビルマ、タイ、トルコ中南部、レバノン、シリア、西アジアに住むイスラム教シーア派の人々。キリスト教やイスラム教に完全に改宗していない西アフリカや東アフリカのいくつかの民族。ブラジルの一部の部族(アフリカの部族から持ち込まれたものらしい)。北アメリカ北西部に居住する先住民族。トロブリアンド諸島の住人。オーストラリア中央部の諸部族。北日本のアイヌ民族(51/149)。(著者は日本については調査していないが、調査すれば日本人にも生まれ変わり信仰はあることが判明するだろうと予想している)。あと、ドゥルーズ派の信者は、生まれ変わりを信じるどころではなく、故人が誰に生まれ変わったかを探り当てたいという強い願望を抱くのが普通、というようなケースもある(233)。 また、生まれ変わり信仰というと、カルマ信仰(現世の行いが来世に影響する、という考え方)とタイアップして考えられがちですけど、必ずしもそうではないんですって。生まれ変わり信仰を持つ文化圏であっても、カルマ的な考え方とは無縁のところも多いらしい(66)。 さらに、前世と現世の間の中間生について言うと、前世で死亡してから生まれ変わるまでに中間生に逗留していたと語る子供はいるのだそうで(173)、特にビルマやタイにそういうケースが多いらしい。逆にドゥルーズ派やジャイナ教徒のように、人間は死んだらすぐに生まれ変わると信じている文化圏では、中間生を想定していないんですと。で、中間生を体験した子供の証言によると、その世界では人々はゆったりとした着物を着、豪華な食事もあるが、別にそれを食べなくてもいいのだとか。 しかし、その中間生が事実であるかどうか、確認されていない(262-6)し、スティーヴンソンとしても、それを実証する方法が分からないということで、この点については深入りをしておりません。ただ、それでも前世の記憶を次に繋ぐ媒体が必要であるということはスティーヴンソンも理解していて、そのため「中間生」という仮説の代わりに、彼は「心搬体(サイコフォア)」というものがあるのではないか、という仮説を提唱しております(359)。 なお、生まれ変わり現象を信じる文化圏と信じない文化圏の間で、この件に対する対応は非常に異なるのだそうで、例えば著者が研究助成をもらって生まれ変わりの研究をしているというと、西洋人の研究者とアジア/西アフリカの研究者の間で同じ反応――「そんなことにお金を無駄にするなよ」という非難するような、憐れむような表情――が見られものの、前者の場合は「馬鹿だね~、そんなあり得ないことを研究してどうするんだよ・・・」という意味、後者の場合は「馬鹿だね~、そんなあったりまえのこと研究してどうするんだよ・・・」という意味なのだとか(341)。 さて、スティーヴンソンは世界各地で生まれ変わり事象が報告されると、そこへ通訳を連れ、現地スタッフも雇った上で調査に向かうわけですが、彼は自分がこの主題で調査をするに当たって、具体的にはどういうことをしたのか、その「調査方法」の実態を細かく明らかにしておりまして、それを読むと、まあ、この種の調査としてはほぼ完ぺきと思われる方法を採用しております。 それによると、まず生まれ変わりであるという本人へのインタビューはもちろんのこと、その親へのインタビューや、親戚や近所の人など、本人が生まれ変わりであるという話をし出したのを直接聞いていた人たちの証言もとってクロスチェックし、さらに調査が可能であれば、前世で住んでいた村などを尋ねたり、文書に当たって本人の発言の当否を調べる。そして、そうして集めた証言のうち、意図的なものであれ、無意識的なものであれ、ウソが混じる可能性(例えばトルコでの調査で「息子はジョン・F・ケネディの生まれ変わりだ」と言い張る親が三人もいたという)もできる限り排除し、「生まれ変わり」の証拠として確定してよいものとダメなもの、さらに最終的な確認はとれなかったものの相当に信憑性の高いものに分類する、といった手法で、まさに石橋を叩く要領でデータを採取していくんですな。例えば、ある家に、殺人事件で殺された男の記憶を持った子供が生まれた場合、他のすべての証言が生まれ変わり事象の正当性を証していたとしても、仮にその殺人事件が当事者の家から比較的近い場所で起こっていた場合、報道や噂話でその殺人事件のことを両親(あるいは本人)が耳にした可能性は否定できないし、たとえそのことを両親が忘れていたとしても、心のどこかに残っていた事件のデータがテレパシーで子どもに伝わったかも知れないので、これは生まれ変わり事象の証拠としては採用しない、という程の厳密さで、信憑性の低い事例を考察対象から排除していくわけ。 なお、本ブログでも前に扱ったように、「生まれ変わり」現象言説の一つとして「退行催眠」によってそういう現象の存在が発覚した、というのがあるわけですが、スティーヴンソンは、退行催眠によって過去生の記憶を獲得する、ということについては非常に批判的です。そういうのは、「過去生リーディング」同様、インチキの入り込む隙が大きすぎると。ですから、スティーヴンソン自身は退行催眠には一切かかわらないのですが、有名なヴァージニア・タイの事例(バーンスタインの著書『ブライディ―・マーフィーの捜索』で明らかにされたケース)については、退行催眠によって過去生が証明された数少ない例の一つだと認めています(71-78)。 で、それだけ厳密にデータを選別し、インチキ臭い例を排除していっても、やっぱり、どう考えても前世の記憶を持って生まれてくる子供がいる、という例が残っていくわけですよ。で、スティーヴンソンは、そうした絶対確実という例だけを取り上げていく。 で、その絶対確実だと思われるケースに絞って考えた場合でも、スティーヴンソンは必ずしも最初から「生まれ変わり」という現象を無批判に当てはめているわけではないんですな。 例えば「生まれ変わり」という考え方を採用しなくとも、「潜在意識」とか「記憶錯誤」などによってこの現象が説明できるのではないかとか、「遺伝」によって過去の記憶が伝わったのではないかとか、そういうこともちゃんと検討しているわけ。あるいは超感覚的知覚(要するにテレパシー)によって情報が伝わったのではないかとか、霊が「憑依」したのではないかとか、そういうことも検討している。けれども、そういう様々な可能性を検討すると、やはりそれぞれに説明の出来ないところが出てくる。例えば「過去に死んだ霊が新生児に憑依した」とすると、ある程度生まれ変わり現象を説明することはできるけれど、(後述するように)多くの子供が8歳以降、前世の記憶を失うことの説明がつかない、とかね(238)。何かの理由があって憑依したのなら、そのままその子が成人した後までずっと憑依してればいいじゃないか、というね。 で、そうやってあらゆる可能性を検討した結果、最後の最後に、こう考えると無理なく現象の説明がつく、というのが、「生まれ変わったのだ」という考え方だったと。 つまりスティーヴンソンは、安易に「生まれ変わり」という現象を認めているのではなく、様々な可能性を検討した挙句、この考え方が一番、現象を無理なく説明できるという意味で、「最後に受け入れるべき解釈(242)」として採用しているわけ。 で、本書にはそういう確実な生まれ変わり事象の例が幾つも上がっているのですが、これがまあ、実に面白い。 過去生の記憶を語る子供というのは2歳から5歳までがほとんど(162)で、以後、5歳から8歳くらいまでの間にその記憶が薄れていき(168)、その後は過去生のことをさほど語らなくなるそうですが、逆に2歳以前、すなわちまだ言葉が話せない時点で既に、過去生からの影響が見られる子供がいる。例えば、家族の中に今までそういう子が居なかったのに、その子だけ異様に水を怖がるとか、川に連れていくと火が付いたように泣くとか、そういう行動を取る子がいる。で、その子が言葉が話せるようになると、かつて自分は〇〇という名前で、その川のその辺りで溺死した、などと言い出したりすると。で、実際に調べて見ると、確かにかつてそこで死んだそういう名前の子がいたことが判明する。 ま、そんな調子で、いたいけな子供が、過去の記憶を語ったり、その影響を受けた行動を取るわけですけど、例えば、誰から言われたわけでもないのに、その辺から木の小枝とかを集めてきて箒を自作し、やたらに家の周りを掃除し始めたりする子がいるというのですな。で、何かと思ったらかつて自分は掃除婦だった、などと言い出すとかね。 あと酒好きの男の生まれ変わりの少年は、2,3歳の頃から「酒持ってこい~!」などと言い出して親を困らせるとか。前世でナイトクラブを経営していた幼児が、自宅でクラブを開こうとするとか(182)。あと、ハイティーンの頃の死んでしまった少年の生まれ変わりの幼児は、幼児なのに性欲満々で、年頃のお姉さんに抱き着いてはあらぬことをしようとしたりして困らせるとかね。あと、前世でビスケットやソーダ水を売るお店を経営していた子供が、お店屋さんごっこに熱中しすぎて学校に通うタイミングを失し、以後、公教育の中で落ちこぼれてしまって成人してから苦労する(191)というようなこともあるのだとか。 あと、戦後ビルマに生まれた子供で、かつて日本人の兵隊だった、と前世を語る子供がいるそうで、そういう子供の前でイギリスとかアメリカの話をすると、烈火のごとく怒ったりする。前世の日本人も、本当は日本に生まれ変わりたかったでしょうけど、戦争中に戦地で戦死するという特殊な地理的要因で、そういうわけにもいかず、仕方なく現地の子供にうまれかわっちゃったんでしょうな。 あと、インドの場合、違うカーストに生まれ変わる場合もある。例えば元バラモン階級の人が、下位カーストの家に生まれ変わった場合など、幼い子供が家人が触った食器が汚いといって手にしようとせず、あやうく餓死しかけるとか(190)。あと、家の手伝いをさせようとしても、「そんなことは召使のやることだ、俺を誰だと思っているんだ!」とはねつけるとか。あと「あーーあ、前の家の時は裕福で良かったのに、こんなクソみたいな家に生まれ変わっちまって情けねーなー」などと不満を言い続け、家人から総スカンを食らうとか。逆に、バラモン階級に生まれたのに、下層階級的な嗜好を表明して家族の総スカンを食らうケースもある(182)。 それから、生まれ変わりの場合、前世の嗜好が反映するらしく、これは南アジアのケースですけど、家族の中に他にそういう者がいないのに、その生まれ変わりの子だけ、ある特殊な麵料理を食べたがる、ということがあったりして、調べて見るとその麺料理は、その子が前世で住んでいた地域の名物料理であることが判明したりする。またそういう場合、その子のお母さんも、妊娠中にどういうわけかその麺料理を食べたくなるようなことも起こるのだそうで。 その他、ようやく言葉を話せるようになった幼児が、(普通は、「ママ」とか「パパ」とか言いそうなものなのに)開口一番「ぼくはここで何をしているんだ。港にいたのに」と言い出すとか(166)。この子は前世が港湾労働者だったんですな。 ちなみにこの港湾労働者のケースは、たまたまこの労働者が職場で眠りこけていた時に、同僚の不注意で大きな荷物をこの労働者の上に落としてしまって死んでしまい、その後、生まれ変わったのですが、このように「非業の死」を遂げた場合、生まれ変わることが多い(あるいは、死んだ状況のことを覚えていることが多い)ようで、先に述べた「溺死」のケースのように、生まれ変わった後に水を極端に怖がるとか、あるいはナイフで刺された場合は刃物を、また銃で撃たれて死んだ場合は銃器を怖がる子供として生まれ変わることが多いらしい。中には、自分を殺した相手の名前を憶えていて、復讐したいという強い意志をもって生まれ変わってくる奴もいるのだとか(225)。 そうそう、それを言ったらね、例えばナイフで刺された人が生まれ変わった場合、その赤ん坊には、ちょうど刺された体の場所に母斑(あざ)があることがあって、それも生まれ変わりの一つの指標になるらしい。 ちなみに 生まれ変わりのタイミングですが、文化圏によって異なり、レバノンで6カ月、トリンギット族で最長48カ月というのがあるけれど、前世で死んでから3年半未満で生まれ変わるのが大半で、中間値をとると大体死んでから15カ月で生まれ変わるのだそう(184)。意外に短いサイクルで生まれ変わりが行われていることが分かります。あと、前世を記憶する子どもの過半数(62%)は男児(247)なのだとか。 とまあ、「生まれ変わり」現象というのは、実に興味深いのですが、しかし、先にも言ったように、これを信じる文化圏と信じない文化圏というのがある。その差は一体何なのか。また、「生まれ変わり」現象を、本当にあるものと仮定すると、そこからどういうことが起こってくるのか、ということについて、スティーヴンソンは順次語っていくわけですが、ここまで大分長くなりましたので、この先のことについては、また次回に回すことにいたしましょう。これこれ! ↓前世を記憶する子どもたち [ スティーヴンソン,I.(イアン) ]
September 20, 2021
閲覧総数 1058
-
30

洲之内徹の評伝を読む
昨夜、天気予報で「関東平野部でも未明から雪」なんて言うから、朝起きたら一面の銀世界かと思って楽しみにしてたら、雪なんか全然降ってない。なーんだ、嘘八百のコンコンチキじゃん! とつぶやいてしまったんですけど、そう言えば最近誰も言いませんね、「嘘八百のコンコンチキ」って。 っていうか、「コンコンチキ」って何? それはさておき、ネットで入手した大原富枝著『彼もまた神の愛でし子か』(ウェッジ文庫)を読了しました。これ、『気まぐれ美術館』などの美術エッセイで名高い洲之内徹の評伝なんですけどね。 ま、私、実はさほど洲之内徹のことに詳しくないので、この本を読んで初めて知ったことも多いのですが、洲之内さんと言う人は、まあ、相当な火宅の人だったようで・・・。体格などは貧弱だけど、どこか独特の男性的魅力があった人のようで、女性にもてるけど、女性を幸せにはしないタイプの男だったみたいですね。 ・・・ワタクシとちょうど逆だな、などと言ってみたりして・・・。 でまた、女性に対してだけではなく、誰であれ嫌いな人に対してはとことん冷酷なところのある人だったそうで、そういう面でのエピソードには事欠かないみたい。 だけど、そんな風に色々と欠点のある人ではありながら、絵に対しては、あるいは美に対しては、これまたとことん愛情深く接した人だった、というところがまた、人間の面白いところでありまして。若き日に左翼運動にやぶれ、その後中国における日本軍の手先のようなこともし、引き揚げてからは作家にならんと奮闘し、その夢が破れた後、ひょんなことから画商となり、50代も半ばを過ぎてから「絵をめぐるエッセイスト」という独自の立場を見出したという数奇な人生を送った人なんですと。 さて、で、そういうことが書いてあるこの本、面白いのかと言いますと・・・ うーん、ビミョー! かな・・・。 ちなみにこの本は一応、名著ということになっておりまして、これを評価する人は多いらしいです。ですから、「さほど・・・でもないんじゃないの?」と思っているワタクシは、多分、どこかおかしいのかも知れません。ですから、私が何を言おうが、きっとこの本はいい本なんですよ。 でもね、はっきり言っちゃうと、大したことないよ! これは私の持論でもあるんですけど、やっぱりね、評伝ってのは、調べて書けるもんじゃないね。大原さんは、若い時から洲之内さんと「文学友達」だったそうですが、それはつまり「他人」ということでありまして、本当の意味で洲之内さんを知っていたことにはならない。ですから、この評伝を書くにあたって色々調べなきゃならなかったわけですが、調べた割に作中、洲之内さんが生き生きと描かれているかというと、そうでもない(と私は思う)んですよね~。 それに、も一つ難点を挙げますと、書き方がちょっと変というのか、凝り過ぎているというのか、地の文と引用文とを敢えて交錯させるものだから、ある文章を読んでいて、それが大原さんが書いている地の文なのか、洲之内さんの文章からの引用なのか、それとも洲之内さんの愛人が語っていることなのか、わからなくなってくることが多々ある。これは洲之内さんの内面をよく描いている文だなあ、と思ったら、本人の弁だったりしてね。その辺、妙にややこしや~、ややこしや、というところがある。そんなのちゃんと読めば区別がつくだろうと言われたら、その通りなんですが。 私が「これはすごい評伝だ」と思うのは、岡野弘彦著『折口信夫の晩年』、加藤守雄著『わが師 折口信夫』、ボズウェル著『サミュエル・ヂョンスン伝』の3つで、これらはいずれも、評伝の対象となる人物と、評伝を書いた人物が長い間一緒に暮らした経験があるものばかり。これにやや遅れて続くのがジョージ・プリンプトンの『イーディ』ですが、この場合、プリンプトンはイーディの親戚や親しかった人に徹底インタビューし、そのインタビューだけで評伝を構成しているので、実質、イーディを色々な形で直接知っていた人による評伝ということになる。やっぱ、評伝というのは、そうでなきゃ。で、これらを越すか、せめて並ぶくらいのものでないと、もはや感心できない身体なんです、ワタクシ。で、これらを10段階評価の10とか9としたら、『彼もまた・・・』は1点か、2点か、いずれにしてもそのくらいですな。 で、さらに思うのですが、もし洲之内徹について評伝を書くのであれば、ジョージ・プリンプトンがイーディについてやったように、生前の洲之内さんを知っていた人たちにできる限り沢山面会して、その人たちが洲之内さんのことを何と言っているか、その言葉だけをつないで、一つのポリフォニックな評伝にすればよかったのに。やたらに居た愛人たちが彼のことをどう言っているのか。彼の批評眼を愛した画家たちが彼のことをどう言っているのか。彼の妻や息子たちが、今彼のことをどう思っているのか。そういう、生身で洲之内さんと接してきた人たちの声だけで構成した評伝にすれば、相当面白いものができたと思うのですけどね。 題材が面白いものだけに、惜しい! そんなわけで、今回の洲之内徹伝、教授のおすすめ!・・・は無しよ、ということで。洲之内さん自身に興味が出てきたという方がいらっしゃれば、彼の『気まぐれ美術館』の方をお読みください。
January 9, 2009
閲覧総数 187
-
31

「おいしい生活」と西武文化とコピーライターの時代
昨夜、「給料日ディナー」と称して外食してしまいました。 と言ってもね、今回の給料日ディナーは理由あって節約バージョン。なんと我らが向かった先は・・・「大戸屋」だったのでーす。 なぜ大戸屋かと言いますと、一つにはこの有名な定食屋さんに行ったことがなかったから。それともう一つ、先日、『孤独のグルメ』の再放送を見ていて、井之頭五郎さんが「アジフライ」を食べているのを見て、どうしようもなくアジフライが食べたくなったから。 というわけで、大戸屋に入った我らは迷うことなく「アジフライ定食」をオーダー! 出てきたそれは、アジの身も部厚く、なかなか美味しいものでございました。 だ・け・ど。 うーん、大戸屋。もちろん不味くはないのだけど、普通だな。っていうか、ある意味、豪華過ぎるといいましょうか。定食屋にしては、という意味ですが。 なんか、こう、定食屋って、もう少しショボイものであってほしいわけ。そのショボさも味わいたいのだから。そういう点では、むしろ一品ずつおかずをとっていくタイプの定食屋、ほれ、カフェテリア方式でトレーにメインのおかずと副菜とご飯とみそ汁なんかを乗っけていき、会計してもらってから、お茶とかふりかけとかももらって席に着くみたいな奴、ああいう方がそれらしくていいかなと。大戸屋だと、普通のレストランと変わらないよね。 さて、大戸屋でアジフライを堪能した我らが次に向かったのは、一社駅の近くにあるシャレオツなカフェ、「プレスト・コーヒー」。ここで美味しいカプチーノやら、チーズケーキなどをいただき、備え付けのシャレオツな雑誌などを熟読し、さらにイケメンで感じのいい店長さんとロンドン談義、器談義などを楽しんだ次第。やっぱり大戸屋だけで終ったら、給料日ディナーというには寂し過ぎますからね。 ってなわけで、節約バージョンながら、週末を控えたこの日を楽しく終えたのでございます。 さてさて、「昭和の男」シリーズ、今日はまた1982年頃の雰囲気漂うお話を。 1980年代前半の気分を表す言葉を一つ選ぶとすると、私なら「おいしい生活」という言葉を選びます。これ、西武百貨店の名キャッチコピーで、作ったのは天才コピーライターの糸井重里さん。 このキャッチコピーのすごいところは、「おいしい生活」って何なのか、よく分からないってところだよね! 何だよ「おいしい生活」って。 だけど、分からないことは分らないとはいえ、この言葉をよーく噛みしめているうちに、その云わんとするところは何となく分かってくる。 世に「うまい話」という言葉がありますが、この場合の「うまい」というのは、漢字で書けば「旨い」であって、要するに投下した労働以上の、あるいは投資した以上の大きな見返りがある、というような時に使うわけですな。で、「おいしい生活」の「おいしい」という部分には、今述べた意味での「旨い」というニュアンスが込められていることは確かでしょう。 だけど、それだけだと「得をする生活」ということになってしまって、損得の話になってしまう。ところが、「おいしい生活」と言った場合、そういう損得の話だけではない何かがあるような気もするわけですよ。 つまり、おいしい食べ物を楽しむように、生活そのものを楽しもうよ、というメッセージ。仕事一途なモーレツ社員の生活なんて、ちょっとおいしくないんじゃないの? もっと生活を彩るような何かを始めようよ、っていうようなメッセージ。そういったものが込められているのではないかと。 で、それはメッセージであって、モノではないわけですよね。そこが重要。つまり、西武百貨店は、このキャッチコピーを通じて、百貨店が扱う商品としてのモノではなく、ライフスタイルの向上というメッセージを売ったわけ。それが、糸井重里の天才であり、また西武百貨店のすごさがあった。 実際、この時期の西武百貨店、否、「セゾングループ」は、モノを売る百貨店である以上に、文化を作り出すクリエーターでもあったんですよね。 例えば書店の概念を変えた大型書店「リブロ」、そして洋書や美術書に強い「アール・ヴィヴァン」とかね。「パルコ出版」で本も出版して。音楽方面で言えば「WAVE」、演劇方面で言えば「銀座セゾン劇場」に「渋谷パルコ劇場」。美術方面で言えば「セゾン美術館」。これらすべて、商売の為というよりも文化興隆の為に作ったものであり、企業が文化そのものに投資する、いわゆる「メセナ事業」の走りですな。西武は、まさにこのメセナで名を上げた。 で、これに東急グループが追随したのか、1984年には「Bunkamura」構想をぶち上げると。「オーチャード・ホール」とか、「ル・シネマ」とか、「シアター・コクーン」とか、『ザ・ミュージアム」とか、「ドゥ・マゴ」とか、そういう奴。これで池袋を拠点とする西武、渋谷を拠点とする東急が、互いに切磋琢磨してメセナに打ち込むと、そういう時代に入って行くわけですな。 それに加えて、この時期にもう一つメセナの中心となったのがサントリーじゃないかな。1979年創設の「サントリー学芸賞」とか。1986年開館の『サントリー・ホール」とか。ま、もっともサントリーは寿屋時代の1956年から『洋酒天国』なんて洒落たPR誌を出していた経緯もありますが。 とにかく、こんな感じで企業が競って文化に金を出すようになったことで、ますます東京の街が面白くなっていくと。それゆえに、ますます『ぴあ』のようなガイドが必要になっていくと。1980年代って、そんな感じよ。景気が良かったから、こういうウソみたいにラッキーなことが、文化方面に起っていたわけですな。 だからやっぱり、文化サイドから言えば、企業がじゃんじゃんヒモ付きでないお金をくれるのだから、「旨い話」だったのかもね。 で、そんな時代に気の利いた一言で斬り込んでいき、がっつり儲けるという、まさに「おいしいところ」を卓越したセンス一発で軽やかに泳いでいたのが、糸井重里さんを始めとする「コピーライター」だったわけで、コピーライターなる職業があれほど華やかな脚光を浴びたのも1980年代だったとすれば、1980年代は「コピーライターの時代」、でもあったのかも知れません。
April 15, 2016
閲覧総数 1288
-
32

川本三郎『いまも、君を想う』、萩原健一『俺の人生どっかおかしい』を読む
昨日、野暮用があってイオンに行ったのですが、その中にニトリがありまして。で、見るともなく見ていると、電動ソファーが売っている。 当然、試しに座ってみるじゃん? そしたら・・・ いい! これ、イイ! 電動で背もたれが倒れ、オットマン的に足も上がって、極楽状態。これが10万円以内で買えるのか?! でも、こんなの買ったら、極楽過ぎて堕落しちゃうかもね・・・。 さて、仕事の合間に読んでいた本を読み終わってしまいました。 一つは川本三郎さんの『いまも、君を想う』という本。男性著者が、亡くなった妻の思い出を綴る本というのは沢山あって、城山三郎さんの『そうか、もう君はいないのか』とか、永田和宏さんの『歌に私は泣くだらう』、江藤淳の『妻と私』、亀井俊介先生の『わが妻の「死の美学」』などがパッと思い浮かびますが、思い浮かぶというのは、それらを読んだことがあるということでありまして、要するにその手の本に惹かれるところが自分にあるのでしょう。 で、川本さんの本ですが、ファッション評論家であった奥様との出会いから死に至るまでの思い出が、なるべく抑えた筆で淡々と綴ってある。それを読むと、すごくセンスのある、そしてガッツのある、素敵な奥様だったんだなあということがよく分かる。となると、その奥様を若くして病気で失うということは、川本さんにとってものすごい打撃だったであろうことも推測され・・・。まあ、だから読者にどうすることもできませんが、自分の奥さんは大切にしなきゃという思いを強くしましたね。これこれ! ↓【中古】 いまも、君を想う 新潮文庫/川本三郎【著】 あともう一冊、萩原健一さんの『俺の人生どっかおかしい』ですが、これはショーケンが大麻所持・使用で逮捕された時の騒動を綴った本。出る釘は打たれるじゃないけれど、当時、ものすごい勢いでいい仕事をされていた萩原さんだけに、この事件を機に彼を叩く人・マスコミの攻勢がすごくて、執行猶予付きながら実刑判決を受けたことで、その後もしばらく散々な目にあわされたと。 もちろん、自業自得の面はありますが、こういうことがあると、見たくもない人間の悪辣なところが見えちゃうんですなあ。その一方、それでも彼に救いの手を差し伸べようとする人たちもいて、救われるところもある。例えばガッツ石松氏の、萩原さんへの温かい行動なんかを読むと、ガッツさんってスゴイ人なんだな、と思います。瀬戸内寂聴さんも優しいし。あと、当時萩原さんの奥さんだったいしだあゆみさんの苦労とかね。これこれ! ↓【中古】 俺の人生どっかおかしい 萩原健一さんって、難しい人ではあったようですが、この本や『ショーケン』(これはいい本!)なんかを読む限り、人間的に深いところもあって、色々な意味で興味深い人物ではありましたね。私は一度、二子玉のデパートのエレベーターに、ショーケンと乗り合わせたことがあって、その時は何も言えませんでしたけど、せめてひとこと、「『ショーケン』読みました! 素晴らしいと思います!」と、感想を言えば良かったなと、これは今もって後悔しているところでございます。これこれ! ↓【中古】 ショーケン
September 21, 2024
閲覧総数 573
-
33

映画『ヒットマン・インポッシブル』を観た
ハンガリー映画『ヒットマン・インポッシブル』を観ましたので、心覚えを。以下、ネタバレ注意ということで。 っていうか、ハンガリー映画って久々に観たなあ。『アンダーグラウンド』以来かも。あれは面白かったけど。『ヒットマン』も、『アンダーグラウンド』同様、ちょっと現実と非現実が混在するような、独特の味があります。 本作の主人公はゾリカという青年なんですが、生まれつき下半身に障害があり、車椅子生活なんですが、障害のせいか内臓が圧迫され、早期に大きな手術を受けないとまずい状況。しかし、自分を捨てて母親と離婚した父親からの援助を受けたくないこともあり、手術を拒否。自暴自棄に陥っている。そんな彼の面倒を見るのは、障害者施設で一緒に暮す親友のバルバのみ。バルバもまた身体に抱えた障害により、女性とつきあったことがなく、そのことがコンプレックスに。 で、そんな若くして世を拗ねた二人が唯一、熱中するのが、コミックの制作。年に一度のコミケに参加し、自分たちの作品が世に出ることが、二人の夢でもある。 そんな二人の前に現われたのが、元消防士のルパゾフなる人物。火事現場での事故が元で下半身不随になり、かつての恋人もついに彼を見放し、別な男と結婚することに。英雄から一転、絶望の淵に生きるルパゾフは、その障害を利用し、今は殺し屋として生計を立てている。 そして、障害者のリハビリ施設で出会ったゾリカ、バルバ、ルパゾフの三人は、それぞれ絶望の中に生きているという共通項もあり、なんとなくルパゾフの殺し屋家業をゾリカ、バルバの二人が手伝うという、妙な共犯関係が生まれるんですな。 で、ルバゾフの雇い主というのは、セルビア系マフィアのボスなんですが、彼の依頼により、ルパゾフとゾリカ&バルバは、対抗組織のボスを殺すわけ。しかし、ゾリカやバルバといった素人の若者を巻き込んだことで、そこから足が着くことを怖れたマフィアのボスは、ルパゾフにゾリカとバルバを殺すことを命じるんです。 で、ルパゾフは一旦は二人を溺死に見せかけて殺しかけるのですが、結局最後に情がわいて、二人を助けてしまう。で、そのことがボスにばれ、ルパゾフもゾリカもバルバもボスから命を狙われることに。 さて、身体の不自由な三人は、マフィアのボスから身を守ることは出来るのか?! そしてその先に待っていたものは?? みたいな話。 で、これがね、結構面白かったのよ。 物語の重要な伏線としては、ゾリカと実の父親の関係があるのですが、結局、父親に対して反目を続けていたゾリカにとって、突然現れたルパゾフは、父親の代理になるわけですよ。ルパゾフのリーダーシップで、ヒットマンという危険な仕事をやり遂げたり、あるいはルパゾフに命を救われたりする中で、自暴自棄になっていたゾリカが、もう一度生きる力というか、生きている実感というか、そういうのを再び掴み始めるわけ。失われた父親像を、ルパゾフが演じるような形になるんですな。 もっとも、ただのきれいごとのロールモデルを演じただけではなくて、ルパゾフもまた、恋人に捨てられた絶望の中で、色々と不様なカッコ悪いことをやらかすんです。でも、そういう醜態をさらしながらも、一途な愛に苦しむ姿をゾリカの前で晒すことで、それがゾリカ自身の世を拗ねた態度を改めさせることにもなると。 それで最後、ゾリカはこの代理父と協力し合いながら、マフィアのボスを仕留め、自分の命を救うお金を奪うことに成功、そしてそれまでかたくなに手術を拒んでいたゾリカは、この金で手術を受けることにする。ただ、ボスとの対決の過程で、ルパゾフは命を落とすのですが・・・。 そしてゾリカとバルバは、「車椅子の殺し屋」というコミックを完成させ、それがコミケでとある美人女性編集者の目に留まり、二人のマンガ家デビューが実現しそうな感じにもなってくる。しかも、バルバはこの美人女性編集者に普通の男性のように扱われ、彼の長年のコンプレックスも吹き飛びそうな勢い。 そして、ゾリカも、自分のコミックが認められたことで自信を得、長年音信不通だった父親(もう別な女性と再婚し、娘も二人いるのですが)に、このコミックを送ることで、二人の間の関係が復活するのではないかということがほのめかされると。 しかし、この最後のシーンで、コミックの主人公たる「車椅子の殺し屋」(もちろんモデルはルパゾフ)の顔が、ゾリカの実の父親にそっくりだということが判明するわけ。 ということは? ルパゾフという、元消防士の寂しい殺し屋は、本当に実在したのだろうか? それは、心の底で父親を求めるゾリカの空想の中から生れたものであって、ルパゾフ(やバルバ)と一緒に危ない橋を渡ったというのは、単に彼が作り出したコミックの中の空想ドラマだったのではないか? その辺が「ん? あれれ?」と思わせ、この映画を観る者を混乱させつつ、この映画は終わると。 最初に言いましたけど、その辺のね、現実なんだか現実じゃないんだかが曖昧になっていくところがまた、いいのよ。 というわけでこの映画、私の採点では「83点」と、久々の80点越えでございます。大作ではないけれど、いい感じの佳作です。こんなリアルで、かつ幻想的な身体障害者映画って、あんまりないんじゃないかしら。アカデミー賞外国映画部門のノミネート作品になったのも頷けます。珍しいハンガリー映画という事も含め、一度ご覧になって損はない映画と思いますので、教授のおすすめ!と言っておきましょう。ヒットマン:インポッシブル [ サボチ・チューローチ ]
July 16, 2017
閲覧総数 1630
-
34

かつての同僚、F先生の驚くべき最期
今日、大学で同僚と話をしていて、偶然、かつての同僚で、もう四半世紀以上も前に他大学に移られたF先生の話題になりまして。 このF先生、ご専門が国語学で、私とはまったく専門が違うのですが、何というか、さすが大阪出身というか、お若い頃から妙に太っ腹かつ大物感があり、ズケズケと辛辣なのに人を遠ざけないところがあるというのか、とにかく異様なリーダーシップがありまして、当時、うちの大学の若手研究者を糾合し、月一くらいで勉強会を始めたんですな。題して「一升瓶の会」。 専門は関係なく、とにかくやる気のある若手なら誰でも参加でき、順番に研究発表をするんですけど、一通り発表が終わった後、聞いていた専門外の参加者からめちゃくちゃにけなされるというのがお定まりで、まあ、完膚無きまで批判される。 で、そうやって凹ませた後は、持参した一升瓶から茶碗酒を酌み交わし、後腐れなく大いに談笑して解散すると。まあ、そういう会だったんですな。もちろん会の立ち上げから運営まで、F先生が中心となっていたのですが、会の当日は本当にF先生が一升瓶を持ち込み、それを会場(学内の空き教室)の真ん中にドーンと置いた状態で始まるのですから、今ではちょっと考えられない。 でまあ、かく言うワタクシも、赴任早々、この世にも恐ろしい「一升瓶の会」に誘われ、なかなか面白い経験をさせてもらったものでございます。 でも、あの頃はまあ、いい時代でした。「学際的」とか、そんなお飾りの空虚な言葉など端から必要ないほど、野蛮なまでに「学問をしよう」という空気がビリビリと学内に漂っていて、文字通り若手同士、学問分野も何も関係なく、勉強しているかどうか、研究しているかどうかだけを判断基準に切磋琢磨しあっていたものですよ。 ところが私がこの会に入ってから二年かほど経った頃、会の中心だったF先生が滋賀県の大学に移籍(その後、さらに大阪の大学に移籍)されてしまった。まあ、元々関西人なので、郷里に近いところに戻られたということなのでしょうが、ために会は求心力を失い、加えて他の参加者の中にも他大学に移籍する人が続いたりして、いつの間にか自然解散となってしまった。 やっぱり、こういう会というのは、カリスマ的なセンターが必要なんですな。 それから幾星霜。今やうちの大学には、あの頃のようなギラギラした、学問・研究への情熱とかそういうのがたぎっている状態など想像すらつかないほどになってしまいました・・・。 で、そのF先生なのですが、今日伺ったところによると、なんとなんと二年ほど前に亡くなったのだそうで。私より数年年上でしたから、多分、60歳をちょっと超えたくらいのところだったのではないかと思うのですが。 で、亡くなったということ自体、もちろんショックだったのですが、その亡くなる前の状況というのがまたすさまじいものだったんです。 まず結婚されなかったF先生は、生涯お一人。またご実家・ご兄弟とも折り合いが悪かったようで、そちらとはもう一切縁を切っていたと。だから天涯孤独の身の上で、すべてを学問・研究に捧げていたんですな。 で、癌に侵され、余命一年と言われた。 でも、「自分は学問をやる人間だから、死ぬのなんてぜーんぜん怖くない。それに一年あれば、今やっていることを本にする時間はある!」とポジティヴに捉え、その言葉通り、病室にパソコンを持ち込み、命の最後の力を振り絞って本の執筆に明け暮れた。私の同僚は、その頃F先生のことを病院にお見舞いに行かれたそうですが、「もう体力がなくてトイレにも行けない。だから看護師さんにおむつを替えてもらうのが恥ずかしくて」と笑いながら、意気軒高に執筆中の本のことを語っていたそうです。 で、実際、F先生はそれから本を2冊出した。一冊は国語学の研究書、もう一冊は、先生が長年温めていた戯曲(創作)だったそうです。 で、その戯曲の方を寄贈してもらった私の同僚は、それを読んだそうですが、すごく面白いものであったと。それで、その感想を書き送ったところ、既に亡くなった旨の連絡が来た。 先にも言ったように、F先生はご実家とも縁を切っていたので、葬儀というようなことはせず、ただお別れの会のようなものを開いたとのこと。で、その会を取り仕切ったのは、F先生の本を数多く出版していた国語学専門の小出版社の社長さんだったのですが、F先生は自分が研究者として長いこと世話になったということで、その出版社に遺産を全額寄贈したのだそうで。 ううむ。すごい人生の仕舞い方じゃありませんか・・・。 もし自分がその立場だったら、余命一年と言われて、心穏やかに本の執筆なんかできるだろうか。絶望的な気持ちになって、心が乱れて、とても書けないんじゃないだろうか。 そう思うと、猶更F先生のすごさが分かります。いやあ、凄いな。 というわけで、たまたま雑談の中で知ったことですが、かつて、私が今の職場に赴任した当時、短い時間ながら「一升瓶の会」を通してお付き合いのあった方の壮絶な死の話を伺い、何とも、心がぞわぞわするような、そんな気持ちにさせられてしまったのでした。 最後まで高く研究者魂を持ち続けた・・・というか、大阪風に言えば「どてらい奴」だったF先生のご冥福をお祈りいたします。合掌。まあ、そんな神妙なことを私が言えば、F先生から「あんたなあ、そんなしょーもないこと言うてる暇に、勉強せいや!」とかなんとか、叱られそうですけどね。
September 13, 2021
閲覧総数 1495
-
35

常盤新平『雪の降る夜に』を読む
延々続く常盤新平沼。今日は『雪の降る夜に』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 これは短篇集。8つの短編が並んでいる。で、内容はいつもの通り。ストーリーはなく、エピソードだけ。60前後の初老の離婚男の悲哀か、妻子ある男との不倫をする女の話。で、そのすべてが常盤さんが実際に体験したことを、手を変え品を変えて再現したもの。 「夕ざくら」は、妻と離婚した男の話。その男には愛妻家の友人がいるのだけど、その男の妻が病死すると。で、その死んだ妻には親友(女)がいて、男とその女は、友人夫婦を通じて知り合ってはいたのだけど、この度、共通の友人を失ったことをだしにして懇ろになるという話。 続く「雪の降る夜に」と「出おくれ癖」は、もう、常盤さんの実体験そのもの。不倫して再婚した女との予想以上に気の合わない生活、そして不倫後に出来た二人の娘が反抗期を迎えて、父親とあまり合わなくなってきた、そんな日常生活の一場面を切り取ったもの。不倫男が、結果罰を受けるという話。 「課長の姿」は、上司の課長が、飲み屋のフィリピン人のママと不倫している、そんな渋いシチュエーションを見ながら、課長の部下である主人公の若い男が、課長の秘書に思いを寄せるという話。 「古い万年筆」は、ちょっと年の離れた女性同士(かつて会社での先輩後輩だった)が、久しぶりに電車の中で出会い、互いの来し方を語る的な話。年上の女は、かつて妻子ある男と付き合っていたのだけど、なんとその男は肺がんで若くして死去し、愛用の万年筆を彼女に遺した。そのことを先輩から聞かされ、女二人、感傷にふけりましたとさ。 「娘の家出」は、主人公の男の親友の娘が家出をしたというので、その親友に頼まれて会う話。なんで娘が家出をしたかというと、父親が不倫している現場を見ちゃったから。でもいい娘で、ちょっと父親にお灸をすえるために家出しただけだった。主人公に「男なんてみんなそんなもんだ」と説得され、いずれ家に戻るだろうという見込みがついたところで終わり。 「土曜日の朝食」は、初老の男と年頃の娘二人の話。男の妻はもう死んでいる。下の娘は不倫しまくり。上の娘は少し晩生だけど、男はそんな娘たちの生活にあまり干渉せず、見守っているという話。 ラスト「別れのあとに」は、妻子ある男と不倫し、子供ができたのだけど、相手の男に堕せと言われて熱が冷め、別れてしまった。と、そこに男の妻から夜中に無言電話がかかって来るようになり、結局、電話で妻と不倫相手の女との間でバトル勃発。互いに言いたいこと言って、なんとなく清々したところで終わり。 ナニコレ? 常盤さんは、自分がW不倫の経験者だからって、ほとんどの作品が不倫の話と、その後日譚ばっか。実話を元にしたことしか書けないからそうなるんだけど、さすがにさあ、食傷もいいところよ。 まあ、その中では「別れのあとに」が、ちょっと女同士の修羅場で面白かったかな。もうすでに事が終わった後で、難癖をつける妙な電話がかかって来るという点で、ちょっとレイモンド・カーヴァ―的な味わいがあるというか。 ということで、仕事だから読むけど、さすがに臨界点近くまで飽きてきた常盤ワールドなのでした。これこれ ↓【中古】 雪の降る夜に / 常盤 新平 / 東京書籍 [単行本]【宅配便出荷】
February 20, 2025
閲覧総数 545
-
36

『愛されてお金持ちになる魔法のカラダ』を読む
今週も卒論と、相続関係の手続きで自分の仕事が出来ない状況ではあるのですけれども、せめて一冊くらいは何か読もうと思い、佐藤富雄著『愛されてお金持ちになる魔法のカラダ』なる本を読んでみました。 ま、表紙のイラストからしてそうですけど、これ、50代のおっさんが読む本ではないですよね・・・。 しかし、内容から言えば決してそんなことはなく、男であろうと女であろうと、若かろうとおっさんだろうと、読んで実行したらそれなりにいいことが起こるんだろうな、というものでございます。 じゃ,実際、どういう内容なのかと言いますと、世の中には外見も美しく、仕事も出来て、お金も手にし、楽しそうに人生を謳歌しているタイプの人と、日々の生活にハリがなく、仕事も楽しくなく、お金もカツカツで、どよーんと生活している人がいると。で、もしあなたが後者にあてはまり、しかも心のどこかで前者のようになりたいなと思っているのであれば、何はともあれ3つのことをやりなさいと。 で、その3つのこととは何かと言いますれば・・・1 成功ウォーキング2 1日2食+サプリメント3 想像力 の3つ。 以下、本書ではこの順番に縷々説明されていくわけですけれども、やはり本書において一番の比重は第1点目の「成功ウォーキング」に置かれております。 一般論として、自己啓発本には意識改革から入るヤーツーと、カラダ改革から入るヤーツーがあるのですが、本書は明らかに後者。つまり、まず運動しろと。 で、佐藤先生曰く、数ある運動の中で、ウォーキングこそが成功体質を作る最善の道であると。 正しい姿勢・正しいやり方(やる時間帯や長さなど)を守ってウォーキングすると、まず脳からベータエンドルフィンやセロトニンといった物質が分泌されるので、脳がポジティヴに活性化され集中力が圧倒的に高まる。だから歩きながら考えると悩みは解消されやすくなるし、問題も解決しやすくなるし、夢や希望がどんどん明確になってくる。加えて,当然のことながら姿勢は正しくなり、贅肉は落ち、バストアップ・ヒップアップがなされて、外見的にもどんどん若々しく魅力的になっていくと。 で、そういうベースを作り始めた上で、さらに追い撃ちをかけるように食事改革をすればいい。まず朝食を抜いてプチ断食(早朝ウォーキング効果で、逆に食欲は抑えられるので、朝食を抜いても平気、平気!)。さらにビタミンA・C・E や,その他必須栄養素を賢くサプリメントで補えば完璧! そしてそしてカラダ改革が成し遂げられたところでトドメの一撃として「なりたい自分」をできるだけ具体的に空想し、その空想を楽しめと。そうすれば、不思議なことに、カラダ改革で活性化したカラダと脳が勝手に活動を開始し、その空想の実現に向けてドンドン動き出す。その結果、前までだったら「実現するはずがない」と思い込んでいたことが、ドミノ倒しのようにばんばん実現していきますよと。 ま、本書の主張ってのはそういうことですな。まずカラダを作って、そこから自己啓発本特有の「なりたい自分を空想すれば,その通りになる」という言説を打ち出すというパターン。 で、おそらくですけれども、本書の通りに行動したら、それなりにいいことはあるだろうなと思います。 そりゃそうでしょうよ。朝日と共に60分から120分、正しいフォーム(本書に正しいフォームでの歩き方が書いてある)でウォーキングしたら、間違いなく健康面での改善は図れますわ。で、それにプラスして、脳内ホルモンだかなんだかの好影響で、精神的にもポジティヴになれるんだったら、自分の夢が叶おうが叶うまいが、やるだけの価値はあろうというもの。 だけど、朝日と共に60分から120分のウォーキングかあ・・・。それも、単独で(友達や夫婦でのウォーキングは、雑談しちゃうのでダメ。自分を見つめ、自分の夢を実現するためのウォーキングは、一人でやらなきゃ!)。これ・・・結構ハードル高いよなあ・・・。 ま、佐藤先生曰く、一旦やり始めれば想像する以上に簡単だそうですけどね。それに、ハードル高いよなあ、とか言ってウォーキング一つやらないから、あんたはいつまでも自分の夢を実現できないんだ、と言われたら、まあ、その通りなんですけれども。 ということで、実行したら間違いなくいいだろうけど・・・という内容の自己啓発本たる本書、ご紹介しておきましょう。【中古】 愛されてお金持ちになる魔法のカラダ 王様文庫/佐藤富雄【著】 【中古】afb しかし、自己啓発本って、結局最終的には、この本みたいにウォーキング勧めてくるか、さもなければ瞑想を勧めてくるんだよなあ・・・。 歩くか、瞑想か。カラダに直で刺激を与えるか、脳・精神に直で刺激を与えるか。そこが問題だ・・・。 ウォーキングも瞑想もどっちもやる!とか言ったら、ものすごい超人に変身できちゃいそうですけど、どうなのかな? 本当にそうなのかな? ま、自分で実際にやってみれば、すぐに分かることなんですけどね・・・。
December 2, 2017
閲覧総数 1031
-
37

ついに来た! 深見東洲著『強運』を読む
前々から気にはなっていたんです。気になるでしょ? 深見東州という男。あれは一体、何者なのか? あれほどインチキ臭いのに、何故あれほどのゲストを呼んでイベントが出来るのか? で、その深見大先生の自己啓発本が『強運』という奴。まあ、自己啓発本を研究する上で、一度は読んでおきたいなと。 だけど、何としても定価では買いたくない。できれば108円で買いたい。 と思って、このところずっと古本屋に行く度に探していたんですけど、今日、ついに見つけましたよ。200円でこの本の美本を売っているのを。108円じゃなかったけど、まあ、この辺が妥協点かなと。ちなみに私がゲットした本は、平成10年初版、平成20年版で、この時すでに67刷だからね。かーなーりーのベストセラーではありましょう。 で、早速読んでみた。 要するに、これはアレですね、スピリチュアル系自己啓発本ですな。それも「守護霊系」の。人間一人一人は、それぞれ守護霊に守られているのであって、この守護霊を大事にし、そのパワーを活用すれば、強運は身に付くよと。 例えば織田信長なんて、5000人の大守護霊団がついていた。だから、あれだけの業績を挙げられたのだと。 なんで織田信長が5000人もの守護霊がついていたことがわかるかというと、過去の出来事には「神界ビデオ」ってのがあって、許可をとるとそれを見せてもらえると。それで深見氏はその事実を知ったらしいのですが。 はい、そういう感じでーす。 でも、じゃあ、守護霊に気に入られるようにするにはどうすればいいかというと、まず前向きに生きること、くよくよしないこと、失敗は失敗としてそれをバネに次を頑張ること、人を恨まないこと、人の不幸を望まないこと、自分一人の幸せを望まないこと。天の助けは2割、自分の努力が8割だと思って努力することだと。 まあ、どの心がけも悪いことじゃないですよね。だからこの本、有益か無益かで言ったら有益よ。 しかも。この本はさらに魔法の呪文も教えてくれる。 クワバラクワバラとか、ナムアミダブツとか、そういう呪文も昔からあるけれども、そういうのはもう古い。家電製品だって新しいものの方が大抵は優れているわけだから、ナウな呪文を唱えようと。 ということで、深見先生、5つほど「パワーコール」を教えて下さっております。 じゃ、それはどういうのか、と言いますと・・・ 残念! それは教えてあげられないの。だって、それを人に教えちゃうと、パワーが落ちるらしいので。それは自腹でこの本買った人だけが秘かに学ぶものらしいのよ。 さらにこの本には袋とじがついていて(袋とじだよ、世のお父さん方の大好きな!)、幸運を呼び寄せる各種図像(パワーマーク))が載っている。自分の願いがどういうものであるかに応じた図像を選び、それをコピーしたりなんかして身に付けたりすると、ご利益があるらしい。 つまり、パワーコールとパワーマークの組合せで、強運を招きよせることが出来る。 そんな大層なものを200円で手に入れた私はどんだけ強運なんだと。 ま、そういうことですわな。 というわけで、前から一度は読んでおきたいと思った深見東州大先生の『強運』をついに手に入れ、これから先の私自身の赫々たる武勲が楽しみなワタクシなのであります。さあて、とりあえず金運アップさせてから、宝くじでも買うかな!【中古】 強運 ツキを呼び込む四原則 タチバナかっぽれ文庫/深見東州(著者) 【中古】afb
December 27, 2018
閲覧総数 1177
-
38
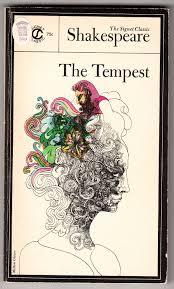
追悼・天才デザイナー、ミルトン・グレイザー
著名なデザイナー、ミルトン・グレイザー氏が脳卒中のため死去されました。享年91。亡くなったのは、同氏の誕生日だったそうで。男は大概、自分の誕生日の直前に死ぬものですが、氏は辛うじて誕生日を迎えることができたようです。 さて、ミルトン・グレイザーと言えば、「I💛NY」のロゴや、ボブ・ディランのアルバム・デザインで知られるわけですけれども、私のような「本の表紙デザイン研究家」からすると、グレイザー最大の功績は、アメリカのニュー・アメリカン・ライブラリー社が出したシグネット版シェイクスピア全集の表紙デザイン、これに尽きます。これこれ!↓ ミルトン・グレイザーのデザインは、そのカラフルな色使いについ目が行きますが、私が見るに、彼の真価は色ではなく、むしろ「空白」ではないかと。上に挙げた本の表紙デザインにしても、当時のペーパーバック本の表紙としては非常に珍しい「白地」がまずある。これがグレイザーの真骨頂。そこに高度に抽象化された黒の線描が来て、さらにそこにきれいに塗り分けられた多色が載るから映えるのであって。 で、このグレイザーの洗練された「空白の美」が、1950年代後半のアメリカン・ペーパーバックの世界に、「白の時代」と呼ばれる流行をもたらしたのでした。 とまあ、アメリカのペーパーバック本の表紙デザインに革命を起こしたデザイナー、ミルトン・グレイザー氏が亡くなられたと聞き、私としてはある種の感銘を受けているのでございます。氏のご冥福をお祈りいたします。合掌。
June 28, 2020
閲覧総数 324
-
39

島田潤一郎著『長い読書』を読む
島田潤一郎さんが書いた『長い読書』というエッセイ集を読みました。 島田さんは、『昔日の客』を出したことでも知られるひとり出版社「夏葉社」を作った人。本の作り手ですが、自らも本を書かれる。私は編集という仕事に興味があるので、とりわけ独自に出版社を作った人のエッセイ集となると、割と小まめに読む方でして、島田さんの本もこのほかに私は何冊か読んでいる。『あしたから出版社』と『電車のなかで本を読む』かな? その中では、今回読んだ『長い読書』が一番好きかも。 この本、前半は島田さんの中学生から大学生頃までの思い出が、本と絡めながらつづられている。本ばかりでなく、ビートルズとかロックとか、音楽も含め。島田さんは私よりも一回り若いけれど、男子中学生とか、その位の年代って大概そんな感じだよね。 で、大学は親の勧めもあったのか、商学部の方に進まれたようだけれども、やはり島田さんの関心は文学や美学方面にあり、そちら方面の授業にも顔を出されたりしたらしい。また文芸関係のサークルに入って、一応、文学修行的なこともされていたり。先輩からの感化とか、そういう思い出話も実に面白い。やっぱり、青春ですよ、青春。文学と共にある青春。 で、卒業後、フリーターのようなことをしながら人生の方向をゆっくりと見定められ、いきなり夏葉社を作ると。その辺の細かい経緯は別なところで書いているので飛ばして、もっと内面的な意味で、本を読むこと、本を作ることと自分との関係、そしてとりとめのない、しかしそれがなければ島田さんの存在が確定しなくなるような経験の数々を訥々と述べられている。それがいいのよ。 たとえば、中学校時代の旧友と何十年かぶりに再会する話とか。 その友達というのは、中学校の時までは親友だったのだけど、いつしか不良のようになってしまって、話が合わなくなってしまった。そして進む道も異なって音信不通になってしまう。そんなことは誰にでもあるでしょう。ところが、そのかつての親友と再会することがあって、久しぶりに話をすると。そこで、そのかつての親友、そして不良になって音信不通になって、久しぶりに再会したその友人が、「島田の誕生日、六月二三日だろ」って言うの。 言ってみればただそれだけのことなんだけど、いい話じゃない。すごくいいと思う。人間のつながりってのは、そう簡単には途切れないんだなと。で、泥酔したその友達はさらに、島田さんに向かって「おれも活字を読むんだ。こう見えても、活字を読まなきゃ眠れないんだ」って言う。その一言で、本を読むってことが、どんづまりのところで人を支えるんだっていうことが分かるじゃない。だから、島田さんのこの本は、本を読むことに関するエッセイ集なわけよ。 あと文芸サークルの先輩のIさんの話もいいんだよね。 Iさんは大学を卒業した後、証券会社に就職する。つまり文学とは無関係な世界に行ったわけだけど、その中でやはりIさんは本を手放さないんですな。で、そんな環境の中で、本なんか読めるんですか、と島田さんが尋ねる。それに対してIさんは、「月曜日から金曜日までめちゃくちゃに忙しいし、お昼もろくに食べられないこともあるんだけど、そういうときもぼくは、立ち食いそば屋でそばをかき込みながら、プルーストを読んだ。谷崎訳の『源氏物語』も全部読んだし、『カサノヴァ回想録』も全部読んだ。それがぼくのエネルギーになったし、いまも文学のことを考えることがぼくのよろこびだ」って答える。 いやはや。本を読むことを生業にしている私やその同業者に、こういう感じで本を読んでいる人って、何人いるんだろうか。 その他、夏葉社にアルバイトに来ていた「秋くん」という青年の話とかね。夏葉社もお金がないから、秋くんを専任で雇うことはできない。だから、アルバイトとしてしか雇えないんだけど、そんなもどかしい中で、二人の面白い関係性というのができあがっていく。もちろん、年齢的に言っても島田さんが秋くんを指導する立場にあり、実際にもそうなんだけど、実は秋くんが島田さんに教えていることも多い。その負い目からして、島田さんは今でも、どこにいるか分からない秋くんに読まれることを期して本を書いているようなところがあるわけ。そういうのも、とてもいい。 というわけで、読みやすいエッセイ集ではあるのだけど、うーんと唸らされることの多い本だったのでした。教授のおすすめ!です。 それにしても、島田さんはこの本を自分が経営する夏葉社からは出さなかったんですな。そこは、何かこだわりがあるのかもね。夏葉社は仕事、書くのは別、という。これこれ! ↓長い読書 [ 島田潤一郎 ]
August 8, 2025
閲覧総数 685
-
40

アメリカで買ってよかったもの
さあて、サンタモニカ滞在もあと週末を残すのみ。段々帰国の日が近づいて参りました。 さて、今回の滞在でも、色々なところに行き、色々なものを買い、色々なものを食べましたが、その中で、印象に残ったものを幾つかご紹介して行きましょう。○最も印象に残った外食(ちゃんとした食事篇) これはもう間違いなく、サン・シメオンの「Moonstone Beach Drive Grill & Bar」で食べたシーフード。まあ、ハースト・キャッスルに興味がない人はまずサン・シメオンに行かないと思いますが、万が一この近辺を通過するようであれば、熱烈にこの店を勧めます。○最も印象に残った外食(軽食篇) カリフォルニア近辺に数店舗あるという「Green Leaf's」のラップサンドとパニーニ。アメリカのものにしては健康的で軽い。実に旨しでございます。○最も印象に残ったアイスクリーム 私の常のお気に入りは「ブライヤーズ」なんですが、今回、「talenti」のジェラートというのを買って食べてみて、実に美味しかった。talenti のジェラートは、最近、日本でも「高級ジェラート」として輸入されているようですが、きっとすごい値段で売られていたりするんだろうな。こちらのスーパーでは、せいぜい5ドルくらいですよ。○最も印象に残った缶詰 旅行中、しばしば「Pea Soup Andersen's」という看板を高速道路上で見かけ、何だろうと思って調べたら、ソルバングに本店があるエンドウ豆のスープの専門店だそうで、それならばということでここに寄って缶詰のスープを買い、帰ってから食べてみたらこれが旨かった。濃厚なエンドウ豆のスープですな。さすがに、これは日本では手に入らないかも。○最も印象に残ったコーンフレーク 「Post」というメーカーのコーンフレークがもともとお気に入りなのですが、今回、ここの「Honey Bunches」の「イチゴ入り」というのを買ってみたら、すごく美味しかった。乾燥させたイチゴがゴロゴロ入っていて、風味もバッチリ!○最も印象に残ったソフトドリンク 多少甘過ぎでジャンクな感じではありますが「Brisk」のレモンアイスティーにハマりました。○最も印象に残った本 今回も色々なところで色々な本を買いましたが、サンタモニカのプロムナードの一角にある西海岸最大のアート/建築関連本の専門書店「アルカナ・ブックス」で買い求めた『New Homes for Today』という本は、今回ゲットした本の中で最大のヒット。いや、何のことはない、アメリカの普通の家の設計図集なんですが、この設計図を見ていると、アメリカの一般住宅のフロアデザインの優秀さがよく分かる。建築ファンにとっては垂涎の書と言えましょう。アマゾンでも買えます。○最も印象に残ったもの そしてもう一つ、これはアメリカで買ったものではなく、日本で買って持って行ったものなのですが、ガーミンのナビゲーションをおすすめ。ガーミン製のナビは日本だけでなく、世界で使えるのがいいところなのですが、今回、そのナビ用にアメリカ合衆国の地図(マイクロSDとして売っている)を8000円くらいで買い、それをぶち込んで持って行ったのですが、これが役に立つ立つ。ハイウェイを走っていても、どのレーンを走ればいいかまで指示してくれますからね。もうこれがあれば、どこに行っても迷うことなし! 方向音痴の私にとっては、天佑でございました。 ということで、ま、こんなかんじかな〜。 さて、残り少なくなったアメリカ生活。せいぜい最後まで楽しむつもりです。
September 15, 2013
閲覧総数 430
-
41

4つ目の条件が本物?
昨日、美容院から帰って来た家内から面白い恋愛テストのことを聞きました。家内担当の美容師さんから聞いたらしいのですが、このテストで「あなたが恋愛対象に求めるもの」が分かるというのです。 さあ、皆さんもご一緒にどうぞ。 いいですか、あなたが恋人に求めるもの(条件)を3つ挙げて下さい。即答でお願いします。考え込んじゃダメですよ。ちなみに、家内からそう聞かれた時、ワタクシの答えはと言いますと・・・1 聡明であること2 優しく善良であること3 私の主観から見て好ましい容姿・物腰・声質であること でした。皆さんはいかがです? 3つ条件を挙げられましたか? さて、それでは次。この3つの条件をすべて同程度に満たした2人の恋人候補者がいるとします。その際、この2人のうち、どちらを選ぶかの基準として、4番目の条件を挙げて下さい。 挙げましたか? よろしい。ではこの恋愛テストの結論を申し上げましょう。 あなたが挙げた「4番目の条件」、それこそが、あなたが恋人に求める一番重要な条件でーす! ガーン! ちなみに、ワタクシはその4番目の条件として、「ユーモアがある人」と即答してしまいました。ということは、ワタクシが恋人に求める一番大きなものは「ユーモア」ということになるのでしょうか・・・。 私がこの「恋愛テスト」に一目置いたのは、この点です。よーく考えてみたら、たしかに私は「ユーモアのある人」が好きなのかも知れない・・・。いや、まさにそうだ! という気がしてきたんです。最初に挙げた3つの条件は、いわばベーシックなもので、それプラス「ユーモア」のセンスが効いていてはじめて、私はノック・アウトされるような気がします。 じゃ、どうして恋人選びの第一条件に「ユーモア」を挙げなかったんだろう? 「4つ目の条件」を問われてはじめて、最も「決め手」となる条件がポロッと出てきたとは、これ如何に?? 不思議だなあ! 私はこの種の「恋愛テスト」的なものなど、まるで興味がないのですけど、今回のコレに関しては、ちょっと一本とられてしまった、という感じですね。 さて、皆さんはどうでしたか? 「4つ目の条件」に思い当たるところはありましたか? 皆さんが恋人に求める一番重要な条件って、一体何ですか? 私と同じように、ご自身について何か発見があった方、レスポンスをお願いします。
October 8, 2006
閲覧総数 5443
-
42

清里の荒廃
週末を利用して、八ヶ岳の方にドライブ旅行に行って参りました~。この時期、八ヶ岳南麓は桜満開。東京や名古屋で観終わった桜を、もう一度見られるというのが、この時期、この辺りを旅する醍醐味の一つでね。今回も、桜、きれいでしたよ。 ところで、今回の旅の目的の一つは、清里にある「安達原玄仏画美術館」を訪れること。 ここは女流仏画師・安達原玄さんの作品を置いてある美術館なのですが、玄さんの息子さん、文彦君が、実は私の中学校時代の同級生でありまして。卒業後初めて、すなわち三十数年ぶりに会いに行った訳。 で、事前になんの予告もせず、ただふらっと美術館を訪れて、展示物を一通り見て、帰り際に受付の人に「実は文彦さんは私の同級生なのですが・・・」と伝えると、奥からキートン(=文彦君)が飛び出してきて久々の邂逅。「なんだよ~、前もって来るって言えよ~!」 で、即席で互いの近況を話したのですが、彼はもう三人の子供のお父さん、一番上のお嬢さんはほやほやの大学生とのこと。でも、本人を見ると、とてもそんな大きなお嬢さんがいるようには見えず、お互い15歳同士の感じがしてしまうんですけどね。ま、彼も僕も、大分白髪が混じるようになりましたが。 でまた、人脈ってのは不思議なもので、話をしているうちに意外なところに共通の友人がいることが判明したりして、世間は狭いもんだなあと。 実は彼のご母堂様、安達原玄さんは残念なことに先月お亡くなりになったのですが、美術館は文彦君が、また仏画については彼の奥様が玄さんの衣鉢を継ぐことになったらしく、その点では安心できるようになったとのこと。 今回は、長居できませんでしたが、これでお互いのことが大分判りましたので、次はちゃんと事前に連絡して、一緒に飯でも食おうかな。でも、子供の頃の友人に何十年かぶりに会うってのは、面白いね! ところで、今回は清里周辺を見てきたのですが、観光地としての清里の衰退ぶりというのは怖ろしいようなもので。 ネットで「清里、廃墟」などと検索すると、駅前の凄まじい荒廃ぶりなどを見ることができますが、大学時代、御多分に洩れずこの辺で合宿をした世代のワタクシとしては、清里駅前のシュールな荒廃風景をみると、感無量という感じがします。清里駅前の象徴でもあった「ミルクポット」とか、シュール過ぎて、「ファンシー廃墟」と呼ばれているんですってね。 それと、今回、清里フォトアートミュージアムで「ヤング・ポートフォリオ」(これは素晴らしい展覧会でした)という展覧会を見てきたのですが、ここでも清里の凋落を目の当たりに。 このミュージアムは、モダンで巨大な建物の半分を占めていて、残りの半分は「パトリ」というところが経営する会員制ホテルだったんです。ところが、そのパトリがホテル経営から撤退してしまったということで、ホテル側の建物が今、放置されているわけ。 バブル末期に建てられていますから、重厚なコンクリ造りのすごい豪華な建物だけに、維持費も大変なようで、暖房用のボイラーの修復時期が来ているのだけど、その修復に1千万かかる。しかし、パトリが手を引いた後、それを払う母体がないものだから、建物全体の暖房もままならないようで、フォトアートミュージアムでも、あちこちに電気ストーブが置いてありましたなあ。 しかし、こんな重厚なコンクリの塊、壊すのも相当金が掛かるでしょうし、壊すこともできないまま、廃墟への道を進むことになるのでしょうか。 その他、清里の至るところに「兵どもが夢の跡」的な建造物が朽ち果てていて、その荒廃感がすごい。 八ヶ岳に別荘を! というのがワタクシの長年の夢なんですけど、清里の荒廃を見るにつけ、「こういうところに終の棲家を作って大丈夫なのか?!」という疑問がちらっと脳裏をかすめるようになってきたというね。ま、小淵沢の方は、清里ほどブームにならなかっただけに、あれほどの荒廃は感じられませんけど。 ま、とにかく、昔の友だちに会ったり、清里の荒廃ぶりに改めて接したりして、懐かしいやら何やら、印象的な旅となったのでした。
April 19, 2015
閲覧総数 1051
-
43

谷川俊太郎死す
そうか、谷川俊太郎さん、亡くなったのか。享年92。10月に亡くなった私の母と同い年だったわけだ。 谷川さんというと、何ですかね。『二十億光年の孤独』? いやいや、私にとっては『ピーナツ』の翻訳、かな。 自慢ですが、私は谷川さんの『ピーナツ』ものの翻訳の、いわば最初期の読者なのよ。 というのは、谷川さんの息子さんが、私の父の教え子だったから。その息子さんが、父のところに、谷川さんの訳されたスヌーピーの漫画を持ってきて、「今度、親父がこういうものを翻訳したんです」と紹介したわけ。で、それを家に持ち帰った父は、今度こういうのが出たらしいけど、お前、読むか?と、私にくれた。だから、出版されたばかりのスヌーピー漫画を、私はその本が市場に出回るよりも早く手にしたと。 だけど、それは日本の漫画とは全然違う。オチもあるんだかないんだかわからないようなところから、チャーリー・ブラウンがため息をついて終わるという。日本の『サザエさん』のような分かりやすい笑いではない。あー、これは理解するのは難しいだろうなと、子供心に思いました。 だけど、スヌーピーの可愛さは、理解しやすいだろうなと。初期のスヌーピーは、もっと犬っぽかったしね。 だから、私はスヌーピーの絵を真似して描いて、同級生たちにみせびらかしたわけよ。美術の時間には、スヌーピーの塑像を作ったりして。とにかく、スヌーピーの宣伝部長みたいな感じで、同級生たちにこの犬を売り込んだわけ。 当時、私は自分でも動物を主人公にした自作の漫画を描き、雑誌のようにしてクラスに回覧したりしていましたから、同級生たちは「スヌーピー」もまた、私が考えた新キャラなんだろうと誤解し、大人気になってしまった。私も、敢えて「これは僕じゃなくて、チャールズ・M・シュルツという人が作ったキャラだよ」なんて、訂正しませんでしたからね。 だからね、スヌーピーが日本で人気になったのは、私のおかげなの。(ホントに?!) さて、そんな戯言はともかく、谷川俊太郎ですよ。 彼は「日本で唯一、詩で食っていける詩人」と考えられてきたわけですけれども、私の感覚はちょっと違う。私はね、あの人は詩人というよりは、非常に優秀なコピーライターだったと思っているの。 その意味で言うと、谷川俊太郎の直接の後継者は、糸井重里だと。言葉のセンスにしても、企画力にしても、すごく似ている。『ピーナツ』の日本への紹介だって、あれは企画力だからね。 ま、私の谷川俊太郎観に、どれだけの人が賛同してくれるかは分からないし、私にとっても誰にとってもどうでもいいことだけれども、まあ、とにかく、スヌーピーを介して、私と谷川さんが一瞬、交差したということだけが、楽しい思い出として残っております。 そういうものとして、谷川俊太郎さんのご冥福をお祈りしたいと思います。合掌。
November 19, 2024
閲覧総数 671
-
44

井上尚弥選手ほどの傑出
昨夜、井上尚弥選手のボクシングタイトル戦を堪能いたしました。 もともと昨年のクリスマスに対戦の予定だったグッドマン選手が目の上の負傷を理由に対戦を辞退。それに伴って急遽、ランク11位の韓国人選手が井上選手とタイトル戦を戦うことになった次第。世界的には無名の選手、しかもたった2週間ほどの準備期間ということで、相手選手にほとんどチャンスはなかったとはいえ、昨夜の試合は一方的でした。 井上選手の場合、パンチの音が違うもんね! ドスッ! バスッ! と、あり得ないほど異様な打撃音をマイクが拾ってしまうという。トドメの右ストレートで、相手選手はひとたまりもなく吹っ飛んだという感じ。圧勝でした。 それにしても、井上尚弥選手ほど完璧なボクサーって、60年以上生きてきて、見たことがないな。モハメッド・アリ選手の現役時代のすごさは見て知っているけれど、ヘビー級と軽量級ではボクシングの闘い方が違う。一瞬の隙ですら致命傷になり得る軽量級のボクシングで、あれほど完璧なボクシングって、あり得るのかなと。 まあ、毎試合、スゴイものを見せてもらっているという感じがしますなあ。中谷潤人選手がもし井上選手と闘ったら、いい線行くのではないかという人もいますが、現時点ではまだまだ井上選手が上と見た。 それはそうと、井上選手の試合を見つつ、ここまで傑出した同時代人を、自分はどのくらい知っているかな?ということを数えてみた。で、出た答えがコレ。〇井上尚弥(ボクシング)〇モハメッド・アリ(ボクシング)〇ビートルズ(ロック・ポップ)〇プリンス(ロック・ファンク)〇藤井聡太(将棋)〇大谷翔平(野球)〇ウサイン・ボルト(陸上)〇アベベ・ビキラ(マラソン)〇ミハエル・シューマッハ(F1)〇千代の富士(相撲)〇大鵬(相撲)〇田中角栄(政治家)〇ジョルジェット・ジウジアーロ(カーデザイナー) 他にもいるかもしれないけど、パッと思いつかない。でも、こういうスゴイ人たちと同時代を生きてきたというのは、幸せなことですな。 他に「この人はスゴイ」という人がいたら、是非、教えてください。
January 25, 2025
閲覧総数 561
-
45

文学の好み
バルガス・リョサがついに死んだか・・・。 なんの感慨もない。 なんか苦手なんだよなあ、南米文学。ガルシア・マルケスもまるで読めなかったし。我々の世代は結構、南米文学世代で、ひところはやれ「マジック・リアリズム」がどうとかこうとか、盛んにもてはやされたもので。それで私も何度かトライはしたんだけど、読めなかった。 なんか、こう、感性がしっとりはまらないんでしょうな。 なんだろうね、そういう、文学上の「好み」って。 それを言ったら、現在、鋭意研究を続けている自己啓発本についてもいえる。 例えば『7つの習慣』とか。あれの重要性とかはわかるのよ。実際、すごく重要な作品で、何故重要かということだったら、いくらでも言える。だけど、じゃあ、アレを愛読しているか?と問われると、いや、それほどでも、という感じになる。もっとマイナーな自己啓発本の方が、好きか嫌いかで言えば、よっぽど好き、というところがある。 まあ、私は昔からそうだからね。アメリカ文学の巨人たるフォークナーとか、面白いと思ったことがないからなあ。なんかインチキ臭い奴だなと、ずっと思っていた(思っている)。 もっとも、今、フォークナーをウィキペディアで調べると、私が書いた論文やら何やらがやたらに参照されているんだけどね! あれ、どゆこと? まあ、こればっかりは、「こうあるべきだ、これを好きになるべきだ」と言われても仕方がないので、あきらめるしかないな。自分は自分の好みのまま、云々するしかない。 だけど、そうね、死ぬまでにもう一回くらい、マルケスやリョサにチャレンジしてみるのも、いいかもね。だけど、フォークナーは、もう無理だな。
April 15, 2025
閲覧総数 638
-
46

デイビッド・ハミルトン著『親切は脳に効く』を読む
デイビッド・ハミルトンが書いた『親切は脳に効く』という本を読了しましたので、心覚えをつけておきましょう。 ハミルトンはスコットランドの有機化学博士で、プラシボ(偽薬)の専門家。つまりは科学者であるわけね。で、その人が「親切」という人間の行動の実質的な効果について云々しているのがこの本。 で、それによると、親切というのは、心にも身体にもとてもいいことだと。 たとえば親切をする/されると、「幸せホルモン」ことオキシトシンがドバっと出て、これが欝を治すし、ストレスへの抵抗力も増えるし、心臓の負担も減らすと。あるいは「NO」(一酸化窒素)の血液濃度が増し、これが血管由来の病気(心臓病とか脳卒中とか)を予防する。そしてこれらの物質は抗酸化作用があって、老化を防ぐことにもなるので、長生きできるようになると。 もう一つ、親切の好ましい効果として、伝染性があるということも、ハミルトンは指摘しております。 つまりね、人から親切にされる、あるいは人が他の人に対して親切にしているところを目撃したりすると、自分も他の人に親切な行為をしたくなるらしいんですな。それが3次まで続く。だから、仮に私が誰か他の人一人に親切にしたとすると、その人も他の人に親切にし、さらにその人も他の人に親切にし、さらにその人も他の人に親切にし・・・という具合に、4人の人に影響を与えると。すると、その4人の人もそれぞれ3次ずつ他人にいい影響を与えるので、合計すると一度の親切が64人に好影響を与えることになると。 すごくない? これはビジネスの場でも同じことが起こるので、たとえばいい店長がいて、この人が部下に対して親切に振る舞うとすると、店長から親切にされた店員(スタッフ)も機嫌がよくなり、客に対して親切に振る舞うと。そうすると、店員から親切にされた客も気分がよくなり、この店を贔屓にするようになる。そうやって一人の店長の親切さが、5%もの売り上げアップに跳ね返ってくるんですと。 じゃあ、なんでそれほど親切が効果があるかというと、人間にそもそも親切DNAがあるからだと。 何億年も昔、親切なDNAを持った人間と、自分勝手なDNAを持った人間のグループがいたんですな。 さて、それぞれのグループはどうなるか。 親切なグループは、たとえば食べ物をゲットすると、みんなで分かち合うわけ。だから、たとえば10人のグループだったとすると、そのうちの3人くらいが食べ物を取りに行けば一日の食糧はなんとかなる。翌日はまた別な3人が交代で行けばいいのでね。 ところが親切じゃないグループは、食べ物を分かち合うという発想がない。だから、毎日の食べ物を、10人がそれぞれ取りに行かなければならなくなるわけ。と、その過程で事故ったり、獣に食われたりすることもある。 だから、親切なグループと親切じゃないグループでは、前者の方が生存率が高くなる。これを繰り返していけば、遠からずして親切なDNAを持った人間が地上を覆うようになるのは明白。だから、今、この世界に生きている我々は、全員が親切なDNAを持った人間の子孫なわけですよ。だからこそ、親切というものを受ければそれが分かるし、逆に人にも親切にしたくなると。 とまあ、そういう風に科学的に親切の効能というものを実証した本、それがこの『親切は脳に効く』なんですな。だからこの本を読むと、なるほど、人間としてこの世を生きていく限り、親切というのは優れた戦略だ、ということがよくわかる。親切になれば自分も幸せになるし、他人も幸せにできるし、双方ウィンウィンでハッピーになれるんだから、もう、言うことないじゃん、と。 親切ってのはいいものだ、というのは誰もが分かるけど、それには科学的な根拠があるんだというのをきちんと解説してあるという点で、この本は非常に有用であると、まあ、そういう結論になるでしょうか。 正直、飛び抜けて面白い本というわけではないけれど、とにかく親切にしておけば色々間違いなし、ということはよく分かる。その意味で、教授のおすすめ!と言っておきましょうかね。これこれ! ↓親切は脳に効く [ デイビッド・ハミルトン ]
April 28, 2025
閲覧総数 580
-
47

読むアマチュア、読むプロ、読むセミプロ
仕事柄、本は間違いなく沢山読むのですが、なんかこう、時々、「俺はこれで本を読んでいるのかな?」と思うことがある。 子どもの頃、つまり本を遊びで読んでいた頃、本を読むことから何かを引き出そうなどとしないで、ただ面白いから読んでいた頃は、本当に本を読んでいたという実感がある。 一方、プロのライターが、読んだ本のことなんかを書いているのを読むと、ああ、なんだか楽しそうにいい本を読んでいるな、という気がする。 それに比して、今の私は・・・。本を読み、その読んだ内容を使って本を書いているわけだから、プロっちゃープロの本読みなんだろうけれども、なんか苦しいんだよね。これを読み終わったら、次はいついつまでにこっちの本を、それが終わったら、今度はそっちの本を読まなくちゃ、という意識で読むからね。ノルマで本を読んでいる感じ。 しかも、それだけではダメだからというので、ノルマで読む本の合間にノルマとは無関係の本を読むことをノルマにしているところがある。急いでノルマ外の本を読まなくちゃ、だって、ノルマをこなさないとダメだもん、ってなもんで。 これは、一体何なの? アマチュアの幸福な読み方ではないし、プロの読み方でもなくて、いわばセミプロの読み方なのかねえ? まあ、そんなことを言っている間に、とにかく次の本を読まなくては。 これで、定年にでもなって少し時間に余裕ができたら、昔のアマチュアな読み方に戻れるのだろうか。 そうなれればいいな。
August 6, 2025
閲覧総数 673
-
48

追悼 ロバート・レッドフォード
はあ・・・ついにこの日が来ましたか・・・。米俳優のロバート・レッドフォードさんが亡くなりました。享年89。 私が子供の頃、アメリカの二枚目俳優といったらこの人、という感じがしましたねえ。『明日にむかって撃て!』、それに『スティング』。ポール・ニューマンとのコンビが素晴らしかった! ポール・ニューマンが明るいキャラ、レッドフォードがクールなキャラ、という感じは、ちょっとルパンと次元のコンビにも似てましたな。 それから『華麗なるギャッツビー』ね。ギャッツビー役としては、やっぱりレッドフォードが一番なのではないかしら。あと、ダスティン・ホフマンと組んだ『大統領の陰謀』も忘れてはいけない。 あの見目麗しい俳優が、ついに・・・。 私が子供の頃に「かっこいいなあ」と思った俳優たちがどんどん亡くなっていくね。マーロン・ブランドも、スティーブ・マックイーンも、チャールズ・ブロンソンも、ライアン・オニールも、アラン・ドロンも、ジャン・ポール・ベルモントも、みんな死んじまった。クリント・イーストウッドは驚異的に頑張っているけど、それもそう長くはないでしょう。 なんかなあ・・・。寂しいのう。 しかし、まあ、俳優というのは、羨ましいことに、肉体は滅びても、フィルムは残る。もう少しして、私も暇になったら、昔観た映画を片っ端から見直して、往時の華やぎを思い起こそうかな。 美形俳優として一世を風靡し、サンダンス映画祭を企画して若手の育成にも貢献したロバート・レッドフォードさんのご冥福をお祈りしたいと思います。合掌。
September 17, 2025
閲覧総数 689
-
49

モンテ・クリスト伯
フランスで元大統領のサルコジ氏が、かの有名な、かつてルパン(三世じゃない方)も収監されていたラ・サンテ刑務所に入れられたらしいじゃん? ま、確かに、サルコジって、見ようによってはルパン三世っぽい顔しているもんね。 それでまた面白いのが、サルコジが牢屋に持って行った本よ。デュマの『モンテ・クリスト伯』を持参したって言うじゃない? もう、脱獄する気満々っていうことじゃないの。これがフレンチ・ジョークか! しかし、脱獄するかどうかは別として、牢屋に持って行くのに『モンテ・クリスト伯』ほどうってつけの本はないよね。私もこれまでの人生で読んだ本の中で、ベスト10には入る本だし。 それにしても、大統領が牢屋入りって、割とよく聞く話だよね。権力を持つと、色々悪い誘惑があるんだろうね。 権力がまるでない私なんか、牢屋に入らずに『モンテ・クリスト伯』が読めるんだから、それはそれでいい人生なのかもね。
October 22, 2025
閲覧総数 704
-
50

「釜玉スパ」を食べ、『ものすごくうるさくて・・・』を観る
最近テレビCMで見かけるハウス食品の「釜玉すぱ」シリーズ、早速試してみました。 私が食べたのはシリーズの中の「バター醤油」という奴。作り方は簡単で、茹でたてのパスタに粉末状の「釜玉すぱ」一袋をかけ、さっと和えた後、そこに生卵を一つポンと割り入れるだけ。後は卵を適宜絡め、うどんの「釜玉」と同じ状態にして食べると。 で、そのお味ですが・・・ 旨ーい! これほど簡単に作れてこのレベルの味なら文句なし。このシリーズには他に「カルボナーラ」とか「明太子」もあるようですので、次はこれらも試してみましょうかね。週末のお昼、簡単に、しかも美味しく済ませたいという時に最適。教授のおすすめ!です。これこれ! ↓ 釜玉すぱ バター醤油 / 釜玉すぱ / パスタソース★税込1980円以上で送料無料★釜玉すぱ バター...価格:158円(税込、送料別) さて、昨夜、DVDで『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』という映画を観ましたので、軽く感想を。以下、ネタバレ注意です。 例のニューヨークの同時多発テロで父親を失った主人公のオスカー君。アスペルガー症候群が疑われるオスカー君は、賢いことは賢いものの、偏執狂的なところもあり、また様々なものに対する恐怖心を持っているのですが、父親のトーマス氏は生前、そんなオスカー君のことを暖かく見守りながら、彼の良い所を伸ばしつつ、少しずつ彼の恐怖心や偏執狂的なところを是正しようとしていたんですな。で、オスカー君もまたそんな父親が大好きだった。 で、そんな大好きな父親をテロで失うことになったわけですから、その喪失感にオスカー君もどーんと落ち込むわけ。 ところが、ある時、父親の遺品の中に見たことのない鍵があることに気付いたオスカー君は、それが父親が彼に残したチャレンジなのではないかと思い、その鍵が当てはまる錠を探し出す冒険に乗り出すと。 手掛かりはその鍵が入っていた封筒に書かれた「ブラック」の文字。おそらく「ブラック」という名前の人物が、その鍵の秘密を知っているに違いないと判断したオスカー君は、ニューヨークに住む400人超の「ブラック」さんを虱潰しに探しだし、鍵の秘密を知っているブラックさんを特定するという無謀な行動に出る。 とはいえ、色々なものが怖いオスカー君にとって、この冒険はなかなかに手ごわい。さて、彼はこの冒険を成し遂げ、父親が残した鍵の謎を解き明かすことが出来るのか? そしてその謎が解けた時、オスカー君はどんな錠を開くことが出来るのか? というような話。 さて、この映画に対する私の点数ですが・・・ 「68点」でーす! 惜しい! うーん、この映画の概要を伝え聞いた時、もう少し感動的な映画かと思ってたんですよね。事前にハードルを上げ過ぎてしまったのか、実際に見たらそれほどでもなかったかなと。 例えばオスカー君の錠探しを手伝うことになる「間借り人」(実はオスカー君の実の祖父)とオスカー君との交流ですが、映画の中では随分多くの時間を占める二人の交流の中から、何かが達成されるのかと思いきや、意外にそうでもないんですよね・・・。 また「間借り人」は、声を失った人物として描かれるのですが、その必然性はあったのかどうか。例えば、実の息子(オスカーの父親)を失ったショックで声を失った、というのなら分かるのですが。その場合、ああ、祖父と孫、それぞれがあのテロで何かを失ったんだな、ということになりますから。でも、そうじゃないですからね。 そして、この映画の最大の山場は、オスカー君が父親を失って1年もの間、ずっと黙っていたある秘密に触れるところなんですが、オスカー君がずっと後悔している彼のある行動についても、何故彼がそういう行動をとったのか、観客を納得させる理由が提示されていない。 それに、まあ、これを言ってしまったら元も子もないのですが、オスカー君ほど賢い子であれば、鍵に当てはまる錠探しなんてことをしないような気がする。そういう無駄なことをすることで、父親不在の状態を一時的に忘れようとしたのだ、ということなのかも知れませんが、それにしても、ああいう探し方はしないような気がする。 つまりオスカー君の造形を、「頭の切れる子」ではなく、「実年齢より精神的にずっと幼い子」みたいに設定しないと、成立しない物語なのではないかと。 せっかく面白い物語になりそうなのに、ちょっとずつの瑕疵が積み重なって、惜しいものにしてしまった、という感じかな~。 っていうか、大体私は、繊細で感情の浮き沈みの激しい子というのが苦手なのよね(爆!)。もっとのんびりした、静かな子が好き。私自身、子どもの頃、すっごい静かな子で、周りのうるさい同年齢のガキどもが嫌で嫌で仕方なかった方だし。 というわけで、この映画、私は良い鑑賞者ではなかったのかもしれません。他の人はもっと高い評価をするかも知れませんので、興味のある方はどうぞ!
January 13, 2013
閲覧総数 217









