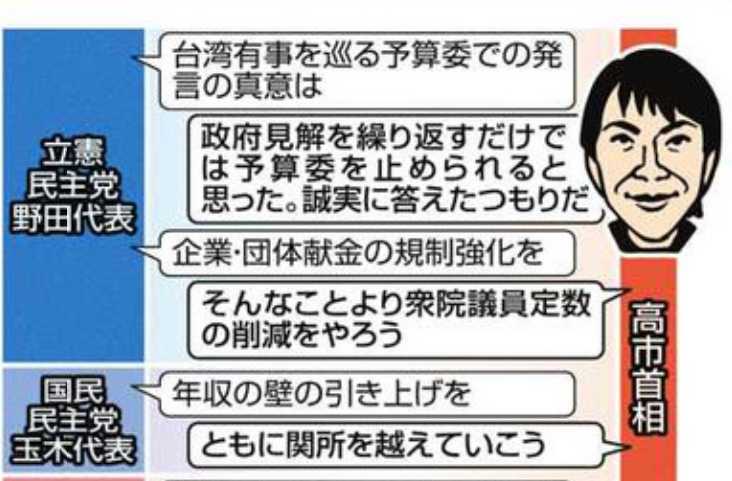2010年01月の記事
全6件 (6件中 1-6件目)
1
-

画像診断 その1
急性期では、CT、MRI画像を発症直後だけではなく、経過とともに、時間をおいて撮影することがあります。出血/梗塞など、経過とともに色が異なることがあり、わかりにくくこまっていましたが、以下の書籍に整理されて載っていたので、今、勉強中です。ポイントがわかりやすく載っていて、読み進めやすいです。お勧めです。ゼッタイわかる頭部画像の読み方第4版
2010年01月28日
コメント(0)
-
全身状態・リスク管理の勉強会に参加
先日、全身状態・リスク管理についての地域のST勉強会に参加してきました。バイタル・聴診法など、実技もまじえて教えていただきました。日頃からバイタルの測定など、疑問点もあったので、いくつか質問し参考になりました。新たに知ったこととして、血圧の触診法では、最低血圧は測れない。インスピロンのネーザル(鼻カニューラ)では、3リットルが限度で、それ以上では鼻粘膜を痛める。COPDでは、酸素投与量を上げると、動脈血二酸化炭素分圧も上がるため、CO2ナルコーシスになることがある。水分のin-outで、outバランスになると、脱水となり、それにより1回の心拍出量が減少、頻脈となる。など
2010年01月24日
コメント(0)
-
血圧 その2
急性期を主に担当しているので、血圧測定をする機会は多くあります。病棟で使う血圧計はさまざまあるのですが、自動血圧計(上腕式、巻きつけ型、エアー手動)で測定すると「Err」となることが良くあり、少し困っています。患者さんの負担もあるので、2回くらい測定してもErrなら、手動の血圧計を取りに行って再度測定します。不整脈で、「Err」となる場合はわかるのですが、それ以外の理由はわかりません。マンシェットの巻き方が悪いのか、衣服の上腕部が厚いためか・・・。
2010年01月14日
コメント(2)
-
三宅式記銘力検査 その2
記憶の検査として、三宅式記名力検査を行うことがあります。有関係対語は通常通り実施しますが、無関係対語は点数が低いと患者さんが自身を失いそうになることが多く、苦慮しています。「次(無関係対語)は、すごく難しくなっていますので、1問もできない場合もありますので、チャレンジとしてやっていただければと思います」のように伝えてから実施しますが、有関係対語で10問正答していても、無関係対語で、0点や1点という結果になると、自分の記憶の能力に対して不安になるようです。できる限り、この課題をリハビリの最後にもってこないようにしていますが。
2010年01月06日
コメント(5)
-
血圧 その1
急性期を主に担当しているので、血圧を測定する機会が多いですが、どのような患者さんに対して血圧測定が必要か迷うことがあります。(基本的に迷う時は測定しています)全員にリハビリ前後で測定すれば、問題はないと思いますが、時間の問題もあるので。自分としては、以下のような観点の組み合わせで血圧測定をしています。(全て充たすというわけではありません)超急性期を脱し、血圧が安定しているか病棟での血圧測定回数訪室時の患者さんの様子、表情、歩行状況など自分の疲労感などに対して十分訴えが可能な方かどうか外泊を既にしているかPTのリハビリ状況(立位訓練か負荷をかけた歩行訓練レベルか)
2010年01月05日
コメント(0)
-

流涎 その1
流涎の原因として、『脳卒中の摂食・嚥下障害』に、以下のようにありました。唾液の分泌の亢進唾液が嚥下できない口唇閉鎖不全心理的要因また、『急に患者の流涎が増加した場合には、[1]脳卒中の再発、[2]口腔内の疾患を考えるが、原因がよくわからない場合も多い』とあったので、急性期の流涎の量には注意していきたいと思います。絵でみる脳と神経第3版では、以下のように載っていました。唾液の分泌促進 副交感神経で、顔面神経唾液の分泌抑制 交感神経で、胸髄視床下部視索前野の刺激によって、副交感神経機能亢進が起こる。唾液分泌の亢進の機序は詳しく調べれていませんが、唾液腺のアイスマッサージがよいとのことなので、流涎や、唾液嚥下回数が多い患者さんには、状況により実施しています。
2010年01月02日
コメント(0)
全6件 (6件中 1-6件目)
1