全470件 (470件中 1-50件目)
-
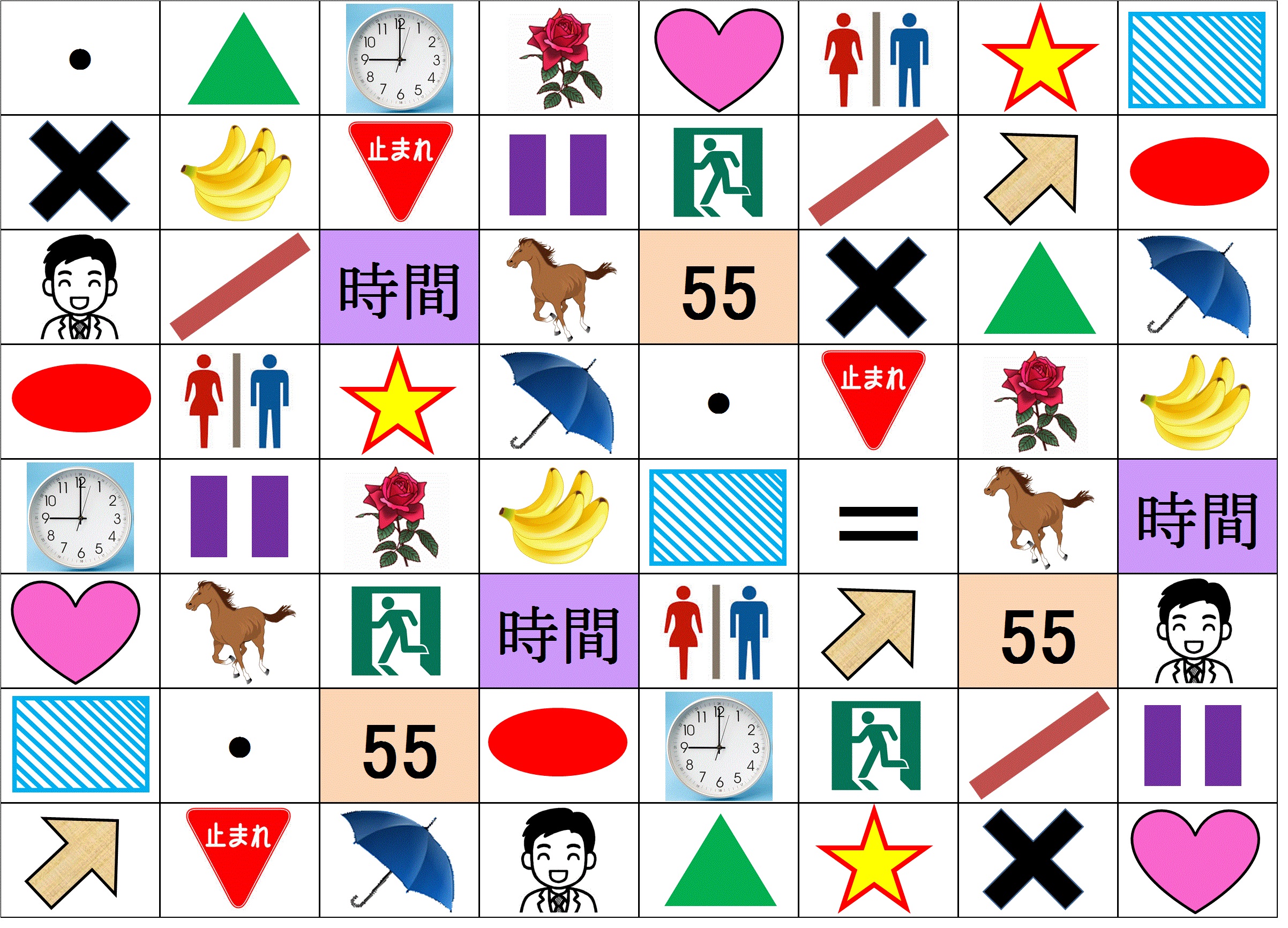
テスト公開
テスト公開
2022年12月13日
コメント(0)
-
薄めとろみを外す目安
嚥下障害があり、水分の薄めとろみを外す目安について、私が経験的に考えていることをまとめました。<今回想定した患者>脳血管障害JCSⅠ桁、簡単な会話可能今回の発症前は嚥下障害なし発症後、1ヶ月以上経過(ある程度自然回復しても、嚥下障害が残存している)お茶を細いストローから摂取し、10~20口に1回程度、軽度のむせがある。固形物の嚥下は問題なし。薄めのとろみ茶を摂取。ティースプーンで一口ずつ飲むなどは現実的に困難。<私が経験的に実施している「薄めとろみを外す目安」>本人の強い希望がある(飲み方の注意喚起を受け入れてもらいやすい)。咳嗽力がある。むせた時に、2~3回の咳嗽で喀出できる(むせが続かない)。唾液によるむせがない。RSST 2回以上、MWST 4点以上(随意的な嚥下反射が不十分でも、唾液でのむせがなければ、ある程度の量を取り込めば、嚥下反射が起きるという考え)。痰の増加がない。細いストローでの摂取の受け入れが可能、または一口量の調整が可能。一旦誤嚥性肺炎になっても回復が見込める体力がある(平行棒以上の歩行訓練を実施、リハ・食事・入浴以外にも車椅子離床しているなど)。現在、誤嚥性肺炎以外の要因でも発熱していない(尿路感染での発熱中であれば、誤嚥性肺炎との原因の切り分けができないため)。<その他>CRPが「基準値以下(0.3以下)」。少なくとも「上昇傾向でなく、1.0以下(これはあくまで目安)」ただし、回復期では頻回な血液検査をしていないことが多い。最終の血液検査で0.9となっていても、実際は現在0.4かもしれない。また、尿路感染の改善後や、関節の炎症などでも上がっていることもあるため、CRPを誤嚥だけの目安にするのは難しい。咳嗽力の目安 最大呼気流量が、「240ℓ/分 以上:自己喀痰が可能」「100ℓ/分 以上:気管吸引が不要」「100ℓ/分 未満:気管吸引が必要」VF検査では、10~20回に1回のむせは出現しにくい。
2020年05月07日
コメント(4)
-
リハスタッフが病棟で挨拶できない理由
リハスタッフが病棟で挨拶できない理由。習慣化していない、意識の問題、指導不足、挨拶をしている先輩が少ないなどの問題はあるとして。朝、病棟に行った時、例えば、 ①1番目に行く患者のことを考える(リハ内容、移乗方法・・)、 ②あのNsに会ったら、○○を伝えよう ③○○PTにあったらリハ時間調整しようなど・・・など、複数のことを考えていることも少なくない。この時点で、頭の中がフル稼働している。この状況で、すれ違う患者・Nsに挨拶をしていくとなると、他の思考が脱落しかねない。挨拶ができないのは、こんな理由もあるかもしれません。習慣化するまでは、思考を切り替えたり、配分性注意が必要なため、大変だと思います。いずれにしても、挨拶は必要であり、また、患者サービス、病院の雰囲気向上を考えれば必須のことです。時間を要してでも実施すべきだと思います。新入職として入った時から習慣化できるよう指導していくことが、その後の負担軽減になると思います。挨拶しないと「-10点」、挨拶は当たり前だから挨拶しても「0点」の評価では、今挨拶できていない人にとっては、習慣化しにくいかもしれません。それなら、①病棟・職場の雰囲気を盛り上げる、②患者・家族へのサービス向上を目的にした”戦略的な(意図のある)挨拶”と考えて、挨拶できることは、「+5点」という意識で取り組むのはどうでしょうか。
2020年04月07日
コメント(0)
-

「リハビリテーション管理・運営実践ガイドブック」を読んで
「リハビリテーション管理・運営実践ガイドブック」を概ね読みましたので、印象に残った点など記載します。買って正解でした。・リハビリテーションにおける業務管理・教育・労務管理・実習・リスクマネジメントなど、幅広い内容が掲載されている。・これを入門書として、深めたい場合は、更に専門書などを読めばよいと思われる。・リーダについて、「スタッフが大切にされいきいきと働いてこそ、マンパワーを十二分に効果発揮することができる。そのような職場には人が集まりやすい。スタッフに支えられて自分(リーダ)があることを肝に銘じる。リーダにとって、スタッフは大切な宝物である。」➡共観した。・リハ部門内でのストレス対策について、厚生労働省のサイトの案内もあり、参考になった。・学術活動への参加が、具体的に何に効果があるのか、何を目的に行うかがわかり、考えの整理ができた。・これからの臨床実習指導方法は、参考になった。・ラダーの考え方は示されていたが、具体的な項目の内容も記載があればよかった。リハビリテーション管理・運営実践ガイドブック [ 金谷さとみ ]
2019年01月27日
コメント(0)
-
気管切開カニューレ(高研)の研修
地域の気管切開カニューレの勉強会に参加してきました。高研(コーケン)の方が講師でした。簡単に学んだことをまとめておきます。(私としては、ほとんど知っている知識でした)<学んだこと>「コーケンマイスターブレス」は、カフ圧インジケータ付きで、シリンジでカフ圧が調整可能。(カニューレに簡易なカフ圧計がついれいる)カフは、必要に応じて1日1~2回5分程度のカフのエアーをほんの少し抜くことにより、粘膜の血流阻害を軽減させることができます。(カタログより)適正カフ圧は一般的に20mmHg前後がよいとされている。カフは気管への固定を目的としていません。外径 OD:Outer diameter 内径 ID:Inside diameter<その他Q&A>コーケンネオブレススピーチタイプの内筒が2~3年前に比べて、ロックが甘く、抜けやすくなった印象だが?➡形状や規格などは変わっていないとのこと。コーケンネオブレススピーチタイプのワンウェイバルブの取り付け時に、きついことがある印象だが?➡形状や規格などは変わっていないとのこと。カニューレ抜去のプロトコルが書かれている文献はありますか?➡わかりませんとのことでした。標準化されたカニューレ抜去の手順はないですが、「ビジュアルでわかる早期経口摂取 実践ガイド」には、数ページに渡って、その病院でのカニューレ抜去+嚥下訓練の流れが掲載されており、私も参考にしています。ビジュアルでわかる早期経口摂取 実践ガイド
2019年01月21日
コメント(1)
-
車椅子離床して注入を実施
JCSII桁~III桁の経鼻経管栄養管理の患者について、車椅子(標準型またはリクライニング車椅子)で離床をしながら注入を行うことのメリットを考えてみました。<今回想定している状況>・脳血管疾患などの急性期~亜急性期・意識レベルがII桁~III桁のため、直接嚥下訓練は開始できない・麻痺は重度で、移乗は中等度~全介助レベル・病巣の大きさやそれまでの経過から、大きな改善(意識レベルがI桁になるなど)は見込めない。<メリット>廃用症候群の予防としては、体位交換、移乗の機会が増えることにより、・拘縮予防・姿勢変更による心負荷の増加・腸の運動促進・移乗時にわずかでも下肢へ荷重がかかる車椅子座位をとることにより、・抗重力筋が使用される(舌骨上筋群も抗重力筋といえるか)・体幹・頸部の筋力向上による姿勢安定・座位の方が咳がしやすい・下肢が下がる姿勢のため、心負荷の増加・視覚、聴覚、触覚などへの刺激入力の増加<デメリット>・注入時に車椅子移乗する介助量・作業量に比して、目に見える機能の向上が見込めない。(その病棟の総合的な費用対効果を考えると、他の患者のケアに時間を当てたほうが良い)・心負荷、身体機能への負荷があるため、ベッド上に比べて、必要なリスク管理が増える。<その他>・ベッド上の注入でも角度を上げれば、リクライニング車椅子とほとんど同じではないか?→車椅子では下肢が下がることにより、ベッド上に比べ、心負荷がかかる。 逆に、ベッド上の下肢が下がらない状況では、心機能の廃用が起こる可能性がある。→例えば、背面を45度に設定する場合、「ベッド上45度では結構高く感じる」が、リクライニング車椅子の45度は「かなりリクライニングしている(倒している)ように感じる」。これらにより、ベッド上ではベッド角度は低くなりがちである。(※ベッド45~60度では褥瘡発生リスクが高くなるとしている文献もある)
2018年11月30日
コメント(0)
-
Twitterやっています
Twitterやっています。https://twitter.com/haru1193
2016年07月05日
コメント(0)
-
「モニター・機器が少ない状況下におけるフィジカルアセスメントと早期離床」に参加
日本離床研究会の講座「モニター・機器が少ない状況下におけるフィジカルアセスメントと早期離床」に参加してきました。キーワードなど、個人的なメモです。<苦しい>◆離床時の「苦しい」はまず、呼吸、循環を疑う。◆キャピラリーリフィリングタイム(末梢血管再充填時間) 爪床部を押して、爪の色が元に戻るまでの時間。3秒以上かかる場合は、末梢循環不全、ショックの兆候。◆循環障害で、体重増加が1日2kg(経験的には1~2kg/日)の増加は心不全を疑う。 慢性心不全治療ガイドラインより<意識レベル>◆意識とは自己及び外界を認識している状態。要素は「覚醒」と「認知」。◆意識のメカニズム上行網様体賦活系(覚醒)→視床下部賦活系(中継点)→大脳皮質または皮質下(認識・認知)◆鎖骨を叩くと骨刺激が脳に届きやすい。<痛み>◆高齢者・糖尿病・ステロイド投薬では、痛みに対して鈍感になっている場合がある。◆転倒にて骨折した場合、転倒した原因も調べる。◆痛みと原因場所) 限定的→骨関節系、このあたり→内臓系時) 運動時→骨関節系、安静時→内臓系◆脈拍が収縮期血圧より高値の場合は、プレ・ショックの兆候。<けいれん>◆けいれんは、止めようとして押さえないこと。けいれん時に刺激を与えないこと。(けいれんが誘発されるため)<疲れ>◆感染症による疲れの離床目安体温が38度以上、または、ベースより1.5度以上上昇では控える。デルタ心拍数20のルール→熱が1度上がった時、脈が20以上上がると感染症の疑い。<めまい・失神>◆長期臥床では軽い脱水の可能性が高い体液の上方シフト→圧受容器を刺激→体液を過剰と判断→交感神経抑制・利尿ホルモン分泌→利尿促進◆失神の発症脳の血流が瞬間的に遮断されて起こる。<むくみ>◆心原性の浮腫は下肢に出現しやすい。◆両下肢の浮腫は心原性、片側の浮腫は静脈病変を疑う。◆肝臓由来の浮腫は全身性、腎臓由来のものは眼瞼・顔にでやすい。
2016年07月02日
コメント(0)
-
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会に参加
日本呼吸ケア・リハビリテーション学会 第2回近畿支部学術大会に参加してきました。キーワードなど、個人的なメモです。◆経皮的動脈血酸素飽和度測定(1日につき)30点◆酸素療法ガイドライン(2006)◆E-SAS評価 1 生活の広がり(LSA:Life-Space Assessment) 2 ころばない自信(転倒に対する自己効力感尺度) 3 自宅での入浴動作 4 歩くチカラ(TUG:timed Up & Go Test) 5 休まず歩ける距離 6 人とのつながり(Lubben Social Network Scale-6)◆IPAQ 身体活動量評価 身体活動度を3段階で評価する質問法。◆HLC Health Locus of Control尺度◆JHLC HLCの日本語版◆LINQ Lung Information Needs Questionnaire 患者さんがCOPDの情報をどのくらい必要としているかの傾向を測定するもの。 病気の理解度、薬、自己管理、運動、栄養の項目がある。◆新しい呼吸リハビリテーションの定義 ATS/ERS呼吸リハビリテーションとは、徹底した患者のアセスメントに基づいた包括的な医療介入に引き続いて、運動療法、教育、行動変容だけではなく、慢性呼吸器疾患患者の精神心理的な状況を改善し、長期の健康増進に対する行動のアドヒアランスを促進するために患者個々の必要性に応じた治療が行われるものである。◆MCIの4つのタイプの内、COPDは「非健忘型MCI 単領域障害」タイプが多い。◆NRADL 長崎大学ADL評価表。食事、排泄、整容、入浴、更衣、病室内移動、病棟内移動、階段昇降、外出・買い物の10項目。それぞれの達成度を動作速度、息切れ、酸素流量から測定される。◆SGRQ COPDの疾患特異的な健康関連QOL評価尺度。76項目の質問紙。症状、活動、衝撃の領域と総スコアから構成されている。活動は呼吸困難感や身体機能を表わし、衝撃は精神心理的社会要因に関連した領域と考えられている。◆HADS 身体疾患患者の抑うつと不安をスクリーニングするために開発された自己評価式質問紙◆はがくれ呼吸リハ評価表
2016年06月29日
コメント(0)
-
第17回日本言語聴覚士学会に参加
第17回日本言語聴覚士学会 in 京都に参加してきました。キーワードなど、個人的なメモです。◆「P1-1-05 当院回復期病棟設立からの活動報告と部門間における情報共有の重要性」急性期―回復期のSTの連携に関する発表。回復期は3か月以内の入院を目安にしている。点滴があっても早めに急性期から回復期へ転棟となることも多い。急性期と回復期のSTミーティングで回復期対象となる患者の情報共有を早めに行っている。◆CBA 認知・行動アセスメント⇒森田秋子・石川 誠・金井 香・牧迫飛雄馬 2014 認知機能を行動から評価するための「認知関連行動アセスメント」の開発 総合リハ,42,877-884.また、内容を詳しく見てみます。◆「1-4-18 軟起声発声を行い発話明瞭度に変化が生じた痙性麻痺性構音障害の一例」 この症例での音響分析では、通常発話に比べて軟起声発声を行うことで無声区間とVOTの延長を認め、子音が強調されていた。◆「2-6-05 高齢者肺炎症例に対する摂食嚥下機能評価MASAの有用性の検討」 MASA(マーサ) 177点以下は嚥下障害 170点以下は誤嚥のリスクあり。 148点以下は30日以内の肺炎再発率アップ◆「2-2-03 唾液腺上皮膚のアイスマッサージ施行方法に関するいくつかの検討」ALS症例における唾液腺のアイスマッサージの効果の検証(一症例)本人の印象で評価。アイスマッサージは左右3分ずつ実施。アイスマッサージを毎日続けると、唾液は減少する。2~3日空くと唾液が増える。⇒この症例に限って言うと、効果はあるように思われます。かつ、毎日行うことが重要のようです。◆「2-6-06 高齢者肺炎患者の経口摂取獲得に必要な評価項目の検討」経口摂取獲得とMASAの分析では、食塊クリアラス、咽頭相、舌の筋力、失語症が重要であると考えられた。◆「2-3-19 当院における最大舌圧と食形態の相関について」常食摂取者は30kPaに近い舌圧が必要となることが示唆された。◆JSS-E 脳卒中情動障害スケール JSS-D 脳卒中うつスケール JSS-DE 脳卒中感情障害(うつ・情動障害)スケール同時評価表 ◆NHCAP(エヌエッチキャップ) 医療介護関連肺炎◆FOIS(フォイス)7段階◆FILS(フィルス)藤島先生の摂食・嚥下レベル 10段階◆等尺性膝伸展筋力
2016年06月22日
コメント(0)
-
離床研究会学術大会に参加
日本離床研究会 第6回全国研修会・学術大会に参加してきました。キーワードなど、個人的なメモです。<人工呼吸器関連>◆無気肺(アプニア)では、PEEPを上げる。◆PEEPの目安 気管切開 3~5cmH2O 経口挿管 5~8cmH2O 肺水腫・肺胞出血 10cmH2O 15cmH2O以上なら、モードの変更が必要。◆PEEPを上げると、胸腔内圧が上昇し、血圧が低下する。◆FiO2は、0.6以下なら安全という報告あり。 値が上がるほど、肺胞が破壊される。 値が上がると、吸収性無気肺を生じる。◆出納バランスで、+バランスだと、肺に水が溜まる恐れがある。◆利尿剤(ラシックス) 作用:利尿、うっ血による息切れ防止、浮腫の軽減 副作用:低カリウム血症◆呼吸パターン 吸気しにくい時は、胸鎖乳突筋が浮き出ることがある。 気道狭窄により、呼気しにくい時は、腹筋収縮を認め、呼気が延長することがある。◆ICU-AW(ICU関連筋力低下)では、横隔膜も薄くなっていることが考えられる。◆通常は、座位であれば、横隔膜が下がり、一回換気量が増加する。◆人工呼吸器の波形 異常波形(痰貯留、結露) プレッシャー波形やフロー波形で評価する。 波形がギザギザになる。 異常波形(リーク) ボリューム波形にて評価する。 呼気波形が基線に戻らない。◆RASS 沈静スケール(+4~-5)◆例えば、RASSが0か-1で、換気量低下、呼吸数上昇なら、病状が悪く、疲弊要素があることが考えられる。 ⇒リハでは、負荷量を吟味、サポート的な介入が必要。◆例えば、換気量多く、呼吸数上昇なら、興奮やストレス、痛みなど考えられる。<早期離床>◆ICU-AWの患者の8割に横隔膜の機能不全が起こっていた。◆DVTのガイドライン(米)が出来ている。 Dダイマーが下がるまで安静は× 下腿静脈フィルターがあれば離床し、 なければ、抗凝固法の種類によって判断する。◆離床チームの対象患者の選定に、B項目を利用することもある。◆Bakhruによると、以下の項目が早期離床と関連している。「早期離床のプロトコルがあること」、「リハビリスタッフの介入があること」、「鎮静プロトコルがあること」、「多職種による毎日のラウンドがあること」、「患者のゴールが書かれていること」など。 ⇒ラウンドでは、患者のゴールを多職種間で共有する機会となる。 <褥瘡、栄養>◆低栄養は在宅における「全褥瘡」、「重症褥瘡」に最も強く関連する因子。◆血液検査の値のひとつの目安(下記の値より低いと褥瘡が重度) アルブミン 3.0 ヘモグロビン 10 総リンパ数 1500◆栄養介入した群では、褥瘡の創サイズの改善効果あり(特に巨大褥瘡)
2016年06月18日
コメント(0)
-
「失語症の回復における大脳対側半球の役割について」を読んで
担当患者さんで、左脳梗塞で失語症を呈し、約1か月後に、右前頭葉の脳梗塞となり、失語症状が悪化した方がいました。以下の文献を読んでみました。「失語症の回復における大脳対側半球の役割について」五十嵐浩子ほか, 高次脳機能研究24(4):353~359, 2004以下は個人的なメモです。◆失語症の機能回復に関わる機序(説)1.左半球損傷部位周辺の部分的な機能回復あるいは再構築説2.反対側右半球内における言語野対称部位の活性化説3.発症後早期の回復には左半球の機能回復が関与し、その後の長期にわたる回復には反対側右半球の機能回復が大きいとする二段階説◆左半球損傷による失語症→8年間の機能回復→再発による右半球損傷で、失語症状の著しい悪化をした症例。◆再発により、左半球に新たな病巣や脳血流の低下も認められなかった。◆しかし、失語症状の重篤な悪化を認めた事実は、再発以前の言語機能において反対側右半球が何らかの役割を担っていたことを裏付けるものではないかと考えられる。
2016年03月28日
コメント(0)
-
「医療機器を活用した嚥下障害の評価と治療アプローチ」に参加
関西摂食嚥下勉強会「医療機器を活用した嚥下障害の評価と治療アプローチ」に参加しました。表面筋電図のデモンストレーションでは、挺舌、舌の挙上、開口訓練などで、舌骨上筋群が働いていることが見てわかり、自分のモチベーションアップになりました。以下は個人的なメモです。◆咳反射の評価として、咳テストを用いる。目的)咳の惹起性(気道防御の感受性)を評価する。方法)超音波ネブライザを用い、1%クエン酸生理食塩水を1分間吸入。判定)咳が1分間に5回以上誘発される:正常(陰性)咳が1分間に4回以下:異常(陽性)解釈)陰性なら、ムセを指標に直接嚥下訓練が進められる。⇒陽性の時の対策はどのようにしたらよいのでしょうか。(感覚自体を改善させる方法?)また、調べてみます。◆舌圧の評価◆舌圧測定器を用いて頬筋を測定する。(測定値は標準化されていませんが、訓練効果を見ることはできると思います)歯を咬合した状態で、頬の内側と歯の外側の間にバルーンを挟み、バルーンをつぶす動作をする。これを訓練に用いることも可能。食塊の破砕や咀嚼時には、舌と頬の働きによって、食塊は臼歯咬合面に保持される。⇒舌の運動だけではなく、頬の運動も重要。◆口唇閉鎖力の測定◆咬合力の測定◆表面筋電図表面筋電図を舌骨上筋群で使用し、訓練中のバイオフィードバックとして用いる。⇒デモンストレーションにて、挺舌、舌の挙上、開口、メンデルゾン手技、おでこ体操などで、舌骨上筋群が働いている様子が、よく確認できました。これが使用できれば、訓練効果はアップすると思われました。(残念ながら、表面筋電図は当院にはありませんでした)◆電気刺激治療バイタルスティム、ジェントルスティムの紹介。◆開口力の測定
2016年03月24日
コメント(0)
-
「簡易型舌圧測定装置を用いる最大舌圧の測定、『顎口腔機能の評価』」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「簡易型舌圧測定装置を用いる最大舌圧の測定、『顎口腔機能の評価』」、津賀一弘、日本顎口腔機能学会、41-44、2010≪簡易舌圧測定装置(ALNIC社製試作機TPS-350)を使用≫<概要>◆舌の能力の数値化を目指して、簡便な舌圧測定装置を開発した。◆Utanoharaら(2008)の最大舌圧測定値より、目安(試案)を示す。年齢別最大舌圧の目安成人男性(20-59歳) 35kPa~成人女性(20-59歳) 30kPa~60歳代(60-69歳) 30kPaは欲しい70歳以上 20kPaは必要
2016年03月23日
コメント(0)
-
文献「Standard values of maximum tongue pressure・・・」
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。他の文献中に記載されていた内容です。Utanohara, Y., Hayashi, R., Yoshikawa, M., Yoshida, M., Tsuga, K., Akagwa, Y. : Standard values of maximum tongue pressure taken using newly developed disposable tongue pressure measurement device,Dysphagia,23:286-90,2008≪簡易舌圧測定装置(ALNIC社製試作機TPS-350)を使用≫<概要>◆856名の最大舌圧を測定した。年齢別最大舌圧成人男性(20-59歳) 45±10(kPa)成人女性(20-59歳) 37±9(kPa)60歳代(60-69歳) 38±9(kPa)70歳以上 32±9(kPa)
2016年03月16日
コメント(0)
-
「要介護高齢者の食事形態と全身状態および舌圧との関係」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「要介護高齢者の食事形態と全身状態および舌圧との関係」津賀一弘ほか、日本咀嚼学会雑誌、14:62-67、2004≪簡易舌圧測定装置(ALNIC社製試作機PS-03)を使用≫<概要>◆介護保険施設の65歳以上の要介護高齢者66名を対象とした。◆食事形態は普通食、おかゆ、キザミ食、ミキサー食の4群に分けて検討した。◆ADLの低下とともにミキサー食が有意に増えていた。◆痴呆が高度になるにつれて食事形態も有意に軟らかいものへと移っていた。◆ADLと痴呆の影響を除いたうえで、舌圧と食事形態との間に有意な関連性が認められた。◆食事形態の選定基準として、ADLや痴呆の程度のほかに、簡易的な口腔機能評価として最大舌圧を利用できる可能性が示された。(各食事形態での最大舌圧はグラフのみ示されており、数値は未掲載)
2016年03月15日
コメント(0)
-
「「高齢者ソフト食」摂取者の食事形態と舌圧の関係」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「「高齢者ソフト食」摂取者の食事形態と舌圧の関係」津賀一弘ほか、日摂食嚥下リハ会誌9(1):56-61、2005≪簡易舌圧測定装置(ALNIC社製試作機PS-03)を使用≫<概要>◆介護老人施設の65歳以上の61名を対象とした。◆食事形態とADL、HDS-Rならびに最大舌圧の間には有意な関連性を認めた。◆HDS-Rと最大舌圧との間には有意な正の相関が認められた。これは、HDS-Rの低いものでは測定指示がうまく理解できず、それが原因で舌圧が低下している可能性が考えられた。◆HDS-R 20点以上の被験者について、食事形態と最大舌圧の関係をみたところ、最大舌圧はソフト+常食群は平均20.9kPa、ソフト群は6.1kPaとなり、有意な相違があった。
2016年03月14日
コメント(0)
-
「入院患者および高齢者福祉施設入所者を対象とした食事形態と舌圧、握力および歩行能力の関連について」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「入院患者および高齢者福祉施設入所者を対象とした食事形態と舌圧、握力および歩行能力の関連について」田中陽子、日摂食嚥下リハ会誌19(1):52-62、2015≪簡易型舌圧測定器(JMS製)を使用≫<概要>◆舌圧と食事形態の関連性、握力や歩行状況と食事形態の関連性を調べた。◆病院・施設入所者201名を対象とした。◆常食摂取群の舌圧は五分食摂取群、刻み食摂取群、ミキサー摂取群およびゼリー摂取群と比較して有意に高く、五分食摂取群はゼリー食摂取群と比較して有意に高かった。このことより、五分食摂取群以下の調整食摂取群は常食摂取群と比較して有意に舌圧が低く、常食を摂取するためには、ある一定以上の舌圧が必要であると考えられる。◆舌圧が25kPa以上あればほぼ常食摂取可能と考えられる。20kPa未満では食事形態を調整する必要のある者が多かった。◆舌圧と歩行能力が、食事形態を判断する際の参考になることが示唆された。◆舌圧が食事形態決定に際して、有効な指標であることが示唆された。
2016年03月13日
コメント(0)
-
「施設入所高齢者にみられる低栄養と舌圧との関係」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「施設入所高齢者にみられる低栄養と舌圧との関係」児玉実穂ほか、老年歯学 第19巻 第3号 2004 ≪広島大学で開発された簡易型舌圧測定装置を使用≫<概要>◆特別養護老人ホームに入居する要介護高齢者83名を対象。◆常食を摂取している者の舌圧は22.1±9.3kPa、調整食を摂取している者の舌圧は18.3±7.6kPaであり、統計的に有意な差がみられた。◆むせのある者の舌圧は15.2±7.2kPa、むせのない者の舌圧は28.8±8.3kPaであり、統計的に有意な差がみられた。◆ADLと舌圧との関係に有意な相関を認めた。◆舌圧は運動速度および運動範囲の良否と関係を示した。◆これまで臨床で用いられてきた運動範囲や運動速度と今回定量的に測定された舌圧が有意な関係を示したことは、舌の運動機能を客観的に評価できる方法として舌圧の評価は有用であると示している。
2016年03月12日
コメント(0)
-
「「舌圧」という新しい口腔機能の評価基準が歯科医療にもたらす可能性」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「「舌圧」という新しい口腔機能の評価基準が歯科医療にもたらす可能性」医療機器として初めて承認された「舌圧測定器」と臨床応用 津賀一弘、GC CIRCLE No.139 2011-11 p28-34≪簡易型舌圧測定器(JMS製)を使用≫<概要>◆舌圧測定器の紹介、使用方法、舌圧値データ、症例の紹介。◆舌腫瘍の手術後、摂食・発音障害を認めた。治療用義歯の調整では、途中、舌圧を繰り返し測定しながら、口蓋部に即時重合レジンを筆積みした。3ヶ月間で舌圧は2.0kPaから8.4kPaに改善し、発音と嚥下も大きく改善した。また、日常生活において舌を鍛えるよう動機づけに役立てることができた。◆交通事故による上下顎前歯および舌の外傷例。リハビリにより、開始時には最大舌圧が2.0kPaだったが、約1年半後には20kPaまで改善し、口蓋部の食物残留は解消した。
2016年03月11日
コメント(0)
-
「高齢者の舌圧が握力および食形態に及ぼす影響」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「高齢者の舌圧が握力および食形態に及ぼす影響」中東教江、JOURNAL OF THE JAPAN DIETETIC ASSOCIATION Vol.58 No.4,2015 43-47≪簡易型舌圧測定器(JMS製)を使用≫<概要>◆70~89歳の一般高齢者(女性)21名と、病院・老人保健施設・ケアハウスに入院・入所している女性41名を対象。◆入院・入所者群で、加齢に伴い舌圧と握力の低下が見られた。◆握力において、きざみ食喫食群と常食喫食群で、有意な差が見られた。◆舌圧と握力には相関が見られたため、今後、対象者を増やすと、舌圧と食形態に関連が見られる可能性がある。◆全対象者において、舌圧が35kPa以上、または握力が20kg以上では、形態調整をしている対象者は見られなかったため、この範囲では常食を提供できる可能性が示唆された。
2016年03月11日
コメント(0)
-
「嚥下障害または構音障害を有する患者における最大舌圧測定の有用性」を読んで
舌圧測定器の有用性を調べるために読みました。「嚥下障害または構音障害を有する患者における最大舌圧測定の有用性-新たに開発した舌圧測定器を用いて―」武内和弘ほか, 日摂食嚥下リハ会誌16(2):165-174、2012≪簡易型舌圧測定器(JMS製)を使用≫<概要>◆本邦初の医療機器承認を取得した舌圧測定器を用いて、舌機能の定量的評価法としての舌圧測定の有用性について検証した。◆嚥下障害または構音障害を有する患者115名(障害群)と有しない患者29名(対照群)を対象とした。◆障害群の舌圧値は20.9kPa、対照群の舌圧値は28.5kPaと有意差を認めた。◆藤島の嚥下グレードと舌圧値との関連性が示唆された。◆舌圧値の低さと構音障害との関連は指摘できず、嚥下障害の有無との関連が強いと考えられた。◆舌圧値は、単に舌の上方への運動機能だけでなく、前方や左右に対する運動機能を含めた舌全体の運動機能を推定できる定量的指標となりうることが示唆された。◆JMS舌圧測定器で測定した舌圧値は、良好な再現性を示し、本器は、臨床上問題なく使用できることが明らかとなった。◆さらに、測定した舌圧値と従来の機能評価の関連性も指摘できた。◆すなわち、舌圧の測定が、従来の定性的評価を主体とする機能評価に、客観的で定量的な指標を与え、例えば嚥下障害等の評価において、本舌圧測定器が臨床上有用な測定ツールとなることが示唆された。
2016年03月11日
コメント(0)
-
舌圧測定器の導入に向けて
舌圧測定器の機器購入の申請のために作成したものです。結局、申請と伴に、この資料も使われたかはわかりません。何とか、導入したいです。<舌圧測定器とは>簡易型舌圧測定器(JMS製舌圧測定器:(株)ジェイ・エム・エス)は、舌の挙上の力を測定する装置である。ディスポーサブルのエアーバルーンを舌と口蓋部に挟み、舌を挙上させてエアーバルーンを押しつぶすことにより測定を行う。小型軽量であり、測定時の患者への負担も少ない。嚥下障害に対する訓練では、舌の運動機能や筋力の向上により、嚥下障害が改善したとの報告は多く認める。また、嚥下機能に関わっている舌骨上筋群の筋力増強には、これまで、頭部挙上訓練やメンデルゾン手技などが主に用いられてきたが、舌挙上訓練により、これらの訓練と同等以上に舌骨上筋群の筋力増強に効果があるとの報告も散見される。 患者の負担が少なく、短時間で定量測定ができるこの舌圧測定器の導入により、嚥下障害に対する訓練効果の向上が期待できると考える。また、食形態と舌圧値の関係性が示されている報告もあり、食形態選定における補助となると考える。<主な特徴と使用目的>◆舌圧の定量測定が可能。◆訓練経過における舌圧の変化が確認可能。これにより、患者の訓練に対するモチベーションアップにつながる可能性がある。◆バイオフィードバックを使用し、舌筋力増強訓練が実施可能。舌圧値を確認しながら、訓練の実施が可能。◆舌圧値により食形態の選定の補助となる。文献により、食形態と舌圧の関係が示されている。◆性別、年代別の基準値からの差を把握できる。◆研究発表にて、定量的な値を示すことができる。◆舌トレーニング用具(ペコぱんだ)のレベル選定の目安となる。<使用施設>第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会にて、JMS製舌圧測定器が使用されていると考えられる発表は17件あり、研究発表における舌の客観的指標として主要な測定機器の一つとなっている。全国では約1200台販売されている。(2016年2月の情報) <文献より>文献では、この舌圧測定器において、以下の記載がある。◆JMS製舌圧測定器は、信頼性、再現性がある。◆舌圧と以下の項目に関連が認められる。食形態、嚥下グレード、舌運動範囲、舌運動速度、むせの有無、流涎の有無、食べこぼしの有無、ADL◆舌の筋力増強訓練は、他の嚥下訓練(頭部挙上訓練、メンデルゾン手技など)以上の訓練効果がある可能性が示唆されている。
2016年03月11日
コメント(0)
-

失調の患者へのストロー付きボトル
失調の患者さんに対して、ストロー付きボトルで、とろみ茶を飲んでもらったケースがあったので、報告します。◆脳幹梗塞◆四肢・体幹に失調あり。起立は物的支持で見守り~軽介助◆嚥下障害あり。水分は濃いめのトロミ。食事は移行食(全粥、キザミ+トロミのあん)◆食事動作は、右手スプーンで、前半自己摂取も、後半は失調による食事動作の疲労でむせが増えるため介助◆発話明瞭度3レベル(痰が多く湿性嗄声で聴取しにくい)とろみ茶は、コップでは口唇からこぼれる。口唇閉鎖不全のためストローでは吸えない。よって、スープカップからスプーンで自己摂取してもらっていました。しかし、時折、スプーンで取り込む前にこぼれてしまったり、失調のため過剰に力が働くことがあり、動作での疲労もあります。そこで、以下のようなボトル+ストローを製作し、持ち手(右手)で握って出てくるようにしました。失調のため握力の調整は難しいですが、ボトルに適度な反発力があり、うまくいきました。取り込みも、スプーンに比べてストローの方が、口腔内へ入りやすく、摂取における疲労も少し減少したようです。【作り方】◆「ダイソー」のドレッシングなどをいれるボトルを使用◆ボトルの注ぎ口が細く、ストローは入らないため、ボトルの上部を1~1.5cmほど、ニッパで少しずつ切る。◆切りすぎると、ストローとの間が開いてしまい、空気がもれ、ボトルを押しても出てこない。◆ストローとの間に隙間がないようにする必要があります。◆ストローとのサイズを見ながら、少しずつニッパで切っていきます。ストローを合わせるときは、注ぎ口の下から入れます。◆下からストローを入れると、少しきつめでも入れることができて、隙間の調整がしやすいです。◆下からストローを入れるときは、ストローのジャバラ部分は伸ばして入れます。◆切り口はヤスリで削る。◆材料がそろっていれば、製作時間は、40~60分程度。ただ、ここに至るまでは、いろんなボトルを試したり、いろんなストローの長さや径のものを調達したりと、試行錯誤しました。同じ6mm径のストローでも、商品によって、微妙に径が違いました。上記の通り、微妙な径の違いで、空気が漏れたりするので、実際に使用していくストローで調整しました。このボトルで、濃いめのトロミ茶、カロリーメイトゼリーを摂取してもらっていました。
2016年01月06日
コメント(0)
-
回復期専従STの食事観察
回復期専従STの利点を生かして、食事場面観察の意義を考えてみました。これらは、回復期専従STが実施しなくても、リハ担当者や病棟看護師がすべき内容もあると思います。しかし、回復期専従STは回復期患者の代行も多く、回復期病棟にいる時間も長いので、効率的に出来ることはあると考えて、できるだけ多くピックアップしてみました。当院の回復期は60床で、概ね脳外科30人、整形外科30人です。食堂は2つに分かれており、30人が見守りフロア、20人が自立されているフロア、残りが経腸栄養や自室での食事となっています。この見守りフロアを見ています。下記の件は、その場で対処できることもあれば、看護師さんと協力して解決することもあります。また、リハ担当の意見が必要な場合や、そもそもPTさんやOTさんのフォローが必要なこともあります。いずれにしても、介入結果は担当リハに報告しています。 <姿勢の確認>◆体幹の傾き 麻痺側の筋力低下による麻痺側への傾き 健側の突っ張りによる麻痺側への傾き ⇒座位姿勢の調整、麻痺側の背中にクッションを入れるなど◆麻痺側上肢の位置 車椅子のアームレストから落ちていないか 麻痺側上肢は、膝の上(のクッション)に置いたほうがよいか、机の上に置いたほうがよいか。 または、車椅子用のテーブルを使用したほうがよいか。◆クッションの必要性◆車椅子の高さが机と合っているか。机が高すぎる場合は、車椅子用テーブルの使用も検討する。<食具の環境設定>◆角皿、滑り止めシートの必要性◆スプーン/箸の選択 麻痺側の利き手か、健側の非利き手のどちらを使用するか◆スプーンの形状 嚥下機能が不安定で一口量が多い場合は、小さめのスプーンの選択も考慮に入れる。◆トレーや食器はできる限り手前にセッティングした方がよいか。 失調の患者。 麻痺側の上肢操作が不安定のために取り込みまでにこぼれがある。 口唇閉鎖が不十分でこぼれがある。<摂食嚥下状況の確認>◆新患、食形態変更時、水分のとろみが外れた時などは特に確認する。◆取り込み時のこぼれ、咀嚼動作、ムセなどの確認◆一口量の調整の可否◆摂取ペースなど<食形態アップできるか>◆嚥下食の段階アップや常食へのアップ◆全粥⇒米飯への変更◆副食は、キザミ⇒粗キザミ⇒一口大⇒常食への変更の可否◆軟菜の制限を外すことができるか<左USNの対応>◆左側の忘れの確認、声掛け◆セッティング位置の考慮 右側にセッティングするか、中央へセッティングし認識を促すか<高次脳機能障害の影響>◆注意散漫となり、摂取が進んでいない場合 ⇒声掛けや環境設定(端の席、端の席で他の患者とは反対を向くなど)<リハ栄養関連>◆摂取量(認知症の患者さんで、毎回きっちり半分残す患者さんもいた)◆摂取時間(咀嚼や嚥下に時間を要しているか、摂取動作に時間を要しているか) 長くなって、摂取量が減少している場合は、半介助も考慮◆食べこぼし(実質の摂取量が少なくなっていないか)◆食べ残しの偏りの有無(嗜好品を聞いてみる)◆飲水量少なければ、お茶ゼリーを試してみるなど。<関連するADL>◆薬の摂取 1回~1週間配薬など 開封が必要か、手渡しや見守りが必要か◆義歯洗浄、歯磨き、うがいなどが自立できるか◆食後の混雑時の移動に注意できているか<その他>◆リハビリが時間通りに食道に戻ってきているか ⇒今は見ているだけです。◆看護師さん、ヘルパーさんの動き ⇒どんな作業をどういう手順で行っているのかを見ています。他部門の動きもある程度わかっていた方が、こちらも動きやすいことがあります。例えば、配膳、配薬まではとにかく忙しそうで、その後、数分は話しかけてもよい時間帯(と私は思っている)。歯磨きが始まると、介助の口腔ケア、歯磨きで水道へ誘導、トイレや病室への移動を介助と、この時間帯はかなり忙しそうです。◆病棟での食事介助の様子 ⇒姿勢、ペース、一口量など、より良い方法があれば、声を掛けます。 現在は、毎日介入いている訳ではありません。また、上記、すべての項目を見れている訳でもありません。今は、主に、どういうことができそうで、どういう効果があるか考えるために実施していますが、時間の捻出も考えると、「必要とする時間」と「効果」を上司に提案・説明していく必要があります。
2015年11月20日
コメント(0)
-

「STが診る呼吸って何?」勉強会に参加
地域のST勉強会「STが診る呼吸って何?」に参加しました。以下は、メモ書きです。 ◆横隔膜長期間の臥位では、内臓によって横隔膜が押し上げられ、横隔膜の可動域が制限される。横隔膜は、通常の呼吸では1~2cmの可動。深呼吸では10cmの可動。呼吸の一回換気量は、おおよそ400ml◆呼吸不全呼吸不全とは、呼吸機能障害のため動脈血ガス(酸素と二酸化炭素)が異常値を示し、そのために正常な機能を営むことができない状態血液ガスのデータは安静時の結果であるため、これが異常値なら、運動するリハの時は、より注意が必要。◆低酸素血症 動脈血中の酸素濃度が低下。(SPO2、PAO2の低下している状態)◆低酸素症動脈血中の酸素濃度は正常。末梢では酸素がうまく交換できない。例:貧血ではSpO2やSaO2、PaO2の低下はないが、血液中の酸素の絶対量は減っており、その結果、末梢組織に必要な酸素を運ぶことができない。例:狭心症では冠動脈が一部細くなっており、その先には血液が少ししか流れない。流れている血液の酸素分圧は正常でも、絶対量が少ない。そのため末梢組織は十分な酸素を受け取ることができない。◆ばち指 低酸素血症が持続した場合に起こりやすい。◆呼吸困難感の評価修正Borgスケール 運動中の主観的な呼吸困難を指標とする。BS5までが安全域。◆COPD 慢性閉塞性肺疾患[肺気腫] or、and [慢性気管支炎] (+気管支喘息)症状:労作時の呼吸困難、咳嗽、喀痰治療:禁煙、呼吸リハ(口すぼめ呼吸など)、薬、HOT病態:滴状心、肺野の透過性亢進、肺コンプライアンスが低下し呼気が困難となる(1秒率70%以下)、樽状胸郭(呼気を吐ききるまでに次の吸気を行うため肺が大きくなる)、肺胞壁の破壊、気道壁が肥厚、気道に粘液が貯留◆COPDと嚥下障害の関係COPD患者は、嚥下障害は発症しやすい。口腔・咽頭期の嚥下障害を増悪⇒嚥下反射惹起遅延 輪状咽頭筋開大不全⇒口腔・喉頭蓋谷・梨状窩の残留、胃食道逆流症の有病率(+) (COPDでは胃食道逆流症を併発することが多い)⇒増悪時は誤嚥・嚥下反射遅延が増加仮説)COPDでは呼吸数が増加し、口腔内乾燥をきたす。また、痰が常にあり、刺激の閾値が上がっている可能性がある。そのため、嚥下障害を増悪しやすい可能性がある。◆通常、「呼気⇒嚥下⇒呼気」のパターンが、呼吸器疾患・心疾患では「呼気⇒嚥下⇒吸気」のパターンになりやすく、誤嚥が増加する可能性がある。コウメイ塾 http://ishikokkashiken.com/hypoxia/ を参照しました。「病気がみえるvol.4 呼吸器」を参照しました。病気がみえる(4)第2版 [ 医療情報科学研究所 ]
2015年10月31日
コメント(0)
-
第21回摂食嚥下学会に参加
第21回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会 in 京都に参加してきました。業務の関係で2日目のみ参加しました。◆「O35-4 喉頭蓋の反転運動に対して舌抵抗訓練は有効か?」喉頭蓋の反転角度が、舌抵抗運動で変化するかを調べた研究。対象は咽頭残留を認めた嚥下障害患者12名5-7名(細かい人数は忘れました)は喉頭蓋の反転が改善し、咽頭残留も減少した。という内容の発表でした。しかし、3名は逆に反転角度が減少したとのことで、原因の考察について質問がありました。明確な原因はわからないながらも、3名はいずれも、訓練後、喉頭蓋が咽頭壁で引っかかってしまうようになったため、反転角度が減少したとのこと。このため、訓練経過で咽頭収縮力が強くなったためという可能性もあるとのことでした。(あくまで推測)◆「O35-3 脳卒中に対する舌圧強化訓練の効果」舌圧強化プログラムが紹介されていましたが、この発表でのポイントは、1、最大舌圧の80%の等尺性収縮訓練を50回2、空嚥下時に舌圧測定のプローブを舌尖部で押し付ける舌圧パターン訓練発表者は2を強調されていました。舌圧を高める目的のひとつは、実際の嚥下時に舌圧が高くなるようにするということを考えると納得のいくものでした。その他としては、◆抄録題名集(冊子)と抄録(CD-ROM)に。(でも結局必要な部分は印刷しました)◆ポスター発表は、フリーディスカッション形式に。◆ポスターの場所が1か所でとても見やすかったですが、フリーディスカッションの時はすごい混雑。どうにか、スペースを広げてほしかったです。
2015年09月13日
コメント(0)
-
Twitterしてます
最近は、記事が書けていません。Twitterをやっています。まとめて、こちらに書こうと思っているのですが・・・。https://twitter.com/haru1193
2015年08月12日
コメント(3)
-
最近の業務
このところ、忙しい。というか、常に忙しい。自分の力量を把握せずに、いろんなことに手を出してしまうのが良くないか?集中力が足りないか?行動力が足りないか?やる気が足りないか?今、抱えている業務や勉強は、◆VF検査の評価法や見る観点を調べる◆回復期STとして、また、回復期専従メンバーとともにできることを考える。◆舌圧測定器を使用した舌筋力に関する研究テーマを考える。◆業務効率として、退院サマリーの形式を変更する。◆急性期の勉強を後輩STと一緒にする。◆リハ栄養を進める◆高次脳機能関連の課題を整理する。◆地域のST勉強会の症例発表準備一つ一つやっていけば、時間は十分あるはずなんですが、多くあると、どれから手をつけたらよいかわからなくなり、結局、全然作業が進んでいないという状況が続いています。
2015年06月23日
コメント(0)
-
回復期専従ST
今年度から回復期専従となりました。半月実施しての感想は、◆長期に関われるため、その分、リハビリの効果がより求められる。(もちろん急性期も大切なのは変わりないですが)◆リハ時間の調整がつきやすい。検査や病状変化などのイレギュラーが少ない。◆車椅子離床している患者さんも多いため、移乗動作などのADL動作の能力を把握しにくい。◆PT、OTの回復期専従と組むことも多く、共観の話がしやすいが、逆に、知識や考え方の広がりが少なくなってしまう可能性がある。 今後、回復期で実施していきたいことは、◆(自分としては)特に、高次脳機能障害に対する評価・訓練を再度勉強しなおす。◆患者状況を把握し、回復期STとして、何ができるか検討していく。◆システム的な効率化を図れる方法を模索する。◆高次脳機能障害に対する課題や、メモリーノート、一日の予定表など、共通で使用できそうな資料を整理する。◆活動量の推移(増加)や、嚥下機能も含む摂取状況を把握し、リハ栄養につなげる。◆病棟で実施してもらえるようなリハ要素を含んだリクレーションなどを病棟と協力して作成する。どこまで実現できるかわかりませんが、少しでも達成したいです。
2015年04月27日
コメント(0)
-

嚥下補助パッド(LEAP)
「VFなしでできる! 摂食・嚥下障害のフィジカルアセスメント」大宿茂 監修・執筆で、嚥下補助パッド(LEAP)が紹介されています。摂食嚥下時に、肩甲帯から頸部にかけて位置を調整する器具です。今まで(少なくとも私は)、喉頭挙上の障害は、舌骨・喉頭の下垂や舌骨上筋群の筋力低下などが要因として考えられていましたが、この嚥下補助パッドは、肩甲帯の伸展により舌骨下筋群(肩甲舌骨筋)が伸長し、舌骨を引き下げてしまっているという考え方のもとに製作されています。つまり、肩甲帯を屈曲位に、(頸部を屈曲位に)、姿勢調整できるような構造になっています。第19回日本摂食嚥下学会(2013年)の一般口頭でも発表がありました。「頸部・肩甲帯のアライメントが喉頭挙上に与える影響(1)~舌骨下筋群の伸長が喉頭挙上を阻害する~」(SO2-5-3-5)要約すると、喉頭挙上正常群と障害群を比較。障害群の方が、肩甲骨間距離が短く、肩甲骨の前傾角が小さかった(→肩甲帯が伸展していたということ)。また、障害群の方が、喉頭が下垂していた。リクライニング位では、姿勢調整に必要な筋活動が極度に減少するために、parking functionにより肩甲帯・頸部は伸展位となる。また、骨盤が後傾位となるために、腰椎の前彎減少、胸椎の後彎増強という運動連鎖を招き、結果的に頸部は伸展位となる。さらに、頸部伸展と肩甲帯伸展は肩甲舌骨筋や胸骨舌骨筋などの舌骨下筋群を伸長させ、喉頭挙上を阻害する。「頸部・肩甲帯のアライメントが喉頭挙上に与える影響(2)~嚥下補助パッドの試作と効果~」(SO2-5-3-6)要約すると、リクライニング位で、頸部と肩甲帯が伸展しないよう調整できる「嚥下補助パッド」を作成した。この嚥下補助パッド(LEAP)の購入有無は別として、直接嚥下訓練時には肩甲帯を屈曲位に姿勢調整することも考える必要があると思いました。この書籍に付属しているDVDには、嚥下補助パッドの使用時・未使用時でのVFの比較映像が掲載されています。この1例では効果があるように見えます。VFなしでできる!摂食・嚥下障害のフィジカルアセスメント [ 大宿茂 ]
2015年03月31日
コメント(0)
-
「脳卒中・・・検査・データ・・・判別講座」を受講
日本離床研究会の「脳卒中患者の疑問がスッキリ晴れる! とっておきの検査・データ「マル秘」判別講座」を受講しました。脳卒中における◆脳画像読影◆血液データ◆薬剤、t-PA◆症例検討についての2日間の講義でした。脳画像の読影は、5つの水平段を基本とし、単純化して読影していく方法でした。脳画像の読影は何度講義を受けてもしばらくすると忘れてしまうこともあり、今回、再度復習と新たな知識が得られ役立ちそうです。病院に帰ってから、早速、新患の読影に役立ちました。血液データは、重要なデータに絞っての解説で、復習になりました。薬剤は、元々少し勉強していたので、復習と新たな知識が少し得れました。t-PAは当院でも使用しているので、興味深かったです。統一見解はないものの、ある程度の離床基準を示してもらえ、今後はこれを参考にしたいと思いました。
2015年03月28日
コメント(0)
-

書籍「摂食・嚥下障害のフィジカルアセスメント」
書籍 「VFなしでできる! 摂食・嚥下障害のフィジカルアセスメント」大宿茂 監修・執筆内容がわかりやすく、特に新人STにお勧めです。特徴は、◆データに基づいた記載もありますが、筆者の臨床経験からのような記載もあり、役立ちます。◆臨床の摂食嚥下評価・訓練で必要な項目が広い範囲で網羅されていると思います。姿勢、誤嚥、情報収集を含めた初期評価の方法、嚥下病態別の具体的なリハビリ方法、栄養評価などなど。◆細か過ぎず、臨床で必要な知識が、丁度いいレベルで記載されていると思います。新人でないSTの方にはもしかして物足りないかもしれませんが、私は今までの知識の総ざらえと、新たな発見もあったので、良かったです。「第3章 体位と喉頭挙上障害」では、嚥下補助パッド(LEAP)が紹介されています。「第7章 原因疾患別対応」では、脳血管障害、パーキンソン病などの嚥下障害の特徴や対応について、端的に記載されています。DVDでは、VF(頸部聴診含む)や訓練方法の映像が掲載されています。VFなしでできる!摂食・嚥下障害のフィジカルアセスメント [ 大宿茂 ]
2015年03月25日
コメント(0)
-
「0度仰臥位法」の適応患者
第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術集会でのポスター発表にて、「0度仰臥位法」が紹介されていました。現在、当院で対象となりそうな、送り込み障害の患者さんがいます。適応できるか、STスタッフで検討中です。「0度仰臥位法」とは、嚥下時の姿勢の一つで、ベッドアップを0度、頚部前屈位にした姿勢で行い、主に送り込み障害の患者が適応となります。以下は、学術集会での福村先生の発表の要約です。『0°仰臥位での経口からのアプローチ~食塊移送不全患者への導入を経験して~』 福村直毅【対象】VFで、「0度仰臥位、頸部屈曲20~30度」で経口摂取可能と判断した2症例(脳梗塞、パーキンソン病)。【0度仰臥位の適応】◆頸部回旋困難◆食塊移送不全あり◆一定量の食塊で嚥下反射が惹起すること【まとめ】30度仰臥位以上で食塊移送不全やムセを認めた場合でもVF透視下ではあるが、条件が整えば「0度仰臥位」により経口摂取継続が可能であることが示唆された。※「頸部回旋困難」とは、おそらく、一側嚥下や側臥位法+頸部回旋が困難という意味だと思います。『0度仰臥位での経口摂取』 福村直毅【緒言】2010年に「0度仰臥位」で経口摂取する方法に気づいた。適応症例が100例を超えたので報告する。【嚥下機能の適応】◆口腔からの送り込み障害がある。◆嘔吐や食道咽頭逆流の明らかなリスクがないこと。◆上咽頭逆流がないか軽度であること。◆咽頭残留が少ないこと。【身体機能の適応】◆体幹機能が低下していて座位が不能な症例。◆ギャッジアップ時に姿勢が崩れる症例。◆体幹が緊張して嚥下機能が有意に低下する症例。【利点】◆姿勢保持の重点である頚部前屈の管理に集中できる。◆姿勢介助が楽にできるため在宅や施設において介護負担軽減が期待できる。
2015年03月08日
コメント(0)
-
「リハ栄養学術集会」に参加 その3
第4回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会(in 名古屋)に参加。その3です。今回の口演、ポスター発表の概要です。◆栄養状態と身体機能・嚥下機能との関連性の研究 ⇒相関や関係性あり◆リハと栄養管理を行うことでADLがアップした症例や、複数人数を対象とした発表。 ⇒しかし、栄養管理の未介入例と、リハ栄養管理をした例とを比較した発表は見られず。◆回復期でのリハ栄養の活動報告◆リハ栄養の意識調査◆体組成モニターによる筋肉量増加のモニタリングなどがありました。やはり、リハ栄養管理を「実施した群」と、「実施していない群」を比較するのは難しい。リハ栄養を開始した後では、「しない群」を作るわけにもいかず。かといって、リハ栄養を開始していなければ、そもそも、このような発表はされない。
2015年01月17日
コメント(2)
-
日本ST協会の「基礎・専門プログラム」修了証
日本言語聴覚士協会の「基礎プログラム修了証」「専門プログラム修了証」が届きました。これだけでは、特に何もないのですが、とりあえず、少し達成感です!認定言語聴覚士になるための講座の受講資格が得れただけで、現状では、来年度、受講するかも決めていません。症例報告もあり、内容としては厳しいという話も聞きます。修了証に至るまでに、何度も講習会や学会に行き、受講票はいっぱいになりましたが、それに費やした時間や費用に見合うだけの勉強ができたか?、臨床に活かせているか?というと、感覚的には1/3~半分程度でしょうか。学会参加では、新しい情報の収集や、STとして刺激を受けた場として、役立ったと思います。また、学会発表、地域の症例発表では、自分の臨床などをまとめ、見直すきっかけとして、大変役立ちました。無駄にならないよう、復習もしていきたいです。
2015年01月14日
コメント(0)
-
ディサービスでの勉強会
以前、ディサービスの施設の知り合いのスタッフから、言語聴覚療法についての勉強会をしてほしいと依頼を受けました。迷いましたが、自分の勉強のためとも思い、引き受けました。事前にいくつか質問事項をもらい、言語聴覚士の仕事内容や失語症、構音障害を中心に準備しました。いつものように、準備がギリギリになってしまい、だいぶ、かなり焦ってしまいました。(逆に、これを乗り越えられたら、自信がつくかなと考えながら)結局、STの先輩が以前、他の施設で勉強会を実施したパワーポイントを参考に作成していき、何とか形になりました。いや、形になったかわからない状態で、勉強会が開始となりました。スタッフの方20人ぐらいに対して、まず、講義を1時間弱行い、その後は質問を受けました。質問は少しかと思っていましたが、10件以上の質問を頂き、そのやり取りだけで30分ほどかかりました。非常に熱心に質問して頂けました。その施設や関連施設にはSTはおらず、失語症や嚥下障害で困っていることが多いようでした。あらためて、「失語症の方への対応」など、再考する機会となり、勉強になりました。
2015年01月12日
コメント(0)
-
「リハ栄養学術集会」に参加 その2
第4回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会(in 名古屋)に参加。その2です。今回の学術集会で、一番印象に残った講義は、高畠英昭先生の『脳卒中におけるリハビリテーション栄養』でした。内容は、「絶食により肺炎は予防できるのか?」がテーマです。先生の研究では、脳出血の患者で、◆通常の嚥下訓練を進めるコントロール群(RSSTやMWSTなど)と、◆早期から口腔ケア(ブラッシング、リンシング)、早期離床、早期経口摂取を行う介入群を比較すると、介入群の方が、経口摂取に至る割合が多く、肺炎の発症率も低かったとのことです。いきなり、この方法を取り入れるのは難しいですが、◆早期からの口腔ケア(口腔内への刺激、清潔にする) ⇒口腔ケアの頻度を増やす。間接嚥下訓練。◆早期離床を行うことは重要であることが再認識されました。病態や主治医の指示による絶食期間はありますが、いつでも、経口摂取訓練ができる準備をしておくことが大切だと思いました。「日本リハビリテーション栄養研究会」への入会は無料で、Facebookをされていれば、誰でも入会可能です。この講義資料は、リハ栄養のfacebookからダウンロードできます(現在は)。
2015年01月08日
コメント(0)
-
「リハ栄養学術集会」に参加 その1
第4回日本リハビリテーション栄養研究会学術集会(in 名古屋)に参加、および、発表してきました。参加者は626名だったそうです。今回のテーマは「リハビリテーション栄養と食支援~多職種で地域へ~」で、内容としても、「多職種、地域、急性期~在宅などの栄養連携」と「摂食嚥下」に関わるものが多かった印象です。発表は何とか無事終わり、いくつか質問もして頂けました。発表が終わってからも、質問してもらえ、発表内容に興味を持っていただけて良かったです。今回は、発表だけで終わりというわけではなく、今後のリハ栄養の活動へ向けての課題が多数見つかったので、これから検討し、1つでも実現していきたいと思っています。「日本リハビリテーション栄養研究会」への入会は無料で、Facebookをされていれば、誰でも入会可能です。来年度の学術集会は、広島で開催されます。
2014年12月21日
コメント(2)
-

「実践リハビリテーション栄養」を読んで
「実践リハビリテーション栄養 病院・施設・在宅でのチーム医療のあり方」日本リハビリテーション栄養研究会 監修、若林秀隆 編著を読みました(回復期の部分だけですが)。本当に、”実践”という感じで、病院・施設で具体的にリハ栄養をどのように運用しているか、詳しく書かれていて、大変参考になっています。「急性期」「回復期」「施設」「在宅」におけるリハ栄養実践が掲載されています。回復期は、3つの病院が掲載されています。リハ栄養実践に向けて、いろんな項目の知識が必要ですが、”実践”に向けて、私が今知りたいことは、◆スクリーニング(評価)の方法 MNA-SF、BMI、体重変化率、アルブミン、下腿周囲径、上腕周囲径、握力、歩行速度、下痢・嘔吐、褥瘡など、どの項目をどう組み合わせればよいか。◆対策の効果を示すデータは、どのようなものを蓄積すればよいか 下腿周囲径、上腕周囲径、握力、歩行速度、BMI、アルブミンなど、どの項目を使用すればよいか。 体組成分析機での筋量評価(高価なため、現実味が薄い?)。◆活動量に合わせたカロリーをどのように計算するか 最終目標体重と目標期間から計算し、1日の栄養付加を検討。 リハの活動量をメッツで計算して上乗せ。 体重増加したい場合は、200~400kcalを上乗せ。 など。◆カンファレンスの方法 リハの目標と栄養の目標から、どのような基準で、リハ活動量と摂取カロリーを検討しているか。【実践リハビリテーション栄養 [ 若林秀隆 ]
2014年12月10日
コメント(0)
-
摂食嚥下学会での「完全側臥位法」の発表数
第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会にて、「完全側臥位法」に関する報告数を調べました。◆「完全側臥位法」を主体とした発表◆経過の中で、完全側臥位法を用いている発表◆安静時の誤嚥予防として完全側臥位法を用いた発表これらを調べると、口演、ポスター発表を合わせて、15~16件ありました。(一症例での発表が多い)「完全側臥位法」を嚥下の姿勢として取り入れている施設が増えているように感じました。
2014年11月11日
コメント(3)
-
文献「重度嚥下障害患者に対する完全側臥位法による嚥下リハビリテーション」を読んで
福村直毅ほか「重度嚥下障害患者に対する完全側臥位法による嚥下リハビリテーション-完全側臥位法の導入が回復期病棟退院時の嚥下機能とADLに及ぼす効果-」総合リハ・40巻10号・1335~1343・2012年10月を読みました。完全側臥位群9名、対象群14名で比較すると、藤島の嚥下グレードとFIM利得について、完全側臥位群が高かったとの報告。(詳細は文献を参照して下さい)<完全側臥位法を試みるのは>偽性球麻痺で、◆咽頭の知覚障害により嚥下反射が遅れ嚥下前誤嚥がみられる症例◆咽頭収縮力の障害のために中下咽頭残留を来し嚥下後誤嚥がみられる症例<完全側臥位法の利点>◆直接訓練をより早期に開始でき、誤嚥リスクが小さいことで順調に訓練が進みやすい。◆咽頭側壁を底面とする空間に食塊を貯留できる。この空間は誤嚥を防ぐ貯留スペースとなる。◆貯留スペースは、座位の約3倍の容量がある(健常成人男性のMRIから作成したモデル)。◆嚥下前誤嚥でも、嚥下後誤嚥でも、気道に流入しにくく容量の大きい貯留スペースがあることで誤嚥を防止することができる。<完全側臥位法の運用>◆経口摂取が可能な全身状態であれば、完全側臥位法が絶対禁忌となる症例はない。◆完全側臥位における貯留スペースは、咽頭の解剖学的構造に重力が働くことで出現する空間である。そのために患者の頚部や咽喉頭の筋肉の協調運動の巧緻性や、介助者の慣れの程度にかかわらず、再現性が高いと考えられる。2014年9月の第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会でも、完全側臥位法の発表がいくつか見られました。これだけ、はっきり書かれてあると、対象となる患者さんがいたら、試したくなります。ただ、当院で開始する時には、まず、VFで確認してからになるでしょう。今まで、臥位(側臥位)でVF検査を実施したことがないのですが。
2014年10月26日
コメント(0)
-
文献「左半側空間無視患者に対する全般性注意訓練の有用性についての検討」を読んで
菅原光晴、鎌倉矩子、前田眞治 「左半側空間無視患者に対する全般性注意訓練の有用性についての検討」認知リハビリテーションVol.15, No.1, 2010を読みました。左USNの患者7 例に全般性注意訓練を施行し、抹消課題および車椅子操作時のUSN発生頻度を測定した報告。ベースライン期、介入期(全般性注意訓練実施)、フォローアップ期で評価を実施。それぞれ、改善した症例と改善しなかった症例あり。長期効果が得られた症例では、全般性注意訓練において、課題遂行時間が開始当初の35%以下になっていた。(詳細は文献を参照して下さい)◆全般性注意訓練Modified attention process training(MAPT)(豊倉ら 1992)を使用。1、持続性注意訓練2、選択性注意訓練3、変換性注意訓練4、分配性注意訓練から、構成されており、正答率が85%以上になれば、訓練課題を変更する。<この文献内で記載されていた左USNの訓練に対してのコメント>◆左USNのリハビリは多彩で、訓練した課題の成績が訓練後に向上することは知られている。しかし,訓練後にその課題以外のADLなどに汎化し、良好な改善が長期的に得られたという報告は少なく、決定的な治療法は模索状態である。◆机上課題で改善が認められてもADLへは汎化しにくい。理由は、机上課題は意識的に行われる課題であるのに対し、ADLは無意識的に行われる課題であることが挙げられる。また、机上課題は狭い空間で行う課題であるため1 つのことに集中しやすいのに対し、ADLは環境を取り巻くさまざまなものに注意を分配したり、切り替えながら行動する必要があり、それぞれの課題遂行において必要とされる注意機能の相違が関連しているものと推察された。◆全般性注意訓練が左半側空間無視の改善に影響する非空間的な注意機能に作用し、すくなくとも机上課題の左半側空間無視を改善させること、日常生活場面での左半側空間無視症状を改善させる場合があること、長期効果においては課題遂行における情報処理能力が大きく関与するものと考えられた。 <感想など>◆やはり、左USNに対しては、注意障害への訓練も重要である。◆MAPT(豊倉ら 1992)は一部が文献上で公開されているが、原本を入手する方法は?(少しずつ、自作も試みています)◆左USN患者への抹消課題への訓練では、まず、「ゆっくりでいいですから、見落としが無いように」と促す場合が多い。抹消課題の難易度を下げて、遂行速度を上げる課題の検討も必要。
2014年10月22日
コメント(0)
-
文献「高次脳機能障害を呈した外来患者の働きたいとの希望に沿う為に-病識低下で目標設定に難渋した患者への就労支援-」を読んで
酒谷景介、平澤政由、三上直剛 : 「高次脳機能障害を呈した外来患者の働きたいとの希望に沿う為に-病識低下で目標設定に難渋した患者への就労支援-」北海道作業療法 30(3), 30-34, 2013-12を読みました。ADLは自立。高次脳機能障害、情動障害の患者に対し、「目標共有の為の面談」と「目標指向型環境調整」を主眼に行い、就労に至った症例報告。症例:60代男性、くも膜下出血(開頭クリッピング術)退院後、家族からは「人が変わった」と。本人は、「自分はどこも悪くない」と。外来でのOTリハを週一回20分実施。<目標>◆患者の希望や要望を引き出す。◆自己洞察を促し内省できるようにする。<経過>◆リハへの要望が聴取できず⇒自己の行動や認知を客観視することで課題を認知しその対処スキルを獲得することが必要と考え認知行動療法的な関わりを実施。前頭葉機能障害に対しては構成課題や視覚探索課題を実施。◆「リハで何をやっているかわからない」と発言あり。⇒改めて目標設定が必要と考え、Occupational Self Assessment Revisedにて評価。⇒自己表現、自己責任、自己管理、課題への集中が問題領域とわかる。⇒患者から「上手く言いたいことを表現できない」など、自己に対する違和感、病感の存在などの自己分析が得られた。 また、「働きたい」との発言もあった。⇒シルバー人材派遣センターなどの一般就労を目標とした。◆注意障害などの高次脳機能障害が残存しており、一般業務を単独で実施することは難しいと判断。⇒福祉的就労の支援を共通目標とした。⇒役場担当者の協力と、OTからの情報提供や調整により、授産施設勤務が可能となった。臨床では、特にADLがある程度自立していると、自己の障害(高次脳機能障害)に気付きにくい症例を経験します。この報告では、「目標共有」や「自己洞察」が重要であるとのことでした。病識低下を呈する患者に対して、リハビリの目標が正しく理解されないまま、注意課題などを実施している場合もあるため、「目標共有」が重要であると再認識しました。
2014年10月20日
コメント(0)
-
文献「左半側空間無視患者に対する認知リハビリテーションの有用性についての検討」を読んで
菅原光晴、前田眞治「左半側空間無視患者に対する認知リハビリテーションの有用性についての検討」高次脳機能研究・第30巻 第1号・2010年3月を読みました。 ◆対象者は左USNを有し、 左USNへのアプローチと認知リハを実施する「実験群」13例と、 左USNへのアプローチのみ行う「対象群」12例◆訓練内容 週5回、12週間実施。「実験群」 認知リハビリテーション30分 ADL訓練や機能的作業療法、左USNへのアプローチを60分 病棟ADL訓練60分「対象群」 ADL訓練や機能的作業療法、左USNへのアプローチを60分 病棟ADL訓練90分 ※訓練時間を同じにするため、対象群の病棟ADL訓練は30分長い。◆認知リハビリテーションの内容(1日30分)「注意」「視覚構成」「思考」の活性化を目的としたドリル課題。具体的には、 Modified Attention Process Training(豊倉ら1992) フロスティッグ視知覚訓練学習ブック上級用(飯鉢ら1997) 「チャレンジワーク推理・思考」受験研究者(鈴木ら1990)◆結果BIT通常検査、BIT行動検査、CBS(日常生活での半側無視評価法)で評価を実施。有意差が出た期間はそれぞれ異なるが、いずれも、介入4週間後、フォローアップ期(実験後6か月後)には、実験群の方が有意に成績が高かった。◆考察USNに対する認知リハビリテーションは、USNの改善を早期に促進させ、訓練終了後も訓練効果を維持させる可能性が高いものと考えられた。臨床的には、左USNがある患者には、注意障害あり、構成障害も合併することが多いため、左USNに対する訓練のほかに、注意課題や図形模写課題など実施することが多いです。この文献を読んで、注意課題や構成障害に対する課題の必要性が再認識できました。また、フォローアップ期(訓練をしていない期間?)も、実験群のほうが優位に成績が高かったため、その意味でも、認知リハビリテーションは必要だと、自信がつきました。
2014年10月12日
コメント(0)
-

リハビリテーション栄養ポケットガイド
株式会社クリニコさんから、「リハビリテーション栄養ポケットガイド」 監修:若林秀隆を頂きました。栄養科の方から、いくつかまわして頂き、リハスタッフに配りました。32ページでポケットサイズ。リハ栄養のことがコンパクトにまとめられています。当院のリハスタッフでは、個人でリハ栄養に関する書籍を持っていない人が多いと思います。このポケットガイドのようにまとまった資料を手元おいてもらい、少しでもリハ栄養に関心を持ってもらえればと思います。
2014年10月09日
コメント(0)
-
文献「日常生活上での半側無視評価法 Catherine Bergego Scaleの信頼性、妥当性の検討」を読んで
長山洋史ほか「日常生活上での半側無視評価法 Catherine Bergego Scaleの信頼性、妥当性の検討」総合リハ・39巻4号・2011年4月を読みました。海外で開発された日常生活での半側無視の評価法であるCatherine Bergego Scale(CBS)を日本語訳し、信頼性などを検討した研究です。CBS観察評価法は10項目の観察項目からなり、それぞれ、0点「無し」~3点「重度の無視」までで評価し、合計0点~30点となります。点数が高いほど、半側無視が重度となります。また、「病態失認得点」の算出もできます。同じ10項目をインタビュー形式で患者本人に質問し、「自己評価得点」をつけます。セラピストが評価した「観察得点」から「自己評価得点」を引いたものが「病態失認得点」となります。 ⇒病態失認を数値化でき、経過を見るのに活用できると思いました。BIT、FIMとの相関や、検者間信頼性は概ね良好であったようです。また、CBS観察得点と病態失認得点には有意な相関があった。 ⇒つまり、半側無視が重度であるほど、病態失認が重度ということ。BITに比べ、CBSのほうが検出感度が高かったとのことです。<CBS評価項目>1 整髪または髭剃りの時,左側を忘れる.2 左側の袖を通したり,上履きの左を履く時に困難さを感じる.3 皿の左側の食べ物を食べ忘れる.4 食事の後,口の左側を拭くのを忘れる.5 左を向くのに困難さを感じる.6 左半身を忘れる.(例:左腕を肘掛けにかけるのを忘れる.左足をフットレストにおき忘れる.左上肢を使うことを忘れる.)7 左側からの音や左側にいる人に注意することが困難である.8 左側にいる人や物(ドアや家具)にぶつかる.(歩行・車椅子駆動時)9 よく行く場所やリハビリテーション室で左に曲がるのが困難である.10 部屋や風呂場で左側にある所有物をみつけるのが困難である.
2014年10月04日
コメント(0)
-
文献「注意機能トレーニングによる転倒予防効果の検証」を読んで
文献 「山田実「注意機能トレーニングによる転倒予防効果の検証─地域在住高齢者における無作為化比較試験─」理学療法科学24(1):71–76,2009を以前、読みました。対象者数は少ないものの、TMTなどの注意課題を実施することで、転倒発生率が減少したという報告です。文献の概要◆対象要介護・支援状態にない高齢者63名「注意運動群」・・・注意機能トレーニングと運動介入を行う群21名「運動群」・・・運動介入のみ行う群21名「コントロール群」・・・21名◆訓練方法6ヶ月実施。運動介入は、標準的な運動介入を週に1回と、自宅での自主訓練。「注意運動群」は、運動介入に加えて注意機能のトレーニングを実施。◆結果「注意運動群」のみで、介入後6ヶ月間の転倒発生率が減少した(24%から11%へ)◆注意機能トレーニング方法TMT-A、TMT-B、かなひろいテスト いずれも数字・文字並びなどは検査とは異なるトレーニング用を使用週1回20分実施。自宅での1日の自主訓練量は、TMT-AもしくはTMT-Bと、仮名拾い。TMTなどの視覚探索課題や、仮名拾いなどの抹消課題を行って、注意機能が向上し、かつ、ADL動作(今回は、転倒予防)につながった報告でした。日常的に、注意機能訓練として実施しているこれらの課題の有効性が少しでも報告され、少し根拠が持てました。
2014年09月26日
コメント(0)
-
摂食嚥下リハビリテーション学会に参加 その2
「完全側臥位法」が発表されていて、興味深く見てきました。当院ではまだ導入されていない方法です。帰ってきてから、文献を読みました。基本的に禁忌となる症例が無いとのことで、該当する患者さんがいたら、実施してみたいと思いました。まずは、自分が方法を理解して、病院のST内に伝達しないといけないですが。福村直毅 他,「重度嚥下障害患者に対する完全側臥位法による嚥下リハビリテーション -完全側臥位法の導入が回復期病棟退院時の嚥下機能とADLに及ぼす効果-」,総合リハビリテーション,40巻10号,1335-1343,2012年10月同じ福村先生が共同演者となっている「0度仰臥位法」も発表されていました。今まで、嚥下訓練の基本としては、禁忌となっている姿勢でしたので驚きました。対象者は限られると思われますが、内容を読んでいくと、納得させられるものでした。
2014年09月15日
コメント(0)
-
摂食嚥下リハビリテーション学会に参加 その1
東京(新宿)で開催された第20回日本摂食嚥下リハビリテーション学会学術大会に参加してきました。場所の関係からか、会場が3つに分かれていて、少し歩きまわりました。今回は、口演発表、ポスター発表を中心に見て回りました。全体的な感想など。◆「完全側臥位法」の発表が増えてきている。◆「0度仰臥位法」の発表も散見される。◆大学研究室からの複数発表(継続的な研究)◆多職種連携や、複数施設での共同研究◆後方視的研究や、若年健常者での研究が少なくない。◆meijiが開発しているSWALLOW VISIONという嚥下シュミレータが興味深かった。◆舌の評価では、JMS舌圧測定器が使用されていることが多かった。
2014年09月15日
コメント(0)
全470件 (470件中 1-50件目)











