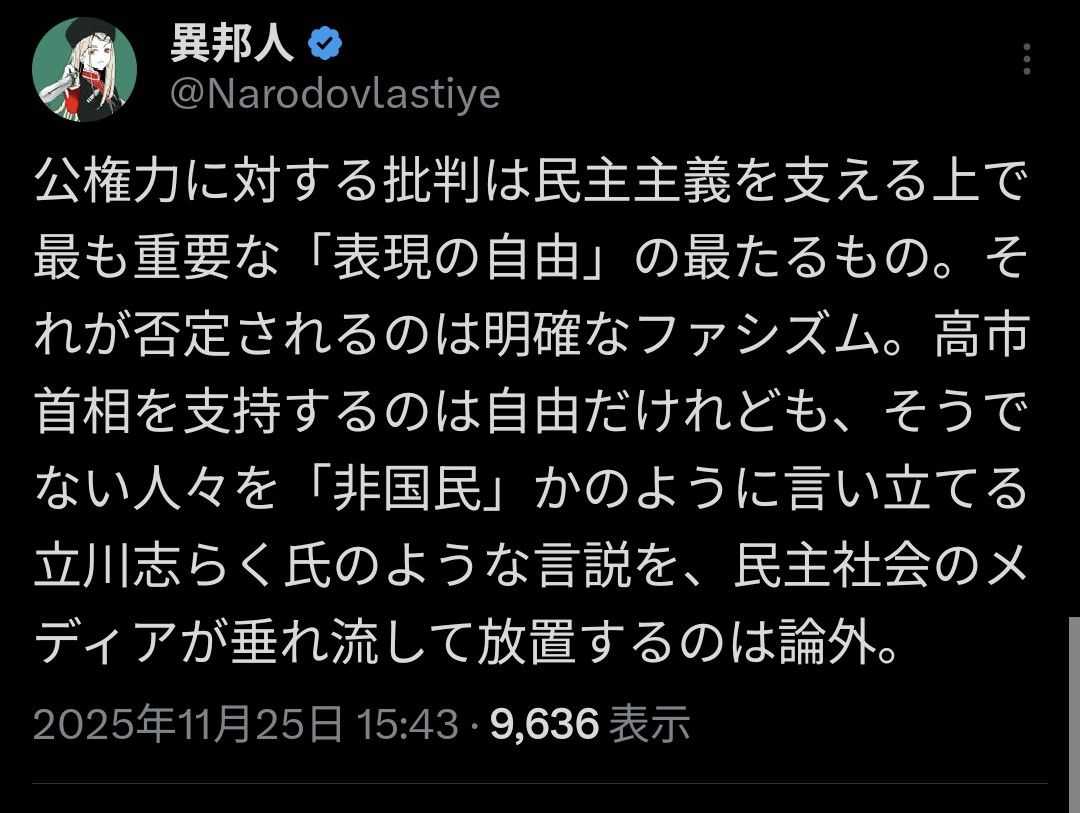2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2009年04月の記事
全3件 (3件中 1-3件目)
1
-
立川談志@よみうりホール、初ナマ談志の深み。
昨夕行われた談志の独演会、朝から宇都宮でやっていたゴルフの進行が遅れ気味で、開演ギリギリでしたが何とか滑り込みセーフ。(・・・って懐かしい言葉だ)若めの客層(オンライン予約だから?)の期待感と緊張感満載の中、お囃子が流れてかなりしてから談志がちょっと戸惑い気味に登場。満場の拍手の中(「待ってました!」という掛け声がバンバンとんでます)、座布団に座ってお辞儀をしたあと、突然横に倒れてしまいます。 もちろん半分ギャグなんですが、どうやら、ガンの治療後に飲んでいる睡眠薬の影響なのか気力がなくなってきているようで、食欲も薄く(この日も朝からほとんど何も食べず、お腹は空いているのだが直前にサンドイッチを半分つまんだだけだとか)、2年前に死んでしまおうかと思ったものの、そうするとタイミング的に、メディアから 「ポール牧に続く訃報」 と言われてしまうのでやめたとか(会場、ちょっとホッとしながら爆笑)。 そんな話も含め、国内外の昔からの小ネタを、その膨大な記憶から思いついたように話しつつ、 「最近、噺の登場人物が談志(自分)に反抗する」 という。どういうこと?と思うと、つまり自分が話をしていると、そこに出てくる登場人物が、本来の筋と違うことを喋ってしまう(=談志が自分で意識しないのに会話が変わる)、ということだそうな。 例えば、芝浜の最後のほうで、女房がお金を隠していたことを話すシーンで「いつか言わなきゃ、と思っていたんだけど言ったらあんたがまた酒飲んじゃってだめになると思って」というようなことを本来言う場面で、「あたしゃ談志の思う通りのようないい人になりたくないんだよ」 と言ってしまうとか、噺の流れで会話の主従が変わったりする(「今日はお酒を飲もう、ということを女房から言わせる」)ことで自分では思いもしなかった深みや流れが出来、たぶん自分としてはこれ以上の芝浜はできないと思ったことなども。 漫画家が、自分の描いているマンガの主人公たちが自分の当初の意識とは違うセリフや行動をするようになることがある、というのに似ているなあ、と思いつつ、30分や1時間の一発勝負の噺の中でそれが出てしまう、というのは、膨大な知識と経験があって初めて到達する境地かも、とも思い、なるほどこれが談志なんだ、とアタマで確認していたところ、ふとホールの客に向かって 「(大丈夫、)落語もやるからね」 などと話して(ちょっとそう心配していた観客から)爆笑をとったあと、しばらくして最初の演目、『二人旅(ににんたび)』へ(噺に入った直後に「いま、落語入ったのわかるよね?」など言って笑いを取るのを忘れずにいつつ)。この噺、かなり中身が自由なもののようで、お金がなくてお腹のすいた旅人二人が謎かけなどをしながら、一膳飯屋のばあさんとも掛け合う、というもの。 ちょっと前に談志の独演会を見た人から、元気がなくって愚痴を言っているみたいだった、という話を聞いていたのですが、そんな感じは見えず、ふむふむ、というところで中入り。 中入り後、なかなか幕が開かなくって、「これってもしかすると『今日は具合が悪いからもうやめた』とか言ってるんじゃない?」などと思っていると、しばらくしてまた戸惑い気味の登場。 観客からまた「たっぷり(噺を聞かせてくれ)!」という掛け声がかかったのですが、話の切り出しで「待ってました、とかたっぷり、と言われるのは、ちょっと嬉しいんだけどプレッシャーもかかるんだよね」と、何だかウブなような正直そのもののような一面を見せつつ、二つ目の演目へ。 その前のまくらとして、落語の『粗忽』というものの面白さを語り始めました。彼が常日頃語っている(落語の魅力・特徴の重要な要素としての)『イリュージョン』そのものである粗忽、これは単なるバカじゃないんだ、ということを色々な噺を取り上げつつ話しながら、ある意味当然の流れで『粗忽長屋』へ。これ、「私は談志の粗忽長屋を生で聴いたことがあるんだ!」と、きっと後々色々な人に話(=自慢)ができるんだろうなあ、と思えるような、正統派の粗忽長屋でした。しかも、最初の二人旅よりもずっと元気が良くって、リズムもあって、談志が本当にこの噺が好きなんだなあ、ということも伝わってくる出来。 もちろん、随所に彼ならではのクスグリが入り、この話を何度も聴いたことがある人にも楽しめる、とても感慨深いモノでした。サゲが終わった後、下りかけた幕を再度上げさせて、観客と対話をするように、サービス精神を発揮してまたいくつか小ネタを披露し(家にいるときはほとんどひざを抱えてじーっとしていることがほとんどだとか)、「もういいだろ?」と言って万雷の拍手を浴びつつ、しっかりとお辞儀をしたまま幕に。 ああ、私は本当に生の談志を見たんだ、という感慨を抱きつつ、ふと 「・・・これって、落語をあまり知らない人にも本当に楽しいものなんだろうか?」 とも思ってしまいました。つまり、私は「あの談志」が、「癌から復活」して、「当初は本調子じゃない」状態だったにもかかわらず今日は(結果的に)元気にあそこまで、いろいろバラエティに富んだマクラを聞かせてもらい、しかも王道の粗忽長屋をやってくれた、ということでかなり堪能させてもらったのですが、そういう事前情報を知らずに来た人がいたとしたら、そこまで面白い、と思えたのだろうか、ということです。つまり、初めて聞く落語としては、きっともっとわかりやすくて楽しい噺家のほうがよいのかも、などと。 ・・・まあ、余計なお世話なんですけどね。w それよりも、今の談志を生かし続けているのは、きっと落語という存在なんだ、落語がなければきっと彼は生きていないのだろうなあ、とも思い、談志がいかに落語を愛しているのか、落語そのものが彼の血であり肉であるのだ、ということを実感・目撃できた幸運にも感謝、でした。チケットを取ってくれた友人にも感謝!
2009/04/19
コメント(0)
-
熊本でホンダ・インサイトに乗る。
先週の水曜日、仕事で熊本に行きました。 熊本空港からレンタカーで移動したのですが、ホンダの新しいハイブリッドカー、『インサイト』が借りられるのに気づき、さっそく車を指定して予約。でもって、往復2時間弱くらいでしたが、ドライブしてみました。 ・・・これ、189万円だったら、かなりアリです。(しかも、税制優遇とかがあるので実質30~40万くらいマイナスになるとか) 私の身長だと普通のホンダ車は小さすぎて、座席を一番後ろにしてもハンドルの下で両膝がつかない(=ゴーカートに乗っているようなものだ、と想像してください)のですが、これは大丈夫。 でもって、高速道路でもスムーズに加速、エコモードであるにもかかわらず気がつくといつのまにかXXXキロ(!)まで違和感なく。後ろのトランクも十分な容量があるし、フロントのデザインもなかなかカッコいい。 以前、やはりレンタカーでプリウス(いまのひとつ前の2代目モデル)にも乗ったことがあるのですが、それに比べるとちょっと乗り心地が硬いかな?という印象もあるものの、エコカーがここまで身近になっていることを実感したのでした。 でも普段あまり車に乗らないので、今の車を買い替えるのも、それはそれでもったいないかなあ・・・
2009/04/11
コメント(2)
-
新宿末広亭で聴く立川談春。
昨日、新宿末広亭で行われた『第18回 三派連合落語サミット』に行ってきました。 これは末広亭がやっている「余一会」(毎月31日に通常の公演とは違う特別企画による興行をやる)の一つで、落語協会と落語芸術協会と立川流の三派が一緒になってやる、という年1回の驚きの企画。(しかしすでに18回目とは知らなかった・・・) でもって、立川談春がここで夜の部の中入りの前でやる、という情報をつかみ、しかも・前売り券なしの全席自由席、なおかつ昼夜入れ替えなし・昼の部のトリが立川志らく(昔、談春と「立川ボーイズ」を組んでた人でもある)・夜の部のトリは柳亭市馬、昔々亭桃太郎も出る ということも知ってしまったため、一週間前くらいから画策して会社を午後半休し、14:30ごろに会場入りしてしまいました。(汗)近くのコンビニで助六とおにぎりとお茶もしっかり買い込み、準備万端で。(末広亭はアルコール飲料以外は持ち込み・演じている間も飲食可なのです)談春さん、先週土曜日深夜に六本木の東京ミッドタウンでやった東京アートナイトがあまりにも場所がひどかったのでちゃんとしたところで見たかったのと、それより何より末広亭という寄席の舞台に出ている彼を見てみたくて。でもって末広亭の談春。話は『三方一両損』、落とした財布を届けたのに落とし主がそこに入っていた三両を受け取らず、届けた方も江戸っ子だから受け取らず、でケンカになって大岡越前の裁きを受けるという有名な話です。 ・・・ひとことで言うと、良かったです。寄席という場所にもぴったりな、江戸っ子のかたまりのような噺。談春のキレのいい早口の啖呵と大岡越前のタメのある話し方、きっちり魅力を活かしていて、安心して楽しめました。 ただ、今までホールでの彼しか見ていないためか、何だか視覚的な違和感も感じてしまいました。なおかつこれだけの人たち(全26組)が出てくる中でやる、という彼にはあまり経験していない環境、ということからか、個人的には本人もちょっとした戸惑いを覚えつつやっていたのでは、とも。 桃太郎さんとか市馬さんみたいに、こういう中でもリラックスして(というかその雰囲気をプラスに取り込んで)やっている、というように見えたら談春のもっともっと違う魅力も出てきそうで、それも楽しみにしたいなあ、と感じた晩でもありました。 しかし14:30から21:00まで、間に休みがあるとはいえ5時間以上も寄席にいて、おなかいっぱいです。鯉朝さんと遊雀さんがノーマークだったのに面白かったのと、桃太郎さんの場を巻き込む『平成のおとぼけ爆笑王』ぶりと、これだけのメンツを従えて大トリをとったにもかかわらずの度胸のよさとおおらかさで楽しんでいた(ように見えた)市馬さんの器の大きさが印象に残りました。大トリ前の正楽さんの紙切りの技も堪能。 でもって、私が着いてからの出演者と演目とひとこと感想を:(昼の部・途中から)・立川談幸 「時そば」 ・・・うーん立川流なのに?・三遊亭歌之介 「母ちゃんのあんか」 ・・・というか落語ではなく雑談で終わり?・ボンボンブラザーズ (曲芸)・立川志らく 「たまや」 ・・・映画『天国から来たチャンピオン』をモチーフにして、主人公を江戸時代の玉やの花火師にした新作シネマ落語。確かに理論派の雄、という才気はほとばしっているんですが。。。何となく志ん朝を感じさせる人ですね。(夜の部)・立川こはる 「手紙無筆」 ・・・前座で談春さんの一番弟子、こはるちゃんが頑張ってました。・桂三木男 「(珍獣)動物園」 ・・・三木助さんの息子さん。二つ目だそうですが似てない?・滝川鯉朝 「街角のあの娘」 ・・・南千住駅前商店街の不二家のペコちゃん人形の噺。この人の独特(?)の雰囲気と、声の高さと、体型が抜群に活きてます。他の噺も見てみたい!・マグナム小林 (バイオリン漫談) ・・・バイオリンの音色で相撲の呼出と行司をやったり、コンビニの入り口の音やったり、タップしながら弾く「暴れん坊将軍」の主題歌はアイディアの勝利。・三遊亭遊雀 「十徳」 ・・・この人も髪の毛を金髪に染めていますが、中身はしっかりしていて(いや、もう一人がしっかりしていないわけではないんですが・・・)、かなり正統派で楽しめました。・立川文都 (漫談) ・・・もと立川関西、つまり関西出身で関西弁で東京落語をやるのだそうですが、漫談だけで終わってしまったので残念。・鏡味正二郎 (太神楽曲芸) ・・・寄席といえばこういう曲芸、ですよね。・春風亭勢朝 「荒茶の湯」 ・・・戦国時代のそうそうたる大名が茶の湯に呼ばれ、何も分からない池田輝政や加藤清正、福島正則が唯一心得のある細川忠興の真似をするんですが。。。という噺。でもこの人、噺の合間に必要のないギャグをはさみすぎ。自信がないように見えてしまいます。・立川談春 「三方一両損」 ・・・いいねえ、オレオレの江戸っ子噺。(中入り)・東京ボーイズ (漫謡) ・・・かなりのお年のコンビ、歌なんて上手じゃないんだけど脱力芸の一つの到達点か?(笑)・立川左談次 (漫談) ・・・文都さんが「本当は立川流は左談次が一番上で、ちゃんとやって売れていてくれれば順序がちゃんとしたのに、全然やる気がないんですよね」と言っていたそのご本人。確かにその通り。「落語やろうと思ったんだけど、市馬に歌1曲分歌う時間を残すのでこれで終わりにします」と言って引っ込んでしまいました。・昔々亭桃太郎 「春雨宿」 ・・・山の中を君塚温泉に向けて歩いていた二人の旅人が途中で出くわしたボロ宿に泊まることになり、そこで働くおばさんたちのものすごい訛りとおとぼけの会話に翻弄される噺。しかしこの間の取り方は凄い。古典も聞いてみたい(出てきたときに「明烏!」とか言われてましたが、「うん、最近古典もやるんだよね・・・」とおとぼけで軽く返すのは至芸の域)・林家正楽 (紙切り) ・・・日本が誇るステキな芸ですよね、紙切り。最後に女の子にリクエストされた「ポニョ」をやりきるあたりはお見事!・柳亭市馬 「らくだ」 ・・・長屋で嫌われ者だったらくだというあだ名の人がふぐにあたって死んでしまい、そこに来た彼の兄貴分が、たまたま通りかかった屑屋を使ってご祝儀やお酒を手に入れ、ごねた大家には死んだらくだをその前に持ってきて踊らせる、という荒業を出すものの、酒が入ってきて段々屑屋の人柄が変わっていくのに押されてしまう、という、彼の持ち味と体格にぴったりの噺です。途中で唄も歌ってたし。
2009/04/01
コメント(0)
全3件 (3件中 1-3件目)
1