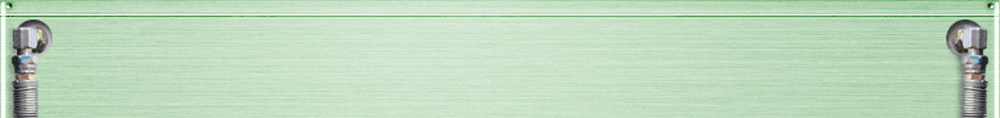白血球の分化を制御する仕組みの発見
2014年10月27日、東北大学は、大阪大学との共同研究により、白血球の分化を制御する遺伝子のスイッチ(転写因子)を発見したことを明らかにしました。
研究成果は2014年10月26日(現地時間)から、Nature Immunologyにオンライン版で公開されています。
私たちの体では、侵入した病原体に対する防御は白血球により主に行われています。白血球は、「自然免疫」を担う骨髄球と「獲得免疫」を担うリンパ球に分類できます。
研究グループはBach1やBach2といった複数の転写因子が協調して働き、造血系幹細胞からBリンパ球への分化を制御していることを突き止めました。
リンパ球に分化する前の細胞(リンパ球前駆細胞)の中ではBリンパ球の分化に必要な遺伝子も骨髄球の分化に必要な遺伝子も、どちらも発現しています。
今回、Bach1やBach2の遺伝子の機能を欠損させたマウスの解析から、Bリンパ球の分化の際に、リンパ球前駆細胞でBach1やBach2は骨髄球に分化するための遺伝子の発現を抑え、これによりBリンパ球が産み出されることを証明しました。
骨髄球とBリンパ球の分化は、造血幹細胞が前駆細胞へなる時に決定されると考えられてきましたが、今回の結果は、リンパ球前駆細胞は骨髄球とBリンパ球の両方に成り得る能力を持っており、Bach1や Bach2は前駆細胞がBリンパ球に分化する側に傾けるということを強く示しています。
これはBリンパ球への分化を遺伝子発現のバランスから説明する新しいモデルです。このような遺伝子発現の調節には、近年注目を集めているエピゲノム注9)の変化が関わる可能性が示唆されており、今後さらに遺伝子抑制とエピゲノム制御との関連を調べていくことで、細胞分化の仕組みが明らかになっていくことが期待されます。
生物のDNAの塩基配列情報の全てをまとめてゲノムと呼ぶのに対して、塩基配列の変化によらずに遺伝子発現の制御を行う情報をエピゲノムと呼ぶ。具体的には、配列情報には変化が無いが、DNAの化学修飾やDNAが巻き付いているヒストンというタンパク質の化学修飾によって、遺伝子の発現が変化するしくみがあり、このような修飾を受けたDNAとヒストンの情報全体をエピゲノムと呼びます。
免疫のバランスの乱れは、感染症の重篤化やアレルギー性疾患などの発症につながることが想定されていることから、今回の発見は免疫関連疾患のより詳細な理解へとつながることが期待されます。