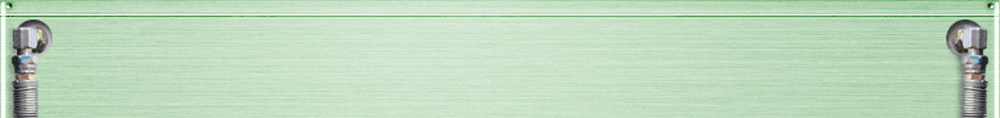全て
| カテゴリ未分類
| プレスリリース
| ドライアイ
| 文献発表
| 厚生労働省通知
| 妄想
| 新聞報道
| お勉強
| 前立腺がん
| 医療費
| 原発
| 制がん剤
| 政治
| 自閉症
| 子宮頸がんワクチン
| 哲学
| 宣伝
| 憲法
| 医療用医薬品
テーマ: 気になったニュース(30387)
カテゴリ: プレスリリース
2型糖尿病の進展や治療効果はHbA1cを測定することによって判断されています。
皮下連続式グルコース測定システムが臨床使用されるようになって約10年、保険適用されるようになって、約3年ついにHbA1cよりも鋭敏に動脈硬化をとらえるという論文が出ました。(色々検討されているのは知っていますが、HbA1cよりも鋭敏というのは私にとって初耳です。)
研究を行ったのは順天堂大学
発表論文の書誌事項 Stomi Wakasugi 1), Tomoya Mita 1), Naoto Katakami 2), Yosuke Okada 3), Hidenori Yoshii 1), Takeshi Osonoi 4), Nobuichi Kuribayashi 5), Yoshinobu Taneda 6), Yuichi Kojima 7), Masahiko Gosho 8), Iichiro Shimomura 2), and Hirotaka Watada 1)
Association between continuous glucose monitoring-derived metrics and arterial stiffness in Japanese patients with type 2 diabetes
著者所属:1)順天堂大学 2)大阪大学 3)産業医科大学 4)那珂記念クリニック 5)三咲内科クリニック 6)たねだ内科クリニック 7)むさし野ファミリークリニック 8)筑波大学
DOI: 10.21203/rs.3.rs-78697/v1
Cardiovascular Diabetology volume 20, Article number: 15 (2021)
プレスリリース の研究のポイントを引用します。

結論としては、動脈硬化には一日の血糖変動の方がHbA1cよりも相関が高かったということです。
先日も糖尿病について、 糖尿病は心血管病で死ぬ可能性は高くなるが、血糖値を下げてもその可能性は低くならない。
の記事を書きました。
今回の研究は疫学的な研究で、動脈硬化を表す指標は血糖の日内変動が影響しているというものです。
薬剤が血糖の日内変動を抑えるかどうか、それによって動脈硬化を抑えるかどうか、結果として心血管系障害による死亡率が下がるかということを前向き試験で確かめる仮説が出てきたということです。
食後血糖値高値やHbA1cを指標として糖尿病治療薬が開発されてきて、恐らく糖尿病性合併症を防ぐであろうと考えられています。
2型糖尿病の治療目的は食後血糖値やHbA1cを指標としています。糖尿病治療薬の場合には低血糖やケトアシドーシスが命にかかわる副作用となることから、血糖を下げすぎないことも薬に求められています。
本来の抗糖尿病薬の目的は糖尿病性副作用(腎炎、網膜症、神経症)を起こさずに長生きすることだと思います。適正な血糖値やHbA1cは本来それを指標として定められるべきです。しかし、現実には半年ぐらい(もっと短いか)、食後高血糖が高値にならない、あるいはHbA1cがある数字以下に保ったということで評価されて、承認されます。
今回の発表はその評価システムに一石を投じるものだと思います。
また、現在用いられている抗糖尿病用薬以外にドラッグ・リポジショニングで新しい効能を取れる薬剤が出るかもしれません。(治験方法はかなり工夫がいると思います)。
誰か、一緒にやりません?
皮下連続式グルコース測定システムが臨床使用されるようになって約10年、保険適用されるようになって、約3年ついにHbA1cよりも鋭敏に動脈硬化をとらえるという論文が出ました。(色々検討されているのは知っていますが、HbA1cよりも鋭敏というのは私にとって初耳です。)
研究を行ったのは順天堂大学
発表論文の書誌事項 Stomi Wakasugi 1), Tomoya Mita 1), Naoto Katakami 2), Yosuke Okada 3), Hidenori Yoshii 1), Takeshi Osonoi 4), Nobuichi Kuribayashi 5), Yoshinobu Taneda 6), Yuichi Kojima 7), Masahiko Gosho 8), Iichiro Shimomura 2), and Hirotaka Watada 1)
Association between continuous glucose monitoring-derived metrics and arterial stiffness in Japanese patients with type 2 diabetes
著者所属:1)順天堂大学 2)大阪大学 3)産業医科大学 4)那珂記念クリニック 5)三咲内科クリニック 6)たねだ内科クリニック 7)むさし野ファミリークリニック 8)筑波大学
DOI: 10.21203/rs.3.rs-78697/v1
Cardiovascular Diabetology volume 20, Article number: 15 (2021)
プレスリリース の研究のポイントを引用します。
- 大きな血糖変動が血管硬化に関連することを明らかに
- 血糖変動をコントロールすることが動脈硬化を抑制するために重要である可能性

心臓からの血液が押し出される際に生じる動脈の脈動が末梢へと伝播する波が脈波であり、血管が硬いほど速く伝わるという原理を利用して、血管の硬化を簡便に検査できるのが脈波伝播検査です。両上腕、両足首に血圧測定カフ(腕帯)を巻いて、血管を流れる血液の脈動の速さ測定します。
結論としては、動脈硬化には一日の血糖変動の方がHbA1cよりも相関が高かったということです。
先日も糖尿病について、 糖尿病は心血管病で死ぬ可能性は高くなるが、血糖値を下げてもその可能性は低くならない。
の記事を書きました。
今回の研究は疫学的な研究で、動脈硬化を表す指標は血糖の日内変動が影響しているというものです。
薬剤が血糖の日内変動を抑えるかどうか、それによって動脈硬化を抑えるかどうか、結果として心血管系障害による死亡率が下がるかということを前向き試験で確かめる仮説が出てきたということです。
食後血糖値高値やHbA1cを指標として糖尿病治療薬が開発されてきて、恐らく糖尿病性合併症を防ぐであろうと考えられています。
2型糖尿病の治療目的は食後血糖値やHbA1cを指標としています。糖尿病治療薬の場合には低血糖やケトアシドーシスが命にかかわる副作用となることから、血糖を下げすぎないことも薬に求められています。
本来の抗糖尿病薬の目的は糖尿病性副作用(腎炎、網膜症、神経症)を起こさずに長生きすることだと思います。適正な血糖値やHbA1cは本来それを指標として定められるべきです。しかし、現実には半年ぐらい(もっと短いか)、食後高血糖が高値にならない、あるいはHbA1cがある数字以下に保ったということで評価されて、承認されます。
今回の発表はその評価システムに一石を投じるものだと思います。
また、現在用いられている抗糖尿病用薬以外にドラッグ・リポジショニングで新しい効能を取れる薬剤が出るかもしれません。(治験方法はかなり工夫がいると思います)。
誰か、一緒にやりません?
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[プレスリリース] カテゴリの最新記事
-
子ども庁に関して 2021年04月09日
-
少年庁 いい人 奇策 2021年04月02日
-
麻生大臣 物忘れ 自閉症スペクトラム 2021年03月22日
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.