2010年01月の記事
全19件 (19件中 1-19件目)
1
-

ウコンの根を掘り起こしてみました
去年初めて一人前に葉がおおきくなったウコンですが、根がどのようになっているのか確認するため、掘ってみました。初めて約1mくらいの大きさまで葉が伸びたので、花が咲くのを期待しましたが咲きませんでした。ウコンの花は綺麗な花なので、一度咲くところを見たいと思いますがなかなか見れません。ウコンは漢方薬などに利用され、カレーなどの香辛料にも使用され、相当大きくなるように効きます。さて我が家のウコンはどうでしょうか。鉢の土を取り除いていくと、細かな根がびっしりと張っていました。掘り進むと黄色っぽい塊が見えます。鉢から取り出したところです。細かな根がまだたくさん付いています。根を整理してみました。大きな塊が二つ見えています。最終的に三つに分かれました。根を整理して鉢に戻しました。整理した時に少し折れてしまった塊や小さな膨らみの根は別の鉢に移植しました。また大きくなればいいですね。
2010年01月31日
コメント(0)
-

梅の花です
今日は天気が良かったので梅の花の写真を撮ってみました。 一輪いかがですか。 開きかけの蕾もあります。 不思議ですね、一度にパッと咲かないんですね。 開ききっていないものもあります。もうすぐ開くでしょう。
2010年01月30日
コメント(0)
-
梅の花が賑やかになってきました
12月の半ばに1輪咲き始めた梅の花が3分の1位咲いています。少し寒さも和らいだので、写真を撮った後、一斉に咲き始め、今では半分くらい咲いています。小さな木ですが花はいい香りがします。梅の花の香りは好きです。花に鼻を近づけて思いっきり香りを吸い込みます。春は間近です。
2010年01月29日
コメント(0)
-
椿の蕾が大分大きくなってきました
種を植えて7年目にやっと花が咲き、花が咲き始めて3年目の椿の蕾が膨らんできました。まだまだ蕾は固いですが、順調に冬を越しそうです。もっと膨らんでくると、花の赤い色が見えてくるのですが、まだまだ先になりますね。椿よりも早く咲く山茶花も椿に似た花をつけます。椿に比べると山茶花の方が歌によく出てきますね。さざんか さざんか さいたみち~さざん~かの~やど~アンコ~つばき~は~など、花は歌詞の中によく出てきます。それだけ馴染みが深いということだと思います。
2010年01月28日
コメント(0)
-
菊の蕾を植えてみたら・・・
去年の10月半ばに間引きした菊の蕾をいたずら心が芽生え植えてみました。約3か月半経過しました。寒さのせいか、2か月近く緑色していた葉も茶色く変色を始め、今ではほぼ完全に茶色に変わってしまいました。万が一、発根して翌春に成長したら面白いな、いや画期的とほのかな期待をかけて植えてみたわけですが、期待を裏切る結果となりそうです。まだこのまま置いておき、もう少し暖かくなってきたら掘ってみて見届けたいと思います。秋に咲きそろった菊は新しく芽が出てきています。もっと成長して暖かくなれば切り取り、挿し穂として世代交代です。
2010年01月27日
コメント(0)
-
川鵜だと思います
近くの池で黒い鳥がいたので写真を撮りました。少し離れた所にいたので望遠で撮りましたが、画質は良くありませんが鳥の種類が確認できるかと思います。くちばしの特徴などから鵜の仲間だと思います。多分、川鵜だと思いますがどうでしょうか。時々水中に潜ります。思わぬところにまた浮いてきます。餌を捕っているのでしょう。この池は数年前までは釣り池になっていて、土、日曜日には太公望で賑わってました。某テレビ局の釣り番組にも登場していました。今は釣り台も撤去され、広々とした池になりました。近頃は見ませんが、青鷺がいたり、秋口には白鷺が一羽小魚を獲ったりしていました。夏には牛ガエルが合唱し、この近辺では貴重な自然のある場所です。
2010年01月25日
コメント(0)
-

トクサのはなし
トクサはトクサ科の植物で原産地は北半球温帯地方で広く分布するそうです。スギナの親戚にあたるようです。茎は中空で表面は細かい毛のようなものでざらざらしています。スギナのように節の部分を囲むようにギザギザのはかまがあります。夏に茎の先端に綿棒のような花ができて胞子を飛ばします。表面のざらざらした部分はサンドペーパーの代わりに昔からよく使用されてきました。日本の伝統的な工芸品の製作にも使用されています。昭和50年代の初めに、当時の通産省が伝統的工芸品の産業を振興するため、「伝統的工芸品産業の振興に関する法律」(伝産法)を整備し、昔ながらの伝統的な技法により工芸品(多くは生活用品)を作成する産業の振興を図ろうとしました。産業振興の計画を立てて、後継者を育成していこうというものです。対象は産業の振興なので、一人だけが伝統技法を継承していくものは対象から外れていました。この伝産法の指定を受けた産業の中でも、研磨の技法でトクサを使用するというものもありました。トクサを煮込んで乾燥させてサンドペーパーのように使用するというものです。昔から一度トクサのサンドペーパーを作ってみたいと思いながら実現していません。写真はこの冬に撮影したものなのでトクサの色が悪いです。夏になればもっと濃い緑色になります。
2010年01月24日
コメント(0)
-
アオキのはなし
アオキはミズキ科の日本原産の植物です。春から初夏にかけて花が咲き、秋には実が赤くなります。実は楕円形で緑の葉に赤が冴えてきれいです。葉も枝も緑色をしているので「青木」と名付けられたそうです。日陰にも強く育てやすいので生け垣などにもよくつかわれます。カイガラムシが付くと排泄物の影響でスス病にかかりやすくなるそうです。よく葉の先の方が黒くなってしまったアオキを見ることがあります。風通しが悪いとカイガラムシが発生しやすいそうです。風通しを良くするには間引き剪定をするのがいいそうです。
2010年01月22日
コメント(0)
-
大寒なのに暖かい
今日は二十四節気の大寒です。本来は一年のうちで一番寒い日といわれているのですが、今日は大変暖かい日になりました。大阪では4月上旬の暖かさとなったなったようです。大阪城の梅林でも梅がちらほらと咲き始めたとニュースになっています。我が家の梅は12月半ばから咲き始めています。1月半ばから2月にかけて満開になるかと予想しましたが、今のところちらほらを少し越し始めたかというところです。それでも20輪近く咲いています。思っていた以上に咲きそろうのが遅れていますが、1月に入ってから結構冷え込んだのが影響しているのかもしれません。過去の大寒の日の大阪の気温を調べると、21年ほど前に16.9度という年がありました。今日の暖かさは、それ以来という感じですね。来週になるとまた例年の寒さに戻るようです。三寒四温という言葉があるように、これからは暖かくなったり寒くなったりを繰り返して春が近づいてきます。関西では奈良のお水取りが終わらないと春が来ないといいます。節分が過ぎ、啓蟄(2010年は3月6日だそうです)が過ぎるともうすぐ春です。草花に活気が戻ってきます。
2010年01月20日
コメント(0)
-
海藻と海草のはなし
海藻と海草、どちらも「かいそう」と読めます。「かいそう」と読んでしまうと区別がつきにくいので、海藻は「かいそう」、海草は「うみくさ」と読むようですね。実際に海藻と海草は生態も違い、区別されています。海藻は海中にはえる藻類のことで、花は咲かずに胞子によって子孫を増やすそうです。多くは食用とされます。岩礁海岸に多く生育し、根は栄養を吸収するものでなく、岩に固着するためのもので、多くは岩に生え、砂泥底には殆ど生えないそうです。色の違いによって緑藻類、褐藻類、紅藻類に分類され、太陽のよく届く浅いところには緑藻類(アオサ、アオノリなど)、深くなるにつれ褐藻類(コンブ、ワカメなど)、紅藻類(アサクサノリ、テングサなど)があります。海草は花を咲かせ、種子を作って繁殖します。陸上にある植物とよく似ています。陸上の花と同じようなので、根を張り砂泥地に多く見られるようです殆ど食用にされることはないそうです。生で食べると中毒を起こすようなものもあるみたいです。波のあまりあたらない内海や干潟に多く生育するようです。ウミブドウをいただいて調べていたら勉強になりました。海藻と海草の違いなど普段気にしていなかったので、改めて違いがわかりました。卵と玉子、海老と蝦、魚(うお)と魚(さかな)など改めて違いを考えてみると理由があるのでしょうね。。
2010年01月17日
コメント(0)
-
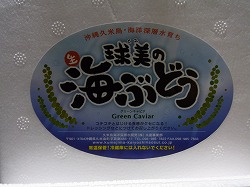
ウミブドウのはなし
ウミブドウを沖縄の土産でいただきました。ブドウと名がつきますが果物のブドウではありません。ウミブドウはイワズタ科の海藻です。正式な名称はクビレズタといいます。その形からウミブドウやグリーンキャビアと呼ばれています。元々はくびれがあるツタという意味で「クビレヅタ」という名前でしたが、2000年に現代仮名遣いに従って「クビレズタ」に表記されるようになったそうです。日本では南西諸島の浅い海域に分布するそうです。沖縄では昔から食用にされているそうです。醤油や三杯酢にタレのように浸けて食べるといいようです。ドレッシングなどかけて置いておくと縮んでしまい、独特のプチプチ感がなくなってしまうので、食べる時に浸けて食べるのがいいようです。低温に弱いので冷蔵庫に保存すると縮んでしまうそうで、注意書きにも冷蔵庫に入れないように書いてあります。出まわているものはほとんどが養殖もので、通販でも手に入るようです。何もつけずに食べてみましたが、自然の塩味がして独特のプチプチとした食感がちょっぴりはまりそうなります。
2010年01月16日
コメント(0)
-

ガーベラのはなし
ガーベラの切り花をいただきました。ガーベラは南アフリカを原産とするキク科の草花です。草丈は低いのですが大輪の花を咲かせ、花つきもよく人気がある草花の一つです。日当たりを好み、日当たりが悪いと花つきが悪くなるそうです。というものの、夏の暑さには弱いそうで、夏は直射日光の当たらない風通しのよい明るい日陰で育てるといいそうです。また、雨に当たると花が痛むそうで、雨に当たらない場所で育てるのが良いそうです。ということは、水やりのときには花に水がかからないように気をつけなくてはいけないですね。こんなに書くと結構手間のかかる花ですね。この花に限らず、多くの花は手間をかけなくてはしっかりと咲きません。当たり前の話ですね。
2010年01月15日
コメント(0)
-

10日戎に行ってきました
1月11日に残り福の10日戎に行ってきました。しっかり福を貰ってきたつもりですがどうでしょうか。行ったところは、兵庫県西宮市にある西宮神社です。毎年1月10日朝6時から「開門神事福男選び」が行われることで有名です。開門と同時に四千人以上の人が参加して、1番福を目指して先頭にいる人たちは猛ダッシュで本殿を目指します。多くの露店が出るので夜は活気が溢れ、たくさんの人が参拝します。1月9日から11日までの三日間で毎年百万人以上の人が参拝するそうです。今年は昼間に行ったので、去年の夜に行ったのに比べると混雑もましでした。おそらく夜には残り福を求めてもっとたくさんの人が参拝し混雑したかと思います。帰りに金太郎飴の福飴を買いました。絵柄は金太郎じゃないですが福をもたらす福娘のように思えます。(そのように思いたい)
2010年01月14日
コメント(0)
-
菊が一輪まだ咲いています。
菊がまだ咲いています。年が明けてもう十日戎も過ぎているのに二年越しで菊が一輪咲いています。去年の菊は少し遅く咲き始めたのですが、この一輪は一番最後に咲いた花です。花の台をつけなかったので花の重みで傾いたまま咲いています。菊は終わりに近づくと花びらが少しずつ赤茶けてくるのですが、まだ黄色いままでしっかりと咲いています。こんなに遅くまで咲くのは初めてです。
2010年01月13日
コメント(0)
-
菊の蕾を植えてみたら
10月半ばに菊の蕾を間引きして興味半分挿し木にしてみました。当然すぐに枯れてしまうだろうとの予測に反し、2か月半ほどきれいな緑の葉が見ることができました。流石に蕾が開くことはありませんが、2か月近く蕾もしっかりしていました。蕾が茶色くなってきて硬さもなくなってきた後、片側の葉が茶色くなり始め、今ではもう一方の葉も茶色くなってきました。茎は最初の時よりも曲がってきましたが、全体が萎えることなくまだしっかりと自立しています。葉が茶色くなってきたのは寒さのせいではないかと推測しています。(そうであってほしい。)枯れているならば、全体的にもっと萎えてしまい、これほど自立していることがないのではないか、と考えてもいます。春になれば掘り起こし、根が出ていたら感動もんです。もしそうでなければ、弁慶が矢を射られても立ち尽くしたという感じですね。生命力の神秘にまた感動です。春が楽しみになってきました。
2010年01月09日
コメント(0)
-
七草粥のはなし
今日は1月7日。七草粥を食べる習慣がありますね。七草粥は正月7日に部病息災を祈り、春の七草を入れて炊いた粥を食べます。正月におせち料理やおもちなど食べて疲れた胃袋を整えるために食べるともいわれています。この風習は中国伝来のもので、平安時代の中期ごろに始まったともいわれています。春の七草は、セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ、スズシロですね。皆さんよくご存じだと思います。昔は旧暦でしたので、今の2月になります。その頃になると七草も出そろうようですが、今ではまだ出そろわないですね。だからスーパーで売っているもので間に合わせることになります。本来は朝に食するものだそうですが、今晩いただきました。病気じゃなくてもたまにお粥を食べるのもいいですよ。最近一時のことを思うとインフルエンザのニュースも減っていますが、まだまだ油断はできません。無病息災をお祈りして食べましょう。
2010年01月07日
コメント(0)
-
ダルマクンシランのはなし
ダルマクンシランを買いました。ダルマクンシランは君子蘭を小型にしたものです。普通の君子蘭より小さく、葉の幅が広く丸みを帯びています。菊なども小さい種類をダルマ菊と呼ばれます。ずんぐりとした形がだるまのように見えるから名づけられたのでしょうか。君子蘭はランという名前が付いていますが、ランの仲間ではなく、ヒガンバナ科の植物で原産は南アフリカだそうです。秋から冬にかけて10度以下の低温に1か月以上当てないと花芽がつかないようです。といっても、霜に当てたりするとダメになります。冷えてきたからと言って早めに屋内に入れてしまうと花が咲きません。昔結構大きくなった株がありましたが、強烈な冷え込みがあってダメになってしまったことがあります。今回購入した株はまだ小さく葉の数も少ないので、後2,3年位は花が見れないかと思いますが、温度管理など気を付けて立派な花を咲かせたいと思います。
2010年01月05日
コメント(0)
-

葉ボタンのはなし
葉ボタンはお正月の定番植物ですね。12月になるとお店に並び始めます。ボリュームがあり、寄せ植えにも最適の植物です。アブラナ科の花でヨーロッパ中南部が原産だそうです。冬場の鑑賞期間を過ぎて放っておくと、茎が伸びてきて春になるとアブラナのような黄色い花が咲きます。種ができれば夏に蒔くと、新しく芽が出て冬にまた楽しめるようになります。比較的育てるのに簡単な花のようです。踊り葉ボタンという茎の長い種類の葉ボタンもありますね。茎が曲がって踊っているように見えます。縁起ものの南天と寄せ植えにしてみました。 キャベツの仲間なのでキャベツに似ていますね。
2010年01月03日
コメント(0)
-
おめでとうございます
あけましておめでとうございます。昨日の元旦は寒かったですが穏やかなお天気でした。風が吹くとさすがに寒く冬を感じます。大晦日には近くの神社にお参りし、今年こそいい年になるようお願いしてきました。おみくじは中吉でした。まずまずの1年かと思います。今年は五黄の寅年だそうですね。九星の五黄土星は最強の星といわれ、干支の最強の寅と重なり五黄の寅と呼ばれます。36年に一度巡ってくるということです。昔から五黄の寅年生まれの人は気が強いといわれ、特に女性は嫁に行かれないという迷信があります。また、60年に一度の丙午(ひのえうま)年生まれの女性は、男を食い殺すとさえいわれ、実際に丙午の年には子供の数が少なくなっています。この年に女の子が生まれるとかわいそうなどということで敬遠されたようです。多くの人はこのような非科学的な迷信を信じないとは思いますが、やはり気になるようですね。昨年は変動の年でした。今年こそよい年になるよう期待したいと思います。
2010年01月02日
コメント(0)
全19件 (19件中 1-19件目)
1










