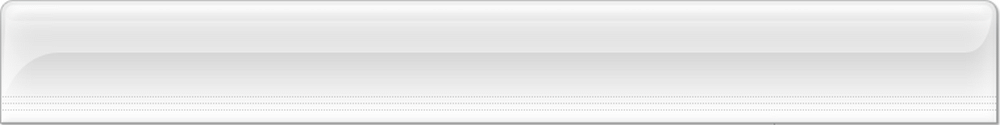カテゴリ: カテゴリ未分類
多くの人が勘違いしてしまうことに、会社の規模さえでかければそれは強いことだし、よいことだと思いがちな部分がある。
元IBMのルー・ガースナーでさえ巨象も踊るで、でかいことはいいことだという、しかも 「象が蟻より強いかどうかの問題ではない。その象がうまく踊れるかどうかの問題である。見事なステップを踏んで踊れるのであれば、蟻はダンス・フロアから逃げ出すしかない」
とまで言っている。
ほんとうにそうなんだろうか?
これを検証するには、ウォルマートをはじめとするリテール(小売)業界を検討してみるといい。ウォルマートは世界最強の小売企業なのだろうか?
え?
一体誰がそんなことを言ったの?
あれは単に速くてでかいだけだ。
アメリカのニューヨーク州には、ウォルマートが牙城をほんの少しも侵食できない、ニューヨーク州最強スーパーチェーンがある。
最強スーパーが、速く動けないから、というだけなのだ。
その説明をしよう。
あ、その前にこの言葉をぶつけておこう。
「もし、たった一つだけあなたの生活に存在するスーパーを選ぶとしたら、それはウォルマート?」
やだなぁ(笑)。
想像しただけで怖くなってくる。
さて、わたしは、ECが長かったので、小売の研究はよくしている。
その中には、ウォルマートの強さを宣伝する記事ばかりが多いが、専門家の見方は違うようである。普通に考えれば、IT技術を駆使し、卸価格を下げさせ、徹底的な効率化をすれば、小売では勝ててしまうように見えるのだが、実際には全くそうではない。
日本に、外資系スーパーが参入したのは記憶に新しいが、未だに目立った成果を挙げていない。
日本は現在、イオン系・イトーヨーカドー系の二社に絞られつつあるように見えるようなのだが、実際にはそうではないことをまず言っておく。
小売は感情の産物である。
ある大手チラシ会社の社長は、ウォルマートが参入して、カルフールが参入してきたとき、実際に店舗を見に行ってほっと息をつき、胸をなでおろしたという。
「やつらは、生鮮売り場を全く理解していない!」
嬉々として、そう言ったらしい。
別に日本の小売業界が閉鎖的なわけではない。
単純に、ウォルマートが日本の小売を知らないだけなのである。
さて、えらそうに語ってきたのだが、実はわたしが話そうとしていることは、日経系のリアルタイム・リテールというサイトで語られることの受け売りである。
・リアルタイム・リテール
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/
このサイトは非常に上質な情報が集まっているのでお気に入りだったのだが、二年ほど前から連載がストップしてしまっている。
ほんとうのことを言うと、ここにある記事を全部読んで頂くのが手っ取り早いし、どれを読んでもためになるのでお勧めなのだが、全部読むのに数時間かかるだろうから、わたしがポイントと思える部分を抜き出して紹介したい。
ウォルマートはちっとも強くないことがよく分かってくるはずだ。
■実は、地域独占が進んでいる日本の小売業
さてまずはこの記事から言ってみよう。
「塗り変わる勢力地図——国内小売業最前線 第7回 元気な地方小売業」
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/column/kazama/07/index.shtml
この記事は、小売業の成長率が高い会社は地方の小さい企業が多いということ。引用してみよう。
・熟知したホームグラウンドで戦える強み
・むやみに規模拡大を狙わないことも共通点の一つ
と言っている。
実は小売とはこういう性質を持つ側面もあるのを理解しないといけない。小売は感情の産物である。お客さんに愛されることにおいて一番を目指すのであれば、安易な規模拡大化をしないほうがよい事は、わかりやすいことである。
■実は、アメリカも、地域独占が起こっている。
続いて、冒頭に書いた、ニューヨーク州最強スーパーの話。
「米国注目企業に見る最新流通戦略 第3回 常識を超えよ!究極のコンビネーションストア ウェッグマンズ」
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/column/suzuki/03/index.shtml
食品シェア80%だそうである。そして、アメリカでは珍しいことではないと。
ちなみに、サイトはここ。
http://www.wegmans.com/
店舗はほんとうにニューヨーク州付近にしかない。
http://www.wegmans.com/about/storeLocator/index.asp
ちなみに、売上高は年間40億ドル。日本のイオンの1/10である。
そして、非上場企業。
つまり、株価は気にしなくていいわけだ。
良識ある、東海岸の雰囲気がぷんぷん漂うサイトで、ここ数年、働くのに最もよい会社ベスト100で上位をキープし続けている。
わたしも働くなら、買い物するなら、こっちの方がいい。
これは物凄くまっとうな競争の結果起こっている現象である。
■では、なぜウェッグマンズはウォルマートになれないのか
それはこの記事が参考になるかもしれない。
「日本の小売業は優れた感性を持つからこそ、それを生かすデータ分析が重要」
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/interview/10/
要するに、ウェッグマンズのやり方は、属人的なので、スケールできない、という事。
続いて、日本とアメリカの違い。
結局、スケール問題だけであって、お客さんに愛される、健全な企業として運営するという意味では、特に問題はないということ。小売は感性です。
ついでに、サイト外だけど、イトーヨーカドーの理念。
伊藤雅俊の「『ひらがなで考える商い』のこころ」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20060414/101346/
商売は「難しいことば」で考えてはいけない
必要なのは高度な知識より、深い知恵
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20060616/104561/
との事。
わたしって、けっこう本気でECやってたんだなぁと改めて実感。
以上。
ウォルマートは強いんじゃない! 単に上手くスケールできただけだ、という話でした。
元IBMのルー・ガースナーでさえ巨象も踊るで、でかいことはいいことだという、しかも 「象が蟻より強いかどうかの問題ではない。その象がうまく踊れるかどうかの問題である。見事なステップを踏んで踊れるのであれば、蟻はダンス・フロアから逃げ出すしかない」
とまで言っている。
ほんとうにそうなんだろうか?
これを検証するには、ウォルマートをはじめとするリテール(小売)業界を検討してみるといい。ウォルマートは世界最強の小売企業なのだろうか?
え?
一体誰がそんなことを言ったの?
あれは単に速くてでかいだけだ。
アメリカのニューヨーク州には、ウォルマートが牙城をほんの少しも侵食できない、ニューヨーク州最強スーパーチェーンがある。
最強スーパーが、速く動けないから、というだけなのだ。
その説明をしよう。
あ、その前にこの言葉をぶつけておこう。
「もし、たった一つだけあなたの生活に存在するスーパーを選ぶとしたら、それはウォルマート?」
やだなぁ(笑)。
想像しただけで怖くなってくる。
さて、わたしは、ECが長かったので、小売の研究はよくしている。
その中には、ウォルマートの強さを宣伝する記事ばかりが多いが、専門家の見方は違うようである。普通に考えれば、IT技術を駆使し、卸価格を下げさせ、徹底的な効率化をすれば、小売では勝ててしまうように見えるのだが、実際には全くそうではない。
日本に、外資系スーパーが参入したのは記憶に新しいが、未だに目立った成果を挙げていない。
日本は現在、イオン系・イトーヨーカドー系の二社に絞られつつあるように見えるようなのだが、実際にはそうではないことをまず言っておく。
小売は感情の産物である。
ある大手チラシ会社の社長は、ウォルマートが参入して、カルフールが参入してきたとき、実際に店舗を見に行ってほっと息をつき、胸をなでおろしたという。
「やつらは、生鮮売り場を全く理解していない!」
嬉々として、そう言ったらしい。
別に日本の小売業界が閉鎖的なわけではない。
単純に、ウォルマートが日本の小売を知らないだけなのである。
さて、えらそうに語ってきたのだが、実はわたしが話そうとしていることは、日経系のリアルタイム・リテールというサイトで語られることの受け売りである。
・リアルタイム・リテール
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/
このサイトは非常に上質な情報が集まっているのでお気に入りだったのだが、二年ほど前から連載がストップしてしまっている。
ほんとうのことを言うと、ここにある記事を全部読んで頂くのが手っ取り早いし、どれを読んでもためになるのでお勧めなのだが、全部読むのに数時間かかるだろうから、わたしがポイントと思える部分を抜き出して紹介したい。
ウォルマートはちっとも強くないことがよく分かってくるはずだ。
■実は、地域独占が進んでいる日本の小売業
さてまずはこの記事から言ってみよう。
「塗り変わる勢力地図——国内小売業最前線 第7回 元気な地方小売業」
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/column/kazama/07/index.shtml
この記事は、小売業の成長率が高い会社は地方の小さい企業が多いということ。引用してみよう。
先ほどのデータが示すように、地方小売業はとにかく元気だ。また、このランキングにまでは入らなかったものの、イオンやイトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパン、さらにはオートバックスセブン、コジマ電機、マツモトキヨシ、大創産業といった、それぞれの業態ではトップブランドにある小売業をたじたじさせるような地方小売業も少なくない。筆者は、その強さの秘密として、
もちろん、地方小売業は企業規模ではトップブランドに歯が立たない。だが、局地戦や限定したマーケットでは、“ホームグラウンド”の強さを発揮できるため、トップブランドと互角もしくはそれ以上の業績を上げているケースもある。実際、あまりにもリージョナルチェーンが強いため、大手チェーンが尻尾を巻いて撤退したような事例もある。
・熟知したホームグラウンドで戦える強み
・むやみに規模拡大を狙わないことも共通点の一つ
と言っている。
実は小売とはこういう性質を持つ側面もあるのを理解しないといけない。小売は感情の産物である。お客さんに愛されることにおいて一番を目指すのであれば、安易な規模拡大化をしないほうがよい事は、わかりやすいことである。
■実は、アメリカも、地域独占が起こっている。
続いて、冒頭に書いた、ニューヨーク州最強スーパーの話。
「米国注目企業に見る最新流通戦略 第3回 常識を超えよ!究極のコンビネーションストア ウェッグマンズ」
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/column/suzuki/03/index.shtml
必勝プロトタイプを引っさげて他州へ進出開始
ウェッグマンズの本社は、ニューヨーク州のロチェスターという田舎にある。余談だが、米国の優良小売企業の本社は田舎であるケースがほとんどである。その理由は、田舎で超寡占化を実現し、この金城湯池をベースとして赤字覚悟で他商圏へ打って出ることができるからである。競合が入って来ることのできない、儲かるドミナンスエリア(一定の地域において、他社を寄せ付けない、または取引を有利にコントロールできてしまうようなシェアを意味する)を最低1つ作ることは、チェーンストアにとっては必須であり、この要件は日米に違いはない。
ちなみにウェッグマンズはこの城下町ロチェスターで、食品シェア80%というずば抜けた寡占状態を作り上げているとのことだ。80%という数値は異常に高そうに見えるが、私が知る限り、このレベルの寡占状況を持つチェーンは他にも数社あり、実は米国では珍しいことではない。
食品シェア80%だそうである。そして、アメリカでは珍しいことではないと。
ちなみに、サイトはここ。
http://www.wegmans.com/
店舗はほんとうにニューヨーク州付近にしかない。
http://www.wegmans.com/about/storeLocator/index.asp
ちなみに、売上高は年間40億ドル。日本のイオンの1/10である。
そして、非上場企業。
つまり、株価は気にしなくていいわけだ。
良識ある、東海岸の雰囲気がぷんぷん漂うサイトで、ここ数年、働くのに最もよい会社ベスト100で上位をキープし続けている。
わたしも働くなら、買い物するなら、こっちの方がいい。
これは物凄くまっとうな競争の結果起こっている現象である。
■では、なぜウェッグマンズはウォルマートになれないのか
それはこの記事が参考になるかもしれない。
「日本の小売業は優れた感性を持つからこそ、それを生かすデータ分析が重要」
http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/interview/10/
日本の小売業は属人的なため急成長が望めない
──日本の小売業が米国の小売業に最も遅れている点はどういったところでしょうか。
藤野: 「スケーラビリティ」です。すべての作業を人手で行うのでは、10店舗程度なら運営できても3000店舗ともなると対応できません。ウォルマートが1日に50店舗ものスーパーセンターを同時にオープンして、年間では500店舗もオープンしているというようなことは日本では考えられないことです。日本の小売業では、多くが店舗の運営やオペレーションを人材に依存しており、経営システムになっていないからです。
例えば中国のマーケットに進出しようとした場合を考えてください。年間100店舗程度の出店なら対応できるでしょうが、500店舗となった場合に日本の小売業が対応できるかというと、おそらく難しいと思います。人材を育てない限りうまくいかないからです。
要するに、ウェッグマンズのやり方は、属人的なので、スケールできない、という事。
続いて、日本とアメリカの違い。
──日本は米国に比べて相当遅れているということでしょうか。
藤野: 一概に遅れているというわけではありません。日本と米国は、そもそも目指すベクトルが違います。日本では人間技でうまく対応することで結果としてのパフォーマンスが出ていますが、経験と勘が中心の属人的なオペレーションのため、スケーラビリティが足りないのです。 “暗黙知”の世界で“組織知”や“形式知”になっていない。
日本の小売業はすばらしい感性を持っていると思いますよ。感性とデータ、つまりアナログとデジタルというのは決して対立概念ではありません。小売業というのは、結局顧客の心の中に入っていかなければなりませんから、感性は重要なのです。顧客はどういう気持ちでいるのか。たとえ同じものを購入したとしても、それしかないから仕方なく購入しているのか、それともそれがどうしてもほしくて満足して購入しているのかによってその内容はまったく異なります。これは絶対にデジタルでは分かりません。
結局、スケール問題だけであって、お客さんに愛される、健全な企業として運営するという意味では、特に問題はないということ。小売は感性です。
ついでに、サイト外だけど、イトーヨーカドーの理念。
伊藤雅俊の「『ひらがなで考える商い』のこころ」
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20060414/101346/
商売は「難しいことば」で考えてはいけない
必要なのは高度な知識より、深い知恵
http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20060616/104561/
「商人が漢字や難しいことばでものを考えるようになると、現場から遠ざかっている」というのが私の持論です。
小売業の経営者も、ある程度会社が大きくなると、現場で接客するよりも、銀行とのお付き合いや同業者との会合が多くなります。頼まれて経営理念を講演したり、ものを書いたりする機会も増えてきます。ときには政府から声がかかり、審議会の委員にと言われることもあります。
そうこうしているうちに、漢字やカタカナ、難しいことばが会話の中でしばしば出てくるようになります。そうなったときは要注意です。現場が遠のき、肌身で感じ取ることが少なくなって、商いの活力が失われ始めているのです。
「ひらがなで考える」ことが重要です。「ひらがなで考える」とは、本で読んだり聞きかじって得た知識でなく、実践を通して身に付いた知恵を生かす思考です。
との事。
わたしって、けっこう本気でECやってたんだなぁと改めて実感。
以上。
ウォルマートは強いんじゃない! 単に上手くスケールできただけだ、という話でした。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
Calendar
November , 2025
October , 2025
September , 2025
October , 2025
September , 2025
August , 2025
July , 2025
July , 2025
Comments
Keyword Search
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.