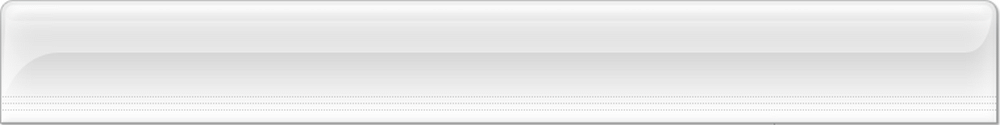全384件 (384件中 1-50件目)
-
『鉄鎖の次王の恋』41.
41. 「おれはそもそも、イオがボルニアの支配者であってもいいと思っていた」 問い詰めるようなレトの次王の目の前に、おそろしく刺激的な言葉を放り投げた。 義兄弟の本心に触れて、呆然とする。 背筋まで冷えたというよう。「い、いま、なん、て?」 聞いたとおりだとつぶやき、なにか重要なことを考えるように虚空をにらむ。「それは、為政者の慢心から一番離れているからだ。……わかるか?」 い、いやと弱々しく首を振る。「たしかにおれたち3王は新しいボルニアを作るかもしれない。だがそれをチェックする『誰か』は必要だ。おれたちが間違ったら正す奴が必要だ。イオにはあらゆる権限がない。だが、わかっている通り、3王に等しく接触して、あらゆる物事を動かしている。その現状認識に異論はないな。おれたちが個々では知らないことも、イオはぜんぶ知っている」 レトの次王はしばらく考える。「……たしかに」「イオの出自は知っていると思う。老王に滅ぼされた部族の出身だ。現在の王政におそろしく恨みを持っている人間だ。おれとイオの馴れ初めを聞くか?」「知ってますが、改めて聞きたいです」 次王は不機嫌そうに鼻を鳴らす。「へりくだるなといっただろう。おれはおまえの意見を聞きたい。遠慮なく話せないようであれば、おまえを3王の一人と認めなくするが、それでもいいか?」 イオは自分に求婚した男をじっと見た。 気づかないうちに、レトの次王が気になり始めている。「イオはなんで副官になったのですか?」 直球の質問に次王は頷き、それだとつぶやく。「イオは、老王を暗殺しようとしていた。重罪である。おれは、老王の様子を探っていたが、常に前にいてじゃまをしていたのはこいつだった。イオはおれよりも老王の陰謀を熟知していたし、まっさきに殺したいと思っていた。それは、迷惑だった。それはわかるだろう? いまだれかの手で殺させるわけにはいかなかったんだ。しかし、イオはおれよりも優秀で、しつこかった」 しばらく長い間、レトの次王は考えていたが、言っていることの意味が分かり始めてはっとする。「暗殺者として優秀だから、副官にしたのですか? 何かあれば自分を暗殺してくれるとでも!?」「そうだ」 それで息をついて次王はいう。「これは、リュディアでは既知だ。イオはそういうやつだと思われている。レトがどう取るかはおれが決められないが、これは一般的に広まるものだと思って対処してくれ」 自分のことのはずなのにそれが掴みようのない速度と権限で流れていく。「おれは、イオにはもしおれが間違ったことしたら遠慮なくその背中を刺せと言っている。これもリュディアは知っている。おれは怖いのだ。いつおれも愚かな人間になるかわからない。おれは復讐に燃えるイオに出会った時、このちっぽけな赤毛のチビに、生きるに値する未来があるのだと、見せてやりたいと思った。それが老王の暴政を防げなかったおれたちのせめてもの贖罪だと思った。だから老王と同じだと思ったら殺せと命じた。おまえは老王のような暴政をする王に自分が成り下がる恐怖に耐えられるか?」 この王は、常に同じことしか言わない。 正直であろうとしているというよりも、根が素直なのだ。 しばらく呆然としているレトの次王に、鉄鎖の次王は言う。「おまえを引き入れた時」「え、あ、いつですか?」「おまえが旅の話をしてくれるのを拒まなかった時だ。正直、ボルニアが南進政策をとれるのはおまえがもたらしてくれた話のおかげだ」 あ、あのときかと呟き、その視線が次王に向く。「おれは、リュディアとヴァンダルではいつか破滅すると思っていた」 神妙にレトの次王は頷く。「仲が良すぎるし、お互い考え方が似すぎている。だからおまえの接触は助け舟のように思えた。そもそも乗り気だったのはリュディアの次王だし、おれはそれに反対しないだけですんだ。感謝しているんだ。それが結果的にレト族だったが、そんなのはどうでもよかったんだ。おまえは簡潔で、下手に恩を売ったりしない。ドライで、外からやって来る旅人だ。商人だ。それがたぶんよかったんだ」 イオは手元に紙がない事に悔しさを感じた。 一言一句書き留めたい。「リュディアもおまえを認めている」「紙を……、」 イオは思わず言ってしまい、それからぽかんとする2人に冷や汗が滝のように流れる。「あ、あ、あ、あ、す、すみません……、」「ああ、そうか、イオ、そういえばアリエスと通じた交易に必要な紙がアイギスにはないんだったな」 違うけど、合ってる。「レト族はリュディアの紙をこのアイギスまで運べるか? べつにエメラルドでもいいのだが、安定した交易品は紙だ。その隊商を組めるか? この包囲下だ。そんなことができるのはレト族しかいない」 色男は考える。「アイギスに運ぶのでいいのか? 海運ならばシドの辺境の商人につてがある」「それでいい」 これは独立気風の強い、シド北限商人の事を言っているのだが、この連中は北方の交易路の中枢であるアイギスに頻繁に船を送っている。クローナ河貿易圏の主流派からはずれた商人で、シド主流派ではない。 これは単純に荷を、北方大陸の北西端のシド領から、船を出してそこからアイギスに運ぶと言っている。レト族が大陸を陸路で縦断できるから言えることである。(レト族はどれだけ交易に長けているのだろう?) 地図が頭に入っていないイオには、なにが起こっているのかさえわからなかった。 ※ イオにとって分からなかったのは、それがセスクとどう関係するかということだった。 そう考えるうちに、セスクとパントの御前試合が盛り上がりを見せ、そもそもイオが企んだにも関わらず、歓声を上げる客席を地べたから見ると、おそろしい光景に見えてしまう。 格好の娯楽なのだ。 包囲されて自由がないアイギスで許される唯一の娯楽。 それがエスト対ボルニアであれば盛り上がる。 罵声がいくつも飛ぶ。 その空気の中、セスクは武者震いをした。「もし、もし、もし、勝てなかったらどうしたらいいんでしょう?」 イオは笑った。「キミが勝ったら奇跡だ。そんなことはだれも想定していない。キミはリュディア流を見せればいんだ。つまり磨き上げた剣技を見せればいんだ。手合わせする? それで落ち着けばいいのだけど」「イオ姉は弱いから、練習にならないよ」 思わず笑ってしまう。「それでいい。あたしより強いというのは参考にならない? あたしは鉄鎖の次王の副官をしているんだ。キミはもっと自信を持っていい」 セスクは、何回も素振りをする。見た感じ必殺の剣で、あまりお勧めできないものだったが、言っても聞きそうになかった。「ようセスク、今日の調子はどうだ? 残念だがこの戦いはおまえの戦いだ、おれは手を貸せない」 にこにことしたようすでルキウスが励ましに訪れ、型通りの素振りをするセスクを見て苦笑いする。ルキウスは訓練用の木刀を握って、イオに放る。「ほら、稽古つけてやってくれよ。すぐに忘れそうだ。リュディア流を思い出さないと勝ち目はない。おれはリュディア流は使えない。イオ、頼まれてくれないか?」「あ、あ、えと、疲れませんか?」「一日中でも戦場で戦い続けるだけの体力はつけさせた。こいつはもう戦場では失敗できないんだ」 なるほどと片手で木刀を構えると、セスクの空気が変わる。(す、隙がない) 泰然とした鷹揚なリュディア流の構えで、無防備に見えるがこの構えが一番怖いことはリュディア流を知り尽くしていればよく分かる。(なに、なに、なに、なにしたの!? ルキウス、なにしたの?) まったく勝てる気がしない。 それで、イオは木刀をおろして、つぶやく。「もう君には教えることが、ただの一つもない。勝てる気がしないよ」 セスクはムスッとしたが、ルキウスが慌ててとりなす。「セスク、叩きのめすことがいいことではない。相手が降参したら、もう追い詰めてはいけない。ヴァンダルが闇雲に戦っているわけではないことは話しただろう? 勇猛であることと、相手を殺した数とは違う。族長は相手の命を奪うことを望まない。流した血の量を誇るのは蛮勇だ。ヴァンダルが信用されるのは、恨みを買わないからだ」 考えてみれば、セスクをルキウスに預けたのは、ルキウスが真にリクトルの副官に相応しいだけの人格者だったからなのかもしれない。「おいおい、イオ、ここにいたのか。なんだセスクもいるじゃないか」 そうのんきな声をかけたのはパントで、横柄な感じで気安く話す。「そうか、セスクはヴァンダルの特訓を受けているのか。これは手強いな、しかし、これはちょっと反則じゃないか?」「なに言ってんだよ。こんなにチビなんだよ? あたしよりも小さいし、13才だよ。これぐらい許してよ。それにこの訓練は果たし合いのためにしてるんじゃないよ? リクトルさまを守れるだけの力をつけるためだよ?」 イオが抗弁するのに、パントは困ったように苦笑いをする。「こっちだって近衛兵団のプライドを背負っているんだ。負けたらレイが首になるかもしれない。おれはあの人の下にいることに満足しているんだ。あの人はああ見えても、自由にやらせてくれるんだ。エマが口うるさいのもあるんだけど」 その名前が出てくると、イオはどうしても微笑んでしまう。(あの紙風船、役に立ってるんだ) ああ、エマと他愛もない話をしたいなあと、思えてきてしまって困る。 42.
February 5, 2016
コメント(0)
-
『花とアリス殺人事件』を見た。
えーと、唐突なのですが、これはジブリつながりです。 ジブリ汗まみれという東京FMの放映中に、この作品の紹介がされていて、わたしはポッドキャストで聞いているのですが、だいたい面白そうだというか、わたしは岩井監督作品はスワロウテイルで見ているので、だいたいどんなものかはわかっていたのですね。 ただ、「花とアリス」観ておらず、それで、いろいろと不安感はあったのですが、結論から言うと面白かったです。 この作品はまずアリスという人物を細かく描くことから始まります。 いい加減で、脚が早く、それでいいて鷹揚な懐の深い14才です。それが殺人事件に巻き込まれて(ネタバレはしない主義です)、隣家のひきこもりである花と接点を持って行きます。 所々に中学生だなあという描写があって、そこには好感が持てます。 幾つかの契機がありながら、ひきこもりだったはずの花がアリスに引きずられ始めるところが、やっぱりこの作品の一番ぐっとくるところで、それをさらっとながしているので、多分ほとんどの人はわからないんですよね。 あんたなにやってんのと罵りながら、引き釣り出されている花を見ていると、アリスのあのいい加減さが救いになっていくのです。 というわけで、短いのですが、これぐらいの短さで投じていくのがいいかなと思います。あんまり構えてしまうと、瞬発的に書けないんですよね。 すごく大切なシーンがたくさんある映画です。 多分一番挙げられるのが、終電後の過ごし方ですが、わたしは名前さえない老人との過ごし方のほうが、ぐっときたかなあ・・・。
January 31, 2016
コメント(0)
-
『鉄鎖の次王の恋』40.のリリースにあてて
こんばんわ! hikaliです。『鉄鎖の次王の恋』40.をお届けしましたが、いかがだったでしょうか? 今回は、いろいろ難しいパートが多くて、どこから説明していいのか困ります(^_^; そもそも、この40.のプロットは、40.41.の合成なのです。プロット書いているうちに、これは合併できるだろうと、考えて強引に合成したのですが、41.はもうちょっと長い予定だったのですが、それを途中でぶちっと切ってしまいました。 正直、41.のプロットにはパントとの御前試合の記載があります。 いろいろプロットに対して考えてしまう内容なのですが、そこまで行かなくてもいいだろうと思ったのです。 実際に書いてみるとこの40.で描いたシーンはこの物語全般のバックグラウンドミュージックに近く、正直ここまで書いてしまっていいのかと迷いました。ただこの辺りで書いてしまわないと、突きつけるところまで行けないだろうと、決断した部分ではあります。 次回がたぶんテーマとしては一番深いところを書く内容になり、明確にこの話が一体何だったのかが理解できる内容になると思います。そこまでの覚悟はまだないので、困ってしまうのですが(^_^; それでも、えいやと書いてしまって、後に引けないようにしてしまうのが、わたしの書き方です。正直ぴりぴりしています(笑)。やってしまったけれど、ほんとにこれはうまくいくのだろうか? それをわたしはよくわかっていないのです。 今回の物語は、事前に自分の書いたものをプロットに書きなおしてみるという「逆プロット化」とでも呼ぶべき作業をし尽くして、ああ、そういう話を書いていたのかと思った結果生まれたものです。 結末はともかく、なんであんなことを熱心に書いていたのだろうと言う部分が見えた時に、物語の筋が一本につながって、大声で笑いたくなってしまいました。ここに帰結するのか、と。非常にぼかして書いているのは、ネタバレにならないようにしているからで、まず次回、そして最終的な物語の帰結を読んでいただけたらと思います。 この辺りは詳しく書けないのは申し訳ないのですが、なにか由来を明らかにしなければならないことがあったような気がしたんですが、なんですかねえ・・・。 ああ、そうか、レトの次王のエピソードですね。 前回になりますが、レトの次王がイオと会談をして、レトはなんとしてもリュディアとヴァンダルの同盟の間に割って入りたかったという話をしているのですが、これはグーグルを参考にしています。 個別具体的に言えばIN THE PLEXで書かれている、初期グーグルの姿です。実際にどこに書いてるのかを探すのはおそろしく困難なのですが(そもそもIN THE PLEXが600ページ超の大著なので)、初期メンバーの中に、ブリンとペイジが困っていた時に、なんでもいいから口実を作ってその仲間に加わりたかったという発言があるのです。 わたしの記憶が確かならば、サーバのメモリの効率を良くするどうでもよいような技術だったのだけれども、それに乗ってくれて、グーグルメンバーに入れて億万長者になれたというようなエピソードだった気がします。 このレト族のエピソードはここから採ってるのです。 あと、これは言ってなかった気がしていて、どこかで言わなければと思っていたのですが、シドの首都であるラスペのデルタを形成するクローナ河の名称の由来って、たぶん書いてないですよね? わたしは非常に単純な性格で、だいたい命名するときに、著名な名称の一字違いにすることがほとんどです。一字削る場合や、一字変える場合が多いのですが、クローナ河の名称を考えていた時は、クローネという北欧の通貨単位から採ったつもりだったのですが、なんとスウェーデンではその通貨はクローナと呼称されるという、いろいろおかしな状況になっているのです(笑)。 これは偶然なんですw 本人としては避けたつもりなんだけど、避けた先がクリーンヒットだったというw なので、スウェーデンの通貨のクローナから採った、でいいですw ちなみにクローナ河はライン河がモデルです。 もっと露骨な言い方をすると、ハドソン川とライン河の合成がクローナ河です。 というわけでこの辺で切り上げたいと思います。 次回が難敵というか、修羅場ですねえ・・・。これを何事もなかったように乗り切りたいというか、乗り切れたらたぶん最期までうまくいく気がします。 というわけで、ぜひともお楽しみいただければ幸いです。
January 29, 2016
コメント(0)
-
『鉄鎖の次王の恋』40.
40. セスクが落ち着くと、次王はイオを伴って、ヴァンダルの宿営地へと向かった。 不安そうについてくる少年を振り返りもせず、大きな背中で次王は言う。「おまえの剣の師匠に会わせてやる。ヴァンダル族でも一目置かれている猛者で、もしおまえがいなければ、そいつをリクトルの副官にするつもりでいた」 セスクはしばらく考える。「ルキウス、ですよね」「そうだ。歳は3つ上だ。おまえは剣の腕は十分かもしれないが、年齢による体格差はどうしようもない。ルキウスだって常に強くなるだろうし、3才の差は膨大だ。一生ルキウスには追いつくことはできないだろう。だからおまえの師匠にルキウスを選んだ。あいつに学べ。そしてあいつに追いついてやると思え。そうすればあいつは負けられないと、もっと強くなろうとする。おれはそれを望んでいる」 まさにボルニア流というよりは、ヴァンダル流の戦士の育て方だった。 このレト族の少年をヴァンダルの流儀で鍛え上げようと言うのだ。「怖気づいたか?」 しばらく黙ったセスクを挑発するように、次王が聞く。「つよく……、どんな方法を使ってでも強くしなければならないんですね?」 次王はおや? と振り返って、その武者震いする少年を頼もしげに見つめて頷く。「そのとおりだ」 宿営地は次王の来訪を受けて蜂の巣を叩いたようになった。 暇つぶしに訓練をしていた面々が慌てて汗を拭い(そういう部族なのである)、支給され始めたばかりの毛皮を羽織って、続々と次王の前に集まってくる。「リクトルさまは、副王は無事ですか?」「ああ、命に別状はないと聞いている。正直エストにこれほどの高度な治療法があるとは思わなかった。知っていたか? 刀傷が膿むのを防ぐのには、ウィスキーを吹きかけるのがいいらしい。ただ、これは想像を絶するほど苦痛をもたらす。あのリクトルが子供のように呻いていたよ。それをしつこいぐらいに永遠に続けるんだ。エストの連中はそれを消毒と呼んでいる」 それはほっとするというよりは、慣れないボルニア人には異教徒のしわざのように感じるのだが、具体的になにをしているのかが分かるのは、少しは心の足しになる。足がかりになるからだ。「エストの治療団に任せておけば、おれが倒れても、きっと元通りにしてくれるだろう」「冗談はやめてください」 そう直言したのは、イオにも顔なじみのルキウスで、イオよりだいぶ若いが真っ直ぐな性格の好青年である。イオが次王の副官に選ばれた時に一番傷ついたはずなのだが、イオには非常に協力的な姿勢を示し、むしろ反対するヴァンダル族を説き伏せて回った。 イオの立場を作ったのはこの青年だ。 それはイオと次王とただならぬ呪われた関係を察知したからだろう。 おそらくルキウスには、厄介事を次王とリクトルに押し付けている自分たちの姿が見えていたのだろう。イオからしてみれば理解力のある同僚だった。「ルキウス、ついさっきリクトルの副官が決まった。元々ルキウスにしようと思っていたが、考えを変えた。こいつにする。このチビだ」 セスクが紹介されると、ヴァンダル族の面々は口々に言う。「レト族のガキじゃないですか!」「こいつは、リクトルさまの重傷の原因になったんです!」「こんな線の細い子供にリクトルさまの護衛なんてできない!」 怒号のように叫ばれる非難を、ルキウスは黙って耐えた。 次王はそれを涼やかに見ていて、ルキウスはその次王の考えていることが、たぶんわかった。「こんなチビだと、お前たちは言う。それは正しい。こんなチビでは、話しにならないのは明らかだ。だがこいつは目の前で自分のせいでリクトルが重症を負った時に、常に責任を感じて、いっさいの言い訳もせずに、いっさい逃げようとしなかった。13だぞ。こんな重大なことをしでかして責任を取ろうとするやつがいるか?」 それで黙る。 しばらく沈黙が続いたがルキウスが答えた。「おれもそうした」「そうだルキウス、おまえもそうだ。こいつはおまえと同じだけの責任感がある。だが、こいつはリクトルに対して一生かけて償わなければならない借りがある。こいつはリクトルを命を投げ出しても守ろうとするだろう。こいつは呪われているんだ」 イオは自分と次王の関係を考えざるを得なかったが、呪われているから上手く使われているのだろうかと考えてしまう。「それにルキウス、おまえは前線にいて欲しい。イオのようにおれの背中にしがみついているのではなく、隣にいて前を見て戦友として共に戦って欲しい。おまえは若いがヴァンダルでも一二を争う猛者だと思っている。陣で隣に並んで欲しい、不満か?」 ルキウスは言葉を失った。 しばらく困ったように言葉を探し、やっと言う。「い、いえ、そこまで認めてもらっていたとは……」「ただ、こいつが足手まといのままでは困る。おれも困るし、リクトルも困るし、ヴァンダルも困る。ルキウス、おまえは馬鹿にしているかもしれないが、こいつはイオより剣技は上らしい。リュディア流の剣技を叩きこまれている。だから送り込まれた。こいつを鍛えあげてやってくれ。ヴァンダル流の何たるかを叩き込んでくれ。それができるのはおまえだけだ」 震えるセスクが訓練用の剣を握ると、ルキウスは同じように木刀を握って、軽く息をついた。 次王やヴァンダル族はそれを賑やかに取り巻いて、地べたに座り、くつろいだ様子で果たし合いを見守る。おそらくこれはヴァンダル族の文化なのだろうとイオは思うのだが、たぶんこのような訓練の光景を娯楽として楽しんでいるのだ。くちぐちに下馬評を語り合うのは、剣術に対する評価に対する見識を高めるのに役に立つだろうし、それが評判になると分かれば、お互いに手が抜けなくなる。「まず、おまえの剣技を見る。それからどこまでその身体でやれるか試す」 ルキウスは宣言し、非常に一般的な構えをする。 それに対して、セスクはすぐに防御一辺倒の構えをして、備える。 どちらが動くというでもなく、二人の剣が合い始め、ルキウスが剣を叩き込むが、それを奇怪な剣技で受け流すという展開が続く。「リュディア流だ、しかもかなり上手い」 どこからともなくつぶやきが漏れる。 なんどルキウスが打ち込んでも、セスクは巧妙に受け流し、それで相手の態勢を崩してわずかな息をつく。もちろん、セスクからの攻撃はない。速い太刀筋を受けるのに精一杯なのだ。「どちらも強いな……」 だれかが呟く声に、木刀が打ち合う音が響く。 業を煮やしたのはルキウスだった。その胸に炎が灯るのがイオには見える気がした。 イオがやったように力勝負に持ち込み始め、相手の体力を削ろうとしていく。強靭な筋力に裏打ちされた強打を浴びせられ、それが支えられなくなる。揺らいだところに、ルキウスは体当たりをした。 おそろしく泥臭い。 それで重心を崩したセスクの脚を払い、転んだところに剣を突きつける。 肩で息をしていた。「おまえは強い。それは認める。だが、おまえは身体ができていない。そんなのは、誰もひと目で分かる。だが、いまから急激に大きくなることは無理だ。だからおまえの仮想敵は常におまえとの体格差で勝負してくる。その時にどんな手を使ってくるかを知り尽くせ。その対策をとれ。正直リュディア流と戦うのは楽しい。たっぷり付き合ってもらうぞ。どんな手で来るのかを理解し尽くすまで、付き合え」 イオはふと思い出し、次王に言う。「そういえば、レトの次王と約束しました」「なんだ」「セスクをパントと御前試合で戦わせて、勝たせると」 次王はしばらく考えていたのだが、諦めたように言う。「それはあいつの承諾が必要だ。あいつと話に行こう。レトの次王と話すのは久々だ」 ※ 次王は一応毛皮をまとっていく。 それが礼儀なのかはイオにはわからなかったが、もしかしたら寒かったからなのかもしれない。 雪がちらつく大要塞を歩きながら、白い息を吐く。 各部族の宿営地に立ち寄り、いちいち地方色豊かな鍋に匙を伸ばし、それを食べて美味いという。イオはつまみ食いをする次王について行っていいのかさえわからず、申し訳程度に、匙を伸ばして、味見をする。「レトの次王との直談判するんではなかったのではないですか?」「わるい。ちょっと我慢してくれ、おれはなにも知らないんだ」 その弁明は、食欲を満たすのは許せと言っているようで、聞いたこともない部族の料理に感心しきっている姿とは、変なミスマッチに思えた。 次王は味見をしながら、ボルニアの諸部族と食べ物の話をしていく。 それは盛り上がる時もあったし、次王の口にあわない時もあった。 もちろん、理解できないのはイオの未熟さではあるのだが、正確にいうと、この王はボルニアを知りたかったのだ。 それで食べる。 これは、おそろしく効率的な方法で、食べることでこの王は簡単にボルニアを理解した。 ジャングルの部族たちはなにを食べていて、どんな食卓を囲んでいるのか。 これは辛すぎないか? ロゴス族では、子供もこんなものを食べるのか? いえいえ、子供にはつらいので、この香辛料を掛けるのは大人だけです。もうちょっと温かいものとか、芋のたぐいが殆どです。でもこのキノコは入れるんだろ? ええ、これがいい味になるんです。 イオはそれがおそろしく豊穣な情報であることに気づき始めた。 これは食べることを通して、その部族の家族の日常を聞いているのだ。 外交上すぐれた情報収集をしているとイオが思ってしまうのは、官僚部族であるリュディアの考え方にイオが染まっているからだ。次王は素直な好奇心の発露として、ボルニアの諸部族を知りたいと思っている。 それを次王は心の底から楽しく満喫している。「イオ、すまん、次が最後だ」 もう、何回告げられたかわからない言葉だ。 それでも次王は部族の食事のはしごを続け、ようやっとやめようと思ったのは昼食の時間が終わり始めた頃になってからだった。 鉄鎖の次王が現れると、レトの宿営地は騒然とし、慌てるレト族の面々を見ながら、「いい話を持ってきた。族長はいるか?」 と端的に聞く。 するとレトの重臣らしきものが前に立ち、おそるおそる次王の顔を伺う。「いい話だといった。おれが嘘を言ったことがあるか?」「いえ、ありませんでした。どうも耄碌するといろいろ大切なことを忘れます」「貴公はレト族に忠実なだけだ。警戒するのもわかるが、おれとレトの次王は盟友だ。幼児の頃からの親友だ。あいつは交易から帰ってくる度におれたちに外の世界の話をずっとしてくれた。おれたちはそれで外の世界を知った。おまえたちは族長を軽視しているのではないか?」 ちくりというのは、レトが割れているからだ。「めっそうもない」「では、早くレトの次王に朗報を伝えたい」 イオは3王の相変わらずのやり口に感心してしまうのだが、結局のところ鉄鎖の次王の権威の行使が部族を動かしているのは、どうしようもない。 レトの重臣は次王のもとまで案内し、その顔を見るなり、ヴァンダルの青年は歩み寄って肩を抱いた。「いいのを送り込んでくれたな。セスクだ。あいつは使える。リクトルの副官にすることにした。あいつにレトとの連絡は任せることにする」「喜んでもらえると思いましたよ」 とうとつに次王の表情が怒気をはらむ。しばらく沈黙したのちに言う。「へりくだった言い方はやめろ。おまえはレトの次王だ。新しいボルニアは3王が等しく並立する国だ。リュディア、ヴァンダル、レトが共に同じ立場にあって協力する国だ。ヴァンダルに責任を押し付けるな。それに不満があるか? おれに責任を押し付けたいか?」 軽口が出てこないことを確認して、イオはあんがいこの夫立候補者は良く出来たやつなのかも知れないと思い始めた。「イオに求婚したそうだな」 とうとつに次王は言う。「たしかにおれも気が合うかもしれないとは思う。ただ、リュディアとレトが同盟を結んだと思われると、ヴァンダルがざわつく。ヴァンダルを統治するものとしては、余計な厄介事を持ち込んでほしくないのだが」 しばらくレトの次王は考えて言う。「だが、これは本気だ。話すうちに、ますます惚れ込んでいく。はじめはそうだ、打算だった。レトがリュディアとヴァンダルの同盟に食い込むためには、その情報の中枢であるイオに常に接触できる口実がほしいとは思っていた。だが話してみると、想像を絶するほど魅力的だった」 あまりにも正直すぎる発言にイオが戸惑ってしまう。 イオの周りにはあまりにも魅力的な人物がいる。それらに好かれるのは、ただ単に、イオがなんの遠慮もなしに暴力的な発言をするからであるのだが、それが地位的に上位の人達に響くのは、それが珍しい現象だからなのかも知れない。「イオ、リュディアに似たような跳ねっ返りがいるだろ? 紹介してはどうだ?」 これは不意であり、かつ、こころがキュンとする言葉だった。 はじめて、鉄鎖の次王が嫉妬を見せた。 それはイオの勘違いだったのだけど、こころが乱れた。「あ、あ、あ、リュディアはいまは写本で忙しいですし……、優秀なのは本国にいるのです……。あっちは兄貴がいないから大変で、出せる人物がいないのです……」 イオが慌てて言うと、次王はにやりと笑う。「この役をセスクに任せたい。ヴァンダルとレトの橋渡しになる副官だ。おまえが送り込んだあいつはなるほど、それに適任だ。まず族長としての許可がほしい」 優男はしばらく考えていたが、端的に許可しますという。「ちがう、ちがう、ちがう!」 次王が大声で叫ぶのに、レト族がびくりとした。「おれが求めているのはそれじゃない! キュディスの政治体制はそうなっていない。各騎竜兵団の投票で許可するかしないかを決める。ボルニアの3王が等しい投票権を持っていて、多数を持ってその行動を許可するかどうか決める、分かるか?」 たぶんレトの次王はびっくりしていて、完全に平等な票を3王は持っていると言っていることに、言葉にするのが難しくなっていた。レトは差別を受ける下等部族としてあつかわれている思っていたのだ。「レトは……、レトはなにを差し出せばいいのでしょう?」「セスクだ。あいつはレトの未来だ。おまえがそういった。おれもそう思う。あいつはイオに預けた。イオは預かった少年をむげにはできない。どんな手を使っても、セスクを大切に守ろうとする。おまえのところに殴りこんだだろう?」 色男はイオをチラと見て、ため息をつく。「イオが、アンタッチャブルになってしまうがいいのか?」 41.
January 28, 2016
コメント(0)
-
震災ストレス解消法
注:この小説は、震災ストレス解消法として、寄付をオススメする内容です。 寄付は義務ではないですが、ストレス解消法として大変効果がありますと書いています。 NHKラジオを聞いていたら、震災被災者を西日本の温泉旅館に避難してもらって、国費でその費用を出すなんて話があって、温かいお風呂に入ると、身も心も温まるなんて話をしてた。 いいんじゃん。 バスなんてじゃんじゃん送っちゃってさ、とりあえずほっとしてもらえれば、どんなにかいいかさ、病院だってあるし、食べものもあるし、国費で神戸牛を食べてもらってもいいし、西日本の腕の立つ料理人は、ボランティアでもおいしいものを食べてもらおうと腕を振るうだろうしさ。 電車に揺られて、何か計画停電であわてふためいて買った携帯ラジオを聞くのがなにか最近マイブーム。 単四電池で毎日聞いても4日は持つし。 イヤホンから流れてくるニュースを聞きながら、これは夢じゃないんだって思う。それでも流れてくる話を聞きながら、ああ、日本の形が変わってしまったのだと、そう思う。(地図が変わっちゃったんだよね) もういっかい、書き直しじゃん、地図、大変だね。 それでもコカコーラZEROを飲むとしゅわっと口の中ではじけるだけで、元気になる。このおいしさを味わえばみんな元気になるのに、なーんて思ってしまう。 休日の私鉄電車はがらがらで、みんなそれほど暗くない顔で乗っている。 明るい日差しに照らされる人たちの顔をみていると、ここは平穏で、あの震災のこわい混乱から隔絶された世界のように見えてくる。 車窓の外に見える明るい街並みを見ていると、なにかほっとする。 あたしにとっては、初めて身近に感じた震災。 テレビで見て、ラジオではずっと聞いている、そんな震災。 沢山のひとたちが苦しんで、あたしたちは今のところ安全な所にいる、そんな震災。 ときどきある計画停電にもだいぶ馴れて、それでも停電のたびに、むっと怒るのだけど、それでも被災地のことを思うと、まあ、しゃーないかって、そう思う。 電車を降りると、言葉の少ない人たち。 そこをすたすた歩いて、改札へ向かう。 あたし、言っちゃったんだよ。 お前たちのクズみたいな言葉よりも、500円玉の方が価値があるって。おまえらがくだらないことをぎゃーぎゃー言い合っているよりも、100円募金する方が価値があるって。だからこれは自己責任。この前、もらったグーグルの広告費を崩しに行く。こんなのあぶく銭みたいなものだし。 携帯を開くと、ネットの怒号がすぐにやってくる。 なんだろ、この人たち、白痴みたい。 ストレスを処理できなくてわめき散らしているだけなんだって、あたしでも分かる。(そうでなければ、悪意を持って混乱させようとしているのだけど) かわいそうな人たち、ばいばい。 あたしにはそんなのにかまっている暇はない。 昨日のテレビでは、無残な被災地の様子が映し出された。途方にくれたようなリポーターの正直な感想が、ああ、あそこに立ったらこう思うのだろうなって、それぐらいは感じた。 被災地では、避難所で暖房もなく、食料もないのだという。 黒い波に呑み込まれる街と、逃げ戸惑って波に飲まれる自動車。 淡々と正常を維持しようとする、妻を失った老人。 もうそんなのが、現実なんてイヤじゃん。そんなの受け入れられないじゃん。 でも、それが現実なんだって、分かるしかないじゃん。 それが出来ないひとたちが、騒いでいるだけなんだよねって、分かる。「お前たちのクズみたいな言葉よりも、500円玉の方が価値がある」 そう呟いて、グーグルマップの印刷を見る。 銀行がすぐそこにあるはずだ。エスカレーターに乗って、エレベーターに乗って、土曜日に開いている銀行窓口に行く。あたしみたいなお客をブルーのシートと、大画面のロイターの為替情報が迎えて、親切なお姉さんが、応えてくれる。「あの、募金したいんですけど。今あるドルを全部円にして」「ではまずサインと、ここと、こことですね、ご記入をお願いします」 さらさらっと書いていく。 困って聞くと、お姉さんが丁寧に答えてくれる。「お振込口座はどこですか?」 しまった、分からない。 でも、そう、確かそうだ。「テレビ朝日でやってたんです。振り込めって」「ああ、ではお調べします」 しばらくして、お姉さんがあたしよりもきれいな字で書き込んでくれて、それで全部終わったらしい。「大変もうしわけありませんが、週明けの処理になります」 うん、それでいい。 丁寧な複写用紙を受け取って、その銀行を出て、エレベータに乗って、電車に乗ったけれども、なにか実感が湧かなかった。(あのお金でなにが買えるだろう?) そう想像した途端、沢山のひとたちが、おいしいあったかいコーヒーを飲んでいる光景が浮かんできて、コーヒー、おいしいって言葉がきこえて来て、なにか背筋が震えた。あたしが払ったたいしたことのないお金が、少なくともあたしみたいなどうでもいい人よりも役に立つんだって想像できて、吊革を握っているのが困難になった。(あたし、役に立ったじゃん) そう思った途端に、なにかこれまでの震災ストレスがなくなってしまったような気がして、その代わりにコーヒーおいしいと言っている人たちの顔が浮かぶようになった。 気付いたら、なにもかもが消えていて、暖かかった。 駅を降りて、あたしすっからかんになっちゃったなと思った。 まあ、もともとすっからかんなんだけど、なんでかあった貯金まではたいたのかと、思った。でも、まあ、死ぬわけじゃないし。 改札を出て、自動販売機に150円を入れてコカコーラZEROを買おうとして、手が止まる。(このしゅわしゅわ、被災地の人に味わってもらいたいかも) そう思って、今日の150円は募金に回そうって思うと、心が軽くなる。 ひとり100円、一億人なら毎日100億円じゃん。 一年続ければ3兆6500億円。 こんなストレス抱えているぐらいならば、一日百円寄付する方が楽なのにね! あたしは、駅を出て、自宅へと帰っていく。「ばかばかばか、みーんな、ばか、おおばか。なんにも分かってない。こんちんちきの、くたびれもうけだ!」 そう大声で叫んで、あたしはご機嫌で商店街を歩く。 節電しているお店の間を歩くうちに、ふふっと笑みが漏れる。「でも、ないか」 世界が輝いて見えた。
March 19, 2011
コメント(2)
-
サマーウォーズを見て来た。
もはや、このサマーウォーズが面白いか、面白くないかは話にならない。 問題はこの映画が何十億円売り上げるか、が唯一の問題になりつつある気がする。 休日しか予定が開けられないのであれば、見ることが出来るのは、数週間後になるかもしれない。 もはや、この映画のチケットは早い者勝ちになっている。 本日は県内で鑑賞。 18時までに家に戻る予定だったので、満席だけは避けたかった。 そこで、本命館とは別に予備館を設定、二重の備えで出陣(あの映画を見た後ではそう書きたくなってしまう)した。 本命の新都心のシネコンまで来て状況の予測があますぎたことを理解する。 次の回はもちろんのこと、その次の回も満席で、その次の回も残券少。早速、予備シナリオに切り換え、浦和駅から浦和美園駅行きのバスに飛び乗った。 サマーウォーズは、時をかける少女の細田監督の原作作品で、期待を集めていた作品だ。配給はワーナーブラザース。おそらくこれは独占配給だと思われる。つまり全国のワーナー系の映画館でしか見ることが出来ない。 おそらくワーナーは需要を見誤っていて、上映しているのは200席程度のミニスクリーン。本来なら500席はあるメインスクリーンで上映しなければならない映画をそうしてしまうと、どうなるかは分かりやすい。 来週どの映画館も一杯との噂を聞いてメインスクリーンに観客が殺到する。 そして、もしかしたら、その客席も一杯になるかもしれない。 なぜならば、この映画は抜群に面白いからだ。 もっと面白く出来るという猛者はあったとしても、つまらないという人はないに違いない、この全世界にたったひとりも。 そう、よく出来たジブリ映画のように。 浦和美園まできてあふれる浦和サポータに遭遇。 そのショッピングモールの駐車場が埋まっているのをみて、焦りが出てくる。 浦和美園のショッピングモールって閑散としていたイメージだったのだが、甘い甘い。モール中お客にあふれ、しかもユニホーム姿の赤い連中までかなり多くいる。まあ、試合前に暇つぶしなんてまあありそうな事だけど、ワーナーのコンコースまできて焦る。見慣れたユニホーム姿がわらわらと。 ちょwww 試合前に映画もみておこうなんてシナリオ想定してませんでしたからwww もう完全にマーケター失格。 チケット売場の前の長い列に慌てて飛び込んだ。 しかし幸いにも、サマーウォーズが家族連れに抜群にいい映画という認知がまだ形成されていない(そして来週には形成されている)。しかも今年の子供映画は大ヒットが狙える良作揃い。その微妙なセグメントがずれていたせいで、ぎりぎりチケットゲット。当然のようにわたしがみた回は満席だった。 サマーウォーズの見所はどこかといえば、やはり29人にも及ぶ個性豊かな大家族の面々といえるだろう。そんなに大勢の個性を出せるのかといえば、出てるんだから、できたんでしょ? としか言いようがない。 はじめのうちは突然にそんな大家族にほうり込まれた健二くんのような気持ちになる。 しかし、いくつものシーンを経ると、その大家族内にある生態系のようなものが染みてくる。そう、健二くんのようになんとかやっていけるのではないかと、思えてくるのだ。これが、この映画のすべてと言い切ってしまってよいような気がするのである。 たとえば、このヒロインである夏希は終盤に来るまで、全く活躍するシーンがない。 主人公である健二もほぼ同様で、主人公とヒロインにいいところがなくて、面白い映画なんて作れるのであろうかと、たぶん思う。 しかし、それでいいのだ。 この映画の主役は健二でも、夏希でも、侘助でも、まあちょっとは主役っぽいところがあるがキング・カズマこと、佳主馬でもない。 この映画の主役は、総勢29人にも及ぶ、陣内家の個性豊かなひとりひとりであるのだから。 はじめのうちは、この人たちがどんな人なのか、まったくさっぱり分からない。 それでも、この陣内家には、当主たる90歳のおばあさん、陣内栄を筆頭に、何かよく見えない絆のようなものがある。はじめはそれがいったい何なのか分からずに、おそらくよそ者のように居づらい心地にさせられるだろう。 しかし、事件が起こり、栄を筆頭にまさしくサマーウォーズが開始させると、これは夏の陣とでも訳すのがいいのだろうが、夏の陣が始まった途端に、それぞれの個性が見えてくる。 高校野球にしか興味のないおばちゃん、はりきる男たちをよそにそんなことやってどうするんだろうと、淡々と準備をし、家をまわすおばさん(ここはネタバレになるので、抽象的に書いているが)、家中を駆け回り、お風呂で遊ぶ子供たち、嫌がらせをする夏希を好きなまたいとこ、豪快な漁師であり師匠でもあるおじいちゃん。 いま、わたしは家系図を見ながらそれぞれの表情を回想して、にやにやとしているが、この映画を見た人であるならば、同じ感想を抱くだろう。 家系図を見るだけで、シーンが思い出されて楽しくなってくると。 まるで、テーマパークをみるよう。 それが、夏の陣内家を駆け回り、呼吸をし、時にはぶつかり合い、そして、一緒にごはんをたべて、この陣内家のお屋敷に生息している。 そういう映画だったよ、サマーウォーズは、といえばすべてが伝わる気がする。 この家族が戦っているのは、OZと呼ばれる仮想世界に入り込み、世界中を混乱に陥れているAI(これぐらいは書いてしまおう)。これが二重三重に陣内家と因縁がつき、戦わざるを得なくなる。 スーパーコンピュータが、自衛隊の極秘装備が、イカ釣り漁船が、ブラウン管の巨大モニターが家族のつてを通じて運び込まれ、反攻が始まる。 このエスカレートしていく様子は見ていてとてもわくわくしてくる。 まったく心の面白さをゆるませることなく、夏の陣は盛り上がり、家族は世界と繋がっていく。 いくつぽろりとしてしまうシーンがあったかと指おると両手では足りなくなってしまう。 いくつ、ぐっとくるシーンがあったかと指おると、足の指でもとうてい足りない。 その他、ちいさなにこっとしてしまうようなシーンなど、数えるのも馬鹿らしくなってしまう。 すべてが余すところなくいいのだ。 ハリウッドとはまったく違う、ジブリともまったく違う、独特の時間の流れがこの映画には満ちていて、それがテンポ良く次々と起こるので、退屈という言葉とはいったいなんだったのかさえ忘れてしまう。 加速度的にそれは心に伝染して行き、わたしは映画を見終わって、急いで電車に飛び乗って、物凄い勢いでこれを書き始めてしまう。 つまらない言葉など忘れてしまおう。 なんか変なことを言っているお偉方の言葉は忘れてしまおう。 サマーウォーズ、面白かった! それでいいじゃないか。 あした、仕事さぼって、もう一回見に行こうかなあ・・・。
August 2, 2009
コメント(0)
-
ネゴシエイトする世界
というか、わたしは変だ。 小説が書けて、デザインができて、プログラムができて、歴史に厚い知識があって、美術品を取り扱う仕事を昔していて、ネゴシエイター役ばかりやっていて、物語の研究をしていて、サッカーが好きで、ゲームも好きで、リサーチマーケターで、いろいろな事を分析することが大好き。 現在は知財系の仕事で、親の仕事を継ぐ準備をしている。 文字にしてみると、はちゃめちゃすぎて、ヨクワカラナイ。 正直言うと、わたしも、なんだこいつはと、首を傾げてしまう。 変なやつだと。 わたしはとびきりに変なやつかも知れないけれど、人というのはたいてい変なやつで、ヨクワカラナイ。 真夏の品川で、上司と歩きながら大学時代の話をする。わたしはその上司は馬が合わず、たぶんこの人に潰されるだろうなと漠然と感じていたのだけど(実際そうなった)、エレベータの制御方法の話を聞いたり、難航したプロジェクトの話を聞く。 たぶん、わたしはその人の心や境遇から何光年も離れていたのだろう。 ただ、それでも感じるところはあって、わたしは言った。「そういう勉強をしている人は尊敬します。すごいですね」 ただ、わたしは現場のスペシャリストとしての訓練ばかり受けていて、学際的な方向からの指向とは水が合わない性質だったし、性格的にも、学問を振りかざして現場に介入されるのは嫌っただろう。 わたしはすぐに分析して、その理論が事実と異なる事を突きつけて、崩壊させる道を選ぶだろう。現場でうまく回っているのを勝手な言説で壊して欲しくないのだ。そして、これはまったくそうなのだが99.9%の言説は精度を欠いてまったく役に立たない、単なるなまくらなのだ。 どうやったら、そんなにも馬の合わない上司と息を合わせられるのか、ヨクワカラナイ。 それは機能しない事を、目の前で見せつけられても、考えを変えない人は切り捨てるしかない。 これが今の社会の、根本的な不幸だと思う。 議論を機能させることができる人は、ほとんどいない、とわたしは思う。 有効なのは、交渉であって、ネゴシエーションで議論に陥ったら、完全に失敗であると、ネゴばっかりやってきたわたしは思う。 ネゴは簡単。 お互いが利益になる地点を見つければいいだけだ。 やることは、相手をみて、自分をみて、どの地点に着地するのが一番いいだろうかをみつけるだけなのだ。お互いが笑える場所を常に柔軟に探し続ける。その努力がネゴシエーションと言ってよいと思う。 敵対は無意味。協調がすべて。 ゼロサムは機能しない。プラスサムが機能する。 ゲーム理論は役に立たない。誰か、それ以上のノーベル賞ものの理論を作って! それが今の世界で、そう動いていることが分からない人がいるのが、ヨクワカラナイ。 ネゴシエイトする世界なのだ。 今は。 世界中が、協調の仕方を模索している時代なのだ。 そのとき、ヨクワカラナイ人は不利なのである。 なぜなら、相手がわたしにとってのネゴポイントを見つけてくれないので。 そのために、ヨクワカラナイ自分を発掘して、どう説明すれば、わたしにとってはそれは利益になっているし、わたしはとても楽しいし、とても嬉しくて仕方ないかを、理解してもらえるのだろう? 物凄く遠いところにやり投げの選手のように投じなければならない。 それが当たってはじめて伝わる。 どれほどの精度が要求されるのだろう。 ヨクワカラナイ人の苦労はなんとなく伝わるだろうか。 まあ、いいや、この辺で投げておく。
June 25, 2009
コメント(0)
-
好きこそ物の上手なれよりも、苦痛のマネージメントの方が大事では?
開発ブログの方で進めていたFLASHゲームブックをリリースした。 だいたい、原稿用紙換算450枚ぐらい、コーディングしたActionScriptは1000行ぐらいである。 分かる人には、それなりの規模であることが分かるのではないか。 それなりによくできたものにはなっていると思う。 ■FLASHゲームブック「ジャングルの要塞」リリース!!! http://blog.story-fact.com/?eid=1099100 今わたしはこの文章を宣伝のために書いていて、それはそうとしてここは本家なので、それなりの知見らしいことも提供しないとまずいなあと思っている。 そこで、なにか有益な経験はなかったかと思い起こし、表題の件について思いついた。 まず、事実であるが、このプロジェクトは3/25にシナリオが15分で作られ、そこからまるまる一ヶ月にわたって原稿が執筆され、4/25に完成している。そこから、開発に入り、リリースが5/4。なので、発案15分、原稿30日、開発10日であったと気付く。 原稿用紙450枚分というと、分厚い文庫本程度なので、それなりの文章量であることが分かるのではないだろうか。 これは文章量だけを見れば、専業としてもそれなりの文章量であろう。 しかし、わたしはこれを平日の夜と土日だけを使って書いている。 それこそ、つぎ込まれた時間はおそらく何百時間の小さい方になるけれども、特に予定を入れず、余暇時間をほとんど書くことにつぎ込めば、これぐらいの時間は捻出できると思う。 問題は、わたしがなぜ、それだけの時間、原稿を書くことに使うだけの、これは一般に広まっている表現で言えば熱意があったかと言うところだ。 果たしてこれは熱意だったのだろうか、と首を傾げしまうのである。 わたしは、毎日のように嫌がる自分を追い立てていたし、書くように追い立てた。書くのを嫌がったのは、やはり書き始めればつらいし、つかれるし、脳味噌を絞らなければならないからで、やはりこれは苦痛を伴うのである。 しかし、一方、書き上げることは、楽しい結果が待っているのである。また、想いも掛けないよいシーンを書けることもある。これは一種のごほうびだ。 漫画家のまんが道でもなんでもいいのだが、その自伝的な作品を読むと、その生みの苦しみと、書き上げた喜びを読むことができる。 その一面を取り上げると、実はめちゃくちゃ苦しい。もう自殺したくなるほどに苦しむ。果てしなく大きな苦しみに出会う。 また、別の一面では、天に昇るほど嬉しい想いもする。自分は生きていてよかったと、こんなことがあるから漫画家は止められないのだと。 果たして、どちらが正しい姿なのだろうか? こう書けば分かるとおり、どの側面も事実なのである。 とても苦しい一方、とても嬉しいこともある。 わたしが、なんで書けるのかと言えば、この両方を合わせたときの合計がわずかにプラスになるから、だと思うのだ。 書けるのは、わたしがわたしの周りの環境を調節して、うまく苦痛とうれしさの収支がプラスになるように保っているからだと思う。決して、楽しくて楽しくて仕方ない訳ではない。企業の収支報告を思いだしてもらえればわかりやすいが、例え売上高数兆円の大企業であったとしても、数百億円の特損を計上して、最終赤字なんてことがある。わずか一パーセントの誤差で、書き続けるのが馬鹿らしいように思えることもある。 生き残れる人というのは、この収支をプラスに保ち続けるのがばつぐんにうまい人のような気がするのだ。 著作権の議論などで、商業創作が語られる局面で、書き手なんか、お金を払わなくても書くのが好きなのだから書くよという極端な議論がある。これは、まったく理解していない発言で、そう言うのは、この機会に改めたい。 実際、お金が理由というのが、その書き手の10%とか、5%ぐらいのモチベーションにしかなっていないとする(実感では25%ぐらいなのでは、という気がする。職業人としての誇りも含めればもっと大きい気もする)。しかし、先ほどの収支の考え方で考えれば、それが実はとても大きいことに気付く。 たとえば、売上高2兆円の企業の5%の損失は1000億円である。 この損害が発生した時点で株価は急落し、おそらく最終赤字に達する企業もあろう。 たしかに書き手のモチベーションの95%はお金とは関係ないかも知れない。 しかし、収支で考えたとき、その5%でぎりぎり持ちこたえている書き手もいるのではないかと思うのだ。もし、この5%が永続的に失われれば、どうであろうか? その書き手には致命傷になり得る。 こういう認識に立って欲しいのである。 しかし、別の見解も提案できる。 好きになれば続けられるとか、好きこそもの上手なれと、若干の楽観論があちこちに溢れているのだが、それ見ていて、わたしはむしろ逆ではないかと思うのだ。 好きなら苦痛はない、は嘘である。 苦痛は存在するし、それは消えない。 しかし、どうだろう? その苦痛を緩和する方法があったとしたら? 苦痛を和らげる手段を身につけた方が、続けられるのではないかと。 好きこそものの上手なれが、プラスをのばす方法であるに対して、わたしが書こうとしているのはディフェンシブな、企業で言えばコスト体質が良質な堅実経営におそらく該当する。 もし売上高が一定で、コストが下がれば収支はプラスになる可能性が高い。 ■習慣性、追い詰め方の上手い下手、+5%を常に狙っていく 実を言うと、これから書くことは、体育会系の部活動(しかも、強いチームの)でよく取られている方法で、たぶんそれを知っている人は、まったく新鮮さはないと思う。わたしはこれを書きながら、体育会系の部活動の日々の練習は、練習の苦痛を和らげる方法のノウハウが膨大に積み上がっているのだなと思うのである。 ・習慣性 練習はきつい。だけど、毎日耐えている練習ならば、それは日常なので、別にきつくない。これがけっこう負荷を下げることはあちこちで語られる。 毎日、この時間からは練習と決まっていれば、苦痛が減ると言うよりは、慣れる。それを何週間も続けていると、それをしていない日を不安の内に過ごすことになる。部活動というのは、たとえばわたしはバドミントン部だったのだが、そのバドミントンがなんか役に立ったかと言われれば、首を傾げる 中高大とバドミントンを続けたが、結局なんの役にも立たなかったといわれればそうだろうと頷くいがいにない。 部活の練習というのは、だいたいスケジュールが決まっている。 バドミントンで言えば、 1.ランニング 2.ストレッチ 3.チャイニーズステップ 4.フットワーク 5.基礎打ち 6.カット練習とか 7.2対1とか 8.1セットゲーム 9.練習試合(試合が近ければ) 10.整理体操 と、かなりラフに書いてみたがこういう感じのスケジュールになる。 これは中高大変わらなかったので、おおよそどこでもとっているスケジュールだと思う。 だいたい3時間の練習だとすると平均20分、10分から30分ぐらいの感じで次の練習に移っているさまが分かると思う。 このスケジュールが決まっている、というのが結構大きいのだ。ペース配分もできるし、次にくる苦痛も計算できることになる。それが数十分おきにくる。この環境は先読みができるし、どこでどれだけ頑張ればいいかがわかりやすい。先に来る読めない苦痛が最も大きな苦痛なのだ。 部活動というのは、けっこう理不尽にみんな苦痛を背負うのであるが、それが練習の中で全体像が事前に把握できているので、その苦痛にどう対処しようかということを事前に計画が立てやすいのである。 なので、まず、創作の苦痛を減らす第1の方策としては、 ・飛び込みの苦痛をできるだけ排除せよ。 ・苦痛は細分化し、計画的に与えよ(自分に)。 ということである。 ・追い詰め方の上手い下手 自分を追い込む。これには、実は上手い下手がある。 目の前にある苦痛の塊に対して飛び込むためには、やる気もあるかも知れないが、それよりもおしりをたたいて、無理矢理突っ込ませた方が手っ取り早い。 たとえば、部員に対して、おまえら、こんなことで○○校に勝てると思っているのか! これははっきりと無能だと断言できる顧問である。 なぜ、これはだめだめなのだろうか? すこし時間を用意するので、各自考えてみて欲しい。答えを見れば、疑問を感じなかった自分に恥を感じるはずである。 では、よいだろうか。 この追い詰め方は、得体の知れない物に対して、追い詰めてしまっているのである。 たとえば同じ地区の学校の部だとして、そのチームがいまこの時点でどれぐらいの実力があるのかは、まったく分からない。事前に試合をしていれば多少違うが、たとえば高校生ならば毎月試合をしている訳ではない。そして、高校レベルでは1月で信じがたい程度の上達をすることもあるのである。 なので、この顧問が発言した時点で、なにを目標にしていいか分からなくなる。 これに対して、優秀な顧問は(わたしが出会った方々はほとんどそうだったが)こういう。「○○校ではこんな練習をしているらしいぞ」「うちでもやりましょうよ!」「○○校ではフットワークに30分も使っているらしい」「うわー、信じられねえ」「○○校の田中は20分間の3対1で5点しか取られなかったらしい」「すげ・・・。」 まあ、部活をやっている人はわかりやすいというか日常なので、特に驚きもないでしょうが、こうやって創作の側面や会社の業務の側面に落としてみると、なんかとんでもさんが跋扈している様子が分かってくるのではないでしょうか。 「無能」とわたしが言うのはそういう体育会系的な世界での嗅覚に照らして、まあ無能だよねと、そう思っている、そういう感じなのである。 なので、第2の方策としては、 ・追い詰めるときは計測可能な状況で追い詰めること。 ・もし目標に届かなくても、何パーセント届いていないのか、努力目標を示すこと。 ・即座に実行可能なレベルまで具体的な努力目標に落とすこと。 ということである。 さらにいえば、足りないのは未熟なので仕方ない、そこまで伸びるにはどうしたらいいかを考えろ。おまえが真剣に考えている限りは一切の文句は言わない、と伝えることである。 ・+5%を常に狙っていく。 もし、昨日と今日があって、その違いに5%以上の差があったら、驚きというか軌跡である。部活動というのは毎年300日ぐらい練習するのであって、その中で毎日5%ずつ上達したら、とんでもない事になる。 計算したところによると、2273996。 1が2273996になる。 これは、227,3996なので、225万倍強ということになる。 にわかには信じがたい数字なのではないか。 1%にしてみよう。 19.788。 それでも20倍弱。 この1%から5%の間にとてつもなくでかい可能性の差があることが分かるのではないか。 このわずかな上達を惜しむようになると、上達は滞る。 奇跡的に上達するなんてことは、まあ、ありはするのだが、わたしの経験で言えば10年に二三日ぐらいだよ、それ以外は、地道な成長だよ、と、書いておきたい。 なので、第3の方策としては、 ・些細な成長を喜べ。それは積み上がるととんでもない事になる。 ・ほんのちょっと成長で十分だ。問題は毎日成長し続けられるかだ。 ・自分の成長の些細なところに敏感になれ。0.1%の成長を常にトレースできるどうかで、上手くいくかどうかが決まる。 以上。 義務は果たしたかな(笑) ■FLASHゲームブック「ジャングルの要塞」リリース!!! http://blog.story-fact.com/?eid=1099100 追記:くそ、三割ぐらい削った。楽天爆発しろ!(笑)
May 5, 2009
コメント(0)
-
マイナスゲーム
世界中がマイナスに陥ろうとしている。 世界の、豊かになるはずの、豊かさを努力とともに勝ち取ろうとしている人々の努力まで奪われようとしている。世界を豊かにし、世界中の市場で争って率先して最も豊かな生活を産もうとする人々は、幸福を味わうべきだ。 金の流れを見ていて、そうはなっていないなと。 であれば、この金の流れは間違っている。 強い意志を持って、この流れをぶっ殺すべきだと、当然ながら思う。 空売り禁止は、時限的には非常によい方法だ。 価格発見機能に、この膨大な乱高下に唱える意味の無意味さを、感じてしまう。おまえはどんだけ、状況が分かっていないのかと、殴り飛ばして、頬を叩いて、ここは嵐だ、おまえの天気予報はどうでもいい、というだろう。嵐で死ぬかも知れない乗員を考えれば、だとうな話だ。 なぜ、暴風雨ツアーを、まるでリスクがないように語るのか、と。 わたしはかなり公正に書いている。 そうじゃない人を、その言葉は、自分の良識に照らして罪悪感を感じない程度ですか? とといたい。 もちろん、経済的なクライシスは、その辺の麻痺から起きる。 だれが、自分は冷めていると、言えるのだろう? ここでとどめておくと、たぶん警句として回収されそうだ。 だけど、やはりこれは避けられない。 資本主義はどうも間違っているようだ。 これを書くのにはかなりの、才能が要った。 資本は重要ではない。重要なのは所有権なのだ。たぶん多くの人には、かなり馬鹿らしい論点なのだけど、この辺は深いので、どうしよう。対価請求権が時間軸に左右され変動する場合(つまりドル建てで減価するばあい)はどうなるんだろう? たぶん、この辺に近い議論である。 変動する所有者と、変動する価値の中で判断が難しすぎるんじゃない? という話でもあるし、あー、その辺はあんまり関係ないしという話でもある。 まあ、究極的には、グロスでペイなら文句言うなボケという話なんだろうが・・・。 これは究極的すぎる。 その辺が分かっていないのが、今の米国市場である。 複雑骨折に近い、状況下で、どう政治的な決着を図るのか。 麻生さんの優れているのは、どうもこの状況を理解していると思われるところなのだ。念のために言っておくと、現場を理解している人は一人もいない。あまりにも複雑すぎて、だれも理解できない状況にある。 もちろん、わたしは、一年ぐらい前から理解していたし、その解決策も示した。 しかし、わたしは、今の状況を把握していた訳ではない。 わたしは、普遍的な日本のあり方を示しただけだ。 日本は、どちらにしても大東亜共栄圏的な、アジア連合を唱えなければならなくなる。なぜならば、日本はアジアの中で、生き、その生存をすべて寄託し、その域内の幸せのために汗水を垂らせなければならないと思うからだ、というのはたぶん大東亜共栄圏の理念とほとんど変わらないと思うので、そっちを参考にして欲しい。 で、問題は生存権だが、それは東アジアに寄託してもいいのではないだろうか。 もともと日本は生存権を、WTOに寄託していた。 日本は貿易がならなければ、世界中が保護主義に動けば生きていけない国だった。 幸いにも東アジアであれば、生存権を保守できる。 もちろんそれは、それ以外の域内と活発な貿易をしないというわけではない。 それに東アジアで始まろうとしている結束も、その実際はEPAであり、これは極めて透明性の高いオールウェルカムの条約である。米国が加わる用意があるなら、喜んでだれもが拍手を持って、自由貿易主義と適材適所主義と、世界の発展のために祝福するであろう。結局のところ、これはIBMがやっていることと変わらないのだから。 グローバル化からワールドソーシングへ。 実に時流を捕らえた言葉だし、世界中のIBMを米国の最も尊敬すべき企業だと思っていないひとはほとんどないはずである。 問題は、尊敬に値する世界的な企業として、日本の企業はどうあるべきかなのではないだろうか。
April 10, 2009
コメント(0)
-
三井アウトレットパーク入間へ行ってきた。
えーと、わたしは結構服は三井のアウトレットパークで買うことが多いのですが、本日は近いということもあって、入間に行ってきました。 隣接するコトスコの馬鹿でっかさも驚きなのですが、さらに輪をかけて馬鹿でっかい、空港のような異様をしたショッピングモールです。 ■最近の雑感/南大沢アウトレットモール http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200612230000/ 実は同じ三井系なので、南大沢とほとんど同じ構成。 大きい分、中央に「セントラル区画」がブーストされている感じで、南大沢をZガンダムだとすれば、入間はZZガンダムといえば、多くの人には一発でどんな様子か分かるに違いない。 さすがにアウトレットだけあって、価格は3割から5割は安い。 ただ、入り口にそびえるBEAMSとDIESELはあんまり値引きしていない感じ。 BEAMSはおなじみだと思うが、DIESELはイタリアで今勢いのあるデニム中心のファッションブランド。値札を見たら、ジーンズが25000円とか、「ちょwww イタ公、アウトレットの言葉の意味分かってねえwww」 と唖然としてしまうわけです。 エドウィンのプレミアジーンズがこの価格帯ですかねえ・・・。 高級ジーンズとしてブランド作りたいんだろうけど、それをいくら客が来るからって、アウトレットモールでやるなよwww と突っ込みたくなるわけです。 ちなみに、わたしは英国好き、もしくはアメリカンカジュアル好きなので、そっち系なので、この辺にはご用はないのですが、イタ公がぶちかましているのを見るのは外野として楽しいわけです。 よくこういった、ショッピングモールへ行くのが好きなのは、やはりデザインの勉強になるからでしょうか。 そんなに本気でやっているわけではないのですが、昔仕事でしていたのが惰性で残ってしまっているだけで、それでも、ショッピングモールへ行くと、あちこちの色味が気になってしまう。 ブランド名をぱっと見て、ぱっと店内の色彩を見つめて、配色を頭に入れる。 服なんて、4割ぐらいは色味なので、まあ、非常に洗練された色があちこちに飾られているわけです。ロゴのフォントを見たり、文字面を見たり、それで配色とのマッチングを考えて、「おっと、NEXTDOORってこの色なのか」 とか。そうやっていると、結構勉強になる。 そういう色味とブランド構築の見本帳が、ショッピングモールなんです。 だいたい価格帯がそんなに高くないメジャーブランドは押さえられているので、まあ、ざっと刺激を受けるにはちょうどいい場所と言えるかも。 見て、おっとstory-fact.の次のデザインは、ちょっと色味が強すぎたなあ、もうちょっと慎重にやらないと、という感じで、自分がしているデザインのまずいところも気付く。 どうでもいいですが、story-fact.のロゴは、実はあれは、服のタグをイメージしていたりする。服のタグと付箋紙のイメージを合体させたようなイメージ。本当にどうでもいいのですが・・・、何となくわたしのショッピングモール巡りとのつながりが見えるかも知れません。 しかし、この三井系のアウトレットモールは、本当にあちこちで子供が跳ね飛び回っている。なんか子供浮かれさせる何かがあるのでしょうか、お父さんとお母さんで、子供と追いかけっこしている様子に、頻繁に出くわす。 セントラル区画にはカルディコーヒーファームが、あって、輸入食品屋さんで、コーヒーを中心にチーズとか、お菓子とか、パスタとかが所狭しと置いてあるお店なのだけど(カルディで画像検索するとどんな感じの店か分かるはず)、なんか、ついつい、カルディって入っちゃうよね(そして買っちゃうよね)、と困りながらレジに並んでいたら、子供2人(姉弟)が、わーぁ!!!! という感じで駆け込んでくる。(これはお父さんも買わざるおえないなあ、すごいなあ) と、思ってしまうのです。 あの子供が跳び跳ね始める催眠効果みたいなのが、三井のアウトレットモールにはあって、それを駆使して、子供が駆け回る公園&ショッピングモールとして舞台装置を作ってしまっている。 だって、考えてみてくださいよ。 子供が、DIESELとか、NOLLEY’Sとか(おっと、NOLLEY’S入ってるのか、気付かなかった・・・)、Franc Francとか、COACHとか並んでいるところで、きゃっきゃ言って遊んでいるんですよ。 このハイセンスなファッション感覚を、三つ子の魂に植え付けられてしまうんですよ? この子が大きくなったら、どうでしょう? どんな服を買うんでしょうか。 DIESELとか、NOLLEY’Sとか、Franc Francとか、COACHとかじゃないでしょうか? Franc Francとか、BLEU BLEUETとかは、けっこうおしゃれ系な女の子たちには人気なブランドですが(BLEU BLEUETもあったか、この人気ブランドはとりあえず集めてみました! って感じはすごい・・・)、結構これらの店は小物も扱っているので、子供がおもちゃでも見るみたいに、この辺の小物をいじっているわけです。 セグメント的にはちょうどOLになってお金に余裕が出てきて、おしゃれなもので周りを固めたいなあというぐらいの女の子にちょうどいい価格帯とおしゃれ度で攻めている小物を三つ子の魂に植え付けてしまう。 これはびっくりするというよりは、新手の消費喚起マーケティングだなあと思ってしまうわけです。 カルディコーヒーファームは結構あっちこっちにありますが、子供が駆け込むようなカルディは見たことがない。同じように、子供駆け込むFranc Francも、BLEU BLEUETも見たことがない。 この公園とショッピングモール(しかもメジャーブランドばかり)の組み合わせで、子供をドリブンにして、あちこちに突撃していくような構造。 日本で今、服飾流通系に起こっているのは、このショッピングと遊び場を合体させてしまう巨大な舞台を中心とした、消費市場作り。 当然のように、イオンの武蔵村山で書いたアイスクリーム屋さん、Cold Stone Creameryも入っていて、初体験してきました。 このお店、店員がアイスクリームを作ってくれるお店。 たとえば、チョコミントクッキーを頼むと、ミントアイスを店員さんがすくってきて、鉄板の上(多分溶かすためだと思われる)で、お好み焼きみたいにチョコと混ぜて、オレオのクッキーをそのままばこっと入れて、あとは鉄製のへらでぐしぐしとクッキーを潰して、混ぜ合わせて、できあがり! みたいな感じ。 これはおそらく、フルーツ系の(イチゴとか、バナナとか)食材をアイスに混ぜる事がもともと発祥だと思うのだけど、まあ、見ていて壮観なわけです。しかも、発生タイミングはよく分からないのですが、何らかの条件が揃うと、店員たちが歌いながらアイスを調理するというパフォーマンスが行われる。 これが実際に調理している内容を面白おかしく、ディズニー調で盛り上げる歌で、たぶん4人の店員がたまたまのタイミングでちょうど同じ工程に入るというビンゴ状態になると発生するみたいで、これがまた楽しい。 もう圧倒されるというか、まあ、ちょっとぐらい高くてもいいか、と思ってしまう力がある売り方なわけです。ちなみに、お値段は500円から1000円ぐらい。アイスとしては高いのだけど、こういうハレな場だったらいいか、まあ、生ビール500円って高いだろうと思いつつ(笑)。 しかし、アイス屋さんの店員さんたちが、あまりにも楽しそうなのが印象に残りました。やっぱりその楽しいアイス屋さんを演じるのが楽しいのだろうなあと。これはディズニーランドとかでもそうなんだろうけど、みんなが楽しがってくれるのが楽しいのだろうなあと、そのためのショーは楽しくて仕方ない、見たいな感じが非常に伝わってきました。 セントラル広場では三井系のアウトレットモールではおなじみの、インディーズの方々によるコンサートが開かれている。 なかなか人選が優秀というか面白くて、聞き甲斐のあるグループが集まってくる。 ロックとかそういう方向ではなくて、ゴスペルとか、インストールメンタルグループとか、そういう系のグループ。 三井のアウトレットモールは大抵二階建てなんだけれど、その二階の手すりにもたれかかって通りかかった人が、音楽に耳を傾けている、そういう光景が、何か「時をかける少女」に出てきた学園風景のようで、ああ、ひょっとしたら日本で一番googleの社内っぽいところは、このアウトレットモールなのかも知れないなあと思ってしまった。 今日のステージは、デルソールという、バイオリン・ギター・ベース・ドラムという4人のインストールメンタルバンドで、なかなか味わい深い音が聞ける。 デルソールでgoogle検索するとトップに出てくるので、それを参考にして欲しいのだが、CDを買わせていただいて、それを聞きながら、これを書いている。 S.E.N.S.の影響を結構受けている感じするグループで、本家と比べて、そんなに劣る感じはしない。むしろ、果敢にS.E.N.S.越えを狙って欲しい。そう思う、バンド。つまりいいものがたいへんいいものが聞けたわけだ。(しかし、iTunesで取り込んだら、アルバム情報が表示されたのにはびびった(笑) Appleすげー・・・。) なんというか、この一期一会な感じが、三井のアウトレットモールなのかなあ。 もしそこで、買ってしまわないと、もう2度と、出会えないかも知れない。 そういう演出が、あちこちにあって、ぐっとくるのだ。
January 18, 2009
コメント(1)
-
内向き思考の特効薬。費用も副作用も、たぶんなし。
最近、世界中が内向き思考になっているせいか、日本人が内向きだと心配する声が多い気がする。 わたしは特許系の人なので、どうしても日本企業の進出先の(つまり製造業の工場が建っているところ)に目が向きがちなので、どっちかというと東アジアや、中南米とか、途上国へ意識が向いてしまうのであるが、外向きであることは違いないと思う。 日常生活でも、フランクに、たとえばシンガポールの特許法がとかいう話が聞こえてきて、これは仕事直結の問題でもある。 しかし、実はこの内向き思考はとても簡単に解消する方法があるので、そっちを勧める方向はどうだろうとと思う。 とても、身も蓋もない方法ではあるのだが、効果は抜群で、しかも無料だ。 なんでこれを勧める人が少ないのかなあと、不思議に思うのだが、恐ろしいほど簡単だ。 現地在住の日本人のブログのRSSを購読するのである。 日本人は実際にあちこちに在住しており、そういう人だからだろうか、積極的に情報発信する傾向にある。 東南アジアでは、たぶん意外かも知れないけれど、韓国に一大クラスターみたいなのがあって、韓国情報はとにかく困ることはない。あと多いのはタイとか(「曼谷煩悩通信」とかはめちゃくちゃオススメである。おっとこの人はタイと日本を行き来している人なんですね)。インドネシアもまあまあ。逆にシンガポールは少ないなあと思う。中国はフィード漁りをしたことがないかなあ。 おそらく東南アジアに限らず、あちこちに日本人は散らばっていてブログで頻繁に情報発信をしている。なので、そのフィードをごっそり漁って、google readerにでもぶち込んでおけば、バックグラウンドミュージックのように、世界各国の日本人からの報告が舞い込んでくる環境が作れるのである。 もちろん、それを全部読む必要はなくて、タイトルだけをさーっと流し読みするだけで、十分に楽しい。 とりあえず、500フィードぐらい集めて鑑賞していれば、内向きなどと揶揄されることはなくなるだろう。 ■RSSの収集方法 これは以前書いているので、こっちを参考にしてもらうといいだろう。 ■RSS収集法 30分でプロ以上の事情通になれちゃいますね・・・、これは。 http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200610140000/ うーん、2006年の記事か・・・。 ここでは、テクノクラティをオススメしていますが、今回は海外在住ブロガーを捜す旅なので、Googleブログ検索で十分。 その際のキーワードであるが、これはシンプルに国名または都市名でいい気がする。 わたしの経験でもそれで困ることはあまりなかった。 ■首都の一覧 - Wikipedia http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%A6%96%E9%83%BD%E3%81%AE%E4%B8%80%E8%A6%A7 ただ、注意するのは、必ずしも首都に日本人クラスターが形成されているわけではないということ。 たとえば、アメリカならサンフランシスコに多かったり、ニューヨーク在住のセレブブロガーもあるだろう。反対にワシントンDCに住んでいる日本人は報道関係者だけなきがする。 インドではムンバイあたりですかねえ。あとバンガロール。 こうやって、ざくざくとどうも在住邦人っぽいのを集めて、あとで見直してみてどうも違うようだったら切って、そうじゃなかったら保護する、という事を繰り返していくと、あら不思議、にわかインド事情通のできあがり! ほんとインスタント事情通という感じなってしまうのである。 もちろん、世界全土の情報に通じている必要はなくて、自分が知りたい情報だけで十分だろう。たとえばスペイン料理が好きならスペインだけでいいし、南米縦断旅行を夢見ているのであれば、南米だけでいい。 これはやってみると分かるのだが、これをやると、ほんとフィードが空気みたいになっていき、気付いたら、あれ、なんでわたしはこんなにもタイのことを知ってるんだろう(しかもB級グルメとか、ナイトスポットとか、そういう情報ばっか(笑))、という状況になっていることは保証付きである。 そして、どうしても行ってみたくなるだろうし、海外進出してみたくなってしまうだろう。やっぱり、工場はタイかな。タイ料理旨いし、行ってみたい店が大量にあるし、みたいな。こうなれば、パーフェクトな外向き人間のできあがりだ(なんか、ちょっと歪んではいるが(笑))。 ただ、このやり方はフィード収集が慣れないうちはかなり大変だ。 また、わからない事だらけの情報を読むことになるので、たぶん経験してみれば分かるけれど、結構ストレスが大きい。新しい情報の奔流にさらされると、それを処理する負荷が、膨大になるのである。 数十フィードを集めたあたりで、疲れを感じるであろう。 そうしたら、その辺で打ち切って、しばらくその数十フィードでまわしてみることをオススメする。まわしているうちに、何となく不足感を感じるはずだ。そうしたら、またフィードを増やす旅に出ればいい。 2回目は1回目よりは負荷が低いはずだ。 以上、とりあえず、簡単に概略を示した。 というわけで、日本人の内向き思考を解決する特効薬は、面白い海外在住ブロガーのブログを紹介しまくること。もう、ほんとこれしかないなあと、思ってしまう。
January 17, 2009
コメント(0)
-
スペースノイドの傾向と対策
(本エントリーは、「情報の差分と、政治」「事実と仮説と、仮説の仮説」で展開した情報リテラシー関連エントリーの第三弾です) 以前会社に妙な電話がかかってきたことがあった。 なんだかよくわからない理由を上げて、電話番号を聞き出そうとする電話だった。 こいつは一体何なのだろうと、小首を傾げていたのだが、あることに気がついて、びっくりした。 これは、ソーシャル・エンジニアリングだと。 世界最強のハッカーとして名高いケビン・ミトニックの本に欺術という本がある。 捕まったミトニックが、釈放の代償として自分の手口を明らかにした本で、その手法は総称してソーシャル・エンジニアリングと呼ばれる。詳しくは該当書を読んでほしいのだが、一見、何でもないような情報を引き出しているようにして、致命的な情報に迫る手法の総称と思えばよい。 この手法はほとんど無敵であり、これに対抗するには、ソーシャル・エンジニアリングのその傾向と対策を熟知していないといけない、という非常に困った手法なのである。 わたしは、この本を読んでいたので分かったのだが、原理的にこれを防ぐ方法はない。 同様に、これも原理的に防げないハッキング方法がある。 名前がなかったので、スペースノイドとわたしが勝手に名付けたのだが、ありふれた手法なので、すぐに理解できるほど簡単なことだ。 このスペースノイドは情報を攪乱する、情報戦の陽動作戦みたいなものである。 例えば、数人でハッキングをするケースを考えてみよう。 まず、陽動部隊であるハッカーが、重要な脆弱性を突こうとする行動をとる。あわてた管理者はこの陽動ハッカーたちを叩こうとするのだが、実際にはこれは陽動であって、目的は管理者のリソースを消耗させることにある。そして手薄になった、本当にどうでも良いように見えるところを、一人のハッカーが確実に突く。 これはルパン三世などをみれば、ありふれた盗みの手段であることは分かるだろう。 そして、これを防ぐ方法はないことも分かるだろう。 しかし、最近この手法が悪用されている光景を見ることが多くなった気がする。 もちろん、それはハッキングではなく、世界中のありとあらゆるところで使われている。 このスペースノイドは、わたしがSFを書いていた時に思いついた手段だ。 地球人から見えれば、ハッカーたちは衛星軌道から致命的な箇所に降下してくるように見えるが、実際には地上にいるハッカーが宇宙を見上げている管理者を尻目に盗みをはたらく。 それが、ガンダムのジオン軍のように思えたのでスペースノイドと名付けたのだが、最近になって、このスペースノイドはありとあらゆるところで使われていることに気づいた。 ライブドア事件は典型的なスペースノイドだと思う。 この手口の傾向は、厳密には実行できないし、何らかの欠点があるのだが、専門家にもその否定をすることは非常に難しく、反論がしにくい事を大量に行うというところにある。 例えば、殺人予告をあちこちで行って警備を攪乱する。 例えば、実現不可能な政権公約をたてる。 例えば、水に毎日言葉をかけた実験結果を示す。 なんか、見たことがあるような気になってこないだろうか(^_^; 以前、堀江被告のインタビューが出て、おっと、これはスペースノイドじゃないか、と気付いたのが、このエントリーを書くきっかけになっている。 ■沈黙を破ったホリエモン,ITを語る http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/Interview/20080910/314505/ この中でソニー買収などを語っているのだが、実際にはこれをやっていれば致命的な失敗になっていたと、自信を持って指摘することができる。プロであれば、iPhoneと言うのは結局の所、Mac OS Xであって、Mac OS Xと言うのはスティーブ・ジョブスが1985年に設立したNeXTという会社の技術がベースになっているのだから、もうかれこれ20年以上も続けてきた事業の成果であることを知っているからだ。 対してソニーにはそれだけの優秀なソフトウェア資源はなく、人材に厚みがあるのはゲーム関係のソフトウェア開発者で、携帯はエリクソンとの合弁と、あまり見るところはない。 しかしどうだろう? 完全に否定することはかなり難しいのである。 この反論をすることが難しい(が、ほぼ確実に実現しないことは分かっている)点ばかりを突いて、反論できないのだから間違いではないとするのが、この戦術の主な特徴だ。 こうやって情報陽動を連続的に起こしながら、情報を攪乱させ、リソースを奪って正常な判断ができない状況に追い込むのが、このスペースノイドなのである。 目的はなんなのかと言えば、正常な判断ができない状況に追い込むことなのである。 言っている言葉にはほとんど意味がない。 口にしていることが本当の目的ではないからだ。 そういえば、悪質な宗教の勧誘はこういう手法を使うことが多い。 このわたしがスペースノイドと名付けた手法は、アジテーションには極めて有効に働く。 アジテーションはそれほど専門的な知識のない人々を扇動する手法だ。 塩野七生によれば、民主主義の最大の脆弱性は、このアジテーションに対抗するすべを持たないことにあるらしい。 この専門家を黙らせ、民衆を麻痺させる手法がアジテーションの局面において有効であることは少し考えれば分かるのではないだろうか。そしてそれがどんなに恐ろしいことであるかと言うことも。 しかし、民主主義もこれに対抗する機能を備えている。 幾重にも張り巡らされた「手続き」がそれであり、重大な権力が複雑な手続きを経なければ発生しないようにされている所にある。たとえば、アメリカの大統領選で扇動を行うことは難しい。一年以上掛けて行われる大統領選には、厳密なチェック機能が備わっており、混乱させ続けることは極めて困難になっている。それを具体的に言えば、七面倒くさい数々の手続きがこれに当たるのである。 実際に、どのような法律がこれに当たるのかと言えば、六法の二法である、民事訴訟法と刑事訴訟法がそれにあたる。 この七面倒くさい法律は、裁判の公正を担保するためにある手続き法なのである。 こういう七面倒くさい手続きがないところでアジは発生しやすい。 ここまで、悪意ある手口としてのスペースノイドを説明してきた。 しかし、この情報陽動戦術は、ありとあらゆるところで使用されており、一概に詐欺の手口とは言うことはできない。 近しいところでは、小泉さんの政権運営方法は典型的なスペースノイドだった。 国民にわかりやすく、そして意外性があり、実質はあんまり意味がないことで、日本国中を掻き回すのである。政敵のリソースを奪い、国民を麻痺状態にする。小泉改革には全面的には賛成できないのではあるが、何はともあれ、全く身動きが取れない所から日本を救い出すには、あれしかなかっただろうという気もする。 だから、靖国参拝の問題はなんだのかと言われて見ると、はっと気付く。 あれはスペースノイドだ。 靖国参拝自体にはなんの意味もないのだ。中国怒らせてしまってすまん、ぐらいな所はあるかもだが、問題は、情報攪乱を起こすこと自体にあったのだと思う。 そうやって政治を見つめてみると、あちこちでスペースノイドと思わしき現象を発見することができる。 政治は世論誘導であり、情報戦なのであるから、当然その代表的戦術である陽動戦術が使われないはずがないのであるが、こうやってその実態を明らかにして、俯瞰してみると、政治の世界には、本質的にはほとんど意味がない、陽動用の情報があちこちにちりばめられていることに気付く。 これが、政治の情報が混乱気味になる原因である。 また、以前勤めた会社の社長がこれを多用していたことにも気付く。 社長が理不尽な理由で何かを問題にし、社員全員に改善を求めるのだ。問題とされていることは些細であるが、社内がどたばたし、徹夜が発生し、混乱する。実際にあの問題自体を社長が重要視していたのかと言えば、たぶんしていなかったのだ。目的は、社内を暴風雨のような活気のある状態に保っておくことであり、社内が落ち着いてくると、危機感を持って、社内を掻き回していたのだ。 社長としては、正しい判断なのかも知れない。 ただまあ、引っかき回される社員としてはたまったものではないが(笑)。 こういった手法に対抗するには、事前に突かれそうな脆弱性を消しておく以外にあまり手段はない。 もしくは事前にその脆弱性を熟知しておくしかない。 たとえば、以前、分家の方で書いたエンガジェットというブログが突いた、色商標の問題がある。これはパリ条約のテルケル商標の脆弱性なので修正はほとんど不可能に近い。これに対して特許庁の公式見解に近いパリ条約講話は70ページにも渡って、このスペースノイドに対抗する理論武装をしている。 なんと、説明の難しいところを突くのだろう(笑)。 エンガジェットの目的は、色商標を問題化したかったのではなく、知財法なんていくらでも悪用できると言うことを、周知させたかったというところだろう。 特許法にも実は、このスペースノイドに悪用されそうな箇所がある。 重大なところに説明が異様に困難なところがあるのだ。 これは、特許法概説や逐条解説で説明されているので、書いてしまうのだが、出願公開がなぜ特許出願から一年六月後なのかが説明しにくいのである。 特許法は、発明を一般に公開し、その公開の代償として一定期間の独占権を得る制度だ。 発明がブラックボックスになるのを防ぎ、発明の情報をシェアし、重複研究が発生することを防ぎことを目的としている。その代わり、発明者にも実施の独占権を与え、公開のインセンティブを与える。 と言うことはこうならないだろうか? 出願から公開までが短ければ短いほどいいんじゃない? なんで1年6月も秘密にしておくの? これに答えられる人は、あまりいないのではないだろうか。 そして、一般の人に説明できるような人は皆無に違いない。 スペースノイドはこういうところを突くのだ。 「出願公開がなんで一年六月後なんだ! せめて半年にしろ!」 あー、いやねえ・・・(笑)。 非常に筋のいいスペースノイドである。たぶんこれぐらいの精度でつける人は、その理由もたぶん知っているはずである。スペースノイドは主張には全く意味がないことに特徴があるのだ。目的は攪乱であったり、対象を攻撃することであったり、相手のリソースを奪うことに意味がある。 これは陽動なのだ。 1年6月の期間は、パリ優先権経由の出願との公正のため、と説明される。 パリ優先権が1年、方式審査に3ヶ月、公開公報の準備に3ヶ月。 これが1年6月の根拠である。 実際のところは、特許法は最も早く公開できるタイミングで出願公開する制度を取っているのである。 分かります? 分からないですよね(笑)。 説明が極めて困難なのだ。 これ以外にもあらゆる条文が絡んでくる。 別に誤魔化している訳でもなく、わざとわかりにくくしている訳でもない。 ただ、まったく正しいことを説明するのにもの凄いリソースを必要とし、わかりやすく説明することが極めて困難なことなのだ。 特許法は、膨大な特許庁の資料や学者の学説が蓄積されているので、こういった手口にも頑丈にできている。特許法概説に書いてあるよ、でいい。しかし、脆弱な分野もある。 そういったところにスペースノイドを仕掛けられたとき、アジテーションから守るのは、スペースノイドという手口があり、もしかしてこれはそれかも、と思うこと以外にはないのである。 このスペースノイドは防ぐ手立てがないのだ。
November 19, 2008
コメント(0)
-
そして、21世紀が始まる
2001年のある日、わたしはなにをしていただろうと思い出す。 たぶん、ネット系のマーケティング会社でオペレータをしていた。 入社したのは2000年でドットコムバブルのさなか、わたしは大きな仕事の重要な立場をそうとは知らずにアルバイトでやって、信頼を上げた。 単調で、つまらない仕事であったが、その意義に興奮した。 調査費用も馬鹿でかかった。 数千万円の規模だった。 重大な基礎研究の、データ収集であったのだ。 現在であれば、googleのストリートビューの写真撮影の現場監督みたいな仕事。 2008年である現在において、そのデータを活用した成果は、そのクライアントからは、出ていない、まだ。たとえそのデータを持ったのがgoogleであったとしても、今後さらに十年以上の時間が掛かるだろう。 そのときを、その夏のグロッキーとなった日々を、昼飯に食べた新橋の定食屋のおいしいご飯を、吉野屋で飲んだ味のないお茶を思い出すと、隔世の感を抱く。 わたしは、なんて変わってしまい、そして変わらないのか。 2000年と2008年のわたしはあまりにも違う。 なにも変わっておらず、なにもかもが変わった。 もう戻らない日々が指の間を滑り落ちていく一方、あたらしい日々を掴む手が大きくなったように感じる。 所詮は小さな手なのだが、わたしは月にはしごを掛けようとしているわけでも、星に手を伸ばしているわけでもない。 そこに明確にあるものを、確実に手にしたいだけなのだ。 今日、オバマ大統領候補の当選が確実になり、アメリカはあたらしい未知を選んだ。 積算する金融問題のツケは想像を絶するほどであるが、フロンティアに突入する勇気を持つアメリカ人を、日本人は、いや少なくともわたしは賞賛する。 未曾有の金融危機は、20世紀のパラダイムの放棄を要求しており、これはすなわち、これまでの知識人が全部役に立たないと解雇することを意味する。もちろん、現実はそんなにはドラスティックには進まないので、この変動についていこれる柔軟性を持った人間のみが生き残れることを意味するが、あんまり経済界の寛容さに頼らない方がいいとは思うのだが、どうだろう。もちろん、最善は21世紀に相応しい最新型の理論を打ち立てることに他ならない。 少なくとも、今決まっているのは、20世紀のパラダイムは全く役に立たないということが判明したということで、アメリカ国民があたらしい船出を選択したという、鮮明すぎる事実だけである。 21世紀は8年間のロスタイムを消費した。 ここから、21世紀は始まる。 その世紀の節目にいて、わたしは興奮を収めきれない。 どんな未来が、この先の100年に待っているのだろう。 技術的には、ロボット、クリーンエネルギー、全世界的な情報ネットワーク、宇宙開発、テラフォーミング技術と、わくわくする技術が目白押しだ。 テラフォーミングの主役はアラブ勢だろう。 中東の全く生命のない土地に桃源郷を構築しつつある。 これはアフリカに適応できるし、もしかすると月や火星の主役はアラブ勢かも知れない。 ロボットは日本の独壇場だ。 少子化なんていう些細な問題を解決できるかも知れない。 もちろん、ロボットは月にも火星にも必要だ。 クリーンエネルギーは、どこが主役になるか明確な指標は出ていない。 日本も得意だし、アメリカもすごい、EUもやるし、東アジア経済圏の生産力は絶大だ。 目下の所の主戦場と見られているだけに、激しい競争が世界をよい方向に変えてくれることを望みたいところだ。 もちろん、セグメントが細分化されているので、南米などの伏兵にも目が離せない。 ネット革命はアメリカが中心であるが、若干、2008年現在は停滞気味である。 日本をはじめとする「ネット後進国」の需要に、アメリカの供給が追いついていない気がする。これは日本企業がつけ込む隙なのだけど、誰も言ってないなあ(笑)。馬鹿だなあ(ため息・・・)。 まあ、たとえば、すごい簡単なことを言えば、全国で発行されるスーパーのチラシをデジタル化したら、もの凄い利益になるわけです。価格情報を全部押さえている訳ですからねえ・・・(というか、基本中の基本ですよね)。 これは確実に儲かる。 唾棄したくなる企業は、大量にあるわけで、まあド素人ですなと、ド素人たちが巻き起こす市場を見ていて、はいはい素人素人と、馬鹿にしているというか、ダンスを鑑賞して楽しんでいるわけですが、こんなド素人を持ち上げる市場は、やっぱりド素人だと思うしかないのかなあ・・・。株価は役に立たないということです。 宇宙開発は、ゼネコンが海外需要を取り込めるかがポイント。 日本特有の険しい地形で培った技術がどれだけ優位性を、価格構成力を発揮するかというところ。なので、見るべき所は、地形が険しい、インドネシア、インド、ブラジルと言ったあたり。中国とかは見ても意味がない。 カルフォルニアは技術供与がたぶん鍵になる。 具体的には、中核技術を全部「州と」共有技術とすることが肝。共有特許の全条文と全要件は憶えているよね(笑)。もちろん、金は取れよ(200億円とか)、金の授受のない契約は空文だから。実施に対して、不安を解消する。州内での産業の活性化に対して、全面的に支持する。 ただし、資本をねじ込む余地は残しておく。 現地特有の問題に対して、新たな発明を出願する基盤を整えておく。 結局の所、その技術を他所でどう活用して、どう儲けるかというのが、特許法のありきたりな問題なのだ。 で、結局、2100年の経済情勢はどうなっているのだろうか。 日本は、豊かな国となっているのだろうか。 しかし、今思うのは、この豊かな国という概念がなくなってしまうのではないかと、そういう感慨だ。 これは現在、日本に住んでいる人々が不幸になるというビジョンではない。 2008年に始まり、2009年に確定するであろう、21世紀のあたらしい地球の姿を俯瞰したときに想起される姿である。 日本は戦前の大東亜共栄圏以来の念願を獲得し、東アジアに溶けるように存在する、大ブロック圏の一員としての満足しているだろう。地位は下がったかも知れないが、地域は豊かであり、生活は安定しており、域内の行き来は頻繁で、もう、日本人という感覚は、だいぶ薄れている。 東アジアは溶けている。 緩やかな文化交流が行われ、日本にイスラム教徒が増える。 マニラは、東京と対して変わらない。 シンガポールは、世界の首都である。 しかし、東京はそれでも、ロンドンの地位を失わない。 パリがパリであるように、ベルリンがベルリンであるように、上海が上海であるように、ハノイがハノイであるように。 都市機能とブランドは、たぶん一般が想像している以上に保守的なのである。 その想像をするのに2000年ぐらい歴史を振り返る必要があるだろうか。 鼻で笑うレベルの想像性である。 鉄道の歴史を追えば、アメリカがどのように連結されていったかが分かるし、ヨーロッパのほとんどの都市の起源はローマ時代の軍団基地であることがわかる。シンガポールがなんであんなに戦略上重要な箇所にあるかといえば、英国海軍が築いた衛星都市が起源であることがわかる。 京都は京都で、大阪は大阪で、東京は東京なのだ。 現在、世界は、世紀をまたぐ創造性を要求されている。 この言葉は、本当につまらない言葉として処理される。 21世紀はどう始まったか。 その証人は、たぶん、われわれだけなのである。 21世紀は2008年、もしくは2009年に始まったと主張する人々のみなのである。
November 5, 2008
コメント(2)
-
ダウはいったいいくらで下げ止まるのか。プロ中のプロの見解。
大変なことになっている株式相場ですが、あまりにも見当違いな意見が大量に放出されているのようなので、バブル崩壊とはどんなものなのかを、バートン・ビッグスの「ヘッジホッグ アブない金融錬金術師たち」からの引用で紹介しましょう。 ■バートン・ビッグスはこんな人。名門投資銀行モルガン・スタンレーで、世界最高峰とされる同社リサーチ部門を立ち上げると同時に運用部門の設立にも携わり、30年間にわたって同部門を率いた。 ■そして引用する書籍 ヘッジホッグ ―アブない金融錬金術師たち― ■わたしが書いた書評 プロフェッショナルのメンタリティ - [書評]ヘッジホッグ-アブない金融錬金術師たち http://blog.story-fact.com/?eid=869116 バートン・ビッグスは、この本の中の「第九章 長期サイクルという分水嶺」の中で、バブル崩壊の事例を紹介し、その際どのようになるかを紹介しています。九章の中の表題を並べてみると、 ・一般投資家のお金は最悪のタイミングで出入りする ・長期と短期の下落相場の違い ・上昇相場とバブルにおける日米の違い ・七十年代の長期下落相場から何を学ぶべきか ・やり直せることの喜び こんな感じ。 ちなみにこの方は、アメリカのヘッジファンドの中では強気派の方です。 その辺は割り引いてご参考頂けば幸いです。 さて、あなたはダウが何ドルで下げ止まると思いますか? この文章の最後には、正真正銘のプロ中のプロが何ドルになると考えているかが、明示されています。ちょっと、自分のかんがえを紙にでも書いてみてください。 準備できましたか? それでははじめましょう。 投資があれほど難しく、混乱しているのは、市場には大きな好調・不調の長期サイクルがあるからだ。長期サイクルは一世代に一度くらいしか起きない。好調は少なくとも十年、場合によるとそれ以上続き、不調はもっと短いが、暮らし、財産、ビジネスモデルを破壊してしまう。「シクリカル」という相場用語は「サイクル」から来ていて、これは、ウェブスターの辞書によると「何らかの事象や現象が繰り返し同じ決まりで起こる年月の一巡、あるいは繰り返される期間」という意味である。 (この間、実際の事例の紹介なのでもったいないけど略) 長期の下落相場と短期の下落相場の定義から始めよう。わたしの場合、長期下落相場とは主要な銘柄が平均で少なくとも四十パーセント――主要でない銘柄はさらに大きく――下落し、そうした下落が少なくとも三年から五年継続することだととらえている。市場が下落し、それまでの行き過ぎが是正されるまで何年も後遺症が残る。そんな長期の下落相場の中で短期の上昇相場が起きることはあるが、主要な市場インデックスが過去の最高値を更新し、新しい最高値をつけに行くような新しい長期の上昇相場が起きるまでには長い時間がかかる。 対照的に短期の下落相場とは十五パーセント以上四十パーセント未満の下落であり、一年以上続くことはまれである。パニックは非常に短く急激な下落である。長期の下落相場の定義で重要なのは時間の長さであり、それは時間の長さと苦痛の持続が人の行動パターンに影響を与え、社会を変えるものだからである。そうした定義に基づくと、前世紀のアメリカでは長期の下落相場が二回(1929年から1938年、および1969年から1974年)、パニックが少なくとも3回(1916年、1929年、1987年)、そしてありきたりな短期の下落相場が25回起きている。 前世紀におけるアメリカ株式市場の長期サイクルは次の通りである。1921年から1929年が長期上昇相場、1929年から1949年が長期下落相場、1949年から1966年が長期上昇相場、1966年から1982年が長期下落相場、1982年から2000年が長期上昇相場だ。新しい長期の下落相場が2000年に始まり、今はその後遺症の中で短期の上昇相場が起きているということは明らかだとわたしは思う(注:本作は2006年の刊)。ここで大きな問題が二つある。この長期下落相場はすでに安値をつけたのだろうか、そしてこの長期下落相場はいつまで続くのだろうか。 ■チャートはこちら。 http://finance.google.com/finance?chdnp=1&chdd=1&chds=1&chdv=1&chvs=maximized&chdeh=0&chdet=1223638997939&chddm=2022469&q=INDEXDJX:.DJI&ntsp=0 えーと、この辺を読んでいて、ちょっとびびったのは、バートン・ビッグスは現在が長期下落相場であることをすでに読んでいたのですね・・・。強気派のヘッジファンドのマネージャーの見解がこうですから、まあ、この辺を理解していない人の声を聞いても馬鹿らしいレベルでして、ダウが10000ドルを割ったぐらいで騒ぐようじゃあ、まったくなんというか相場が分かっていない(<といいつつもわたしも請け売りなのだが・・・)。 えーと、無駄話はやめて引用を続けましょう。 安値はすでにつけたと思うが(注:この方は強気派)、いつも頭に浮かぶのは日本とその長く残酷な下落相場であり、ほとんど十五年もたった今もそんな状態が続いていることである。長期下落相場の間、日本の市場は短く急激な上昇相場を体験したが、毎度毎度だましに終わり、その後はさらなる下落が起きて、そのうち新安値をつけていた。ジェレミー・グランサム、ネッド・ディヴィスといった、わたしが尊敬してやまないプロたちは、アメリカ株式はそのうち2002年秋と2003年春の最安値を下回ると考えている。すべてが終わるまでに、S&P500で600ポイント近辺、ダウ・ジョーンズ工業株平均でおそらく6000といった水準を目指すことになるだろうと言う。これは現在の水準からみればだいたい45%の下落である。 とりあえずダウは6000ドルを目指すとのこと。 この後、現在起こっているデリバティブ周りが悲惨になるだろうという弱気派の見解を紹介し、「世界の終わりがやってくるリスクに、投資家としてどう対処しろと言うのだろうか」と言い、強気派らしく、そんな大崩壊にヘッジをかけられないと言っている。 この方の投資方法はロング・ショートと言って、上がると思う株をロングに、下がると思う株をショートに賭け、上がっても下がってもバランスが取れるようにヘッジする投資方法なので、この下落相場でも、ショートのポジションで儲けてはいると思うのだが・・・。 ちなみにこの弱気派の見解は現状をかなり正鵠に描き出している。 続けよう。 わたしの頭の後ろにいやな感触があるのだが、それはアメリカも他の国も1990年代の株式市場バブルでは、もっと早くに破裂したそれまでのほとんどのバブルに比べて、より幅広く行きすぎがみられたことだ。それでも、これまでのところ1970年代終わりの苦難や日本が経験した苦痛にはまだほど遠い。2005年の急上昇の後でさえ、ン異本の株式市場はまだ最高値から70パーセントも低い水準にある。日本の不動産価格は50パーセントも下がってやっと安定してきたところだし、日本の株式投資信託の運用資産は1990年の史上最高から95パーセントも下落した。長期下落相場が金融サービス産業に与える影響とはそれほどなのである。アメリカでそんなことが起きたら、あの巨大な金融サービス業界がどんなことになるか想像してみればいい! また、主要な商業用不動産の価格が50パーセント下がればどんなことになるだろう。 過去の長期下落相場では、市場はそれまでの長期上昇相場が始まったときの水準まで下がり、あるいはそれさえ下回っていた。 えーと、つまり、この相場は1982年に始まっているので・・・、ダウが900ドルですか・・・。スゴイデスネ・・・。念のために言っておくと、これはバートン・ビッグスが書いていることに忠実に、数字を当てはめているだけですから。わたしが予想している訳ではありません。しかし、900ドルか・・・。10000ドルを切ったぐらいでピーピー騒ぐなボケというカンジですね・・・。 この後、バートン・ビッグスは日米を比較して、 日本の商業不動産の上昇が異常すぎたこと(皇居の地面だけでカルフォルニア全体の不動産の価値を上回っていたと紹介。確かに異常すぎ・・・。)、 アメリカの投資は新産業(ネットなど。現在は新エネルギーに流れている。これは西海岸のマネーが健全な流れをしていると言うこと。東がこけても西が隆盛するというのは、確かにアメリカの強さ。GEもグーグルとぐるになって新エネルギーやるらしいので、金融部門を切り捨てれば、案外簡単に復活するかも)に流れていて無駄なものには流れていないこと、 日本の金融政策が致命的な間違いを犯したこと(これはよく言われる)を挙げて、こう締めくくる。 対照的に、アメリカでは連邦政府がほとんど即座に所得と投資の両方に対して減税を行った。実際、アメリカ経済は財政・金融による過去に例のない景気刺激策の恩恵を受けたのであり、そうした政策のおかげで不況がさらに深刻になる事態が避けられたのは疑いようもない――今のところは。完全に回避できたのか、それとも避けられない天罰を少し先延ばしにしただけなのかはまだわからない。 うむ。極めて正確である・・・。 実力が圧倒的すぎて、唖然としてしまう・・・。 続ける。 アメリカと日本の経験の違いを注意深く指摘したつもりだが、だからといって、アメリカでは株式市場バブルが起きなかったとか、膨大な投機や詐欺が行われていなかったとか主張するつもりはない。アメリカは間違いなく長期下落相場に入っており、三年続けて市場は下がっている。わたしが心配しているのは、今回の下落相場が1969年から1974年にこの国が経験した長期下落相場ほど深刻であるように見えないし、当時ほど長期にわたってはいないようである点だ。つまり、まだ完全に終わったわけではないのではないかという気がする。間違いなく1930年代の相場の苦痛にはほど遠い。 この後、細かな事例と数字を丁寧に挙げていかにすさまじい下落であったかを紹介している。この辺は分離して紹介することができないので、この辺にしておこう。 こうやってみてみると、正真正銘のプロのヘッジファンドマネージャーは、ほとんど今の状況を読み切っているのである。そして、かれらがみているのはダウ900ドルであって、もちろんこの下落相場でもうけようとしているのである。 本書は、この章のレベルの、圧倒的な実力をひしひしと感じる内容ばかりが詰まった本ですので、読んでみて損はないですよ。実力差というものに打ちのめされます(笑) ■わたしが書いた書評 プロフェッショナルのメンタリティ - [書評]ヘッジホッグ-アブない金融錬金術師たち http://blog.story-fact.com/?eid=869116
October 10, 2008
コメント(0)
-
崖の上のポニョを観てきた。
えーと、のっけからですが、これは宮崎駿監督の最高傑作ということでいいのではないでしょうか。 異論がある方、いらっしゃいますか? いらっしゃいますか? うーん、なんか多くいそうですねぇ。 では、言葉を変えて。 『崖の上のポニョ』はわたしにとっての宮崎監督作品の最高傑作です。 これに異論がある人はいないでしょう。 ポニョの魅力は、とにかくうつくしい水の表現、海の表現、幻想的な光景、そして、それでいてリアリティのある表現、これに尽きます。 あんまり小難しいことを考えず、ざぶんざぶんとやってくる津波の波に身をゆだねて、その波頭を駆けてくるポニョの元気いっぱいな姿をにこにこと眺めてればよい。 うつくしい光の表現と、にぎやかな海の生き物たち。 ときとして不気味に見える生き物たちだけど、別に彼らは彼らの生をまっとうしているだけであり、誰かに害を与えようとしているわけではない。ゆらゆらと泳ぐデボン紀の魚たち、ふわふわとたゆたうくらげたち。 これは、宮崎監督が描いたファインディング・ニモなのだ。 いや、失礼。 これは宮崎監督が描いた、すてきな海のファンタジー、崖の上のポニョという傑作なのだ。そして、たぶん、最高傑作だ。 この映画を見ながら、わたしは宮崎監督というのは、ずっと昔から、こういうのをやりたかったんだなと確信した。どこかでやせ我慢して、自分の描きたいものを地に足をつけようと必死に取り繕っていたのだな、これまで、と思うようになった。 ハウルは取るに足らない失敗作で、千と千尋は奇跡的な傑作だが、崖の上のポニョは違う。 これこそ、ナチュラルな宮崎監督の映像への欲望だとわたしは思う。 だから、実際のところ、物語のあちこちをつついて、なんであそこはああなっているのだと考えてみても、それは壮大な徒労となる。なぜなら、そこには必ずたった一つの答えしか返ってこないからだ。「それが描きたかった、そう描くのが自然だった」 あの映画の中にあるのは、宮崎監督が描きたい海の表現しかない。 なぜああなったのかといえば、単純に、それが描きたかったから。 それ以外の答えが返ってくる気配が全くない。 なぜ、あのようにゴミだらけの海底を底引き網で引く光景が描かれているのかととわれれば、たぶん答えはひとつしか返ってこない。 正常な想像力を持ったものが海を描けば、人間の住む港の海底はゴミの山であろうと。 なぜ、あのように老婆ばかりを描いたのかととわれれば、たぶん答えはひとつしか返ってこない。 正常な想像力を持ったものが宗介の相手をしてくれる人は誰かを考えれば、老人ぐらいしか思いつかないだろう、ほかは仕事中だと。 そんな風に、問いを投げかける度に、本当に自然な答えが返ってくる。 拍子抜けしてしまうほどだ。 さて、物語解析的な分析だが、実は、これは意味がない。 なぜかといえば、この物語は、どんな映像が作りたいかを基にして組み上げられ、実際のところ物語は描きたいところではないからだ。 例えば、なぜ、宗介と父は、崖の上の家と波間に浮かぶ貨物船の間で、ライトを使ったモールス信号で会話するのかといえば、それが描きたかったからでしょ? というおかしみでくすくすと笑いながら、思ってしまう。 あー、意味なんてないですよ、ただ描きたかったんですよ、そういう絵が、アニメが、きっと。 ものすごい欲望に忠実に描かれている、ただそれだけなのである。 まあ、ちょっと考えて、外洋(なのか?)に一人重要人物がいないと、外海を描けないという問題もあるのだが、まあ、そんな初歩的にテクニカルなところは、宮崎監督ぐらいのキャリアの人なら、自然に普通に考えるまでもなく配せるでしょう。 念のためにいっておくと、これは熟練した宮崎監督だからできる技であって、わたしもそうだけどひよっこはまねをすると、きっとやけどをするはずである。 特別の才能を持った人物の、職人芸であるのだ。 全体的な構想は、物語の整合性を取らないですむように、周囲をぼかして描かれている。まるでそこは重要ではないと言いたげだ。 例えば世界の均衡が壊れて、地球に月が近づきすぎるなどという表現があるが、たぶん世界の均衡うんぬんの話は、一切理屈などを考えていないはずである。「説明、魔法、以上」 みたいな世界。 だからこういうところつついても意味がない。 まあ、全体的にこれといった破綻らしい破綻もないので、まあ、いいのでは? という、すさまじくいい加減な結論に達するのだが、どうであろうか。 しつこいように書くが、これは宮崎監督が、海をテーマに描きたい映像に対する欲望の集成であって、物語も、その周辺の設定も、かなり控えめに道具のように使用されている痕跡が見えるだけである。 つつく意味はない。 これが描きたかったんですね・・・。 えーと、堪能させていただきました。面白かったです。 それでいいのではないだろうか。 最後に、これは報告であるが、映画館の、わたしが鑑賞した回の状況をリポートしておこう。 田舎のショッピングモールにあるシネコンプレックスで、9割以上は家族連れである。 子どもたちの反応はすこぶるよく、宮崎監督が心配するようなことは一切ない。 みんな楽しんでいた。 また劇場は一杯だった。 純粋に、素直に、子どもたちは楽しんでいたと思いますよ。 追記: 映像を通した物語構築理論みたいなのはあるのかもと思う。 ただ、それはわたしの専門範囲ではないので、放棄している。 わたしが言及しているのは、文脈的なところであって、それ以上でもそれ以下でもない。 なるほど、映像の作り方の話しはあるなあと思った。
August 3, 2008
コメント(1)
-
事実と仮説と、仮説の仮説
今年の2月、アメリカのネット調査会社comScoreが、googleの検索連動広告のクリックスルー率が下がっていることを発表し、google株は壊滅な下落に襲われた。 もともと下落傾向にあったgoogle株は最高値の747ドルから412ドルへ下落し、google神話の終焉かとささやかれた。 この記事がくわしい。 ■Google株4%下げ―クリックスルーの低下に市場は過剰反応か? http://jp.techcrunch.com/archives/did-the-market-overreact-to- googles-click-through-woes/ TechCrunchは冷静に 従来から comScoreのクリックスルー推計と現実のGoogleの収入とは相関が非常に低い傾向があった。とにかく1対1に対応していないことは明白である。 と指摘し、comScoreの調査結果とgoogleの業績にはなんら相関性はないと分析した。 事実、googleの第1四半期決算は極めて好調で、株価もその後537ドルへと戻している。 わたしはネットを周回しながら、googleが落ちているという感覚を全く感じていなかったので、これはおかしいと首をかしげた。ネット屋さんであれば、google帝国が衰退どころか拡大の一途をたどっていることはひしひしと感じているし、もう少しgoogleのことを知っている人は、googleはすでにネットの広告屋さんでないことぐらいわかっているはずだと思っていたからだ。 googleの強みは組織であり、テクノロジーではない。 一万人単位のDrを高度に組織化し、そのテクノロジーのレバッジで、圧倒的な高効率をたたき出す新世代のテクノロジー企業である。 高学歴の人材を、効率的に活用できる組織というところが革命的なのである。 なので、べつにテクノロジーのレバッジが利く分野であればコンピュータ分野に限ることはなく、最終的にはすべてがgoogleの活動フィールドになる。 エジソンが現役だった時代のGEみたいな会社と思えば、ほぼ間違いはない。 それが、たかだか広告のクリックが減ったからと言って10%以上も株価が下落するとは何だろう? TechCrunchはこう結ぶ。 これは投資家の参考になるような情報をいっかな公開しようとしないGoogleの秘密主義が裏目に出ている例といってよいだろう。情報の真空状態では、少しでも悪い情報が出ると、今日のように、市場は最悪を予期して行動に走るものだ。 そうだろうか? わたしには見えすぎるぐらいに見えてしまって、どこが秘密主義なのかわからない。 あまりにも異質すぎる企業なので、普通の企業と同じような視点で見ると見えなくなってしまうだけなのであると、わたしは思う。これはgoogleを全く理解していない株主がgoogle株を持っているという、そういうことなのだと思う。 ■仮説はあくまで、仮の説。検証しないかぎり正しくはない。 マーケティング・リサーチの分野では、そのリサーチの際に守る鉄則がある。「事実があり、そこに仮説を立てることにより、意見になる」 というものである。もしくは反対にいえば、「意見は、事実情報と仮説に分解できる」 というもので、これは定性マーケティングの世界では、結構知られた教えだと思う。 例えば、「わたしはこう思う」 と意見を述べた際、必ず上司には、「そのうち事実はどれだろう? そして君はどんな仮説を立てたのだ?」 と聞き返された。 このふたつは全く性質の違うものであり、分けて考えなければならない、という教えなのだ。事実に対してはその観測方法よってどれだけ誤差が出るか、または観測方法が正しかったのかと問われ、仮説に対してはその仮説を検証するにはどのような事実を収集したらよいかを問われた。 なかなかお堅いようだが、これをしないと水掛け論になってしまうのである。 例えば、「OLにヒットする飲みものはどんなものだろう?」 という疑問に答えるのは非常に大変である。 事実を収集して、仮説を立て、そしてその仮説を検証する。 典型的な新製品マーケティングのフローである。 ここで大切なのは、 事実は事実であり、動かしようがない。 仮説は無限に立てることができる。 よって、意見は仮説の数だけ生まれる。 ということだ。 優秀なマーケターであれば、仮説は無尽蔵に生み出せる。 仮説は唯一解ではなく、テストマーケティングよりそれを検証しないかぎり、正しい「説」にはならない。仮説は仮説だ。なので、仮説を戦わせても意味がない、というのが一番厳しいところでの教えだったような気がする。 もちろん、これは、何億円もかける新製品開発の話である。 明日、映画館に行ったらいいか、それとも遊園地へいくべきかにわざわざこれほど厳密な調査をする必要はない。 このやり方はグーグルでも主流のよう。 ■音楽業界を救えるか--グーグル元CIOに聞く http://japan.cnet.com/special/story/0,2000056049,20370791-2,00.htm より具体的には、Merrill氏はGoogleの広告モデルが音楽業界でもうまくいくのか試してみたいと述べた。しかし、Merrill氏はサブスクリプション型音楽サービスと、さらにはISP料金も試してみたいと考えている。確かに、Merrill氏が使う予定の戦略についての筆者の印象について述べると、同氏は1つのアイデアに固執していないということだ。(中略) われわれはそれらすべてを試してみるべきだ。そして、データが何を示すかを見るべきだ。そしてそれがどのような結論であってもわれわれはデータに従うべきだし、ユーザーに従うべきだ。それらを自分たちの指針にするべきなのだ。われわれはアートについて幅広い会話をするべきなのだ」(Merrill氏) これは、仮の説で論を戦わしても正解にはたどり着けないし、それよりもテストして事実を収集したほうがよい、というだけなのだ。 ■事実と向き合うのはつらい。 このやり方は実はとてもきついやり方でもある。 実際のところわたしたちは、自分の意見や仮説に愛着を持つ性質のようで、ときには事実の断片を無視したり、気付かないふりをして、自分の意見や仮説を通そうとする。 事実と向き合えるようになるのは、とてもたくさんの修行が必要で、今のわたしにも充分に事実に向き合えているような気はしない。会社の教えは、どうしたら事実をまっすぐ見つめられるかを書いた教えが多数あり、とても優しい言葉で、事実と向き合う心構えが書いてあった。 なんというか禅の修業みたいな内容なのである。 それがどのような結論であってもわれわれはデータに従うべきだし、ユーザーに従うべきだ これを実践するのは、本当に大変なのだ。 実際のところ、これを完全に行えている人にはあんまり出会ったことがない。 そしてわたしもできているとは思えない。 なので、ほとんどの人は、多かれ少なかれ、事実に向き合うことができずに、仮説をこねくり回したり、実際にはどうとでも言える意見を振りかざしていることになる。 これは効率が悪いのではあるが、悪いことをしているとは思わない。 できなくて普通なのだ。 むしろできる人は超優秀なマーケット・リサーチャーなのである。 冒頭のgoogle株の話で言えば、まず真っ先に調べなければならないのは、comScoreの調査方法は妥当かという部分の検証である。続いて、それが事実だとして、googleの成長戦略に影響があるかを検証しなければならない。 この段階では、仮説の段階だ。 マーケターは、さらにそれを裏付けるデータが出てくるまで判断を保留する。 もちろん、それでは、株を買う/売る機会を逸してしまう。 わたしがギャンブルをしないのは、こういうところにあるかもしれない。 わたしのやり方は、充分に仮説が検証されるまでは、検証し続けるというやり方なのである。もちろん、それはトレーダーの速度ではない。 ■仮説の上に仮説を重ねる 事実情報が不足しているとき、人はどうしても、仮説を立ててそのもっともらしい結論を事実の代わりにして、さらにその上に仮説を立てていく。 検証されていない仮説の上に、さらに仮説を立てるのは、間違っている可能性が非常に高い方法である。 なので、事実情報に基づいていない仮説は、実はほとんど意味がない。 ひとつの仮説でさえ間違っている可能性が高いのに、さらにその上に仮説を立てているからだ。 これは物理学などでもそうである。 例えば相対性理論などはかなりシンプルな仮説の上に成り立っているが、それでもその仮説が正しいという保証はどこにもない。観測値などで、事実を収集してそれがどうも正しいらしいというレベルまでしか行くことができない。 ひも理論などは、検証ができないために仮説に仮説を重ね、厖大な論に分岐してしまっている。このひも理論は、インフレーション理論というなかなか突飛な仮説の上に成り立っている。仮説の上に仮説を重ねている。なので、ひも理論が正しい可能性は、実際のところあんまり大きくない。 また、敢えて言えば、この世に正しい仮説などない、とも言える。 ニュートンの万有引力の法則でさえ、速度が光速に十分に近づくと成り立たなくなる。 厳密にはこの法則は正しくないのである。 仮説とは、今のところ正しいようだという、暫定的な正しさであって、唯一無二の真実ではないのだ。常に仮説は塗り替えられることを前提に、使えているうちは、便利な道具だとでも思って使うぐらいが、たぶんいい。 しかし厄介なことに、かなり訓練された人でないかぎり、この事実と、仮説、もしくは仮説によって導き出されたそれらしいものを、人はごっちゃにしてしまう。わたしも、そういう傾向があったので、上司に何度も何度も、これを分解するように訓練された。かなりつらかった記憶がある。 特に、長い間、仮説を事実と信じきってしまうと、それは事実ではないと指摘しても、それを直すことができない。 例えば、アメリカという国は常に変化している。 なので、事実情報は常に流動的であるのであるが、アメリカとはこういう国だと認識ができてしまうと、そこから離れられなくなってしまう。特に、事実情報が極端に限られた、分野においてはその振れ幅がとても大きくなる。仮説に仮説を重ね、化け物のような妖怪を生み出してしまう。 例えば、軍事機密の世界では、どれほど情報公開をしても、機密があるかもしれないという余地があるというだけで、仮説の仮説が横行し、何が真実かわからなくなってしまう。イラクに大量破壊兵器が存在することになってしまう。 もちろん、それはアメリカの最高の知性でさえそうなってしまうのであるから、人並みな人間であれば、これに太刀打ちするのは困難である。 この仮説偏見というのは、深刻な間違いを起こさせてしまう怖さを持っている。 また、頭のよい人ほど固執してしまう。 量子力学に頑迷に抵抗したアインシュタインがそのいい例だ。 アインシュタインは相対性理論の仮説から、生涯離れることができなかった。 これは誰にでも起こるのである。 そして、これは全く理不尽な結果に陥る。 投資のプロでさえ、不十分な情報を元に、google株を売ってしまうという失態を侵してしまうである。 結局のところ、事実の細かな断片を、丁寧に地道に拾っていくしかない。
July 7, 2008
コメント(0)
-
情報の差分と、政治
3月30日だったかのNHKラジオを聴いていて、高校野球が雨で順延になった。 番組が空いたと思ったら、なぜか突然、福田首相のインタビューが始まった。 なんかやたらとタイミングがいいとびっくりする。 のちに、テレビの放送を音声だけ流したものだと分かる。 福田さんが日米関係の共鳴外交について、絆は見えませんがね、と苦笑していたのが印象的だった。ステレス政治と揶揄される福田さんだか、もちろん見える人には見えるので、問題なく映るのだろう。 日本も、ヨーロッパも、アメリカも環境技術で次の成長セクターを作ろうとしている。 日本は、省エネ技術で。 ヨーロッパは、規制振興政策中心で。 アメリカは、ダイナミックな投資で。 特にアメリカの記事で、この危機を乗り切るには環境でバブルを作らなければだめだ、と力説していたのは笑った。 アメリカらしい。 既にアメリカのリスクマネーは、クリーンエネルギー技術にじゃぶじゃぶと流れ始めているし、先進国すべてが「環境」で一致しているのでここでバブルが発生し、アメリカでは華々しい新興企業が生まれ、次の時代の旗手となるのであろう。 21世紀は環境が安全保障となる時代だ。 これは間違いない。 日経などを見ると、福田さんが経済成長戦略で環境を打ち出した当初はピンと来ていなかったようだが、現在、ほとんど全力で「新興国のインフラ整備」と同時に「持続可能な成長のための環境技術」へと舵を切っていることが分かる。 先進国がお互いの顔を見合わせて、「お前も環境?」「あ、お前も?」「ってことは、環境かぁ」「ああ、環境だな」 という感じがして、この辺の空気感は面白い。 こういう感じって、他の時代にもあったのだろうか? これはどうでもいいことだが、とても知りたい。 見えない情報というのは不思議なもので、実際には見えているのに、気付いていない場合のほうが多い。 先日、NHKラジオの深夜にNHK福地会長を参考人として呼んでの、委員会の様子が流れた。その中でどなたか、忘れてしまったのだが、NHKの朝の番組をさして、非常に評価しているといっていた。「これまでは、イチローのオープン戦での打率などの放送が多かった。だけど、今のNHKはもっと国民が知るべきものを伝えている。例えば、国際情勢。この前の、メコン河に架橋して完成した南北回廊の特集。すばらしいと思った。新聞などでも伝えられていないことだ。ぜひとも続けて欲しい」 というような内容だったと思う。(ちょっと左寄りの特集も多くないか? という指摘もあった(笑)。左寄りも大切ですよ~) 実際には、NHKのテレビもNHKラジオ並みにマニアックな内容もやるようになったという話なのだが、わたしが、そのとき思ったのは、あー、南北回廊って、やっぱ国会議員も重要だと思ってるんだぁ、ということだった。 南北回廊はこの記事にくわしい。 ■メコン川流域、「南北回廊」がもたらした変化(上) http://www.chosunonline.com/article/20080401000023 ちなみに、わたしのアジア情勢の情報源はほとんどNHKラジオと朝鮮日報である。(もちろん、各国国内情報は各国の報道機関がくわしい) NHKは実はすぐれた国際部を持っているのだけれど、テレビではなかなか露出できず、ラジオのほうで鬱憤を晴らすみたいな状況になっていたのだ。それをテレビのほうに漏出するようになった、それだけなのだけど(ちなみに日経系は企業とのコネクション中心で、日経ビジネスが日経国際部の牙城になっている気がする)。 わたしが国際情勢に敏感なのは、単純に知財という国際的なアンテナが必要な仕事に就いているからである。 なので、興味があるのは、産業分野だけ。 地政学的リスクとかは、あんまり興味がないので、念のため。(そうか、これは、わたしのリスクではないからなのだな・・・。どうでもいいけど・・・。ちなみに環境技術はスーパー・ダイレクト。技術移転のスキームとか見とかなければねえ・・・。タイ語で特許出願よろしくとか来そうである) しかし、日本人は東南アジアの情勢にあんまり詳しくないようである。 例えば、ベトナム新幹線が日本のODA3兆円で、日本企業が受注したみたいな話はたぶん知らない人が多いだろう。 わたしは直撃。 多くの第二次産業の職に就いている人も直撃だろう。 でも、例えば、服飾系の人は知っているのだろうか? Web系の人は知らないと思う。 マスコミの人も多くは知らないかも知れない。 ちょっと注意深く情報を見ていれば、どこかにちょろっと載る話なのだけど、世論というのはマスコミが一週間に3時間ぐらい騒ぎ立てなければ気付かないようになってしまったのかも知れない。 情報というのは、誰かに騒いでもらってはじめて知るのではなく、取りに行くものだと思う。 新聞でも丹念に読めば、重要な情報の断片は書いてある。 ただ、それがパッチワーク状になっていて、そのピースをちゃんと組み合わせないと全体像は見えてこない。どうつなげるかは、その人の情報分析力による。 例えば、情報は、受信の際そして発信の際に歪む。 なので、新聞記者が現地情報を受信した際に歪んでいるはずであり、発信した際にも歪んでいるはずである。もちろんわたしの受信も発信も歪んでいるはずなので、それは考慮に入れて欲しいのだが、文字にする以上、実際の現地情報との間に差分があることを考慮に入れなければいけない。 国会中継を聞くことは一次情報を直接入手することだけど、ずっと国会中継を聞いているわけには行かない。 なので、新聞を読むのだが、そこにある歪みを前提で読まないと、そこから情報の断片をつかむことができなくなってしまう。一次情報と二次情報の差分を取るには、その両者を比較してみるしかない。そして、ああ、これぐらい歪むのだな、この辺は歪まないのだなという部分を、差分として常に自分の感覚として持っていないといけない。 どんなに公正な人を通しても、すべての情報は歪むのである。 ローマ史の最優秀歴史家タキトゥスでさえ歪み、塩野七生でさえ歪むのだ。 情報とは歪む特性を持っているのである。 なので、事実と思われる部分だけを保留つきで取り出して、それを再構成して自分なりの解釈で読まなくてはいけない。 これは、おそらくほとんどの人が無意識でやっていることだと思う。 ただ、その精度にたぶん差がある。 つまり、情報の差分をちゃんと取っている人と、取っていない人、極端な場合は丸呑みに近い人の間では情報力に違いが出るのだと思う。 情報の差分を取るのに、最も簡単な方法は一次情報と二次情報を比べることだ。 しかし、一次情報は要約されていない上に、手に入れにくい。 そこで、世間一般には複数情報に当たるという方法をとる。 例えば、新聞は二紙読めというのはそれに当たる。 今はネットで気楽に読み比べられるので、複数情報に当たることは難しいことではない。 大量の情報に当たれば当たるほど差分情報がたまっていき、それを長い年月続けることで差分把握力は格段に上がっていく。 もちろん、極端に受信と発信が正確な情報源はいる。 受信力があり、発信力があるということだ。 しかも、両方とも尋常じゃないほど力があるということ。 こういう人はとてもまれで、貴重であるのでぜひとも逃したくないのだが、なかなか見つけにくい。なので、この人はこの辺は正確だが、この辺は当てにならないというのを、あちこちの情報源に当たって、断片的に「正確な人」のパーツを集める。 そして、「正確な人」を再構成する。 できれば、「正確な人」同士からさらに差分を抽出するみたいなことまでやりたいのだが、たぶんこれは、わたしが情報分析マニアだからか。 さて、政治の話をみていて、福田さんというのは結構この差分を組み合わせてステレスしているのだなあと思えてくる。 分かる人にはわかる。 それはその差分が読めるからだ。 だけど、その差分が読めない人にはわからない。 カエサルにしても、アウグストゥスにしても、ローマ市民の声を適切に聞き(つまり適切に受信し)、問題解決をしていたように見える。政治とは国民の声を聞き、その差分を適切に把握して国の全体像を把握して、問題を解決して行くものだと思う。 国会議員だけでも、相手にするのは大変だ。 それが、全国民、それどころか世界中の声を聞いて、意思決定するというのは大変なことだ。 最近になって、経営者というのはそれをしているのだなと、なんとなく納得した。 現場を見て差分を取る人もあり、幹部の声を聞いて差分を取る人もある。数字しか見ない人も居る。 これはマーケティングも同じだ。 市場の声をどう掴み、なにをし、どう声を発するかなのである。 受信だけが強い人も、発信だけが強い人もいる。 あー、そうだったのか、と、腑に落ちた。 国際政治においてトップの顔が変わらないほうがいいというのは、トップが替わってしまうと、この差分が把握しにくくなってしまうから、ではないだろうか? 適切な長期政権が望ましいのは、差分をリセットしなくてもよいからではないだろうか? アメリカの大統領が分かりやすいのは、たぶん長期の大統領選挙でその差分を把握する期間が長いからではないだろうか? 中国やロシアが不気味に見えるのは、この差分が取りにくいからではないだろうか? わたしはそんな気がするのだ。
April 4, 2008
コメント(0)
-
どうすればデジタルコンテンツは売れるのか
テレビ業界の競争力がひどいことになっているようなので、ちょっと書いておく。 これはマーケティングの四則演算である。 2006年度に邦画の興行収入が洋画を抜いて、邦画が面白くなったからだといっている人々がいた。わたしはそれを見て唖然としたのだが、これは単純に2006年の洋画がつまらなかったからに過ぎなかったことは2007年に証明された。 基本的に、映画のマーケットニーズ、つまり、映画でも見に行くかニーズは急拡大するわけがなく、限られたパイの中で競争に過ぎないからだ。 「おれの映画には1800円の価値がある」わけがなく、それどころか300円の価値もないことを理解しないと、かなりひどい状況に追い込まれることになる。価値があるのは、休日を退屈しないで過ごす、というニーズを満たすことであり、映像コンテンツに価値があるからではないのだ。 面白い映画があるから見に行くわけではなく、映画を見る休日という枠が先行するのである。 邦画か、洋画かはその後の選択なのである。 ロード・オブ・ザ・リングが面白い、が先行するのではなく、恋人と見るのにちょうどいい映画が先行するのだ。 これがマーケットニーズだ。 ニーズを満たした後に、選択が起こるのである。 こう考えてみると、キラーコンテンツとは何かという問題がすぐに解ける。 一番売れるコンテンツとは何かといわれれば、一番多くのニーズを満たすコンテンツなのである。 恋人同士で見てもいいし、家族連れで見てもいいし、一人で見てもいい、ならば多くのニーズを満たすことになる。ハリウッド映画がどうしても似通ってくるのは、たくさんのニーズを満たす映画が平均的になってしまうからだ。よく売れる車が似通った形になってしまうのは、このせいである。 しかし、この戦略にはいくつかの落とし穴がある。 真っ先に思い浮かぶのはどの映画も同じような映画になってしまい差別化ができないということだろうし、そうなると価格競争に陥り、過当競争に陥る。 また、同じような映画ばかりだと、すぐに飽きてしまう。 みんなが同じような映画を作りまくると陳腐化の速度が極端に速くなるのである。 例えば、ハリー・ポッターが売れると分かった瞬間に、ファンタジー映画が乱立し、ファンタジー映画自体の目新しさがなくなってしまう。これはみんな経験したはずなので分かりやすいはずである。 ティム・バートンとジョニー・ディップのコンビの映画が長生きなのは、このコンビにはほかの人には真似しにくいエグさがあるからだ。ティム・バートンだけではたぶん、多くに売れることはないエグいだけのニッチ商品になることは請け合いだが、ジョニー・ディップの滑稽さがプラスされると、エグいけど売れる商品になる。 このコンビは、極めて難しいところでぎりぎり広く受け入れられるバランスを保っているので、他の人間にはそのバランスが難しすぎて、まねができないのである。だから陳腐化しにくい。 ほかに選択肢もないので、ティム・バートン映画市場を独占できる。 これがキラーコンテンツの秘密である。 ティム・バートン映画市場を、どうティム・バートンは作ったのかは、説明が面倒なので省く。簡単に言うと、またあいつの映画をみたいというファンをじわじわ増やしたというだけだ。難しくないのだが、説明が長くなる。村上春樹にはたくさんファンがついているが、わたしは大っ嫌いというからくりである。あとは村上春樹のほうが知っていると思うので、彼に聞いて欲しい。そういえば、よしもとばななも顧客制だとか言ってたなあと思い出す。 あー、そうかパイレーツ・オブ・カリビアンって、日本人の何パーセントが見たのだろうか? でいいかな? みているのはごく限られた層なのである。つまり、めぐりめぐってそこを侵食されないことが強みなのだ。 さて、パイレーツ・オブ・カリビアンほど売れなくてもいいから、新しい市場を作って、そこそこ売りたい場合はどうしたらいいのだろう。 つまりプロになるのはどうしたらいいのだろう? これはマーケティング的には一つしか手段がない。 とんがった作品を作るのだ。 とんがった作品ということは、想定顧客が少ないということである。 丸くなるの反対だ。 例えば、八王子市を舞台にした映画は、八王子市民なら見る可能性が高いだろう。 だけど福岡の人が見るとは思えない。 対象を狭くすると、つまりニッチを狙うと、ニッチマーケットに刺さりやすくなる。 だけど、ニッチのままでは食っていけない。 これは同人のレベルだ。 この自分市場を少しずつ大きくして食っていけるだけにまで広げた人がプロなのである。 特定のニーズを満たした作品は、案外売れる。 例えばガンダムの電源なしゲームは、コミケに持っていけばライバルは極めて限られているわりにニーズがある。ただ、もちろん、食っていけるほどには売れないのだが。 また、この自分作品市場を作るためには、継続的に買うお客を繋ぎとめておく必要がある。ようはまた買ってもいいなあとと思ってもらえることで、そのためには、そこそこの品質が必要になる。 ただ、これは別にその人物の作品に数百円の価値があるわけではない。 このお客に売れるのは、そのお客には既にキュービッドの矢が突き刺さっているからであり、品質が高いから売れるわけではない。お客の暇な時間を潰すというニーズを満たす選択肢としてその人の作品が入っているためであり、たとえどんなに品質が高くても、村上春樹作品はわたしにとっては粗大ごみだ。 品質が必要なのは、飽きられたり幻滅させないためなのである。 ということをめぐりめぐって考えてみると、結局、どう刺すかがすべてなのだ。 まあ、たまにスピルバーグのような同じ人類とは思えない超天才もいたりするのだが。 えーと、何だったけ? あー、そうかデジタルコンテンツの売り方だったか・・・。 多くの人が勘違いしていることは、面白い作品があればうれるということだ。 んな、馬鹿な話はない。 映画は、「映画でも見に行くかニーズ」を満たしているから売れるのである。 うそだと思うなら6時間の映画を作ってみるといい。 日本市場では絶対に売れない。 映画が売れるのは2時間の時間を、映画館で過ごすという経験が、既に多くのユーザに突き刺さっているからだ。映画はその規格化が高度に進化しているので、他のエンターテイメント商品と比べてマーケット競争力があるのである。 だから1800円の値段をつけられるのだ。 繰り返すが、パイレーツ・オブ・カリビアンに1800円の値段がついてるわけではない。 映画を見る時間に1800円の値段がついているのだ。 映画のシステムについている値段なのだ。 もう少し回り道をして、そのシステムを作るにはどうしたらいいかを考えよう。 ようは「映画でも見るかニーズ」の作り方である。 これは非常に簡単であって、ニーズを作るスペースをまず作る(見つける)、そのスペースに居る人にこれはどう?とオススメしてみる、試した人がその体験に満足すれば完了。 どうすれば、iTunesのコンテンツを売ればいいかといえば、iPodを売ればいいのだ。 iPodが魅力的な商品で、思わず買ってしまった人は、どうしてもそこに音楽を入れたくなる。 まず、iPodを動かすにはiTunesを起動しなければいけない。 はじめは持っているCDをリッピングして入れるが、あまりにもiTunesが快適なのと、iTunesが進めるので、まずはじめの一歩を買ってしまう、その購入経験がトータルですばらしければ、ユーザは買い続ける。 これだけだ。 あとは独自の販売システムに、侵入しようとする者をがしがしとぶったおして行くだけだ。ただ、まあ、iPodがあまりにもあっという間にぶっ壊れて、幻滅すればもう二度とiTunesでは買わないと思うけど。 なので、実はiTunesって簡単に値上げできるのは? と思うのだが、まあ、誰も言ってないので、放置しておくことにしよう。 さて、この考え方でみてみると、どうすればデジタルコンテンツを売ればいいのかが分かってくる。 1)まず、あいているニーズを探す。 2)続いて、そのニーズにコンテンツを勧めてみる。 3)とにかくスムーズにして、障壁をなくす。 4)ユーザが満足すれば、幻滅させないかぎり、永久に買い続ける。 ということなのである。 みるべきは、コンテンツではなく、ニーズなのである。 ■で、なんで、テレビ番組って売れてないの? これは結論から言えば、刺さるコンテンツじゃないから。 というか、視聴率20%をめざすコンテンツと、ネット売れるコンテンツは違う。 テレビの満たすニーズはお茶の間で家族全員でがははと笑うコンテンツ、ネットが満たすニーズは一人ひっそり見るコンテンツ。 違うでしょ? 実は競合しないのである。 幾らネットにコンテンツを流しても(有料で)、テレビ番組の価値は毀損しないのである。だって、値段はニーズにつくものだから。 というか例えば4人家族だとして、一人がPCを占有できる時間ってどんなもんじゃろうか? 1時間も占有できるのだろうか? PCでテレビ番組を見るなんて考えられない、目が疲れるなどというなよ友よ。 最近の高校生は、ケータイで小説読んでるんだぜ? 書いているのは、プロ作家経験のない子達。 品質はそんなに関係ない。 そこにニーズがあったということなのだ。 さて、頭を働かそう。 ケータイでユーザたちが喜んでみるコンテンツとはどんなものだろう? このニーズを埋めているやつって、あんまり居なくない? で、テレビの広告費がまずいらしい。 広告費を出しているのは企業。 ってことは、広告費が出る意思決定は企業がしているわけだ。 これは、想像するしかないのだが、テレビ広告が効かなくなっていると判断されているのではないだろうか? というか企業が広告を減らす理由は、それがあんまり効率的ではないからという理由以外に思いつかない。 で、広告の効かなくなっているのは、たぶん、ニーズがなくなって来たから。 ん? 分かりにくい? お茶の間で家族全員でがははと笑うというニーズがなくなってきたのではと思うのだ。 つまり、視聴率は変わらなくても、テレビを見ている人自体の数は減ってきているのではないか、と想像される。まあ、テレビのコンテンツの品質が下がってきて、幻滅されて買うのやめてしまったというのも考えられるのだが・・・。 さて、では、テレビを見なくなったユーザはどうしているのだろうか? その考察は、あなたに譲ろう。 少なくともYoutubeをみているわけではないと思うんだよね。 Youtubeの一人辺りの滞留時間を調べたことある? 月に1時間とか、そんなもんだった気がするんだけど? ちなみに、今、わたしは、R.O.DというアニメをレンタルDVDで見ている。 フルハイビジョンでみていて、DVDは画質がへぼいなあと、思っていたりする。 もちろん、オンラインでもR.O.Dは見ることができるけど、オンラインは決済がへぼいので(わたしはクレジットカードを持っていない)見る気がしない。三菱東京UFJのオンライン決済ができるサイトがあればいいのに。 あまりにもいいマッドビデオがあって、すごい面白いアニメであることが分かったので、思わず全9巻×300円を投入してしまった。TSUTAYAがちゃんと払うなら、いや、払うと思うが、ちゃりんと権利者に落ちるはずである。 わたしには、このサイクルは結構刺さっている。 売れない売れないという人は、マーケットを完全に舐め切っている。 アニメが売れるようになるまで、どんだけかかったと思ってるのだろうか? 今、急速にアニメはお客さんを幻滅させているけど。 (おっと、機能ニーズの話をしなかった・・・。まあ、いいか。泣けるって機能ニーズは売れるという話なんだけど、そのうちに)
March 26, 2008
コメント(0)
-
空気が作るスポーツ
ソフトバンクがパリーグの放映権を掌握して、ネットで全中継をみることができるようになった。 これは、異論があるだろうが、まず思うのは、金額が異常に安いなということ。 続いて、ソフトバンクは(というかYahooだが)これにCMをつけていないので、どうやって回収するのだろうということ。 また、ネットを介して、各ファンがそれぞれのチームの違いを見始めたということ。 これは、これほどまでに価格が安くならなければできなかっただろう、ということ。 しかし、放映権は球団経営において大きな収益源なので、このままじゃあまずいだろうなあ、というところ。 興味の範囲は二転三転するが、今年はプロ野球の興行において、特異点となる時代なのだろうなあと思ってしまう。ソフトバンクは長い視点で、戦略を立てているような気配がする。ダイエーホークスの買収から、ソフトバンクがたどってきた道を俯瞰してみると、短期間でパリーグでの電通の地位を得ながら、その先を見据えている気がしてくる。 つまり、パリーグにおける、戦略的代理店の地位である。 これは5億円で買えてしまうのか。 すごい時代だなと思った。 さて、はて。 わたしが気になっているのは、わたしが愛する浦和レッズのことである。 Jリーグの各チームは、浦和も含めて、ヨーロッパのチームとの財政的な格差に悩んでいる。浦和が年間80億円ぐらいの収益があり、ヨーロッパのチームは200億円ぐらいの収益がある。この差をつめているのはすばらしい努力だが、チームの収支のほとんどが選手獲得・維持の費用であるのであるので、その数字がそのまま、チームの選手の価格になってしまう。 いい選手には、払ってほしいと思うが、お金の問題は、何で払えないかではなくて、なんで稼がないかなのである。 会社の経営者は、なぜ利益を上げられないかに対して、労働者に対して説明する義務がある。もちろん、なぜ払えないかとこれは同質になるのだが。 Jリーグに関していえば、これは、放映権料をどう得るか、の問題である気がするのだ。 ただ、ここは本論ではないので、割愛しよう。 まあ、ここは、上層陣以外に変えようがないので、経営陣の問題であるのだが。 それよりも、もうちょっと、みんなが参加できる部分を書きたい。 チームを囲む空気の熱狂の話である。 パリーグのゲームを、Yahooを使えば、各チームの中継を見ることができる。 ネットでいろいろな人の雑感をみていて、ライオンズファンと楽天ファンは試合を見ている注力度が違うと感じた。 わたしは埼玉県人なので、浦和レッズファンであり、西武ライオンズファンである。 これは、もう20年ぐらい変わらないので、たぶん一生変わらないだろう。 東京都の東大和市にいた頃から、その市は西武線の路線地域なので、路線に住む人たちは、西武ファンになることが自然に思えた。 ファンというのは、地域につくというのが最近の潮流であるが、どっちかというと情報流通圏ではないかと思う。わたしはinfoseek、つまり楽天情報圏なので、楽天に対しては、守備範囲になってしまう。 ファンではない。 この辺が重要である。 なんか話題が、それたので、修正しよう。 すさまじく重要な話をしようとしたことは、君と僕との秘密だ!(笑) (この辺は実弾が飛び交う世界であるなぁ・・・) えーと、なんの話だったろうか。 あー、そうか。 ソフトバンク=楽天戦、西武=オリックス戦の中継を見ていて、どう考えても、楽天戦の中継が熱狂的という問題である。 これはなんなんだろうね。 選手に関していえば、もっとファンに、いい選手だと思わせて欲しい。 みんな、試合は見ているし、情報はあらゆる情報源からえているので、いい姿を見せて欲しいかなあ・・・。 これは話せない。 そうか。 話せないのか。(これは、単純に話すために、これまでの職歴から得た情報を、もしくはノウハウを出さざる終えないからである。これはどうしたらいいのだろうね・・・。) この話は、なんかうまい方法を見つけたら、そのうち書く。
March 22, 2008
コメント(0)
-
「肩こり」との戦い
どー、でもいいことであるが、わたしは肩こりしやすい体質である。 デスクワークだし、パソコン仕事。 姿勢は悪いかもだし、運動の趣味はない。 休日は外出しようとしてはいるが、週末に二三時間歩いても、運動不足は解消しない。 Webデザインの仕事をしていた頃、それはそれはすさまじい肩こりだった。 ばりばりと筋肉が音を立てそうなほどの肩こり。 全身が鉛のような肩こり。 慢性的な頭痛。 それもそのはずだ、当時の働きぶりは肩こり製造マシンのような状況だったからだ。 Webデザインの仕事は、非常に緻密な作業を続ける細工師のような仕事に似ている。 もしくは、CADで設計図を引く設計者。 画面は非常に激しく動き、視線や脳みそは、いかにも知的に動くのだが、よく見ると身体の動きはほとんどない。おそらく、キーボードを使ってタイピングしているほうが動いているはずである。 マスキングをするのも、ベクターを書くのも、彩色するのも、コーディングするのも。 ほとんどの作業をマウスの数ミリの動作で行ってしまうので、後に張り付いて、画面ではなく、わたしの動作を見ていると、わたしはなにもせず、コンピュータが自動でデザインをしているように見える。 それを気が入った状態で、数時間ぶっ続けで行う。 肩がこらないはずがない。 しかし、わたしはその当時、自分が肩こりであることに気付かなかった。 毎週土壇場のような職場であり、わたしの作業速度がサイトの更新速度を支えており、わたしは作業速度と売り上げだけに注力していればよかったことになっていたからだ。 週に二三回は徹夜。 それでも、わたしは黙々とやるタイプだった。 週末の更新が終わると、土日は何もやる気が起きず、寝てすごす。 たっぷり寝たつもりが、週初に出社すると、どっしりと身体が疲れていた。 これはなんだろう? わたしはしばらくそれが肩こりであることに気付かなかった。 そうするうちにどんどんと状況は悪化し、頭痛や耳鳴り、しまいには神経までやられ始めた。 どんなに寝てもわたしの疲れは解決しない。 それどころか、疲れは増す一方だった。 そしてあるとき気付く。 これは肩こりだ、と。 即座にネットで検索し、近所の指圧師を見つけて、駆け込んだ。 指圧師の兄ちゃんはわたしよりたぶん2歳ほど若い人で、電機店で働くストレスに耐えられなくなって、指圧師になったという。 見てもらうと、「これは、すごいっすね・・・」 と苦笑する。 どうもめちゃくちゃな状況になっていたらしい。 わたしはしゃべる気力もなくなっていたから、ほとんど話すことができなかったが、その兄ちゃんから、あれこれと指圧の知識を教わった。 肩こりというのは、疲労物質が筋肉の毛細血管に詰まって、そこへ血がいかなくなっている状況を言うらしい。それをその兄ちゃんは「硬くなっている」というのだが、ようは筋肉がブレーキになって、その「硬くなった」筋肉によって神経が圧迫されたり、脳に血がいかなくなったりしている状況らしい。 そういうとたぶん多くの人は、目詰まりを起こした水道を思い浮かべるだろう。 でも、人間の血の巡りは水道の仕組みとは違って、もうちょっと複雑だ。 実際、人間の血流のうち、心臓が果たしている役割はあまり多くないという。 実は全身の筋肉がポンプの役割をして、心臓に血を送り返す機能も持っているらしい。 たとえば、人間の脚は第二の心臓と呼ばれる。 これは脚の筋肉が重力に引かれて下に集まる血を心臓まで送り戻すからだ。 血を下から上に持ち上げる力と、下から上に流す力を比べて見れば、なるほど脚のポンプとしての力は強いのだなと納得できるだろう。 よく足裏マッサージというものがあるが、これを理解すれば、分かりやすいだろう。 足の裏というのは、実は毛細血管の塊であって、そこを経由して脚へ流れてきた血は心臓に送り戻される。しかし、そこが「硬くなっていた」としたら、その血は容易に戻らなくなる。 つまり、血が流れなくなってしまう。 足の裏は痛がらないから分かりにくいのだが、足裏マッサージというのは足の肩こりを治しているようなものなのである。 指圧師の兄ちゃんは時間をかけてわたしの全身を押したり、叩いたり、ひねったりしながら、筋肉を「軟らかくして」いく。がちがちに固まった筋肉をほぐすのだから大変なことだろうと思うのだが、わたしはほとんど余裕なく、ただうんうんと頷くしかなかった。 そして、長い時間がかかって、指圧が終わる。 終わって先生(兄ちゃん)は、にこやかにいう。「たぶん30分ぐらいすると疲労物質が流れ始めますから、安静にしていてください。水分をたくさんとって、横になってください」 わたしは、意味も分からずうんうん頷いて、お金を払って、帰りがけにミネラルウォーターを飲んで、帰宅しようとした。 そのとき、めまいのような得もいえない疲れに襲われた。 全身を疲労物質が流れ始めたのだ。 これまで目詰まりしていたものが一斉に。 もうこうなったら、腎臓にがんばって濾してもらう以外にない。 コンビニで水のペットボトルを買って、帰って、寝た。 それからというもの、週に一回は先生(兄ちゃん)に頼んで、指圧をしてもらうようになった。 週を追うごとに回復して行くのが分かった。 わたしは肩こりだったのだ。 かなり深刻な。 しかし、肩こりの怖さというのは、それに気付かないことだ。 たぶん、深刻な肩こりであればあるほど、それが肩こりであることに気付かない。 はじめのうちは、あれ? 肩こりかな? と思うのだが、仕事に集中して行くうちにそれが麻痺していってしまう。 次第に体調が悪くなり始め、神経のほうがやられ始める。 こうなってくると、本当は医者に相談して、薬を処方してもらったほうがよいのだが、いかんせん医者でも肩こりであることに気付かないケースもある。 肩こりは、あらゆる検査で検出することができないのが怖い。 そして、深刻に悪化すれば、かなりやばい状況まで行ってしまうのは、わたしは経験済みだ。 なので、もっとも適切なアドバイスは、もしかしたら肩こりかも、と脳裏のどこかに入れておくことかもしれない。肩こりと分かれば、対処法は無数にある。なんたって、それは筋肉が「硬くなって」血が流れなくなってしまっているだけなのだから。 肩こりの対処法としてよく聞くのは、ストレッチをする方法である。 わたしの文章のひそかな師匠だった方の言葉によれば、汗がじっとりにじむぐらいまで30分ぐらい念入りにストレッチをするといいらしい。しかし、これはわたしのしょうには合わず、わたしは指圧師に頼むことにした。 もちろん、これ以外にも、Webを探せばいくらでも肩こり解消法は見つかる。 なので、その中から、自分が続けられそうなものをチョイスして試してみるのがいいのかもしれない。根本的には、肩こりの原因は運動不足なので、何らかの運動をすることにはなると思うのだが。 最近、といってもここ半年ほどなのだが、わたしは自分にぴったりな肩こり解消法を見つけた。こんなシンプルなことだったのか、とびっくりしたぐらいだ。 わたしは、ここのところ、週に一回か二回、走ることにしている。 大体、30分ぐらい。 それだけ? と拍子抜けされるかも知れないが、わたしの場合はこれでうまく回るようだ。わたしは昔運動部だったので、30分走るぐらいなら、そんなに苦ではない。だけど、あんまり走った経験がない人には、30分、つまり5~6キロを毎週走るというのは結構きついかもしれない。なので自分に適切な方法を選ぶといい。 わたしが走るのもたいした理由ではない。 健康維持とか、体力保持とかそういう格好いい動機ではない。 筋肉質で、小食なので、ダイエットの必要はわたしにはない。 これが一番楽だと気づいただけなのだ。 肩こりのきつさが分かっていれば、30分走るぐらいは、たいした苦痛ではない。 じつは最近になって、人に限らず「肩こり」に苦しんでいるように見えるものが多くなった。 たとえば、わたしはこれまで4社ぐらいの会社を回ったが、どうもあれは「肩こり」なのではと思える状況をしばしば見た。 わたしが一番心地よかったのは最初の会社である。 仕事の量はとんでもない量になっていたが、それでも4年(あれ、3年か?)続いていたのは、今になってみれば不思議である。全社的に疲弊していたし、どこかやり方を間違っていて、なにか方向を見失っていたが、それでも「肩こり」はなかったように思う。 みんなで迷っていた。 そんな感じだった。 そして、それは先端を切り開こうとすれば、よほど幸運でないかぎり、絶対にぶち当たる時期である。 わたしは、どうもこれを勘違いしていたようで、最近になって悪いところの中によいところがたくさんあったと思うようになった。 なぜ、あの会社に「肩こり」はなかったのだろうか、と。 考えをめぐらすうちに、あの会社では、宴会が異様に多かったことを思い出す。 たぶん、月に1回はあった。 何かにつけ、理由をこじつけて、宴会するなり、リフレッシュするなりする。 あれが実はよかったのではと思うのである。 宴会といってもただ飲むだけではない。 結構熱心に楽しくしようとしていた。 リフレッシュしにスキーでもしにいったとき、もし、頭に仕事のことがあれば、たぶん充分なリフレッシュにはならないだろう。スキーでも、水泳でもなんでもいいのだが、やるからには本気で楽しんでやる。 たとえば上司は、わたしに水泳勝負を挑んでくる。 わたしはこれでもスイミングスクールに通っていた。 勝負となれば本気で受けて立たなければならない。 宴会もこれと同じ感覚でやっていた気がする。 宴会を競うというわけではないが、じゃあここからは面白いこと言ったやつが勝ちな、みたいな、そういう宴会だった。数人の女の子を囲んで、けしかけて男同士で討論させたりしていた。みんな本気で宴会をやっていたのである。漫然と、仲良くするみたいな、そういう宴会ではなく。 今になって気付くのだが、それはわたしがやっている毎週30分走る、というのと同じだったのでは? という気がする。 あれは、実はすごく有益だったのではないか、と。 もちろん、酔ってする議論に生産性などない(毎週30分走ることが肩こり解消以外の意味がないように)。でも、その「肩こり」を解消するにはじつに有益だったのではないかと、そう思うようになった。 「肩こり」は自覚症状がないから怖い。 それが致命的な状況に「人」を追いやるから、とても怖い。 そして、気付きさえすれば、すぐに解消できるのだ。 さて、仕事納めの本日、みなさま、いかがお過ごしでしょうか。 どっしりとした疲れに身をゆだねているのではないでしょうか。 わたしも、今年一年、そんなにたいしたことをしていたわけでもないけど、へとへとに疲れ果てました。 もう、あちこちの身体がぱんぱんに張っており、肩も「硬くなって」来ています。 なので、これから走りに行こうっと。 これはこれで、わたしにとっては、神聖な戦いなのだ(笑)。 今年一年、お疲れ様でした。
December 28, 2007
コメント(0)
-
YouTubeで見れる、黄金期のマッドビデオ3
第一弾はこちら YouTubeで見れる、黄金期のマッドビデオ 第二弾はこちら YouTubeで見れる、黄金期のマッドビデオ2 えーと、マッド飢えがやってまいりました・・・。 さくさく紹介してしまいたいと思います。 ■【MAD】 明日のナージャ 約束の場所へ (曲:約束の場所へ /カレイドスター) http://jp.youtube.com/watch?v=xf1ft-9sE2w アニメは知らないのだが、できはいいかなあ。 ★★★ ■(MAD MOVIE) バイオマンOP+セーラームーン.avi http://jp.youtube.com/watch?v=yt2kdM0y_oo バイオムーンあった! これははじおうだと思われる。 ★★★ ■少女革命Gガンダム http://jp.youtube.com/watch?v=Bx3iyb90ZbY これも懐かしい。これだれが作ったんだろう? ★★★ ■【MAD】 新世紀GPX サイバーフォーミュラSAGA 「誰よりも速くなれ」 http://jp.youtube.com/watch?v=yjuFDZmzP1c サイバーフォーミュラーオタクの道へようこそ。しかし、超ネタばれ映像である・・・。 ★★ ■(まっど) ガンダムSEED DESTINY + ゴッドマーズOPMAD http://jp.youtube.com/watch?v=yL9EsFBvZPo ゴッドマーズですか・・・。懐かしすぎる・・・。 ★★ ■装甲騎兵ボトムズ:哀・戦士 http://jp.youtube.com/watch?v=Smqu8jxGVbo おわー! 見つけた! これは夫婦企画の作ですね。改変されてるけど。 ★★★ ■レッドショルダーのシャア http://jp.youtube.com/watch?v=gNb5oo_Ouhw これも夫婦企画だと思われる。 ★★ ■ToHeart2 MAD http://jp.youtube.com/watch?v=JA-5TdMEmvM 空間の使い方が異様にうまいんだよなあ・・・。 ★★★★ ■【MAD】セーラームーン+レイズナー http://jp.youtube.com/watch?v=0fDMoT5Y4qk おー、これはなつかしー! 傑作マッドと呼ばれていた。 ★★★ ■(まっど) ガンダムSEED DESTINY + レイズナーOPMAD http://jp.youtube.com/watch?v=tK0mL4FM75s レイズナーつながり。レイズナーマッドの見所はセリフだったりする。 ★★ ■キン肉革命ウテナ2世 http://jp.youtube.com/watch?v=YWxTlivDO4I これは有名なはず。出来はいい。 ★★★★ ■ジャイアントロボ x 機動武闘伝Gガンダム x ドラゴンボール http://jp.youtube.com/watch?v=pxQx5Lmjyqo これは誰なんだろう・・・。 ★★★ ■頭文字DTo Heart2 http://jp.youtube.com/watch?v=RWZ9Wawdz_k いちおう貼っておく・・・。 ★★ ■美少女戦士アレンビー NOBELL STARS http://jp.youtube.com/watch?v=axm1Ye7P6MY これは、アレンビーがヒロインと誤解する良マッドだ・・・。 ★★★ ■仮面ライダーAZIO http://jp.youtube.com/watch?v=oFoeT_dzLH0 こんなに行きすぎアニメだったか・・・。 ★★ ■【MAD】 不思議の海のナディア 「THE FORCE」 http://jp.youtube.com/watch?v=DuN_KOMMWE0 愛だな、これは・・・。こんなに面白いアニメだったか・・・。 ★★★★ ■【MAD】ふしぎの海の誓い http://jp.youtube.com/watch?v=wQU_4RN1ObA 大体、マッドの出来を見ると、その作品のレベルが分かるのだな・・・。 ★★★ ■【MAD】グレンラガン+ブルーウォーター http://jp.youtube.com/watch?v=MN27lh3e0Yk なぜここまで劣化するかが謎である・・・。これを面白いと思っている人はなんと不幸なことか・・・。 ★★ ■サイバーフォーミュラ Gガンダム http://jp.youtube.com/watch?v=WemdDNiEjtA&NR=1 できはそこそこ。 ★★ ■(MAD) セーラームーン - パタリロ! http://jp.youtube.com/watch?v=QO26XJ6AOQM これは実ははじめてみたのだなあ・・・。こんなのあったのか・・・。 ★★ ■【MAD】機動武闘伝Gガンダム「僕であるために」 http://jp.youtube.com/watch?v=nvcrBCkCqRI 個人的に好み。けっこうこういうスローな感じは好き。 ★★★ ■【MAD】創聖のGガンダム「創聖のアクエリオン」 http://jp.youtube.com/watch?v=JfF-x_VtMJ4 これは最近ですね。ちょっと普通すぎるかなあ・・・ ★★ ■【MAD】 ぷちぷり☆ユーシィ 「Princsess Maker」 (曲:フルメタルパニック?ふもっふOP) http://jp.youtube.com/watch?v=WYgfuEc_Zwk プリンセスメーカー。こんなすさまじいプロモは見たことがない・・・。初めての星五つをつけておこう。感動が止まらない。 二分であそこまで持っていくのが、ちょっと、有り得ない才能。 まあいいや、とりあえず星5つで。 ★★★★★ ■【MAD】ムーンライトましまろ http://jp.youtube.com/watch?v=eGs_PcpGUQU あいはつたわった・・・。 ★★★ ■セーラームーン&聖闘士星矢 http://jp.youtubecom./watch?v=WSP-En4UT6I 馬鹿マッドぶりが発揮されていて受ける。 ★★★ ■教皇アーレス http://jp.youtube.com/watch?v=y56Vasz9iaI 馬鹿連投。なんかほっとする。 ★★ ■【MAD】 マリア様がみてる 「MY FRIEND」 (曲:ZARD/マイ フレンド) http://jp.youtube.com/watch?v=uq7McyrdMnI 多少たるさがある・・・。 ★★ ■【MAD】 ToHeart2 【toy memory】 http://jp.youtube.com/watch?v=fS6wq6c6HsY これは出自が不明・・・。 ★★ ■機動武闘天使Kガンダム http://jp.youtube.com/watch?v=dMnNma4EdTw 懐かしい・・・。 ★★ ■[HUNTER×HUNTER] FLYING IN THE SKY(MAD) http://jp.youtube.com/watch?v=1WWWBfdc-XM 音楽とは合っている。 ★★★ ■【MAD】 ラーゼフォン 「Cry」 (曲 杏里/悲しみがとまらない) http://jp.youtube.com/watch?v=P5Xqo5lzzUI この流れで見ると、見劣りするから不思議だ・・・。 ★★ ■【MAD】 R.O.D MAM (曲:FLYING IN THE SKY/機動武闘伝GガンダムOP) http://jp.youtube.com/watch?v=_eiAqYm2sGM この曲を乗せて、耐えられるアニメってなかなかないんですね・・・。 というか、これは誰だ? すごいんだけど・・・。 ★★★ ととりあえずピックアップは終わり。 あと、選外を並べておこう。 追記: おっと・・・、金鉱発見! いっこ金鉱が見つかると、そこから芋づる式に行くので、ちょっとフィーバー状態・・・。というわけで探索中なので、待て! 続編!・[AMV] [Nostromo] Magic Pad [MAD] http://jp.youtube.com/watch?v=CWMvYW5Uk7I・To Heart 2 game-op MAD http://jp.youtube.com/watch?v=md1ESU0dzU0・機動戦士ガンダムOO OP1 MAD ギガンティックフォーミュラ http://jp.youtube.com/watch?v=IYCjVa5H7Mw・セーラームーンでギアスOP http://jp.youtube.com/watch?v=hxW7DlgzIM4・走れG http://jp.youtube.com/watch?v=6owvMlECGCs・[MAD] ファイブスター武闘伝 http://jp.youtube.com/watch?v=OgUZ3eR2OzQ・(まっど) ガンダムSEED DESTINY + 聖闘士星矢(ソルジャードリーム)OPMAD http://jp.youtube.com/watch?v=E-DMWPHlL7M・【MAD】ガンダム00 聖闘士星矢「ペガサス幻想」SE入り http://jp.youtube.com/watch?v=mvugyvBWAJw・(まっど) ガンダムSEED DESTINY + マジンガーZOPMAD http://jp.youtube.com/watch?v=5bT-NUn5xn8・(まっど)ガンダムSEED DESTINY + おじゃ魔女ドレミ♪OPMAD http://jp.youtube.com/watch?v=nEy0-5G9q6M・(まっど) ガンダムSEED DESTINY + シャーマンキングOPMAD http://jp.youtube.com/watch?v=Km8OwhA7OAA 第一弾はこちら YouTubeで見れる、黄金期のマッドビデオ 第二弾はこちら YouTubeで見れる、黄金期のマッドビデオ2 いいmいm
December 25, 2007
コメント(0)
-
現実を支配しはじめるゲーム
いつの頃からか、たぶんファミコン全盛期のころだと思うのだが、ファミコンの優秀なプレイヤーを軍事利用するというフィクションを見たことがある。 ファミコン大会が開かれ、その優秀者が軍のヘリコプターを遠隔で操作する。 今にしてみれば、なるほど、米軍の無人機などはそうじゃないかと思えてしまうのだが、当時はその発想が斬新だった気がする。 あー、そうか、ゲームはいつか現実に組み込まれるのか、わたしはそう思った。 小学生のわたしには、ありそうな未来に見えた。 しかし、どうも、状況は逆のようである。 これに気付くのはしばらく時間がかかったのだけど、どうも事実のようだ。 考えてみれば、至極当然な帰結であって、なにも化け物じみた事実は一つもない。 ゲームが現実を組み伏せる。 というか、シミュレーションが現実の前に存在するという、当たり前のことなのだが、これを説明するのは難しい。しかも、これは誰も語っていないことだから、説明のしように困る。 wccfというゲームがあって、これはサッカーのゲームである。 正確には、ワールド・クラブ・チャンピオン・フットボールであり、セガから出ている業務用のサッカーゲームである。ゲームセンター配置される大型のゲーム機であり、人気を博している。 このゲームは、監督となってクラブを率いるというもので、欧州リーグの選手たちがカードとして配布される。そのカードを盤面に配置すると、それに従ってゲーム中のサッカーゲームが展開されるという内容である。 わたしはこのゲーム機の出始めの頃から、wccfに親しんだ筋であるが、持っている選手カードの特性に合わせてフォーメーションを考えたり、連携を考えたり、自分の好きな選手をひいきしたりして、このゲームに多くのお金をつぎ込んだ。 このゲームは、非常にタイトなバランスをしていて、カードを置く位置が5ミリ違うと、全く違う結果になったりした。 たとえばアルメイダとサネッティーというすさまじくマニアックなダブルボランチを組んだのだが、本来であれば中盤の底で、完璧な仕事をしてくれるこの二人も、ちょっとでもその間隔がずれると、その中央を抜かれてしまう。 わたしのチームはボランチの構成がかなり異質なチームだったので、ここが抜かれてしまうと、あとは相手の成すがままにゴールを許すことになる。反対にここで攻撃を止めれば、そこから、こちらの攻撃が始まる。トッティーの出番だ。 わたしは、守備の仕方は完全にそのゲームで体得したのだけど、どうしても攻撃の仕方が分からなかった。能力の強いカードを配置し、エースストライカーを配する。それでも、このゲームでは容易に点を取ることができず、かなり悩んだ。 そこで、わたしは、サッカー誌を買い漁り、ヨーロッパのチームがどういうフォーメーションをしており、どんな選手が活躍しているのかを調べるようになった。わたしがよく買ったのはカルチョというイタリアサッカーリーグ、セリエAの雑誌である。 そこには最新のサッカー事情が書かれ、そしてかなり精密なフォーメーション分析、そして各選手の丁寧なインタビューが何十ページにも渡って掲載されていた。 いまだに全盛期がいつなのか分からないほどの活躍を続けるカカなどは毎月のようにインタビューが掲載されていた。 わたしは夢中になった。 わたしにとってカカは、カズよりも近しい存在である。 そして、わたしはカカのカードが欲しくて欲しくてしかたなかった。 もちろん、大活躍をしていたトッティーも大好きだったのだけど。 しかし、それを続けるうち、わたしはヨーロッパのサッカー選手をほとんど覚えてしまったのである。 たとえば、最優秀なディフェンダーは誰かといわれれば、カンナバーロとネスタを挙げるだろう。なんたって彼らはDF能力が20(このゲームでの最高の能力)だ。スタムは19、サムエルが18。 わたしは、テュラムも好きだ。 彼はDFが18もあって、それでいてスピードが16もある。 理想的なサイドバックだ。 ネドベド、シェフチェンコ、ザンブロッタ。 わたしのチームを彩った選手の枚挙は尽きない。 この前のクラブワールドカップも、ACミランの選手は全部、そらで挙げられるほどだった。ジラルディーノ、インザーギ、セードルフ、カカ、アンブロジーニ、ピルロ、ガットゥーゾ、ヤンクロスキー、ネスタ、カラーゼ、オッド。 いつの間にシミッチはセンターDFから落ちたんだろと思うほど。 わたしは、どれほどジラルディーノのインタビューを読んだだろう? カカは毎月のように読んだ。 わたしがファンである浦和はともかく、今季優勝した鹿島は全選手を挙げる自信はまったくない。 そして、このわたしが読んでいたカルチョという雑誌は、実はセガが作っている雑誌だったのだ。イタリアの著名な週間雑誌スポルティーボと協力して、日本のwccfオタクのために作られた雑誌だったのだ。 これに気付いたときの衝撃は、なかなか言葉にしにくい。 気付くと、日本の欧州サッカー雑誌はセガからなんらかの広告料を受けて、wccfオタク向けに編集されていた。 詳細なフォーメーション、各選手のインタビュー、すばらしいクラブのドラマ。 中でも忘れられないのは、インテルのモラッティーオーナーの記事である。 イタリアクラブのオーナーとは何かを見事にえぐった記事だった。 これは衝撃を受けた。 タイトルは今でも憶えている。 1000の資金、100の選手、10のシーズン、1のタイトル。 (資金がどういう単位だったかは忘れた) インテルが10年間つぎ込んできた厖大な労力を費やして、ようやっとコッパイタリアカップというマイナーなタイトルを取れたという、そのファンとオーナーの姿を書いた話だ。 現在、インテルはセリエA最強のクラブとして君臨しているし、最高の選手を擁していることは疑う余地がないのだが、この記事は、そのどん底で書かれた記事だった。 わたしは、ここで、振り返るのだ。 わたしにとってサッカーとはなんだろう? wccfのことなのだろうか? わたしは今でもサッカーがとても好きだし、それは浦和ファンだということもあって、熱心にサッカーを見ている。しかし、わたしの源流を振り返れば、わたしにとってサッカーはwccfから始まったのだ。 そして日本のサッカー誌はwccfを中心に回っている。(ここで、マネーボールを想起する人はあるだろうが、その話は、それを想起した人々に託すことにしよう) それだけではない。 これは日本だけで起こっている事象である。 しかし、カルチョにはイタリアサッカー選手のあいだで、日本のゲームが根付いていることを知りびっくりする。これは、ウイニング・イレブンというコナミのゲームなのだが、セリエAの選手は、これをよくやるらしい。 合宿中はプレイステーションをやっていたよ、などという言葉がフランクに出てくるのだが、これはウイニング・イレブンのことをさす。 トッティーが、サッカーゲームをしているのである。 これは何かとしばらく考えていたことがあったのだが、たぶん、イメージトレーニングの一種だと気付いて納得した。 たとえばトッティーはフォワードなのだが、彼はディフェンダーをプレーしたことはたぶんない。そうするとディフェンダーの経験が全く乏しいことになるのだが、ゲームでプレイすることは可能だ。 もし、現実にディフェンダーを体験したいとすれば、とても多大なコストが掛かる。 そこで、トッティーはウィニング・イレブンでその仮想体験をするのである。 一見遊んでいるように見えるのだが、これはイメージトレーニングなのだ。 そして、それに使われているのはゲームなのである。 昨今、PS3になり、グランツーリスモが実際の自動車会社の設計図データをもらってモデリングしているという話を聞く。シム・シティSocietiesのスポンサーが石油会社だとびびる。 いつの間にかゲームは優秀な、ある概念を伝える媒体となってしまった。 たとえばサッカーの面白さを伝える媒体にwccfがなったように、そして、wccfが日本のヨーロッパサッカーの認識を占拠してしまったように。 この流れに誰も気付いていないのはなぜだろう? ちなみに、ニコニコ動画はなにも変えてない。 Youtubeもね。 wccfはサッカーを支配してしまっているのだ。 これが不思議だ。 有り得ない夢を見るのがゲームの特権だった気がする。 でも今は現実を伝える、道具になりつつあると思い、納得するのだ。 シリアスゲームなどとのたまう暇があれば、wccfにはまってみてはどうか。
December 24, 2007
コメント(4)
-
安倍首相は、サブプライム辞職であった可能性を検討する
安倍首相の辞意表明を受けて、あちこちから混乱気味な論が林立している。 わたしも、もうひとつ新たな説を加えてみようと思う。 それは、サブプライム・ショックを見限ったという説だ。 これは、安倍首相が自分の役割は終わったことを悟って、賢明な政治判断をしたという説である。 経済ニュースを熱心に追っている人間には、この辞任があまりにも、経済界の大激震と重なりすぎていることが気になる。 米国は、9/7の雇用統計ショックで、完全な景気減速に陥ることが明白になった。 これまで、円高を円キャリーの巻き戻しとしていた論も、きれいさっぱり消え去り、完全なドルの独歩安局面に入ったことが確認されつつある。 長期的なドル安局面は、米国の長期的な経済破綻への転落に直行し、もうサブプライム問題で米国債権を買う諸外国はなくなるだろうから、米国経済を支える根拠は何一つなくなることを意味する。 ジ・エンドである。 これ以外に状況を説明する言葉は見つからない。 各中央銀行の資金供給額を見れば、その地域の債券市場が受けた打撃は明らかで、ほとんど無風だったのは、ロンドンと東京である。 翻って、大打撃を受けたのは、米国と欧州である。 この辺は、前回のエントリーを参照していただきたい。 ■今、ぼくらは基軸通貨ドルの終焉を見ているのかも知れない 週末の雇用統計ショックは週をまたいで持ち越され、日本に到着したのは、9/10。 ロイターは緊急日本株特集と銘打って、大激変を分析し始める。 よくウォッチをしている人にとってみれば、「目の色が変わった」と映っただろう。 明らかに、意識のスイッチが切り替わった。 特集の記事を並べてみよう。 緊急日本株特集:米経済減速による日本株調整は避けられず http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-27804620070910 緊急日本株特集:海外勢の大口売りはヤマ越す、短期需給に改善の兆し http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-27802920070910 緊急日本株特集:米国内需に懸念、米株市場は新興国需要の底堅さ期待 http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-27802820070910 なぜ、ロイターがこのような記事を並べているのか不明なのだが、ロイターは日別にニュースを表示できるので、見比べて欲しい。 9/11 http://jp.reuters.com/news/archive/businessNews?date=09112007 9/10 http://jp.reuters.com/news/archive/businessNews?date=09102007 9/8 http://jp.reuters.com/news/archive/businessNews?date=09082007 9/7 http://jp.reuters.com/news/archive/businessNews?date=09072007 (注:9/9は記事がないので省略) じわじわとやってきていたのが、突然論調が変わったのが9/10からなのである。 雇用統計ショックから、米国がブラックマンデーを超える大激変に見舞われる可能性があることが現実味を帯び始めている。 わたしは、たぶん一生に一度見れるかどうかの経済ショックだと思っている。 わたしの編集は偏向編集である可能性があるので、ロイターでじっくり検討して欲しい。 ただし「誰が何を言っているか」をよく見たほうがよい。 人は自分の都合よいように発言するに決まっているからだ。 そして「誰が何をやっているか」をよく見るといい。 お金を動かす手の動きは非常に正直だ。 ■運命の9/7、そして9/10 9/7に大激変が起こり、9/10にほぼ論調が固まり始めたと見て取れることはすでに述べたとおりである。 9/11はなんの関係もない。 ただの数字である。まあ、象徴的な数字だけど。 そして、9/12だったのは、なにか不思議なことがあるだろうか? ■首相の辞意表明、タイミングはいかがなものか=自民幹事長 http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-27854120070912 麻生幹事長によると、安倍首相の辞意を聞いたのは10日午後の自民党役員会の終了後で、この場で話を聞いたのは、麻生幹事長1人だったという。麻生幹事長は「3日間、決意は変わらなかったということだろう」と語った。 タイミングは9/10である。 しかも絶好の引き金があった。 安倍首相、辞任を表明 http://jp.reuters.com/article/businessNews/idJPJAPAN-27846520070912 首相はその理由として、テロとの戦いの継続を新しい首相の下で目指すべきだと判断したとし、自らけじめをつけることで局面を打開することが必要との考えを示した。 NHKが記者会見に先立って報じたところによると、小沢一郎民主党代表との党首会談を断られ、安倍首相は辞任する決意を固めたという。 これを言い訳だという人もあるが、首相の言葉であるし、塩野七生にうそがつけない人と太鼓判を受けており、思ったことは正直に言うという部分だけはわたしは安倍さんを信用しているので、これは真実であろうと思う。 つまり、小沢民主党との外交方針の違いのこじれが絶望的であり、自分には絶対に解消できないでないであろうと信じるに足る確証を得たので辞めるということであると思えるのだ。 外交方針は、 小沢外交 国連憲章・憲法・日米安保の原理原則を堅持、もしくはその調和。 日中米の正三角形。 麻生外交 自由と繁栄の弧 → 基本的にユーラシアへの経済援助により自由と繁栄をもたらす方針。 → 諸外国にこの経済援助政策に乗れ、という方針。 → シーレーン確保と、環太平洋とユーラシアの緊張緩和が目的。 安倍外交 テロとの戦い、日印豪米同盟。 となっており、どうも米国もテロとの戦い、つまり小泉=ブッシュ機軸の方針を維持できないと考えたのであろうと思う。安倍首相はタカ派的な外交を政治信念にしており、それが有効な局面ではなくなり、米国型経済への改革が米国の自沈で崩壊したことを悟ったのであろうと思われるのである。 ある意味、きっぱりとした判断だったような気がする。 ・一刻も油断を許されない全世界的な経済構造の大変革が始まった。 ・世界の多極化局面への移行が決定的になり、小泉路線は完全否定された。 ・自民党内も小泉路線からの脱却を目指しており、極端な米国寄りはやめる方向に移行しつつある。 ・テロ特措法の更新期限が迫り、こちらも一刻も時間がない。 ・そして、小沢民主は、日米関係がダメージを受けようと、自らの政治信念を貫く決心でいる。 などなど。 安倍首相は、情勢をしっかり読んでいるのではないかと思えてくる。 そして、こう俯瞰してみると、安倍首相は孤立無援どころの話でも、四面楚歌どころの話ではない。 何の陰謀も、やましいことも、打算もない。 時代が変わったことをたぶん悟ったのだと思う。 そして、それが確定したのが、9/7であり、9/10にそれがわかり、9/11は避け、9/12にしたのではないか。 追記: ひどい論調が多いので、新自由主義に対しては、ちゃんとケアしておこうと思う。 ■安倍晋三的なものの敗北と日本の政治土壌 賢い人だと思うから、もっと広い視野を持って欲しいと思うのだ。
September 12, 2007
コメント(0)
-
今、ぼくらは基軸通貨ドルの終焉を見ているのかも知れない
塩野七生が、歴史とは戦争を書くことが多いと言ったが、わたしは歴史を書く歴史家は戦争が好きなのではなく、歴史がダイナミックに動く転換期が大好きなのだと思う。 ただでさえ歴史が好きな上に、その大転換点だったら、とてつもなく胸が沸く。 しかも、それが、自分が生きている、今、このとき、本日、8月17日金曜日、日本時間午後9時だったら? 多くの人が想像している通り、わたしは血沸き肉踊る興奮の中にある。 ロイターのWebページは世界中の大激動を伝えていて、世界中の専門家たちがいっせいにブログで生の声を聞かせてくれ、ボタンを押すたびに新たなRSSがわたしに更新を告げる。 日本の、クーラーの効いた、暗くした部屋で、ジュリー・アンド・マリーを聞きながら、これを書いている。 わたしが見ているのは、劇的なクレジット危機。 7月の末のサブプライム問題より始まった、マネーの大激流である。 第二次世界大戦以前の大転換は戦争や革命によって起こったが、21世紀の大転換はグローバル市場において、全くの無血で起こるようだ。 これは、歴史家の新しい教訓になるかもしれない。 実は、わたしは分家の方で、サブプライム問題を書いている。 ■夏休みのサブプライム観察日誌 ここでの結論は、 まあ、良くも悪くも、一生に一度みれるかどうかの大破綻をおそらくわたしは見ているのだろう。わたしにはできることはないし、プレイヤーたちがなんとかどうにかしてくれることを祈るしかない。 これを教訓にどう生きるかを、考えるしかない。 という言葉に集約されている。 サブプライム問題は米国の経済の崩壊であり、致命的なモラルハザードによってそれは起こった。 あ、そうそう、念のために言っておくと、わたしの資産(ほとんどないに等しい額だが)は全額ポンドの外貨貯金となっており(単純に英国好きなだけだったりするのだが)、たぶん最高値から20%ぐらい円換算で価値が下がるはずだ。 なので、わたしも被害を受けているといってもよいかも知れないし、もし利害があるのだとすれば、急激な円高が進んでいる現在を喜んでいるはずはない。 しかし、この激動を嬉々と見つめずにいられようか。 たった今、全世界の金融商品からマネーが逃げ出し、安全な債権に向かっている。 全世界的に株式は下落し、日本でロイターを見ている限りは、全通貨が下落しているように見える。エコノミストの指摘では円キャリー取引の手仕舞いで急激な円高が進んでいるのが原因で、円は一日に2円というすさまじい勢いで高くなっている。 わたしは、しばらく、この状況でどこにマネーは流れているのだろうか、とぴんぼけした感想を抱いていた。 円とスイスフラン以外がすべて下落しているのであれば流れているところは1つしかない。円に流れているのである。急激な勢いで、すさまじい勢いで円に資金が流入しており、円でしばらく投資先を見つける間、休息して、またどこかに流れていくのである。 7月末からの資金の流れを見ていると、次の二件のロイターが象徴しているような気がしている。 ■将来的に欧米で商業銀行の買収も検討=三菱東京UFJ銀 これは8月16日の記事。つまり昨日。この金融危機において、三菱東京UFJは大打撃を受けた欧米の銀行の物色を始めており、アジアを主戦場とする意思を固めている。これは非常に簡単で、顧客=欧米、投資先=アジアという方針を固めたということだ。 ■米ブラックストーン、インドや日本での投資に関心 ちなみに、ブラックストーンは、つい最近IPOしたばかりのファンドであり、中国政府から30億ドルの投資を受けていたりする。 四半期決算は絶好調。 ■米ブラックストーンの第2四半期は増益、買収や不動産売却が寄与 崩壊寸前の米国市場からかなりぎりぎりで逃げることに成功した。 ■米ブラックストーン、エクイティ・オフィスの不動産大半売却か (ロイター) ブラックストーンは、インドの急成長小規模企業に投資するらしく、日本ではたしか不動産に投資する予定だった気がする(未確認情報)。 それ以外の多数の有力(察しのいい)資本が、米国から資金を引き上げ、アジアに資金を投入しようとしている。リスク債に投じられていた資金が、いますさまじい勢いで円に逃避し、休息し、アジアへ向かおうとしている。 なぜ、今、円に逃避しているのであろうか? それは、少し考えればよく分かる。 今、もっとも安全な通貨が円だからだ。 円キャリーの巻き戻しなどと、ぴんぼけした感想を抱いていたわたしは頭をハンマーで殴られた気分になった。 円建てで借りていたのは、円の金利が低かったからではない。 円がもっとも安全だったからだ。そして、その円の資産を生かす投資先が円建てでは見つからなかったので、キャリーされて外国の高利債に投資されていたのだ。 そして、全世界的な金融不安とともに、円の元にマネーが戻ってきた。 それに気づかせてくれたのはこのエントリー。 ■[経済] 株価はフラクタルだ いつの間にか「暫定」基軸通貨は円になっていたのだ。 しかし、日本は米国と、なんと言うか「べったりな」同盟関係にあり、為替政策はドルペッグと言ってよいほど二人三脚状況だったので、ドル=円同盟が基軸通貨として機能していたのだと思う。 しかし、米国経済の崩壊の兆しが見え始め、新興国市場が急速に立ち上がり、アジア金融危機などを経て、ユーラシアがドルを嫌い始めた。その経緯は、次の2エントリーに詳しい。 ■ドルの基軸通貨からの転落への準備を怠るな ■円・元・ドル・ユーロの同時代史 最終回~基軸通貨の危機 特に、後者はこれまでの通貨の流れを詳細に追っているので非常に参考になると思う。 この2つのエントリーが告げているのは、日米同盟にアジア通貨を組み込んだアジア共通通貨単位に基軸通貨は移るということである。ストーリーはこうだ。 アジアはアジア金融危機によりドルを膨大に積み上げた。 だから、アジアはドルを投売りすることはない。 ただ、ドルの政策に強権を振るわれ、揺さぶられ続けるのは我慢しがたい。 なので、製造業で結びつきが強くなったアジア経済圏にアメリカを組み込んで、ゆるい金融同盟を作ろう。 基軸通貨は歴史のいたずらなのかそうでないのか、ポンド→ドル→円と移り、旧宗主国からその植民地へと移動し、英米日同盟にアジアを含めようとしている。 もし、歴史に法則があるのであれば、ロンドン・ニューヨーク・東京市場はその後も主要マーケットであり続け、次の主役はアジアであるが、それによって主役を譲った者が一方的な衰退をするわけではない、と読むことも出来る。 直近では、激しい乱高下でなかなか先を見通すことは難しくなっている。 しかし、確実にやってくるのはドルの一極支配の緩やかな崩壊であり、強烈な同盟国である日本の円を媒介としたアジア経済圏の勃興であり、世界の多極化である。 ドルの崩壊は免れない。 ■綻目前、サブプライムの猶予は3カ月 / SAFETY JAPAN [大前 研一氏] / 日経BP社 しかし、致命的な崩壊が起こるはるか以前に、暫定的な経済同盟がすでに日本を媒介として出来上がってしまっており、運命共同体である以上、米国が切り捨てられるという事態には陥らないという歴史のようだ。 緩やかな調整が行われ、主役がアジアにシフトしていくのだろう。 それが、はからずも90年代初頭の日米の経済戦争に端を発しているようで面白い。 ■円・元・ドル・ユーロの同時代史 第38回~為替を武器にしたクリントン政権 90年春に始まったいわゆるバブルの崩壊を受け、当時は日本経済が「失われた10年」へ向け下降を続けていた時期だ。円高にならなければならない経済ファンダメンタルズはなかった。 にもかかわらず、市場参加者の総意によって作り出された円高環境は、マサチューセッツアベニュー・モデルが説いていたように、日本経済の構造を変えてしまった。輸出採算を悪化させた企業が挙って(こぞって)東南アジア諸国へ、次いで中国へ盛んな直接投資を始め、製造拠点を移動させ始めたからである。 このようにクリントン政権に徹底的な攻撃を浴びせられた後、「円の国際化」、「円の自立」、「円圏の確立」といった方向が日本国内で盛んに論じられ始めたのは当然の成り行きだったと言わねばならない。ただし威勢のよかったこれら議論は、結論を先に言えば、ただの議論で終わってしまった。 分かった。 ブッシュがどんなに致命的な失敗を繰り返しても、クリントンの勝ちは馬鹿でかかった。 米国をぶっ壊れない国にしてしまった。 たぶん、そういうことだ。 追記: このドルの一極体制の崩壊は、かなり多くの識者が予測していたようである。 ■基軸通貨でなくなるドル 2005年3月15日 田中 宇 http://tanakanews.com/f0315dollar.htm ただ、そこへソフトランディングする方法を模索していて、結局、サブプライムを震源としたハードランディングで、決着がつくということになる。 この記事を読んだときは、そんなばかなと思ったのだけど・・・。
August 17, 2007
コメント(0)
-
ちかくてとおい旅ととおくてちかい旅
趣味の都合で、北関東一円を周る旅をする。 埼玉から、群馬県の伊勢崎に出て、太田に出て、そこから足利(栃木県)を経由して、久喜に出て(埼玉県)、小山に行き(茨城県)、また戻ってきて、越谷(埼玉県)が最終目的地。 そこから、帰宅。 日帰りの旅である。 地図を見れば分かるが、北関東をぐるっと回る。 駅から各目的地まで、往復1時間は歩くから、恐ろしいほど時間がかかる。 バスはない。 企画をしたときは、熱でもあるんじゃないかと思ったのほど、気の狂った旅程なのだが、案外満足して、脚をぼうにして帰ってきた。 朝十時に出て、帰宅は終電。 ちかいように見えてとおい旅である。 やってみるとわかるけれど、気が遠くなる旅である。 ショートカットする方法はない。 どんなに努力しても、旅程は短くならない。 普通は耐え難い。 わたしの両親は7泊でイタリアを旅行し、わたしにさんざんに土産話を聞かせてくれた。 これは以前書いたので、詳細はそちらを参考にしてほしいのだが、その中で、面白い気付きがあった。「そういえば、日本に旅行に来てた外国人がうれしそうに言うんだって」 という話が出た。「一昨日北海道から着きました。昨日の日光もいいけど、浅草もいいですよね! 明日は瀬戸内海です」 常識的な日本人だったら、「おいおい、その調子で、京都・奈良・東京・大阪・九州まで見るのか!?」 と感じるだろう(笑)。しかし、これは逆転すれば七泊のイタリア旅行、わたしの読んだジオグラフィックの記事が正しければ、最低二年住まないとナポリの良さは分からないとのことで、母が聞いた話をが本当であるならば、トスカーナの良さはよそ者が一生住んでも分からないらしい。 7泊でイタリアを回るだなんて、すごいショートカット(笑)という話なのだが、よくいう海外旅行は、超高速で走り回る旅である。そういう旅もあるだろうと思う。 とおいようでちかい旅。 昔だったら、イタリアなんて船しかなかったからとんでもない旅だったのだが、技術の進歩はふつうのおじちゃん、おばちゃんが気軽に出来る旅にしてくれた。 わたしの妹は、卒業旅行でパリ・ロンドン・ローマに行ったらしい。 これはさすがにないだろー(笑)という話なのだが、お金を掛けて航空機を乗り継げば不可能ではないことはよくわかる。 この二つの旅を見比べてみると、大きく違うのは移動速度だ。 さまざまなところを周ることは変わらない。 方や電車とバスであり、方や航空機を利用している。 たとえばわたしが、北関東をヘリコプターで回ってれば、たぶん夕食には間に合う時間に帰ってこれただろう。しかし、そんなお金はわたしにはないし、第一、ヘリコプターが着陸する場所が整えられているわけではない。 現代という世界を俯瞰してみると、ちかくてとおい世界と、とおくてちかい世界が混在していることが分かる。 交通手段が発達した結果、世界の距離はまだら模様となった。 お金さえあればニューヨークは近いが、お金がどんなにあっても小笠原諸島は遠い。 御蔵島は天候が悪いと入れてもくれないのだけど。(御蔵島でググッてね) どんなに努力しても、どんなにお金をつぎ込んでも、そのとおさがちかくならない場所というのはどうしてもある。 どんなに走っても、どんなに疲れても、それは徒労である場所がある。 たとえば、伊勢崎から太田までは、実は1時間に一本しか電車がなかったりするので距離に比べてすさまじく遠いのだが、タクシーを使うならともかく、それ以外の方法で、電車より早く移動する方法はない。 太田からは、特急が走っているので、700円払って久喜まで気楽な旅をすればよい。 なので、わたしがしたような旅をしなければならないのであれば(そんな人はいないだろうが)、すさまじく地道でながいながい気の遠くなるほど長い旅をしなければならないことを飲み込まなければいけない。 まっくら森のようにちかくてとおいのだ。 それを飲むこむ覚悟がなければ、こういう旅に出ることは、あまりお勧めしない。 開発の分野にも、ちかくてとおい分野ととおくてちかい分野がある。 前者は基礎研究に分類される世界であって、後者は実装方法の模索にちかい。 前者は研究所の仕事で、後者はマーケティングの仕事である。 一見すると、後者はたくさんの距離を移動しているから、いかにもえらいたくさんの仕事をしているように見える。しかし、7泊のイタリア旅行を思い出してもらえばわかるとおり、移動距離が長いことはとおいこととイコールではない。逆に言うと前者はとてつもなく狭い世界を移動しているように見えるが、ツアー旅行よりは果てしなく冒険に満ちた、苦難続きの世界である。 わたしははやい仕事も、おそい仕事も経験したことがあるけれど、わたしの性格はどうもおそい仕事に合っているようだ。 はやい仕事は、お金と人数を持って、力技で勝つことができる。 おそい仕事は、どんなにお金を注ぎ込んでも、たったひとりのキチガイのながいながい旅に勝つことはない。 青色ダイオードを作ったのは、赤も、緑も、黄緑もあったダイオードを青くするためだけに世界中の研究者が競争していたのだが、結局成し遂げたのは一人の奇人であったことは著名な事実だ。 社長が、このダイオードを青くしろ、青がいいと言って、すぐに青くなるわけではない(笑)。マーケットが青を求めても、青くなるわけではない。 血まみれになっても、青くはならない。 泣いても、叫んでも、何兆円を積んでも青くはならない。 それほど、基礎研究の世界は残酷だ。 それは徒労である。 盛大な無駄だ。 この両者はまったく流儀が違うのだ。 なぜか最近はマーケ屋や、ブローカーばかりが多くなって来たせいか、地道な努力をしている人が非難されやすくて、つらい。 それでこんな文章を書いているのだけど。 さて、ちかくてとおい旅をするには、実は分かりやすいコツがある。 もちろん、気長な性格である必要がある。 上手くいかなくても、諦めない粘り強さが必要である。 遠回りをいとわないことも重要かも知れない。 その上で、こういう旅を楽しむときは、ながくながく長い旅であることを覚悟して、それから、一石二鳥、三鳥、四鳥、五鳥を狙っていく、用意周到さがたぶん損をしないコツである。 たとえば、大型書店に出る用事があったとしよう。これは自分が単に行きたいだけであるから、別にいつ行ってもいいはずである。だから、行きたいと思っても、衝動的に行動するのではなく、「あー、新宿でなくちゃいけないのか・・・。本屋だけのために出るのもなあ・・・」 という、一見怠惰な見える理由で先延ばしにするのである。 そのうち、「あー、映画見に行きたいなあ・・・、でも、映画と本屋のためだけに出るのもなあ」 と、また先延ばしにする。 そして、ついに、「あー、旨いラーメン食いたいなあ・・・。よし、じゃあ、ラーメンと映画と本屋のために新宿でるか!」 という感じでやるのである。 これは何が重要かというと、やりたいことを常日頃からずっとストックしておいて、いくつかの条件が重なるまで実行に移さない、ということが重要なのだ。 たとえば、わたしは今、イタリアに行きたいか、といわれれば、さすがに行きたい。 でも充分に今すぐ行きたいか、と言われれば、別に3年後でもよい。 問題は、その3年間、イタリアに行きたい気持ちを、同じ温度のままで、ずっと保持し続けることが出来るか、その熱意を持ち続けることができるか、ということなのだと思う。気長に20年間保持し続けることが出来るか、という事だと思う。 チャンスが来るまで、ずっと待てるか、ということなのだと思う。 もし、それが出来るのであれば、そのための準備を20年間掛けて用意周到にすることが出来る。 本を読み、イタリア語を覚え、出来ればイタリア人の友人を作っておく。 とてつもなく極端な例なのであれなのだが(笑)、その上で、イタリアに一ヶ月間滞在したとしたら、どれだけ有意義な時間が作れるだろうか。もし都合がつくなら一年間いてもいいし、何なら永住してもよい。 少なくともパック旅行の7泊よりは楽しいはずだ。 もちろん、それだけの努力を払ったからその成果を受け取る資格があるだけであって、べつにパック旅行を否定したいわけではない。単純に、この両者は流儀が違う、と言いたいのである。 わたしは、ちなみに北関東を旅しながら、 原稿を書いていた(わたしは移動中は筆が進むのである)、 こもりっきりだったの運動がしたかった、 ずっと旅行にいっていなかったので旅行に行きたかった、 定期的に発生する「特急乗りたい病」を解消したかった、 新しいMP3プレイヤーの耐久テストをしたかった、 刺激が欲しかった、 というようなことをついでにやった。 やりたいことのストックリストを見ながら、それが揃う条件を探しながら、タイミングを計っていたのである。これがもし、目的を達成するためだけにやらなければならないのであったとしたら、ぜったいに耐えられないであろう。 わたしは越谷で道を間違えて2時間ぐらい歩いて数駅はなれた駅にやっと辿り着いた。 そういうことがひんぱんに起こりうる、長い旅をするのであれば、そういうことが起こっても耐えうる大量のモチベーションが必要だ。 たぶん、みんな、やりたいことはとてもたくさん常に生まれていると思う。 もし、つぎつぎと新しいものに飛びつく性格であれば、ちかくてとおい旅は向かないかも知れない。とおくてちかい旅がお勧めだ。それも楽しい。 ちかいととおいを冷静に判断した方がいい。 でも、ずっとその熱さを持ち続ける自信があるのであれば、辛抱強く待ってみてはどうだろうか。チャンスをつかみさえすれば、どんなにつらくて長い旅でもきっと耐えられると思う。 そう、一石五鳥ぐらいの旅であれば。 【参考エントリー】 Life is beautiful: 私がMBAを取得することにした10の理由 この旅が、よい旅である事を、祈りつつ。 これを読む多くの人が、よいお手本をしっかりとみて、そうかと思うことを祈りつつ。
August 3, 2007
コメント(0)
-
畳む思考と、はてなスターにみる畳まない思考 → 熟考中
たぶん、この話は広い意味でのPtoPに繋がってくると思うのですが、なんとなく本質はここだと目星がついたのと、結論は当分出なそうなので、熟考がてら。 何か複雑なものを把握するとき、もしくは上手く動かすとき、力技的な方法を使うと失敗するケースがある。 たとえば、試験範囲を丸暗記する方法。 たとえば、盲目的に書きはじめから小説を書いてしまう方法。 たとえば、網羅的な引継ぎ資料を作ってしまう方法。 みんな何らかの経験があって、たぶん失敗があって、こういう方法に移る前に、ちょっと熟考して、それから筋道がよさそうだったら始めるという事を多かれ少なかれ、やっている気がする。 たとえば年金問題はどう解決したらいいだろうか。 たぶん、イキナリ入力を始める人はいないだろう。 力技で勢いだけでやってしまうと、膨大なデータと面と向かわなければいけない。 これは何の工夫もない人海戦術だ。 では、年金問題はどういうやり方で動き始めているかというと、ご存知の通り、サンプルを取ってみて、大体どれぐらいミスがあって、どの辺に問題があるかを調べて、それからやり方を検討している。 これは段階的な人海戦術とでも呼べばいいのか。 とりあえずぶつかってみて、威力偵察のように状況を把握し、それから一時撤退し、綿密な作戦を立案する。 よく、とりあえず飛び込んでみろという言葉があるが、この言葉が意味するのは、全部人海戦術でやれという意味ではなく、威力偵察しろ、という意味だとわたしはとっている。IT系の人たちはたぶん、それぐらい分かっているのであまり多くは語らないのだが、その根底にあるのは、「飛び込んでみないと、どうエレガントなコードを書いていいかわからない」 という事だと思うのだ。 わたしはこの言葉は、一般的な人には分かりにくいと思うので、言葉を置き換えてみる。 つまり、どう畳んだらよいのか分からない、と。 エレガントなコードはイキナリ書ける訳ではない。 問題に対処しているうちに、エレガントな解決方法を思いつくのである。 よく、仕事術などで、整理整頓の大切さを説く人がいる。 また逆に整理しない方がよいという言う人もある。 これは両極なので、一概に言えないが、官僚的な仕事を望むなら前者、芸術家的な仕事を望むなら後者。もちろん、両方は極端。これとはまったく別の次元の話が、どうもほんとうなような気がする。 つまり、畳むのである。 畳むには、充分なところまで畳む対象を広げてその形を確かめなければいけない。 ぐちゃぐちゃになった紙を、立方体に固めて紙の塊にすることは整理かも知れないが、畳んでいない。 整理整頓は結果であって、過程ではない。 思考済みであって、思考中ではない。 思考中であれば、部屋一面に洗濯物を広げてしまった方がよい。 思い切ってばっと展開してしまった方がよい。 とにかくあるものを全部広げつくして、仔細に眺め、検討した方がよい。 偏見なく、うんうんと悩んだ方がよい。 それからひとつひとつ畳んでいけばいい。 整理整頓を言う人は、どうもこの展開しきった状態を許さずに、常に整理整頓されていないという感じで言う。 これは、大きな誤解を生む。 そうじゃない、結果として整理整頓するために、雑多に広げつくした状況は必要だと思うのだ。 何が入っているかどうか分からない段ボール箱の2万枚のCDがあってどう整理するだろう。実際に作業をしてみれば分かるけれど、とても広いスペースがないとこれをするのはかなり困難だ。 ダンボールからダンボールに移すのではない。 ダンボールから、広大なスペースに広げて、ダンボールに詰め直すのである。 この辺が欠落していると、ヘンな解決方法ばかり提案するようになる。 そのスペースは要らないというなら、その人は、大きく複雑な情報を扱うことは出来ない人であり、本質的な解決が出来ない人である。 法律の問題を考えていると、この情報をあらゆる段階に移して見て、尺度を変えてみて、マクロを考え、ミクロを考え、それから、結論に畳むという過程を経る。 たとえば、判例などは、問題を仔細まで検討して、最終的に結論をだす。 判決文を読むと、この法学特有のやり方がよく分かると思う。(ひよこの立体商標の判決文がかなり面白いらしいので、それを試してみるとよい) 結論が分かっているようなときでも、とりあえず展開する。 いや、展開せざるおえない構造になっている。 それからすべての事実関係をチェックし、結論を出す。 いきなり、2条3項違反で死刑、なんて結論をだす裁判官は当たり前だけどいない。 まあ、最近は、この手続きを法廷ではやらず膨大な書面でやるのが主流になり始めているのだけど(特許法では書面審理というのだけど、なんというのだろう?)。 だから、言葉尻を取って、何条違反だというのは、あんまり意味がない。 判決は畳んだ結果であって、それには事前に展開するという作業があるからだ。 しかし、判決は、類型化され、以後、「便利に畳まれた」前例として扱われるから面白い。過去の判決文を見せて、説明以上、つまり結論はこれと同じ、でよいから面白い。 非常に効率的である。 勿論、当事者がそれでも争う気があるなら、もう一回展開して再検討するのが、裁判制度である。これも、非常に面白い。 なんか話しすぎた、たぶん言いたいことからかなり離れている。 この畳むという行為が顕著なのは、実際法律の条文だったりする。 エレガントな条文は、物凄い大量の判例やら学説やらを内包して出来ていて、表面どおりに読むと、その畳まれた洗濯物を上手く広げることが出来ない。畳まれたままでは、着ることは出来ないし、自分の一部にすることも出来ない。 条文というのは制度であり、たとえば特許法の職務発明制度は、1条しかない。 組物の意匠の制度も1条しかない。五行しかない。 あ、そうか、書くか。 意匠法8条 同時に使用される二以上の物品であって経済産業省令で定めるもの(以下「組物」という)を構成する物品に係る意匠は、組物全体として統一があるときは、一意匠として出願をし、意匠登録を受けることができる。 これが弁理士試験の意匠法で難題に分類される組物の意匠の条文だ。 なんでこんなに短いのだろう? これは、すさまじい圧縮率でエレガントすぎるほどにエレガントに畳まれているからだ。 難解な文章だなんていわないで欲しい。 これはすさまじくエレガントなのだ。 同じように、民主主義というのは極めてエレガントに畳まれた制度といえる。 ようやっと本題に入ってきたのだが、この辺が今熟考しているところ。 たとえば、全国民がひとつの議場に集まり、議論し尽くすのは不可能であることは想像に難しくない。そこで、選挙という方法で議論を国会議員に「畳み」、国会議員が議論し、法にするのである。 勿論、畳み方はたくさんあると思う。 大統領制がいいという人もあれば、国民投票がいいという人もある。 議論はあっていいし、たくさんの声があるべきだ。 すべての議論は展開されるべきだ。 だけど、どこかで畳み、また議論し、また畳み、そして結論を出す。 今の学校教育があんまりよくないというのは、この畳むという作業をしないからではないか。 畳まれた物を覚えることに注力し、それを広げてみることを許さない。 逆に、反動として、展開することだけに注力するケースもある。 一番重要な畳むということをしないのだ。 それで、その重要性がわかっている反骨者たちは、ネットに向かう、そんな感じだと思っていた。 わたしはネットのサービスとは、畳み方の模索だと思っていた。 先日、はてなスターがリリースされ、それを見て戸惑った。 これは上手く畳んでいるようであって、畳まれるのを拒んでいるようでいて、なんとも言いがたい気持ちになったのだ。 PtoP的な個人間のやりとりに注力するのであれば、これはもはや畳む必要はない。 これはどう発展するのだろう? 畳むのだろうか? 畳まないのだろうか? 最近のトレンドはゆるく畳む。 ある意味、時流をよく読んだ、物凄いたくさんのことを考え付くし、飲み込み、仔細を見つめ、熟考し、そして畳んで出てきたサービスなのだろうと一目見て分かる。 膨大なトラフィックが生まれ、そしてゆるく畳まれるのだろう。 わたしは、その畳む手を見ていたいのだ。 と、わたしも現在膨大に広げて畳んでということをやっている最中なので、横目で眺めつつ。 他のサービスと違って、みていると風流な気分になるから不思議である。 ■はてなスター日記 http://d.hatena.ne.jp/hatenastar/20070712 ■はてなスター http://s.hatena.ne.jp/
July 12, 2007
コメント(0)
-
バックヤードのバックヤードのバックヤードのバックヤードとコピペ
オープンソース系の話をずっと考えていた時期があって、それが特許法と対立していることに悩んでいた時期がある。最近になって、それがぶつかっているのは単にフロントヤードの話なのではないかと思うようになって、なんとなく氷解した気がしてきた。 それと同時に、ではソフトウェア企業はどうこの問題を解決しているのだろうというのが、わたしの素直な現在の疑問だ。 (といいつつも、わたしも大手の子会社で遊び半分でnucleusとかをぐりぐりいじってblogポータル作ったりしてたが。ここでの社内でのやり取りがかなりハードだったので、問題の根深さを実感しているのだ) 多くの人が認識しているとおり、フロントヤードの後ろにはバックヤードがあり、そのバックヤードのバックヤードがあり、さらにそのバックヤードのバックヤードがあり、と、たった一つのフロントヤードには、延々と続くバックヤードがある。 これはたった一人の開発者の深い深い思索の過程と置き換えてもよい。 たとえばディゼルエンジンを想像してみよう。 ディーゼルエンジンは、分解すれば、どのような構造になっているかはすぐに分かる。 材質や細かなディテールは分からないかも知れないが粗悪な模造品であれば、同じようなものを作ることはそんなに難しいことではない。 パーツをレーザで3Dスキャンして、自動旋盤を回すだけである。 これは非常に簡単だ。 製造業でいうところのデッドコピーというのはこういうことをいう。 しかし、よく考えてみれば、ディーゼルエンジンはそのままぽんと出来るわけではない。そこには工場というバックヤードがあり、ここでの生産工程があることによって、製品は生まれてくるのである。 効率的に製品を作る生産ライン、もしかするとそのコピー業者がなんの考えもなくコピーしたシリンダーの形状は、生産性を考慮して設計されているのかも知れない。 あんまり細かく言うときりがないので、簡単に言うが、エンジンの背後には工場というバックヤードがあるのだ。 しかし、よく考えてみれば、工場はそのままぽんと出来るわけではない。そこには会社というバックヤードがあり、ここでの会社組織や、会社文化、経営手法、配されている人材の切磋琢磨など卓越した(卓越していない企業もあろうが)大手企業として営みがあり、ここから工場は生まれてくるのである。 グローバルな大企業、もしかするとコピー業者が何の考えもなくコピーしたシリンダーの形状は、経営的判断でそれほど高価でない素材を使っているかもしれない。 工場の背後には会社というバックヤードがあるのだ。 しかし、よく考えてみれば、会社はそのままぽんと出来るわけではない。そこには国というバックヤードがあり、ここでの法制や、税制、風土文化などの先進国としての活動があり、ここから企業は生まれてくるのである。 先進国の一国、もしかするとコピー業者が何の考えもなくコピーしたシリンダーの形状は、環境政策上許された排ガス規制に従うべく作られているのかも知れない。 企業の背後には国というバックヤードがあるのだ。 一番恐ろしいのはこういう強固なプロセスを経て出てきた製品が、デットコピーによって駆逐され、その思想も背景もなにも理解されないままに、それが消え去ってしまうことなのだ。 この考え方は、こういった方向だけでなく、もっと技術レイヤーの方向に切る事ももちろん出来る。 たとえばgoogleを想像すると分かりやすい。 あの会社にはバックヤードのバックヤードのバックヤードのバックヤードが強力だから強い製品が出てくるとは考えられないだろうか。 逆に考えれば、コモディティ化したビルドするだけで充分な市場には、イノベーションは生まれにくいといえなくもない気がする。 こういった多層的なレイヤーを縦断して、技術的思想を記載した文章が特許文献である。読めば読むほど企業を巡る状況が見えてくるようで、その特許を生み出した人々の思考を読むことが可能になる。 なので、オープンソースとの違いはここなのではないだろうか。 ひょっとして、コードさえ読めば、ノウハウさえ盗めれば、すべてが分かるというのであれば、それは粗悪なコピー業者とあんまり大差がない。 もし、高度な技術的思想の継承があり、脈々とした、強固なバックヤードとして確立しているのであればそれはあまり心配がない。 でもそうじゃないならば、心配になる。 それは単純にビルドしてるだけなんじゃないかって。 わたしはオープンソースと対立しているのではなく、特許ってそんな簡単じゃないんだよぉと言いたいだけだ。少なくとも、こう俯瞰すると、本質的には対立していない。特許で守られた巨大な企業のソフトウェアにも価値があって、その特許を非難するべきではないといいたいのだ。 たぶん、そういう広大なバックヤードを持った人たちが作ったソフトウェアのイノベーションの恩恵も、オープンソースの人たちは、受けているのだから。 莫大な額の開発費を投入して開発されたUIであり、カーネルであり、言語なのだ。 その開発費はビルドにかかった金だけではないと思うのだ。 なので、切っ先を返して言うのだけど、大手メディアが著作権でうるさく言うのも、その恩恵を受けていないわけではないでしょ? といいたいのだ。そこには莫大な制作費がかかっている。 コピーしているなら、文句はいわないでほしいのだ。 現行は、そんなに取り締まりは厳しくないし、そんなにトラブルになることもない。 いやなら、オリジナルでやるしかない。 無駄なコピーや改変にお金を掛けるぐらいなら、自分で一から作った方が儲かるし、そっちの方がめちゃくちゃ楽しい。 と過去デジタルコンテンツ業者だった人間の気持ちです。 あっと、安易な特許を与えちゃうのは、行政庁の質の問題です(あと、それを盾にたかってくる人のモラルの問題)。 特許制度の問題ではないです。 権利者は大切に。追記: わたしは、成文化された完璧なルールで権利範囲を確定した上での、全自動システム的な完全に公正な利益分配に興味があり、そういう意味では、オープンソースとは対立している気がしないでもない。 本当は、そのルールとシステムが空気のように見えないほど、何の争いも対立もなく、参加する人間がすべて幸せになるように進めばよいのだけど、現在は非常に混乱していると思う。たぶん、この考え方はGoogle的である。追記2: 工業製品は、特許などなくともすでにオープンソース状態なんですよね。 改良OK、分解OK、リバースエンジニアリングOKなんで、秘密なんてほとんどないのです・・・。GPLはそういう意味では、工業製品より閉鎖的といえるかもしれません。 特許の公開性はその上なんです。 これがようやくわかりました・・・。
July 3, 2007
コメント(0)
-
ウォルマートは強いんじゃない! 単に速くてでかいだけだ。
多くの人が勘違いしてしまうことに、会社の規模さえでかければそれは強いことだし、よいことだと思いがちな部分がある。 元IBMのルー・ガースナーでさえ巨象も踊るで、でかいことはいいことだという、しかも 「象が蟻より強いかどうかの問題ではない。その象がうまく踊れるかどうかの問題である。見事なステップを踏んで踊れるのであれば、蟻はダンス・フロアから逃げ出すしかない」 とまで言っている。 ほんとうにそうなんだろうか? これを検証するには、ウォルマートをはじめとするリテール(小売)業界を検討してみるといい。ウォルマートは世界最強の小売企業なのだろうか? え? 一体誰がそんなことを言ったの? あれは単に速くてでかいだけだ。 アメリカのニューヨーク州には、ウォルマートが牙城をほんの少しも侵食できない、ニューヨーク州最強スーパーチェーンがある。 ウォルマートが独占しつつあるのは、強いからではない。 最強スーパーが、速く動けないから、というだけなのだ。 その説明をしよう。 あ、その前にこの言葉をぶつけておこう。「もし、たった一つだけあなたの生活に存在するスーパーを選ぶとしたら、それはウォルマート?」 やだなぁ(笑)。 想像しただけで怖くなってくる。 さて、わたしは、ECが長かったので、小売の研究はよくしている。 その中には、ウォルマートの強さを宣伝する記事ばかりが多いが、専門家の見方は違うようである。普通に考えれば、IT技術を駆使し、卸価格を下げさせ、徹底的な効率化をすれば、小売では勝ててしまうように見えるのだが、実際には全くそうではない。 日本に、外資系スーパーが参入したのは記憶に新しいが、未だに目立った成果を挙げていない。 日本は現在、イオン系・イトーヨーカドー系の二社に絞られつつあるように見えるようなのだが、実際にはそうではないことをまず言っておく。 小売は感情の産物である。 そんなことはちょっとでも一般客相手の商売をしたことがあるのなら、あっという間に分かるはずだ。 ある大手チラシ会社の社長は、ウォルマートが参入して、カルフールが参入してきたとき、実際に店舗を見に行ってほっと息をつき、胸をなでおろしたという。「やつらは、生鮮売り場を全く理解していない!」 嬉々として、そう言ったらしい。 別に日本の小売業界が閉鎖的なわけではない。 単純に、ウォルマートが日本の小売を知らないだけなのである。 ■リアルタイム・リテールってサイトご存知ですか? さて、えらそうに語ってきたのだが、実はわたしが話そうとしていることは、日経系のリアルタイム・リテールというサイトで語られることの受け売りである。 ・リアルタイム・リテール http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/ このサイトは非常に上質な情報が集まっているのでお気に入りだったのだが、二年ほど前から連載がストップしてしまっている。 ほんとうのことを言うと、ここにある記事を全部読んで頂くのが手っ取り早いし、どれを読んでもためになるのでお勧めなのだが、全部読むのに数時間かかるだろうから、わたしがポイントと思える部分を抜き出して紹介したい。 ウォルマートはちっとも強くないことがよく分かってくるはずだ。 ■実は、地域独占が進んでいる日本の小売業 さてまずはこの記事から言ってみよう。 「塗り変わる勢力地図——国内小売業最前線 第7回 元気な地方小売業」 http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/column/kazama/07/index.shtml この記事は、小売業の成長率が高い会社は地方の小さい企業が多いということ。引用してみよう。 先ほどのデータが示すように、地方小売業はとにかく元気だ。また、このランキングにまでは入らなかったものの、イオンやイトーヨーカ堂、セブン-イレブン・ジャパン、さらにはオートバックスセブン、コジマ電機、マツモトキヨシ、大創産業といった、それぞれの業態ではトップブランドにある小売業をたじたじさせるような地方小売業も少なくない。 もちろん、地方小売業は企業規模ではトップブランドに歯が立たない。だが、局地戦や限定したマーケットでは、“ホームグラウンド”の強さを発揮できるため、トップブランドと互角もしくはそれ以上の業績を上げているケースもある。実際、あまりにもリージョナルチェーンが強いため、大手チェーンが尻尾を巻いて撤退したような事例もある。 筆者は、その強さの秘密として、 ・熟知したホームグラウンドで戦える強み ・むやみに規模拡大を狙わないことも共通点の一つ と言っている。 実は小売とはこういう性質を持つ側面もあるのを理解しないといけない。小売は感情の産物である。お客さんに愛されることにおいて一番を目指すのであれば、安易な規模拡大化をしないほうがよい事は、わかりやすいことである。 ■実は、アメリカも、地域独占が起こっている。 続いて、冒頭に書いた、ニューヨーク州最強スーパーの話。 「米国注目企業に見る最新流通戦略 第3回 常識を超えよ!究極のコンビネーションストア ウェッグマンズ」 http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/column/suzuki/03/index.shtml 必勝プロトタイプを引っさげて他州へ進出開始 ウェッグマンズの本社は、ニューヨーク州のロチェスターという田舎にある。余談だが、米国の優良小売企業の本社は田舎であるケースがほとんどである。その理由は、田舎で超寡占化を実現し、この金城湯池をベースとして赤字覚悟で他商圏へ打って出ることができるからである。競合が入って来ることのできない、儲かるドミナンスエリア(一定の地域において、他社を寄せ付けない、または取引を有利にコントロールできてしまうようなシェアを意味する)を最低1つ作ることは、チェーンストアにとっては必須であり、この要件は日米に違いはない。 ちなみにウェッグマンズはこの城下町ロチェスターで、食品シェア80%というずば抜けた寡占状態を作り上げているとのことだ。80%という数値は異常に高そうに見えるが、私が知る限り、このレベルの寡占状況を持つチェーンは他にも数社あり、実は米国では珍しいことではない。 食品シェア80%だそうである。そして、アメリカでは珍しいことではないと。 ちなみに、サイトはここ。 http://www.wegmans.com/ 店舗はほんとうにニューヨーク州付近にしかない。 http://www.wegmans.com/about/storeLocator/index.asp ちなみに、売上高は年間40億ドル。日本のイオンの1/10である。 そして、非上場企業。 つまり、株価は気にしなくていいわけだ。 良識ある、東海岸の雰囲気がぷんぷん漂うサイトで、ここ数年、働くのに最もよい会社ベスト100で上位をキープし続けている。 わたしも働くなら、買い物するなら、こっちの方がいい。 これは物凄くまっとうな競争の結果起こっている現象である。 ■では、なぜウェッグマンズはウォルマートになれないのか それはこの記事が参考になるかもしれない。 「日本の小売業は優れた感性を持つからこそ、それを生かすデータ分析が重要」 http://premium.nikkeibp.co.jp/retail/interview/10/日本の小売業は属人的なため急成長が望めない──日本の小売業が米国の小売業に最も遅れている点はどういったところでしょうか。藤野: 「スケーラビリティ」です。すべての作業を人手で行うのでは、10店舗程度なら運営できても3000店舗ともなると対応できません。ウォルマートが1日に50店舗ものスーパーセンターを同時にオープンして、年間では500店舗もオープンしているというようなことは日本では考えられないことです。日本の小売業では、多くが店舗の運営やオペレーションを人材に依存しており、経営システムになっていないからです。 例えば中国のマーケットに進出しようとした場合を考えてください。年間100店舗程度の出店なら対応できるでしょうが、500店舗となった場合に日本の小売業が対応できるかというと、おそらく難しいと思います。人材を育てない限りうまくいかないからです。 要するに、ウェッグマンズのやり方は、属人的なので、スケールできない、という事。 続いて、日本とアメリカの違い。──日本は米国に比べて相当遅れているということでしょうか。藤野: 一概に遅れているというわけではありません。日本と米国は、そもそも目指すベクトルが違います。日本では人間技でうまく対応することで結果としてのパフォーマンスが出ていますが、経験と勘が中心の属人的なオペレーションのため、スケーラビリティが足りないのです。 “暗黙知”の世界で“組織知”や“形式知”になっていない。 日本の小売業はすばらしい感性を持っていると思いますよ。感性とデータ、つまりアナログとデジタルというのは決して対立概念ではありません。小売業というのは、結局顧客の心の中に入っていかなければなりませんから、感性は重要なのです。顧客はどういう気持ちでいるのか。たとえ同じものを購入したとしても、それしかないから仕方なく購入しているのか、それともそれがどうしてもほしくて満足して購入しているのかによってその内容はまったく異なります。これは絶対にデジタルでは分かりません。 結局、スケール問題だけであって、お客さんに愛される、健全な企業として運営するという意味では、特に問題はないということ。小売は感性です。 ついでに、サイト外だけど、イトーヨーカドーの理念。 伊藤雅俊の「『ひらがなで考える商い』のこころ」 http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20060414/101346/ 商売は「難しいことば」で考えてはいけない 必要なのは高度な知識より、深い知恵 http://business.nikkeibp.co.jp/article/manage/20060616/104561/ 「商人が漢字や難しいことばでものを考えるようになると、現場から遠ざかっている」というのが私の持論です。 小売業の経営者も、ある程度会社が大きくなると、現場で接客するよりも、銀行とのお付き合いや同業者との会合が多くなります。頼まれて経営理念を講演したり、ものを書いたりする機会も増えてきます。ときには政府から声がかかり、審議会の委員にと言われることもあります。 そうこうしているうちに、漢字やカタカナ、難しいことばが会話の中でしばしば出てくるようになります。そうなったときは要注意です。現場が遠のき、肌身で感じ取ることが少なくなって、商いの活力が失われ始めているのです。 「ひらがなで考える」ことが重要です。「ひらがなで考える」とは、本で読んだり聞きかじって得た知識でなく、実践を通して身に付いた知恵を生かす思考です。 との事。 わたしって、けっこう本気でECやってたんだなぁと改めて実感。 以上。 ウォルマートは強いんじゃない! 単に上手くスケールできただけだ、という話でした。
June 25, 2007
コメント(0)
-

サムスンが「なぜか」強く見えない理由と、グローバリゼーションに潜むひとつの錯覚
まず、冒頭に結論。 グローバル化 → 市場単一化(世界英語圏化) × グローバル化 → 市場多極化(世界多極言語化)○ これがこれから長い時間をかけて説明したいことである。 そして、サムスンは後者をよく理解していて、機動的に戦略を構築している。 たぶん、多くの人が、え?と思うだろう。しかし、わたしは事実のみを伝えよう。 では、はじめよう。 特許という仕事柄、世界中の特許の情報はいやでも入ってくる。 特に東アジアの三地域(中国・韓国・台湾)からは、事務所宛にダイレクトメールと各地域の詳細な特許状況のレポートが送られてくるので、かなり頑固に世界を見ないように努力しない限り、世界の状況が目に飛び込んでしまう。 国際法は弁理士の試験範囲なので、当然やらなければならない。 特許文献は、世界中の産業力をストレートに現したものであり、それを読むのがわたしの仕事であるので、それが「何語で書いてあるか」がどうしても気になる。 PCT(特許協力条約)規則によれば、国際出願はアラビア語、英語、スペイン語、中国語、ドイツ語、日本語、フランス語、又はロシア語でしなければならず、韓国人大変だぁと思いつつも(というかそのうちはいるだろうが)、国内出願は当然ながらその国の公用語で書かれる。 日本の特許文献が英語で書かれていないのと同様、中国の特許文献は中国語で書かれている。 翻って、全世界の特許出願件数を見ると、一位は日本、二位は米国、三位は韓国、四位は中国、五位は欧州の順になる。ちなみにこれは2004年の数字らしい(WIPOは集計が遅いのである)。 これを見れば明らかなとおり、中国・韓国の産業技術の革新力は目を見張るほどであり、欧州に勝ってしまうほどなのだ。 さらに、中国・韓国の知的財産権への取り組みは非常に力強い。 韓国は改革を経て世界最強の特許庁を作ってしまったし、中国は20万人もの人材をどばっと投入して知財意識を普及させようとしている。 もちろん行政の引っ張りだけでなく、韓国のサムスン・ヒュンダイ、中国のハイアール・ベンキュー(あっと、エイサーを忘れてたよ・・・。え? レノボってなに?)と国際的なブランドに育ちつつある二次産業企業の勃興は目覚しく、マザーボードのほとんどを生産している台湾などを入れても、二次産業は東アジア・東南アジアより革新が始まる構図になりつつある。 これではっきりするのは、もし二次産業に従事しているのであれば、中国語と韓国語の特許広報が読めないとついていけないという事である。 その中でも、日本企業を除いて最強といえるのはサムスン電子であることは、誰の目にも明らかであると思う。 しかし、思うのだ。 その割には、あんまり印象がないんだけど? その答えはこの記事の中にある。 三星プリンター「世界2位」に -中央日報 たぶん多くの人が首を傾げるだろう。(というか、コメントがあまりにも馬鹿すぎて笑ってしまう。好んでわたしのエントリーを読む人にそんな認識の人はいないだろうけど) え? サムスンって、プリンター売ってたっけ? 「日本語の」サムスンのページへ行って見よう。プリンターを売っているなって一言も書いてない。 「韓国語の」サムスンのページはどうか。わたしは読めない。 では「英語の」サムスンのページはどう? たぶん、日本語のサムスンのページになれている人はかなりぎょっとするのではないだろうか(笑)。わたしも、プリンターでキャノンをぶっちぎっているサムスンの記事を見てぎょっとしたたちなのであんまりえらそうなことはいえないのだけど、わたしは思わず笑ってしまった。 以前、サムスンとLG電子が、アラブ諸国の高級ホテルで薄型テレビの販売合戦をしている記事を見たことがある。たぶん、七ツ星のドバイのホテルに入っている薄型テレビはサムスン製。決して、ソニー製でも、松下製でも、ましてやシャープ製でもない。 わたしは、あー、なるほどとサムスンの戦略にうなずく。 そして、それになぜ日本人が気付かないのかに気付いて、ぎょっとしたのだ。 ■サムスンのブルー・オーシャン戦略 サムスンは、世界でもっとも力強くブルー・オーシャン戦略をとっていることで有名である。ブルー・オーシャンという概念を作り出した人々一人が韓国人であるかということもあるのだけど、たぶん、これを積極的に取り入れた理由は、日本家電メーカの強固な壁を避けるという戦略からだろう。 なので、サムスンは、日本家電メーカーのブランドが強く浸透している市場には積極的に乗り出さない。 なぜなら、熾烈な競争が始まってしまうから。 日本市場に乗り出すなんてもってのほかである。 その代わり、現在立ち上がりつつある市場に資源を集中している。ここに強固なサムスンブランドを構築してしまうことにより、日本メーカーの参入を阻もうというのである。 これは理にかなっている。 消耗戦を避けるのであれば、別の市場を選ばなければならない。 幸いにも、先進国市場と発展途上国市場では、市場に求められている製品が違う。 40万円もするソニー製は絶対に買えない。 つまり、サムスンは、日本・米国・欧州の市場を、戦わざる終えない場合以外は避けているのである。発展途上国が登ってくるのに合わせて、商品のラインナップをそろえていく。 なので、サムスンの強さがなかなか見えてこないのは当然といえる。 なぜなら、サムスンは、そこでは戦っていないのだから。 日本人が戦っている市場に、サムスンの最強部隊はいないのである。 ■英語経由という、意外な目隠し なぜ、このような事が起こってしまうのだろうと、しばらく考え、それは言語の壁であるとわたしは気付いた。 日本人は、未だに英語圏が世界のほとんどと考えてしまう癖がある。 しかし、どうだろう、世界中で英語の特許文献は全文献の何パーセントだろう? わたしは、日本の発展は日本語という暗号にかなり助けられたと思ってはいるのだけど、それと同じ状況が、韓国・中国にも起こっているとは考えないだろうか? 特に外国の情報は、英語の情報で受け取ることが多く、それをすべてと思いがちである。 日本語で得られる情報に限りがあるのと同様に、英語で受け取ることが出来る情報にも限界がある。 ためしにBRIC'sの公用語が何語であるかを考えてみるとよい。 ブラジル → ポルトガル語 ロシア → ロシア語 インド → ヒンディー語、英語及び複数の各州公用語 中国 → 中国語 ではVISTAはどうであろうか。 ベトナム → ベトナム語 インドネシア → インドネシア語 南アフリカ → アフリカーンス語、英語、バントゥー諸語 トルコ → トルコ語 アルゼンチン → スペイン語 英語が通じるのは、僅かインドと南アフリカだけである。 もちろん、すべての言語を覚えることはほとんど不可能であるが、世界中が何語で会話をしているか、そしてわたしにとってはとても重要なのだけど、特許文献が何語で書いてあるかに想像力を働かせてみることはそんなに悪いことではないだろう。 英語は世界共通語であると同時に、世界で話され書かれている言語ではないのである。 ちょっと認識を変えるだけだ。 英語は万能ではないと。 ■「ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語る」を読む そんな中、最近話題になっている、 ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語るを読んだ。対シドニーFCの埼玉スタジアム決戦に行きがてら、駅ナカの本屋でなんかためになる本はないかなぁ、と思ってたら目に留まったのである。 幸いも、今日、日経で書評が出ていた。 『ベネディクト・アンダーソン グローバリゼーションを語る』~読破時間 1:30 この書評は非常に正確で、付け加えることはほとんどない。 ただひとつ言えば、グローバリゼーション現象は、実はローマ二ゼーションと同じ現象なのかそうではないのかという、実はとてつもなく重要で深く鋭い部分に、踏み込むのを避けているということ。 これは、ローマじゃなくて別の文化圏でも同じことがあったぞばーかという論者は、検索すれば出てくるので調べて欲しいのだが、それ以外の部分では、なるほどとうなずくことが多かった。 大切なのは、単言語単思想では、グローバリゼーションは進行しない、という部分。 それぞれの国がそれぞれ違う状況を抱えているので、方程式でも当てはめるようにぴたっとひとつのスケールでは進展しないということ。 世界単一市場化など、誰が言ったんだろう? 世界中には、それぞれの言語・宗教・風習・政治体制があり、それが統一されることはない。 多極的なそれぞれの言語圏でそれぞれの事件が発展し、ダイナミックに世界は揺れ動く波のような激動を経験するだけであり、それが、どことどこがつながって突然革命が起こるかなんて、分かるはずもない。 スペイン語・ポルトガル語圏で、先端技術の勃興が始まるかもしれないし、それはロシアであるかも知れないし、一番確率が高いのは中国かもしれない。 ベネディクト・アンダーソンは後者の意味でグローバリゼーションを語っていて、なぜか日本の日経新聞などでは前者で語ることが多い。 前者の兆候を示すことは何一つ起こっていない。 あ、IT業界と金融業界だけはそうか。 グローバリゼーションという言葉が、非常に多くの意味を内包してしまっていて、勘違いを犯してしまいやすい言葉になってしまっている。わたしは、ハーモナイゼーションでいいのではと思うのだが、まあ、蔓延してしまったものはどうしようもない。 ただ、これを読んだ人は少なくともグローバリゼーションには、二つの全く正反対の思想が含まれてしまっている、ということを認識してもらえたら、これを書いたわたしの苦労も報われるものである。 そして、サムスンの実力を見誤るような、がっくりくる見識だけは持って欲しくないのである。 彼らは、日本人とはまったく違う市場で戦っているだけなのである。 最後に、アンダーソンも助言をしている。 英語と、そしてそれプラスもう一言語を覚えるようにと。 わたしはそれを見ながら、がっくりとしながら、それからあきらめるように思う。「あーあ、英語と中国語と、あとプラスもう一言語ぐらいは覚えなきゃなあ・・・」 たぶん、暗号に見えない程度でよいと思う。 流暢である必要はないと思う。 わたしの場合は特許文献だけ読めればよいと思う。 書けなくてもよいと思う。 でも、どの言語なのかなぁ。 英語と中国語を覚えてからの話だと思うし、ずいぶん先の話なので、そのころは有望な言語はがらっと変わっているとは思うのだけど、スペイン語か? そういう、仕事なのである(ため息・・・)。 ちなみにサムスンの新入社員のTOEICの平均点は900点だそうである。 バイリンガル当然。で、プラス3はどの言語を選びたい? 3つでいいよ。 たぶん、こんな認識のはずである。
June 22, 2007
コメント(2)
-
データにまみれないと、なにもみえない
わたしがお気に入りにしているCDアルバムは、けっこう聞き込んだものが多い。 あんまり人が知らないマイナーアーティストが多い。 たとえば、Sing Like Talking。 ファンの方なら、「マイナーというな(笑)!」 と怒られそうなのだけど、ほとんど多数の人々が聞いたこともなく、名前をやっと知っているアーティストではないだろう。 わたしはかなり昔から、Sing Like Talkingを聞いているから分かるのだけど、このグループは、とにかく頻繁に音楽性を変える。 HumanityでSing Like Talkingらしさを確立した後、 Togetherness でジャズフュージョンに大変換、続くDiscoveryではフュージョン色が強くなり、Welcome To Another Worldでパンクっぽくなる。 たぶん、HumanityのSing Like Talkingが好きなファンはついて行けなかっただろう。 その後、METABOLISMと続き、RENASCENCEが最新である。 わたしは、Sing Like Talkingを最新作を聞くとき、そのアルバムを嫌いになることを覚悟する。 とにかくまったく受け付けないのである。 こんなのSing Like Talkingじゃない! と喉元まで文句が出かけて、わたしは慌てて飲み込む。 これはずっとこれまでそうだったのだ。 そしてもう諦めて、20回ぐらいぶっ続けで聞いていると、ふと、思う。「あ、いいじゃん・・・」 そうしてわたしの胸の中に、大好きなアルバムが一枚増える。 昔、マーケティングの仕事をしていたときのわたしの初めの頃の仕事は、定性データの打ち込みであった。 四百枚ぐらいどさっとやってくるアンケートを打ち込む。 たとえば、新商品である洗剤の使用感レポート。 一枚に多いときで10問ぐらいの定性データ、もちろん定量データもある それを一人で2日ぐらいで打ち込む。 その部署は、打ち込み量が膨大かつ納期が厳しいことで有名な部署で、社内でもベテランの定性職人が集まっていたから、首をほぐしながら先輩たちの手の動きを見る、話しかけ上手くなる方法を教わる、観察をすると、アンケート用紙の扱い方ひとつにもコツがあることが分かってくる。 わたしは、新米だから、ずいぶん遅いし、間違えも多い。 先輩にからかわれながら、ずいぶんオペレーション力(つまり、ミスひとつなく、データを扱う力なのだが)を鍛えられたが、標準的な力に到達し始めると、どうも、その部署の空気がそういう空気で動いているわけではないことが分かる。 「あー、○○さん、またやったな・・・。電話電話!」 「これどうかな? 「ん」かな? 「んー」かな?」 「「やたー」だってさ、××さん、めっちゃ面白い」 わたしのいた会社は、定性の神様と呼ばれた創業者が立ち上げた会社、おそらく一般的なアンケート会社を想像すると、まったく違う光景を想像していることになる。 数千人の専属モニターが会社に所属し、それが会社と密な関係を持っていて、家庭状況も把握している。もちろん、先輩たちは名前を全員覚えている。そのモニターさんの眼力をまとめ企業に提出していた。 なので、慣れてくると、アンケートを書いている人の状況が鮮明に思い浮かぶようになる。手書きの文字には、その性格が乗っている事が手に取るように分かるようになる。各家庭での様子がありありと浮かんでくる。浮かんでこないような「死んだ」レポートを書いてくると、ひどいときは、電話で問い詰める。 四百枚ものびっしり書かれた定性の打ち込みを完了すると、その商品の事が手に取るように分かるようになる。 これは不思議な世界だった。 何千枚ものアンケートを入力しなければ、到達できない世界。 もっとも、数千枚なんて一ヶ月で打ち込むのだけど。 それだけの定性データにまみれていると、その文章が、どう書かれたのかが分かってくる。 ちょっと脚色が多すぎるもの、 はしゃぎすぎなもの、 無理やりに書いているもの、 何らかの怒らせる要素があって悪意がにおうもの、 なぜ、それが分かるようになるのか。 それはよく分からない。 なんとなく文章ににおいがあるように感じられるようになるのだ。 創業者の言葉残っている。 定性データの海で溺れなさい、格闘しなさい、まみれなさい、そうしなければ定性は分からない。 わたしはパソコン通信でログにまみれて生活していた時期があったから覚えが早かったのだが、たぶん、このデータにまみれて見えてくる世界というものはある。 Webデザインをやっていたとき、ふとやってきたインターンなどにPhotoShopを教えるとき、100枚のJpegを渡して、色調補正してということをよくやった。 へろへろになって上がってきた100枚を、今度はわたしはその子を後ろに座らせて一枚一枚全部わたしが補正しなおす。その際に、細かく色調の誤差やら、トーンカーブが甘いとか、レベルの取り方が間違っている、おおこれはよい、といったように寸評を交えながら、手早く補正をかけていく。 これを何回かやると、だいぶ上達する。 だから、たぶんPhotoShopの画像補正を教えるには、画像にまみれさせてあげないといけない。 これは理屈でも何でもなく、体得するということだ。 わたしがデータベースであるMySQLを玩具でも扱うように、あれこれいじるのは、MySQLをいじくりまわして体得した感覚なのだろう。 わたしには、たかだかMySQLの本番環境での全文UPDATEぐらいで、びくびくしていた上司が信じられなかった。 ほんとうのことを言うとわたしの気軽さもいけないのだけど、わたしはこう思っていた。「UPDATE文ちょろっと投げるだけじゃん。テーブルなんて、コピッてバックアップしときゃいいんだよ」 わたしはデータベースのオペレーションには自信があったのだ。 わたしが不思議に思うのは、まみれた経験がない人が、指揮系統の上のほうにいることをしばしば見ること。 データにまみれ、データと格闘し、データを身体にしみこませる作業は、まるで下っ端の仕事にように取り扱う人をしばしば見かけたこと。 まるで万能な理論があり、もしくは誰かの頭の中で生まれた「面白そうな」理論があり、世界がそれにしたがって動いているとでも言いたげな人があること。 オイゲン・ディーゼルが『技術論』のなかで書いているように、発明する、とは、無数の誤謬の皮を剥いで取り出した正しい根本思想を幾多の失敗と妥協を経て実際的成果に帰すことなのである。 ■プロイセンの歴史読了、アル・アジフ・・・、もとい! 「技術論」がやってくる。 だから、もちろん、わたしにとって法律の勉強は法律にまみれることであり、ゲームブックの研究はゲームブックにまみれる事によってしか成し遂げられないと信じる。 どろんこ遊びをしている人がいて、汚れるからといって傍観している人がいて。 一方はどろんこ中に面白さを発見し、一方はどろんこ遊びがいかに不衛生かを話す。 だから、よさそうなどろんこがそこにあったら、いい服着ているからとか、今日髪をセットしてきたからとか、格好悪いからとかそんなどうでも言い訳をくちもとでぼそぼそとつぶやいて、その言葉はそよ風に流されちゃって、何も残んないんだからさ、 飛び込め! 飽きたら、また別のどろんこを探せばいい。 追記: これに関しては、一ヶ月ぐらいしたらエントリーにまとめます。 グラフ理論が直接の原因で書きたくなったエントリーだったりする・・・。
June 4, 2007
コメント(0)
-
新聞vsポータル、テレビvs観戦、週刊誌vsブログ 野球予告先発に見る各メディアの損得。
2ヶ月ぐらい前から、スタートページをYahooから、楽天傘下のインフォシークに替えて非常によく分かったことが2つある。 ひとつは、楽天は2ページ目以降はえぐい広告も多いが、Yahooは1ページ目こそえぐさの真骨頂であるということ。 そしてもうひとつは、インフォシークが、 「これでもか、くそ」 とばかりに楽天ゴールデンイーグルスの宣伝をしまくって、そのおかげで、わたしは異様にイーグルスの情報に詳しくなってしまっていることだ。 念のため言っておくと、わたしは埼玉県人なので、西武ファン。 西武は今何位かは知らないのだが、楽天は借金1の4位(6月1日現在)。 何で知ってるんだろうと、おかしくて笑いが出る。 球宴は楽天・山崎が打点・本塁打2冠王でファン投票トップ。田中は投手部門一位。 わたしはふしぎに思い、Yahooを見ると、山崎のニュースがない。 これを読んでいるあなたは、楽天が勝率五割になったときの野村監督の名言を知っているだろうか?「記者:(勝率が)5割になりましたね 野村:ほ~明日は雪か。野球って楽しいね。」 楽天は、田中効果が好循環を生んでいるようで、それがチームを活性化している。 ちなみに次の日の記事は、「ノムさん完敗、雪降らず安打の雨あられ」 ネタとしか思えない(笑)。 今日、たまたま昼飯を食べたカフェ(地方都市にもおしゃれなカフェがあるのだ)で、読売新聞を見て、その巨人のニュースの大きな見出しに驚く。 どう考えてもテレビ映像を無理やり引き伸ばしたとしか思えない写真。矢野の殊勲の代打満塁ホームラン。おお、矢野ってのが出てきたのかと思って、ふと思った。「この記事の大きさは読売新聞だけなのではないだろうか?」 Yahooニュースにはまったく出てない、インフォシークは気付くと楽天関係のニュースしかない。 ははんと納得して思う。 読売新聞は巨人を傘下に入れて部数を大幅に伸ばしたが、楽天(正確にはインフォシーク)で見られる戦略は読売のそれである。これは正当な行為である。 さて、本題に入ってくる。 面白いニュースを見つける。 ■楽天の奇襲!ノムさんニヤリ…中2日でマー君先発もあるぞ http://news.www.infoseek.co.jp/sports/story/25sankei120070525011/ 記事を読むと分かるのだが、これは引用が一番分かりやすいだろうか。「「正攻法のなかにどうやって奇襲を組み込んでいくかだな」と予告先発がない交流戦の醍醐(だいご)味を話していた野村監督。古巣のヤクルト相手に正攻法で連勝したあとは、奇襲の出番?」 わたしははっとした。 野村監督は、もともとパリーグの予告先発に苦言を述べていた。 前日から、明日の先発は誰だろうかって考えて次の試合を楽しむのが野球の醍醐味というのが策士野村監督の持論なのだ。 わたしはインフォシークの記事を見て思う。 確かに新聞やポータルサイトのニュースには、予告先発がないほうが、記事が書きやすい側面がある。明日の先発は順当に青山だろうか、それとも奇襲で田中だろうか、というのはかなり面白い記事になる。これはわたしが浦和レッズのフォーメーション予測をブログのネタにしていたから(最近更新してないけど・・・)、よく分かる。先発予測だけでも、記事になるのである。 予告先発は常に満員になるとは限らないパリーグが、呼び水となる投手が先発する日ぐらいは観客を入れようという趣旨の元導入された制度である。これは松坂先発試合だけを生中継するテレビ局の思惑とも重なる。 要するに、予告先発を巡っては、反対する新聞・ポータル陣と賛成する不人気球団・放映権料が高いテレビと2派に分かれているのだ。 これは、つまり、この両派が同じようなメディアであるということを意味する。 ちなみにラジオは、反対派に属する。 ラジオのメディア特性は実はあんまりスポーツ業界は分かっていないのかもと思った。わたしは、これは全力を持って断言し、損をさせない事は間違えないと思うのだが、楽天はポータルサイトで全試合ラジオ中継をすべきである。これは新聞的なメディアである。放映権ただだし、コストもかからないだろう。広告は、楽天市場の各店舗の広告を入れればいい。ローカル感は武器になる。 TBSなんていらんだろう。 ニュースバードを分社化し、どかんと資本注入して、それだけ独占配信してCNNみたいな企業に育てればいいのである。 冴えた提言だとは思うけど。 さて、こうやって話をしてくるとブログがどんなセグメントになるかなのだが、ブログの持っている即時性は、実は既存のメディアとあまりかぶらない。あえて言えば、週刊誌であろうか。 わたしも浦和レッズのフォメを追うエントリーを書きながら、なんか週間サッカーを思い浮かべた。もちろん、こっちはかなり適当に分析記事を書いているので、質のレベルでは到底及ばないのであるが、いちいちフォメを書いてどういう動きをしていたかを分析しているところはまさに週刊誌のノリ。専業化すれば、週刊誌になるだろう。 メディアというのは、整理されていて役割分担が出来ているように見えるのだが、メディアを使う側は、あんまりよく分かっていない。楽天がTBSを買おうとしているように、ネットに出てきてもあんまり意味がない話をしているように感じる。 わたしはシンプルに、 ニュースバードが欲しい。CNNようなメディアにしましょう。 でよいのではと思うのだ。 みなさんはどう思いますか?
June 1, 2007
コメント(0)
-
捨てられないこだわりでうじうじするのは、たぶんしょうがない(前編)
クリエイティブな人って何らかのこだわりがあると思う。 直接的なものに対するこだわりなのか、間接的なものに対するこだわりなのかは分からないけど、とにかく無数に近いぐらい細かな好き嫌いがあると思うのだ。 たとえば本ブログを見ると分かると思うけど、わたしは薄い色の文字が好きである。 何でといわれるとよく分からない。 わたしは黒い字、つまり#000000の字が嫌いなのだ。 テキストエディターは、黒のバックに白の字。 ライフハック的な、マーケティング的な理由はない。 もし無理やり作ろうとすれば、それは、黒という色彩の中で最強の色を、別の色で代換え可能な文字に使いたくないとかいう、そんな理由になるかも知れない。 とにかく生理的に、黒字はゾッとする。 たぶん、赤といっても#FF0000を使う人がデザイナーにはほとんどいないのと同じ理由だとわたしは、思う。 真っ黒というだけでも強烈などぎつさなのに、それを主張の多い文字というものに載せるなんて、なに考えてんだろう? というような感触。 これは理不尽なこだわりのもっとも分かりやすそうな例なのだけど、クリエイティブで飯を食っていたような人は、ものすごく細かい雑多なこだわりをあちこちに持っていて、それがその人のクリエイティブを支えていたりする。 Webで商業デザイナーなんてことをやっていて、ものすごく大きなこだわりなど通せるはずがない。 たとえば、わたしは赤系のWebページしか作りません、などというこだわりを持ってしまうと、突然お客さんがいなくなってしまうことは、想像に難くない。赤の表現力では世界一のデザインセンスを持っていて、それが誰の目にも明らかであっても、たぶん生活をしていくのは難しいのではないだろうか。 もちろん、「赤色」が流行る瞬間もあるだろうし、赤好きな顧客をゲットできる事もあるかも知れないのだが、わたしは赤でしかデザインしません、というのは、赤でない限り、顧客の要望は聞きません、ということを意味する。 日々の生活費さえままならないのに、赤を捨てない人というのは、人並みならぬ、赤へのこだわりを持っている。 そして、わたしは思うのだ。 おそらく、世界で一番赤のデザインが上手い人は、きっと赤でしか、デザインしないことを心に誓った人であろう、と。 しかし、これは、優秀なクリエイター≠商業デザイナーという訳ではない。 お客さんと話してて、「何か、デザインでこだわりたいことはありますか?」 ときかれても、わたしはたぶん、「とくにこだわりたいことはありません」 と答える。 けっこうこれを本気で言っていたりする瞬間もあるのだが、これは裏返すと、「こだわって、NGなんて出されたら、わたしはノイローゼになります。だからこだわってるようには見えないようにします。自分もだまします」 という意味である。 端的に、わたしのデザインという仕事に向き合っていた時代のいい加減さ、というか覚悟のなさをあらわしているのかも知れない。 しかし、ちょっとでもクリエイティブな人は作るものに何らかのクセがある。 このなんとなくにおうその人らしさの背後には、実は素人には分からない精度で無数に散りばめられたその人の好みがあり、そのネットワークの絶妙なバランス感で作品のクリエイティブが築かれていたりするので、ちょっとでも難癖をつけると、あれほどこだわりはない、といっていたクリエイターから火のような反発が降りかかってくる。 たとえば、#111111で文字の色をつけていた、わたしに、「なんか文字が薄くないですか?」 というと、たぶん次の納品は#0C0C0Cで納品される。 ここでまた、「やっぱり薄いと思うのですが?」 というと、今度は#090909で納品される。 さらに、「薄いって言ってるでしょ!?」 というと、#050505で納品される。 しまいには、「このぼけデザイナー! #000000で納品せいといってるんだよ!」 といわれても、たぶん、#010101で納品される。 ちなみにデザイン側も、文字色を変えるたびに、それに伴って、他のデザインを微調整していたりするので(そしてこの調整に素人は気付かない)、もう何度、全面修正したと思ってんだ、このDQN担当者め! とはらわたが煮えくり返っている。 なので、それなりに出来るデザインを納品するクリエイターに発注するときは、些細な点をあんまり修正させないほうがよかったりする。あと、出来るだけわかりやすい指標を渡したほうがよい。たとえば、「わたしのノートパソコンでは、その文字色は薄くて見えないので、見えるようにしてくれ」 であれば、おっとそれは失敗、と無難な修正をしてくれる。 ちなみにデザインは、その要望を聞くために、会社をうろつきまわって、ヘボいデルのノートPCを探し出し、ちょっとごめんね、5分貸して、と同僚に断って、発色チェックをしていたりするのである。 顧客の言うとおりに、CSSでちょろっとカラーコードを修正しているとしたら、たぶんそれはあまり優秀でないデザイナーである。そんなにこだわりがないから、ときどき適当にごまかしてたそんなに優秀ではないなんちゃってデザイナーのわたしが言うのだから、間違えない。 これはプロフェッショナリズムとはまったく関係ない。 クリエイター気質の話である。 生理的に受け付けないのである。 ティッピング・ポイントに出てくるナイキのマーケターの言葉を借りれば、非常に分かりやすい。「だって、文字色の明度を5%も落とすんだよ? どんなページになったのか気にならない?」 そして、気になったところを修正し始めるのである。 こだわりというのは、けっこう掘り下げてみると、自分も含めたその人がその分野に対してクリエイティブな人かどうかを見る、リトマス紙になる。 たとえば、わたしは、プログラミングはぜんぜんクリエイティブではない。 何で、phpで書いてるの? と言われて、たぶん第一声は、「え? 簡単だから」 であり、ほかの言語のほうが簡単だと薦められても、わたしは、「でも、本が沢山でてるし」 といい、あれも出来ない、これも出来ないと言われて、「そんな高度なプログラムは書かないから必要ありません」 と突っぱねる。 とにかくわたしがphpで書いている理由は、単純に、知っている言語だからということであって、慣れているから、という以外にない。この分野においてはなんの取っ掛かりもないつるつるの人間であり、誰かが書いてくれるなら、何の問題もなくお任せするし、自分で書いている理由は、自分で書く以外の選択肢がないから、という理由でしかない。 わたしはコードが吐き出す結果が欲しいのであって、その結果がもたらされる事によって喜ぶのであって、コードを書くことを喜んでいるわけではない。 なので、一番怠惰な方法で、問題を解決する。 そう、たとえば、CSSでカラーコードを修正するようなものである。 追記: 終了の文章を、「修正するようなものである。」 から、「修正するように。」 に直そうか、非常に今でも迷った。 6文字の修正なのか。 それが気になる人が、クリエイターである。
May 24, 2007
コメント(0)
-
ゼロ・サム・ゲームでしか考えられない? 変だな・・・。世界はゼロサムじゃないのに・・・。
ボードゲームには四大聖典があって、ゲーマーはそれを信仰している。「モノポリー」 → 不動産ゲーム「リスク」 → 世界征服ゲーム「アクワイア」 → ホテル買収ゲーム「ディプロマシー」 → 一次大戦ゲーム これらのゲームは非常にすばらしい出来で、わたしもやりこんで夢中になった。 確かに完成度が高く、戦略性が高い。 プレイは練りに練られたルールで、そのプレイの質が保証され、プレイヤーにへぼがいなければ、緊迫したセッションとなることが、ボードと駒により保障されている。 わたしも、サークル時代には「ディプロマシー」のルネサンス期版であった「マキャベリ」を死ぬほどやって、オンライン用にホームページを作って、新聞を作り、FLASHで戦局を解説するアプリケーションを作った。 わたしはゲームとしてのマキャベリは大好きである。 ナポリ狂であったわたしは、教皇領・フィレンツェ連合、フランス、トルコとどんぱちやることがたまらなく好きで、広大なティレニア海を舞台にした海軍戦には特にびりびりする快感を味わった。 ナポリにとってはほとんど本拠地といってよい自国の半分の領土に接するこの海域は、フランスの絶対防衛線リヨン湾に接し、トルコのジョーカー・チュニスを伺う。 ■マキャベリ ~イタリア年代記~ http://homepage3.nifty.com/souryu/machiavelli/ しかし、この海域は、教皇領の本拠地ローマに接し、フィレンツェの主要都市に接しているのである(地図参照)。 ナポリがティレニア海の女王として君臨するためには、仮想敵を各種勢力に納得させティレニア進軍を正当化し、もっとも隙がありそうな勢力を奇襲的に弱体化させ、一方に安全海域を作る以外ない。 たとえば、フランスにはトルコを叩くといい、フィレンツェにはフランスを叩くといい、トルコにはフィレンツェを強襲するという。教皇領はどうやっても戦わざる終えないので、冷戦状態を作って戦線を膠着させておく。 誰を敵とするかが明らかになる時期はなるべく遅らせたほうがよい。 たとえば、フランスにとってもフィレンツェにとっても生命線となるのはコルシカ島であるが、フランスにはフィレンツェを叩くからといって、フィレンツェにはジェノバを譲るからコルシカを「貸してくれ」と言い、次の年にどちらをたたくかを決める。 これはゲームだからとても楽しい。 こういうスリルあふれる、人から領土を奪うことに情熱を割くことは、人を裏切ることは、軍事力でティレニアから他海軍を追っ払うことは、ティレニアの女王として君臨することは、それ自体がアーティスティックであり、芸術的であり、陶酔的であり、絶妙のバランス感を試される至高の時間といってよい。 だからわたしはナポリが大好きなのだ。 ただしゲーマーとして。 この4大聖典に共通しているのは、それが全てゼロサムゲームであること。 そのお互いの境界線がタイトであればあるほど、ゲームとしては厳しく、激しく、激動に包まれる。 現在発表されているボードゲームに、ゼロサムでないものは恐らくほとんどなく、そのタイトさ、偶然性をどう取り入れるかに若干変化がある(カタンも、かなりゆるいゼロサムである)。調べれば調べるほどボードゲームはゼロサムでデザインされており、ほかのデザインは出来ないものかと、わたしはふと首をかしげる。 ゲームデザイン論ではここでTRPGが登場するのだが、ゼロサムゲームというのは、結構プレイヤーの負荷が高いので、初心者にはあまり薦められないのである。 ディプロマシーなどは、その裏切りがあんまりにも鮮烈な印象を与えてサークルの人間関係が崩壊するという現象が発生するので、サークルクラッシャーゲームと呼ばれる。 さすがに、サークルを崩壊させるゲームはお勧めできない。 グローバリズム、フラット化という用語で定義される経済ゲームは、これとまったく同じ、メイド・イン・アメリカな、ゼロサムデザインだ。 しかし、わたしは知財界にいておかしいなあと首をかしげる。 いつの間にそんなのが、世界標準になっちゃったんだろう? 少なくとも、国際条約にはグローバリズムなんて言葉は出てこない。 アメリカがWTOに絡むと無茶が出来なくなるのは、実は、WTOの条約がグローバリズムとはまったく正反対な、表裏一体の思想で出来ているからだ。 ハーモナイゼーションという。 国連的志向というと分かりやすい。 特許業界に入って、さまざまな人々に話を聞くと、日本の特許業界がこの「ハーモナイゼーション」の洗礼を受けていることが分かる。 誰に聞いても、この言葉を誇らしげに言う。 それが、ハーモナイゼーションだ、と。 全世界が、それぞれ生まれも、政体も違う、声質の違う国家たちが、全世界の声に耳を傾け、自分の発する声もハーモニーの一部にするのだと。 ハーモナイゼーションは日本語にすると調和(もしくは国際調和)なのだが、この言葉が出てくるとぎくりとする。 どっかで聞いたことがあるのである。 この辺とか。 ■南方機車 年内に「時速300キロ」 高速鉄道の“中国化”進む http://www.business-i.jp/news/china-page/news/200704240043a.nwc (調和号ですよ! どうよ、このすさまじい意欲(笑)) ■中国の裁判所、調和の取れた社会に適切な司法保障を http://japanese.cri.cn/151/2007/01/08/1@83344.htm 今、中国のスローガンは「調和」である。 恐らくこれは、非常に国内・国外ともに響きやすいスローガンだからだと思われるのだが、わたしは、グローバリズムに対する最強の対抗軸が、ハーモナイゼーションであるからでは、と勘ぐってしまう。 知財系の中国の発言を追っていくと、日本の知財の教科書に出てくるような見解を読むことが出来る。これは単に、日本が高度成長期に起こした摩擦をどう解消したかを非常によく勉強しているから、似てくるのである。 ■中国、知的所有権保護で自信満々 http://japanese.cri.cn/151/2007/04/26/1@92321.htm これが100点の取れる答案である(皮肉(笑))。 中国の打つ施策を見ていくと、どうもしばらくしたら日本なんて抜かれてしまうほど、勉強しまくってんじゃないかと思ってしまう。 日本の知財界の人間の直接競合は、たぶん日本語を覚えた中国人知財移民であろう。 グローバリズムとハーモナイゼーションを眺めてみて、それをBRIC’sに当てはめ、VISTAに当てはめてみると、どう考えても前者は分が悪い。 なので、フラット化という言葉はなんの意味も持たない言葉なのである。 なぜなら、これはゼロサム・ゲームを意味するから。 経済成長率がかなり低い国々では、一見正しそうに見えてしまうのだが、年率10%に迫るような高成長国には、この言葉はまったくちんぷんかんぷんなのだ。 世界は、毎年4%近い経済成長をしているのだ。 普通にしていれば、みんな4%ずつ豊かになれるのだ。 毎年4%ずつ給料が上がるのだ。 もしくは労働時間が4%ずつ減るのだ。 マイナス成長ではないのだから。 みんなパイの奪い合いなどする必要はないのだ。 高度成長を味わいたいなら、ベトナムにでも行って、そこに永住するとよい。 ベトナム語を覚えれば、バイリンガルになるので、もうこれだけで有利である。 日本の弁理士資格でも持っていけば、もう競合は存在しないも同然であろう。 世界的には、今は上げ潮なのである。 そして、これは今後も、長い期間続くかも知れない。 どうやって、世界の経済成長を4%から8%、10%と向上させればよいのかを考えればよいのだ。 とても簡単じゃない? 協力し合えばよい。 ん? なんか、変ナコト、イッテル? 長々と話してきたけれど、わたしはいつも不思議に思うのだ。 何で、アメリカのゲームデザイナーはゼロサム好きなんだろ? まあ、4大聖典が偉大すぎるから仕方ないといえば、仕方ないのだけど。「モノポリー」 モノポリーは1920年代後半に、エンジニアのチャールズ・ダロウが考案したと言われている「リスク」 このゲームのオリジナルも,ディプロマシーと同様に40年以上の歴史を持つ,その筋では有名なボードゲーム「アクワイア」 1960年代にシド・サクソンによって創案され、アバロン・ヒルより発売された。「ディプロマシー」 ディプロマシー(diplomacy)とは、アラン・B・カラマー(Allan B Calhamer、1931年 - )が制作したボードゲーム。1954年に完成し、1959年より小規模ながら一般に販売される。 コンピュータのゲームデザイナが情けなすぎるともいえるけど。 世の中というのは、案外馬鹿なのである。 ばーか、ばーかと馬鹿にして、こつこつと改良に勤しめば良いのである。 もし、世界を悲観するならば、そう信仰してみるとよい。 そして、ひょっとして自分もとんでもなく間抜けなラットレースをしてるんじゃないかって。 ゲームに酔ったらおしまいである。 追記: ちなみにハーモナイゼーションという言葉は、多くの知識人の間で誤解されて認識されているようである。 特許法は、基本的にパリ条約から国際調和がされ始めているのであるけど、その基本原則は、各国の特許は独立している、という原則にある。特許であるかどうかは、その国々に任される、という原則であり、その特許になる条件をどう刷り合わせていくか、という話であって、「お前の国は間違っている。それは特許にすべきだ」 という話ではないのである。 最低限の、これは条件にしないやつとは協力しない、というすさまじく大枠な条約にみんな批准していて、批准するかしないかは、各国の決定にゆだねられる。 これは、「みんな、それぞれの国を尊重します。で、みんなが納得できる約束事を決めましょう。同意できる国は、批准してください。批准すれば、批准した国々の間で、恩恵をもたらしあいましょう」 という話で、PCTの条文とか読めばよく分かるけど、すさまじく高度である。 ハーモナイゼーションは、この、約束事を出来るだけ増やして、みんなが問題なくやり取りできるようにしましょう、という話であって、その約束事どうよ、と仲間はずれにしたくなる人があっても、何とかして仲間にしよう、という思想であって、どうすれば、みんなが納得できる決まりを作れるかという話なのである。 これを誤解している、よく分からないビョーキな文章に出会うと、気の毒になる。 国は、尊敬すべきである。 問題は、どう、調和していくか。 5分ぐらい考えたけど、結局、調和かよ(笑)。 調和周りで、本出すと、かなり実は、デファクトスタンダードになるかもと思ったりした。
May 11, 2007
コメント(0)
-

拒絶の壁
『マネー・ボール』を読んでいて、思わず声が上がった。 もう、数回は読んでいる。 何で、見逃していたのかわからない。 「野球抄」を書いたビル・ジェイムズのくだりである。 -守備力や投手力でなく攻撃力にとりわけ固執し始めた理由は、打撃の数字が”言葉の力”を持っているからだ。”心象数字”とジェイムズは名づけている。文学の薫りがする数字。読み取ると、情景が思い浮かぶ。- この気付きが、これから膨大な文章量をもって、説明することのすべてともいえる。 ジェイムズは、新聞に載っているボックススコア(よく新聞で見る打率とかが書いてあるやつである)を収集して、野球統計に革命をもたらした変人で、『マネーボール』はその理論に従ってアスレチックスのGMとして活躍しているビリー・ビーンを描いた本である。かなり話題になった本なので、おそらく多くの方が読んでいるだろう。 わたしは気付かなかった。 ジェイムズは、あの簡単な数字を見て、”心象数字”などといっているのだ。 これはビリー・ビーンに引き継がれていて、わたしはのけぞった。 -セーブポイントがつく場面といえば自軍がリードしている9回にランナーなしで登場、という形が多いだろう。投手の真価が本当に問われるのはそんな場面ではない。したがって、セーブポイントというデータは、”言葉の力”を持っていない。たんなるデータだ。- マネーボールは、同じアスレチックスの若年のコンピュータ青年ポールが、次々と衝撃的な数字を挙げるので、そちらの印象が強いのだが、よく読んでみると、ポールは”言葉の力”を見つめていない。 決定的な衝撃だった。 私事であるが、法律試験が1ヶ月後に近づいている。 もちろん、たった一年で全範囲をやれると思っておらず、本質的な理解に時間を割いたので(ついでに、この期間を趣味にも使っている)、受からないことはわかっている。 短答・論文・口述とある試験のうち、短答の勉強しかしていない。 短答も範囲が広く、すべて捨てずに丁寧に拾っているので、あと一ヶ月でどこまでいけるかはわからない。 ただ、戦えるレベルまでは上がってきた。 コンスタントに50%は取れる。 合格ラインは70%。 この20%の間の5%ごとがものすごい差であることは分かったので、無理かも知れないととりあえず言っておきたい。 ただ、合格は時間の問題であることだけは楽観している。 ようやっと法律が身体に馴染んできたし、全貌は把握した。 あとは時間をかけて丹念に知識を拾っていくだけ。 それはそんなに苦にはならない。 長い長い道ではあるけれど、わたしはもう拒絶の壁を越えた。 数学にしても、物理にしても、世界史にしても、地理にしても。 あらゆる学問は本質的には、理解の難しい学問であるから、どこかに理解の壁がある。 わたしは体質的に数学が受け付けない。 これでも、受験期は数学と物理だけで乗り切ったタイプなのだが、どうもわたしは受験期にずるをしてしまったようだ。だからわたしは罰を受け、数学の理解を拒絶してしまう生理的な反応をしてしまう。 もっと本質的な勉強をしていれば、少しは違っていただろう。 受験勉強に意味がないという人は多いが、少なくとも同じような試験のうちで、最高峰とも思われる法律試験の勉強をしていて、それは違うと思うようになった。 これはおそらくWeb屋さんとしてデジタルコンテンツの最前線にいたからだろう。 父親が特許の仕事をしているし、今私もそれを手伝っているからだろう。 法律には”言葉の力”がある。 野球のスコアから芝生のにおいがするように、知財法からはライセンス交渉のシーンが浮かび上がってくる。 法律は文学の薫りがするし、格調高い歴史の息吹も感じるし、現在進行形のシリコンバレーが思い浮かぶし、アジア諸国の人々の顔が見えてくる。 これは不思議である。 なぜわたしはビル・ジェイムズ同じように、この無味乾燥に見える文章の羅列に、生命感を感じることが出来るのだろう? 誰かが、数学に世界の神秘を見るように? 誰かが、地図と統計の向こうに生きるすべての人々が見えるように? わたしは小学生時代、暇があると地図帳を見ていた。 どういう子供かと思う方もあるだろうが、単純に高速道路を追い、線路を眺めて、地形を見て、あちこちにある市を見るのが楽しかったのである。 わたしはおそらく、その記号の向こうに現在のgoogleMapのような航空写真を見ていた。 わたしには地理の才能が、たぶんある。 そして、こっちは非常に強烈なのだが世界史の才能がある。 以前書いた、オイゲン・ディーゼルの技術論を読む。 その前に予習としてプロイセンの歴史を読んで、当時の社会状況を的確に把握してしまったから非常にまずかった。産業革命から始まり、二回の大戦、冷戦後の現在と、300年分ぐらいの激動の歴史を一気に吸収してしまう羽目になる。 これがいまだに衝撃的過ぎてうまく消化できていない。 現代に戻って話を読むと、どうも誰もその300年の激動を目撃していないようであることに気付く。わたしが数百年を目撃しているのに、たかだか50年も見つめられない人々が本質的でない話をしている。 奇妙な中世人を見ているタイムトラベラの気分。 世界史の本質である。 年号を覚えることは意味がない。 わたしはゲルマン大移動がいつだったかさえ知らない。 というか、ゲルマン人は西暦なんて知らなかったし。 そうそう、それは”言葉の力”を持っていない。 たんなるデータだ。 試験の作り方が悪いのである。 法律は多くの人にとっては無味乾燥なもので、しばしば理解できないようであるが、ちょっと理解のポイントを間違っていないだろうか? あなたの指摘は”言葉の力”があるだろうか? 条文集にある条文というのは、いわば野球のルールブックみたいなものである。 ボックススコアだって、たんなる数字だ。 大切なのは、その向こうに広がるグラウンドであり、松井のバッティングであり、試合の空気であろう。 特許法の35条(職務発明)は、日本の技術開発のほとんどすべてに影響する条文であり、最近大激論になり、判決も大量に出て、今年はそこから試験問題が出るだろうと言われていて、改正があったばかりだが、たった40行ぐらいしかない(ん? 60行はあるか? まあ、改行位置によるのだが)。 教える側もネタが大量にあるもんだから話も盛り上がり、わたしもその伝え聞いただけでも2時間ぐらいは話せそうな状態だ。 これは野球のストライクゾーンを巡って過去の名勝負を振り返りながら野球マニアが語り合っている状況に等しい。 ルールとはそういうものだ。 サッカーのオフサイドに合理性などあるだろうか? 法律の改正法解説書を読めば、なぜ法律が改正されたか書いてある。 以下は平成18年改正法解説書の意匠法の存続期間を15年から20年にした理由を述べた部分である。「特許権と意匠権は、発明や意匠について、創作を保護することに共通する面があるが、発明は、あまりに長期間の独占権を与えることにより、技術開発を通じた技術の向上を阻害するおそれがあるのに対し、意匠は、審美的な観点から保護されるものであるため、存続期間を長くすることによる弊害は比較的小さいものと考えられる。 一方、意匠法では、美感を起こさせるものであれば、機械器具等の物品の機能や技術に関連する形状等も対象としており、特許権の存続期間と大きく乖離することは適切ではないと考えられる。また、出願人間の公平性の観点からは、意匠権の存続期間を20年を超えるものとした場合には、改正法施行前にされた出願と施行後にされた出願で権利期間が大幅に異なることとなり、改正前における権利期間の保護を受ける出願人と比較してバランスを失することとなるのではないかと考えられる。 この点、特許庁が実施したアンケート調査(有効回答件数505件)においても、存続期間の延長が必要とする企業のうちの約7割から、20年が適切であるとの回答が得られたところである。こうした観点から、意匠権の存続期間は設定登録の日から20年とした。」 ぶっちゃけ、最終的にはアンケートで決めているのである(笑)。 合理性なんて、これっぽちっもないんです(笑)。 法律は生きていて、そのつどそのつど、都合が悪くなるとバランス調整する。合理性はなく、妥当性がある。論理と論理をぶつけて妥当にいたる。裁判には必ず両方に言い分がある。 法の彼岸に絶対の解はない。 もしオフサイドに合理性があるのであれば、それは「サッカーが面白くなるから」「これまでそうだったから」というのがもっとも合理的な誰もが納得できる理由だろう。 なんで、オフサイドがあるとサッカーが面白くなるのだろうか? 点が入りすぎないようにとか? ここにサッカーマニアが入ってくると、1934年のイタリアW杯が出てきたりしてめちゃくちゃな議論になる。あの大会からサッカーがつまらなくなった! とか。 法律試験は全てを見渡してからじゃないと合格できないところがある。 法律が無味乾燥に見えるのは、その周りで活躍するプレイヤーを描いていないから。 しかし、ビル・ジェイムズがボックススコアに文学の薫りを感じられるように、法律も読み込めば、”言葉の力”を感じられるようになる。 だから、もう一度、自ら拒絶の壁を作っていないか、振り返ってみてはどうだろう? 短絡的に勝手な理解をして、数学はつまらないと決め付けるのは、こんなのは社会では使わないと決め付けるのは、人生の時間の盛大な浪費である、これこそ無駄だ。 わたしもたった一年でここまできた。 法律試験のいいところは”言葉の力”が見えるところまでやりこまないと合格できないところだ。一度見えれば、もうあとはずっと一生見える。 特許法で日本の仕組みが分かるし、条約で世界の仕組みが分かる。 硬い壁に頭を打ち付けていても、痛いだけだ。 受験勉強も、正しくやれば楽しいはず。 ”言葉の力”を感じられるようになれば。 ■これまでのエントリー 受験がはじまる日 http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200605290000/ 日本で屈指の難解さを誇る文章・・・。 http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200608190000/ 知性のある世界と、そうでないのの残酷な差 http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200610190000/ 知性で瞳をらんらんと輝かせる子たち(今のところ、想像の産物) http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200611070000/ 難解な試験 http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200701130000/
April 17, 2007
コメント(0)
-
銀の弾丸が発明されにくい理由 → 発明者は頭がおかしいから
タイトルのようなエントリーを書こうと思って、面白い記事にであう。 ■デスマーチが起きる理由 - 3つの指標 非常に長いのだが、googleで銀の弾丸で調べるとトップに出てくる文章だけあって、中身は非常に濃い。 簡単に引用すると、開発者が努力して、作業を効率化したとします。すると、その開発者は普通より早く仕事が終わりますから、少し手が空いた状態になるんです。ところで、『分業が進んでいる職場では、プログラマがプログラミング以外の仕事をすることは許されない』ため、他の人の仕事を待つ必要が出てきてしまいます。憶測でコードを書くことも出来ますが……『仕様が決まっていないのにコードを書いても、どうせ作り直し』になります。やるだけ無駄です。さて、暇そうにしている開発者の元に、次の仕事が回ってきます。開発者はその仕事も片付けます。ここで、『より多くの仕事が回ってくるようになっても、それに比例するほどには評価は上がらない』点が問題です」 が問題で、要は、 「効率化している人ほど鬼のように仕事が降って来る」 ↓ 「効率的な人から辞めていく」 という事なのだが、これはわたしが経験したことでもある。 これにはもうひとつ追加したいことがあって、これが本旨であるが、 「効率化は、基本的に発明であり、発明というのは本質的にクレイジーであるから、普通の人には理解できない」 ということだ。 これから非常に長い文章を掛けて丹念に説明していくのだが、この部分が本質だ。 そして結論は、どんなにばかげたことに見えても、それを真似ろ、ということになる。 ■ゲームブック解析の近況 分家のブログで、ゲームブックの解析をしていて、圧倒的な効率化が進む。 どれぐらいの効率化かというと、これまで1冊3時間ぐらいかかっていたのが30分で終わるようになったというレベル。 普通にゲームブックを研究する方法に比べれば、わたしはいきなりグラフ解析ツールを作るところからはじめているので、普通の人に比べておそらく20倍とかいうぐらいは間違えないと思えるほどの効率化である。 わたしが行っているのは非常に簡単で、選択肢をエクセルに打ち込んで、グラフ解析ツールにぶち込んでいるだけ。これでも慣れないうちは3時間ぐらいかかっていたが、徐々に作業フローが改善され、短時間で処理できるようになってきた。 改善される内容は非常にシンプルなもので、キーボードを代えたり、エクセルデータの作り方を代えたり、データベースの更新の仕方を代えたりと、誰にでも思いつくこと。 銀の弾丸の話は、「銀の弾丸は存在しない、だから鉛の弾丸をたくさん撃ちなさい」 という話なのだが、効率化というのは、指の動かし方ひとつで劇的に変わったり、作業を小分けにして行うことにより別のことを考えながらできるようになったりと、本当に地道なことの積み上げで構成されている。 ただ違うのは、その構成の仕方が、その問題独自の構成方法である、という部分だ。 わたしが行っている効率化は、「ゲームブックの解析にのみ有効」なのであって、もしわたしがこれを小説の解析に適用しようとしても、まず間違えなく何の役にも立たない。 これは本質的に、小説とゲームブックがまったく違う構成であるから。 もっとわかりやすくいうと、野球の知識はまったくサッカーに役に立たない。 さらにいえば、キーパーの知識は、ディフェンダーにはあんまり役に立たない。 本質的には、クラブチームでのチームプレイは日本代表のチームプレイには、あんまり役に立たないし、昨日の試合と来週の試合では、これまたまったく状況が違う。 何が大切かというと、「常に状況にあわせ、作業方法を変える方法を身につけること」 つまり効率化=発明の仕方を蓄積すること、という事になる。 まあ、ぶっちゃけトヨタのカイゼンの思想である。 ■一度たりとも同じフォームから投球されることはない 野球を見ていると、ピッチャーが調子のよいときの自分のビデオを見ながら、調子を戻そうとしている光景に出くわす。 これはスポーツをやっていた人には当たり前のことで、フォームというのは常に修正し続けないと同じフォームを保つことはできない。なので素振りはするし、ビデオを見るし、練習中は常にフォームを意識しながら、運動する。 同一人物内でもこのような状況なので、野球のピッチングフォームに誰にでもお手本にできるパーフェクトなフォームはない。 このたとえならわかりやすいと思うのだけど、その人間に適切なフォームがあるだけで、自分の身体や調子に合わせて、適切に対応していくことが大切になる。 プロは、そのぶれを徹底的に小さくしている。 そして、新しい状況に出くわすたびに(怪我とか)、迅速に再構築をはじめ、あっという間に効率的なフォームに戻す方法を熟知しているのである。 ■体育会系が一般的に優秀な理由 わたしが昔バドミントンのとても強いチームにいたとき、とにかくたくさんの人から、ああしなさい、こうしなさいと指導を受けた。 毎日の練習中、試合が終われば、顧問先生のところへ行き、その講評を聞いた。 怒鳴られるときもあったし、ほめられるときもある。 そして、困ったことに、時折その内容が食い違う。 一人の先生でもそうであるから、先生が変わると、まったく正反対のことを言われたりすることもある。それは矛盾しているのではないか、と思う人もあるのだろうが、さていったい、どのように吸収するのが正しい姿勢なのだろうか。 答えは全部受け入れること。 一見矛盾しているように見えても、 ・単純に自分の理解不足 ・先生が伝え切れていない ・そういう側面もあるということ ・先生の勘違い といったような阻害要因があり、時間がたつと吸収できたりすることがあるからだ。 この吸収の過程に至るまでに、その教えを捨ててしまうと、なんの役にも立たなかったことになる。また吸収の仕方が悪いと変な方向へ行ってしまう。なので、体育会系である程度上達した人というのは、吸収の仕方だけは覚えている。また、先生を選ぶことも上手くなる。 体育会系の人は、小さいころから教わる訓練を受けているようなものなので、教わり方や盗み方に長けている場合が多いのだ。 決して、一般に体育会系的と言われるやり方が正しいわけではない。 ■長嶋監督が教え下手なのはなんでだろか? しかし、一般的に一流選手であったからと言って教え方が上手いわけではない。 これはなぜかというと、そういった選手は、自分独自の、自分にしか適用できない自己解決手段の膨大な積み上げで成立しているケースが多いからだ。 他人の真似できない方法でやれというのはよい言葉だけど、本当にまねできない方法で構築してしまっている場合がしばしばある。 しかもそういった方法は、非常に効力が大きい場合がしばしばあり、多くの選手はその強みに磨きを掛けていくので、さらに真似できないものになっていく。 発明者というのは、しばしばこういう人間であることが多い。 よい記事があったので紹介しよう、典型的な発明者というのは、こういう人である。 ■ 時速500kmの未来列車エアロトレイン開発者、小濱康昭 仕事柄、発明者の話を小耳で聞いていることが多いのだが、しばしば、この人頭がおかしいなと思う。もちろん、そういう人の話を特許にするのが仕事なのだが、話半分で聞いている限りは、どういう頭の構造をしているのか、理解できないことがほかの分野に比べて圧倒的に多い。 Web屋さんをしていて、クリエイティブな仕事だっただけに、風変わりな人は多かった。 エンターテイメント業界はユニークな人間の集まりのように見えるが、ぜんぜんそうではなく、常識的な人々がほとんどだ。たいていは格好だけだったり、面白そうな事を考えるのが好きだったりするだけなのだが、発明者というのは、そういうレベルではない。 明らかに発想がおかしいのである。 発明や、人格がおかしいのではない。 脳みその構造がおかしいのだ。 しばしば、発想順で説明をしだす人があるのだが、それで聞くとさっぱりわからない。 また結論から聞くと、さらにわからない。 そこで、おそらく弁理士はほとんどそうしていると思うのだが、発明特定事項を詳細に聞くことによって対応する。 発明というのは基本的にクレイジーなのである。 クレイジーでなくても発明はもちろんできるのだが、発明を連発して事務所のよいお客さんになって特許もばんばんとる人というのは、クレイジーである。 ■技術進歩はものすごく小さな奇の積み重ね 一般に技術の進歩というのは小さな改良で行われているように認識されていると思う。 もちろん、一つ一つの発明は小さい改良なのだが、それがたとえば、エアロトレインのダンパー部に使用する複層皮膜の縫合方法、みたいな物だったりする。よくよく考えてみると、ほかの分野でも応用可能、みたいな。 すごく小さい発明ではあるのだが、特許事務所に持ち込まれるものというのは、本質的な奇であるのだ。 そういう奇が無数に集まってひとつの製品になる。 よく見つめてみると、世の中というのは不思議にできている。 わたしがゲームブックの研究をしているのが、かなり奇妙に見えるように、工学の世界の正しい態度というのは、一般人から見ると奇人にしか見えない。 ■完成された発明が奇であれば、そこに至る過程はもっと奇 特許事務所にやってくる発明は「完成された発明」である。 つまり、他人が同じようなものを作ったときにまったく同じ効果が出ないといけないので、試案段階のものがやってくることはない。発明は、長い試行錯誤ののち、完成されてから、特許事務所へやってきて、噛み砕かれて明細書になり、特許になる。 なので発明されている最中は、さらに意味不明なものであることが多い。 そう。やっと、結論に近づいてくるのだが、効率化というのは、この発明中の状況にきわめて近い。 毎日のようにフローをカイゼンし、次第にマニュアルに落とせるレベルまで完成されていく。つまり効率化の作業というのは、基本的にクレイジーな発想の連発中であるのだ。決まりきった効率化手順があるわけではなく、論理的でもなく、本質的な試行錯誤であることが非常に多い。 これが毎日つみあがると、どう考えても頭がおかしいとしか思えない方法で作業フローを作っていたりする。そして、マニュアルを作ると、理解できないと言われる。明らかに20倍の効率化が保障されている方法でも、誰も真似をしようとせず、その効率化をしている人のところに、ばんばん仕事を投げることの方を選ぶことが多いようである。そして効率的な人は誰にも理解できないマニュアルを残して辞めていく。 銀の弾丸が発明されにくい理由はここにある。 ・まず発明する人は、頭がおかしい。 ・せっかく発明しても誰も理解できない。 ・というかそもそもそういう人は銀の弾丸を必要としていない。 ・論理的に説明できない発明は、なぜか通用しないものと考えられている。 ・合理化を、効率化と勘違いしている。 (合理的→ロジカル 効率化→クレイジー) グーグルが強いのは、ラリー・ペイジが本質的に発明者で、サーゲイ・ブリンが理論家で、エリック・シュミットが経営者であるからだ。 グーグルがクレイジーに見えるなら、それはとても本質を見抜いている。 おまけ:ちなみにゲームブックの研究は特許文献のグラフ構造解析に繋がったりするだとか、誰も見てないだろうから書いておく。遊んでるんじゃないんだよ(笑)。
April 4, 2007
コメント(0)
-
著作権保護期間は、150年にでも500年にでもできる、ディズニーが存続する限り。-ディズニーCEO語る
米国の不埒極まりない著作権法ですが、ついに大手メディア最高責任者より、本音とも言える発言が飛び出しました。 著作権法の、保護機関はTRIPs協定が定めるとおり、原則として著作者の死後50年というのが国際合意です。しかし、米国をはじめ、著作権者(著作者ではない)の圧力が強烈な欧米では、その圧力団体の暗躍により、70年、96年と、保護期間が切れる寸前にどう考えても公正ではないだろうと思われる札束で政治家のほほをたたいた圧力活動により、これまで延長されてきました。 日本の文化庁は非常に賢明でもありながら、しかたなしに米国の圧力に屈し、映画の著作権に限っては70年に延長、これをめぐってさまざまなさまざまないざこざが起こりましたが、結局、延長されてしまったのです。 しかし、このディズニーCEOの発言は、今後、著作権が死後500年に延長される可能性があることを示唆しています。 ようは、年間売り上げ数兆円の企業が、その源泉である著作権を失いたくない、よって、その利益を保護するために、期限を迎えるたびに札束でほほをたたいて、ずるずると延長していく戦術が今後、ずっと通用するだろう、という魂胆なのです。 (注:日本国はキルビー特許事件により、最高裁判決でそのような暴虐無尽は権利の乱用であるという、画期的な判決で拒絶している) まあ、米国の知財意識なんてそんなもんなので、これは反面教師にしつつ、日本国の知財法制がどうなっていくかは非常に興味があります。 映画の著作権が製作後70年というのは、国際法規上、まったく根拠がありません。ようはディズニーの著作権500年間保護戦術に、馬鹿みたいにほいほいと乗ってしまっているという、そういう間抜けな状態なわけです。 今回のディズニーCEOの発言はそういった状況を、端的に表しているということができます。「聖書は、キリストの言葉を弟子たちが書いたものだ。だから、その著作権はキリストにあり、弟子たちは著作隣接権者と言える。聖書の同一性保持権を考えれば、著作隣接権の保護期間は3000年ぐらいがだとうではないか。それが文化を守るという意味だ。われわれもミッキーを聖書につぐ聖典に育てたいと思っている」(注:かなり適当に書いていますので、法的な突っ込みはなしで) 最近、キリストの著作権の相続人がいるのではというナショナル・ジオグラフィックの調査が激しい攻撃にさらされている背景には、このような「聖書の著作権問題」が存在します。 これまで、不当に複製されてきた聖書の著作権侵害者に対し、その相続人が損害賠償訴訟を起こすのではと、業界は色めき立っています。 まあ、米国はサブマリン特許のように、保護期間を過ぎた後に、「しまった! これはおれの権利だった!」 と気づいたときに、その権利行使を認めてしまう非常にスイートな法律がありました(現在はさすがになくなった)。この法認識を当てはめると、聖書の著作権の正当な相続人が、何千年もの闘争を経て、ようやっと著作権者の相続人だと認められた瞬間、それを行使する期間を担保するという思想の元、損害賠償をし、勝訴する可能性も非常に高いというのが、なんでもあり国(<つまりめちゃくちゃ)アメリカなのです。 (エイプリルフールは、こうなかなか言いたくてもいえなかったことをテキトーに書けるのがホントいいですね。)
April 1, 2007
コメント(0)
-
しっぺ返しの戦術を強制発動させてしまう人々
囚人のジレンマという著名な実験があって、その中で最強と言われるしっぺ返し戦術というモノがある。 協調か裏切りかを選ぶゲームで、最初は常に協調を選ぶのだが、相手が裏切った瞬間からその後は常に裏切り続けるという戦術だ。普通に誰もがずるいことを考えずに協調し続けていればみんな幸せになるのだが、誰かが一度でも裏切った瞬間から、その者に対して常にダメージを与え続ける行動をし続ける。 もう本当にオン・オフの二種類しかなく、一度オフになったら永久にオンになることはない。 わたしも結構ネット生活は長いのだが、ネットで生存する最良の戦術はこのしっぺ返し戦術であるように思える。もちろん誤解はあるので、オフに切り替える瞬間を図るのは慎重にやるのだが、そのオフに切り替える瞬間に最大限のダメージを与えるように計算する。 わたしはネットでなにをやるにしてもしっぺ返しでダメージを与える方法を担保せずに何かをすることはない。 陰険と言うよりも、用心深いと言うよりも、そうしないと生存できないと、単純に思っているだけなのだ。 しっぺ返し戦術とは基本的には、無制限の協調戦術であると言える。 普通なら、常識的には、よほどのことがなければ、まともな世界なら。 しかし、残念なことに、このしっぺ返しを発動させてしまう人に出くわす。 慎重に、一週間とか一ヶ月とか一年とかかけて状況を見るのだけど、それでも巧妙に裏切っていることに気付いて、わたしはしっぺ返しを発動させる。 瞬間的にダメージを最大化させるが、それでその存在が死んでしまうこともある。 世の中、しっぺ返しを食らわずに裏切り続けることが出来るとでも思っているのだろうか? 本来なら許されるべき事ではない。 パソコン通信時代、わたしも行儀の悪いことをして、しっぺ返しを食らった。 それ以降、裏切り行動が得にならないことを学び、同時にしっぺ返し戦術を覚えた。 基本的に、裏切りがない限り、その場は協調行動以外の行動はない。 だから非常に生産的なのだが、ときたま常識がない行動をする人に出くわすことがあり、そこにいる全員がしっぺ返しを発動する。これは結構壮観で、瞬間的にぼこぼこにされているように見える。しかし、実際にはしっぺ返しの発動時期が人によって異なるため、即座にしっぺ返しをする者もあれば、それはまだはやいだろうと宥める人もいて、全体がもみくちゃになってその裏切った人物が今後どのような行動を取るかを見極めるように動いていく。 もし、全員から見捨てられれば、最終的には誰からも相手にされなくなり、常に苦痛を受けるようにされるのだが、そこまで至る人物はまれである、というかわたしは見たことがない。 たいていは、どこかから協調関係を結ぶようになるか、去っていくかである。 もし、それを怖いというのであれば助言がある。 裏切りさえしなければいいのだ。 もう一言踏み込めば、裏切り続けなければいいのだ。 もう一言いうか。 どうしたらお互い助け合えるのだろうかを、考え合えばいいのだ。 たぶん2000年ぐらいからだと思うが、ネット上で、どんなに裏切ってもしっぺ返しを受けることはない、という、スイーティーな風潮を持つ人々が現れ始めた。 わたしはサービスを提供する側だったので、目を光らせることが職務になったのだが、コミュニティに1000人もいれば、悪い人は必ず1人はいる。職務上、それに対応しなければならなかったが、この際、重要だったのは確実にしっぺ返しが届くようにしておくことだった。 インターネットというのは、基本的にはしっぺ返しが効果的に効く仕組みでない。 なので、ネットのオプティミストには、軽蔑の念を送る以外にないのだが(まあようは、スパマーを許すネットでどうすんの? という話だ)、どうも最近、その病的な思考が現実社会の勘違いになりつつあるのがちょっと怖い。 裏切れば必ずしっぺ返しを発動される。 そのしっぺ返しは、発動した個人の意志なので、それをおかしいというのはおかしい。 しっぺ返しは主観で発動され、客観ではない。 一度発動されれば、二度と協調にはならない。 それは、個々で見れば、とても正しいこと。 生存行為である。 しっぺ返しをあたかも操作可能な世論であるかのように扱って、それは公正ではないという論理に持っていくのはおかしい。 それは裏切られたという感情を生み出した代償なのです。 ライブドア事件は、たぶんそういう事件だった。 期待が大きかった分、裏切った代償が大きかった。 法の話は、しっぺ返しから見るとたぶんうまくいく。 そして、どうすればしっぺ返しの応酬になる非生産的な社会から逃れられるかということを考えると上手くいく。 ネットで行動しようとすると、どうしても、裏切り逃げを捕捉できず損を見るだけのように思えて、創作的な行動がとれないことを歯がゆく思う。 物語解析系では核心部分がどうしても語れないし、実験も、しっぺ返しを担保するまでは行うことが出来ない(これは今日やっとその方法を思いついた。正直、げんなりする)。わたしはネットのプロだったので、それが出来るのだが、普通の一般的な創作者たちはどうなのだろうと思う。 わたしは昔書いた小説をWebに出すことは決してないし、多くの事件を見ていて、非常に暗い気持ちになるする。 どれほどの価値が失われただろう。 どれほどの信頼が失われ続け、致命的な流血が続いていくのだろう。 急速的に連結していく世界は加速度的に、本質的な価値は失われている気がする。 それはたぶん現実世界の文化的にも、致命的なダメージを与え続けている。 どうしたらいいんだろか。 悲観的ではなく、とてつもなく前向きにそう思い、しっぺ返しを軽視する人々に、軽蔑を送る。 現実を見つめよう。 そして実効を考えよう。 ニコニコ動画の事件を見ていて、発動されたしっぺ返しをよく見つめる。 協調する見込みがないことに対して、遮断をすることは非常に正しい行為である。 そのつけは、たぶんトラフィック回線料で払うのだろう。 著作権はどう始末をつけるのだろうと、人ごとなので、ぼんやり思う。 その協調を失ったことに対して、敵対心を持っているような発言を見て、ちょっと深刻になる。 この人たちは、一生協調することを覚えることはないのだろうか、と。 しっぺ返し戦術がどうやら正しいらしい、この宇宙で。 PCT(特許協力条約)を読めば=TRIPs協定を読めば=WTOの精神を読めば=GATTの条文を読めば、これはすべて分かる。 つまり、国際的な経済の関係は、すべてこの法体系にある。 経済をやるなら、最低限読んでいてほしい。 この枠組みが、制裁規定、つまり、しっぺ返しの規定がすべてであることを理解すれば、たぶんとてつもなく理解が早い。 そういうことをいっている人を一人も見ないので、悲しくなるのだが、これが、世界秩序の聖典である。 世界の秘密のほとんどすべてである。 条文自体は一冊の文庫本以下の文章量。 マスタコード中のマスターコードである。 半年あれば、全部理解できる。 あとはおまけで、たとえば、プリンタードライバーみたいなものだ。 これを考えた、アメリカ人はノーベル賞では足りないぐらい、神に近い、賞賛と名誉を受けていい。 わたしは尊敬する
March 23, 2007
コメント(0)
-
コンピュータと仲良くしましょう。
分家ブログの方で進めているゲームブック解析が軌道に乗り始める。 もう何ヶ月も壁にぶつかりっぱなしだったのが、わたしの技術的向上によって、拡大路線に入れる局面に入った。スムーズに進展し、毎日のように新しい成果が出る時期ほど楽しいものはない。これまで全く先が見えず、五里霧中であったのが、毎日のように画期的な拡張アイデアが浮かんでくる。 柔軟なグラフ構造解析アルゴリズムのお陰である。 書くのに数週間かかったたった300行のphpが劇的な進展をささえている。 ここ二週間、わたしはハッピーだ。 そのせいで、本家がおろそかになっていることは、一応、謝っておくけど。 今やっているのは、ゲームブックのグラフ構造解析で、単純に以前わたしが紙とボールペンを使ってゲームブックと樹形図を書いていたのと全く同じである。 しかし紙とボールペンには限界があって、ある仮説により表現方法を変更するといったような変更が入った場合、まっさらからもう一度図を自分で書かなければならないという、致命的な部分がある。 コンピュータを使用した解析では、データを格納するデータベース、解析するアルゴリズム、画面表現する描画エンジンに分業され、例えば表現方法を変更する際に、データベースのデータを変更する必要はない。 紙はそうではない。 多分これが紙とディスプレイの決定的な差である。 文学論でも、歴史でも、おそらくこのコンピュータ解析の洗礼をうけずに済むことは難しい。プログラムができない文学論者は次第に淘汰されていくと思う。 単純な話なのだが、同じ知識、同じ知性を有する2人の文学論者があった場合、プログラムができる/できないの差異があれば、5倍程度の生産性の格差ができると、わたしは思う。 これは単純に演算速度の問題で、人間がやるべきことと、コンピュータがやるべきことの切り分けの問題であって、人間性とか文学性とかそういう問題ではない。 以前、平家物語を研究している文学部生と話して、平家物語の中にある宗教的文言の数を調べたという話を聞いたことがあって、わたしは、当時絶句した。 OCRでデジタル化して、正規表現でしょ! 普通! 平家のプレーンテキストなんてありそうだし、ないならば文学者連中の(というか学会の)その常識を真っ向から疑わなければならない。 テキストさえあれば、わたしなら2日だよ、その研究。 紙に書くより、グラフ構造解析プログラムを書いたほうが早いのである。 宇宙論でひも理論をうだうだいじっているより、粒子加速器を建設して原子をぶつけたほうが早いのと全く同義である。 コンピュータが使えるとは、イコール、プログラムがかけるという意味。 これはわたしにプログラムを勉強しろ、ばーか、人生損するよ? と忠告してくれた先輩の受け売りではあるが。 アルゴリズムは発展する仮説により、毎日変更される。 つまり、自分で書けなければ、仮説→実証の世界では、なんの役にも立たないのである。 研究に厳密な意味でのルーチンワークは、存在しないでしょ? コンピュータの英知が最も早くやってくるのは法学だと思う。 ビジュアルスタジオライクな、コードジェネレータ(ただし読むだけだけど)があれば、生産性は10倍ぐらいになることはうけあいだ。 これは特許法を勉強しながら、何度も真剣に考えた。 知財法は非常に難解だというが、わたしが把握している総文章量を考えても、プレーンテキストで10MBを超えることはない。 原稿用紙5000枚ぐらい。 ただし、人類の英知のつまった5000枚であるが。 ああ、そうか。 たぶん、ギボンのローマ帝国滅亡史ぐらいの文章量である。ただ、難しいのはそれが特許法なら6層、実用新案法は3層、意匠法が3層、商標法が5層、不正競争防止法が2層、著作権が4層と多層化してそれがグラフ構造的に密接にあちこちでリンクしているというのが複雑さの原因で(おっと、TRIPS協定と判例を忘れていたので、全+2層で)、これはテクノロジーで超えることが出来る壁だ。 法律は、Windowsのコードに比べれば、極端にシンプルで、構造化され、常にメンテナンスされ、洗練されている。 ただ、われわれにはビジュアルスタジオがないのである。 使いやすいGUIが登場すれば、こんな簡単な事をうんうんうなっていたのかと、みんな気付くようになる。 大切なので繰り返そう。 データベースと、解析エンジンと、描画エンジンの切り分けだ。 法文は、全部が一緒くたになっていて、操作が出来ないのですなあ、これが。 この観点から言うと、人類はまだコンピュータと仲良しではない。テキストマイニングとかの研究を見ていて、何をしているのだろうと思う。グラフ構造解析の研究を見ていてそれは意味があるのだろうか、と考える。 だから、わたしは助言する。 法律をやると、たぶん道が開ける。 ここが一番仲良しなはずなのである、本質的には。 ゲームブックの研究は、以前書いた、RGNのセミナーでの川邊氏のプレゼンに勇気付けらたことを書いておく。 ■六本木のゲームシナリオ研究会に参加してきました! http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200612140000/ わたしはこの当時、紙とボールペンで研究を進めいていたけれど、川邊氏の言葉を聴いてぱっと目の前の景色が開けた気がした。 わたしだけが興味を持っていたニッチだと思っていたものが、突然大洋につながっていたことに気付かせてくれたプレゼンであった。 まず、感謝の言葉を。 勇気を頂きました。 続いて、決意を。 絶対ものにして見せます。 わたしは覚えている。「分岐の構造は、作家の文体である」 わたしはその言葉にこう付け加える。「判断のポイントは、作家とユーザの接点である」 選択肢によって、作家とユーザはコミュニケートする。 わたしの定義によれば、「ゲームとは判断を楽しむために作られたもの」 であり、ゲーム性とはユーザに判断の楽しみを与えることであるから、選択肢が実はゲームブックの本質なのである。どれだけそこで判断を楽しめるか。これが本質だとわたしは思っているのだ。 その集大成であるゲームブックの解析は、非常に有意義で、興味深く、発展性があり、そして、わたしを夢中にさせる。 知財法はよい。 だれかビジュアルスタジオライクを作って、わたしに1万円ぐらいで売りつけてくれればそれでよい。 物語は、誰も革新をする人がいなさそうなので、わたしがやる。 今日、はまろぐさんのエントリーが非常に面白くて、夢中になって読んだ。 ■続・ファンタジーの世界設定に考証の正しさは必要か? http://blogs.dion.ne.jp/hamalog/archives/5223081.html どれだけわたしの、 「書きたいぞ!! 書かせろ!! うわー、書きてー!!」 心に、ぴゅっぴゅと水鉄砲で攻撃を受けたか知れず、書きっぱなしで放置してある、ゲームブックを完成させたい気持ちに駆られる。 うっひっひ、すごいのいくぜ、ちょいとお待ちを。 1月ぐらいお待ち下せい。 一応、知財法の勉強もしているので、念のため。 PCT辺りなんて面白いので、ちょっと書いてみよう。 22.1 手続き (a) 第11条(1)の規則に基づく決定が肯定的である場合には、国際出願を国際出願として取り扱うことが国の安全に冠する規定によって妨げられない限り、受理官庁は、国際事務局に記録原本を送付する。その送付は、国際出願の受理の後速やかに又は、国の安全を保持するための点検が行われなければならない場合には、必要な手続きを経た後できる限り速やかに行う。受理官庁は、いかなる場合にも、優先日から十三箇月を経過する時までに国際事務局に到達するように記録原本を送付する。受理官庁は、その送付を郵便で行う場合には、優先日から十三ヶ月を経過するときの五日前までに記録原本を発送する。 非常に重要なPCT規則の一部なのだが、こういう規則が500個ぐらいあって、ようやっと国際的な特許秩序が守られている。 まあ、先は長いよ(笑)と思いながら勉強する。
March 9, 2007
コメント(0)
-
森進一氏と川内康範氏の攻防の本質
短く言います。 著作権の問題ではないです。 著作権は、不正な行為に対して抑止力として働きます。 現在、実際に実効力のあるのは、著作者による、差止請求権。 著作者人格権による侵害行為は、実はこのケースでは法律的な論理から全く外れています。 意味なし! 知識人は、よく周知のこと。 ここをこねても、仕事になんないんですよ? 著作権は、著作をしたことが偉い、すばらしい、それが社会の富だ、という部分から入り、だけど、いろいろな使い方には許してあげましょう、という論理体系です。フェアユースを訴えるGoogle組はちょっと法律に甘えています。根本的には、知財法は権利者を守るための法律です。 ただし、権利者が横暴になるのを防ごうとしています。 だから、著作をした人のおこぼれで、自分は生かされている、という意識を持つことはとても大切。新しい知財を作った人に対して、敬意を払うことは非常に大切。単純に、先人に対する敬意が大切です。 もちろん、それによって、新進の人々が新しいチャレンジが出来なくなることは非常に困ります。これは老害です。 しかし、敬意を持って問題に望んでいるでしょうか? エジソンを尊敬するように、川内氏を尊敬しているでしょうか? 世界は先人の上に成立しており、それを無視して、学ぶことなく強奪することによって発展するとは、とても思えない。 知財法というのは、敬意の法だと思う。 わたしが買って読んだ本のすべての先人たちに、ありがとうと言う。 あなたがたがいなければ、わたしはこんなに学べませんでした。 法文集を読みながら、こんなに、厳格でフェアな法を作り上げてきた人々を誇りに思う。 新しい時代に合わせた法改正は任せてください。 きっとすばらしい法秩序を考え出してみせます。 これからは、ぼくらの時代だ。 どうしたら、いい世界を作れるのだろうか? 30代のぼくらの世界でなく、80代の川内氏も頷いていくれる世界を。 そして、5才の次世代の子達にも、幸せが訪れる世界を。 ぼくが今見るニュースは、とても狭隘で、わたしの世代しか見ていないような、ぞっとする、近眼的な世界にいつもある。 はてなの近藤さんは、今迷っているように思うけど、みんなを幸せにしたいと思っている。 それはどうしたら叶うだろう? すごいたくさん、いろいろな世代の人に会うといいと思う。 悪いけど、2010年までのネットの中心は、団塊世代になりそうでありそうであるのだ。 キーボードをどう打つんだろ? マウスはどう使うんだろ? 毎日、テレビは、何を見ているのだろう? これは簡単! その世代の人と一緒に暮らせばいい! 聞けばいい! そこからネットで解決できそうな、問題が浮かび上がってくる。 簡単! 簡単! ふつうに、いろんな世代の人と話せばいいんですよぉ! 頑張ってちょうだい。 話がずれた・・・。 法律的には、JASRACは差止請求権に関しては訴権を持っているので、これは自由自在。著作者人格権は、当たり前の話だが譲り受けていないが(<譲り受けていれば超問題だが)、それをちらつかせると言うのは、非常に深刻な状況なわけです。 つまり、森氏はそれをちらつかせる以外ないような状況に、著作者を追い込んだわけで、著作者サイドからすると、かなりいやらしい。 ここはVSな状況なので、安易な言葉を避けるけど、普通だったら、こんなにこじれないのではないでしょうか? 普通に敬意を払っていれば、普通にお許しが出たような。 普通でしょ? インフレーションというか、バブリーな、マッシュアップ思考は、盗賊意識がないことにちょっと危機感を覚える。 挑戦はがんがんしてください! ただ、キミは全能の神でないことを理解してください! しょせん、先人の知恵の集積を、整理しているだけと思ってください。 しかし、それは有意義な仕事です。 先人に、敬意を払えばね。
March 8, 2007
コメント(0)
-
プロイセンの歴史読了、アル・アジフ・・・、もとい! 「技術論」がやってくる。
クトゥルフ神話で著名なラブクラフトの評論に「文学と超自然的恐怖」という書籍があり、ホラーという分野を語る上では、外せない。 ラブクラフトという人物は1920年代の米国作家であるが、現在の日本人が米国ホラー作家というとスティーブン・キングを想起する人が多いだろう。米国ではモダン・ホラーに分類される作家であり、それ以前がゴシック・ホラー、ラブクラフトは特別にコズミック・ホラーと言われている。 ただ、恐怖小説という漢字にしてみると、これらは微妙にニュアンスが違い、キングが代表するモダン・ホラーは、厳密に言えばダーク・ファンタジーである。 日本のホラー作家は、厳密にはダーク・ファンタジーの系譜を引いている。(ちなみに夢野久作はドグラ・マグラに代表される自作を探偵小説といっている。怪奇小説→ポオ→江戸川乱歩→探偵小説という流れである) 文学としての恐怖小説とは何かといえば、ラブクラフトの該当書を引けば足り、その冒頭に、「人間の感情の中で、何よりも古く、何よりも強烈なのは恐怖である。その中でも、最も古く、最も強烈なのが未知にものに対する恐怖である」 としてある。 この序説だけなら、創元のラブクラフト全集(多分4巻)で読める。 全文は、絶版の定本ラブクラフト全集にしかないと思われる。 序説以降はホラー小説史を執拗としか思えない毒舌でばっさばっさと切っていくのが永遠と続いているだけなのだが、何せ恐怖小説研究家だったんだろうなあ、と思われるラブクラフトであるから、怪しげな伝承やら神秘主義やらの原初から始まり、精密な考察を続けていくので、興味がある方は手にとって欲しい。 今日たまたま、日経夕刊において高橋源一郎が、文学についての長文コラムを載せていた。偶然にも1920年代の文学者たちのエネルギーに触れ、文学のエネルギーはこの時代に爆発していたといったような趣旨を書いているのだが、その中で、現代の次第に難化し、まじめくさり、堅苦しくなって権威になっていく文学についての迷いを綴っていた。 原初のエネルギーという意味で、この時代は何があったのだろう、と思えるほど、分類化されず、本質を追い求め、複雑化しておらず意味が明確な時代は珍しい。 しかも、なぜだか分からないけれど、異様な勉強家ぞろい。 文明の始まりから考察しているのである。 ■第一次産業革命とIT革命の類似のお話 - FIFTH EDITION http://blogpal.seesaa.net/article/34876648.html 奇遇にも、本日、FIFTH EDITIONさんにおいて、1900年代初頭と現在の類似点についての興味深い考察を綴ったエントリーがあった。 つねづね、最近本質的に、様々なことを再考しなければならないことが多いなと思っていただけに、やはりインターネットの到来が、様々なこれまでの神話を再咀嚼し、新しい時代に適合しなければならない局面にあるのかもと感慨深く読んだ。 プロイセンの歴史を読むに至り、1500年代から1945年までのヨーロッパ史を、いまさらながら把握した。 ドイツは、1871年のドイツ帝国統一によって、プロイセンという強大で厳格で秩序があり強靭な精神的主柱を飲み込むが、それにより拡大志向に歯止めが利かなくなった烏合の衆によるドイツナショナリズムが、二度の大戦の引き金となる。 これは興味深い歴史だ。 このばら色の全世界的産業拡大のバブル狂乱が、世界恐慌となり、大戦に繋がる。 戒めとしよう。 しかし、当時の原初的エネルギーは、今なお読んでも、そのパワフルな理論構成でたじろぐほど強烈である。 まるで、ラブクラフトの作品に登場する原初の知を伝える魔道書ネクロノミコン(アル・アジフ)のようであり、ビックバンのように拡大する新しい無秩序が記載されている。その後、幾度もの反省を経て秩序へと向かうが、この無秩序は現在のインターネットによる知の爆発を連想してしまう。 わたしは仕事柄、現代的特許法の成立過程に興味があるのだが、それを記したネクロノミコンが今日届く。 オイゲル・ディーゼルの技術論である。 発刊は昭和17年(1942年)であるが、ディーゼルエンジンの発明者である、ルードルフ・ディーゼルの息子の作とあり、おそらくじかに接したであろう先人の英知が、ここに数多く記載されている。 引用しよう。「発明とは何か。探求せられたものの終結である」 強烈であり、本質でもある。 このレベルの文章が、所狭しと並んでいる。 しかし、引用を始めると、全ページを引用しそうになるので、重要な、ルードルフ・ディーゼルの長い言葉を引用して、わたしはこの本を読み始めることにしよう。「理念だけでは発明とは絶対に言えない。発明品の目録から何でも取って見るといい。望遠鏡でもマグデブルグ半球でも紡績機でもミシンでも蒸気機関でも。発明と言われるものは常に実行された理念だけである。発明は決して純精神的な産物ではなく、理念と肉骨の世界との闘争の結果にすぎぬ。それ故にどんな完成せる発明にも、同じような思想は多かれ少なかれ確実に意識的に、時には既にずっと以前に、他の人々の念頭に浮かんでいたことを○○(旧字体のため不明。推測?)立てることができる。 理念と完成せる発明品との間には、発明行為の本来の仕事と苦難の時間が存在する。常に天翔る思想の小部分しか肉骨の世界に押し付けることは出来ないし、又常に、完成せる発明品は、本来精神が見た、決して達しえぬ理想とは全然別の相貌を呈する。それゆえいかなる発明家も未聞の不評を受けながら理念や計算や実験に従事する。何かに達せんがためには、多くのことを欲せねばならぬ。最後に残るのはその最も小部分である。 従って発明する、とは、無数の誤謬の皮を剥いで取り出した正しい根本思想を幾多の失敗と妥協を経て実際的成果に帰すことである。 それ故に発明家は楽観主義者でなければならぬ。理念の力の全衝撃力は創造者個人の魂の中にだけあり、この者だけが実行の聖なる火を持っているのである」 ぼうぜんとするような名文である。
February 28, 2007
コメント(0)
-
著作権者が何を怖がっているか、は、おれおれ詐欺を考えると良く分かる
著作権の問題で、どうしても消えないおかしな理屈が、沈んでは浮き、沈んでは浮くので、何がいけないかを書いてみたい。 ちょっと暴論になることまず謝りたい。 ただ、皮膚感覚的には非常に似ているので、ここで並べることを許して欲しいのだ。 多分、この感覚が分かれば、オープンソースVSマイクロソフトで何が対立しているかが分かると思う。 また、多くの知識人が超えられない壁というのもここにあると思う。 YouTubeが生存を許されているのはなぜかという理由の解明にもなると思う。 著作権をはじめとする知財問題でこれほどまでにごちゃごちゃになっているのは、多分この問題に集約する気がする。 著作権者がNOと言えば、NOであることを、NOと言ってはならないのだ。 また、先走って、結論を言えば、著作権者がNOと言えば、著作権者に不便さがやってくるように誘導するのが解である。不便さを許容するか、YESというか。YESを強要するのは強奪以外の何も出もない。 これがどうしても、ほとんどの人に理解できないらしい。 先日、我が家にもおれおれ詐欺がやってきて、いやな時代になったね、という話になった。 どうも、大学の名簿が流出しているらしく、わたしの名前を使ってやってきたというから、うっかりだまされ掛けたという。話を聞くと、どうも同じような手口でやってきた電話が近所にあり、どうも大学だろう、という話しになった。 もちろん、ふつうは騙されるほど馬鹿ではない。 だけれども、そんな電話を掛ける方だって、ふつうの人間が騙されるわけはないと思っている。だから、1日に100件も、10日に1000件も詐欺電話を掛け、誰かが引っかかってくれればペイ、という寸法である。 もちろん、引っかからなければ害はない。 そうだろうか? このわたしの心に染み付いた、この不愉快さはどうしたらよいのだろう? 実家にいちいち電話を掛けるにも、合言葉を三回、それから毎週変わるパスワードを述べてから会話なんて、背筋がぞっとしないだろうか。 わたしの生年月日なんかじゃだめだ。 なんたってあらゆる個人情報は、ゆびとまの件を見れば明らかのように、非合法組織間を流通しているのだから。 この事件が不愉快なのは、電話番号の差し止めが出来ないからだ。 もし、一件でもあやしいと思われ通報されれば電話番号が差し止められるのであれば、おれおれ犯罪団は、闇で仕入れた電話番号に払った金額をペイできない。 そうすれば、1000件もの詐欺電話は掛けることが出来ず、自然消滅すると思われるのである。 わたしは、以前、電子書籍の会社にいて、その社長の言葉が耳にこびりついて離れない。「作家にとって、コンテンツというのは自分の子供のようなものだ。だからその懐に手を入れてうちで儲けさせてあげますよ、なんていうのは、言語道断。そんな大切なものを預かるのだから、銀行などよりも信頼できるパートナーになりなさい」 わたしは様々に、コンテンツ業界を歩いたけれど、その著作者たちが感じている不安感というのは、好き勝手にされるのではないか、という恐れであった。 例えばアニメ業界において、わたしがアニメの販促ページを作ったとする。 そのときに、クリエイターが心配するのは、不当に自分たちの作ったコンテンツがチープに宣伝されるのでは、ということだ。 だから使用する画像等は先方業者のチェック済みのものだったし、加工さえNGのところが多くあった。しかし、販促する側では、お客様にアピールするよう多少の押しが必要になるし、いただいた素材では、十分にアピールできるものが出来そうにないこともしばしばあった。 それでもわたしは、とにかく売ることを優先したので、ばしばしとルールぎりぎりのところで攻めまくる事が多かった。 そうしないと、売れないのだ。 そして、著作者チェックとなるのだ。 これが悩ましい。 一概にアニメの権利者といっても、たいていは数社あるので、それを順番にOKを貰っていかなければならない。しかも、その権利者の中には、自社でWeb展開したいので、わたしのところがおおっぴらに注目を集めて話題になるのを避けたいと思うところがあったりする。 そんなこうごちゃごちゃした権利関係の中で、大胆にどかんとプロモーションをすると、こちらとしては良かれと思ってしても、ぼこぼこに叩かれたりすることもしばしばある。 これはどういう構図かというと、 数社で合同でプロモーション → 一部サイトが突出 → 難癖つけて止める という感じだ。 参加する数社とも、それぞれにビジョンを持っているので、勝手なことをしては困るということなのだ。 この場合、だれかがNOと言えばNOとなる。 だから、だれかが叫んだNOが、効力を発しないことはない。 しかしもし、このとき、「いや、うちはうちの権利を買っているのだから、その範囲内で何をやっても自由だろう」 とそれを押し切ったとしたら、全員が全員で好き勝手なことをし始めたら、みんなのNOが消え去ってしまうことが想像できる。 そうなれば、原作者の希望はないがしろにされ、アニメ制作会社の希望はないがしろにされ、音楽製作者の希望はないがしろにされ、協力していたスタッフたちの希望がないがしろにされる。 誰かにプロモーションの判断を一任し、その人に全権を委ねるのであれば、交通整理が出来そうだが、数社の合議体でこれをうまくまとめきるのは難しそうではないか。 これは特許などでも頻発する問題で、共有に係る権利の問題、として試験に良く出る。 知財法における手続きにおいて、共有に係る場合の原則は、誰が一人がNOと言えばNOである。 知財において、NOと言う権利行使は、最も強い権利行使であり、最低限守られるべき権利なのだ。 ■NOと言える権利は(=差止請求権なのですが)、違法な電話を止める権利と同じ もし、違法な自分の知財の流通を発見したとき、差し止める事が出来ないということほど、怖いことはない。 合法であっても、例えば契約をしたエージェンシーが、契約したんだから好き勝手にしてもいいだろ? というのは、著作者にとっては至極怖いことである。だから、やめて、といったときに、即座にやめる、ということが知財系においては最も大切なのだ。 YouTubeがあれほどまでに違法状態にありながら生存が許されているのは、差し止める機能を充実しようとしている部分にある。 著作者にしてみれば、たとえ全世界に、自作の作品が違法に流通していても、「やめて!」 といえば、全世界の全作品の流通がストップするのであれば、多分、これほどまでにネットに対して恐怖感を感じることはない。 もしくは、ここまではよい、という約束の範囲内で自由に流通するなら良い。 いつまたおれおれ詐欺の電話がかかってくるか分からない気持ちの悪い社会で生活をする事が耐えられないのであって、本当は静かにしていて欲しいのである。 きみんち、おれおれ詐欺の電話かかってきたって、別に騙されてないからいいじゃん? は通用しない。 YouTubeが生かされようとしているのは、いずれ、やめてといえば全部やめてくれる機能を実装してくれるであろうという期待感であり、YouTubeは、YESという事のメリットを大量に提示して、YESといわないと不便だよ? と働きかけているのである。 メリットを提示できなければ、そりゃダメでしょ。 知的財産権は、無体物であって姿かたちのないものである。 わたしが、いまここで、画期的な発明をしたとする。 もちろん、特許は取った。 例えばそれが、画期的な傘のアイデアだったとして、長年の研究の成果だったりする。 わたしの手元には設計図があって、売れることが間違いないとする。 この際、それを「盗んだ」、大手自動車会社(注:かなりありえない例として例示している)が3000億円の投資をして傘の大量生産工場を作ったとして、傘で大もうけする。この際、わたしから盗まれた財産は何だろう? 知財はもともと形のないものであるから、非常に盗まれやすく、しかも、盗まれたことを証明することは非常に難しい。 例えば、画期的な圧縮方法があったとして、それがマイクロソフトのソフトウェアに盗まれて実装されていることを証明することは非常に困難だ。 そういった極めて無法地帯になりやすい状況から、創作者を守るために知財法はあり、差止請求権という極めて強力な権利を権利者に付与するのである。 お金のためじゃないんですよ。 お金のためでもあるんだけどね。 マーケティングの話じゃないんですよ。 金融の話でもない。 知財の話なんです。 創作者が不愉快にならないためにはどうしたらよいか、なんです。 公正なルールでみんなが公正にやるならば、それでやりましょうって話なんです。 創作者を脅かすようなことを言うと、おれおれ詐欺が蔓延しているのだと思って、余計硬化するんです。 権利者は大切に。 http://peer2peer.blog79.fc2.com/blog-entry-275.html
February 26, 2007
コメント(0)
-
FIXの話
昔の仕事で、自分の書いたストーリーに、イラストレータさんの書いたイラストがついた。 仕事として事細かに指定を書いて、あがってきたイラストを見て驚く。 わたしの書いた指定と違うものができあがってきたのだ。 わたしは窓口の人に、これは設定を変えなければならなくなるとクレームを付けたが、時間的コスト的余裕などなく、しかたなくわたしは用意していた物語の一部を破棄して、そのイラストに合うように書き直した。 たぶん、30枚分ぐらいは書き直したはずである。 わたしは共同作業である以上、こういうことは起こりうると諦めた。 そんな中、お客さんから、イラストが物語と合ってないとクレームが付く。 わたしが付けた致命的なクレームとは違い、イラストレータさんの雰囲気が合ってないんじゃないかというクレームだった。 いくら商売でも、そんなことを言われても対応のしようがない。 適当にいなしたのだが、そのときわたしはしゃーないじゃんと諦める以外になかった。 致命的なほどな差違ではなかったし、わたしはそのイラストレータさんに合わせて、物語の雰囲気を変更していたから、差違があると言われれば、わたしの技量のせいでもあるからだ。 ちなみにわたしが付けたクレームは、「この子は外国人ではありません! 名前が明らかに日本人じゃないですか!」 というものだった。 その仕事はゲームの仕事だったので、リアルタイムでお客さんの感想が届く。 進むうちにどうも、キャラクターに心酔した方が現れて、夢に出てきたと、どう考えてもポエマーだろと思える内容の文章を送りつけてきた。 いくら長時間鮮明にイメージして描いていても、書き手の夢に出てくることはない。 ちなみに、送りつけてくる人はA4封筒で20枚とか平気で送ってくるので、A6封書であったそれは、序の口の部類に入る。 わたしはそれを読んで嬉しいというよりも、うーん、という感じだった。 なんとなくドリームが入っているようで、どうしたらこの人を傷つけずに済むかを考えるのが非常に大変だったからだ。 わたしは仕方ないので、その雰囲気に多少すり寄せて、描写でフォローする。 もうこういうのは多かれ少なかれ頻発するので、慣れっこである。 こういうのを全部受け入れて、どうまとめ切るかが勝負みたいな仕事だからだ。 わたしの経験則を言えば、そういうイレギュラーがあった場合の方が、できがよくなる傾向にある。ひとりの個人というのはなんとなく欠落した部分があり、静かにしていて、地道にコツコツやっている人のところにやってくるあらしは、なぜか豊饒を落っことしていってくれる物であると思う。 わたしは、あらしがすぎるとまた静かになる。 そしてまたコツコツとやりはじめる。 Webデザインの仕事をしていたときは、常に暴風雨に巻き込まれたようだった。 ひどいときは毎分のように電話が鳴り、わたしは話を聞き半分、デザインを修正するすべを身につけた。もう、ラフ作りながら、こんな感じ? Jpeg行ったぜ、色男さん、とやり取りしていたりしていた時もある(さすがに、認識あわせが難しそうな場合だが)。 社内FIXであれば、席の後ろに張り付かれる。 こういうのになれてくると、結局、どこで合わせるかとか、FIXのとれそうなところとかを探りながらの仕事になる。 高度に、デザインが必要な場合は、なんとかいいわけをつけて、シャットダウンして一発OKを狙いに行くが、逆に言うとそういう状況になるって事は、あまりにも複雑な利害関係がありすぎて、その辺クオリティでぶちこわすぜ、そこんとこよろしく、という場合であって、結構やばい場合であることが多い。 思いの外、商業ベースのクリエイティブというのは、利害関係者の合意の仕事であって、合意を取るのが最下のデザインまで丸投げになってしまっている場合、わたしのような散々に振り回される状況に陥る。 これは文章でも、デザインでも経験しているので、たぶんなにをクリエイトするかによって左右されることはないと思う。 わたしがWebデザインでよく言っていたのは、「それじゃあ、FIXとれないよ」 という事であり、こうやって文章を書きながら思うことは、自分の書きたいことと読んでくれる人との興味のバランスであり、少なくともわたしが軽い文章を書きたいか、重い文章を書きたいかではない。 だから、この文章のバランスをわたしは支配していない。 書きたい文章が当然にわたしはあって、それを書くこともわたしにはある。 シャットダウン → 一発ノックアウト スキームの文章であり、前述したとおり、このスキームが必要なときは、結構勝負を掛けにいっているときである。利害関係が複雑すぎてがんじがらめのとき、誰もが一発OKを出すクオリティで、文句が出なかった瞬間の隙を狙って、全部のFIXを一気に取ってしまう、豪快な場合である。 この際、ちょっぴりでも、窓口の想像を下回ると(難癖をつける隙を与えると)、ずるをしようとしたかのように、ねちねちとどうでもよいところまでちくちくやられる。 この場合は、一時撤退して、純粋に相手の要望を全面的に受け入れ、どんなにひどい物ができあがったとしても、わたしは一切文句を言わないことにしている。 もう、抵抗しても無駄だからだ。 そして、この場合、相手が敏腕の営業であった時のみ、かちっと火花が爆発するような助言をくれたりする。 辛抱強く話を聞き、適切なところでわたしの感触を伝えていると、次第に、そのクリエイトするべきビジョンが見えてくる。 あれ、この人けっこう勉強してるな、そう思う。 わたしが喜んで協力するタイプはこのタイプである。 これまで、4人いた。 そのうちの2人までが同じ会社だったので、今振り返って、ちょっと驚く。 思いの外という言葉を使うことに、こうやって話してくると、かなり違和感を感じるのであるが、クリエイティブというのは、共同作業である。 普通の企業人が提案書を通すのと大して変わりなく、営業と違って制作サイドはツーカーチームプレイなので、フランクで、クリエイティブである。 対立もあれば、重箱の隅をつつくような話もある。 ただ、例えばサイト一個みたいな小さな制作物が多いので、スパンは短く、失敗しても次で何とかしましょうでごまかせる。 多くのクリエイタ志望が誤解しているのがこの部分で、FIXが取れなければ何も進まないし、あなたのことなんて誰も大切にしていないのである。 うまくFIXを取れる人が、大切にされる。 ただ、まあ、大切にされる=こき扱われるなので、幸せではない。 大切にされない=話も振ってもらえないよりはいいかもしれないが。 Webデザインは、立場の割には極端に安いのが玉に瑕だ。 まあ、Webやりたい人なんていくらでもいるし。 森博嗣さんという著名なミステリー作家がブログを書いていて、その中に「薄い本」というエントリーがあった。 有名なブログなのでちょくちょく拝見し、書店で本をとったが、ちょっとわたしには合わないかなと思ってすぐに平積みに戻した。 今日、そのエントリーを読んで、「今の僕が、薄いスマートなものが書きたい「季節」だ、というだけである」 という言葉に引かれた。 書きたい文章を書くことは、けっこう難しい。 薄いのは、なかなか書けない。 もし何でというのであれば、全5巻ぐらいでめちゃくちゃ面白い漫画って思いつきます? の言葉を投げたい。 わたしはたくさん知っている。 ■【HR】 薄い本 http://blog.mf-davinci.com/mori_log/archives/2007/02/post_981.php
February 21, 2007
コメント(0)
-
有力各紙はアジアをよく見ててほしい
ベトナムに新幹線が輸出されることになって、その計画を見て驚く。 全長1360km、総工費330億ドル(4兆円ぐらい?)、工期は6年、ハノイ-ホーチミン間を10時間という。 日本で言えばたぶん、東京-博多よりながいぐらい(正確には福島まで)。 六年で作っちゃうと言うのだから、どれほどベトナムが元気かよく分かる。 とても大きいニュースなのだが、たぶんこれを読んでいる方は、2/16現在このニュースを知らないはずである。第一報はロイターで2/6、第二報は外国紙2/7、そして第三報以降はなかったからだ。 わたしは職業柄、海外の特に工業関係のニュースはチェックせざるおえないが、日本における新聞各紙の興味範囲が、おそらく製造業関係者の興味範囲と大きく食い違っている気がして、どうしてもならない。 だからわたしは中国紙と韓国紙を読まざるおえない。 両国とも、海外進出に熱心で、ライバル視する日本の状況を見るのに熱心だからだ。 わたしにベトナム新幹線の話を教えてくれたのは、韓国紙の中央日報である。 ロイターの報を聞き、取材をし、まとめたものだと思われる。 日本の各紙はロイターを読んでも、ぴくりとも反応しなかったようである。 これは非常に、感覚が麻痺しているように思う。 世界地図を広げてみて、資源の流れを線で描いてみると、思いの外、その線は偏っていることに気づく。 石油は黄色、天然ガスはオレンジ、石炭は赤、鉄鉱石は緑、銅は青、穀物は紫。 あらゆる種類の資源をたとえば256種類に絞った主要資源をWebセーフカラーの256色で表してみると、この日本という国の、世界の国々の、生命線とは何かが見えてくると思える。 もちろん印刷図面ではそんな図を描くことは不可能に近いが、脳内では可能だし、グーグルはそういうリアルタイム・ビジュアルも追求してみてほしい。 そして、そのほとんどが東南アジアを通っている。 オーストラリアからの便にしても、中東からの便にしても、東南アジアは通らざるおえない。 また、製造業を考えてみよう。 中国を始め、製造業の現地生産シフトが進んでいる。 アジア向けでは中国、インド、台湾。 北米向けは北米で。 欧州向けは東欧かロシアで。 わたしはその状況を見て、製造地の特許法の心配をしてしまうのだが、実際のところ、日本の主力工業企業のシフト先は、フィリピン、タイ、シンガポール、マレーシアと言った東南アジアに集中している(下請けのシフトかもしれないけど)。 一番分かり易いのはIT系で、世界中はインドだ、中国だと言っているさなか、大手メーカはこう言った東南アジア諸国に1次請け以下、つまりオフショア開発を振っている。インドや中国は欧米メーカがすでに押さえていて、都合が悪いのである。 わたしが心配するのは、もう、日本という国は東南アジアなしには生きれないのではないかと言うこと。 もちろん、どの国も何らかの依存関係にあると思うが、日本の東南アジア依存は重度である。 これも中央日報だったか(朝鮮日報かも)、日本のトヨタが東南アジアでの生産のために2万人近い熟練工を派遣し、現地シフトを進めているのを紹介し、これこそが現地シフトであって、下請けのように扱き使うのが、現地シフトではない、と痛撃する記事があったりした。 トヨタだけで、2万人というのは尋常ではない。 すでに、日本の中のコモディティな部分の生産技術は、外に出してよいという時代になっているのだと、思っている。つまり、見せたくないものだけ、国内で作るという寸法。ブラックボックスだけ、日本においておくという考え方だ。 日本だけでは、完成品は作れないのだ。 そんな状況を見ていると、新聞各紙が運命共同体である東南アジアを見ていないことはとても怖い事である。ASEAN+3だとか、非常に威勢のよい大がかりな枠組みには熱心であるが、東南アジアの情勢なんて事はたぶん気を配っていない。 よくソースにする田中宇さんの記事でも、東南アジア情勢が記事になったのはなんと2003年。 結構知らないのである。 東南アジア最大の国家インドネシアはイスラム教徒が大半を占める諸島連合で、先の東ティモールのような民族紛争が多発している。 マラッカ海峡を望む要所にあるシンガポールとマレーシアは犬猿の仲である。 ベトナムはラオス・カンボジアと過去より何度も戦争を繰り返しており、あそこも火薬庫といっていい。 タイは東南アジアの盟主的存在であるが、クーデターが頻発する国で、現在もクーデター中で未遂も併せてこれで17回目だそうである。 ミャンマーは、未だに軍事独裁国家である。 フィリピンは平和だ(笑)。 こうやってみると、決して安定した地域ではない。 グーグルマップでもいいから東南アジアを見てみると、微妙なパワーバランスが均衡したような状況で、おっとおっとと、綱の上でバランスを取りたくなる。 国際的には、中国、韓国、日本、オーストラリア、インドの周辺強国に、アメリカまで顔を出して外枠を作り、その中のASEANを浮き彫りにして、安定しろ、安定しろと、魔法の呪文をみんなでぶつぶつ呟いている。 そういう状況を俯瞰してみるに、この地域にあまり注視しないで、大枠だけを語っている新聞記事を読むと、これはあまりにだめな部分を見つけたときにみんながすることだが、だめだなあ、とため息をつきながら、がっくりくるのだ。 ベトナム新幹線の総工費4兆円のうち、3兆円は日本のODAだけど、知ってますでしょうか、と日本の、特に日経の記者に聞きたい。 中央日報は、日本が莫大なODAを出したから、韓国は手が出せなかったという。 自分の国がすることぐらいは教えてほしい。 ましてや、これほどまでに共存関係が強くなっている地域なのだから。 産経新聞の記事によれば、シンガポールが窮地らしい。 インドネシアが環境悪化を理由に建材用の砂提供の拒否。 マレーシアが河口の埋め立てにいちゃもんをつけ洪水はおまえたちのせいだと非難(ここは毎度のようである。ちなみにシンガポールの水道はマレーシアからの供給に頼ってるらしいけど、大丈夫なのだろうか・・・)。 安定味方だったはずのタイがひっくりがえって、軍事情報を傍受している、文句を言っているらしい。 根底には、シンガポールの富への羨望があるらしい。 それがタイのクーデターで表面化したと。 シンガポールはベトナムシフトを打ち出しており、ちなみに、この付近は1998年の通貨危機、2004年、2006年の大地震で疲弊している。 優秀な記者であれば、なにを取材すればいいか明白なはずだ。 がんばって頂戴とエールを送るついでに、東南アジア支局も強化してねと言っておきたい。 念のために聞くけれど、大丈夫ですよね? 地理、未履修なんて事は、ないよね? 鮮明に東南アジアの状況、頭の中に描けているよね? たとえば、ベトナムの総人口とか。
February 16, 2007
コメント(0)
-
レッシグ理論には限界があることを指摘しないと、wikipediaがダメになると、思った。
以前、YouTube問題でネット界が揺れていたとき、わたしが気付いたことがある。 YouTubeが違法問題でつぶれそうになっていたとき、日本中の議論は奇妙に捻じ曲がっていて、アメリカもどうもダメのようだった。 わたしが書いた解決方法は、知財界では当然と思われる常識を書いたまでだったのが、知識人たちがでたらめなことを言っていることにわたしは気付いた。 この正体をわたしは、解き明かそうと、実は情報を丹念に洗っていたことがある。 そしてそのとき気付いたのは、その根元がすべて同じだということだった。 ただ、その問題を当時書くことは意味がなく、しかもネット界では常識的なことと思われていたので、あえてその問題に言及することは避けてきた。 YouTubeはしばらくして現実的な解にたどり着き、結果的にわたしの提示した解と同一であったが、わたしはその残照を見ながら、どうしても拭い去れない根深い問題がそこにあるような気がした。 わたしが気付いていたのは、著作権をはじめとする知財をコモンズにしていくという美しい理屈が、現実的に崩壊している理論であるということであり、知識人はその理想に感情的情熱を持ち、壁に頭を打ち付けるように突進していたという事だ。 wikipediaが崩壊するかもしれないという報を聴いて、またわたしは頭をひねらなければならないのか、と感じたことを正直に言う。 そして、何で、わたしが考えなきゃいけないんだよ! と文句を言いたくなったことも。 世の中にはたくさんの学者がいて、毎日フルタイムで研究に勤しんでいるのであるから、そっちの方が頑張ってほしいと思うのだ。 なので、わたしは最も現実的な方法をとったほうが良いと思うのだ。 クリエイティブ・コモンズは限界があると指摘することによって、知識人の目を覚まさせるほうが良い。 知財法は修正局面にある、これは本当だ。 しかし、知財共有も修正局面にあると、わたしは思うのだ。 スケールダウンを検討しなければならないと思うのだ。 ■wikipediaの問題を俯瞰する 今、wikipediaをめぐっている問題で、本質的な問題は、維持コストの急拡大に、寄付が追いついていないという部分だ。 その額はGIGAZINEの試算によると、6ヶ月で2億円ぐらい。 この額が払えないと、維持できないかもというのだ。 2億円という額は、全世界的ブランドであると言うことを加味すると、十分に安い額であるように一見すると思える。 しかし、本質的な問題はその部分にあるわけではないと思える。 問題は、維持コストの拡大曲線と、寄付の拡大曲線がかみ合っていないという部分。 今後もその格差が広がっていくことが予想されることを考えると、果たして今後寄付によってまかなわなければならない額はいくらになるのか、と暗い未来を想像するのは難しいことではない。 寄付モデルではやばそうだ、と今のうちに気付くしかないのかも知れない。 しかし、クリエイティブ・コモンズの理論構成で言えば、クリエイティブに対しては、対価を得ないことを是としているので、その集積であるwikipediaは、対価を得ることが出来ない。 これは非常に分かりやすい理屈であって、クリエイティブ・コモンズの理論破綻の端的な一面である。 つまり、クリエイティブを循環させるためのインフラ費用は、誰が捻出するの? ということだ。 誰かがクリエイティブを創作する。それを世界共有とする。 ここまでは良い。 では、それを誰かに届けるためのコストは誰が捻出するの? プールするためのコストは誰が捻出するの? 特許業界にいる人間として、数々の国際条約の分散的な、非常に高度なコスト負担体系を見ていると、クリエイティブ・コモンズは、おかしい。 知財共有は良い。 ただ、その知財が盗まれたものでないことを、誰かが保障しなければならない。 その秩序維持に膨大な維持費がかかる。 ここを逃げている。 そのため、めちゃくちゃな理論構成になり始める。 知財共有に同意しないものにまで、知財は共有しなければならないと、押しつけをしている。 それが無理なようなので、知財秩序まで崩壊させようとしている。 これはダメだ。 NGだ。 同意している者の間での、取り決め、これはいい。 同意していないものへの、押し付け、犯罪といっていい。 ここが崩壊してしまっているのだ。 クリエイティブ・コモンズに致命的に欠落しているのは、知財同盟であるという観点。 同意者のみに恩恵を与えるという、国際条約では当たり前の理屈が良く分かっていないのである。 十分に維持費用が安かった時代は、論理破綻は見えなかった。 わたしが思うのは、無料ということと、ほとんど無料には絶壁のような断絶があるということ。多くの人はほとんど無料であれば十分で、完全無料である必要はない、という事に、知的情熱をもった人はなかなか気付きにくい。 そして、完全無料であることにはなんの社会的意味もないことに気付いてほしいのだ。 さらに、wikipediaの問題は、社会に流通する富を失わせたことを認識する必要がある。 たとえば、ブリタニカとwikipediaは激しく対立しているが、わたしが思うに、ブリタニカの執筆者に払われていた報酬は、社会的善を考慮に入れたとき、高すぎると思える額だったのか? という部分。ブリタニカに問題があったとすれば、スペースがかさばることと、購入額が高額になること。少なくとも寡占による弊害は起こっていなかったとわたしは想像するのだ。 そういう意味で、有意義な職務についていた執筆人の職場を失わせたことは、社会的損失といえないこともない。 もし、問題の把握が遅れ、ブリタニカが破壊され、その後、wikipediaが自壊したとしたら、その社会的責任は誰が負うのか、ということは、なかなか認識されていないことである。 ブリタニカはそれほど問題でないにしても、Microsoftのエンカルタは確実に殺されて、しばらくたつ。マルチメディア百科事典が、現在のテキストベースのwikipediaに取って代わったことは、コンテンツ的には損失である。 エンカルタが十分に安かった場合を想定し、その範囲内でマルチメディアコンテンツが集まってきた場合と比較すると、すでに社会的損害があったと考えることも出来る。 問題なのは、こういった問題の把握が、まだwikipediaでは出来ていなそうな点。 優秀な知財系の人材を雇うとすれば、さすがに高額な費用がかかりそうだが、そういった費用を、誰が捻出するのかという問題もある。 わたしがこんな文章を書いているのは、ボランティアと言えなくもないが、厳密にはこのブログから売りあがっている楽天の販売管理費から出ているのである。 ついこの間も、このブログから、ノートPCが売れた。 わたしは楽天に存在価値を認めさせ、ほんのわずかなキックバックを受けているのである。 もし、楽天日記を使っているユーザの全体から利益が上がらないなら、誰がこんなインフラを維持する意味があるのだろう? 別にわたしはキックバックが欲しいわけではないけど、この日記のインフラを維持するためには合理的な方法論といえると思う。 ■他の問題との対比 wikipediaとYouTubeは皮肉にも、ブランド的に同じような名声を博している。 しかし、YouTubeは、現実的な部分を何とか解決しつつあり、wikipediaは泥沼に陥りそうな予感がわたしはしている。 どう違うのだろうか? わたしは、完全無料とほとんど無料の差であると思っているのだがどうであろう? なんか疲れてきて、ついでに飽きてきたので、端的に。 ネットの中立性問題が指摘されていて、非常に的確な論が出ている。 根本的な問題はこれと全く同一である。 よく読んで欲しい。 解決策はわたしの以前のエントリーを読んで欲しい。 ここに書いてある。 ■Web2.0で儲かる方法を考えてみた(『電子化の波』を改稿) ■2ちゃんねるの特許法による統治の実現性に関する考察 関係あるエントリーを列記するので、読んでから、文句は言って欲しい。 利権のコントロールの話にいけなかった・・・。 あまりにもあほらしくて、てめーで考えろ、と言いたくなってしまうのだ。
February 13, 2007
コメント(1)
-
NGN構想はちょっとまった! 今後、トラフィック爆発が予定されている!
昔、電子書籍をやっていた頃、NTT系の関係者がやってきてFrets光の転送速度を使い切れるコンテンツがないと言って嘆いていた。当時、 100Mbpsの光ファイバーというのは確かに使い切りようがない転送速度で、ADSLとの差別化を行いたい会社としては、非常に深刻な悩みであったと思 う。 数年たってフルHDという規格が主にPS3の暗躍によりテレビ標準になりつつあり、この転送となると、さすがに光ファイバー以外にはあり得なくなる。 昔はwinny以外に光ファイバーを使いこなせるソフトはないと、専門家が言っていた。 これは端的に技術センスのなさである。 思い出すだけでも頭が痛くなる。 と思ったら、今度はNGNである。 次世代ネットワーク。 仕様を眺めていると、どうもこの人たちは伝送路のプロではあるけれど、コンテンツを扱うプロではない、ソフトウェアのプロではないと次第に分かってくる。 コンテンツフォーマットと、PtoPの進もうとしている道を眺めていると、実はとんでもない勘違いをしていることに、はたと気付くのだ。 今からでも遅くないので、何の役にも立たない、レガシーで仕様を固めてしまう前に、再望してほしいところである。 現状の詳しい説明はここで読める。 ■NGNって何だろう?---目次:ITpro http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20070123/259317/?ST=network 世の中の人々は、現在目に見える最終生成物でインフラを判断しがちである。 技術の仕事というのは、どうしても過去の統計に頼りがちである。 実は今、トラフィック爆発の兆候が見え始めており、わたしが把握している限り、その主役となるのは、ソニーとAdobe、そして遅れてマイクロソフトである。 説明しよう。 この問題を理解するために、どうしても必要な概念が、圧縮と非圧縮というものだ。 たとえば、JPGファイルはBMPファイルを「圧縮したもの」であり、100kbのJPGファイルであれば、通常元のBMPファイルは10Mbぐらいはある。 よく考えてほしい。 JPGは2020年も通用しているフォーマットだろうか? 将来項として、 ベクトルデータ →SVG GIFの代替え →PNG JPGの代替え・フォトフォーマット →TIFFもしくはDNG となりそうな感じに標準化が動いている。 まあ、簡単に言えば、Webでの閲覧用のフォーマットも、現在クリエイターである人々が使用しているフォーマットに統一されると思われ、この際、1ファイルの大きさはおおよそ10mbぐらいになる。 だから、昔、ADSLなんていらないよ、ダイアルアップで十分と言っていた言葉がばかげているように、光なんていらないよ、ADSLで十分というのがばかげている。 Webクリエイターは、わざわざダイアルアップに合わせて、「1ページは50kb以下!」 などと、当時は有効であったが、今では全く馬鹿らしいルールを遵守して、ページを作っていたのである。 ADSLが普及すれば、当然一面画像で作られたサイトに移行する。 光が普及すれば、デザインソフトの原稿ファイルをそのままぺろっと張りそうな気がして、ならない。 そうなると、Webページ1枚は50Kbではなく、10Mbとなる。 現在の感覚で聞くと、すさまじくばかげた話に聞こえるかもしれないが、その全く逆なのだ。ダイアルアップに無理矢理合わせるために、どれだけ理不尽なフォーマットを人々が使い続けてきたのだろうか? よく考えてほしい。 10MbのBMPファイルが、100Kbになるのである。 どれだけのものを非可逆的に削ぎ落としたか、冷静に考えてみれば分かると思う。 ちなみに、現在WebでTIFFを見ることはない。 なぜかって? ADSLでは重すぎるフォーマットなのだ。 この問題は、動画の世界に踏み込むと鮮明になる。 最近ではYouTubeが流行ってきたおかげで、動画を見る機会が多くなってきたと思うのだが、一昔前は、WMVを見るだけでも大変だった。サイトで動画 を探し、たとえば最新PCゲームのデモムービーを見る。AoE3のデモは心が震えるほど感動したものだが、マイナーな会社のデモとなると、必ず帰ってくる 言葉があった。「コーディックのダウンロード・エラー」 理不尽なことにわたしはそれを見ることは出来ない。 ただでさえ、WMPとREALとQTと三つも動画プレイヤー規格があるのに、さらに、その中でコーディック、つまり圧縮形式規格がある。これが困ったことに頻繁にあちこちでバージョンアップする。つまりほとんどの動画が実質上みれないのである。 この混乱の中に、YouTubeが登場した。 彼らは、一切のコーディックの必要のないFLASHムービー形式でサイトを運営しており、そしてありとあらゆるファイル形式・コーディックを登録することが出来た。 YouTubeのスタッフは60人ぐらいいるようだが、おそらくその半分以上はコーディックの研究をしているはずである。 彼らはコーディック屋なのだ。 ありとあらゆる圧縮形式を熟知しているのだ。 こんな話をするとほとんどの人が不思議に思うだろう。 え? 画像の圧縮形式はたとえばJPGは、どんなブラウザでもみれるじゃんか、と。 この問いに辿り着ければ、ほとんどあらゆるものが見えるはずである。 ちょっと考えてほしい。 何で、JPGはどのブラウザでもみれるのか? ヒントは大量に撒いたつもりだ。 わたしは、動画配信系の会社にいたので、動画の問題には大量につきあってきた。 ちょうどYouTubeが出てくる前に辞めたのでどうなっているのかは知らないのだが、たぶんひどいことになっていることは間違いない。 最大手の子会社だけに、優秀な人材がそろった会社だったが、完全に混乱をしていた。 たとえば、動画をストックしてあるファイルサーバの一つが2ヶ月に一度はクラッシュする。 社内のギガビットイーサがパンクし、ファイルが社内間でも送れなくなる。 40Gはあるわたしが担当するサービスの動画をバックアップしようとしたら、わたしのマシンにCD-Rさえついていなかった。 DRMに仕様が錯綜し、頻繁に担当者が変わるので、誰もなにが起こっているのか理解していない。 そんな中、取引先がエンコードした画像を確認できないと泣きついてくる。動画エンコード部隊に相談すると、それはコーディックの問題なので、非圧縮で行くしかないですねと言う。 15秒のCMなので、じゃあそれでという。 非圧縮の動画は、1Gになった。 bpsに換算してみるとおもしろい。 多くの人が誤解していることであるが、圧縮された画像・動画は非可逆である。 可逆のフォーマットはTIFFぐらいで、後は大量の情報を間引きしている。 これは編集すればするほど、画質が劣化していくという事実を映しており、クリエイタの視点からすれば、編集する元素材としては適切ではない。 そうでないファイルは何なのだろうか? わたしは的確に答えようとする。 フロー用のフォーマットだと。 ライブラリ用のフォーマットではないと。 もっと的確にしよう。 ストリーミング用のフォーマットだと。 販売するフォーマットではないと。 だからiTunesのように、一見ライブラリに見えるけど実質上はフロー、に持っていかないとだめなんだよと。 なので、フルHDで、ライブラリ用の映像となると、どんな容量になるかぐらいは、bpsでいくらかぐらいかはわかるよねえ・・・、聞きたくなる。 つまり、光の普及が加速的に広がるにつれ、Web上のファイルサイズもでかくなっていくということなのだ。 それが200倍とかいうようなスケールで起こる。 これがまず第一である。 ■PtoPの技術動向 続いて、PtoPの動向も見逃せない。 ついこの間ソニーのストリンガーCEOのインタビューがあり、そこで見逃せない発言があった。 ■ソニーの勇敢な騎士、ストリンガーCEO(後編) - CNET Japan http://japan.cnet.com/interview/biz/story/0,2000055955,20342438,00.htm この中で、ぽろりと出てしまったのだろうが、革新的な言葉が語られている。 引用してみよう。 コンテンツは、あらゆる方向から、あらゆるデバイスでユーザーに届きます。すべての無線LANを備えたデバイスは、なんらかの種類のコンテンツを配信できます。まず顧客が何が便利かを決めなければなりません。 ここでデバイスといっていることに注目してほしい。 くしくもわたしが以前書いたエントリーの新型ウォークマンに酷似している。 ■ソニー・ウォークマンに対する処方箋 -これでiPodを粉砕せよ http://plaza.rakuten.co.jp/hikali/diary/200609150000/ ここで描いているわたしのビジョンは、ポータブル・デバイスに搭載された無線LANによるPtoPによる、メッシュネットワークというものだ。 これは、 これまで議論されてきたラストワンマイルの先の話で、家までやってきたFONのような無線LANポイントをステーションにして、そこから毛細血管のような メッシュネットワークが生まれるのではという構想だ。 この考え方は、PtoPよりもMtoMの概念に近い。 そうそう。 RFIDもこれに乗ってくる。 また、PtoPというと未だにwinnyを想起するかも知れないが、次世代ともいえる、BitTrent、BitCometといったソフトウエア郡は、これまでのPtoPと一線を画す。 これは分割ダウンロードを想像すると分かりやすいのだが、複数のノードから少数ずつダウンしてくるという構成だ。つまり細分化された100近い通信をノード間でやり取りをするという、MtoMで想定されている通信形式をとっているのだ。 NGNは大容量ファイル転送を主眼にしており、最も小さいやり取りを、音声通信レベルに設定している。 わたしが見ている世界は、たった一つのPCが1万程度のノードと通信をしている世界。これは数年で普及してくるように思える。 ■VISTA後のインターフェイス WindowsVistaが出て、ディスクトップが3Dになった。 だいぶ進歩したように見えるが、でも壁紙は、ビットマップだよねえ、と思ってしまう。未だに、我々は流れている振りをしている河を、風に揺れない木立を飽きずに眺めているのである。 わたしは大胆に予測するが、次のWindowsは動画が壁紙代わりになりそうな気がしている。画面解像度はフルHD。ここがもし変わってしまった場合、トラフィックが大幅に増えることは想像に難しくない。 簡単に振り返ってきたが、PS3の今後の動向も見逃せない。 ディスクトップがDirectX標準となれば(マイクロソフトはやるだろうが)、FDからCDへ、CDからDVDへ移ってきたように、DVDからブルーレイに移ることはもはや時間の問題だ。 また、実際、CDからブルーレイまでの遷移は、実のところ光ピックアップのレーザー長の変更だけであり、ぶっちゃけ、赤色から紫に変わっただけ、といってしまえば本当にそれだけのものなのだ。 その次のフォーマットももう出てきている。 ■日本発“ホログラムディスク”国際標準化へ――オプトウエアが説明会 (1/2) http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0502/03/news087.html 2008年頃とのこと。 この時点で、300G。 理論的には1Tまで行きそうな技術である。 それが標準ドライブとして普及するのを2010年としたとき、NGNはどんな伝送路であるべきだろうと、ふと思う。 フルHDも普通の解像度として普及しているであろう。
February 8, 2007
コメント(0)
-
新聞の読み方について
新聞の読み方というのは千人千色で、どのように読んでもかまわない。 毎日40ページ近く、細かな文字がぎっしりと詰め込まれている。 これは確か日経新聞の言であったか、その新聞1ページに原稿用紙16枚分ぐらいの文章量が流し込めるとのこと。 おおよそこれは、わたしの書く長めのエントリー一本分になる。 そんなの40本も毎日読まされちゃあ大変だな、というのがそれを知っての感想だが、冷静に振り返ってみれば、我々日本人は、ぶっとい文庫本ぐらいの情報量を、朝刊・夕刊、朝日・日経という感じで、大量摂取しているのである。 これだけ活字漬けにされて、賢くならない訳がなさそうに思うのだが、読み方によって圧倒的な差が出るようなのだ。 インテリ層と一般層の新聞による情報摂取の効能と紙面なんて問題は、新聞社が喜んで取り組みそうなので、わたしの考察は省くが、思いのほか新聞というのは情報に溢れている。 今日(2月4日)の朝日新聞朝刊があったら、テレビ面を見てほしい。 ここでわたしは頭を悩ませてしまった。 5分ぐらい、うんうんとうなった。 そうなのか、これが世の中の流れなのか。 ちょっと衝撃だったと言って良い。 まじまじとそれを見つめ、その意図を読みとろうとあれこれと頭を動かす。 あなたは、このテレビ欄になにを感じ取ることが出来るだろうか? さて、わたしの場合を説明することにしよう。 わたしは元々、Webでの広告デザインちっくな仕事であったから、広告はよく見る。 今日のテレビ欄の広告は、WOWOWのキャンペーンで、今なら980円で見放題というものであった。 デザインは、黒バック・ゴールドという、ゴージャス感を出す典型的なレイアウト・配色・フォントで、その教科書とも言うべき安定的な効果が見込める作りになっている。 ただ、一点。 キャッチがゴールド系ではなく、レモン色である、という点を除いて。(れ、レモン色? い、いいのか? 折角の重量感が、一気に軽くなるぞ?) デザインの基礎からすれば、定跡外しと言える。 脳味噌の中で、いろいろと色変換をしてみて、これはこれで狙った通りなのかもという考えに落ち着く。なにを狙ったかを正確に書くと、あまりにも長くなりすぎるので割愛するが、まあ簡単に言って「おも軽い」なのかな? という感じなのだ。これを実現するために尽くされている莫大な配慮の軌跡を丹念に追い、デザイナーの思考を読む。 しばらく考えていると、左下の広告も気になる。 「ムザビ通信で学ぶ」 とキャッチがある。 武蔵野美術短大の通信講座の広告で、一目でパンフレット屋が作っていることが分かるレイアウトである。 この「ムサビ通信」も結構気になる。 なんかこのキャッチを聞くと、桜通信を想起させ、何ともどうでもいいが、パソコン通信のようでもあり、無駄にエロい感じがするのである。 うーん、エロいなあ、このキャッチ考えた人・・・。 うーん、エロいんだけど、微妙に上品さに隠れてエロさが見えないようになっているんだよねえ・・・。 こういうのなんて言ったらいいんだろう? エロ上品? そうそう、この重さと軽さの微妙なマッチングが最近のノリなのかなぁ、とテレビ欄を見ながらわたしは考えていたのである。 労働法制に関する論説委員の解説があり、これが結構読ませる。 労働ビックバンがどうこうという内容の「補助線」というタイトルのコラムであり、一目読んで生臭いはらわたのような構成に、一瞬眉を潜めた。 紙面が生きているようにうごめく瞬間は、もっとも新聞を読む甲斐がある瞬間だとわたしは思う。しかし、わたしには明らかなうごめきを見て取れるのに、それを読めない人もいる。 迫真に怖いホラー小説はなかなかその真実の姿が隠されているもので、わたしがこの本は怖いよと言ってわたしても、え、なにが、怖かったの? ときょとんとした顔で返される事がしばしばある。 労働法制は現時点でのネット言論界での華であり、大量の言葉が尽くされているので、かなり濃密に経営者側・労働者側の言い分や、そのお互いに調整をしようとする意見を読んでいる。 最近、政府のブレーンのインタビューが出て、またかざむきが変わった。 この記事は、その流れを的確にとらえた敏腕新聞記者が、そのすべてを受け止めた上で放った一撃で、経営者側にうんともすんとも言わせないほど強烈なアッパーカットで、わたしの推測が正しければ、ブラインドから放たれた右腕は的確に顎を捉え、宙を飛び、リングに倒れ、今ちょうどわたしはカウントを7まで聞いている。 まあ、ぶっちゃけ、致命的な一撃なのである。 それが、普通の人にはさっぱり分からないほど、落ち着いた論調で書かれている。 わたしはそれを見ながら思うのだ。 たとえどんなに立派な法制を作っても、強欲な経営者に、労働者は酷使されるのだと。ねじ曲げられ、つまみ食いをされ、法を潜り抜け、潜り抜けるどころか違法であり、それでそれが違法にならないように政治に圧力をかけるのだと。 社会的な善は考えてないのだと。 そう読めるように書いてあるのである。 ネットの仕事をやるような人間であり、特に情報伝達系の仕事であったから、わたしはおそらく全人口の上位5%ぐらいに入りそうなほどのネット漬け人間である。 しかし、ネットを歩けば歩くほど、新聞紙面の上質さに驚く。 インターネットがあるから新聞はいらないという向きがあるが、わたしの場合は逆だ。 ネットで論説を追えば追うほど、新聞が必要になってくる。 そして、おそらく一年前には読みとれなかったであろう、生々しい世界の動きが、その小さな活字から浮き上がってくるのを感じるのである。 そして、驚くべき事に、おそらく、新聞記者はそれを意図していない。 論説委員ほどになればそれぐらいは知得していると思うのだが、普通の新聞記事に客観性以外の質は要求されていない。 びびるのである。 新聞紙面は、人が作っているのではないと。 新聞社というシステムが作っていて、それが今も機能しているのだと。 そして、新聞記者は記名記事でない限り、顔のない歯車なのだと。 WOWOWの広告は意図した結果ではないと。 全自動で紙面に載ると。 オリコンの訴訟がらみで、元朝日新聞社の記者が書いた暴露記事を読んだ。 まあ、ぶっちゃけ、保守的で硬直化した、救いようのない組織という書き方なのだが、わたしは最近、冷酷な思考になってきた。 この紙面がアウトプットとして出てくるなら、どうでも良い、と。 中の人がどんなに不幸でも、よいと。 もちろん、法を犯してもらっては困るし、新聞社の記者の待遇がひどくてみんなワーキング・プアであるというのは困るのだが、現状のままで致命的な問題が発生しているという訳ではないし、待遇はたまに揶揄されるほど好待遇である。 むしろ驚くのはこれほどまでに強烈なインターネットの揺さぶりがあっても、新聞社の質量による慣性力は強靱で、ネットがチェック機能を果たし始めるようになると、そのフィードバックを得て、さらに強固になりつつあるようにわたしは感じるのだ。 米国の新聞社が次々と身売りをしているのを見ると、日本の販売制度がいかに新聞社に強固な地位を与え、ゴージャスな記事を書くことを可能にしているかをまざまざと見せつけられる気がしてしまう。 全国紙にしか出来ない役割というのは確かにある。 たとえば、世界には賢人が多いが、そういう人々言葉を伝えるのは、新聞の役割である。日本の全国紙が強烈なのは、それがたとえ、クリントン元大統領のような超大物でも、日常的に独占インタビュー出来てしまうこと。 高級たれと言うわけではない。 新聞料金は、使うべきところに使ってほしいと、一読者として思うだけだ。 昔、高尾から品川まで通っていた頃、わたしはよく日経をキオスクで買った。 片道2時間ぐらいかかるので、その時間を潰すために、片っ端から全部記事を読んだ。 そうやって固定的な時間を、新聞を読むことにすると、案外、新聞リテラシーというのはついてくるのである。 読み方は自由だけど、毎日1時間は新聞を読む時間に使う。 わたしの場合は半ば強制であったが、これを習慣に取り込むと、次第に幅が広がってくる。 たとえば、テレビ欄で1時間をつぶすのはかなりの想像力を必要とするだろう。 そうするとスポーツ欄も見出すが、それでも日経などは2面分しかないので、さすがに15分は持っても、それ以上はもたない。 となると、今度は1面。 続いて、2面、3面。 毎日読むとどこにどの記事があるかが分かるようになるし、続き物を読む楽しみも出てくる。 そうやって読み始めると、結構新聞っておもしろいことを書いている事に気づくのだ。 ただ、どんなものにも質のばらつきがあるように、とびきりにいい記事と、どうしようもなくだめな記事がある。それを嗅ぎ分ける力を付ければいいだけであって、だめな記事はだめだなとつぶやけばいいだけだし、良い記事は熱心に読めばよい。 ただ、それだけなのだ。
February 4, 2007
コメント(0)
-
模倣と創作の話をとりあえず木っ端微塵にしておく
著作権がらみで、少々おかしな議論が出ている。 創作は模倣から始まるが、模倣と創作の間には果てしなく巨大な壁があるというのだ。 果たして、そうだろうか。 一見正しそうに見えるけど、実はそうではないとわたしは思う。 この辺は知財法制と絡めて話をすると実は結構深い。 知財六法(特・実・意・商・不・著)の第一条(法目的)と第二条(定義)を読み、それぞれの保護期間を眺めるだけでだいぶ新しい発見が出来ることは保障するので、やってみると面白い。 ■【知はうごく】「模倣は創作のうちには入らない」著作権攻防(4)-2 http://www.sankei.co.jp/culture/enterme/070130/ent070130001.htm 念のためにわたしのことを言っておくと、わたしは模倣よりも創作に近い側。 ただ職歴的には商業デザインが長いのでこれはあんまり創作的な仕事であったとは言いにくい。 意図的に模倣をしたのは文体ぐらいだが、この今ここに書かれているわたしの文体を見た限りでは、誰の影響を受けているかはほとんど推測することは不可能であろうと、わたしは踏んでいる。 デザインといっても絵はまるっきり駄目。 作曲も出来ない。 フィルムも撮れない。 写真はへぼ。 唯一、創作と模倣を兼備しているのは、物語だけである。 そして、それは知り尽くしている。 物語において模倣と創作の問題に踏み込むと、たった一言の思考停止で議論が終わってしまうから面白い。 シェイクスピアと。 わたしはここからスタートしているので何の障害にもならないのだが、便利な言葉である。「創作とは模倣である」を地で行き過ぎているにも関わらず、未だに、史上最高の文豪。 この人の話を始めるとわたしの話は非常に長くなるので割愛するが、結論は二つある。「シェイクスピアのオリジナルの物語は2本しかない」「すべての映画はシェイクスピアの模倣である」 どこぞかで議論をしたとき、この局面に突入しかけてしなかったので残念だったのだが、創作論云々を振りかざす前に、とりあえず事実をみつめる必要がある。 シェイクスピアは38作ぐらい書いているが、果たして、そのうちオリジナルの2作はどれであろうか? 多分、解説や研究者の成果を読まずとも、全作を読めば、推測が可能であろうと、わたしは思う。 結論は、 「夏の夜の夢」と「テンペスト(邦題:「あらし」の場合も)」 研究者によれば原作が見つからないとの事なのだが、創作者の嗅覚でこの作品を見ると、「何らかの資料を参考にした形跡が感じられない」となる。 シェイクスピア先生にこんなことを言うのは失礼かもしれないが、のびのびとしている、束縛を感じない、自由である、こだわりなく素直に物語が現れている、奔放な構成である、キャラクターが走っている、あとどんな言葉がほしいだろう? シェイクスピアは一般に天真爛漫な大天才というイメージが固定されていると思うが、研究者の間では「それだけでない」という部分ではおそらく一致している。 まず、確かに天真爛漫である。 しかし、卓越したインテリである。 そして、当時でさえ非難されるほど派手な盗作者であった。 ここまでは研究者の受け売りで、わたしはそれにルネサンス人としてのシェイクスピアという相を見逃すわけには行かない。 ルネサンス期とは自然科学と芸術が混然一体としていた不思議な世紀であるが、シェイクスピアもこの時代の薫陶をもろに受けているどころか、本人がもっとも鮮明に体現していたりする。 例えば人物造型はダ・ビンチの人体解剖図を見るように、生々しい。 例えば物語構造は大聖堂を見るように多層的で、左右対称。 例えば台詞回しはボッカチオが切り開いたように、口語主体。 例えばそのテーマに宗教的寓話は存在せず、哲学的な議論もない。 例えば悲劇の登場人物はパズルでも見るように、論理的に全部死んでいく。 ルネサンスの文学はダンテより始まるが、教会の権威が短い時間の間に解体されるにつれ色彩が薄まっていき、その台本を読む限りは、キリスト教の影響を感じる部分はほとんどない。 しかし、彼が採用している題材は、彼が革命を起こした時代以前の題材に拠っている。 それを、実験でもするように切り刻み、測定し、ピース組み合わせ、再構築したのがシェイクスピアであるとわたしは考えている。 だから勘違いしないでほしい。 シェイクスピアは、模倣はしなかったよう見えるが、そのあらゆる材料は他人から盗んできたのである。それこそ手を広げられるほど広げ尽くして、貪欲に、大衆とパトロンの支持を受け、そして、その著作者の意図を完璧に捻じ曲げ切って(勝手にヒューマニズムの話としてしまって)、大胆に改変に継ぐ改変を尽くしきったのだ。 そして、ネタもとの著作者は歴史に忘れ去られ、シェイクスピアは未だに世界最高峰の巨匠である。 ここまで冷静に聞けるだろう。 なんたって、著作権のなかった時代の話だ。 特許の原型はあったけどね。 しかし、このシェイクスピアが物語を創作する過程をつぶさに眺めると、ふと疑問が湧く。 シェイクスピアは歴史物語をよく書くのだが、この歴史物語というのはねたもとを追っていくと結構面白いのである。 例えばジュリアス・シーザを彼は、ブルタークのカエサルの伝記だけを読んで書いたとされる。しかし、現在の作家である塩野七生により、あれは史実どおりのカエサルではないと酷評される。 つまり彼はブルタークの著作を完全にパクったわけだ。 きっとカエサルの著作であるガリア戦記さえ読んでないはずである。 ではブルタークはどうやって書いたのかといえば、これは当時の風評を参考に書いたと言うことになってる。つまり、ブルタークは当時の風評をパクったわけだ。つまり、彼はパクり伝記をパクったわけで・・・。 ん? なんか、変ですか? そうかな? よく考えてみよう。 混乱してきたら、現在の歴史物語に視点を移してみるとよい。 なんたって、現代には著作権がある。 日本でもっとも大きな歴史物語といえば、NHKの大河ドラマであることは衆目一致するところであろう。 今年は風林火山。 武田信玄公の歴史を山本勘助を主人公として描くらしい。 しかし、この誰もが知る名軍師、実は史実では存在しない人間であることがほぼ確定してる。史実でないとなれば、誰かの創作物である。つまり誰かが創作したキャラクター。しかもまずいことに、この創作物たる名軍師、著作権が生きている可能性が大なのである。 山本勘助は江戸の講談などで頻繁に語られたらしいが、これは根拠のない風評がエンターテイメントとしてキャラクター化していったようである。 ■参考 wikipedia 山本勘助 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E6%9C%AC%E5%8B%98%E5%8A%A9 近代文学で山本勘助の初出と確認されているのは井上靖の小説『風林火山』。 もちろん、江戸より諸説の伝説が生きていて、それを参考にしたのは想像に難くないのだが、困った事実がある。どこまでが井上靖の創作であるかがわからないのだ。 江戸期の講談を参考にしていたとは言え、史実がない以上、少なくとも人物造型等、まあ、ぶっちゃけ言ってキャラデザぐらいは、井上靖がやっていたといっても、間違いがないことは確かだ。 つまり、山本勘助を扱う歴史作家は、井上靖の著作権を侵害することを避けられない。これぐらい調べれば誰にでもすぐに分かるので、すべての歴史作家の故意認定は自明。 困ったことに、著作権は山本勘助を殺すのである。 さて、わたしは著作権の話をしたいのではない。 模倣と創作の話をしたいのであって、この両者は一体不可分であると言いたいのだ。 この観点に立つと、芥川龍之介の羅生門はアウトだ。あれは確か雨月物語(あれ、宇治拾遺だっけ?)が基である事が確定している。小泉八雲も駄目そうだ。江戸期の民間伝承を基にしていることが確定している。 雪おんななどは武蔵国の調布村の伝承と伝えられている。 この話はさらに複雑になる。 わたしは雪おんなのラストに疑問を持って、国立国会図書館で25以上の邦訳を調べつくし、一般に認識されている雪おんな像が、実は岩波旧訳の平井呈一訳たったのひとつによって醸成されたことを突き止めた。 英文で書かれるラフカディオ・ハーンの原文には、雪おんなのラストに恐ろしげな表現はない。平井呈一の訳によって初めてあの雪おんなのイメージは確立し、それが定着しているし、わたしはそれを調べきった後に、満足して平井呈一訳を唯一の雪おんなと認めることにしたのだ(ちなみに旧訳がもっともよい)。 ということは、雪おんなを恐ろしげに描くと平井呈一のパクりであることになるのだろうか? まあ、物語が決定的に違う物語になってしまうので、そういわざるおえない。 ちなみにわたしは、その25の邦訳を呼んで、小泉八雲ラブな人間であるから当然、その訳が納得がいかなすぎて、自分で訳したい気分になる。わたしは25もの邦訳を読んでいるから、英語は赤点レベルのひどいものなのだが、訳することが出来てしまう。 これはパクっているのは自明である。 しかし、どれをパクっているのだろう。 わたしは創作していないのだろうか? 模倣と創作の問題は、踏み込むと、こういった話になってくる。 ここまでは、著作権の話。 知財法に踏み込むと、もっと根本的な問題になる。 知財法のボスである特許法は、ほとんどが、改良技術で構成される。 つまり99%は従来の技術を使うが、1%の部分で前進があり、これが非常に革新的であれば特許と認められる。 特許は、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度なものと定義され、すくなくとも著作権上の創作より、巨額のお金の動く世界である。 バーコードの特許は年間600億円ぐらいの特許料収入であったらしい。 経済学上、金銭面で比較すれば、著作権上の創作は特許法上の創作に比べ、100分の1ぐらいの価値しかない。 そして、その特許法上の創作は、99%はパクりで、1%が創作なのだ。 なんか飽きてきたのでこの辺で。 もうちょっと勉強してきてから、創作論をぶちまけてほしいものである。 わたしも人のことは言えないが、勉強不足である。 著作権法を語るぐらいなら、知財六法の定義趣旨ぐらいは読んでほしい。 この先は、非常に深い。
January 31, 2007
コメント(0)
-
PC周りの環境が整ってくる。
工人舎のサブノートを、CRTモニターにつなぐ。 USBでも挿すみたいに、アナログRGBピンをつなぐと、画面が数倍に広くなる。 ついでにUSBにはキーボードとマウスを挿す。 何の設定作業も必要なく、きわめて快適な環境になる。 もう、サブノートについている機能のうち、7割ぐらいは意味がないのではと思ってしまうのだが(笑)、AMDのGeode LX800が結構がんばるチップなのか、特にそれらしい不便さは感じていない。 GIMPの2.2を落としてきて、横1024の画像をレタッチする。(ちなみに、800×480時はGIMP1.x系のみ利用可能) 別に絵描きじゃないので、数十枚もレイヤーを駆使しないせいか、これといった反応の遅さはない。やっぱこれぐらい広くなくちゃあ、レタッチは出来ない。FireWorksとか立ち上げると、あっという間にハングりそうだが、今のところ必要ないので、とりあえず問題はない。 やっぱ、トリニトロン、発色いいなあ、などといいながらいじっている。 極めて静音で、HDDシーク音がなければハンドヘルド。 唯一、今、ガーガー、いっているのは足元にある暖房だけ。 昨日などは、WMPを立ち上げて、オーディオの音のあまりの大きさにびっくりしてしまった。これでも音量は最小だったのだが。 目の前にある、パタンと閉じると1kgにもならないサブノートに、とりあえずわたしが必要としたものは詰まっている。 おっと、忘れていた。 この機器は89000円。 そして、わたしは今、その3割の機能も使っていない。 つまり、わたしが必要としているPCなんて所詮そんなものなのだ、と気付くのだ。(念のため、使用しているモニターは高価なものを中古で買ったもの) えいやあと思い切ってディスクトップPCを捨てて、その代わりにサブノートを置いてみると思いのほか快適。 ただ、動画処理速度とDirectX(ゲームを動かす技術)は捨て切っているので、実はYouTubeを見るのだって一苦労なのだが(ついでに言うと、iTunesがなぜか動かない)、早く動くのはなしということにしてみた、とルールを決めてしまうと、思いのほか重いソフトでもさくさく動くから不思議だ。 こうやって環境を移行してみて気付くのは、PCってやっぱり性能は要らないんじゃないかと言うこと。 Vistaを勝手に載せられていらんスペックを押し付けられる前にXP機を買おうと思い立って現行の環境に移ったのだが、ゲームとかのハイエンドはPS3でいいよと諦めると、非常に手堅い環境を選択したことに気付く。 そうか。 もうディスクトップPCの時代は、少なくともホームでは終焉した。 馬鹿でかい、ガーガーいうタワーのPCはハンドヘルドをちょっと大きくしたサブノートで十分代換が効くし、どのみち、PCゲームのハイエンドを求め続けたら、いつも最新のチップセットを用意していないといけない事になる。 動画編集も夢のまた夢。 わたしが理想とするのは、 ・いつも生活の中心にある汎用型ノートPC(出来れば安価) ・ハイエンドのみに特化した高級専門機(出来れば安価) の組み合わせ。 今のサブノートを端末にして、必要なときにPS3にアクセスして重い処理をやらせる光景が夢一杯の未来として思い浮かんでくる。 オンライン経由で自宅のPS3に繋ぐと、リモートでサブ機になってくれるみたいな。(夢見すぎという話もある) とりあえずPS3買うまでは、PSoneが主力だなあ。 このトリニトロンに繋ぐケーブルがあるらしい。 買わなきゃなぁ・・・。
January 29, 2007
コメント(0)
-
最近の雑感/引越しが無事終わる
引越しが終わって一息つく。 大量の本と、ダンボール12箱ぐらいを収納していた本棚を改めてみつめる。 こいつの収納力はすごいと。 引越し業者は、直前まで迷った。 中小を物色したが、交渉決裂。 引越しとグーグルに打ち込んで、アドワーズでトップに出たところに電話した。 プロっぽい(当たり前だ)営業が出て、5分話しただけで、詳細までがあっという間に決まる。部屋にある荷物の寸法を大まかに伝えると、的確な見積りが出てくる。2トンのロングを押さえて、懸案の馬鹿でっかい本棚の吊りはナシでまとまった。 ちなみに積載量はぎりぎりだった。 悪条件なので5万円なり。 両親は高いというが、中小はもっと高い。 条件提示を2秒で飲んだ。 こういう交渉は好きだ。 昔、会社でシステム発注をしていたことを思い出す。 交渉が長いところは高い。 能率的な人は、ぎりぎり妥当なところを一発で提示してくる。5分ぐらいで、交渉相手の力量を読むのだろう。 あたりに散らかった荷物を次々にダンボールにつめ、いったい自分がどんだけモノを溜め込んでいたかを思い知らされる。 本、資料。 結局自分はそれが大切なのだ。 引越しにやってきた二人は、指示を出し、指示を受けながら、てきぱきと荷積みをしていく。 わたしが、一箱さえ持ち上げるのがやっとの本入りダンボールを、二箱も運んで4階から長い階段を下りていく。「先に箱に詰めてください」「なるほど」 かちかちと噛み合って何かが進行するのは、ストレスフリーでいい。 みるみるうちに荷物は減り、わたしは二人の作業状況を横目で見ながら、二人はわたしの作業状況を横目で見ながら、微調整を繰り返しながら、引越しが進んでいく。 ちなみに、わたしの20ぐらい経験したアルバイト経験をもとにして言うと、これがチームワーク。引越しのような肉体作業は進捗を互いに目視できるから、無言のコミュニケーションで作業の効率化が進む。 そういうチームだと、とても気持ちがいい。 引越し先に荷物を運んで、やはり本棚があがらない。「上がりません!」「絶対に上がりませんか?」 すこしの迷いがある。「絶対に上がりません」「わかりました」 もう何年もしてなかったんだろう、こういう会話。 結局、自分で吊った。 とても不思議な引越しだった。 すべてが何一つ問題なく、スムーズ進行した。 あんなに大量の本を運んでいただいて、最後はグロッキーぎみな二人には申し訳ないのだけど、事前に正確な通告はしてました、その上での見積りでしたと、言い訳混じりに書いておく。 荷物だらけの部屋のダンボールの本を、本棚に収納していく。 本棚に入れない予定の本は、押入れに詰め込んでいく。 ずいぶん廃棄したはずが、3箱ぐらい、いらない本が押入れに詰まる。 工人舎のサブノートが来てから、廃棄する予定だったPCセットのうち、ディスプレイだけが捨てきれない。 ソニーの、21型のトリニトロンCRT。 たぶん、定価10万ぐらい。 中古で2万で買った。 その図体ばかりが馬鹿でかいディスプレイを見ながら、それに雑巾をかけながら、ああ、そうか、わたしは元も今もデザインなのだなと、しみじみ思う。
January 25, 2007
コメント(0)
-
贅沢は言わない
海にゆれる船にいて、水面をみつめるよう。 上半身を乗り出して、南の子供みたいにざっぷりと、海中に顔を突っ込んでみる。 それから目を開く。 きらきらと美しい色彩の熱帯魚たちを見て、ほっと息をつく。 顔を上げて、深呼吸をして、もういっかいして、鼻をつまんでみて、息を止めて、もう一度深呼吸して、飛び込む。 海の世界は、くらげやら、小魚やら、海草やら、岩場やら、蟹みたいなのやら、なんだか知らないものやらに満ちているけれど、珊瑚も、真珠も、さざえも、うにも、なまこもここからやってくると思うと、親しみがわく。 遠くまで泳げるようになるのはそんなにむずかしいことではなくて、潮の流れさえ、そして自分が戻るべき船の位置さえ、自分の息のつづく時間さえ分かっていれば、危険でもない。 すこしうまくなれば、沖に出れる。 ただし、猛毒のうつぼには要注意。 沖に出れば、回遊魚たちの大群。 何千キロも太平洋を泳ぎ、新大陸沖から暖流に乗って、ここまでやってくる。 あの、すました顔。 青光りする鱗。 何千、何万もの魚たちが、一糸乱れぬ隊列が、脇をものすごい速度で泳ぎぬけ、どこだかわからない遠くの島国をめざす。 回遊魚たちは、大小さまざまないろとりどりの群れを成し、海洋の主役たる。 ときおり、エイやら、海亀やらが混じり、そのゆうゆうとした姿で、ぼくはわらう。 サメの話は、みんな知っていると思う。 シャチの話も、知っていると思う。 だけど、彼らはよわっちい小魚や、回遊魚の群れを主食にしているので、気をつけていれば危険なことはない。 群れを襲うほうが喰いっぱぐれないんだ。 群れなければ危険でない。 もちろん、安易に近づくのはよくない。 どんなに、その泳ぎがきれいでも。 そんな、魚たちを見ていると、泳ぎがうまくなる。 どう泳いでいるかをよく見つめて、それをまねるようになるから。 泳ぎがうまくなると、だいぶ遠く深いとこまで潜ることが出来る。 きれいに泳げるようになると、イルカたちが楽しげに唱を歌いながら一緒に泳いでくれることもある。海面をジャンプして、100メートルも潜って、跳ねるように泳ぐ楽しさを教えてくれる。 深くまでいくと、マッコウクジラの悠々とした姿を見ることもある。 だけど気をつけたほうがいい。 彼は短気で、むっとすると船まで食い破ってしまうんだ。 彼は深海で大王イカと戦って、帰ってきたばかりだから、いつも気が立っている。 めじりの下に生傷があるときは、そっとしておいたほうがいい。 深海の魚たちは、奇妙な形をしている。 もし、興味があるのならば、ちょっとばかり見に行ってもいいかも知れないけど、深海はいつも食べるものが不足しているから、安易に近づくのはどうだろう。 それに息も切れるし、いくらみつめてもぼくは理解できない。 軟体なやつらが多い。 口と歯が大きい。 ときどき、ひかるんだ。 それでいつも静かにしているんだ。 自分たちが、深海から上に上がれないことを知っているんだ。 だからそっとしておこう。 それより、深層海流に乗ろう。 どう? まだ、船の位置は覚えてる? ぼくはいつも、どこかで自分が魚でないことに気付く。 自由自在に泳いでいても、自分は魚ではないと。 まねているだけだと。 すこしさびしくなって、海に愛おしさを感じて、それから海面に浮上していくんだ。 波間に船を見つけて、無造作に上がる。 それから太陽をみつめて、深呼吸をして、ひとしきりないて、考え始める。 海とはどんな世界なのか。 (ラブクラフトなら、海洋生物はなんでも邪悪な化け物で片付けてしまいそうなのだけど(笑))
January 24, 2007
コメント(0)
全384件 (384件中 1-50件目)
-
-

- 楽天ブックス
- [楽天市場]「カレンダー」 検索結…
- (2025-11-15 21:30:44)
-
-
-

- 連載小説を書いてみようv
- 59 タムタムさんカッコいい
- (2025-11-11 14:59:50)
-
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0929 ゴールドマン・サックス…
- (2025-11-15 00:00:13)
-