-
1

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその4
鵠沼海岸7丁目にあった本真寺を後にして次の目的地・原の辻に向かって北に進む。鵠沼海岸3丁目の住宅街の一角にあった浅間家の立派な墓地。この浅間家もこの地域の旧家なのであろう。皇大神宮が、かつて家臣の「浅間某」を看護するために建立されたという歴史的経緯から、「浅間」という名前で呼ばれることがあります とネットから。右側に鮮魚店「堀川網」。 この店でも生シラスを販売中。そして「原の辻 供養塔と庚申塔」に到着。 「原の辻 史蹟案内光明真言供養塔寛政九年(西暦一七九七年)鵠沼村観音講中が百日観音、七面、板東、秩父を巡礼し、それを記念して造立した供養塔です。出羽三山供養塔江戸末期の文化六年(西暦一八〇九年)鵠沼中村(現湘南山手)集落の人穣山を詣しそれを記念して造立した供養塔の三塔です。明治十三年『鵠沼花月(北村盛花)』で紹介されました。庚申塔宝暦三年(西暦一七五三年)鵠原地区の庚申講中が造立した青面金剛像と三猿像の庚申塔です。現在も庚申講が継続しています。平成十六年十二月原 講 中」場所:藤沢市本鵠沼4丁目13[原の辻この場所は、浜道へ続く本道と脇道との分岐点になり、鵠沼宿から海岸部へと続く道は、鵠沼村内の主要道であり、江戸時代には追分筋に集落が広がってゆきました。徳富蘆花の「思い出の記」には、藤沢停車場から友人に連れられてこの地を歩いた時のことを「夕日に照りて鵠の音鵠沼なる村に入って五六町、路は二筋に岐れて羽黒山にいたる供養塔が立って居る」と綴っています。これは、鉄道の開通前でない明治22年の事と思われます。辻には、現在も三基の石塔が残されていいます。三叉路独特の風景は当時をしのばせます。 参考:鎌倉を巡る千一話 第0147話 徳富蘆花「思い出の記」 ● 光明真言供養塔:湧護国三十三所供養塔 寛政七年(1795)正月 相州湧護村 法主 智門寺(講中 19名の名) 西国三十三所とは、日本最古と云われる観音霊場、巡礼道一円ある。● 出羽三山供養塔:湧護山月山羽黒山 西国秩父板東百部 大権現供養塔 文化六年(1809) 相州湧護村鵠沼屋檀中建立 謹子智門寺 善英 この塔には明治四年の年銘があリ、修造したものとみられる.● 庚申塔:六部行者如実建立 宝暦三年(1753)庚申講中(17名の名)]庚申塔:六部行者如実建立 宝暦三年(1753)庚申講中(17名の名)青面金剛像に近づいて。六部行者如実建立 宝暦三年(1753) 庚申講中(17名の名)青面金剛像と三猿像の庚申塔・庚申塔の典型的特徴:・中央に青面金剛(多臂の神像)・台座に三猿(みざる・きかざる・いわざる)・舟形の石造庚申とは、 60日に1度巡る干支の日を指し、その夜、体内の「三尸(さんし)」という小さな虫が 天に悪事を報告し、寿命を縮めると信じられていました。そのため、人々は青面金剛を拝み、 徹夜で祈り語り合い、病魔や災厄を防ごうとしました(これがいわゆる「庚申講」)。出羽三山供養塔 159cm。「奉月山 湯殿山 羽黒山 大権現 供養塔西国秩父 板東百番」 光明真言供養塔寛政九年(西暦一七九七年)鵠沼村観音講中が百日観音、七面、板東、秩父を巡礼し、それを記念して造立した供養塔である と。原の辻を南側の道路から北向きに撮影。出羽三山供養塔(文化六年・1809) の側面(横面)。逆光のため、文字は解読できなかった。「藤沢警察署前」交差点に向かって住宅街の路を北に進む。 「藤沢警察署前」交差点。「藤沢警察署」の建物。 神奈川県下でも有数の観光・娯楽地である「江の島」や鵠沼海岸、片瀬東浜・西浜等の各海水浴場の治安を担う(藤沢駅周辺は警察本部により歓楽街総合対策重点取締地区に指定されている)。所在地:藤沢市本鵠沼四丁目1番8号最寄駅:小田急江ノ島線 本鵠沼駅そして次に訪ねたのが「本鵠沼の道祖神・庚申塔」。 「道祖神庚申塔の由来道祖神道祖神は路傍の神で、集落の境や、村の中心、村内と村外の境界、道の辻、三叉路などに、石碑や石像の形態で祀られる神で、村の守り神、子孫繁栄、交通安全の神として信仰され、広く全国的にも信仰されている。当地域のものは、明治四十二(一九〇九)年正月建立された。庚申塔庚申塔は当地では、宝暦三(一七五三)年に、中国より伝来した庚申信仰に、基づいて建立された。起源は中国の道教で、日本に伝わって変化し、「見ざる、言わざる、聞かざる」の教えが庚申講となった福の神である。どんど焼き左義長とも言われ、地方によって呼び方が異なり、どんど焼き、だんご焼きなど呼ばれ、その年の門松や、注連飾り、書き初め等を持ち寄って、その火で焼いた餅や、だんごを食べると、その年の病を除くと言われている。正月十四日に行われる火祭りの行事である。ニ〇〇六年一月吉日 仲東町保存会」 私の住む地域の「どんど焼き」👈️リンクの光景。左義長とも言われ、地方によって呼び方が異なり、どんど焼き、だんご焼きなど呼ばれ、その年の門松や、注連飾り、書き初め等を持ち寄って、その火で焼いた餅や、だんごを食べると、その年の病を除くと言われている。右:道祖神。左:庚申塔。近くにあった歴史を感じさせる墓地。小田急江ノ島線「本鵠沼」駅方面への路。 「本鵠沼の道祖神・庚申塔」を後にする。JAさがみ鵠沼支店では「収穫祭」が開催されていた。 JAさがみ鵠沼支店は11月15日、鵠沼支店・直売所「米ディハウスくげぬま」で「収穫祭」を開催。地元新鮮野菜の即売会をはじめ、フランクフルトや甘酒などを販売 と。数多くのテントが設営中であったが、客の姿はこれから増えるか?そして次の目的地の「大東町内会館」に到着。藤沢市本鵠沼2丁目4−36。大東町内会館の横に広がる墓地の中に鎮座された六地蔵。そして「大東観音堂」。 [大東観音堂:準四79番霊場この場所は「大東の辻」と呼ばれ、かつては藤沢最古の銘のある道祖神(現在行方不明)がありました。観音堂は、平成二十九年に町内の篤志者により大東町内会館として改装されました。場所は昔のままです。大東観音堂は、十一面観音菩薩像をお祀りしており、昔門寺の僧侶浄がここに庵を結んだのが始まりとされています。庵主浄心は、師匠である普門寺住職善応密師に命じられ、四国八十八ヶ所霊場を巡り、霊場の砂土をお持ち帰りました。これを、相模国高座郡、鎌倉郡の各所に埋めて巡拝地としたのが、準四十九八十八か所です。大東町内会館の隣のお堂に、弘法大師像(年銘欠)が納められています。また、お堂の脇には、浄心の巡礼結願を期したとみられる供養塔(文化十四年(1817))があります。この供養塔の正面には「百番供養塔」、左側面には「四国八十八箇所」と彫られています。百番とは、西国三十三・坂東三十三番・秩父三十四番計百ヶ所の観音震場のこと、浄心は日本各地を巡礼していたとみられます。御詠歌:施しの 布きてむすぶ 草まくら さむるもをしき あかつきのゆめ大東町内会館の中の観音堂は、観音講中の人により、毎月十八日の縁日にご開帳されていました。残念ながら、コロナ禍を機に現在では行われなくなりました。]御詠歌の意味は旅の途中、施しの心に包まれながら草を枕に眠ると、 たとえ寒さの厳しい夜であっても、 夜明けに覚めてしまうのが惜しいほど、 心が安らぐ夢を見るものです と。「大東大師堂由来の記大東大師堂は相模国八十八箇所霊場の第七十九番の札所です。この霊場は、堀川の浅場太郎右衛門が相模にも開設しようと、普門寺の僧善応密師に相談し、文化十四年(一八一七)善応の弟子で大東観音堂の庵主浄心に依頼して、四国八十八箇所の霊場の砂と宝印を集めさせ、真言宗の宗派を越えて、現在の鎌倉市、横浜市泉区、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の寺院に大師像と御堂を建てました。霊場造立は、尽力した浅場太郎右衛門が文政十年(一八ニ七年八月三十日)に没したが、子の太郎右衛門(弘化四年、一八四七年九月十二日没)が文化十四年から弘化四年の間に建立されたと思われます。建立から百七十年以上たち、大正十五年に、大東観音講中により再建されましたが、大分傷んでまいりました。山口雅吉氏をはじめ旧町内有志が普門寺山主第五十六世川島弘之、師弟弘耀に相談し、尽力され大東大師堂を改修することができました。この篤信の浄行により、天下泰平、国土安穏、現世安穏、無病無難、息災延命、諸災消除、家内安全、子孫永久、富貴繁昌、諸願成就、大東観音講中、弘法大師の擁護にあつからんことを。 密巖山遍照院普門寺 第五十六世 川島弘之 師弟 川島弘耀 大東旧町内有志平成ニ十九年十一月十九日」 墓地内にはこの付近の名家・関根家の墓が並んでいた。「第七十九番札所 相模準四国八十八箇所」。 「百番供養塔」百番供養塔とは、江戸時代に広まった観音信仰に基づき、西国三十三所、坂東三十三所、秩父三十四所の「日本百観音」の霊場をすべて巡拝した人が、その満願を記念して建立した石碑 と。大東観音堂を正面から。大東観音堂(旧・大東大師堂)の内部に安置されていた弘法大師像。大東観音堂(旧・大東大師堂)の前に並ぶ石仏。左側の石仏:地蔵菩薩(立像)右側の石仏:観音菩薩(立像)。大東観音堂(旧・大東大師堂)の敷地内にあった懐かしい手押し式ポンプ(井戸ポンプ)。揚水レバー式の「ストローク型」ポンプハンドル(レバー)を上下に動かすことで内部のピストンを上下させ、井戸水を吸い上げるタイプ。この形式は「通称:カバポンプ」「ガチャポンプ」👈️リンク(正式には“ピストン式井戸ポンプ”)と呼ばれている。昭和30〜50年代(1955〜1975) に多く出回った形式か?「大東町内会館」の玄関か? 扉の片方には様々な「お知らせ」が掲示されていた。 大東観音堂(旧・大東大師堂)入口に掛けられた幕(内陣幕) の様子。幕にはふたつの紋が見えた。■ 左:五三の桐 紋 かつては皇室専用の紋章であり、足利尊氏や豊臣秀吉といった 歴代国家指導者の使用でも知られる桐花紋の一種■ 右:巴紋(ともえもん)・三つ巴 仏堂でも用いられる 真言宗ゆかりの寺にも多い 井上家の紋としてもよく見られる とネットから。施主の家紋?と、堂の守り紋が両方入っている可能性が高い?? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.28
閲覧総数 195
-
2

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその3
前方の五差路を左折して進む。藤沢市本鵠沼3丁目13−19付近。左手前方にあったのが「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」。その前の造成工事中の場所は相模準四国八十八箇所の開創者の浅場太郎右衛門・浅場家の本家である と。よって、当時は浅場家の本家の屋敷の角に「堀川大師(地蔵)堂:準四56番霊場」があったのだ。造成中の土地・屋敷が広く、以前は広い敷地内には庭木が青々としていたのであろう。 堀川大師(地蔵)堂に近づいて。[浜道堀川大師(地載)堂:準四25番震場お堂の中には、安永九年(1790)の銘がある地蔵菩薩像(向かて右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国八十八簡所案内にも、”浜道地蔵堂”と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川講中と刻字されています.御詠歌:のりの舟 出る津寺と いろくすも うの浜道に つとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮影て、右側が宝暦十ニ年(1831)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。】御詠歌の意味は【仏さまの教えという“法(のり)の舟”が出て行く港のようなお寺だと聞いて、いろいろな人びとが、この浜道を通って、朝早くから(熱心に)お参りして来ることでしょう】と。「堀川 弘法大師堂」。 「相模準四国八十八ヶ所 堀川地蔵菩薩堂とほつおや(遠つ祖)の みたま(御霊)まさしく 有あけの 影さやかにぞ す(澄)める堀川第五十六番 金輪山泰山寺」 【遠い祖先の御霊が まさしくそこに宿っているように、有明の月の光が 澄んだ姿で 堀川を照らしている。】堀川とは現在の境川の旧称の一つ。藤沢市域を南北に流れる 境川(横浜市青葉区〜藤沢〜江の島に至る河川)は、時代・地域によってさまざまな呼び名がありました。境川の主な古名・堀川(ほりかわ)・境の川・境河・高座川(たかざがわ)・藤沢川(ふじさわがわ)このうち 堀川(ほりかわ) は、▶ 鵠沼・片瀬・藤沢宿の周辺で古くから用いられた名称で、江戸初期〜明治にかけて文献に登場しま と。古語で「堀」は、単に掘った溝ではなく境界・領域の区切りとしての水路を表すことがあります。境川は、・武蔵国と相模国・高座郡と鎌倉郡の国境・郡境になっていたことから、“境を示す川=堀(境界の水路)”= 堀川という説であると。左:弘法大師像右:地蔵菩薩坐像左:弘法大師像、椅子に座り、左手に数珠、右手に独鈷杵(とっこしょ)を持つ。独鈷杵とは、両端に1本の突起がある密教の法具で、古代インドの武器が起源。煩悩を打ち砕く仏の智慧の力を象徴し、チベット仏教や日本の真言宗、天台宗、禅宗などで用いられます。右:地蔵菩薩坐像。右手に錫杖(しゃくじょう)、左手に宝珠(ほうじゅ)を持つ坐像。造成工事中の浅場家の本家の広大な敷地跡。「鵠沼における淺場家の本家は、現在の藤沢市に相当する地域にあった「原の淺場太郎右衛門」です。この家は、明治時代初期に鵠沼を代表する豪農であり、水田、畑、山林などを広く所有していました。戦後に鵠沼を離れたため、浅場家に関する資料は現在見つけることが非常に困難となっています。 ●本家の名称: 原の淺場太郎右衛門●本家の特徴:・明治初期に豪農として知られていた。・水田、畑、山林などを広範囲に所有していた。・当時の屋敷には「千両箱のうだつ」が上がっていたという。・当時21軒あった淺場家の総本家とされていた。」 在りし日の「浅場家の本家の広大な敷地」をGoogle Mapから。 そして次に訪ねたのが、100mほど東側、小田急江ノ島線沿いにあった尼寺・本真寺。[本真寺 通称「尼寺」夢想山本真寺(浄土宗)。本尊阿弥陀如来。創建は明治36年(1903)、颯田本真尼により下鰯(現鵠沼海岸三丁目)の細川家別邸に布教及び日清戦争病没者の供養のため「慈教庵」として開山されました。しかし、関東大震災て慈教庵は倒壊。翌年現在地に移転し仮本堂を建立し、昭和10年(1935)に再建されました。震災後何時から本真寺と号されたかは不明です。現在は男性の住職てすが、昭和8年に書かれた『現在の藤沢』(加藤徳右エ門著)には、”本庵は全部尼僧にして男気なし”と記されています。境内には「文士宿」の異名で知られる旅館東屋の初代女将長谷川ゑいの墓や、鵠沼海岸別荘地を開発した伊東将行の墓碑もあります。][【颯田本真】弘化2年(1845) ~昭和3年(1928)愛知県生まれの尼僧。慈善事業家。現在のボランティア活動家の草分け的存在。全国の地震や津波などの被災地に衣類等の援助物資を送るとともに、自身でも被災地に足を運び救援活動を行っていました。本眞尼を敬慕する人たちが関東での布教を懇願し、なかでも細川糸子という人が三河まて本真尼を訪ね熱心に依頼しました。再三の要請に心が動かされ、鵠沼の細川家の所有地の一角に慈教庵を結び布教活動を行いました。昭和10年の再建を見ず、昭和3年に故郷の三河で入寂。「布施の行者」と尊称された颯田本真の生涯は、書籍等にも綴られています。 参考:鵠沼を巡る千ー話「第0155話 慈教庵創建」]颯田本真尼をネットから。ここ鵠沼に来たのは、本真寺の前身となる説教所「慈教庵(じきょうあん)」を開設した支援者の一人に招かれたからだと。山号の「夢想山(むそうざん)」は、本真尼が同庵を訪れる10年ほど前に見た夢の光景と、鵠沼の光景が似ていたからだという。境内にある池を跨ぐ小さな朱塗りの太鼓橋。仏教寺院の「放生池」を模したもの。朱塗りの太鼓橋の先には観音堂(供養堂・題目堂)が。「鵠沼海岸開拓者 伊東将行之墓」👈️リンク。鵠沼別荘地開拓創始者として、また多くの文人達が逗留した旅館「鵠沼館」や「東屋」を築いた伊藤将行のお墓。本堂を斜めから。宗派: 浄土宗山号: 夢想山歴史:もとは「慈教庵」という庵が鵠沼海岸にありましたが、大正12年(1923年)の関東大震災で倒壊しました。大正13年(1924年)1月、尼僧の**颯田本眞尼(さったほんしんに)**によって、現在の位置に仮本堂が建立され、再興されました。颯田本眞尼は「全国6万戸を救った尼僧」としても知られています。境内:境内はこじんまりとしていますが、手入れが行き届いており、静かで美しい雰囲気です。朱塗りの太鼓橋が特徴的な景観を作り出しています。本堂前の石造三重塔。動物供養塔。三界萬霊塔。本堂を正面から。薬師瑠璃光如来像。右手:施無畏印(せむいいん)「恐れることはない、安心しなさい」と示す手左手:与願印(よがんいん)「願いをかなえる、救いを与える」印 そして、万病に効く薬が入っていると信じられている「薬壺」を持つ。 五劫ごこう思惟しゆい阿弥陀仏。五劫思惟阿弥陀仏は、通常の阿弥陀仏と違い頭髪(螺髪らほつ)がかぶさるような非常に大きな髪型が特徴です。「無量寿経」によりますと、阿弥陀仏が法蔵菩薩の時、もろもろの衆生を救わんと五劫の間ただひたすら思惟をこらし四十八願をたて、修行をされ阿弥陀仏となられたとあり、五劫思惟された時のお姿をあらわしたものです。五劫とは時の長さで一劫が五つということです。一劫とは「四十里立方(約160km)の大岩に天女が三年(百年という説もある)に一度舞い降りて羽衣で撫で、その岩が無くなるまでの長い時間」のことで、五劫はさらにその5倍ということになります。そのような気の遠くなるような長い時間、思惟をこらし修行をされた結果、髪の毛が伸びて渦高く螺髪を積み重ねた頭となられた様子を表したのが五劫思惟阿弥陀仏で、全国でも16体ほどしかみられないという珍しいお姿です。落語の「寿限無寿限無、五劫のすり切れ」はここからきています。屋根瓦(本瓦)を積み重ねて造った塔・「瓦塔(がとう)」瓦を積み重ねて造った塔を 瓦塔(がとう) といい、本来は奈良時代の古寺(例:法隆寺・飛鳥寺・元興寺など)で発見されることが多い、貴重な遺構の形式。しかし江戸時代以降にも、庶民の信仰や講中の寄進で作られた「模造瓦塔」「供養瓦塔」 が実在。本真寺のこれは、まさにその後者の系統と考えられる と。近づいて。境内の六地蔵。笑顔が可愛らしい六地蔵。こちらも。「尾﨑恒子(おざき つねこ)」供養塔。本真寺は、ジャーナリスト・作家である横山源之助の恋人であった尾﨑恒子ゆかりの寺院。 詳細は以下の通りと。尾﨑恒子:横山源之助が明治40年頃から亡くなるまで関係を持った恋人とされる人物。源之助の臨終にも偶然居合わせた友人と共に立ち会っている。関係:横山源之助の墓所が元々あった場所から鵠沼の本真寺に改葬され、後に尾崎恒子と彼女の娘である梢もこの寺に埋葬されている。 このように、本真寺は横山源之助と尾﨑恒子の墓所がある、ゆかりの深い場所 と。境内の地蔵尊。近づいて。「延命地蔵(子育地蔵)」であっただろうか。再び朱の太鼓橋を反対側から。御堂の内陣。三体の仏像(+小像数体) が安置されていた。左:大黒天中央:観音菩薩(聖観音or如意輪観音)右:地蔵菩薩朱の太鼓橋越しに本堂を見る。こちらが本真寺の山門。 山門脇にある「不許葷酒肉入門」の石碑「葷」の意味は「ニンニク、ニラ、ネギ、ラッキョウ、ショウガ」の総称。精がつく食べ物なので、酒、肉と共に、修行の妨げになるということ?「葷酒肉」は私の大好物であるが、この日は山門をくぐらせて頂いたのであった。「私たちの宗旨(しゅうし)名称 浄土宗宗祖 法然上人(源空) (承安五年—西暦一一七五年〜建暦二年—西暦一二一二年)開宗 承安五年(西暦一一七五年)ご本尊 阿弥陀仏(立像・座像)称名 南無阿弥陀仏教え 阿弥陀仏を深く信じ、ひたすら南無阿弥陀仏とお念仏を称えるだけ でどんな罪深い人でも救われるお経 お釈迦様が説かれた 「無量寿経」「観無量寿経」「阿弥陀経」の三部経を大切にしております本堂のご本尊に、先ず合掌」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.27
閲覧総数 234
-
3

鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその2
鵠沼海岸7丁目の住宅地の路地を最初の目的地に向かって進む。この先が最初の目的地であった。藤沢市鵠沼海岸7丁目21−8。右手に大きな石碑があった。松岡静雄先生之庵趾碑。[この場所は、かつて海軍大佐であり言語学者・民族学者の松岡静雄が退役後に居を構えた場所です。明治十一年(1878)生まれ、松岡家の7男。民俗学の大家 柳田国男を兄に持ちます。海軍きっての吉語学者であり、病により退官した後、精力的に言語学・民族学を研究し、「日本古語大辞典「太平洋民族誌」 「ミクロネシア民族誌」等の多数の著書を残しています。関東大震災後の大正十ニ年末、鵠沼・堀川集落の南に隣接する納屋(ないや)地区に移り住みました。この庵を《神楽舎(ささらのや)》と名付け、在野の言語学者として日々研究を重ねていました。次第に、教えを乞う人々が集まり“神楽舎講堂”と呼ばれるようになり、湘南国語研究会というものをつくって、この舎から「国語と民族思想」というものを発刊していました。昭和11年(1937) 5月23日松岡静雄が逝去した翌年、先生を基う弟子たちにより石碑「松岡静雄先生之庵趾」が建立されました。くくコラム> >民俗学の大家柳田國男線の人々:松岡静雄と丸山久子と鵠沼民俗学者丸山久子は、20歳のころよリ父が鵠沼海岸に家を建て、この近くにあった神楽舎の講義にも参加していました。静雄の長女と丸山久子は、高等学校時代の同級生だったという縁もあり、静椎の没後も松岡家の人々との交流は生涯にわたります。静雄の妻の誘いを切っ掛けに、久子は柳田国男の講演「国語の将来」を受講します。これを機に本格的に民俗学を学ぶようになり、世田谷にある柳田の自宅て行われた研究会にも熱心に通っていました。昭和十七年頃からは、柳田の助手を務めるようになりました。 参考資料:『地名の会会報 117号』遠藤の民俗ー丸山久子の足跡と仕事ー粂智子著]海軍退役後、神奈川県藤沢市(当時は藤沢町)鵠沼に居を移すが、直後に起こった関東地震では、遭難死した東久邇宮師正王の遺骸を運ぶために軍艦を相模湾に回航させたり、遭難死した住民26体の遺骸を地元青年団が荼毘に付す際の指揮を執ったりしたという逸話が残っている。震災後は鵠沼西海岸に居を構え、神楽舎(ささらのや)と名付けて言語学、民俗学を研究し、同じ軍人出身の「岡書院」店主岡茂雄の勧めもあり、十数年で多くの著作を残した。また、扇谷正造をはじめ多くの青年たちが訪れて学んだ とウィキペディアより。海軍時代の松岡静雄(ウィキペディアより)。家族・親族実父:松岡操 - 儒者、医者実母:たけ兄姉 松岡鼎 - 医師 松岡俊次(早世) 井上通泰(松岡泰蔵) - 国文学者、歌人、医師 松岡芳江(早世) 松岡友治(早世) 柳田國男 - 民俗学者弟 松岡輝夫(松岡映丘) - 日本画家柳田 國男は、日本の官僚、民俗学者。 東京帝国大学法科大学を卒業して農商務省官僚となり、貴族院書記官長まで昇り詰めた。退官して約20年を経た1946年に枢密顧問官に補され、枢密院が廃止されるまで在任した。 日本学士院会員、日本芸術院会員、文化功労者、文化勲章受章者。位階・勲等は正三位・勲一等。松岡家兄弟らの写真(前列右より、松岡鼎、松岡冬樹〔鼎の長男〕、鈴木博、後列右より、柳田國男、松岡輝夫〔映丘〕)没後1938年(昭和13年)、弟子たちによって建てられた「松岡静雄先生之庵趾」碑。裏面には何か書かれていたのでろうか?おそらく建立年月・建立者名などが刻まれている??「松岡静雄先生之庵趾」碑を後にして、次の目的地に向かって鵠沼海岸7丁目の住宅地内を進む。左手に石鳥居が現れた。ここが「高根地蔵尊」。藤沢市鵠沼海岸7丁目19−11。石鳥居前での説明を聴く。石鳥居の奥に小さな御堂が建っていた。石鳥居を潜って進むと目の前には木製の「地蔵堂」が。 近づいて。「高根地蔵尊」。 地蔵堂の内部に安置されていた「高根地蔵尊」。今でもお地蔵さまの足元には、子供の病が治ったお礼として奉納された小石が山のように積み上げられているのであった。 [高根地蔵神楽舎に近く堀川部落の南側に、高根地蔵はあります。“高根”はこの辺りの小字名て、昔は田の畦道の中に小さな祠がありました。天保十四年(1843)ニ月、堀川部落の開祖山上新右衛門建立したものです。鎌倉時代のある合戦で、とあるやんごとなき若者を負い郎党四人を伴った武者が最後をとげたのを村人が弔ったという伝承があります。明治初年には、祠堂改築のため盛土を崩したところ、刀身ニロ、断碑片若千、土器十ニ枚が発見されたと云われます。その後、松岡静雄の発起て祠堂が建立されました。『現在の藤沢』加藤徳右衛門著(昭和8年刊行)には、次のように記されています。「部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の祟ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び、以来恐ろしき祟りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかでえあると云われ四時香華の絶えぬものたり」 ]以下もネットから 『藤沢の民話』第一集の山口紋蔵氏からの聞き書きには、鎌倉時代との説もあるので引用しよう。藤沢の高根地蔵藤沢町鵠沼堀川海岸にある高根地蔵と云う伝説の霊験あらたかの地蔵がある。この地蔵は天保十四年二月四日鵠沼堀川部落の開祖山上新右衛門が建立したもので鎌倉時代の合戦に或るやんごとなき若君を負い郎党四人を引具した武者がこの地まで落ちのびたが武運拙なく遂に敢なき最後を遂げたるを村人等が之を悼み茲に葬むりしものと伝う。明治初年両堂改築の為め盛土を取崩した処刀身二口、断碑片若干、土器十二枚を発見したと当時鑑識の明なく徒に散逸したものたりと。部民はこの地蔵に触れると必ず生命に関する程の崇ありと恐れ、安政五年頃より毎年九月四日追善供養をおこなって今日に及び以来恐ろしき崇りも絶え、小児の疾病本復を祈れば殊に霊験あらたかであると云われ四時香華の絶えぬものたり。この逸名の小公子と忠臣の冥福を祈り一面郷土史跡記念物として保存の為の同所の海軍予備大佐松岡静雄氏等の発起で出来た小さな祠堂が建てられている と。決して歴史の教科書には載らないような名もなき武将であろうが、確かにここに存在した歴史の秘話に触れることができるのも、このような「小さな地域史」探訪の醍醐味なのであった。「高根地蔵尊」をズームして。その先を右折して、鵠沼新道線を進む。コモダ歯科医院手前の路地を左折。藤沢市鵠沼海岸3丁目3−1。「しらす直売所 田むら丸」前には列が。藤沢市鵠沼海岸7丁目15−15。毎朝しらす漁をして釜揚げしらすを作っているオジサンと製造販売しているオバサンが二人でゆるりと営んでいる湘南しらすの直売所である と。美味そう!!小田急線に沿って北に歩く。そして次に訪ねたのが「浜道堀川大師(地載)堂:準四25番霊場」。藤沢市鵠沼海岸7丁目4−16。この日、最初の相模準四国八十八箇所霊場。「第二十五番 南無大師偏照」まで読み取れる石柱が建っていた。「南無大師偏照」の下に「金剛」と続くのですがありませんでした。[浜道堀川大師(地蔵)堂:準四25番霊場お堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められています。江戸期の新四国へ十へ箇所案内にも、”浜道地蔵堂"と書かれていることから、この地蔵菩薩のお堂がある所を巡礼地としたものと見られます。弘法大師像には、文政三年(1820)の年銘と、台座には堀川溝中と刻字されています。御詠歌:のりの舟出る津寺といろくすも うの浜道につとひよるらんお堂隣にある、2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫で、右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作。お堂前の標柱も、天保ニ年(1831)堀川講中により建てられたものです。]「浜道 弘法大師堂」。 本家四国八十八ヵ所津照寺の御詠歌の木札が掲げられていた。「準四国八十八ヶ所法の舟 入るか出るか この津寺 迷ふ吾身を もせたまへや第二十五番 宝珠山津照寺」 【仏の教えという救いの舟に、私は今、乗るべきか乗らざるべきか迷っている。 この寺に立ち止まる私の迷いを、どうか仏さま、正しい道へお導きください。】と。堂の中には、安永九年(1780)の銘がある地蔵菩薩立像(向かって右)と、その隣に弘法大師像(向かって左)が納められていた。地蔵菩薩立像をズームして。弘法大師像をズームして。隣の2基の庚申塔は、いずれも青面金剛像浮彫。右側が宝暦十ニ年(1762)、左側が宝永六年(1709)の作 と。いずれも「青面金剛」や「三猿」が彫られていたが、彫られた石の素材や像の姿かたち、さらに剥離摩耗などの違いが見てとれます。左側が宝永6(1709)年、右側が宝暦12(1762)年と、50年以上差がありますが、左の方が形態をよりとどめていた。こうした歴史を積み重ねてきた石塔・石仏などは、区画整理や道路拡張などによって一か所にまとめられることが多いとのこと。しかし、この堂の前の通りは古い地図を見ると昔から続いている道。庚申塔は、おそらく別の場所から移動されてきたのだと思うのだが、こうしたものが残っていることは、歴史を大切にされてきた証だと思うのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・
2025.11.26
閲覧総数 235
-
4

龍の口竹灯籠へ-2
本堂の手前、右奥にあった日蓮大聖人像を撮ったが・・・。昼間であれば。しっとりと闇に沈む竹筒の奥、ひとつの小さな灯が、まるで呼吸するように揺れていた。外の冷たい夜気とは対照的に、内側の竹肌は炎にあたためられ、淡く琥珀色に染まり、何十年も風雨にさらされてきた竹の表情までも優しく浮かび上がっていたのだ。龍の口竹灯籠の灯りは、ただ“照らす”のではなく、見る人の心に柔らかな静寂をしみ込ませ、急ぐ時間の歩みをふっとゆるめてくれるのだった。大書院手前の「幻想庭園」。夜の闇を背景に、光・竹・水・そして“物語”がひとつの舞台のように組み上げられていた。 ■ 空間の主役 ―― 龍の姿画面右側に横たわる流木から形づくられた龍は、まるで今にも息をし、闇へと舞い上がるかの如くに。赤い点の“目”がほのかに光り、静寂のなかに潜む力を象徴しているようでもあった。近づいて。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っていた。それはまるで地から立ち上る気のよう。■ 背後に浮かぶ天女の影竹垣に映し出された天女は、光の線がかすかに震えながら形を保っており、龍が天へと昇る時に現れる導き手の如くに。龍と天女が同じ画面に収まることで、“龍口”という土地の伝承性がとても濃く演出されていた。そして右下の水面は青く照らされ、龍が棲む清浄な池のイメージ。竹の黄色い光と対比することで、「地の灯」と「水の灯」が呼応していた。様々な角度から。青い水面に散った緑の光は、ただの反射ではなく、水の上に咲く星の花の如くに。ひとつひとつの光は鋭く、しかし水のゆらぎに合わせて静かに形を変えながら漂っています。まるで、「夜の池に、緑の星座が降りてきた」そんな印象であった。青の深い水底は夜空のようで、その上に落ちた緑の光は瞬き、淡く滲み、やがてまた別の姿に生まれ変わるのであった。■ 流れる光 ―― 水と竹の呼応左下の竹灯籠の群れは、柔らかい切り抜き模様から光がこぼれ、白い霧に反射してゆらゆらと漂っているのであった。それはまるで地から立ち上る気の如くに。■ 竹の灯りがつくる、やわらかな陰影手前の丸い竹格子の灯りは、光が細かい編み目を通って外へこぼれ、周囲にやさしい揺らぎの模様を落としていた。■ 奥に浮かぶ竹細工の明かり後ろの吊り灯籠は、竹の表皮を薄く削ったような柔らかな曲線を持ち、まるで小さな行灯(あんどん)が枝先にとまっているかの如し。木の葉がわずかに揺れると、灯りもふわりと呼応し、“晩秋の息づかい”を感じさせるのであった。ズームして。■ 編み目からこぼれる、温かな光竹の細かな輪の連なりが無数の小さな“窓”となり、そのひとつひとつから温かな光がこぼれ出ていた。強い光を受け止めながらも、編み目がそれを和らげて。そして、その先右側にあった龍の竹灯籠。■ 闇に浮かぶ金色の龍切り抜かれた竹の隙間から漏れる灯りが、鱗、爪、髭、そしてうねる体の曲線を鮮やかに浮かび上がらせていた。灯りは一点ではなく、竹一本一本に宿っているため、龍の輪郭は“燃えるような揺らぎ”をまとい、まるで今にも息を吹きかけて動きだしそうに。右側には「龍」そして「竹かぐや」の文字も浮かび上がっていた。 左側下には、山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿が。ズームして。■ 闇から現れる龍の横顔横から見ると、光が竹の奥から溢れ、彫り抜かれた線のひとつひとつが浮き彫りのように立体的に浮かび上がっているのであった。細長い鱗の並び、胸の張り、うねる胴の曲線――どれもが光の強弱と陰影で生命感を帯びて見えたのであった。山門先の境内に並ぶ竹灯籠の姿を見下ろして。龍口寺・大書院。その前には、竹灯籠が横向きに地面に置かれ、ただの“道の明かり”ではなく、歩く人を静かに導く、光の川のように見えたのであった。■ 線となって流れる灯り細長い竹に空けられた無数の丸い穴から、白い光が点々とこぼれていた。その光が連続すると、まるで夜の大地の上に一本の光の流線が描かれているように。歩くたびに、視線の先へすっと伸びていくその線は、流れゆく川のようでもあり、星座を地面に散らしたようでもあったのだ。近づいて。■ 粒が生む「光の流れ」竹の中を流れる光が、そのまま大地へ滲み出して。大小の丸い穴からこぼれる光は、ひとつひとつが金色の粒のように。その粒が密になったり疎になったりしながら曲線を描くことで、まるで光自身がしなやかに蛇行する一本の川になっているのであった。「遠藤笹窪谷公園竹灯籠エリア藤沢市で最も豊かな自然が残されている場所の一つである「遠藤笹窪谷公園」の【ほたるのタベ】イベントで使用された灯籠が並べられています」。 そして仁王門まで下り、「龍口刑場趾」を見る。■龍ロ刑場跡とは?龍ロ刑場跡(神奈川県藤沢市片瀬3丁目)は、鎌倉時代に設けられた処刑場で、現在の龍ロ寺周辺に位置する歴史的霊場です。1271年、日蓮聖人(日蓮大聖人)が幕府の弾圧を受け、「龍ノロの法難」として知られる処刑未遂事件の舞台となりました。この時、日蓮は斬首されそうになったものの、伝説によれば江の島方面から光の玉が飛来し、処刑が中止されたとされます。この出来事が「龍ロ法難」として日蓮宗の四大法難の一つに数えられ、現在は龍ロ寺がその歴史を伝える場所となっています。周辺は住宅地に変わっていますが、過去の処刑場の記憶が残っているとされています。 再びテント作りの「受付」を見る。 そして龍口寺前交差点を通過する江ノ島電鉄の車両を。神奈川県藤沢市片瀬海岸1丁目にある江ノ島電鉄と道路併用のカーブが、江ノ島電鉄・龍口寺前交差点。江ノ島電鉄は、江ノ島駅のすぐ東側、龍口寺前交差点付近から鎌倉方面の神戸橋交差点までが、道路併用区間で、龍口寺前交差点のR=28mは、普通鉄道としては日本一の急カーブとなっているのだ。そして江ノ島電鉄・江ノ島駅に到着。ポスター「SHONAN SUNSET」。夕陽に照らされた雲が、赤、橙、紫へと滑らかに溶け合い、まるで空全体が燃えているかのよう。湘南の空が時折見せる、“奇跡の色彩”が完璧に捉えられていた。 遠くに見える富士山は、赤く染まる空に黒い影として浮かび、堂々とした存在感を放って。このシルエットこそ、湘南の夕景が人の心を惹きつける大きな理由のひとつ。「江ノ島」駅。 鎌倉行きの電車が入線。■江ノ電はどこで列車すれ違いするのでしょうか?鵠沼、江ノ島、稲村ヶ崎、長谷の各駅と、鎌倉高校前-七里ヶ浜間にある峰ヶ原信号場ですれ違います。鵠沼と稲村ヶ崎は島式(1面2線)、江ノ島と長谷は対面式(2面2線)です。峰ヶ原信号場には客扱いをするホームはありません。島式ホームとは、ホームの両側が線路に接している形状のこと。まるで線路が島を取り囲んでいるかのように見えることから島式ホームと呼ばれています。そして利用した藤沢駅行きの電車が。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.11.24
閲覧総数 373
-
5
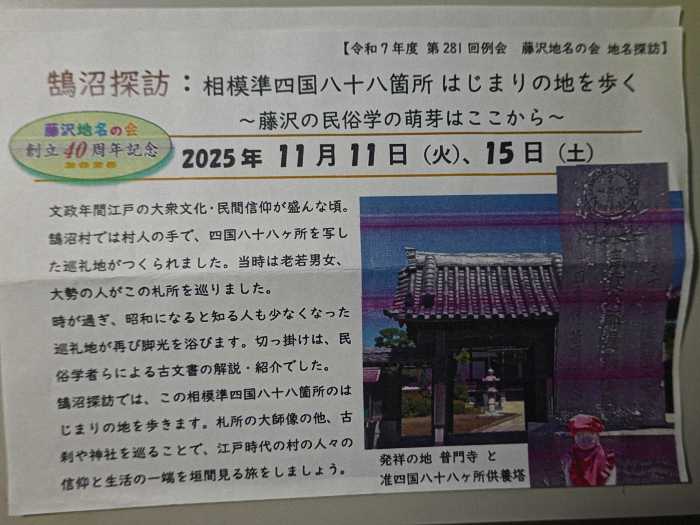
鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩くーその1
この日は2025年11月15日(土)、「藤沢地名の会」主催の【令和7年度第28回例会・藤沢地名の会 地名探訪】・「鵠沼探訪:相模準四国八十八箇所はじまりの地を歩く」に参加しました。「文政(1818年~1831年)年間(は)江戸の大衆文化・民間信仰が盛んな頃。鵠沼村では村人の手で、四国八十八ヶ所を写した巡礼地がつくられました。当時は老若男女、大勢の人がこの札所を巡りました。時が過ぎ、昭和になると知る人も少なくなった巡礼地が再び脚光を浴びます。切っ掛けは、民俗学者らによる古文書の解説・紹介でした。鵠沼探訪では、この相模準四国八十八箇所のはじまりの地を歩きます。礼所の大師像の他、古刹や神社を巡ることで、江戸時代の村の人々の信仰と生活の一端を垣間見る旅をしましょう。」 ●予定コース鵠沼海岸駅→松岡静雄先生之庵趾→高根地蔵→準四25番→準56番→本真寺→原の辻→茂兵衛の辻→大東観音・準四79番→準四41番→斎藤家長屋門→普門寺・準四5・47・88番→藤森稲荷→浅場太郎右衛門墓→昼食(宿庭町内会館)・法照寺・準四48番→空乗寺→宮の前首塚→共同墓地・準四63番→万福寺→皇大神宮:解散(午後2時半頃予定)予定コース(都合により一部変更することがあります)[ 7.0km程度、高差なし]※準四:相模国八十八箇所の霊場番号、弘法大師像の場所日時:令和7年(2025)11月11日(火),15日(土) 2回開催(同じ内容です) ※小雨決行、荒天の場合11月18日(火)に延期します。集合:午前10時00分 小田急線鵠沼海岸駅改札前集合 (午後2時半ごろ 皇大神宮で解散予定)参加費:一般7 0 0円、会員2 00円 (資料代と保険料を含みます)定員 :両日とも3 0名 計6 0名 (先着順、会員もお申し込みが必要です)申込日 :11月3日(月)~11月7日(金) 受付専用電話 電話 070-9040-2614 (担当:布施) ※お電話は9:00ー17:00の間にお願いいたします.持ち物:弁当、飲み物、ゴミ袋、雨具10:00集合とのことで9:10に自宅を出て、小田急線鵠沼海岸駅に40分ほどで到着。改札出口で地名の会の方が迎えてくれ、集合場所を案内してくださいました。藤沢駅方面の線路沿いの空き地の集合場所には既に10人ほどが到着済み。受付をし会員会費200円を支払う。この日の散策用資料(全20ページ)をいただきました。そして定刻10:00になりこの日の案内人の方からこの日の散策ルートの紹介が始まった。参加人数は15名、2班(8名、7名)に分かれてそれぞれに案内人の方が付いてくれたのであった。私は7名の2班にてスタート。鵠沼海岸3丁目5の道路を北西に進む。左手にあったのが、入口表札から法華宗本門流の晴明庵。鵠沼海岸駅周辺👈️リンクの昔からの路を進む。鵠沼海岸郵便局(藤沢市鵠沼3丁目)前の細い商店街の路地を進む。この通りは、実は“近代以降につくられた道路”ではなく、江戸~明治期以前から存在した「鵠沼村の生活道」を引き継いだものと。道がゆるくカーブし、幅が急に狭くなる地点もあった。これは近代の都市計画で作られた道路には見られず、江戸~明治の農道の曲がり方(地形に沿う道)と同じ特徴であると。つまり、この曲がり道は、昔の地形に沿っていたために残った“古道の線形”と言えるのだと。今回、主催者の「藤沢地名の会」さんからいただいた資料を[ ]つきで転記させていただきます。転記することにより、私のこの日の散策地の歴史等の復習が主な目的です。[【=鵠沼地域の概要=藤沢市域は、歴史的にみても古くは鎌倉幕府、江戸幕府の周縁地域に当り、現在も東京近傍の地域として、中央の政治的・文化的影響を受けて発展してきました。藤沢南部の鵠沼地域は、東に境川、西に引地川、南は湘南の海に囲まれ、北は旧東海道の辺りまでになります。鵠沼から茅ヶ崎一帯に続く砂丘地帯は、海の波や潮流によって形成された砂州が、堆積した砂が風によって運ばれ小高い丘になったものです。鵠沼地区全体がなだらかな平地になっており、高い場所ても海抜10m程度です。【鵠沼の歴史】奈良時代、相模国司が記した『相模国封戸租交易帳』には、土甘(とがみ)郷という地名があり、古くからこの辺りに集落があったと見られています。さらに、北部にある皇大神宮は、土甘郷の総社であったと云われます。平安後期、大庭氏が荘園を伊勢神宮に寄進し“大庭御厨(おおばみくりや)“👈️リンクが成立しました。鵠沼はこの大庭御厨に含まれます。源義朝らが鎌倉から越境乱人した事件が「天養記」に記され、その場所は鵠沼てあったとみられています。鎌倉時代から室町時代、京から鎌倉への”鎌倉街道”がこの地を通っていました。中世の和歌や紀行文に登場する“砥上が原(とがみがはら)”という地名は、この辺りが荒野てあったことを示す地名です。また、鎌倉にほど近いため、鎌倉末期からの戦乱に巻き込まれていたと見れれています。江戸時代になると、鵠沼村の北西部を皇大神宮の周辺を中心に農を営む集落が発達してゆきます。江戸初期には、鵠沼村は2家の旗本(大橋氏・布施氏)の知行地と天領になりました。大橋領は江戸中期に上知(幕府に返す)となりますが、布施家の領地は幕末まで続きます。砂地が多いため田圃は鵠沼北部川沿いに集中しますが、南部の海岸地帯では地引網による漁が行われ生活の糧となります。また、江戸後期には、砂丘地帯が幕府の鉄炮場として使われていました。また、東海道・藤沢宿と江の島をつなぐ“江島道”が村内を通っており、境川を渡る場所は石上の渡し(または石亀の渡し)と呼ばれ、江島参詣に訪れた旅人の道中記にも度々登場しています。明治時代になると、鵠沼にも新時代の波が押し寄せます。海岸が海水浴場として注目されると、我が国初の別荘分譲地が開発力ぐ立ち上がります。明治35 (1902 )年9月1日に、藤沢一片瀬駅(現:江ノ島駅)間に江之島電気鉄道(現江ノ電)が開通、碁盤の目状の整備された別荘地には東京から移り住む人もありました。さらに、鵠沼海岸を目の前にした旅館東屋は、「文士宿」の異名で知られ、多くの文人が集いました。また、江の島と湘南の海の美しい景色は芸術家らにも愛され、鵠沼海岸は東京からほど近いリゾート地として人気を博していきます。戦後、鵠沼南部は別荘地の名残を留めつつ、比較的緑が多い閑静な住宅地が形成されていきます。鵠沼北部も、藤沢駅にほど近い利便性の高さから商業地・住宅地も増え、藤沢市の中心市街地となりました。また、交通の便がよく、環境にも恵まれている鵠沼は、現在では藤沢市内13地区の中で最も人口が多い地域になっています。] [【鵠沼の集落】明治初期の鵠沼村には 14 の集落があり、戸数も 300 戸に満たない村でした。その中でも、人口の集中した集落は 9 つ(上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川)で、この辺りを鵠沼本村といい、いずれも皇大神宮の氏子集落です。ほとんどの家は農業を生業としていましたが、網元を営む家も数軒あり、鰺・鯖・鰯・カマスなどを主に獲っていたそうです。明治時代に入ると漁法の革新により盛んになり、漁業組合もできましたが、現在では堀川網一軒が残るのみになりました。]明治初期の鵠沼村。鵠沼地区の小字名・集落名(下記はネットから)上村・宮之前・清水・宿庭・苅田・大東・仲東・原・堀川の9村の位置図。ここ「鵠沼地区宗教史年表」👈️リンクから。 左:明治時代の鵠沼村の集落と小字右:現在の鵠沼地区の住居表示 をネットから。相模国準四国八十八ヶ所👈️リンクとは。[=四国遍路とは= 参考:「四国路八八ヶ所巡礼の歴史と文化」 森正人著古来、四国は都から遠く難れた修行の場でした。弘法大師(空海)もこの地で修行され、八十八ヶ所の寺院などを選び四国八十八ヶ所霊場を開創されたと伝わります。中世には修験者が、未開の地(四国)の弘法大師の霊場を巡る修行が行われていたことが知られています。四国遍路の成立時期については諸説あり、江戸時代にはいってからと見る説が有力です。四国遍路の特徴は、札所寺院の本尊は、阿弥陀如来もあれば弥勒菩薩もあり、さらに宗派も真言宗だけではありません。四国八十八ヶ所の寺院に共通しているのは、本堂の他に大師堂があり、このニつを参拝することが求められている点です。※お砂踏み~現代の四国八十八ヶ所巡り~参考: (ー社)四国八十八ヶ所震場会四国八十八ヶ所霊場各札所の「お砂」をそれぞれ集め、その「お砂」を札所と考えて「お砂」を踏みながらお参りするこです。そのご利益は、実際に遍路をしたことと同じであるといわれております。江戸時代には、四国八十八ヶ所霊場を模し新四国、島四国、八十八ヶ所などと呼ばれるうつし霊場やお砂踏み道場などが日本全国に数多く造られました。=相模国準四国八十八ヶ所=相模国準四国八十八ヶ所は、文政年間に鵠沼村堀川の浅場太郎右衛門によって作られ、現鎌倉市の西部から、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町の各地に札所が置かれました。その経緯は、浅場太郎右衛門の父が、下総国相馬郡に本四国を写した霊場を見たことに端を発します。後に、鵠沼の近辺にも作りたいと普門寺の住職善応密師に相談し、弟子の浄心を派遣し、霊場の砂土を採ってこさせました。相模の霊場は、元々御堂のある場所や墓地を選び、霊場の砂を埋めた上に、大師像を安置しました。その事情は、江戸時代の巡礼案内書にも記されています。この霊場の完成は、父の十七年忌(文政四年(1821))を期して、息子の浅場太郎右衛門が大師像を造り各地に設置したという説が有力です。その根拠は、大師像のいくつかの年銘が、文政3、4年であることにあります。霊場番号については、本四国が阿波から1番、2番と巡礼道の順に振られているのに対し、相模の札所番号はバラバラてす。震場として選んだ場所それぞれを、本四国の震場と環境が似ている、名前が似ているなど、何らかの類似点を見出し割り振ったのではないか見られています。なお1番札所の感応院👈️リンクは普門寺の本山であります。1番と結願の88番札所(普門寺)の2箇所は、本四国とは関係なく決められたものでしょう。この霊場をつくった縁によるものか、感応院の「霊簿記」には浅場太郎右衛門の名が大旦那扱いで記名されているそうてす。=藤沢の「相模国準四国八十八ヶ所」研究=創設当初は巡礼者でにぎわっていた相模国準四国八十八ヶ所も、時代が過ぎ戦後になると巡拝する人もほとんどなく、「藤沢市史」等に戦前の大師講の様子が僅かに記されている程度でした。(「藤沢市史第7巻」民俗編 第六章 信仰と民間療法)] 私の「四国八十八ヶ所霊場巡り」👈️リンクは車での移動であったが、既に2015年に結願しているのだ。[昭和30~40年代、忘れ去られていた相模準四国八十八箇所について、江戸時代に書かれた巡礼案内書が読み解かれました。一つは、茅ヶ崎の南湖金剛院が所蔵していたもの。もう一つは、鵠沼堀川の山上家が所蔵していたものです。これらの古文書から、相模国に八十八ヶ所を創設した経緯、各札所の御詠歌、お勧めの巡礼行程など判明しました。その後、平成になり「鵠沼を語る会」の有志の方々によリ弘法大師像が安置されている位置も調査され、一冊のガイドブックにまとめられました。なお、山上家本の方は、鵠沼に住んていた民俗学者丸山久子氏が解読し発表されました。]相模国準四国八十八か所の順路をズームして。以上 ポイントを纏めると●相模準四国八十八箇所の概要 ・概要: 四国八十八箇所の写し霊場で、弘法大師石像が各札所に祀られています。 ・構成: 藤沢市、鎌倉市、茅ヶ崎市、高座郡寒川町、横浜市泉区にまたがる88か所の札所。 ・起源: 江戸時代の文化・文政期に普門寺の善応師と鵠沼(くげぬま)の浅場太郎右衛門が 発願し、文化3年(1806年)に計画されました。 ・ご利益: 四国霊場を巡るのと同等のご利益があるとされ、手軽に巡拝できることから 流行しました。 ・現状: ・明治時代の神仏分離令や関東大震災、開発などにより、廃寺・移転・消失した札所が あります。 ・昭和50年代以降、調査が進み、現在では85体の弘法大師像が残っていることが 確認されています。 一部の札所では、ウォーキングイベントなども開催されています。相模国準四国八十八か所の札所リストをネットから。・相模国と呼ばれたエリアの弘法大師霊場。・霊場札所の御本尊は、弘法大師石仏となる。・堂となっていても、屋外に石仏が祀られているだけのケースもある。・開創者の浅場太郎右衛門は鵠沼村の住人で、善応は88番普門寺の住職だった人物。・慶応4(1868)年の神仏混淆廃止、明治2(1869)年の神仏分離、廃仏毀釈、さらに 関東大震災によって廃寺や廃堂となった札所が多い。・結果、札所の移動もかなりあり、弘法大師の石仏が行方不明のケースもある。・当時の札所配置で、春の彼岸の際に4日ほどで巡拝する人が多かったようだ。・不定期ながら、巡拝ウォーキングのイベントなども開催されている。霊場の写真もネットから。鵠沼の弘法大師像堀川の淺場太郎右衛門父子二代の発願になる「相模國準四國八十八箇所」のうち、鵠沼村内に置かれたものは次の9か所である。この他に法照寺境内には、もう1体の弘法大師像が小堂内に安置される。手前が第48番札所の大師像とされる。相模國準四國八十八箇所の概略は第0084話、詳細は相模国準四国八十八ヶ所を参照されたい。第七十九番 大東観音堂第六十三番 毘沙門堂第五番 原地蔵堂 地蔵立像と併置第二十五番 濱道堀川地蔵堂 地蔵立像と併置第五十六番 堀川大師堂 地蔵坐像と併置第四十一番 苅田稲荷社第四十七番 密嚴山遍照院普門寺大師堂第四十八番 善光山天龍院法照寺第八十八番 密嚴山遍照院普門寺本堂=結願札所鵠沼地区地蔵尊・弘法大師像年表 西暦 和暦 月 日 記事1654 承応 4 5 吉 石上の地蔵菩薩立像、造立(鵠沼最古の石仏。昔は石上の 渡し場近くにあった)1655 承応 5 石上稲荷神社境内の地蔵菩薩立像、造立(遺失)1670 寛文10 8 16 本鵠沼2-4-36大東町内会館裏の地蔵菩薩立像(南無阿弥陀仏)、造立1780 安永 9 11 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の地蔵菩薩像(立像丸彫り)、造立1820 文政 3 6 吉 法照寺境内の第48番札所弘法大師石像(坐像丸彫)、造立1820 文政 3 6 吉 鵠沼海岸7-4-17地先浜道地蔵堂の第25番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 6 吉 浅場邸内の準四国八十八箇所霊場第56番札所弘法大師像(坐像丸彫)、 造立1820 文政 3 本鵠沼5-10-21苅田稲荷の第41番札所弘法大師像(坐像丸彫)、造立1821 文政 4 3 浅場太郎右衛門、普門寺境内に大師石像と大師堂建立1843 天保14 2 4 堀川山上新右衛門、鵠沼海岸7-19-12に地蔵尊立像・高根地蔵堂造立1943 昭和18 日本精工拡張で東毘沙門堂準四国第63番大師像を鵠沼墓地 髙松家墓所に移動1958 昭和33 1 20 鵠沼松が岡4-19-5小田急線一木通り踏切脇の地蔵菩薩立像、造立1986 昭和61 11 21 鵠沼神明3-4(鵠沼墓地)の延命地蔵、造立1995 平成 7 関根善之助、普門寺境内に大師堂建立、寄進 ・・・つづく・・・
2025.11.25
閲覧総数 305
-
6

龍の口竹灯籠へ-1
すばな通りを進むと、右手にあったのが江ノ島電鉄「江ノ島」駅。 江ノ島電鉄「江ノ島」駅前の小鳥オブジェ・通称『江のピコ』。小鳥のオブジェ付きの車止めの名は「ピコリーノ」。地元の女性が季節に合わせて手編みのカラフルな衣装を着せ替えていることで有名で、観光客の人気スポットになっている。もともとは、子どもがポールに飛び乗って怪我をしないようにという安全対策の工夫として小鳥のデザインが採用されたもの と。踏切を渡り、「江ノ島駅」を見る。 そして目的の「龍の口竹灯籠」の行灯(あんどん)型の照明 。和紙風のパネルに、幾何学模様(和柄・アイヌ文様にも近い図形)がプリントされていた。模様は矢羽根、山形(杉綾)、菱形などを組み合わせたデザイン。「龍口明神社(元宮)」の石鳥居が左手に。もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んでいたという。大正12年 (1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年 (1933年)に龍口の在のままで改築したが、昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転した。なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており(周りは藤沢市片瀬)、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で残されている。扁額は「龍口明神社」。「第十五回 龍の口竹灯籠」のポスター。・開催日: 2025年11月14日(金)、15日(土)・時間: 午後5時~午後8時・場所: 龍口寺境内(神奈川県藤沢市片瀬3-13-37)・内容: 龍口寺境内に約3,000基の竹灯籠が並べられ、ろうそくの光に包まれる幻想的な秋の夜を楽しむイベント。詣者のご先祖様の供養や願いごとの祈願も行われると。龍口寺境内に並べられた約3,000基の「竹灯籠」に灯るロウソクの光に包まれながら本堂前に施餓鬼壇を整え、参詣の方々のご先祖様や、亡くなられた方のご供養や、お願いごとなどの祈願を行います。竹灯籠の灯りが描き出す幻想的な夕べを大切な人とお楽しみください と。灯籠奉納受付所のテントが前方に。「奉納者芳名板(ほうめいばん)」が右手に。 龍口寺の仁王門(山門)前の「第十五回 龍の口竹灯籠」の入口の飾り。複数の竹灯籠を組み合わせたゲートが設置されていた。● 左側の竹灯籠の刻字「龍 口 寺」1本の竹に「龍」「口」「寺」の3文字が、節と節の“間”に1文字ずつ縦に配列されていた● 右側の竹灯籠の刻字「藤 沢 市」(同じ構造)● 中央下部の竹筒「竹灯籠」と刻まれた短めの竹灯籠が金属製U字ガードレールの前に置かれている。仁王門。扁額「龍乃口」と。 仁王門の先の石段。山門前の石段を斜めから。山門は元治元年(1864)竣工で、欅造り銅板葺。大阪雲雷寺の発願で、豪商鹿島屋某が百両寄進し建立された。正面から。短い竹筒の上部を斜めに切られた竹灯籠が中央、左右に並べられ、内部に本物の蝋燭が灯されていたのであった。LED ではなく蝋燭の灯りが特徴。蝋燭の灯りの特徴。・光が 揺らいでいる(ゆらぎのある光)・光の色が 温かみの強い橙色で、中心が明るく外側が徐々に弱まる・切り口から漏れる光が不均一で自然な形状をしている・同じ灯籠でも光の強弱が微妙に違う・LED特有の白っぽさ・均一な広がりがない上部から覗くが如くに。龍の口竹灯籠会場図。山門の両側に置かれた和傘が刻々と色・模様が変化する、プロジェクションライト(模様投影ライト)が照射されて。左側。右側。「アメリカデイゴ(亜米利加梯梧)」の花もライトアップされて。バナナのように反り返った形 をしている赤い花をズームして。山門を潜ると参道の両側には、多くの竹灯籠(たけとうろう) が びっしりと並んでいた。大小さまざまな竹灯籠。斜めの切り口から炎の橙光が漏れるのであった。光がひとつひとつ微妙に揺らぎ、均一ではない自然な光のゆらめきが生じている。LED光ではなく蝋燭のため、光の揺れ方・明滅の仕方が柔らかいのであった。参道の右側に並べられた竹灯籠は、渦巻き状・曲線状の軌跡を描いて配置されていた。移動して。竹灯籠一つひとつの内部で灯る蝋燭(ろうそく)は、・揺らぎのある光・中心が明るく、周囲が自然に減衰する光・個体差のある微妙な強弱を持っているのであった。大書院への石段にも竹灯籠が並び、その上にも竹灯籠のオブジェの姿が。ズームして。裏側から見ても絵柄模様が判らなかった。周囲は暗く、灯籠だけが明るいため、コントラストが高く、光の形状が際立つのであった。竹筒は一本一本、太さ・節の位置・切り口の角度が僅かに異なる。その差が光の強弱として現れ、LED照明とは違う自然な揺らぎとなって視覚に訴えるのであった。竹灯籠の光が地面や石段に反射し、弱い二次光が全体の明るさを底上げしていると感じるのであった。手水舎手前を。大本堂とのコラボ。闇に沈んだ境内の土の上に数え切れぬほどの小さな灯りがまるで呼吸するように揺れていた。ひとつひとつは、竹の内奥で燃える小さな炎にすぎないのに、寄り添い、並び、つながるとまるで大地そのものが灯っているかのようであった。渦を描く火の道は、見えない風の手に導かれ、やがて階段の灯りへと吸い込まれていく。その先には、古い寺の影が青白い光に照らされて、息づいているのであった。炎は風に怯えながらも、一瞬のために命を燃やし、闇の中で人の心をそっと照らしていた。立ち止まったその場所だけ、時が静かに、柔らかく、滲むように流れていたのであった。左手には浄行菩薩像が。大本堂前。大本堂前から山門方向を見下ろして。参道には多くの見物客の姿が。 ・・・つづく・・・
2025.11.23
閲覧総数 430
-
7

片瀬西海岸からの夕景-1
この日は11月15日(土)、朝から鵠沼へ「藤沢地名の会 地名探索」に参加し15時前に終了し解散する(後日ブログアップ予定)。17時から始まる片瀬・龍口寺で開かれている「第15回 龍の口 竹灯籠(たけとうろう)」を観に小田急片瀬江ノ島駅に向かう。片瀬江ノ島駅構内には大型のクラゲの水槽が設置されているのだ。半透明のミズクラゲでゆったり浮遊する様子は実に幻想的なのである。クラゲ水槽に近づいて。クラゲ水槽は改札内へのコンコースにあり乗降客は早速記念写真やスマホに撮っていた。この水槽は少し離れた場所にろ過装置が設置されていて、配水管を通し水質管理、水温調節、異常が生じれば新江ノ島水族館に即伝わる仕組みなどが備えられているのだと。同館クラゲ担当の方は毎日、餌やり、海水の状況、ミズクラゲの姿の確認など行うのだ と。ミズクラゲ(Aurelia aurita)をズームして。特徴は・体が円盤状で透明。・中央に四つ葉のクローバー状の“4つの輪”(=生殖腺)が見える。・触手は細く短い と。■ どこに生息している?・世界中の温帯〜熱帯海域に広く分布。・日本では沿岸部ならほぼどこでも見ることができる。・港湾や内湾など、やや富栄養化した場所にも多い。1. 傘の縁に細かい“フリル状のひだ”が並んでいるミズクラゲ最大の特徴は、傘の縁に多数の触手(短いタテガミ状)がずらりと並ぶこと。この縁の部分だけがくっきり写り、「レース」「羽毛」のように見えたのであった。・薄くて平たい傘 横から見ると、ミズクラゲは扇形・半月形に見えることがある。・傘表面に模様が無い タコクラゲ、サカサクラゲ、アマクサクラゲなどは模様があるが、 ミズクラゲは透明で模様がほぼ無いのだと。傘をゆっくり収縮→拡張のリズムで動いていた。主に“漂う”生き物で、潮流や水流に大きく影響されるのだと。小田急電鉄・片瀬江ノ島駅(2020年改築の新駅舎)。この駅舎は、日本でも珍しい 「竜宮城(りゅうぐうじょう)をモチーフにした駅」 として有名。■ 1. 竜宮城をイメージした外観・建物全体が「浦島太郎がたどり着いた竜宮城」をモデルに設計・朱色・金色・青緑の屋根という華やかな配色・千鳥破風・唐破風、曲線の軒先など“神社建築+竜宮城”のデザイン → 江ノ島観光の玄関口として象徴的な駅舎に仕上がっている■ 2. アーチ形の入口(白い「門」)・写真中央の白いアーチ部分は、・竜宮城の入口「門」のような造形を模しており、・曲線を強調した意匠になっています。■ 3. 金色の装飾・屋根の各所に金箔風の装飾が施され、・「竜宮城の豪華さ」を演出。そして片瀬西浜にある片瀬漁港に向かって進む。片瀬江ノ島駅前(駅前ロータリー付近)から美しい夕日の姿が現れた。時間は17:12。この場所のこの日の日没は17:37と。椰子(ヤシ)と夕日のシルエット。フェニックス(カナリーヤシ)。江ノ島周辺のランドマーク的な植栽で、リゾート感を演出しているのであった。国道134号線が前方に。江ノ島周辺ならではの植栽である フェニックス(カナリーヤシ) が逆光でくっきり浮かび上がり、晩秋の江ノ島らしいドラマチックな夕景が眼前に拡がったのであった。まっすぐ伸びた高いヤシの木は、江ノ島周辺によく植栽されているフェニックス・カナリエンシス。幹が真っすぐ、頭頂に大きな扇状の葉、シルエットが非常に美しい樹形なのであった。夕日との相性が抜群で、まさに「湘南らしい風景」を象徴しているのであった。雲の下に空隙(すきま)があり、太陽光がそこから漏れていた。晩秋・初冬特有の澄み切った空気によって、黄金色が強く出ていて、海面からの反射光が写真下部を明るく照らしているのであった。江の島漁港の整備完了を記念して、「無事故を祈願して」建てられたという「海の詩」の像。■ 作品名海の詩(うみのうた)■ 作者親松 英治(おやまつ えいじ)日本の彫刻家で、湘南地域に複数の作品を残しています。■ 所在地片瀬漁港(片瀬海岸)の広場江ノ島水族館の少し西側、片瀬漁港荷捌き場の前に設置。■ モチーフ海の生命力人と魚が一体化したような躍動的造形「海とともに生きる片瀬・江の島」の象徴的作品 と。「海の詩」のシルエットが完全に夕日と重なり、“躍動感”が強調された写真が撮れたのであった。移動して、江の島を背景に。片瀬漁港(片瀬江の島漁港)から見た相模湾の夕日 を捉えて。手前が片瀬漁港の内湾。静かな水面が夕日の光を伸びやかに反射していた。片瀬漁港の外側の防波堤には人影が見え、散歩や写真撮影をする人が立ち並んでいるのがわかるのであった。雲の下側が切れているため、雲と地平線の隙間から光がこぼれる“ドラマチックな夕焼け” の典型的パターンを捉えることが出来たのであった。非常に薄くだが、遠くに箱根・伊豆半島の山影が見えた。条件が良い日はこの位置に富士山のシルエットも現れるのだが、この日は富士山は雲に隠れて。海面の反射(グラデーション) が主役になっていたのであった。片瀬漁港の外側の防波堤をズームして。その手前には、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が現れていたのであった。太陽から海面にまっすぐ伸びる光が美しく、静かな片瀬漁港の雰囲気を引き立てていた。片瀬漁港から江の島を望む夕景を。漁船の静かな佇まいと、江の島シーキャンドル(灯台)のシルエット、そして海面に映る柔らかな光が融合して、まさに “片瀬漁港らしい夕景”なのであった。写っているのは片瀬漁港の定置網・釣り船・遊漁船など。写真中央の船には「第十八ゆうせい丸」と読み取れる文字があり、実際に片瀬漁港に所属する船。太陽が雲に隠れて、水面の黄金の“光の道”(サンロード)が姿を消した。夕陽が沈みゆく空の中で、雲の縁だけが薄く金色をまとい、まるで空が自らの境界をそっと縁取っているように白い輝きが静かに滲んでいるのであった。雲のふちに夕陽の光が当たって、白くきらりと光っている。まるで雲が輪郭だけ輝いて浮かび上がっているようなのであった。そして沈みゆく太陽が厚い雲の下からわずかに顔をのぞかせ、その光が雲の縁を内側から焼き付けるように再び白く輝く。闇へと沈む雲の下で、陽光だけが最後の抵抗のように鋭い光の縁を刻んでいるのであった。沈む陽が雲の縁を白く照らし、港の水面まで夕光が流れ込む時間なのであった。停泊した漁船の影が静かに伸びて。いつまでも佇んで見つめていたい時間、空間なのであった。ズームして。太陽に近い部分は、黄色・白色・ややオレンジが混ざった高輝度の輝きが確認できる時間なのであった。反射の中心は太陽直下にあり、強い橙色の帯(光の道)が水面に伸びていた。水面は完全な静水ではなく、小さな揺れ(リップル)があるため、反射光が細かな線状に分解されて揺れて見える状態なのであった。太陽は水平線に向かって。円形がほぼ完全に見える状態に。厚い雲の縁は太陽が真下にあるため、逆光によって輝く「エッジライト」現象が発生しているが如くに。 ・・・つづく・・・
2025.11.21
閲覧総数 404
-
8

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-5
★六会地区 歴史年表-14年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代昭和21年 1946 NHKのど自慢開始👈️ 極東軍事裁判👈️ 23年 1947 第一回市長公選、無投票で飛嶋繁当選 学校教育法に基づき新制六会中学校発足 旧横須賀海軍無線送信所の兵舎を仮校舎 とする 24年 1948 六会に市役所の支所(旧六会村役場)設置 一ドル三六〇円の 日本大学農林高等学校創立 為替レー ト設定 市制施行一〇周年、市歌・市章制定 ソ連からの引揚船 大船駅と小田急六会駅間にバス運転開始 舞鶴港に到着 湯川秀樹👈️ ノーベル物理学賞 25年 1950 六会中学校校舎増築完成 朝鮮戦争勃発👈️ 日本大学藤沢高等学校へ改称 藤沢市人口 土棚円行耕地整理組合結成 八四五八一名 会長に高瀬知治就任 26年 1951 市内各小学校で完全給食開始 第一回紅白歌合戦放送 日本航空発足 27年 1952 部落長を自治会長に改称 六会小学校の給食調理室完工 韓国李承晩ライン👈️ 設定宣言 28年 1953 六会中学校校歌👈️制定 テレビ放送開始 👈️ (広田俊夫作詞、市川達雄作曲) 六会小学校六〇周年記念事業の校庭 整備工事完成 六会慰霊塔除幕式挙行 29年 1954 六会地区体育振興協議会設立 第五福竜丸ビキニ環礁で 下土棚の精米所閉鎖される 被爆(水爆実験)👈️ 自衛隊発足 👈️ 青函連絡船「洞爺丸」👈️ 遭難事故発生 30年 1955 六会中学校増築工事完成 第一回水爆禁止大会(広島) 石川山田橋竣工 神武景気始まるテレビ・ 亀井野の平川秀雄、六会幼稚園を創立 電気洗濯機・電気冷蔵庫 六会駅近くの山林の一部が造成され、 普及(三種の神器) 三期にわたって分譲地として販売始まる 第一〇回国民体育大会 開催(藤沢を中心会場に) 31年 1956 亀井神社の参道が改修される 六会地区有線放送電話開通 32年 1957 六会小学校の図書館完成 南極観測隊昭和基地開設👈️ 六会中学校にプール完成 33年 1958 横浜開港一〇〇年 34年 1959 石川中の塚に市汚物処理場起工 メートル法実施 石川丸石公民館落成 伊勢湾台風上陸👈️ 石川に市農村青年研修所新設 藤沢市民交響楽団誕生 35年 1960 市制ニ〇周年記念式挙行 36年 1961 いすゞ自動車(株)藤沢工場操業開始 インスタントコーヒー 、 プレス工業(株)操業開始 即席ラーメン発表 住宅開発始まる ダッコちゃんブーム ★六会地区 歴史年表-15年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 37年 1962 堀江謙一ヨット世界一周 👈️ 国産第一号炉に原子の火 38年 1963 亀井野地区の工業用水工事中、 トンネル内で五名生き埋め、 三名死亡事故 発生 39年 1964 六会中学校増築工事落成 東海道新幹線開業 👈️ 下土棚市営住宅起工 東京オリンピック開催 東京オリンピック聖火リレー藤沢市内 「高砂丸」👈️ 通過 北部第一区画整理事業認可(一九八四年 完了) 40年 1965 六会小学校体育館落成 名神高速道路開通👈️ 猿田彦大神の石廟市の文化財に指定 藤沢市の人口 一七五一八三名 41年 1966 六会地区社会福祉協議会発足 敬老の日 六会地区青少年育成協力会発足 体育の日設定 善行小学校創立、生徒数 四一五名 (六会小学校内に仮設) 円行石川の一部に桐原町誕生 小田急線湘南台駅開設 42年 1967 六会中学校体育館落成 北部学校給食合同調理場が六会中学校の 敷地内に開設 桐原公園開設 石川の伊沢暁ガソリンスタンド設置 藤沢北郵便局、下土棚に開設 富士見台小学校創立 石川の畑信裕ハタ・オートキット開設 (洋蘭の温室経営) 43年 1968 東京府中、三億円事件 発生👈️ 全国一一〇の大学で 学園紛争起こる 44年 1969 藤沢市農業協同組合設立 (村岡・藤鵠・明治・六会・御所見・ 小出の各農協合併) 老人福祉センター「やすらぎ荘」開設 45年 1970 湘南台幼稚園設立 国産初の人工衛星 六会行政センター(市民センター)改築開館 打ち上げ成功 石川の角田ヨシ方の「梅の木」市の 「おおすみ」👈️ と命名 天然記念物に指定 大阪万国博覧会開催👈️ 六会地区自治会連合会結成 三島由紀夫ら楯の会、 六会中学校コンピューター教育の実験授業開始 自衛隊乱入、割腹事件 下土棚、善然寺本堂起工式 発生👈️ 県立ゆうかり園開園 藤沢市人口 ニニ八九七八名 46年 1971 六会小学校前歩道橋完成 大相撲、大鵬引退👈️ 俣野小学校創立 (優勝三ニ回) 六会郵便局町田線沿いから六会駅前に移転 西俣野初老(五〇才~六〇才)を対象に 常磐会結成 (会員五十名) 六会地区交通安全対策協議会発足 六会地区防犯協会発足 47年 1972 今田郵便局開設 札幌冬季オリンピック 下土棚が長後地区へ編人される 開催👈️ 石川東部土地区画整理組合結成、 沖縄日本復帰👈️ (組合員一五〇名) 連合赤軍、浅間山荘 亀井野に六会東部土地区画整理組合結成 事件発生👈️ (組合員五三〇名) 横井庄一、グアム島で発見 田中角栄通産大臣 「日本列島改造論」発表👈️ ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.14
閲覧総数 820
-
9

片瀬西海岸からの夕景-2
太陽が再び顔を見せ、見事な光の帯が。反射光が細かく分断され、光の帯がざらついた質感で揺れて見えていた。手前側は比較的影になっているため、反射光の明るさがより強く際立つ状態で。光の帯の先端の砂浜で遊ぶ親子連れ。これは典型的な「サンロード(太陽の道)」と呼ばれる現象。「太陽の道」とは、弱い風が吹き、水面に小さな波が立つなど特定の条件が揃った時に、水面に光が反射して道の様に見える自然現象を指す。ズームして。太陽が水平に伸びる雲に一部隠されている状態を正面から。太陽の上半分は雲の上に出ており、下半分は雲の下から。海面には太陽の光がまっすぐ縦に反射していて、明るい光の帯が海の表面に伸びていた。水面は大きく荒れてはいませんが、小さなさざ波があり、光の帯が細かく揺れた模様に。空は太陽の周りが濃いオレンジ色で、上の雲は暗く、下の方へ行くほど赤みのある色に変わって。遠くの海は影になっていて、徐々に暗く見えて来たのであった。片瀬西浜から平塚方面へ向かって、長い砂浜がゆるやかに湾曲しながら続いている様子が見えた。相模湾沿いの特徴で、江の島を基点にして西方向へ大きな弧を描くように海岸線が伸びていた。伊豆半島がプレート運動で北北西へ押し込まれているため、相模湾全体が湾口が開いた弓形の地形になっているのだ。相模川・酒匂川などの河川が運んだ砂が、沿岸流によって東へ運ばれ、藤沢・茅ヶ崎方面に供給されることで砂浜が維持されているのだ。明るい光の帯(サンロード)が次第に弱くなり始めた。太陽をズームして。夕日が水平に伸びた雲の隙間から見えている場面。太陽はほぼ沈む直前で、細長い楕円形のように見えて来た。雲に隠れているため、上半分が覆われ、見えている部分が横に押しつぶされたような形なって来たのであった。海面が適度に揺れているため、光は一本の線ではなく、細かく分かれた光の筋が連なって帯状になっている状態に変化して。手前の海面では光が広がり、ゆらぎを伴った反射となり、光の帯がやや太く見えて来た。全体として、夕日が海面に強く反射してできる、典型的な日没時のサンロードが。太陽が水平線上部の黒い雲に隠れて、これがこの日の日没の如くに。空全体は夕方の光で淡い橙色から赤みへと変化し、上層の雲も同じ色調に染まって来た。水平線上部は暗く影になっており、その上に太陽の明るい部分だけが強く浮き上がって見えているのであった。この日の日没を追う。そしてこの日の太陽は完全に水平線上の雲に隠れて。江の島の姿を。江の島シーキャンドルの灯りは未だ。ゆるやかに湾曲する西浜からの砂浜の光景を見る。真っ赤に色づいた太陽が地平線近くに沈み、相模湾の海面からは光の帯が完全に消えて。海は夕方の暗さを帯び、表面にはわずかな揺れだけが残り、静かな水面が一様に赤みを含んだ淡い光を受け止めていたのであった。相模湾全体が静まり、光も影もゆっくりと均されていく、落ち着いた夕暮れの瞬間なのであった。江の島を背景にした、片瀬漁港周辺の夕方の光景。左奥には江の島シーキャンドル(展望灯台)があり、島全体が落ち着いた薄暗い色に包まれて来たのであった。西浜を後にして国道134号を江の島入口方向に向かって歩く。辻堂方面を振り返って。関東ふれあいの道「関東ふれあいの道」は、一都六県を巡る自然歩道です。沿線の豊かな自然にふれ名所や史跡を訪ねながら、古里を見直してみませんか。⑥ 湘南海岸・砂浜のみちこの道は、県内17コースのうちの6番目です。ここから江の島を背に国道134号を西へ、新江ノ島水族館、湘南海岸公園を通り、鵠沼橋の西縁には聶耳(ニェアル)記念碑が建っています。鵠沼橋を渡るとサイクリングロードに入り、右手に松林、左手に砂浜を眺めながら歩くと、茅ヶ崎柳島海岸が終点です。途中、海に浮かぶ烏帽子岩(えぼしいわ)や平島を見ることができます。終点からは、国道134号を渡って、北へ600mくらい歩くと、浜見平団地バス停(茅ヶ崎駅行)に到着します。片瀬橋から境川の河口そして江の島を見る。上流側には小田急線・片瀬江ノ島駅に続く弁天橋を見る。江の島上空も僅かに赤く染まって。江の島入口交差点の横に建つマンション群。小田急線・片瀬江ノ島駅を弁天橋越しに見る。片瀬江の島観光案内所のすぐ横、江の島へ渡る橋(弁天橋)に向かう歩道沿いに設置されている沿道アート(ストリートモニュメント) 。天に昇るモダンなイメージの龍が。折しも観光客を乗せた人力車が2台。中国人であっただろうか?国道134号「江の島入口」交差点越しに江の島を見る。 すばな通りを江ノ島電鉄・江ノ島駅方向に進む。「塩バニラ君」と。名物江の島塩バニラ・ソフトクリームの店。口に入れると塩気→甘味→塩気と風味が移り変わるのだと。「すばな通り」とは神奈川県藤沢市・片瀬江ノ島駅前から江の島弁天橋へ向かう商店街(約250m)の通り。観光客が江の島へ渡る際に必ず通る“江の島参道の入口”にあたります。江ノ電「江ノ島駅」、湘南モノレール「湘南江の島駅」から江の島に向かう道。「すばな通り(洲鼻通り)」の名前の由来は、この地域に古くからある地名 「洲鼻(すばな)」 に基づくと。● “洲鼻” の意味「洲(す)」= 川口や海辺にできる砂州(砂が堆積した細長い土地)「鼻(はな)」= 地形が突き出した部分(岬のような意味)つまり「海に向かって細長く突き出した砂州の先端部分」を意味する。江の島の付け根(片瀬側)は、昔は砂州が東西に伸びる地形で、まさに「洲鼻(すばな)」と呼ぶのにふさわしい土地であった と。「ここは すばな通り 江ノ電江ノ島駅」碑。 ハラミステーキカレー・ピザの店「Kalae Ribs kitche」。すばな通りを北へ進むと左側に「道標」と案内板。江の島弁財天道標。この道標は、平成十一年一月、ここより170メートル南の洲鼻通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたもの と。「市指定重要文化財(建造物) 昭和四十一年(1966)一月十七日指定「江の島弁財天道標」この石柱は、江の島への道筋に建てられた道標の一つです。江の島弁財天道標は、管を用いて鍼をさす管鍼術を、江の島で考案したという杉山検校が寄進したと伝えられ、現在市内外に十数基が確認され、そのうち市内の十二基が藤沢市の重要文化財に指定されています。すべて頂部のとがった角柱型で、その多くが、正面の弁財天を表す梵字の下に「ゑのしま道」、右側面「一切衆生」、左側面に「二世安楽」と彫られています。この文言は、江の島弁財天への道をたどるすべての人の現世・来世での安穏・極楽への願いが込められています。この道標は、平成十一年(1999)一月、ここより170メートル南の洲鼻(すばな)通りの地下から、道路工事中に発見され、追加の指定を受けたものです。 平成二十六年(2014)三月 藤沢市教育委員会 」 「湘南しらす」の幟旗の店。 「湘南生しらす井 ¥1,450」と。 ・・・もどる・・・ ・・・おわり・・・
2025.11.22
閲覧総数 397
-
10

成田山新勝寺へ
ここ5ヶ月ほど、アイルランド・ロンドン旅行記を長々とアップしてきましたが、今日からは、その後の旅行についてアップさせていただきます。この日は6月13日(金)、成田山新勝寺に自治会役員仲間と向かいました。成田山新勝寺の総門に向かって進む。右手奥に見える大きな屋根の建物が総門で、その先に仁王門や大本堂へと続きく。道の両側には土産屋さんや飲食店が並び、参拝客でにぎわう場所。このあたりは「成田山表参道」と呼ばれ、うなぎ料理や和菓子のお店が多いことで知られているのだ。成田山新勝寺の総門(そうもん)が前方に現れた。総門は新勝寺の表玄関にあたる荘厳な門で、平成19年(2007年)に建立された比較的新しい建築物。門の前には「成田山金剛力院新勝寺」と刻まれた大きな石柱があり、参拝者が記念撮影をしている様子が見えるのであった。この総門をくぐると、次に「仁王門」、そして「大本堂」へと続いていた。ちなみに、総門の屋根は銅板葺きで、木組みの細工や装飾も非常に見事で、伝統的な寺院建築の美しさが感じられたのであった。成田山新勝寺案内図。地図の下の方(南側)から参道を通って入ると、次のような順に主要な伽藍が並んでいた。1.総門(そうもん) — 表玄関2.仁王門(におうもん) — 金剛力士像が守る門3.大本堂(だいほんどう) — 成田山の中心、本尊・不動明王が祀られている4.三重塔(さんじゅうのとう) — 色鮮やかな重要文化財5.釈迦堂(しゃかどう) — 旧本堂6.光明堂(こうみょうどう) — 江戸時代初期の建築7.平和の大塔 — 新しい時代のシンボル塔(仏舎利奉安)また、右上の方には広い池と庭園が描かれており、ここは成田山公園。春は梅や桜、秋は紅葉が美しい散策スポットになっているのだ。ネットから。名称:総門(そうもん)所在地:千葉県成田市 成田山新勝寺建立:平成19年(2007年)再建形式:入母屋造(いりもやづくり)、重層門特徴:伝統的な木造建築で、組物(斗きょう)や彫刻が極めて精巧。屋根の反りや飾金具などに荘厳な意匠が施されています。🔹中央の扁額(へんがく)中央に掲げられている額には成田山(なりたさん)」と。これは成田山新勝寺の山号(さんごう)であり、正式名称:成田山金剛王院新勝寺(なりたさん こんごうおういん しんしょうじ)宗派:真言宗智山派本尊:不動明王(ふどうみょうおう)所在地:千葉県成田市成田1番地創建:天慶3年(940年)開山:寛朝大僧正(かんちょうだいそうじょう) その起源は、平将門(たいらのまさかど)の乱を鎮めるため、朱雀天皇の勅命によって、 寛朝僧正が京都・東寺から不動明王を奉じて成田に来たことに始まります。 戦乱が収まった後も、不動明王は「ここにとどまりたい」と示したため、寛朝が堂宇を建立し、 これが成田山新勝寺の始まりとされています。通称:「成田不動」「成田のお不動さま」・成田山(なりたさん) 「成田」は地名ですが、「成(なる)」=成就・成功、「田」=豊穣を意味することから、 「すべての願いが成就し、豊かに実る地」という吉祥的な意味もあります。・新勝寺(しんしょうじ) 「新たに勝つ寺」すなわち「平和と安寧の勝利を祈願する寺」という意味。 開山の際、平将門の乱を鎮めるために護摩修法を行い、「戦乱を鎮める=勝利する」という 願いから名付けられたのだと。総門を振り返る観光客そして我が旅友。その先に仁王門。仁王門。新勝寺の境内入口正面石段を登ると阿形、吽形の二力士像を安置した仁王門がある。その正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)、左側に口を閉じた吽形の蜜迹金剛(みしゃくこんごう)、裏仏には右側に広目天、左側に多聞天が安置されており、境内の入口にあって伽藍守護の役目を担う。この仁王門は、3間1戸の八脚門であり、屋根正面は千鳥破風及び軒唐破風、背面は軒唐破風付きの入母屋造の銅板葺である。組み物は三手先で、軒は二軒の扇垂木である。両側面の壁には、ケヤキの一枚板を用いるなど、堅牢で宏壮に建造され、材料、工法とも優れており江戸時代末期の特色が見られる。また、頭貫上の各柱の間には、後藤亀之介、天保2年(1831)の竹林の七賢人、司馬温公瓶割りなどの彫刻が施される。建立は、棟札の記述から文政13年(1830)である。名称:仁王門(におうもん)建立:文久元年(1861年)構造:入母屋造(いりもやづくり)・銅板葺(どうばんぶき)・二重門(にじゅうもん)重要文化財指定:1958年(昭和33年)場所:成田山表参道の終点、大本堂へと続く石段の手前に位置仁王門は、成田山新勝寺の表玄関にあたる壮麗な山門で、参拝者が俗世から聖域へと入る「結界の門」としての役割を持ちます。門の中央には、ひと際目をひく大きな赤い提灯が掲げられていた。「魚がし」と書かれた大提灯は、東京・築地の魚河岸の旦那衆が、1968年に奉納したもの。紙張りのように見えるが骨部分は砲金(青銅の一種)製で、重量が800キログラムにもなる と。正面向かって右側に口を開いた阿形の那羅延金剛(ならえんこんごう)。左手に堂庭御護摩受付所横の「光輪閣」入口門。「光輪閣」脇門へと進む。「光輪閣」。1975年(昭和50年)建立本坊(寺務所)及び客殿を備える地上4階・地下2階の建物四階「光輪の間」は千数百人が、一度に入れる480畳の大広間がある。一階が受け付け・二階から四階は坊入りなどの接待をする客殿。明治天皇成田行在所碑。明治14年と明治15年に明治天皇が宮内庁下総御料牧場へ行幸(ぎょうこう)する時に成田山を行在所(あんざいしょ)と定めた。御座所として御駐泊になられたのが明治天皇行在所です。光輪閣後方にある行在所は2014年に修復した と。三重塔。日光東照宮の五重塔と成田山の三重塔が日本で一番絢爛豪華であろう。二軒の板垂木で有名。他の社寺では見ることが出来ない見事な造りである。厚さ20cm以上ある板に雲水紋が彫られていた。三重塔心柱の墨書きには、下記の様に書かれています。棟梁は「櫻井瀬左衛門」の宮大工としての、素晴らしい技術棟 梁 常州那珂郡羽黒村 桜井瀬左衛門次棟梁 同国同郡 中野左五兵衛 同国茨城郡笠間 藤田孫平次 竜の尾垂木彫刻 下総国武射郡堺村 伊藤金右衛門彫物師 江戸○○住 無関圓鉄 羽目板「十六羅漢図」彫刻 法起寺(ほっきじ)の三重塔(国宝)が現存最古の三重塔である。創建は慶雲3年(708年)近づいて。三重塔は、宝永6年(1709)に起工され、正徳2年(1712)に完成した中規模な塔です。心柱の墨書から、宝暦7年(1757)、享和元年(1801)、安政5年(1858)に修理されたことがわかります。高さ約25メートルのこの塔は、初重(第一層)の柱や長押に地紋彫を施し、各重の尾棰を竜の彫刻とし、二間の板軒に雲文が浮き彫りされており、極彩色を施すなど華麗な塔です。この塔は、近世の塔としては、全体の均衡もよく、良質であり、江戸時代中期以後にみられる過飾な建物の、早い時期の遺例として貴重なものです。周囲の十六羅漢の彫刻は、島村円鐡の作です。塔内には五智如来が安置されています。なお建立の際には、佐倉城主から成田の並木及び三之宮神社の松17本と将門山(佐倉市)松5本が寄進されています。板垂木。ズームして。常香炉。聖徳太子堂。移動して。1992年建立の聖徳太子堂。成田山新勝寺の聖徳太子堂は、1992(平成4)年に建立され、2007(平成19)年に修復された。日本の仏教興隆の祖である聖徳太子の理念にもとづき、世界平和を願って建てられました。堂内には、大山忠作画伯の壁画が6面に渡り描かれており、聖徳太子像が奉安されています。聖徳太子像。大山忠作画伯の壁画が堂内六面にあります。写真では牡丹・白鷺・菊が見えた。常香炉を振り返って。左から、三重塔、一切経堂、鐘楼。一切経堂、鐘楼をズームして。巨大灯籠。移動して。石段上から仁王門を見る。常香炉と本堂。仁王門前から総門を見る。参道の両側には石灯籠が並ぶ。
2025.11.16
閲覧総数 416
-
11

牛久大仏へ(その2)
牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)をデザインした絵馬。大仏型の絵馬も、外国人の方が書かれたものがチラホラと。木製の絵馬に青色で牛久大仏の全身シルエットが印刷されていた・右手は「施無畏印(せむいいん)=恐れを取り除く印」・左手は「与願印(よがんいん)=願いを叶える印」・蓮の台座に立つ姿も忠実に描かれていた・紐(赤色)を通して奉納できるようになっていた發遣門(ほっけんもん)牛久大仏の参道に設置された門で、参拝者を阿弥陀如来の世界へ“送り出す”という意味を持つ門。二階建てのガラス張り建築。上階に額(扁額)があり「發遣門」と書かれていた。門の向こうに大仏が一直線に見える参道の構図。左側に石仏が配置されていた。「發遣門(ほっけんもん)」の内部にあった親鸞聖人像と梵鐘(ぼんしょう)。① 親鸞聖人(しんらんしょうにん)像浄土真宗の宗祖牛久大仏は「阿弥陀如来」+「親鸞聖人の教え」を基盤として建立された発遣門の内側に祀られている理由は参拝者が“阿弥陀の教えへ送り出される”象徴 のため像が手に持つのは「念珠(ねんじゅ)」と「杖」 ② 梵鐘(ぼんしょう)寺院で鳴らす伝統的な大きな釣り鐘発遣門内に置かれているのは珍しい配置彫刻には八葉蓮華(はちようれんげ)や唐草模様が確認できるチェーンにつながっている木の撞木(しゅもく)で打てるようになっていた 親鸞聖人像を正面から。参道と牛久大仏。ズームして。牛久大仏が「發遣門(ほっけんもん)」の2階のガラス窓に映り込んでいた。手前には黄金の釋迦三尊像のお姿が。ネットから。釋迦三尊像 釋迦牟尼佛 弥勒菩薩 阿難尊者参道の左手には池が。「群生海「群生」とは、すべての生きとし生けるもののこと。この池は現世そのものをあらわし、水辺を埋め尽くす四季折々の花々はうつろいゆくこの世の無常をあらわしています。」 再びズームして。「お花畑のご案内」。 参道前方に大きな香炉の姿が。牛久大仏の「桜&芝桜エリア」への案内看板。春になると、・ソメイヨシノ・八重桜・芝桜(ピンク色の絨毯)が同時に満開になるため、牛久大仏の春の名物になっている のだと。八重桜と芝桜(ピンク色の絨毯)のコラボ。参道右手にあったのが牛久大仏の「鐘つき堂(自由に撞ける梵鐘)」日本一の大香炉と牛久大仏。近づいて。日本一の大香炉を振り返って。「あじさい 六月中旬~七月中旬」案内板。 「花菖蒲(ハナショウブ)」。そして「紫陽花(アジサイ)」。 牛久大仏を見上げて。ズームして。■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■高さ120mの巨大な阿弥陀如来立像 世界最大級(青銅製立像としては世界最大)■手の印 ・右手:施無畏印(せむいいん) 「恐れを取り除く・安心を与える」 ・左手:与願印(よがんいん) 「願いを叶える・救いを与える」 牛久大仏の最も象徴的な姿勢。 ■蓮台の上に立つ姿 写真の下部に巨大な蓮弁(れんべん)が見える → 阿弥陀如来が極楽浄土に立つことを象徴 ■外側の造形 ・青銅の板を貼り合わせた外殻 ・なめらかな衣紋のライン ・胎内に入れる構造(右胸あたりに展望窓)背中側から見上げて。背中側にも深い衣紋(えもん:布のしわの造形)が刻まれており、下から見ると立体的に浮き出て見えたのであった。牛久大仏の台座の周囲にはサツキの刈り込み生け垣が波のごとくに。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.18
閲覧総数 411
-
12

牛久大仏へ(その4)
牛久大仏の内部見学を終えて、地上へ。「本願荘厳の庭(ほんがんしょうごんのにわ)」・本願(ほんがん) 阿弥陀仏の「本願」(衆生を救う誓願)を意味します。・荘厳(しょうごん) 仏教語で「飾り整えること」「厳かに美しく整えること」。 仏や浄土を荘厳=美しく表現する、という意味があります。・庭(にわ) そのまま「庭園」。つまり 「本願に基づいて荘厳(美しく整え)られた庭園」 という意味で、牛久大仏周辺にある浄土庭園の一部(日本庭園)を指す案内板牛久大仏の敷地内にある 「本願荘厳の庭」 の一部、つまり日本庭園の中心となる 池泉回遊式庭園 の景観。① 池泉(ちせん)庭の中心に広がる大きな池で、水面に周囲の木々が映っていた。池泉回遊式庭園は、日本庭園の中でも歩きながら景観を楽しむタイプで、牛久大仏の庭園でも代表的な構成。② 配石(石組)右側に大きな岩が配置されていた。これは山や島を象徴し、庭園の構図に重心と静けさを与える伝統的な手法。③ 滝口と流れ左奥には小さな滝(流れ)が見えた。水が動くことで庭に生命感を与え、「浄土」の象徴としても用いられていた。④ 植栽(松・低木・刈込)池の周囲には松やサツキ、日本庭園らしい丸く刈り込まれた低木を配置。これらの植栽は四季を感じるために計算されて配置され、春の花・夏の緑・秋の紅葉・冬の雪景色を楽しめるのであった。■ この場所の意味牛久大仏の庭園は「浄土の世界」をイメージして造られており、・水面の静寂・石の安定感・緑の優しさなどが調和した、非常に落ち着いた雰囲気の庭となっていた。滝口と流れ。「大心海(だいしんかい)阿弥陀如来(あみだにょらい)は大海のように広く深い慈悲と智慧のお心ゆえに「大心海」とも言われます。この池は阿弥陀如来そのものを顕わしています。」 ● 「大心海(だいしんかい)」とは?仏教で阿弥陀如来の心を形容する言葉で、「大海のように広く、深く、限りない慈悲と智慧を持つ」という意味がある。「心」が海のように無限に広がり、すべての存在を受け入れ救うという阿弥陀如来の性質を表した表現。● この庭園の池=阿弥陀如来を象徴看板にあるとおり、この池は単なる景観要素ではなく、阿弥陀如来の大いなる心を象徴するために造られた池 です。浄土庭園では、水面に「浄土」を表す意味があり、牛久大仏の庭園でもその伝統が受け継がれている。アジサイの花が開花中。近づいて。牛久大仏の胸部にある三つの長方形のスリット窓(展望窓)を下から見上げて。・大仏の胸(胸部外壁) を下からアップで撮影。・中央に 縦長の窓が3つ・下には袈裟(けさ)のひだを表した曲線の外装パネルが見えた■ この三つのスリット窓の役割① 展望窓(胸部展望室)牛久大仏の内部にはエレベーターで上がれる展望フロアがあり、高さ約85m付近(胸の位置)に展望室があった。そこから外を見るために設けられているのが、この3つの窓。② 外から見るとスリット状に見える理由・仏像の外観デザインを損なわないように細い形になっていた・内部の明かりが外に漏れさせない工夫でもある と。構造上、強風の影響を受けにくい窓形状■ この位置から見える景色胸の展望室からは牛久市一帯、天気がよければ筑波山遠方にはスカイツリー、反対側は霞ヶ浦方向まで見渡せる非常に見事な眺望とのことだが、この日は曇天で視界はあまり良くなかった。再び牛久大仏を正面から。ズームして。戻りながら、牛久大仏の境内にある「売店エリア(仲見世通りのような商店街)」 の様子を。青唐辛子 ちびっこみそ、れんこん関係の商品、にんにく味噌漬けごぼう、野沢菜、きゅうりなどの漬物などが並んでいた。牛久大仏の入口付近に並ぶ土産店のひとつ・「時代屋」。特に 漬物・佃煮・味噌・干し芋・れんこん加工品 など、茨城らしい特産品を多く扱っている店。牛久大仏の「阿弥陀如来像(立像)」を描いた絵馬。牛久大仏のスタンプ(御朱印ならぬ“記念スタンプ”)。丸い頭、柔らかい表情、赤ちゃん風の体型で描かれているのは阿弥陀如来をデフォルメした「子ども阿弥陀さま」 です。・頭の粒々 → 螺髪(らほつ)のデフォルメ・手を合わせている → 合掌(礼拝)・衣は阿弥陀如来の定型の袈裟(衣紋)・足は結跏趺坐ではなく、キャラ風に簡略化牛久大仏の巨大さとは対照的に、親しみを持ってもらうための“癒やしキャラ” に仕上げられていた。御朱印を頂きました。光雲無礙(こううんむげ)意味:阿弥陀如来の光明(慈悲の光)は、雲のようにすべてを覆い、何ものにも遮られることなく(無礙)、すべての衆生に届く。浄土三部経(特に『無量寿経』)に基づく思想で、“阿弥陀仏の光はあらゆる人を隔てなく照らす”という浄土真宗の中心思想。中央の角印は「東本願寺印」(ひがしほんがんじ)を 篆書体(てんしょたい)で分割して図案化したものであろうか。そして帰路へ。大黒PAにてトイレ休憩後、横浜ベイブリッジを渡る。海運業・T.S. Linesの大型トラック。横浜ランドマークタワーがある「横浜みなとみらい21」地区を望む。日本船籍の大型クルーズ客船「飛鳥Ⅲ(Asuka Ⅲ)」。船籍港 日本/横浜全長・全幅 230m×29.8m総トン数 52,265GT喫水 6.7m航海速力 最高20ノット横揺れ減揺装置 フィン・スタビライザー乗客数 740名乗組員数 約470名客室数 381室 (全室海側バルコニー付き)そして、定刻に無事到着し、この日の日帰り旅行を終えたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.20
閲覧総数 334
-
13

牛久大仏へ(その3)
牛久大仏の胎内への入口。■ 牛久大仏・胎内構造(参考)階層 名称 内容地下 光の世界 阿弥陀如来の光を表す演出空間1F 知恩報徳の世界 壁いっぱいの金色の万体仏2F 蓮華蔵世界(ご慈光の世界) 絵画・展示3F 霊鷲山の間 説法の場を模した空間4F (機械室) —5F 展望室(地上85m) 窓から外の景色を眺望※「光の世界」は実際には地下フロアに位置しています。牛久大仏の内部「光の世界」(地下・胎内 1階)。阿弥陀如来像(あみだにょらいぞう) の小型立像で、背後に大きく放射状に広がる 後光(ごこう) が特徴。「光の世界」は牛久大仏の胎内の入り口であり、・阿弥陀如来の十二の光・救済の光・浄土の入り口を象徴した空間。足元には賽銭箱が置かれていた。ズームして。牛久大仏の胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 の内部通路。「光の世界」に続く通路にあたる空間。胎内 2階「蓮華蔵世界(れんげぞうせかい)」 に展示されている光の書(ライトアップ書作品)「本願:阿弥陀如来の根本の誓い「四十八願」の総称。浄土真宗ではとても重要な言葉 無碍光(むげこう):阿弥陀如来の「十二光」のひとつ “さまたげられることのない光”“無限の智慧の光”」 万燈会(まんとうえ):無数の灯り(ろうそく・灯籠)を供え、仏や霊に追善供養する 法会(ほうえ) のこと。 牛久大仏でも、夏の行事として「万燈会」が開催され、 夜の大仏と灯りの幻想的な雰囲気が人気である。 そのため胎内展示にも「万燈会」という書作品が並べられていた。大仏胎内1階の香りは蓮花(はす)の香りです。知恩報徳の世界(2階)阿弥陀如来への報恩感謝の気持ちで、祖師の御化導としての写経をさせていただきましよう と。「東本願寺 浄土真宗東本願寺派 本山」。ここは牛久大仏の内部、展望階(地上85m)へ向かう導線付近の壁面装飾。『空と佛 SORA × HOTOKE地上120m 世界一の大仏様と天空の眺め』“地上120m” は牛久大仏の総高を指し、“天空の眺め” は 大仏胸部(地上約85m)に設けられた展望室からの景観を表していた。さらに進む。額の下の札に書かれている文字:浄土の阿弥陀如来(切り絵)額の右下の小さなラベル:阿弥陀如来立像この作品は、阿弥陀如来(阿弥陀仏)を切り絵で表現したもの。・背後の放射状の光(光背)は「十二光仏」としての阿弥陀如来を象徴・足元の蓮華は「極楽浄土」の象徴・右手を上げ左手を下げた姿は「来迎印(らいごういん)」で、 亡くなった者を浄土へ迎えるときの姿素材が金色で描かれており、切り絵としては非常に豪華な表現。世界最大青銅製の大仏様ギネス世界記録:1995年に登録されました各部寸法・全長 120m・展望台 85m・総重量 4000t・左手の平 18.0m・顔の長さ 20.0m・目の長さ 2.5m・口の長さ 4.0m・鼻の高さ 1.2m・耳の長さ 10.0m・人差指 7.0m(比較図)自由の女神(40m)奈良の大仏(14.9m)階層表示4・5F 蓮華山の間3F 知恩報徳の世界(20m)2F 知恩報徳の世界1F 光の世界牛久大仏 ギネス証「WORLD RECORDGUINNESS BOOK OF RECORDSTHE TALLEST STATUEIS A BRONZE STATUE OF BUDDHA120 METRES HIGHIN USHIKU CITY, JAPANSTRUCTURALLY DESIGNED AND BUILTBY KAWADA INDUSTRIES, INC.AND COMPLETED IN 1993PETER MATTHEWS NORRIS McWHIRTER(Peter Matthews の署名) (Norris McWhirter の署名)」【世界記録ギネスブック(ギネス世界記録)世界で最も高い像は、日本・牛久市にある高さ120メートルの青銅製の大仏像です。この像は 川田工業株式会社 によって構造設計および建設され、1993年に完成しました。(ピーター・マシューズ、ノリス・マクウォーター署名)】 「光雲無碍(こううんむげ)浄土真宗でよく用いられる言葉で、・阿弥陀如来の光明(智慧の光)は、雲に遮られることなく、すべてを照らす・どんな迷いや煩悩があっても妨げられず、平等に救いが及ぶという教義を表す語」 と。右足親指先端の実物大模型牛久大仏の右足親指は、長さ:約1.7m人がすっぽり入るほど巨大で、展示されている模型はその 先端部分 をそっくりそのまま再現したもの と。世界一背が高い大仏浄土真宗東本願寺派・本山東本願寺の開祖・親鸞聖人ゆかりの地である、常陸の国。その地に仏都の中心的なものとして建立されたのが、台座をふくめると120mもの高さになる青銅製立像「牛久阿弥陀大仏」です。この茨城県牛久市にある世界一背が高い大仏は、胎内に入ることができ、地上85mまでエレベーターで上がることができます。総重量は4000t。目の長さ2.5m、耳の長さ10m、人差し指7mという大きさです。浄土庭園本願荘厳の庭(図中の各名称)・正覚の滝(しょうがく)・四十八願の石(しじゅうはちがん)・大心海(だいしんかい)・願船亭(がんせんてい)・因位の流れ(いんい)・悲願の湧泉(ひがんのゆうせん)・願力廻向の流れ(がんりきえこう)・横超の橋(おうちょう)浄土庭園・牛久阿弥陀大仏・本願荘厳の庭・群生海(ぐんじょうかい)・發遣門(はっけんもん)・定聚苑(じょうじゅのその)・正門御本尊(東本願寺御本尊阿弥陀如来立像)四天王寺の宝塔心柱をもって制作された鎌倉時代前期の名作。東京都の有形文化財に指定されている。親鸞聖人御旧跡(~関東における親鸞聖人の足跡~)建保二年(一二一四年)四十ニ歳の春、親鸞聖人は妻子をともなって常陸の国へと移り住まわれ以降、約二十年間にわたってこの地で布教の日々を送られました。稲田を中心に教化を進められ、以降、筑波山、鹿島など各地をまわり布教された親鸞聖人の足跡は、数多くの寺院や旧跡、伝説などによって、今もしのぶことができます。浄土真宗の根本聖典となる「顕浄土真実教行証文類」(教行信証)」は、この間に著されたものであり、その完成年をもって浄土真宗立教改宗の年(一ニニ四年)としています。「親鸞聖人略年譜親鸞聖人は承安三年(一一七三)京都日野の里にてお生まれになりました。養和元年(一一八一)九才のとき、青蓮院において慈円僧正のもとで出家され仏教を学ぶため比叡山に登られ、横川の常行三昧堂で修行された聖人は、どうしても自らの問題を解決できませんでした。建仁元年(一二〇一)二十九才のとき山をは下りられ六角堂に百日間こもられてのち、吉水の法然上人のもとへ行かれました。法然上人のもとで阿弥陀如来の本願による完全な他力念仏(浄土門)を学ばれました。聖人は、阿弥陀如来の本願による念仏の教えは、すべての人々に平等であり、釈尊がお生まれになったのは、この教えを説くためであったと確信し、布教活動をされました。しかし、承元元年(一ニ〇七)三十五歳のとき、念仏禁止の法難にあい越後(新潟県)に流罪になりました。(法然上人は土佐へ流罪)五年後赦免になりましたが、しばらく越後にとどまりました。聖人は、 四十二歳の頃、越後から常陸の国(茨城県)笠間の郡、稲田郷に移られました。稲田を中心に精力的に布教活動を行い、念仏の普及につとめられました。その間、『教行信証』の執筆に力を注ぎ、浄土真宗の教えを文章で著しました。それは阿弥陀如来の本願を信じ、念仏申せば、仏となるという教えであります。六十歳を過ぎてから聖人は、京都に帰ることになりました。京都での聖人は、著述に精進されました。今日残る浄土和讃など親鸞聖人の著作の多くは、晩年に書かれました。幾多の出会いを順縁とし、多くの苦悩を逆縁とし、ますます信仰を深めていった親鸞聖人は、弘長ニ年(一ニ六ニ年)十一月二十八日京都の僧坊にて逝去されました。」 2021年(令和3年)1月12日(火曜日)読売新聞にて掲載された記事です。「渦巻く思い、受け止めて」 牛久大仏胎内の2階には大仏建造に関する資料が展示されていた。頭部の鉄骨模型。牛久大仏(全高120m)内部の骨組み(鉄骨フレーム)を、縮尺模型として表現したもの。実物の牛久大仏は、外側が青銅パネル、内部が鉄骨構造(ビルのような構造)で作られていた。写真の模型は、その内部構造がどのように組まれているかを分かりやすく示した、「立体トラス構造モデル」であった。実際の牛久大仏の内部構造(豆知識)・鉄骨総重量:約6,000トン・鋼板(ブロンズパネル)枚数:約3,000枚・内部は「展望台」「写経の間」などがある複層構造・建築方式は「スチールフレーム構造(鉄骨造)」で、巨大建築物そのもの。牛久大仏の顔と手の骨組みの模型。「高さ100メートルの大掃除」と御本尊。高さ100メートルの大掃除日本一大きい牛久大仏で、秋のお彼岸に年に一度の大掃除が行われた。清掃員は大仏の眼からロープにぶら下がり、高さ約1 0 0メートルにある大きな顔の汚れをプラシなどで手際よく流して行く と。牛久大仏の外部メンテナンスでは:・外壁の清掃(高圧洗浄)・銅板継ぎ目の点検・腐食・亀裂の有無チェック・塗装補修・避雷針の点検・受雷による金属疲労の検査などが行われていると。牛久大仏は落雷を頻繁に受けるため、避雷設備は特に重要である と。作業員がロープアクセス(高所作業技術)で清掃のため大仏の「まぶた部分」から外部へ出る場面の写真をネットから。写真位置は大仏の目の高さ(約80m前後)にあたるのだと。螺髪の清掃に向かう清掃作業員。これもネットから.春には桜の花が。エレベーターで牛久大仏の高さ85mの展示室・展望台まで上がる。(写真はネットから)牛久大仏の展望窓。牛久大仏の展望窓(胸部の高さ約85m地点)から見下ろした景色 。窓の隙間から見えているのは、大仏の足元に広がる 牛久浄苑(うしくじょうえん) という大規模な霊園。「お胸の部分の三本の窓この窓は、右端から見ても左端から見ても、同じ景色が見えます。三つの窓は、私達が迷わす信心を深める為心を一つにさせて頂けることを表現しております。」 参道と發遣門。こちらも参道と發遣門。白い建物の屋上一面に並ぶ太陽光パネル。「大仏比較図」左から順に🗿 牛久大仏(120m)・台座まで含めた総高 120m・地上85mに展望台(胸の位置)・立像として世界最大級・奈良の大仏(約18m)の約6〜7倍の高さ🏛️ 国会議事堂(高さ 約65m)・牛久大仏の半分強ほどの高さ・比べると大仏がいかに巨大かよくわかる🗽 自由の女神(台座込み 40m前後)・ニューヨークの自由の女神・牛久大仏の3分の1ほどしかない🗿 奈良の大仏(14.9m)・こちらは有名な東大寺の大仏・牛久大仏は奈良の大仏の「約8体分」の高さに相当■ 牛久大仏の圧倒的なスケールがわかる図この図からわかるポイント:牛久大仏(120m)は、→ 国会議事堂(65m)の 約2倍→ 自由の女神(40m)の 約3倍→ 奈良の大仏(15m)の 約8倍と、世界最大級の圧倒的な高さを誇ることが一目でわかるのであった。「仏教四大聖地」 を紹介している展示。① 成道の地(悟りの地)ブッダガヤ(右上)お釈迦さまが菩提樹の下で悟りを開いた地大塔(マハーボディ寺院)が有名仏教徒なら一度は訪れたい最重要聖地② 初転法輪の地 サールナート(左上)最初に説法をした場所(初めて“法”が転じた=初転法輪)ダメークストゥーパ(円筒形の大塔)が象徴仏教布教の始点③ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)された地横たわる涅槃像が安置されている未だ静かな雰囲気が残る聖地④ 誕生の地 ルンビニー(左下)お釈迦さまが生まれた地(現在のネパール)アショーカ王の石柱や池などが残る四聖地の中で最も穏やかな場所① 初転法輪の地 サールナート(左上)お釈迦さまが悟りを開いた後、初めて説法した場所写っている巨大な建造物は ダメーク・ストゥーパ(Dhamek Stupa“初めて法を転じた(初転法輪)” 聖地として世界中の仏教徒が巡礼に訪れる② 成道の地 ブッダガヤ(右上)菩提樹の下でお釈迦さまが “悟りを開いた” 場所写真は マハーボディ寺院(大菩提寺)仏教世界で最も重要な聖地の一つ③ 誕生の地 ルンビニー(左下)ネパールにあるお釈迦さまの生誕地アショーカ王の石柱 や、生誕の池がある世界遺産にも登録されている④ 涅槃の地 クシナガラ(右下)お釈迦さまが入滅(亡くなった)した場所長い涅槃像が安置される静寂の地パネルには「釈尊入滅の地」と説明があるはず牛久大仏内部では、ただ仏像を見るだけでなく、仏教の歴史・釈迦の歩みを学ぶためのミニ資料館 となっていた。この四枚の写真パネルは、釈尊の人生の重要な四か所(四聖地)をまとめて紹介している展示である。牛久大仏の胎内 4・5階「霊鷲山(りょうじゅせん)の間」 にあった金色の御仏(みほとけ)を安置した納骨堂(霊位奉安室)●霊鷲山の間(れいじゅせんのま)・牛久大仏の胎内で最上階付近(エレベーターで上がれる最上部)・三日月状の黄金の空間・数千体の金色の阿弥陀仏が並び、納骨ができる部屋として機能●金色の仏像一体ずつが「御霊(みたま)」を供養する際の御仏・各一つの棚が「一霊位」・中には遺骨または遺品が納められている場合がある・「永代供養」のための区画として申し込めるつまり、これは一般的にいう「納骨堂」「霊座」「永代供養墓」にあたるもの。ここが胎内の最上部で、静寂と光に包まれた空間であった。牛久大仏・胎内「霊鷲山の間」 にある永代供養の奉安者名(霊位)を記す名簿塔(霊位掲示柱)「南無阿彌仏」 「万燈会」。 これも 牛久大仏の胎内(4〜5階・霊鷲山の間)にある「胎内仏(小仏像)を安置した納骨壇(納骨棚)」牛久大仏の内部・納骨堂(霊堂)の中央祭壇(ご本尊前)。・阿弥陀如来の名号「南無阿弥陀仏」の掛け軸・周囲に多数の小金仏(観音像)が並ぶ・金色の荘厳された空間■ 左右にある仏像阿弥陀如来立像(胎内仏) の見本牛久大仏の胎内に奉安される小仏像(約20~30cm)極楽浄土へ導く阿弥陀如来を現したものその後ろの光背は「放射光」と呼ばれ、阿弥陀の無量の光明を表します■ 胎内仏奉安(永代経)主な内容(案内板から読み取れる部分)・胎内仏に亡き人(先祖・家族など)の法名を記す・牛久大仏胎内の「霊鷲山の間」に半永久的に安置される・毎朝・毎夕、さらに年忌にあわせて永代経(供養)が営まれる・供養料(永代経志納金)が一口 20万円(案内板に明記)・希望により複数口の申し込みも可能・法名(戒名)、俗名、没年月日などを記録し管理仏教で最も重要な象徴のひとつ「蓮華(れんげ)」蓮は泥の中から清らかな花を咲かせるため、「迷いの世界(煩悩)から悟りへと開く清浄さ」 を象徴。牛久大仏の胎内にある「写経(写仏)・休憩スペース」。壁に掛けられているのは、写仏(しゃぶつ)作品・仏さまの線画に、花や季節のモチーフを加えた彩色写仏・背景に筆文字(願い・法語)・作者による手書きの書と絵が組み合わされた奉納作品牛久大仏では参拝者が写仏をして奉納することもでき、その代表的作品が展示されていることがあるとのこと。座布団の並んだ段状の座席は 写経や写仏、または法話・瞑想などを行うための座席 と。ズームして。写経・写仏体験コーナー」で、写真の二人は 写経(または写仏)をしているところ。「宗教の共通点(しゅうきょうのきょうつうてん)信じること感謝すること奉仕すること(ほうしすること)」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.19
閲覧総数 356
-
14

牛久大仏へ(その1)
利根川の排水機場。道の駅 発酵の里こうざきに立ち寄る。千葉県香取郡神崎町にある、発酵食品をテーマにしたユニークな道の駅「発酵の里こうざき」、住所:千葉県香取郡神崎町松崎 855。「発酵」をテーマにした全国でも数少ない道の駅。味噌、醤油、酒といった発酵食品が盛んな地域で、発酵文化を「食」と「体験」で発信していた。建物は「新鮮市場」「発酵市場」「レストラン」「カフェ(はっこう茶房)」など複数のゾーンで構成。観光案内板「発酵の里 こうざき」。左側のマスコットキャラ:「なんじゃもん」(神崎町のシンボルキャラクター、巨大な樹の精霊)発酵の魅力が詰まった「発酵市場」。全国から集めた発酵食品をとりそろえた、土産ショップ。店に入ると、みそやしょうゆ、甘酒、チーズ、漬けもの、日本酒など約500種類の商品がずらり。店内で土産物を買う旅友。親しい「仁」の文字がある日本酒。 仁勇(じんゆう)ラベルに大きく「仁勇」と書かれている緑色の瓶。蔵元:鍋店(なべだな)株式会社所在地:千葉県香取市(佐原)利根川流域の代表的な酒蔵のひとつ青ラベル(本醸造)赤ラベル(辛口)緑ラベル(純米)など複数の種類が並んでいた。仁勇は利根川流域(“水郷地域”)でもっともよく見かける地酒の一つであると。「鍋店 神崎酒造蔵」や「寺田本家」など、地元酒蔵の甘酒や酒かすを使った商品も豊富。新利根川大橋。利根川を渡る。すぎのや本陣 阿見店で昼食。稲敷郡阿見町、国道125号線バイパス沿いの店舗。蕎麦、うどんと各種セットが充実している和食レストラン。そば定食を楽しむ。そして目的地の牛久大仏が姿を表した。牛久大仏👈️リンク を訪ねるのは2021年以来、4年ぶり。・全高120m(台座含む) → 自立型の青銅仏として世界最大級・建設:1993年・参拝者は内部に入ることができ、 ・地下1階:蓮華蔵世界 ・1階:知恩報徳の世界 ・2階:御慈光の世界 ・3〜5階:展望室(地上85m) までエレベーターで上がれた。・周囲には広い庭園と小動物公園もあり、家族連れにも人気 と。牛久大仏の入口案内板。近づいて。正式名称:牛久大仏(正式には「牛久阿弥陀大佛」)所在地:茨城県牛久市久野町2083右側に大仏の全身写真下部に ギネス世界記録 認定 のロゴ → 「世界最大の青銅製仏像」として登録された記念牛久阿弥陀大仏(内部フロア説明)案内板には、大仏内部の各階の施設が紹介されていた。1F:光の世界・青い光に満たされた幻想的な空間・参拝前の「心を整える場所」という意味合い2F:知恩報徳の世界・阿弥陀如来への信仰や感謝をテーマにした展示・仏教美術や資料が並ぶ3F:御慈光の世界(銅板写経の間)・約3万枚の金色の小さな仏像が並ぶ荘厳な空間・「写経」を奉納する場所として知られる4F(外周部):展望室(地上85m)・牛久市や関東平野を一望できる大パノラマ・晴れていれば筑波山がよく見える5F:御膳台・大仏内部の最上部・一部は構造上のスペース(一般公開はフロアによって制限あり)牛久大仏の大きさ(案内板の比較表)大仏の高さ(本体):100m蓮台(台座):10m総高さ:120m→ 自由の女神(約93m)より高いその他、奈良の大仏や鎌倉大仏との高さ比較も描かれていた。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)エリア全体の案内図。■ 1. 牛久阿弥陀大仏(中央) 敷地の中心にそびえる高さ120mの大仏。 内部に入れる日本でも珍しい巨大仏です。🌼 周辺の庭園・スポット■ 2. 牛久浄苑(うしくじょうえん) 大仏の背後に広がる広大な霊園エリア。春は桜、初夏は新緑が美しい場所。■ 3. ふれあいガーデンテラス 大仏横にある花壇と散策路。 季節ごとの花が楽しめるスポットです。■ 4. 大香炉(だいこうろ) 大仏前にある大きな香炉。 参拝前にお線香を供える場所です。🌷 花エリア 写真の左側に広がるカラフルな場所。■ 5. 群生海(ぐんせいかい) 季節の花々(ネモフィラ、コスモス、ポピーなど)が一面に咲き誇る広場。■ 6. 釈迦三尊像 三体の仏像が並ぶ厳かなエリア。写真にも小さく写っていた。🌳 その他の見どころ■ 7. 定業苑(じょうごうえん) 休憩所やお土産コーナーのある施設付近。車椅子対応のトイレもある。■ 8. 本願荘厳の庭 滝や池がある和の庭園。涼しげな雰囲気で、写真によく合うスポット と。■ 9. 本願荘厳の滝(右下) 庭園内にある滝。流れ落ちる水が美しい場所。■ 10. 想い出処「浄蓮門」(入り口付近) 入場ゲート近くのお土産・記念写真スポット。牛久大仏(牛久阿弥陀大仏)内部へ入るための「大仏入口」案内板。「東本願寺 牛久阿弥陀大仏」→ 牛久大仏の正式名称で、宗派は浄土真宗東本願寺派。牛久大仏の「入場受付・料金案内」付近。■ 1. 営業時間(上部の紫の帯) 季節によって営業時間が変わる。 3〜9月(平日) 9:30〜17:00 3〜9月(土日祝)9:30〜17:30 10〜2月(平日・土日祝)9:30〜16:30 ※最終入場は閉園30分前まで■ 2. 料金案内(中央の大きな表) 大仏胎内or園内散策の料金が。● セット券(庭園+大仏胎内) 大人:800円 子ども:400円● 入園券(庭園のみ) 大人:500円 子ども:300円入場チケット。移動しながら牛久大仏を。これは 牛久大仏の「顔の模型」 。「大仏様のお顔は、この模型1000個分のボリュームに相当します。」と。「大仏入口(順路)」案内板。 通路のマンホールは牡丹(ぼたん)文様のモチーフ・中央に大きな花弁・両側に蕾(つぼみ)・周囲に茂る葉という構成で描かれており、典型的な牡丹唐草や牡丹文様の構成。牡丹は、仏教美術でも寺院装飾でもしばしば用いられる吉祥文様(めでたい文様)で富貴、高貴、美、吉祥を象徴すると。牛久大仏世界最大 120M 青銅製仏像鎌倉時代、御開山親鸞聖人は、常陸国(茨城県)で、他力念仏の教文を人々に伝えられるとともに、浄土真宗の根本聖典となる「教行信証」のご執筆にかかられました。 このご著書の成立年をもって、浄土真宗立教開宗の年(1224年)とされております。そして、立教開宗からおよそ800年の時代を超えてそのゆかりの地に、東本願寺第25世興如上人のご発願により、人類救済、世界平和の願いを込めて西方極楽浄土の主である阿弥陀如来(牛久大仏)が建立されました。牛久大仏の一部を実物大で再現した展示物のひとつでこれは大仏の頭頂部「螺髪(らほつ、大仏さまの髪の毛)」=頭の盛り上がり部分の実物大模型「この螺髪は阿弥陀大仏の頭部螺髪と同じものです。概 要 直径 1m 重さ 200kg 総数 480ケ」 牛久大仏の総重量は4,000t、顔の長さ20m、左手の平18.0m、目の長さ2.5m、鼻の長さ1.2m、とすべてが規格外の大きさ。牛久阿弥陀大仏阿弥陀如来は方便法身の大尊形として顕現されたもので、高さは阿弥陀如来の十二の光明にちなみ120m。その尊形を外から仰ぎみるだけでなく、胎内で阿弥陀如来の広大無辺なる本願の世界を体感することができます。四季の移り変わりや朝夕の光により、また見るものの心により、さまざまな表現を見せてくれる阿弥陀大仏、その御慈悲とは常に智慧と慈悲に満ち、すべてのものをやさしく包み込みます。地上高 高さ 120m重 量 本体主鉄骨 3,000トン 外殻鋼板重量 1,000トン左 手 挙手 18.0m親 指 直径 1.7m足の爪 長さ 1.0m人差指 長さ 7.0m 目 長さ 2.5m 鼻 高さ 1.2m 口 長さ 4.0m 耳 長さ 10.0m顔の大きさ 20.0mラホツ(頭部) 直径 1個1m 重さ 200kg 全体 480ケ基壇部 高さ 10m蓮台部 直径 30m 高さ 10m製造期間 10年再び牛久大仏(牛久阿弥陀大仏) 園内マップ「SORA × HOTOKE(そら × ほとけ)」の案内板。■ 左上:園内写真と名称● 大香炉(だいこうろ) 大仏の正面にある巨大な香炉● 群生海(ぐんせいかい) 季節ごとの花が広がる花畑エリア● 釈迦三尊像 ミニ仏像が三体並んだエリア● 浄蓮門(じょうれんもん) 入口付近の門と休憩場所■ 中央地図(園内図) 観光スポットがイラストで示されており、色分けされているのが特徴● 牛久阿弥陀大仏(メイン) 園内中央に大きく描かれた大仏像 胎内(内部)に入るルートもここから● ふれあいガーデンテラス 花畑・フォトスポットがある休憩エリア● 本願荘厳の庭 滝や池、水のある庭園● 仲見世 お土産・軽食・物販が集まるエリア● 足湯苑 無料または低料金で利用できる足湯施設● 駐車場(P) 園全体にアクセスしやすい大きな駐車場● 現在位置(YOU ARE HERE) 赤色の表示で、案内板のある場所が指示されています。牛久阿弥陀大仏を正面から。青空であれば(ネットから)。 ・・・つづく・・・
2025.11.17
閲覧総数 510
-
15

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-6
★六会地区 歴史年表-16年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料昭和時代 49年 1974 今田地区に県立藤沢工業高等学校創立 小野田寛郎、フィリピン・ (現藤沢工科高等学校) ルバング島より帰国👈️ 50年 1975 スエズ運河開通👈️ 藤沢市人口 ニ六五九七五名 52年 1977 亀井野小学校創立 藤沢市あづま保育園石川に開園 県立藤沢北高等学校石川山田に創立 県立藤沢養護学校開校 53年 1978 亀井野保育園開園 鶴山洋子、円行につくし乳児園開園 今田、鯖神社境内に太平洋戦争 戦死者の「忠魂碑」建立 第一回公民館ふるさとまつり開催 六会地区生活環境協議会発足 石川市民の家開所 54年 1979 太平洋戦争戦死者七四名の慰霊碑を 東名高速道路、 雲昌寺境内に建立 日本坂トンネル👈️ 内自動車火災事故発生 55年 1980 石川、伊沢良一「イザワ テニスガーデン」開設 藤沢市立またの保育園開園 六会市民の家開所 56年 1981 天神小学校創立 湘南台中学校創立 西俣野の曹洞宗花應院本堂庫裡の 改築工事落成 57年 1982 西俣野御嶽神社梵鐘成る 58年 1983 開業医、三木洋「相模国四国八十八箇所 (弘法大師像をめぐりて)発行 59年 1984 石川東部区画整理事業完了に伴い 天神町誕生 60年 1985 西俣野史跡保存会会長、渋谷彦三 「小栗判官一代記」を発行 小栗塚市民の家開所 61年 1986 藤沢市民総合図書館完成 六会地区民生委員・児童委員協力者 会議発足 ★六会地区 歴史年表-17年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料平成時代 平成元年 1989 今田、円行の大部分が湘南台地区へ 移行される 六会地区は石川・亀井野・西俣野・ 天神町と今田・円行の一部となる 六会地域子供の家「どんぐりころりん」 開所 2年 1990 六会市民センター・公民館、 地下体育室完成 6年 1994 石川小学校創立 六会市民センターに地区福祉 窓口開設 7年 1995 六会駅橋上駅舎と東西を結ぶ オウム真理教による 自由通路完成 地下鉄サリン事件👈️発生 8年 1996 日本大学「バラ園」開設 9年 1997 六会ふるさと音頭完成 六会地区くらし・まちづくり会議発足 第一回湘南ねぶたまつり開催 10年 1998 六会駅から六会日大前駅に改名 12年 2000 六会地区防災リーダー連絡会発足 15年 2003 天神ミニバス開通 (六会日大前駅西口天神町循環バス) 16年 2004 六会市民センター石川分館設置 新潟県中越地震👈️発生 県立藤沢北高等学校が県立長後 高等学校へ統合 19年 2007 新潟県中越沖地震👈️発生 22年 2010 六会地区地域経営会議発足 23年 2011 宮城県亘理郡山元町に自転車・ 東日本大震災👈️発生 ヘルメット等寄贈 (六会地区震災支援金) 24年 2012 新潟県柏崎市北条(きたじょう)地区と 六会地区との地域間交流の覚書を 取り交わす 25年 2013 六会地区郷土づくり推進会議発足 六会日大前駅周辺バリアフリー化 工事始まる 小田急線六会一号踏切取り付道路 安全対策実施 26年 2014 六会市民センター・公民館建替えに 熊本大地震👈️発生 伴い仮庁舎に移転 28年 2016 新六会市民センター・公民館完成 29年 2017 天皇退位、2019年4月末に 衆院選で自民大勝、民進 が分裂 森友・加計政権揺るがす 「ものづくり」信頼揺らぐ 30年 2018 平昌五輪で日本は冬季最多 13メダル。フィギュア・ 羽生結弦は連覇 西日本豪雨、死者220人超 日大アメフト部選手が 危険タックル。スポーツ界 で不祥事相次ぐ 日産・ゴーン会長を逮捕 テニス・大坂なおみが 全米オープン優勝 31年 2019 はやぶさ2、小惑星 「リュウグウ」への着地 に成功 大リーグ イチロー引退 ★六会地区 歴史年表-18年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料令和時代令和元年 2019 【以下 後日記入】 天皇陛下が即位。「令和」 に改元 ラグビーW杯日本大会開幕、 日本8強 京都アニメーション放火、 36人死亡 消費税率10%スタート 東日本で台風大雨被害、 死者相次ぐ 2年 202 コロナ感染拡大 緊急事態宣言 志村けんさんら死去 東京五輪・パラ 1年延期 安倍首相 辞任表明 菅首相誕生 新内閣発足 3年 2021 コロナワクチン接種 熱海で土石流・27人死亡 眞子さま 小室圭さん 結婚 大谷メジャーMVP 4年 2022 知床観光船 沈没事故 安倍元首相撃たれ死亡 大谷2桁勝利2桁本塁打 村上 56本塁打・三冠王 W杯日本代表16強 5年 2023 WBC14年ぶり優勝 最強侍 列島沸く ジャニーズ性加害問題 大谷メジャー本塁打王 藤井竜王史上初八冠 阪神38年ぶり日本一 6年 2024 石川・能登で震度7 新紙幣 20年ぶり パリ五輪メダル 日本45個 大谷 初の「50―50」 闇バイト強盗 続発 7年 2025 善行長後線開通 ・・・つづく・・・ ・・・完・・・
2025.11.15
閲覧総数 402
-
16

日本平~久能山東照宮へ(その6):久能山東照宮(3/5)
久能山東照宮「唐門」(重要文化財) 。拝殿正面にあり、屋根は銅瓦本葺黒漆塗の四方唐破風造という(重要文化財)普段は通り抜けが禁止されているため階段を登ることはできなかった。久能山東照宮唐門は元和3年(1617)に建てられたもので、久能山東照宮の中核部である本社社殿(拝殿・石の間・本殿)の正面に配され、聖域の正門的な役割を持っています。形式は四方唐破風造り、四脚門、一間一戸、本瓦葺き、四方唐破風造りとは屋根の4方向に唐破風を設けたもので、格式の高く、聖域の正門として相応しい意匠となっています。構造部は朱色で塗られ、木鼻や門扉、蟇股、唐破風などには唐獅子(左右に阿吽)や鳥類、植物など多彩な彫刻が随所に施され、彫刻は極彩色で彩られ、金物や本瓦の軒先、獅子口には金を使用しています。久能山東照宮唐門は江戸時代初期に建てられた唐門建築の遺構として大変貴重な事から明治45年(1912)に国指定重要文化財に指定されています。さらにズームして。。「高野槙」。コウヤマキ(高野槙、高野槇、学名:Sciadopitys verticillata)は、マツ目コウヤマキ科の日本および韓国済州島の固有種。常緑針葉樹で高木となる。別名ホンマキ。「高野槙」。コウヤマキとは・・・・高野山で多く見られ、高野山では「霊木」として保護されている。・成長が緩やかで手入れが比較的簡単である。・ヒマラヤスギ、ナンヨウスギとともに「世界三大庭園樹(世界三大公園木」)に数えられる。また、サワラ、ヒノキ、クロベ(ネズコ)、アスナロ(ヒバ)とともに「木曽五木」とされる。・秋篠宮悠仁親王の「お印」とされている とネットから。石段の上には「神庫」が。「神庫」への石段下の「末社 竈(かまど)神社御祭神(火の神)台所の神様です。御希望の方に神札をお頒ちしております」と久能山東照宮神庫は元和3年(1617)に建てられた建物で、木造平屋建て、入母屋、銅瓦葺、平入、桁行5間、梁間3間、建物の構造体が朱色に壁が黒色に彩色され、瓦と木組の端部が金箔欄間部は極彩色で彩られています。久能山東照宮の境内の中で唯一の校倉造(建材を横に組合せ、積重ねることで壁とする工法、調湿性能に優れ正倉院などにも使用されました。)の建物で奉納された神宝や鉄砲などが置かれていました。久能山東照宮神庫は境内を構成する要素として大変貴重な事から昭和30年(1955)6月22日に国指定重要文化財に追加指定されています。「河津桜」も満開。「河津桜」。ズームして。ここにも2基の石灯籠があったのだろうか?「日枝神社」。「重要文化財 日枝神社(ひえじんじゃ)祭神 大山咋命(おおやまくいのかみ)旧御本地堂で薬師如来を安置してあったが、明治三年神仏分離の際に仏像を廃し後に今の名称に改めた。元和三年(西暦一六一七年)の建造である。」久能山東照宮日枝神社は元和3年(1617)に建てられたもので、木造平屋建て、入母屋、銅瓦葺、平入、桁行3間、梁間3間、正面1間向拝付、外壁は真壁造板張り、建物全体が朱色で塗られ、蟇股や向拝の蝦梁の彫刻などが極彩色で彩られ、金物や瓦の軒先などが金が使用されています。当初は久能山東照宮の本地堂として薬師寺如来像が安置され薬師堂と称されてきましたが、明治時代初頭に発令された神仏分離令とその後の廃仏毀釈運動により明治3年(1870)に薬師寺如来像が大正寺へ移され、天台宗の守護神である山王社の御神体を遷して日枝神社に改め久能山東照宮の末社となりました。久能山東照宮日枝神社は江戸時代初期の御堂建築の遺構として大変貴重な事から昭和30年(1955)6月22日に国指定重要文化財に追加指定されています。歴史を感じさせる青銅製の吊り灯篭。ここにも歴代将軍の様々な葵の御紋が。「天水桶」。「拝殿、石の間、本殿」への入口門・「東門」。久能東照宮・東門は元和4年(1618年)に造られ、日枝神社より社殿に向かう際にくぐる門。小さな門となっていますが、彫刻などが間近に見ることができ社殿同様の極彩色の朱塗りが施されていた。国の重要文化財に指定されている。入口から、「石の間」、「拝殿」を見る。この写真はネットから。「透塀」。久能山東照宮透塀(玉垣)は元和4年(1618)に建てられたもので、本社社殿周囲を囲っている。塀は銅瓦葺、飾金具は金、壁は朱色で塗られ、腰部に施された精緻な彫刻には極彩色が施されている。東門も同年に建てられたもので本社社殿の東側に位置し、門の周りは透塀(玉垣)によって囲われていた。東門は切妻、銅瓦葺、一間一戸、棟門、透塀と同様に朱色を主体として彫刻部が極彩色に彩られている。透塀と東門は久能山東照宮の境内を構成する要素として大変貴重な事から明治45年(1912)2月8日に国指定重要文化財に指定されています。玉垣の「玉」は神聖なものや美しいものを意味し、「神聖な神様を囲む垣」という意味と言われている。「透塀」沿いにあった「家康公御手植えのみかんー駿府城より分木」。「拝殿」を横から。「国宝」の文字が。移動して。「国宝 本殿 石の間 拝殿」と。「拝殿」、「石の間」、「本殿」の間取り図。拝殿 : 桁行五間、梁間二間、一重、入母屋造、正面千鳥破風付、向拝三間、銅瓦葺石の間 : 桁行一間、梁間一間、一重、両下造、銅瓦葺 C&Dの出入口あり。本殿 : 桁行三間、梁間三間、一重、入母屋造、銅瓦葺写真中央が「石の間」。出入口の扉が確認出来た。久能山東照宮拝殿は元和3年(1617)に建てられたもので、入母屋、銅瓦葺、屋根正面には千鳥破風、桁行5間、梁間2間、3間向拝付、棟梁は中井正清(初代京都大工頭)。外壁は黒の漆塗り、金物の多くは金で仕上げられ、組物や木鼻や蟇股、海老虹梁などの彫刻、桁に描かれた絵画は極彩色が施されています。本社社殿は本殿、拝殿、石ノ間が接続し一体となっている所謂「権現造」でこの後、造営される日光東照宮(栃木県日光市)はじめ全国の東照宮の規範となっています。久能山東照宮拝殿は極めて貴重な事から平成22年(2010)12月24日国宝に指定されています。「中井大和守正清は、永禄8年(1565)に法隆寺門前の西里で誕生しました。正清は、慶長5年(1600)の関ヶ原の戦後に、徳川家康公より上方の大工支配を仰せつかったと伝えられています。その直後には徳川家の御大工として二条城、伏見城の作事に携わり、慶長11年7月に従五位下大和守に叙任され、公儀大工の第一人者となりました。徳川家康公は、二条城、伏見城、江戸城、駿府城の城郭や、知恩院、増上寺の作事でみせた正清の手腕を高く評価しました。そして、「何事も御普請方之儀、大和次第」と言い、正清に全幅の信頼を寄せ、名古屋城、内裏の作事を命じました。正清はまさに東奔西走の日々を過ごし、慶長17年(1612)に従四位下に昇叙しました。その位階は大名に与えられるもので、大工棟梁としてはきわめて異例の出世でありました。この時期の正清の作品で現存するものは少ないですが、仁和寺の金堂(国宝)は、慶長18年に上棟した慶長度内裏の紫宸殿を、寛永年間に移築したもので、京都に残っている正清の代表作として貴重な建物です。元和2年(1616)4月、徳川家康公は駿府城に薨去されました。御遺骸は遺言により久能山に埋葬され、正清に社殿の造営が命ぜられました。これが久能山東照宮で、正清が渾身を込めて造った社殿は四百年の時を経て今もその姿を伝えています。久能山東照宮の造営を終えた正清は、元和5年正月21日、徳川家康公のあとを追うかのように、近江水口で55歳の生涯を閉じました。このように、久能山東照宮は、徳川家康公の側近として仕えた中井正清の最晩年に全身全霊を込めて造った最高傑作といえるでしょう。」と ネットから。唐門は四方唐破風造りであることが解かるのであった。黄金の木鼻、精緻な彫刻を見る。木鼻にズームして。団扇型の松の彫刻をズームして。「唐門」から上って来た石段の下の石鳥居を見る。ズームして。唐門の扉?の見事な彫刻。白梅?と青い鳥の姿が。近づいて。反対側の扉?同様に。唐門の横梁の見事な彫刻。そして振り返って「拝殿」の入口部を。江戸時代奥に入れる者は将軍だけ、御三家の徳川家も立ち入る事は出来なかったと。近づいて。中央の蟇股の彫刻・「甕割りの彫刻」。中国の故事、政治家・司馬温公の「甕割り」の彫刻。子供の頃、一緒に遊んでいた友が水甕に落ちてしまったのを救うため、その甕に石を投げつけると、甕に穴が開き、仲間が水と一緒に流れ出てくる場面。高価な甕を割った少年の物語で『命の大切さ』を表しています と。別の場所にあった案内板「久能山東照宮『司馬公の甕割り』この絵は中国北宋の政治家、司馬温公の少年時代のお話です。ある日、一緒に遊んでいた友達が水甕の中に落ちて溺れてしまいました。もう一人の友達はハシゴをかけて助け出そうとします。いっぽう聡明な司馬少年は「それでは間にあわない!」と近くの石で甕を割って助け出しました。この故事の彫刻が久能山東照宮拝殿の正面に施されております。御祭神徳川家康公が現代の私達へ向けて、「命の尊さ」を説かれているといえるでしよう。」右側。左側。内陣を望む。蟇股内部を花鳥の透彫とするなど細部も整った意匠が。下段中央。その左。下段最左。下段右。その右。最右。拝殿(右側)最奥の下段の蟇股。吊り灯篭。木鼻(右)。ズームして。吊り灯篭越しに「拝殿、石の間、本殿」への入口門・「東門」方向を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.03.11
閲覧総数 246
-
17

江東区・大島(おおじま)、亀戸を歩く(その17)・ 亀戸 香取神社(その2)
更に「香取神社」境内の散策を続ける。「病気平癒身代わり像」のお水掛け。「恵比寿神像」と「大国天像」に水鉢の水をかけ、身体の痛い場所を洗い清めます。「恵比寿神像」と「大国天像」。柄杓が置かれていて、神像に水掛け祈願が出来るのだ。痛いところを洗い清めて、1年の無事と健康を祈願するのだと。とりあえず、2像の頭から水をかけさせて頂きました。「恵比寿神像」。七福神中で唯一の日本の神様。いざなみ、いざなぎの二神の第三子といわれ、満三歳になっても歩かなかったため、船に乗せられ捨てられてしまい、やがて漂着した浜の人々の手によって手厚く祀れれたのが、信仰のはじまりと伝えられている。左手に鯛をかかえ右手に釣竿を持った親しみ深いお姿の、漁業の神で、特に商売繁昌の神様としても信仰が厚い。「大国天像」。大黒天は、大自在天の化身ともいわれ、大国主命と神仏習合したものである。一度仏となったが、人々に福徳を授けるために再びこの世に現れたという。大地を掌握する神様(農業)でもある。大きな袋を背負い、打出小槌をもち、頭巾をかぶられた姿が一般によく知られていて財宝、福徳開運の神様として信仰されている。痛いところをこのタワシで擦ってやると、更にご利益があると。「亀が井」亀戸の地名のもとになった井戸だが、遺構ではなく復元されたものであると。「若水や 福を汲み上げ 亀が井戸」と添え書きが。「亀戸」の地名由来にもなった「亀ヶ井」を2003年に復元したもの。かつてこの地には臥龍梅庭内に「亀ケ井」と呼ばれる井戸があったと。亀島もしくは亀津島が亀戸という地名になったのは、この「亀ケ井」と混同され亀井戸と呼ばれるようになったという説もあるのだと。そして「拝殿」。飛鳥時代の天智天皇4年、藤原鎌足により創建されたといわれる。建武年間(1334~37)香取伊賀守矢作連正基が始めて当社に奉仕し、香取神社初代神職となり、応安4年(1372)社殿再建、降って大永3年(1524)修造を営み、後寛永3年(1627)4月8日本殿改築に着手、同年9月24日竣工、文政年間(1818~29)拝殿造営、明治5年11月16日村社に定められました。昭和20年3月9日第二次世界大戦にて本殿炎上、同23年8月社殿再建。更に昭和63年10月19日現在の社殿が建立されました。御祭神は香取大神」のほか、相殿に鹿島神宮の祭神・「武甕槌神」も祀り、武道の御神徳から現在ではスポーツの神として崇敬を集めるのだと。拝殿神額は往年の「香取太神宮」の文字が残る。『江戸名所図会』においては「香取太神宮」として紹介されているのだと。スポーツ振興の神としても有名で、国際舞台で活躍する多くのアスリートも参拝する神社としても有名。拝殿の横に、水泳選手で闘病中の池江璃花子選手の病気平癒祈願が設置されていた。「池江璃花子 必ず 有言実行!!」と。参拝客が池江璃花子への思いを込めたとみられる多くの絵馬も掛かっていた。そして白血病からの復帰を目指す競泳女子の池江璃花子が、このほどプールでの練習を再開。昨年1月の三菱養和スプリント以来、1年7か月ぶりのレースとなる東京都特別水泳大会(8月29日、東京辰巳国際水泳場)の50メートル自由形へ出場とのニュースが。50m自由形では24秒21の日本記録を持つ池江ではあるが。どんな泳ぎを見せるのか、いや、大会で泳ぐ姿が見られるのが嬉しいのである。そして、10月1日、東京辰巳国際水泳場で行われた日本学生選手権の50m自由形で25秒62の4位となり「このインカレを目標として1年間頑張ってきた。感慨深い」と話したのであった。「拝殿の内陣」★御祭神:経津主神(ふつぬしのかみ):刀剣の威力を神格化した神、海上守護・国家鎮護の神[相殿]武甕槌神(たけみかづちのかみ):雷神、刀剣の神、弓術の神、武神、軍神、 武道・競技の必勝、事業の創始、旅行安全の神[相殿]大己貴命(おおなむち)※[別名]大国主命:国造りの神、農業神、商業神、医療神そしてこの後に明治通りから見た「本殿」。由緒:西暦665年、中臣鎌足公が東国下向の際、当地に来訪。香取大神を勧請し、太刀ひと振りを納め、旅の安泰を祈った。これが、創立の起因であると「勝石」。「勝石」の上にある剣。「勝石」の由来が書かれた石。「勝石の由来亀戸香取神社は天智天皇四年(六六五年)、藤原鎌足公が東国下向の際、この亀の島に船を寄せられ、香取大神を勧請され太刀一振を納めて、旅の安泰と御神徳を仰ぎ奉りましたのが起こりであります。御鎮座一三五〇年記念事業の一環として、この故事に基づいて太刀一振りを冠した「勝石」を建立いたしました。ご参拝の皆様に香取大神の御神徳が授かりますよう氏子并びに崇敬者が心をこめての寄進によるものです。四年に一度の神幸大祭に際し平成二十八年七月二十四日、関係者相寄り盛大に除幕式が挙行されました。勝石に触れ、願いを掛けることによって勝運と幸運を授かるお力どころ(パワースポット)として、末永く崇敬を集められますことを祈念申し上げております。」社務所を訪ねる。「御朱印」を頂きました。ちなみに、東京都江東区は、その昔、下総國・葛飾郡でした。下総國の一之宮は、千葉県香取市に鎮座し、正一位勲一等の神階を持つ『香取神宮』です。「社務所」の前にあった2基の石塔。境内から「拝殿」を再び見る。「参道」、「二の鳥居」方向。東門脇の石碑には「日露戦役 紀念百度碑」と刻まれていた。裏面には、「明治三十八年十月建之 發起者 若連」と記されていた。そして「舞殿」の明治通り側の壁に掲げられていた「香取神社」のご祈祷案内。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2020.10.15
閲覧総数 207
-
18

四国八十八ヶ所お遍路の旅・2回目(その16):見奈良・菜の花まつり、51番・石手寺
翌朝(3月29日(木))四国八十八ヶ所お遍路の旅4日目、ホテルを6:00に出発し東温市(とうおんし)の見奈良 ( みなら ) ・菜の花まつりの会場に向かう。折しもこの日の朝日が目の前に。時間は6:18。この日も快晴。菜の花畑の前の「坊ちゃん劇場」の駐車場に車を駐め【 見奈良 菜の花まつり】会場へ。1万5千平方mの菜の花畑に、約200万本の菜の花が満開で咲き誇る圧巻の「菜の花の海」が広がっていた。【 見奈良 菜の花まつり】は3/10(土)~4/15(日)までの開催。菜の花畑の先には松山自動車道が。一面に広がる金色の菜の花畑は特に美しい春の風景。早朝の為か、ミツバチの羽音や姿は確認出来なかった。鮮やかな色と菜の花の香りが。パノラマ撮影してみました。私のカメラではズームでのパノラマ撮影は出来ないのです。------------------------------------------------------------------------------------------------------51番札所:石手寺(いしてじ)短い時間であったが菜の花畑を満喫した後は、県道40号線を戻り、前日通った久米八幡神社前を再び通過。石手寺 弘法大師像が車窓から見えたのでズームで。県道317号線沿いの駐車場に車を駐める。「世界一立体曼荼羅皆一緒大楽仏」というものらしい。1年ほど前ここにマンション建設計画があり、石手寺が建設反対の幟を立てていたと。それがいつのまにか敷地が石手寺の駐車場になっていて、多くの石仏が並んでいた。石手寺はとても「お金持ち」なのだと、ネット情報から。その時は美しい仏像であると思い、カメラを向けたのであったが。この仏像も。ホテルから見奈良・菜の花まつりそして51番・石手寺までの走行ルート。入口には山門もなく、「渡らずの橋」から境内へ。境内 配置案内図。「県道より伝説の残る渡らずの橋、衛門三郎像の横を過ぎ、両脇に露店の並ぶ回廊を行くと山門に至る。くぐると、右に茶堂・納経所、左に鐘楼があって、その先に阿弥陀堂がある。正面奥に進んで一段高い位置に石段を上ると本堂が建つ。本堂の右に絵馬堂あり、その先に大師堂が並ぶ。本堂大師堂の背後にある山にはマントラ洞窟といわれる洞窟があり、本堂左後方に入口があり大師堂の裏に出口がある。大師堂右側には訶梨帝母天堂(祠)があり、石段を下りるとその右に三重塔が、左に一切経堂、護摩堂、弥勒堂が並ぶ。ここから左奥に入ると宝物館、大講堂がある。」「南無大虚空蔵主」碑。朝日を浴びて黄金色に輝く大師像。龍にのった観音様は、龍頭観音。入るとすぐに土産や食事ができる店が並んでおり、このような長い屋根付きの回廊が。奥の方には両側にお遍路グッズなどを販売している出店や屋台が並んでいたが、早朝の為か未だ開いている店は殆ど無かった。衛門三郎像。遍路の元祖とされる衛門三郎の再来伝説ゆかりの寺であると。入口には仏像が所狭しと並んでいた。色っぽい天女像?八幡大菩薩絵伊予13佛霊場第5番札所、地蔵院の山門。石手寺 案内図が毛筆で精緻に描かれていた。仁王門。仁王門は国宝で、高さ7m、間口は三間、横4m、文保2年(1318)の建立、二層入母屋造り本瓦葺き。この仁王像は、鎌倉時代後期の湛慶の作と伝わっているのだと。仁王阿形像。仁王吽形像。大草離。仁王門前左の恵比寿像?しかし釣り竿を持っていないので??その後ろに何故か「集団的自衛権 不要 不殺生祈りの会」の大看板が。伊予七福神像。三重塔。(重要文化財)弘法大師像。鐘楼。「建長3年」(1251)の銘が刻まれた愛媛県最古の銅鐘。昭和6年(1931年)11月3日、与謝野寛・晶子夫妻は石手寺に参拝していると。晶子の歌碑「伊豫の秋 石手の寺の香盤に 海のいろして 立つけむりかな」。石手寺裏の東山山頂に巨大な弘法大師を再び。弘法大師没後1150年を記念して、昭和59年に建立。高さ16M 顔の長さは2.4M。姿は、遣唐使として西安に行った31歳の頃のもの。体は西安を、顔は天竺を向いていると。鐘楼を正面から。阿弥陀堂。二王門を入って左側にある阿弥陀堂はぼけ防止の祈願者が多く参拝するスポットとして有名。本堂(重要文化財)「寺伝によれば、神亀5年(728年)に伊予国の太守、越智玉純(おちのたまずみ)が夢によってこの地を霊地と悟り熊野十二社権現を祀った。これは聖武天皇の勅願所となり、天平元年(729年)に行基が薬師如来を刻んで本尊として安置して開基したという。創建当時の寺名は安養寺、宗派は法相宗であったが、弘仁4年(813年)に空海(弘法大師)が訪れ、真言宗に改めたとされる。寛平4年(892年)河野氏に生まれた子どもが石を握っていたという衛門三郎再来の伝説によって石手寺と改められた。河野氏の庇護を受けて栄えた平安時代から室町時代に至る間が最盛期であり、七堂伽藍六十六坊を数える大寺院であった。永禄9年(1566年)に長宗我部元親による兵火をうけ建築物の大半を失っているが、本堂や仁王門、三重塔は焼失を免れている。」熊野山 虚空蔵院 石手寺(くまのさん こくうぞういん いしてじ)宗派:真言宗豊山派本尊:薬師如来創建:(伝)天平元年(729年)開基:(伝)行基、聖武天皇(勅願)所在:愛媛県松山市石手2丁目9-21”本尊真言:”おん ころころ せんだりまとうぎ そわか”本堂内部。納経堂。堂内部。納経したという証として「納経所」で納経帳に印・「お納経」を頂きました。そして御本尊様の分身・御影(おみえ・おすがた)も頂きました 。様々な効能のある石が納められている堂。大きな輪の除罪苦与楽輪くぐり、そしてその奥に元気再生石。「マントラ洞」入場門。修行大師像。元気再生石。衛門三郎の罪と再生の伝説にちなみ、石を1つ持って帰って、1年したら改心と復活をし、7つ添えて8つ返す。七転び八起きの石訶梨帝母天堂。この堂の周りに落ちている石を妊婦が持って帰ると安産祈願になると。そして無事に出産すると石を2つにして返すというお礼参りの風習があるのだと。茶堂大師。この堂の大師像は絶対秘仏で住職も見たことがないと。堂の前の香炉には線香を奉納した煙が絶えない名所。本堂前より境内。正面に仁王門、左に茶堂。絵馬堂。絵馬堂内部。大師堂。石手寺の大師堂には落書き堂という別名が付けられていると。これはかつて夏目漱石や正岡子規など多くの名士が落書きを残していたことから付けられた。ただし壁は第二次大戦中に塗りなおされていると。三重塔(重要文化財)。三重塔地上部。四国88ケ所のお寺にお参りしたのと同じご利益があるといわれる「お砂撫で」もできるようになっていた。鐘楼国の重要文化財。鎌倉時代。全国でもめずらしい建造物。子育地蔵尊。参道脇の歌碑。「やま知古えて 一人由希登 主の手にす加れる 身ハ安介志」 西村清雄。多くの国宝、重文がありながらも、何故か他の遍路の寺とは雰囲気が違う寺であった。この二面性はもちろんだが、それ以上に、全体にサービス精神にあふれているのであった。わかりやすく仏教の教えを説いたり、仏の一生を説明したりと、仏教というものを真剣に教えようという姿勢を感じたのである。また国宝の仁王門の前に「集団的自衛権 不要 不殺生祈りの会」の大看板が。時間の関係で見られなかった仏堂もあり、住職の熱き思いをゆっくりと聞いてみたかったが・・・・・。 ・・・つづく・・・
2018.05.19
閲覧総数 737
-
19

旧東海道を歩く(川崎~保土ケ谷)その6・神奈川区:本覚寺~西区:勧行寺
『旧東海道を歩く』ブログ 目次青木橋を渡ると右側高台にあったのが曹洞宗青木山『本覚寺(ほんがくじ)』。階段途中からの国道1号線(第2京浜)と東海道線。本覚寺がある丘陵は、戦国期には砦があったと。現在は、丘陵を分断して鉄道が走っており、対岸には戦国期の城跡(権現山城跡)が。おそらく、この丘陵は続いていて、岬のような立地だったと。「本覚寺は、臨済宗の開祖栄西によって、鎌倉時代に草創されたと伝えられる。もとは臨済宗に属していたが、戦国期の権現山の合戦で荒廃し、天文元年(1532年)に陽廣和尚が再興し、曹洞宗に改めた。開港当時、ハリスは自ら見分け、渡船場に近く、丘陵上にあり、横浜を眼下に望み、さらには湾内を見通すことのできる本覚寺を領事館に決めたという。領事館時代に白ペンキを塗られた山門は、この地域に残る唯一の江戸時代に遡る建築である。」『史跡 アメリカ領事館跡』江戸時代の末、日米修好通商条約が結ばれるにあたり、この本覚寺にアメリカ領事館が置かれたと。三年ほど、この地に領事館がおかれた。初代は有名なタウンゼント・ハリス。また、生麦事件の時には2名が騎馬で本覚寺に逃げ込み、ヘボン博士(ヘボン式ローマ字で有名)の手当を受けたとのこと。この石柱は開港100年の記念に立てられたと。山門の右脇に、レリーフ像をはめこんだ石碑が建っていた。この石碑は、幕末に横浜の開港を首唱した岩瀬肥後守忠震(いわせひごのかみただなり)の顕彰碑。横浜郷土研究会有志により、横浜開港の恩人への感謝の碑として、昭和57年に建立。 岩瀬忠震は、幕末に海防掛目付に任ぜられた後、外国奉行にまで出世し、開国論の中心的存在として活躍をした人物。日米修好通商条約においてはアメリカ総領事ハリスに対し、下田奉行井上清直と共に交渉にあたり、ハリスの要求した江戸・品川・大坂などの開港希望地をしりぞけ、幕府百年の計のためにと横浜の開港を首唱したのが岩瀬忠震。その結果、1859年に横浜が開港し、発展めざましい今日の基を開くことになったのだと。山門前の戒壇石に「不許葷酒入山門」(葷酒、山門に入るを許さず)が。葷酒とは仏教の戒律で禁じられた臭気の強い葱ねぎ、韮にら、蒜にんにく、薤らっきょう、興渠はじかみという五辛および酒のこと。臭の強いものや、酒を持ち込む事は禅宗の修 行に差し障りがあるのでこれを許さないと。山門。当時の領事館員達は、当時日本には存在していなかった西洋塗装法(ペンキ)で、建物の彫刻等を塗装して行ったと。今でも唐獅子や蛙股などにペンキ塗装の跡を残っていると。『青木山』と書かれた扁額。正面に本堂。『全国塗装業者合同慰霊碑』。安政三年(1856)アメリカ総領事ハリスは、神奈川宿本覚寺を領事館と定め、本覚寺をすべて白ペンキで塗らせた。これが元で、本覚寺に「全国塗装業者合同慰霊碑」が建立されたと。『地蔵堂』。本尊・地蔵願王菩薩坐像を安置する。俗に子育地蔵と呼ばれ、子供の成長祈願、病気平癒、安産供養の信仰があると。地蔵菩薩立像が地蔵堂の前に。『鐘楼』。『寺務所』。本堂を再び。『水子子育地蔵』。水汲み場には懐かしい手押し井戸ポンプが。境内を散策すると本堂左隣にお釈迦様の涅槃像が。ズームで。本覚寺を後にし、山門前の階段からの横浜駅方面。『東横フラワー緑道』「東横フラワー緑道」は、平成16年(2004)2月の「みなとみらい線」の開通に伴い、「東急東横線」が地下化されたことから、その上部を緑道として整備したもの。当時の写真を掲示していた。『大綱金刀比羅神社』。この神社は、社伝によると平安末期の創立で、もと飯網社といわれ、今の境内後方の山上にあった。その後、現在の地へ移り、さらに琴平社を合祀して、大綱金刀比羅神社となったと。かって眼下に広がっていた神奈川湊に出入りする船乗り達から深く崇められ、大天狗の伝説でも知られている。また江戸時代には、神社前の街道両脇に一里塚が置かれていた。この塚は、日本橋より七つ目に当たり、土盛りの上に樹が植えられた大きなものだったと。『神奈川宿 袖ケ浦』十返舎一九『東海中膝栗毛』よりの文章が掲載。『歴史の街 神奈川宿』。田中家のあるこのあたりは、むかしから神奈川台町と呼ばれ、かつては海沿いの景勝地として広く知られていた。この神奈川は、江戸時代には、東海道五十三次の中の、日本橋から数えて、品川、川崎に続く第三番目「神奈川宿」として栄えていた。その頃の神奈川宿の様子は「東海道中膝栗毛」(十返舎一九)にも描かれているが、昼夜を問わず、街道を行き交う人々でたいへんなにぎわいだったと。幕末の偉人、坂本龍馬の妻おりょうは、龍馬亡きあと、ここで住み込みの仲居として勤めていた。月琴を奏で、外国語も堪能で、物怖じしないまっすぐな性格が、ことに外国のお客に評判だったと。横須賀に嫁いでいき、田中家をやめたあとも、ひいき客からいつまでも話題に上ったと。坂道を登っていくと旧東海道脇に老舗料亭『田中家』が左手に。田中家の前身は、歌川広重の浮世絵にも描かれていた。『田中家』のパンフレットより。今でこそ埋め立てが進み、国道1号と横浜駅を越えて海に出るまで1キロほどあるが、昔は探訪絶景で欄干から釣り糸を垂らせたという。伊藤博文ら明治の元勲や夏目漱石ら文豪も投宿。日本囲碁界の第一人者、呉清源の対局戦も行われるなど数々の著名人に愛されたと。『神奈川の台と茶屋』。「ここ台町辺りは、かって神奈川の台と呼ばれ、神奈川湊を見おろす景勝の地であった。弥次さん、喜多さんが活躍する『東海道中膝栗毛』にも「ここは片側に茶店軒をならべ、いづれも座敷二階造、欄干つきの廊下桟などわたして、浪うちぎはの景色いたってよし」とある。二人は立ち寄り、鯵をさかなに一杯ひっかけている。」「茶屋 うどんそば切有」「そば切ちゃ屋」の文字が見える。更に旧東海道を進む。「神奈川台関門跡」「袖ヶ浦見晴所」と刻まれた石碑。『神奈川台の関門跡』「ここよりやや西寄りに神奈川台の関門があった。開港後外国人が何人も殺傷され、イギリス総領事オールコックを始めとする各国の領事たちは幕府を激しく非難した。幕府は、安政六年(一八五九)横浜周辺の主要地点に関門や番所を設け、警備体制を強化した。この時、神奈川宿の東西にも関門が作られた。そのうちの西側の関門が、神奈川台の関門である。明治四年(一八七一)に他の関門・番所とともに廃止された。」と。「思いきや 袖ヶ浦波立ちかえり こに旅寝を重ねべしとは」正二位権大納言鳥丸光広(江戸前期の歌人・能書家)の歌。『ブローテ横浜高島台』が右手高台に。横浜駅そばの高台にそびえたつブローテ高島台は、バルコニーの青いガラスが目を引く大型賃貸マンション。2015年度グッドデザイン賞。『上台橋』を渡る。かつてこのあたりは、潮騒の聞こえる海辺の道であった。この場所から見えた朝日は、ひときわ美しかったと。『神奈川駅中図会』にも、その姿が描かれていると。この地に橋ができたのは、昭和五年(1930)。開発がすすみ、切り通しの道路ができるとともに、その上に橋が架けられたのだと。上台橋の上から横浜駅西口方面を見る。首都高速神奈川2号三ツ沢線が高架で。『神奈川宿歴史の道←リンク』はほぼこの図の範囲を対象とし、上台橋から神奈川通東公園に至るおよそ4kmの道のりである。旧東海道の標識。これは横浜市西区歴史街道シンボルマークらしい。「区内には、三つの古道、旧東海道、横浜道、保土ケ谷道が三角形をかたどるように通っている」のでこのデザインになったのだと。この辺りの歩道面には、約100mごとにこのマークが。『勧行寺(かんぎょうじ)』。法華宗学陽山勧行寺。越後本成寺末で三ツ沢豊顕寺三世日養をもって開山とする。ご本尊は大曼茶羅、一塔両尊だが境内にも面白いものがある。まず天然理心流の流祖近藤内蔵之助長裕(こんどうくらのすけながひろ)の墓。新撰組局長近藤勇は四代目にあたる。もう一つは水車舟制作の道周翁の墓。水車舟とは外輪船のことだろう。その功績をたたえた水戸藩主の和歌一首が彫られている。他に作家の北林透馬夫妻もこの墓地で眠る。浅間下歩道橋上より。 ・・・その5・・・に戻る ・・・つづく・・・
2019.01.09
閲覧総数 549
-
20

ネパール旅行記(2) カトマンズ早朝散歩
6時に起床し身支度を調え7時にホテルを出発しタメル地区への早朝散歩。ホテルは旧王宮の近くのカンチ道り沿い。ホテルを出て暫く歩くと赤い3重の塔をもつ トリデビ寺院 が左手に。日曜日のそして日本の正月に当たるダサイン祭の為か、店はシャッターを閉め開いている店は未だ無し。しかしこの場所は、ネパールの首都カトマンズ市内で外国人観光客に一番人気のタメル地区。あか抜けして洗練されたレストランやホテル、それに観光地の証し「みやげ屋」の立ち並んでいる街並。観光客だけではなく、地元の人たちも買い物やビジネスにやって来るので昼間はいつも人が溢れる混雑した街なのである。電柱に絡みついている電線の数に驚く。ぐちゃぐちゃ電線。これでは毎日停電するのも解る。そして一軒のみが停電した場合の原因を探すのに時間が掛かることは十分理解できる。複雑に絡み合った電線が、生き物のように街中を行き交っているのである。狭い道路の横には既に野菜を広げて売っている。ミニトマト、短めのダイコン、そしてカリフラワー・・・・・・。生きたナマズを売っている店もあった。ネパールは海のない国、よって魚は殆ど売られていない。唯一海の魚の干物が売られていた。 コインの木。コインが打ち付けられた仏像。近くでみるとネパール・ルピーの硬貨がクギで幾重にも重ねられて打ち付けられているのが確認できた。ちょっと遠目からみると「いったいアレはナンだろう?」と想像もつけられないような形状。立派な由緒のある仏像とのこと。地元の人たちはひっきりなしにやって来て、仏像の中央部に右手を伸ばし祈っていた。何千枚?ものコインが釘付けされている。歯痛を治す神様が祀られているとのこと。散歩の道には多くの野良犬が屯したり、横に寝ている。ただし殆どの犬が吠えずに物静かなのである。しかし朝から元気に子孫を残そうと頑張っている我々と同じく4人組が。朝から誠にご苦労様なのである。既に道端で髪を切ってもらっている者も。手に載せたうどん粉の液体を油鍋に見事に注ぎ込み、リングドーナツが出来上がって行く。ただ、揚げ油が古そうだ...。1つ買って食べて見たかったが、胃もたれしそうな感じの為断念。でも、1個10円ならこの油でも仕方ないのかもしれないが。衛生面も若干気になるところではあるが、高温の油で揚げていて、中までしっかり火を通しているので、大丈夫な気もするが...。ネパールで過剰に衛生面を気にしすぎると、ローカルな旨いいものを食べ損ねるばかりか、生活ができなくなってしまうのではと感じた。もちろん、自分の身を守るための、必要最低限の衛生・清潔はこだわる必要があるが。タメルとダルバール広場の中間地点くらいにあったストゥーパ。このカトマンズを代表するストゥーパはネパール人の熱い信仰の対象であり、それ自体がマンダラの構造をなしているとのこと。描かれた目は四方を見渡すブッダの知恵の目であり、常に変わることなく世界を照らしているというから、崇高にして有り難い図像なのである。日本では常に仏様の顔も姿も荘厳で慈悲に溢れるものとして造形されるが国と民族によって変容する仏の一端を見たように思ったのは私だけであろうか。約2時間弱の早朝散歩を楽しんだが、ネパールには日本でおなじみのコンビニがないのである。海外でも良く見かけるセブンイレブンもファミリーマートもない。早朝散歩時は必ずコンビニでお茶を買っていた私としては、ちょっと寂しいのであった。それでも、外国人が集まるこのタメルには大きめの雑貨屋さんはあった。飲み物(アルコール類も含む)、お菓子、シャンプーやトイレットペーパーや洗剤などの日用品、チャウチャウ(インスタントラーメン)などが売られていた。日本のコンビニと違うのは、弁当類がないことと雑誌類がないことくらいであろうか。店の広さも、日本のコンビニと同じくらい(地方にあるコンビニ限定)ということは、かなりコンビニに近いということか。9時には今回の旅行をアレンジしてくれた、このカトマンズでトレッキングツアーの会社の社長であるRam氏が、ホテルに来てくれることになっていたため、ホテルに急いで戻ったのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2010.10.17
閲覧総数 239
-
21

横浜市泉区の古道を巡る(その29) 柏尾通り大山道~岡津公園~領家谷道祖神群~西恩寺~御霊神社
「永明寺別院」を後にして「柏尾通り大山道」を西に進む。「永明禅寺」の裏山に沿って進むと、左手の荒れ地の奥の高台にあったのが大きな「忠魂碑」👈リンク。「旧中川地区出身各戦役戦没者諸英霊荘厳菩提供養塔」と刻まれた石柱が「忠魂碑」の前に。「忠魂碑」の左側に「戦没者芳名碑」そして「旧中川地区出身戦没者名碑」があった。この敷地は岸井家によって寄付されたと。神奈川県横浜市泉区岡津町1574 岡津公園。「岡津公園」の前の家の表札も「岸井家」。「柏尾通り大山道柏尾通り大山道は、東海道の前不動(柏尾)から岡津の永明寺別院前の大山道道標前を経て、大山へ向かい、西田谷(にしだやと、現、桂坂)で坂道(男坂・女坂)へとつながる道です。「上り 大山道・下り かしを道」と刻まれた道標になっている地神塔は、坂の上り口に立っていましたが宅地造成のとき現在地に道されました。地神塔の立っている前の土手(現在は住宅)にあった庚申塔などは、現在、中川地区センター駐車場横にあります。また、周辺には製糸場もありました。 泉区役所」2基の庚申塔が左手に。左:駒型双体道祖神・・1813(文化10)年右:角柱型文字「地神塔」・・文字「秋葉大権現」「庚申供養■■ 巳待祭神」「桂坂公園」内を歩く。「領家西側」交差点を左折して進む。「西田・領家土地区画整理事業竣功記念之碑」が道路沿いに。その周囲の石碑群。そして左に折れて進んだ所の左手高台にも朱の鳥居の先に石碑群があった。横浜市泉区岡津町1294-3周辺の領家谷(りょうけやと)地域。正面に朱の鳥居と小さな「社」が。左手に丸彫双体道祖神・・1794(寛政6)年と石灯籠。左から角柱型文字「庚申塔」・・1859(安政6)年唐破風笠付角柱型六手合掌青面金剛塔+三猿・・元禄??(1688~1704)角柱型文字「庚申塔」左から角柱型文字「猿田彦大神」塔唐破風笠付角柱型聖観音立像笠付角柱型六手合掌青面金剛塔+日輪月輪+三猿その後、南下した後「弥生台駅」方面への道を進む。左手にあった「老人福祉センター横浜市泉寿荘」前を通過する。横浜市泉区西が岡3丁目。そして「浄土真宗 本願寺派 西恩寺」に立ち寄る。「龍王山 西恩寺」掲示板。「本堂」。宗派は浄土真宗本願寺派に属す。通称西本願寺、又は「お西」と言われています。東京で言えば、築地本願寺と同じ宗派になると。ご本尊は阿弥陀如来。「特別養護老人ホーム恒春ノ郷」の美しい生け垣のある坂道を上って行く。そして「御霊神社(ごりょうじんじゃ)」に到着。横浜市泉区中田北3丁目42-1。神社の前の河津桜も満開に近かった。見上げて。中田町御霊神社の鳥居横に石碑が建っていた。「この碑の建つ土地は大正七年に当時御霊神社総代人であり、また同碑建立世話人であった小山良作氏によって寄進されたもので、このたびの参道改修に際し嫡男小山俊雄氏の赤誠により、整備された。後世のために之を誌す。昭和五十乙卯年二月吉日 宮司 宮本忠直」と刻まれた石碑。「宮本湊(いたる)先生頌徳碑(しょうとくひ)」👈リンク。中田の子弟の教育に尽力された中田学校教師宮本湊の頌徳碑である。「御霊神社戸塚区・栄区・鎌倉市域の御霊神社と同しく鎌倉権五郎景政を祀った神社で、昔から中田のごりょう様と呼ばれていました。明治の廃仏毀釈前は宮司家の東端に実相院の不動堂や護摩堂がありました。保安林に囲まれた石段下の弁天池は村岡川(宇田川)の源流になっています。池の前の庚申塔は、区内最古のもので、地域文化財に登録されています。鳥居横には、中田の子弟の教育に尽力された宮本湊先生の頌徳碑があります。 泉区役所」「御霊神社 石鳥居」。扁額「御霊神社」。社号標「村社 御霊神社」。参道を進むと掃除中のおばあちゃんの姿が。右手にあったのが「弁天池」と「厳島神社」。「弁天池」の傍らには石碑が建ちそこに「弁天の湧水 村岡川源流」と。村岡川とは宇田川の別名。弁天池に湧いた水は流れ出て宇田川となって境川に合流し相模湾に流れ出るのだ。「弁天池」のすぐわきに「ふどうばし」がかかり、そこにも「村岡川源流」と記されていた。「手水舎」。「石造庚申塔」が左手に。泉区内で最も古い庚申塔といわれていて、横浜市指定有形文化財に指定。「横浜市指定有形文化財(石造建造物)石造庚申塔指定年月日 平成十三年十一月一日所有者 宗教法人 御霊神社所在地 横浜市泉区中田北三丁日三三六五番地時代 江戸時代 寛文六年(一六六六)在銘法量 総高一〇九・〇 cm 笠高 一八・〇cm 巾四四・〇cm 奥行き三九・〇cm 塔身高 六六・五cm 巾ニ七・〇cm 奥行きニ五・五cm 台石高 ニ四・五cm 巾五三・五cm 奥行き四七・〇cm形状 角柱笠塔婆型員数 一基この塔は、横浜市域に所在する庚申塔の中でも古く、方形の台石の上に角柱の塔身を立て、笠を置く角柱笠塔婆型で、台石の上部には、コの字形の池をめぐらし、正面の左右に円形の半島をつきだし、花立を造っている。塔身の四面には、南無河弥陀仏の名号が刻まれ、正面には耳をふさいだ猿、向かって左側面にはロをふさいだ猿、右側面には目をふさいだ猿がそれぞれ浮き彫りにされている。」平成十四年三月 横浜市教育委員会」「庚申塔(大山道道標)」。「この庚申塔は、今から百五十九年も前の嘉永六年(一八五ニ)に、根下集落の庚申信仰集団(根下講中)の人たちによって、中田東ニ丁目一六九七番地先の大山道(旧長後街道)と柏尾道(戸塚を経由せず白百合を越えて江戸方面への近道)の分岐する道端に建立されました。道路の北側に南向きで建立されましたから、「右 とつか道」、分岐の「東 かしを道」、また反対方向の「西 大山道」と、碑面の左右に記され、庚申信仰の対象物だけでなく、道案内(道標)も兼ねています・今回、今までお祀りされていた場所が開発によって鎮祭が不可能となったため、現在の根下講中及び向根下自治会の人たちが相談し、鎮守様、御霊神社参道のこの地に遷座しました。」「狛犬(右)・阿形像」。狛犬(左)・吽形像であるはずだが・・・。「社殿」。御祭神:鎌倉権五郎景政(かまくらげんごろうかげまさ) 平安時代後期の武将、相模国鎌倉の領主、後三年の役で右目を射たれながらも 奮闘した勇将、関東平氏五家(鎌倉氏・梶原氏・村岡氏・長尾氏・大庭氏)のひとつ「社殿」は享保11年(1726)に再興されたといいます。しかし関東大震災で倒壊し、その主要部分を再利用し翌大正13年9月に現在の本殿が再建された。さらに昭和7年に拝殿、渡殿など新築され、社殿となっている。扁額「御霊神社」。「神楽殿」。「敬神崇租(けいしんすうそ)」碑。神を敬い先祖をあがめる、 尊いものとしてあつかうこと と。「敬神崇祖」 の四文字熟語は、 第二次世界大戦(太平洋戦争)までは国語辞典に記されていたとのことですが、 戦後教育において“政教分離”のもとに、現在、国語辞典には掲載されていないと。社殿の向かって右側に境内社が並んでいた。「矢並稲荷社」「大日大聖不動社」「日枝山王社」「金比羅社」、石廟数基。境内社「矢並稲荷社」。扁額「矢並稲荷」。「矢並稲荷」の「社殿」。境内社「大日大聖不動社」。「???」。境内社の「日枝山王社と金比羅社」。境内社「石廟」。「御神木」。「神輿庫」横浜市最古の木造学校建築物であると。「お知らせこの建物は大正十五(一九ニ六)年六月に、中和田小学校の奉安殿(その頃の学校では、主要行事が行われるときに、講堂の正面に、天良皇后両陛下のお写真をお飾りした。また、主要行事が行われるときには、校長先生が教育勅語を奉読して子供たちに聴かせ、その情神を伝えた。お写真は普段は取り外し、教育勅語と一緒にこの泰安殿に納めて置いた)として建てられたもので、横浜市最古の木造学校建築物となりました。平成ニ十六年ニ月の大雪で、上部の楠の技か折れて瓦屋根が壊されました。先ごろ、瓦下地の木工事や高価な特注の鬼瓦や平瓦を焼いて、修理が終わったばかりです。この建物には現在お祭りの時に使う、大人用と子供用のお神輿が納められています。」「御霊神社幼児園」正門。地域の鎮守さまの「御霊神社」が、昭和43年4月に境内の続きに開園したと。帰路の参道横にあった「石塔」。これも庚申塔であろうか?「山岳信仰碑と起立講遥拝所(きりゅうこうようはいしょ)」本社鳥居前の右手に石段が山を上って行く。この石段の上り口に建つ石柱には「木曾御嶽神社」とあった。この石段を上ると起立講(きりゅうこう)の御嶽山遥拝所(おんたけさんようはいしょ)に至っる。各地に残る山岳信仰の場の一つ。遥拝所には山岳信仰碑が立ち並んでいた。向かって左に板石碑が建ち、「國常立尊」(くにとこたちのみこと)、「三笠山神社」、「御嶽山神社」、「八海山神社」と刻まれていた。その右わきに、大黒天像がありその台座には「起立講中」と刻まれていた。その右わきに板石碑が建ちそこには「神武天皇白川神社」と。起立講とは木曾の御嶽山を信仰する山岳信仰をおこなう集まり。この御嶽山遥拝所でお参りし、また木曾の御嶽山に登りお参りをしていたのだと。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.03.29
閲覧総数 692
-
22

横浜市泉区の古道を巡る(その36):専念寺~三嶋神社(横浜市戸塚区深谷町)
次に訪ねたのが「専念寺」。ここも我が藤沢市に隣接する横浜市戸塚区深谷町1021。旧東海道沿いの「戸塚区」👈リンク は既に歩いていたのである。寺号標「浄土宗 深谷山 青陽院 専念寺」。脇門入口には元禄6(1693)と刻まれた石道標(尖頭角柱)。高155㎝(塔身部)、幅35㎝、厚24㎝。正面:「(梵字)婦可や藥師 青陽院江之道」右面:「深谷山」左面:「専念寺」と 刻まれていた。「法然上人像」。ズームして。「ただ一向に念佛すべし」と。勲八等瑞寶章を受勲された川邊氏御兄弟の墓碑であろうか。そして手前に墓地、その奥に本堂。「鎌倉権五郎景正と専念寺の深谷目薬師前九年の役の鎮定功労者陸奥守源頼義の嫡男八幡太郎義家は陸奥守となり赴任したが、奥州の覇者清原武則家の家督争いにまきこまれ、まれに見る大乱となった、戦場は沼冊からさらに要害の地金沢冊に移るが義家軍の苦戦の報が都に届くと義家の弟新羅三郎義光(甲斐源氏武田祖)が京から来援 これに力を得た義家が総政撃し非常な苦戦の末、寛治元年十一月(一〇八七)、金沢冊を陥落させ、家衡と武衡を討つことに成功し、後三年の役はようやく終冪となった。この戦いに弱冠十六歳の鎌倉権五郎は金沢冊の戦いで敵の矢に左目を射抜かれると戦友三浦為次が駆け寄り、景正の顔に足を掛け、その矢を抜こうとするや景正は「武士の顔に足を掛けるとは」と怒り刀を抜いて切りかかったと言う。凱旋後景正は守り本尊の深谷薬師に治療の願をかけ、寺の前の深谷薬師で目を洗ったところ、たちまちにして目の傷が癒えたと言われる。深谷薬師は霊験あらたかな目薬師如来として信仰厚く、今も十ニ年毎に開扉している。鎌倉時代に活躍した大庭、俣野、梶原一族も戦国大名上杉謙信も鎌倉権五郎景正の子孫である。」そしてこちらが「かまくら道」側の正門で「宇田川」に架かる赤い欄干、親柱に擬宝珠(ぎぼし)を載せた橋。橋の名は「専念寺橋」。「宇田川」の下流方向を見る。この先1.5km程先で「境川」に流れ込む川である。本堂への参道を進む。正面に「山門」の冠木門が。「是者鎌倉権五郎景正守本尊 ふかや薬師青陽院江之道」と刻まれた石碑。寺号標石「浄土宗 深谷山 専念寺」「鎌倉権五郎景正守本尊 薬師如来」鎌倉権五郎景正の守本尊薬師如来(行基作)を安置していると。「山門」と「本堂」。「本堂」。「当寺は深谷山青陽院専念寺(しんこくざんせいよういんせんねんじ)と言い、元は鎌倉岩瀬にある大長寺の末寺でした。開山は大長寺と同じ鎮連社感誉存貞(ちんれんじゃかんよぞんてい)上人で、鎌倉権五郎景正(ごんごろうかげまさ)の祈願所として、康平五年(1062)に起立したと伝えられています。その後文治年間(1185~89)景正の末裔である梶原景時が再建し、福泉寺といって当時は真言宗でした。永禄年中(1558~69)住職であった長順法師が感誉存貞上人より浄土の教えを聴き、その素晴らしさに感銘し、以来浄土宗に改宗し、一心院専念寺と呼ばれていました。」と「専念寺」👈リンク のHPから。扁額「専念寺」。「本堂内陣」。新装なった「納骨堂」。右手に「六地蔵」。「六地蔵」を正面から。両脇に市松模様の描かれたガラス窓の奥の堂内にも地蔵様が。蓮の花のエッチングガラスの姿も美しく。エッチングガラス(彫刻ガラス)とは硝子表面にサンドブラスト処理(金剛砂等を圧縮空気で吹き付けて削る)を行いさらにフッ素加工(薬品処理)を施したガラスのこと。「本堂」手前の2本のイトヒバの大木は切られていた。専念寺の本堂は一見すると近代以降の建築のようであるが、享和元年(1801)の再建になる、という。昭和44年(1969)には屋根の大がかりな改修が行われ、部材が新しいものに置き換わっている、と。墓地内の「永代供養塔」。「南無阿弥陀仏 ○源空」、「俱會一処(ぐえいっしょ)」と。「源空」は法然(ほうねん)上人の諱(いみな・生前の実名)。「俱會一処」とは「たとえこの世で大切な方との別れを迎えようとも、南無阿弥陀仏とお念仏をおとなえする者どうしは、阿弥陀さまのお迎えをいただき、必ず俱(とも)に一つの処(ところ)、すなわち西方極楽浄土でまたお会いすることができるのです」という教えであると。墓地内の「永代供養塔」から「本堂」を見る。枯山水の庭園の中の「十三重塔」とその奥に「客殿」、「庫裡」が。正面が「客殿」。「庫裡」、「寺務所」。「会館」。「トイレ」。次に隣の山の上にある「三嶋神社」に向かった。「専念寺」の川沿いのカイズカイブキの生け垣も見事に刈り込まれていた。三嶋神社参道入り口の専念寺側にある「石碑群」。「川邊勝三郎君頌徳之碑」。横浜市と合併したこの地域、大正村の村長だった人物のようだ。富士塚の富士講碑。「富士元一講長 中講義川邊徳次郎君之碑 登山参拾参回」。「富士仙元大菩薩 元一○照?」(照の文字を○で囲っている?)。「小御嶽 后尊 大天狗 大権現 小天狗」。「石碑群」の前の橋は「宇田川」に架かる「宮前橋」。「宮」とは三嶋神社のことであろう。そして「三嶋神社入口」碑。石段を上って行く。竹藪の前に「三嶋神社」があった。「三嶋神社」の石の鳥居。鳥居を潜って進む。「社殿」。大正3年(1914)築。扁額「三嶋神社」。「三嶋神社祭神 大山咋命 鎌倉権五郎景政所在地 戸塚区深谷町一〇ニ六番地宮司 中川 港由緒今より約七百七十余年前の文治年間に梶原平三景時が創建したものである。景時はその祖、鎌倉権五郎景政が崇敬していた専念寺を再建するに当り傍の丘陵を開拓して社殿を建て景政の神靈をまつり相殿に伊豆三嶋神社を勧請して御靈社と稱した。後に至り社名を三嶋神社と改め現在に至った。社殿については寛延二年十二月八日(今より三百余年前徳川時代)の棟札があり現在の社殿は大正三年三月三十日新築され昭和四十九年十月修理改築されたものである。」水引虹梁の上の中備(なかぞえ)に龍の彫刻がおかれていた。右側の「木鼻」は獅子鼻、獏(ばく)鼻。左側の「木鼻」。「社殿」の廻廊の両側にある彫刻(左側)、鷲の姿であろうか。「社殿」の廻廊の両側にある彫刻(右側)。「社殿」前から境内を見る。境内の「稲荷社」。「秋葉神社」。火除けの神・秋葉大権現を分祀する。「地神塔」(文久元年(1861年)銘)。大地を司る神様を祀る。「大六天神社(大六天様)」。名木古木指定「スダジイ」。名木古木指定「樅(モミ)」。名木古木指定「檜(ヒノキ)」。そして竹林。「三嶋神社」からの帰路に「専念寺」の「本堂」を裏から見る。そして再び「専念寺」の生け垣と「宇田川」、前方に朱の欄干の「専念寺橋」。ハクセキレイ(白鶺鴒)に似ているがそして「横浜市 消防訓練センター」の案内板を見つけたので行ってみた。坂を上っていくと左手にあったのが「横浜市消防局 消防訓練センター」入口。この訓練センターでは、消防学校教育として次の教育を実施していると。・新採用職員教育 新採用の消防職員に、消防業務に必要な基礎的知識・技術を修得させるとともに、 「自ら考え行動できる職員」を育成。・現任教育 活気ある強力な組織を作るため、経営・運営責任者に対する教育や、救助隊員等の養成教育、 各種資格取得講習等を幅広く実施。・消防団員教育 それぞれの職責と階級に応じて、消防団の活動に必要となる規律、活動要領、安全管理などの 教育を実施。建物内に見学用ブース等はないのであろうか?門の前の道路を進んで行くと左手に、様々な訓練用施設が確認できた。隊員が消防自動車の前でミーティング中?訓練用タワー。反対側には消防自動車や救急車の姿も。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.04.05
閲覧総数 668
-
23

茨城県内「続日本百名城」と社寺巡り その7:牛久大仏
「大杉神社」を後にして国道125号を霞ヶ浦方面に向けて車を走らせる。前方に橋が見えて来た。「小野川」に架かる「新古渡橋( しんふっとばし)」を渡る。この一帯は,昭和25年の茨城百景に「古渡(ふっと)湖畔」として選定された場所。「小野川」は、茨城県南部を流れ霞ヶ浦に注ぐ利根川水系の一級河川。更に進むと左折すると「JRA美浦トレーニング・センター」へ向かう「トレセン入口」交差点を直進する。「JRA美浦トレーニング・センター」は茨城県稲敷郡美浦村にある日本中央競馬会(JRA)の施設(トレーニングセンター)である。中央競馬の東日本地区における調教拠点である。略称は「美浦」「美浦トレセン」「美浦TC」など。上空から見た「JRA美浦トレーニング・センター」。 【https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%BE%8E%E6%B5%A6%E6%9D%91】より茨城県道34号線に移り進むと前方に見えて来たのが「圏央道」。ここは「圏央道」の「阿見東インター入口」交差点。「圏央道」の下を通過し300m程進むと、「牛久大仏」➡右折 の案内板。そして車窓前方に巨大な「牛久大仏」の姿が。「牛久大仏」の駐車場に向けてケヤキ並木を進む。そして駐車場に車を駐め、「牛久大仏」の散策開始。牛久大仏(正式名称:牛久阿弥陀大佛)は、日本の茨城県牛久市にあるブロンズ(青銅)製大仏立像で、全高120メートル(像高100メートル、台座20メートル)あり、立像の高さは世界で6番目。ブロンズ立像としては世界最大。浄土真宗東本願寺派本山東本願寺によって造られた。小動物公園や花畑などがある浄土庭園内にあり、公園墓地「牛久浄苑」との複合施設となっている。総面積は37万平方メートルに及ぶ と。牛久市久野町2083。「牛久大仏建設の事業構想は1983年に関係者によって着手された。1986年に着工、1992年12月に完成した。事業主体は浄土真宗東本願寺派本山東本願寺。浄土真宗東本願寺派の霊園である牛久浄苑のエリア内に造られた。その姿は同派の本尊である阿弥陀如来像の形状を拡大したものである。全高120メートル(像高100メートル、台座20メートル)を誇り、奈良の大仏(像高14.98メートル)が掌に乗り、アメリカ合衆国ニューヨーク州にある自由の女神像(全高93メートル、手を掲げた姿勢の像高46.05メートル)の実質的な像高(足元から頭頂までの高さ33.86メートル)の3倍近くの大きさである。地上高世界最大の"ブロンズ製"人型建造物(仏像)であり、ギネス世界記録には「世界一の大きさのブロンズ製仏像」として登録されている。地上高最大の人型建造物は、インドのグジャラート州ナルマダー県にある建国の父の1人とされる指導的政治家ヴァッラブバーイー・パテールをかたどった全高240メートル(像高182メートル、台座58メートル)の「統一の像(Statue of Unity)」。なお、近代以前に造営されたものでは、唐の磨崖仏である楽山大仏の像高59.98メートルが世界最大である。」とウィキペディアより。「高さの比較」図。「牛久大仏」は全長120m。インドのグジャラート州で、最近世界一高い像・統一の像(Statue of Unity)。この像は、ガンジーの信奉者で、インドの統一に貢献した政治家サルダール・パテールに敬意を表したもの。つまり、彼を像にしたのだ。建設費は実に約4億2000万ドル(日本円で約476億円)。建設期間は、約4年。高さは182m、台座を含め約240mに達するという。 【https://guardindustry.com/reference/statue-of-unity/】より世界の像高の比較。2位は「魯山大仏」、3位に「牛久大仏」。 【https://narmadatentcity.info/how-to-reach-statue-of-unity-and-tent-city/】より再び「牛久大仏」のお顔をズームで。頭の上に避雷針が。「牛久大仏」駐車場入口から。「牛久大仏」は南南西を向いている。その方角には浅草・本山東本願寺があり、またその先には仏教誕生の地・インドがあると。超巨大な「仏」の姿。「牛久大仏」が結んでいるのが「来迎印(らいごういん)」と呼ばれる印相。親指と人差し指を合わせて輪を作っているのが特徴。来迎とは人々を救うために阿弥陀如来が迎えにくることで、右手は掌を外に向けて胸の前に上げ左手は掌を外に向けて垂れ下げ、両手とも親指と人差し指をつける印相で手が左右逆の場合を逆手来迎印という と。左掌の長さ:18.0メートル親指の直径:1.7メートル 人さし指の長さ:7.0メートル。臨終の際、阿弥陀仏が西方極楽浄土より迎えに来るときのポーズと。「牛久大仏」が正面に見える位置まで道路を進んで行った。そして塀の隙間から「牛久大仏」を。建設施工は川田工業による。建築にあたっては主に高層ビルで用いられるカーテンウォール工法が採用された。まず中央に、大仏全体の重量を支える役割を果たす鉄骨の主架構を組み上げる。次に、主幹の役割を果たすこの鉄骨の周囲に、枝を生やすように、あらかじめ地上で作っておいたブロックを組み合わせていく。高さ100メートルの仏像本体は20段の輪切り状に分割して設計されており、さらにそれぞれの輪切りが平均17個のブロックに分割されている。加えて、各ブロックは平均1.5メートル四方の青銅製の板金を9枚程度並べて溶接し、下地となる鉄骨と組み合わせることで作成された。この下地鉄骨が、複雑な形状をとりながら主架構と青銅板との間を繋ぎ、樹木でいうところの「枝」に相当する役割を果たしている。仏像表面の青銅板は葉のように浮いているだけであり、巨大な質量を支える必要がないため、6ミリメートル程度の厚みしかない。これは、銅板で全体の重量を支える奈良の大仏などとの大きな違いである。特に形状が複雑な両手部分についても、別に地上で組み上げ、巨大クレーンを用いて吊り上げられた。像の表面には、これを覆うための6,000枚以上の青銅板が用いられている とこれもウィキペディアより。そのため、像の表面を注意深く見れば正方形のタイル状の継ぎ目を確かめることができる。これらブロックの継ぎ目部分には隙間があり、台風や地震、気象変化による板金の伸び縮みに対して構造上の余裕を持たせる役目を果たしている 再び「牛久大仏」のお顔をズームで。顔の長さ:20.0メートル、螺髪(らほつ)は総数:480個。1個の直径:1メートル、1個あたりの重量:200キログラム)壁の隙間から「牛久大仏」の頭の縮小版を見つけた。高さは約2mと。「牛久大仏のお顔の大きさは、この縮小の1000個分のボリュームに相当する」と。なるほど、実物のお顔は20mあるので20m/2m=10、体積は3乗に比例するので10☓10☓10=1000個分のボリュームに相当。大仏前の「大香炉」。大仏の前に置かれて いる「大香炉」は青銅製香炉として日本一の大きさであると。壁の隙間から「牛久大仏」のミニチュアの姿も確認できた。その後ろにあるのが「發遣門」であるようだ。牛久市の雨水マンホール蓋。「かっぱの里」牛久市観光協会のマスコットキャラクターである、かっぱの「キューちゃん」。 右手に打ち出の小づち、左手にキューリを持ち、いたずら小僧みたいな表情。 郷土の画家、小川芋銭がよく描く対象がかっぱであると。 右下には水連の葉とカエルも描かれていた。「牛久大仏」の入苑入口に向かって進む。拝観料は大仏胎内入場込みのセット券で800円/人。開苑は9:30、この時の時間は9:22で開苑前であった。「牛久大仏」を再び見上げる。「牛久大仏」の内部は鉄骨構造の高層ビルディングの如きと。 【https://www.eco.kawada.co.jp/blog/on-site/4177/】より主鉄骨の外部はジャングルジムの如く、下地鉄骨が張り出していると。そして下地鉄骨から外装材の青銅板を固定した鉄骨を連結していると。 【https://www.kawada.co.jp/technology/gihou/pdf/vol36/3601_03_01P.pdf】より「牛久阿弥陀大仏頭部鉄骨模型 S=I : 30 (紙製)地上93.5メートルから119.65メートルのお顔内部の鉄骨模型。緑色に塗られている鉄骨が主架構、白色の鉄骨が下地鉄骨。下地鉄骨はお顔の形に合わせ設計されている。架設にはカーテンウォール工法を採用したため、42個のプロックに分かれる構造になっている。プロック1つの量は板を含め約6トン。」組み立てた時の写真を『ネット』👈リンク から。お顔を地上で仮組。 【http://photozou.jp/photo/show/1075137/81249567】よりそして据え付け。 【https://4travel.jp/travelogue/11695451】より大仏の胸部にあたる地上85メートルまではエレベーターでのぼることが可能で、美しい関東平野の景色を展望することができる。ただし、像自体の美観の問題から広々とした展望場所は設けられておらず、胸部からの景色は4・ 5階の「霊鷲山(りょうじゅせん)の間」にある3つのスリット状に設けられた小窓◯から見ることになるのだと。3階は極楽浄土の別名「蓮華蔵世界」で、壁一 面に約3,400体の胎内仏を安置。2 階は写経を行う「知恩報徳の世界」、1階は阿弥陀如来の大きな慈悲を表す美しい光の空間「光の 世界・観 想の間」が広がっているのだと。「展望台」👈リンク4・ 5階の「霊鷲山の間」にある、3つのスリット状に設けられた小窓。 【https://hirakana.hateblo.jp/entry/2020/12/19/230651】より3階は極楽浄土の別名「蓮華蔵世界」で、壁一面に金色に輝く約3,400体の胎内仏を安置。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より2階は写経ができる「知恩報徳の世界」。心を落ち着けて写経ができる席は全部で77席。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より周囲には繋ぎ目の線が確認できたのであった。左腕にも小窓が見えた。その外にぶら下がってあったのは風速計?、地震計?桜の時期にはこの様な見事な光景に。「牛久大仏 浄土真宗東本願寺派 本山 東本願寺」と書かれた銘板。「エレベーターで地上85mの展望台へ」案内板。「ようこそ 牛久大仏へ」。「像の基本情報」をウィキペディアより。構造:青銅板張立像全高(地上高):120メートル像高(立像の場合、本体の長さ):100メートル台座の高さ:20メートル(うち、基壇部は高さ10メートル、蓮華座は高さ10メートル・ 直径20メートル)総重量:4,000トン(うち、本体重量:3,000トン、外被青銅版の総重量:1,000トン)顔の長さ:20.0メートル目の長さ:2.5メートル 口の長さ:4.0メートル 鼻の長さ:1.2メートル 耳の長さ:10.0メートル左掌の長さ:18.0メートル親指の直径:1.7メートル 人さし指の長さ:7.0メートル足の爪の長さ:1.0メートル螺髪(らほつ。総数:480個。1個の直径:1メートル、1個あたりの重量:200キログラム)造営期間:1989年 着工、1993年6月 落慶存続期間:1993年 - 現存内部構造と情報内部にはパネル展示等があり、歴史や仏教の世界について学ぶ事ができる。1階:光の世界(Infinite Light and Infinite Life) 観想の間:浄土の世界を観想する(思い描く)空間。2階:知恩報徳の世界(World of Gratitude and Thanksfulness) 念仏の間:毎週土曜日、ここで法話がある。阿弥陀如来への報恩感謝の気持ちを籠めて 写経を行う空間。写経席は77席。3階:蓮華蔵世界(World of the Lotus Sanctuary) 約3,300体の胎内仏に囲まれた金色の世界。「蓮華蔵世界」とは極楽浄土のこと。4・5階:霊鷲山の間(Room of Mt.Grdhrakuta) ここには仏舎利(釈尊の遺骨)が安置されており、参拝できる。 また、四方に窓があり、東西南北を見渡せる。地上に置かれている巨大な右手。 【https://gurutabi.gnavi.co.jp/a/a_650/】より平均1.5メートル四方の青銅製の板を繋ぎ合わせているのが確認できたのであった。賑やかなペットボトル飲料の自動販売機。ここにも見事な桜と芝桜の写真が利用されていた。ここが入苑通路。両側には土産物等の売店が並んでいた。そして車に戻る途中に振り返り「牛久大仏」に別れの挨拶を。そして先程、このブログを書いている時にネットから見つけた写真。年に一度の「牛久大仏」の清掃では清掃作業員が大仏の目の部分からロープで垂れ下がり汚れを洗い落とすのだと。 【https://www.sankei.com/photo/story/news/151021/sty1510210007-n1.html】より螺髪の清掃に向かう清掃作業員。 【https://ameblo.jp/kakurekumanomi2008/entry-12635274619.html】より ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.11.06
閲覧総数 2130
-
24

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その53)・ スリーハンドレッドクラブ~茅ヶ崎配水池~甘沼 八幡大神
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次「成就院」を後にして、ゴルフ場「スリーハンドレッドクラブ」の前の道への坂道を上って行った。道路脇には紫の菖蒲(しょうぶ)の花が。近づいて。ゴルフ場の入口に向かって坂を上って行った。相模川方面の街並みを見下ろす。そして左側にあったのがゴルフ場「スリーハンドレッドクラブ」の入口。神奈川県茅ヶ崎市甘沼441。ここスリーハンドレッドクラブは日本の政財界の超一流人300人だけが会員になることが許されている超が付く名門コース。歴史を紐解けば昭和37年、東急電鉄が造成したメンバークラブで、当時の入会基準は、政治家は首相か外相の経験者のみ。財界人は東証一部上場企業で50歳以上という狭き門であったと聞くが現在でも?アメリカのトランプ大統領が来日した際に安倍首相が埼玉県・川越市にある『霞ヶ関カンツリークラブ』でゴルフ外交をしたのは有名だが、その直前に“コソ練”をしたのが、ここスリーハンドレッドクラブだったのだと。さすがに、多くの高級車が駐車していた。その先、左にあったのが「茅ヶ崎配水池」。「茅ヶ崎配水池災害用指定配水池概要構造 鉄筋コンクリート造大きさ 12m☓12m☓1池 48m☓48m☓1池有効水深 4.0m満水時水位 標高50.0m容量 5184m3この配水池は、寒川浄水場から送られてきた水を貯えて、茅ヶ崎市の皆様に供給するために築造されたものです。また、この配水池は、地震など災害が発生した場合に応急給水に必要な飲料水を確保する配水池に指定されています。」配水池の平・断面図。そして坂道を下って行くと右手に小高い山への上り口があった。そこを上って進むと、次の目的地の「甘沼 八幡大神」の社殿境内への裏道が続いていた。前方に「新湘南バイパス」、その先に「江の島」の姿が。「江の島」をズームして。裏道を下り、「甘沼 八幡大神」の境内に入り、正式な入口まで進む。石段の先に石鳥居そしてその奥に拝殿の姿が見えた。社号標石「甘沼 八幡大神」。石段横の老木の内部には空洞部も。石灯籠と石鳥居。「甘沼八幡大神と甘沼村の由来八幡大神社 格 相模国高座郡甘沼村明治六年十二月披列村社候事祭 神 八幡大神は誉田別命(注応神天皇)軍の神様境内に末社あり殿山稲荷と云う祭神に倉魂神 農業の神様創 立 明暦二年丙甲(西暦1656年)今から参百弐拾六年前である。現建物 奥殿は昭和二十六年十月に再建された。本殿は昭和四十八年九月に村有志により再建 されたものである。甘沼村の由来由 来 昔より高座郡に属す起源詳ならず口碑に今の本村の田地震にて概て一円沼地にして其辺 甘草の生茂せしを漸々開墾したるを以って甘沼村と云い懐島郷(旧大庭の庄)の一つで あったが冠稱を廃して現今は単に村名のみを用う。沿 革 往古詳ならず永禄年間北条氏の臣近藤孫三郎来地たり天正十八年庚寅徳川氏に代り 承応三年甲午旗下堀順三郎の知行所となり明治元年戊辰八月韮山県に属し同年九月に 神奈川の所轄となる。」石鳥居の下を進む。右手にあったのが「鐘楼」。「八幡大神拝殿新築記念」と。「昭和四十八年九月吉日再建」と。「平和の鐘」と。その先に「庚申塔」。青面金剛像をその表に彫りつけた形式の庚申塔の出現期のものである。4臂の像で、2猿を従えている。この形式の庚申塔は今までに7基が知られており、内1基は年号が分からないが、他は承応2年(1653年)から明暦4年(1658年)の間の年号銘をもつ。しかもそのいずれもが、相模川下流域に集中している。この庚申塔は、この7基の内の2番目に古い年号銘をもっている。「八幡神社の庚申塔 平成十八年二月十四日 神奈川県指定有形民俗文化財庚申塔は、庚申信仰に基づいて江戸時代に盛んに造られるようになったもので、人の延命招福を願ったものである。この塔は青面金剛像を彫った庚申塔の出現期のもので、承応三年(1654)の年号が見える。基部には造立者十人の名が刻まれている。四臂(よんび)(うで)で二猿を従えるこの形式の塔はこれまで七基が見つかっており、いずれも相模川下流域(茅ヶ崎三、平塚二、寒川一、藤沢一)に分布している。初期の青面金剛像の庚申塔として貴重なものである。」石碑群。左から●舟形光背型「廿三夜塔」・明治三十七年一月吉日、●山状角柱型「道祖神」・「丙安政三年/辰正月吉日」(1856)、●山状角柱型「道祖神」・「安政二乙卯正月吉日」(1855)石段を上り終えると正面に「拝殿」。狛犬「阿形像」。狛犬「吽形像」。太い丸太で蓋をしてあったのは手水場であっただろうか。「拝殿」御祭神 誉田別命( ほむだわけのみこと )祭礼 1月1日 元旦祭(がんたんさい) 7月15日 浜降祭(はまおりさい) 8月4日 例祭(れいさい)屋根の鬼瓦とその下の彫刻。頭貫の彫刻。裏に 木彫師 渡辺豊雲 と。木鼻(右)。木鼻(左)。扁額「八幡大神」。「境内社」。「神輿殿」。扁額「神輿殿」。「甘沼 八幡大神」の神輿。 【https://ameblo.jp/syounan0211/entry-10016796571.html】より「神楽殿」。この境内社の名前は??「甘沼八幡大神」を後にして小出県道に出て南西に進み暫くして左折した場所にあった「小祠」。神奈川県茅ヶ崎市甘沼594。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.05.30
閲覧総数 278
-
25

3か月でマスターする数学・『新幹線の座席が2人席と3人席である利点は?』
この日のNHK放送の授業テーマは、『新幹線の座席が2人席と3人席である利点は?』新幹線の普通車の座席は、通路を挟んで2人席と、3人席という構成になっています。レールや車体の幅から1列の座席は全部で5席に決まったと考えられますが、実は2人席と3人席になっていることには乗客にとって意外なメリットがあります。それは、グループ旅行に対応しやすくなるということ。グループで旅行する際、できる限り隣の座席は同行する人であってほしいですよね。2人席と3人席という配置になっていることで乗客のグループがどのような人数であっても、隣接した座席には同行者が座る状態を作ることが可能になるのです●2人で旅行するなら2人がけの席を、●3人なら3人がけの席を予約するでしょうし、●4人の場合なら2人席を2つ分取れば、隣は必ず同行者になります。 それ以上の場合はどうでしようか。●5人なら2人席と3人席、●6人なら3人席x2、または 2人席x3●7人なら2人席x2 + 3人席、●8人なら3人席x2 + 2人席 または 2人席x4●9人なら3人席x3、または 3人席x1+2人席x3●10人なら3人席x2 + 2人席x2 または 2人席x5●・・・・・・・・・・・・・~というように予約すれば、やはり隣は同行者です。どんな人数であっても(1人旅の場合は除きますが)、隣が同行者になるため、1人ぼっちになる人はいなくなり、楽しく旅行できるというわけです。そしてJR側もどんな数の団体客が予約に来ても、ぴったりに座席を埋めることができるのです。すなわち、1人だけが使う2列席・3列席とかを極力なくすことができるのです。つまり、新幹線の座席が2席の列と3席の列に分かれている理由は、座席の余りを可能な限りゼロにするためだったのです。※ もちろん、一人客に対してはどうしようもない。以上のことを、もう少し数学的に表してみましょう。n人で旅行する際、2人席をx個、3人席をy個分予約すると考えれば、次の式で表すことができます。2x十3y=n(x,yは自然数)実は、『どんな数nでもx,yは存在する』のです。nがどのような値を取るかによって、当然、x,yの値は変化します。nが偶数の場合は2人席だけを使えばよいですし(y=0)、nが3以上の奇数なら3人席を1つ、残りは2人席にすればよいとわかります。つまり、nが2以上の整数であればすべてのパターンを作れるということです。つまり、2以上のすべての自然数は、2の倍数と3の倍数の和で表わすことができます。(例えば、13=2×2+3×3)同じように、飛行機で3人席と4人席の配置になっているとしたら、6人以上のグループ客について「隣は必ず同行者」という状態が作れます。注意したいのは、これが成り立つのは2つの整数が「互いに素」のときだということ。 「互いに素」というのは、2つの整数が1以外に共通の約数を持たないことを意味します。4と9は互いに素ですが、2と4の場合は2が共通の約数になりますから、互いに素ではありません。 「互いに素」ではない座席の例このような座席配置では、任意の整数を作ることができない。ちなみに3列シートの中央の座席は他の座席よりも横幅が2㎝広いそうです。今回の授業にはありませんでしたが、なぜ東海道新幹線・山陽新幹線の3列の座席が車両の南側に配置されているのか?って、考えたことがあるでしようか?もし、そのように聞かれたら、別に北側に配置してもいいんじゃないの?と私は思ってしまったのでは!?。実は、日本の鉄道車両は昔から塩害に悩まされてきたためか、車両の心臓部てもある駆動装置は、できるたけ海から遠ざけるという考えが常識になっていました。なので、重い駆動装置を海から少しでも遠い北側に配置して、できるたけ塩害を避け、左右の重量バランスを取るために、3列席を南側に配置した というのが真相のようです。東北、上越、山陽の各新幹線の多くの普通車でも2列+ 3列という座席配置となっていますが、3列座席が海側に配置されているか、乗る機会があったら気にして見てください。因みに東北新幹線の車両も3人席は海側・太平洋側になっていると記憶しています。「新幹線の指定席、どこが一番好き?」をネットから。新幹線の指定席の中で、一番好きな座席はどこだろうか。私が現役時代に選んだのは、3列シートの窓側。2列ではなく3列シートをチョイスするのは、隣が空席になる可能性に期待を込めてのことであった。「圧倒的な人気を誇った指定席は、「2列シートの窓側」席で、選んだ人の割合は61.2%(473票)となった。2位は、「2列シートの通路側」席(15.8%、122票)。全体の75%以上、つまり4人に3人が「2列シート」に投票。つまり、3列シートのいずれかの席を選んだのは、全体の4分の1のみ。みなさん、3列よりも2列シートが大好きらしい。3位「3列シートの窓側」席(11.9%、92票)と4位「3列シートの通路側」(10.5%、81票)の間には、大きな差はない。とはいえ、2列シートの時と同じく、3列シートの場合でも通路側より窓側が人気という構図は変わらない。人気を博した「窓側」席について、大手掲示板サイトの5ちゃんねる(旧2ちゃんねる)には、景色が見放題であることはもちろん、日よけを自由に上げ下げでき、コート掛けまで使えることを「勝ち組」だと評するスレッドがたっている。また東海道新幹線の場合、2列シートの窓際......つまりE席では、窓から富士山を見ることができる。」と。最後にもう一つ。新幹線(電車)の席次は?上座・下座について。学会や結婚式・法事などに上司や目上の人と一緒に列車や新幹線などを利用する機会もあると思います。乗車してから席順で慌てることがないよう、新幹線等の席次についても基本を覚えておきましょう。現役時代は、皆個人で座席指定をしていたので、このようなことを考えたことは皆無に近い私なのです。以下、ネットからです。新幹線をはじめとする列車内での席次の基本は「窓側が上座・通路側が下座」です。この基本に、ドアの位置や進行方向を考慮して、目上の人を上座に案内します。新幹線のグリーン車や列車等では、2人掛けシートの窓側が上座、通路側が下座になります。4人掛けボックスシートでは、窓側の進行方向を向いた座席が一番上座。窓側の進行方向と反対の座席が2番目、通路側の進行方向の座席が3番目、通路側の進行方向と反対の座席が下座になります。進行方向を向いた座席を上座とする考え方もあり、その場合は、2番目と3番目が入れ替わります。新幹線の普通車のように3人掛けシートの場合、窓側の座席が上座、通路側が2番目、真ん中の座席は狭く感じられ不便なので下座になります。2人掛けと3人掛けがあれば、2人掛けの方が通路に出やすいため、上座になります。6人掛けボックスシートの場合は、4番目までは4人掛けと同じ、進行方向を向いた真ん中の座席が5番目、その正面が下座となります。窓側を上座と考えると上記のようになりますが、進行方向を向いた座席を上座とする考え方では、進行方向を向いた窓側から1、3、2番目となり、進行方向と反対のシート窓側から、4、6、5番目となります。いずれの場合も、目上の方の意向を確認してから案内する気配りが欠かせません。例えば、車両出入口付近は人の出入りが多くうるさいため、出入口から遠い方が上座になります。また、窓側に座ると通路に出にくいため、携帯電話を利用するなど頻繁に席を立つ場合はデッキに出やすい通路側を希望する方もいます。特に指定がなければ、目上の人を上座に案内しますが、必ず「窓側でよろしいでしょうか?」「進行方向とは逆向きになりますがよろしいですか?」などと声をかけるようにすれば、相手に対する心配りが伝わります。5名の場合は窓側➡️通路側の席次順。6名の場合は、下図の如き考え方もあるとのこと。進行方向最優先で窓側➡️通路側の席次順。こちらは窓側最優先➡️通路側➡️中央席。ここまで列車内の席次について紹介しましたが、これらはあくまでも原則です。たとえば、時間帯や進行方向によって窓からの陽射しの入り方が変わります。周囲の乗客の様子や、空調の当たり具合・トイレの頻度など体調の変化にも気を配り、美しい景色が見える方角があれば座席交代を提案するなどの心配りも身につけたいところです。原則を踏まえた上で、相手や状況に合わせて臨機応変に対応する姿勢が大切です。目上の人の希望をたずねるなど、相手とのコミュニケーションをしっかりとることで、移動が心地よい時間と空間になると思います と。今日は新幹線の『座席』に対する『学び』でした。但し、2+3人席が最初から乗客の便宜の為に考えられていたのかは疑問であると考える私なのである。つまり、後付の偶然の産物ではなかったのか!?と。皆さんはどのように考えますか? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2024.09.25
閲覧総数 1790
-
26
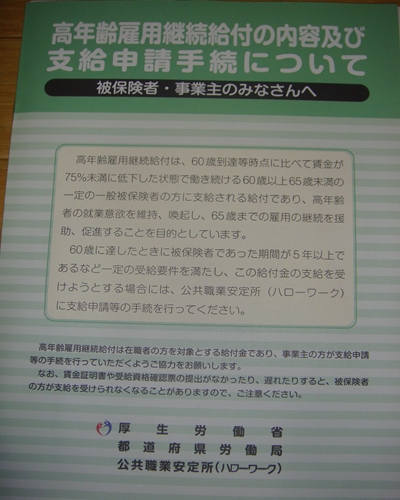
高年齢雇用継続給付金
昨年12月に60才の定年を迎え、そのまま現在も『嘱託』として勤務を継続しています。給料が大幅に下がった以外は勤務時間も、勤務内容等は全く変わりません。毎月の給料が大幅に下がった為に国から『高年齢雇用継続給付金』の支給を受けています。高齢化社会が進行する中で、働く意欲と能力のある高齢者の方に対して、60歳から65歳までの雇用の継続を援助、促進するための制度なのです。高年齢雇用継続基本給付金を受け取るには、以下の条件を全て満たしていなければならないのです。1.現在の給料が、60歳になる直前6ヶ月間の、平均月額(ボーナスは含まず)の75%未満の時2.60歳以上~65歳未満の被保険者であること。すなわち60歳以上になっても、雇用保険に加入していること。3.被保険者期間(=雇用保険加入期間)が、通算して5年以上必要。そして高年齢雇用継続基本給付金の支給期間は、60歳になった月~65歳になる月まで支給されるのです。具体的な支給額は、以前の給料に比べてどのくらい下がったかによって、以下のように変わるのです。60歳になる直前、つまり定年退職直前の6カ月間の平均の給料を100として、現在の給料がA.75%以上のとき・・・給付金の支給なし。B.61%以上~75%未満のとき・・・現在の給料の15~0%が支給。C.61%未満のとき・・・現在の給料の15%が支給。1月にいただいた『高年齢雇用継続給付支給決定通知書』です。現在の給料の15%が最大支給されるような給料体型を選択しました。よって支給金額=??,???円。偶数月に2ヶ月分まとめて支給されるとのことです。給料から引かれる税金、保険類は前年度の年収に対してかかるため、給料が下がっても税金、保険類金額は前年と同様。よって1月の手取り給料は悲惨なものでした。この金額を給料の穴埋めとし、しばらくは我慢の生活なのです。
2011.02.09
閲覧総数 3420
-
27
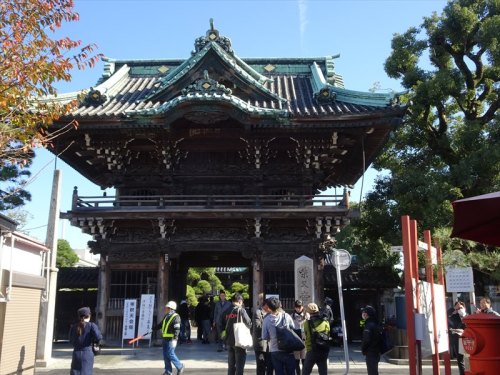
柴又帝釈天へ(その2:帝釈天境内散策)
“柴又"と言えば柴又帝釈天。また、“帝釈天"と言えば、この柴又帝釈天が代名詞のようにもなっている。正式名称は「経栄山題経寺」という寛永年間創建の日蓮宗寺院であるが、江戸時代から帝釈天として知られていたと。明治以降も、文芸作品に登場するなど名所であり続けていたと。二天門。入母屋造瓦葺の楼門(2階建て門)で、屋根には唐破風とその上に千鳥破風を付す。帝釈天の配下の四天王のうち、南方守護の増長天、西方守護の広目天を安置。明治29年、江戸期建築の最後の名匠と言われた、坂田留吉棟梁によって造りあげられた、総欅造りの豪壮な門。日光東照宮の陽明門を模したと言われ、桝組は、三手先、扇タルキの見事な出来映えは、この寺の建造物の中でも、ひときわ優れているのだと。この二天像は、奈良大安寺にあった往古の文化財と伝えられ、奈良時代の造像。多くの木彫群によって荘厳された重厚優美な二天門は、門前通りの正面にそびえ立っていた。寅さんの映画では、二天門の柱にもっと「千社札」が貼られていた記憶があるが。奥に見える大鐘楼は昭和30年に出来たもので、寅さん映画での、寺男源吉(愛称:源公、佐藤蛾次郎演)が打つ鐘の音が聞こえて来そうなのであった。そして御前様(笠智衆)も現れそうなのであった。虹梁や柱貫、木鼻などには浮き彫りの見事な装飾彫刻が施されていた。 柴又帝釈天の二天門は表側を加藤勘造一門、裏側は四代伊八・信明が施した作品であり、関東の彫刻を語る上で欠かせない存在感となっていると。加藤勘造はこの後訪ねる彫刻ギャラリーの装飾彫刻『法師守護の図』を製作し全体を纏めた加藤虎之助の父親であると。何故か他人事とは思えない加藤一族なのであった。二天門扉の虎。二天門扉の龍。虹梁の表側の十六羅漢の図。裏左、羅漢図。裏左、猿遊図裏右、羅漢図。裏右、遊猿図。羽目板裏・左、羅漢図 羽目板裏・左、遊猿図。羅漢図。木鼻部の龍も見事。 初層左右には四天王のうちの増長天および広目天の二天を安置し、門の名はこれに由来する。二天像は平安時代の作とされ、門の建立時に同じ日蓮宗の妙国寺(大阪府堺市)から寄贈されたものであるとのこと。金網の隙間にカメラのレンズ部を挿入し写真撮影にTRY。「増長天」。増長天は左手に剣を持ち南方を守護。 「広目天」。広目天は右手に剣を、左手には巻物を持ち西方を守護。帝釈天境内案内図。 福祭殿。「帝釈天王」の御朱印を頂きました。そして柴又七福神の「毘沙門天」の御朱印も併せて頂きました。いずれも正式寺名の「題経寺」の文字が。境内から袴腰付きの大鐘楼を見る。昭和30年、名匠、林亥助棟梁によって完成された総欅の大鐘楼。高さ約15m、四手先の豪壮な桝組と木彫を施し、関東一の鐘楼と言われる。梵鐘は、吉田兼好の徒然草に登場した妙心寺の名鐘「黄鐘調(おうしきちょう)」と似た響きを持つようで、昭和の銘鐘の名が高いと。 環境庁選定「日本の音風景100選:柴又帝釈天界隈と矢切の渡し」の主役。寅さんの映画でも必ずこの大鐘楼の効果音が挿入されているのは有名。御神水のほど近くには菩薩様が安置されていた。 帝釈天に参拝した人々の多くがこの浄行菩薩に水をかけていた。遠目から見ても凛とした雰囲気が。 浄行菩薩。法華経に説く地涌(ちゆ)の四菩薩の一人で、地水火風の四大の内、水大の菩薩として、この世を浄化し、人々の罪や穢れを洗い清めて下さるのだと。病をかかえている場所を磨けば痛みが和らぐとの事で頭に水をかけてきました。二天門をくぐり正面にあるのが「帝釈堂」の拝殿。入母屋造瓦葺の拝殿と内殿が前後に並んで建つ昭和4年製の建物だと。帝釈天が有名だが、帝釈天は本尊ではなく、帝釈堂も本堂ではないらしい。帝釈堂内に、東方守護の持国天、北方を守る多聞天が、帝釈天の脇士として配置。手前にある見事な樹形の「瑞龍松」が。内殿は大正4年(1915年)、拝殿は昭和4年(1929年)の建立。内殿に帝釈天の板本尊を安置し、持国天と多聞天(毘沙門天)を安置する。帝釈堂内殿の外側は東・北・西の全面が装飾彫刻で覆われていたのであった。そして内殿は建物ごとガラスで覆われ、見学者用の通路を設け、「彫刻ギャラ リー」として有料公開してこの後にじっくりと鑑賞したのであった。帝釈堂の扁額『善見城(ぜんけんじょう)』。帝釈尊天がおわします帝釈堂の正面、堂々たる扁額に光る金文字は「善見城」。遥かな高みの仏の天の忉利天にそびえる帝釈天の居城、善見域を現世で拝礼する唯一の場がこの帝釈堂。「瑞龍松」の根本。南向きの14.5mの枝は、途中から西に9m分枝している。東に12.5mの枝が非常に長く延びて見える。枝先の枝分かれ、屈曲も多く、年月を経た樹形であることが見て取れるが、幹は細く、また、若々しい。200年前の江戸時代の絵図にも記載があるということから、伝承通り460年かと言われる名木。“帝釈天で産湯をつかい・・・"と言うから、たぶん寅さんも使ったに違いない御神水。 帝釈堂の横からは、昭和48年に庫裡のあった場所に「鳳翔会館(ほうしょう会館)」を完成させブリッジで繋げていた。手水舎。昭和の時代の作品で切妻式で勾配が柔らかい屋根の形が美しかった。稚児達?が大きな手水鉢を支えていた。 寅さんおみくじは200円。おみくじ筐体にはペラペラのラミネ加工のPOP広告が貼られており、「おみくじの運勢なんて信じない?それを言っちゃ、おしまいよ。」「寅さんのこころに残る言葉 全48種類」との惹句が書いてあった。 改修記念碑。草木供養の碑。【人類は平和で緑豊かな環境で暮らしたいものです。 社会に見られる都市開発が日々と進み快適さ、利便性を求め、実益を優先して様々な建設工事が激増して居ります。此の事は其れなりに意義あるもので御座居ますが、其の都度多くの草木が失われ、やがて地球温暖化に繋がってしまいます。 自然環境は守りたいものです。土の恵みを伝え、植樹する時も自分の心に木を植える事と思い、草木を愛し現在ある緑の保全と小さな緑を広げ緑に覆われた地球を創り出したいものです。 其の様な事を念頭において、建設事業に携わる東京造園業組合員一同は、草木に思いを起こし、 感謝をこめて、心よりの草木供養之碑建設を決意致しました。 なお僭越ですが、社会の皆々様にお呼びかけをして、御一緒に手を取り合って草木の大切さを語り合える場所にもしたいと思います。幸いにも東京都知事石原慎太郎様より題字の揮毫を戴き、その上柴又帝釈天題経寺住職望月日翔様、 望月洋靖様の御厚情により、多年念願であった、緑を大切にするための草木供養之碑建立を達成する事が出来ました。平成十六年六月十八日 東京造園業組合】と。題字を書いたのはこの当時都知事の石原慎太郎氏なのだと。 柴又帝釈天出現由来碑。 【この碑は、安永8年(1779)題経寺本堂改修の時発見した日蓮上人自刻の帝釈天板本尊を後世に伝えるため、弘化2年(1845)俳人 鈴木松什および壇徒 石渡忠右衛門等などが協力し、その由来を記し、併せて帝釈天の功徳を述べている。碑の総高は、1.48メートル、撰文は宮沢雉神遊、書は荻原翬、刻者は窪世昌である。題経寺縁起の整ったものは、明治29年(1896)に作成されたが、本碑は、それ以前における由緒資料として貴重である。葛飾区立教育委員会】と。 水原秋桜子句碑.『 木々ぬらし 石う可ちつひに 春の海』水の偉大さを称賛した句か?秋桜子は高浜虚子に師事し、後に「馬酔木」を主宰した俳人。代表的な句集に「葛飾」があるのだ。帝釈堂からは渡り廊下で祖師堂(本堂)へ繋がっていた。 祖師堂(本堂)。帝釈堂の向かって右に建つ。帝釈堂と同様、入母屋造の拝殿と内殿が前後に並んで建つ。こちらが日蓮宗寺院としての本来の本堂であり、本尊は大曼荼羅。 柴又帝釈天 題経寺の中で、一番古い堂はこの「釈迦堂」。文化・文政期とされているので西暦1800年頃の建造物。当時の建築様式が見られる貴重な建造物。奈良時代作という釈迦如来立像と、開山日栄上人と中興の祖日敬上人の木像を安置。本堂前から二天門方面の境内を望む。 金銅仏の坐像が2体鎮座。 左側が観音菩薩坐像 右側が大日如来坐像。富士親時が檀那となり奉納された観音菩薩像であり、元は富士山頂に位置した下山仏であると。 『納札巴連 納札碑』。 『東日本大震災 犠牲者供養塔』。 南大門越しに本堂を見る。境内では寅さんサミット 2016の会場準備が行われていた。 『人生劇場 青春立志の碑』。【 遺す言葉死生、命ありだ。くよくよすることは一つもない。お前も父の血をうけついでいるのだから、心は弱く、涙にもろいかも知れぬが、人生に対する抵抗力だけは持っているだろう。あとは、千変万化。運命の神様はときどき妙な、いたずらをする。しかし、そこで、くじけるなくじけたら最後だ。堂々とゆけ。よしんば、中道にして倒れたところで、いいではないか。永生は人間にゆるされてはいない。父は地獄へゆくか極楽へゆくか知らぬが、見ろよ、高い山か谷底見れば瓜やなすびの花ざかりだ。父は爛々たる目を輝かして、大地の底から、お前の前途を見まもっていてやるぞ。尾崎士郎】と。 大鐘楼下の西門を境内から見る。 通用門か?車の出入り口として使われているのだろうか? 黄葉した銀杏の葉の奥に再び袴腰付きの大鐘楼が。
2016.12.14
閲覧総数 1480
-
28

旧東海道を歩く(三島~原)その1:三島駅~三島・源兵衛白旗橋
『旧東海道を歩く』ブログ 目次新年の1月4日に箱根関所~三島大社を歩きましたが、引き続き1月16日(水)に旅友のSさんと三島駅から原宿に向かって歩きました。この日の三島~原への旧東海道ルートマップ。JR東海道線に乗って8:01に三島駅に到着し南口を出る。駅前広場の水飲み機能を一体化した『水琴窟』。水琴窟は窟内に水滴を落としたとき発生する反響音を楽しむもの。少し金属的な音で、琴の音に似ていることから水琴窟と呼ばれています。三島市内にはこのように水を用いた仕掛けが点在しているとのこと。そして散策開始。駅前から旧東海道に向かって歩く。左手の分離帯の中には『愛染院(あいぜんいん)跡の溶岩塚』が。この溶岩塚は今から一万年ほど前、富士火山の爆発により噴出した溶岩が、約40㎞流下し凝固したものであると。溶岩は表面が冷却し凝固しても、内部から突きやぶり小丘となる場合があり、本溶岩塚もその活動がうかがえる貴重な例であると。そしてその近くにあったのが、『交通安全祈願の母子像』。「交通の災禍を絶とう愛の手で」。道路右側には『三島市 市民文化会館 ゆうゆうホール』が。そして赤い板状のモニュメントは「『からくり時計』⬅リンク。毎時0分になるとホイッスル調のオープニングメロディーが流れ、それと共にミラーボールの様な丸い扉が回転し、3体の人形が出て来るのだと。そして『寿楽園』入口。ここ以降しばらくは、前回に訪ねブログにアップ⬅リンク していますが、旅友が未だであるとのことでしばし案内しました。『浅間神社』入口。『源兵衛川(げんぺいがわ)』入口。静岡県都市景観賞 優秀賞の石碑。富士山の伏流水が湧く楽寿園内小浜池を水源とする清流。「オランダカイウ」であろうか、この日も白きカラーの花に似ていた。シロサギであろうか、2羽が仲良く。『旧中央水道水源』。旧中央水道の水源は富士山からの湧水を、この界隈の飲み水として使用してきたが、平成15年度に三島市の水道への切り替えに伴い廃止されたもので、普段は自噴していたが、水位が下がった時はポンプアップしていたと。『鎌倉古道』。「鎌倉古道は、伊豆国分寺前から赤橋・祓所神社まで通じる道で、平安時代から戦国時代頃まで伊豆の主要道として用いられた。その沿道には、多くの寺院などが立ち並び、江戸時代初めに近世東海道が整備されるまで、大変な賑わいを見せていました。」と。『伊豆国庁址碑』。iPhoneで『国庁址(こくちょうあと)』を探すが、民家のオバチャンに聞いてもわからない中、ブロック塀と一体化された碑を見つける。掘立柱建築跡や布目瓦を出土したことから、軽部慈恩氏が国庁跡と推定し、碑を建立したとのこと。そして『廣澄山 圓明寺(えんみょうじ)』へ。円明寺『表門』(伝旧樋口本陣表門)。円明寺 『本堂』。そしてこれからは新たな散策道。赤い欄干の橋が眼前に。三嶋大社の西側にある『祓所神社』から西へのびる道(桜小路)を横切る御殿川にかかっている橋がこの『赤橋』です。この橋の欄干が赤く塗られていることから赤橋と呼ばれており、江戸時代には駿豆五色橋の1つに数えられていたと。 三島市ではレンタサイクルも行われている模様。『問屋小路(とんやこうじ)』。三島宿でみんなに親しまれ、その名が知れていた八つの小路や七つの石、七つの木。江戸時代、箱根の関所を通るのに、これらをスラスラ言うことができれば三島人の証明となり通行手形を持たなくても通行することができたと。問屋小路は三島田町駅を起点として北へ向かい、UFJ銀行を通過し、市役所中央町別館横を通り過ぎて赤橋の通りまでをいうと。江戸時代には現在の市役所別館の所に問屋場があったと。三島中央郵便局のところにあったのが『問屋場跡の碑』。三島の宿は、慶長6年(1601)徳川幕府の交通政策として宿駅に定められ、東海道有数の大宿として認められたが、この宿場の施設として同年この場所に問屋場(現・市役所中央町別館)が設置されたと。そして旧東海道に出る。せせらぎルート 『全体案内図』と『静岡県景観賞の記念碑』。『御殿川』。御殿川は白滝公園付近の水門で桜川から分流するが、この水門は水量が多く、川の落差を利用して激しく流れ落ちることから「どんどん(どんど)」と呼ばれていると。三島駅方面に曲がる交差点を直進する。『世古本陣址』。三島の宿には世古本陣と、道を挟んで樋口本陣があった。本陣の建物は書院造りで、門構え、玄関、上段の間、控え の間などの部屋や湯殿、庭がある広大なものだった。郷土館には宿泊した大名 の関札があり、樋口家にある『樋口本陣文書』と『織部灯籠』は、市の文化財 に指定されている。なお、三嶋大社には茶室『不二亭』も移築されていると。道路の反対側にも『樋口本陣』の石碑が。江戸時代格式の高い樋口本陣は、現在の山田園のあたりにあり、その門は今は先ほど訪ねた芝本町の円明寺山門になっていると。『東海道三島宿・樋口本陣跡』案内板。「本陣について本陣とは江戸時代五街道などの宿場 に設けられ、大名、公家、幕府役人などが宿泊した施設で、大名宿とも言った。三島の宿にはここに樋口本陣、道をはさんで北側に世古本陣があった。本陣の建物は書院造で、門構え、玄関、上段の間、控の間などの部屋や湯殿、庭がある広大なもの。三島市郷土資料館には樋口本陣文書(市指定文化財)と宿泊した大名の関札があると。なお三嶋大社には樋口本陣の茶室「不二亭」も移築されているのだと。三島宿について三島は古くから伊豆の中心地として栄え、三嶋明神の門前町として大変な賑わいを見せていました。慶長6年(1601)徳川家康 は宿駅制度を作り、最終的には東海道に53の宿駅を設け、三島宿 は江戸日本橋から数えて11番目の宿駅でした。また、三代将軍家光が参勤交代を制定した事により各大名の東海道往来が多くなり、箱根に関所が設けられると三島宿は「天下の険」箱根越えの拠点としてさらに賑うようになりました。また、東西を結ぶ東海道と南北を結ぶ下田街道・甲州道との交差する位置にあった三島宿は、さまざまな地域の文化や産業の交流地点ともなっていました。伝馬、久保、小中島、大中島の4町辺りが宿の中心地で、実際の運営もこの4町が核となり行われていました。三島宿は初代安藤広重 の浮世絵代表作「東海道五十三次」では、三嶋明神鳥居前を出立したばかりの旅人が描かれています。また文政9年(1826)に訪れたオランダ人医師シーボルトが三島・箱根の自然観察記録を、安政4年(1857)には三島宿に泊まったアメリカ人ハリスが、宿泊先(世古本陣)の日本庭園の素晴らしさを日記に書いています」と。『中央水道跡公園』『四ノ宮川』四ノ宮川は、広瀬橋下で源兵衛川から分流する小さな川だが、近年は湧水の枯渇や街中での占用が多く忘れ去られた存在であった。周辺の開発に伴い、街中の貴重なせせらぎとして修景整備をした。廃止された近くの簡易水道「中央水道」の水源井戸の清流を利用し、四ノ宮川の水源地のように表現してある。周辺には中央水道のノスタルジックな建物も残っていると。『曹洞宗 向富山 常林寺』。『山門』。『法堂』。天正元年(1573)開創の曹洞宗の寺で、開山は麒庵東麟大和尚(きあんとうりんだいおしょう)。本山は永平寺、總持寺。法堂(はっとう)には本尊として聖観世音菩薩(しょうかんぜおんぼさつ)が祀られている。現法堂は、昭和5年(1930)の北伊豆地震の直後に再建立され、三門・庫裡とともに木造の伝統的な建築物。「 向富山 」と書かれた『扁額』。境内の『慈母観音』。『西国観音礼場巡拝記念供養塔』。多くの石仏が並んでいた。一体一体異なる『観音像』。『庫裡』。質素な石仏も。そして三島大通りに架かる『原兵衛橋』。源兵衛川にかかる源兵衛橋は『源兵衛白旗橋』とも呼ばれて江戸時代に駿豆五色橋の1つに数えられていた橋で、三島市には他に青木橋・赤橋があり、沼津市には黒瀬橋・黄瀬川橋があるのだと。 ・・・つづく・・・
2019.04.08
閲覧総数 866
-
29

横浜市泉区の古道を巡る(その35):深谷通信所跡地
次に訪ねたのは「深谷通信所跡地」。神奈中バス停を通過し振り返る。ここ神奈川県道402号阿久和鎌倉線(かながわけんどう402ごう あくわかまくらせん)は、神奈川県横浜市瀬谷区阿久和東(阿久和交差点)から鎌倉市岡本に至る県道である。この路線は通称「かまくらみち」と呼ばれるのである。1180年(治承4年)頃、源頼朝が鎌倉から府中方面へ抜ける街道として整備したと。別名「陣街道」、「西の道」とも呼ばれたのだと。「通信隊前」。近くにあった「モクレン」の花。ズームして。ハクモクレンに似た花で、薄いピンクが入ったモクレンが咲いていた。ハクモクレンとシモクレンの交雑種のサラサモクレンであろうか。道路の反対側のバス停の横には立派なトイレが設置されていた。横浜市泉区和泉町 で番地はない様子。「深谷通信所跡地」の入口ゲートは固く閉ざされていた。「この区域は、在日米軍から日本国政府に変換された国有地です。当局の許可なく当該区域への立入りを禁止します。またこの区域の以下の行為は固く禁止します。・喫煙及び火気の使用・ゴミ等の投棄・ゴルフ、ラジコン(飛行機)等危険な行為・ペットの放し飼い横浜市関東財務局関東財務寺務所」との表示。当時は下の如きプレートが設置されていたと。「U.S NAVAL RADIO TRANSMITTING FACILITY TOTSUKA JAPAN」と。当時はここは横浜市戸塚区であったのだ。 【http://home.p04.itscom.net/yama/US_Fukaya/Fukaya.htm】より左手に入る道もゲートで塞がれていたが、散歩されている方がいたので、私も内部に入って行った。車両のみの進入禁止のようであった。「右のサインを読みなさい」と上から目線の文字が。しかし右側には特別の案内はなし。ここ深谷通信所(ふかやつうしんじょ)は神奈川県横浜市泉区に所在していた旧在日アメリカ海軍基地(面積:773,747m2)。旧日本海軍の基地を第二次世界大戦後に接収し、運用していたもので、2014年6月3に施設を含めた土地全体が日本へ返還されたのだと。横浜市泉区の和泉町および中田町に位置。全域が国有地であり、アメリカ海軍厚木航空施設司令部が管理を行っていたのだと。googleマップより。まるで巨大なミステリーサークルの如し。旧日本海軍時代には、電波干渉を防ぐため直径約1kmの円形状に用地買収され、米海軍がその形状のまま接収した。接収後、米海軍は施設中心部に事務所等やアンテナ部分の囲障区域(フェンス等で囲まれた内側)を設け、関係者以外立入禁止としていたが、囲障区域外は野球場、ゲートボール場、菜園耕作等の使用が認められ、さらに神奈川県道402号阿久和鎌倉線が通過し一般の通行が認められていた他、バス停も設置された。衛星通信が発達し送信機能が他施設に集約されたことで部隊は撤退し遊休地化していたが、2014年6月末を目処として囲障区域も含めた土地全体を米側から日本へ返還することが決定し、予定通り手続きが完了したことから同年6月30日に返還が行われたのだと。当時の通信施設をネットから。 【http://prc77.livedoor.blog/archives/471356.html】より当時の通信施設をネットから。 【http://prc77.livedoor.blog/archives/471356.html】より当時の通信施設をネットから。 【http://prc77.livedoor.blog/archives/471356.html】より右手の忍び返し(有刺鉄線)を取り付けた進入防止用フェンスの奥には「FIRE STATION NO.10」と記された建物が残されていた。有刺鉄線を取り付けた進入防止用フェンスに沿って進む。「旧深谷通信所跡地中央広場」案内板。そして正面に真っ白な雪を戴いた富士山の勇姿が現れた。ズームして。右側には大山の姿も。「中央広場」の掲示板。「ノーリードでの愛犬の散歩はご遠慮下さい。」と。直径1kmの緑地には大小の野球場が10ヶ所以上。芝生広場では富士山を背景にゲートボールを楽しむ老人の姿が。電線が邪魔、しかしここは昔の通信所であるので・・・・。頂上では強風で雪が舞っているのであろうか。大山をズームして。「中央広場」を独り占め。再び「旧深谷通信所跡地中央広場」案内板。広大な跡地。横浜薬科大学の図書館棟(旧ホテルエンパイア) の姿も。こちらにも建物がそのまま残されていた。そして入口まで戻ったが、立派なテーブルと椅子が置かれていたが散歩の休憩用か? ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.04.04
閲覧総数 905
-
30

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その31):伊勢宮大神宮~養蚕発祥の地~川寿稲荷神社
【海老名市歴史散歩】 目次「諏訪神社」を後にし南下すると直ぐ右手角にあった朱の鳥居のある神社。海老名市中新田2丁目27−50。正面から。内陣には石祠が。そして西に進むとを小さな橋が。相模川に流れ込む水路の名は?左にカーブする場所にも水路が。こちらには水が流れていなかった。そして右手にあった「伊勢宮大神宮 (いせのみやだいじんぐう) 」に到着。海老名市中新田3-7。「伊勢宮大神宮」は、延宝6年(1676)に創祀以来、天明6年(1786)・明治10年に修理され維持されて来たが、神社整理令により明治43年中新田諏訪神社に合祀された。昭和25年氏子中の希望により元の鎮座地に還座したのだと。「社殿」。祭神は天照大神。扁額「伊勢宮大神宮」。内陣。「伊勢宮大神宮」を後にして、南東に向けて進む、左手にも神社が。海老名市中新田3丁目8−20。これも稲荷社であろう。「伊勢宮下」交差点を直進する。次の路地を右に進むとあったのが大きな石碑。「蠶神」と刻まれた石碑。裏面には「神奈川縣蠶業試験場 創立ニ五周年記念昭和十年十一月 神奈川蠶友會建之」。「神奈川県蚕糸技術 発祥の地」碑。神奈川県蚕業試験場の創立25周年を記念して神奈川蚕友会が建立した記念碑。蚕業試験場は明治43年神奈川県農事試験場養蚕部として藤沢町に設置され(本碑の「創立25周年」はこれを指している。)、大正11年、蚕業試験場と改称された。大正14年、支場が中新田に作られ、昭和24年、本所が藤沢町から中新田に移転した。その後、県の養蚕関係機関の再編に伴い昭和42年、蚕業センターに統合され、本所は中新田に置かれた(神奈川県養蚕センター『要覧』1968年)。しかし養蚕業の衰退により、平成7年、神奈川県農業技術センター(本所は平塚市上吉沢)に統合され、跡地は宅地、および公園となっている。その先にあったのが火の見櫓(ひのみやぐら)。「中新田自治会館」。海老名市中新田3丁目25−1。「カンバーランド長老キリスト教会海老名シオンの丘教会 牧師 玉井幸男」案内板。そして次に「川寿稲荷神社」を訪ねた。海老名市中新田3丁目17。入口には松の手入れをされる職人さんの姿が。「社殿」。倉稲魂(うかのみたまのかみ)をご祭神とし、文政8年(1825)、京都の伏見稲荷神社の神霊を勧請し、中新田の河原宿のとうかの森に鎮座する。川は川原、寿は長寿に由来する。扁額「川寿稲荷大明神」。内陣。境内の「ケヤキの木」。「海老名市自然緑地保存樹木第267号 令和2年9月15日指定樹木名 ケヤキ幹の周囲 1.88メートル」「六刀碑天正十八年七月豊臣秀吉小田原城を」攻略北條氏を降しました。次いで八月関八州の統治を徳川家康に任命され其の家臣高木主水正清秀が伍阡石の海老名郷を治められました。私共先祖六名はその家臣であります。高木主水正正次は元和九年九月河内河南壹万石の領主となり赴任されましたが六名は随行せす此の稲荷の森に刀を納め此の地に土着し農業に精進したので有ります。爾来荏苒(じんぜん)三百六十余年を経た今日その痕跡を明らかにすべく茲に碑を立て永く記念するもので有ります。昭和四十一年丙午師走 子孫敬白」現在も残る「六刀碑」は、その言い伝えを残すために昭和41年(1966年)に子孫の人たちによって建てられたと。碑の末尾からも解るのであった。「郷土かるた 「ろ」」「六刀碑 武士すてさりて 農となる」。「川寿稲荷神社」を後にして、海老名市中新田3丁目の住宅街を北に進む。そしてこの先右手で県道45号線に通じる道を横断。角にあった「稲荷森の道祖神」碑。更に直進する。再び水路を横断。そして次の目的地「東興寺」まで200mを確認。「中新田小学校入口」交差点が前方に見えて来た。そして歩道橋の先に「東興寺」の屋根が見えたのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.10.25
閲覧総数 574
-
31

アイルランド・ロンドンへの旅(その75):Dublin市内散策(14/)・ダブリン城(Dublin Castle)-1
Christ Church Cathedral・クライストチャーチ大聖堂を後にして、東方向に歩く。ダブリン城(Dublin Castle) の敷地内、アッパー・ヤード(Upper Yard) の入り口にある石造りの門が現れた。ダブリン城は13世紀初頭(1204年頃)、イングランド王ジョンの命で建設が始まった。城は防衛拠点として機能するため、四方に高い石壁と堀(moat)が巡らされていた。この堀は、ポドル川(River Poddle)の流れを取り込み、水堀(水のある堀)として利用されていた。実際、ポドル川は現在も地下を流れており、城の下を通過しているのだ と。この太鼓橋の下は現在埋め立てられているが、元々は堀や防衛溝が存在していた空間である と。ダブリン城(Dublin Castle)内の中庭(Upper Yard)に入る石造アーチ門と橋.石造アーチ門は、Upper Yard(アッパー・ヤード)と呼ばれる中庭への主要な出入口の1つ。ダブリン城(Dublin Castle)の配置案内図。近づいて。1 Dublin Castle Ticket Office チケット売場(入口案内所)2 State Apartments 国家行事用の部屋群(一般見学可)3 Viking & Medieval Excavation ヴァイキングと中世遺構の展示エリア4 Chapel Royal 礼拝堂(歴代総督の使用)5 Record Tower 城で最も古い塔(13世紀)6 Dubh Linn Garden 城裏手の公園エリア7 Coach House Gallery アートギャラリー(展示あり)8 Terrace Café カフェスペース9 Hibernia Conference Centre ハイバーニア会議センター (会議や公式イベントに使用される施設)10 Bedford Hall ベッドフォード・ホール (かつてのバンケット会場、現在も多目的に使用)11 Printworks Conference Centre プリントワークス会議センター (大規模イベントや展示会、会議等に対応)12 Chester Beatty チェスター・ビーティ図書館・美術館 (貴重な写本・東西の美術コレクションを所蔵)13 Revenue Museum 税務博物館(Revenue Museum) (アイルランドの税制の歴史を紹介)14 Revenue Commissioners 税務当局(国税庁本部の一部) (事務所棟)15 Assay Office 貴金属検査局(アッセイ・オフィス) (金・銀などの純度を検査・認定)16 Garda Museum ガルダ博物館(警察博物館) (アイルランド警察の歴史・資料を展示)ダブリン城(Dublin Castle)内の「アッパー・ヤード(Upper Yard)」と呼ばれる中庭の様子。写真に見えるのは 「アーチ門(Main Archway)」の内側から見た建物中庭を囲むこの一連の建物群は、18世紀以降に整備されたジョージ王朝様式の公共建築であり、左側の建物は旧軍事用途、右側の建物はかつての「副王(Lord Lieutenant)」の公邸や政庁部門であった。「アーチ門」と「八角形の時計塔付き建物・Bedford Tower(ベッドフォード・タワー)」。 ダブリン城(Dublin Castle)内の「アーチ門(Main Gate/Civic Sword Gate)」を北側(中庭側)から南方向に見る。この門は、Upper Yard(アッパー・ヤード)と外部をつなぐ主門であり、通常「Main Gate」または「Civic Sword Gate」と呼ばれている と。頂上には剣を掲げた人物像が立っていた。通称:「Civic Sword」像。この像は、明確な歴史的人物ではなく、市民権・統治権の象徴(Civic Authority)としての擬人像と考えられている と。主に以下の特徴があるのだと:右手に掲げた長い剣(または槍):「市民の権利と統治の正当性」を象徴(剣に見えるが、 直線的な棒状で槍とも解釈可能)軍装風の服装: 古代ローマ風の軍装スタイル(市民の守護者、都市の防衛)足元のライオンの頭: 「勇気」「権威」「支配力」の象徴。しばしば国家や権力の 象徴として用いられる頭部の羽根付き兜: 戦士・防衛者の姿を表す(ローマ兵のヘルメット風)設置場所: 旧城門の上、通行者の頭上に立ち、都市と城の「守護者」を 象徴する役割ダブリン城(Dublin Castle)の中心的構造物のひとつ、「Bedford Tower(ベッドフォード塔/ベッドフォード・タワー)」。建設時期: 1750年代(ジョージアン時代)建築様式: ジョージアン様式+ロココ的装飾を一部含む構造: 八角形の塔身に銅葺きのドーム屋根(緑青により緑色)役割: 18世紀当初:城の兵器庫(Armoury)の一部 現在は儀礼的シンボル塔として保存・公開時計: 東西南北四方に時計文字盤を配置、視認性を高めている ・右手前(白い三角破風の建物): State Apartments(ステート・アパートメンツ)の入口がある建物。 かつては貴族や賓客を迎えるレセプション・エリアとして使用された。現在は博物館施設。・右側中央(国旗の掲揚): ガバメント棟(Government Buildings)一部。 国旗(アイルランド三色旗)が掲げられており、迎賓施設の一部でもある。・左奥に伸びる建物 :19世紀以降に再建・改修された行政系建物。同一様式のアーケードが続くことから、 ジョージアン建築の統一感が見られる。・背後に見える塔状の建物: Bedford Tower(時計塔)の一部がクレーンの左下に少しだけ写っていた。こちらは「パレス・ストリート門(Palace Street Gate)」この門は「Palace Street Gate」で、ダブリン城の北東側に位置し、現在のシティ・ホール(Dublin City Hall)近く。門の上には、「正義の女神(Lady Justice)」の像が立っていた。上部には、天秤と剣を持った「正義の女神(Lady Justice)」の像が載っており、西洋では裁判・法・秩序の象徴。他の門と異なり、この女神像は目隠しをしていない(blindfoldなし)点が特徴 と。 ズームして。天秤(Scales): 公平さ、証拠の重さを量る剣(Sword): 正義の厳しさ、裁きの権力目隠し(Blindfold): 偏見のない裁き(※この像は目隠しをしていません)このポスターは、犯人検挙のために発行されたもので、当時の懸賞金£1,000は非常に高額(現在の貨幣価値で約13万ポンド=約2,600万円以上)に相当この案内板は、Bedford Tower(ベッドフォード塔)に関する情報を伝えていた。 「DUBLIN METROPOLITAN POLICE.£1,000 REWARDSTOLENFrom a Safe in the Office of Arms, Dublin Castle, during the past month, supposedby means of a false key.Bedford Tower, 1761 ADThis is the centrepiece of the north side of the Upper Courtyard, which is one of the most beautiful architectural compositions in Dublin.It was occupied successively by the Dean of the Chapel Royal, the Second Secretary, the Master of Ceremonies and the Viceroy’s aide-de-camps. The balcony was used by State musicians.In 1907 the diamond Chains of Office of the Knights of St. Patrick were stolenfrom the ground-floor library of the then Office of Arms.The mystery of what became known as the missing‘Irish Crown Jewels’ has neverbeen solved.This is now the Bedford Hall Suite and Castle Hall conference facilities.【ダブリン首都警察懸賞金 1,000ポンド盗難ダブリン城内の紋章官事務所にある金庫から、過去1か月以内に盗まれた。偽の鍵を使ったと考えられる。ベッドフォード・タワー(1761年建造)ここはアッパー・コートヤード(上の中庭)の北側の中心に位置し、ダブリンでも最も美しい建築構成の一つとされています。この塔は、チャペル・ロイヤル(王室礼拝堂)付きの司祭、第二書記官、儀典長、副王の副官らが順に使用していました。バルコニーは国家音楽家たち(State musicians)が使用していた場所でもあります。1907年には、聖パトリック騎士団(Knights of St. Patrick)のダイヤモンド装飾の官職チェーンが、当時の紋章官事務所(Office of Arms)の1階図書室から盗まれました。この事件は後に「アイルランドの王冠の宝石(Irish Crown Jewels)失踪事件」として知られるようになりましたが、いまだに解決されていません。現在は「ベッドフォード・ホール・スイート(Bedford Hall Suite)」および「キャッスル・ホール(Castle Hall)」という会議施設として使用されています。】「チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)」。ダブリン城構内に位置する、19世紀初頭・1814年に建てられた英国国教会様式の礼拝堂。チャペル・ロイヤルは、ベッドフォード・タワー(Bedford Tower)やステート・アパートメントと並び、アッパー・ヤード(Upper Courtyard)を構成する代表的建築のひとつ。ダブリン城の北東側に位置するCork Hill Gate(コーク・ヒル門)を外側から。外へ出るとすぐに Dublin City Hall(ダブリン市庁舎) や Lord Edward Street に通じていた。「Cork Hill Gate」と「Civic Sword Gate」は、場所は同一ですが、呼び名や意味合いが時代や文脈によって異なるのだと。Cork Hill Gate:現代の公式名称 城の北東側の出入口。 Cork Hill通り(市庁舎 City Hall 側)に面しています。Civic Sword Gate:歴史的・儀礼的文脈での名称(18〜19世紀) ダブリン市長が「市の剣(Civic Sword)」を手にしてこの門を通る儀式に ちなんだ呼び名。王権への忠誠を表す儀式の場でした。この案内板は、ダブリン城(Dublin Castle)の見学ツアーに関する情報、料金を示していた。「WELCOME TO DUBLIN CASTLE,a place where Irish history has been made for over 1,000 years.On this site, kings and queens have held court, Irish presidents have been sworn intooffice and old orders have been swept away through rebellion and revolution.Once the centre of British rule in Ireland, from 1204 to 1922, the Castle is now the setting for some of the Irish nation's most important state ceremonies.Come with us on a tour through time, from a hidden underground excavationto the magnificent Chapel Royal and State Apartments, from British rule toIrish independence and beyond.」 【ダブリン城へようこそここは、アイルランドの歴史が1000年以上にわたり刻まれてきた場所です。この場所では、歴代の王や女王が裁判を開き、アイルランド大統領たちが就任の宣誓を行い、そして旧体制が反乱と革命によって一掃されてきました。ダブリン城は、1204年から1922年までアイルランドにおけるイギリス統治の中心地であり、現在ではアイルランド国家における最も重要な国家儀式の舞台となっています。ぜひ私たちと共に、時を超えたツアーへお出かけください。地下に隠された発掘跡から壮麗なチャペル・ロイヤルや国家の間(State Apartments)へと進み、イギリス支配の時代からアイルランド独立、そしてその先へと、歴史をたどる旅が始まります。】ダブリン城(Dublin Castle)の「State Apartments(国家の間)」の正面玄関この建物は、Upper Courtyard(上の中庭/アッパー・コートヤード)の東側に位置。ダブリン城の見学コースでは最も主要な建物の一つで、次のような重要な部屋へ通じていた。・Throne Room(玉座の間)・St. Patrick’s Hall(セント・パトリックス・ホール)・State Drawing Room(控えの間) などこの建物内の部屋では、かつてイギリス統治下のアイルランド総督(Lord Lieutenant)が国家行事を行っていたほか、現在も大統領就任式などの重要な儀式に使われている。現在はガイドツアーやセルフツアーで内部を見学することができ、アイルランドの政治的・歴史的変遷を伝える展示空間として機能しているとのこと。ダブリン城(Dublin Castle)Upper Courtyard(アッパー・コートヤード/上の中庭)の 北側と東側を。1.中央左側の三角破風(ペディメント)を持つ建物 ・Bedford Hall / Castle Hall(旧Office of Arms)) ・ここはかつてアイルランド騎士団(Knights of St. Patrick)のためのダイヤモンドの 「チェーン・オブ・オフィス(Chains of Office)」が保管されていた場所であり、1907年に アイルランド王冠宝石”(Irish Crown Jewels)が盗難された場所 と。2.右手の角の建物(オレンジ色系の壁、窓が多い) ・State Apartments(ステート・アパートメンツ)への一部 ・議場・レセプション用の国家的施設が入っており、右端に見えるのは「Civic Sword Gate」 (市民の剣の門)。3.最も右端の石造アーチ門: ・Civic Sword Gate または Ship Street Gate ・城の南側へ通じる主要な門。 ・上部に剣を掲げる像(JusticeまたはFortitudeとされる像)が立っているのが特徴。「WelcomeVISITOR OPTIONSA Guided Tour option includes a visit to the Underground Medieval Section, the Chapel Royal and 18th century State Apartments. (1 hour)A Self-Guided visit is available to the State Apartments (30 minutes approximately)ORVisitors can also choose to view the Medieval Section and Chapel Royal by Guided Tourand then self-guide through the State Apartments. (Full Price Ticket applies)」 The rest is omittedOPENING HOURSDaily: 09:45 – 17:45Last admission: 17:15】【ようこそ見学オプション・ガイド付きツアー には、以下の見学が含まれます: 地下の中世セクション、チャペル・ロイヤル(王室礼拝堂)、18世紀のステート・ アパートメント。 所要時間:約1時間・セルフガイド(自由見学) の場合は、ステート・アパートメントの見学のみ(約30分) または・ガイド付きで中世セクションとチャペル・ロイヤルを見学し、その後にセルフガイドで ステート・アパートメントを見学することも可能です(この場合もフルチケット料金が 適用されます)】途中 略・開館時間 毎日:09:45 ~ 17:45 最終入場:17:15】「The State Apartments1680–1830 ADFormerly the residential and ceremonial quarters of the Viceroys (Deputies of the British Monarch) and the Viceregal Court, and the focus of fashionable social life, they are nowthe most important ceremonial rooms in Ireland.The State Apartments include the former State Bedrooms, the Drawing and ThroneRooms, the Portrait Gallery, St. Patrick’s Hall and George’s Hall.St. Patrick’s Hall, the venue for prestigious State functions, including the inauguration ofthe Irish President, was last used for such by British monarchs in 1911.Upon her first state visit to Ireland, Queen Elizabeth II spoke in St. Patrick’s Hall in 2011.」 【ステート・アパートメント(国家公式室)1680~1830年かつては英国王の代理である副王(ヴァイスロイ)とその宮廷が住まいとし、また格式高い社交の中心でもあった空間で、現在ではアイルランドで最も重要な儀式用の部屋群となっています。ステート・アパートメントには、かつての王室用寝室、謁見室、玉座の間、肖像画ギャラリー、セント・パトリックス・ホール、ジョージ・ホールが含まれています。セント・パトリックス・ホールは、アイルランド大統領の就任式など、格式ある国家行事の会場として使用されており、1911年にイギリス王室が最後に使用した記録があります。2011年、エリザベス2世女王が初めてアイルランドを国賓として訪れた際も、このホールでスピーチを行いました。】「クロック・タワー(Clock Tower)」を中心とした「ベッドフォード・タワー(Bedford Tower)」 ダブリン城の「Civic Sword Gate(シヴィック・ソード・ゲート)/Cork Hill Gate」の上に設置されていた「正義の女神(Lady Justice)」を再び。ダブリン城の「Upper Yard(上の中庭)」にある門の上に設置されているこの像は、勇気(Fortitude)または武勇(Valour)を象徴する寓意像(アレゴリカル・スタチュー)。時計塔(Clock Tower)のクローズアップ。Upper Yard(アッパー・ヤード/上の中庭)の北側中央に位置する建物の上部。中世のダブリン城(Medieval Dublin Castle)に関する解説パネル。Medieval Dublin CastleCaisleán Bhaile Átha Cliath sna Meánaoiseanna「This Great Courtyard corresponds closely with the almost rectangular Castle establishedby King John of England in 1204 AD.It became the most important fortification in Ireland and functioned as the seat of English rule and the centre of military, political and social affairs. At various timesit housed the Chief Governors of Ireland, Treasury, War Office, Privy Council, Courts of Justice and the Parliament. It remained in continuous occupation and wasadapted to suit changing requirements, in particular following the great fire of 1684when it became a palace rather than a fortress.It was here, on 16th January 1922, that Michael Collins received the handoveron behalf of the new Irish Government.」 【中世のダブリン城(アイルランド語:Caisleán Bhaile Átha Cliath sna Meánaoiseanna)この「グレート・コートヤード(大中庭)」は、1204年にイングランド王ジョンによって築かれたほぼ長方形の城郭とよく一致しています。この場所は、アイルランドで最も重要な防衛施設となり、イングランド統治の本拠地として機能しました。また、軍事・政治・社会活動の中心地でもありました。さまざまな時期に、アイルランド総督、財務省、陸軍省、枢密院、裁判所、議会がここに置かれました。この城は長年にわたり使用され続け、特に1684年の大火の後は、要塞ではなく宮殿として改修されていきました。ここで1922年1月16日、マイケル・コリンズが新しいアイルランド政府を代表して城の引き渡しを受けました。ステート・アパートメント(State Apartments)は南側の建物群を占め、カンファレンス・センター(Conference Centre)は西側の横棟および北側の棟を、税務署(Revenue Commissioners)は北東隅にある旧アイルランド官房長官室の周辺に配置されています。】「グレート・コートヤード(Great Courtyard)」 を東側から。左側のゴシック建築:チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)・19世紀初頭(1807〜1814年)に建設されたゴシック・リヴァイヴァル様式の礼拝堂。・英国支配時代、アイルランド副王や英国王族の礼拝所として使われました。・建物の外観は、尖塔型の装飾やランセット窓(尖りアーチ窓)などが特徴。現在では展示・コンサート・ガイドツアーの場として使用されることもあります。右側の円塔:レコード・タワー(Record Tower)・13世紀のオリジナルの防御塔で、現存する唯一の中世部分。・ダブリン城がもともと要塞(fortress)だった頃の面影を残す構造。・厚い石壁と小窓、防御用の城壁構造を備えています。名の通り、かつては重要文書の保管所(記録保管塔)として使用されていました。レコード・タワー(Record Tower)・建設年代:1204年以降、13世紀初頭・建築様式:ノルマン様式(円形石造塔、防御構造)・特徴: ・厚い石壁とわずかな小窓(攻撃に備えた設計) ・上部にある櫓(マシュキュレーション風の装飾)は、矢や石を落とす防御構造の名残を 模している ・現在も原形を保つ、ダブリン城で唯一残る中世要塞部分ダブリン城(Dublin Castle)の外壁に設置された案内パネルの一部で、中央右側に見えるのが「レコード・タワー(Record Tower)」「The Record Tower is one of the oldest surviving parts of Dublin Castle, and one of the oldest buildings in the city of Dublin.It was constructed between and 1228 and was the largest of four round towers that formed the corners of the medieval castle of Dublin. Over the centuries, two of thesetowers disappeared entirely while a third, the Bermingham Tower, was rebuilt in the 1770s andcan be seen from the Castle’s Dubh Linn Gardens today.During its 800 years, the Record Tower served as a medieval wardrobe, where garmentsand other precious items were stored. It became a prison in the late 1500s and remainedin use until the 1700s. The upper rooms were refurbished for the storage of public records, giving the tower its name. The base of the tower housed prisoners awaiting execution, including notable Irish rebels Henry and John Sheares in 1798 and Robert Emmet in 1803.Between 1811 and 1813, an extra floor was added to the Tower and it was turned into a repository for important state papers and documents. It was at this time that it becameknown as the 'Record Tower'. It continued to fulfil this purpose up until the early 1990s, when the records were moved to the National Archives of Ireland.In conjunction with Fáilte Ireland, the Office of Public Works has embarked on a majorproject of conservation and redevelopment of the Record Tower. This building has stood as silent witness to the nation's history for 800 years, as it unfolded in and around thehistoric complex of Dublin Castle. It will soon reopen to the public and its fascinating stories told once more.」 【レコード・タワー(記録の塔)は、ダブリン城に現存する最古の部分の一つであり、ダブリン市内でも最も古い建物の一つです。この塔は、1204年から1228年の間に建設され、ダブリンの中世の城を形作っていた四隅の円塔の中で最大のものでした。数世紀のうちに、これら四つの塔のうち二つは完全に失われ、三つ目の塔であるバーミンガム・タワーは1770年代に再建され、現在もダブリン城のダブリン庭園(Dubh Linn Gardens)からその姿を望むことができます。800年の歴史の中で、レコード・タワーはかつて中世の「ワードローブ(衣装部屋)」として使われ、衣類や貴重品の保管場所とされていました。16世紀後半には牢獄として利用されるようになり、18世紀までその用途が続きました。その後、塔の上層部は公文書の保管のために改装され、これにより塔は「レコード・タワー(記録の塔)」と呼ばれるようになります。塔の下層部分には、死刑を待つ囚人たちが収容されており、中には1798年の反乱に関与したヘンリーとジョン・シアーズ兄弟や、1803年の反乱指導者ロバート・エメットといった著名なアイルランド人反逆者たちも含まれていました。1811年から1813年にかけて、塔にはもう一階が増築され、国家の重要な文書や記録の保管庫へと改修されました。この時期に正式に「レコード・タワー」と呼ばれるようになり、1990年代初頭までその役割を果たしていました。その後、保管されていた記録はアイルランド国立公文書館へと移されました。現在、Fáilte Ireland(フォールチャ・アイルランド)との協力のもと、公共事業局(Office of Public Works)は、この塔の保存と再開発のための大規模プロジェクトに着手しています。この建物は、800年にわたり、ダブリン城という歴史的複合施設の中で展開されてきたアイルランドの歴史を静かに見守ってきた証人であり、間もなく再び一般公開され、その魅力的な物語が人々に語られることでしょう。】チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)の側面(北面または西面)を捉えたもの。背景右奥にはレコード・タワー(Record Tower)の一部も見えていた。「The Chapel RoyalThis Chapel was designed by Francis Johnston and opened by Lord Lieutenant Whitworth at Christmas 1814. It replaced an earlier church.It is an exceptional example of Gothic Revival architecture and functioned as the King's Chapel in Ireland as well as that of the Viceroy, his household and staff.The oak galleries and stained-glass chancel windows display the coats of arms of successive Lord Lieutenants and senior Dublin Castle officials, which were painted/carved either during their terms of office or afterwards.The first guest preacher was Thomas Lewis O'Beirne, the Bishop of Meath, and the lastwas the Bishop of Tuam, John Orr, in 1922, just before the Lord Lieutenant of Ireland left.」 【チャペル・ロイヤルこの礼拝堂はフランシス・ジョンストンによって設計され、1814年のクリスマスに総督ホイットワース卿によって開かれました。それ以前の教会に代わるものでした。この建物はゴシック・リヴァイヴァル建築の傑出した例であり、アイルランドにおける国王の礼拝堂として、また総督とその家族や職員の礼拝堂として機能していました。オーク材のギャラリー(回廊)やステンドグラスの内陣窓には、代々のアイルランド総督やダブリン城の高官たちの紋章が描かれ/彫刻されています。これらは彼らの在任中または退任後に設置されました。最初のゲスト説教者は ミーズ司教トマス・ルイス・オバーンであり、最後の説教者は トゥアム司教ジョン・オールで、彼が説教したのは1922年、アイルランド総督が退任する直前のことでした。】「チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)」の正面(西面)入口。建物名:Chapel Royal(王室礼拝堂)竣工年:1814年(クリスマスに落成)設計者:フランシス・ジョンストン(Francis Johnston)建築様式:ゴシック・リヴァイヴァル様式(Gothic Revival)用途:英国統治下におけるアイルランド総督とその家族・職員のための礼拝堂。上部に城郭風のギザギザ(=クレネレーション)が施されており、防御的な中世の城を模したデザイン。「チャペル・ロイヤル(Chapel Royal)」の南面。左端:レコード・タワー(1204〜1228年築)中央〜右:チャペル・ロイヤル(1814年完成)この南面はダブリン城の「中庭(Upper Yard)」側に面していた。ダブリン城(Dublin Castle)の西面を南西方向から。写真中央から左へレコード・タワー(Record Tower) 1204〜1228年頃に建てられた、ダブリン城に現存する最古の部分。中世の円形防御塔で、19世紀には記録文書保管庫に転用され「Record Tower」と呼ばれるようになりました。 チャペル・ロイヤル(Chapel Royal) ネオ・ゴシック様式で1814年に完成した礼拝堂。レコード・タワーの右隣に連なる尖塔のある」壁面群がそれにあたります。 上級裁判所棟(Upper Castle Yardの北西翼) レコード・タワーに接続する形で左側に見える古典主義的ファサードの建物。18世紀以降の再建で、国家の行政機能を担ってきました。ダブリン城(Dublin Castle)の構内案内バナー。Gairdíní Dubh LinnDubh Linn Gardens ダブ・リン庭園(Dubh Linn ガーデンズ)Músaem Chester BeattyChester Beatty Museum チェスター・ビーティー図書館・美術館ダブリン城敷地内で開催されている展覧会の案内看板「The Fine Art of TextileContemporary artists explore the expressive potential of an ancient art formFringe Collective & Guests&The Wild Donegal Tweed ProjectCurated by Judith CunninghamFRINGE COLLECTIVE:Amanda Jane Graham ・ Bernie Leahy ・ Carmel Brennan ・ Jennifer Trouton ・ Sandra DeeryGUEST ARTISTS:Alice Maher ・ Michael Cullen ・ Orla Kaminska ・ Paula Stokes ・ Shani Rhys James06.06.2025 – 24.08.2025Chapel Royal, Dublin CastleMonday to Saturday: 10am – 5pmSunday & Bank Holidays: 1pm – 5pmLast entry: 4:45pmFree Admission」 【テキスタイルの美術— 現代アーティストが、古来の芸術形式の表現的な可能性を探る —フリンジ・コレクティブ & 招待作家たち&ワイルド・ドニゴール・ツイード・プロジェクトキュレーター:ジュディス・カニンガムフリンジ・コレクティブの作家アマンダ・ジェーン・グラハムバーニー・リーヒーカーメル・ブレナンジェニファー・トラウトンサンドラ・ディーリー招待作家アリス・マハーマイケル・カレンオルラ・カミンスカポーラ・ストークスシャーニ・リース・ジェームズ会期: 2025年6月6日~8月24日会場: ダブリン城 チャペル・ロイヤル ・月〜土曜:午前10時〜午後5時 ・日曜・祝日:午後1時〜午後5時 ・最終入場:午後4時45分 ・入場無料】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.11
閲覧総数 604
-
32

アイルランド・ロンドンへの旅(その121): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-4
【海外旅行 ブログリスト】👈️リンクV&A(ヴィクトリア&アルバート博物館/ロンドン)日本展示室に掛けられている浮世絵(木版画)。額装されているのは主に 歌舞伎や武者絵を題材にした錦絵で、江戸末期〜明治期の作品。「Legendary Women in Japanese PrintsWoodblock prints were an affordable art that could be enjoyed by people of all ages,genders and social classes. In the 19th century printed images of illustrious andnotorious women found new popularity in Japan. Going beyond conventional imagesof female beauty, government directives to improve social morality encouraged theportrayal of women of exemplary strength and skill, while literature and drama delighted in villains who were ready to bewitch and betray.These prints show not only the creativity of Japan’s printmakers, but also the many ways in which women came to be depicted: dangerous, talented and powerful.」【浮世絵に描かれた伝説的な女性たち木版画は、あらゆる年齢・性別・社会階層の人々が楽しめる手頃な芸術であった。19世紀になると、日本では高名な女性や悪名高い女性の姿を描いた版画が新たな人気を博した。従来の美人画の枠を超え、社会道徳を向上させるための幕府の指導は、優れた力と技を備えた女性像の描写を奨励した。一方で文学や演劇は、人を惑わし裏切る妖しい悪女像を喜んで描いた。これらの版画は、日本の版画師たちの創造力を示すだけでなく、女性がいかに危険で、才能に満ち、力強い存在として描かれてきたかを物語っている。】 左上:1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより 団扇絵右上:2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図下 :3.安倍泰成、妖狐を退治する図1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより 団扇絵2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図 をネットから。3.安倍泰成、妖狐を退治する図 をネットから。「1. Ono no Komachi, from the series The Thirty-six Immortal Women Poets1843–47Ono no Komachi, who lived during the 9th century, is one of Japan’s most celebratedpoets. Her unparalleled beauty is upheld as a feminine ideal, and her work conveyspassionate intensity. The poem in the cartouche translates to:‘It must have been because I fell asleep tormented by longing that my loverappeared to me. Had I known it was a dream, I should never have awakened.’Utagawa Hiroshige (1797–1858)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.2933-1913」 【1.小野小町《女三十六歌仙》シリーズより1843–47年9世紀に生きた小野小町は、日本で最も著名な歌人の一人である。比類なき美しさは女性の理想像として称えられ、その和歌は情熱的な切実さを伝えている。画中の詞書に記された歌の現代語訳は次の通り:『思ひつつ寝ればや人の見えつらむ 夢と知りせば覚めざらましを』「恋い焦がれて眠りに落ちたために、夢にあなたが現れたのだろう。夢と知っていたなら、決して目覚めたりはしなかったのに。」作者:歌川広重(1797–1858)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.2933-1913】「2. Tomoe Gozen fighting Musashi Saburōemon Arikuni1815–20Tomoe Gozen is Japan’s most famous female warrior. While her historical existence is debated, chronicles of the 12th-century Genpei War describe her commanding troopsand highlight her skill in archery, sword fighting and horse riding. Here, Tomoe is shown preparing to behead her opponent Musashi Saburōemon Arikuni. Prints of famous warriors became increasingly popular in the early 19th century.Katsukawa Shuntei (1770–1820)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.12602-1886」 【2.巴御前、武蔵三郎衛門有国と戦う図1815–20年巴御前は、日本でもっとも有名な女武者である。史実性については議論があるが、12世紀の源平合戦の記録には、彼女が軍勢を指揮し、弓術・剣術・馬術に優れていたことが描かれている。本作では、巴御前が敵将武蔵三郎衛門有国を斬首しようとする場面が表されている。19世紀初頭、有名武将を描いた浮世絵はますます人気を高めていった。作者:勝川春亭(1770–1820)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.12602-1886】「3. Abe no Yasunari exorcises a demon1847–48In Japanese folklore, foxes are shapeshifters with supernatural powers. The mythical Tamamo no Mae was a cruel and ambitious nine-tailed fox. Disguised as a beautifulwoman, she became the mistress of the emperor and caused him to fall ill.When exorcist Abe no Yasunari exposed her true nature with a magic mirror, she wasdefeated and turned to stone.Utagawa Kunisada (1786–1865)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.5558-1886」 【3.安倍泰成、妖狐を退治する図1847–48年日本の伝承において、狐は超自然的な力を持つ変化の存在とされてきた。伝説の玉藻前(たまものまえ)は、残酷で野心的な九尾の狐であり、美しい女性に姿を変えて帝の寵姫となり、病に陥らせた。陰陽師・安倍泰成は、魔法の鏡によってその正体を暴き、彼女は敗北して石に変じたと伝えられる。作者:歌川国貞(1786–1865)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.5558-1886】左:4.神功皇后と武内宿禰(たけうちのすくね)中央左:5.二代目 岩井粂三郎の揚巻役中央右:6.木曽のお六の櫛右下:7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図「4. Empress Jingû and Minister Takeuchi,from the series Banners as Interior Decoration1844–62Before the Imperial Household Law of 1889 prevented female succession, eight ofJapan’s historical rulers were women. Empress Jingû is a mythical figure said tohave led an army into the Korean peninsula in the 3rd century. A shaman and powerful warrior, she is often portrayed carrying a sword, a bow and a quiver of arrows.Utagawa Kunisada (1786–1865)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.1373-1899」 【神功皇后と武内宿禰(たけうちのすくね)《室内装飾の旗(バナー)》シリーズより1844–62年1889年の皇室典範が女性の皇位継承を禁じる以前、日本の歴代統治者のうち8名は女性であった。神功皇后は3世紀に朝鮮半島へ軍を率いたと伝えられる伝説上の人物で、巫女的性格を持つ強力な女武者として、しばしば剣・弓・矢筒を携えた姿で描かれる。作者:歌川国貞(1786–1865)制作地:江戸(東京)技法:木版画(錦絵)所蔵番号:E.1373-1899】 「5. The Actor Iwai Kumesaburō II as Agemaki1824–25Beautiful women from the brothel district were a mainstay of prints, drama andliterature; in reality, they worked under exploitative contracts. In the kabuki theatre, female roles were played by male actors known as onnagata. Here, actorIwai Kumesaburō II plays the formidable Agemaki of the Miura brothel. Perfecting the performance of femininity, onnagata set new standards for female beauty. Some onnagata are recorded as living as women off-stage.Utagawa Toyoshige (1777–1835)Edo (Tokyo)Woodblock PrintMuseum no. E.12645-1886」 【5.二代目 岩井粂三郎の揚巻役1824–25年遊郭の美しい女性たちは、版画・演劇・文学において主要な題材となったが、実際には搾取的な契約の下で働かされていた。歌舞伎では、女性役は女形(おんながた)と呼ばれる男性俳優によって演じられた。ここでは、二代目 岩井粂三郎が三浦屋の花魁揚巻を演じている。女形は女性らしさの演技を完成させることで、新しい「女性美」の基準を作り上げた。中には、舞台を離れても女性として生活したと記録されている俳優もいた。作者:歌川豊重(1777–1835)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.12645-1886】「6.Kiso no Oroku Combs, from the series A Compendium of Famous Artisans1843–47The story of Oroku of Kiso is an example of filial piety and inventiveness. Oroku’s familywas poor, but she supported them by making combs out of a fine-grained local woodwhich, legend says, could cure headaches. In the Edo period (1615–1868), women from working households often contributed to the family business. Handmade combs from the Nagano area are still named after Oroku.Utagawa Hiroshige (1797–1858)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.2918-1913」 【6.木曽のお六の櫛《諸職人尽(しょしょくにんづくし)》シリーズより1843–47年木曽のお六の物語は、孝行心と工夫の好例である。お六の家は貧しかったが、彼女は地元産のきめ細かな木材を用いて櫛を作り、家族を支えた。その櫛は「頭痛を治す」との伝説もあった。江戸時代(1615–1868)には、働く家庭の女性が家業に従事することも多かった。長野地方の手作り櫛の中には、今も「お六櫛」と呼ばれるものがある。作者:歌川広重(1797–1858)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.2918-1913】「7. The manifestation of Benzaiten overwhelming Taira no Kiyomori at Miyajima1862Japan’s two major religions, Shintō and Buddhism, incorporate several female deities.Benzaiten is associated with water, music and eloquence, and is one of the Seven Godsof Good Fortune. This print shows her appearing to the 12th-century military leader Taira no Kiyomori. Kiyomori attributed his success in battle to Benzaiten andbuilt a temple in her honour.Utagawa Yoshitora (active 1830–80)Edo (Tokyo)Woodblock printMuseum no. E.13975-1886」 【7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図1862年日本の二大宗教である神道と仏教には、複数の女神が取り込まれている。弁才天(弁財天)は水・音楽・弁舌に結びつけられ、七福神の一柱でもある。この版画は、12世紀の軍事的指導者平清盛の前に弁才天が現れる場面を描く。清盛は戦での勝利を弁才天の加護と信じ、彼女を祀るために寺を建立した。作者:歌川芳虎(1830–80年頃 活動)制作地:江戸(東京)技法:木版画所蔵番号:E.13975-1886】7.厳島における弁才天の顕現が平清盛を圧倒する図V&A日本展示室(Room 45, Toshiba Gallery of Japanese Art) の一角、浮世絵コーナーとは別のガラスケースを振り返って。左側 上段・蒔絵の小箪笥(黒漆に金蒔絵)・兜(武具の一部、脇に十字架が見えるため「南蛮兜」=キリスト教受容期の影響を示す可能性)左側 下段・蒔絵の箱(文箱か手箱)・日本刀(鞘入り、拵え付)中央〜右側 上段・染付磁器の壺(有田・伊万里焼様式、藍色と赤絵の彩色)・大皿(色絵磁器で人物図)中央 下段・壺型の磁器(肥前磁器)・小型の磁器人形(狛犬のような形)・小皿類「日本の陶磁器・漆工芸の国際交流」 をテーマにした展示で、江戸期の肥前磁器(伊万里焼・柿右衛門様式など)を中心に、西洋輸出向けの豪華な大皿・壺を紹介。・中央 ・大きな色絵大皿(鮮やかな瑠璃地に金彩、中央に人物図、周囲に唐草や花文様) → 有田や伊万里の大皿で、17世紀後半~18世紀輸出磁器の典型。ヨーロッパ向けの 華やかな装飾様式。・左側 ・染付や色絵の壺類 ・着物(黄色地に文様)もケース内に一部展示されているように見えます。・右側 ・青地に赤・金で装飾された壺(花瓶)数点 ・その下には小さな器群ウォーターフォール・オン・カラーズ(水の色彩滝) 千住博。・千住博の代名詞である「滝」シリーズのひとつ。・通常の墨色や単色の滝図とは異なり、多彩な縦色帯が滝となって流れ落ちるように描かれている。・ラベル解説にあったように、コロナ禍の隔離生活中、庭に刻々と変化する色彩を希望の象徴 として捉えた経験が反映されている。・滝の裏側から外を眺めたような感覚を意図しており、自然の力強さと人間の内的感情が 重ね合わされている。・江戸時代の浮世絵・工芸と並べて展示されることで、日本美術が古代から現代まで「自然」を 核心に据え続けてきたことを強調している。「Waterfall on Colors2023Often monumental in scale, Hiroshi Senju’s paintings embrace the overwhelming powerof nature. During the Covid-19 pandemic, when Senju was in isolation at his homein New York, he found hope in the constantly changing colours of his garden. The vibrant hues in this work represent a landscape as seen from behind a waterfall.Hiroshi Senju (born 1958)New York, United StatesColours on paperMuseum no. FE.69-2023」 【ウォーターフォール・オン・カラーズ(水の色彩滝)2023年平面でありながらしばしば記念碑的な規模を持つ千住博の絵画は、自然の圧倒的な力を抱擁するものである。新型コロナウイルスのパンデミックの際、ニューヨークの自宅で隔離生活を送っていた千住は、庭に絶えず変化する色彩に希望を見いだした。本作における鮮やかな色彩は、滝の裏側から眺めた風景を表現している。作家:千住博(1958年生)制作地:アメリカ合衆国 ニューヨーク技法:紙に彩色所蔵番号:FE.69-2023】再び「根付(netsuke)、印籠(inrō)、小型漆器」などの展示コーナーを。展示内容の特徴・左側の棚 ・小型の根付(netsuke)が多数並んでいる。材質は象牙・木・漆・磁器など多様で、 江戸時代の装身具として作られたもの。・中央の展示台 ・印籠(inrō)と緒締め(ojime)、それに付属する根付が組み合わせて展示されている。 ・中央下には大型の漆工芸品(蒔絵の箱)が見える。・右側の棚 ・さらに数多くの根付コレクションが並ぶ。動物・人物・神話モチーフなど。根付 (netsuke) コレクションに近づいて。・材質:象牙、木彫、漆塗り、陶磁器など多様。・形態: ・動物(犬・鼠・兎・鳥など) ・人物(七福神風、力士や僧形) ・神話・民話モチーフ(鬼、霊獣) ・抽象的な小形意匠根付は 印籠や煙草入れを帯から吊るすための留め具として17世紀から発展。江戸時代後期には、実用品であると同時に 高度な彫刻芸術に進化し、武士から町人まで愛好された。19世紀後半、ヨーロッパやアメリカでも「小さな彫刻」として収集熱が高まり、V&Aにも多数が収蔵された。V&Aの所蔵点数は数百点規模におよび、代表的な作例がこのようにまとめて展示されている と。「NetsukeTraditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets. A man would carry everyday items in containers suspended on silk cords fromthe sash (obi) around his waist. The arrangement was held in place by a toggle known as a netsuke. Netsuke were an ideal medium for inventive decoration and developed into miniature works of art. Most of the netsuke displayed here weremade between 1700 and 1870.」 【根付(ねつけ)着物などの伝統的な日本の衣服には、ポケットがなかった。そのため男性は日用品を容器に入れ、腰に巻いた帯(おび)から絹の紐で吊り下げて持ち歩いた。この吊り下げの仕組みを支えた留め具が根付である。根付は創造的な装飾表現の媒体として理想的であり、やがて小さな美術作品へと発展した。ここに展示されている根付の大半は、1700年から1870年の間に制作されたものである。】なんとか解読できました。根付と一緒に展示される 印籠(inrō)とその付属品(緒締め・根付)👈️リンク のコーナー。「SmokingTobacco was introduced to Japan by the Portuguese in the late 16th century.Despite attempts to ban it, smoking became popular among both men and women. Men carried personal smoking sets consisting of a tobacco container, a pipe and a pipe-holder. These were hung from the waist and held in place by toggles callednetsuke. Both men and women used communal smoking cabinets, which were usually made from decorated lacquer. These incorporated small braziersfor burning charcoalwith which to light the pipe.」【喫煙たばこは16世紀後期、ポルトガル人によって日本にもたらされた。禁止の試みがあったにもかかわらず、喫煙は男女ともに広まった。男性は、たばこ入れ・煙管(きせる)・煙管筒からなる個人用喫煙具を持ち歩いた。これらは腰から吊り下げられ、根付(netsuke)と呼ばれる留め具で固定された。また男女ともに、漆塗りで装飾された共用の喫煙棚(喫煙キャビネット)を使用した。そこには小型の火鉢が組み込まれており、炭を焚いて煙管に火を点けることができた。】根付(netsuke)展示ケースの全景。・4段の棚に配置され、合計30点以上の根付が並んでいる。・素材は象牙・木彫・漆など多彩。・上段には細密な象牙彫刻(群像・龍など)や動物形。・下段には黒っぽい木彫の人物や面形。「NetsukeTraditional forms of Japanese dress such as the kimono did not have pockets. A man would carry everyday items in containers suspended on silk cords from the sash (obi) around his waist. The arrangement was held in place by a toggle known as a netsuke. Netsuke were an ideal medium for inventive decoration anddeveloped into miniature works of art. Most of the netsuke displayed here weremade between 1700 and 1870.」【根付(ねつけ)着物など日本の伝統的な衣服にはポケットがなかった。男性は日用品を容器に入れ、帯(おび)から絹の紐で吊るして持ち歩いた。この仕組みを支える留め具が「根付」である。根付は創意工夫を凝らした装飾の媒体として理想的であり、やがて小さな美術品として発展した。ここに展示されている根付の大部分は 1700年から1870年の間に制作されたものである。】着物・衣装コーナーを再び。・左: ・現代的な意匠の浴衣/着物。大きなドットや幾何学模様をパッチワーク的に配置した デザイン。おそらく戦後以降の「モダン着物」か現代アーティストによる作品。・中央: ・黒または濃茶色の羽織/外套。絹地に無地あるいは渋い文様。実用的な装いか、儀礼用。・右: ・茶系の地に虎の刺繍(または友禅染)が大きく入った豪華な打掛または能装束。 力強い図柄から、武家や芝居に関わる衣裳である可能性。「Kimono for MenThe kimono is a garment worn by both men and women. Although sleeve length varies, the basic shape is the same. From the 17th century, male dress was characterised by dark colours and subdued patterns. Yet restrained exteriors often hid flamboyantlinings and under-kimono, a fashion that continued into the 20th century. Today, few men in Japan wear kimono, but in recent years there has been a revival.More and more designers cater for this growing market, giving kimono for men renewed style and panache.」 【男性用の着物着物は男女ともに着用する衣服である。袖の長さには違いがあるが、基本的な形は同じである。17世紀以降、男性の着物は暗い色調や落ち着いた文様が特徴となった。だが、その控えめな外観の下には、華やかな裏地や襦袢(下着の着物)を隠すことが多く、このファッションは20世紀まで続いた。現代では着物を着る男性は日本では少なくなったが、近年は復興の兆しが見られる。ますます多くのデザイナーがこの成長市場に注目し、男性用の着物に新たなスタイルと華やかさを与えている。】「MODERN & CONTEMPORARY(現代日本美術)」展示コーナー。極彩色の現代陶芸作品をアップで。Heart on Wave 川合 一仁。「Studio CraftsToday, many Japanese makers use traditional craft media to create unique works of art.They are supported by an extensive system of art colleges and a well-developed art market in Japan. Numerous craft associations also encourage their activities, as doregular competitive exhibitions. All the objects have been made since 2010, many ofthem very recently.」 【スタジオ・クラフト(現代工芸)今日、多くの日本の作り手は、伝統的な工芸の素材や技法を用いて、独自の芸術作品を創り出している。彼らの活動は、日本の充実した美術大学の制度や発達した美術市場によって支えられている。また、数多くの工芸団体がその活動を奨励しており、定期的に行われる公募展や競技的な展覧会も後押しとなっている。ここに展示されている作品はすべて2010年以降に制作されたもので、多くはごく最近のものである。】「1. ‘Heart on Wave’2023Kawai Kazuhito uses clay to express his nostalgia for 1980s Japan. After an initial biscuit firing, he painstakingly applies dots of glaze to his sculptures to blurthe boundaries between reality and illusion. The porcelain figurine of Ariel fromThe Little Mermaid at the top refers to Tokyo Disneyland’s opening in 1983.It was the first Disneyland outside the United States and symbolises Japan’s economic prominence during Kawai’s childhood.Kawai Kazuhito (born 1984)Kasama, Ibaraki prefectureGlazed stoneware, with a porcelain figureGiven by Hiroyuki Maki / Buffalo Inc.Museum no. FE.61-2024」 【1. Heart on Wave(波の上の心)2023年川合一仁(かわい かずひと)は、1980年代日本への郷愁を粘土で表現している。素焼きの後、彼は現実と幻想の境界を曖昧にするために、丹念に釉薬の点を彫刻表面に施す。作品上部にある『リトル・マーメイド』のアリエルの磁器人形は、1983年に開園した東京ディズニーランドを示唆している。それは米国以外で初めてのディズニーランドであり、川合の幼少期における日本の経済的繁栄を象徴している。川合 一仁(1984年生)茨城県笠間市釉薬を施した炻器、磁器製人形付き寄贈:牧浩之/Buffalo Inc.所蔵番号:FE.61-2024】こちらも「MODERN & CONTEMPORARY(現代・現代美術)」セクション。木工によるデザイン作品(おそらく屏風風の木製パネルや円形構造物)コーナー。中央に展示されているのは、木工によるデザイン作品(おそらく屏風風の木製パネルや円形構造物)で、横には椅子や織物、籠などが並んでいた。・中央の作品:格子状の木製パネルと円形の木工フレーム。伝統的な木工技法を使いながら、 現代的な抽象オブジェとして再構成されたもの。・右側:シンプルな椅子や織物(黒布)など、生活とアートの境界を意識した現代工芸。・左側:陶器・籠・白い紙造形など、素材ごとにまとめられた展示。メモリー 熊井恭子。「Studio CraftsToday, many Japanese makers use traditional craft media to create unique works of art. They are supported by an extensive system of art colleges and a well-developed artmarket in Japan. Numerous craft associations also encourage their activities, as do regular competitive exhibitions.」 【スタジオ工芸今日、多くの日本の作家たちは、伝統的な工芸の媒体を用いて独自の美術作品を制作しています。彼らは、日本における広範な美術大学の制度や発達した美術市場によって支えられています。多くの工芸協会もまたその活動を奨励しており、定期的な競技的展覧会もそれを後押ししています。】「1. 'Memory'2017Kumai Kyoko is an internationally recognised fibre artist. She created this work in remembrance of the Tōhoku Earthquake and Tsunami of2011, which caused over 15,000 deaths. Kumai works mainly with stainless steel wire. Here she has shapedthe wire into a bundle of organic forms. These represent people’s feelings about the unforgettable disaster that has had a lasting impact in Japan.Kumai Kyoko (born 1943)TokyoStainless steel wireGiven anonymouslyMuseum no. FE.57-2023」【1. メモリー2017年熊井恭子は国際的に認められたファイバー・アーティストです。彼女は2011年の東北大震災と津波(死者15,000人以上)を追悼して、この作品を制作しました。熊井は主にステンレススチールワイヤーを用いて制作を行います。ここではワイヤーを有機的な形態の束に組み上げ、それを通じて日本に長く影響を残した忘れがたい災害に対する人々の感情を表現しています。熊井恭子(1943年生まれ)東京素材:ステンレススチールワイヤー寄贈:匿名寄贈館蔵番号:FE.57-2023】「民芸・復興(Discovery and Revival)」セクションの一部で、柳宗悦の民芸運動の文脈で紹介されている作品群。手前の陶磁器・漆器・左:漆塗りの小箪笥(収納箱)・中央:緑釉鉢・黒釉壺・右:青磁花瓶・染付小壺・これらはいずれも江戸~近代にかけての実用品で、民芸運動では「無名の職人による 日常の器こそ美しい」と再評価されました。藍染の幕(のれん/幔幕の類) で、流水に菊の花、さらに上部に家紋が配された文様。「Discovery and RevivalAn interest in folk crafts arose in Japan in the early 20th century as a reaction to rapid industrialisation and urbanisation. Still active today, the Japanese Folk Craftmovement was established in 1926 by the critic and theorist Yanagi Soetsu. He and his followers collected historical folk crafts and founded museums in whichto show them.They also encouraged the preservation of traditional craft techniquesand the making of contemporary work in the style and spirit of historical models.」 【発見と復興20世紀初頭、日本では急速な工業化と都市化への反動として、民芸(フォーククラフト)への関心が高まりました。現在も活動が続いている日本民芸運動は、1926年に批評家で理論家の柳宗悦によって設立されました。柳とその仲間たちは歴史的な民芸品を収集し、それらを展示するための博物館を設立しました。また、伝統的な工芸技術の保存と、歴史的な様式と精神に基づいた現代作品の制作を奨励しました。】「5. Bedding cover1850–1900The traditional Japanese form of bedding is the futon, which comprises a mattressanda cover laid out on the floor. The cover is often decorated. This boldly patterned example was probably part of a bride’s trousseau. It reveals how subtle shading canbe achieved using only one colour. Careful mending is evidence of how greatly suchtextiles were treasured.Cotton with freehand paste-resist dyeing (tsutsugaki)Museum no. T.331-1960」【5. 布団カバー1850~1900年日本の伝統的な寝具の形は布団であり、床の上に敷かれる敷布団と掛け布団から構成されています。掛け布団のカバーはしばしば装飾が施されます。この大胆な文様の例は、おそらく花嫁の嫁入り道具の一部であったと考えられます。ここでは、1色だけを用いても微妙な濃淡表現が可能であることが示されています。丁寧に施された繕いは、このような織物がどれほど大切に扱われていたかを物語っています。素材:木綿、筒描きによる防染染色館蔵番号:T.331-1960】伊万里焼・柿右衛門様式を中心とした日本磁器(17~18世紀)。特にヨーロッパに輸出された伊万里焼や柿右衛門様式のコレクションが多く展示されている と。・上段中央の壺:色絵(赤・緑・青)で花鳥が描かれた柿右衛門様式の磁器。ヨーロッパで 特に人気が高かったスタイル。・上段左右の壺:藍一色で描かれた染付(sometsuke)、竹や花などの文様。・中段中央の大皿:色絵伊万里。赤・青・金を用いた豪華な意匠で、オランダ東インド会社を 通じてヨーロッパへ輸出されたもの。・中段右の像:獅子または象の置物(伊万里の輸出向け磁器)。ヨーロッパで装飾品として 人気を博した。・下段の皿類:いずれも染付や色絵の伊万里磁器。文様は唐草や人物図、風景など。「Porcelain for EuropePorcelain was first made in Japan in the early 17th century at kilns in and around the town of Arita. The earliest pieces were designed for the domestic market. In 1644,following the fall of the Ming dynasty, Chinese porcelain became temporarily unavailable and the Dutch turned to Japan as an alternative source for this highlysought-after commodity. Japan increased its output of porcelain, with much of it being aimed at the export market and often made in shapes copying Europeanceramics.」【ヨーロッパ向けの磁器日本で磁器が初めて作られたのは17世紀初頭、有田の町およびその周辺の窯においてでした。最初の作品は国内市場向けにデザインされていました。1644年、明王朝の滅亡に伴い、中国磁器が一時的に入手できなくなると、オランダ人はこの需要の高い商品を得るために日本を代替供給地としました。日本は磁器の生産量を増加させ、その多くを輸出市場に向け、しばしばヨーロッパの陶磁器の形を模した作品を作りました。】「南蛮貿易・キリシタン関連展示」の一部。展示内容(上段)1.螺鈿細工の小箪笥(cabinet with drawers) 漆塗りに螺鈿や金粉を施した豪華な小型箪笥。ヨーロッパへの輸出品として特に人気が ありました。2.十字架(Christian cross) キリスト教が16世紀に日本へ伝来した証拠の一つ。隠れキリシタンが所持していた可能性が あります。3.南蛮兜(nanban kabuto) ヨーロッパの兜を模した日本製の甲冑。安土桃山時代に西洋甲冑の影響を受けて制作 されました。展示内容(下段)4.蒔絵の箱(lacquer chest/box) 蒔絵技法による装飾箱。西洋の修道院や貴族の館でも保存され、装飾芸術として高く評価 されました。5.火縄銃(hinawajū / matchlock gun) 1543年、ポルトガル人によって種子島に伝来。日本で大量生産され戦国時代の戦術を変革 しました。6.刀剣(sword with European-style hilt) 柄や鍔に西洋風の装飾が施された刀。南蛮貿易期にヨーロッパとの交流を示す作品。】「Europe in JapanThe first Europeans to reach Japan were the Portuguese. Arriving in the early 1540s, they brought with them guns and Christianity. The latter ultimately proved unwelcome. Christianity was banned and the Portuguese were expelled. From 1639 the Dutch were the only Europeans permitted to trade with Japan. They were kept under close scrutinyon Dejima, an artificial island in Nagasaki Bay.Despite the restrictions placed on the Dutch, the goods and scientific knowledgethey brought with them werethe subject of both scholarly enquiry and popular interest.」【日本におけるヨーロッパ日本に最初に到達したヨーロッパ人はポルトガル人でした。1540年代初頭に到来し、鉄砲とキリスト教をもたらしました。しかし後者(キリスト教)は最終的に歓迎されず、禁教とともにポルトガル人は追放されました。1639年以降、日本と交易を許された唯一のヨーロッパ人はオランダ人だけとなりました。彼らは長崎湾の人工島・出島に厳重な監視のもとで滞在しました。制限が課されていたにもかかわらず、オランダ人がもたらした商品や科学的知識は、学問的探求や一般の関心の対象となりました。】 これは「南蛮漆器(Nanban lacquerware)」の代表的な輸出用大型箱(coffer / chest)。「Kamaboko(蒲鉾型)」のドーム状蓋をもつ大型キャビネット。・南蛮漆器は16〜17世紀、日本で欧州輸出を目的として作られた漆工芸品。「Nanban」または 「Namban」と呼ばれます。 ・輸出先に欧州貴族や宣教師が含まれ、キリスト教用具(十字架箱など)や豪華な装飾箱として 使われた例も多い。 ・技法としては、漆(urushi)を塗った上で蒔絵(maki-e:金銀粉などを散らす技法)、 螺鈿(raden:貝殻象嵌)、金銀装飾を組み合わせたもの。 ・形状として、「ドーム状/丸みを帯びた蓋」「箱体」「金属の金具・鍵・取っ手」などを 備えているものが多い。壁掛けではなく、家具・収納箱としての用途。「Lacquer for EuropeWhen the Europeans came to Japan in the mid-1500s, they were immediately by the lustre and decorative brilliance of objects made from lacquer (urushi). The Japanese soon began to produce lacquer items for export copying European shapes. Early pieces were decorated in mother-of-pearl using techniques similarto those found in China, Korea and India. Export lacquer from the 1600s onwards was decorated primarily in gold on black, and featured elaborate pictorial schemes.」【ヨーロッパ向けの漆器1500年代半ばにヨーロッパ人が日本に来航したとき、彼らはすぐに漆(うるし)で作られた器物の光沢と装飾的な華やかさに魅了されました。やがて日本人はヨーロッパの器物の形を写した輸出用漆器を生産するようになります。初期の作品は螺鈿(らでん)で装飾され、中国・朝鮮・インドで見られる技法と類似していました。1600年代以降の輸出漆器は、黒地に金を主体とした装飾が施され、精緻な絵画的意匠が特徴となりました。】「1. The Mazarin Chest1640–43This extremely high-quality lacquer chest is one of the most important pieces of Japanese export lacquer ever made. It is recorded as having been shipped toEurope by the Dutch East India Company in 1643. Its first owner was the French statesman and Catholic cardinal Jules Mazarin. The scenes on the front and sides allude to episodes from classical Japanese literature. The landscape on the lid featurestemple buildings and a castle complex.Probably Kōami workshopKyotoWood covered in black lacquer with decoration in gold and silver lacquer; silver foil and mother-of-pearl inlay; details in gold, silver and shibuichi alloy; gilded and lacqueredmetal fittings; French steel keyMuseum no. 412-1882」【1. マザラン・チェスト(Mazarin Chest)1640–43年この極めて高品質な漆塗りの大形収納箱は、日本の輸出漆器の中でも最も重要な作品のひとつです。1643年にオランダ東インド会社によってヨーロッパへ輸送された記録が残っています。最初の所有者はフランスの政治家でありカトリック枢機卿であったジュール・マザランでした。前面と側面の場面は日本古典文学のエピソードを示唆しており、蓋の風景には寺院建築や城郭群が描かれています。おそらく高阿弥(こうあみ)派工房京都黒漆塗木地に、金・銀漆による加飾、銀箔・螺鈿象嵌を施す。細部は金・銀・四分一合金(しぶいち)を使用。金銀蒔絵の金具を付属し、フランス製鉄鍵を伴う。館蔵番号:412-1882】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.10.27
閲覧総数 390
-
33

六つの村の睦み合い・藤沢市六会地区の歴史-2
以下 表にすべき内容ですが、スペースで文字配置を調整していますが、上手くいきません。ご容赦願います。旧六会駅の写真(1984頃)をネットから。★六会地区 歴史年表-3年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料室町時代応永30年 1423 小栗判官満重、鎌倉への謀反により 常陸の小栗城落城後行方不明となる その後の巷の噂を基に小栗判官と 照手姫の伝説が生まれる 33年 1426 遊行寺焼失 小栗判官満重没すと伝わる永享 5年 1433 関東に大震災発生(九月一六日) 12年 1440 照手姫没すと伝わる長禄 元年 1457 北条早雲、小田原城に入る 👈️明応 4年 1485 北条早雲、小田原城に入る天文 5年 1536 下上棚、白山神社創建し村中安穏を 祈願して鎮守とする元亀 2年 1571 武田信玄、遊行寺に藤沢二〇〇貫、 「貫」とは田地の収橋高を 俣野のうち一〇〇貫の土地を寄進する旨 銭に換算して表したもの 書状を渡す 面積は一定しない 天正 3年 1575 長篠の戦👈️天正10年 1582 武田勝真、識田信長・徳川家康らに 本能寺の変👈️ 天目山で滅ぼされる、その残党多数、 相模国に逃亡★六会地区 歴史年表-4年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料室町時代天正13年 1585 大阪城築城👈️天正18年 1590 徳川家康、江戸城に入る 「禁制」とは、 禁示事項 今田村・西俣野村・円行村は徳川の 領地となる 亀井野村に不動堂建立される 豊臣秀吉、亀井野村雲昌寺に禁制を 揚げる 19年 1591 石川村、旗本中根権六郎貞重の 「知行地」とは 知行地となる 将軍、大名が家臣に俸給 下土棚村、旗本竹尾伝九郎元成の として支配権を与えた土地 知行地となる 「検地」とは土地の測量、 亀井野村、幕府代官彦坂小刑部元正 調査 により検地が施行される 20年 1592 朱印船貿易始まる👈️ 22年 1594 太閤検地施行一反を 300歩とする👈️慶長元年 1596 亀井野村雲昌寺、水害を被り今田村より 現在の藤沢工科高校の 亀井野村に移建されこの時より寺号 グランド裏と境川の間に 雲昌寺と改む👈️ あった。(現在住宅地)慶長 3年 1598 豊臣秀吉没す(六十三才)慶長 5年 1600 西俣野村に浄土宗法王院十王堂 関ヶ原の戦👈️ (通称閻魔堂)建立と伝わる。 8年 1603 徳川家康、江戸幕府を開く 👈️ ★六会地区 歴史年表-5年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代慶長 9年 1604 俣野村に曹洞宗花應院建立と伝わる👈️ 石川村、自性院建立、開基は領主旗本 中根臨太郎、開山は龍見とされる👈️ 19年 1614 大阪冬の陣 👈️ 20年 1615 大阪夏の陣 👈️元和 9年 1623 亀井野村、領主旗本青山氏の減転封 により幕領支配地となる寛永 3年 1626 石川村、領主旗本中根権六郎貞重 により検地施行寛永 4年 1627 亀井野村、松平伊豆守信綱(川越藩)の 領地となる寛永12年 1635 外様大名参勤交代始まる👈️ 寛永14年 1637 島原の乱 👈️寛永16年 1639 亀井野村 、領主松平伊豆守信綱 松平氏の加増転封により亀井野村は 「幕領支配」とは 幕領支配となる 徳川幕府の領地正保元年 1644 円行清雲寺(現存せず)👈️ 雲昌寺住僧の退穏所として同僧により 開山(相模風土記稿) 正保 3年 1647 代官成瀬五左衛門、代官坪井次右衛門に よって俣野村の検地が進められ幕領と なる慶安 4年 1648 亀井野村の雲昌寺、幕府より寺領九石の 朱印状を与えられる万治元年 1658 亀井野村、町野壱岐守幸長の知行地となる 「朱印状」とは徳川幕府の 公認の文書👈️寛文 4年 1664 下土棚村の白山神社、広田主水ほか氏子に より再建される 4年 1665 亀井野村、町野壱岐守幸長により検地施行宝永11年 1671 円行村、代官成瀬五左衛門により検地施行 今田村の一部(幕領)が旗本細井左次衛門勝茂の 知行地との二給支配となる延宝元年 1673 西俣野村 戸数 66戸 人口404名★六会地区 歴史年表-6年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代延宝 2 年 1674 西俣野村、新田検地施行 5年 1677 亀井野村、不動堂に経塚奉納碑が 建立される 8年 1680 猿田彦大神の石廟が御所ヶ谷に 建立される元禄 7年 1694 西俣野村、松波重純(重隆流)の知行地 となる 下土棚村、善然寺炎上元禄10年 1697 西俣野村、旗本長谷川玄通道可の知行地 となる 14年 1701 下土棚村、旗本竹尾氏と遠山久四朗安算の 両氏の知行地 亀井野村、旗本町野氏知行地、上地とされ 上地とは、幕府に理行地 幕領となる を没収されること元禄16年 1703 関東に大地震、津波来襲 (元禄地震)👈️ 浅間山噴火宝永 3年 1706 円行村、畑方名寄帳作成される 名寄帳(なよせちょう)」 円行村、一部が旗本石川織部の知行地となり とは年貢負担ごとにその 二給支配となる 土地の種類、面積、年貫 の額などを書いた帳簿 4年 1707 富士山の噴火により宝永山出現 20cm~30cm の降灰で被害甚大(宝永大噴火)👈️ 亀井野村の幕領の一部が旗本岡部石見守長倶の 知行地となり二給支配となる 岡部石見守長倶により亀井神社の社殿改築 7年 1710 円行村、幕領の一部が旗本石川織部盛行の 知行地となり二給支配となる 自家用酒製造許可 享保元年 1716 徳川吉宗将軍に就任 👈️ 10年 1725 円行村、神明社建立(棟札あり) 16年 1731 境川の洪水により堤防2000間の 所々決壊する ★六会地区 歴史年表-7年号 西暦 六会地区歴史年表 参考資料江戸時代享保17年 1732 水車設置の許可 境川の淵に横土手(御公儀様御役場通り) 構築される元文 5年 1740 石川村、御林帳が作成される延享 2年 1745 石川村、神尾若狭守春英による 新田検地施行 3年 1746 円行村、八幡社に梵鐘が作ら寛延 元年 1748 一人の瞽女が境川に落ちて溺死する 「瞽女(ごぜ)」とは 盲目の女旅芸人宝暦13年 1763 下土棚村、善然寺炎上安永 4年 1775 引地川に船を出す事について大庭 ・ 稲荷・石川・円行・羽鳥・辻堂の 各村より差し支えない旨、幕府に書状を 提出する 下土棚村、白山神社改築天明 2年 1782 石川村、自性院の梵鐘鋳造される 6年 1786 猿田彦大神の石廟、御嶽神社内に移築 7年 1787 円行村、村負担による水田開発を実施 8年 1788 下土棚村の夏刈に四臂(よんび)金剛像供養塔 「四臂金剛像」とは 造立される 四本の腕を持つ金剛像 下土棚村、善然寺火災により本堂・ 寺宝・過去帳焼失する寛政 元年 1789 西俣野村、旗本柳生久通の知行地となる 8年 1796 西俣野村、御嶽神社の梵鐘が鋳造される 文化 3年 1806 石川村、鯖明神社の梵鐘が鋳造される 下土棚村、地頭旗本竹尾氏の知行分幕領となり 代わって松平筑前守地頭となる 「地頭」とは土地の領主 下土棚村の夏刈、柳生五兵衛ほか四名が 八臂青面金剛像庚申供養塔を建立する ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.11
閲覧総数 600
-
34

紅葉狩り(その1):岐阜・大垣・圓興寺(えんこうじ)へ
今年も、旅友のSさん、そして元同僚のNさんと3人で岐阜、愛知の紅葉狩りに行ってきました。高速料金を減らすために高速道路に早朝4時前に入ることを決断し茅ヶ崎に住むSさん宅に3:30に集合。練馬に住むNさんは2時近くに愛車でご自宅を出て茅ヶ崎に向かったのでした。Nさんのワゴン車で無事4時前に圏央道・寒川南から高速に。これにより高速料金の3割引を確保。そして新東名高速を選択し進む。明るくなった豊田JCTを順調に通過。 そして名古屋高速16号線一宮線に入り、名神高速道路と東海北陸自動車道のジャンクションである一宮JCTから名神高速道路で東海北陸道岐阜を目指す。 木曽川を渡っていると前方に伊吹山の姿が。伊吹山は滋賀県米原市、岐阜県揖斐郡揖斐川町、不破郡関ケ原町にまたがる伊吹山地の主峰(最高峰)標高1,377 mの山養老JCTから東海環状線の大垣西インターを目指す。 そして最初の目的地の圓興寺に7:30過ぎに到着。茅ヶ崎から4時間のロングドライブ。円興寺は、岐阜県大垣市にある天台宗の寺院。山号は篠尾山。本尊は木造聖観音菩薩立像(国の重要文化財)。西美濃三十三霊場第三十二札場。 境内は紅葉の名所であり、飛騨・美濃紅葉三十三選に選定されているとのことでこの寺を訪ねたのであった。寺伝によれば、790年(延暦9年)、美濃国不破郡青墓(現大垣市青墓町)の大炊氏に懇願され、最澄が開山したという。1574年(天正2年)、織田信長により焼き討ちにあい、全てを焼失。この際本尊が勝手に動き、石の上へ難を逃れたと。このことから、本尊を石上観音と呼ぶ。1658年(万治元年)に再興され、現在地へ移転する。旧圓興寺かつては金生山山頂に存在していたと。山の中にある旧円興寺跡地には礎石が残り、源朝長(みなもと の ともなが)の墓、源義朝、源義平の供養塔などが残るとのこと。この墓までは時間の関係上行く事を諦める。現在の円興寺には源朝長の位牌や関わる各種遺品があると。 源 朝長は、平安時代末期の武将。源義朝の次男。母は波多野義通の妹。源頼朝・義経の異母兄なのである。相模国松田郷を領して松田冠者(まつだのかじゃ)と号した。また、松田殿とも呼ばれたと。父や兄弟とともに平治の乱で平清盛と戦うが敗れ、父や兄弟とともに東国へ落ちる途中でここ美濃青墓宿で落ち武者狩りに遭い負傷、傷が悪化したため父義朝の手にかかり十六歳を一期に相果てたとのこと。 境内下の紅葉は朝の陽光を浴びて見事なまでに赤くなっていた。 参道脇には自然石に手彫りで刻まれた歌碑が建っていた。人馬の往来の激しい街道筋にはつきものの、遊女や傀儡にまつわる伝承も多く残され、とりわけ平安時代中期から鎌倉時代にかけて流行した「今様」はこの地が発祥と言われているのだと。『遊びをせんとや生まれけむ 戯れせんとや生まれけむ 遊ぶ子どもの声聞けば わが身さえこそ揺るがるれ』(遊びをしようとしてこの世に生まれてきたのであろうか、それとも戯れをしようとして生まれてきたのであろうか。無心に遊ぶ子供たちの声を聞いていると自分の体までが自然と動きだすように思われる)境内を覆う大きな「楠」。 赤と黄色そして白塀が朝の陽光に輝きのBEST MIX。そして鐘楼の姿も。 境内下には一筋の水の流れが。 境内に向かって階段を上る。両脇には南無観世音菩薩と西美濃三十三霊場の幟が。 青空を背景に、緑、黄、赤の輝き。 本堂の向かって右前にある鐘楼。 義朝・義平・朝長の父子と大炊一族の位牌を祀る本堂。円興寺は美濃五山の天台宗寺院。かつては山の上に七堂伽藍を構えた大寺院だったが織田信長の焼き討ちにあいながらも、本尊だけは不思議と難を逃れたと。源氏との関わりが深い寺のようで、源朝長の位牌もあると。その他、本堂には本尊の聖観音の他、如意輪観音、薬師如来、阿弥陀如来、四天王など様々な仏も安置されていると。境内の祠。 「飛騨・美濃紅葉三十三選」にも選ばれている名所だけあって、紅葉が色鮮やかに染まり、季節に彩りを添えてくれていた。侘び寂び豊かな風情のある境内に真っ赤に色づいたモミジを多いに楽しんだのであった。かり
2016.11.26
閲覧総数 202
-
35

湖西市・本興寺(ほんこうじ)を訪ねる(その2)
『旧東海道を歩く』ブログ 目次『奥書院』から『遠州流庭園』を見る。奥に見える屋根は『大書院』の屋根。『大書院』は、二十九世日壇の代の文政10年(1827)、上段・下段の間取りを持つ公式対面の場所として建立された。完成の記念として上段の間には、壁面七面、襖四本の両面の対十五面に、谷文晁によって「紙本水墨四季山水壁画」が描かれ、このことから当寺は「谷文晁寺」とも言われている。下段の間には岸良筆の「双竜争珠の図」や杉戸絵が描かれていた。『谷文晁の間』『文晁之間』本興寺 大書院襖谷文晁筆大書院は、文政十年(1827)建立、上段の間十五畳、中之間十八畳、岸良の間十八畳からなる。『花鳥図屏風』(左)と 『四季山水図』の『秋の景色』(右)『花鳥図屏風』『花鳥図屏風』 1双「作者製作不詳「桃山風金屏風」と伝えられ、群青や緑青豊かん花鳥が描かれている。吉田城久世広之の寄進と伝えられる。」「六曲屏風二帖」=「六曲屏風一双」。『谷 文晁』「詩人谷麓谷の子として、宝暦恰三年(一七六三)江戸に生まれた。画をもって田安侯に仕え、松平定信の庇護を受けた。円山派の波辺南岳、北山寒巌の北画風をはじめ、宋、元、明の諸家の名蹟に学び、あらゆる画風の長をとって折衷した。山水、花鳥、人物など一つとして可ならざるはなく、大和絵までこなし、光琳瓜、四条派瓜をとり入れるなど。その画風は江戸期の全流派を集大成した感じがある。旅を愛し、最も得意とするところは山水画で、北宗的な堅い筆法と南宋的で柔和な空問のひろがりを総合して一派を創始、南北総派の祖といわれる。山水画の中でも三十歳前後の作品は、賦彩や濃淡のニュアンス、構成の新しさにおいて当代無類、江戸第一の大家と目され、この期の作は世に「寛政文晁」と珍重される、学才にもすぐれ「画学大全」、「歴代名工両譜」など著述も多い。晩年には流行におぽれて乱作したが。渡辺華山などを門下に輩出、先近代的な画壇形成に力があった。天保十二年十二月十四日(一八四一)七十八才にて没。大書院壁画谷文晁筆・『冬の景色』(中央)と『其三』(左)『冬の景色』(左)、『晩秋の景色』(右)別の角度から。本興寺 大書院壁画谷文晁筆(其一)・『晩秋の景色』本興寺 大書院壁画谷文晁筆(其二)・『春の景色』。大書院から見る庭園。蘇鉄の後ろにある茅葺屋根の建物は奥書院で、山門同様吉田城からの移築と。本興寺大書院の板戸絵16枚は湖西市指定文化財になっている。『瀧の山水画』・『河寺七瀧之由来』『大衝立 安房宮之図』暁堂筆。阿房宮は秦の始皇帝が即位35年(前212)一万人を入れる客殿を造営したところという。『国指定重要文化財 絹本著色』「法華経曼荼羅図 四幅鎌倉時代の作、法華経の経意を四幅にして絵解きに資する絵図。」そして『大書院 一棟』「文政十年(一八二七)建立、上段の間十五畳、中之間十八畳、岸良の間十八畳から成る。」『国指定重要文化財 絹本著色 法華経曼荼羅 四幅』鎌倉時代の作、法華経を四幅にして絵解きに資する絵図。回廊。回廊を伝って客殿に向かう。庭園は「遠州流庭園」となっており、小堀遠州の作庭と言われています。歌人北原白秋は「水の音ただに一つぞ聞へける その外は何も申すことなし」と詠んだと。四季折々の趣があり、特に春は桜の名所となると。静寂な佇まいが心を癒してくれたのであった。客殿。客殿内に展示されていた駕籠・『網代乗物』網代駕籠(あじろかご)の上等なもの。江戸時代、一定の身分に限り乗用を許された。『客殿内部』。客殿は寛永14年(1637)、十三世日渕の代に建立され、安永2年(1773)二十五世日義の代に再建された。『客殿』より外を見る。『客殿』の『仏間』『ごぼち凧』には本興寺の『寺紋』が描かれていた。昔、遠州・鷲津(湖西市鷲頭)には、『ごぼち凧』という独特の凧があったとのこと。特徴は、凧の足の部分(ひらひらした)がないことと。『十一面観音像』か。御朱印を頂きました。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2020.01.21
閲覧総数 689
-
36

藤沢市内にある『天嶽院』の紅葉を愛でに(その1)
この日は12月16日(金)、この秋も多くの場所の黄葉・紅葉を楽しんで来たが、地元市内にある「天嶽院」の参道の紅葉も美しいので、今年も訪ねたのであった。駐車場に車を駐め、この日も散策開始。「天嶽院」の「山門」は西向きに建っているので、紅葉の参道に陽光が入りこむのは15時前後からが良いのである。この日も15時過ぎに到着。「功徳山 早雲禅寺 天嶽院(てんがくいん)」。所在地:神奈川県藤沢市渡内(わたうち)1丁目1-1頂いたパンフレットから「天嶽院境内案内図」を。「嶽」の字について学びました。 【https://okjiten.jp/kanji342.html】より「---北条早雲公開基の古刹--- 天嶽院」文明年間(1469年 - 1487年)に「虚堂玄白」が草庵を営んだ。この草庵を「玉縄城主、北条綱成」が「北条早雲」を弔うために寺院として創建。虚堂を開山、早雲を開基とした。 天正19年(1591年)11月、徳川家康より朱印地30石を賜る。パンフレットより。「功徳山早雲禅寺 天嶽院」。パンフレットより。「参道」入口の門柱。この門柱に書かれている文字は、一昨年?我が高校時代の友人Sさんから教えて頂きました。「雨花知佛境 流水識禅心」と。「雨花佛境を知り 流水禅心を識る」と。「雨花知佛境」(右側)の門柱。「流水識禅心」(左側)の門柱。「山門」とその前の「寺号標石」と「金剛力士像・仁王像」。寺号標石「天嶽院」。・真言密教の古寺「不動院」から始まる。・治承四年、源頼朝公は、伊豆で挙兵、鎌倉を目指すが、途中「不動院」に立ち寄り 不動明王様に大願成就祈願をされたとの伝説がある。・明応四年、北条早雲公によって伽藍の一宇が創建され、「不動院」を改めて曹洞宗の禅寺とし、 虚堂玄白禅師を迎えて開山。・天正四年、火災に遭い伽藍は全焼。・中興開基 玉縄城主北条綱成公、氏繁公父子。・再中興開基 紀伊大納言徳川光貞卿。・昭和平成伽藍復興。向かって右側の「阿形像」。上半身をあらわにした2体は、筋骨隆々。カッと両の目を見開いて、睨みをきかす迫力たっぷりの表情。左手に長い金剛杵(こんごうしょ)を抱え、右手の五指を下に向けて大きく開いて。長い金剛杵(こんごうしょ)。この金剛杵はあらゆるものを打ち砕けるほど硬く、金剛力士はこれを用いて仏敵や業魔を粉砕するのだと。お顔をズームして。向かって左側の「吽形像」。左手に短い金剛杵(こんごうしょ)を抱え、右手の五指を正面に向けて大きく開いて。短い金剛杵(こんごうしょ)。お顔をズームして。「掲示板」。「利に群がるな 心で集え 目先の欲は 分裂のもと」と。「山門」前から「参道」の「モミジトンネル」を望む。そして「山門」を額縁にして、モミジの参道を。「山門」を潜りながら。モミジのトンネルに続く切石敷の参道....石畳とその左右に敷き詰められた苔の緑が絨毯のようで美しいのであった。「参道」を歩く。モミジのトンネルの中から眺めた石段上の堂宇境内。言葉はいらない!!そして苔生した参道を進み、石段の上から「山門」を振り返る。午後3時の逆光にモモジ葉が輝く。「山門」をズームして。自然石を刳って作ったのであろうか、「手水場」が。「舟落葉」が一枚(ひとひら)。正面に「中雀門」を見る。「不動殿」横の道沿いに建っていた祠。三体の石仏が祠の中に。右の小さな2体の石仏。左の大きな石仏。「鐘楼」。梵鐘をズームして。安永3年(1774年)の銘のある梵鐘。総高161.8センチメートル、口径81.6センチメートル、鐘身111センチメートル。銘文の文中には「功徳山早雲禅寺天嶽院北条氏繁公草創」とある と。「鐘楼」の先、右手にあった「六地蔵」。「庫裡」を横から。この奥に「鶴夢楼」があった。「早雲閣」。「早雲閣」の玄関。「東司」は手洗い。手洗の中の額に書いてあった言葉を紹介させて頂きます。「禪寺では御手洗のことを東司(とうす)と申します。一、佛殿(ぶつでん)ニ、法堂(はっとう)三、僧堂(そうどう)四、庫裡(こり)五、山門(さんもん)六、東司(とうす)七、浴室(よくしつ) 以上が禪寺に於ける七堂伽藍であります。」と。休憩所「黄楳亭」。そして引き返して再び「鐘楼」を見る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.12.27
閲覧総数 735
-
37

藤沢地名の会・サバ神社と湘南台地区(その9):徳本上人名号供養塔~亀井神社
「リサイクルプラザ藤沢」を後にして、この日の最後の訪問場所の「亀井神社」に向かって県道403号線・菖蒲沢戸塚線を進む。「円行新橋」交差点の手前左側にあったのが「徳本上人名号供養塔」。「徳本上人は宝暦8(1758)年紀州で生まれ、文政元(1818)年に61歳で亡くなった念仏行者です。天明4 (1784)年に出家得度し、寛政10(1798)年、4 0歳のときに高野山に登ります。文化11(1814)年5 7歳のとき、京都を発ち増上寺住職典海大僧正の招きで関東に下向し、典海大僧正に出迎えを命じられた鸞洲和尚と藤沢で落ち合います。徳本上人は鸞洲和尚とともに、鎌倉光明寺・英勝寺を経由して、6月12日に江戸に到着し、伝通院内の清浄心院に入られました。・徳本上人名号供養塔(重頭角柱型)安政6 (1859)年7月15日 全高158cm 供養塔のある場所の隣地で旧円行571番地にある町内会館敷地は、昔、曹洞宗の青雲寺の跡地と いわれています。青雲寺は円行山と号し、亀井野村雲昌寺の末寺でした。本尊正観音で 開山浄清は本寺の住僧で正保元(1644)年に本寺を隠居寺として開創しました。 なお、亀井野の雲昌寺には青雲寺から持ち出された相模国準四国8 8ヶ所のうち、4 6番 弘法大師像が移動されています。 鏝頭形円頭 方柱型、塔身高1m、幅37.5㎝、厚35㎝ 銘(塔身正面)南無阿弥陀仏 徳本 花押 (塔身背面)維時 安政六舎己未之天七月十有五日造立(1859年) (台石向って 右面)世話人 亀井野村 七ッ木村 上土棚村 菖 蒲沢村 葛原村 用田村 (台石前面)講中 (台石向って左面)元世話人 石川村 下土棚村 下和田村 遠藤村 (台石背面)長後村 中田村 深谷村 福田村 大庭村 徳本上人の筆になる「南無阿弥陀仏」の名号碑」藤沢市湘南台3-17-17・旧円行字中丸 青雲寺跡。塔身正面:「南無阿弥陀仏 徳本 花押」と。台座:「講中」。台石向って 右面:世話人 亀井野村 七ッ木村 上土棚村 菖 蒲沢村 葛原村 用田村塔身背面:維時 安政六舎己未之天 七月十有五日造立(1859年)台石背面:長後村 中田村 深谷村 福田村 大庭村「徳本上人名号供養塔」の裏にあったのが「藤沢市消防団 第十七分団」。「円行新橋」交差点の先「カメラのキタムラ」の角にも小さな石碑があった。雑草の中に隠れるように。「南無妙法蓮華経 征清戦士忠魂供養塔」。日清戦争(一八九四~一八九五)の戦没者の供養塔。藤沢市湘南台3丁目18−1。「発起人 青木綱治郎」と。そしてこの日の最後に「亀井神社」に到着。藤沢市亀井野553-5(大字亀井野字不動上)。石鳥居手前の左側に社号標石「亀井神社」。境内を見る。亀井野の鎮守亀井神社の祭神は天迦具土神(あめのかぐつちのかみ)です。古くは源義経の家臣である亀井六郎重清により崇敬されました。天正18 (1590)の年に再建され、宝永の頃(1704ー11)この地を知行していた旗本岡部和泉守の崇敬が厚く社殿を改築しました。明治初期の神仏分離までは不動明王を本尊と祀る不動堂もありました。なお、神社周辺は旧小字「不動上」、「不動前」といわれていました。「御由緒」碑が見えた。「御由緒不動ヶ岡の先住民族は此の地に定住すると農地の開拓にのりだした。そして彼等の中には信仰心の厚い者もいた、即ち不動の森を霊山ときめ法華の教を信じた。當時の信仰「の流れとして経文一文字を一石に書き塚を作る之が経塚であり水に因んで不動明王を祭り不動堂を作った。それが不動様の初めである。天正十八年(一五九〇年)。明治のはじめ日本は神国なりと時の政府は各村落に社を作り神を崇拝するように命じた。私達のお不動様も亀井神社と名を改め村の鎮守社となる。祭神 天軻句突知命(あめのかぐつちのみこと、火の神様)當社は源義経四天王亀井六郎の祈願せし所にして天正十八年堂宇建立 宝永年中岡部和泉守崇敬厚く社殿を改築せりと傳う。大正十二年大震災により社殿鳥居等崩壊せしを後日氏子中にて再建す。 平成五年六月之建」右手に社務所と御神木。「身代り不動尊」と両側には真っ赤な「幟」が並ぶ参道を見上げる参道、石段の上に社殿。手前右手に手水舎。龍の吐水口からは清水が。右手池のほとりのに石鳥居は「身代わり不動尊社」の石鳥居か?「玉垣奉賛者御芳名」碑。社殿を斜めから。扁額「亀井神社」。「亀」の字の成り立ちは「かめ」の象形文字から と。下の中央の文字が似ているが、ネットからは上の写真と全く同じものは見つからなかった。知っている方の父親の名前も。社殿の「唐破風」を見上げる。破風とは屋根の裏側に山形に取り付けられた板部およびその付属品の総称。唐破風は破風の一つで破風板の中央部を高く、左右両端に曲線状に反っているもの。主としては玄関、門、向拝などに取り付けられる。唐破風下は白鳥の懸魚であろうか。社殿、本殿を斜めから。「絵馬のいわれ絵馬は本來神の乗り物と考えられた生き馬の代わりに神前に捧げられたものです。のちに祈願文は願い事がかなったお礼として絵馬に画いた板額を奉納する風習が現在に残った物です。」奥にあった石碑。「大震災復興記念碑」。当地は震災当時は高座郡六会(むつあい)村字亀井野でした。1942年(昭和17年)に藤沢市に編入。六会村の死者数は15名でしたが、石碑の記載によると亀井野で14名が亡くなっており、六会村の死者のほとんどは亀井野が占めていたようです。「大震災復興記念碑噫(ああ)大正十ニ年九月一日午前十一時五十八分旻天(びんてん)何ノ□情ゾ此日此時有史未曾有ノ大震火災ニ遭遇ス 天地鳴動□震源地ハ伊豆大島ノ東方四十五里ノ海底ニシテ帝都ヲ囲む東京神奈川静岡千葉埼玉ノ一府四縣ニ及ビ其死者三十萬傷者百余萬家屋被害五十萬戸損害額実ニ一日十五億人類史上凄絶空前ノ大惨事タリ當時摂政デアラセラレタ今上陛下ニハ畏(かしこく)モ御内帑金(ごないどきん)一千萬円ヲ御下賜ニ相成リ山本新内閣を非常徴発令を布キ金九百三十億円ヲ救護費ニ宛テ戒厳令忙裡暴利取締令等三大緊急勅令ヲ布キ罹災民ヲ護セリ 當時亀井野ハ総戸数百八十戸全憒家屋百十三戸半憒家屋六十七戸死者十四名傷者百余名神社佛閣ヲ始メ殆ド全減ス 茲ニ於テ百七十四ノ氏子協力ニヨリ大正十四年十月神社再築ニ着手シ本殿奥行九尺間口九尺拝殿奥行ニ間間ロ三間其他鳥居石垣等総工費五千三百円ヲ以テ大正十五年四月落成ス 爾来辛苦粒々十有余年茲ニ漸ク復興ス 斯ノ苦シキ試線ハ人ヲ偉大ナラシメ大災ノ人生ニ與フル教訓ノ深甚測リ難キモノ存ス 是ヲ永久後世ニ傳フ昭和十年四月建之 長」「拝殿」横から境内を見下ろす。社殿脇には「身代わり不動尊社」見事な唐破風下の懸魚の彫刻がここにも。角度を変えて。こちらの虹梁周辺の彫刻も見事。扁額「不動明王」。境内の池を見下ろす。不動明王と六地蔵尊。「身代り不動尊」への参道と両側には真っ赤な「幟」が。「身代わり不動尊社」の石鳥居を振り返る。そして、この日の行程を全て完了し、ここ「亀井神社」で解散したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・END・・・
2023.07.20
閲覧総数 328
-
38

浅草を歩く(その2):浅草寺-2・浅草寺歴史案内板~宝蔵門~五重塔
さらに「宝蔵門」に向かって進む。左側には、提灯が並ぶ。「浅草寺のご本尊は聖観世音菩薩さまです。お参りの時は、合掌して『南無観世音菩薩』とお唱えしましょう 金龍山浅草寺」 浅草、浅草寺の歴史についての案内板が並んでいた。「一、浅草のあけぼの浅草は利根川・荒川・人間川が運ぶ上砂の堆積によって作られた。古墳時代末期に人々が住んでいたことは、浅草の本坊・伝法院(でんぽういん)に残る「石棺」が示している。この東京湾に面した浅草は、はじめ漁民と農民の暮らす小さな村であったろうが、やがて隅田川舟運による交通の要衝として、また、観音様の示現による霊地として歴史的あけぼのを迎えるのである。二、ご本尊の示現「浅草寺縁起」によれば、推古天皇三十六年(六ニ八)三月十八日の早朝、隅田川(当時の宮戸川)で魚を捕る檜前浜成・竹成(ひのくまのはまなり・たけなり)兄弟が一躰の仏像を感得した。三、浅草寺の草創ニ人の漁師が感得した仏を郷司の土師中知(はじのなかとも。名前には諸説ある)に示した処、聖観世音菩薩像とわかった。そこて、この兄弟は深く帰依し、中知は自ら出家し、自宅を寺に改めて尊像を祀ったのが淺草寺の始まりである。この三人を祀ったのが「浅草神社(三社さま)」である。一方、そうした縁起とは別に、十人の童子がアカザという草で堂を建てたという伝承もあった。四、慈覚大師中興の開山となるご本尊が示現して十七年後、大化元年に勝海上人(しようかいしようにん)が浅草寺に来られ、観音堂を建立し、ご本尊を秘仏と定めた(秘仏の由来)。その後、天安元年(八五七)慈覚大師円仁(えんにん)が比叡山(天台宗の総本山)より来寺し、ご秘仏に代わる本尊ならびに「御影版木(みえいのはんぎ)」を謹刻された。板木が作られたことは、参拝者が増えてきたことを物語るものだろう。五、平公雅堂塔伽藍を建立平安時代中期、天慶五年(九四ニ)安房の国守であった平公雅は京に帰る途次、浅草寺に参拝した。その折、次は武蔵の国守に任ぜられるように祈願した処、その願いがかなったことから、そのお礼に堂塔、伽藍を再建し、田地数百町を寄進したと伝える。その伽藍に法華堂と常行堂の二堂があったことから浅草寺が天台宗の法の流れに属していたことが知られる。」 六、源頼朝の参詣治承四年(一一八○)、源頼朝は平家追討に向かうため浅草の石浜に軍勢を揃えた際、浅草寺に参詣して戦勝を祈った。やがて鎌倉に幕府を開いた後も 信仰を寄せた。鎌倉鶴岡八幡宮造営に際しては浅草から宮大工を召している。このように武将や文人らの信仰を集めた浅草寺の霊名は次第に全国に広まっていった。七、徳川将軍の篤い保護天正十八年(一五九〇)江戸に入った徳川家康は天海僧正の勧めで浅草寺を祈願所と定め、寺領五百石を寄進した。元和四年(一六一ハ)には家康を祀る「東照宮」の造営を認め、随身門(現、ニ天門)も建立されるなど浅草寺への信任は篤かった。寛永年間に観音堂が炎上した際も徳川家光により慶安ニ年(一六四九)再建された。以後、関東大震災にも倒壊せす、国宝観音堂として参詣者を迎えた。だが、昭和ニ〇年の東京大空襲により焼失、現在の本堂は昭和三十三年に再建された。八、江戸時代 境内と奥山の賑わい江戸の繁栄とともに浅草寺の参詣者も増え、やがて江戸随一の盛り場となった。江戸文化の最盛期、境内には百数十の神仏の祠堂(しどう)が建ち並ぶ庶民信仰の聖地となる一方、奥山では松井源水のコマ廻し、長井兵助の居合抜き、のぞきからくり、辻講釈などの大同芸や見世物が参詣者を喜ばせ、水茶屋・揚枝店・矢場(やば)なども立ち並んだのである。さらに春の節分をはじめ季節の行事は大変な賑わいを呈した。明治に人って、浅草寺の境内地は「浅草公園」となり、その第六区が興行街となって日本の映画史、演劇史の上に大きな足跡を残した。同十五年鉄道馬車が開通、同ニ十三年には浅草一帯を眠下に望む「十ニ階」が開業されるなど、浅草は文明開化のさきがけを誇った。九、浅草寺の寺舞(じまい)戦後、東京の復興は浅草の復興でもあり、地元の祈りでもあった。昭和三十三年に本堂が再建されたことを記念して「金龍の舞(きんりゅうのまい)」、昭和三十九年には宝蔵門(旧仁王門)の落慶記念に「福聚宝の舞(ふくじゅたからのまい)、昭和四十三年には東京百年祭を記念して「白鷺の舞(しらさぎのまい)が、それぞれ浅草寺縁起や浅草芝居の由来を受けて創作され、縁日に奉演されている。「浅草名所七福神日本の福神信夘は室町時代に恵比寿・大黒天をはじめとして、商業の盛んな京都方面で発達しました。その数は次第に増えて七福神となりましたが、当初、その顔ぶれは一定ではありませんでした。七という数の根拠には諸説ありますが、一種の聖数と考えられます。京都を中心に盛んとなった七福神信仰ですが、七福神すべてを巡拝する風習は十八世紀末~十九世紀初めに江戸で成立しました。江戸名所七福神も江戸では有名でしたが戦後に中断し、一九七七年(昭和五十ニ年)に再興されて今日に至るものです。なお、福神の働き(ご利益)は次の通りです。恵比寿 漁労・商売の守護。大黒天 五穀豊穰(食物) 出世を司る神。弁財天 知恵・音楽・財福を司る神。毘沙門天 四天王の一つ。 財宝・勇気・決断を司る神。福禄寿 幸運・生活の安定 長寿を司る神。寿老人 延命長寿を司る神。福禄寿 と同一とする場合もある。布袋尊 弥勒菩謹の化身とされる人神。 福徳・家庭円満を司る神。浅草名所七福神 浅草寺 大黒天 浅草神社 恵比須神 待乳山聖天 毘沙門天 今戸神社 福禄寿 不動院 布袋尊 石浜神社 寿老神 鷲神社 寿老人 吉原神社 弁財天 矢先神社 福禄寿」 そして正面に「宝蔵門」が大きく見えて来た。「浅草観光案内図」と「浅草の観光行事」 。「宝蔵門」。「宝蔵門 台東区浅草二丁目三番一号 浅草寺宝蔵門は、大谷米太郎 の寄進で、昭和三十九年に浅草寺宝物の収蔵庫を兼ねた山門として建てられた。鉄筋コンクリート造で重層の楼門である。外観は旧山門と同様に、江戸時代初期の様式を基準に設計されている。高さ二十一・七メートルある。下層の正面左右には、錦戸新観、村岡久作の制作による、木造仁王像を安置している。浅草寺山門の創建は、「浅草寺縁起」によると、天慶五年(九四二)、平公雅によると伝える。仁王像を安置していることから仁王門とも呼ばれる。その後、焼失と再建をくり返し、慶安二年(一六四九)に再建された山門は、入母屋造、本瓦葺の楼門で、昭和二十年の空襲 で焼失するまでその威容を誇っていた。 平成十八年三月 台東区教育委員会」 雷門をくぐり、人通り賑やかな仲見世を歩いてゆくと、前方に堂々たる朱塗りの楼門が参拝者を迎える。浅草寺山門の宝蔵門である。門は初層が五間で、両端の二間には仁王像を奉安し、中央の三間が通行のために開口している。仁王像が安置されていることからもわかるように、この門はもともと仁王門と呼ばれていた。『浅草寺縁起』によれば、平公雅が天慶5年(942)に武蔵守に補任され、その祈願成就の御礼として仁王門を建立したのが創建という。以来、数度の焼失と再建ののち、徳川家光の寄進により慶安2年(1649)に落慶した仁王門が、昭和20年まで諸人を迎えていた。今に伝わる錦絵の数々に描かれた仁王門は慶安の門である。昭和20年(1945)、仁王門は東京大空襲により観音堂・五重塔・経蔵などとともに焼失する。昭和39年(1964)に大谷重工業社長・大谷米太郎ご夫妻の寄進により、鉄筋コンクリート造り、本瓦葺きで再建された。経蔵を兼ねて伝来の経典や寺宝を収蔵することから、仁王門から宝蔵門と改称された。宝蔵門に収蔵されている経典とは、「元版一切経(国の重要文化財)」である。もとは鎌倉の鶴岡八幡宮に収蔵されていたものであるが、明治の神仏分離の際にあわや焼却処分されるところを、浅草寺に深く帰依していた尼僧の貞運尼が買い取り、浅草寺に奉納したという由緒をもつ。この「元版一切経」を鎌倉から浅草まで運ぶ際に助力したのが、町火消し十番組の組頭・新門辰五郎である。境内にあった新門の門番を務めたことから新門と名乗り、安政年間(1854~60)に浅草寺の経蔵を寄進している。戦災で経蔵は焼失したが「元版一切経」は疎開しており無事だった。宝蔵門は篤信の人びとに守られた宝物とともに、多くの参拝者の安寧を見守っている。「浅草寺」額京都・曼殊院門跡の良尚法親王筆の模写 と。「小舟町」と書かれた「大提灯」。高さ 3.75m・幅 2.7m、重さ 450kg。 日本橋小舟町奉賛会より平成26年(2014)10月奉納掛け換え(4回目)。「吊灯籠」 高さ 2.75m、重さ 1.000kg 銅製。 魚がし講より昭和63年(1988)10月奉納掛け換え(2回目)仁王尊像(木曾檜造り 重さ 各約1,000kg)「阿形像」 ネットから。「仁王様(阿行)昭和39年(1964)に、現在の宝蔵門の再建に際し、仏師の錦戸新親氏によって制作された。総高5. 4 5メートル、重さ約10 0 0キログラム、木會檜造りである。仁王さまのご縁日は8日。身体健全、災厄除けの守護神であり、所持している金剛杵は、すべての煩悩を破る菩提心の象徴である。この仁工さまは、宝蔵門にあって、日々参詣諸人をお迎えし、人々をお守りしている。」 「仁王様(吽行)ネットから。「仁王様(吽行)昭和39年(1964)に、現在の宝蔵門の再建に際し、仏師の村岡久作氏によって制作された。総高5. 4 5メートル、重さ約1000キログラム、木會檜造りである。仁王さまのご縁日は8日。身体健全、災厄除けの守護神であり、所持している金剛杵は、すべての煩悩を破る菩提心の象徴である。この仁工さまは、宝蔵門にあって、日々参詣諸人をお迎えし、人々をお守りしている。」 「五重塔」 日本で最も有名な五重塔のひとつが、浅草寺の境内にある五重塔。その高さは約53.32mで、ビルでいうと15~20階だてに相当します。浅草の五重塔は西暦942年に建てられたと言われています。江戸時代には寛永寺、池上本門寺、芝増上寺にある五重塔と合わせて「江戸四塔」と呼ばれ親しまれてきましたが、太平洋戦争の時の空襲で一度焼失してしまいました。いまの五重塔は焼失した後に場所を改めて建て直したものです。現在元の場所には石碑が建っています。五重塔の先端にあるのは「相輪」と呼ばれる金属製の装飾。これは、露盤、伏鉢、請花、九輪、水煙、竜舎、宝珠などが組み合わさったもので、上部に位置する「宝珠」が最先端にある。「相輪」案内図。 上から順に宝珠:仏舎利(釈迦の骨)が納められる。竜舎:奈良時代から平安時代の高貴な者の乗り物水煙:火炎の透し彫り。火は、木造の建築物が火災に繋がるため嫌われ、水煙と呼ばれる。 お釈迦様が火葬されたことをあらわす。九輪(宝輪):五智如来と四菩薩を表す。9つの輪からなる[注釈 1]。受花(請花):飾り台。蓮華の花。伏鉢(覆鉢):鉢を伏せた形をした盛り土形の墓、ストゥーパ形。お墓を表している。露盤:伏鉢の土台。宝珠は仏舎利が納められるため、最も重要とされる。 なお、中心を貫く棒は「擦」(または「刹管」)と呼ばれる。 また、仏舎利は塔の中に安置されていることもある。そしてこちらは「東京スカイツリー」の最上部をズームして。 正面に「浅草寺 本堂」。 「宝蔵門」を「本堂」側から見る。 「大わらじ高さ 4.5m・幅 1.5m、重さ 500kg、藁 2,500kg使用。山形県村山市有志より平成30年(2018)10月奉納〔昭和16年(1941)の初回以来、8回目〕わらじは仁王さまのお力を表し、「この様な大きなわらじを履くものがこの寺を守っているのか」と驚いて魔が去っていくといわれている。」 右側。左側。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.05.13
閲覧総数 193
-
39

アイルランド・ロンドンへの旅(その71):Dublin市内散策(10/)・Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)1/4
「Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)」が前方に。・写真左の大きな建物: → クライストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)本体。 アイルランド国教会(アングリカン)のダブリン主教座聖堂であり、12世紀にノルマン人に よって建てられたロマネスク様式とゴシック様式が融合した建築。・中央奥のアーチ状の通路: → 通称「シナジー・ブリッジ(Synod Hall Bridge)」。 このアーチ橋は大聖堂と向かいの建物(旧シナジーホール)をつないでおり、博物館展示や 管理施設として使われている建物への連絡通路となっています。・右の建物(やや奥): → 元々はシナジーホール(Synod Hall)で、現在は「Dublinia(ダブリニア)博物館」という バイキングと中世ダブリンの体験型歴史博物館として利用されています。ズームして。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) ・創建:1030年頃(ハムダール=ヴァイキング王による) ・改築:1172年頃、ノルマン人指導者ストロングボウ(Richard de Clare)による拡張。 ・特徴:地下納骨堂(クリプト)、ストロングボウの墓、バイキングとノルマンの融合した 建築、合唱席など。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) の側面(南側)をズームして。手前中央の突き出た部分をズームして。これは大聖堂本体から突き出した小聖堂(チャペル)または構造上の付属室。特徴は以下の通りと: 特徴 解説アーチ状のドア ロマネスク様式を彷彿とさせる円形アーチの木製扉。三連アーチの開口部 中央部に見られる3つの小アーチは、中世風の窓あるいは装飾的要素。丸窓(円形の開口) 光を取り入れるための開口部で、象徴的な配置。装飾のない壁面 石材の質感がそのまま残され、修道院風の質素な趣を見せています。この突き出た構造はしばしば「アプス(後陣)」や「チャプター・ハウス(参事会室)」などと解釈されることがありますが、クライストチャーチ大聖堂の場合、地下納骨堂(Crypt)や礼拝室に通じる部分とも考えられます と。移動して。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) の「西面(West Side)。近づいて「西正面(West Front)」を 。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂) に隣接する シナーズ通り(Synod Hall / Synod House) と、それをつなぐストーンブリッジ(空中廊下/連絡橋) を西側(Lord Edward Street 方面)から見上げて。ストーンブリッジ(空中廊下/連絡橋)をズームして。さらに、クライストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)と、隣接するSynod Hall(現 Dublinia 博物館)とを繋ぐ有名な連絡橋(Sky Bridge / Footbridge)。◆アーチ部分 丸みを帯びたローマンアーチ(ロマネスク様式)で構成。重厚な石造りで、 街道をまたいでいます。◆ 窓(開口部) 小さな円形(オクルス)や狭長の尖塔アーチ窓(ランセット窓)など、 中世風の意匠が並びます。小さなバラ窓のような構成です。◆ 突き出し部 左上部の三角屋根の小尖塔(ペディメント付き)は、橋の頂部装飾です。 装飾性と垂直性を強調しています。◆背後の建物 ネオ・ゴシック様式の建物で、かつて教会会議場だったものを (Synod Hall) 改修し、現在はDublinia(中世・ヴァイキング博物館)として公開されて います。窓や石積みの細部に注目すると、現代的な復古デザインであることが わかります。◆細部の意匠 開口部の周囲には、装飾的な柱頭・小アーチトリミングが施されており、 建築全体に「教会的・修道院的な荘厳さ」を与えています。東側に隣接するSynod Hall(シノッド・ホール)を正面から。現在この建物は、Dublinia(ダブリニア)ヴァイキング&中世博物館として活用されている と。観光案内サインポスト。アイルランド語(Gaeilge)と英語の併記で、主要な観光スポットや文化施設への徒歩ルートが示されていた。Christ Church Cathedral, Dublin(ダブリン・クライストチャーチ大聖堂)を南側から。・創建:約1030年(シトリック・シルケンベアード王による)・様式:ノルマン様式とゴシック様式の融合・管轄:アイルランド国教会(Church of Ireland)・特徴:大規模な地下納骨堂(クリプト)、美しいステンドグラス、ネオゴシック再建(19世紀)・中央奥の高い塔:鐘楼(bell tower)、建物のランドマーク的存在。・左側のファサード:尖頭アーチ窓や控え壁(バットレス)が並ぶ典型的なネオゴシック。・右側の八角塔屋根の部分:聖具室(sacristy)や礼拝室が含まれます。・手前の旗: ・青い旗:EU旗 ・緑白オレンジ:アイルランド国旗 ・虹旗:LGBTQ+フレンドリーな姿勢の表明と思われます。Christ Church Cathedral(クライストチャーチ大聖堂)の鐘楼(bell tower)をズームして。形状:四角形の堅牢な石造り塔。上部には尖塔(スパイア)が載る。屋根:ピラミッド型のスレート屋根。塔の四隅にはミニタレット(小塔)付き。窓:各面に尖頭アーチの2連ランセット窓。鐘音を通すための開口部(ルーバー)付き。装飾:クレネレーション(城のようなギザギザの胸壁)あり。中世の要塞風。上部の十字架:屋根の頂点にはクロス(キリスト教の象徴)が立っている。立体模型(ブロンズ・モデル)。視覚障害者の方にも触って構造を理解してもらう目的で設置されており、1870年ごろの姿を再現している と。アルファベットと対応建物名のプレートが手前に設置されており、視覚障害者が指で個別確認可能。クライストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral Dublin) のオーディオガイド・ツアーの内容を紹介するもの。「Explore three sides of the cathedral’s amazing story with our audio guideChrist Church Cathedral Dublin・Power and Politics・Christ Church and The City・Music and Spirituality」【オーディオガイドで巡る、大聖堂の驚くべき3つの物語クライストチャーチ大聖堂(ダブリン)・権力と政治・クライストチャーチと都市(ダブリン)との関係・音楽と霊性(信仰)】歴史的・社会的・宗教的コンテクストの中で大聖堂を体験できるように工夫されているのであった。Christ Church Cathedral(クライスト・チャーチ大聖堂)の南正面(South Front)。・左側に長く続く側廊(南壁)があり、ランセット窓が連なる構造。・写真中央の突き出た部分が南翼廊の正面入口(South Transept Entrance)。・四角形の塔が背後に確認でき、これは建物の交差部上にある中央塔(Crossing Tower)。 上部にはバトルメント(城郭風の縁飾り)が施され、尖塔(スパイア)が。南側外壁(南面 / South Elevation)を見る。・右端にあるファサードには正面玄関とバラ窓(rose window)が見えた。・中央の高い塔(中央塔/Central Tower)は、教会の交差部(transeptとnaveの交点)に位置。・左に続く長い部分が身廊で、写真の左端方向が西側。南正面の中央部分、すなわち南トランセプト(南翼廊)の外壁を真正面から。・中央の円形窓はバラ窓は花弁状に放射線状の石材トレーサリーを持つゴシック様式。・中央塔(bell tower)は背後に立ち上がる四角形平面の鐘楼で、クライストチャーチの ランドマーク的存在。ロマネスク〜初期ゴシックの堅牢なデザインが踏襲。・窓(ランセット・ウィンドウ) 上層の3つの細長いランセット窓は、内部のステンドグラス窓(主題:キリストと美徳)と 一致。 特に下層の中央の2列の窓はバラ窓直下に位置し、この内部にも大きなステンドグラスが はめ込まれていることが写真から確認できるのであった。移動して、南東方向から北西方向を見る。写真右側がアプス(内陣・祭壇方向=東側)。アプスとは、教会堂の奥、祭壇がある半円形の部分を指す言葉。ズームして。南東側の庭園にあったのが、ティモシー・シュマルツ(Timothy Schmalz)による「ホームレスのイエス像(Homeless Jesus)」。この像は以下のようなテーマを象徴しているのだと。・貧者・弱者への共感と連帯・「あなたがたが最も小さな者にしたことは、わたしにしたことだ」(マタイ福音書25章40節) という聖句の視覚的表現・現代における社会的無関心に対する挑戦 南側の側廊壁には連続する尖頭アーチ窓と扶壁(フライング バットレス)が並ぶ。引き返して、大聖堂南側の中庭(南ポーチとチャプター・ハウスの前)から南面の左側方向を見る。正面にバラ窓が2つ。3種類の旗が。左:レインボーフラッグ(プライド旗)中央:アイルランド国旗(Irish Tricolour)右:欧州連合(EU)旗左:レインボーフラッグ(プライド旗)・意味:LGBTQ+の尊厳、多様性、平等、社会的受容を象徴する旗。・詳細:もともとは6色が基本(赤、橙、黄、緑、青、紫)ですが、現在はさらに多様性を示す 新デザイン(Progress Pride Flagなど)も使われます。・備考:教会や公共機関が掲揚することで、LGBTQ+コミュニティへの包摂的姿勢を示します。なぜ教会でプライド旗が掲揚されているのか?クリストチャーチ大聖堂(Christ Church Cathedral)は、アイルランド国教会(聖公会系)に属しており、近年では多様性と包摂性を掲げる姿勢を示しています。このような背景から、プライド月間(6月)や特定のイベント時に、プライド旗を掲げることが一般化しているとのこと。中央:アイルランド国旗(Irish Tricolour)・構成:縦三色(緑・白・オレンジ)・意味: ・緑:カトリック系(ナショナリスト) ・オレンジ:プロテスタント系(ユニオニスト) ・白:平和と和解 ・公式採用:1937年(アイルランド憲法下)右:欧州連合(EU)旗・構成:青地に12の金色の星(円形)・意味:・星の数は「完璧」や「完全性」の象徴(加盟国の数とは無関係)・円形は「団結と調和」を表現・アイルランドはEU加盟国(1973年加盟)観光案内標識を。英語とアイルランド語(アイルランド・ゲール語)の併記。・Halla na Cathrach City Hall 市庁舎・Caisleán Bhaile Átha Cliath Dublin Castle ダブリン城・Barra an Teampaill Temple Bar テンプル・バー(文化・飲食街)・Coláiste na Tríonóide Triity College トリニティ・カレッジ(大学)・Músaem Uisce Beatha ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.09.07
閲覧総数 480
-
40
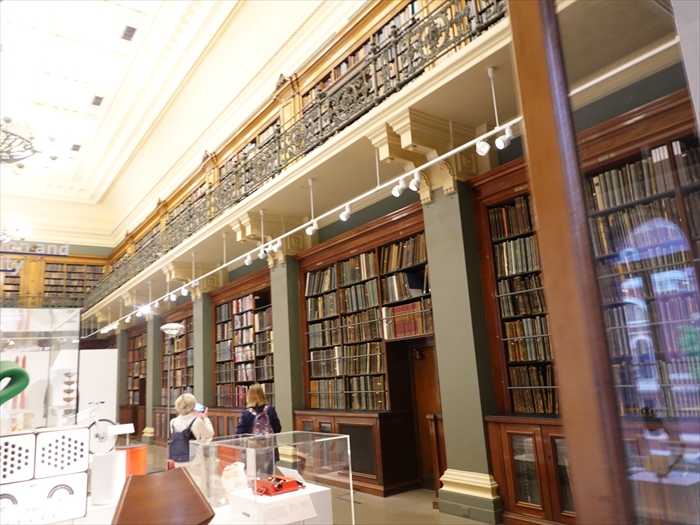
アイルランド・ロンドンへの旅(その126): ロンドン散策記・Victoria and Albert Museum・ヴィクトリア&アルバート博物館-9
【海外旅行 ブログリスト】👈リンク部屋の全景をネットの写真から。Design 1900–Nowギャラリーの長い通路・Room NO 76.V&A の National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー) の書庫が見える一角二層吹き抜けに鋳鉄の手すり、壁一面の木製書架、天窓からの採光という内装が決め手。手前にあるプロダクトの展示ケースは、ギャラリー側の通路に置かれており、ガラス越しに実際のライブラリーの本棚が見える構成になっていた。中の書籍は本物で、閲覧は登録制(閲覧室は別室)とのこと。・英国随一の装飾美術・デザイン専門図書館。展覧会図録、装飾美術・建築・ファッション・ 写真などの大型資料や雑誌合本を所蔵。・書庫はクローズドスタック(直接は取れず、請求して閲覧)。閲覧室の参考棚のみ開架。利用の基本(実務メモ)・無料で利用可。ただし資料の閲覧は利用者登録(身分証)が必要。・事前にオンラインで請求→来館時に閲覧、の流れが標準。・閲覧室では通常鉛筆のみ使用、飲食不可。資料撮影は可否が分かれるので 係員の指示に従う。・落下防止バー:各段の前面に通る金属バー。地震・人の動き・清掃時に閲覧ゾーン側への 落下防止&整列保持の役割。 必要に応じて上げ下げして本を出し入れしする と。・下段のガラス扉:大型判(フォリオサイズ)の画集・製図集・製本済み雑誌などを収納。 湿度や埃から守るためガラス扉付き と。「Design 1900–Now」ギャラリー側通路から見た、National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー)書庫の外壁。右手の背の高い木製書架は図書館の実物の書庫、左手の白い展示ケースと“Sustainability and Subversion”のサインはデザイン・ギャラリーのテーマ展示の一部。二層構成になっており、上階は鋳鉄手すりの回廊、天井からシャンデリア。「Design 1900–Now」ギャラリー通路から見た、National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー)書庫の外壁。右側:John Madejski Garden左側:National Art Library(ナショナル・アート・ライブラリー)の入口 金文字「NATIONAL ART LIBRARY」扉はこの左壁沿い(写真フレーム外)にあった。前方:西(Room 74 側)Level2のMAP。■がRoom NO 76そしてこれが金文字「NATIONAL ART LIBRARY」の入口。近づいて。Art Library(閲覧室)への入口。Art Library(閲覧室)内部の写真。・まっすぐ先のガラスの両開き扉が、外の Design 1900–Now(Room 76)通路へ戻る出入口。・右側のアーチ窓は 南側(外光が入る窓列)。・左側の高い本棚の壁が 北面で、この壁の向こう側が先ほど歩かれた展示通路(Room 76)。・机の並びや緑色シェードのスタンドは、閲覧室の標準レイアウト。ズームして。・机が整然と並び、緑のスタンドランプと胸像(バスト)が列状に配置されているのが 閲覧室の標準レイアウト。・画面一面に見える高い本棚の壁は、歩いた Design 1900–Now(Room 76)の通路と 背中合わせの“北面”。・金文字「NATIONAL ART LIBRARY」の入口は、この本棚の並ぶ北面の中央付近 (写真の右奥方向にあたる位置)にあった。 扉を出ると、先ほどの展示通路(Room 76)に出た。中庭南辺の通路(Room 76)から東寄り(No.25 付近)の階段/エレベーターで Level 3 へ上がり、Rooms 118–125 の表示に従って進む。V&A の “BRITAIN (1760–1900)”(British Galleries)への案内サイン。表示の 118–…(~125c など) は該当する部屋番号を示す。産業革命期からヴィクトリア時代までの英国の家具・銀器・陶磁・室内装飾などを展示。このケースは、V&Aの英国ギャラリーで紹介されているVasemania(花瓶熱)を一望できる展示。正面から。18~19世紀の新古典主義期、古代ギリシャ・ローマの「壺(vase)」の形や装飾が大流行し、実用品や室内装飾までをも壺風にしてしまった――という現象を、実物で示していたのだ。・中央の大壺:古代ギリシャのクラテル(混酒壺)型。黒地に赤い人物像の帯状画 (赤絵式”を思わせる意匠)で、18~19世紀の工房が古典壺を写したり 再解釈して作ったもの。 暖炉やコンソール上に飾る「ガーニチャー(壺飾りの組)」の主役であった。・上段の小ぶりの壺群:取っ手付きのアンフォラやオイノコエ型など、古典形のバリエーション。 素材は磁器・ストーンウェア・ガラスなどさまざま。・右下の金色の燭台:よく見ると胴体が「壺の胴」形。花瓶のフォルムが燭台・茶筒・香水瓶 などの実用品にも転用されたことを示す好例です。・左右に見える色ガラスの器:多層ガラスを削って文様を出すカメオガラスや、色被せ ガラスに金彩を施したものなど、壺モチーフがガラスにも波及 したことが分かります。・背面の赤×金の額装パネル:メダリオン(円形レリーフ)や古典主題の装飾で、壺と同じ 古代趣味を室内全体の意匠に広げた例。 ・18世紀後半、ウェッジウッド(Josiah Wedgwood)が壺形の器を大量に生産し、彼自身が この流行をvasemania(花瓶狂)と呼んだ。 ・ポンペイやヘルクラネウムの発掘、ギリシャ壺の版画集の出版(コレクターのハミルトン卿 など)がデザイン資料となり、陶磁器・金工・ガラス・家具の意匠にまで壺の語彙が 広がった。「VasemaniaLabels for the objects in this case are in a booklet to the right of the case.Vases were a very important element of the Neo-classical style. The pottery manufacturer Josiah Wedgwood, who could hardly make them fast enough, spoke of“vasemania”. They appeared as three-dimensional objects and as decorative motifs. Vase forms also influenced the shape of practical items of all sorts, from teacanistersto candlesticks. Designers plundered sources far and wide for new designs, from Greekpottery to 16th- and 17th-century prints.」【ヴェーズマニアこのケース内の各作品ラベルは、ケース右手に置かれた冊子にあります。花瓶は新古典主義様式において非常に重要な要素でした。陶磁器メーカーのジョサイア・ウェッジウッドは、需要に追いつけないほどで、この現象を「ヴェーズマニア」と呼びました。花瓶は立体作品としてだけでなく、装飾モチーフとしても登場しました。さらに花瓶の形は、茶葉用キャニスターから燭台に至るまで、実用品の造形にも影響を与えました。デザイナーたちは新しい意匠を求め、ギリシャの陶器から16~17世紀の版画にいたるまで、広範な資料を貪欲に参照しました。】国王のゴールド・ステート・コーチの模型。・ロココ~新古典主義的な重厚な鍍金装飾に、四隅や側面にトリトンや海のモティーフが。・実物のゴールド・ステート・コーチは戴冠式や大規模な儀礼で使われる王室馬車で、 ここでは展示用の縮尺模型として紹介されていた。・手前のパネルが下の説明板(オブジェクト番号 53)。 材質や設計者・装飾担当者の名がまとめられていた。材質:鍍金・彩色木、金属、絹、革、ビロード張り。設計:ウィリアム・チェンバース(1723–1796、スウェーデン生)絵画:G. B. チプリアーニ(1727–1785、イタリア)彫刻:ジョゼフ・ウィルトン(1722–1803、英国)製作(車体):サミュエル・バトラー(活動 1749–1798、英国)発注:王室(国王造営局)〔ジョージ三世の戴冠に関連して〕。この模型は1760年ごろに作られた。実物のゴールド・ステート・コーチは戴冠式や大規模な儀礼で使われる王室馬車で、ここでは展示用の縮尺模型として紹介されていた。「53 MODEL OF THE STATE COACHAbout 1760The basic design of this State Coach was intended to reflect Britain’s [power] underthe new King George III. In the decoration by William Chambers, [painted] panels by Giovanni Cipriani and carving by Joseph Wilton show [sea-gods] and figures of[Tritons] symbolising sea-power. The coach has been used since 1762 and is still used onimportant ceremonial occasions.Gilded and painted wood, metal, silk, leather and velvet upholsteryDesigned by William Chambers (born in Gothenburg, Sweden, 1723–1796); painted byGiovanni Battista Cipriani (Italian, 1727–1785); carving by Joseph Wilton(British, 1722–1803); coach built by Samuel Butler (British, active 1749–1798). Commissioned for the Office of the [King’s/Works] for the [Coronation] of George III; completed in 1762. This model was made c.1760.Museum no. [----]」【53 国王のゴールド・ステート・コーチの模型1760年ごろこのステート・コーチ(王室儀礼用の馬車)の基本設計は、新王ジョージ三世のもとでのイギリスの(海上)パワーを表す意図で作られました。建築家ウィリアム・チェンバースのデザインにより、ジョヴァンニ・バッティスタ・チプリアーニの絵画パネルと、ジョゼフ・ウィルトンの彫刻が施され、トリトン(海神)などの像が海軍力を象徴しています。実物のコーチは1762年に完成し、以後も重要な国家儀礼で用いられてきました。】 「Britain (1760–1900)」セクションに展示されている部屋の装飾の一部。壁面と扉を含む豪華なインテリアで、19世紀の英国室内装飾様式を示していた。・扉 緑色の地に金の装飾枠をあしらった両開きのドア。枠には古典的なアカンサス文様や 幾何学的パターンが施され、華やかな仕上がり。・壁面パネル 深紅の地に、金の植物文様・幾何装飾が浮き上がるデザイン。ネオクラシカルな 「シンメトリー」と「規則性」が強調されており、18世紀末から19世紀初頭に流行した様式。・円形メダリオン画 扉の上には円形画(メダリオン)が額装されており、古典風の人物群像が描かれている。 これは神話や寓意画を題材にしている可能性が高く、部屋全体のテーマ性を示す装飾の一部。・装飾要素 周囲には丸いロゼット(花飾り)、蔓草文様、金の縁取りが連続しており、ルネサンス風・ 古代ローマ風のモチーフを取り入れている。「32 PART OF THE GLASS DRAWING ROOM, NORTHUMBERLAND HOUSE, LONDONDesigned from 1770; made 1773–1775This panelling was from the glittering drawing room, panelled entirely in glass, that the architect Robert Adam designed for the 1st Duke and Duchess of Northumberland at their London house in the Strand. The scheme was based on the richly ornamentedinteriors of ancient and modern Rome. Adam used glass backed with coloured pigmentsand metal foils to imitate the porphyry of Roman decoration and copied plaster and painted decoration in gilded metal, cast from moulds.Given by Dr. R. A. McIntosh FSAMuseum No. W.12-1972」【32 ガラス張り応接室の一部 ノーサンバーランド・ハウス(ロンドン)1770年に設計、1773~1775年制作このパネル装飾は、ロンドンのストランド通りにあったノーサンバーランド公爵・公爵夫人邸の、きらびやかな「ガラス張り応接室」から移されたものです。建築家ロバート・アダムが設計しました。デザインの構想は、古代ローマと近代ローマの華麗な装飾的室内に基づいています。アダムは、ガラスの裏に着色顔料や金属箔を貼り、ローマ装飾に見られる斑岩(ポルフィリー)を模倣しました。また、石膏細工や彩色装飾を、鋳型で鋳造した金メッキ金属で再現しました。寄贈者:R.A. マッキントッシュ博士(FSA会員)収蔵番号:W.12-1972】 ピア・グラスに取り付けられた祭壇額。・「ピア・グラス(pier glass)」とは、壁と壁の間(柱=pier の間)に置かれる大型の姿見鏡を 意味します。しばしば家具調の装飾が施され、室内を豪華に見せる効果がありました。・この鏡は、先ほどの案内板にあった「ノーサンバーランド・ハウスのガラス張り応接室」の 一連の装飾の一部であり、部屋の豪華さを象徴する重要な要素 と。・フレームの左右に配置された人物像(天使や寓意像)は、当時流行したネオクラシカル装飾の 典型で、金箔仕上げによって室内照明の輝きをさらに増す役割を果たしました。「38 MIRRORMounted in a pier glass1770–1771This pier glass was made in Rome between 1770 and 1771 for Robert Adam, one of the most fashionable architects in England. It was designed for the glass drawing room at Northumberland House, London. The richly carved and gilded frame was made by Seffer in Alken, one of the best carvers in London in the 18th century.Carved and gilded wood frame」 【38 ピア・グラスに取り付けられた祭壇額1770–1771年このピア・グラス(大きな姿見鏡)は、1770年から1771年の間にローマで制作され、当時イギリスで最も人気のあった建築家の一人、ロバート・アダムのために作られました。ロンドンのノーサンバーランド・ハウスにある「ガラス張り応接室(Glass Drawing Room)」用に設計されたものです。】イギリス・ギャラリー(1760–1900) の展示風景で、18世紀末から19世紀にかけての「ファッショナブルな暮らし(Fashionable Living)」をテーマにした一角。・中央の肖像画 中年の男性像で、イギリスの富裕層あるいは文化人を描いた肖像画。家具とともに展示され、 邸宅の室内装飾を再現。・左右の小型楕円画(オーバル絵画) 神話または寓意的な場面を描いた小型絵画。肖像と組み合わせて飾られており、当時の邸宅の 壁面装飾の一例を示している。・家具類 中央の金彩のコンソール・テーブル:ロココから新古典主義へ移行期に流行した、壁際に置く 装飾的な半卓。 緑張りの椅子、透かし細工の背もたれ椅子など、デザインの異なる椅子が並べられ、 18世紀後半~19世紀前半の室内様式を比較できるようになっている。・左端の展示物 ガラスケース内にシャンデリア付きの楕円鏡(Irish Mirror with Chandelier, 1780–1790) が見えており、アイルランドのカットグラス産業の発展を示す展示が隣接している。44 IRISH MIRROR WITH CHANDELIER・アイルランド製 鏡付きシャンデリア1780–1790。・楕円形の鏡の前に、カット・グラスで作られたシャンデリアが取り付けられています。・鏡がシャンデリアの光と煌めきを反射し、室内をより豪華に演出する仕組み。・細かくカットされたガラスのプリズムやドロップ(涙型パーツ)が光を乱反射させ、 ダイヤモンドのような輝きを放ちます。・この構造は、18世紀末のアイルランドで発展したガラス工芸の特色をよく表している。「44 IRISH MIRROR WITH CHANDELIER1780–1790In the last twenty years of the 18th century Ireland developed a thriving glass industry,which supplied its own markets as well as those of Britain. Mirrors set with a cut-glasschandelier were an Irish speciality. The Neo-classical style, with its emphasis on glitterand small-scale detail, was particularly suited to the decoration of cut-glass for lighting.Cut glassMade in Ireland, possibly in DublinMuseum no. C.6-1974」 【44 シャンデリア付きアイルランド製鏡1780–1790年18世紀後半の20年間、アイルランドは活発なガラス産業を発展させ、自国市場だけでなく英国市場にも供給していました。カット・グラス製のシャンデリアを組み込んだ鏡は、アイルランド特有の製品でした。きらめきと精緻な細部を強調する新古典主義様式は、照明用のカット・グラス装飾に特に適していました。素材:カット・グラス制作地:アイルランド(おそらくダブリン)】V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)「THE WOLFSON GALLERIES(118)」 の入口部分。・The Wolfson Galleries(ウルフソン・ギャラリー) は、V&Aの中で18世紀から19世紀に かけてのイギリス美術・工芸を集中的に展示しているエリア。・ギャラリー番号 118 は、その中でも「産業革命期の工芸」「新素材・新技術」 「ファッショナブルな暮らし」といったテーマを取り扱う区画の一つです。・入り口横のパネルには「Developments in the Metal Trades 1740–1840(1740〜1840年の 金属産業の発展)」などの展示解説が掲示されており、産業革命期の英国を象徴する工芸品 (シェフィールド・プレート、カット・スティール、ブリタニア・メタルなど)が 紹介されていた。「WHAT WAS NEW?Developments in the Metal Trades 1740–1840Between 1740 and 1840 the metal trades expanded dramatically. New materials were energetically exploited and new techniques of manufacture and marketing were applied.These advances resulted in a wide range of cheaper goods. The search for cheapsubstitutes for silver led to the invention of Sheffield plate, made from copper with a fine layer of silver. Alloys such as Britannia metal and Pakfong, a golden-coloured metal from China, were also used. Japanning imitated lacquer with paint. Brittly goodsandjewellery were decorated with cut steel that sparkled like diamonds.The use of labour-saving machinery meant that goods could easily be made in standard forms. These goods could then be exported and sold throughout the world.」【新しいものは何か?金属産業の発展 1740–18401740年から1840年の間、金属産業は飛躍的に拡大しました。新しい素材が積極的に利用され、製造や販売の新しい技術が導入されました。これらの進歩により、安価な製品が幅広く生産されるようになりました。銀の代用品を求めた結果、シェフィールド・プレートが発明されました。これは銅に薄い銀の層をかぶせたものでした。また、ブリタニア・メタルや、中国から伝わった金色合金の「パクフォン」も使用されました。さらに「ジャパニング(Japanning)」と呼ばれる漆の模倣技法が塗料で施され、鋼を細かくカットした装飾は宝石のように輝き、装飾品やジュエリーを飾りました。労力を節約する機械の利用によって、製品は標準化された形で容易に大量生産されるようになり、輸出され、世界中で販売されました。】 作品名:The Campbell Sisters dancing a Waltz ワルツを踊るキャンベル姉妹作家:Lorenzo Bartolini(1777–1850、イタリア) 。・特徴 ・二人の若い女性・キャンベル姉妹 Emma & Julia の二人が寄り添って歩く姿。 ・衣の表現は古代風のトーガ風で、流れるような薄布の表現はカノーヴァ派の特徴。 ・台座には花綱(ガーランド)が飾られ、祝祭的な雰囲気を添えている。・テーマ ・寓意像(友情 Friendship / 調和 Harmony / 優雅 Grace など) ・あるいは神話の二人の女性人物(ニンフや女神のペア)。 ・新古典主義では、神話的題材を「理想化された女性像のペア」として表現することが多く、 この作品もその系統。「FASHIONABLE LIVINGThe Private Sculpture GalleryMany British collectors developed a taste for classical sculpture during the Grand Tour of the mid-18th through Europe as young men. On their return, the owners createdspecially designed settings for the sculptures they had bought, either in their London or their country houses.Such interiors could often be seen at Holkham Hall in Norfolk, where the Sculpture Gallery was established in the 1750s. At Syon House, Robert Adam designed a sculpture gallery during the 1760s.In the early 19th century, a new interest in contemporary sculpture, in the classical style, developed, aimed at the decoration of fashionable domestic interiors.In Britain, the leading sculptor was Antonio Canova’s pupil, Antonio d’Este, who produced idealised marble sculptures of mythological subjects.」【ファッショナブルな暮らし個人彫刻ギャラリー18世紀中頃、多くのイギリス人コレクターは「グランド・ツアー」(ヨーロッパ大陸への教養旅行)を通じて古典彫刻への嗜好を育みました。若者として大陸で学び、収集した彫刻を持ち帰ると、彼らはそれを展示するための特別な空間を、自宅のロンドン邸宅や地方の館に設けました。そのような室内装飾は、ノーフォークのホルカム・ホール(Holkham Hall、1750年代に彫刻ギャラリーを設置)や、ロバート・アダムが1760年代に設計したサイオン・ハウス(Syon House)の彫刻ギャラリーで見ることができます。19世紀初頭には、新古典主義様式の現代彫刻への関心が高まり、流行の邸宅インテリア装飾に用いられるようになりました。イギリスにおける代表的な彫刻家は、アントニオ・カノーヴァの弟子アントニオ・デステ(Antonio d’Este)であり、彼は神話的主題を理想化した大理石像を制作しました。】 V&A(ヴィクトリア&アルバート博物館)の ブリティッシュ・ギャラリーの一室。・中央手前 黒い台座の上に大きな 犬の彫像(セント・バーナード犬のような姿) が置かれています。 白と黒のコントラストがあり、毛並みを強調した写実的な作品。・中央奥 大きなシャンデリアが天井から吊るされ、空間に豪華な雰囲気を与えている。・右手の壁面(黄色) 18世紀後半から19世紀の英国家具・調度品が並んでいる。金装飾の椅子やソファ、 楕円形の額鏡(オーバル・ミラー)、さらに壁面には肖像画や小型絵画が掛けられている。・左手の壁面(紫〜黒) 絵画や漆工芸品(日本や中国からの輸入品も含まれる)が飾られており、英国の室内装飾が 「東洋趣味(シノワズリー)」を取り込んでいた様子を反映している。British Galleries 1500–1900 の「19世紀室内装飾」展示の一部。・このセクションは、19世紀イギリス上流階級の邸宅サロンを再現する構成。・家具・肖像画・鏡・室内装飾を一体的に展示し、当時の「ファッショナブルな暮らし (Fashionable Living)」の様子を伝えています。・背景壁の黄色は、当時流行した室内色彩を意識した演出でもある。中央・楕円形の大きな鏡(オーバル・ミラー) ・豪華な金色の額縁に収められ、上部には羽根飾りのようなクラウン装飾。 ・19世紀初頭、リージェンシー様式やロココ復興の影響を示す華麗な意匠。左側・赤い張り地の寝椅子(カウチ/シェーズロング) ・金のフレームに赤い織物張り。 ・社交空間やサロンで使われた家具。・大型の肖像画(女性像) ・豪華な金のフレームに収められた油彩画。 ・この展示セクションでは、肖像画と家具を組み合わせて「邸宅のインテリア空間」を 再現しています。右側・緑の張り地の肘掛椅子 ・ギリシャ風の脚部装飾があり、ネオクラシカル(新古典主義)の影響を示す。・小型の黒いスタンド(読書台または譜面台のような家具・二枚の肖像画 ・左:白いドレスを着た女性像。 ・右:黒衣をまとった男性像。Spode(スポード窯)のディナーサービス(約1820年)。上段・小型丸皿 ×6・長方形小皿 ×1・中皿(楕円・八角形)×2中段・楕円大皿(ミートディッシュ)×2・中型楕円皿(野菜皿またはサイドディッシュ)×2・丸皿(スープ皿・デザート皿)×2下段(左右の棚も含む)・深鉢(サラダボウル、野菜ボウル)×2・オーバル大鉢 ×1・蓋付きスープチュリーン ×2・ソースボート(片口小鉢)×1最下段・大型のサーヴィングプレート(中央に大花束文)×1「PART OF A DINNER SERVICEAbout 1820; numbers 30–34, 1831This large service is characteristic of the extensive and richly decorated porcelain that was available to an increasingly wide range of buyers during this period. Marketing through London showrooms played an important role in the selling of such ensembles. Massed displays were a familiar sight to the visiting public as in theWedgwood showroom illustrated on the left.PorcelainMade by the Spode Factory, Stoke-on-Trent, Staffordshire」【ディナーサービスの一部約1820年(カタログ番号30–34, 1831年)この大規模なディナーサービスは、19世紀初頭に広く出回った、装飾豊かで華やかな磁器を代表しています。当時、ロンドンのショールームでの販売戦略が重要な役割を果たしました。ウェッジウッドのショールーム展示に見られるように、大規模なディスプレイは訪問客にとっておなじみの光景でした。素材:磁器製造:スポード窯(Spode Factory)、ストーク=オン=トレント(Staffordshire州)】「The Wolfson Galleries(ウォルフソン・ギャラリー)」の一部で、18世紀末〜19世紀初頭の室内装飾と家具 を再現するようなセクション。写真中央には 大きな円形の凸面鏡(Convex Mirror, 約1790年) が掲げられています。鏡は金箔仕上げの松材フレームに収められ、上下にアカンサスの葉飾りや鷲のモチーフが加えられている。これは当時の流行で、家具デザイン集(George Smith, 1808年刊)でも紹介された様式。1.凸面鏡(Convex Mirror, c.1790) ・松材、金箔仕上げ、凸面ガラス。 ・装飾には鷲(eagle)、アカンサスの葉が使われ、クラシカルな権威を象徴。 ・所蔵番号:W.25-1922。2.肖像画(右壁) ・女性の肖像(白いドレス、赤い背景)。 ・男性の肖像(軍服を思わせる装い)。 → いずれも19世紀初頭の貴族・上流階級を描いた作品。鏡と共に飾られることで、 当時の邸宅の「ファッション性」を表現。3.家具(下部) ・赤い張地の寝椅子(シェーズ・ロング)。 ・緑の布座面の椅子(ギリシャ風装飾)。 ・小型テーブル(木製、彫刻装飾)。 → ナポレオン時代からジョージアン期にかけての「新古典主義スタイル」を示す。「19 CONVEX MIRRORAbout 1790Mirror of this type became popular in about 1790. Various examples were illustrated in George Smith's Collection of Designs for Household Furniture and Interior Decoration, published in 1808. This example shows how various details such as the eagle and the acanthus leaf were added to a basic circular mirror.Pinewood, gilded with convex glassMuseum no. W.25-1922」 【19 凸面鏡約1790年この種の鏡は 1790年頃 に流行しました。さまざまな例が、1808年に出版されたジョージ・スミスの 『家庭用家具と室内装飾のデザイン集』 に図示されています。本作は、基本的な円形の鏡に、鷲(イーグル) や アカンサスの葉 などの細部装飾が加えられた様子を示しています。素材: 松材、金箔仕上げ、凸面ガラス所蔵番号: W.25-1922】左側の肖像画・タイトル: Mary Linwood・画家: ジョン・ホップナー(John Hoppner, RA, 1758–1810)・制作時期: 約1800年・技法: 油彩・カンヴァスこの肖像画は、羊毛刺繍による巨匠絵画の模写作品で知られた メアリー・リンウッド(1756–1845) を描いたもの。彼女はレスター・スクエア(ロンドン)でギャラリーを運営し、刺繍芸術を「高級芸術の展示形式」と結びつける先駆者であった。ジョン・ホップナーは当時のイギリスを代表する肖像画家の一人で、リンウッドを優雅な白いドレス姿で描き、彼女の文化的な地位と知的活動を示している。右側の肖像画。・油彩画ではなく、メアリー・リンウッド(Mary Linwood)による毛糸刺繍の ナポレオン・ボナパルト像(19世紀初頭のイギリス肖像画) であろう。・作品:Portrait of Napoleon Bonaparte(刺繍)・作者:Mary Linwood(1756–1845)・年代:18世紀末〜19世紀初頭・技法:クルーエル刺繍(coloured worsteds)・サイズ:およそ 2 ft 7 in × 2 ft 2 in(資料記載) ・所蔵:Victoria and Albert Museum(収蔵番号 1438-1874)「13 MARY LINWOODAbout 1800Mary Linwood (1756–1845) was famous for exhibiting her crewel wool needlework copies of old master paintings in her gallery in Leicester Square, London. Linwood'senterprise was an example of how the luxury goods trades began to use similartechniques of display to those used for high art, attracting customers with public exhibitions.Oil on canvasBy John Hoppner RA (born in 1758, died in 1810)Bequeathed by Miss Ellen MarklandMuseum no. 1439-1874」 【13 メアリー・リンウッド1800年頃メアリー・リンウッド(1756–1845)は、ロンドンのレスター・スクエアにある自身のギャラリーで、オールド・マスター(巨匠画家)の作品を羊毛刺繍(クルーエル刺繍)で再現した作品を展示したことで有名でした。リンウッドの事業は、高級品の取引が「美術作品の展示」で用いられるのと同じような展示手法を取り入れ、公開展示によって顧客を惹きつけるようになった一例です。油彩・カンヴァス画家:ジョン・ホップナー RA(1758年生 – 1810年没)エレン・マークランド嬢の遺贈美術館番号:1439-1874】「TEAPOYThe teapoy became popular in about 1800 as a table with receptacles for tea.This example is close to the design included in Peter and Michael Angelo Nicholson’s Practical Cabinet-maker, published in 1826. A copy is displayed nearby. Such pattern books not only provided designs for cabinet-makers but also influenced popular taste.Carved mahoganyBy an unknown British makerPurchased with the assistance of the Brigadier Clark FundMuseum no. W.16-1973」 【15 ティーポイ(茶卓)1825–1830年ティーポイは、1800年頃にお茶用の容器を収める小卓として人気を博しました。この作品は、ピーターとマイケル・アンジェロ・ニコルソンの著書『実用家具製作者 (Practical Cabinet-maker)』(1826年刊行)に掲載されたデザインに近いものです。その本の一部が近くに展示されています。このような「パターン・ブック」は、家具職人にデザインを提供しただけでなく、大衆の嗜好にも影響を与えました。素材:マホガニー材の彫刻作者:不詳(イギリスの製作者)ブリガディア・クラーク基金の援助により購入所蔵番号:W.16-1973】レディ・アン・ハミルトン・Lady Anne Hamilton (1766–1846)👈️リンク。・レディ・アン・ハミルトン は、王族に仕えた著名な宮廷女性で、特に キャロライン王妃 (ジョージ4世妃)の侍女・側近 として知られています。・彼女は王妃キャロラインがロンドンに帰国した際の「議会審問(離婚裁判のような性質)」に 同席し、その忠誠心から政治的にも注目されました。・絵画では、黒いドレスと大きな帽子(当時の宮廷・社交界での正装) を身につけ、威厳のある 姿で表されています。背後の赤いカーテンや椅子にかけられた毛皮付きマント (アーミン=白テンの毛皮)は、貴族的な地位や儀礼を象徴している。9 TORCHERE or candelabrum・ トーチャー(燭台)またはカンデラブラ「9 TORCHERE or candelabrum1816–1818George Bullock used British woods and British marbles, but he often worked for export.One of his major commissions was for the British Government who furnished the houseon St Helena in which Napoleon was held captive after the Battle of Waterloo.Pollard oak veneer with ebonised and gilt gesso details; light fittings of glass andsilvered metalDesigned by George Bullock (born in 1782 or 1783, died in London, 1818) andmade in his London workshopMuseum nos. W.62A-1887 (torchere), W.62B-1887 (sconce)」 【9 トーチャー(燭台)またはカンデラブラ1816–1818年ジョージ・ブロックはイギリス産の木材や大理石を用いたが、しばしば輸出向けの仕事も行った。彼の主要な仕事のひとつは、ワーテルローの戦い後にナポレオンが幽閉されたセント・ヘレナ島の邸宅を、イギリス政府の依頼で家具調度したことである。素材:斑木(ポラード・オーク)の化粧張り、黒色仕上げと金色ジェッソ装飾、ガラスおよび銀メッキ金属の照明器具デザイン:ジョージ・ブロック(1782年または1783年生、1818年ロンドン没)製作:彼のロンドン工房所蔵番号:W.62A-1887(燭台)、W.62B-1887(ブラケット燭台)】V&A博物館(Victoria and Albert Museum, London)内の「CLORE STUDY AREA(クロア・スタディ・エリア)121室」 の入口。この展示はV&Aの Medieval & Renaissance Galleriesに置かれており、中世美術の実物に囲まれながら「19世紀の中世趣味」を示す重要なコントラスト作品。「The Yatman Cabinet(ヤトマン・キャビネット)」👈️リンク。・このキャビネットは、Charles Francis B. Yatman(1823–1902) の依頼で作られた 豪奢な家具で、彼の名前から「Yatman Cabinet」と呼ばれています。・外観はあたかも中世の聖遺物箱(Reliquary Shrine)のようにデザインされ、宗教画風の パネル装飾やアーチ構造が特徴。・実際には19世紀の「ネオ・ゴシック様式(Gothic Revival)」の産物で、当時のイギリスで 流行した「中世趣味」を反映している。近づいて。キャビネットの扉や引き出しには、寓意的なパネル画がはめ込まれており、テーマは 「知識と文明の発展」 。・左の場面:古代における知識の口伝・写本伝達・中央の場面:学者(もしくは詩人・哲学者)が机に向かって記録・右の場面:印刷機による本の大量生産(グーテンベルクの活版印刷を象徴)つまり、知の継承 → 記録 → 普及 という人類文化の進展を順に表したもの。「Gothic Revival(ゴシック・リヴァイヴァル)」1830–1880 展示コーナーの一部。1.左側の大きな展示布・中世の文様を模した複雑なパターンの織物または壁紙。・「ゴシック・リヴァイヴァル」期のデザイナーたちが、ステンドグラスや古代織物に 基づいて色彩豊かなパターンを創作したことを示す典型例。2.中央〜右側の壁面・壁掛け時計(木製ケース入り):19世紀らしい直線的で重厚なデザイン。・文様図版(3点):ゴシック様式のパターンやアーチ形の装飾デザイン。 建築や家具、織物デザインに用いられたサンプル。・建築画(右端額装):ゴシック風建築の立面図。19世紀に流行した教会・公共建築の 設計案を反映している可能性が高い。3.下部の椅子群・赤い張地に金糸刺繍で「王冠」や「紋章」をあしらった椅子。・おそらく 英国議会のチェア またはそれを模したデザイン。ネオ・ゴシック様式の家具として 権威や伝統を示す役割を持つ。「Gothic Revival(ゴシック・リヴァイヴァル)」 の解説「STYLEGothic Revival 1830–1880Gothic, the dominant style of architecture and decoration in the Middle Ages, becamethe most popular revival style in Britain in the 19th century. The Victorians used it not just for churches but for every type of building, including houses, railway stationsand banks.The characteristic Gothic motifs of pointed arches, spires and turrets were also applied to domestic objects such as clocks and jewel plates. Designers created richly coloured patterns for fabrics and wallpapers based on the complex decoration found inMedieval stained glass and on ancient textiles.To its supporters Gothic was a morally superior style. They saw it as both British andChristian, unlike the foreign and pagan styles of classical Greece and Rome.」【様式ゴシック・リヴァイヴァル1830–1880中世において建築と装飾の主要な様式であったゴシックは、19世紀のイギリスで最も人気のある復興様式となりました。ヴィクトリア朝の人々は、それを教会に限らず、住宅、鉄道駅、銀行などあらゆる建物に用いました。特徴的なゴシックのモチーフ――尖頭アーチ、尖塔、塔など――は、時計や宝飾品の台座といった日用品にも応用されました。デザイナーたちは、中世ステンドグラスや古代の織物に見られる複雑な装飾に基づいて、豊かな色彩の布地や壁紙の模様を創り出しました。支持者たちにとって、ゴシック様式は道徳的に優れた様式と見なされました。彼らはそれを「外国的で異教的な古代ギリシャやローマの様式」とは異なり、「英国的かつキリスト教的」なものと考えたのです。】「Gothic Revival(ゴシック・リヴァイヴァル)」セクション に展示されている 教会祭具・聖具の一式。1.聖体顕示用クロス(大十字架)・左:銀製の大きなクロス(浮彫装飾あり)。典礼用の祭壇十字架。・中央:金色のクロス。下部は釣鐘形の台座に載っており、典礼で視覚的に荘厳さを演出。2.聖杯と典礼器具・中央下:金と銀で装飾された複数の聖杯(chalices)。・右下:装飾写本や典礼書(豪華な装丁)。・左下:銀製のピクシス(聖体容器)やカラフなど、聖体やワインを扱う容器。3.司祭祭服(Chasuble, カズラ)・右:深紅の織物に金糸刺繍が施されたカズラ(ミサ用外衣)。・背面には大きな円形の装飾(オーフリース/orfray)に、十字架や聖体シンボルが刺繍されている。4.背景の装飾布とステンドグラス・上部:赤地に金糸刺繍の祭壇前掛け(antependium)。 中世風の唐草文様とキリスト教シンボルを表現。・右端:小さなステンドグラス断片(キリストの受難を描いた場面の一部)。「Religion in Britain 1800–1900In 1800 the Church of England, the established church, exercised a unique power.Methodists and other Protestants, Roman Catholics, members of other faiths andatheists all faced obstacles to education, professional advancement and public office. The Catholic Emancipation Act of 1829 is the best known of many changes in the lawthat marked the development of religious freedom and led to the gradual removal ofbars to education or employment on religious grounds.Religion in 19th century Britain was fiercely debated and different groups held stronglyopposing views. All religious groups were active in building churches, chapels, meetinghouses or synagogues to provide for the spiritual needs of existing communities and for those that were developing in the expanding cities. Religion also became the spurto many programmes of social care for the poor. Religious observance came to be seen as a mark of respectability and individuals and communities spent large amounts on building and decorating their places of worship.」【イギリスにおける宗教 1800–19001800年当時、イングランド国教会(国教会)は特別な権力を有していました。メソジスト派やその他のプロテスタント、ローマ・カトリック、他宗教の信徒、そして無神論者たちは、教育・職業的昇進・公職就任において数々の障害に直面していました。1829年のカトリック解放法(Catholic Emancipation Act)は、宗教的自由の発展を示す数多くの法改正の中でも最も有名なものであり、宗教を理由とした教育や雇用の制限を徐々に撤廃する道を開きました。19世紀のイギリスにおいて宗教は激しく論争され、各派は強い対立的見解を持っていました。すべての宗教団体は、既存の共同体や拡大しつつある都市の新しい共同体の精神的ニーズに応えるため、教会・礼拝堂・集会所・シナゴーグの建設に力を注ぎました。また宗教は、貧困層への多くの社会福祉プログラムの原動力にもなりました。宗教的な実践は「社会的尊敬性の印」とみなされ、個人も共同体も礼拝所の建設や装飾に多額の資金を投じるようになったのです。】「The Church 1840–1900During the 19th century there was a powerful religious revival in Britain and many churches were built. As new laws increasingly guaranteed religious freedom, all Christian denominations took up the challenge of producing new churches for a population that was growing rapidly, particularly in the cities.Different groups held strongly opposed views on what was appropriate for the architecture and decoration of churches. Roman Catholics and some Anglicans saw rich decoration and furnishings as important elements of worship.Other denominations favoured plainness both in buildings and services.Artists, architects, and in particular A.W.N. Pugin designed both churches and their complete contents. As demand increased, specialist suppliers such as Cox & Sons(established 1837) and Jones & Willis (established 1855) church furnishings could beordered from published catalogues.」 【教会 1840–190019世紀のイギリスでは、力強い宗教復興があり、多くの教会が建設されました。新しい法律が宗教の自由を次第に保障するようになると、すべてのキリスト教宗派は、急速に増加する人口、特に都市部における新しい教会建設の課題に取り組みました。異なる宗派は、教会の建築や装飾において何が適切かについて強く対立した意見を持っていました。ローマ・カトリックや一部の英国国教会信徒は、豊かな装飾や調度品を礼拝の重要な要素と考えました。一方、他の宗派は建築や礼拝において簡素さを好みました。芸術家や建築家、とりわけ A.W.N. ピュージン は、教会そのものとその内部装飾のすべてを設計しました。需要が高まるにつれて、Cox & Sons(1837年創業) や Jones & Willis(1855年創業) などの専門業者が登場し、教会用の家具や調度品を出版されたカタログから注文できるようになりました。】 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2025.11.01
閲覧総数 471
-
41
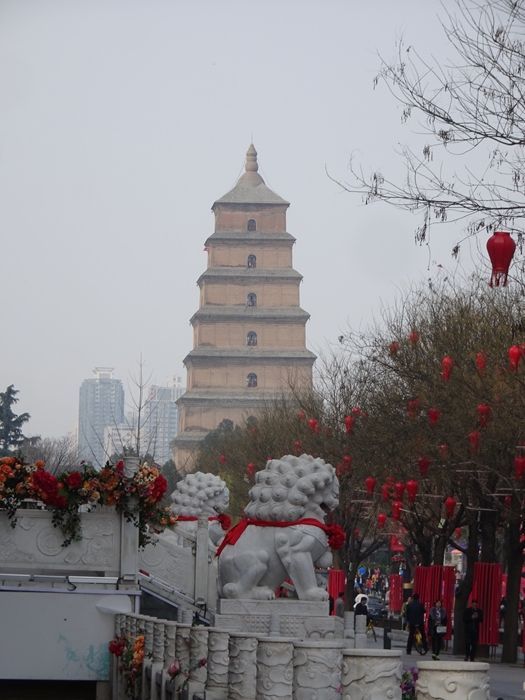
中国・西安を訪ねる(その15・大雁塔へ-1/2)
大雁塔に向けてバスは雁塔南路を走る。バスの車窓に大雁塔が姿を現す。大雁塔に向けて雁塔南路進むと、車窓から中央分離帯に様々な人物の像がある事に気がつきシャッターを。 この辺りは大雁塔の南に新しく出来た、南の開元広場から玄奘広場まで「大唐不夜城」と呼ばれる地域。雁塔南路の両側はショッピングセンター、雁塔南路に沿ってモノレールが走り、雁塔南路の中央は公園になっていて、何処からでも大雁塔を見る事が出来るのだ。公園にあった、左に柳公権、中央に 顔真卿の像。右手に「撃壌歌(げきじょうか)」の歌碑が。同じく李白像。閻立徳・閻立木兄弟の像。唐時代の書家。 バスを降り「大雁塔」の観光開始。 「福」の左右に「西安年・最中国」の文字が。西安の旧正月こそ、最も中国らしい」という意味。今年の春節では、安市曲江新区にある、西安大唐不夜城「現代唐人街」、大唐芙蓉園、大明宮、そして西安城壁の4カ所の景勝地が同時にライトアップされ、西安は世界に向けて招待のメッセージを発信したと。この企画には、光のショーによって市民や観光客に、歴史的、文化的な味わいのある旧正月を味わってもらい、西安ならではの魅力を感じてもらいたいという期待が込められていたのだと。 「中国年」は「春節(旧正月)」の別称。中央に「大雁塔」と右に「玄奘三蔵」の像。大雁塔(だいがんとう)は唐の時代の高僧、玄奘三蔵(げんじょうさんぞう)がインドから持ち帰った仏教の経典や仏像などを保存するために、当時から大寺院であった長安(今の西安)の大慈恩寺に建てられた塔。玄奘三蔵は大慈恩寺の高僧で、玄奘三蔵はこの大雁塔の設計にも携わっている。玄奘三蔵がインドから帰ってきたのが645年。唐は名君と言われた二代目の太宗が皇帝の時代で、太宗は玄奘三蔵が持ち帰った経典の翻訳を指示し、玄奘三蔵はこの翻訳を彼が没する664年の直前まで続けたと。玄奘三蔵は657の経典を中国に持ち帰り、それらを翻訳する中で中国仏教の誤りを正し、後に生まれる法相宗という中国仏教の宗派の開祖になったと。インドへの旅を地誌『大唐西域記』として著し、これが後に伝奇小説『西遊記』の基ともなったのだ。なお、西遊記には三蔵法師が出て来るが、三蔵法師の「三蔵」というのは仏教用語で経蔵・律蔵・論蔵の三蔵に通じている僧侶のことで、固有名詞ではないのだと。正面に高さ7層64mの大雁塔の雄姿が。玄奘の設計により、当初は5層であった。各階に仏舎利がおさめられ、経典は上層部の石室に置かれた。玄奘自ら、造営に携わったと伝えられる。大雁塔が作られた当時は. こんな茶色っぽい色ではなかったそうだが. 今のような色になったのは黄砂のためだと現地ガイドから。入口門の前では若者の集団が記念写真の撮影中。横断幕には「大富豪餐飲我們是一家」の文字が。大富豪?一家?どの様な集団なのであろうか?暫くすると、お巡りさんが来てこの場からの解散命令が出していたが・・・。 大慈恩寺の入口門。大雁塔は西安市の東南郊外にあるこの大慈恩寺の境内に建っているのだ。大慈恩寺は唐の第3代皇帝高宗が、母である文徳皇后を供養する為に建立した寺院。江沢民前主席の揮毫による額。大雁塔 配置図。巨大な香炉と大雁塔。大雁塔にも専任ガイドが待っていてくれた。右手に「鐘楼」。左手に「鼓楼」。「客堂」。大雁塔の手前に建っている「大雄宝殿」への階段を上がる。ガイドによると大雁塔は傾いているのだと。そして、 大雁塔の傾きが、この10年間、毎年1ミリの速さで元に戻りつつあるのだと。西安の大雁塔は唐代に建てられ、古都・西安市を代表する建築物の一つで。史料の記載によると、清の康熙58年(1719年)に、大雁塔は北西方向に198ミリ傾いていた。そして1996年には、大雁塔の傾斜は1010.5ミリに達した。関係部門は、地下水浸出防止などの措置を取り、古塔を保護。大雁塔保管所によると、こうした処理の後、大雁塔は1997年から毎年1ミリのスピードでまっすぐに戻りつつあると。昨年の測量の結果では、傾斜1000.2ミリ(約1m)になったと。階段の中央には白い大理石に見事な彫刻が。下段には龍。上段には花が。「大雄寳殿」。大雄とは釈迦を意味し、釈迦を本尊としている場合はそこを大雄宝殿と名付けて本尊を安置すると。よってこの寺の本堂。本尊のお釈迦様を正面から。天井まである立派な釈迦仏。 左手より。 右手より。 十八羅漢(正面に向かって左)。十八羅漢(正面に向かって右)。「先覚堂、至現堂、観音殿」。 伽藍殿、甘露堂、財神殿。 「人天歓喜」 の扁額が掲げられていた堂。金色のこの仏像は、釈迦が誕生した時、四方に七歩ずつ歩み、右手で天を、左手で地を指して唱えたという言葉、『天上天下唯我独尊(てんじょうてんげゆいがどくそん)』の御姿。金色の仏像も。大雁塔という名称は、菩薩の化身として雁の群れから落ちて死んだ一羽を塔を建てて埋葬したことに由来しているのだと。 二殿前で、ガイドから有料(30元)で大雁塔に登れると。「大雁塔」銘板。大雁塔の傾斜のきつい内部階段を登る。内部は階段がらせん状に7階まで250段続いているが、各階毎に踊場的なスペースがあった。人がすれ違うのもやっとの狭い階段であったが、中国人もこういう場所では階段を譲り合うのであった。そして最上階からのガラス越しの眺め。北側、雁塔北路。西側、雁塔西路。昔は最上階のこの西窓から外を眺めると遠くシルクロードが一望できたはずだが今は高層ビル群が建ちそれは想像するしかなかった。塔は四角形で、柱を使わず黄土を餅米で突き固め、外側をレンガの壁で覆った分厚い構造になっているのだと。南側の眺望、雁塔南路。こちらからの眺めは、広い通りが大雁塔から真っ直ぐに走り、 日本の平城京や平安京の手本となったこれぞ長安の街並みを見るが如し。大雁塔内に展示されていた「風鈴」。右側は修繕された時に取り換えた唐代の煉瓦。1999年にインドの玄奘寺から寄贈された「舎利子」だと。お釈迦様の遺骨が入っているようであった。 明代の金銅仏。そして再び大雁塔の狭い急な階段を下って行ったのであった。 ・・・つづく・・・
2018.03.23
閲覧総数 1165
-
42

旧古河庭園へ
この日、4月20日(金)は10年前のスペイン旅行以来お付き合いしている旅友の一人の女性の60歳還暦の宴が夜、五反田で行われ、これに参加しました。旅友のSさんと、昼間は都内の庭園を散策し、ツツジの花を楽しもうと。そしてJR上中里駅で10時に待ち合わせ。この駅を利用するのは初めて。そして歩いて10分もかからず最初の訪問場所・旧古河庭園(きゅうふるかわていえん)へ到着。「祝 100年 旧古河庭園」と書かれた表示板が。チケット売り場でその後に予定してた六義園とのセット券を購入。旧古河邸は100年前の1919年(大正8年)に古河虎之助男爵の邸宅として現在の形(洋館、西洋庭園、日本庭園)に整えられた。現在は国有財産であり、東京都が借り受けて一般公開しているとのこと。国の名勝に指定されている。東京のバラの名所として親しまれている人気スポット。ウィキペディアによると「1917年(大正6年)5月、西洋館と洋風庭園が竣工。洋館と洋式庭園は、イギリス出身の建築家、ジョサイア・コンドル(他に旧岩崎邸洋館、鹿鳴館、ニコライ堂など)により設計監理された。さらに虎之助により、大正8年(1919年)、日本庭園も竣工し、現在の形となった。日本庭園は近代日本庭園の先駆者・京都の庭匠「植治」こと七代目小川治兵衛(他に京都無鄰菴、平安神宮神苑、円山公園など)により作庭された。」と。英国貴族の邸宅にならった古典様式で、躯体は煉瓦造、外壁は真鶴産の新小松石(安山岩)の野面積で覆われ、屋根は天然スレート葺き、地上2階・地下1階の造り。大正12年9月1日に発生した関東大震災では約2千人の避難者を収容し、虎之助夫妻が引き払った大正15年7月以降は貴賓の為の別邸となった。昭和14年頃には後 に南京政府を樹立する国民党の汪兆銘が滞在し、戦争末期には九州九師団の将校宿舎として接収され、また戦後は英国大使館付き武官の宿舎として利用されたと。北側の洋館(大谷美術館)入口。上部に古河家の家紋が。洋館の1&2階 間取り図。館内は撮影禁止と。旧古河邸 配置図。庭園のツツジはかなり開花していたが、バラはこれから。メイズ(迷路)のように入り組んでおり、様々な種類のバラが植えられている。左右対称性は「フランス整形式庭園」から、そして石の欄干や石段などは「イタリア露壇式庭園」から着想を得ているのだと。展望台(四阿・あずまや)から旧古河邸を。バラ園まで下り、旧古河邸を南側から。左右対称の美しい造り。 館は地上2階・地下1階からなるジョサイア・コンドル最晩年の作。赤と白そして緑のアンジュレーション(うねり)。西側。南側正面からもう一度。ツツジ園は満開に近かった。キアゲハが。ツツジ園の下の「黒ボク石積」。黒ボク石とは富士山の溶岩で、多孔質で軽く、加工もしやすい。山の雰囲気が出るため、主に関東で石組みとして用いられる事が多いが、石垣は珍しいと。苔の緑も光を浴びて輝いていた。モミジの新緑も陽光を浴びて。兜門。茶室のある庭によくある門であると。日本庭園の心字池と一枚岩の石橋。こちらの一枚岩は2枚互い違いに。松の手入れ中。我が家の五葉松も・・・と。日本庭園には多くの形の石灯籠が説明板付きで置かれていた。濡鷺型灯籠(ぬれさぎがたとうろう)。「他の形式に比べて笠が厚く、むくり(反り)が無い。図柄は「濡れ」を文字で「鷺」を絵で表現するか、「濡鷺」を文字で表現する2種類がある。」と。泰平型灯籠(たいへいがたとうろう)。「笠の縁が蕨(わらび)のように渦巻状に沿った部分を「蕨手」(わらびて)という。竿が太くて節も3つあり、名が示す通りどっしりとした「泰平感」を漂わせている。」と十五層塔。「その語源はスツーパ(積み重ね)からきていて、現地では仏塔の一種として信仰を集めていますが、日本でも石塔は塔婆と同じ考え方で用いられ共通性がある。奇数積みが原則」と。最上部は地震で落下したのであろうか?横の地面上に設置されていた。雪灯籠と心字池。心字池は「心」の字に似せて、鞍馬平石や伊予青石などで造られた池。池を眺める要となる「船着石」があり、正面には「荒磯」、雪見灯籠、枯滝、石組み、そして背後には築山が見られた。雪見型灯籠。「この灯籠は水辺によく据えられ、その姿が水面に浮いて見える「浮見」と点灯時にその灯が浮いて見える「浮灯」が「雪見」に変化したとする見方がある」と。奥の院型灯籠。「灯袋に牡丹・唐獅子・雲・七宝透かしを、中台に十二支を、基礎に波に千鳥又は波に兎を刻んでいる。奈良の春日大社の奥の院にあるものを本家として発展した。」と。別の角度から。中台の十二支が良く理解出来た。「崩石積(くずれいしづみ)」。京都で発達した伝統的な工法。ぎりぎりのバランスを保ちながら石を組み上げ、造形美へと昇華する。当庭園のものは小川治兵衛の力作とされる。茶室。大滝。「この滝は、本郷台地と低地の斜面を巧みに利用した、小川治兵衛の最も力を入れた場所の一つであり、滝壺まで20m落ちる景観は氏の作風の中でも珍しく丘陵幽玄の境地を如何なく発揮している。」と。「10数mの高所から落ちる滝。園内のもっとも勾配の急な所をさらに削って断崖とし、濃い樹林でおおって深山渓谷の趣があります。曲折した流れから始まり、数段の小滝となり最後は深い淵に落ちるという凝った造りです。」と。井戸水をくみ上げているようであった。階段を上り再び展望台へ。バラのシーズンを思い描きながら。そして東側の芝生広場より旧岩崎邸を。植木職人が花壇に花を定植中であった。
2018.04.26
閲覧総数 881
-
43

古都「鎌倉」を巡る(その26): 日本山妙法寺~鎌倉山神社~扇湖山荘~聖福寺阯~龍口明神社~経六稲荷社
『鎌倉散策 目次』👈リンク鎌倉山の「檑亭」を後にして、次に訪ねたのが「日本山妙法寺」。鎌倉市鎌倉山1丁目19−5。民家のような建物であった。2015年10月05日に設立した法華経系宗教法人「日本山妙法寺 鎌倉道場」であるようだ。扁額「日本山妙法寺」。題目塔「南無妙法蓮華経」。「立正安国」の文字が。境内の「五輪塔」。そして次に訪ねたのが「鎌倉山神社」。鎌倉市鎌倉山2丁目27−11。「鎌倉山神社祭神 大山津見命(おおやまつみのみこと) 御父 伊邪那岐尊(いざなぎのみこと) 御母 伊邪那美尊(いざなみのみこと)当神社はもともと本村笛田の農民の鎮守でまた津村の漁民の海上守護の神・(「山の神」)であったのを昭和の御代に当地が鎌倉山住宅地として発展すると共に住宅地の鎮守として奉斎された。昭和十年に鎌倉山在住の有志達の浄財により改装され「鎌倉山神社」と改称された。爾来今日に至るまで鎌倉山住人有志たちが社殿を御守りし毎年八月八日例祭を執り行っている。」社号標「鎌倉山神社」。「社殿」は石宮。「社殿」には、釈迦や、亀に乗った摩利支天の木像が安置されているとのこと。石宮の屋根には「隅切り角に三の字」の紋が。我が市内にある時宗総本山「遊行寺」の宗紋と同じ、その理由は??相模湾が見えた。湘南モノレールの先に相模湾が。ズームして。湘南モノレールの軌道が案外急勾配なことが分かるこの場所。鎌倉山で一番高い場所から江ノ島の姿も。そして更に東に進んでいくと、歴史を感じる黒門があった。ここは別荘・「扇湖山荘(せんこさんそう)」の入口であったが閉まっていた。この別荘を構えたのは戦前の実業家だった長尾欽彌氏で、胃腸薬「わかもと製薬」で財を成した人物。東京世田谷の深沢に本邸があり、1934年(昭和九年)当地に土地を求めて別荘としたものです。敷地は緩やかな傾斜地に一万四千坪もの広さを誇り、飛騨高山から移築した民家や宮家の茶室などが点在し、名立たる庭師の手による庭園が広がるまさに絵に描いたような大豪邸。戦後は人手に渡って「鎌倉園」の名称で料亭となり、三和銀行の研修所を経て市に寄贈され現在に至っていると。「傾斜地に建てられてあるので変則的な三階建てになっており、土台として鉄筋コンクリート造りの洋風建築を築き、その上に木造二階建ての民家を乗せてある」と。ネットからの写真を転載させていただきます。母屋(本館)の奥の部屋の囲炉裏をこちらもネットから。 【https://hosaka.kanagawanet.jp/blog/2017/11/25/2033/】より次に「聖福寺跡」を訪ねた。「聖福寺公園」の中を歩く。この公園の八重桜は今が満開。シバザクラも濃いピンクの花を。近寄って。ネモフィラも。和名を瑠璃唐草(るりからくさ)という花。そして「聖福寺公園」を出た場所にあった石碑。場所は、江ノ電・稲村ヶ崎駅手前の道をひたすら山に向かって上って行ったところ。ここまで鎌倉観光で足を伸ばす人は稀有であろうと。鎌倉市稲村ガ崎5丁目39−6。北条時頼が子供のために建てた寺・「聖福寺阯」碑。「あと」という読み方を持つ漢字には「址」「阯」「後」「迹」「痕」「趾」「跡」「踪」「墟」「蹟」「蹤」などがあり、石碑によって違うのだ。「聖福寺ハ建長六年(紀元一九一四年、一ニ五四年)四月 関東ノ長久並ニ北条時頼ノ息、時輔(幼名聖寿丸)時宗(幼名福寿丸)ノ息災延命ノ為建立セシモノニシテ、其ノ寺号ハ両息ノ名字ニ因ミシモノト伝ヘラルモ、廃寺ノ年代詳ナラズ、此谷ヲ聖福寺谷ト呼ブ鎌倉町青年團建」【聖福寺は1254年4月に、北条時頼(ときより)により建てられた寺です。その目的は、鎌倉幕府が長く続くことと、時頼の2人の息子、時輔(ときすけ、幼児の名前:聖寿丸[しょうじゅまる])と時宗(ときむね、 幼児の名前:福寿丸[ふくじゅまる])が病気をせず長生きできることとを願うためでした。寺の名前は、2人の息子の名前を採ったものと伝えられていますが、この寺が廃止された時期よく分かっていません。 この谷を聖福寺谷(しょうふくじがやつ)と呼んでいます。】と。・建長6年:1254年。宝治-建長-康元。天皇は後深草天皇(89代)、将軍は宗尊親王(6代)、 執権は北条時頼(5代)・北条時頼:1227-1263。鎌倉幕府5代執権。建長寺を建立。出家後は最明寺殿。次に近くにあった「熊野権現社」を訪ねた。正面に石鳥居、その奥に石宮の社殿が。社号標「熊野權現社」。石宮の「社殿」。「不動明王」の石像も。そしてこの日の最後に「龍口明神社(りゅうこうみょうじんしゃ)」まで車で向かう。駐車場に車を駐め石鳥居に。鎌倉市腰越1548−4。社号標「龍口明神社」。「掲示板」。石灯籠。「記念碑 龍口明神社由来御祭神 玉依姫命(神武天皇母君) 五頭龍大明神 玉依姫は海神族の祖先豊玉彦命の姫君に在して彦炎出見尊の妃に在します上に鵜鷀草葺不合尊の母神に在しまし、豊玉姫の妹御に在し給ひ、龍神として尊崇された。 五頭龍大明神の御由緒は欽明天皇十三年四月十二日戌の刻より二十三日辰の刻に至る迄大地振動して終日息ず。即ち孤島を湧出した此を江の島と云い天女降む。是辨戝天の作るところなり。天女惡龍の惡業を戒めた。龍は遥かに天女の麗質を見、其の後改心し村人に害を与えることなく山と化した。村人はその山の海に突出た所の龍の口の様な岩上(龍の口)に社を築き白髭明神と称し村の安泰を祈願した。此龍口明神社の発祥と伝えられている。養老七年三月より九月迄江の島岩窟中にて泰澄、慈覚両大師が神業修行中夢枕に現れた神々を彫作し辨戝天一体を岩本院に、二体を白髭明神社へ納めた。即ち玉依姫命(長さ五寸)と五頭龍(長さ一尺)の御木像が御神体である。此の時、龍口明神社と名付け、江の島と当社の繁りと両地の平和と隆昌を祈願した。鎌倉時代には神䕶により如何なる惡業をした者も此処に血を流すことにより世人に尽すと此の前の地を刑場とした事もある。又氏子はその祟りを恐れ当社の移転改築を長年拒んできた。然し大正十二年関東大震災で全壊した社を昭和八年改築し今日に至ったが、境内地が藤沢市片瀬地域内の飛地津一番地に有ることゝ時代の推移と共に同地区の発展及び人口増加に伴い御祭神のご神慮に依り、此度氏子百余名は江の島遠望清浄の地、竜の胴に当る蟹田ヶ谷一五四八番地の四の当地に遷座申し上げ、此の地の守護神として奉祀するものである。」「龍口明神社」の白い幟の先には。「御神木」はタブの木であろう。正面に「二の鳥居」。「手水場」。龍の手水口。「社務所」。「拝殿」前方に。もともとは龍口(たつのくち)の龍口寺西隣に建っていたが、安政2年(1773年)に龍口が片瀬村(現藤沢市片瀬)に編入されて以降、境内地のみ津村の飛び地として扱われた。鎌倉時代には刑場として使用された時期もあり、氏子達は祟りを恐れ、長年移転を拒んでいたという。大正12年(1923年)、関東大震災により全壊、昭和8年(1933年)に龍口の在のままで改築したが、 昭和53年(1978年)に、氏子百余名の要望により、江の島を遠望し、龍の胴にあたる現在の地へと移転した。なお移転後の現在も、旧境内は鎌倉市津1番地として飛び地のまま残っており、拝殿・鳥居なども、移転前の姿で「元宮」として残されているのである。狛犬(阿形像)(右)。狛犬(吽形像)(左)。「五頭龍大神」は武相鎌倉と江の島に伝わる「五頭龍と弁財天」の伝説に登場する一身五頭の龍神。「拝殿」御祭神は玉依姫命。五頭龍大神創建522年と伝わる鎌倉一の古社といわれ江島神社とは夫婦神社と云われている。723年江の島岩窟中で泰澄大師が修行中夢枕に現れた神々を彫刻。弁財天は江島明神へ玉依姫命と五頭龍大神の御木像を白鬚明神へ納めたといわれその時に龍口明神社と名付けられたと。60年毎に還暦巳年祭が行われ近年では昭和4年・平成元年に斎行。平成13年には御鎮座1450年祭が斎行。この時と還暦巳年祭に限り五頭龍大神の御神体が御開帳され江島弁財天と共に江島神社中津宮に安置されると。龍口明神社は昭和53年、龍の胴に当たる現在の地に遷座され日本三大弁財天として名高い江島神社と夫婦神社として崇敬されているのだと。扁額「龍口明神社」。「内陣」。「拝殿」の屋根。「五頭龍大明神」像が今年・令和三年(2021)十月鎮座予定であると。「社務所」。「絵馬」。御朱印を頂きました。境内を振り返る。そしてこの日の最後に訪ねたのが境内社の「経六稲荷社」。鎌倉市腰越1543−6。石鳥居を潜り社殿に進む。朱の「社殿」。扁額「経六稲荷」。境内の「庚申塔」。「この庚申塔はもと手広と津村の境の庚申塚にありましたが、永く後世に伝えるため龍口神明社のご厚意を得て当地に移しました。」「板状駒型庚申塔上辺に日月を浮き彫りし、中央に合掌六手の青面金剛像、その下に三猿がつきます。像の向かって右に「庚申供養 久遠成就、左に「正徳三年(1713)葵巳」とあります。下の壇には9名の名前がある。「駒形庚申塔」上辺に日月を彫り、中央に「庚申供養塔」と彫り、下に三猿がつく。向かって右側面に文政十一年(1827)、左側面に九月吉日とある。同じく「駒形庚申塔」。上辺に日月を彫り、中央に「庚申(以下破損のため不明)」と彫り、下に三猿がつく。向かって右側面に弘化五年(1848)戌申正月吉日とあった。「舟型庚申塔」上辺に日月を浮き彫りし、中央に合掌六手の青面金剛像が邪鬼の上に立っている。像の足元向かって右に「奉」、左側に「納」と。向かって右側面には安永三年(1774)、左手には十一月とある。「石祠」。(明治18年(1885年)銘)。「山王大権現」碑。「社殿」前にあった「石祠」には稲荷様が。そしてこの日の2回目の「古都「鎌倉」を巡る」を終え、帰宅したのであった。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.05.19
閲覧総数 547
-
44

古都「鎌倉」を巡る(その36): 円覚寺(6/7)・唐門~蔵六庵~浴場跡~弁天堂~洪鐘~洪鐘道~帰源院~三門
『鎌倉散策 目次』👈リンク「庫裡」の玄関から外に出ると正面にあったのが「唐門(方丈正門(勅使門))」。大方丈の正門にあたる門。こちらが裏側。唐門としては小振りではあるが、寺格に相応しく鬼板、拝飾や木口飾の金具には菊の御紋があしらわれ、紅梁下や門扉の応龍の彫り物も見事であった。「唐門」の左側の柱の中間部の飾りにも「菊の御紋」が。唐門(勅使門)の龍の彫刻(方丈玄関側)。唐門(勅使門)の扉の彫刻が見事。この写真は以前に撮った写真であるが。唐門(勅使門)の扉には飛龍の彫刻(方丈側)。唐門(勅使門)の扉には飛龍の彫刻(百観音霊場側)。そして表に廻って。唐門(勅使門)に舞う2羽の鳥の彫刻。その上に浪の彫刻。唐破風屋根の懸魚には菊の彫刻。そしてその上の唐破風拝飾りや木口飾りにも「菊の御紋」が。そして左手には「円覚寺派宗務本所」そして南側の参道を下っていく。この後に訪ねた「国宝洪鐘(おおがね)・弁天堂」の案内板があった。前方右手に「佛殿」が見えて来た。手前の緑の場所は「法堂跡」。七堂伽藍の一つ「法堂跡」を帰路には反対側から見る。 「直指堂」と呼ばれた法堂は、元享三年(1323年)に建立されたが、応安七年(1374年)の大火で焼亡した後は再建されていないのだと。「佛殿」の南側に吊るされている梵鐘。この鐘は、仏殿で行われる諸行事の開始を告げるため、鳴らされるのだと。「国宝洪鐘」の案内に従い進む。左手に「蔵六庵(ぞうろくあん)」の案内板があったので、訪ねて見ることに。「蔵六庵」は、第二世大休正念(仏源禅師)の塔所。本尊:釈迦如来。正念が壽福寺に開創したのを、正念の示寂(僧の死)後、門弟によって円覚寺境内に移された。『大休正念法語』は国重要文化財。大休正念は宋の禅僧。八代執権北条時宗に招かれ、建長寺、壽福寺、円覚寺の住職を勤め、浄智寺や大慶寺を開創している。扁額「蔵六庵」。石段の横には竹林があった。そして南側参道の左側にあった「七堂伽藍 浴場跡」案内板。この辺りが七堂伽藍の一つ「浴場跡」で、現在は駐車場になっていた。前方の石段の上に石鳥居が見えて来た。石鳥居の左側に「洪鐘道」と刻まれた石碑が。「洪鐘(おおがね) 国宝一三〇一年「正安三年)に鋳造された国宝の洪鐘です。北條時宗公の子、貞時公が国家安泰を祈願して鐘の鋳造を鋳物師に命じましたが、鋳造がうまくゆかず、江ノ島の弁天さまに七日間参拝したところ、ある夜の夢の中で円覚寺の白鷺池の底を掘ってみよというお告げがあり、その通りにしてみると池の底より龍頭形の金銅の塊を発見、それを鋳造してこの洪鐘を造ったといわれています。この霊験に感激された貞時公は江ノ島の弁天さまを洪鐘の神体として「洪鐘大舟才功徳尊天」と名付けて弁天堂を建立しました。」更に石段を上って行った。「弁天堂」碑。石段の上に「弁天堂」の姿が見えて来た。「弁天堂」。「弁天堂」正面。龍の彫刻。扁額「大弁財天」。「円覚寺 弁天堂執権北条貞時(時宗の子)か7日7夜江の島弁財天に参籠し天下泰平、万民和楽を祈り霊夢を感して大鐘を陦造(正安3年、1301年)し、当山に奉納した。あわせて弁天堂を建立し、弁才天を祀り当山の鎮守とした。以来霊験あらたかにして祈願すれは必す惑応を蒙むといわれて来た。又、この境地は眺望絶住にして遠く富士山をも望むことが出来、多くの人々より称賛されてきた。因に当弁才天の祭礼は11月28日である。又、60年毎の己の年に大祭を行い、江の島弁才天と当山との間て盛大にとり行なわれる。」内陣。上部に龍の透かし彫りの入った欄間、左右に随身を配した内陣の中央には、なんとなく仏壇風の御神座が置かれていた。石造蛇形の御神体は御簾に御隠れであったが、御神座には前立ての位牌があり「洪鐘大弁才功徳尊天 」と書かれていた。いかにも寺院の鎮守らしい社殿内部の造り。そして両側の壁面には絵画が。何かの行列の儀式が描かれていたが・・・。「弁天堂」と向かい合う位置に「洪鐘(梵鐘)」が。だんだんとズームして。1301年(正安3年)の刻銘があり、「洪鐘」(おおがね)と呼ばれています。大旦那は九代執権北条貞時で、鋳物師は物部国光。鎌倉で最大の梵鐘で、鎌倉三名鐘の一つで建長寺の梵鐘とともに国宝に指定されている。関東で最も大きい洪鐘、国宝。「洪鐘」と書いて「おおがね」と読むのだと。円覚寺の開基である北条時宗公の子である貞時公により、正安3年(1301)国家安泰を祈願して寄進されたもの。総高259.4cm、口径142cmもの大作。「洪鐘(梵鐘)正安3年( 1301年)に北条貞時が国家安泰を祈って鋳造、寄進した時の住持は西潤子曇、鎌倉第一の大鐘で国宝に指定されている。物部国光の作て、形が雄大てありながら細部にまて緻密な神経がゆさわたり技法も洗練されている。鎌倉時代後期を代表する梵鐘である。」「表忠碑(ひょうちゅうひ)」。日露戦争の戦病没者を表忠する碑。表忠とは忠義をあらわすという意味。永冶宜雄さんの発願によって、明治39年2月、円覚寺の弁天堂脇に建立された。篆額は大教正宮路宗海氏、碑には船茂孝阿による慰霊のための歌が刻まれている。「表忠碑 加まくらや む可しな賀良乃 鐘の音 耳寄りつとふら志 も能ヽ婦能靈 孝阿」歌の内容であるが、「円覚寺の鐘は、北条貞時が父時宗と元寇の殉難者の冥福を祈って鋳造したものだという、今も昔と同じ音色を響かせる鐘の音には、日露戦争の戦病没者の魂も集まって来るに違いない」と。碑高140cm、幅90cm、厚さ20㎝、台石(3段)83cm「休縁禅定門 光清禅定尼」の墓碑であろうか。禅定門、禅定尼は仏門に入って剃髪した者を指し、禅定門士、禅定門尼の略であると。「弁天堂」横から「北鎌倉女子学園」の校舎、体育館が見えた。「東慶寺」の境内を「弁天堂」横から。「洪鐘弁天茶屋」はコロナ禍の影響で休業していた。「洪鐘」を後にして石段を下る。途中にあった石碑の上部は破損していた。「洪鐘道」と刻まれた道標。苔生した道が南側の「参道」に繋がっていた。石段の先に藁葺の山門が見えた。ここに塔頭「帰源院(きげんいん)」の「山門」があった。風情ある藁葺きの「山門」。漱石が書いた小説『門』が、この「帰源院」の門であることはよく知られている。藁葺の厚さに驚いたのであった。「山門」には「鎌倉 漱石の会」とあった。前からあったのだろうが、今回初めて気がついた。28歳の漱石は2週間ほど円覚寺で座禅を試みたが、神経衰弱は直らず、もちろん悟りも出来ず、山門にたたずんだまま帰って行ったと。ある意味、漱石にとって円覚寺は挫折の場所であったのか。「山門」の先の境内の参道。アーチ型の「樹門」が前方に。「山門」から横に廻って「帰源院」の正面に。帰源院は、第三十八世傑翁是英(けつおうぜえい)の塔所。本尊は傑翁是英。中興開山は奇文禅才(きもんぜんざい)、中興開基は北条氏康。是英は、大慶寺や浄智寺にも住した。1894年(明治27年)末から翌年にかけて止宿した作家夏目漱石は、釈宗演に参禅し、その体験は小説『門』に描かれた(参考:円覚寺の山門)。境内には、夏目漱石の句碑「仏性は白き桔梗にこそあらめ」が建てられているのだと。作家島崎藤村もここに出入りし、そのときの様子を『春』に描いた。開祖木像を安置していると。「山門」を見上げて。そしてこちらの円覚寺の「三門」横に戻る。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.05.29
閲覧総数 540
-
45

古都「鎌倉」を巡る(その53): 宝戒寺~筋替橋跡~西御門碑~西御門 八雲神社
『鎌倉散策 目次』👈リンクそして次に訪ねたのが「横大路」の突き当りにあった「宝戒寺」。鎌倉市小町3丁目5−22。寺号標「天台宗圓頓寶戒寺」。この寺、正式な名称は「金龍山(きんりゅうざん)釈満院(しゃくまんいん)圓頓寶戒寺(えんどんほうかいじ)」。鎌倉の花の寺・梅の花や萩の花でも有名。「鎌倉大聖天」碑の前には、提灯の雨よけの屋根が対で。「金龍山寶戒寺伽藍復興大勧進ご案内」「北條執權邸舊蹟」碑。「往時此の地に北条氏の小町亭在り 義時以後累代の執権概ね皆之に住せり 彼の相模入道が朝暮に宴筵(えんえん:宴会)を張り 時に田楽法師に対し列座の宗族巨室(重臣)と倶(とも)に直垂(ひたたれ:礼服)大口(おおくち:大口袴)を争ひ解きて 纏頭(てんとう:褒美)の山を築けりと言ふも此の亭なり 元弘三年 (1333)新田義貞乱入の際 灰塵(かいじん:灰)に帰す 今の宝戒寺は 建武二年(1335) 足利尊氏が高時一族の怨魂忌祭の為 北条氏の菩提寺東勝寺を此の亭の故址(こせき:旧跡)に再興し 以て其の号を改めしものなり」【昔この場所に、北条氏の小町亭がありました。北条義時(よしとき)以後代々の執権(将軍代理職)はたいていここに住みました。あの北条高時が、朝に夕に宴会をして、ときには田楽法師に対して、列席している重臣と共に、 ひたたれや袴(はかま)を投げ与えて褒美(ほうび)の山を築いたというのもこの場所であります。1333年に新田義貞(にったよしさだ)が鎌倉に攻め入った時、戦火で焼けて灰になってしまいました。現在の宝戒(ほうかい)寺は、 1335年に足利尊氏(たかうじ)が建てたものです。この寺は高時一族の恨みを鎮めるために、北条氏の菩提寺であった東勝寺を、この屋敷跡に建てて名前を変えたものであります。】と。六角形の踏石が並ぶ参道を進む。「宝戒寺新田義貞の鎌倉攻めにより、この寺の南東にある「腹切りやぐら」で、最後の執権・北条高時をはじめ北条一族八百七十余名が自害したと伝えられています。滅亡した北条氏の霊を弔うため、また修行道場として、後醍醐天皇が足利尊氏に命じ、北条氏の屋敷があったとされるこの地に寺を建立させました。境内には四季を通じて花が咲き、九月には白いハギで理めつくされる「萩の寺」として有名です。・宗派 天台宗・山号寺号 金龍山円頓宝戒寺・建立 建武2年( 1335 )・開山 五代国師(円観慧鎮)・開基 後醍醐天皇」「掲示板」。「山門」「宝戒寺」境内配置図。「本堂」。宝戒寺は、後醍醐天皇の勅命をうけた足利尊氏公により、北条氏の霊を弔うため、また国宝的人材を養成する道場として北条氏執権屋敷跡であるこの地に建立された。ご本尊は鎌倉二十四地蔵尊の第一番とされる子育て経読み延命地蔵様で鎌倉三十三観音霊場の寺院の中で唯一、准胝観音様をお祀りし、また、鎌倉江の島七福神の毘沙門天様をお祀りしている。近づいて。「宝篋印塔」。1333年滅亡した北条氏並びに鎌倉合戦東勝寺(とうしょうじ)戦没諸精霊を供養する慰霊塔。鎮魂の祈りを込めた写経、写経石が納められているのだと。「鐘楼」。「聖徳太子堂」。聖德太子は仏教を深く信仰され、仏教の保護に尽力された。また優れた工芸技能者の育成を図ったといわれ、これにちなみ諸職人の守り神として信仰されている。毎年1月22日に聖德太子講が厳修(ごんしゅう)されると。「徳崇大権現堂」。鎌倉幕府執権北条高時公を德崇大権現(とくそうだいごんげん)としてお祀りしている。鎌倉幕府が滅亡した5月22日には北条氏鎮魂の為、毎年大般若転読会(だいはんにゃてんどくえ)が厳修(ごんしゅう)されると。「大聖歓喜天堂」。秘仏である大聖歓喜双身天王(だいしょうかんぎそうじんてんのう)(歓喜天・聖天様(かんぎてん・しょうでんさま))をお祀りしている。毎年5月23日には諸願成就を祈念し大聖歓喜天供(だいしょうかんぎてんく)が厳修される。正面から。扁額は「大聖天」。以前に戴いた「鎌倉三十三観音第2番:仏母准胝観音尊」の「御朱印」です。以前に戴いた「鎌倉二十四地蔵第1番:子育経読地蔵尊」の「御朱印」です。以前に戴いた「鎌倉・江ノ島七福神:毘沙門天」の「御朱印」です。「宝戒寺」を後にして、県道204号線・金沢街道を右に進むとカーブの場所に石碑があった。ここが「筋替橋(鎌倉十橋)跡」。「筋替橋」碑。「鎌倉十橋ノ一ナリ 寶治元年(1247)六月 三浦康村(やすむら)一族ノ叛乱ニ際シ 北条時頼(ときより)ノ外祖(母方ノ祖父)タル安達景盛(かげもり)ハ 其ノ一族ト共ニ 兵ヲ率(ひき)イ此ノ橋ノ北辺ヨリ康村ノ第(屋敷)ヲ攻メシコト 東(吾妻)鑑ニ見エタリ 又文平二年(1265)三月 鎌倉ニ於ケル商家ノ営業地域ヲ数カ所ニ限定セル触書(フレガキ:告知書)中ニ「一所須地賀江橋」トアルハ 即チ此附近ノ事ナリ」【鎌倉十橋のひとつです。1247年6月に三浦康村(やすむら)一族が反乱を起こしました。その時、安達景盛(あだちかげもり)は、その一族と共に兵を率(ひき)いて、この橋の北の辺りに集まり、康村の屋敷を攻めたことが吾妻鑑(あずまかがみ)に書いてあります。また鎌倉において、商店の営業できる地域を数か所に限定するという告知書が1265年3月に出され、その中に「須地賀江(すじかえ)橋」と書いてあり、これはこの付近のことであります。】名所案内。「来迎寺」方面に向かって進む。突き当りにあったのが「YNU 横浜国立大学 教育学部 附属鎌倉小・中学校」正門。鎌倉市雪ノ下3丁目5−10。民家に庭の樹の花。ピンクの「マロニエ」の花であろうか?突き当りを左折し、「YNU 横浜国立大学 教育学部 附属鎌倉小・中学校」の校庭の脇の道を北上する。左手に「頼朝の墓⇒」の案内があったが直進した。更に進むと前方左手に石碑が。先ほどと同じ場所の案内表示。「西御門」碑。「西御門は 法華堂西方の地をいふ 大蔵幕府西門の前面に当たれるを以て此名あり 報恩寺 保寿院 高松寺 来迎寺等此地に在り 今 高松 来迎の二寺を存す」【西御門は、法華堂(ほっけどう)の西の方の土地を言います。大蔵幕府の西門の前面に当たるため、この名前が付いています。この地域には、報恩寺(ほうおんじ)、保寿院(ほじゅいん)、高松寺(こうしょうじ)、来迎寺(らいごうじ)等がありました。 現在は来迎寺のみが存在しています。】このグランド付近が「大蔵御所西御門跡」だったのであろう。現在地は鎌倉市西御門2丁目1−11付近。更に北に向かって鎌倉市西御門1丁目の住宅街を北上する。右手に小さな石碑があった。「右 来迎寺」と。ここを右折し進むと左手にあったのが「西御門 八雲神社」。鎌倉市西御門1丁目13−1。「西御門八雲神社祭神 須佐男命(すさのうのみこと)建立は定かではありませんが、『風土記稿』に因れば字大門の天王社がもとだと考えられます現在の社殿は天保三年の建造だと言われています。須佐男命は『古事記』『日本書紀』でも知られる神様で特に須佐男命は乱暴で天照大神が怒って天の岩戸に隠れた神話や八岐大蛇(やまたのおろち)を退治した伝説はよく知られています。」3基の庚申塔が並んでいた。右側から「笠塔婆型庚申塔」上辺に日月、六手の青面金剛が彫られている。体の前においた右手には髪の毛をもって人を吊り、左手には剣を、ほかの手には剣、輪宝などを持つ。下に三猿が厚彫りされている。文化五年(1808)の銘が。中央は「船型庚申塔」上辺の右に月、左に日、中央上辺に大日如来を表す梵字を刻みむ。四手の青面金剛が邪鬼の上にたっている。右の上手には鉾、下手は矢をもち、左上手は棒、下手は弓を持つ。下には、三猿が。庚申塔で四手の青面金剛像は少なく、鎌倉でも2基だけだとのこと。左は「船型庚申塔」上辺に「阿弥陀」をあらわす梵字を刻み中央に合掌六手の青面金剛像、下には鶏と三猿が彫られていた。元禄五年(1692)の銘が。小さな石の社も境内に。そして「社殿」。鎌倉の八雲神社は山ノ内、大町、常盤とここの4か所あると。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.06.15
閲覧総数 145
-
46

古都「鎌倉」を巡る(その78) : 鎌倉歴史文化交流館(5/5)~合鎚稲荷社跡~古我邸~結の蔵~巽神社~八坂神社
『鎌倉散策 目次』👈リンク「鎌倉歴史文化交流館」の別館で開催されていた企画展「鎌倉大仏-みほとけの歴史と幻の大仏殿-」の見学を終え、「鎌倉歴史文化交流館」の庭の見学に向かう。ここは2002年(平成14年)の発掘調査で建物礎石や1293年(永仁元年)の大地震後に造営されたと考えられる庭園遺跡が発見されたのだと。「無量寺谷は興禅寺の西方の谷で、昔、無量寺という泉涌寺末の寺があった」ことが記されていると。そして、『吾妻鏡』の安達義景の十三回忌に触れ、「義景は盛長の子で居宅は甘縄。この辺まで甘縄の内であるので、『吾妻鏡』の無量壽院は、後に無量寺と呼ばれたか?」という内容が記されているのだと。「やぐら風の横穴と庭について庭に見える3つ並んだアーチ状の横穴は、当地が岩崎家の所有であった頃に造られたものといわれています(庭の意匠あるいは貯蔵庫ともいわれますが、詳しい用途は不明です)。その左にある横穴や、別館工ントランス正面にある横穴は、中世に遡る「やぐら」で、当館の敷地内には同様の横穴が点在しています。やぐらは横穴式の埋葬施設で、鎌倉の各所に見られます。別館の発掘調査では、玉砂利を敷いた鎌倉時代後期の池と遣水の遺構が発見されています。切り立った岩肌を借景に池を配する庭園様式は、著名な瑞泉寺の庭園にも共通するものです。中世の池に設けられた遣水は、この窓の正面付近へと伸びていました。現在でも岩肌から水が染み出し、小さいながらも多様な植物や生物が共存する空間を作り出しています。自然的景観と建物が調和する風景は、鎌倉の谷戸に見られる特徴の一つです。近世以降に多くの手が加えられながらも、中世的な景観の痕跡を感しられる当館の庭をお楽しみください。」中央の3つ並んだアーチ状の横穴は、当地が岩崎家の所有であった頃に造られたもの、そして左にある横穴が中世の「やぐら」であると。それにしても鎌倉の歴史を物語るこの場所をよく選んでこの「交流館」を建設したもの。石段を上って行った。左手に「合鎚稲荷祠道」と刻まれた石碑が。そして石段を上り終えると右手に一段高い場所が現れた。この場所にはかつて「合鎚稲荷社(あいづちいなりしゃ)」があったのだと。この博物館開館前に「 葛原岡神社」👈リンク 既に移設されていたと。「合鎚稲荷社跡」について当館の建つこの谷戸は「無量寺谷」と呼ばれ、江戸時代には、相州伝の刀工正宗の後裔である綱廣の屋敷があったと伝えられます。そしてその敷地には、刀鍛冶を守護する「刃稲荷」が祀られていたと推測されています。大正年間には、三菱財閥第4代当主の岩崎小弥太が、母早苗のための別荘を構えていました。岩崎氏は、大正8年(1919)、かってここに祀られていた稲荷社を「合鎚稲荷」として復興し、参道や鳥居、石造神狐像や社祠を整備しました。その後平成12年(2000)、センチュリー文化財団がこの土地を取得した後、老朽の著しかった社祠を新たに再建しました。建造にあたっては、愛媛県松山市石手寺の重要文化財「訶梨帝母天堂」(鎌倉時代後期)を模して造られました。このたび、鎌倉市への土地と建物の寄附にあたり、社祠や神狐像、参道鳥居は、近隣の葛原岡神社へと移設され、現在も大切にお祀りされています。高台にある稲荷社の跡地は、現在は見晴台としてご利用いただいております(雨天時は閉鎖)。」「合鎚稲荷社跡」前の見晴台から逗子マリーナのマンション群が見えた。「鎌倉歴史文化交流館」の別館裏の広場を見下ろす。石段を下りて、「鎌倉歴史文化交流館」の本館裏を見る。再び中央の3つ並んだアーチ状の横穴を見る。中央が別館から本館への連絡口。「鎌倉歴史文化交流館」をほぼ独り占めして、ゆっくりと見学し、鎌倉の歴史について多くを学んだのであった。そしてこのブログを書きながらも、知らなかったことが次々と目の前に現れて来たのであった。再び通路の脇にあるアジサイ・「アナベル」の色合いを楽しみながら「鎌倉歴史文化交流館」を後にしたのであった。前方に「佐助隧道」が見えた。竣工 昭和40年(1965年)延長 62.0m 道路幅 5.1m そして若い女性達やカップルが並ぶ姿が前方に。「茶房 雲母(キララ)」。鎌倉で有名な行列の絶えない白玉専門店。ピンポン玉のような、ふわふわでもちもちの白玉がごろごろ入った白玉あんみつ、みつまめは絶品。出来立ては白玉がほかほか温かい。ほうじ茶と昆布茶が付いてきて、これだけでも満足出来る とネットから。鎌倉市御成町16−7。人気の「宇治白玉クリームあんみつ」、美味そう!!食べた~い!! 【https://snapdish.co/d/emyzia】より「今小路通り」を目指して進むと左手に大谷石の表面が剥離して剥がれ落ちた痛々しい長い石塀がある料亭の如き屋敷があった。その角にあったのが「指月庵」案内。指月庵の看板には、三菱の岩崎家別荘地の後を柳屋ポマードの外池五郎三郎氏が入手した。上方から職人を呼んで茶室を造った。命名は当時の円覚寺管長朝比奈宗源師による旨が記載されていたが、閉鎖しているようであった。鎌倉市扇ガ谷1丁目2−10。この「指月庵」看板のある角を左手に入っていくと左手奥にあったのが「古我邸」。鎌倉市扇ガ谷1丁目7−23。「古我邸」。フレンチレストラン古我邸。100年の歴史ある古我邸で、旬の食材と自家菜園の野菜を中心に厳選された食材で調理されたフランス料理を味わえると。鎌倉三大洋館のひとつ古我邸は、1916年(大正5年)に建てられ、今年で築105年を迎えた。1916年 三菱合資会社専務理事兼管事 荘清次郎の別荘として完成。内閣総理大臣 濱口雄幸や近衛文麿も別荘として利用した。鎌倉は扇ガ谷、1500坪の敷地に堂々とそびえる洋館。2015年4月17日にフレンチレストラン&カフェとしてオープンした。何も具体的な案内が無いので、ここがレストランだと知らなければ入るのを臆してしまう立派な門構えであった。門をくぐれば目の前には何もない広大な緑の敷地が広がっていたのだ。2017年1月より若き実力派シェフが就任して以来、その皿の上の世界観と、鎌倉食材と敷地内で収穫される“古我野菜”のメニューに魅せられ、多くの美食家が足を運んでいると。設計は、日本人初の英国公認建築士で、東京の旧三菱銀行本店や丸ノ内ビルディングの設計を行った桜井小太郎。完成は大正5年、その歳月はなんと15年。戦後G.H.Qに接収され、将校クラブとして使われた時期を越えて、この「古我邸」の名になったのは、昭和12年に日本土地建物株式会社の経営者、古我貞周がこの建物を取得してからのこと。戦後日本のモータースポーツのパイオニア「バロン古我」こと息子の古我信生氏にちなみ『古我邸』の愛称で親しまれて来たのだと。そして「今小路通り」に出て北鎌倉方面に進むと、左手に大きな蔵があった。鎌倉市扇ガ谷1丁目10−6。「結の蔵(ゆいのくら)■元所在地 秋田県湯沢市■建築年 1888年(明治21年)■移築年 2004年(平成16年)■元の用途 酒蔵■現在の用途 賃貸住宅■規摸 向口7.3m 奥行16.5mこの建物は秋田県湯沢市に明治21年に建てられた造り酒屋の酒蔵であった。それをほぼ原型のまま移築し、歴史都市鎌倉で土壁等の伝統的技術を使い、住宅として再生したと。移築再生は、わが国に古くから残る相互扶助制度である”結”に習い、多くの人々の力添えにより進められた。その精神を永く記憶に留める意味で「結の蔵」と命名したのだと。多くの名所案内が。ここは「巽神社(たつみじんじゃ)」。鎌倉市扇ガ谷1丁目9−7。「巽神社」。「巽神社「巽荒神」由緒鎮座地 鎌倉市扇が谷1丁目9−7祭神 奥津日子神(おきつひこのかみ)、奥津日女神(おきつひめのかみ)、 火産霊神(ほむすびのかみ)例祭 11月28日由緒 御祭神は竈の神、火の神として霊験あらたかな神で延暦20年坂上田村麻呂東夷鎮換の際 葛原岡に勧請したと伝えられる。 永承4年に源頼義が社殿を改築す。 その後(年代不詳)現在の地に遷座された。 古くは壽福寺の鎮守神として崇敬され、その位置が壽福寺の巽の方に当るので 巽荒神と称された。 天正19年に社領1貫文を賜った。 近世に至って浄光明寺の持ちとなり、明治6年に村社に列格された。」「社殿」。巽神社は、延暦20年(801)蝦夷征伐に向う途中の坂上田村麻呂が葛原岡に勧請、永承4年(1049)に源頼義が改築したと伝えられます。壽福寺の南東(巽)に位置することから壽福寺の鎮守として崇められ、巽荒神と呼ばれていた。江戸時代の別当寺は浄光明寺、明治6年には村社に列格していた。境内の「猿田彦大神」碑。境内にあった「諏訪神社」。扁額「諏訪神社」。更に「今小路通り」を北に進むと左手にあったのが「八坂神社」。「八坂大神(相馬天王)由緒鎮座地 鎌倉市扇ガ谷一ー十三ー四十五祭神 素戔雄尊、桓武天皇、葛原親王、高望王例祭 七月十二日由緒 建久三年相馬次郎師常、己が邸内に守護神として勧請して崇敬したのに始まる。 その後現在の地に奉遷する。世に相馬天王と称するのはこの故である。 神幸式は五日十二日の両日に行われていたが、今では十二日のみとなった。 中世御神幸の神輿荒ぶるを以て師常館の岩窟に納め、新たに調進したと傳へられる。 独特の六角神輿は宗社である京都祇園八坂神社の形を伝承したものである。 享和元年、慶應元年に社殿の改築が行われた。 明治6年、村社に列格される。」「石鳥居」。「石鳥居」の先にも二の鳥居のような2本の老木が。正面に「社殿」。「八坂大神社殿」八坂大神は、建久3年(1192)千葉常胤の子相馬次郎師常が自宅の守護神として勧請したといい、相馬天王とも通称する。その後、浄光明寺裏山にある網引地蔵付近の岩窟へ、壽福寺本堂脇への移転を経て、当地へ移転した。明治維新の神仏分離令により八坂大神と改称、明治6年には村社に列格した。境内社の子神社(ねのじんじゃ)。「記念碑」。鎌倉市佐助の銭洗弁財天の神域である境内地と、神域の尊厳な環境を保持している、周囲の山林は、扇が谷に古くから居住している諸氏が代々共有管理し、主として扇が谷に鎮座する八坂大神、巽荒神、銭洗弁財天、各社の維持運営の当たってこられました。今回神威の末永い隆昌を企図された右諸氏は總意をもって、この土地を扇が谷の鎮守である当宗教法人八坂大神に寄進して下さいました。よってここにこの土地保有の主旨と経過を明確にして、今後扇が谷三社相互間のきずなを一層深め、地域の繁栄を計る一助とすることと致しました。ここに記念碑を建立して御好意にこたえると共に、右諸氏の芳名を刻み、後世に永く敬神崇祀のあかしと致すものであります。昭和五十九年三月吉日 宗教法人 八坂大神 壽福智光書」神輿舎。神輿は六角形で京都の祇園社(八坂神社)と同じ形だという。「元神興之碑」。相馬天王(八坂大神)の神輿は鉄でできていて、祭りのときには血をみないではすまない神輿だったと。そこで、この神輿を師常の墓近くに埋め、新たに木の神輿を造ったのだという。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.07.10
閲覧総数 398
-
47

海老名市の寺社旧蹟を巡る(その13): 海老名氏記念碑~上郷水管橋~有鹿神社~有鹿姫之霊地史跡~總持院(1/2)
海老名市河原口3丁目の路地の角には石碑が。ここが「海老名氏記念碑」。海老名氏記念碑(上郷遺跡)は、畑の耕作中に偶然発見された遺跡であると。発掘調査により、五輪塔や板碑、集石遺構が確認されました。板碑は室町時代の年号が彫られたものが大半を占めており、御屋敷などの小字名や宝樹寺(廃寺)などから、この地を治めた海老名氏に関係する墓地ではないかと考えられています。発掘調査により、五輪塔や板碑、集石遺構が確認されました。板碑は室町時代の年号が彫られたものが大半を占めており、この地を治めた海老名氏に関係する墓地ではないかと考えられていると。海老名市河原口3丁目28−5。五輪塔。「昭和四十六年十二月二十六日海老名市国分一、八八七番地寄贈者 齋藤正」碑「誌河原口 上郷あたり一体の有鹿郷は古くから有鹿神社を中心に一大集落を営んでいたと思われます約八百年以前相模守として当地にまいりました源四郎親季を祖とする海老名氏の一族には 孫の源八季定をはじめ武勇をもって聞こえた人びとが数多く輩出したと言われます今日残っているお屋敷道場前等の名称は海老名氏往時の盛況を物語るものでしょう 時流茫々かかる幾多武勇の士の拠ったゆかりの地も今や世人の記憶からその言い伝えさえ忘れられようとしているときこれらの諸霊を慰めその由来を永く後世に伝えるため海老名市が記念碑を建てるにあたりこれを記します海老名市文化財保護委員 児島視□造 撰昭和四十六年三月二十六日 建之海老名市」更に北西に進む。更に相模川に向かって進み川沿いの遊歩道に突き当たりここを左折した。眼下に相模川の姿が見えて来た。そして右側に見えたのがプラットトラスの「上郷水管橋(水道橋)」。1918年3月竣功とのことで100年以上の歴史が。直径20インチ(Φ500mm)の鋳鉄水道管。既に水道管も使われておらず撤去を待つのみであるようだ。ところで、和歌山市は今月3日、紀の川をまたぐ「六十谷(むそた)水管橋」👈リンク が(全長546m)2本の一部が59mにわたり、水面に崩れ落ちたと発表したのであった。昭和50年(1975)3月完成で、46年目で耐用年数を迎えていないと。この「上郷水管橋(水道橋)」は1918年竣工とのことで103年を経過しているのである。いかにその後のメンテナンスが重要であることが理解できるのであった。そして和歌山の橋はアーチ橋と水道管が一体になった構造で、専門家は橋の部材が劣化していた可能性を指摘しているのである。ここ相模川のものはアーチ橋と水道管がそれぞれ独立しているのであった。 【https://www.sankei.com/article/20211005-3MEO6PFK45M65PWLIAJYXCG5YE/】よりそして「有鹿神社(あるかじんじゃ)」に裏から入り正面に向かう。「自然と歴史のさんぽみち」。「有鹿神社」の正面。「海老名總鎮守 有鹿神社」。「石鳥居」。「手水舎」。郷土かるた「あ」「有鹿社は 式内社にて 水守る」.「有鹿」の名は古代の言葉で「水」を意味し、川に近く豊かな水資源に恵まれた土地に感謝して創建された と。鎌倉時代まで広大な境内を持つ大神社であったが、室町時代に戦乱で荒廃して大きく衰退してしまった。戦国時代後期から復興が始まり、江戸時代には大部分の復興を達成。明治以降も地元・海老名の総鎮守として篤い信仰を受け続けている と。「有鹿神社 御由緒有鹿神社(あるかじんじゃ) お有鹿様は、相摸國で最古の歴史と高い社格を有する。創生 遥か遠い昔、相模大地は、海底の隆起により出現する。有鹿谷の泉を水源とし、これより 流れ落ちる鳩川(有鹿河)の流域に人々は居住し、有鹿郷という楽園が形成された。 縄文の頃より、有鹿の泉は水神信仰されてきたが、弥生の頃になり農耕の発展に伴い、 人々は、農耕の安全と豊穣を祈り、水引祭を越し、有鹿大明神と称え、有鹿神社を創建した。 有鹿谷の奥宮、鳩川中流の座間の中宮、相模川に合流する地の奥宮である。発展 奈良平安の頃、相模国府は有鹿郷に所在し、有鹿神社は、国司の崇敬を受け相模国の 延喜式内社中随一の社格を有した。天智天皇3年(664)、始めて祭礼を行い、 天平勝宝6年(754)8年(756)、藤原廣政の社殿の修理と墾田五百町歩の寄進を受け、 貞観11年(869)、従五位上に昇階し、永徳元年(1381)、正一位の極位となる。 広大な境内に美麗な社殿が建ち、条里制の海老名耕地を領有し、また、明神大縄(参道)は、 社人の住む社家を経て寒川に至り、一大縄は、相模国分寺に至る。変動 やがて、国府も移転し、有鹿郷から海老名郷に地名も変わり、有鹿神社は、豪族の海老名氏の 崇敬を受けるに至った。その後、室町の二度の大乱を蒙り、海老名氏は滅亡し、美麗な社殿と 広大な境内や社領も喪失した。 その結果、鳩川中流に鎮座した中宮も現在地に遷座し、有鹿姫の伝説(座間では、鈴鹿明神 創建の伝説となる)として残る。有鹿神社は、農耕を礎とした産業の発展を背景とし、 水引祭りの斉行により、海老名耕地の用水を守り、相模国五宮として人々の崇敬を集めた。現代 明治維新となり、県社に列せられたが、郷柱に留まり、神饌幣帛料供進社となった。 第二次大戦後、宗教法人有鹿神社として神社本庁に属する。有鹿神社は、水引祭を通し、 瑞々しい活力を与え、人々の生活の安全と繁栄を見守り続ける。本宮 大鳥居の跡地(鳥居田)から四百米参道を進むと、鐘楼跡の有鹿姫霊地の碑を傍らに、 松無しの有鹿の森が茂る本宮が鎮座する。鳥居の右側に手水舎、左側に鐘楼と神楽殿、 正面に本殿を覆う覆殿・幣殿・拝殿の三棟一字の社殿がある。本殿の建築と社殿の天井の 龍絵は、海老名市の重要文化財の指定を受ける。社殿の左側に日枝社・稲荷社・諏訪社の三社、 また、社務所の東門近くに有鹿天神社が鎮座する。中宮・奥宮 東方四百米の地に有鹿井(有鹿姫化粧井戸)、更にニ百米の地に有鹿池(有鹿明神影向池)が あり中宮が鎮座する。鳩川に沿って上流に進むと、相模原の磯部勝坂の有鹿谷には奥宮が 鎮座し、その奥には有賀の泉が今も湧き出している。」「鐘楼」。鐘楼が設置されている点も神社としては珍しいポイント。明治時代に神仏分離で多くの神社から撤去されたが、有鹿神社をはじめ海老名・座間周辺の神社は鐘楼が多く残っているとのこと。「梵鐘」。「本殿」創建時期は不明ですが、永和3年(1377)の作成とされる「有鹿明神縁起」では、神亀3年(726)にすでに存在し、天平宝字元年(757)に海老名郷司藤原広政が中心となり再建、鎌倉幕府滅亡時に兵火にかかり、「本殿」以外の付属建物が失われたとしています。「本殿」と拝殿天井画は、市指定重要文化財となっている。「本殿」は春日造り、屋根は檜皮葺だそうで、格式の高い有鹿神社に相応しい造りであった。扁額「有鹿大明神」。「祈祷受付所」。この駅名の如き表示板は?境内左手に「参心殿」と社務所。近年SNS上で話題を集めているのが、有鹿神社の名物「パンダ宮司」。パンダが神職者の装束を着たようなキャラクターで、神社の境内でもたまに見かけることができると。パンダ宮司の「中の人」は神社の禰宜を務める女性で、宮司を務める父の代理として「パンダ宮司」👈️リンク の活動を行っているのだとか。写真の「パンダ宮司」は人形であった。ズームして。境内にはうっそうと生い茂る社叢があり、ケヤキやムクノキ、イチョウの大木があった。この他にも板根を張ったエノキの大木やカゴノキ、タブノキなどもみられたのであった。そして次に訪れたのが境内社の「有鹿天神社」。「社殿」。学問の神様である菅原道真公をお祀りしていると。入口にあった「郷社 有鹿神社」碑と「相模國十三座内 有鹿神社」碑。延長5年(927年)の『延喜式神名帳』に記載されている相模国の延喜式内社十三社の内の一社(小社)とされ、さらに同国の五之宮ともされるが諸説ある。旧社格は県社格の郷社。。中央にあった「有鹿神社誌」碑。鎮座地 海老名市上郷字宮畑ニ七九一番地 祭神 大日靈貴命創建の時代は詳かでないが祭行事等から東国に水稲栽培伝わった頃と推察され古くから延喜式内相模國十三座の一として住民から崇敬されている。相模國古風土記残本に天智天皇三年紀元一三ニ三年甲子夏五月初めに・・・・・「有鹿神社」の前にあったのが「有鹿姫之霊地史跡」碑。悲恋の姫君が相模川に投身すると、蛇体となり海老名の川辺に流れ着いたので、これを不憫に想い、里人が小祠に祀りました。現在、有鹿小学校の敷地(有鹿神社の元境内地)の一角に「有鹿姫之霊地史跡」の碑が立てられていた。以下ネットから。有鹿姫(あるかひめ) 今から約五百年前、愛川の小沢(こさわ)というところに金子掃部助(かもんのすけ)という武将がいました。金子掃部助は、関東管領 山ノ内上杉家の家来、長尾景春が起こした戦に加わりましたが、武運つたなく破れ、小沢城を捨てて敗走しました。この掃部助と奥方の間には、美しい姫君がいました。姫は早くから有鹿の地、すなわち海老名の河原口に住んでいた郷士の青年と婚約中で河原口にある海老名館に来ていましたが「小沢城危うし!」といううわさに、急いで小沢に戻りました。しかし、時すでに遅く、父は戦死、母は行方知れずと聞き、すっかり生きる望みを失いました。覚悟を決めた姫は、見苦しい姿を人目にさらしたくないと、薄化粧をして、まだ燃えている小沢城を後に、天に向かって手を合わせると、ざぶん!と相模川に身を投げたのでした。するとどうでしょう、美しかった姫の体は、たちまち恐ろしい大蛇に変わり、大きくうねりながら下流に向かって泳ぎ出しました。途中、六倉(むつくら)という所で大きく身震いすると、相模川の水が舞い上がり、中津の原に大きな水たまりができました。 さらに水しぶきを上げながら進み、河原口に近づくと、姫は再び人間の姿に戻り、息絶えて有鹿神社裏の河原に打ち上げられました。神社の氏子らは、海老名の地に嫁ぐ日を夢見ていた姫の死を悲しみ、せめてもにと「有鹿姫」の名を贈り、神社の片隅に、そのなきがらを葬りました。現在、有鹿神社と有鹿小学校の間には、若くして散った有鹿姫をしのぶ碑が建てられています。(こどもえびなむかしばなし第4集より)その先直ぐ右手にあったのが「總持院」。海老名市河原口3丁目11−10。山号は「海老山」。「總持院」。前方に「山門」。「高野山真言宗 海老山 満蔵寺 總持院宗祖 弘法大師(空海) 本尊 虚空蔵菩薩開基 藤原廣政 開山 弘吽大行創建 天平勝寶6年(皇紀1414年・西暦754年)第46代孝謙天皇の御字(奈良時代)に海老名の郷司藤原廣政が霊夢により建立した寺で、周囲に濠を巡らせ、12の坊舎が甍を並べ棟を競っていた.そのため、近年までこの地の小字を「坊中」と称した。元弘の乱(鎌倉末期)の新田義貞の兵火により坊舎をことごとく焼失し、足利持氏がこの地を本陣とした永享の乱(室町時代)に再び大兵火の及ぶところとなるが、天正年間(安土桃山時代)に慶雄大徳により9間四面の大本堂や6間四面の大庫裡などが復興され,小田原北条長氏・氏康らの外護の下に発展し,小田原北条氏滅亡後に関東に入国した徳川家康からは特に他の有力大寺院に先駆けて寺領寄進の朱印状とその後の厚い庇護を受ける。江戸時代に「不入」「葵の紋所」を許され,高座・愛甲・大住の3郡に末寺19寺を持つ中本寺(中本山)となって,法談所・古義真言宗関東壇林本寺として興隆を極め、神仏分離(明治元年)までは有鹿神社の別当寺も務める.明治初年の廃仏棄釈の嵐の中で多くの貴重な寺宝も失われ、威容を誇った大本堂や大庫裡などの建物も関東大震災にて現山門を残して全て倒壊したが、順次復興して今日に至る。」「山門」。石灯籠と石碑。参道にはサルスベリの花が。「六地蔵」。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2021.10.07
閲覧総数 724
-
48

茅ヶ崎市の寺社旧蹟を巡る(その32)・下寺尾官衙遺跡群(1/2)
【茅ヶ崎市の神社仏閣を巡る】目次更に「茅ヶ崎北陵高校」の東側の道を進んで行くと、正面角に石碑が立っているのが見えた。石碑、案内板を正面から。近づいて。「七堂伽藍跡」と。更に。「下寺尾寺院跡(伝、七堂伽藍跡)茅ヶ崎市下寺尾字西方このあたりは昔から七堂伽藍跡と呼ばれており、周辺からは古い布目瓦や土器が出土し、建物を支える礎石も多数発見されています。「上正寺略縁起」によると、昔この地に、「海円院」という寺院があって寿永・文治の頃(一一八ニ~一一九〇)兵火によって焼け落ちたと記されています。昭和五十三年七月に茅ヶ崎市史編さん事業の一環として行われた確認調査の結果、瓦の破片、灯明皿として使われた多量の土師器などが出土して、このあたりが古代寺院の跡であることが明らかになりました。平成十二年度から開始された詳細確認調査では、寺院の主体である伽藍域を囲む大型柱穴列などの区画遺構が発見されたことから、一辺約八十メートルに及ぶと推定される方形区画の伽藍域を中心に、七世紀の終わり頃に創建された寺院であることがわかってきました。また、この伽藍域の中では、丁寧に版築した「掘り込み地業」と呼ばれる土地造成遺構が確認され、この部分に礎石建ちの主要な建物があったことが明らかになっています。また、こうした調査によって、銅匙、軸端、墨書土器、香炉など寺院に関連する建物も出土しています。なお、石碑の土台石は当時の礎石を利用しています。」「七堂伽藍跡碑について本碑は、昭和32年(1957)12月15日に七堂伽藍遺跡保存会によって建立されました。保存会には、石碑建立の発起人142名、特別賛助員19名、寄付等に協力された45の市内の商店や会社などが参加していました。碑文には、七堂加藍跡の歴史的説明に加え、建立の趣意が次のように刻まれています。「今回我等が建碑の趣意は是等の貴重な資料の保存と今後研究家の訪れるのを待っ為に他ならない」七堂伽藍跡は、下寺尾官衙遺跡群の一部(下寺尾廃寺)として、平成27年(2015) 3月10日付けで国史跡に指定されその中心部が保存されています。今回建碑60周年を記念し、遺跡保存の足跡を後世に継承するため説明板を設置しました。石碑仕様石質 新小松石 産地 根府川規格 高さ325cm 幅44cm 厚さ24cm揮毫 内山岩太郎(神奈川県知事)碑文 撰文 鶴田栄太郎 書 佐々木孝之製作 石工 殿代忠義」建碑式の記念写真 昭和32年(1957)12月15日下寺尾の「人物」&「民話」紹介。「下寺尾の都市資源紹介「人物」 鶴田栄太郎氏( 1888 ~ 1968 下寺尾遺跡群の一画にある「七堂伽藍跡の碑」建立の中心となったのが、鶴田栄太郎氏です.彼は茅ヶ崎生まれの郷土史研究家で、一生を茅ヶ崎の史跡発掘、研究、紹介活動に尽くしました。伝説の七堂伽藍については、本当なのかどうかや時代者証などで多くの議論があり、結論は将来の『研究』にゆだねられました.彼は、この「七堂伽藍」研究を機に、西久保宝生寺の阿弥陀三尊像の発見、東海道ー里塚は、懐島の碑など数々の句碑の建立、大岡祭の開催など茅ヶ崎の文化財保護活動をはじめ、郷土史小冊子「あしかび叢書」を創刊し、郷土史雑誌「武相文化」などにも積極的に投稿し、茅ヶ崎の史跡・文化財を積極的に紹介し読けました。1968年10月20日、講演を終えた後、「これで今日の講座を終わります」と言い終えるや、隣の人に倒れかかり絶命したと言ういきさつは、終生の研究者を象徴しています.近年「古代寺院( 七堂伽藍跡)」の存在が証明され、国の史跡になるにあたり、草むす「碑」のそばに立ら、大いに喜んでおられることでしよう。こんなに素晴らしい宝を探究し伝えてくださった鶴田栄太郎氏に、茅ヶ崎市民として深く感謝いたします。(増田・富水)」「下寺尾の都市資源紹介「民話」 民話 【七堂伽藍】昔、下寺尾に大きな寺がありましたが、火事で焼けて今はありません.この火事は住職の尼さんの比丘尼が、南港の漁師の苦情に耐えかねて寺を焼いたというお話です.今からハ百年ほど昔、現在の茅ヶ崎北陵高校の南の所に、海円院というお寺がありました。大きな規模ですので近在の人々は七堂伽藍とも呼んでいました。比丘尼は、30歳そこそこで、美しく聡明で気立てがよく、近郷の村人にたいへん慕われていました。比丘尼は空腹で倒れていた乞食の助三の看護をして、寺にしばらく住ませていました。お寺の灯明の灯りのせいで魚が取れないという漁師の苦情に思い悩む比丘尼に、助三は心を痛め、本堂を焼いて姿を消しました。海円院の火歩の後、南湖の海ではもとどおり豊漁が続くようになりました.身代わりになって役人に捕らえられた比丘尼は、詮議を受け、処刑されたとのことです.「茅ヶ崎の民話劇 第一集」編集 茅ヶ崎民話の会(要約 川合)」 【https://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/006/155/vol12.pdf】よりそして更に下寺尾の住宅街を進む。前方にJR相模線の線路が現れた。「下寺尾官衙遺跡群」の上空からの写真を「Google Map」から。右側に「神奈川県立茅ヶ崎北陵高校旧校舎」、左下に斜めにJR相模線は走る場所。そして前方に「下寺尾官衙(かんが)遺跡群・下寺尾西方遺跡」が現れた。「史蹟 下寺尾官衙(かんが)遺跡群」案内板。ここは相模国・高座郡家のあった場所。郡家(高座郡家)・郡寺(下寺尾廃寺)、関連施設の川津(船着場)・祭祀場などが発掘調査で明らかになっている。相模国では2例目とのこと。寒川駅を過ぎ茅ヶ崎駅方面に向かうと左手に『下寺尾官衙遺跡群」の大きな看板が設置されていてこの文字だけはJR相模線に向いているので車窓からも確認できるのであった。以前から気になっていたが、今回初めて訪ねたのであった。案内板が2基、それぞれ詳細に書かれていた。「史蹟 下寺尾官衙遺跡群」案内板が手前に設置されていた。「発見された下寺尾官衙遺跡群は、今から約1300年前のもので、官衙(かんが)とは役所のこと。当時は律令国家と呼ばれる、天皇を中心とした政治がおこなわれていた時代で、国家を国―郡―里という形で統治してい ました。全国は約66か所の国に分かれており、現在の神奈川県は、相模国と武蔵国の一部にあたります。 地方の国には都から役人が派遣されるとともに地方を統治する役所である国府が置かれ、その下の郡には郡衙(郡家)と呼ばれる役所が設けられていました。相模国には8郡が存在しており、現在の茅ヶ崎市は高座(たかくら)郡に該当していることから、下寺尾で発見さ れた官衙遺跡は、相模国高座郡の郡役所の跡であることが明らかになりました。」「相模国の八郡現在の神奈川県は、古代においては相模国と武蔵国の一部に該当していました。このうち相模国は、さらに8郡に分けられていました。」相模国には、足柄上(あしがらのかみ)郡、 足柄下(あしがらのしも)郡、余綾(よろぎ) 郡、大住(おおすみ)郡、愛甲(あゆかわ)郡、 高座(たかくら)郡、御浦(みうら)郡、鎌倉 (かまくら)郡の8郡があり、この中でも高座 郡はその位置や大きさなどから相模国の中心的な郡であったと推定されます。 ここ下寺尾は、郡の役所(郡衙)としては、古い 段階に造営されたと考えられます。「史蹟 下寺尾官衙遺跡群下寺尾官衙遺跡群は茅ヶ崎市下寺尾に所在する西方遺跡と七堂伽藍跡を中心に、香川北遺跡や隣接する寒川町の大曲五反田遺跡、岡田南河内遺跡を含めた複数の遺蹟からなるもので、今から約1300年前に古代相模国高座郡に設置された官衙(役所)を中心とした遺跡群です。本遺跡は比較的限定された範囲に郡家(ぐんけ・高座郡家)や郡寺(下寺尾廃寺)さらには関連する施設(川津)と祭祀場などが発掘調査によって明らかになっており、地方における官衙遺跡の全体像や変遷、立地を知る上で重要であると評価され、平成27年(2015)3月10日に国の史跡に指定されました。」「下寺尾官衙遺跡群周辺の景観推定復元図(平成20 (2008)年作成)(田尾誠敏:構成霜出彩野:画)」下寺尾廃寺(七堂伽藍)全域遺構配置図。「下寺尾廃寺(七堂伽藍跡)」案内「下寺尾廃寺(七堂伽藍跡)下寺尾廃寺では昔から古瓦などが発見されており、昭和32年(1957)には142名の有志が中心となり遺跡の調査と保存を願い「七堂伽藍跡」の石碑が建立されています。昭和53年に行われた確認調査で伽藍域の範囲、主要建物の内容、年代などが明らかになりました。寺院の年代は創建期が7世紀末から8世紀前半、再建期が8世紀後半、改修期が9世紀第2四半期から中ころ、そして寺院廃絶期は9世紀後半と考えられています。さらに10世紀後半から11世紀代にも仏堂が建てられていたと考えられます。」掘込み地業模式図。金堂発見された金堂は丁寧に版築された掘込地業を伴う基壇建物で、周辺からは瓦が多数出土しており瓦葺きであったと思われます。掘込地業とは重量のある建物を建てる部分を掘り下げ、新たに土や粘土などで突き固め堅牢な地盤として安定させる工法のことです。礎石建物(金堂)の掘込み地業(西から)。講堂講堂と考えられる建物は柱が3間×7間の規模を有する大型掘立柱建物で、東西方向に建てられています。この建物には各面に廂が付いており格調の高い建物であることが窺えます。建物は再建期においてもその場所を引き継ぎながら建替えられたと思われます。大型立建物復元図(上)大型堀立柱建物(北から)(下)伽藍域寺院の伽藍域については、大型柱穴列や区画溝によって規模や時期が確認されています。創建期には掘立柱塀によって区画され、不整の方形に囲まれた形であることが、また再建期には築地塀によって一辺78mの正方形に区画されていたと考えられます。区画遺構復元図(築地塀)(上)区画溝と土器集中遺構(北から)(下)区画遺構復元図(掘立柱塀)(上)大型柱穴列(掘立柱塀) (北から)(下)案内板 中央部。「川津と祭祀場小出川河川改修に伴う調査で、川津(船着き場)が発見されました。近くには掘立柱建物が複数並立して建っており、役所に関連する物資の荷揚げや積み出しのための一時保管施設であったと考えられます。時期は8世紀後半から9世紀中ごろと考えられています.また川津が発見された付近からは、人面墨書土器や、皇朝銭、斎串などが出土しており、この場所で水辺の祭祀が行われていたことが明らかになっています。官衙周辺で行われていた穢れなどを祓う神祇祭祀がここでも行われていたと考えられます。」小出川河川改修関連遺跡の河道跡と祭祀関連遺物(「小出川Ⅱ・Ⅲ」より転載一部改変)河道跡と川津(北から) (「小出川Ⅲ」より転載)案内板 右部高座(高倉)郡家郡庁、正倉、館、厨など郡家を構成する建物が明らかになっています。郡家の範囲は区画を示す溝状遺構が発見されており、東西約270mの規模を有していた時期があったと思われます。また、郡家の年代については中心となる郡庁の遺構状況からⅠ期が7世紀末から8世紀中葉、Ⅱ期が8世紀中葉から9世紀前半と考えられています。なお、郡家は台地に配置されており往時は遠くから郡家の存在を知ることができたと思われます。正倉正倉は納められた税を保管していた倉庫で、郡庁北側約100m地点で、東西方向に総柱の高床構造を持つ掘立柱建物が4棟以上並んで建っていました。また、南側には並行して東西方向に2間×12間以上の長い建物があったことも明らかになっています。郡庁郡家の中心となる郡庁は政務や儀式が行われた場所で、規模は東西約66mを測り、中央に位置する正殿は建物の四面に廂(ひさし)が付いていた格調の高いものでした。当初は正殿の北側に後殿、東と西側に脇殿が配置されていましたが、後に塀で区画する形に変化しています。祭祀場みずき地区の区画整理事業に伴う調査では、発見された旧河道から木環、墨書土器、皇朝銭、銅鈴、櫛、さらには漆紙文書などが出土しています。川津付近で発見された祭祀場と比べるとやや仏教的要素が見受けられる内容の祭祀が行われていたことが窺えます。」雑草の生える遺跡の中に防草用?&遺跡保護用シートが貼られた帯状の一角があった。「寺院の伽藍域を区画する遺構寺院西側の区画遺構で、溝状遺構とその中に規則的に掘られた柱穴列が確認されました。創建期のものと想定される堀立柱塀が構築されていたことが明らかになりました。」 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.05.09
閲覧総数 425
-
49

『港・ヨコハマ』を巡る(その20):旧横濱鉄道歴史展示(旧横ギャラリー)
桜木町の北改札西口出口前から横浜駅方面を見る。ーーがこの日・(その20)の散策ルート。「桜木町2丁目交差点」の横断歩道を渡り、旧横濱鉄道歴史展示(旧横ギャラリー)に向かって「東京環状道路」に沿って進む。左側にJR東日本ホテルメッツ(HOTEL METS) 横浜桜木町の看板があった。そして「旧横濱鉄道歴史展示(旧横ギャラリー)」内部に入る。ここシアル桜木町アネックスは1階には「成城石井」、フードホール「KITEKI(キテキ)」、2階に「スターバックス」が出店していた。また1階には旧横濱鉄道歴史展示「旧横ギャラリー」があり、誰でも見学無料なのであった。右窓側に鉄道創業期に使われていた110形蒸気機関車。「鉄道記念物」だと。近づいて。110形は、かつて日本国有鉄道の前身である鉄道院・鉄道省に在籍した蒸気機関車。150形などと共に、1872年(明治5年)の日本初の鉄道開業に際して、イギリスから輸入された蒸気機関車5形式10両のうちの1形式で、1両のみが輸入された。1871年(明治4年)、ヨークシャー社 (Yorkshire Engine Co., Meadow Hall Works) 製(製造番号164)で、国鉄、私鉄を通して日本唯一のヨークシャー製蒸気機関車であった。正面から。主要諸元をウィキペディアより転記。原形と水タンク増大後の値をスラッシュ( / )の前後に示す。全長 : 7,004mm/7,194mm全高 : 3,353mm/3,327mm軌間 : 1,067mm車軸配置 : 2-4-0 (1B)動輪直径 : 1,219mm弁装置:スチーブンソン式基本型シリンダー(直径×行程) : 292mm×457mmボイラー圧力 : 7.7kg/cm2火格子面積 : 0.74m2全伝熱面積 : 51.0m2/51.3m2煙管蒸発伝熱面積 : 46.6m2/46.9m2火室蒸発伝熱面積 : 4.4m2ボイラー水容量 : 1.7m3(1914年版形式図による)小煙管(直径×長サ×数) : 44.5mm×2,565mm×130本機関車運転整備重量 : 22.31t(1909年版形式図による。1914年版では23.01t)機関車空車重量 : 18.84t(1914年版形式図による)機関車動輪上重量(運転整備時) : 15.50t(1909年版形式図による。1914年版では15.88t)機関車動輪軸重(第1動輪上) : 8.48t(1909年版形式図による。1914年版では8.61t)水タンク容量 : 2.01m3/2.34m3(増大後は推計値)燃料積載量 : 0.56t機関車性能シリンダ引張力(0.85P): 2,090kgブレーキ装置 : 手ブレーキ、蒸気ブレーキ(後付け)1961年(昭和36年)に鉄道記念物に指定され、鉄道開業90周年を記念して開設された東京都青梅市の青梅鉄道公園に移され、同公園で車体を切開されたままの状態で静態保存されていたが、2019年(令和元年)8月31日]をもって展示を終了し、青梅鉄道公園から搬出された。2020年(令和2年)に入りここ、神奈川県横浜市の桜木町駅南側で新たに開業した複合ビル「JR桜木町ビル」の1階にある商業施設「CIAL桜木町 ANNEX」の「旧横濱鉄道歴史展示(通称・旧横ギャラリー)」に移設し、切開部分の復元が施行されたうえで英国の資料や専門家の協力を基に作成された中等木造客車の実物大レプリカなどの資料と共に設置され、6月27日の新南口の供用開始とともに公開されたのであった。「帰ってきた110形機関車」展示の実物機関車は、1872年の鉄道創時に英国から輸入された蒸気機関車です。この地に荷掲げされて以来、日本各地で活躍し、2020年に再びここへ戻りました。「長き航海を経て日本に到着、ここ横浜の地に陸揚げされた。」「鉄道創業時の機関車」1871 (明治4)年、英国からス工ズ運河(1869年開通)を経由し、横浜港に5種10両の機関車が到着しましたこれらの車両は、この地に存在した横浜停車場構内の作業場で組み立てられました。「受け継がれる鉄道への夢」憧れの汽車とモノづくり明治期から、蒸気機関車の疾走する力強い雄姿、そして汽笛の音と煙は、子供たちの興味と憧れの対象であリ、科学の扉を開く教材でした。「憧れの汽車とモノづくり明治期から、蒸気機関車の疾走する力強い雄姿、そして汽笛の音と煙は、子供たちの興味と憧れの対象であり、科学の扉を開く教材でした。」「技術者への道昔の製図器・蒸気気関車図面・製図教本等明治初期から政府は日本人技師の育成に努め、その結果、明治10年代には日本人技師設計による建造物や、同26年には国産の蒸気機関車を造るまでになった。以降、産業立国として数多くの優秀な技術者か登場した。」「夢を載せて走る!鉄道玩具造らせて遊び、なりきって楽しむ・・・いつの時代も変わることがない、鉄道玩具に投影する想い」エスカレーターで2Fに上がると、正面には「STARBUCKS」があった。2Fから、「110形機関車」を見る。廻り込んで。客車を見る。エスカレーターを下りながら。ボイラー部分のバルブ、配管。ここが「運転台」であったのであろう。レールと車輪。動輪直径は1,219mm (4ft) 、のちには1,245mm (4ft1in) とされている。車軸配置2-4-0 (1B) で2気筒単式の飽和式タンク機関車である。同時に輸入された10両のうちで、最も小柄な機関車であった。弁装置は当時多かったスチーブンソン式、安全弁はサルター式で、ボイラーの中央上部に蒸気ドームを有している。運転台は、前面に風除けを設け、屋根は4本の細い鋼管により支持されるのみで、後部は完全に開放されていたが、後に後部にも丸窓を設けた風除けを整備している。水タンク高さも原形では低かったが、1887年(明治20年)から1892年(明治25年)の間に5インチ (127mm) ほど上に継ぎ足している。枕木が全く見えないほどの砂利が敷かれていたのであったが・・・。現在の線路では枕木の上部は見えるのだが・・・。車輌の速度が上昇し、上部の砂利の飛散が発生するのが理由だったのか?「双頭レール1872 (明治5 )年の鉄道創業時は、英国から輸入した錬鉄製の双頭レールが使用されました。双頭レールは裏返して再使用する予定でしたが、摩耗や腐食などにより再使用されず、1879 (明治12)年から順次、鋼鉄製の平底レールに置き換えられました。このレールは1873 (明治6)年、英国のダーリントンで製造され、新橋~横浜間または大阪~神戸間にて使用するために輸入したものと考えられています。後に日本石油(株)柏崎製油所(新潟県)で使用され、地元有志の尽力により長年大切に保管されてきました。レールには標記(ロールマーク)が付せられており、製造者・製造年・発注者の情報が読み取れます。下の拓本は本展示のロールマークを縮小表示したものです。●重量:60lb/yd(29.8kg/m) ●レール1本の全長:24ft(7.32m)」機関車に連結されている客車は、イギリスから輸入した当時の客車を再現しているのだと。前後にデッキを有する中央通路式で、室内左右にロングシートが配置されていた。「鉄道創業時の中等客車(再現)日本に輸入された客車は、上等車1 0両、中等車40両、緩急車8両の計58両で、全て英国製でした。外観や車内の構造は上等車、中等車ともにほほ同じで、両端に出入口を兼ねたオープンテッキがあり、車内は中央通路式となっています展示の客車は、鉄道開業期にM.モーザーが撮影した、横浜停車場に留置中の車両写真、英国製古典客車図面、車両形式図等の記載寸法を参考に、中等客車として再現しました。木造の客室部、車輪脇の板バネは新造し、本来は金属製である緩衝器は、木地をろくろ挽きで製作。他の国内で入手困難な金属部品は英国から輸入した古物を使用しています車輪の外観は、創業期に用いられ乗り心地に優れているとされる、木製の「マンセルホイール」をイメージし、その造形を施しました。室内照明(オイルランプ)は、古文献や英国製のものを参考に電気式で再現しています。色彩は、当時の浮世絵、M、モーザー撮影写真のコントラスト、そして昔の英国車両を参考に配色しました●客車サイズ:全長7,630mm(緩衝器含む) 全幅約2,21Omm (客室側壁部) ●定員: 24名」壁面パネルや明治初期の横濱停車場と街の風景を再現したジオラマなど鉄道発祥の地にちなんだものを多数展示。鉄道ファンならぜひ一度は足を運びたいコーナーでは。「最初の客車と明治のお客様」「創業時の客車と出札新橋~横浜間29kmにおいて、創業時の時刻表では1日9往復で、全線所要時間は53分でした。当時の人々にとって、馬より速い乗り物で移動することは大変な驚きでした。」「創業時の客車客車は全て英国から輸入され、その数は上等車10両(定員18名、サロン客車の定員12名)、中等車40両(定員22名または24名)、貨物緩急車8両の計58両であった。中等車のうち、26両は鉄道開業時までに下等車へと改造された。模型は明治の資料や洋世絵、写真を元に、イメージ、再現したものである。」「鉄道創業期の切符仮開業時の横浜~品川間の運賃は上等1円50銭、中等1円、下等の料金が50銭で、4~12才の小児は半額だった。以下略。」「旅の小物と駅前送迎明治期、鉄道に乗って旅する人々のスタイルは江戸時代の風情を残しながらも、あらゆる面で利便性が追求され、現代へとつながる進化が始まりました。」ホームに停車中の写真。「旧横濱停車場~乗降場の演出本施設では、開業時の汽車の発車情景をイメージし、音と光による演出を行なうています。実際には当時の横浜と新橋の汽車出発時刻は下記の通りで、1日9往復、片道53分の行程でした。( 12 : 00と13 : 00発は無し)■1872 (明治5 )年10月、開業期の汽車発車時刻(横浜、新橋共通) 08 :00、09: 00、10: 00、11 : 00、14 : 00、15 : 00、16 : 00、17 : 00、18 : 00列車の時刻が迫ってくると、その5分前と2分前に振鈴(鐘)が鳴らされました。駆け込んで来る乗客も多く、石貼りの停車場内には下駄などの足音が響いていました。機関車の運転台では動力源の蒸気圧を上げるため、シャベルで石炭を火室に投炭し、出発の準備をしています。客が乗り終えると、係員が安全のため客室ドアを施錠しました。定刻に駅長が手笛の合図を発すると、汽笛一声!蒸気と煙を吐きながら、汽車は一路、新橋方面に動き出すのです。」「道床の砂利創業時の道床は主に川砂利が利用され、焼土・細砂・砕石も用いられました。道床(砂利部)の高さはレールの外側はレール上面まで、内側はレール上面から約5cm下までで、レールを固定するチェアや枕木は砂利に覆われていました。現在のように砂利が枕木の上面までとなったのは1906 (明治39 )年以降です。」明治初期の横濱停車場と街の風景のジオラマ。別の角度から。「明治初期の横濱停車場と街の風景1872 (明治5 )年に開業した日本初の鉄道駅である横浜停車場は、外国人居留地に隣接する野毛浦の海を埋め立てた現在のこの場所に存在しました。明治初期、厳重な柵に囲まれた広大なこの鉄道施設は、江戸時代からの生活感が漂う対岸の野毛の街並みとは対照的でした。柵越しに当時の人々の目に映る機関車や客車、モダンな建築、設備、そこに行き交う洋装の職員や乗客たちの様子は、まさに西洋の科学技術・文化を知るショーウインドウとなりました。明治初期の庶民にとって停車場を利用し、汽車に乗車する事は大きな憧れであったことでしよう。以来、この地は長きにわたって日本の産業や文化の発展を支えていく、重要な場所となっていくのです。」横濱停車場の駅舎をズームして。「横濱停車場構内案内圖 明治初期の施設配置★現在地 このジオラマおよび案内図の位置①駅本屋 1871 (明治4)年竣工。新橋駅舎とほぼ同じ造り。②乗降場 長さ90.9mのプラットホーム。③造車庫 貨客車用車庫。修繕や組立てにも使用された。④荷物積所 貨物や小手荷物の積み卸しが行われたと思われる。⑤荷物庫 構内において最大規模の面積を持つ建物。⑥三ツ車台 貨物車用の転車台。隣の線路への移動が可能。⑦鍛冶所 車両修繕などの金属材料の加工を行なっていた。⑧機関車庫 機関車を収納。一般的な扇形でない特殊な形状。⑨転車台 蒸気機関車の方向を転換させる装置。直経12m。⑩給水塔 蒸気機関車に水を供給するための貯水設備。⑪石炭渡所 蒸気機関車に石炭を積み込むための台状の足場。⑫倉庫 最初に建てられ、機関車等の組立てを行なった建物。⑬石炭庫 蒸気機関車に使用するための石炭貯蔵施設。⑭外国人官宅 上級職(技師など)以外の、外国人作業員の官舎。」「明治の鉄道建設と発展に貢献した人々お雇い外国人の顔ぶれ明治政府は殖産興業と富国強兵を推し進めるため、欧米の技術・学問・制度の導入を決定し、英国をはじめ、大勢の外国をを雇用しました。中でも鉄道関係者は多かったといわれます。・エドモンド・モレル・トーマス・R・シャービントン・ウォルター・フィンチ・ページ・フランシス・ヘンリー・トレビシック鉄道建設に尽力した日本人鉄道導入の成功と、その後の飛躍的な発展は、政府の役人をはじめ、実業家・技師・職工・職員に至る、多くの日本人関係者による献身的な努力の賜物でした。・井上 勝・高島 喜右衛門・佐藤 政養・三村 周」1階に下りて、蒸気機関車と客車の連結装置。「銘板」と「案内板」。「鉄道記念物 110形蒸気機関車 1961(昭和36)年10月14日指定」。「110形蒸気機関車(110号)1871(明治4)年、英国のヨークシャー・エンジン社の製造で、1872 (明治5)年の鉄道創業時に「10号機関車」として新橋、横浜間で使用され、後に「3号機関車」と呼ばれた日本で最も古い機関車の一つです。1909 (明治42)年、「110号」に名を改められ、1918 (大正7)年まで各所て活躍し、廃車後は車体の一部を切開ののち.大言工場内にあった「鉄道参考品陳列所」て技術者育成の教材として展示されました。1961 (昭和36)年には「鉄道記念物」に指定され、翌年から2019(令和元)年まで青梅鉄道公園で保存展示されました。その後、大宮工場にて溶接を使用しない工法で切開箇所を閉腹し、錆の除去や破損箇所の修復を行い、本機の晩年頃の姿を再現しました。(形状が不明な箇所は資料が残る明治初期の形状を参考にしました。)そして、2020 (令和2)年、旧横濱停車場であるこの地へ戻りました。●機関車全長:7,214mm●動輪直径: 1,245mm●動輪配置:1・B・0●シリンダ直径x 行程: 299x 432 mm●機関車重量:運転整備23.04t 空車18.85t●購入時価格:2,600ポンド(船賃含む)●使用蒸気圧: 8. Okg/cm2」「移りゆく野毛山からの景色桜木町駅近くの野毛山は、昔から横浜の風景を一望できる景勝地でした。人々は幕末から近代にかけて変貎する街の姿をここから展望してきました。」「初期の横濱停車場構内とその界隈1923(大正12)年9月1日、関東大震災発生。」「鉄道創業時の信号や設備日本で最初の鉄道は、様々な技術や車両の導入だけでなく、その運用を安全かっ正確に行なうための仕組みも英国に倣って整備されました。」「ステンショ周辺の名所と施設外国人居留地に隣接した横浜停車場の周辺には、昔からの名所とともに、他に先駆けて設置された最新の施設がありました」鉄道創業期の遠方信号(再元)。「鉄道創業期の遠方信号機(再現)これは、日本初の鉄道信号機を実物大で再現したものです。創業当時の信号機は、英国製で「相図柱」と呼ばれ、木造でした。相図柱は高さ約9.3mの「ホームシグナル」(場内信号機)と、高さ約6.9mの「ジスタントシグナル」(遠方信号機)の2種類があり、新橋~横浜間ではこの腕木式信号機が計16基設置されていました。列車への走行指示は、腕木の角度やランプの光の色で示し、腕木垂直(夜間白色光)は「進行」、腕木水平(夜間赤色光)は「停止」を意味しました。この信号機は設置当初、ランプの昇降装置が装備されておらず、はしごを登って設置、点火していました。」外に出ても、展示品が外に向かって。「初代鉄道建築師長 エドモンド・モレル」。「エドモンド・モレル」。窓ガラスが反射して・・・。「旧横濱鉄道歴史展示この地に存在した、日本初の鉄道駅「横濱停車場」の様子と横浜~新橋間を駆け抜けた機関車や客車、そして新たな時代を「鉄道」という文明の利器によって切り拓いた、明治の先人達の活躍を紹介します。」「鉄道創業時に使用され蒸気機関車展示の110形蒸気機関車について1871 (明治4)年 英国にて製造され、日本に輸入。1872 (明治5)年 鉄道創業時、10号として運用。1876 (明治9)年 機関車の番号を3に改番。1909 (明治42)年 形式称号改正で110形となる。1923 (大正12)年 廃車(諸説あり)後、大宮工場に展示。1961 (昭和36)年 鉄道記念物に指定。1962 (昭和37)年 青梅鉄道公園へ移転。2020 (令和2)年 この地へ移り、屋内展示となる。」「英国から輸入された最初の客車再現された創業時の客車輸入された客車は、上等車10両(定員18人)、中等車40両(定員22か24人)、荷物緩急車8両の計58両でした。構造は前後にデッキを有する中央通路式で、室内左右にロングシートが配置されていました。開業時に中等客車を改造し、26両を下等客車としました。展示の客車は英国や、明治期の資料を元に再現した中等客車です。」「この地に存在した日本初の鉄道駅「横濱停車場」旧横濱停車場と桜木町駅1872 (明治5)年 横濱停車場がこの地に開業。1915 (大正4)年 横浜駅は移転、桜木町駅に改名。1923 (大正12)年 関東大震災にて初代駅舎消失。1927 (昭和2)年 2代目桜木町駅舎が完成。1964 (昭和39)年 根線開通に伴い、駅舎を改築。1989 (平成元)年 3代目駅舎は高架下駅となる。」現在の地図に重ねた鉄道創業期の横濱停車場。 ・・・もどる・・・ ・・・つづく・・・
2022.08.31
閲覧総数 575
-
50

ナスカの地上絵 新発見と
『山形大の研究グループは8日、世界遺産「ナスカの地上絵」で知られる南米ペルーのナスカ台地とその周辺で、新たに168点の地上絵を発見したと。研究グループが発見した地上絵は、今回の発表分を含め、計358点に上る。』とのニュース報道一昨日・12月10日(土)のテレビで見ました。以下の写真はテレビ画面をカメラで撮影したものです。同大ナスカ研究所副所長の坂井正人教授らの研究グループが2019~20年にドローンを活用して現地調査を行い、168点の地上絵を確認した。16~18年の調査でも142点の地上絵を発見しており、分布の傾向がある程度明らかになっていたことから、ドローンを用いて計画的に調査した。今回見つかった地上絵は、人間や鳥、ヘビなどの動物が描かれており、絵柄の特徴から紀元前100年~紀元300年頃に作られたと考えられる。最も大きいもので全長50メートル以上あったが、ほとんどが10メートル以下の小型のものだという。下の写真は分かりやすくするため線を加えたもの(山形大学提供)とのこと。新発見のナスカの地上絵は『かわいい人型』。『人形』。『人形』。『人と首』と。『鳥』。20m以上の大きさと。『ネコ』。10mほどの大きさと。『ヘビ』。これも10mほどの大きさ。『ナスカの地上絵』の配置図。以下の写真は、私が2009年にペルーの『ナスカの地上絵』👈リンク を訪ね、『遊覧飛行』にて撮影したものです。『ハチドリ』。『コンドル』。『犬』。『猿』。ナスカの地上絵が描かれた年代は今からおよそ2000年前、パルパの地上絵は更に古く今から3000年ほど前に描かれたものと言われている。地上絵にはサル、リャマ、シャチ、魚、爬虫類、海鳥類が描かれ、ナスカ式土器の文様との類似点が指摘されてきた。ナスカの地上絵は何のために描かれたのか?下記の如き説があると『ネット』👈リンク には。 1.「カレンダー説」 2.「雨乞い儀式説」 3.「巡礼に関する役割説」 4.「水のありかを示していに説」 5.「権力者の埋葬説」 6.「UFOの発着場説」 1.「カレンダー説」 ナスカの地上絵を構成する直線には、意図的に太陽と星の動きを表しているものが あり、農業用のカレンダーとして描かれたという説。 この説だと、他の地上絵の線はいらないですし、何のためにあれほどまでに 大きな絵を描いたのかも謎 と。2.「雨乞い儀式説」 ナスカは地球上で有数の乾燥地帯なので、雨乞いのために描かれたという説。 地上絵の中にクモを描いたものがあり、クモは雨を象徴するものだったと言われている。 また、古代ナスカ人が雨乞いの儀式に使っていた貝殻(エクアドル産)が地上絵周辺で 多数発見されている。 ナスカの地上絵には「水源を確保する」といった実用的な機能はないので、古代の人たちが 宗教的な意味合いで地上絵を描いた可能性はあると。 ただし、この説だと雨とは関係のない植物や動物などの地上絵をなぜ描いたのか? という 謎は残る と。3.「巡礼に関する役割説」 古代の人々はナスカの地上絵を歩いて渡り、聖なる場所に向かったという説。 もしかしたら、巡礼地に向かうための目印としてや途中で儀式を行うポイントと して地上絵が機能していたのかもしれない と。4.「水のありかを示している説」 ほとんど雨が降らないナスカでは、地下水に頼って生活する必要がありました。 そのため、水脈や水源を示す目印としてナスカの地上絵を描いたという説もあります。5.「権力者の埋葬説」 ナスカ文化では権力者が埋葬された際、地上絵をひとつ描いたという説。 ナスカ文化では死者は太陽に帰るとされていて、太陽に向けて地上絵を描いた のだとか。6.「UFOの発着場説」 ナスカの地上絵は宇宙人によって描かれ、UFOの発着場になっていたのでは? という説。 ナスカの地上絵のひとつに宇宙飛行士(もしくは宇宙人)を描いたような絵もあります。 確かにこの説なら、たやすく200メートルを超える地上絵を描くことができたでしょう。 地球を訪れることができるほどの科学技術を持った宇宙人 と。現時点では、有力な説はあれど、決定的にこの説が正しいと証明されたものはない。おそらく、ナスカの地上絵はひとつの目的でつくられたのではなく、複数の目的でつくられたのだと。また、時代の移り変わりや気候変動によって、ナスカの地上絵を描く目的が変わった可能性もあるのでは と。
2022.12.12
閲覧総数 982
-
-

- ちいさな旅~お散歩・日帰り・ちょっ…
- 岐阜城に行ってきました・・・(^o…
- (2025-11-28 19:52:59)
-
-
-

- 英語のお勉強日記
- ビットコインが101,000ドルから106,0…
- (2025-11-28 15:59:05)
-
-
-

- 国内旅行どこに行く?
- 島根県立美術館
- (2025-11-28 22:48:24)
-







