PR
X
Comments
Freepage List
Keyword Search
▼キーワード検索
テーマ: 最近、読んだ本を教えて!(24653)
カテゴリ: 近代文学
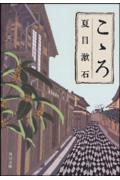
前に読んだのは二十年以上まで、大まかなところ以外はすっかり忘れていた。
「先生」と出会った時のことを語った文章ですでに「先生が亡《な》くなった今日になって」(p15)とあり、読者には、この「先生」はいずれ死ぬのだ、ということが提示されている。
小説の中での「現在」は、主人公が列車の中で手紙を読んでいる時であるようだ。
以前は、なんとなく、「私」は「K」を失うことをおそれて「お嬢さん」に求婚したのかと思っていたが、読み直すとそうではない。純粋に「お嬢さん」を自分のものにしたかったのだ。
内容もさることながら、言葉が興味深い。
その代表が「寂しい」。
「ちっとも寂《さむ》しくありません」「うちほど寂《さむ》しいものはありません」(p23)
「家《うち》はまた寂《さみ》しくなる」(p112)
「寂《さむ》しいからもっといてくれ」(p115)
「無人で寂《さむ》しくって困るから」(p158)
「無人で寂《さむ》しいから」(p169)
「一人で寂しくってしかたがなくなった結果」(p256)
という具合で、「さみしい」「さむしい」はあっても「さびしい」はないようだ。最も、どこまで漱石自身がルビを振ったのかはわからないが。
「その言葉の耳ざわりからいうと」(p45)では「耳ざわり」が「耳障り」とは違う意味で使われている。
主人公は漱石と同じく、近代的自我を持ち、前近代的な自我の持ち主とは合わない。
「父の無知から出る田舎《いなか》臭いところに不快を感じだした。」(p94)
「私は田舎の客がきらいだった。(中略)私は子供の時から彼らの席に持するのを心苦しく感じていた。」(p99)
「学問をさせると人間がとかく理屈っぽくなっていけない」(p100)という父親の、主人公への不満は自我のありかたの違いによるものだ。
「私は兄に向かって、自分の使っているイゴイストという言葉の意味がよくわかるかと聞き返してやりたかった。」(p128)というところに、自分と同じように教育を受けた兄が、前近代的な自我の持ち主であることへのいらだちがあらわれている。
「ページさえ切ってない」(p173)は、洋本は袋とじになっていて、自分で切らなくてはならなかったということだろう。
「自分の愛人とその母親」(p241)の「愛人」は現代とは意味が異なる。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[近代文学] カテゴリの最新記事
-
「文鳥・夢十夜」 【夏目漱石】 2011.11.17
-
「暗夜行路」 【志賀直哉】 2010.10.28
-
「日本文壇史 23 大正文学の擡頭」 【… 2006.09.07
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
Category
カテゴリ未分類
(527)江戸時代を知る
(137)時代小説・歴史小説
(111)岡本綺堂
(10)中国関係(漢字・中国文学)の本
(70)日本の古典
(59)近代文学
(50)民話(伝説・昔話)
(31)民俗学・社会風俗・地誌・歴史・博物学
(45)欧米露の本
(57)ミステリ
(20)その他の読書録
(272)気になる言葉・文字
(369)PC・IT関連
(251)目についたもの写真館
(234)旅行・観光・名所・レジャー・おでかけ
(683)プロレス
(271)特撮・アニメ・SF・マンガ
(340)時代劇(映画)
(179)時代劇(テレビ)
(259)その他の映画
(535)芸能・テレビ
(521)フォークソング
(49)野菜作り
(105)教育関連
(54)心・体・健康・病気・障害
(229)マス・メディアにつっこみ
(103)気になるニュース
(88)アウトドア
(63)飲食店
(77)Shopping List
1枚までネコポス発送可能【1枚までネコポス対応】【お買得】04804 ストレッチライトメッシュベスト S-5L シンメン ベスト ストレッチ メッシュ 軽い 3シーズン 作業服 作業 アウトドア 釣り
純正品よりお安く純正の機能が充実。パナソニック ブルーレイ レコーダー リモコンN2QAYB001171 N2QAYB001087パナソニック ディーガ リモコン ブルーレイ N2QAYB000994 N2QAYB000993 N2QAYB001056 N2QAYB001071 N2QAYB001172 N2QAYB001055 N2QAYB001142 N2QAYB001148 N2QAYB001044 N2QAYB001086 N2QAYB000995 Panasonic DIGA 代用リモコン REMOSTA
タテ型洗濯機 5KG 6KG 7KG 5.5KG 5キロ 6キロ 7キロ 5.5キロ ステンレス洗濯槽 手動水位設定 洗濯コース切替 予約洗濯機能 柔軟剤自動投入 糸くずフィルター 給水ホース 排水ホース【期間限定5%OFFクーポン 9/8 10:00まで】 洗濯機 6kg 全自動洗濯機 一人暮らし 1人暮らし コンパクト 引越し 縦型洗濯機 風乾燥 槽洗浄 凍結防止 小型洗濯機 残り湯洗濯可能 チャイルドロック マクスゼン MAXZEN JW60WP01WH PB00003 エクプラ特選
【送料無料】ウルトラマン青春記
南方熊楠
純正品よりお安く純正の機能が充実。パナソニック ブルーレイ レコーダー リモコンN2QAYB001171 N2QAYB001087パナソニック ディーガ リモコン ブルーレイ N2QAYB000994 N2QAYB000993 N2QAYB001056 N2QAYB001071 N2QAYB001172 N2QAYB001055 N2QAYB001142 N2QAYB001148 N2QAYB001044 N2QAYB001086 N2QAYB000995 Panasonic DIGA 代用リモコン REMOSTA
タテ型洗濯機 5KG 6KG 7KG 5.5KG 5キロ 6キロ 7キロ 5.5キロ ステンレス洗濯槽 手動水位設定 洗濯コース切替 予約洗濯機能 柔軟剤自動投入 糸くずフィルター 給水ホース 排水ホース【期間限定5%OFFクーポン 9/8 10:00まで】 洗濯機 6kg 全自動洗濯機 一人暮らし 1人暮らし コンパクト 引越し 縦型洗濯機 風乾燥 槽洗浄 凍結防止 小型洗濯機 残り湯洗濯可能 チャイルドロック マクスゼン MAXZEN JW60WP01WH PB00003 エクプラ特選
【送料無料】ウルトラマン青春記
南方熊楠
© Rakuten Group, Inc.










