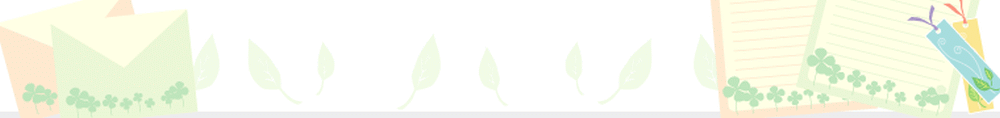-
1

ジャパン ブルー
先日、呉服屋さんから届いたDMの中にありました。ジャパン ブルー藍色づくし青は藍より出でて藍より青しという古いことわざがあるように藍は昔から常に私たちの生活の中にあった人類最古の染料です。また藍は万葉集にも謳われているように、古来より憧れの色として愛用され江戸期に入りますと木綿の栽培とともに藍染が全国に広がり、藍は庶民の労働着から高級な衣装まであらゆるものに染められました。明治期には暮らしの基本色になった紺色の魅力に驚嘆した外国の人々がこの藍の色を「ジャパンブルー」と呼ぶようになりました。そして日本人は藍の生み出す多くの色相に名称をつけ分類して愛してきました。瓶覗(かめのぞき)、浅葱(あさぎ)、縹(はなだ)、納戸(なんど)、紺(こん)等々と。けれどもこうした豊かな色の文化は科学染料の導入や急な生活環境の変化のもとに私たちの周りから姿を消してしまいました。青、藍色といってもこのように細かく分けられています。いつもはDMはそのままゴミ箱へ・・・ですが、今回のこの写真は、興味深くしまっておきました。この本は、そのお店においてあったのをみて、読んでみたいと思って楽天ブックで買いました。加賀友禅、西陣織、献上博多織など、全国を代表する染めと織りの産地を作家の立松和平氏が訪ね、伝統を受け継ぐ職人たちを紹介する紀行エッセイ。登場する職人には人間国宝級の職人も多く、着物愛好家は必見。 ↑↑とありますが、着物を着る人ばかりではなく、伝統の手作業のすごさというか、すばらしいことに感嘆!畑で綿を作る。桑の木を育てて蚕を育て、自然の染料を使って染める。残念なことに、この伝統を引き継いでいく人が少ないのです。今日の収穫です。茄子・・・1個、ピーマン・・・10本、サラダピーマン・・・2本
2009年06月11日
閲覧総数 627
-
2

四条流包丁式
四条流包丁式を見てきました。 ●日本料理の祖神(ツール) 日本料理の故事を調べますと、十二代景行天皇の御代に磐鹿六雁命(いわかむつかりのみこと)の勅命により、初めて大膳職として大御食(おおみやけ)の御膳部を創立しました。やがて、九世紀の藤原時代に光孝天皇の御代に四条山陰中納言藤原政朝が大膳職を継いだ際、古来の方法と海外の料理法を広く取り入れ、四条流という料理方法を確立しています。同時に、豊漁・豊作を天地に感謝する方法として、真魚箸(まなばし)と包丁刀(ほうちょうとう)をもって、清らかに包丁さばきする形式を定めていますが、これが四条流包丁式の始まりです。そのため磐鹿六雁命料理の祖神であり、四条山陰中納言が日本料理の中興の祖となっております。したがって、四条流が日本料理の本流であり、その後、大草・園部・進士・生間(いかま)等の緒流が分派ししていますが、現在では、東京は主として四条流、関西では生間流が相当の地番を占めているようです。という説明もありました。鯉を切り分けるのに手で触れないで、すべて箸と包丁だけでするのです。切り方は沢山あるそうです。(聞いてきたのに、忘れてます。)映画「武士の一分」でも、ちらっとこの四条流の包丁さばきがでてました。なんでも、つぶ貝をあのように包丁で切ることはないそうですが・・・今回のものではありませんが、ここに動画が見られるところがありました。千倉町商工会ホームページから・・・動画で見る包丁式ちょっと長いですが、時間があったらごらん下さい。
2007年05月20日
閲覧総数 320
-
3

アロエの花芽が…
楽しみにしてたアロエの花芽が~ 雪のせいで、こんなになっちゃいました。 もちなおしてくれるかな~?
2005年12月21日
閲覧総数 5
-
4

寺山修二X美輪明宏・・・ワールド
美輪明宏「毛皮のマリー」寺山修二が美輪明宏のために書いた伝説的名作を8年ぶりに再現!ゴージャスな美貌の男媚・マリーと、外界を知らずに育てらてた絶世の美少年・欣也との妖しくも哀しい近親愛と近親憎悪の物語この世界は理解できませんでした幕開けは・・・「鏡よ鏡よ鏡さん。この世で一番美しいのはだれかしら?」毛皮のマリーは入浴中。そこへ執事が入ってきて・・・脛毛と腋毛を剃ってもらう一緒に暮らしているのは、美少年「お母さんとお呼び!」と言っているが、このマリー、男色・女装の麗人出演者はすべて男性。途中、裸の男性のラインダンス(?)が・・・幻想的な(?)展開で???よくわからないまま、終わってしまいました。
2009年06月05日
閲覧総数 234
-
-

- 美味しいお店を教えて!
- EXPO2025 大阪・関西万博②*
- (2025-10-14 12:33:18)
-
-
-

- 取り寄せ美味しい物
- 10.14 20時~お買い物マラソン④
- (2025-10-14 10:19:17)
-
-
-

- 朝食メニュー
- 20251014火☀️朝食
- (2025-10-14 07:59:59)
-