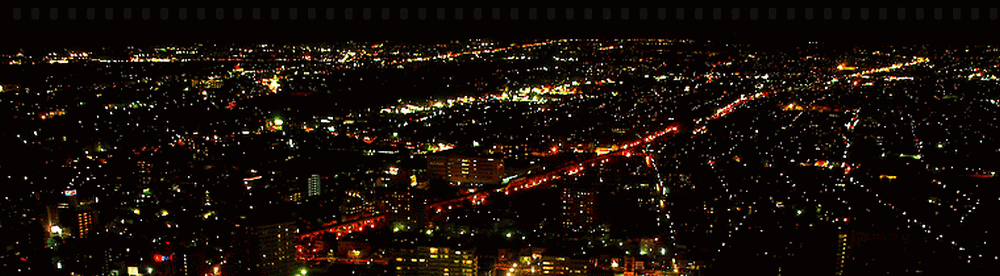PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
まだ登録されていません
Comments
コメントに書き込みはありません。
Freepage List
カテゴリ: 研究会発表
実際、技術の未熟な「下手な役者」を「名優」と呼ぶことはできません。この場合の「名」という修飾には、「他の者が目指すべき優れた」という意味が含まれていると思います。技量の乏しい演技者を名優と呼ぶことは、まずないでしょう。
では「良い役者」というのはどうでしょうか。技量が不足していても「良い役者」と呼んで良い演技者はかなりいます。しゃべりが滑らかでないとか、役の変化があまり見られない人でも、「良い役者」と呼ばれます。大滝秀治さんなんか、そうかなと思います。
「うまい」とは言われないが、「良い」と言われる演技者は、映画やテレビの世界に多く登場しているように思います。典型は高倉健さんでしょうか。「スター」と呼ばれる人の多くは、この傾向がありそうです。舞台人には「スター」はあまりいませんね。おそらく「松井須磨子」が最初の舞台の大スターだと思いますが、彼女の演技がうまかった、という評は聞きません。
一方で、「あの人はうまいけれども、いやな演技をする」とか、「演技はうまいけれど、好きじゃない」と言われる演技者も多くいます。いわゆる「くさい芝居」をする人は、多くこんな風に言われます。こういう演技者を「名優」と呼ぶ事はためらわれます。
そうすると、「うまい役者」でなおかつ「良い役者」ということが、「名優」の条件といえるように思われてきます。つまり、高い演技の技術を持ち、かつ観客がその演技者(の演技)にすなおに共感できる役者が、「名優」と呼ばれて良いということでしょうか。
では「巧い役者」であり、かつ「良い役者」である、つまり技術と観客からの共感という、別の概念のものを同時にもつということはどういうことでしょう。ここで、「演技」とは何かを考える必要があると思います。
わたしの結論を先に述べますと、「演技」とは舞台の上で作り出される劇世界の中で、一人の確固たる人間像を、確かに描き出すことです。その人物を、人間として生きさせることです。
朗々と名調子を聞かせるとか、運動能力が高くて身のこなしがしなやかであるとか、そうしたことは望ましい技術ではありますが、それができるから名優であるとは決して言えません。
確かに、古典劇の時代には、こうした技術は名優の条件、というよりも俳優のスタンダードな技量でした。イギリスの俳優であれば、シェイクスピア劇の台詞がしゃべりこなせること、フランスの俳優であれば、詩をしっかりと語れることは、俳優と認められるための第一条件でした。今もそうでしょう。
しかし名優であるためには、そうした技術の上に、舞台の上で生きられること、明確な人間像を描き出す力をもっていなければなりません。それが英雄であろうと、普通の人間であろうと、演劇的存在として、人々が観るに足る人物としての内容を持っていなければなりません。舞台にただ出ているのではなく、存在していなければならない。その人物に現実性が伴わなければならないのです。頭の中で作られたとしか見えない抽象的な存在ではなく、具体的な人間です。
すると、「名優」がうまれなくなった理由は、舞台でそうした「人間」を描き出すことが難しくなった、その能力が無くなってきた、ということになりそうです。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.07.24 09:00:08
[研究会発表] カテゴリの最新記事
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか、(続2… 2019.08.03
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか。(続1… 2019.08.02
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(10) 2019.08.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.