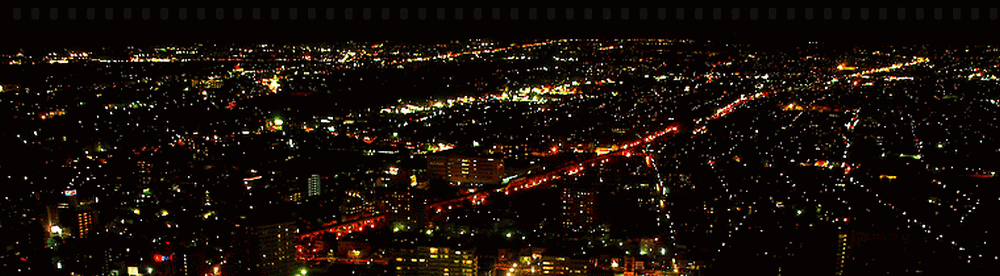PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
まだ登録されていません
Comments
コメントに書き込みはありません。
Freepage List
カテゴリ: 研究会発表
その原因は、劇作家、演出家、演技者、そして批評家に、それぞれあると思います。
劇作家は、作品の中に存在官をもつ人物を描き出せなくなった。
演出家は、自分を目立たせようと突飛な技法を好むようになった。
演技者は、舞台演技の基礎を身につけず、映像演技を正しいと思い込み、またあやまった「自己表現」に走るようになった。
批評家は、正しい鑑賞眼をもたず、自分の好みの劇団ばかりをほめるようになった。
ということだと考えます。
名優がその力を発揮するためには、彼が創造するべき人間が戯曲に登場していなければなりません。古典劇の時代には、シェイクスピア劇に見るように、独特かつ強烈な主人公たちが登場し、各時代の名優たちがそれぞれに優れた人物造型をしてきました。近代劇においても、ノラで『人形の家』を、ラネースカヤ夫人で『桜の園』を、ウィリー・ローマンで『セールスマンの死』を、ブランチ・デュボアで『欲望という名の電車』を思い浮かべます。その登場人物たちによって芝居を語ることができました。
では、現在発表されている戯曲、特に日本の創作劇に、そのような登場人物が存在しているでしょうか。問いかけずにはいられません。わたしとしては、そうした人物たちは随分と数を減らした、舞台から姿を消しつつあるように思っています。
その理由は、現在に活躍している劇作家たち、若い(既に40代50代に入っている人達が大勢ですが)作家たちが人間を描くことにほとんど関心を示さないからではないでしょうか。
生きている存在、個人としての存在官をもつ人間像を作り出す力が弱いのではないでしょうか。
特に若い世代の劇作家の作品において、人生を背景としてもたない、作者の頭の中だけでつくり上げられる世界のピースとして、決まり切った思考をし、当たり障りのない正論を語り、すべてを他人事のようにうけとめて行動している。こういう登場人物ばかりのように、わたしには思われます。
戯曲は社会を映し出します。であれば、戯曲が確固たる人間像を描き出さなくなってきた理由は、社会にそうした人間が出てこなくなったからだとも、言えるかも知れません。戯曲の世界から自覚的で強烈な意志をもつ、魅力的な登場人物が姿を見せなくなったのは、こうした社会的風潮を劇作家たちが受けているからではないかと思います。
by 神澤和明
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.07.25 09:00:09
[研究会発表] カテゴリの最新記事
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか、(続2… 2019.08.03
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか。(続1… 2019.08.02
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(10) 2019.08.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.