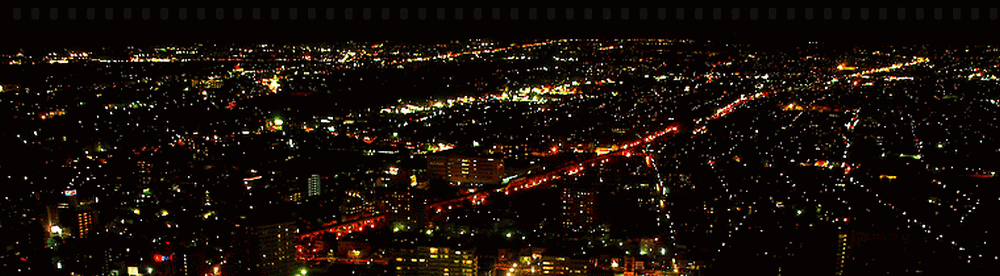PR
X
Keyword Search
▼キーワード検索
Calendar
まだ登録されていません
Comments
コメントに書き込みはありません。
Freepage List
カテゴリ: 研究会発表
さらに、現在の若い劇作家たちは自分たちの世界に留まる傾向があり、広く人間を観察することを怠っています。ですから登場する人物たちはいつも同じように定型的な人間で、そうでなければ極端な変人たち、ということが多いようです。書く方も演じる方も苦労がいらなくて楽ですが、そこから印象に残る「演劇的人格」は生まれてきません。
演出家は劇作家と演技者の間にいて、劇作家が書いた青写真としての脚本を、立体的に舞台に構築してゆく手助けをする存在だと、わたしは考えています。舞台で現実化されるものを観客に受け止めやすい、理解し易い形で表現するために苦労するのが仕事だと考えています。作家と役者が中心で、演出家はその後ろに隠れるべき存在だと思っています。そもそも演出家にしろ指揮者にしろ、演劇の世界では最も後に生まれてきた役職なのですから。ところがいつからか、演出家が表に出てくる、いや出過ぎる傾向が生まれてきました。他の人が思いつかないような、奇抜なアイディアで観客を驚かせるのが、優れた演出であるという、誤解が生じました。そうなると、芝居の必然と関係なく、演出家の思いつきで舞台が飾られて行きます。装置や音響や照明が幅を利かし、演技者の演技を覆って行きます。下手な演技者にとってはありがたいですが、演技力で観客の心を動かそうとしても、努力は消されて行きます。
演出家が自分を見せようとして、俳優をそのための道具としている舞台では、演技者の力は十分に発揮できません。従って、名優も生まれません。
今の若手劇団の芝居ではたいてい、作者が演出者を兼ねています。そうなると、作者の頭の中にあるものを舞台に出すだけですから、人間性をもたない役の人物ばかりがうろうろしていても、誰も気にしません。若者に人気を得た多くの若手劇団が解散した後、劇団を主宰していた作家兼演出家だけが残り、役者たちは多くが消えていったのは、そうした芝居が演技者の力を伸ばさなかったことを示しています。
演技者のことは後にまわして、先に批評家の問題に触れます。わたし自身を含めての問題です。
そもそも日本には、演劇批評というしっかりしたジャンルは根付いていないと思います。勿論、何人かの優れた演劇評論家はいらっしゃいましたが、ジャンルとして見れば非常に寒い状況です。
それは批評と現場とか乖離しているからです。欧米の演劇評論家には権威があります。彼らが褒めた舞台はロングラン、けなした舞台はすぐに公演打ちきりになります。劇場が中心となり、ロングランを基本とする上演形態を取っていますから、これは重要なことです。
日本の場合、商業演劇以外はロングランの上演方式を、ほとんどとっていません。たいてい2,3日で上演が終わります。ですから、批評がその公演に観客を呼ぶということは、期待できません。演劇評論家の多くは、新聞記者や演劇関係の雑誌の記者です。そして商業演劇はこうした人達を公演に「招待」し、普段から色々と繋がりを作っています。ですから、新聞に載るこうした公演についての批評は、観客に来てもらいたい興業会社の意向を汲んで、褒めるものばかりになります。新聞の歌舞伎評を見れば、おわかりになります。
そして小劇場関係の批評の場合は、批評家が自分の贔屓する劇団、作家をもっており、いつもその人や劇団について書きます。当然、良い様に書きます。そして他の劇団については、ほぼ書かない、というより、観に行きません。それでも新聞などは、そうした若手劇団について書いた記事が新しい、芸術的だと誤解して、喜んで載せます。新聞の劇評は若手劇団の小さな公演まで載せているのに、古くから活動を続けているいわゆる「新劇団」の公演にめったにふれていないことを、皆さんはどうお考えになりますか。
by 神澤和明
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2019.07.26 00:00:19
[研究会発表] カテゴリの最新記事
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか、(続2… 2019.08.03
-
今、なぜ「名優」が生まれにくいか。(続1… 2019.08.02
-
「今、何故『名優』が生まれにくいか」(10) 2019.08.01
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
© Rakuten Group, Inc.