2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2010年11月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-

維新の三傑
昨日の西郷ドンからの流れで、いつもの言葉の紹介とは趣を変えてみる。西郷は「維新の三傑」と称され、維新の十傑の1人でもある。この「三傑」とは西郷隆盛のほか、木戸孝允、大久保利通の2人。明治政府「三傑」なら納得なんだけど・・・・個人的には、幕末の志士の代表といえばすぐに思い出される3人を三傑としたい。kenkenppa版「維新の三傑」・・・西郷隆盛、高杉晋作、坂本龍馬。一般的にはこの3人の名前が挙がるような気がするのだが・・・・単にミーハー的な趣味なのか?!龍馬伝以前から幕末に惹かれ研究してきた人達や、今流行の歴女といわれる人からするとお笑い草の人選かもしれない??でも勝海舟などの幕府側の人間は除外されるらしいので、この人達しかいないっしょ!吉田松陰をはじめ、いろんな人達が綺羅星のごとくいる時代なので、人によって推したい人選は変わってくるだろうが、この人達の方が通常の「三傑」より納得感があるんではないか。3人とも歴史に残る大人物で、評するというとおこがましいが、今、隣にいたとすると、友達だったら、というキャラクター的なお話しをしてみる。しかもあまり維新マニアではない私のイメージ上のキャラとしてなので維新好き、歴史好きの方々にすれば見当違いのキャラかも知れないが、お遊びなのであしからず。高杉晋作このブログのタイトル「おもしろき こともなき世を おもしろく」もこの人の言葉。志士の中でこの人が一番好き。「動けば雷電の如く、発すれば風雨の如し」と評される行動力。その場の盛り上がりで外国人居留地を焼き討ちしてやろうと、実際に行動に移したり・・。幕末の志士は皆、革命を目指してるのだから、当然、時の政府から見たらテロリスト。その中でも群を抜くハチャメチャ振り。無鉄砲で、時にいいかげん、でたらめな行動力が回りを振り回しつつも引っ張っていく行動のリーダー。傍観者としてみてる分には面白いけど、やんちゃ過ぎ。何をやりだすかわからない。ヤンキー友達も引くヤンキーって感じかな。現在隣にいたら、一緒に遊ぶ友達。坂本龍馬みんなと違う考えを行動に移す大胆不敵。倒幕なら幕府をやっつける事を考えるのが普通。その流れ、仲間達と違う考えを周囲に流されないで実現させようとすることは大変なこと。一人だけ次元が違う事を考えているスケールのでかさ。ファンが多いのも頷ける。高い志や大きな夢を語って実現させる行動力もあるからみんなに付いていきたいと思わせる。自分の理想を語り仲間を惹きつける言葉のリーダー。大言壮語を吹きまくる面白い人。魅力があるが敵も一杯作り危なっかしい。私は一緒に行動するというより、たまに話を聞いて刺激を受けたい。現在隣にいたら、話友達。西郷隆盛「敬天愛人」の座右の銘が顕すように包容力があり、誠実な人。龍馬のように世界の中の日本という大きなスケールで考えていたのではなく、薩摩藩を一番に考える堅実派。人間的な大きさが破格で人徳で慕われる情のリーダー。逆にいうと意外性は少なく、物語などの主人公としては面白みには欠けるか?でもこの人は間違いない、裏切らない、無鉄砲やいい加減な事もしないと安心させる。政府高官となっても驕ることはなく、謙虚で清廉な人物だったらしい。一言で言うと人格者であり常識人。現在隣にいたら、仕事など一緒に行動をしたい人。一緒に何かするとなるとやっぱり西郷ドンだな~!自分が常識的で面白くないので、高杉さんや龍馬さんには憧れるけど、同じ次元で、友人として一緒にいたら2人ともイライラしたり、ハラハラしたり、怒ったりで疲れそう。笑その点、西郷さんは隣にいても、スゴイ人なんだけど、安心できる。今日は龍馬伝も終わってしまうらしい。さびしいね。
2010.11.28
コメント(0)
-

人を相手にせず、天を相手にせよ
人を相手にせず、天を相手にせよ。天を相手にして己を尽くし、人を咎めず、我が誠の足らざるを尋ぬべし西郷隆盛『南洲翁遺訓』 人を相手にしないで常に天を相手にするように心がけよ。天を相手にして自分の誠を尽くし,決して人を咎めるようなことをせず,自分の真心の足らないことを反省せよ 西郷隆盛解説は不要の偉人。幕末の志士。薩摩藩士。『南洲翁遺訓』旧庄内藩の関係者が西郷から聞いた話をまとめたもの。薩摩藩関係者ではなく、庄内藩とうところが西郷どんらしい。東北戦争で官軍に降伏した庄内藩は「薩摩藩邸焼き討ち事件」の遺恨もあり、厳しい処断を覚悟していた。ところが意外にも西郷が寛大な処置を指示。庄内藩で西郷の名声は広がり、鹿児島に旧藩士を派遣し教えを受けるなど親交が深まった。という経緯からのようだ。このあたりは庄内南洲会「南洲翁遺訓の由来」をご参照。仇ともいえる間柄の人達をして信奉者にしてしまうのだから懐が深い。人を相手にしないで、天を相手にしなければならない。天には「空」など多くの意味があるがここでは「天地万物の支配者。造物主。神。天帝。また、天地万物を支配する理法。」ということろだろう。「運を天にまかせる」の天。人間は他人の目を気にして、他人の見ている前では悪いことをしないが、他人が見ていないとか他人に知られる虞がないとなると悪いことだと感じつつも間違いを犯してしまう事がある。そこで、他人の目ではなくいつでも天を相手にしておけば悪い事などはできないしまた間違いもない。「天知る、地知る、汝知る、我知る」四知の故事と同じ意味合いだろう。やはり、「お天道様に恥じない」「俯仰天地に愧じず」ことが大事だ。それにはいつも天を相手にして自分の誠をつくさなければならない。うまくいかないのを人の所為にしたりして咎めたりすることはせず、ただ自分が誠を尽くしているかどうかを反省するべきである。「天知る、地知る、汝知る、我知る」(楊震が賄賂を断った時のせりふ『後漢書』)誰も知らないと思っていても、天と地とあなたと、自分自身も知っている。悪事は、いつかは必ず露見するものであるということ。 「俯仰天地に愧じず」仰いでは天の神、うつむいては地の神に恥じることがない。少しも恥じる事がない。俯仰(ふぎょう)天地に愧(は)じず-(「孟子‐尽心上」の「仰不愧於天、俯不於人」から)神様というとどうも違和感があるが、天といわれるとすんなり入ってくるから不思議だ。偽装、粉飾などのニュースが後を絶たない現在。他人事としてみているだけでなく自分自身を省みて教訓とし、西郷さんのいう様に、天を相手に生きていきたいものだ。人を相手にせず、天を相手にせよ。ちなみに、西郷は佐藤 一斎(江戸後期の儒学者)の『言志四録』を座右の書としており、書き抜きし「言志録 南洲手抄」を作るほどだったという。その『言志四録』におよそ事をなすには、すべからく天につかうるの心あるを要すべし。人に示すの念あるを要せず とある。おそらくこの言葉に影響を受けての言葉だったのだろう。こちらの言葉もいい!人に示すことなんか不要だ!この人はこのブログに未だ登場してませんが、いつか登場させるつもり。「重職心得箇条」などいいかも。西郷の他の言葉総じて 人は己に克つを以って成り自らを愛するを以って敗る自分の欲望を制すれば成功し、自分本位では失敗する。道は天地自然の物にして、人はこれを行うものなれば、天を敬するを目的とす。天は我も同一に愛し給ふゆえ、我を愛する心を以て人を愛する也。道というのはこの天地のおのずからなるものであり、人はこれにのっとって行うべきものであるから何よりもまず、天を敬うことを目的とすべきである。天は他人も自分も平等に愛したもうから、自分を愛する心をもって人を愛することが肝要である。これは 西郷の座右の銘ともいえる『敬天愛人』(天を敬い人を愛する)という言葉について。似た言葉を思い出したのでついでに・・・夏目漱石が晩年に理想とした境地を表した言葉で、宗教的な悟りを意味するとも、漱石の文学観とも解されている言葉。『即天去私』(天に則り私を去る)小さな私にとらわれず、身を天地自然にゆだねて生きて行くこと。「則天」は天地自然の法則や普遍的な妥当性に従うこと。「去私」は私心を捨て去ること。
2010.11.27
コメント(0)
-

求めよ、さらば與へられん。
求めよ、さらば與へられん。尋ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。すべて求むる者は得、たづぬる者は見いだし、門をたたく者は開かるるなり。『新約聖書』マタイ傳福音書(文語訳)第七章 日本聖書協会 求めよ、そうすれば、与えられるであろう。捜せ、そうすれば、見いだすであろう。門をたたけ、そうすれば、あけてもらえるであろう。すべて求める者は得、捜す者は見いだし、門をたたく者はあけてもらえるからである。『新約聖書』マタイによる福音書(口語訳)日本聖書協会最初にお断りしておきますが、私は全くの無宗教。キリスト教をお勧めするわけではありませんので、あしからず。幼稚園はミッション系(?)だったので、クリスマス等は羊飼い役を好演(自分で言うな!笑)していた記憶はある。全く門外漢なのでクリスチャンの方からすると誤解などもあるかもですが、悪意は全くありませんので、ご容赦を!キリスト教についての知識はというと、ユダヤ教の一宗派から今や世界一の信者数を誇る一大宗教。(ユダヤ教の一宗派って信者の方は怒る?いやきっと大丈夫だろう!笑)カトリック(ローマ法王、神父)、プロテスタント(聖書、牧師、ルターやカルヴァンの宗教革命)ローマ帝国が分裂した時に教会も分裂。東西に分かれる。(ローマとギリシャ)と世界史レベルのこの程度。ご本家のユダヤ教を下に見てるようなところがあるのはちょっとおかしい感じがする。イスラム教でも聖書は経典の内の一つというのが意外。文化ともなっているし、尊重しますが・・・・。愛を説くわりには諍いや憎しみ、果ては戦争の原因になってる宗教って何なの??というのが、私の宗教観。(キリストだけではないけどね。イスラムも兄弟宗教でしょ?)信仰は尊くても教団なりの組織は不要なんじゃないのかな。そして、信仰するにも妄信・盲信はいかんと思う。狂信者は論外。自分の頭で考える!ことを放棄しては終わってる。そんなことだと「ポアしてしまえ!」(by麻原彰晃こと松本智津夫)という命令に従ってしまう。宗教以外に思想も同じ。戦時中の日本や、ナチスドイツ。現代でも未だそんな感じがありありと窺える国がある。先日来のデモを見ていてもそう。政府がやらせているのか、自然発生的なものなのかはわからない。自然発生していて、当人達は自分で考えているつもりでも情報が制限されているのだから、踊らされている感じが拭えない。具体的な問題の情報だけでなく、根本に反日教育や外敵を作って団結させようという意図があるのだから。誰だって自分の国が大事。ましてや領土問題であれば感情的にもなるだろう。でも何か異質な集団と感じるのはこういうところからだと思う。(この国の歴史大好きな私ですが、しばらく漢文等をご紹介する気分ではないのだった。笑)ああいう行動は何もかの国だけではないという事も分かってはいるんだけどね。自由の国アメリカでも日本車を叩き壊していたり、イスラム圏でも星条旗を燃やしたり、コーランを燃やす事件だったりと・・・・仲良くやって生きたいもんですがね。(炎上してしまうのか?面倒くさいから止めてね。笑)イヤ如何いかん。思い切し脱線。聖書の言葉に全く造詣の深くない私でも、冒頭の言葉は知っていた。望めば神様が何とかしてくれる。という意味ではないと勝手に解釈。希望を抱き、それに向けて努力していけば報われるのだ。という事だと解釈したい。口語訳より文語体の方がずっしり来ていい感じ。求めよ、さらば與へられん。どんどん、求めましょ!
2010.11.23
コメント(0)
-

君の内面の平和は君の想像からのみ生じる
何よりも次の二つの真理を記憶せよ。まず第一に、外界は君の魂に触れることはできず、常に揺るぎ無く外部に立つものであるから、君の内面の平和は君の想像からのみ生じるということ、そして第二に、君がいま目の前に見ているものは、たちまち変化してもはや存在しなくなるということだ。実際、君はこれまで、いかに多くの変化の目撃者であったことか!世界とは永遠の変移であり、人生とは迷妄である。 マルクス・アウレリウスマルクス・アウレリウス・アントニヌス(Marcus Aurelius Antoninus)第16代ローマ皇帝。五賢帝最後の1人。ストア派哲学に精通。「哲人皇帝」と称された。唯一の著作として伝存する書物は『自省録』。『自省録』公にする為ではなく、自分自身へ向けた自問自答の書。諸行無常、生の儚さを基調とし、そうであるならば名声や富に執着せず、あらゆることに心乱されず、常に「死」を意識して生きることが大切。行動は世界市民として適切であるべき。などストア派的な倫理の書。表題の言葉もそのような考えがあらわされている。内面の平和とは幸福についてだろう。そう思える心がある人が幸福を感じる事ができる。次は、世界は諸行無常だという。日本人には受け入れ易い考え方。外界は君の魂に触れることはできない。内面の平和は想像からのみ生ずる。かっこいい表現。外部の環境その他の要因は心に触れる事はできない、内面の安らぎは考え方次第っていうこと。魂は自分自身の心の持ちようでしか変わらない!外部にどんな強力なものが待ち構えていようとも触れることさえできない。であるなら・・・・なんとなく安心! 笑似たようなのに君がなにか外的の理由で苦しむとすれば、君を悩ますのはそのこと自体ではなくて、それに関する君の判断なのだ。何かが起こって落ち込んだら、痛みの原因はその起こった事ではなく、それにかけていた期待である。そしてこの期待は、いつでも自分で取り消せる。自分自身に向けて、内省のために書いてるので繰り返し同じ事が出てくる事も多い。皇帝様も落ち込み、心痛む事が多かったようだ。彼の統治時代ローマ帝国は災難の連続だった。疫病の流行、度重なる外的の浸入。治世の半分は出征していたほど。その中で、彼はこう叫ぶ。『なんて私は運が悪いんだろう、こんな目にあうとは!』否、その反対だ、むしろ『なんて私は運がいいのだろう。なぜならばこんなことに出会っても、私はなお悲しみもせず、現在におしつぶされもせず、未来を恐れもしていない』である人生の困難を不運とみるか幸運とみるか、捉え方次第。ポジティブシンキングは遙かローマにもあった。他にもわれわれの人生とは、われわれの思考が作りあげるものに他ならないこれなんて、ナポレオン・ヒルさんと同じ。ナポレオン・ヒルさんがこの台詞を知ってたかどうかは知らないが、その通りだ!物事は考え方・捉え方次第! 思考が大事!幸せを捜し求めるばかりではなく、身近な幸せを感じ取りましょう!PS自然に前向きに思えるようになる事はいいことだ。が、こう思わねばならない!という痛々しい人もみかける。そういう人はあんまり無理はしなくていいんじゃない。余りにも、「でなきゃいけない、・・でもできない」という強迫観念が強いと逆の暗示になってしまっている事もある。力まず、自然に行きましょう!
2010.11.21
コメント(0)
-

年年歳歳報徳を忘るべからず
報徳訓 二宮尊徳 父母の根元は天地の令命にあり 身体の根元は父母の生育にあり 子孫の相続は夫婦の丹精にあり 父母の富貴は祖先の勤功にあり 吾身の富貴は父母の積善にあり 子孫の富貴は自己の勤労にあり 身命の長養は衣食住の三つにあり 衣食住の三つは田畑山林にあり 田畑山林は人民の勤耕にあり 今年の衣食は昨年の産業にあり 来年の衣食は今年の艱難にあり 年年歳歳報徳を忘るべからず二宮尊徳日本の江戸時代後期に「報徳思想」を唱えて、「報徳仕法」と呼ばれる農村復興政策を指導した農政家・思想家。1904年以降、国定教科書に修身の象徴として取り上げられるようになり、昭和初期に各地の小学校に像が多く建てられた。像のように薪を背負ったまま本を読んで歩いたという事実が確認できないことと、児童が像の真似をすると交通安全上問題があることから、1970年代以降、校舎の立替時などに徐々に撤去され、像の数は減少傾向にある。報徳思想(ほうとくしそう)二宮尊徳が説き広めた道徳思想であり、経済思想・経済学説のひとつ。経済と道徳の融和を訴え、私利私欲に走るのではなく社会に貢献すれば、いずれ自らに還元されると説く。この思想の普及活動に努めている。大日本報徳社のHPによると、--------------------------------------報徳の思想を形成する三つの柱は、『勤労』、『分度』、『推譲』という言葉で表されています。 『勤労』 『勤労』は、積小為大という言葉に代表される考え方です。大きな目標に向かって行動を起こすとしても、小さなことから怠らず、つつましくつとめなければならないということ。「今まく木の実、後の大木ぞ」という尊徳の有名な言葉が残されています。 『分度』 『分度』とは、適量・適度のこと。分度をしっかり定めないままだから、困窮してしまうし、暮らし向きも楽にならない。家計でも仕事でも、現状の自分にとってどう生き、どう行うべきかを、知るということが大切だという考えです。 『推譲』 『推譲』とは、肉親・知己・郷土・国のため、あらゆる方面において、譲る心を持つべきであるという考え。分度をわきまえ、すこしでも他社に譲れば、周囲も自分も豊かになるものだという教えです。 --------------------------------------ということらしい。 他に『至誠』という概念も大切であるようだ。まず誠を尽くしたものでなければならない。我の心を大極と積極的にかかわる状態、つまり誠、徳、仁、の状態に置くこと至誠とよび、至誠がまず実践の第一をなす。二宮尊徳、二宮金次郎というと、小学校にある(私は実際に見た事はないが)蒔きを背負って歩きながら読書している少年像から小柄な人を連想していたが、実際は170~180cmと当時としては巨漢だったらしい。他にも苦学の末大成した努力の人、清廉潔白で無欲な人格者というイメージがある。どうもこうした人物像は、明治以降の帝国政府が二宮を政治的に利用し、修身の象徴としてしまったことによるところが大きいようだ。そのため二宮・報徳というと軍国主義を思い起こす人達もいるらしいが、中身をみればそういったこととは全く関係ないことは明らかであり、残念なことだ。(報徳思想による教えを指して報徳教と呼ぶ事もあるらしいので宗教的な匂いがついて、 紛らわしいとは思う。と思えば報徳二宮神社という神社もあるし・・・・とほほ。笑)今では、「誰でも名前は知っているが、よく知らない」という人物の代表が二宮尊徳(二宮金次郎)じゃないだろうか。私も農村を復興し、農民からは神のように慕われたというようなうろ覚えな知識から、農業の専門家だと勘違いしていた。実際には財政再建の専門家だったようだ。キャリアのスタートとなった小田原藩譜代の名家服部家の殿様から再建を打診された時、金次郎個人の家の再興の秘訣を問われ答えたのが下記の言葉。入るを図って出るを制す核心をズバッと言い得てる。(当たり前といえばそれまでなんですが・・・・苦笑)「租税負担率を上げて、財政を均衡させる」という今の官僚のような安直ことはしていない。逆に、緊縮財政をしきながら租税負担者の収入増加をめざす施策を実施し、租税負担能力の拡大を図り、やがては、負担者も藩(役所)もに豊かになるという方式をとっている。何かというと「消費税増税」を目論むどこかの国の官僚に是非とも見習ってもらいたいものだ。 前置きが長くなりましたが、今日の言葉「報徳訓」。甲子園などで聞いたことがある報徳学園高校では入学式などの行事でこの報徳訓を朗読するらしい。(トレビア 笑)人間は自分ひとりだけで生きているのではなく、天地自然があり、親があり先祖がある。そして親や先祖の行いによって自分の境遇が決まってくるし、自分の行いが子孫の富貴を決める。人間にとって衣食住は大事だが、これは経済に掛かっている。経済は勤労によってなりたっている。今年は昨年の、来年は今年の頑張りが反映されるんだ。周りの人々へはいつも徳によって報いていく事が大事だ。感謝と勤労と積善、報徳の奨めを説いている。※田畑山林について、報徳二宮神社HPによると「自然と神の恩恵」のことだとしているが、私は産業という事だと推測。産業という言葉が後に出てくるのでここでは経済としておく。当時の産業とは農林業だったことからそのことを言っただけだと思うのだが・・・。昨年の実りで今年生活でき、今年、困難を乗り越えたら来年があるというのは農業ベースなので、もっと成果は早く来ることもあるでしょうが、基本は現代にも生きてる言葉。普段、先祖のことなんてあまり・・・イヤ全然考えないけれども感謝しなければいけない。先祖・自分・子孫。昨年・今年・来年。すべての事柄が繋がっている。顧客・自分・自分が買い物をするお店。自分・顧客・顧客の顧客。友人・自分・友人(これはmixi、GREE等のSNSみたい)感謝・感謝・感謝!!ということかな。それから勤労の大切さについては、積小為大の精神。大事をなさんと欲せば、小なる事をおこたらず勤べし。小積もりて大となればなり日々の努力の積み重ねが大事!仰るとおり。(日々是決戦は昔懐かしい予備校のスローガンでしたが・・いまもあるのかな?)年年歳歳報徳を忘るべからず中根 東里の言葉「施して報を願はず、受けて恩を忘れず。」を思い出す。が、こちらは恩を受けなくても報徳と、より深い。 二宮尊徳の他の言葉。道徳なき経済は犯罪であり、経済なき道徳は寝言である道徳と経済との一元化を説いたのが二宮尊徳の根本思想。『論語と算盤』を著し、「道徳経済合一説」という理念を打ち出した渋沢栄一と似てる。同じ時代に生きた2人だが、渋沢が16歳で二宮は亡くなっている。おそらく出会う事のなかった2人が語り合っているところが見てみたい。二宮尊徳の門人が著した「二宮翁夜話」。論語のように門人が師の言葉を書き記したもの。これを現代語訳したサイトがありましたので興味ある方はどうぞ。 「現代語訳 気軽に読みたい人のための二宮翁夜話」 報徳訓父母根元在天地令命身体根元在父母生育子孫相続在夫婦丹精父母富貴在祖先勤功我身富貴在父母積善子孫富貴在自己勤労身命長養在衣食住三衣食住三在田畑山林田畑山林在人民勤功今年衣食在昨年産業来年衣食在今年艱難年々歳々不可忘報徳
2010.11.20
コメント(0)
-

しあわせは 歩いてこない だから歩いて ゆくんだね
三百六十五歩のマーチ 作詞:星野哲郎 しあわせは 歩いてこないだから歩いて ゆくんだね一日一歩 三日で三歩三歩進んで 二歩さがる人生は ワン・ツー・パンチ汗かき べそかき 歩こうよあなたのつけた 足あとにゃきれいな花が 咲くでしょう腕を振って 足をあげてワン・ツー ワン・ツー休まないで 歩け ソレ ワン・ツー ワン・ツーワン・ツー ワン・ツーしあわせの 扉はせまいだからしゃがんで 通るのね百日百歩 千日千歩ままになる日も ならぬ日も人生は ワン・ツー・パンチあしたのあしたは またあしたあなたはいつも 新しい希望の虹を だいている腕を振って 足をあげてワン・ツー ワン・ツー休まないで 歩けソレ ワン・ツー ワン・ツーワン・ツー ワン・ツーしあわせの 隣にいてもわからない日も あるんだね一年三百六十五日一歩違いで にがしても人生は ワン・ツー・パンチ歩みを止めずに 夢みよう千里の道も 一歩からはじまることを 信じよう腕を振って 足をあげてワン・ツー ワン・ツー休まないで 歩けソレ ワン・ツー ワン・ツーワン・ツー ワン・ツー 星野哲郎(本名・有近哲郎)昭和の歌謡史に残る多くのヒット曲を世に送り出してきた作詞家。三百六十五歩のマーチ(水前寺清子1968年)男はつらいよ(渥美清1970年)兄弟仁義(北島三郎1965年) 昔の名前で出ています(小林旭1975年)黄色いサクランボ(スリー・キャッツ1959年)・・・etc. 作詞家の星野哲郎さんが昨日15日、亡くなった。「星野さん逆境乗り越え生涯4000曲」これは私が見かけたネットニュースのタイトル。 4000曲って半端じゃない。しかも有名な曲がごろごろある。書斎に眠ったままの遺作も2千以上あるという。“七転八起”の人生だったそうだ。肺結核(45年)、腎臓結核(49年)、心筋梗塞(79年)、腹部大動脈瘤(92年)と病と闘っていた。最愛の妻も94年に先立つ。だが、星野さんは「上を向いて前を向くから挫折がある。挫折があるから強く、優しくなれる。転んでも立ち上がれる」と話していたと、関係者が明かしていたとのこと。すごい人だね。腕を振って 足をあげてワン・ツー ワン・ツー休まないで 歩けソレ ワン・ツー ワン・ツーワン・ツー ワン・ツー 星野さんに負けずに頑張って歩いていきましょう!一日一歩 三日で三歩三歩進んで 二歩さがる子供の時は、「そんなんじゃ、ちっとも進まね~よ!」と思っていましたが・・・汗“一歩”確実に進んでる。ゆっくり、確実に行こう!急がなくてもいいんだ!というだね。(成長したな、俺!笑)ご冥福をお祈りいたします!合掌
2010.11.16
コメント(2)
-

何をするにしても遅すぎる事はない
何をするにしても遅すぎる事はないなりたい自分になればいいタイムリミットはない、いつ始めてもいいんだ変わってもいいし、変わらなくてもいいルールなんて無いんだよ人生は最高にも最悪にもなる。もちろん最高の方がいいけど驚きに満ちたものを見つけてそれまで感じたことのないことを感じて人と出会いさまざまな価値観を知って欲しい誇りを持って人生を生きるんだ道を見失ったら・・・大丈夫、自分の力でまたやり直せばいいんだ ベンジャミン・バトンから娘への手紙『ベンジャミン・バトン 数奇な人生』(The Curious Case of Benjamin Button)2008年のアメリカ映画。主演:ブラッド・ピット、監督:デヴィッド・フィンチャー。F・スコット・フィッツジェラルドの短編小説をもとに、デヴィッド・フィンチャーが映画化。フィンチャーとブラッド・ピットにとっては『セブン』『ファイト・クラブ』に続くコンビ作品となった。舞台は1918年のニューオーリンズ。80歳の姿で生まれた赤ん坊はある施設の階段に置き去りにされていた。黒人女性のクイニーはその赤ん坊を拾い、ベンジャミンと名付け、自身が働く老人施設でベンジャミンを育てる。ベンジャミンは成長するにつれ若返っていった。昨日に続き手紙シリーズ!正直に言うと私自身はこの映画を面白いとは思えなかった・・・・ありえない設定で、物語の中に入っていけなかった。成長過程をみてみると、生まれた時は、大きさは普通の赤ちゃんと同じで、しわくちゃ、全身関節炎状態。成長(?)すると(身長は伸びていく)しわ・しみがとれていく。車椅子生活だったのが、歩けるようになる。年を取るにつれて、身長が縮み、子供になっていく。痴呆症が発症し、記憶がなくなる。最後は玉のような赤ちゃん(しわ等は全くない、つるつるの皮膚)になり老衰で死ぬ。成長してるのか、若返ってるのか訳が分からん。若返ると身長が縮む???どうせなら、身長等は大人の状態で生まれてきて、縮んでいく方が分かり易い。(母親を中から突き破ってしまうけど・・・やっぱり無理か?!笑)若返っていってるのに、痴呆症????老衰???????自然な死因があるとすれば、細胞が活性化し過ぎて、血流が増え脳内出血とかはどうだろう?SFなどありえない状態はままあることで、(宇宙で火が燃えるはずはないとかetc)設定として一貫していれば物語として楽しめるが、これはダメだった。私がだめだっただけで、私のようにへそ曲がりではない、皆さん方は物語に入っていけさえすれば面白いと思います。ブラッド・ピットはかっこいいしね。とはいえこの手紙は、優しさに溢れていて良い手紙だったので、ご紹介。いい感じに若返っていって、青年として年齢と外見が釣り合った頃、普通に年を取り、成長した幼友達(?子供と老人としての友達だった)女性と結婚。子供ができるが、自分はドンドン若返ってしまう・・・。一緒に年を取っていける父親が必要だし、奥さんも夫と子供両方を育てるのは無理。との判断で二人の下を去ってしまう。離れ離れになった娘に宛てて書いた手紙。遅すぎる事はない、なりたい自分でいい、ルールなんて無い、やり直せばいい。そうなんだよね。あまり肩肘はらず、すべきとか、こうでなきゃならない、なんていう考えをやめて、気軽に、楽しんでいく事が大切。自分を認めてあげること、肯定して受け入れることも大事。何をするにしても遅すぎる事はないなりたい自分になればいいタイムリミットはない、いつ始めてもいいんだ変わってもいいし、変わらなくてもいいルールなんて無いんだよ子供に関してもこういう態度でいたいものだ。
2010.11.14
コメント(0)
-
打ち負かされる事自体は、何も恥じるべき事ではない。
ダレル・ロイヤルの手紙親愛なるロングホーン諸君打ち負かされる事自体は、何も恥じるべき事ではない。打ち負かされたまま、立ち上がろうとせずにいる事が恥ずぺき事なのである。ここに、人生で数多くの敗北を経験しながらも、その敗北から、はいあがる勇気を持ち続けた、偉大な男の歴史を紹介しよう。1832年 失業1832年 州議選に落選1833年 事業倒産1834年 州議会議員に当選1835年 婚約者死亡1836年 神経衰弱罹病1838年 州議会議長落選1845年 下院議員指名投票で敗北1846年 下院議員当選1848年 下院議員再選ならず1849年 国土庁調査官を拒否される1854年 上院議員落選1856年 副大統領指名投票で敗北1858年 上院議員、再度落選そして1860年、エイブラハム・リンカーンは米国大統領に選出された。諸君も三軍でシーズンをむかえ、六軍に落ちる事があるかもしれない。一軍で始まり、四軍となるかもしれない。諸君が常に自問自答すべき事は、打ちのめされた後、自分は何をしようとしているのか、という事である。不平を言って情けなく思うだけか、それとも闘志を燃やし再び立ち向かっていくのか、ということである。今秋、競技場でプレーする諸君の誰もが、必ず一度や二度の屈辱を味わうだろう。今まで打ちのめされた事がない選手など、かつて存在したことはない。ただし、一流選手はあらゆる努力を払い、速やかに立ち上がろうと努める。並の選手は立ち上がるのが少しばかり遅い。そして敗者はいつまでもグラウンドに横たわったままである。 テキサス大学アメリカンフットボール部[ロングホーンズ]の名コーチ、ダレル・ロイヤルが夏休み帰省中の選手達に送った手紙より。『ダレル・ロイヤルの手紙』と題された有名な文章。この文章をどこで読んだのか覚えておらず、出典は不明だが名文であることに異論はないだろう。最近では「アイシールド21」(週間少年ジャンプ)の中でも紹介されていたらしい。また、『圧勝!受験なんてヘッチャラだ』 (斎藤孝の「ガツンと一発」シリーズ) 斎藤孝にも後付の引用として載って入る模様。手紙の経歴は、事実とは若干違うところもあるようだが、改めてみるとリンカーンってやっぱりスゴイ。貴乃花の言葉(大関推挙伝達式での口上)として話題になった「不撓不屈の精神」を体現している。すべてが順調で言う事ないという人はなんて事のない言葉だと思うのかも知れないが、今の時代そういった人は希少だろう。一流選手はあらゆる努力を払い、速やかに立ち上がろうと努める。 一流といえども立ち上がる為にはあらゆる努力をしているんだ。我々は、より一層頑張らねばならない!倒れても倒れても立ち上がる人の中には、自分が倒れた事も忘れて、「俺は倒れてなんかいない!」というのかも知れない。笑逆に、随分長い間横たわったままの人もいるのではないだろうか?!もうそろそろ、立ち上がりましょう!打ち負かされる事自体は、何も恥じるべき事ではない。打ち負かされたまま、立ち上がろうとせずにいる事が恥ずぺき事なのである。 打ち負かされた事のない人はいない!頑張ろうっと!それにしても6軍まであるアメフト部っていったい何人いるんだろう?
2010.11.13
コメント(0)
-
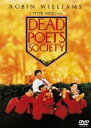
Carpe diem
Carpe diem その日を摘め! (カルペ・ディエム) いまを生きろ!Carpe diem(ラテン語:カルペ・ディエム)直訳すると「その日を摘め」紀元前1世紀の古代ローマの詩人ホラティウスの詩に登場する語句。(『詩集』第1巻第11歌)「一日の花を摘め」、「一日を摘め」などとも訳される。(carpeは動詞 carpoの命令法、通常は花や果実を「摘み取る」の意で使われる) また英語では「seize the day」(その日をつかめ/この日をつかめ)とも訳される。個人的には映画『いまを生きる』の主人公キーティング先生の口癖として好きな言葉。(山下太郎のラテン語入門さんを参考にさせていただきました。)ホラティウスクィントゥス・ホラティウス・フラックス(Quintus Horatius Flaccus)古代ローマ時代の南イタリアの詩人。アウグストゥスと同時代に生きたラテン文学黄金期の詩人。作品に『風刺詩』、『詩集』、『エポーデス』などがある。『いまを生きる』(原題:Dead Poets Society)1989年のアメリカ映画。ロビン・ウィリアムズ主演、ピーター・ウィアー監督。規則の厳しい全寮制のエリート名門校。規律で縛られ人生のレールに乗せられた生徒達。そんな学校に型破りな英語教師が新しく赴任してきたところから物語が始まる。彼はつまらなそうに授業を受ける生徒達に向かい「教科書なんか破り捨てろ」と言い放つ。また、机の上に立ちあがり、視点を変える事の重要さを説く。こうした破天荒な授業を通して、詩の本当の美しさ、生きることの素晴らしさについて教えようとする。徐々にこの教師に惹かれていった生徒たちは、彼がかつて学生だった頃に作っていた詩の朗読同好会を自分たちの手で復活させる。そして・・・・ロビン・ウィリアムズ扮するジョン・キーティング先生は、テニスン、ソローやホイットマン等の詩を通して固定観念に縛られない事、今を大事にする事等、人生について教えていくわけだが、そこで登場したのが、昨日のO Captain! My Captain!(リンカーン大統領の追憶)だ。この詩は朗読にちょっと出てきたというものではなく、物語全体に関わるモノだった。自分の事をキャプテンと呼ばせ、キーティング先生と呼ばれても返事をしなかったりと、生徒達から面白い先生だと信頼を得ていく切っ掛けになる。また最後のシーンでも・・・原題はキーティング先生がこの学校の生徒だったころ結成した同好会の名前。“死せる詩人の会”既に死んでしまった詩人による古典詩を朗読する事からの命名。邦題は冒頭のキーティング先生の口癖であるカルペ・ディエムから。命令形ではなくなっている。キーティング先生の型破りな授業に対して批判的だった校長はある事件の責任を彼に押し付け、退職に追い込む。最後に生徒達がキーティング先生をキャプテンと呼び、机の上にあがるシーンは感動もの。保守的な校長へのせめてもの反抗なのだが、生徒全員が参加するわけではないところも現実味がある。気が弱く仲間の後ろを付いて行くような生徒が先導を切るのが憎い。涙が自然に溢れてくるシーン。私の一番好きな映画の一つ。(キーティング先生は英語教師ということだが、英語圏で英語の先生という事は国語の先生。 先日の 『ROOKIES』(ルーキーズ)川藤先生といい、金八先生といい、もはや学園モノに 国語教師は定番ですな。)同じラテン語で関連するが異なった表現に、「メメント・モリ」という言葉がある。「(自分が)死ぬことを覚えていなさい。」という意味。 Memento mori. 死を忘れるな 一日一日を花々と思う。何気なく過ぎゆく毎日を、いわば花畑の花々とみなし、花の一本一本を愛おしむように日々を愛すのがよい、という意味が込められているそうだ。Carpe diem カルペ・ディエム一日という花を摘んで行こう!! 最後にホラティウスの詩もご参考に(ここも山下太郎のラテン語入門さんから。)Tu ne quaesieris, scire nefas, quem mihi, quem tibifinem di dederint, Leuconoe, nec Babylonios temptaris numeros. ut melius quicquid erit pati, seu pluris hiemes seu tribuit Iuppiter ultimam, quae nunc oppositis debilitat pumicibus mare Tyrrhenum: sapias, vina liques et spatio brevi spem longam reseces. dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem, quam minimum credula postero. Quintus Horatius Flaccus神々がどんな死を僕や君にお与えになるのか、レウコノエよ、そんなことを尋ねてはいけない。それを知ることは、神の道に背くことだから。君はまた、バビュロンの数占いにも手を出してはいけない。死がどのようなものであれ、それを進んで受け入れる方がどんなにかいいだろう。仮にユピテル様が、これから僕らに何度も冬を迎えさせてくれるにせよ、或いは逆に、立ちはだかる岩によってテュッレニア海を疲弊させている今年の冬が最後の冬になるにせよ。だから君には賢明であってほしい。酒を漉(こ)し、短い人生の中で遠大な希望を抱くことは慎もう。なぜなら、僕らがこんなおしゃべりをしている間にも、意地悪な「時」は足早に逃げていってしまうのだから。 今日一日の花を摘みとることだ。明日が来るなんて、ちっともあてにはできないのだから。クィントゥス・ホラティウス・フラックス(『詩集』第1巻第11歌)
2010.11.07
コメント(0)
-

O Captain! My Captain!
おお「船長」、わたしの「船長」よ おお「船長」、わたしの「船長」よ、われらが恐ろしき旅は終わった、船はあらゆる危機を乗り切り、念願の宝も手中に収めた、港は近く、鐘の音が聞こえ、人びともこぞって歓声をあげ、目ではどっしりした竜骨を、大胆不敵でいかめしい船体を追う、されどおお、心よ、心よ、心よ、おお、したたり落ちる赤い雫よ、甲板の上にはわたしの「船長」が、今はすでに息絶えて冷たく。 ウォルト・ホイットマン (『草の葉 中』岩波書店) O Captain! My Captain! O Captain! my Captain! our fearful trip is done,The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won,The port is near, the bells I hear, the people all exulting,While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;But O heart! heart! heart!O the bleeding drops of red,Where on the deck my Captain lies,Fallen cold and dead. Walt Whitman (the Leaves of Grass)ウォルト・ホイットマン (Walter Whitman)はアメリカ合衆国の詩人、随筆家、ジャーナリスト。アメリカ文学において最も影響力の大きい作家の一人でもあり、「自由詩の父」と呼ばれる。生涯をかけ代表作『草の葉』の増補改定を続けた。ホイットマンは A Broadway Pageant(ブロードウェーの華麗な行列)に続き2回目の登場。彼の詩は、力強く、何故か心惹かれる。元々は"MEMORIES OF PRESIDENT LINCOLN"「リンカーン大統領の追憶」との題名だったようだ。< われらが恐ろしき旅は終わった、 船はあらゆる危難を乗り切り、 念願の宝も手中に収めた >とは 南北戦争という内戦を乗り越え、奴隷解放を成し遂げた、という事。Captainはリンカーン、The shipはアメリカ合衆国。内戦という苦しい旅路をくぐりぬけてきたのに、暗殺によって亡くなってしまった。今回の詩はその悲しみを詠ったもの。『おお「船長」、わたしの「船長」よ、』という日本語より、『O Captain! My Captain!』の原文の方が数段小気味好い。自らの国の大統領をマイ キャプテン と呼ぶ感覚がすごい。それだけ思慕が深かったのだろう。敬愛されるリーダーがいないからなのか?!日本ではありえない。『いまを生きる』(原題:Dead Poets Society)という映画にも引用され、印象的だったのを覚えている。この映画、大好きなので今度、ご紹介しますね。 おお「船長」、わたしの「船長」よおお「船長」、わたしの「船長」よ、われらが恐ろしき旅は終わった、船はあらゆる危機を乗り切り、念願の宝も手中に収めた、港は近く、鐘の音が聞こえ、人びともこぞって歓声をあげ、目ではどっしりした竜骨を、大胆不敵でいかめしい船体を追う、されどおお、心よ、心よ、心よ、おお、したたり落ちる赤い雫よ、甲板の上にはわたしの「船長」が、今はすでに息絶えて冷たく。おお「船長」、わたしの「船長」よ、起き上がって、いざあの鐘を聞きたまえ、起き上がるのだ――旗があなたのためにはためいている――らっぱがあなたのために鳴っている。あなたのために花束もリボンをかけた花輪も――あなたのために渚は人で埋まり、あなたの名前を人びとは口々に呼び、群れ全体が揺れ動きつつ、火照った顔をいっせいに振り向ける、さあ「船長」、愛する父よ、この腕をどうかあなたの枕として、きっと何かの夢なんですあなたが倒れ、息絶えて冷たく横たわったのは。わが「船長」は答えず、唇は青ざめて動かぬまま、わが父はわが腕に触れず、脈搏もなく意志も示さず、船は恙なく錨をおろし、はや船旅も終わりを迎え、恐ろしき旅から目的を遂げてようやく港に凱旋した、喜ぶがいい、おお出迎えの岸辺たちよ、響きわたれ、おお祝賀の鐘よ、だがわたしは悲しみゆえに足どり重く、わが「船長」が倒れて息絶え、今は冷たく横たわる甲板で行きつもどりつ。 (『草の葉 中』岩波書店) O Captain! My Captain!O Captain! my Captain! our fearful trip is done,The ship has weather'd every rack, the prize we sought is won,The port is near, the bells I hear, the people all exulting,While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring;But O heart! heart! heart!O the bleeding drops of red,Where on the deck my Captain lies,Fallen cold and dead.O Captain! my Captain! rise up and hear the bells;Rise up ― for you the flags is flugs ― for you the bugle trills,For you bouquets and ribbon'd wreaths ― for you the shores a-crowding, For you they call, the swaying mass, their eager faces turning;Here Captain! dear father!This arm beneath your head!It is some dream that on the deck,You've fallen cold and dead.My Captain does not answer, his lips are pale and still,My father does not feel my arm, he he has no pulse nor will,The ship is anchor'd safe and sound, its voyage closed and done,From fearful trip the victor ship comes in with object won;Exult O shores, and ring O bells!But I with mournful tread,Walk the deck my Captain lies,Fallen cold and dead.
2010.11.06
コメント(0)
-

気持ちよい生活を作ろうと思ったら、 済んだことをくよくよせぬこと
処世のおきて気持ちよい生活を作ろうと思ったら、 済んだことをくよくよせぬこと、めったに腹を立てぬこと、 いつも現在を楽しむこと、 とりわけ、人を憎まぬこと、未来を神にまかせること。 ゲーテ「警句的」ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ(Johann Wolfgang von Goethe)ドイツの詩人、劇作家、小説家、哲学者、科学者、政治家。ドイツを代表する文豪であり、小説『若きウェルテルの悩み』『ヴィルヘルム・マイスターの修行時代』、叙事詩『ヘルマンとドロテーア』、詩劇『ファウスト』など広い分野で重要な作品を残した。74歳の時に17歳の少女に求婚する位の女性好き。(当然失恋)『若きウェルテルの悩み』もストーカーの原型のようなお話しであんまり面白くなかった記憶が・・・・最後の「未来を神にまかせること。」は宗教的な意味合いを読み込んだ場合の「レット・イット・ビー」(ビートルズ)(神の意のままに)に似てる。人事を尽くして天命を待つぐらいの意味だろう。「気持ちよい生活」という表現も好き。大袈裟じゃなくていい。過去に囚われるな、怒りを抑える、現在を楽しむ、憎しみを捨てる、未来は神にまかせる。と5つの項目をあげている。怒りと憎しみという二つの負の感情をコントロールしろという以外は時間軸に関すること。 過去 → 現在 → 未来反省は必要だが、過ぎ去った過去の事をいつまでも悔やんでいても何も始まらない。未だ起こっていない未来の事を、先取りして不安に駆られても意味がない。悪い結果になるのではと不安ならば、今、いい結果になるように準備すればいい。大事なのは過去でも未来でもない、今!この現在が重要だ。過去を反省し、未来に対して備えをしたら、後は 現在を楽しみましょう!!おまけでゲーテの他の言葉も一つ。知識を身につければ十分? 否。何事かに応用せよ。望むだけで十分?否。行動を起こせ。 ヨハン・ヴォルフガング・フォン・ゲーテ行動を起こせ!
2010.11.03
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- 本のある暮らし
- Book #0940 瞬時に「言語化できる人…
- (2025-11-26 00:00:13)
-
-
-

- この秋読んだイチオシ本・漫画
- 『 REAL 15 』 井上雄彦
- (2025-11-24 15:48:35)
-
-
-

- NARUTOが好きな人、投稿はここだって…
- ナルト柄のTシャツ再び!パープル色…
- (2025-08-27 07:10:04)
-







