2025年08月の記事
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
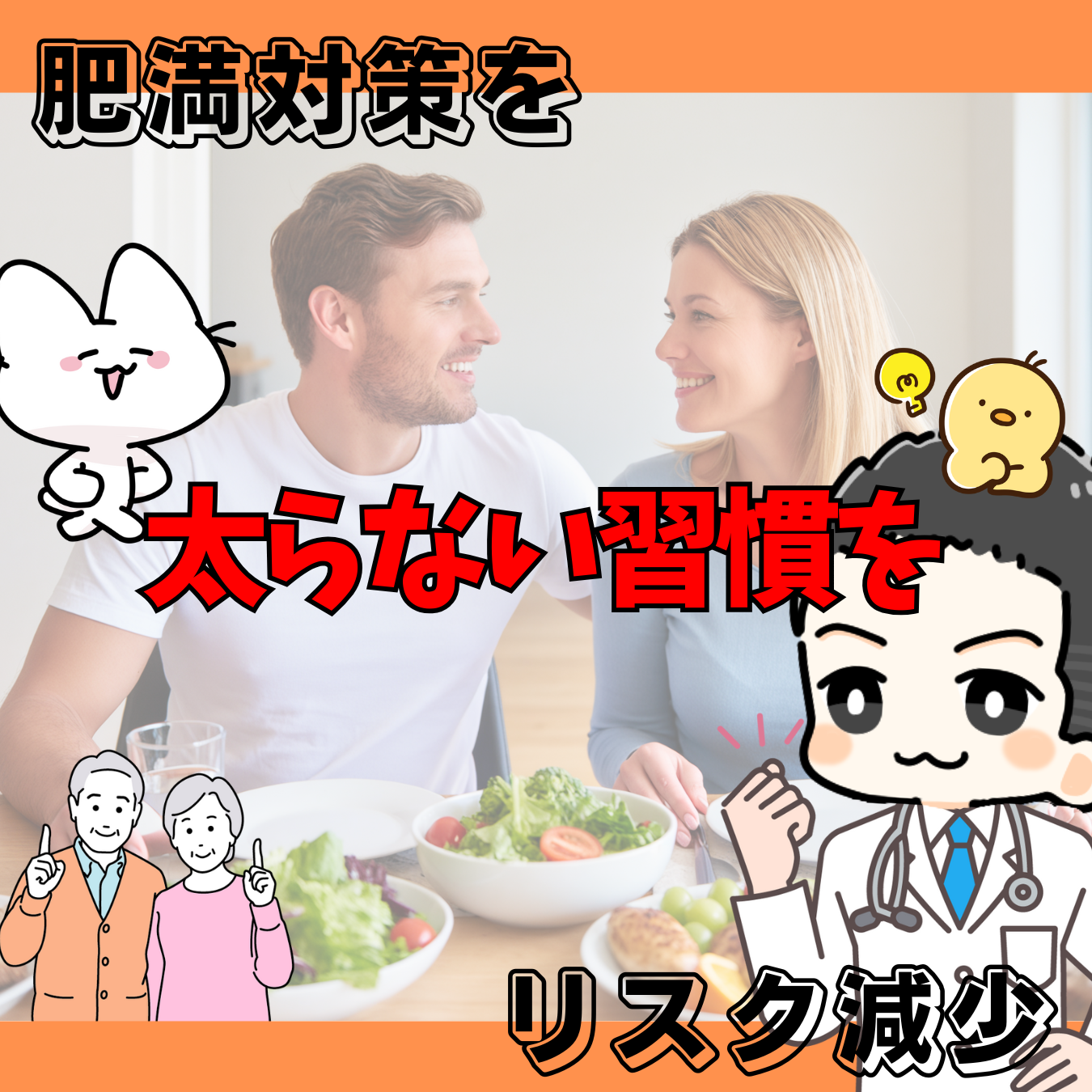
【肥満対策を】太らない習慣を作る リスクの少ない体へ
週に一回夜の断食を始めていく 年齢を重ねると、若いころとは違い、体重が増えやすく、減りにくくなったと感じる方が多くなります。 基礎代謝の低下や筋肉量の減少、そしてホルモンバランスの変化など、年齢を重ねた身体には様々な変化が訪れてしまいます。 こうした変化の中で、肥満は健康を脅かす「静かなリスク」として無視できない存在になり、糖尿病や高血圧、脂質異常症など、生活習慣病の多くが肥満と深く関係しているのです。 しかし現実には、多くの人が「どうやって痩せたらいいのか分からない」「痩せてもすぐにリバウンドしてしまう」と悩んでいます。 一度挫折を経験すると「自分には無理だ」とあきらめの気持ちが芽生え、再挑戦する気力が持てなくなってしまい、失敗体験が強く記憶に残り、行動を止めてしまうのです。 けれども、年齢に関係なく、正しい知識と習慣があれば、健康的に体重を減らすことは十分に可能です。 そして、何より大切なのは、減らした体重を無理なく維持し、病気のリスクを下げ、元気に毎日を過ごすことにあります。 シニア世代に最適な年齢を重ねたからこそ始められる、無理のない健康習慣を一緒に見つけていきましょう。 シニア世代の体にやさしい減量法として注目されているのが「週に一回の夜の断食」夕食を抜くだけのシンプルな方法ですが、胃腸を休めて代謝を整え、肥満や生活習慣病のリスクを下げる効果が期待できます。夜断食で体を活性化していく 痩せるためには、ただカロリーを減らすだけではなく、「体脂肪を燃やすスイッチ」を入れることが大切になります。 食事をしている間、体はまず血液中にあるすぐに使えるエネルギーを優先的に使い、その次に肝臓や筋肉に蓄えられたグリコーゲンを使って活動するので、これらが十分にある間は、なかなか体脂肪は燃焼されません。 実は、体脂肪をエネルギーとして使い始めるのは、最終段階の食後から10時間以上経過して、ようやく脂肪を分解して使うスイッチがオン しかし、食事の間隔が短い生活では、脂肪が使われるタイミングが訪れず、どんどん蓄積されてしまうというわけです。 そこでおすすめなのが「夜断食」です。週に一回、夕食を抜くだけでも、翌朝までに12〜14時間の空腹時間ができ、体脂肪の燃焼が自然に促されていきます。 これは単なる減量だけでなく、細胞の修復を促すオートファジー(自食作用)も働き始める時間帯でもあり、体の中から若返りが始まるチャンスなのです。 「空腹は敵」ではなく、あえて空腹を作ることで、体は本来のエネルギー代謝を取り戻し、内臓にも休息が与え、無理なく週に一度の夜断食から始めることで、シニア世代でも安全に、そしてリバウンドせずに、体を軽く、若々しく保つことができるのです。睡眠時間を入れて胃腸を休息 夜断食の効果をより高めるためには、内臓をしっかり休ませる時間を確保する必要があり、その目安となるのが「16時間断食」というサイクル。 食後から16時間何も食べないことで、消化にかかるエネルギーを使わず、肝臓や腸などの臓器がしっかりと休息できるようになり、これは単なる減量だけでなく、全身の代謝や免疫にも好影響を与えるとされています。 一見すると長く感じるかもしれませんが、実際には睡眠時間も含めて考えれば意外と簡単で、夜7時に食事を終え、翌日の昼11時に次の食事をとれば、自然に16時間の断食が完成します。 つまり、1食を抜くだけで体に大きなリセット効果を与えることができるのです。【ポイント10倍&クーポンで最大10%OFF!】 ダイエット 酵素ドリンク ファスティープラセンタ100,000 1本 960ml 酵素 ファスティング 断食 プチ断食 選べる3タイプ 送料無料体と一緒に胃も整える 人の胃の大きさは、実は拳ふたつ分ほどしかないのですが、日常的に食べ過ぎていると、胃は徐々に伸びてしまい、満腹を感じにくくなっていきます。 特に肥満気味の人は、知らず知らずのうちに「膨らんだ胃」で多くの食事を必要とする状態になっているのです。 そこで有効なのが、夜断食によって胃や腸などの消化器官をしっかり休ませていき、食事の間隔を空けることで、胃は本来の大きさを取り戻しやすくなります。 さらに、味覚もリセットされ、濃い味や油っこいものを好む傾向が和らぎ、自然と薄味でも満足でき、体と一緒に胃も整えることで、無理なく太らない体づくりへと近づいていけるのです。【83%OFF】 3ヶ月セット ダイエットサプリ ダイエット サプリ お腹の脂肪を減らす 体脂サポート 内臓脂肪 皮下脂肪 ブラックジンジャー カルニチン HMB BCAA配合 90日分180粒 送料無料 機能性表示食品 ポイント消化脂肪は病気のもとに 体に余分な脂肪が蓄積されると、見た目だけでなく、健康にも大きな影響を及ぼしてしまいます。 内臓脂肪が増えると、糖尿病や高血圧、脂質異常症といった生活習慣病のリスクが高まり、いわゆるメタボリックシンドロームと診断されてしまうのです。 これらの病気は放置すると、心臓病や脳卒中、さらにはがんなど、命に関わる重大な疾患につながるリスクが高まります。 しかし、急激なダイエットはかえって健康を損なうこともあるため、無理のない方法でゆっくりと脂肪を減らしていくことが重要になっていきます。 サイクル化で習慣化も 週に1回の夜断食は、たった1日、16時間以上の空腹時間を作るだけのシンプルな方法で、難しい計画や特別な準備もいらず、誰でもすぐに取り入れられるのが魅力です。 週の始まりに断食を取り入れる「月曜日の夜」に実施することで、気持ちも新たにスタートを切ることができ、生活リズムのリセットにもなります。 また、土日は家族や友人との会食や外食の機会が増えやすく、つい食べ過ぎてしまう傾向があるので、週末明けの月曜日に胃腸をしっかり休めることは、内臓を整える良いサイクルにもつながります。 毎週同じ曜日に行うことで、無理なく自然に習慣化できるのも夜断食の大きなメリットになっていくのです。小さな習慣 [ スティーヴン・ガイズ ]夜だけ断食のメリットを知ろう 夜だけ断食は、無理なく実践できる健康法を実践する前に、体に起こるメリットを把握していきましょう。 1日1食を抜くだけで、消化器官を休ませ、体脂肪を効率よく燃やす環境を整えられます。 睡眠中に内臓がしっかり回復し、翌朝の目覚めもすっきり。体だけでなく、心のリズムも整ってくるのが夜断食の魅力になります。 この章では、その具体的なメリットをわかりやすく解説していきます。週に1回だけだから続けられる 近年、「断食」や「ファスティング」という言葉は、健康志向の高まりとともに一般にも広く知られるようになってきました。 芸能人やモデルの間でも実践者が多く、体重を減らすだけでなく体内のデトックスや細胞の若返りなど、さまざまな効果が期待できるとされており、健康番組や書籍でもたびたび取り上げられ、関心を持つ人が年々増えているのが現状です。 しかし、いざ自分が取り組もうとすると、まる1日何も食べない「1日断食」は思っている以上にハードルが高く感じてしまうもの 空腹に慣れていない人にとっては、途中でお腹が空いてつらくなったり、集中力が落ちたり、さらには頭痛やめまいなどの不調を感じることもあるのです。 シニア世代では、体の反応も敏感で無理をすれば逆に健康を損ねてしまう可能性もあるため、慎重な対応が求められます。 そこで「月曜日の夜だけ」と決めることで、心理的にも取り組みやすく「たった1日、しかも夜だけだから」と思えば、気負わずに始められ、習慣として続けやすくなるのです。 週末の外食や会食で食べ過ぎた分をリセットする意味でも、月曜日の夜断食は理にかなっています。 さらに、食べ過ぎやすい体質から、自然と「ちょうどよい量で満足できる体」へと変化していき、週に1回という手軽さが、無理のない肥満解消と健康維持につながっていくのです。【石原医師監修】 ファスティング お試し セット 6P ジュースクレンズ 無添加 ファスティングセット クレンズジュース 断食 コールドプレスジュース 野菜ジュース デトックス 生酵素ドリンク 美味しい 酵素 ダイエット 置き換えダイエット デトックス ドリンク 空腹で体の細胞が活性化する 週に一度、夕食を抜く「夜断食」を行うことで、私たちの体の内側では驚くべき変化が起こります。 空腹状態が12時間以上続くと、「オートファジー」という仕組みが働き始め、16時間を超えるころにはその活動がさらに活発になるのです。 これは、細胞内の古くなったタンパク質や壊れた構造を分解・再利用する機能で、いわば“体内の大掃除”のようなもの 人間の体は、約60兆個の細胞でできており、その細胞一つひとつがタンパク質によって構成されています。 私たちは日々、代謝を繰り返しながら古い細胞を新しく作り替えていますが、このときに劣化した部品が溜まってしまうと、老化や病気の原因になってしまいます。 オートファジーはそれらの不要物を取り込み、分解酵素と結びつくことで新たな材料へと再生してくれるのです。 日々、空腹の時間を意識的に作ることで、細胞のメンテナンスが促され、体の中から若々しく、健康な状態に保たれ 過剰なカロリー摂取を控え、週に1回だけでも夕食を抜いて空腹時間を確保することは、病気予防や老化防止に効果的な「シンプルな再生術」、無理のない範囲で空腹を味方につけ、細胞レベルからのリフレッシュを目指しましょう。落とすのは体重よりも体脂肪 ダイエットというと、多くの人がまず「体重を減らすこと」に目が向きがち、体重計の数字が減れば成果が出たように思えるものですが、実は本当に落とすべきなのは「体脂肪」になります。 なぜなら、私たちの体に悪影響を及ぼすのは、筋肉や骨の重さではなく、過剰な脂肪で、脂肪は大きく分けて「内臓脂肪」と「皮下脂肪」に分類されます。 皮下脂肪は、皮膚のすぐ下に蓄積される脂肪で、女性に多く見られ、お腹やお尻、太ももなどに付きやすいのが特徴で、冷えやむくみの原因になることはありますが、急激に健康を脅かすことは少ないとされています。 一方、内臓脂肪は腹腔内の内臓の周囲に蓄積される脂肪で、男性や閉経後の女性に多く、見た目には分かりにくい“隠れ肥満”の原因にも繋がります。 この内臓脂肪が問題なのは、脂肪細胞から悪玉アディポサイトカインという有害な物質が分泌され、慢性的な炎症を引き起こし、高血圧、高血糖、脂質異常症といった生活習慣病のリスクを高めてしまうのです。 脂肪には重要な役割もあり、寒さから身を守ってくれ、ホルモンの働きを支えたりと、体にとって必要な存在 しかし、現代人の多くは脂肪を摂りすぎており、脂肪細胞のバランスが崩れ、善玉のアディポサイトカインは減少し、逆に悪玉が増えてしまうことで、体はどんどん不調に傾いていきます。 女性は、50代以降に女性ホルモンのバランスが大きく変化し、内臓脂肪が増えやすく、見た目には大きく変わっていなくても、健康診断で腹囲や中性脂肪の数値が高くなることで気づくことも少なくないのです。 だからこそ、「体重」ではなく「体脂肪」の量と質に注目することが、シニア世代の健康維持には欠かせないので、体脂肪を正しく理解し、無理なく減らしていくことが、病気を遠ざけ、長く元気に過ごす鍵となるのです。本日終了\最大P14倍/プロテイン 女性 ダイエット ソイプロテイン プロテインダイエット 置き換えダイエット 置き換え シェイク ファスティング タンパク質 低糖質 低脂質 ホエイプロテイン 低カロリー バンビウォーター 春夏脂肪が蓄えられる仕組み 健康的に体脂肪を減らすためには、まず「脂肪が体に蓄えられる仕組み」と「脂肪がエネルギーとして使われる仕組み」を理解することが重要です。 私たちが毎日口にする食事は、体にとってのエネルギー源となり、糖質(ごはんやパン、麺類など)などは、体内でブドウ糖に変換され、脳や筋肉の活動に使われていきます。 しかし、この糖質が過剰になると、血液中のブドウ糖は肝臓や筋肉に「グリコーゲン」として一時的に蓄えられ、それでも余ってしまった分は、脂肪として体内に蓄積されることになるのです。 脂肪細胞は非常に柔軟性があり、内臓の周りや血管周囲など、体のさまざまな場所に溜まっていき、知らず知らずのうちに脂肪は増えてしまいます。 蓄えられた脂肪を減らすには、「脂質代謝」と呼ばれる仕組みを活性化させる必要があります。 これは、体が脂肪を分解してエネルギーとして使うプロセスのことですが、すぐには始まらず、食事をしてからしばらくの間、体はまず血糖やグリコーゲンといった“すぐ使えるエネルギー”を優先的に消費し、その後、ようやく脂肪を使う段階に入ります。 この脂質代謝が本格的に“オン”になるのは、食後から10時間以上が経過してからと言われているので、1日中こまめに食べ続けているような生活では、脂肪はなかなか燃焼されず、蓄積してしまうのです。 そこで「夜断食」を実行し、翌朝まで12〜14時間の空腹時間が生まれ、脂質代謝のスイッチが自然と入る状態になります。 週に1回でもこのサイクルを習慣化すれば、脂肪の蓄積を防ぎながら、内臓脂肪を徐々に減らしていくことが可能になります。臓器負担は老化の原因に 同じ年齢でも「若々しく見える人」と「年齢以上に老けて見える人」がいるのですが、その違いの一つは、外見だけでなく「体内年齢」にも関係しています。 見た目が若い人の多くは、体の中の代謝や細胞の働きが活発で、内臓への負担が少なく保たれている傾向にあり 反対に、日々の生活の中で内臓に過度な負担をかけていると、知らず知らずのうちに老化が進み、外見にもその影響が現れてしまうのです。 食べすぎや間食が多い人は、消化器官が常にフル稼働しており、疲れが取れにくい状態になっています。 その結果、目の下のクマや顔全体のたるみ、くすみが目立ちやすくなり、「なんだか疲れて見える」といった印象を与えてしまうのです。 胃や腸、肝臓などの臓器に休息を与える時間が少ないと、老廃物の排出もうまくいかず、体内に疲労物質がたまりやすくなります。 一方、消化に負担がかかっていない人は、顔色も明るく、肌の透明感やハリが保たれており、全体的に若々しく見え 日々、消化器官を休ませる時間を設けることで、臓器の修復やリセットの時間が確保され、体の中からの若返りが期待できます。 さらに、若く見える人の共通点として「水をよく飲む」ことも挙げられ、水は体内のあらゆる細胞に行きわたり、細胞の活動をサポートする大切な存在 注目していくのが「ミトコンドリア」の活性化で、ミトコンドリアは細胞の中でエネルギーを生み出す役割を担っており、水が十分にあることでその働きがスムーズになります。 結果として、疲れにくく、代謝の良い若々しい体を保つことができ、重要になるのは、臓器に負担をかけずに水分補給を行うこと。 冷たい水ではなく、常温や白湯をゆっくりと飲むことで、胃腸にもやさしく、吸収もよくなっていき、1日にコップ数杯の水を意識的に飲むことは、内臓を休めながら若々しさを維持するための、簡単で効果的な習慣なのです。素焼きアーモンド (1kg) アメリカ産 【メール便対応/1kgまで】夜断食で睡眠の質も向上していく 夜断食は、単に体重を減らすだけではなく内臓を休める事ができ、体脂肪の燃焼を促すと同時に「睡眠の質を高める」という重要な効果もあります。 実は、夕食を抜くことで体が自然なリズムを取り戻し、深く質の高い睡眠がとれるようになることが、さまざまな研究でも示されています。 夕食を遅い時間にとると、消化活動が活発なまま眠りにつくことになってしまい、胃腸が休むことができず、体は完全な休息モードに入れません。 睡眠中にも内臓が働き続けるため、眠っていても脳や体はしっかりとリカバリーできず、翌朝に「なんだか疲れが残っている」と感じる原因に 一方、夜断食によって夕方以降に食事をとらず、空腹状態で眠りにつくと、消化器官はすでに休息状態に入り、体全体が「回復モード」に切り替わります。 このとき、脳内では睡眠ホルモンであるメラトニンの分泌が促され、より深いノンレム睡眠を得やすくなり、眠りの質が高まり朝の目覚めもすっきりと感じられるようになるのです。 また、夜断食によって血糖値やインスリンの急上昇が防がれることも、睡眠の質の向上にも関係しており、血糖の乱高下は交感神経を刺激し、夜中の目覚めや浅い眠りの原因となることも シニア世代では、睡眠中の血糖バランスが乱れることで不眠や夜間頻尿などのトラブルも起こりやすくなるため、夜の食事量を控えることはとても理にかなった対策となります。 加えて、睡眠中には成長ホルモンが分泌され、体の修復や免疫の調整、脂肪燃焼などが加速し、夜断食によって深い眠りが得られるということは、これらのホルモンの働きもスムーズに行われるということ。 つまり、「太りにくい体」と「疲れにくい体」の両方を同時に手に入れるためのカギが、夜断食には秘められているのです。まとめ:肥満解消にぷち断食を取り込む シニア世代にとって、肥満は見た目の問題だけでなく、心臓病、糖尿病、脳卒中、がんといった生活習慣病のリスクを大きく高める「健康の敵」に しかし、多くの人が「どう痩せればいいか分からない」「一度試してダメだった」という経験を持ち、自信を失っています。 そんな中、今回ご紹介した「週に一回、夜だけ食事を抜く断食法」は、シンプルで誰でも取り組みやすく、体に優しい食事習慣になります。 16時間の空腹時間を作ることで、体脂肪が燃焼され、細胞の修復を促すオートファジーも活性化、胃腸を休めることで、味覚が整い食べ過ぎも防げるようになるのです。98キロの私が1年で40キロやせた 16時間断食 [ 青木 厚 ]インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく19-2
2025.08.10
コメント(0)
-
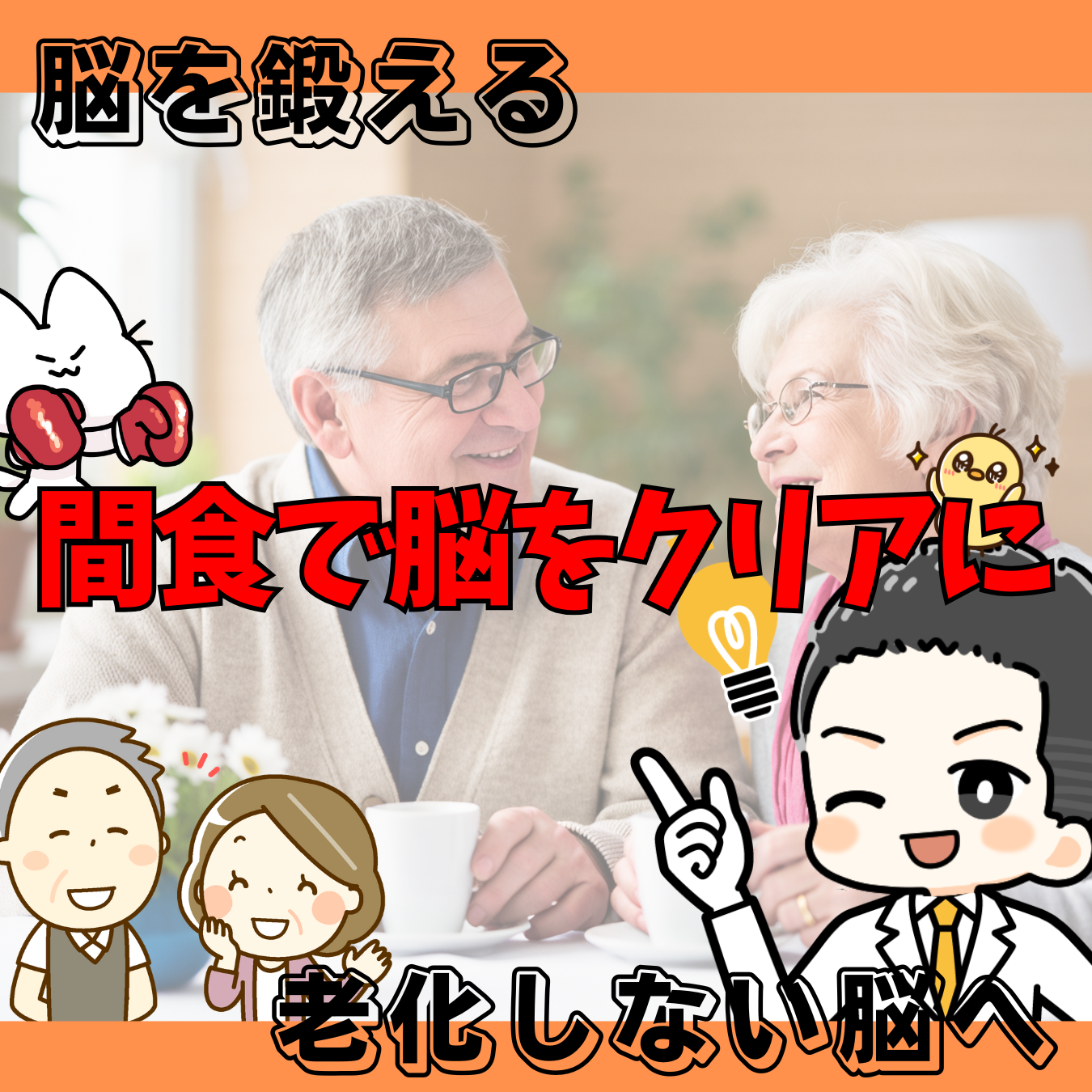
【脳を鍛える】間食で脳をクリアに 老化しない脳へ
脳の毒を食事で排出していこう 現代の食生活では、知らず知らずのうちに脳に「毒」が溜まっていきます。 食品添加物、過剰な糖質、悪質な油、腸内環境の乱れてしまい、これらが脳の働きを鈍らせ、老化や病気の原因に変わっていくのです。 第3章では、こうした毒を体の外へ追い出すために、毎日の食事でできるシンプルで効果的な方法を実践して若い脳を作っていきましょう。 食べ物で少しずつ脳の毒を出す 私たちは日々の生活のなかで、知らず知らずのうちに「毒素」を取り込んでいます。 空気中の排気ガス、飲み水に含まれる重金属、農薬の残留する野菜、食品添加物を多く含む加工食品など、現代社会では避けきれないものも少なくないのです。 特に水銀、カドミウム、ヒ素、鉛といった重金属は、体に蓄積されやすく、肝臓や腎臓だけでなく、脳にも悪影響を与えることがわかっており これらの毒素は神経細胞にダメージを与え、思考力や記憶力の低下、慢性的な疲労感、さらには認知症のリスクを高める要因にもなり得るのです。 しかし、体に入った毒素をただ嘆いても始まりません、私たちの体には「解毒(デトックス)」というすばらしい働きが備わっています。 その力を引き出し、サポートする鍵が「食事」になり、食べ物を選び、食べ方を工夫することで、体内に溜まった毒を少しずつ排出していくことが可能になるのです。 まず意識したいのが、なるべく「加工食品を避ける」こと、加工食品には保存料や着色料、人工甘味料、乳化剤などの添加物が多く含まれており、これらが肝臓や腸に負担をかけ、解毒機能を低下させることがあります。 毎日の食事で、できるだけ自然な素材を選び、手作りのシンプルな料理を心がけることで、体への負担を減らすことができるのです。 さらに、毒素の排出に役立つ栄養素も積極的に摂っていきましょう。 たとえば、ブロッコリーやキャベツ、玉ねぎなどに含まれる「硫黄化合物」は、肝臓の解毒酵素を活性化させてくれます。 また、海藻や味噌などに含まれる「アルギン酸」や「発酵食品」は、腸内の有害物質を吸着して体外へ排出する働きを助けてくれ、水溶性食物繊維も毒素を絡め取り、便として排出を促進するのです。脳を動かすのはブドウ糖だけでない 「脳を動かすのはブドウ糖だけ」と思われがちですが、実は脳の健やかな働きには、さまざまな栄養素が深く関わっています。 その中でも注目したいのが「ビタミンD」の存在になり、ビタミンDは骨の健康に必要な栄養素としてよく知られていますが、実は脳の神経細胞の働きにも欠かせない役割を果たしています。 脳内では、神経細胞と神経細胞をつなぐ「シナプス」が、情報を伝える重要な通路として働き、このシナプスは体の他の細胞と同様に、日々ダメージを受けたり古くなったりしながら、新しく生まれ変わっています。 しかし、ビタミンDが不足していると、新しいシナプスを十分に作ることができず、脳の情報伝達の効率が下がってしまい、ビタミンDが足りない状態では、集中力や記憶力、判断力が低下しやすくなり、脳の老化を早める可能性があります。 さらに、ビタミンDはメンタルの安定にも深く関与し、不安感やうつ症状との関連も指摘されており、気分の波が激しい人や冬季うつになりやすい人は、ビタミンDの不足が原因の一つかもしれません。 加えて、ビタミンDは「炎症を抑える遺伝子」や「腫瘍の発生を抑制する遺伝子」にも働きかけることがわかっており、全身の健康を守る要となる栄養素でもあるのです。 ビタミンDを摂る方法は大きく分けて三つあり、まずは食事から魚類(特にサバ、イワシ、サンマなどの青魚)や、干し椎茸、きくらげなどのキノコ類に多く含まれています。 次に日光浴、ビタミンDは皮膚に紫外線が当たることで体内でも合成されるため、1日15〜30分程度、腕や顔を日に当てることが推奨されます。 そして、三つ目が運動となり、ウォーキングや軽い筋トレなどで筋肉を使うと、シナプスの再生や神経の働きが活性化され、ビタミンDの働きも高まっていきます。カルシウム<栄養機能食品>【ファンケル 公式】[FANCL ビタミンd サプリ サプリメント カルシュウム マグネシウム 男性 栄養 女性 食事で不足 ミネラル ビタミン ヘルスケア カルシウム補給 カルシウムサプリ 健康食品 大容ホモシステインの事を知る ホモシステインとは、脳と体の健康を守るうえで、注目すべき重要な指標のひとつになります。 これは、必須アミノ酸である「メチオニン」が体内で代謝される過程で生じる中間産物で、通常は肝臓で無害な物質へと変換されるため、体内に溜まることはないのですが 何らかの理由で代謝がうまくいかなくなると、血中のホモシステイン濃度が上昇し、さまざまな健康トラブルを引き起こす原因となるのです。 ホモシステインの値が高いということは、脳に栄養が行き届いていなかったり、慢性的な炎症が起きているサインである可能性があり、近年の研究では、ホモシステインの過剰が脳の神経細胞を傷つけ、アルツハイマー病の発症リスクを高めることが示されています。 さらに、血管の内皮細胞を攻撃する作用もあるため、動脈硬化を進行させ、心臓病や脳卒中などの心血管疾患のリスクも増大してしまうのです。 つまり、ホモシステイン値が高い状態を放置することは、脳にも血管にも大きなダメージを与えるリスクがあり、この値を適切に保つことは、老化予防・認知症予防・脳の若さを維持するうえで、極めて重要なテーマとなります。 では、どうすればホモシステインの数値を下げるのがビタミンB群の存在で、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸は、ホモシステインの代謝をスムーズにし、無害な形に変えるために不可欠な栄養素になるのです。 ビタミンB6は、にんにく、まぐろ、バナナなどに多く含まれ、ビタミンB12は魚介類やレバーに豊富に含まれています 葉酸は緑黄色野菜、ほうれん草やブロッコリー、アスパラガスに含まれているので、これらをバランスよく日々の食事に取り入れていき、ホモシステイン値を下げ、脳の健康を維持、守っていきましょう。【セール中】マルチビタミン(約3ヶ月分) [栄養機能食品] 食事で不足 野菜不足ビタミンd ビタミンM 葉酸 ダイエット 美容 健康 サプリメント サプリ 送料無料 オーガランド 12種 の ビタミン 配合 気持ち の バランス 偏食 口コミ 食物繊維で腸を綺麗に 食物繊維は、腸内環境を整え便通を促すだけでなく、体に溜まった毒素を排出するために欠かせない栄養素 現代人は加齢や食生活の偏り、運動不足などの影響で腸の働きが鈍くなり、便秘がちになる傾向があります。 こうした状態が続くと、腸内に有害物質がとどまり、再吸収されるリスクが高まり、全身の不調につながるのです。 そこで、食物繊維を意識的に取り入れ、腸内の“お掃除”をすることが、健康を守る第一歩になっていきます。 食物繊維には水溶性と不溶性の2種類があり、どちらも大腸の働きをサポートするのに役立ちますが、それぞれに異なる特徴があります。 水溶性食物繊維は、水に溶けるとゲル状になり腸内をゆっくり移動しながら便を柔らかくしてくれるのです。 めかぶや昆布などのネバネバ食品に含まれる水溶性食物繊維は、腸に長くとどまり、腸内で固くなった便をやさしくほぐし、スムーズな排出を促してくれ、シニア層に多い便秘の改善にもつながります。。 一方、不溶性食物繊維は水に溶けずに便のかさを増やし、大腸を刺激してぜん動運動を活発にし、野菜、豆類、穀物などに多く含まれ、腸の筋肉をしっかりと動かす役割があります。 この2つの食物繊維をバランスよく摂ることで腸が活性化し、便が自然に、そして、気持ちよく出るようになります。 さらに、食物繊維は腸内の善玉菌のエサにもなり、腸内フローラを整える重要な役割も担っており 善玉菌が増えることで、腸内の腐敗菌や悪玉菌が減少し、アンモニアなどの有毒ガスの発生を抑制、このことにより、腸内での炎症や毒素の再吸収が防がれ、全身の健康状態も改善されていくのです。 加えて食物繊維には、ナトリウムの排出を促す働きがあるため、高血圧の予防にも役立ちます。 余分なコレステロールも吸着し、体外に排出する作用もあるため、動脈硬化や心疾患のリスクを減らすのにも効果的、さらに、腸の働きが良くなることで、肝臓や腎臓の機能も高まり、全身の解毒力がアップしていくのです。イヌリン 機能性表示食品 500g 【食後の 血糖値 や 便秘 が気になる方に】 サプリメント サプリ 菊芋 食物繊維 天然 チコリ由来 ダイエット オランダ産 水溶性食物繊維 パウダー 粉末 イヌリア顆粒 ロハスタイル LOHAStyle 亜鉛の効果で水銀を鉛を弱体化 亜鉛は、私たちの体の中で数百以上の酵素の働きを支える、非常に重要なミネラルの一つです。 もし、最近「傷が治りにくい」「肌の乾燥がなかなか改善しない」「味覚が鈍くなった気がする」そんな症状を感じている場合、亜鉛不足が関係しているかもしれません。 甘さや塩味の強さが感じにくくなったときは、味覚障害の初期サインとも考えられています。 亜鉛は、細胞分裂や再生に必要不可欠な栄養素で、体のあらゆる組織の修復に関与し、新しい皮膚細胞や内臓の粘膜細胞、そして脳の神経細胞にも、常に亜鉛の助けが必要になるのです。 とくに、脳においては神経伝達の調整や記憶力の保持、精神の安定などにも深く関わっているため、亜鉛が不足すると、精神的な不調や集中力の低下、イライラなどの症状が現れることもあります。 加えて、近年注目されているのが、亜鉛が持つ「重金属のデトックス効果」、現代の生活環境では、知らず知らずのうちに水銀や鉛といった有害な金属を体内に取り込んでしまうことも 水銀は一部の魚介類や古い医療用具、鉛は塗料や水道管、喫煙、排気ガスなどが主な原因となり、これらの重金属は体内に蓄積しやすく、特に脳や神経に悪影響を及ぼすことが知られています。 このような有害金属の毒性を弱め、体の外へ排出するのに役立つのが亜鉛となり、亜鉛は、水銀や鉛といった重金属と結びついて、それらの吸収を防ぎ、解毒の過程で無毒化を促進する働きがあるのです。 つまり、脳や体に悪影響を及ぼす毒素の排出を助ける“影の立役者”とも言え、そんな亜鉛を豊富に含む食品の代表格が「牡蠣」になります。 牡蠣は、“海のミルク”と呼ばれるほど栄養豊富で、特に冬場にはその含有量が増加、牡蠣以外にも、赤身の肉、レバー、納豆、ナッツ類、卵黄などにも含まれ、これらを食事にバランスよく取り入れることが、亜鉛の補給に効果的になるのです、 ただし、亜鉛は単体では吸収効率があまり良くないため、「鉄分」と一緒に摂るのが重要になり、鉄分も血液や代謝に必要な栄養素、相互に補完し合うことで、効率よく体内に吸収されやすくなります。 世界では20億人以上が亜鉛不足と言われており、日本でも高齢者や偏食傾向のある人に不足しやすい栄養素なので、毎日の食事で意識して摂ることで、脳の老化を防ぎ、重金属の害から体を守る手助けになります。栄養機能食品 これ1粒で補える 亜鉛 (約3ヶ月分) 送料無料 小粒 亜鉛 サプリ 1日1粒 で 必須ミネラル の 亜鉛 が 推奨量摂取できる サプリメント 男性 元気 亜鉛 サプリ 妊活 中の 食生活をサポート オーガランド 口コミ 亜鉛サプリカレーはスパイスカレーを カレーは私たちにとってなじみ深い料理ですが、脳の健康を考えるなら「スパイスから作るカレー」がおすすめになります。 市販のルーには小麦粉や脂質、添加物が多く含まれており、知らず知らずのうちに体に負担をかけていることもあるのです。 その反面、スパイスを自分で組み合わせて作るスパイスカレーは、余分な添加物を避けられるだけでなく、使用するスパイスの健康効果をしっかりと活かせるのが大きな魅力 とくに注目したいのが「ターメリック」、ウコンとして知られるこのスパイスには、「クルクミン」という強力な抗酸化成分が含まれています。 クルクミンは、脳内の神経細胞の成長を促す「脳由来神経栄養因子(BDNF)」を増やす働きがあり、記憶力や集中力、認知機能の維持に役立ってくれるのです。 年齢とともに減少しがちなこの因子をサポートするためにも、定期的にターメリックを取り入れることは非常に効果的 さらに、クルクミンと相性が良いのが「オメガ3脂肪酸」、オメガ3は脳細胞の膜を構成する大切な脂質であり、不足すると神経伝達がスムーズにいかなくなってしまいます。 クルクミンと一緒に摂ることで、脳内の炎症を抑え、神経機能を高める相乗効果が期待でき、おすすめになるのが「サバ缶入りスパイスカレー」 サバ缶にはDHAやEPAといったオメガ3脂肪酸が豊富に含まれており、クルクミンとの組み合わせで脳を栄養づける理想的な一品となります。 また、カレーに添えるサラダにも一工夫していき、ドレッシングの代わりに「亜麻仁油」や「エゴマ油」を使えば、こちらもオメガ3をしっかり補えます。 野菜の酵素と合わせて摂ることで、脂肪酸の吸収も高まり、腸内環境の改善にもつながり、食事で脳に刺激を与え、しっかりと栄養を届けるスパイスカレーは、まさに“脳のごちそう”なのです。【8/11までクーポンあり】カレースパイス セット 3種 各100g レシピブック付き 初心者でも 約100皿分 チャック袋入り カレー スパイス スパイスカレー カレーパウダー カレー粉 カレースパイスパウダー スパイスセット 送料無料小腹が減ったらナッツを用いる 小腹がすいたとき手が伸びるおやつ、その選択を見直すだけで、脳の健康が大きく変わります。 糖質制限や主食を少量に抑える食事スタイルでは、脳がブドウ糖に依存しにくくなり、次第に「おやつが欲しい」と感じる頻度も減少 しかし、それでも日常生活の中で空腹になる瞬間は誰にでも訪れ、そのときに注意したいのが「何を口にするか」になるのです。 例えば、空腹時にチョコレートや菓子パンなどの砂糖を多く含む食品を食べると、血糖値が一気に上昇し、その後急激に下がる「血糖値スパイク」が起こります。 これが繰り返されると、脳の神経細胞にダメージを与え、集中力の低下やイライラ、疲労感、さらには認知機能の低下にもつながっていくので、空腹時の“間違ったおやつ”は、脳にとって毒にもなり得るのです。 そこで「ナッツ類」、ナッツには良質な脂質が豊富に含まれており、特にオメガ3脂肪酸やオレイン酸など、脳の炎症を抑えたり神経の働きをサポートする栄養素が豊富 また、食物繊維も含まれ、腸内環境を整える作用もあり、便通を改善しながら毒素の排出を助ける働きも持っています。 さらに注目したいのは、ナッツに含まれるミネラル、マグネシウム、亜鉛、鉄、セレンなど、現代人に不足しがちな微量栄養素が自然な形で摂れるのも、ナッツならではの魅力です。 「ブラジルナッツ」には、セレンというミネラルが豊富で、このセレンには水銀を解毒する働きがあるので、水銀は現代の生活の中で魚介類や環境汚染を通して知らずに体に蓄積しがちな有害物質であり、その除去にはセレンが非常に重要な役割を果たしてくれます。 また、ナッツは硬いため、自然とよく噛んで食べるようになり「よく噛む」行為は、満腹中枢を刺激し、食べ過ぎを防ぐだけでなく、脳への血流を増やして活性化させる作用をもたらします。 噛むことによって唾液の分泌も促進され、消化吸収を助けるだけでなく、口腔内の清潔も保たれます。 ナッツをおやつとして取り入れる際は、無塩・無油・無添加のものを選びましょう。 アーモンド、くるみ、カシューナッツ、マカダミアナッツ、ピスタチオなど、種類を変えて楽しめますが、ナッツはカロリーが高めなので、一日あたり小さなひとつかみ(20〜30g)を目安にするのが適量です。3種 ミックスナッツ 無添加 850g【2023楽天グルメ大賞ミックスナッツ部門受賞】産地直輸入 くるみ アーモンド カシューナッツ 無塩 添加物不使用 植物油不使用 防災食品 非常食 保存食果物で不足する栄養を補給する 果物は「甘いから太る」「糖質が多いから控えたほうがよい」と誤解されがちですが、実は脳と体の健康を保つために欠かせない栄養素が多く含まれている重要な食品 確かに果物には果糖(フルクトース)という糖質が含まれていますが、それと同時に、糖の吸収を緩やかにする「食物繊維」も豊富に含まれており、血糖値の急上昇を防ぐ働きをしてくれます。 注目したいのが「ビタミンC」の存在で、ビタミンCは抗酸化ビタミンとして細胞の老化を防ぎ、ストレスへの抵抗力を高め、免疫力をサポートするほか、「コラーゲン」の生成に欠かせない栄養素でもあるのです。 肌や血管、脳を構成する細胞の健全性を保つためにも、ビタミンCの摂取は非常に重要で、キウイや柑橘類、イチゴなどは、手軽にビタミンCが摂れる果物としておすすめになります。 さらに、果物のもうひとつの魅力は「ファイトケミカル」と呼ばれる植物性機能成分 例えばブルーベリーに含まれるアントシアニンや、ブドウのポリフェノール、リンゴのケルセチンなど、果物それぞれに独自の抗酸化物質が含まれています。 これらの成分は、活性酸素を除去し、脳細胞や血管の老化を防ぐとともに、炎症を抑える役割も果たしてくれます。 また、果物には水分と食物繊維が豊富に含まれているため、腸内の老廃物の排出を助け、便通を改善する効果も期待でき、シニア世代は、排便をスムーズにすることが脳や体に毒素を溜めないための重要な習慣になるのです。ドライフルーツミックス 1kg ドライフルーツ クランベリー マンゴー パパイヤ パイン レーズン グリーンレーズン 大人気 6種類ドライフルーツミックス おやつ 健康 栄養 フルーツ 高品質 ドライフルーツ【送料無料】 ハイカカオで甘さを補給 甘いものが欲しくなったとき、脳と体にやさしい選択としておすすめなのが「ハイカカオチョコレート」、カカオ分70%以上のものは、糖分が控えめで豊富な栄養素と機能性を兼ね備えています。 ハイカカオチョコレートに多く含まれる「カカオポリフェノール」は、非常に優れた抗酸化作用を持ち、体内で発生する活性酸素を除去、細胞の老化や炎症を防いでくれるのです。 これは脳の健康維持にも効果的で、神経細胞の酸化ストレスを抑えることで、記憶力や集中力の維持にも役立つとされています。 また、カカオポリフェノールは吸収率が高く、摂取してすぐに体内で働き始めるのも特徴になるのです。 さらに、悪玉コレステロール(LDL)の酸化を防ぐことで、動脈硬化や心血管疾患の予防にも貢献するといわれ、これは脳卒中などのリスクを下げる意味でも重要なポイントになります。 ハイカカオチョコレートには、ビタミンやミネラルも豊富に含まれ、注目したいのが、カリウム、カルシウム、マグネシウム、亜鉛といったミネラル成分です。 これらは神経の伝達、骨や筋肉の健康、免疫機能のサポートなど、さまざまな場面で欠かせない役割を果たしてくれます。 また、甘味を抑えているため血糖値の上昇も緩やかで、砂糖たっぷりのお菓子とは違い、食べても罪悪感が少なく安心して楽しめます。 チョコレートが苦手な方や、もう少しバリエーションが欲しい方は、カカオ100%のピュアな「ココアパウダー」を使ってヨーグルトに混ぜたり、豆乳と合わせてドリンクにして味わっていきましょう。ココアパウダー 「砂糖不使用 2種類から選べるココアパウダー (軽やか!低脂肪ココアパウダー/濃厚!純 ココア パウダー) 500g」 送料無料 [ ピュアココアパウダー 純 ココア ココアパウダー 無糖ココアパウダー 純ココア 無糖 カカオ ]まとめ:間食で脳のデトックスを 「毒を出す」ためには、デトックス作用をもつ栄養素を意識して取り入れることが効果的になります。 空腹時のおやつには、ナッツ類を用いて、良質な脂質とミネラルを補い、甘いものが欲しいときは、ハイカカオチョコレートで満足感を得つつ、抗酸化物質も補給できます。 これらの小さな習慣を重ねることが、脳の健康寿命を延ばし、老化や病気を遠ざける最善の方法になり、食事は毎日の積み重ね。脳のために今日から一歩ずつ、「毒を出す食事」を始めていきましょう。インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく18-終
2025.08.09
コメント(0)
-

【脳をまもる】脳に毒を入れない 老化防止食
脳に毒を入れない食事術 このブログでは「脳に毒を入れない食事術」になり、私たちの食卓には、一見普通に見えても脳に悪影響を及ぼす“隠れた毒”が潜んでいます。 食品添加物や過剰な糖質、トランス脂肪酸などは、知らぬ間に脳の炎症や老化を進める要因となるのです。 ここでは、脳を守るために避けたい食べ物や、逆に脳の解毒を助ける食材を食べていき、毎日の食事から、脳に毒を入れないための賢い選択を身につけていきましょう。糖質制限が脳に毒を入れない方法 糖質を控える食事は、脳に毒をためないために非常に有効な食事法といえます。 過剰な糖質は、体内でタンパク質と結びついて「AGEs(終末糖化産物)」という有害物質を作り出すのです。 AGEsは体の老化を進めるだけでなく、脳にも悪影響を及ぼし、神経細胞を傷つけたり、炎症を引き起こすのです。 とくにアルツハイマー病の患者の脳には、このAGEsが多く見られることから、認知症との関連も深いと考えられています。 また、糖質を多く摂り続けていると、血糖値が慢性的に高くなり、インスリンというホルモンが効きづらくなる「インスリン抵抗性」が生じます。 これは、インスリンがうまく働かず、血糖を細胞に取り込めなくなる状態で、脳の神経細胞へのエネルギー供給も不安定になってしまうのです。 実はインスリンには、脳内での記憶や学習に関わる重要な役割があり、その働きが悪くなることで認知機能が低下するリスクが高まります。 このインスリン抵抗性の原因としては、糖質のとりすぎに加え、肥満や運動不足などの生活習慣も深く関わっていくので早期の改善が必要になるのです。 白米を玄米に変えていく 糖質を減らすことは、脳に毒をためないための重要な食事法ですが、同時に「糖質でお腹を満たしすぎない工夫」も求められます。 つい手軽でおいしい白米を中心に食事を組み立ててしまいがちですが、ここを「玄米」に変えることで、大きな健康効果が期待できます。 玄米と白米は、実はカロリーや糖質の量自体に大きな違いはありませんが、玄米は精製されていないぶん、食物繊維やビタミン、ミネラルが豊富に含まれており、食後の血糖値の上昇を緩やかにしてくれます。 これは、急激な血糖値の変化を防ぎ、インスリンの過剰分泌や脳への負担を減らすことにつながり、結果として脳の老化を防ぎ、認知機能の低下も抑制できるのです。 さらに、玄米は現代人に不足しがちな栄養素である亜鉛、カルシウム、カリウムなどを自然な形で摂取できる貴重な主食になり これらのミネラルは神経の働きを助けてくれ、脳内の電気信号をスムーズに流す役割を果たしています。 また、玄米に含まれる食物繊維は腸内環境を整えるだけでなく、よく噛むことで満腹中枢が刺激され、食べ過ぎの防止にもつながり、噛む回数が増えることは脳の血流を良くし、記憶力や集中力の向上にも一役買ってくれるのです。 ただし、玄米を取り入れるうえで注意すべき点もあり、それは「残留農薬」、玄米は表面のぬか層がそのまま残っているため、農薬の影響を受けやすいのです。 健康のために玄米を食べていても、農薬を一緒に取り込んでしまっては本末転倒になるので、購入の際は、「無農薬」や「減農薬」と表示されたものを選ぶようにしていきましょう。【半額セール★1500円⇒750円】 雑穀米 混ぜるだけ 送料無料 くまモン おまけ 25種雑穀 国産二十五雑穀米 無添加 熊本県産 もち麦 保存食 買い回り 備蓄米 ランキング ≪8月中旬-8月下旬頃より発送予定≫|米以外の糖質にも要注意を 米の糖質だけでなく、それ以外の糖質にも注意が必要で、現代の食生活では、パンやパスタ、うどん、ラーメンなど、小麦粉から作られた食品が多く並んでいます。 これらは柔らかく食べやすいため、あまり噛まずに早食いになってしまい、その結果、血糖値が急上昇し、インスリンの過剰分泌や脳への負担が大きくなるのです。 パンを選ぶなら、小麦粉ではなく全粒粉やライ麦を使ったものを選んでいくことで、食物繊維やミネラルも豊富に摂ることができます。 また、昼食の麺類は、うどんやラーメンよりも、そばを選んでいくようにし、そば粉の割合が高いものを選ぶと、血糖値の上昇がゆるやかで、脳と体にやさしい食事になります。送料無料 岡山県産 半鐘屋の米粉入り食パンミックスセット【10個】(半鐘屋オリジナル・ホームベーカリー・米粉パン)糖質の多い野菜にも気を付ける 糖質制限を意識するとき、主食や甘いお菓子ばかりに目が行きがちですが、実は「野菜や果物」にも注意が必要となり、その判断の目安となるのが「GI値(グリセミック・インデックス)」という指標です。 GI値とは、食品を摂取したときにどれくらい血糖値が上昇するかを数値化したもので、ブドウ糖を100としたときの相対的な数値で示され 一般的に、GI値が高いほど血糖値を急激に上げやすく、インスリンの過剰分泌や体への負担が大きくなるのです。 たとえば、肉や魚、卵、大豆製品、葉物野菜などはGI値が低いため、血糖値を安定させる食材として安心して取り入れられます。 しかし、注意したいのが、調味料や高糖度の野菜、果物、そして芋類や根菜類 じゃがいもやにんじん、かぼちゃといった甘みの強い野菜はGI値が高めで、食べ過ぎると血糖値を急上昇させてしまうことがあるのです。 また、バナナやパイナップルなど糖度の高い果物も、摂取のタイミングや量に気をつける必要があります。 さらに、砂糖やみりん、ケチャップなどの調味料も知らないうちに糖質を多く含んでいるため、毎日の調理での使い方に注意が必要で、少量でも積み重なることで血糖のバランスを崩す可能性を持っています。 脳の健康を守るためには、血糖値の急激な上下を避けることが基本になり、GI値を意識して食材を選び、血糖値のコントロールをすることが、脳への負担を軽減し、老化や認知症のリスクを防ぐ食事につながります。 油を味方に変えていく 脂質というと「太る」「健康に悪い」というイメージを持たれがちですが、実は脂質は私たちの体にとって欠かせない重要な栄養素のひとつ 脂質は、細胞膜の材料になったり、ホルモンの合成を助けたり、脳や神経の働きを正常に保ったりと、多くの生命活動に関与しています。 特に脳は、約60%が脂質で構成されているともいわれ、良質な脂質を摂ることが、脳の健康維持に直結しているのです。 しかし、現代の食生活では、脂質の「質」が大きな問題になっています。 加工食品や外食、スナック菓子、ファストフードなどに多く含まれるトランス脂肪酸や、過剰に摂られるオメガ6系脂肪酸(リノール酸など)は、体に慢性的な炎症を引き起こしやすく、脳にも悪影響を及ぼします。 これらの脂質は血液をドロドロにし、血管を傷つけ、認知症や脳梗塞のリスクを高める可能性も指摘されているのです。 そこで重要なのが、脂質を“敵”ではなく“味方”に変えていき、炎症を抑え脳の働きをサポートしてくれる良質な脂質を積極的に取り入れることを意識し、その代表になるのが、オメガ3脂肪酸とオレイン酸です。 オメガ3脂肪酸には、植物性の「α-リノレン酸」と、魚に豊富な「EPA」「DHA」があり、α-リノレン酸はエゴマ油や亜麻仁油に多く含まれ、体内でDHAやEPAに一部変換されて働きます。 これらの脂肪酸は、脳の神経細胞を保護し、炎症を抑え、血流を改善する働きをもたらし、青魚(サバ、イワシ、サンマなど)を積極的に食べたり、サラダにエゴマ油や亜麻仁油をかけていきましょう。 一方、オレイン酸は、オリーブオイルに多く含まれる一価不飽和脂肪酸で、抗酸化作用に優れ、悪玉コレステロールを下げて血管の健康を保つ働きをもたらしてくれます。 「エキストラバージン・オリーブオイル」は、オレイン酸に加え、ポリフェノールやビタミンEなどの抗酸化成分も豊富で、脳の老化を防ぐ力が期待されているのです。 さらに注目したいのが中鎖脂肪酸(MCT)、これはココナッツオイルやMCTオイルに含まれており、消化吸収が早く、エネルギーとして素早く使われる特徴があります。 MCTオイルは、脳のエネルギー源となる「ケトン体」の産生を促進し、認知機能の改善や脳の活性化に効果があるとされているのです。 脳に毒を作らない、炎症を生まない食生活には、良質な脂質を意識的に取り入れることが重要になり、オメガ3脂肪酸やオレイン酸、中鎖脂肪酸といった“脳によい脂”を選ぶことで、脂質は危険なものではなく、むしろ脳を若々しく保つ強力な味方になってくれます。脂質を脳のエネルギーに変える 糖質を控え、良質な脂質を積極的にとることで、脳のエネルギー源を「糖」から「脂肪」に切り替えることができます。 この状態を「ケトン体質」と言い、脂質が分解されてできるケトン体が、ブドウ糖に代わって脳の栄養源として活躍してくれます。 特に、糖質の摂取量が多い現代の食生活では、血糖値の乱高下やインスリンの過剰分泌によって脳が疲れやすくなっているため、このエネルギーの切り替えは非常に有効です。 ケトン体を効率よく作るための脂質には「MCTオイル」、これは中鎖脂肪酸100%で構成されており、通常の油と比べてすばやく消化・吸収され、肝臓で即座にケトン体へと変換されます。 そのため、朝食や間食にMCTオイルを少量取り入れることで、脳へのエネルギー供給がスムーズになり、集中力や記憶力の向上も期待できます。 また、脂質と聞いて敬遠されがちなバターも、量を守れば優れた栄養源になってくれ ビタミンA、D、Eといった脂溶性ビタミンを含み、さらに「発酵バター」には乳酸菌が含まれており、腸内環境の改善にもつながってくれ、腸と脳は密接につながっているため、腸内環境を整えることは、脳の毒を減らすためにも重要になっていきます。★ポイント2倍★【医師推奨】MCTオイル 360g 仙台勝山館 【送料無料】| ココナッツオイル をお探しの方にも 無臭 で使いやすい 高品質 mct エムシーティオイル mtc mtcオイル 糖質制限 バターコーヒー グラスフェッドバター コーヒー 中鎖脂肪酸 ケトン体トランス脂肪酸とオメガ6に注意 脂質は体にとって必要不可欠な栄養素ですが、すべての油が健康に良いわけではありません。 なかには、摂りすぎたり、質の悪いものを選んでしまうと、かえって体に害を及ぼす油も存在し、注意すべきなのが、「トランス脂肪酸」と「オメガ6脂肪酸」の過剰摂取です。 トランス脂肪酸は、植物油を高温処理したり、水素を添加して加工する過程で生まれる人工的な油脂になり、マーガリン、ショートニング、スナック菓子、パンや洋菓子の一部などに含まれています。 トランス脂肪酸は、LDL(悪玉)コレステロールを増やし、HDL(善玉)コレステロールを減らすことで、動脈硬化や心筋梗塞のリスクを高めるとされており、アメリカやヨーロッパの多くの国では使用規制が始まっている場所もあるのです。 日本では完全に規制されていないため、私たち自身が食品表示を確認し、意識して避ける必要があります。 また、注意が必要なのが、サラダ油やコーン油、大豆油などに多く含まれる「オメガ6系脂肪酸」 これらはもともと必須脂肪酸であり、体に必要な成分ではありますが、現代の食生活では摂取量が過剰になりやすい傾向にあり オメガ6を摂りすぎると、体内で炎症を引き起こす物質が作られやすくなり、動脈硬化や高血圧、さらにはアレルギーや自己免疫疾患などのリスクを高めてしまうのです。 トランス脂肪酸や過剰なオメガ6脂肪酸は、加工食品や外食に多く含まれ、安価で使いやすいため、知らず知らずのうちに私たちの食卓に入り込んでいるので注意をしましょう。調理方法でも老化物質が発生 料理の仕方ひとつで、体内の老化を進める物質「AGEs(終末糖化産物)」が多く発生してしまいます。 AGEsは、糖とタンパク質が高温で加熱されることにより変質してできる物質で、体内に蓄積すると細胞や血管にダメージを与え、老化や認知機能の低下、生活習慣病の原因になるとされています。 注意したいのが、料理の「焦げ」や「焼き色」、黒く焦げた部分は、まさに目に見えるAGEsそのもので、トーストの焼き目や揚げ物のこんがりした茶色い衣なども、AGEsが多く含まれているサインといえます。 こうした調理法を毎日のように繰り返していると、知らず知らずのうちにAGEsを体に取り込んでしまい、脳や体の老化を加速させてしまうのです。 そこで見直したいのが調理方法で、「生」「ゆでる」「蒸す」「煮る」といった低温・短時間の加熱調理は、AGEsの発生が少ないため、体にやさしい選択肢となります。 たとえば、生野菜のサラダにはAGEsがほとんど含まれず、腸内環境の改善や抗酸化作用も期待できます。 また揚げ物や焼き物を食べたいときには、仕上げにレモン果汁やお酢をかけることで、AGEsの吸収を軽減することができるので積極的に使用していきましょう。 お肉は赤身肉を食べていく 牛肉や豚肉、鶏肉といった肉類は、私たちの体にとってとても大切なタンパク源になります。 シニア世代では、食が細くなりがちなうえに、消化力や吸収力も低下しやすくなるため、意識して毎日取り入れていきたい食材のひとつになるのです。 肉類に含まれる良質なタンパク質は、筋肉や内臓、免疫細胞、ホルモン、酵素など、体を構成するあらゆる部分の材料となります。 また、肉類にはタンパク質だけでなく、現代人に不足しがちな栄養素も多く含まれており、代表的なのが「ヘム鉄」と「亜鉛」です。 ヘム鉄は、体に吸収されやすい鉄の形であり、貧血予防や脳の酸素供給に役立ち、亜鉛は免疫力を保つほか、味覚や皮膚の健康、傷の修復にも欠かせないミネラル これらの栄養素は植物性食品には含まれていても吸収率が低いため、動物性食品からしっかり摂ることが効果的になるのです。 赤身肉は、脂肪分が控えめでありながらタンパク質やミネラルが豊富なため、健康的に栄養を補うのに適しています。 筋力の低下は転倒や骨折のリスクを高めるだけでなく、外出や活動意欲の低下を引き起こし、運動不足や孤立を招くきっかけにもなってしまいます。 肉をしっかり食べることは、体を動かす力を維持し、病気の予防や心の健康にもつながるので、積極的に赤身肉を取り入れ、元気な体を支えていきましょう。人工甘味料を避けていく 糖質制限や血糖値のコントロールを意識していても、日常的に使っている調味料や飲み物の中に「見えない糖」が潜んでいることがあります。 ジュースやドレッシング、タレ、加工食品などに多く含まれる「果糖ブドウ糖液糖」、これは、とうもろこしなどのでんぷんから作られた高甘味の糖分で、安価で使いやすいため、様々な製品に使用されています。 しかし、この果糖ブドウ糖液糖は体内で急激に吸収され、血糖値を一気に上昇させる原因にもなり、せっかく糖質を制限していても、こうした“隠れ糖質”を摂っていては、本末転倒になってしまうのです。 最近では「人工甘味料」の使用も増えており、これらも健康への影響が懸念されています。 アセスルファムK、スクラロース、アスパルテームといった人工甘味料は、カロリーゼロや糖質ゼロをうたいながらも、脳の味覚中枢を刺激して甘味への依存を高めたり、腸内環境を乱す可能性が指摘されているのです。 一部の研究では、人工甘味料がインスリンの反応を変え、かえって血糖コントロールを悪化させるリスクも示唆されています。 甘味をどう摂る場合は、自然な甘味を使った代替調味料を取り入れるのがおすすめになり、たとえば、「オリゴ糖」は腸内の善玉菌を育てる働きがあり、血糖値の上昇も緩やかに また、「甘酒」や「塩麹」などの発酵食品には自然な甘味があり、栄養素も豊富で、体に優しい選択肢になります。 これらは料理の味付けにも使いやすく、日常の中で自然と糖質を抑えながら、脳に負担をかけない食生活を実現できるのです。 見えない糖や人工甘味料は、知らず知らずのうちに脳や体にダメージを与える可能性があり、脳の毒をためない食事習慣になりますが、甘味を完全に断つのではなく賢く選んで、脳にやさしい生活を心がけていきましょう。フラクトオリゴ糖 1kg 天然 チコリ由来 【送料無料】【メール便で郵便ポストにお届け】【代引不可】【時間指定不可】 粉末タイプ 約97.5%含有 [01] NICHIGA(ニチガ)グルテンが腸に炎症を招く グルテンとは、小麦・大麦・ライ麦などの穀物に含まれるタンパク質の一種で、パンやパスタ、うどん、ラーメン、菓子類など多くの食品に使われています。 パンや麺類のもちもちとした食感は、このグルテンによって生み出されており、近年このグルテンが健康に悪影響を及ぼすとして注目され、体質によっては深刻な炎症や不調を引き起こす原因となっているのです。 まず代表的なのが「セリアック病」、これは自己免疫疾患の一種で、グルテンを摂取すると小腸の粘膜が傷つき、栄養の吸収障害や慢性的な炎症を引き起こします。 欧米ではセリアック病の患者数が年々増加しており、今や100人に1人が該当するとも言われ、日本ではまだ一般的に知られていませんが、潜在的に症状を持つ人は少なくないと考えられています。 次に「グルテン不耐症」や「グルテン過敏症」、これらは明確な免疫異常は確認されないものの、グルテンを摂取することで体に不調が起こる状態を指し 症状としては、集中力の低下、頭がぼんやりする「ブレインフォグ」、腹痛、下痢や便秘、ガスがたまるなどの消化器症状が多く、日常生活に支障をきたすこともあります。 小麦による反応は「即時型」と「遅延型」の2種類が存在しています。 即時型は食後すぐに症状が出るため分かりやすいのですが、遅延型は食後数時間から数日後に症状が現れるため、原因が小麦であると気づきにくいのが特徴 そのため、グルテンを摂り続けているうちに、知らない間に腸に炎症が蓄積し、慢性疲労や肌荒れ、免疫力の低下につながってしまうこともあります。 グルテンが体に合わないまま摂取を続けると、腸の粘膜にダメージを与え、リーキーガット(腸漏れ)の原因にもつながってしまいます。 腸の炎症はやがて全身に波及し、脳にも悪影響を及ぼし、集中力が続かない、慢性的な不調が続く人は、グルテンを一時的に控える「グルテンフリーチャレンジ」を試してみるのもよいでしょう。 体調が大きく改善される場合は、グルテンの炎症作用に体が反応している可能性が高いといえるのです。 グルテンはすべての人に悪いわけではありませんが、体質によっては腸や脳に大きな負担となることがあるので注意が必要になります。乳製品が毒に変わる人も 牛乳は、カルシウムやタンパク質を豊富に含む優秀な食品として、現代でも多くの人に親しまれて飲まれています。 骨の健康を保つうえで重要な栄養素が多く含まれているため、骨粗鬆症の予防や成長期の子ども、高齢者の栄養補給としても広く推奨をされているのです。 しかし、すべての人にとって牛乳が「体に良い」とは限らず、一部の人にとっては、むしろ体調を崩す原因、すなわち“毒”のような存在になることもあり、その症状が「乳糖不耐症」になります。 乳糖不耐症とは、牛乳に含まれる「乳糖(ラクトース)」という糖質を分解する酵素(ラクターゼ)が不足しているため、乳糖をうまく消化できず、腹痛や下痢、ガス、膨満感などの症状を引き起こす状態を指しています。 実はこの乳糖不耐症は、日本人を含むアジア系の人々に非常に多く見られ、成人の半数以上が程度の差こそあれ該当するといわれているのです。 そのため、「牛乳を飲むとお腹がゴロゴロする」「体がだるくなる」と感じる人は、知らず知らずのうちに乳糖不耐症の影響を受けている可能性が高く また、牛乳には「カゼイン」と呼ばれるタンパク質が含まれており、このカゼインに対してアレルギー反応や過敏反応を示す人もいます。 アレルギーのように強い反応が出なくても、慢性的な炎症や不調の原因になることもあり、カゼインに対する抗体を持っている人は、牛乳を摂取するたびに体の免疫系が反応し、腸や脳に悪影響を及ぼす可能性があるのです。 こうした状態に気づかず、毎朝パンと牛乳をセットで食べていることで、腸内環境が悪化したり、慢性的な疲労感や肌荒れ、集中力の低下などの不調に悩まされるケースも少なくありません。 「牛乳=健康に良い」というイメージは強いものの、体質や遺伝的背景によっては、体に合わない場合もあり、体に不調がある場合は、牛乳を一定期間控えてみることで変化を観察してみましょう。 代わりに、豆乳、アーモンドミルク、オーツミルクなどの植物性ミルクを取り入れていき、これらは乳糖を含まず、カゼインも含まれていないため、牛乳に敏感な人でも安心して利用できる代替品です。 乳製品は体に良い場合もあれば、人によっては“毒”に変わるので、自分の体の反応にしっかり耳を傾け、無理に摂らず、合わないと感じたらやめる勇気も大切になっていきます。[送料無料] 野菜ジュース96本 伊藤園 [1日分の野菜 充実野菜 トマトジュース ビタミン 青汁 黒酢 乳酸菌 ネクター チチヤス 朝のYoo] 200ml・250ml紙パック×96本[24本×4ケース]【3〜4営業日以内に出荷】インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく18-2
2025.08.08
コメント(0)
-
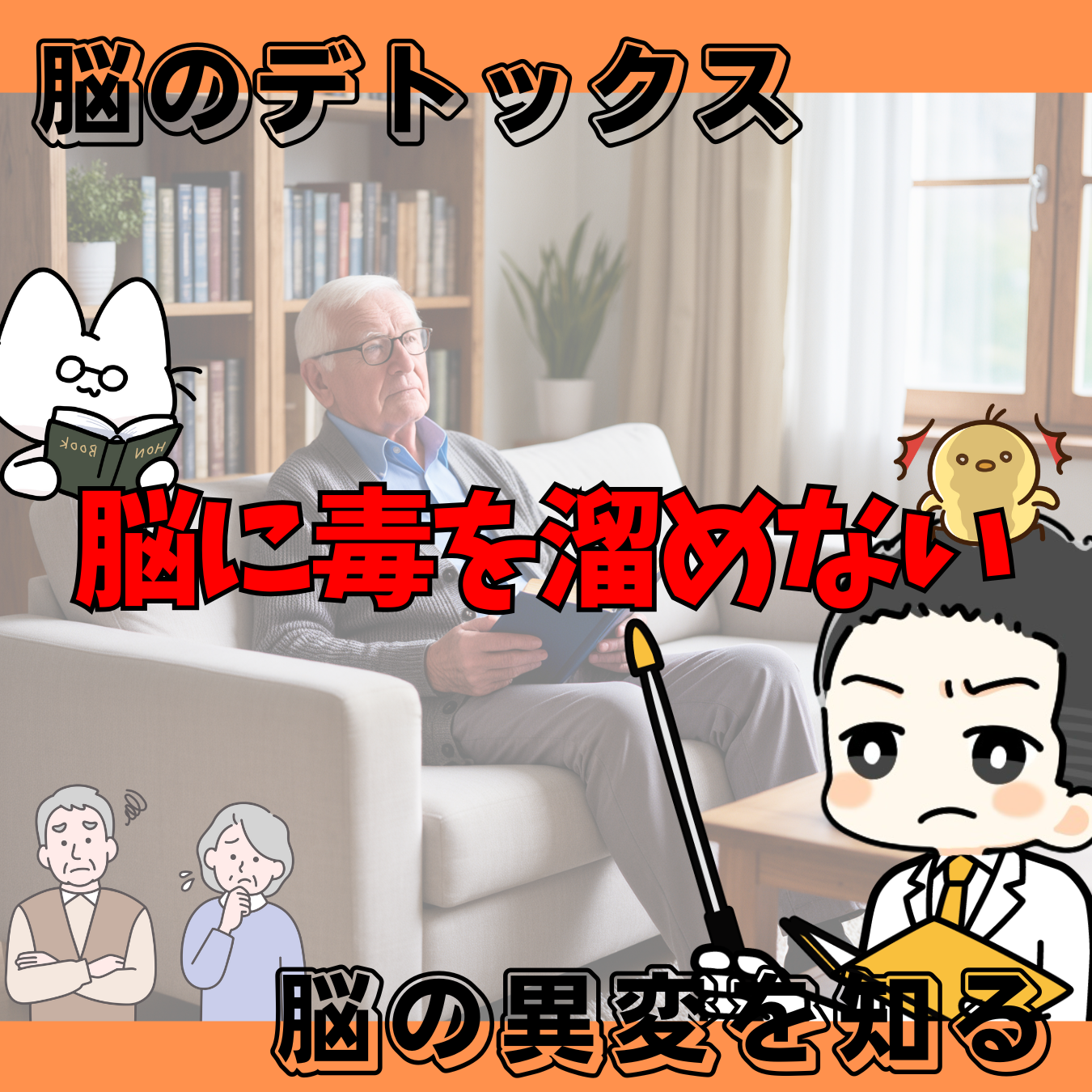
【脳のデトックス】脳に毒を溜めない 脳の異変を知る
脳の健康寿命を延ばしていく 脳も体も健康なままで歳を重ねていく、それこそが本当の意味での“健康長寿”になり、いくら長生きしても、脳が衰えてしまっては人生の質は大きく損なわれます。 実際、認知症のリスクは高齢者だけの問題ではなく、40〜50代からすでに静かに始まっていることもあるのです。 長寿と健康はセットで考えるべきであり、とくに脳の健康を守ることが、人生をいきいきと楽しむための最も重要なカギになるので、今からできる食事や生活習慣の工夫が、将来の脳の明暗を分けていきます。認知機能低下のサインは物忘れから 40代を過ぎたあたりから、「あれ?何をしようとしてたんだっけ?」「昨日の夕食、何食べたかな?」「あの人の名前、なんだったかな?」といった物忘れが増えてきたと感じる人は少なくありません。 こうした一見ささいな記憶の曖昧さは、加齢の自然な変化として捉えられがちですが、実は認知機能低下の初期サインであることもあるのです。 とくに、人の名前と顔を一致させることが難しくなったり、行き慣れた場所で迷うことが増えたりするのは、単なるうっかりミスとは違う可能性があり 若い頃と同じようなペースで脳が働いていれば、こうした物忘れは起こりにくいものです。 それにもかかわらず、「あれ」「それ」と言葉が出てこない場面が増えたり、探し物ばかりしているようになったら、それは脳からの小さな警告かもしれません。 しかし、認知症にも段階があり、いきなり進行するわけではなく、その前段階として「MCI(軽度認知障害)」と呼ばれる状態が存在します。 MCIはまだ認知症とは言えないものの健常な状態との中間にあり、記憶力や注意力に明らかな低下が見られる状態があるのです。 このMCIの段階であれば、生活習慣の改善や食事の見直し、適度な運動などで進行を食い止めることが可能で、生活に大きな支障をださずに済むのです。 つまり、「最近物忘れが増えたな」と感じたら、それは見過ごしてはいけないサイン、脳の健康寿命を延ばすための行動を今すぐ始めるチャンスでもあります。葉酸 鉄 カルシウム強化スピルリナ DHA&ビタミンC 1200粒 約40日分モノグルタミン酸型葉酸 ファスティング ダイエット タンパク質がたっぷり 健康食品 【税込3,000円以上送料無料】認知症を加速させる毒素達 認知症の発症に深く関わっているのが、脳に蓄積する「アミロイドβ」と呼ばれるタンパク質。 この物質が脳内に溜まり神経細胞の働きを妨げてしまい、やがて死滅させていくことで、記憶や判断力の低下を引き起こすのです。 残念ながら、現時点では認知症に対する特効薬は存在しておらず、進行を完全に止めることは難しいのが現実。 しかし、認知症を「加速」させてしまう原因には共通の要素があり、それが「炎症」「栄養不足」「毒素」の3つになります まず、慢性的な炎症は、アミロイドβの蓄積を助長し、脳内環境を悪化させ、次に、脳の働きを支えるビタミンやミネラル、オメガ3脂肪酸などの不足は、神経細胞の修復力を低下させ、認知機能を脆弱にします。 そして、最後に有害な毒素、たとえば食品添加物、重金属(鉛・水銀)、過剰な糖質が脳にストレスを与え、老化を早めていきます。 この3つの要因を脳から取り除くことが、認知症予防と進行抑制に重要になってくるのです。脳に毒が溜まってしまうのか 脳は、私たちの体全体に指令を送る司令塔のような存在となり、体温の調節、心臓の鼓動のリズム、内臓の動き、ホルモンバランスの維持など、あらゆる生理機能をコントロールしているのです。 私たちが意識しなくても生きていられるのは、すべてこの脳の働きによるもので、非常に重要な器官なため、脳は外部からの有害物質を防ぐ強力なバリアを備えており それが「血液脳関門(けつえきのうかんもん)」と呼ばれる仕組みになります。 血液脳関門は、脳の毛細血管に特殊なフィルターのような構造を作り、ウイルスや細菌、有害物質が脳に入らないように日々守っています。 基本的には、ブドウ糖やケトン体など、脳に必要な限られた物質だけを通し、それ以外のものは遮断していき、この構造のおかげで、私たちの脳は清潔で安定した環境を維持することができているのです。 しかし、現代の生活習慣には、この血液脳関門の防御力を徐々に弱めてしまう危険性が潜んでいます。 たとえば、過剰な糖分摂取や加工食品に含まれる添加物、慢性的な睡眠不足、ストレス、喫煙や過度な飲酒などが続くと、血液脳関門が炎症を起こし、働きが鈍感に その結果、通常なら脳に入らないはずの有害物質がすり抜けてしまい、脳に「毒」が溜まりやすくなってしまうのです。 このような毒素の侵入は神経細胞の働きを低下、認知機能の劣化を招いたりする原因になり、年齢を重ねるほど、脳の防御機能は衰えやすくなるため、生活習慣や食事内容がますます重要になってくるのです。◆エントリーで全品P7倍◆【ネコポス送料無料】小林製薬 イチョウ葉【90粒(30日分)】【信頼の製薬会社/機能性表示食品/記憶力/脳/思い出す/フラボノイド/認知機能の一部である記憶力を維持する】最大6個まで【smtb-TD】【RCP】 脳に毒が溜まると体にも異変が 脳に毒が溜まると、その影響は脳の中だけにとどまらず、全身にさまざまな異変をもたらします。 まず最初に現れるのは記憶力や思考力の低下、たとえば、すぐに物事が思い出せなくなり、説明された内容がうまく理解できないといった「認知の鈍さ」が目立ち始めます。 これは、神経細胞がスムーズに情報を伝え合えなくなっている証拠で、脳内に蓄積した毒素がその働きを妨げているのです。 また、脳は体内のホルモン分泌をコントロールしている司令塔的な存在 毒素によって視床下部や下垂体の機能が低下すると、インスリンや成長ホルモン、女性ホルモン(エストロゲン)、男性ホルモン(テストステロン)、さらには甲状腺ホルモンなどの分泌が乱れてしまいます。 これにより、代謝のバランスが崩れ、疲れやすさ、冷え、体重の増減、気分の浮き沈みなどが起こりやすくなります。 さらに、こうしたホルモンバランスの乱れや脳の指令系統の障害は、高血圧や高脂血症、糖尿病などの生活習慣病とも深く関係し、脳が内臓や血管に正確な指令を出せなくなることで、血圧の調節がうまくいかず、脂質の代謝も滞りやすくなってしまうのです。歯周病菌も影響してくる 口の中は、体の中でも特に多くの細菌が生息している場所で、その中でもとくに問題になるのが「歯周病菌」です。 歯周病は、歯ぐきに炎症が起き、進行すると歯を支える骨まで破壊してしまう病気ですが、その影響は口内にとどまらず、全身の健康にも深く関わっています。 実際に、歯周病は心臓病、脳卒中、糖尿病、さらには認知症などのリスクを高めることがわかってきています。 歯周病が怖いのは、炎症によって歯ぐきの粘膜が傷つくことで、細菌が血管内に侵入でき、侵入した細菌は血流に乗って全身を巡り、さまざまな臓器にダメージを与えます。 中でも注目すべきは、歯周病菌のひとつ「ジンジバリス菌」の存在、この菌は非常に厄介で、血液脳関門(血液から脳を守るフィルター)をすり抜ける力を持っています。 つまり、通常であれば脳に到達しないはずの細菌が、このジンジバリス菌を通じて脳内に入り込んでしまう可能性があるのです。 このようにして侵入した細菌が脳内で炎症を引き起こすと、認知機能の低下やアルツハイマー型認知症のリスクを高める原因になると考えられ 口の中の炎症が、血管を通じて脳に影響を与えるというのは、一見するとつながりがなさそうですが、実は非常に密接な関係にあるのです。 だからこそ、歯周病の予防は「口の中だけの問題」ではなく、「全身と脳の健康を守る第一歩」とも言えるのです。 毎日の歯磨きやデンタルフロスの使用はもちろんのこと、歯科医院での定期的な検診を受けることが非常に重要で、早期発見・早期治療が歯周病の進行を防ぎ、結果として体と脳を守ることにつながります。【最大P48倍要エントリー★11日1:59迄】【最短即日出荷】【メール便送料無料】コンクールF 100ml 1個深刻な腸漏れも注意が必要に 最近注目されている「リーキーガット症候群(腸漏れ)」は、腸内環境の悪化によって腸の壁に小さな隙間ができ、そこから本来体内に入るべきでない物質が漏れ出す状態を指します。 普段の食生活で摂る食品添加物や高脂肪食、ストレス、アレルギー反応、さらには抗生物質の多用などが原因となり、腸壁のバリア機能が低下してしまいます。 すると、未消化の食べ物のカスや細菌、ウイルス、有害物質などが血管内に入り込み、全身を巡ります。 とくに問題なのは、それらが脳にまで到達し、炎症や認知機能の低下を引き起こす可能性があることです。 腸は“第二の脳”とも呼ばれるほど重要な器官であり、腸の健康を守ることが脳と体全体の健康を守ることにつながるのです。腎臓と肝臓の働きにも影響 脳の健康を守るには、脳だけに注目するのではなく、体全体、とくに「解毒」に関わる臓器のケアが欠かせず、その代表が「腎臓」と「肝臓」、どちらも、体内に溜まった毒素を排出するための重要な働きを担っています。 まず腎臓は、体中の血液から水分を集めて濾過(ろか)し、不要な老廃物や余分な塩分などを「尿」として排出をします。 濾過された血液は、きれいな状態で再び全身を巡るため、腎臓が正常に働いていれば、体内に毒素が溜まることはありません。 また、必要な成分はしっかり体内にとどめるなど、絶妙なバランスで体の浄化を行ってくれているのです。 そして、肝臓は「解毒」と「代謝」の司令塔のような役割を持っており、肝臓はアルコールの分解はもちろん、薬、食品添加物、化学物質、さらには体内で発生した細菌や毒素など、あらゆる有害物質を処理をしています。 また、脂肪や糖の代謝、たんぱく質の合成、そして消化に必要な胆汁の生成など、多くの生命活動を支えているのです。 この腎臓と肝臓が健康であれば、体内の毒素はしっかり処理され、血液はきれいなまま保たれます。 つまり、血液を通じて栄養や酸素が脳に届くとき、同時に有害な毒素が運ばれてしまうリスクを最小限に抑えることができるのです。 反対に、腎臓や肝臓が疲れていたり、機能が低下していると、毒素が血液中に残ったまま脳に届いてしまい、脳に負担がかかりやすくなってしまいます。 脳の毒をためないためには、まずこの2つの臓器をしっかり労わることが大前提になり バランスの良い食事、水分の十分な摂取、過度なアルコールや薬の摂取を避ける、ストレスを溜めないといった基本的な習慣が、腎臓と肝臓の負担を軽減し、結果として脳を守ることにつながるのです。無添加しじみスープ13g×12★国内産しじみ使用★肝臓ケアにインスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく18-1
2025.08.07
コメント(0)
-

【美便習慣を】朝の行動から変える 便秘改善習慣
今日から始める美便習慣を 美便生活は特別なことをしなくても、日々のちょっとした習慣を整えるだけで、諦めることなく誰でも始められます。 この章では、すっきり出て、見た目も心も若々しく保つ“美便”を手に入れるための生活術を具体的に紹介していきます。 朝の過ごし方、水分の摂り方、食べる順番、運動や睡眠まで、腸が喜ぶコツは日常にたくさんあるので、今日からできることを、ひとつずつ始めていきましょう。美便を出すために意識すること 美便を出すには、単に便秘を解消するだけでなく、毎日の生活の中で「美便生活」を意識することが大切で、腸が本来の働きを発揮できる環境を整えてあげることがポイントです。 まず基本となるのは規則正しい生活、朝起きて、決まった時間に食事をとり、適度な運動や睡眠を確保することで、自律神経のバランスが整い、腸のぜん動運動がスムーズに働くようになります。 腸はストレスにとても敏感な臓器なので、生活リズムを整えることは、腸にとっての安心材料になるのです。 また、食事面では食物繊維をしっかりと摂ることも重要で、野菜、海藻、きのこ、豆類などに含まれる不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸を刺激して排便を促します。 さらに、発酵食品やオリゴ糖を取り入れることで腸内の善玉菌が活性化し、腸内環境が整いやすくなります。 そして、ウォーキングやストレッチなどで腸の動きを促進していき、ストレス解消も同時に行なっていき、美便を作っていきましょう。朝の行動が美便を生成する 美便生活の第一歩は「朝活」、朝起きてカーテンを開け、朝日をしっかり浴びることで、体内時計がリセットされ、自律神経のバランスも自然と整っていきます。 朝の時間帯は、副交感神経から交感神経への切り替わりが起こるタイミング、ここでしっかり目覚めることで、腸のぜん動運動もスムーズに働きやすくなります。 また、早起きしてゆとりを持って朝食をとることで、胃結腸反射が働き、自然とトイレタイムへとつながります。 無理に出すのではなく、自然な便意を感じやすくなるのが朝活のメリットとなり、誰にも邪魔されない静かな朝の時間は、ストレス緩和にも効果的になるのです。朝起きての胃腸を刺激 朝起きたら、まずは空っぽの胃腸に常温の水を一杯飲んで、寝ている間に失われた水分を補いながら、内臓をやさしく目覚めさせることができます。 水分が胃に届くことで大腸が刺激され、蠕動運動が活発になり、便を排出する準備が整い、これが自然な便意を呼び起こす大切な“腸のスイッチ”です。 続いて、朝食も欠かさずに食べていき、卵や納豆、ヨーグルトなどのタンパク質を意識してとることで、腸の筋肉や全身の代謝を支える基盤が整います。 タンパク質は腸のぜん動を助ける筋肉を維持する栄養源でもあり、美便をつくる体づくりにも繋がっていくのです。便秘対策に寒天習慣を 便秘対策におすすめなのが「寒天」、寒天は天草などの海藻を煮て作られる、天然の食物繊維食品 特に水に溶ける「水溶性食物繊維」が豊富に含まれており、腸内でゲル状になって便をやわらかくし、スムーズな排便をサポートしてくれます。 寒天は無味無臭なので、果汁やフルーツを加えればデザートにもなり、甘さ控えめのジュレやゼリーとして楽しむことで、間食しながら自然に食物繊維がとれるのが魅力です。 おやつの代わりに、寒天を取り入れて、簡単で美味しく、続けやすい寒天習慣で美便生活を行なっていきましょう。国内製造 粉末 寒天 120g(粉寒天 寒天粉) 長野県製造 国産 送料無料ヨーグルトを毎日200g 腸内環境を整えるために欠かせないのが、善玉菌であるビフィズス菌や乳酸菌 その代表的な食品がヨーグルトになり、乳酸菌が豊富に含まれ、腸内で善玉菌を増やし、腸の働きを活発にしてくれます。 毎日200gのヨーグルトを目安に取り入れることで、腸内の菌バランスが整いやすくなり、美便の習慣が根づきやすくなるのです。 ヨーグルトが苦手な方は、きなこやココアパウダーを加えると風味がやわらぎ、食べやすく、また、牛乳が合わない方は、豆乳ヨーグルトを選ぶのもひとつの方法です。【楽天1位】 【専用容器付き】 ヨーグルトメーカー 【楽天ランキング1位】 甘酒 R-1 塩麹 甘酒メーカー ヨーグルト 発酵フードメーカー 牛乳パック 風邪対策 発酵食品 カスピ海ヨーグルト 発酵メーカー 冷やし甘酒 ※麹の甘酒 ギフト 豆乳ヨーグルト ★少しずつ運動不足を解消 便秘解消のためには、食事や生活習慣に加えて、運動不足の解消も欠かせません。 特に腹筋力が低下すると、排便時のいきみが弱まり、自然なお通じが難しくなるので、ウォーキングや軽いエクササイズを毎日取り入れることが大切です。 しかし、忙しい日々の中で時間を確保するのは簡単ではないので、そんな時は、エレベーターを使わず階段を利用したり、家事の合間にスクワットを取り入れたりと、ちょっとした工夫で体を動かす時間を作ることができます。 無理なく、続けやすい形で運動を日常に取り入れていくことで、腸の働きも活発になり、美便習慣に重要になっていくのです。お腹が空いて食べよく噛む 便秘を防ぐためには、何を食べるかだけでなく「どう食べるか」もとても大切になります。 まず意識したいのは、「お腹が空いてから食べる」ことを意識し、空腹を感じてから食べると、空っぽの胃に食べ物が入ることで“胃結腸反射”が起こり、腸が動きやすく、自然なお通じを促す仕組みになります。 さらに「よく噛んで食べる」ことも重要になり、噛む回数が多いほど唾液が分泌され、消化がスムーズになり、胃腸の負担も軽減されていき、噛むことで腸が刺激され、ぜん動運動も活発になります。入浴も美便習慣に欠かせない 美便生活には、毎日の入浴も大切な習慣のひとつで、お風呂の湯温は38〜40度程度のぬるめが理想になります。 この温度帯は副交感神経が高まり、心身ともにリラックスしやすくなり、腸も落ち着き、ぜん動運動が促されるため、排便の準備が整いやすくなるのです。 さらに、湯船につかることで筋肉もほぐれ、体が軽く感じられるようになります。 入浴中に軽くストレッチを行えば、疲労回復にもつながり、ハーブや入浴剤を加えると香りのリラックス効果も高まり、腸にもやさしい時間となります。 やさしくマッサージすることで、腸への刺激が加わり、より自然な便意を引き出すことが可能になるのです。朝のトイレタイムを楽しんでいく 朝のトイレタイムは、美便習慣と切っても切れない関係ですが、焦ったり、落ち着かない気持ちになると、それがストレスになってしまいます。 せっかく便意がきても、緊張で交感神経が優位になってしまうと、腸のぜん動運動が抑えられてしまい、ますます出にくくなるのです。 だからこそ、朝のトイレタイムは“リラックスの時間”と考えていき、好きな香りの芳香剤を置いたり、やわらかい光の照明にしたり、居心地のよい空間にすることで、緊張をやわらげて腸も落ち着いた排便を行えます。 毎朝のトイレ時間を快適に、そして前向きに楽しむことで、美便習慣はもっと自然に身につけていきましょう。食べ物で美便を作る 美便生活のカギは、なんといっても毎日の食事にあり、どんな食べ物を選び、どう食べるかで腸内環境は大きく変わります。 腸がよろこぶ栄養をとり入れることで、自然とスムーズなお通じが生まれるので、この章では、便秘解消に効果的な食材や食べ方のコツを、わかりやすく紹介していきます。2種類の食物繊維を毎日摂る 美便を目指すうえで欠かせない栄養素のひとつが「食物繊維」、食物繊維は人の消化酵素では分解されない成分で、野菜、果物、豆類、穀類、海藻などの植物性食品に多く含まれています。 胃や小腸では消化されることなく、大腸まで届き、腸内でさまざまな働きをしてくれます。 注目したいのは、大腸の粘膜を刺激してぜん動運動を促進し、便通をサポートしてくれ、食物繊維をしっかり摂ることで、便がスムーズに排出されやすくなり、便秘の解消に大きく役立ちます。 食物繊維には「不溶性」と「水溶性」の2種類があり、それぞれ異なる役割があり、「不溶性食物繊維」は、水に溶けにくい性質を持ち、腸内で水分を吸収して膨らみます。 これにより便のかさが増え、大腸の壁を刺激してぜん動運動が活発化、不溶性食物繊維は、ゴボウ、キャベツ、かぼちゃ、豆類、穀物のふすまなどに多く含まれています。 便の量が少ない、便が細い、排便回数が少ないといったタイプの便秘には、特に効果的です。 一方、「水溶性食物繊維」は水に溶ける性質を持ち、腸内でゲル状になって便をやわらかく保ち、腸内の善玉菌のエサとなり、腸内環境の改善にもつながります。 海藻類、オクラ、山芋、なめこ、大麦、果物などに多く含まれ、便が硬くて出にくいタイプや、腸内のバランスを整えたい方に必須になっていきます。 美便を目指すためには、この2種類の食物繊維をバランスよく摂っていき、不溶性だけ、水溶性だけでは効果が十分に得られないこともあるため、さまざまな食品を組み合わせて、毎日の食事にうまく取り入れていきましょう。イヌリン 機能性表示食品 500g 【食後の 血糖値 や 便秘 が気になる方に】 サプリメント サプリ 菊芋 食物繊維 天然 チコリ由来 ダイエット オランダ産 水溶性食物繊維 パウダー 粉末 イヌリア顆粒 ロハスタイル LOHAStyle美便を作るために4つの食品を 美便を作るうえで欠かせないのは食物繊維ですが、それだけでは十分とは言えず、腸の健康をさらに高めるために、次の4つの食品を意識的に取り入れていきましょう。 まず1つ目は「オリゴ糖」、オリゴ糖は腸内の善玉菌、ビフィズス菌や乳酸菌の大好物であり、彼らのエサになることで善玉菌を活性化 腸内環境を整える助けになり、玉ねぎやバナナ、ごぼうなどに含まれており、手軽に摂取できます。 2つ目は「発酵食品」、味噌や納豆、ヨーグルト、ぬか漬けなどには乳酸菌が豊富に含まれており、腸内の善玉菌の数を増加し、毎日の食事に発酵食品を1品加えるだけでも、腸の調子が大きく変わってくるでしょう。 3つ目は「オレイン酸」、オリーブオイルに多く含まれるこの成分は、小腸で吸収されにくいため、大腸まで届いて便をやわらかくし排便がスムーズに、毎日の調理油に取り入れていきます。 そして4つ目は「ビタミンE」、ビタミンEには血行をよくする働きがあり、腸の動きを高めるとともに、自律神経のバランスも整うので、アーモンドやかぼちゃ、アボカドなど積極的に食卓に これら4つの食品を意識して毎日の食事に取り入れることで、腸が元気に動き、美便生活がより確かなものになります。CARMプレミアム エキストラバージン オリーブオイル 500ml / 賞味期限2026年5月 / コールドプレス 酸度0.1-0.2% ポルトガル産 原産地呼称 DOPトラズ・オス・モンテスマグネシウム食品をプラス一品 美便生活に欠かせないミネラルのひとつが「マグネシウム」、マグネシウムは、腸内で水分を引き寄せて便をやわらかくし、自然なお通じをサポートしてくれます。 しかし、現代では、精製された食品が多くなったことで、マグネシウム不足が深刻化しています。 毎日の食事に「マグネシウム食品をもう一品」加える意識が大切です。 おすすめは、和食の基本「まごわやさしい」の頭文字をヒントに、豆類(まめ)、ごま、わかめ、野菜、魚、しいたけ、いも類などをバランスよく取り入れること。 これらの食品にはマグネシウムをはじめ、腸にうれしい栄養がたっぷり含まれています。【微粒子】 塩化マグネシウム(国内製造) 1kg 【送料無料】【メール便で郵便ポストにお届け】【代引不可】【時間指定不可】 究極の微粒子 天然海水にがり 食品添加物 [01] NICHIGA(ニチガ)まとめ:今日から始める美便習慣を 美便生活は、毎日のちょっとした意識と習慣の積み重ねになり、身体の声に耳を傾け無理せず、自分のペースで続けていきましょう。 腸内環境が整うと、肌の調子がよくなり、気持ちも前向きになり、健康全体に良い影響が現れ、美便習慣をはじめ、老化知らずの健やかな日々を手に入れてください。【楽天1位 7冠達成/5兆個の乳酸菌】 LACT 乳酸菌 サプリ 善玉 菌 ビフィズス菌 4種類の乳酸菌 ラクトフェリン イヌリン ガゼリ菌 ラブレ菌 食物繊維 タブレット 腸活 スッキリ サプリメント 30日分 菌活 乳酸菌サプリ 腸内環境 デリケートゾーンインスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく17-終
2025.08.06
コメント(0)
-

【美便で健康】今日から快便美便生活を 便秘対策改善
美便が毎日の健康のメーターに 毎日の便の状態は、腸内環境や生活の乱れを映し出す“健康のメーター”です。 まずは、腸がどう動いて排便に至るのか、基本のメカニズムを知ることから始めていき、腸の働きを理解することで、自分の便のサインに気づきやすくなり、体調管理にもつながります。若い人は綺麗な便を出している 「最近、トイレの時間が長くなった」「いきまないと出ない」「出た後もすっきりしない」そんな便通の悩みは、年齢とともに増加してきます。 一方で、若い人の多くは、あまりいきまず、自然にするんと出る“美便”を日常的に経験しています。 美便とは、少しいきむだけでスムーズに出て、排便後もすっきりとした気持ちになれる理想的な便のことです。 形はバナナ状で、ほどよい硬さと水分を保ち、においもきつくない、こうした便は、良好な腸内環境から生まれます。 腸内の善玉菌が元気に働き、食物繊維や水分、適度な運動が習慣になっていると、美便は自然と作られるのです。 若々しく見える人、気持ちが明るい人は、内側の健康も整っており、腸内環境が整っている人は、代謝が良く肌もきれいで、免疫力も高い傾向に つまり、美便は「若さの証」、年齢に関係なく、腸内環境を整えることで、誰でも美便習慣を手に入れることができます。デトックスで腸内がピカピカ シニア世代にとって、便秘や下痢は実に身近な悩みのひとつ、とくに便秘は女性に多い印象がありますが、実は年齢とともに男性にも増えていきます。 「もう何日もお通じがない」「やっと出たけど、コロコロと硬くて残便感がある」といった声も少なくありません。 これは、腸のぜん動運動が衰えたり、水分摂取が不足したり、腸内環境が乱れたりすることが原因になります。 腸は体内で食べ物を消化・吸収し、不要なものを排泄する重要な役割を担っているのですが、便秘が続くと食べたものの「かす」がいつまでも腸内にとどまり、発酵してガスを発生させたり、有害物質を再吸収させたりすることがあります。 これは体にとって非常に負担で、肌荒れ、口臭、疲れやすさ、免疫力の低下など、さまざまな不調を引き起こす要因となります。 こうした状態を改善するには、腸内に溜まった老廃物をきちんと排泄することが大切になり、これが「デトックス」です。 デトックスというと特別なことのように感じられるかもしれませんが、腸の中をきれいに掃除する=スムーズに便を出すというのは、毎日できる最も身近なデトックス方法なのです。 腸のデトックスがうまくいくと、腸内はまるでピカピカに磨きあげたようにすっきりし、腸内環境が整えば、善玉菌が増え、悪玉菌が減少し、便のにおいや形もよくなります。 腸が綺麗になると肌の調子が自然と整い、体のだるさも軽くなり、気分も明るくなっていきます。イヌリン 機能性表示食品 500g 【食後の 血糖値 や 便秘 が気になる方に】 サプリメント サプリ 菊芋 食物繊維 天然 チコリ由来 ダイエット オランダ産 水溶性食物繊維 パウダー 粉末 イヌリア顆粒 ロハスタイル LOHAStyle便の成分の3分の1は腸内細菌 「便は食べたもののカス」そう思っている人も多いかもしれませんが、実はそれだけではありません。 便の約80%は水分でできており、残りの20%が固形成分、この固形部分の内訳を見ると、3分の1は食べ物のカス、3分の1は腸の粘膜が剥がれ落ちたもの、そして残りの3分の1は腸内細菌で構成されています。 そう、便の大事な成分のひとつが「腸内細菌」、私たちの腸内には、約100兆個もの細菌がすみついており、その総重量はなんと約1kgにもなります。 この腸内細菌たちは、善玉菌・悪玉菌・日和見菌に分かれ、食べ物を分解したり、ビタミンの合成、免疫を整えたりと、さまざまな役割を担っています。 そして、腸内細菌の死骸や老廃物が、便の中に混ざって排出されているのです。便秘は悪玉菌が増加する 便秘が続くと、お腹が張って苦しいだけでなく、腸内環境に深刻な悪影響を及ぼし、問題となるのが悪玉菌の増加になります。 大腸内に便が長くとどまると、腸内の温かさと湿気によって、便の中の成分が腐敗し始め、悪玉菌が活発に働き、食べ物のカスを分解してアンモニアやインドール、スカトールといった悪臭のもととなる有害物質を発生させます。 善玉菌もまた、食べ物のカスを分解しますが、乳酸、酢酸、酪酸といった体に有益な短鎖脂肪酸をつくり出し、腸内を酸性に保って悪玉菌の増殖を抑えたり、腸のぜん動運動を促進したりする働きをもっています。 つまり、同じ「分解」でも善玉菌と悪玉菌ではその結果がまったく異なるのです。 善玉菌が好むのは、食物繊維やオリゴ糖などの植物性の栄養素ですが、悪玉菌は動物性たんぱく質や脂質、特に高脂肪・高タンパクな食事を好みます。 便秘が続くと、腸内に未消化の脂質やたんぱく質が長く残るため、悪玉菌の活動がますます活発になり、腸内のバランスが崩れていくのです。 さらに、腸内に存在する「日和見菌」は、善玉菌と悪玉菌のうち、優勢な方の味方をする性質を持っているため、悪玉菌が優勢になると、日和見菌も悪玉菌側に傾き、腸内は一気に悪玉菌優勢の状態に変わります これが続くと、腸の粘膜が炎症を起こしやすくなり、肌荒れ、免疫低下、疲労感など、全身の不調につながっていくのです。【総合女性1位★16年の実績】 ダイエット茶 ダイエットティー 朝スッキリ どっさり 解消 キャンドルブッシュ 茶 ダイエット 茶 お茶 ランキング お試し 送料無料 初回限定 スッキリ茶 ゴールデンキャンドル メール便秘密配送対応可 デルバラスリムビューティ(5g×10包)腸年齢が若い人は見た目と比例 私たちの体には「実年齢」とは別に、「腸年齢」というものが存在します。 これは腸内環境の状態を年齢に換算したもので、腸内細菌のバランスや腸の働きが良いほど若く、乱れていると高齢化しているとされます。 二十代、三十代の若いうちは、腸内細菌のバランスが自然に保たれており、善玉菌、とくにビフィズス菌が優位な状態にあります。 しかし、50代を超えるころから、このビフィズス菌が減少し始め、代わって悪玉菌が増えていき、加齢により腸の動きが鈍くなり、便秘になりやすくなることも腸内環境の悪化に拍車をかけてしまいます。 便秘が慢性化すると、腸年齢は実年齢よりもどんどん高くなっていく一方で、毎日スムーズに“美便”が出ている人は、腸内環境が整っており、腸年齢が若い傾向にあるのです。 腸が若ければ、便はにおいも少なく、形も良く、排便後のすっきり感もあり、腸年齢が若い人は見た目も若くなることがわかっています。 腸内環境が整うと、肌の調子が良くなり、吹き出物やくすみも減少し、脳にも好影響があり、ストレスに強く、前向きな気持ちを保ちやすいのです。便秘のこと知っていこう 便秘とひとことで言っても、その原因やタイプ、体への影響はさまざまです。 「何日出なければ便秘?」「出ているのにスッキリしないのは?」など、意外と知られていないことも多いのです。 まずは、便秘の正体をしっかり理解することから始めていき、正しく知ることで、自分に合った対策が見えてきます。排便は毎日にこだわらないように 「毎日出ないと便秘」と思い込んでいる方は多いかもしれませんが、実は排便の回数だけで便秘かどうかを判断することはできません。 たしかに、排便は毎日あるのが理想的ではありますが、だからといって、二日に1回、あるいは三日に1回の排便でも、すぐに「便秘」と決めつける必要はありません。 たとえば、二日に1回でも、決まった時間にスムーズに排便があり、便の形やにおいも良好、出した後に腸がすっきりする感覚があるのであれば、それは「健康的な排便」と言えます。 つまり、排便が「定期的」で「質がよい」ことが大切であり、「毎日かどうか」にばかりとらわれる必要はないのです。 反対に、毎日排便がある人でも、便が硬くて出にくい、いきまないと出ない、排便後に残便感がある、という場合は、それはれっきとした便秘のサイン。 また、無理に下剤などで排便を誘導している場合も「排便の自然なリズム」が損なわれており、腸の働きが不安定になっている可能性があります。 便秘とは、「便が十分量かつ快適に排泄できない状態」を指し、単純に回数だけでなく、「腸がすっきりしているかどうか」「排便後に心地よさがあるかどうか」がとても重要な指標なのです。 つまり、便秘の判断基準は「出ているか」ではなく、「どう出ているか」にあります。 毎日の排便にこだわるあまり、必要以上にプレッシャーを感じてしまったり、無理な排便習慣をつくってしまうことのほうが、かえって腸内環境を悪化させる原因になってしまいます。便意のタイミングも関係? 便秘対策として「朝の排便」がよく勧められ、これは、朝起きて体が動き始めることで腸のぜん動運動が活発になり、排便しやすい状態になるからです。 とくに朝食をとることで“胃結腸反射”と呼ばれる反応が起こり、自然と便意が促される仕組みがあるため、朝は排便の理想的なタイミングとされています。 しかし、朝以外の時間に便意を感じることもあり、たとえば、昼食後や夕食後など、食後のタイミングで腸が動き出すこともよくあるため、そのときに自然に便意を感じるのであれば、決して問題ではありません。 大切なのは「時間帯」ではなく、「毎日ほぼ同じ時間帯に便意が起こる」という“排便のリズム”が保たれているかどうかです。 また、毎日決まった時間に便意があるけれど、それが朝でない場合でも、無理に朝にこだわる必要はありません。 排便後にスッキリ感があり、不快感がなければ、それはその人にとって理想的なリズムといえるでしょう。 むしろ、朝に出さなきゃと無理にトイレにこもることのほうが、ストレスや習慣の乱れにつながることもあるのです。 「私の排便リズムはこれでいいんだ」と自分自身のリズムを理解し、便意のタイミングを見逃さず、自然な流れで排便できる体づくりを目指していきましょう。【お買い物マラソン 5のつく日 クーポン】 ダイエット お茶 ダイエット茶 健康茶 ブレンド茶 ティーバッグ ティーパック 二十二減肥茶 お試し 6包 ノンカフェイン 無添加 バナバ ギムネマ 食べ過ぎ 運動不足 どっさり 簡便秘密 ギフト美便には水分量が重要に 美便を目指すうえで、忘れてはならないのが「水分量」ですが、便秘になると腸内に便が長くとどまり、その間に腸が水分をどんどん吸収してしまい、どんどん硬くなり、出すのが大変な状態に。 便が硬くなりすぎると、まるで石のような塊になり、排便時に強く、いきんでもなかなか出てこなくなることもあるのです。 無理に出そうとすると、肛門周辺が切れてしまい、出血や痛みを伴ってしまい、排便そのものが苦痛に変わり、便秘を悪化させるという悪循環に陥ってしまいます。 また、硬くてコロコロした便、いわゆる「ウサギのような便」は、大腸が強く収縮してしまっている証拠になり こうした便は、ストレスや緊張が原因で腸の動きが不規則になっているときにもよく見られ、見た目が小さくても出にくく、スッキリ感がないのが特徴になります。 これを防ぐには、毎日しっかりと水分をとることを習慣化していき、朝起きた直後のコップ1杯の水は、腸を刺激して自然な便意を促してくれるのです。 また、日中もこまめに水やお茶を飲むことで、腸内の便の水分バランスが保たれ、出やすくなります。 美便を作るには、まず体の内側に十分な水分を満たしていき対策を、水分は“腸のお掃除役”に変わっていくのです。【ラベルレス限定10%OFFセール!~8/11 9:59まで】BIYOUDO シリカ水 500ml×42本 ナチュラルミネラルウォーター ラベルレス 軟水 美容ミネラル シリカ含有 天然水 シリカウォーター 保存料なし 500ミリリットル 保存水 防災 備蓄 国産 日本製 美陽堂便の色にも重要な意味がある 便の状態をチェックするとき、形やにおいだけに注目しがちですが、実は「色」も非常に大切な健康のバロメーターになります。 健康的な便は、黄褐色や茶褐色をしており、これは腸内で分泌される胆汁酸が食べ物と混ざって消化・吸収される過程で自然に色づいたものです。 しかし、この色がいつもと違う場合、体の中で何らかの異常が起きているサイン、たとえば、脂肪をとりすぎると便の色が黒っぽく濃くなり、ベタついたような便になってしまいます。 食物繊維が不足すると便が腸内に長くとどまり、こげ茶色に近い色になり、これは腸内環境の乱れを示しています。 さらに注意が必要なのが「白っぽい便」と「赤い便」、白っぽい便は、胆汁がうまく分泌されていない可能性があり、肝臓や胆のう、膵臓に異常があるケースも考えられます。 また、赤い便は大腸からの出血の可能性があり、痔のこともありますが、場合によっては大腸ポリープやがんなどの病気が隠れていることもあるため、すぐに医療機関を受診しましょう。トイレで5分以上いきまない 理想的な排便は、トイレに座って30秒もかからず、力まずにスルッと出るのが特徴になり、自然な便意に従ってトイレに入って、短時間でスッキリ排便できる状態になります。 ところが、便秘の方は、便が硬かったり量が少なかったりするため、排便に時間がかかってしまうことが珍しくありません。 トイレで10分以上、時には20分以上も頑張っているという声も聞かれます。しかし、排便にかける時間は「5分以内」がひとつの目安 それ以上かかる場合は、体にとってタイムオーバーで、無理に出そうとするのは避けた方が賢明になります。 長時間トイレに座っていると、肛門周辺の血流が悪くなり「うっ血」、これが続くと、痔の原因となり、排便のたびに痛みや出血を伴うようになってしまうのです。 また、強くいきむことは一時的に血圧を急上昇させ、心臓や脳への負担に変わり、高齢者にとっては、排便中の血圧上昇が命に関わるリスクとなることも少なくありません 便が出ないからといって、長時間トイレに座り続けるのではなく、5分以上出る気配がないときは、いったん席を立ち、水分をとったり、腹部を軽くマッサージしたりして、自然な便意が訪れるのを待つことが大切です。 お腹が張る原因やゴロゴロと鳴る 「お腹がパンパンに張って苦しい」など、お腹が張る主な原因は、腸内にガスがたまってしまう事が考えられます。 ガスがたまるのは、飲食中や会話中に無意識のうちに空気を飲み込んでしまっている場合や、炭酸飲料などによるもの、さらには腸内細菌の働きが関係していることもあります。 さらに便秘が続くと、腸内に便が長くとどまり、悪玉菌がその便を腐敗させてしまうこともあるので改善が必要になるのです。 その過程でアンモニアや硫化水素などの悪臭のあるガスが発生し、お腹が張る原因になり、これは単なる不快感にとどまらず、腸内環境の乱れのサインともいえます。 また、お腹の「ゴロゴロ」や「ギュルギュル」といった音は、腸が過剰に動いているときに起こり、これは下痢の前触れであることが多く、ストレスや緊張によって腸が敏感になっている場合にもよく見られます。 一方、便秘の場合でも、張りや不快感だけでなく、「鳴るけれど出ない」という現象が起きることもあります。 このようなお腹の不調を感じたら、まずは腸をやさしくケアしてあげることが大切になります。 湯たんぽや腹巻きなどでお腹を温めたり、ゆっくり深呼吸をして自律神経を整えたりすると、腸の緊張がやわらぎ、ガスの排出がスムーズになることがあります。\マラソンP10倍/【公式】 ベジパワープラス(30包入) | ベジパワー 青汁 乳酸菌 酵素 腸活 国産 野菜不足 ホールフード 食物繊維 美容 粉末 大麦若葉 パウダー 飲みやすい おいしい スピルリナ 妊婦 健康食品 グルテンフリー ダイエット クロロフィル 送料無料弛緩性便秘を知り対策を ひとくちに便秘といっても、原因や対策も異なり、まず代表的なタイプが「弛緩性(しかんせい)便秘」です。 これは、腸管の緊張がゆるみ、腸のぜん動運動(内容物を押し出す動き)が弱くなっている状態で、便がスムーズに運ばれず、大腸の中で長くとどまりがちになるのが特徴になります。 高齢者に多く見られるタイプで、その背景には運動不足や腹筋の弱さ、加齢による筋力の低下があり、腸も筋肉でできているため、体全体の筋力が落ちると腸の動きも鈍くなってしまい、便秘が慢性化しやすい傾向に このタイプの便秘を改善するには、大腸の動きを活発にしてあげることがポイントです。 まず意識したいのが「食物繊維の摂取」、特に不溶性食物繊維は便のかさを増やし、腸の壁を刺激してぜん動運動を促進するため、野菜、きのこ、豆類、穀物などを積極的に取り入れましょう。 加えて軽い運動も有効、ウォーキングやラジオ体操、腹式呼吸などを日常に取り入れることで、腸への血流が良くなり、腸の働きが高まります。 また、腹筋を鍛えると排便力そのものが上がり、排便時のいきみも少なくて済むようになるのです。便意が喪失してしまう直腸性便秘 便秘の中には、大腸のぜん動運動や水分量に問題がないにもかかわらず、排便そのものに支障が出るタイプがあり、それが「直腸性便秘」 この便秘の特徴は、便意そのものが弱くなったり、完全に消失してしまい、通常は便が直腸に到達すると、その刺激が脳に伝わり、排便したいという感覚=「便意」が生まれます。 しかし、直腸性便秘ではその信号がうまく伝わらず、便意を感じないまま排便のタイミングを逃してしまうのです。 原因のひとつには「便意の我慢」、忙しさや外出先でのトイレを避けたい気持ちから便意を無視し続けていると、脳と腸の連携が鈍くなり、次第に便意が起こらなくなってしまいます。 また、坐薬や浣腸、ウォシュレットによる過剰な刺激を日常的に使用していると、自力での排便が難しくなり、直腸性便秘につながることがあるのです。 このタイプの便秘を改善するには、「便意を取り戻すこと」が何より重要になり、朝起きたらまずコップ一杯の水を飲んで腸に刺激を与え、朝食をとることで胃結腸反射を活性化させます。 そして、お腹を「の」の字にやさしくマッサージすることで、直腸への刺激が高まり、自然な便意が戻りやすくなります。クーポンで最大50%OFF 4日20時~ / 【公式】 黒モリモリスリム プーアル茶風味 約10日分 10包 お試し メール便 ダイエッターサポート* お茶 茶 ティー ティーバッグ ティーパック メール便秘密発送 *ダイエットする方の栄養補給 【ハーブ健康本舗】腸管が緊張してしまうストレス性便秘 「ストレス性便秘」は不安や苛立ち、過度な緊張、疲労といった精神的ストレスが原因となり、腸の動きが鈍くなってしまうタイプの便秘 仕事や人間関係の悩み、環境の変化などによる心の負担が、知らず知らずのうちに腸に影響を及ぼすのです。 腸のぜん動運動は、自律神経によって調整され、リラックスしているときに優位になる副交感神経が働くことで、腸が適度に動き、自然な排便が促されます。 しかし、ストレスを受けると交感神経が優位になり、腸の動きが抑制され、その結果、便意が起こりにくく、排便のリズムが乱れてしまうのです。 また、強いストレスが続くと、腸が緊張状態となり、便が出にくくなるだけでなく、下痢と便秘を交互に繰り返すような不安定な状態となり、このような腸の不調は、さらに不安やストレスを強めてしまい、悪循環に陥りやすくなります。 ストレス性便秘を解消するには、心と体の両面からのケアが重要で、深呼吸をしたり、自然の中で散歩をしたり、ぬるめのお風呂にゆっくり浸かるなど、自分に合ったリラックス方法を日々の生活に取り入れてみましょう。新ビオフェルミンS錠(540錠)【spts4】【ビオフェルミン】インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく17-2
2025.08.05
コメント(0)
-
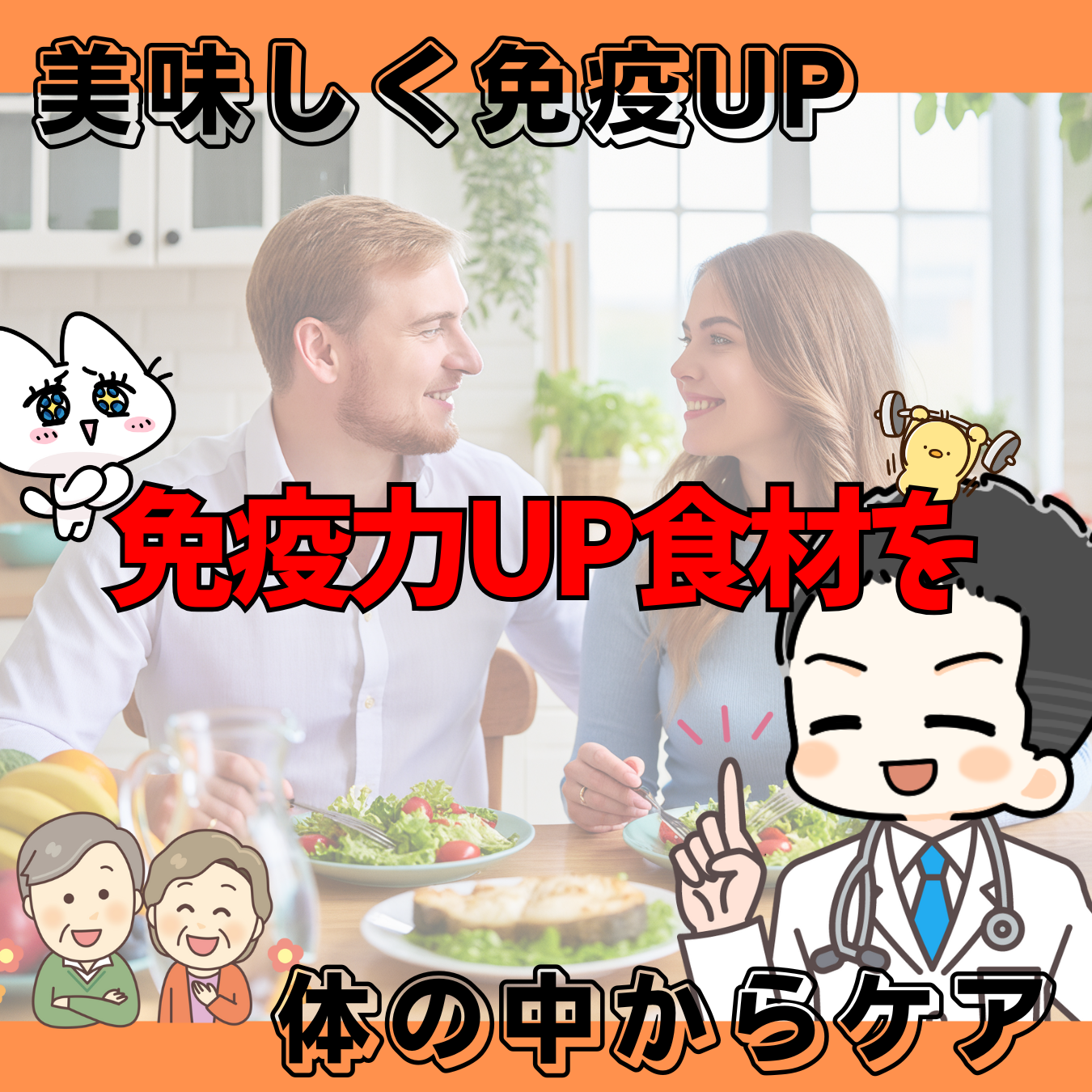
【美味しく免疫UP】食材を足して免疫力を上げる 体の中からケアを
ニンニクが心身の元気の源 古くから“天然の滋養強壮剤”として親しまれてきたニンニク。 その独特の香りのもととなる成分「アリシン」は、血行を促進し、免疫力を高め、疲労回復にも効果を発揮します。 さらに抗菌・抗ウイルス作用もあり、現代のストレス社会や感染症対策においても心強い存在です。 体の内側から元気を引き出す力を秘めたニンニクのパワーに注目していきましょう。ニンニクを食べて高血圧を対策 高血圧は、放置すると脳卒中や心筋梗塞といった命にかかわる病気につながることもあるため、日頃からの予防が大切です。 その対策のひとつとして、注目されている食材が「ニンニク」、古くから滋養強壮や疲労回復に用いられてきたニンニクには、実は高血圧に対しても効果的な成分が含まれているのです。 ニンニクに含まれる代表的な成分「アリイン」アリインは、ニンニクを刻んだり潰したりすることで酵素の作用により「アリシン」という物質に変化し、強い香りとともにさまざまな薬理効果を発揮します。 このアリインは、植物が外敵から身を守るために生み出す「ファイトケミカル」の一種です。 ファイトケミカルとは、野菜や果物などに含まれる天然の機能性成分で、ビタミンやミネラルとは異なる健康効果を持ちます。 抗酸化作用や抗炎症作用、免疫調整、さらにはがん予防効果など、多彩な働きが知られており、近年では“第七の栄養素”として注目されています。 ニンニクのアリインやそこから生成されるアリシンには、血液をサラサラにする働きがあります。 これにより血管内の抵抗が下がり、血流がスムーズになって血圧が自然に下がると考えられています。 また、アリシンには殺菌・抗ウイルス作用もあり、体内の炎症を抑えたり、感染症の予防効果ももたらし、さらに発汗作用によって体内の余分な水分を排出、血圧を安定させる効果も期待されます。 このように、ニンニクは単なる香味野菜ではなく、健康維持において強い味方となる食品です。 高血圧が気になる人にとっては、毎日の食事に少量ずつ取り入れるだけでも、自然な形で血圧のコントロールをサポートし、加熱しても一定の効果が保たれるため、炒め物やスープ、煮込み料理などに活用しやすいのも魅力です。(旨) 黒にんにく 訳あり 200g 100g×2 青森県産 生産から加工まで品質こだわり 栄養価は変わらないお得な訳あり【最近疲れやすい】黒にんにく 津軽 青森県産 にんにく 青森 にんにく ポイント消化 送料無料 ポイント消費 送料無料はちみつを砂糖の代わりに 毎日の食生活で欠かせない「甘み」ですが、過剰な砂糖の摂取は肥満や生活習慣病の原因になりがちです。 そこで注目したいのが、自然の恵み「はちみつ」、豊かな風味と栄養素を含み、砂糖よりも体にやさしい甘味料として知られています。 砂糖の代わりにはちみつを使うことで、美味しさを保ちながら健康意識を高める習慣が始まります。はちみつ短な風邪対策 寒暖差が激しい季節の変わり目や、乾燥する冬場には、喉の不調や風邪を引きやすくなります。 そんな時、昔から「喉にいい」と親しまれてきたのが「はちみつ」です。民間療法の中でも代表的な存在であり、現代の研究でもその効果が裏づけられつつあります。 はちみつはおよそ80%が糖分(主にブドウ糖と果糖)で構成され、約20%が水分、そして微量ながらビタミンB群、ミネラル、酵素、アミノ酸、ポリフェノールといった体に嬉しい栄養素が含まれています。 これらの栄養素が複合的に働くことで、喉の粘膜を保護し、炎症を和らげる効果が期待できるのです。 特に注目されているのが、はちみつの持つ抗炎症作用と抗菌作用があり、研究では、はちみつを摂取したグループの方が、咳や喉の痛みが軽減し、睡眠の質も向上したという結果が報告されています。 薬に頼らずに自然の方法で風邪の初期症状をやわらげたい人にとって、はちみつはまさに頼れる存在です。 喉の痛みや乾燥が気になるときは、寝る前にスプーン一杯のはちみつをゆっくり舐めてみましょう。 のどにやさしく膜を張り、朝まで潤いを保つ手助けになり、また、お湯やハーブティーに混ぜて飲むことで、体を温めながら吸収も促進されます。国産純粋はちみつ300g [瓶] 国産はちみつ 日本製 はちみつ ハチミツ ハニー HONEY 蜂蜜 国産蜂蜜 国産ハチミツ 非加熱血糖値を抑制の働きをもたらす はちみつは甘い食品でありながら、血糖値への影響が少ないという研究結果が報告されています。 特に注目されているのが「HbA1c(ヘモグロビンA1c)」への影響で、HbA1cとは、過去1〜2か月の平均血糖値を示す指標で、糖尿病の診断や血糖コントロールの評価に使われます。 ある研究では、はちみつを継続的に摂取してもHbA1cに有意な変化は見られず、同時に血糖値やコレステロール、中性脂肪の値も悪化しなかったと報告されています。 これは、はちみつが単なる糖分ではなく、自然由来の酵素やミネラル、抗酸化物質を含んでいるためと考えられています。 甘味を楽しみながら健康を守る手段として取り入れていきましょう。蜂蜜 はちみつお試しセット 90g×5個 瓶入り 送料無料 お取り寄せ グルメ 国産、外国産の純粋はちみつ30種以上から5つ選べる! 無添加 お得 おすすめ 本物の品質 効果効能を感じてください蜂蜜専門店 かの蜂 生はちみつ 非常食 100%純粋 健康 健康食品 ポイント消化ランチにはそばを積極的に 忙しい日中の食事こそ、体にやさしい選択をしたいもの。そこでおすすめなのが「そば」です。 そばは低GI食品でありながら、良質なタンパク質やビタミンB群、食物繊維を含み、血糖値の上昇をゆるやかに抑える優秀な食材です。 脂質も少なく、消化にも優れているため、午後のパフォーマンスを落とさずに満足感のあるランチを実現できるので、日々の食事に、そばを上手に取り入れていきましょう。そばはアミノ酸を豊富含む そばは日本の伝統的な主食のひとつでありながら、栄養価の高さでも注目され、優れているのが、アミノ酸バランスの良さです。 そばは植物性食品の中では珍しく、体内で合成できない「必須アミノ酸」をすべて含んでいるのが特徴です。 これにより、タンパク質源としても非常に優秀で、筋肉や内臓、皮膚などの健康を維持するのに役立ちます。 ただし、そばの栄養価を最大限に引き出すには「そば粉の割合」に注目することが大切です。 市販のそばには小麦粉を多く含む「二八そば」や「更科そば」などもありますが、よりそば粉の割合が高い「十割そば」を選ぶことで、アミノ酸やミネラルの摂取量も増やすことができます。 さらに、そばには「ビタミンB1」が含まれており、この栄養素は糖質の代謝を助け、神経の働きを保つうえで重要な役割を担います。 ビタミンB1が不足すると、疲労感や集中力の低下、さらには脚気といった病気を引き起こすこともあり、現代人は精製された白米やパンが中心の食生活になりがちなため、ビタミンB1の不足には特に注意が必要です。 加えて、そばにはカリウム、マグネシウム、亜鉛、鉄などのミネラルも豊富に含まれおり、これらは血圧の調整や骨の健康、免疫力の維持に欠かせない栄養素であり、日々の食事から継続的に摂ることが求められます。1000円ポッキリ 送料無料 蕎麦 讃岐生そば 6食セット 普通麺 平切麺そば 生蕎麦 香川県 産地直送 お試し ポイント消化 送料無 食品 グルメ 在庫処分 フード 人気 おすすめ ポスト投函 麺生 生麺 ギフト どんまいそばのルチンが毛細血管を丈夫に そばには、栄養価の高い植物性タンパク質やビタミン、ミネラルに加え、他の穀物にはない「ルチン」という独自成分が含まれているのが特徴です。 ルチンはポリフェノールの一種で、強力な抗酸化作用を持ち、特に「毛細血管を強化する働き」があることで知られています。 毛細血管は、私たちの体の隅々まで酸素や栄養を届ける重要な血管ですが、その構造は非常に細く、繊細で、加齢や生活習慣の乱れによって壊れやすくなることがあります。 毛細血管がもろくなると、皮膚に紫斑ができたり、内出血を起こしやすくなったりするだけでなく、脳出血や眼底出血など、重篤な病気のリスクにもつながります。 この毛細血管の壁をしなやかに保ち、強くしてくれるのがルチンの役割で、血管の内皮細胞を保護し、炎症を抑えながら血流を促進し、血圧の安定にも関与しています。 また、ルチンにはビタミンCの吸収を助ける働きもあり、相乗効果で血管全体の健康を保つ手助けをしてくれます。 そばは、特に「そばの実」や「そば湯」にルチンが多く含まれており、茹でた後のそば湯を捨てずに飲むことで、ルチンを余すことなく摂取できます。 ルチンは熱に弱いとされていましたが、最近の研究では、加熱後もある程度は活性を保つことが分かっており、調理してもその恩恵を受けられることが確認されています。 高血圧や動脈硬化が気になる人、血管の健康を保ちたい中高年層にとって、そばは手軽に取り入れられる「血管ケア食材」日々の食卓にそばを取り入れることで、毛細血管を丈夫にし、体の隅々まで元気を届ける土台を築いていきましょう。国産 韃靼そば茶 150g [ 北海道産 など 国産100% ] ほんぢ園 < ペットボトルよりお得 蕎麦茶 ダッタンそば茶 だったんそばちゃ 韃靼そばちゃ 韃靼蕎麦茶 韃靼そば ルチン ノンカフェイン 血圧測定 p10 > /セ/ ●まとめ:自分の体をしっかりとケアを 日常の食卓に取り入れやすい食材を通じて、健康を支える知識と実践法を紹介してきました。 どれも特別なものでなく、手軽に入手できるものばかりですが、それぞれに科学的な根拠と歴史的な知恵が詰まっており、大切なのはそれらを継続的に、目的を持って取り入れることです。 どれも特別な薬ではありませんが、毎日の「食」が私たちの健康をゆっくり、しかし確実に形作っています。 この本を通じて、身近な食材が持つ力を再発見し、「おいしく、無理なく、そして効果的に」健康を支える生活に食べていきましょう。\8/5(火)24h限定!エントリー&抽選で最大100%ポイントバック/ ガーリック & しいたけ オリーブオイル 83g 単品 まとめ買い 東洋オリーブ 風味オリーブオイル フレーバーオイル ガーリックオイル 精製オリーブオイル 無香料 おしゃれ 高級 ギフト 手土産インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく9-終
2025.08.04
コメント(0)
-

【間食で免疫UP】朝食で免疫力を高める 腸から元気を
ヨーグルトを食べて腸からキレイを 腸内環境の整備は美容と健康の土台、そこで注目したいのが、手軽に取り入れられる発酵食品「ヨーグルト」。 朝食の定番として親しまれていますが、実は整腸作用だけでなく、免疫力の向上や肌の調子を整えるなど、多くのメリットがあります。 体の内側からキレイを育てるには、まず腸を整えること。ヨーグルトはその最良のパートナーとなる食品です。シニア便秘解消にプレーンヨーグルト 年齢を重ねるにつれて、男女問わず便秘に悩む人が増加し、若いころは毎日自然に出ていたのに、シニア世代になると「何日も出ない」「お腹が張って苦しい」といった声が多くなります。 その背景には、加齢による腸のぜん動運動の低下や、水分・食物繊維の摂取不足、そして「腸内フローラ(腸内細菌叢)」のバランスの崩れが関係、悪玉菌が優位になると腸の働きが鈍くなり、便が硬くなって出にくくなるのです。 さらに、生活習慣の乱れも腸内環境に大きな影響を及ぼし、不規則な食事、運動不足、ストレス、睡眠の質の低下などが続くと、腸内の善玉菌が減り、悪玉菌が増えやすくなります。 こうした腸内のバランスの乱れを整えるためには、腸に直接働きかける食品の力を借りるのが効果的です。 そこで、毎日気軽に取り入れられる「プレーンヨーグルト」、ヨーグルトには乳酸菌が豊富に含まれており、腸内に届くと善玉菌として働き、悪玉菌の増殖を抑えてくれます。 プレーンヨーグルトは余分な糖分や添加物が含まれていないため、腸にやさしく、毎日安心して続けやすいのが魅力です。 朝食時にプレーンヨーグルトを一皿取り入れるだけでも、腸内環境の改善に役立ち、シニア世代の便秘対策には、医薬品よりもまず、自然で穏やかなヨーグルトの力を試してみることをおすすめします。ケフィア 種菌 手作り用 オリジナルケフィア 1袋(16包入)(8L/80食分)| 乳酸菌 善玉菌 酵母 ケフィアヨーグルト ヨーグルト 健康 健康食品 美容 ダイエット 腸活 腸内環境 腸内フローラ 牛乳 豆乳 たね 菌 種菌ヨーグルトで大腸がんの対策も プレーンヨーグルトは、整腸作用だけでなく、大腸がんの予防にも効果が期待できる食品です。 腸内環境を良好に保つことは健康全般において重要ですが、特に大腸がんの予防においては、その働きが注目されています。 大腸がんは、腸内に悪玉菌が多くなり、有害物質が生成されることで腸の粘膜が長期間にわたり刺激を受け、発症リスクが高まると考えられています。 ヨーグルトに含まれる乳酸菌は、腸内の善玉菌を増やし、悪玉菌の働きを抑える力があります。 悪玉菌が作り出すアンモニアやインドール、フェノールといった有害物質の発生を減らし、腸内を酸性に保つことで、病原菌の繁殖を抑制、このような環境を作ることで、大腸の細胞が健康に保たれ、大腸がんのリスクも下げることができます。 特にプレーンヨーグルトは、自然な形で腸内に乳酸菌を届けることができ、毎日継続して食べることで、腸内フローラが整い、腸の動きも活発になります。 便秘がちで腸内に便が滞りがちな人ほど、ヨーグルトを習慣にすることで老廃物の排出が促進され、大腸の健康維持に役立つのです。 腸内環境を整えることは、ただお腹の調子をよくするだけではなく、将来的な病気の予防にもつながり、大腸がんのリスクを少しでも下げたいと考えるなら、プレーンヨーグルトを食べる習慣をつけていきましょう。【楽天1位】 【専用容器付き】 ヨーグルトメーカー 【楽天ランキング1位】 甘酒 R-1 塩麹 甘酒メーカー ヨーグルト 発酵フードメーカー 牛乳パック 風邪対策 発酵食品 カスピ海ヨーグルト 発酵メーカー 冷やし甘酒 ※麹の甘酒 ギフト 豆乳ヨーグルト RSLココアの力で免疫アップ 香り高く、ほっと心が和む飲み物「ココア」実はこの身近な飲み物が、美容と健康を支える力を秘めています。 ポリフェノールやミネラルを豊富に含み、血流改善やリラックス効果など、さまざまな恩恵が期待できます。 甘いだけじゃない、ココアの実力を知ることで、毎日の習慣がより心強い味方に変わっていきます。ココアを飲んで便秘の解消に ココアの原料であるカカオ豆は、古くから健康食材として知られ、近年ではチョコレートの効能も注目されていますが、便秘解消という観点で見ると、チョコレートよりも「カカオパウダー(ココアパウダー)」の方がはるかに効果的です。 チョコレートには砂糖や脂肪分が多く含まれている一方、純粋なカカオパウダーは、カカオ豆を発酵・乾燥・焙煎した後にすりつぶし、脂肪分であるココアバターを取り除いた粉末で、栄養が凝縮されています。 このココアパウダーには、食物繊維やミネラル、ポリフェノールなど、腸に良い栄養素がたっぷり含まれています。 v中でも注目すべきなのが、「リグニン」という不溶性食物繊維、リグニンは水に溶けない繊維であり、腸内で水分を吸収して便のかさを増やし、腸のぜん動運動を促進し、便通が改善、自然なお通じへと導いてくれるのです。 現代人に多い食物繊維不足は、慢性的な便秘の大きな要因となっていますが、毎日1杯のココアを取り入れることで、無理なく食物繊維を補うことができます。 甘さのないピュアココアを使えば、糖分の摂りすぎも防げ、朝の一杯、もしくは夜のリラックスタイムに温かいココアを取り入れる習慣は、心と体の整腸に役立ちます。免疫力アップにも効果をもたらす ココアパウダーには、免疫力を高める働きがあることが近年の研究で明らかになってきました。 特に注目すべきは「NK細胞(ナチュラルキラー細胞)」を活性化し、ある実験では、一定期間ココアを習慣的に摂取した被験者において、NK細胞の働きが高まったことが報告されています。 NK細胞は、体内に侵入したウイルスやがん細胞をいち早く見つけて攻撃する、免疫の最前線で活躍する重要な細胞で、日々の生活の中でNK細胞の働きを保つことは、感染症予防や病気に負けない体づくりに直結します。 実際に、ココアの成分がインフルエンザウイルスにも効果を発揮することが研究で確認されており、A型・B型の両方に対して感染抑制効果があると報告されています。 これは、ココアに含まれるポリフェノールやテオブロミン、食物繊維などの成分が、免疫の調整や炎症の抑制に関与しているためと考えられています。 ココアは飲み物としてだけでなく、ヨーグルトに混ぜたり、料理やお菓子に加えることでも効果が得られるという点で、朝のヨーグルトにスプーン1杯のココアパウダーを混ぜるだけで、免疫力をサポートする一品になります。 甘みを加えず、純粋なココアを使うことで、糖分を抑えながら健康効果をしっかりと得ることができます。 毎日の生活に無理なく取り入れられるココアパウダーは、体調管理の強い味方。寒い季節や感染症の流行期だけでなく、日常の健康維持のためにも、ぜひ習慣化したい食品です。ココアパウダー 「砂糖不使用 2種類から選べるココアパウダー (軽やか!低脂肪ココアパウダー/濃厚!純 ココア パウダー) 500g」 送料無料 [ ピュアココアパウダー 純 ココア ココアパウダー 無糖ココアパウダー 純ココア 無糖 カカオ ]テオブロミンが血管を拡張 ココアには、健康効果が期待される成分が多く含まれており、特に注目されているのが「カカオポリフェノール」と「テオブロミン」です。 カカオポリフェノールは、抗酸化作用に優れた天然成分で、血管をしなやかに保つ効果をもたらし、これにより血管が拡張しやすくなり、血圧の低下を助けることが報告されています。 また、カカオポリフェノールにはLDL(悪玉)コレステロールの酸化を防ぐ働きがあり、動脈硬化や心血管疾患の予防にも効果的とされています。 さらに、強い抗酸化作用によって体内の活性酸素を除去し、細胞の老化を防ぐ効果も期待されます。 これは、シミやシワといった肌の老化だけでなく、内臓や血管の老化防止にもつながり、「食べるアンチエイジング」として、ココアは日常に取り入れたい食品の一つです。 一方で、ココアに含まれるテオブロミンは、穏やかに血管を拡張し、血流を促進、これにより体全体に酸素や栄養が行き渡りやすくなり、冷え性や肩こりの緩和、集中力の向上などの効果も期待できます。 また、テオブロミンは興奮作用が穏やかで、就寝前に飲んでも比較的安心なのも魅力です。 ただし、市販のココアドリンクには、砂糖やクリーム、香料などが多く含まれているものもあり、健康効果を台無しにしてしまう可能性があります。 できるだけ「純ココア(ピュアココア)」や「無糖タイプ」を選び、自分で甘さを調整するのがおすすめです。 また、ココアに含まれるテオブロミンは、犬や猫などの動物にとっては毒性がある成分なので、ペットに与えると命に関わることもあるため、誤って口にしないよう注意が必要です。【Lowタイプ】非アルカリ処理 ココアパウダー 500g 【送料無料】【メール便で郵便ポストにお届け】【代引不可】【時間指定不可】 カカオバター約11% カカオ豆100% [05] NICHIGA(ニチガ)緑茶を飲んで中性脂肪を撃退 古くから日本に親しまれてきた「緑茶」は、単なる飲み物ではなく、健康を支える知恵が詰まった存在です。 緑茶に含まれるカテキンやテアニンといった成分は、抗酸化作用やリラックス効果、免疫力向上など、現代人にうれしい働きを数多く持っています。 日々の生活に取り入れることで、体と心のバランスを整える、やさしい習慣が始まります。緑茶を飲んで日々血管をケアする 毎日の習慣として「緑茶」を取り入れることで、驚くほど体の中の健康バランスが整っていきます。 特に注目したいのが、中性脂肪の低下や高血圧の予防効果、近年の研究では、緑茶を1日500mlほど継続して飲むことで、体内のコレステロールや中性脂肪の吸収が抑えられ、さらに血栓ができにくくなることが明らかになっています。 緑茶の中には、健康維持に欠かせない成分が豊富に含まれ、代表的なものに「カテキン」「テアニン」「フラボノイド」などがあり、これらはすべて茶葉の天然成分です。 カテキンは、緑茶の渋みのもとでありながら、非常に高い抗酸化作用を持つことで知られ、このカテキンが、血中の中性脂肪や悪玉コレステロールの酸化を防ぎ、血管を健康に保つ働きをしてくれます。 また、カテキンは血糖値の上昇をゆるやかにし、脂質の吸収を抑制する効果もあるため肥満予防や血液の流れを改善し、血圧の上昇を防ぐ作用があるため、毎日の緑茶習慣が高血圧のリスクを下げることにもつながるのです。 これらの作用により、脳梗塞や心筋梗塞といった重篤な血管疾患の予防にもつながり、緑茶をよく飲む人は、これらの疾患の発症率が低いという疫学的な報告もあります。 つまり、緑茶は単なる「飲み物」ではなく、日々の生活の中で自然に取り入れられる「予防医学のひとつ」といえるのです。 そして、緑茶はカロリーがほぼゼロでありながら、深い味わいと香りを楽しめるヘルシーな飲み物で、食事中やリラックスタイムに、1日2〜3杯を目安に飲むことで、体の内側からゆっくりと健康を育むことができます。Y1【森のこかげ】 特上 煎茶 (100g×2個セット) 福岡県 ≪八女茶≫ 緑茶 やめちゃ とくじょう せんちゃ 茶葉 (残留農薬検査済み) 北海道 沖縄 離島も無料配送可 森のこかげ やめ茶緑茶でコレステロール値を下げる 緑茶で、近年注目されているのが「コレステロールとの関係」で、緑茶に含まれる成分には、血中コレステロール値を調整する作用があることがわかってきており、生活習慣病の予防に役立つとされています。 まず知っておきたいのは、コレステロールは「すべて悪いもの」ではないということです。 コレステロールは人間の体にとって欠かせない脂質の一種であり、細胞の膜を構成したり、ホルモンや胆汁酸の原料として働いたりする、非常に重要な役割を担い、体内でバランスが崩れると問題が生じます。 特に「LDLコレステロール(悪玉)」が増えすぎると、血管の壁に付着してプラーク(脂肪の塊)を形成し、血管を狭めてしまいます。 これが進行すると「動脈硬化」となり、心筋梗塞や脳梗塞など、命にかかわる重大な病気を引き起こすリスクが高まるのです。 一方で、「HDLコレステロール(善玉)」は、余分なコレステロールを回収して肝臓に戻す働きがあるため、善玉と呼ばれ、大切なのはこのバランスを保つことなのです。 緑茶に含まれる「カテキン」には、総コレステロール値やLDLコレステロールを下げる働きがあることが、多くの研究で示されています。 カテキンは高い抗酸化作用を持ち、血中脂質の酸化を防ぐとともに、腸での脂質の吸収を抑える働きがあり、肝臓での脂質代謝を助け、コレステロールが過剰に体内に蓄積されるのを防ぐ役割も果たします。 ある研究では、1日500ml以上の緑茶を継続的に飲むことで、総コレステロール値とLDLが有意に低下したという結果も報告されています。 緑茶を習慣にすることで、自然と脂質のバランスが整い、動脈硬化や心血管疾患のリスクを下げることができるのです。 緑茶は、砂糖や脂肪分を含まない自然な飲み物でありながら、日常生活の中で手軽に取り入れられる「健康サポーター」です。 朝食のお供に、食後のひと息に、日々の水分補給として、緑茶を習慣にすることで、体の内側から着実に健康を育むことができます。 コレステロールが気になる方や、家族に動脈硬化のリスクを抱える方がいる場合には、まずは「緑茶を一日数杯飲む」という小さな習慣から始めてみましょう。Y1【森のこかげ】 極上 煎茶 白折茶 (茎茶) (100g×2個セット) 福岡県 ≪八女茶≫ 緑茶 やめちゃ ごくじょう せんちゃ しらおりちゃ (残留農薬検査済み) 北海道 沖縄 離島も無料配送可 森のこかげ やめ茶インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく9-4
2025.08.03
コメント(0)
-
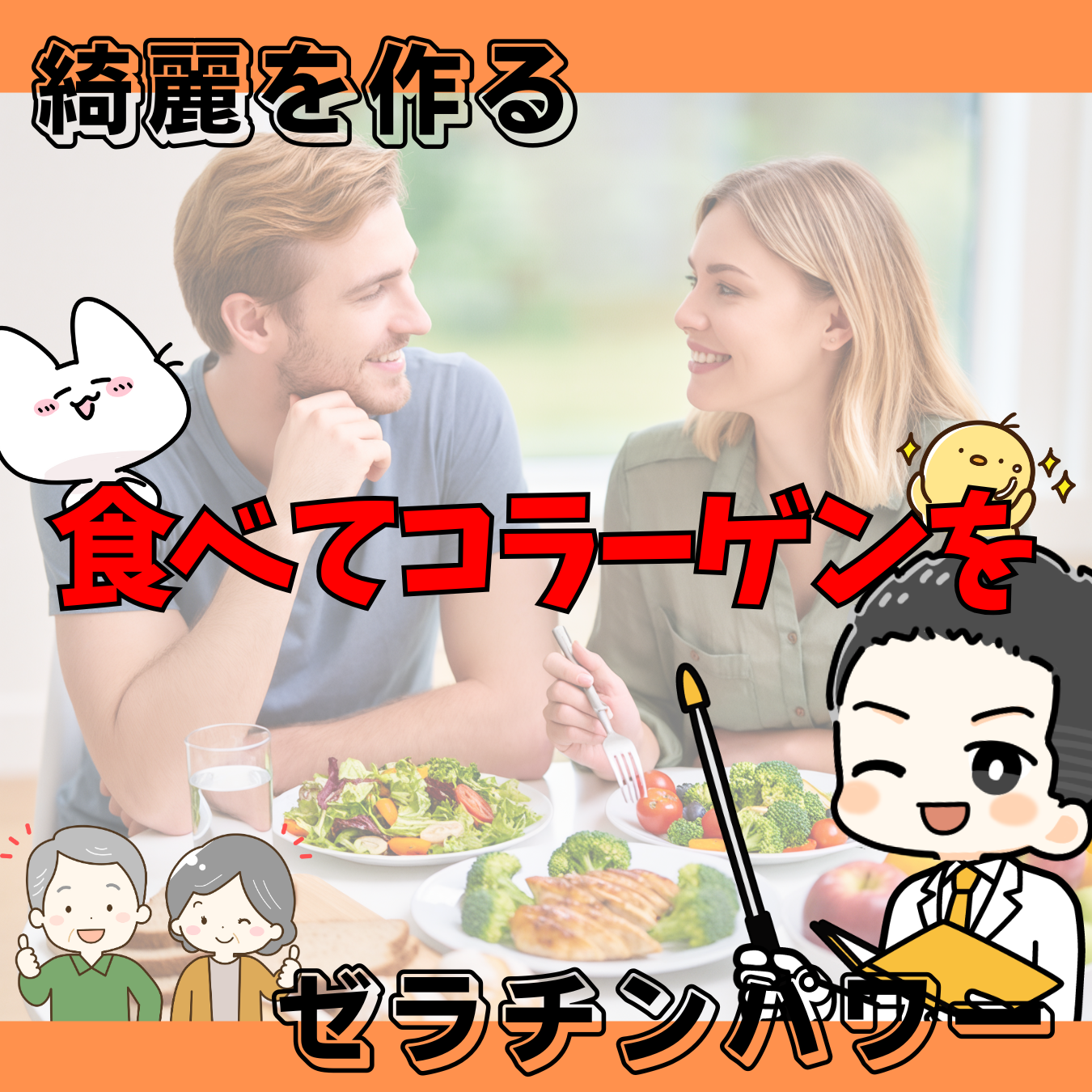
【綺麗を作る】食べてコラーゲンを作る ゼラチンパワーを
ゼラチンパウダーでコラーゲンを日々作る ゼラチンと聞くとお菓子を思い浮かべるかもしれませんが、実は健康づくりにも役立つ優れものです。 ゼラチンはコラーゲンのもととなる成分で、スープや温かい飲み物に溶かすだけで簡単に摂取できます。 コラーゲンは肌や関節の健康に欠かせないたんぱく質で、高価なサプリに頼らず、日常の食事で手軽に体内でのコラーゲン生成をサポートできるのです。コラーゲン不足が血管を脆くする コラーゲンが不足すると、私たちの体には深刻な影響が現れ、注意したいのが、血管のもろさによる脳出血などのリスクです。 コラーゲンは皮膚や関節だけでなく、血管の壁を支える重要なタンパク質でもあります。 人間の体は約60%が水分で構成されており、固形成分のうちの大部分がタンパク質、そしてそのタンパク質の約3割がコラーゲンと言われ、コラーゲンは体の構造を維持する上で不可欠な要素なのです。 コラーゲンは、毛細血管を含む血管壁の柔軟性や強度を保つ役割を担い、ビタミンCが不足すると、体内でコラーゲンの合成がうまくいかなくなります。 かつての船乗りに多く見られた「壊血病」は、まさにビタミンC不足によってコラーゲンが合成されなくなり、歯茎からの出血や皮膚の出血斑が見られる病気で、血管が脆くなり、簡単に破れてしまうことによって起こります。 ビタミンC不足によってコラーゲン不足が続くと、血管の壁が弱くなり、ちょっとした血圧の変動や衝撃で毛細血管が切れやすくなります。 これが脳で起こると、脳出血や脳梗塞といった命にかかわる病気に発展する危険もあります。また、血管だけでなく皮膚や関節、内臓の組織にも影響が出て、老化が進んだり、免疫力が低下したりすることもあります。 コラーゲンの合成にはビタミンCの存在が不可欠です。たとえ体内にアミノ酸やゼラチンを取り入れても、ビタミンCが不足していれば、コラーゲンはうまく作られません。ゼリエース ゼラチンパウダー緑(1kg)【イチオシ】【ゼリエース】脳幹出血もコラーゲンが関係 脳の病気の一つに「脳幹出血」があり、脳の中心に位置する脳幹で出血が起こる、非常に致死率の高い疾患です。 脳幹とは、脳全体の中継地点であり、呼吸や心拍、体温調節、意識の維持など、人間の生命活動を支える極めて重要な部位、この脳幹の働きが止まると、わずかな時間で命を落とす危険性があります。 脳幹出血は、脳の血管が破れることによって起こりますが、破れやすくなる背景には、血管壁を支える「コラーゲンの不足」が関係するのです。 血管はしなやかで強い構造を保つために、内側の構造をコラーゲンによって補強され、毛細血管の多い脳幹では、コラーゲンの役割が非常に大きいのです。 しかし、加齢や栄養不足、ビタミンCの欠乏などによって体内でのコラーゲン生成がうまくいかなくなると、血管は脆くなり、脳幹での小さな出血が一気に命に関わる事態へと発展してしまうのです。 また、脳幹の出血は一般的な脳出血とは異なり、ごく短時間のうちに呼吸停止や意識消失を引き起こすことがあり、搬送中に死亡する例も少なくありません。 そのため、脳幹出血を防ぐには、血圧管理とともに、血管の強度を保つための日々のコラーゲン生成が必要になり、ゼラチンや鶏の皮、魚の皮などを積極的に摂取することで体内の血管をしなやかに保つ手助けになります。 さらに、コラーゲンの合成にはビタミンCが不可欠なので、タンパク質を摂っても、ビタミンCが不足していればコラーゲンは作られないので、バランスのとれた食事と、意識的なコラーゲン・ビタミンCの摂取が、致死性の高い脳幹出血を遠ざけるために必要になります。ゼリエース 顆粒ゼラチン P-160(450g)【ゼリエース】 血管が脆くなると重病に 脳出血にはさまざまな種類がありますが、その中でも「くも膜下出血」は非常に重篤で、突然発症し命に関わることもある恐ろしい病気です。 脳出血やくも膜下出血の背景には「血管の脆さ」が深く関係し、私たちの体には、心臓から送り出された血液を全身に届けるための血管が張り巡らされており、その総延長はおよそ10万kmにも及ぶと言われています。 これらの血管の中でも、毛細血管は直径5〜10マイクロメートルと非常に細く、酸素や栄養素を細胞へ届けるという働きを担っています。 血管は主に3層構造から成り立っています。内側から「内膜」「中膜」「外膜」と呼ばれ、それぞれが柔軟性や強度、血流の調整といった役割を持っています。 中でも重要なのが、中膜と外膜の構造に関わる「コラーゲン」、コラーゲンが血管壁の弾力性や強度を支える“補強材”のような役割を果たしています。 しかし、加齢や生活習慣の乱れ、栄養不足、そしてビタミンCの欠乏などによって体内のコラーゲン量が減ると、血管は次第に弱くなり、わずかな圧力でも破れてしまうことがあります。 これが、くも膜下出血や脳出血の大きな原因の一つです。特に脳の血管は繊細で、血圧の変動にも影響を受けやすいため、コラーゲンによる構造の維持が重要なのです。 くも膜下出血は、脳の表面にある動脈にできた動脈瘤が破裂することで起こり、突然の激しい頭痛、意識障害、嘔吐などを伴い、発症後すぐに適切な処置がなされないと、命に関わることもあります。 コラーゲンを日々構成していき、タンパク質、ビタミンCと共に摂取することが、血管を強くし、脳の命を守ることにつながるのです。【公式】 デイリーランキング1位 【送料無料】 1000円ポッキリ ポイント消化 顆粒ゼラチン 家庭用 ゼラチン ゼリエース 無添加 無着色 お菓子 製菓材料 ゼリー ババロア ムース プリン 冷菓 おやつ 料理 〔らくらくゼラチン 50g×3袋セット〕 ゼラチンパウダーで血管を強化 私たちの体を支えるタンパク質の中でも重要な「コラーゲン」、コラーゲンは、皮膚、血管、骨、関節、内臓など、全身の組織に広く存在し、弾力性や強度を保つために欠かせない構造タンパク質です。 コラーゲンは「グリシン」というアミノ酸を約30%も含んでおり、さらにプロリンやヒドロキシプロリンなどのアミノ酸が繰り返し結合してできたタンパク質の一種なのです。 私たちの体内でコラーゲンを合成するには、まず「材料」が必要になり、それがアミノ酸、つまりタンパク質を含む食材です。 特にグリシンやプロリンを多く含む食材「良質なタンパク質を日々の食事に取り入れること」が基本になります。 おすすめは「動物性タンパク質」です。肉、魚、卵、乳製品などには、体内で利用しやすいアミノ酸がバランスよく含まれており、筋肉だけでなくコラーゲンの材料としても優れています。 しかし、忙しい日常の中で毎回しっかり調理するのは大変になるので、便利になるのが「ゼラチンパウダー」です。 ゼラチンパウダーは、牛や豚などのコラーゲンを加熱・分解して得られる成分で、構造的にはほとんど「コラーゲン」と同じです。 スープやお湯にさっと溶かすだけで、手軽にコラーゲンを補給することができるのが最大の魅力、味にクセがなく、温かい飲み物に混ぜても気にならず、毎日の習慣にしやすい点も大きなメリットです。 年齢とともに体内でのコラーゲン合成は低下していくので、ゼラチンパウダーを活用することで、毎日手軽に良質なタンパク質とコラーゲンを補給し、肌のハリや血管のしなやかさ、関節の柔軟性を守ることができるのです。新田ゼラチン ニューシルバー 顆粒 500g / 凝固剤 粉ゼラチン ゼリー ムース 冷菓 製菓材料ゼラチンが関節痛の対策に 膝の痛みに悩んでいる方は年齢を問わず多く、特に中高年層では「変形性膝関節症」が大きな原因となっています。 この病気は、膝関節の軟骨が長年の使用や負担によって徐々にすり減ってしまい、骨と骨が直接ぶつかることで痛みや炎症が起き、進行すると、歩行や階段の上り下りさえ困難になり、生活の質を大きく損なうことにもなります。 そこで注目されているのが「ゼラチンパウダー」、体内に取り入れるとアミノ酸に分解され、軟骨や靱帯の材料として再利用されます。 特にゼラチンに含まれるグリシンやプロリンなどのアミノ酸は、関節軟骨の成分に近く、関節の修復や保護に役立つと考えられています。 毎日、ゼラチンパウダーを取り入れることで、関節の栄養補給を助け、軟骨の維持や再生を促進する可能性があるのです。 ヨーグルトやスープ、温かい飲み物に溶かして摂取すれば、手軽に継続できます。関節の違和感を感じたら、まずは食事からケアを始めてみましょう。骨粗鬆症にもゼラチンパウダーで対策 年齢とともに増加する代表的な病気の一つが「骨粗鬆症」で、女性は閉経後に女性ホルモンの分泌が減少する影響で、骨の密度が急激に低下しやすくなります。 骨粗鬆症とは、骨の内部がスカスカになり、もろくなってしまう状態で、ちょっとした転倒でも骨折を起こしやすくなり、寝たきりのきっかけになることもあるため、予防と対策がとても重要です。 私たちの骨は硬いだけの組織ではなく、常に「再生(骨形成)」と「破壊(骨吸収)」を繰り返して生まれ変わり、若いうちは再生が優位ですが、加齢により破壊のスピードが上回ると、骨量は減少していきます。 多くの人が「骨にはカルシウムが大事」と思いがちですが、実はそれだけでは十分でなく、骨の構造は、カルシウムだけでなく「コラーゲン」によっても支えられているのです。 骨は、鉄筋コンクリートのように、コラーゲンが鉄筋、カルシウムがコンクリートのような役割をしています。 骨のしなやかさと強さを支えるためには、コラーゲンの存在が不可欠であり、これがないとカルシウムもうまく骨に定着せず、カルシウムをしっかり摂っても、コラーゲンが不足していれば骨の質は改善されないのです。 そこで注目されるのが「ゼラチンパウダー」、ゼラチンは体内でアミノ酸に分解されて再びコラーゲンの材料として利用されます。 特に、ゼラチンに含まれるグリシンやプロリンなどのアミノ酸は骨の形成に関与する重要な成分、ゼラチンパウダーを日常的に摂取することで、骨の質の向上が期待できるのです。 また、ゼラチンを摂取する際には、牛乳や小魚などでカルシウムを補い骨の強化を行っていましょう。粉ゼラチンAU 500g / 凝固剤 ゼリー ムース ババロア 冷菓 製菓材料 ゼラチンパウダーで肌を若々しく 老若男女を問わず、いつまでも若々しくありたいという願いは誰にでもあるもので、特に「肌の美しさ」は第一印象を大きく左右し、年齢を重ねるほど気になるポイントになります。 シワやたるみ、乾燥やくすみといった肌トラブルは、年齢とともに増えていきますが、その根本的な原因のひとつが「コラーゲンの減少」です。 コラーゲンは体内のあらゆる組織に存在していますが、実はその約40%が「皮膚」に存在し、肌の美しさはコラーゲン量と密接に関係しており、ここに「ゼラチンパウダー」が大きな効果を発揮します。 人の皮膚は、「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層構造から成り、一番外側の表皮は、肌のバリア機能を担い、水分の蒸発や外部刺激から体を守る役割を果たしています。 次に、その下にある真皮が、肌のハリや弾力を保つ要となる層で、ここにコラーゲン繊維が網のように張り巡らされ、深部には皮下組織があり、脂肪や血管を含み、肌全体のクッションのような役割を果たしています。 ゼラチンパウダーは、動物の皮や骨などから抽出したコラーゲンを加熱・分解したもので、体内に入るとアミノ酸に分解され、再びコラーゲンとして再合成されます。 特にグリシンやプロリンなど、コラーゲン特有のアミノ酸が豊富に含まれているため、肌の真皮層においてコラーゲン繊維を再構築し、肌の弾力や潤いを内側から支えてくれるのです。 これは外側から塗るスキンケアとは異なり、内側から肌の土台を整えるという点で、より根本的な美容法といえるでしょう。 高価な化粧品を何種類も使い分けて肌の表面を整えるよりも、ゼラチンパウダーを食生活に取り入れて内側からコラーゲンを補い、真皮の状態を改善していく方が、はるかに自然で効率的です。 肌の調子が良くなると、化粧品に頼る必要が少なくなり、経済的にも大きなメリットがあります。高価な美容液やクリームに投資するより、まずはゼラチンパウダーを試してみることで、驚くような肌の変化を感じられるかもしれません。 肌の美しさは、表面ではなく「内側」からつくられる。そんな実感を、日々の小さな工夫で手に入れることができるのです。まとめ:ゼラチンで綺麗と骨の強化を ゼラチンパウダーは、体内でコラーゲンの生成を助ける優れた食品で、血管や関節、骨、肌などの健康維持に役立ちます。 コラーゲンは血管の強度を支える重要な成分で、不足すると脳出血などのリスクが高まります。 ゼラチンに含まれるアミノ酸は、関節や骨、肌の修復に関与し、ビタミンCと併せて摂ることで効果的にコラーゲンを生成できます。 毎日の食事に取り入れることで、見た目も内側も若々しさを保つことができるのです。【公式】 デイリーランキング1位 【送料無料】 ゼリエース ゼラチン ポイント消化 家庭用 ゼラチンパウダー 無添加 無着色 お菓子 製菓材料 ゼリー ババロア ムース プリン 冷菓 おやつ 料理 コラーゲン 〔プラスゼラチン 100g×3袋セット〕インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく9-1
2025.08.02
コメント(0)
-

【食過ぎリセット】暴飲暴食への対策 肝臓への労りが重要
食べ過ぎや飲み過ぎたなど困ったリセット 外食や会食、仕事のストレスによる過食、つい飲みすぎた週末、誰にでも心当たりがあるのではないでしょうか。 そんな時、「もうダメかも」と感じても、体を正しくケアすればリセットが可能になり、重要なのは、無理な断食や極端な制限ではなく、「体をレスキューする食べ方」 内臓にたまった負担をやさしく取り除き、再び元気を取り戻すには、食べ方の工夫が何より効果的です。 この章では、食べ過ぎ・飲みすぎ後の不調をリセットし、老けない体を守るための“食の立て直し術”をご紹介します。 食べ過ぎた次の日が重要になる つい食べ過ぎてしまったり、飲みすぎてしまうことは、誰にでもあるり、外食が続いた、イベントで飲みすぎた、ストレスで間食が止まらなかった。 そんな「暴飲暴食」は一度のことで大きな問題になるわけではありません、しかし、その後の対処を怠ると、体の中では疲労物質や老廃物が蓄積されていきます。 消化器官や肝臓に負担をかけ、結果的に老化を早める原因となってしまい、だからこそ、暴飲暴食した後の対策が重要なのです。 大切なのは、「暴飲暴食の翌日に対策を講じる」こと、多くの人は、ついそのままの食習慣を続けてしまいがちですが、ここで意識的に食事をコントロールすれば、体のダメージを最小限に抑えることができます。 その最も効果的な方法が、「少食」と「プチ断食」、少食は胃腸に負担をかけないように、食事量を控えめにすること。 例えば、朝は白湯だけ、昼はお粥やスープ、夜は軽めの和食など、消化の良いものを中心に摂ることで、疲れた消化器官に休息を与えることができます。 一方、断食(ファスティング)は、一定時間まったく食事を取らず、水やお茶だけで過ごす方法で、体内のデトックス効果が高まると注目されています。 少食と断食の効果は非常に多岐にわたり、胃腸が休まることで消化力が回復し、腸内環境が整います。 また、インスリン分泌が落ち着くことで血糖値の乱高下が抑えられ、体脂肪の蓄積も防ぐことができ、細胞の修復や代謝を促すオートファジー(自食作用)も活性化され、体のリセットが自然に進んでいきます。 大切なのは、習慣として日常に取り入れるのではなく、「リセットの手段」として少食や断食を賢く活用すること。 無理なく、負担のない形で行うことで、体は本来のリズムを取り戻し、結果的に若々しさとエネルギーを取り戻すことができ、暴飲暴食を責めるのではなく、きちんとケアしていきましょう。【次回8月6日以降発送対応】【 ラベルレス 】国産 ミネラルウォーター ピュアの森 500ml 24本×2箱【計48本】軟水 水断食【 送料無料 】【 楽天グルメ大賞2020受賞 】 硝酸態窒素 亜硝酸態窒素 PFOS PFOA PFAS 検出限界以下肝臓の解毒力をサポートする食材 私たちの体内で、日々大量の有害物質と闘い、毒素を無害な形に変えてくれているのが「肝臓」です。 肝臓は“沈黙の臓器”と呼ばれ、自覚症状が出にくいものの、実は解毒・代謝・栄養の貯蔵など多くの働きを担う重要な器官です。 中でも「解毒力」は肝臓の中核的な働きで、食品添加物、アルコール、老廃物、さらにはストレスによって生じる有害物質まで、日々処理を続けています。 この解毒作用をスムーズに進めるには、ある種の栄養素のサポートが欠かせず、特に重要なのが「亜鉛」「マグネシウム」「ナイアシン(ビタミンB3)」の3つです。 亜鉛は解毒酵素の構成成分として働き、マグネシウムは肝臓内の代謝を助け、ナイアシンはアルコールや化学物質の分解を支え、これらの栄養素は、魚介類、ナッツ、豆類、全粒穀物などに豊富に含まれています。 さらにもうひとつ注目したいのが、「硫化アリル」という成分で、これは玉ねぎ、にんにく、ニラ、長ねぎなどの“香りの強い野菜”に多く含まれており、肝臓の解毒酵素を活性化させる働きを持っています。 特に、にんにくに含まれるアリシンは、強力な抗酸化・抗菌作用をもち、解毒作用を後押ししてくれる心強い存在です。 日々の食生活でこれらの食材を意識的に取り入れることは、肝臓の負担を軽くし、その働きを高めることにつながります。 肝臓が元気になれば、疲れにくくなり、肌や消化の調子も整い、老けにくい体に変化していき、体の“浄化センター”とも言える肝臓を、食べ物の力でサポートしていきましょう。肝臓エキス 肝臓の力 1袋 240粒 約4ヶ月分 クルクミン アルコール しじみ オルニチン ウコン アミノ酸 シジミ 43000個分の L-オルニチン くるくみん を高配合! サプリメント 専門店MHS 体内殺菌とストレスから体を守る 私たちの体は、日々さまざまな細菌やウイルス、がんの芽と闘いながら健康を保っており、その中で重要な役割を果たしているのが食べ物の力です。 特に注目したいのが、野菜に含まれる「ファイトケミカル」。 これは、野菜や果物が自らを病害や紫外線から守るために作り出す天然の化学成分で、私たちの体にも抗酸化・抗炎症・免疫強化・抗がんといった多彩な効果をもたらしてくれます。 なかでも、ブロッコリーやキャベツ、大根、わさびなどに含まれる「イソチオシアネート類」は強い抗がん作用を持つ成分として知られています。 これらは体内の酵素を活性化し、有害物質を無毒化する解毒酵素を促進し、さらに、がん細胞の成長を抑制し、炎症を抑える働きもあるため、まさに“食べる薬”とも言える存在です。 こうした食材は、日常の食卓に「薬味」として取り入れることで、手軽に効果を得ることができます。 例えば、大根おろしやおろし生姜、刻みネギやしそ、みょうが、わさびなどは、少量でも料理に香りと刺激を加えながら、体にうれしい作用を発揮し、薬味は、胃腸の働きを助け、殺菌効果もあるため、免疫力を高めたいときや風邪予防にも最適です。 体内の浄化力を高め、がんに負けない体をつくるには、毎日の積み重ねが大切で、薬味や色鮮やかな野菜を積極的に取り入れ、自然の力で体を内側から守る習慣を育てていきましょう。【8/1最大半額クーポン&ポイント最大20倍】 スルフォラファン粒 約1か月分×3袋 T-751-3 (60粒×3袋) 送料無料 リプサ サプリメント ISA アイエスエー ダイエットサプリ ブロッコリースプラウト《単品より10%お得》《リアルタイムランキング1位》インスタでも健康終活を配信しています本を出版しています 終活健康情報をさらに詳しく8-終
2025.08.01
コメント(0)
全10件 (10件中 1-10件目)
1
-
-

- 心の病
- 深淵なる聖堂 (Remastered)
- (2025-10-18 14:20:02)
-
-
-

- 医療・健康ニュース
- マイクロプラスチックが、流産をうな…
- (2025-11-02 21:08:34)
-
-
-

- 健康管理・増進、病気予防、抗加齢(…
- 目指せ絶対的健康体 AIに訊いてみた…
- (2025-11-20 01:17:33)
-






