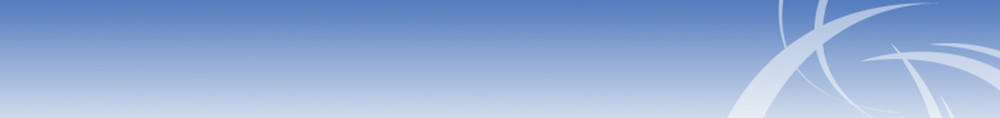詳細については、
「 クロルピリホスに関する規制
」
「 ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その1
」
「 ホルムアルデヒド発散建築材料」の内装仕上げ部分への使用面積の制限 その2
」
をご覧下さい。
ここで大事なのは、ホルムアルデヒド発散建築材料でF☆☆☆☆に分類されている建材には ホルムアルデヒドが全く含まれていないという意味ではないこと
です。
あくまでもF☆☆☆☆建材を使用すれば、室内のホルムアルデヒド濃度を厚生労働省の個別物質の指針値内に抑制でき、面積の制限がなく使用できますということです。
規制に当たり、気象条件は化学物質の発散量が温湿度は上昇するほど増大することを考慮し、外気温、相対湿度及び風速については、室内濃度が最も高くなると想定される夏期の条件によっていますが、実際には夏期では、建材からのホルムアルデヒドの発散量も増え、室内での濃度は厚生労働省の設定したホルムアルデヒドの指針値を超えることがあります。
さらにF☆☆☆☆建材を使用した建築物においても、シックハウス症候群様の症状を引き起こされている方がおられるということです。
これは法律的には違反した建築物で引き起こされた病状ではないので、実際にそこに住まわれる方が建設した側(建設会社、工務店)に訴えても、建設した側にも法律に遵守しての結果ということで、せっかく家を購入したにもかかわらずどうすることもできずに悩み苦しんでいる方がおられるという現実があります。
ここでもう一度整理すると
・建築基準法を遵守して建設された建築物でも、気象などの条件により厚生労働省の
設定した室内濃度指針値を実際超えてしまうということ
・建築基準法を遵守して建設された建築物でも、実際にシックハウス症候群様の症状を
引き起こされる方がおられること
が現実にあります。
このように建築基準法を遵守して建てられた建築物でシックハウス症候群様の症状を引き起こした場合、これは「シックハウス症候群」ではないとされるのでしょうか?
又、そこに住まう人の体質がたまたまそのような症状を引き起こす状態だったので、それは「化学物質過敏症」で責任は本人にあるとされるのでしょうか?
※ 関連として「 シックハウス症候群と化学物質の違い その1
」、「 シックハウス症候群と化学物質の違い その2
」もご覧下さい。
この辺の判断はまだまだ議論の余地があると思われますが、現実的には議論を回避しているような向きも感じます。
建てる側も住む側もしっかりその辺りを認識していく必要があると思います。
-
シックカー症候群 2011.09.22
-
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
-
毒性 2011.09.11
PR
カレンダー
サイド自由欄