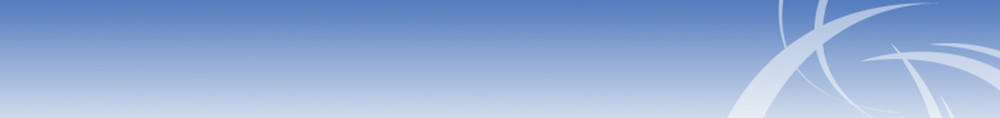又、居室以外の部分(天井裏等)についても制限が設けられおり、下記のような対策が必要となります。
※「天井裏等」については、「 シックハウス対策に係る建築基準法の『概要』
」をご覧ください。
【天井裏への対策】
天井裏等から居室へのホルムアルデヒドの流入を防ぐための対策には次の3通りがあります。
1 .建材の制限
下地材、断熱材その他これらに類する面材について、次にあげる材料をしないことにより
ホルムアルデヒドの発散を抑制し、ひいては居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する。
・第一種ホルムアルデヒド発散建築材料
・第二種ホルムアルデヒド発散建築材料
・令第20条の5第2項の規定により大臣認定を受けた建築材料
(第二種ホルムアルデヒド発散建築材料とみなされる建築材料)
要するにF☆☆☆以上の建材を使用するか、告示対象外の建材を使用するということに
なります。
2 .気密層又は通気層止めにより、居室へのホルムアルデヒドの流入を抑制する。
気密材料を連続して隙間なく設置し、居室と天井裏等の間の通風を遮断します。
・間仕切壁以外の部分については、居室との間に省エネルギー基準に規定する気密材を
設けて区画する。
(参考)省エネ基準で定められた気密材料
一 厚さ0.1mm以上の住宅用プラスチック系防湿フィルム(JIS A 6930‐1997)
二 透湿防水シート(JIS A 6111‐2000)
三 合板など
四 吹付け硬質ウレタンフォーム断熱材(JIS A 9526‐1999)
五 乾燥木材等(重量含水率20%以下の木材、集成材、積層材など)
六 鋼製部材
七 コンクリート部材
・間仕切壁、外壁などでは、ホルムアルデヒドの流入の抑制に関して気密材と同等以上に
気密性を有する材料(石膏ボードなど)により、居室との間に通気止めを行なう。
3 .居室の空気圧が当該天井裏等の部分の空気圧以上となるよう、機械換気設備など
基本的には1の「建築材料による対策」及び2の「気密層又は通気止めによる対策」で対策
することが望ましい。
やむを得ず3の「換気による対策」を行なう場合、換気設備の種類によって次に示す事項の
検討が必要です。
※機械換気設備などにより居室の空気圧を天井裏などの空気圧以上にすることにより、
建築物の構造などによっては、壁内などにおける結露の問題を生じる可能性がある
ので、 その点を配慮していく必要があります。
具体的には
■ 第一種換気設備の場合
居室が天井裏等より負圧にならないように、次のいずれかの対策を講じる必要があります。
・給気ファンの設計換気量を排気ファンと同じかやや大きく設計する。但し、給気を過大に
すると結露防止対策上の弊害があることに注意する必要があります。ダクトを用いた方式
の場合は、給排気両系統の圧力損失と送風機能力が適っているかの確認を行なう必要が
あります。
・天井裏等についても排気を行う。
■ 第二種換気設備の場合
居室内の空気圧が、常に天井裏など空気圧より高く保たれるので、居室内に空気が流入
することはないとみなされますが、躯体内部への漏気により内部結露の危険性は増します。
このため、戸建て住宅で気密性の低い場合は採用すべきでない方式といえます。
■ 第三種換気設備の場合
居室が天井裏等より負圧にならないように、天井裏等の排気を行う必要があります。住宅の
天井裏の場合、天井からの排気量の所要値は、排気量全体の5分の1以上とします。但し、
居室などの必要有効換気量の一部を天井裏からの排気に割り当てればよく、このために必
要有効換気量の割り増しは要求されません。
-
シックカー症候群 2011.09.22
-
化学物質の危険性(リスク) 2011.09.13
-
毒性 2011.09.11
PR
カレンダー
サイド自由欄