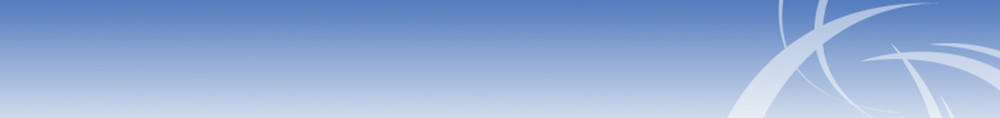そうした中で今年のこの問題に対する全体的な流れはどうなるでのしょうか?
シックハウス問題が我々に教えてくれる本質的な面が徐々に表面化していくのではと考えています。これは「 シックハウス問題を振り返って(2007年)
」でも述べましたが、昨年の流れの中の様々な問題が一般的に徐々に身近になり、今までの考え方だけではこの問題の本質的な解決にならないということに気づき始めるからです。
但し、これも平均的に広がるのではなく、温度差が生じる可能性が高いと考えています。
この辺りについては「 シックハウス問題に対する温度差
」をご覧ください。
では、建設業界の流れはどうなるでしょうか?
まず建材業界は建築供給が減じている中、さらなる技術革新および提案力によりシックハウス対策という概念ではなく安定供給を図るための製品が流通していくと考えられます。その一方で企業のあり方が問われる昨今、シックハウス問題に取り組んだ製品を供給することで企業の姿勢を示すケースも多くなると思います。この辺りも次に述べる建設サイドと同様に温度差が生じると考えられます。
建設サイドでいえば昨年よりも各企業間のシックハウス問題に対する考え方や取り組みの温度差が広がっていくと思います。
と同時にシックハウス問題に特別な関心がない、建築基準法を遵守しているという最低限のシックハウス対策を施している建設会社が思いがけないところでこの問題に直面する可能性が広がる年になると思います。
一般の方のシックハウス問題への関心及び対応はどうなるのでしょうか?
昨年来からの温度差が広がる反面、一部の層を中心にシックハウス問題の本質の面に気づき、シックハウス問題をより大局的な形で捉えられる土壌が出来上がると思います。
※ シックハウス問題の展望を語る中でシックハウス問題の本質という言葉を多用しています
が、これについては過去に下記の項目で述べたことの総称と捉えてください。
「 シックハウス症候群、化学物質過敏症、アレルギーなどの結果を引き起こした原因
」
「 この結果が次の原因となり時間的経過により起こされる次なる結果
」
「生活改善」
「 シックライフ
」
次に、2007年を振り返っての中では述べませんでしたが、実は昨年よりアジア地域でこのシックハウス問題が以前より大きく取り上げられつつあります。この辺りが日本にどのように影響していくかですが、一つには国が定めたシックハウス問題に関する法律、企業が行なうシックハウス対策製品、NPO法人など民間のシックハウス問題に対応する機関などの情報やノウハウなどが輸出される形になるといえます。こうした動きが副次的に日本でシックハウス問題をもう一度見直す契機となるかの一つの鍵といえます。
最後になりますが、このようにシックハウス問題の関心が広がり、さらに多義的に捉えられることで目前の問題(実際にシックハウス症候群や化学物質過敏症などの症状を罹患しているなど)解決を逸しないように専門家の舵取りは今まで以上に必要になるといえます。これについても別項で述べていきます。
2008年1月8日
-
語ってみたこと 2011.04.01
-
思わぬ落とし穴 2011.04.01
-
第三者機関の対応の難しさ 2011.03.31
PR
カレンダー
サイド自由欄