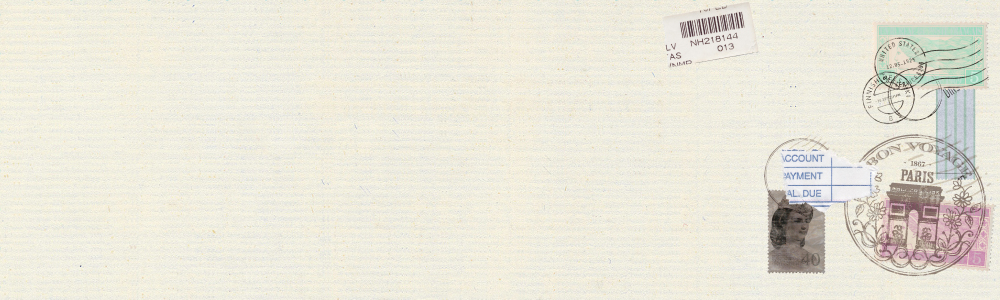PR
X
カレンダー
カテゴリ
テーマ: ☆留学中☆(2582)
カテゴリ: 留学情報
博士課程に在籍している学生に向けて開講されている小規模のセミナークラスである。実際に参加してみると受講者は博士課程の学生4名、修士の学生が3名のたった7名だった。毎回リーディング課題を読み込んで、クラスメイトとディスカッションをする形式だったため、毎週しっかり課題を読み込まないと置き物状態に陥ってしまう。また、毎週ディスカッションをリードする役目が学生に与えられる。自分の担当週では小さなプレゼンをした後にディスカッションに適した設問を3つほど用意しなくてはならない。授業を受けるというより、教授と共に授業を作り上げていく形だ。少しでも理解が浅い部分があるとすぐに博士課程の学生から鋭い指摘を受ける。
受講を認めてくれた教授には感謝しても感謝しきれないほどだ。毎週とてつもない課題量でしんどかったが、教授との距離も近く一番学びが多かった授業かもしれない。記憶を呼び起こしながら激動の15週間を振り返りたいと思う。
Week 1 Introduction to Language Assessment and Testing
教科書のチャプターリーディング(1章)。
シラバスに書かれた内容の確認。自己紹介、研究興味の共有。
第一週から””What is your research interest?”と聞かれて戸惑う自分がいた。しかし、博士課程の学生はスラスラと自分の興味分野を説明していた。博士課程の学生とのレベルの違いを目の前で見せつけられたような気がした。受講していた学生のほとんどがまだ博士課程の2年目でこれからリサーチプロポーザルをするはずなのだが、自分の軸となる研究対象が明らかになっている印象を受けた。やはり博士に進むにはクリアな目標とミッションがないと難しいのであろう。
シラバスに書かれた課題の量に圧倒されてしまったが、受講すると決めたからには最後までやり抜くしかない。まさに「背水の陣」である。
Week 2 Key Theoretical and methodological issues in SLD
教科書のチャプターリーディング(2章)、論文4本、ビデオ視聴1本。
この週は博士課程に在籍している学生二人がモデルプレゼンをしてくれた。二人の知識の量とプレゼンのうまさに言葉を失ってしまった。どうやったら難しい論文をあれほど噛み砕いて説明できるのだろうか。私が何時間かけて読んでも分からずずっとモヤモヤしていたが、説明後にまさに溜飲が下がった。特にontologyとepistomologyの違いの説明は目から鱗だった。現場にいた頃は気にしたこともなかったが、研究の世界ではこの両者は極めて重要な意味を持つ。何を研究対象とするのかという”what”の部分、そしてどのようにしてその対象を明らかにするのかという”how”の部分は研究を続ける限りずっと付きまとうという。そしてリサーチクエスションがそのwhatとhowを支配する。リサーチクエスションが単なる素朴な「疑問」ではいけないことに気づいた。膨大な先行研究とそこから生まれたリサーチギャップを踏まえた上で研究課題を作り出さなければならないのだ。
このコースでは最終的にリサーチプロポーザル(研究計画)を提出することになっている。果たして修士2年目の自分なんかにプロポーザルができるのか今から不安で仕方ない。
Week 3 Major data collection methods
教科書のチャプターリーディング(3章)、論文4本。
教授曰くclassical methods(従来の手法)が使われた研究論文を4本読んだ。この週の論文はimplicit knowledge(暗示的知識)とexplicit knowledge(明示的知識)の違い、そしてその知識の測り方や定義について書かれた論文についてディスカッションをした。Implicit knowledgeとは潜在的に蓄えられた知識を指すのに対し、explicit knowledgeは授業などを通じて得られた知識を指す。Explicit knowledgeが言語の習得に結びつくのか、またいかにして明示的知識が暗示的知識に移行するのかは研究者の間でも意見が分かれているようである。
Week 4 Coding
教科書のチャプターリーディング(4章)、論文4本。
この週は流暢さ、正確性、Task complexity(タスク難易度)を研究者はいかに測定しているか学んだ。タスクを終了するのにかかった所要時間、エラーの個数、認知的負荷など様々な項目を用いて研究者はタスクの難易度を調べていることがわかった。
Week 5 Designing quantitative studies (Age issue)
教科書のチャプターリーディング(6章)、論文4本。
量的研究のデザインの仕方について学んだ。特に言語習得と年齢の関係を扱った研究は長期的(longitudinal)な研究が多く、長期間に及ぶ研究をどのように量的研究に落とし込むかという視点で論文を読み込んだ。Jaekel et at. (2017)の大規模研究は非常に面白く参考になった。改めて「言語習得は早ければ早いほど良い」という考え方に慎重になった。言語習得は環境、言語への適性、発話量、認知能力など様々な要素が複雑に絡み合う。年齢もそのような要素の一つにすぎないというのを改めて思い知らされた気がする。それにしてもlongitudinal studyを実施するには研究者にかなりの覚悟が必要であることがわかった。また、研究期間が長くなるにつれて研究協力者への負担も増していく。統制グループを作るとなるとそこに倫理的な問題が生じる場合もある。サステイナブルな研究の実現は私が思っている以上に難しいことが明らかになった。私が研究を始めたらIRBを通すまでに挫けてしまいそうだ。
Week 6 Qualitative and interpretive studies
教科書のチャプターリーディング(7章)、論文4本。
この週は質的研究の手法と特徴について学んだ。量的研究は数値を重視するのに対して、質的研究は統計的優位では捉えきれない部分をインタビューや観察を通じて明らかにしようとする。したがってどのような形式でインタビューを実施してリサーチクエスションを明らかにするのかが非常に重要になってくる。今回課題として出された論文ではバイリンガルクラスルームでのアイデンティティのシフトと交渉に焦点を当てていた。詳細な観察記録と何度も実施されたインタビューから被験者の児童たちのアイデンティティの変化を明らかにしようする著者の姿勢を垣間見ることができた。質的研究では著者のポジショナリティーが多少なりともインタビューや考察の結果に影響を与える可能性があることがわかった。研究者が研究にどれほど「介入」すべきかクラスで議論した。これに関しては絶対的な正解があるわけではなく、研究ごとに研究者がどれほど研究協力者と接触するか判断をしなければならないらしい。
クラシカルな量的研究は研究手法がある程度確立されているが、質的研究はインタビュー形式を含め千差万別である。量的研究に比べて質的研究は骨組みを組み立てるのが難しいと思った。
Week 7 Classroom research
教科書のチャプターリーディング(8章)、論文3本。
Week 8 Mixed-methods (Survey research, Interview methods)
教科書のチャプターリーディング(9章)論文4本。
この週は質的研究と量的研究を組み合わせたmixed methodsと呼ばれる研究手法について学んだ。両者の良い側面を取ったような印象を受けるが博士課程の学生曰くmixed methodsはデザインをする上で制約が多く、単に両者を合体させれば良いという問題ではないようだ。
Week 9 Meta-analysis
論文4本。
この週は博士課程を終えられた卒業生を招いて、博士論文の概要や構想についてお話しいただいた。彼女は韓国の英語学習者のmorphosyntactic operationsについて研究をされたそうだ。研究の着想から実施する上での課題、コーディングの苦労話まで余すことなくお話いただいた。何十時間にも及ぶインタービューを文字に起こして、分析する作業は本当に気の遠くなりそうな作業である。自身の研究成果を堂々とお話しされている姿を見て、やはり博士課程を終えられる人は別次元の人のように思えた。自分のいつかあの領域に到達できるように努力を惜しまず研究をコツコツ続けていきたいと思った。
検索技術が向上したことで似たような研究論文を比べながら分析するmeta-analysisという研究方法が可能となった。研究論文の「まとめサイト」のような感じだろうか。Meta-analysisの論文を読むことで複数の論文結果を一覧で見れることが可能となった。しかし、研究の手法に微妙なズレがあったり、被験者の数等にもばらつきがあるため、p値だけを並べて判断するのは危険だとして慎重な立場をとる研究者もいるようだ。
Week 10 〜12
学生のプレゼン発表。
この授業では学期の最後に研究計画を提出することになっている。それに向けて中間報告の発表会が行われた。練りに練ってプレゼンの練習も何度も行ったが、実際発表をしてみると私の研究デザインには問題が山積していることが判明した。提出期限まで残り3週間ほどしかない。今から果たして突貫工事が可能なのか心配になった。
Week 13 Replication research
教科書のチャプターリーディング(5章)、論文3本。
この週は博士課程5年目で今学期学位を取得見込みの学生の話を伺った。その学生は教室内における学習者のエンゲージメントに関する研究をされていた。彼は研究のためにわざわざ東南アジアの教育機関に赴きインタビューを実施したという。インタビューや教室内の観察を記録したメモは300ページを超えたという。5年間もの月日をかけて人類の新たな叡智を生み出す営みは尊いと同時に非常に骨の折れる作業のようにも思えた。最後のQ and Aセッションで2つほど質問をしてみた。一つ目は「本研究のlimitaionsと今後のfuture directionsはどのようなものか」と「もし博士課程1年目に戻れるとしたら論文執筆に向けて自分にどのようなアドバイスをするか」と聞いてみた。一つ目に関しては「エンゲージメントはスピーキングに関する研究がほとんどでリーディングやライティングに関する研究が非常に少ない。もっと他の技能におけるエンゲージメント研究が広がることを期待したい」と話されていた。二つ目に関しては「もっと研究方法に関する本を読み込んでおくべきだった」と話してくれた。やはり質的、量的研究いずれにしても最低限の研究手法は身につけておかなければならないらしい。
当初は30分の発表だったらしいが、質疑応答が盛り上がり気づけば60分以上が経過していた。博士課程に進むか悩んでいる自分にとってはまさに目から鱗だった。楽しくも苦しい、それが研究というものなのかもしれない。
Week 14 No Class (Thanksgiving Break)
Week 15 Future directions (Digital technology in SLA)
論文5本。
いよいよ最終週の授業となってしまった。とても学びが多く毎週楽しみにしていた授業だけに終わってしまうのが非常に残念である。この週は私がプレゼンを担当した。De Consta et al.(2020)が著した応用言語学の倫理について発表した。研究を行う際に研究者は常に倫理と向き合わなければならない。IRBの手続きも倫理の一部だし、たとえIRBを通過としてもIRBではカバーされないmicro ethicsに細心の注意を払わなければならないという。昨今はインターネットの普及でオープンサイエンスの動きも出てきている。被験者のプライバシー保護も研究者に委ねられていると言っても過言ではない。個人情報保護が叫ばれる日本では実証研究はますますやりにくくるような気がした。
研究プロポーザルは自分の納得行くものが提出できたが、教授のフィードバックをみると研究手法にたくさんの問題点を抱えていることがわかった。やはり、普段の教育活動を研究に落とし込むのは非常に難しい。ただでさえ普段の授業準備でも手いっぱいなのに研究のデータ収集、コーディング、そして考察と時間を割くことが可能なのだろうか。研究をすることによって普段の授業が疎かになることは避けなくてはならない。15週目でも扱った通り、研究をする際は生徒によって有益になるように配慮をしなくてはならない。色々と試行錯誤を重ねながら研究を実施できるよう進めていきたいと思う。
優秀な博士課程の学生に囲まれAを取るのは難しいと一週目で悟った。成績のことは気にせずとにかく学びたい先生から知識を得ることにフォーカスして受講したため成績はあまり気にしていなかったが、蓋を開けてみたらAをいただくことができた。研究のプロポーザルは正直ボロボロだったが、授業の貢献度を評価してもらえたのかもしれない。
それでは今日も良い1日を。
きたろう
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[留学情報] カテゴリの最新記事
-
米国大学院2年目の学費 2025.06.30
-
アメリカ留学期間中に生活費公開 2025.05.18
-
海外留学を希望されるあなたへ(特に米国) 2025.03.08
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
コメント新着
キーワードサーチ
▼キーワード検索
© Rakuten Group, Inc.