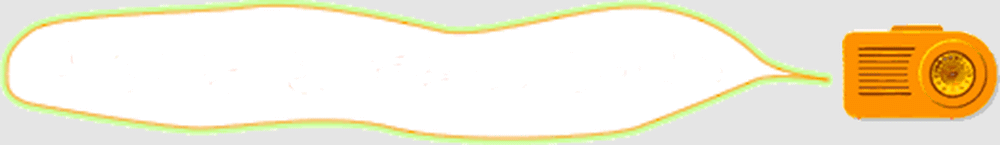2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2006年04月の記事
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
公益通報者保護法対応はどうなっているのかな
公益通報者保護法が4月1日から施行されています。内部通報者とかを保護する法律です。くわしくは、こちらをどうぞ。→「公益通報者保護制度ウェブサイト」(内閣府国民生活局)「公益通報をしたことを理由とする公益通報者の解雇の無効等並びに公益通報に関し事業者及び行政機関がとるべき措置を定めることにより、公益通報者の保護等を図る。」とされています。官僚の隠ぺい体質とか民間での牛肉偽装事件とかをきっかけに検討された法律でしたっけね。ちょっとよく覚えていませんが・・・。通報を受ける事業者(あらゆる事業者が法の対象となります)に求められる事項は、1 解雇等の不利益取扱いの禁止2 通報・相談窓口の設置3 個人情報の保護4 通報者への処理状況の通知となっています。上記の「公益通報者保護制度ウェブサイト」に「民間事業者向けQ&A集」があります。最近、ある企業(一部上場会社)の通報窓口担当者と話す機会があったのですが、その会社では、担当者のデスクに専用電話を設置し、その電話は鳴らないように(消音)し、担当者の携帯に転送されるように設定してあるそうです。そうすることによって、通報者が通報の電話をしても、社内の周りの人間には私用の電話にも仕事の電話にも見え、ちょっと席をはずすこともできます。これは、ある程度、私用の携帯に社外から仕事の電話もかかってくるようなエライ人にしか使えないワザな気がしますけどね。としても、この会社でも、最初は、担当者のデスクに専用電話を設置して終わり、という形式的な対応だったそうです。この担当者が、「これでは(周りに丸聞こえで)通報者が電話してこれないだろう」と指摘して、上記のような対応を提案して、ようやく変更されたそうで・・・。法が施行されたところで、通報がじゃんじゃんかかってくるとは思えませんが、「どうせ通報なんかあるわけない」という意識で形だけの対応をするのでは、意味がありません。何かあったときのための法(ここで関連するのは労働法かな)ですからね。私は仕事上この法律には関わっていないので、この法律にかかわる世の中の「あらゆる事業者」(零細企業など企業規模に関わりなく、あらゆる事業者が法の対象とされています。)がどのような対応をしているのか分かりませんが、労働者の最低限が決められていることになっている労働法の基準も守られていない世の中だったりしますし・・・・こういうところもなんか心配。ちゃんとやってるかな~、ちゃんとやってね、と思います。(う~ん、今度、みんな知ってるかな?っていう記事にしようかな。。。)・・・ていうか、「そもそも(法や法の施行を)知らない」って会社もけっこうありそう?!
2006年04月28日
コメント(6)
-
万引きは前科者
やっぱ書いておきたいってネタを今日は軽くいっときます。「窃盗罪に罰金50万円新設 改正刑法が成立」(yahooニュース共同通信 4月25日)「<改正刑法成立>窃盗罪に罰金刑新設 万引きを抑えこむ狙い」(yahooニュース毎日新聞 4月25日)「窃盗罪は従来懲役刑(10年以下)しか科せなかったが、新たに50万円以下の罰金刑も選択できるようになる。被害額が少なく、起訴猶予になることが多かった万引きを抑えこむのが狙いだ。」(上記yahooニュース毎日新聞)というニュースです。万引きで被害額が少額なのに懲役刑はかわいそう、っていうことで、不起訴となることが多かったと聞いています。そうすると、犯罪で刑罰を受けていればいわゆる「前科」ということになりますから、今まで万引きで不起訴だった場合は前科がつかない。で、今後は、罰金刑でも科されれば、立派な「前科者」となりますね。刑法(刑の種類)第9条 死刑、懲役、禁錮、罰金、拘留及び科料を主刑とし、没収を付加刑とする。(罰金)第15条 罰金は、1万円以上とする。ただし、これを減軽する場合においては、1万円未満に下げることができる。「同省は『罰金刑導入によって万引きの急増に歯止めがかかることを期待する』としている。」(上記yahooニュース毎日新聞)と書かれています。「前科」って聞くだけでちょっと怖い気もする、って考えの人に対して抑止効果が期待できると思います。「04年に万引きで検挙された成人は約7万7000人で、10年間で倍増。」(上記yahooニュース毎日新聞)ということですから、少しは減るかなぁ。これが浸透すれば。交通事犯の場合の刑法や道路交通法改正とかの場合は、車を運転する人が免許の更新の際に講習を受けるので、法律が変わって酒を飲んだ場合とかかなり厳しくなったぞ~ってのとかを教わることができますから、ニュースで知らなくても更新の際に知ることができますし、ニュースで知っていてもたいしたことないと思っていたのがけっこうすごいことになるっていうのを感じることができます。でも、こういうのは、万引きをする人たちにはどうやって伝わるんだろうか。ニュースだってたいしてやってないじゃん。orzやっぱりお店が一生懸命アナウンスするしかないのかなぁ。しかも、前科っていっても、意外とそんなに社会生活に影響ないかも知れない。かえって、見つかっても「罰金で済んだ」とか思われて万引きが続くってのも考えられるか。いや、「怒られただけで済んだ」よりはいいですけどね。(^^;)あと、前科、前科、罰金刑~って言っても、刑法の適用のある成人に対することですね。イメージ的には万引きって未成年もかなり多い気がするけど、その辺をどうしたらいいか。成人の万引きに比べて、未成年の万引きは本屋さんがかなり苦労されてるような気がしますが・・・。万引きはどんどん厳しく取り締まった方がいいとは思うのですが、厳しくしすぎると警察と検察と裁判所(と刑務所)が困るか。。。
2006年04月27日
コメント(4)
-
銀行も貸金業者も違いがなく
何度か記事にしていますが、現在、お金を借りるときに、銀行などの金融機関では15~20%までの金利、消費者金融などの貸金業者では29.2%までの金利となっている金融経済。この違いは利息制限法と出資法という2つの法律が金利を定めていて、利息制限法(15~20%)を超える金利は民事上無効となりますが、貸金業者登録をする貸金業者については貸金業規制法により厳格な要件(要件のととのった契約書面等を貸金業者が債務者に渡していて、債務者が納得して支払う)のもと、29.2%(出資法で定める金利)までとれることになっている、というものです。利息制限法以上、出資法までの間の金利は、貸金業規制法の要件を満たさないと無効となることから、「グレーゾーン金利」と呼ばれています。貸金業規制法での厳格な要件で認められることを「みなし弁済」と言ったりします。この辺の説明は、民法の教科書に小さく書かれています。この法的に不安定な変な制度「グレーゾン金利」と「みなし弁済」ですが、どうやら(やっと)なくなるようです。↓(フクザツなので、いつもよりちょっと前置きが長かった。。。)「上限金利、『引き下げ大勢』明記へ=21日に中間まとめ-金融庁懇談会」(yahooニュース時事通信 4月21日)「上限金利引き下げを明記 貸金業懇談会、中間報告」(Yahooニュース共同通信 4月21日)「貸金業懇談会:『上限金利引き下げを』中間提言まとめる」(毎日新聞 4月21日)「灰色金利廃止で大筋合意、貸金業懇談会の中間整理」(読売新聞 4月21日)「貸金業規制 上限金利20%以下 金融庁懇中間整理『みなし弁済』は廃止」(yahooニュース産経新聞 4月22日)「『金利引き下げ』了承、金融庁の有識者懇」(朝日新聞 4月21日)上記新聞記事らは、金融庁で行われている貸金業懇談会の「中間整理」の内容に基づいているそうです。懇談会では、出資法の上限金利を引き下げ、利息制限法(15~20%)に合わせるという意見で一致しているそうです。これが法制化すると、「グレーゾーン」や「みなし弁済」制度がなくなりますから、今まで「過払い金返還請求訴訟」(「みなし弁済」要件を守っていない貸金業者に払いすぎた金利分を返還請求)がすごい数があり、特に最近では司法で厳格な判断が相次いでいるため急増していると思われるのが、減少するでしょう。裁判所で特定の訴訟案件ばかりあるという状態は法律と経済が機能していないということでしょうから、望ましいことと言えます。でも、銀行と貸金業者の違いは今まではそれなりにあったと思われるのですが、商品がお金で競争するところは金利しかないのにお金を扱う貸す側が全て一律となると、その違いに意味があるんでしょうかね。あくまでイメージですが、今までは、銀行がフランス料理のフルコースだとしたら(質はいいが出てくるの遅い)、貸金業者は吉野家の牛丼(質は悪いがすぐ出てくる)ってな感じだとしたら、今後は、この「質」の部分については、同じになるわけですね。すると、全て競争。中小の貸金業者はコスト的に合わないのでどんどんつぶれるとして、銀行や大手貸金業者もかなり競争して生き残らないといけないでしょう。すると銀行だって、貸金業者っぽく営業していくことになるでしょうね。また、「モビット」「キャッシュワン」「アコム」「プロミス」の違いは、ふつうの一般のふつうの感覚では、分からないでしょう。その4つの中からお金借りようと思って、どこに行くか。まぁ、どれもCMとかしてて有名だし、ヤミ金とかだとやばいからとりあえずCMしてるしこういうところに行こう、くらいな気がします。上記4つの中では、前2つが利息制限法の金利帯(15~20%)、後2つが出資法の金利帯(29.2%)です。でも、お金を借りるときに、金利とか詳しく見て借りる人がどのくらいいるかどうか。上記4つについては、たいして違いがなさそう、有名だしATMとかあるし銀行の窓口に行くよりは簡単そう、とか、そんなもんな気がします。いわゆる多重債務者が問題となっていますが、私は、お金を借りることについての、上記のような「ふつうの一般のふつうの感覚」を上げることが一番よいのではないかと思います。難しいでしょうけど。私は、学校教育で改めて、お金を借りること、使うこと、どのように使うべきか、貯めること、などなどについて、教育を受けたことはありません。学校でないとすると親なんですが、親からも改めて機会を設けて教えられたことはなく、お金については、多分、親の消費行動を見て学んだんでしょう。それは、誰もだいたい同じだと思います。昔は多重債務者ってあまり問題化していなかったと思うのですが、モノも娯楽もあふれてるし、生活に苦しくなっても昔のように質素倹約って世の中でもないし、そういうのも影響してるんでしょうね。たとえば、家やマンションを買う人は、不動産の売買契約などで分からないところは担当者にいろいろ聞きながら納得して買うでしょうね。しかし、経験上及び聞いたところによると、貸金業者からお金を借りるにあたって、契約書をよく読んだり説明をよく聞いたりする人はあまりいないようです。特に、多重債務に陥る人・・・。金額や、人生における重要さの違いはあるかとは思いますが、でも結局のところの影響としては、家やマンションも、お金を借りるのも同じだと思います。借りるも、買うも同じです。まぁ、ついてくる金利と使ったもの(物、時間)を買ったと思えば。よく考えて、買う(=借りる)。それを学ぶ機会を少しでも多く作った方がよいですね。
2006年04月24日
コメント(10)
-
アイフルとコンプライアンス教育
アイフルが業務停止、先週末に大きく報道されましたね。新聞やテレビなどでたくさん出ているので、今回は、新聞記事のリンクではなく近畿財務局の告知にリンクしておきます。「アイフル株式会社(貸金業登録業者)の業務停止について」(近畿財務局)アイフルからの文書はこちら。→「行政処分に関するお知らせ」ちなみに、今行政処分中なので、アイフルのホームページ(http://www.aiful.co.jp/)に行くと「お詫び」の画面が出るようです。最近体調が悪くてかなりブログ更新が遅れがちなんで、ろじゃあさんのエントリー「アイフルの全店舗業務停止・・・厳しいのは確かですね」を見て、コメント代わりに記事書きます。ろじゃあさんのエントリーに、「通常、コンプライアンスがしっかりしているというか法務部が法務部なりに機能している上場企業であれば」というフレーズが出てくるのですが、私も、まがりなりにも上場企業であれば最低限のコンプライアンス教育はできているものと思っていました。でもあれですね、事実関係がどんなんだったかは、財務局からの処分内容でなんとなく分かりますが、貸金業者は貸金業法でいろいろ厳しい制限があるにもかかわらず、こんなこともできてなかったんか、と思われることばかり。ノルマ、ノルマでいくら厳しくても、上場企業の社会的責任などもあるし、やっちゃいけないことだって分からないのかなあ、と思いましたが。。。そこで思い出したのが、以前の職場。人がどんどん辞めて、入れ替わるんですよ。orz私は、教育係をけっこうやってたんですけどね、せっかく新人教育してもすぐ辞めちゃうんですよ。長くても2年くらいしかいないと、いっつも新人ばかりの環境で、いっつも(コンプライアンス的なことを含めて)業界の常識から始まるんですよ。弁護士事務所の事務職員であれば、最低限の基本は守秘義務とかお客様に対する接し方とかでしょうか。で、それだけ入れ替わりが激しいと、それほど能力なくてもいいから一定以上は教えなくてもいいやという方針になってくる。教育も追いつかなくて、だんだん、最低限もできない新人ばかりになってきたりします。で、今回のアイフル。カイシャの規模とかは全然違いますが、状況は似たようなもんなのかなぁ。消費者金融とかって入れ替わりが激しく、定着率はものすごく低いって聞きますしね。新人が多いからコンプライアンス守れてなくていいということではありません。定着率悪いから、追いつかなくてしょうがないじゃんと言い訳することでもありません。アイフルからの出された上記文書にも、「社員指導・教育の徹底」とか「コンプライアンス態勢の充実」とか書いてありますが、教育してもどんどん辞めていくのでは効果がないですよね。該当社員に処分をするだけでも効果はありません。そういう意味では、社員教育を徹底しますというだけでは実効性がないですから、社員を追い込まず、社内環境を良くすることが必要かと思いますね。今までノルマノルマな消費者金融会社が、そんな風に変われるかどうか。(ご参考)いろいろな方向から書かれていて、おもしろいです。↓おかにゃんさん→「取立ては計画的に」
2006年04月18日
コメント(9)
-
あなたは騙されやすいか?
よくテレビで、元・空き巣犯が出てきて「空き巣に入りやすい家」「入りたくない家」を紹介しますが、それと同じような感じです。振り込め詐欺グループからの聞き取り調査。こんな人は、騙しやすいらしい。「『警察』で動揺する人は簡単…振り込め詐欺の容疑者ら」(読売新聞 2006年4月12日)騙しやすいタイプ・・・「容疑者たちが、だましやすいタイプとして挙げたのは、警察官を名乗ると『えっ、警察ですか』と動揺する人や、パニックに陥って『一体どうすればいいですか』と質問してくる人など。演技で泣きじゃくる容疑者に対し、『大丈夫だから。何とかしてあげるから』と話しかけてくる人も、だましやすい人物の代表例だった。」騙しにくいタイプ・・・「一方、法律用語の説明を求める人や、『主人の会社に電話してみます』『警察署にかけ直します』など冷静な対応を取る人は、だましにくいと感じていた。電話をかけてきた相手の番号がわかる『ナンバーディスプレー』の電話機がある家なども、容疑者たちは敬遠していた。 捜査2課は『振り込め詐欺の犯人たちは、法律用語の意味を質問すると必ずボロを出す。分からない用語をうのみにせず、気持ちを落ち着かせて聞き返すことが大切』と呼びかけている。」(以上、上記読売新聞)うーん、警察と聞くと、ちょっとビビリますけどね~ふつう、法律用語とか警察用語って弱い(こわい)ですしね。ちょっとやましいところがあったりすると、「警察」にビビるってのもあるかも知れませんね・・・架空請求詐欺で「アダルトサイト」って書いてあると、家族にも知られたくないしってんで身に覚えがあって払っちゃう、とか。(~_~;)そんな弱いところをついて、痴漢の示談金名目の「おれおれ詐欺」が流行っているそうです。「都内の『おれおれ』倍増 痴漢名目が増加」(yahooニュース共同通信 4月12日)あるかも知れないところをついて、電車内の痴漢(やっちゃった/容疑をかけられたの両方があり得るでしょう)をネタに、騙されやすい用語を連発、警察や鉄道警備隊とかを名乗る。そんな感じでしょう。とにかく、みなさん、そんな電話を受けちゃったら、「確認」をちゃんとしましょうね。ちなみに、私は受けたことはありません。。。そうそう、家族の男性に自分を名乗るとき「オレ」と言わさないってのはどうでしょうね?(゜_゜)自分が騙されやすいか?騙されにくいか?自己診断チェックがありました。↓共同通信社の編集委員室が作る企画ページ ch-Kより「いい人ほどだまされる 被害者は加害者に似る?」ちなみに、私は診断結果は「危険度大」でした。(えwいわゆる日本人ないい人、ってことですかね・・・法律用語なら知ってるけど?
2006年04月13日
コメント(6)
-
プロとシロウト
友人のわん公さんのブログに、「『傾聴』は立派なコミュニケーション技術!」という記事があって、興味深く読ませていただきました。自分や家族宛ではない郵便物がたーくさんポストに入ってて、いい加減にクレームに来たおばさんの話。郵便局の対応は、「法律上、郵便物は投函された以上、私たちには配達をする義務がある」「自分で処分しろ(または)受取拒否しろ」そんな感じです。(要約しすぎ?・・・詳しくは上記リンクへ行ってくださいね。)でも、そんな、他人宛てのものを勝手に処分していいのか不安だし、受取拒否っていっても、やったことない人にとってはなんのことやらさっぱり、ちんぷんかんぷんですよ。で、思い出しました。(以前記事にしたかなと思って探したのですが、なかったので書きます。)数年前裁判所の事件受付係で、訴状を提出するために待っていたときのこと。一般の方(弁護士や法律事務所の職員ではない)と思われる中年の女性が、事件受付係の裁判所職員に対してなにやら怒っている。自分が提出した事件についての問い合わせをしたい風なんだけど、ちっとも教えてくれない、というふうな感じです。裁判所の人は、何言ってんだ、という風で、「だーかーらー! ここは事件受付係で、部に回るんですよ!」てな感じです。でも、それ聞いてて思ったんですが、一般の人からしてみれば、本人で訴訟やっててやっと訴状提出したと思って、単に出したときに問い合わせしに来たわけで、だいたい、提出した訴状が各部に回って、今度はそこが担当になるなんていう裁判所の仕組みなんて、普通知りませんよ。そこは、ちゃんと丁寧に教えてあげないと。で、「部」って言ったってどの部に行ってるか、案件によって違うんだから、どこの部に行ってるかとか、それがどの階にあるかとか、ちゃんと丁寧に教えてあげないと。なんか、あれですね。自分の常識が、他人の常識とは限らない、っと。プロ的な常識、普通の人には通用しませんよ。自分の仕事にも言えることなので、反面教師とさせていただきました・・・。法律用語や法律、訴訟の仕組みって、慣れてしまっているから普通に使ってしまっているんですが、問い合わせが来たときなどに、噛み砕いて相手が話を理解してくれているかどうか、呼吸をおきながら話さないといけません。面と向かって話しているならまだいいですが、電話では相手の様子が分からないので、より一層気をつけなければ。慣れてしまうと、忘れがちです。
2006年04月10日
コメント(8)
-
自転車の交通ルール違反も前科
最近私はとんと自転車に乗らなくなりましたが、高校のときは3年間、自転車通学をしていました。自転車って微妙ですよね。歩きでもないから、速い。車でもないから、歩道も走れちゃったりするのに、危ない。ほんとは通っちゃいけない歩道(「自転車通行可」の標識がない)のところは、ほんとは車道を通らなきゃいけないのだけど、車道を自転車で通るのはかえって危ない。それに、自転車は交通マナーの悪い人が多いですよ。歩行者にとっては、危ないですよ。通行量の多い車道を通っている自転車なんかもいて、車にとっても危ないですよ。そんな現状を踏まえて、自転車も大いに取り締まることになってしまいました。。。「自転車の交通違反、いきなり“レッドカード”へ」(産経新聞 04/06 17:51)「自転車の交通違反の取り締まり強化が盛り込まれ、これまで警察が違反を見つけても注意や指導で止めるケースが大半だったが、悪質な酒酔い運転や信号無視には、刑事処分の対象となる交通切符(赤切符)を積極的に適用することになる」「警察官が何度も警告しているのに飲酒運転を続けたり、信号無視をして車を急停車させるなど周囲を危険な状態に陥らせた場合に摘発する方向で検討している。」(上記産経新聞)今後は、自転車であっても、反則金、払わなかったら、罰金、前科ってことになりますよ~ドーーーーン!(喪黒福造風。)自転車は、道路交通法上、「軽車両」。これは、学校か自動車学校で習いました。道路交通法(定義)第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。11.軽車両自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のものをいう。11の2.自転車ペダル又はハンド・クランクを用い、かつ、人の力により運転する2輪以上の車(レールにより運転する車を除く。)であつて、身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車以外のもの(人の力を補うため原動機を用いるものであつて、内閣府令で定める基準に該当するものを含む。)をいう。道路交通法には、「自転車の交通方法の特例」というのがあって、自転車の交通の仕方がちょっと書いてあります。でも、これってすごく一般的に書かれている気がするし、さっき言ったように、「自転車通行可」の標識、一般に認識されているのかどうか。しかも、「自転車通行可」の標識を意識しながら自転車を運転していたとしても、同じ歩道なのに、途中から「自転車通行可」に変わったり、途中で通行可ではなくなったりするんですよ。この標識、というか交通ルールもどうかと思いますね。今後は、警察で一生懸命取り締まるのもいいですが、そもそも自動車のようにちゃんとした教習がないのが自転車ですから、自転車に乗る人には、定期的に講習を受けなければいけない、とか自転車を登録しなければいけない、とかそんな制度も必要と思います。
2006年04月07日
コメント(4)
-
条文の書き方って難しいよね
「母子手帳」の呼び方が「親子手帳」に変わるんだそうな。「母子手帳を『親子手帳』に 自民、今国会で改正」(yahooニュース共同通信 4月4日)「少子化対策の一環として父親の育児参加意識を高めるのが大きな狙い。」「手帳を交付する対象も、現行法の『妊娠した者』から『子どもの両親となる人』に改正。妊娠や出産、育児について夫にも『正しい理解を深める』よう求めるほか、条文の用語も『母性』を『母親』に書き換えるなど分かりやすい表現とする。」(上記yahooニュース共同通信)へえ。親子手帳。なんじゃそりゃ。母子手帳って、産まれてから予防接種とかにも使うけれど、妊娠中に、妊娠中の女性が使う方が大きいんじゃないか。父親になる男性が持っても、なんの意味もない。なんかしっくりこないなぁ。この名前変えても父親の育児参加意識には影響しないんじゃないかと思ったりしますが・・・。まあでも、この法律、妊娠した女性と育児についてばっかり書いてあるから、父親の育児参加を勧めるとか、文言を変えるのはいいんじゃないですか。よく妊娠中の女性を対象として出産・育児について学ぶ「母親学級」が自治体でやっていますが、最近は、父親になる男性も一緒に参加する「両親学級」が増えてきているようですね。妊産婦や乳幼児の保護の目的を維持、発展させた上で、父親となる男性も妊娠、出産、育児に参加できるような趣旨にできればいいですね。で、この法律に戻るんですが・・・話題となっているのは「母子保健法」らしいです。確かに、変な文言。(母性の尊重)第2条 母性は、すべての児童がすこやかに生まれ、かつ、育てられる基盤であることにかんがみ、尊重され、かつ、保護されなければならない。(母性及び保護者の努力)第4条 母性は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。上の記事には、「条文の用語も『母性』を『母親』に書き換えるなど分かりやすい表現とする。」とありました。上の条文の「母性」を「母親」に変えると、第4条は、「母親は、みずからすすんで、妊娠、出産又は育児についての正しい理解を深め、その健康の保持及び増進に努めなければならない。」となりますね。すると、まだ母親になっていない、初めて子どもを産む妊婦さんを対象としたときに、「母親は」という主語で、「妊娠、出産」「についての正しい知識を深め」・・・とあるのは、なんか違和感を覚えるでしょう。そんなような経緯で、「母性」というなんかよく分からない文言が入ったのかなというような気がします。ちなみに、第6条(定義)でこの法律の中の用語の定義がされていますが、「母性」については定義がされていません。「母親となる性」、つまり、女性ってことで、定義しなくても分かるでしょ、ってことでしょうか。だったら、「母性」を「母親」と置き換えないで、単に「親(または親となる者)」とかしてもいいようなところもたくさんありますけどね。始めからこの法律内で、「保護者」という用語も使っていますし。まあでも、条文の用語をどうするか、というのは、なかなか難しいところですね。いろいろ、こう書いたら問題が、とか、こう書いたらこう読めてしまう、とか、立法者は悩ましいところでしょうね。。。
2006年04月04日
コメント(0)
全8件 (8件中 1-8件目)
1
-
-

- 自分らしい生き方・お仕事
- 温和だが厳しい人になるのです。
- (2025-11-26 07:07:25)
-
-
-

- お買い物マラソンでほしい!買った!…
- お買い物マラソンで損したくないあな…
- (2025-11-25 20:30:05)
-
-
-

- 避難所
- 【大人気】「エアーソファー」 で、…
- (2025-10-30 22:24:38)
-