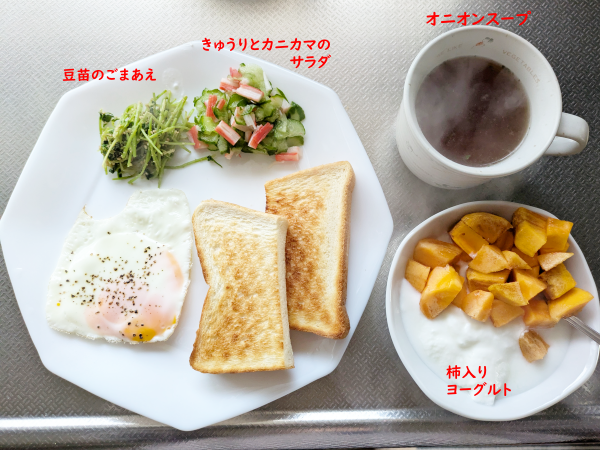-
1

ブルーシートの端切れを有効利用する
ミソジノジスイ本家先日のブルーシートですが、1.8m四方の正方形から1m四方の正方形を切り取ると当然L字型の端切れが出ます。端切れと言ってもかなり大きく捨てるにはもったいないので何んとなくとっておこうと思ったのですが、いつ使うとも分からない切れ端をストックしておくのも芸が無いな…と考えた結果思いつきました。今使っている箱型のブルーシート袋の側面が紫外線劣化でボロボロになってきていてそろそろ寿命だなと思っていたんですが、光があんまり当たらない底面はまだまだ元気。ですんで、この側面だけ新しいブルーシートの端切れと置き換えれば良いんじゃね?と思いつきました。というわけで早速実行。底面と側面をリッパ―で丁寧に分離し、手拭いを挟んだ状態で極低温アイロンを当てて縫い代を伸ばします。端切れを既定の大きさに切り出し、ココで少し考えました。一瞬先に側面を輪に縫いたくなりますが、それをすると多分底面に縫い付けた時にズレが出てしまいます。ですんで、先に側面を底面にミシンで縫った後で輪に縫う方が多分精密に出来るなと考えました。この辺が縫い仕事の面白いところで、学校の幾何学で正方形を描くならどの辺から描いても出来上がる図形は一緒ですが、裁縫の場合どこからどの順番で縫うかで出来上がりの精度が大きく変わります。その辺を考えて出来るだけ精密に仕上げるのが好きです。側面を輪に縫ったら次はほつれ止めと強度維持のために側面の上辺を2回折返してミシン掛けし、とっておいた取っ手を縫い付けて完成。従来の物より100均のブルーシートがちゃちな感じなのでどの程度もつかは未知数ですが、ただ捨てるよりはマシでしょう。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.26
閲覧総数 33
-
2

100均のブルーシートで庭仕事道具をDIY
ミソジノジスイ本家今日は久しぶりのDIY作業。うちでは庭仕事にブルーシートで出来た袋を使っています。この袋は大体50cm×50cm×高さ30cmの箱型に取っ手がついて持ち運べるようになってまして、集めた枯葉や雑草を入れて集めるのに重宝しているのですが、庭木の剪定の際は使い勝手が悪いのが以前から気になっていました。庭木の剪定で出る枝は長いと50cm以上のものがザラで、この袋に入れようとすると縁に引っ掛かって上手く入りませんし、ヘタすると30cm程度の枝でも駄目。おまけに引っ掛かった枝でブルーシートが破れて寿命が明らかに縮むのもどうかと思っていました。それがある日テレビで庭師の村雨辰剛さんの作業風景を見ている時、1m四方程度のブルーシートの四辺に取っ手を付けたもので選定した枝を運んでいるのを見て、コレだ!と思ったのです。シートだったら枝が縁に引っ掛かる事も無く作業がスムーズに進みます。枯葉を集める際は乗せたものが風で飛んでしまいそうなので多分向きませんけど、枝だったら風で飛ぶ事も無いので無問題。ということで今回作ってみました。100均で1.8m四方のブルーシートを買ってきて、1m四方にカット。デフォルトでは周囲は切りっぱなしだったんですが、強度的にコレでは話にならないので、3mcずつ2回折り曲げてからミシンで縫い、そこに寿命を迎えたブルーシート袋から外しておいたまだまだ丈夫な取っ手部分を縫い付けて完成。材料費110円で作れたのもポイントが高いです。ただ気になる点としては、100均のブルーシートが明らかに薄くて弱そうな点です。まぁ、しばらく使ってみて駄目だったら次はもう少しグレードの高いブルーシートで作りますけども。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.25
閲覧総数 42
-
3

貰った鯛を食べ尽くす
ミソジノジスイ本家今日は近所のおっちゃんから40cmクラスの鯛を貰いました。ありがたいことです。40cmの鯛というと大きく感じるかもしれませんが、鯛は頭の割合が大きいうえに身幅が薄いので、刺身にすると驚くほど少なくなります。今回だと2人分×2.5食位。うちでは鯛の刺身を作る場合、皮をひかずに湯霜or焼霜造りにします。鯛は皮ぎしが美味しいと思うので、そこを取り除くのはアホのする事です。ただ皮は弾力があって食べ辛いので、熱湯をかけるorバーナーで炙る事で皮に火を通して食べやすくするのです。コレが湯霜or焼霜造りです。アラの扱いも最近は定番化してきました。アラは身の割合が多くて食べやすい部分とそうでない部分に分けます。具体的に言うと前者はカマと腹身のすき身。ココは軽く塩をしてしばらく置いてから焼き物にします。前回は塩焼きだったので、今回は味醂味噌に漬け込んで味噌焼にします。後者は兜・中骨・血合い骨といったその他のアラ。ココは身の割合が少ないのでそのまま食べる事はせず、一旦蒸してから身をほじくり出し、味醂醤油で要りつけてデンブに加工します。ちなみに鯛のウロコは唐揚げにするとパリパリして美味いと言われていまして、私も何度か作ってみたのですが、労力の割にそうでもないという結論に至ったので最近はそのまま廃棄しています。それでも全体的に見ると廃棄部分は平均よりかなり下だとは思いますね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.18
閲覧総数 40
-
4

砂壁はダメ
ミソジノジスイ本家家が無駄に広い故あちこちに(私の基準で)汚い部分がまだまだ沢山あり、燃える日々が続いています。とはいえ、どう考えてもどうにもならない部分というのもあるわけで、ホントなんでこんな風に作ったんだかと内心愚痴る事も多いです。最近の最大の愚痴りポイントは台所・脱衣場の砂壁。これは大失敗だと思います。この二箇所、どうしても湿気が多くて壁が結露→黴が生えます。おかげで壁の所々に黒いシミが。黴は砂壁の奥深くに巣食ってますんで、拭いても意味がありません。また、カビキラーのようなものを吹き付けると黒い汚れが流れてシミが広がるだけですし、洗剤成分による壁変色のリスクもあります。もうお手上げ、見なかった事にするしかありません。更に黴の上位バージョンとしてゴキブリの糞があります。脱衣場の天井近い角、湿気が特にたまりやすい場所にゴキブリが巣として使っていたっぽい場所がありまして、ゴキブリの糞が大量に。ゴキブリの糞って直径1mm以下の黒い砂粒のような物体で、乾いていれば何て事はないんですが、湿気で柔らかくなった糞が砂壁にしみ込むと、これもまた処置無し状態になります。砂壁って見た目は風雅な場合もありますが、実用面では全く良い事ないですね。こういう湿気の多い場所の砂壁は論外ですが、湿度面では優遇されている居室空間でも、表面の凹凸に埃が引っかかる・経年劣化で砂が落ちてくる・大規模な拭き掃除が不可、などなど。まぁ今時新築家屋で砂壁を選択する人もいないでしょうし、そもそも木舞いを組んで壁を塗るなんて贅沢なご時世ですから参考にはならないでしょうが、砂壁はホント止めた方が良いと思います。人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2014.02.01
閲覧総数 459
-
5

ジャガイモのベストパートナーは塩と油
ミソジノジスイ本家そろそろ本格的に寒くなりそうなので、ギリギリにまで引っ張っていた夏植えのジャガイモを収穫してきました。結果:失敗。1kgの種芋から収穫できたのは3kg。3~4ヶ月で3倍になっているんだから投資だったら大成功ですが、ジャガイモの場合最低5kgは欲しい所。とはいえ、2月に植えて梅雨前に収穫するパターンに比べると難易度が高いのは事実なので、零じゃなかったことを喜ぶべきかもしれません。用途としては指先サイズの極小個体はまとめて炒めて塩振って食べるのが一番だと思います。残りはハッシュドポテトかジャガバターが有力候補。肉じゃがも悪くないんですが、ジャガイモの味をストレートに生かせるかというと、ハッシュドポテト・ジャガバターには劣るというのが私の評価です。ポテサラも美味しいんですが、、数少ない自作ジャガイモを託せるポテンシャルがあるかというとコレも微妙。やっぱりジャガイモはシンプルに塩と油に合わせるのが一番だと思います。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.24
閲覧総数 40
-
6

布の処分にはいつも頭を悩ませる
ミソジノジスイ本家風呂の後下着のシャツを着ようとしたら腕が引っ掛かって大規模に裂けました。私は基本的に直せる物は直して使うの主義なのですが、今回の場合破れた距離が長いのと、破れた場所だけでなくその周辺も満遍なく弱っているという理由から修繕は早々に諦めました。ただこの場合、避けたシャツをどうするかという問題がいつも頭を悩ませます。捨てるのが最も手っ取り早いですが、避けたとはいえ布としてはまだまだ健在なので、補修用の布としてやウェスとしての使い道が無い事もありません。ただ問題は、どちらも供給過剰な事です。繕い作業なんて早々発生しませんから、布は常に余り気味です。ウェスもたまーに使いますがそんな頻繁ではなく、所定の位置に収めてある以上のウェスは基本的にとっておくだけ空間の無駄遣い。結局のところ焼いてアルカリ灰として畑に撒くのが相対的に一番有効な活用法なんですが、それはどうもモッタイナイ気がして腰が引けます。今回は最終的に焼く事になりそうですが、布の処分にはいつも迷いますね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.10.29
閲覧総数 56
-
7

ポリ袋は買いなはれ
ミソジノジスイ本家芋を掘ったら当然大量の地上部分が残るわけで、今までは全部乾かして燃やしてたんですが、サツマイモの葉柄は食えるのです。台湾では普通に野菜として売られているそうで、実際食べると結構美味しい。ですんで今回葉柄部分をバケツ一杯分回収してきました。この葉柄はそこそこ固くて、皮を剥けば本当に柔らかくて美味しいんですが、1タッパー分のキンピラを作るのに葉柄100本強が必要で、それらの皮を剥くのはモヤシのひげ根をとるよりも遥かに重労働です。なのでうちでは皮ごとちょっと長めに下茹でをし、固い部分は頑張って噛むことでリカバーするという原始的な方法を採ってます。今回採れた葉柄も全部下茹でした後、3cm程にカットしてポリ袋に詰めて冷凍保存します。バケツ一杯の葉柄で5タッパー分の下所持済みサツマイモの茎が採れましたんで、とりあえず年内は常備菜を一品確保です。ちなみに今回の様に食品保存に使うポリ袋はドケチの私としては意外ですが100均で買ってます。110円で100袋入っていて私から見ても全然安いですし、何よりスーパーのサッカー台で必要以上にポリ袋をとっていくおばちゃんの姿が本当にみっともないので、反面教師となっています。それ位買えよと思いますし、ああいうのはドケチの風上にも置けないですね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.05
閲覧総数 69
-
8

マツの剪定と徒労感
ミソジノジスイ本家毎日1時間をノルマとしている庭木の剪定ですが、今日は庭のメインとなっているマツ。私、剪定の中で何が嫌いかってこのマツの剪定が一番嫌いです。めんどくさい理由1. 刈り込み挟不可。ツツジなんかは刈り込み挟でガーっと平面を作っていけるのですぐに終わるんですが、マツは刈り込み挟を使って葉っぱを半ばで切ってしまうと、そこから残った葉が茶色く変色して大変汚くなるので、刈り込み挟は原則使えません。不要な枝を辿って元から一本ずつ植木鋏で切らないといけないがちょー面倒臭い。理由2. 樹形がやっかい。マツは末広がりの形になるように剪定を進めますが、高所作業の際はその樹形が仇になります。一番高い真ん中の部分を剪定する場合、スカートの様に広がった樹形が邪魔をして手の届く範囲に梯子を立てるのが滅茶苦茶大変です。一本スッと立ったマキなんかと比べると、面倒臭さが格段に上がります。理由3. 葉が刺さる。ゴヨウマツのような葉が柔らかいマツはともかく、うちにあるようなクロマツは葉が結構硬くて作業中の腕に刺さります。バラの棘程ではないんですけど、入浴時には腕に多数の点々がついていてしみて痛い。理由4. 何の役にも立たない。コレが多分極めつけで、コレだけ手間暇かけて世話をしても果樹の一つ実るわけでもなし、根元からマツタケが生えてくるわけでもありません。確かに格好は良いので、手入れをしたマツを見ながらお茶をして楽しむのが多分マツを庭に植える醍醐味なんでしょうけど、その境地には遠く至れてないんですよね。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.12
閲覧総数 48
-
9

魚は捌いた人が一番美味しい部分を独り占めできるのがルール
ミソジノジスイ本家先日の鯛もそうですが、魚をおろした場合には料理人の特権というのがありまして、捌いた人が一番美味しい部分を独り占めできるというものです。ただしこの一番美味しい部分というのはマグロでいう所の大トロみたいな分かりやすい部分ではなく、目玉の周りとか後頭部といった普通は捨てられがちだけど実は美味しい、という部分であることが暗黙の了解となっています。今回の鯛の場合、私が一番美味しいと思って独り占めしたのは刺身の端の一番尾鰭に近い部分です。この部分は尾鰭に近いだけあって幅が狭いうえに筋が集まっていて固く、刺身としては全然美味しくありません。しかし魚の筋ってのは軽く火を通すとプリプリの歯ごたえに変化して超美味い。私の場合この端の部分を鯛茶漬けにするのが大好きです。使うのはこの尻尾に近い部分に加え反対側の頭に近い部分。こっちは入っている大きな血合い骨を抜く際に身が割れがちなのと、やっぱり端っこなので幅が狭くて刺身にした時の形が悪いので、料理屋なんかでは真っ先に外される部分です。これらを醤油・味醂・胡麻油で軽く和えてからご飯にのせ、熱々のお茶をかけます。鯛の身が熱々のお茶でうっすら火が通った位がベスト。鯛は刺身で食べるよりこの鯛茶漬けにした方がよっぽど美味いと思いますが、その中でもこの刺身の端っこで作る鯛茶漬けは一番じゃないでしょうか。自分でさばかないとまず食べられない贅沢な一品です。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.19
閲覧総数 46
-
10

今年の沢庵第一弾を仕込む
ミソジノジスイ本家畑の大根がいい感じになってきたので、今日は沢庵を仕込みました。いつもはダラダラと先延ばししている内に大根が無駄に大きくなってしまい、半分に割らないと漬けられなくなったりしていたのですが、今年は早めにバッチリ理想サイズ段階で漬けられました。私の沢庵漬けは地元のメーカーが作っている評判の良い沢庵漬けの素を買ってきて、そこに書いてある分量通りに作るので、コツとか全然ありません。敢えて言えば本当に分量通りに作るだけです。私が使っているのは40kgの大根を漬ける量が入った袋ですが、今回漬けたのは7.4kg。ですんでその割合で0.1g単位まで計測し、別途指定された量の食塩を混ぜ合わせたものを大根にすり込んで重石をかけます。また、使い残った素の量もしっかりメモに書いておけば次にいつ新しい素を買い足すかの目安になるので、無駄なくキッチリ資材を使い切れて良い感じになります。ちなみにこの商品は二度漬けタイプでして、今回やったのは一度目の漬け込み。1週間ほどで水が上がったら改めて2度目の漬け込みをやります。大根を漬けこむ場合、一度に大量にそれこそ40kgとか漬け込む場合には問題になりませんが、うちみたいに7.4kgとか少量漬け込む場合、それぞれの大根にかかる荷重が不均一になってそのままだと上手く水が出てこないため、毎日一旦全部取り出して場所替えをしつつ詰め直すという作業が必要になります。また、今時の大根は昔の様に食塩をガンガンに利かせた保存食ではなく、ちょっと塩辛いだけの生鮮野菜と考えた方が良く、沢庵だから常温保存大丈夫だろうとか考えると速攻で腐りますんで要冷蔵です。今時沢庵を自作している家も少ないでしょうが、全然難しくないので大根が一杯手に入る人は作ってみるのも良いんじゃないでしょうか。ツイッター始めました人気blogランキング(別窓):クリックしていただけると、励みになります。
2025.11.23
閲覧総数 30