-
1

サンダーマスク~「サンダーマスク発狂す」はシンナー遊び撲滅を目的とした作品だった・・・とは思えない・・。
70年代前半の第二期怪獣ブーム(変身ブーム)の作品のひとつ「サンダーマスク」は手塚治虫がコミカライズした(原作ではない)ということで非常に有名でありながら何故かDVD化されない作品です。さて今回の本題は「サンダーマスク発狂」です。なんて危険なタイトルなんでしょうか。しかしサンダーマスクが本当に発狂するわけでなく最初から最後までシンナーマンが一人でらりっているだけなんですけどね。場面は公園。昼日中、シンナーを吸って必要以上にトリップして騒いでいる若者たち。(あまりこんなことはないと思うけど・・)そんな彼らを美人婦警がパトカーでシンナー中毒を治すと称して連行するも婦警の正体は魔王デカンダで・・。「 シンナーに侵された狂った人間の脳味噌がお前には何より必要なのだ。吸うがよい、食べるがよい」シンナー中毒の若者たちは シンナー漬けの脳味噌をシンナーマンによってチュウチュウ吸われてしまうのでした・・。このときのシンナーマンが頭に刺すのがコントみたいな巨大なストローで全然怖くない・・・。いろいろと極めて不自然な展開を経てサンダーマスクはシンナーマンと脳味交換手術をされてしまいます。なんの意味があるのかはよくわかりません。婦警デカンダの「まあ、きれいこれがサンダー星人の脳味噌なのですね」というセリフもいかがなものかと思うのですが手術が3秒で終わるところがまたすごい。でこのあと町に出たシンナーマンの脳味噌の入った命光一はうーうーとうなりながらごみばこを蹴り道行く女につかみかかりラーメンの出前をひっくり返す・・わけですが・・・・。一方デカンダは光一の脳の入ったシンナーマンに襲われ「しまったあ」と間抜けさ全開です。いろいろあってシンナーマンと光一の脳は元通り(やはり3秒)。シンナーマンはこれまで食べたシンナー脳味噌の力で巨大化します(なんだかなあ)。支離滅裂にシンナーガスを吐き散らすシンナーマンの攻撃はシンナー中毒の怪獣がまともな攻撃できるわけないよなあなわけで巨大な脳がサンダーシュートでぱっくりわれるというイヤな結末に。飛び散った脳を執拗に焼くサンダーマスクの姿に「人類は自分で自分を滅ぼすようなシンンナーをあやまってついかってはならない。それは人類自らが魔王デカンダに味方することのいなるのだ・・・。」シンナーとデカンダの因果関係がよくわからないナレーションの流れる中フェイドアウトしてゆきます。サンダーマスクと怪獣の脳と替えるという意味不明の展開と手がかかるわりにただのシンナー中毒で役に立たないシンナーマンの姿が泣かせる困ったお話なのでした・・。でもかなり面白いですね・・いろんな意味で。
2006.04.25
閲覧総数 19458
-
2

井口昇監督作品「電人ザボーガー」を面白く観るために
井口昇監督作品「電人ザボーガー」は特別な知識なしにみても十分に面白い作品だと思う。しかしもっとこの作品を楽しむためには事前に幾つかの映像作品を見ておくともっと面白い。なのでここでは映画「電人ザボーガー」をもっと楽しむために観ておいた方がよいものを紹介してみたい。「電人ザボーガー」(TV版)#1「たたかえ! 電人ザボーガー」#2「これが秘密殺人強盗機関シグマだ」#3「大暴れ! 水爆ゴリコング」#4「シグマ殺人基地 殴りこめ」まず設定編であり個性的な幹部が登場する第1~4話は面白く欠かせないだろう。悪之宮博士の悪をなす理由、人間不信の念も悪之宮とが自ら大門博士とのやりとりで口にしており興味深いところだ。4話では悪に染まるザボーガーの姿もみられる。#10「シグマ団・恐怖の地獄作戦」#11「ジャンボメカ 東京破壊作戦!」1クール目の大きなヤマ場であるΩ地獄計画のクライマックス。映画のクライマックスと重なるので比較する意味でも見逃せない。#14「不死身の殺し屋ギルコンフー」#15「死斗!! 謎のシグマ大魔城」映画版にも登場するシグマ大魔城建設編のクライマックス。実は全編で一番面白いのがこの大門豊が兄弟であるザボーガーを救うためにめちゃくちゃな強さと頑張りをみせるこの前後編なのだ。必見。#17「殺人キック! メカボーグチーム」映画版で大暴れする3人組の女サイボーグミス・ラガーズに相当するアメフトサイボーグであるラガーズ1、2、3が登場するエピソード。一般人のラガーメンを改造したラガーズ3の最期がとても重いのはピープロティスト。#19「キリマンジャロの赤い豹」映画版ではの幹部の一人となるバーナー8が登場。脚本の上原正三がウルトラセブンの「700キロを突っ走れ」をセルフリメイクしている点で興味深いところ。#26「強奪! 狂犬ロボット・ブル・ガンダー」#27「激突! ザボーガー対ブル・ガンダー」異形のシグマメカ、ブル・ガンダーの登場編。車型のメカ、ガンダー三体はザボーガーの攻撃を受け付けない強敵として描かれており最強というべきデス・ガンダー編(#23-24)の方が実は面白い。なお、このエピソードは一峰大二がコミカライズしており映像作品よりも漫画の方が人物設定に優れているので興味のある方は是非一読を。映画でも印象的なおでん屋に扮したミスボーグもここでみられる。#31「空飛ぶ鉄拳!! アイ・ロボッター」#35「爆弾フラワーを巨大化せよ!!」ミス・ボーグの最期を描く二部作。31話で悪之宮に爆弾を飲まされたミス・ボーグの死の恐怖と最後の戦いが描かれている。影を強調した死の演出が藤山律子の悲痛な表情とあいまって圧巻。(監督は山田健)死の演出については#8の海賊ジャックの最期も捨てがたい。#30「飛竜三段蹴り対サンダーパンチ」#34「ゴールド・ジャッカー! 首を捜せ!」#36「空飛ぶ巨砲 ドルカノン」#38「決戦!! ザボーガー対悪之宮博士!!」大門のライバルである秋月の物語。#30で大門に敗れシグマから離れた秋月は#34で復活。少女冬子の命を引き換えに再びシグマに従うハメになる#36では秋月の不器用な恋描かれ#38で大門との戦いの日々と決別が描かれる。なお映画版のAKIKOにあたるレディボーグも37話から登場。#38の強敵ブラックヒッターの戦いぶりにも注目。#39「大滅亡! 悪之宮博士の死」シグマ団編の完結編。悪之宮博士の隠し武器にも注目。#52「ストロングザボーガーよいつまでも」ザボーガー感動の最終回。エネルギーのダイモニウム枯渇で活動不能になったザボーガーと大門豊が恐竜軍団に最後の戦いを挑む。「片腕マシンガール」「電人ザボーガー」は井口昇監督の作品やキャストを知っているとさらに面白い。「片腕マシンガール」はアメリカ向けの低予算アクション・ホラーとして製作されたがザボーガーでも同じ布陣となった特殊効果の西村喜廣、VFXの鹿角剛司の協力もあり徹底した血が噴水のように噴き出すスプラッタと抒情・情念、笑いが同居する稀有な作品になっている。本作で息子を理不尽に殺されたヤンママを演じた亜紗美(前作「おいら女蛮」のヒロイン・・・この映画でのあるシーンでの亜紗美の表情はザボーガー劇中のあるシーンでの演技に近い)は井口組のクイーンというべき存在で「電人ザボーガー」ではミス・ラガースのリーダーを演じている。そのほかザボーガーの中で中野を演じたデモ田中(印象的なヤクザのひとり)、松江を演じた岸健太朗(スーパー遺族の一人)、大臣を演じた島津健太郎(凶悪なニンジャニシテヤクザ・キムラ)、眼帯男爵の石川ゆうや(マシンガンの腕の製作者)らは繰り返し井口作品に登場する常連役者たちだ。「ロボゲイシャ」同じく井口監督による「片腕マシンガール」に続く堂々たる娯楽作品。本作に登場する影野製鉄ロボは城のかたちをした巨大ロボでシルエットはシグマ大魔城を思わせる。ヒロインヨシエが変形するゲイシャタンクの疾走はストロングザボーガーに相通じる。また竹中直人が演じる車椅子の老人とその装備は悪之宮博士のものである。「戦闘少女 血の鉄仮面伝説 」井口・西村・坂口祐の三人が監督した文字通り形のアイドル映画。「スケバン刑事2少女鉄仮面伝説」のパロディーはもちろんこれでもかという位のヒルコと呼ばれる異形の乱舞と血しぶきアクションが爆笑の中で展開する。本作で島津健太郎が演じた対ヒルコ兵器雷電はミスボーグに似た二本の角を持つサイボーグである。またザボーガーでの竹中直人の怪演と悪のりは本作を見ていれば納得。この他西村喜廣監督の「東京残酷警察」「吸血少女対少女フランケン」「ヘルドライバー」などもみておくとさらにキャスト面の面白さや特殊効果の面白さがさらに増すのではないか。「ウルトラゾーン」内の「ウルトラゾーンチャンネル」や「古代少女ドグちゃん」および「古代少女隊ドグーンV」にもキャスト・スタッフが共通する。「電人ザボーガー」をみてからでもいいのでさらなる井口・西村作品にふれてみては如何だろう?
2012.03.20
閲覧総数 560
-
3

ウルトラマンエース第23話「逆転!ゾフィー只今参上」
「お前は神を信じなさい、ほれ信じなさい、ほれ信じなさい」「お前は俺を信じなさい、ほれ信じなさい、ほれ信じなさい」謎の老人が世界中の子どもたちを異次元に誘う。それを目撃した北斗は絶叫する!!ヤプールの使者?謎の老人の目的街で末世を説き海辺を走る謎の老人。世界の各地で同じ老人が同じように現れる。子供たちが次々と姿を消した・・・。暗い浜辺で老人が叫び、子供たちが応える。「海は青いか?・・違う海はまっ黄色だ!」「山は緑か?・・・山はまっ茶色だ!」「花は死んでいる・・花はとっくに・・・」夏というのに荒れる海には吹雪が・・・。星が異常に増えた・・・子供たちは星になったのか・・・人類の未来は??今回の脚本と監督は真船禎。大胆かつ前衛的な演出と映像がウルトラシリーズ中でも特殊な今回のエピソードをさらに異色なものにしている・・・。尻からのローアングルとかラストの北斗や南のアップに赤い破片が重なる描写まで凄いものを観た・・という印象の映像の面白さに満ちた異色の作品です。老人が歌い踊る印象的な歌は実はハナ肇とクレイジーキャッツの「学生節」の替え歌です。ヤプール老人を演じたのは岡本喜八作品など多くの映画で知られる大木正司。アニメでは「聖戦士ダンバイン」のドレイク・ルフトも印象的でした・・・。信じてもらえない北斗、その総決算「夢をみてたんじゃないでしょうか」「このナンセンスな話を信じろっていうのか」「話が科学的でないな」毎回、毎回信じてもらえない北斗、今その積もり積もった鬱積が遂に爆発。「俺だって信じられない!俺はこの目で見たんだ!・・誰も俺のことを信じていない!・・・冷たい。寒い!・・隊長・・隊長まで信じてくれないんですか!!」「もうやめて、やめて!!!!」夕子の絶叫で我に返る北斗。その気持ちは・・・痛いほどわかる・・・。夕子と人魂の話夕子は北斗を休暇させるために車を急がせる。同情は真っ平だという北斗に夕子はこどもの頃おしっこに行って人魂をみたという話をする・・・。・・・・それって月での話?ちょっと気になります北斗、異次元へTACに人類の未来は託された・・・ってTACは重い責任しょい過ぎ。しかもカジの異次元へ人を転送する新発明・・・ヘッドギアが怪しすぎです・・・こんなのに人類の運命を託されても・・。で北斗が異次元に子供たちを救うために行くことになるのですが・・・。カジがいうにはこの機械・・・「場合によっては・・・死にます」って・・・。死んじゃだめだろう!!だいたいこの作戦異次元に北斗ひとりを行かせて何をさせようというのか今いちよくわからないんですが・・・。ゾフィー参上異次元に夕子を誘うためゾフィー参上・・・ってそんなことなら最初から・・・。ゾフィーの声は今回山下啓介氏でした。出番は一瞬。これでタイトルがアレなのは・・。メインのヤプールが不憫・・。巨大ヤプールと散るヤプール、空から降る子供異次元でのヤプールとの戦い、曲がり歪む世界での戦いは熾烈を極めるも・・・メタリウム光線でヤプールは爆発四散・・。と同時に謎の老人も斃れる・・・。空から子供たちが降り注ぎ・・・という映像はシュール。ゆっくり、なんだけど何かあぶねー。ヤプールという敵の異常さがシリーズ中最も強く出た話も映像も異色の一本・・・でした。放送の翌日からしばらくあの歌と踊りは小学校で流行っておりました・・・。では最後にも一度。「お前を俺を信じなさい、ほれ信じなさい、ほれ信じなさい」ヤプールは死んだが危機は今まさに迫っているのだ・・・というわけで次回に続く。
2006.10.19
閲覧総数 782
-
4

ウルトラマンエース第21話「天女の幻を見た!」は大美人萌え!
竜隊長は天女の夢を見て目覚める。とその夢に出てきた天女そっくりの女が お手伝いに雇って下さいとやってくる。強引に食い下がる女を身元のわからない人は・・と理路整然と断る隊長。「私は来てはいけないところにきてしまったんですね・・」・・・最初の天女のシーンがなければストーカーサスペンスか何かと間違いそうな展開・・。竜隊長の知られざる生活幸か不幸かひとりもの、極秘の場所にすんでいる竜隊長・・ミステリアス。玄関口で女性を出迎える姿も何気にガウン姿でしたね。設定も実年齢も年齢35歳。渋い、渋すぎる・・。基地で夢の話すると皆ニヤニヤして夕子が「お手伝いさんじゃなくて奥さんじゃないのかしら」とからかい隊長が戒めると「はーい」とはといの間を伸ばす返事・・。珍しく和気藹々としてるなあ。天女アプラザの秘密でその問題の女性は屋敷でひとり暮らしの青年のところに転がり込む。青年は女性の話を聞いて憤慨、TACと隊長に憎しみを抱く(いき過ぎだよなあ)。激しい憎悪と怒声でTACの面々を追い返すシンイチ青年。シンイチ青年は天女の真の姿になった女性=アプラサを見て怪しむどころか結婚を申し込もうとする・・。・・・・ひょっとしてコスプレ好き??天女の美しさがそうさせるのか・・といったところで・・天女を演じているのは三景順子さん。天女といわれたら納得しそうな優しげな日本的美人の女優さんなのですが・・・。※「白獅子仮面」(大岡って・・大岡越前の妹?)のヒロインや若山富三郎の映画「極道VSまむし」、「子連れ狼・地獄へいくぞ大五郎」に出ている瞳順子さんが改名・・したんでしょうか?「極道VSまむし」は菅原文太の「まむしの兄弟」シリーズと若山富三郎の「極道」シリーズが合体した珍品で二人に惚れられるヒロイン。「子連れ狼」では柳生烈堂の娘でお手玉剣の使い手として登場してます・・。どうなんでしょうね・・。天女アプラサはおとめ座の爆発の際、ヤプールに助けられ恩返しを迫られていた・・。わからないのは竜隊長のところへ行った理由。ヤプールが行かせたのだろうがお手伝いにさせて何をしようとしたのか今ひとつわからない竜隊長の居所がわかっているならもっと直接的手段がありそうなんだけど・・独身の隊長をシンイチのように篭絡しょうとしたのか?つまりアプラザは無意識にその美しさで男をおかしくしてしまう力があったとか・・うーん・・・。超獣アプラサールはどうでもいいんだけども・・アプラサが超獣化。羽衣を使った攻撃が強大、隊長機を身体に取り込むなど実体があってないような幻のような超獣。真っ暗闇の戦闘は幻想的だがヤプールのエネルギーを遮断されるもとの姿にもどってしまう・・・って大きさはそのままかい。実は今回最大の見所はここからだったり。「どうしてそんなに大きくなっちゃったんだ!」シンイチ青年の嘆きの声はともかく大きな女の人好きには堪らないビジュアル・・。58mの巨大な天女。さらにこの巨大な女の人がエースについて宇宙を飛ぶ姿(しかも手が前に出てる)は凄いものを観た・・・という他ないです・・。エースはアプラサを白鳥座に連れて行こうとする。その理由がナレーションによると「乙女は白鳥に乗ってこそもっとも美しいからだ」そうですが・・・わからん。・・・・おとめ座が爆発・・・。重要なことを忘れてた・・。じゃあコメットさんの故郷は???※コメットさんは乙女座の出身。↓下記参照。コメットさんとウルトラマンレオおとめ座への誘いどうでもいいもうひとつの見所青年の家を見張る私服のTACの面々なんですが・・山中隊員・・趣味悪・・。
2006.10.17
閲覧総数 1168
-
5

「時をかける少女」のタイムパラドックス
AMAZONの売れ筋DVDランキングをみると「時をかける少女」が1位になっている。 TV放送されたら話題になるだろうとは思っていたのですがTVで観て良かったのでDVD購入、という感じなんでしょうか? まあ何にせよファンからすると喜ばしいことであります。 「時をかける少女」は非常に優れたコメディであり切ない情感のあふれる青春映画であるのに疑問の余地はないのだが実は時間ものとしては非常に大きな欠陥がある。 以下はストーリーを割ることになるのでアニメ「時をかける少女」を未見の方はこのような駄文はほっておいてすぐにDVDをレンタル、または購入して映画本編を観ていただきたい。充実した素晴らしい時間を過ごすことができるはずだ・・・ それでは本作のタイムパラドックスに関わる疑問点を上げてみたい。 まずひとつめ。 真琴がタイムリープの残りを0回だと思いこんでいた点について。 真琴、最初に踏切につく。何事も起こらず・・A ↓ 坂道を登る真琴。千昭の言葉に動揺、「(真琴の)最後のタイムリープ能力」を使う ↓ 功介の事故。目の当たりにして真琴、踏切の前で傷だらけで泣き叫ぶ。・・・B ↓ そこに千昭がやってきて事情を察して「(千昭の)最後のタイムリープ能力」を使う。 ↓ 真琴が踏切に最初についたシーンに戻る。・・・A’ 千昭はあらかじめ功介が自転車に乗らないように過去を変えて真琴の前に現れる。 真琴はこの時点では最後のタイムリープ能力をつかっていない ※ここで重要なことは千昭のタイムリープによってAという時間はなくなってA’というのが現在になっいるということだ。 この次点での真琴はまだ「最後の1回」をつかっておらずまた功介の事故(B)を今後経験することもない。 つまりここでの真琴は功介の事故が発生した事は無論、タイムリープが0回になったという経験もしていないのである。 千昭は時間旅行者の規則に従い姿を消す。 真琴は傷心の時を過ごすがふとしたことでまだ1回タイムリープ能力がのこっていることに気気づく。 真琴は「そうか・・あの時千昭が時間を戻したから・・」というがこの真琴は上記の通り「能力が0回になったこと」を経験していないのでこの台詞は本来意味をなさないのである。 千昭はA’の時点で功介が未来Bで事故にあったのを真琴に説明しているので動転していた真琴がタイムリープ能力をつかってしまったと勘違いしたと解釈することもできるが・・かなり苦しい。 上記の矛盾点は1回目に映画をみているときにはやや気付きにくいだろう。 この真琴の台詞は観客への説明のため、驚きと感動を共有するためにあえて矛盾を承知で付け加えられたと思しい。 ふたつめ。ラストにおいて功介と果穂が付き合っいてないように過去が改変されている点。 この改変の可能性としては ・千昭が功介に自転車にのせないために行った最後のタイムリープ ・真琴の最後のタイムリープ どちらかによるものなのだが真琴が踏切に功介たちより早くついている上記Aのシーンは「功介と果穂が真琴の壊れた自転車に乗って坂の下の踏切に向かっている」という前提がなければ存在しないシーンであるのでこの時点では千昭による改変ではない。 また真琴が最後のタイムリープでたどりつく土曜日の実験室のシーンは真琴が功介と果穂をくつつけたあとのシーンなのでこの2回のタイムリープでは功介と果穂がまだつきあうようになっていない過去に戻ることは不可能なのだ。 と長く、わかりにくい説明を書いたのだけれど・・如何であろうか。 私自身もよくわからないところがあるのでお分かりの方は説明していただけると嬉しい。 そんな弱点があれど「時をかける少女」が優れた青春映画であるのは疑いのないところだろう。 ラスト夕焼けの土手のシーンの美しさ、切なさはアニメ映画の歴史に残るものだと思う。
2007.07.22
閲覧総数 961
-
6

内山まもる「ウルトラマンレオ」のもうひとつの最終回!極悪の改造宇宙人登場編
第二期ウルトラシリーズは小学館の学習雑誌で記事および漫画の掲載が行われました。内山まもるによるコミカライズ「ウルトラマンレオ」をご存知でしょうか?当時内山まもる氏は小学館の学習誌「小学二年生」と「小学三年生」にレオのコミカライズをされておられます。セブンがミサイルを背中にくくりつけて円盤生物に特攻するという場面が印象的ですが、最終回ではブラック司令とババルウ星人が結託するも、レオ兄弟とウルトラ兄弟に倒されレオの両親も無事助かるというこれ以上ない大団円だったりします。これは小学二年生版。これは「ザ・ウルトラマン」に収録されているので存知の方も多いでしょう。今回取り上げるのは昭和50年の小学三年生2~3月号に掲載された作品の方です。宇宙をパトロールするウルトラ兄弟が次々に謎の宇宙人に倒されてゆきます。エースが新マンが、ウルトラマンが殺され残ったゾフィーとレオ、アストラ、タロウは謎の敵に復讐を誓います。次の回でゾフィーは一計を案じます。ペンキで自分の身体に線をペィンティングして新マンになりすまし敵を罠にかけるというものでした。(えーっ!!!)兄弟を殺されるというシリアスなストーリー展開なのに何故?なわけですがこの作戦は見事に成功します(うーん)。敵は最も憎む新マンが生きていることで冷静さを欠いたのでしょう。その正体は自らをサイボーグ化したナックル星人なのでした・・。このセレクトは第二期ウルトラのファンにとってはポイントが高いですね。レオ、ゾフィー、アストラ、タロウらは謎の敵を包囲しますが改造ナックル星人が一枚上でした。改造ナックル星人は加速装置付サイボーグに自らを改造していたのです・・(君は島村ジョーか)。あっという間に全滅の危機の中ゾフィーが決死でしがみつきます。「レオ、私ごとこいつを撃て!」と。躊躇するレオですがナックル星人の攻撃をうけゾフィーは次第に傷つき弱ってゆきます・・。意を決してゾフィーごと改造ナックル星人を泣きながら撃つレオ・・・。爆発・・・。なんという落差。方やレオの両親まで無事に再会を果たす二年生版に対し意三年生版はレオだけが仲間をすべて失い一人生き残る、しかもこれで第二期ウルトラシリーズ、最後だったりするんですよね、この時点で。私の中の第二期ウルトラシリーズの終わりはテレビの最終回よりもこの悲劇的結末の作品の印象が強かったりするのです・・。※間違っていた部分を内山まもるのコミカライズについての同人誌「ザ・ウチヤママモル」を見て修正しました。この本は凄いですね。内山版ウルトラマンをほぼ全てフォローして解説を加えてあります。感動です。
2006.05.10
閲覧総数 1818
-
7

デルザー軍団13人目の魔人・ジェットコンドルの謎
デルザー軍団は「仮面ライダーストロンガー」の敵の組織・・なんてことを今さらいってもしょうがないかもしれませんが念のため。デルザー軍団は13人の改造魔人(あるいは半機械人)からなるヒエラルヒーの存在しない組織でした。ストロンガーを倒した者が組織の頂点に立つという横並びの実力者集団だったのです。しかしヘビ女はシャドウの愛人(?)だったり後半ではマシーン大元帥が指揮権を握ったり最終的には岩石大首領という今までの悪の組織全てを操っていたボスが登場するのでそれも完遂されたわけではありませんが・・・。でここで問題になるのがデルザー軍団は13人いないということです。ジェネラルシャドウ鋼鉄参謀荒ワシ師団長ドクターケイトドクロ少佐オオカミ長官隊長ブランク岩石男爵ヘビ女磁石団長ヨロイ騎士マシーン大元帥以上12人。バンダイのHGでこの間コンプリートになりましたが12人ですね。13人目はしばしば岩石大首領だとかベルトがデルザーな特番に出演した暗黒大将軍ではないかといわれるのですが定かではありません。さらに「デルサー復活」の際の新怪人カニ奇戒人もデルザー・・13人目はカニ??ここでひとつの未確認情報があります。デルザー軍団のジェットコンドルはアメリカから来る途中事故で死んだ・・・。このジェットコンドルとは何者なのでしょうか。「別冊テレビマガジン」掲載の成井紀郎版のコミック「7人ライダー最後の大決戦!」(角川書店刊「決死戦七人ライダー」に収録)には岩に激突して死ぬ鳥類系のデルザー怪人の姿をみることが出来ますが・・・。いつ頃からこの情報が流れたのかはさだかではありませんが実際双葉社から出ている「仮面ライダー激闘ファイル」にはこのジェットコンドルと貝のようなデルザー怪人のデザイン画が掲載されています。この立体物はデザイン画を元に怪人のスーツ風に知人に作っていただいたものです。一応HGサイズなのでシャドウとマシーン大元帥と並んでいただきました。 どなたかジェットコンドルの事についてご存知の方ご教示お願いします・・・。あとデルザー軍団といえば「仮面ライダーSPIRITS」には全く出てきていませんが・・村枝氏がその辺考えていないわけがないので・・・実はかなり期待しています・・。
2006.08.09
閲覧総数 11771
-
8

サンダーマスクのコミカライズ 1 「残酷!サンダーマスク処刑」の過激さ
「サンダーマスク」のコミカライズは小学館の学年誌、少年サンデー及びてれびくんの前身である小学館BOOK、秋田書店の冒険王で描かれています。それぞれの掲載状況をまとめてみると以下のようになります。週刊少年サンデー 手塚治虫 72年43(10月8日)号~73年2(1月7日)号 別冊少年サンデー やまと虹一 73年1月号~73年3月号 小学館BOOK 池原成利 72年11月号~73年3月号 よいこ 森藤嘉宏 73年2月号のみ 幼稚園 池原成利 72年11月号のみ 小学一年生 原成 72年11月号~73年3月号 小学二年生 長谷川猛 72年11月号~73年3月号 小学二年生 西井とおる 73年4月号 小学三年生 池原成利 72年11月号~73年3月号 小学四年生 原成 72年11月号~73年3月号 冒険王 長谷川猛 72年10月号~73年4月号 別冊冒険王 長谷川猛 72年秋~73年5月号 このうち手塚治虫のコミカライズはサンダーマスクとデカンダー、登場人物は共通するもののTVとは無関係なオリジナル作品。こちらは今でも秋田文庫や秋田サンデーコミックスで読めますね。手塚本人が全集の後書きであまりよく書いていないため評判があまりよくない作品ですが同じ時間を生きられなくなった恋人たちの悲しい物語でありTVとは全く別の感興をそそる作品です。サンダーマスクに興味のある方であれはその違いを楽しむ意味でも一読をお薦めします。また『プラモ狂四郎』で知られるやまと虹一の別冊サンデー版は僅か3回ながら独自のヒーローものになっていて漫画としても面白い作品です。デカンダが魔獣でなく雪女や大仏を使役するのが興味深く最終話は何とニセサンダーマスク編。当時ダイナミックプロをやめたばかりだったため永井豪的な可愛らしい美少女、血へどを吐くバイオレンス描写が楽しめる異色のサンダーマスクです。その他の作品は正統なTV作品に準じたコミカライズ。それぞれの作品については色々特徴があるので1度には書ききれないので今回は1話を除くと最もコミカライズされているエピソードである第12話『残酷!サンダーマスク死刑』、第13話『はるかなる銀河の果て』の物語とそれを元に描かれた漫画を紹介してみましょう。 まずTVのおおまかなストーリーを追ってみよう。12話はまずデカンダから流星鉄仮面の幹部交代劇が描かれる。流星鉄仮面はサンダーマスク=命光一の妹リンに化けて周囲の人間を欺く。光一は子供の頃から会っていない(1万年前はリンは子供だったんでしょうね)リンを本物かどうか判断しかね疑いの目を向ける。流星鉄仮面はサンダー星人を発狂させる鈴と魔獣メガトロンを使いサンダーマスクを殺して十字架に磔にしてしまう・・。13話。考古学研究所の面々は正体を現したニセのリンに人類を滅ぼす兵器の開発を命じられる。まゆみの弟・勝也は研究所を抜け出し流星鉄仮面に対抗できるサンダースパークガンV-7 の部品を探していた。一方サンダーマスクは本物のリンに助けられ奇跡の復活を果たす。オリジナルの脚本を担当したのは第1話や最終回など全10話を担当したメインライターの上原正三。主人公が殺されてしまう中盤の山場、ターニングポイントでどことなく『セブン暗殺計画』前後編を思わせる娯楽性に富んだエピソードです 『幼稚園』73年2月号、森藤よしひろ。 大コマの4ページ!メガトロン(なぜかメトロンガと表記)をサンダーイナズマ斬りで倒すそれだけの展開。流星鉄仮面は未登場。 『小学一年生』同2月号、原成(池原成利)。 流星鉄仮面とメガトロンがドライブする光一たちを待ち伏せるもあっさりと倒されてしまうという逆にびっくりな展開。 この原成名義も含めて5誌で『サンダーマスク』を描いた池原成利は手塚治虫のアシスタントで『魔女っ子メグちゃん』が代表作。 当時、特撮やアニメのコミカライズを多く描いています。80年代にも『聖戦士ダンバイン』や『重戦機エルガイム』『機動戦士ガンダム0080』などのサンライズ作品、ゲームの『ロックマン』シリーズも手掛けています。 『小学三年生』73年1月号~2月号、池原成利 デカンダの処刑からニセモノ・リンの登場、弱点の鈴、サンダーマスク処刑(槍で後ろから)と前半は比較的忠実。後半はやや駆け足で必殺の武器サンダースパークガンV7を探す件が省略、メガトロンはTVではサンダーマスク復活のために登場する本物のリンが操る円盤によってなんと倒されてしまう!池原版のリンはいずれもベレー帽を被った手塚調の美少女。 『小学四年生』同1月号、原成(池原成利)。 見開きの漫画による情報ページ。ベレー帽のリンにデカンダの首をはねる流星鉄仮面、鈴の音に苦しむサンダーマスクの姿がダイナミックに描かれています。 『小学館BOOK』同1月号、池原成利 同じくベレー帽のリンが登場するも光一に「誰だ!」と言われる始末ですぐ正体を現す流星鉄仮面。鈴の音で幻惑するも逆転され実にあっさりと倒されてしまう。 コミック版の流星鉄仮面はリンに変身していた、という展開のためか女口調で喋りオホホホと笑うのが定番になってます。 ここであげませんでしたが『小学二年生』では流星鉄仮面は未登場。該当の1-2月号ではドロドロン、デーゴンH が登場しています。 その小学二年生版を描いたのは長谷川猛氏。小学館の学年誌及小学館BOOKで流星鉄仮面未登場なのは唯一小二長谷川版だけ。 しかし同じく長谷川氏が手掛けた冒険王版は他誌にはみられない過激な展開が見られます。それが身体を貫かれ首を斬りおとされるサンダーマスク、の描写です。『冒険王』73年1月~2月号、長谷川猛 当時のコミカライズで圧倒的な分量を誇るのが長谷川『冒険王』版です。1回の連載量が10ページに満たない小学館学習誌の各作品に比べるとTVの内容を不足なくとりこんでいるといえるでしょう。 それどころか過剰な描写が多く73年1月号ではメガトロンのツノがサンダーマスクの胸を貫通、さらには流星鉄仮面が魔剣流れ星でデカンダと同じようにサンダーマスクの首を斬りおとしてしまう、というこの上ない残酷な展開になっています。 なお、この1-2月号(2月号は別冊のTVコミック)の前後編は合わせて100ページ近くの分量なのですがザリバザーンの登場する第11話、及び デーゴンHが登場する第15話が前後を挟んだ内容です。 余談ですが流星鉄仮面の登場するもうひとつのエピソードである第14話『魔獣を呼ぶけむり』(ガエンボー登場)も『冒険王』冬の増刊号で漫画化されているので流星鉄仮面が登場する都合4話分のエピソードは全てコミカライズされていることになりますね。冒険王版の2月号で流星鉄仮面は倒されてしまいます。本来TV最終話で流星鉄仮面は命光一の発明したミサイルを愚かにも自信たっぷりに正面から受けて死んでしまうのですがこの展開ならば漫画版での最後の方がまだ納得がいくような気がします。というわけでその他のエピソードも機会をみて紹介していきますので乞うご期待。
2011.01.12
閲覧総数 6172
-
9

桜多版「ゲッターロボG」衝撃のラストシーン・ハヤトは鬼になったのか?
承前こちらを読む前に異才桜多版ゲッターロボGの衝撃を先にお読み下さい。前回のラストでハヤトは百鬼要塞をダイナマイトで吹き飛ばし、空に顔が浮かんでしまうというどう考えても生きていなさそうな引きだったが・・。大量のメカ百鬼の前に最早なす術もないリョウたち。そこに死んだはずのハヤトが現れる。 3人揃って出撃するゲッター。しかしハヤトはフォーダムGを破壊しゲッター線増幅装置を奪うのだった。 まさか、ハヤトが百鬼に?このあたり当時の最終回前のテレビランドの記事で「ハヤトが鬼に改造される」というのがあり嫌な展開を予想されるのだが ハヤトは鬼ではなかった。桜多版では絶対の危機にはこれしかないわけでゲッターはゲッター線増幅装置で溶けながら百鬼要塞へ特攻する(このあたり本家石川版のムサシの最期を彷彿とさせる展開) 浅間山からでも見える巨大な閃光「ゲッター線増幅装置の大爆発で関東一円が消滅したようです」 「リョウ君は!ハヤト君は!」うつむく博士に呆然とするミチル。 「リョウくん、ハヤトさーん」ミチルは叫んでへたり込む。早乙女博士がミチルへ語りかける「あいつらは死んじゃいないよ。これからもわしらの心の中でいつまでも生き続けるんだよ。その勇気でわしら多くのものを百鬼帝国から救った勇者として・・」というわけなのだがあえていわずもがなのことを言っておくとミチルはリョウとハヤトばかり気遣ってベンケイのベの字も口にしていない。やはり↓のせいなんだろうか・・・。「私に関心を示さない」ばかりでなく「香水くせえ。ませてんなあ」と迄言われてるし・・この後も再三再四に渡り女のプライド踏みにじられてる恨み? 教訓。やっぱり女の子は褒めないと駄目だよ・・・。あと「都民の避難は終わりました」とあるのだが関東一円が消滅して大丈夫だったのか・・・怖い考えになってしまった・・。
2006.05.21
閲覧総数 7913
-
10

「ドカベン世代」の通算成績にみるカナシミ
「ドカベンスーパースターズ編」も13年目のシーズンを迎えた。 単行本でいえばドカベン全48巻、大甲子園全26巻、プロ野球編全52巻にスーパースターズ編が既刊17巻・・・。 山田の高校時代とプロ野球時代では実は既にプロ野球の方が長い(ドカベンの10巻位までは中学生なので)というのは改めて驚きではないだろうか。 昨年のシーズンオフからドカベン世界ではにわかに結婚ブームと記録達成ラッシュになっている。 殿馬はマドンナと入籍、里中は山田の妹サチ子にプロポーズ、岩鬼は夏子はんと復縁、山田も新しい出会いが・・・とかはまあどうでもいい事なのだがこの山田世代の12年目を終えての通算成績にはちょっと・・まあいいや、ですませられない問題がある・・というかなんというか・・全くもう・・・。 以下12年目までの通算成績を列挙する 山田 1999本安打、500本塁打 岩鬼 450本塁打 殿馬 2200本安打 微笑 325本塁打 不知火 200勝 土門 180勝 里中 149勝 とても12年目の成績には思えないトンデモナイ成績である。 殿馬の2200本安打は・・同じく95-06年のイチローの安打数2382本(メジャーは年間20試合も多いことを考慮すればイチローと比べても殿馬の数字には遜色がない)、パの年度別最多安打者のトータルが2162本ということから考えてありえない数字・・・殿馬はこの数字を残しながら首位打者獲得は1回だけなのだ。 この辺り水島新司らしい記録へのこだわりのなさ鷹揚さが伺える。 山田と岩鬼の本塁打数には王の12年目までの本塁打数が447本また清原の12年目までの成績が1468安打の361本塁打だったことを書いておく。 不知火の12年目の200勝だが・・・これはこの12年間のパ年度別最多勝利の総計194勝を越え最後の300勝投手鈴木の217勝に肉薄する数字である。 打高投低の時代においてこれがどの位凄いのかは野茂英雄の12年目までの通算勝利数が139勝であることからも推し量れると思う。 長々と書いてきたのはこれらの破天荒な数字を見ていると悲しい気持ちになるためだ。 これら山田世代の度を越えたバケモノのような成績に反してドカベンで紡がれる物語のなんとつまらないことか。 私が読みたかったのは野球を描く中で描かれる人生のドラマだったはずでありそれは小さな身体故プロの壁に苦悶する里中であって12年目で楽々と150勝する里中ではなかったのである。 近年の水島作品に共通するツマラナさはそういう行き過ぎた超人志向にある・・・というのは今更いっても始まらないのかもしれないが昔からのファンからすると悲しいことである・・。
2007.04.07
閲覧総数 36683
-
11

ウルトラマンエース第10話「決戦! エース対郷秀樹」
「帰ってきたウルトラマン」から次郎君、ルミ子さんそして郷秀樹が登場するお楽しみ編なのですが・・。超獣ザイゴンが現われ次郎とルミ子はピンチに。たすけに入った北斗ですが・・そこに現われた郷秀樹、ですが顔を負傷してしまう。なんか照準を邪魔された北斗は不満そう。美川隊員の「MATのファイルでみたことがあります。ゼットンとの戦いで戦死したと聞いていますが・・」という台詞からもこの2作品が時間的にも離れていない続編であることがわかります。他の昭和シリーズにはこのような前作と繋がる描写はなかった気がします・・。郷をTACに入隊させるかどうかでまた口論。「いいわけはよせ」ああ、北斗も他の隊員も・・。いつものことですけどみんな冷静になりましょうよ。「過半数の賛成は時には危険な結果を招くことがある・・」竜隊長だけは慎重です。・・というか北斗は新マン=郷のことを把握してないのか。教えてやれよエース。郷の正体はヤプールの使者(使者って何だろ)アンチラ星人なのですが、わざわざ左利きで疑われたり(逆ならありだけど)とかボロ出しまくる星人。大体、郷に変身する必要も何もない杜撰な作戦(ですらないなあ・・何をしたかったのやら)・・。いかにも偽者な目張り入り郷になりさらに正体を見せあっけなく最期をむかえるアンチラ星人。無理やり自分の武器で撃たせて・・みたいに見える最期でしたね。ザイゴンも「カルメン」のテーマにのって闘牛・・。サイだろ、サイ(ザイなのか?)。ああなんだか腹立ってきましたよ。ザイゴンを首ちょんぱで倒し北斗と南は次郎君、ルミ子さんとブランコに乗り「遠い遠い旅をしている(そうなのか??)」郷におもいをはせながらウルトラ5つの誓いを唱和するのでした・・。せっかく郷たちをゲストに迎えながらこの脚本(田口成光氏です)はないでしょう・・。別に本物の新マンが出ても全然かまわないだろうに・・。というかそっちの方が感動的な話になりそうなのになあ・・。非常に勿体無い話でした。うーん。
2006.07.09
閲覧総数 297
-
12

ドロロンえん魔くん 完全愛蔵版
「Dororonえん魔くん メ~ラめら」のアニメ化に際し角川から発売された「ドロロンえん魔くん(完全愛蔵版)」。 全1巻で558ページの極厚B6判サイズ、1400円。 若木書房コミックメイトから何回も単行本化されたえん魔くんだが帯にある通り「永井豪渾身の完全版・激大幅加筆修正」が今回の売りだ。 どこが激大幅加筆修正されたのか個人的に興味があるので以下に検証してみよう。 今回比較に使うのは若木書房コミックメイト版のカバー変更版(以下若木版)。タイトル前には今回の単行本の収録順に番号を付した。 他の版が手元にないので完全な比較にはなっていない。MF版が扉絵も多く再現してあるらしいので本来そちらで比較すべきなのかもしれない。 また見落としもあると思うのでお気づきの方はご教示、ご指摘いただければ嬉しいです。 表紙カバー 若木版3巻のP204に掲載の絵。おそらく表紙画のひとつと思われるが詳細不明。3P 「1.えん魔くん出陣の巻」。扉絵は若木版と同じ。10P 閻魔大王が叫ぶ顔のアップに続くコマ、 足のついた食台の画が集合する妖怪のアップ2コマに変更。 合わせて「南こうせつ風に叫ぶ」のキャプションがなくなる。12P 妖怪6匹が大王の前に控える1ページ大ゴマ描きおろし37P 地上に向かうえん魔、雪子姫、カパエルの1P大コマ、えん魔、雪子姫の顔を修正。38P 閻魔大王がえん魔を見送る2コマ、1Pを追加。未収録か描き下ろしか迷うところ。39P 「2.妖怪ヘビ壺の巻」、単行品未収録の扉絵のえん魔、雪子姫の顔を修正。49P ダラキュラと対峙する妖怪パトロール3人のうち雪子姫のみ顔を修正。55P 「ゆくぞカパエル!!雪子姫!!」「はいな あんさん!!」「おっけー!!」の一枚画のえん魔くん、雪子姫の顔描き直し、足の裏にトーン 「はいな あんさん!!」は当時まだ連載中だった「男ドアホウ甲子園」の甲子園の恋女房、豆タンの台詞から・・・だよね。66-67P ヘビ壺の蛇に苦戦する雪子姫の顔をそれぞれ修正。83P 氷を溶かすえん魔くんに続くコマ、従来は第3話「そうはとんやがイカの足の巻」のタイトルがはいっていたのを削除。 悲鳴と雪子姫の「いやーん えん魔くんのエッチ-!!ダメーツ!」の台詞を追加84P えん魔くんを凍った蛇で殴る雪子姫の1P大ゴマ、描き下ろし85P 「3.そうはとんやがイカの足の巻」扉絵。若木版2巻巻末、P203にイカを口に咥えていない画が収録87-88P 地獄へ変えるえん魔くんを追う雪子姫、のあと2P描き下ろし。ゲソーにスカートをめくられ襲われる雪子姫97P ワルターゲソーと対峙するえん魔くん。ゲソーの目の周りを墨塗り。えん魔くんの顔3コマ修正98P えん魔くんの顔修正、ゲソーの顔にトーン99-101P えん魔妖力火炎車でゲソーを倒すくだり従来の2Pを完全に描き下ろして3Pに。103P 「4.眠りが誘う妖魔の宴の宴」、扉絵を収録、えん魔くんのみ顔を修正。(何故か雪子姫は直してない)139P 雪子姫が氷の妖術で妖怪を倒す1P大ゴマ描き下ろし143P 「5.妖怪面食いの巻」の扉絵を収録。修正はない159P 「6.妖怪ハチの巣入道の巻」の扉絵を収録(若木版では2巻巻末に元の絵を掲載)。 シャポ爺を被りマントとステッキを装備した雪子姫、顔や手などを描き直し(個人的には昔の顔が好きなんだケド)。166P 地獄別荘に向かうツトム、この1Pは若木版では未収録。187P 裸で仁王立ちする雪子姫の顔を修正190P ハチに胸を刺される雪子姫の顔を修正208P 「7.妖怪マタサ鬼の巻」の扉絵、雪子姫の顔を修正222P 「8.妖怪でた妖が来たようの巻」は修正はない。239P 「9.妖怪ふくらし子の巻」の扉絵(?)がカット。これについては後述268-270P 「10.ふしだら妖怪けっとばーしの巻」冒頭の3Pを2Pに圧縮。えん魔くんと雪子姫のアップ、トバッチリ先生が蹴られて止まるコマの3コマを削除。 それに伴いトバッチリの台詞を変更318-319P 「11.妖怪猫夢の巻」猫夢に襲われる雪子姫、2P4コマ(1P大ゴマあり)を描きおろし333P 「12.妖怪なだれ小僧」の巻には修正がない348P 「13.妖怪すってん童子の巻」にも修正はないようだ。この回は扉絵もなく若木版そのまま。363P 「14.寒天狗炎天狗」。若木2版ではアイキャッチに使われていた扉絵のえん魔と雪子姫の顔を修正 凧あげの絵なので小学三年生正月号の画じゃなかったか。368P 炎天狗の顔にトーン369P 炎天狗の顔にトーン382-383P 寒天狗と炎天狗、地獄別荘上空で対決の見開き画を描き下ろし392P 炎天狗の顔にトーン453P 「15~20.大妖怪怒黒」その1からその6は大きな修正はない。その3の扉絵、えん魔の顔を修正のみか。527P 「妖怪ふくらし子の巻」の扉絵(単行本ではアイキャッチ的に台詞変更していた…はず)をさらに台詞変更にしてあとがきページに。雪子姫の顔を修正。 尚サンワイドや中公版、MF版に併録された「炎魔地獄」や石川賢版、小山田つとむ版は未収録。「シュルルン雪子姫ちゃん」の出典でもあるわけで石川版は完全収録で単行本化してほしかった・・・。 小山田版+石川版+テレビランドの平松版に後年のハガネ功一版も加えて「ドロロンえん魔くん外伝」、今のタイミングなら出せたんじゃないかしらん。一年生版の真樹村正版も気になるし。 お気づきと思うが今回の完全愛蔵版、何故か従来と収録順が大きく異なっている。 従来は1~6→15~21→7→10→8→11→9→13→12→14の順で収録されていた。今回は記載番号順の収録に変更となり最大の長編「大妖怪怒黒の巻」6話分が最後に置かれている。 もともと少年サンデー版と小学三年生5話分の混載で雑誌掲載分と単行本時の収録が合致しているのか(不勉強なためわかりません・・・こちらもご指摘いただければ) ティストの異なる続編「炎魔地獄」、バイオレンスジャックのエピソード「炎の魔人編」、一応正統な続編の「鬼公子炎魔」(そしてその頭の痛い続編「ケルベロス」・・・あとは短編、永井豪以外によるもの、けっこう仮面のテイストが入った「どろろん艶靡ちゃん」・・・)と続いたえん魔くんだが やはり最初の妖怪退治をしないで雪子姫とHなことばかりしているのがえん魔くんらしい、と今回読み直して再認識。「妖怪猫夢」の回でのえん魔くんのサディストぶりは特筆に値する。 (ただ第3話で百手が「人間を妖怪に変えてどうするつもりだった?」と問われて「今にわかる・・・仲間たちがまたいつの日か」と言い残した伏線はその後返りみらる事はない。 この辺りはアニメ版や「鬼公子炎魔」に活かされていないとはいえないが・・・・。) 今回のアニメ版メ~ラめらは原作(もともとはアニメ企画先行だが)の肝心要な「基本的に無駄で役に立たない」部分(そのままでは映像化出来ない部分であるが)を巧く活かして映像化している点が好ましい。
2011.06.14
閲覧総数 5980
-
13

「伝説日本チャンバラ狂」~時代劇にも黒鉄ヒロシの絵にも陶然
↑「伝説日本チャンバラ狂」・・時代劇製作のウラを独特の画で描いた興味深いドキュメント70年代後半にテレビのバラエティ(たとえば「クイズダービー」)などに出ていた印象が強いですがその実、黒鉄ヒロシはナンセンスギャグ「赤兵衛」や歴史もの「新撰組」や「幕末暗殺」などの時代もの漫画を多く手掛ける優れた漫画家です。その面白さはナンセンス(やや、古い言い回しですが同時代の凡庸な作家と比べて本当にナンセンスな上時折非常に黒い)な笑いに絵のシュールさとそこから生まれる凄みにあるのではないでしょうか。「日本チャンバラ狂」はその作品から十分推し量れる通り時代劇映画に影響を受けた作者によるあまり語られることのない「時代劇」製作の裏側のドラマを描いた連作です。時代劇コラムでおなじみのペリー荻野という相棒を得て黒鉄節が炸裂、映画、TVに関る人々の姿を活き活きと描いていています。語られているのは「新撰組血風録」「木枯し紋次郎」「三匹の侍」「水戸黄門」「てなもんや三度笠」のテレビ時代劇「十三人の刺客」「眠狂四郎」の映画。「東映太秦映画村」誕生と「柳生一族の陰謀」それに時代劇映画への思いを綴った終章です。何にせよ裏側は知りたいものなのですが、素の中村敦夫(インテリ俳優)の紋次郎らしくなさとかやたらとスタアのカッコよさ(たまりません)全開の市川雷蔵、財津一郎の狂乱の演技ぶりなど俳優や監督の姿が興味深く面白いですね。しかし何よりもその画の面白さに価値があります。司馬遼太郎や柴田錬三郎なんかの作家の画も描写も魅力的で面白いので時代劇映画・小説ファンには必見の一冊だと思います。これを読むと「十三人の刺客」や「薄桜記」、「木枯し紋次郎」が見たくてたまらなくなります・・。続編では勝新太郎を是非是非おねがいします・・。時代劇とややははずれますが黒鉄ヒロシ版成田三樹夫とかの俳優列伝が読みたいなあ。
2006.06.29
閲覧総数 61
-
14

坂井孝行版ゴジラ完結・ゴジラVS黒木の決着「ゴジラVSデストロイア」
2体目のゴジラが死んで二日が過ぎた。1体目は1954年、芹沢大助博士の開発したオキシジェンデストロイヤーによって消滅した。そして二体目はここでゴジラが死んだ。すべては4日前に始まった・・・坂井孝行のゴジラ前作までの内容はこちらキングギドラに捧げるエミーの涙 ゴジラVSキングギドラぎゅっと抱いて・・不器用な愛の物語 ゴジラVSモスラゴジラの死を・メカキングギドラの復讐 ゴジラVSメカゴジラシリーズ最高傑作 ゴジラVSスペースゴジラ「ゴジラVSデストロイア」は95年に公開された第22作目、「ゴジラ」(84)を含めての平成VSシリーズ7作目にして最後の作品である。脚本に「ゴジラVSモスラ」以来の大森一樹を迎えた本作は1954年の第一作に負う所の多いストーリーである。初期にあった54年のゴジラが蘇る「ゴジラVSゴーストゴジラ」の企画に川北紘一のゴジを死なせたいという意見が結びつき平成VSシリーズの完結編というかたちになった本作はゴジラがメルトダウンして死ぬというその一点に全てを収束させた映画である。そこでは最早オキシジェンデストロイヤーの産物のデストロイアも山根家の人々もGフォースもその「ゴジラの死」の装飾的な枝葉末節に過ぎない。ただ伊福部昭の音楽が鳴り響く中のゴジラの荘厳な死を観客はみつめるだけなのである。坂井版「ゴジラVSデストロイア」は漫画版に一貫して登場した黒木翔とゴジラの戦いの決着を描いた 物語である。それは映画が三枝未希を2作目以降登場させたのに似ているが「ゴジラVSビオランテ」での付けられなかった決着が付いたとみる事ができるだろう。漫画が黒木特佐を出し続けたことに関係あるかどうかわからないが映画にも黒木は特殊戦略作戦室の特佐としてスーパーX3を操縦、デストロイアを粉砕しゴジラの最期に立ち会うこととなった。漫画の登場人物は 黒木翔(Gフォース司令、自衛隊特佐) 鈴木(Gフォース隊員) 青木一馬(Gフォース隊員) 結城晶(元Gフォース隊員) 佐々木(Gフォース隊員)植杉国守(防衛庁長官)川野博士黒木翔のみが自衛隊特殊作戦室特佐として映画にでている以外は別作品の主要人物とオリジナルの登場人物で映画の主要登場人物の伊集院、山根姉弟、三枝未希、芽留、国友、麻生、山根恵美子はいっさい登場しない。青木は「ゴジラVSメカゴジラ」の、結城晶は「ゴジラVSスペースゴジラ」の(漫画版での)主人公である。佐々木隊長も「ゴジラVSメカゴジラ」から、また「ゴジラVSスペースゴジラ」の権藤千夏、「ゴジラVSモスラ」の手塚雅子、藤戸拓也も1シーンのみ登場している。このあたりは坂井ゴジラの総決算といったオールキャストで嬉しい。細かいことだが元気になった雅子と拓也は3年後も結婚はしてなかったようだ。本作のヒロインである鈴木は「ゴジラVSビオランテ」における女性スーパーX2オペレーター(鈴木京香)と考えられるが坂井版「ゴジラVSスペースゴジラ」における登場時(これは映画版の鈴木京香に似せて描かれている)と大分キャラクターが異なっている。 コミック坂井版の内容紹介に移ろう。 香港にゴジラが出現する冒頭部分はそのまま映画と同じであるがコミックではこの事態にMOGERA2号機、3号機が出動している。これは前作で盗まれたMOGERAをメカゴジラ2が追うというシークエンスに似ているがやはり暴走するゴジラの強さを誇示するために熱線の体内放射で瞬殺される。Gフォースの切り札は海底の泥を研究しオキシジェンデストロイヤーを開発するというもので伊集院の役割がGフォースに振られている。Gフォースは研究室から出現したデストロイア幼体により壊滅、佐々木隊長の犠牲で黒木、青木、鈴木の三人だけが逃げ延びる。佐々木隊長は映画の原田大二郎も好演であったが漫画版の隻眼の鬼隊長として印象深い。「ゴジラの異常、それのこのバケモノ。何とかできるのは黒木さん、アンタだけだ・・。日本をいや世界をたのみましたぜ!」身体にダイナマイト!でデストロイア幼体とともに吹き飛ぶシーンは前半の最大の見せ場であろう。黒木は防衛庁に向かうが自衛隊への復帰を出現したゴジラジュニアを撃退することを条件とされるがデストロイアを作り出し2匹を相打ちにする映画ではジュニアはバース島消滅によりアドノア島へ向かっているところをゴジラをおびき寄せるためにテレパシーで東京に無理矢理上陸させられるのだが漫画ではここで出現し飛行体のデストロイアと相打ちになる。その最期も右の腕と脚を角ミサイルで吹き飛ばされるという残酷なものだ。(青木は新怪獣を作る黒木に怖さを、鈴木はジュニアの死にゴジラの気持ちを考える描写がある)ゴジラは東京に到着し死んだジュニアに姿に咆哮する。黒木は暴走するゴジラの体内で何がおこっているのか調べるためゴジラ内核分析器をスーパーX3で取り付けるパイロットとして前回のモゲラ泥棒で懲役中である結城晶を呼び出す。鈴木が結城を監視する件りは「ゴジラVSスペースゴジラ」を読んでいると結城の出鱈目さが再認識されて面白く、鈴木もここでのやり取りが作中一番活き活きしている。これは前作が漫画として面白く出来ているせいかもしれない。 スーパーX3は映画と違い冷凍兵器に特化しているわけではなくステルス機能を強化した高機動戦闘機といった感じである。ゴジラの脚にとり付いた感じでは全長10m位で映画の38mという設定と比べても用途もデザインも大幅に異なっている。ここからゴジラの核爆発の危険性とスーパーX3の故障、ゴジラ冷却のためのサンダーコントロールシステムの使用(「ゴジラVSビオランテ」の引用、坂井版「ゴジラVSモスラ」でも使用。)、デストロイアの復活、植杉の反乱と計算違いによるゴジラメルトダウンのサスペンスとなっていく。結末は映画と同じなのだがそこへの道筋がかなり異なっている。ゴジラの安心な核爆発、メルトダウンによる地球の危機と刻々と変わる状況に関るサスペンスを映画以上に細かく描いた点は良いとしてもそこがやや面白みに欠ける。怪獣たちが人間の右往左往の中見せ場を失っており(デストロイアは映画以上に影が薄い)、それに関る人間ドラマ部分では前作のような感情の高まりが薄い。本作がサスペンスに優れる「ゴジラVSメカゴジラ」や結城のドラマを貫徹した「ゴジラVSスペースゴジラ」に比べて印象が弱いのはそこが理由だと思う。 また雑誌と単行本では結末が異なる。雑誌版ではゴジラはメルトダウンすることなく立ち往生で結末を迎える。「ゴジラは・・・人類の生んだ最大の被害者、そして最強の敵ゴジラは・・・もう動くこともできません・・・」坂井版では人類はゴジラを生み出し、そして倒しながらまた再び自らの手で(ここが映画と異なる)ゴジラを生み出してしまう皮肉な結末を描いている。但しそこが「君を助けたくて」という愛の告白のような言葉とともに描かれるのが人間ドラマを重視した坂井孝行のゴジラらしいところではないだろうか。坂井版もそうだが映画でも明確に描かれなかったが絵コンテでは新たなゴジラの誕生の後、麻生の「ヤツは人類の敵か?味方か?」という台詞と放射熱線を画面に向かって吐くゴジラ、というショッキングな描写がある。果たしてジュニアは恐怖の王ゴジラになったのだろうか?坂井孝行によるゴジラはこれで完結である。しかし平成モスラ三部作も続けてコミカライズを手掛けることになる。そしてこのモスラシリーズはゴジラとはまた別の深い感動の漫画となるのだが・・・それはまた別の機会に・・。
2007.01.08
閲覧総数 4744
-
15

ウルトラセブン救出・・30年目の真実
セブン(変身できないのでダン)は「MAC全滅!円盤は生物だった!」においてMACの隊員たちと一緒に円盤生物シルバーブルーメに基地ごと食われてしまいました・・・。・・のはずだったのですが今回の映画「ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟」で元気な姿をみせています。事実上別の番組とはいえ「コメットさん」や「ウルトラセブン太陽エネルギー作戦」以降の平成ウルトラセブンには確かに姿をみせているのですが・。前者はあくまでも別の番組。平成のウルトラセブンシリーズは基本的に「ウルトラセブン」のみの続編という作であのセブンのその後ではないようです。セブンの安否については宇宙囚人207さんの同人誌「ウルトラマン裏百科」(傑作です!)において怪獣百科や漫画に描かれた幾つかのその後が挙げられています。この辺は第三期怪獣ブームに書かれた編者や漫画家のオリジナルなのでそこのとこが逆に面白いかと。●・・ゾフィーと初代マンに助けられウルトラアイも修理され宇宙情報局で怪獣学の研究をしているらしい・・※怪獣学を修める学究肌のセブン・・。いい感じかも。●α星で治療をうけているらしい(漫画・ウルトラ戦士の噂話で)※α星・・わし座の α星 Altair(アルタイル)のこと?七夕の彦星、ですが有名な病院でもあるんでしょうか?●パトロール中の仲間に助けられケガも直り元気な姿をみせてくれるだろう(漫画・ゾフィーがレオに)※そんな簡単な話だったのか・・。どこをパトロールしてたのか気になる・・。●マグマ星人に折られた足も今ではすっかり良くなっているよ(大百科?・80談)※80談なので・・折られた足以前にどう救出されたんだよ!●宇宙を漂っていたセブンはマゼラン星雲の宇宙警備隊の支部に助けられ無事・・ウルトラアイが壊れたままなのでモロボシダンの姿のままウルトラの国に帰れないでいる(大百科?コロタン?)※す、凄い。地球からマゼラン星雲、しかも人間の姿のままで・・何年間漂流してたんだ、ダン。現在映画館で「ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟」の号外が頒布されているのですがこれに「これが兄弟たちの戦いだ!!」という略年表が掲載されています。これによると1975年1月に行方不明になったセブンは3月にレオが円盤生物を全滅させたあとウルトラの母に救けられウルトラの星で休養に入るとあります・・。2ヶ月間も宇宙空間を漂っていた・・・ダンの姿のままで・・かどうかわかりませんが「作品スタッフによる新設定を補完して作った」年表らしいので一応これが公式・・ということでいいんでしょうね・・。うーん、ダンの姿のまま16万光年先のマゼラン星雲まで流れていった・・の方も捨てがたいんだけどなあ・・。
2006.08.31
閲覧総数 520
-
16

12/30怪獣少女は坂井孝行の「モスラ1」です!
怪獣少女は12/30(水)のコミックマーケット89に参加します。国際展示場東4ホール メ-39aが怪獣少女の配置場所です。特撮系同人誌がいっぱいの場所になります。今回の新刊は「モスラ1 6500万年の大魔獣」になります。夏コミで頒布した「モスラ2海底の大決戦」に続くコロコロSPECIAL掲載未単行本化作品書籍化計画の第二弾になります。「ゴジラVSデストロイア」に続いて掲載されながら単行本にならなかった本作はVSゴジラシリーズ同様に大胆なアレンジ、仕掛けが施されており特に映画とは全く異なる導入部とクライマックスは必見だと思います。またゴジラシリーズ以上に描きこまれた怪獣バトルは見せ場が多く平成モスラのファンのみならず怪獣ファンには一読の価値がある作品です。この機会に是非。 加えて夏に好評頂いた「モスラ2南海の大決戦」も再度頒布します。尚、今回は坂井先生も来場されます。ゴジラに関するまだ秘密の頒布物もありもしかすると世界でひとつのお宝がGETできるかもしれません。今後のTwitterでの情報にも注目です。https://twitter.com/takayukまた英雄共闘館による新刊ダイナミックプロ同人誌「ゲッターロボ大血戦BOOK」および既刊のマジンガーマガジン1~3も頒布します。私も「桜多吾作のゲッターロボが読みたい」、「ムサシの最期大全」「ゲッターロボGの最終回比較」の記事で参加してます。鬼才ちょんげら。先生の新刊、特撮パロディ漫画集成「変態ヒーロー尻作選」もあります!!これはホントに面白いです(成人指定ではありません、念のため)。まだ新作は未読なので私も楽しみです!!12/30コミケ2日目のご来場をお待ちしております。
2015.12.22
閲覧総数 1143
-
17

残酷ショー開幕・ウルトラマンA第8話「太陽の命エースの命」
承前です。前回分を読んでからお願いします・・。再びエースバリヤーで閉じ込められた星人と超獣。その結果危篤状態なる夕子。迫るゴラン、マリア2号の完成、その打ち上げ寸前に星人と超獣が出現して・・・。今回はムルチの映像があんまりにもグロなので・・そういうのに弱い方はご遠慮の程を・・(そういう方がコチラをご覧になるかどうかわかりませんが・・)いいかな・・・。ムルチ3対1で痛めつけられるエース。ムルチの頑張りが目を引くのですが頑張りすぎて頭からドラゴリーと激突、交戦となりムルチは哀れな最後を遂げます。もし3対1のままだったら・・。これはドラゴリーの失点でしょうね。ちなみにこのシーンでムルチはどうなるかというと 投げ飛ばされた後下顎を引っ張られて胸まで皮を剥がされます。引き裂かれた口から下の赤さが生グロテスク・・その上、血がびゅっと噴水の如く噴出し既になくなった顎を触り悶絶する様子がかなり生生しい。 そのあと左足をねじ切られて投げられます・・・その後の描写はありません赤い目で表情がないはずのムルチの目に生き物らしさが感じられる・・というのは面白いです・・がひどいなあ・・。ムルチが熱演(?)してるので凡百のスプラッタムービー以上にショッキングです。瀕死の夕子「どうしたの・・そんな悲しい目をしちゃって・・」「君がこうなることを承知でバリヤを使ったんだ・・君をいたずらに苦しめるために使ったことになる・・許してくれ」北斗の・・まだ年若い青年が背負うには大きすぎる力と責任の重さ・・。北斗の成長と苦悩の深さを示すシーンです。山中の暴走と隊長の叱咤山中は復讐の念から今野を抱きこんで後先考えずメトロン星人をエースバリヤー毎葬ろうとした挙句開放してしまいます。さらに隊長に反抗する山中。北斗はそんな山中すら庇おううのですが・・お人よし過ぎだなあ・・。メトロン星人Jrシャボン玉のようなエースバリヤーに閉じ込められた姿がラブリーなメトロン星人。マリア2号打ち上げ妨害のため再び出現した星人でしたが隙を突いたバーチカルギロチンで真っ二つに。有名なシーンですが・・メトロン星人の中身がアレなのは・・というかアレはなんなんでしょうか?ギラドラスをおもいだすなあ・・。 ドラゴリー散々ハンディキャップマッチを強いられさらに夕子が危篤状態というエースはメトロン星人を倒したあとカラータイマー停止でぶっ倒れます。しかし・・ゴランが爆破され太陽エネルギーの戻ったエースの敵ではなくパンチで丸く右脇腹に風穴を開けられエースブレードで首を斬られた挙句メタリューム光線で爆散します。ドラゴリー、万全な調子で1対1で挑めばそれ程の敵でもなかったようにもみえますね。三途の川「君を三途の川から呼び戻したのは北斗隊員だ」という竜隊長。三途の川って・・普通・・いうかなあ・・。いや、三途の川の渡し守・隠密同心井坂十蔵の言葉ゆえに真実味と重みのある台詞でした・・。内容盛りだくさんで特に北斗の夕子への思いやりや成長がみられるという点ではよかったかなあと・・。怪獣切り裂きショーとしては・・これ以上は望めない位の作品だとおもいます・・。まあ山中隊員は・・いつものことですからね・・。
2006.09.23
閲覧総数 10674
-
18

シルバーブルーメは強いのか?
『MAC全滅!円盤は生物だった』を観た。●詰め込まれた悲劇 円盤生物によるMAC全滅、百子・カオル・タケシの死・・・というレオ最大のイベント回で悲劇的な内容の回なのだけどこれが全てAパートに詰め込まれているのね。 MACステーションは藍とも子(ファミリー劇場の『ウルトラ情報局』にでていらっしゃいました・・・『メカゴジラの逆襲』の面接はMACのユニフォームのままで受けたらしいですね)・・松木隊員の誕生日の最中に基地を急襲される。シルバーブルーメがレーダーに引っ掛からなかったのか誕生日でレーダー探索を怠っていた(としたら文字通り致命的な・・)のかわからないけれど停電した基地内に黄色いどろどろした液体が垂れてきて・・というのは絶望的な状況。 脱出しようとしたマッキー(3人しか乗ってなかった?)が飲まれる展開も悲惨。ダンはゲン一人だけをなんとかを脱出させる・・・・。 ●ダンの最期 悲痛なセブンのテーマ流れる中、ゲンを脱出させるダン。 「MACの最後は見届ける」とダンは言ってましたが後の映画『ウルトラマンメビウス&ウルトラ兄弟』の時に作られた年表をみると宇宙空間をただよっているところを救助されたとあるので見届けたあと脱出した、という解釈になるのかしら(シルバーブルーメは宇宙で倒されたわけではないので)。 『ウルトラマンレオ』の顔であったダンの退場劇としてはあっという間で寂しい・・・内山まもる版コミックでは最後の力で変身、ミサイルを背負って特攻という描写があったが・・残念。●ジェジェの呟き 百子たちはシルバーブルーメが地上に降りてきた際たまたま買い物に来ていてビルごと潰されたと思われる。 貼り出された被害者名簿に名前があったので死体は確認されていると思しい・・・。 ビルが潰される際の当時人気のあった指のおしゃぶりポーズをする抱き人形ジェジェ(ですよね、正規の本物かどうか気になる)の硬質タイプが喋るシーンが哀しい。 「お勉強しなくちゃダメよ・・・先生にしかられるわよ・・お兄ちゃん・・私眠くなっちゃった・・子守唄を歌って・・」 実際のジェジェは喋らなかったはずなので余計この演出が効きます・・。 ●何事もなかったように でBパートはいきなりゲンとトオルがミヤマ家に下宿してます。 女ばっかりの家で小言を言われて居心地悪そうな、Mな所を刺激されて喜んでいる(おいおい)ような二人・・・事件からかなり時間が経っているとしか思われないのですがその間何やってたんだシルバーブルーメ、というかブラック司令。 ●兜甲児、溶ける シルバーブルーメは何故か小さな皿みたいになって登場。 トオルはあの時の円盤と言って騒ぐのだけど・・似てないし・・。 それをアルコールランプの火であぶるのもどうかしてるけれど最期はシルバーブルーメに溶かされる担任の先生が兜甲児・・じゃなくて石丸博也サン。この辺りロボットアニメに人気の座を奪われて終焉を迎えつつあるウルトラシリーズの怒りが感じられる(れない、れない)。 ●でシルバーブルーメは強いのか? レオとの対戦の様子をみる限りあまり強くない。 トオルたちを逃すために押しあう辺りはともかく救助が終わるや否やあっさり内部に腕を突っ込まれて未消化のマッキー(いやな描写)など中身を引き出されて光線で爆発する。 もともとベムスターの腹部だけが特化し触手がついたようなモノだけに防御力は大したことなかった・・ってことかなあ。 となると初戦でもなんとかなったような・・・。 MACも百子さたちも死なないですんだような気がしないでもない。 結論・・ゲンに適切な指示をしなかったダンが悪い。 ・・・・・いや、路線変更が悪いんだけどね・・。
2009.02.09
閲覧総数 2001
-
-

- Youtubeで見つけたイチオシ動画
- 【日本最大のりもの祭】国内二輪メー…
- (2025-11-29 21:22:25)
-
-
-
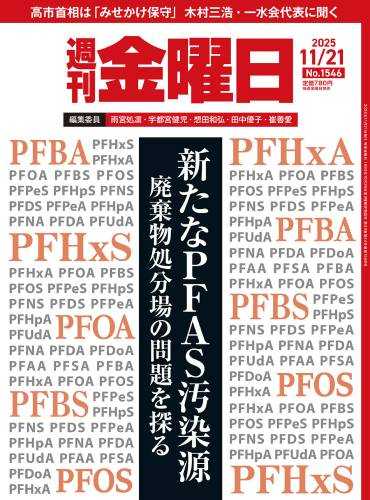
- 【演劇】何か見に行きますか? 行き…
- 劇評:劇団温泉ドラゴン『まだおとず…
- (2025-11-21 13:22:46)
-
-
-

- 芸能ニュース
- アイドルグループメンバーに殺害予告…
- (2025-11-29 18:16:08)
-







