2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年04月の記事
全28件 (28件中 1-28件目)
1
-
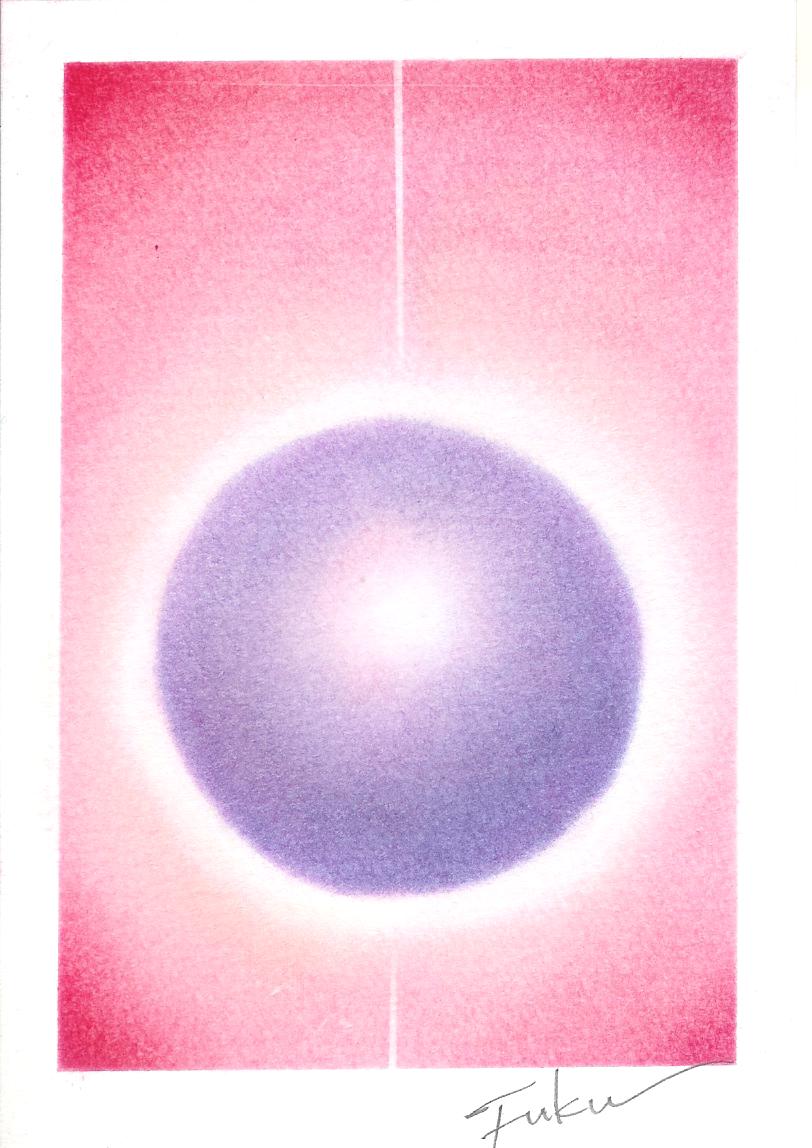
偏見はなくならない
【新しい倫理観】●「偏見をなくそう」から、「偏見はなくならないし、誰でも持っている」自分も偏見を持っているいうことを強く自覚して生きる●「我を捨てましょう」から「我を捨てれば人間ではない」自分の自我を成長させる生き方をする●「物欲を捨てろ」から「物欲を人間的な品格のあるものにしよう」欲が歴史を作っていく。●「足るを知る」から「より高度な足るを知る」へと昇華させていく。とらわれずに、求める姿勢。不完全であることを自覚し、「足らざるを知る」ことも大切●「短所をなくせ」から「短所はなくさず、長所を伸ばして、短所を味に変える」短所があるから人間である。短所があるから謙虚になれる。短所の自覚がない人は、傲慢になる。
2007年04月29日
コメント(1)
-

命には命より大切なものがある
「このためなら死んでもいい」「この人のためなら、命をかけても守る」、「この仕事になら、命をかけて取り組める」と思えるものと出会ったとき、命は最も激しく燃え上がり、最高に輝くのです。「この人のためになら死んでもいい」と思うくらい人を愛さなければ、本当の意味での愛のすばらしさを味わえない。相手からも「この人のためになら死んでもいい」と思ってもらえるような人間になるための努力を続けることも大切です。仕事でも、「この仕事のためになら死んでもいい」と思うくらいでなければ、本当の意味での仕事の醍醐味を味わっていない。理屈を越えたものであり、命の底から湧き上がってくるものです。理性で考えるものではありません。健康のことを忘れて何かに必死に取り組んでいるとき一番健康である。命は、知らないうちに病気を治していることもある。命には、命より大切なものがあるのです。・・・・・・・・・・・「命より大事なものがある」とは何か・・・。家族のためなら、火の中にであっても何も考えず飛び込んでいくだろう。仕事のためにそれができるだろうか・・・今与えられた仕事や人間関係は、仮に自分のやりたい事でなくてもいろいろな縁が重なって与えられたものである。上司が嫌だから・・・好きな仕事じゃないから・・・と別のところに道を求めると、同じような問題が人と場所を変えてやってくる。今与えられたところで、必死になって取り組んだとき、新しい道も開けてくる。一所懸命にやっているかもしれないけど、必死にやっているか。
2007年04月28日
コメント(0)
-
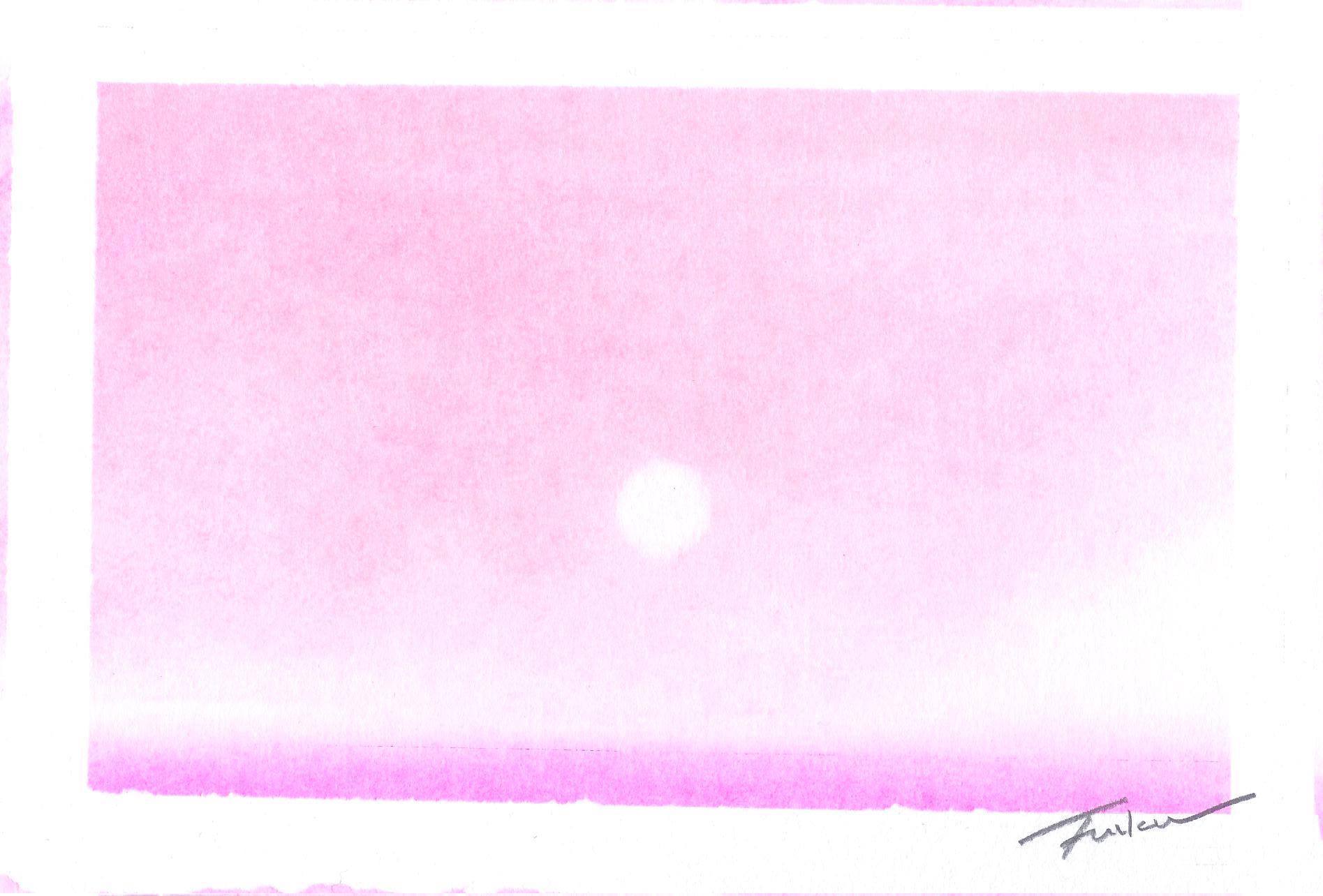
夫婦の愛の10か条
●夫婦の愛の10か条 男女の愛は、「この人のためなら死ねる」という心情 親子の愛は、「どんなことがあっても子供を信じぬく力」 この二つの愛の交差するところが、夫婦の愛である1.家庭も人間的成長のための道場である 家庭の中で、自分を人間として磨いて成長していこうとする意識が大切。 子供が生まれて、父親母親になれる。 子供が悪いことをして、父親としての役割を学ぶ。 夫婦げんかを通して、相手の気持ちを学ぶ。2.どうせするなら心をこめて 惰性に流されないこと。3.共通体験、共同体験を積み重ねる努力 同じ体験や一緒に何かをすること。4.夫婦と言えども、元は他人 夫婦の仲にも節義、節度をわきまえた関係性であること。5.家庭とは、理屈抜きに信じ合い、許し合って生きる場である 家庭は、不完全な人間が安心して帰れる場所でなければならない。 理屈で責め合えば、地獄。理屈を持ちもまない。 理屈を超えた愛を作る場である。 6.結婚という決断に人生をかける 「決」・・・多くの可能性の中からあるひとつの存在を選び取ること。 「断」・・・ひとつの道を選んだならば、同時に他の道への思いを断ち切ること。 捨てる勇気のこと。 オレ、私には、この人しかいないという気持ちが大切。7.子供の存在を強く意識すること。子はかすがい。 子供がいるから、父親母親になれる。 子供のことを思えば、問題も乗り越えられる。 親としてのあり方を自覚させてくれる。8.セックスは人生の三分の一の重みを持つ重要課題 セックスは、人生の1/3の重みを持つ課題。 仕事1/3・生活1/3・セックス1/3 セックスとは、単なる性交渉ではなく、男女のふれあい・命のふれあいのこと 抱きしめることの大切。相手の欲求を満たす努力が必要。9.理念への問いをお互いに持つ 理念とは、夫・妻とは、いかにあるべきか? 父親・母親とは、いかにあるべきか? 真剣に人生を歩き始めた時、命のそこから湧いてくる問いを問い続けること。 10.人生には、失敗の人生はない 人生は、体験の連続。体験とは、真実を語る力。 体験は、やった人間しかわからないものを教えてくれる。 体験には、マイナスがない。 体験の数だけ、幅ができる。 体験の数だけ、重みができる。 体験の数だけ、厚みができる。 体験こそ人生の宝である。最高の愛の形とは 父性愛 母性愛 男性は、父性を極める。 女性は母性を極める。 男は、万物の父となれ。 女は、万物の母となれ。
2007年04月27日
コメント(0)
-
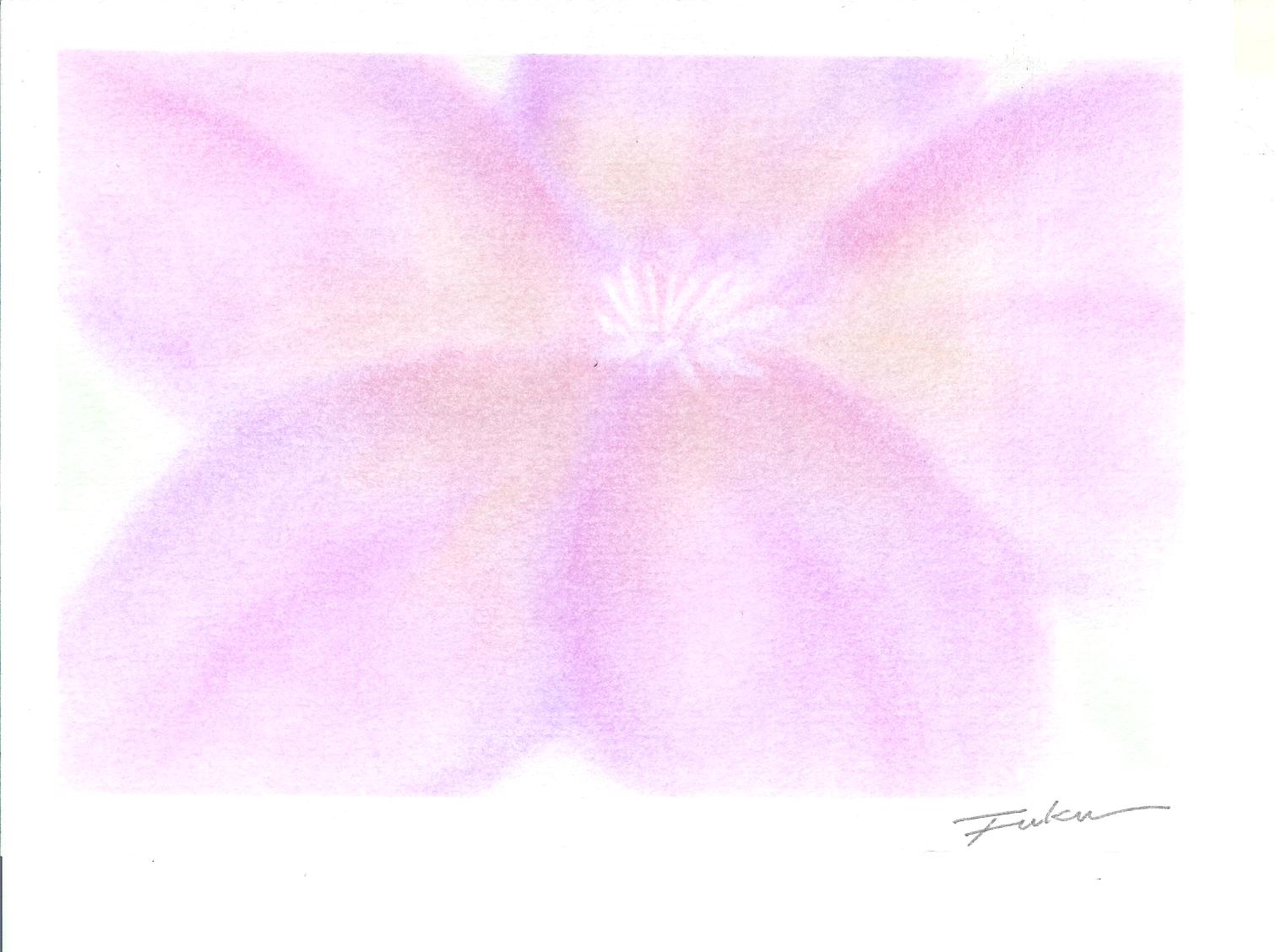
理屈じゃない
人間の本質は、こころ理屈じゃない心が欲しい。だれもがみんな心が満たされたいと願っている。「心をあげる」とはどういうことか?誰もがみな自分の気持ちをわかって欲しい。共感同苦、共感同悲、共感同喜「そうか、そんなに辛かったのか。わかってあげなくてごめんね」「そうだよな~。わかるよ」受け止めること。気持ちを理解してあげること。「頑張れ!」ではない。「そうか~。そんなに苦しかったのか~」心は、満たされきることはない。なぜなら、人間は不完全だから。お互いに「どうして私の気持ちをわかってもらえないのか?」と思っている。誰もがみな「私のことなんかだれもわかってくれない」と思っている。自分がこのように「愛されたい」と思うようには愛されることはない。親は、どんなに努力しても子どもには「父親も、母親も、オレのことをわかっていない」と子どもが思っていることを理解しておくことが大切。それは、子どもが求めるものと、父母が思っていることには、必ず差があるから。男女の関係においても同じ。男性がどれだけ、女性を愛しても女性は満たされることはない。女性がどれだけ男性のことを愛しても男性は満たされることはない。それは、男性が求めるものと女性が求めるものが違うから。「これだけしているのに・・・」と思った瞬間から、押し付けになる。「これでいいのか・・・」「こうしたら喜んでくれるかな・・・」と悩む心に「愛」がある。
2007年04月26日
コメント(0)
-

子供の教育について
年代別教育論A.0~3歳 赤ちゃんの心に、本当に安心して生きていったらいいんだ という安心感と信頼感をしみこませる。 生きる事の原点である信じる力を傷つけずに維持する。 スキンシップを通じて子供に充分な信頼感と安心感、 愛を感じさせる。B.3~6歳まで(第一反抗期) 行動力と自制心(倫理観・善悪正邪の区分の基礎)を創る ことを目的に教育する。C.6~10歳まで(善悪正邪の区分) 子供が主体的に人間的判断をするための土台となる 大人の持っている常識としての善悪正邪の区分を しっかり教え込む。D.10~13歳まで(過渡期) 親は、先生を批判したりけなさず、先生を誉めて好きにさせる。E.13~15歳まで(第二反抗期) 何か質問されてもすぐに答えず、一緒に調べたり、 どのようにすれば答えが出るか、その方法を教え一緒に考える。 この時期に必要なことは、主体性と責任感の二つを作ること。 人格に目覚める頃だから、子供の人格を認めて接することが大切。F.15~20歳まで(自分で自分を教育する) 「自分で自分を教育することを教える。 目的を与えることが大切で、 「将来どんな人間になりたいか」 「将来どんな仕事がしたいのか」 「将来どんな生活がしたいのか」 を問い、考えさせる。G.20~30歳まで 30歳までの人間には、大宇宙の偉大な進化の力が働いている。 「個性を磨きだす」 「常識で考えるのではなく、常識を考える」 「自分に与えられた使命を自覚する」 ことによって創造力を湧き出させる。年代別教育論」(実践論)です。教育論は、感性論哲学講座の中でも取り上げられる事が少なく、また通常は1時間半~2時間で講義されます。年代別に0歳から30歳まで具体的に5時間の講義を講演録としてまとめています。価格:1,000円(税込)+送料DVDもあります。思風塾ホームページ
2007年04月25日
コメント(0)
-
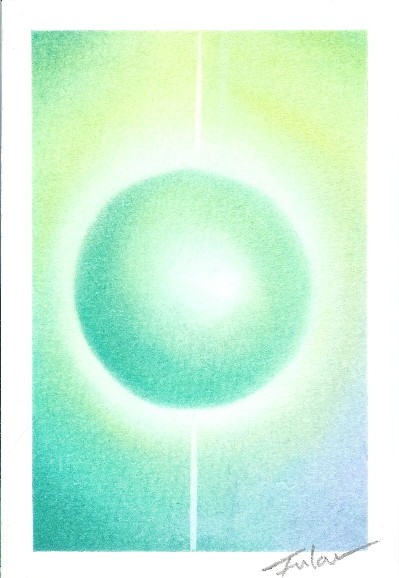
哲学を持つこと
「このためならオレは死ねる」というものに到達したとき、最高の哲学を持ったということ。プロとは、他にもいろいろいい仕事があるかもしれないけど、オレはこの仕事が最高のものと言い切れる人。「職業とは、その仕事に従事する人間を人に喜んでもらえるような人間性と能力を持った本物の人間に鍛え上げるという意味と価値をもっている」社会の修羅場こそ、命を鍛え上げ・磨き上げ本物の人間に成長させる。坐禅・瞑想は、精神力をつくることができるが、それだけではだめ。人間関係の修羅場こそ、自分の人間力を成長させる最高の場である。悩みから逃げない、問題から逃げない問題悩みこそ、実力を作る場である。命の痛みを伴った体験が人間を成長させる。今時分がやっていることにどれだけの「意味と価値」を感じているか?「意味」とは、そのものからにじみ出てくるものであり、存在の内側からにあるもの。「価値」とは、外から付け加えるものであり、関係性から付け加える物。例えば、ダイヤモンドダイヤモンドそのものには、価値はない。人間が持つことで価値がでる。自然界に存在する時は、ただの炭素のかたまりでしかない。
2007年04月24日
コメント(2)
-
一灯照宇の志
一灯照宇の志一灯照隅という言葉がある。「古人言く、径寸十枚、これ国宝に非ず。一隅を照らす、これ則ち国宝なり、と」 最澄「天台法華宗年文学生式」『魏王が言った。「私の国には直径一寸の玉(ぎょく)が十枚あって、車の前後を照らす。これが国の宝だ。」斉王が答えた。「私の国にはそんな玉はない。だが、それぞれの一隅をしっかり守っている人材がいる。それぞれが自分の守る一隅を照らせば、車の前後どころか、千里を照らす。これこそ国の宝だ」と。』 湛然の著「止観輔行伝弘決」安岡正徳さんの言葉によく「一灯照隅」が出てくる。 「賢は賢なりに、愚は愚なりに、一つことを何十年と継続していけば、必ずものになるものだ。別に偉い人になる必要はないではないか。社会のどこにあっても、その立場立場においてなくてはならない人になる。その仕事を通じて世のため人のため貢献する。そういう生き方を考えなければならない。」たとえ一本のロウソクでも身の周りを照らせば明るくなる、それを万人が照らせば「万照」、ことごとく世界を照らせば「遍照」。全ての始まりは常に小さなところから。ひとつの灯火が片隅を照らす。その灯火が次の灯火を点け、また次の灯火を点ける。そして多くの灯火が全国を照らし、ひいては地球を照らす。さらに宇宙を照らすという志を持て!芳村思風先生が、サインを求められた時によくかかれる言葉です。
2007年04月23日
コメント(0)
-
決めたら迷うな、バカになれ!
人生は賭け!結婚も賭け、会社の経営も賭け。人生は、決断の連続。決断とは、いろいろとある選択枝の中からひとつを選び取るだけではない。決めたら、選ばなかった他のものは、すべて捨て去る。断ち切ること。決めたら、バカになれ!オレにはこの道しかないこの人しかいない誰に何と言われようとも、どう思われようともオレが決めたことどんなに真剣に選んでも、問題の出てこない道はない。そのとき自分の持てる最高の力で、全力を振り絞って決める。決めたら自信を持って、出てくる問題を全力で乗り越え続ける。問題が出てきたから、選んだ道が間違っていたではない。人間は不完全だから、問題がないことはない。問題のない道は、成長のない道。決めたら迷うな!バカになって問題に取り組み、乗り越え続ける。「感性経営問答塾」15期が、今日で3日目終了。今回は、人数が少なかった。参加者の方にとっては、先生と直接お話していただける時間がその分多くあった。次回は、5月18日(金)~20日(日)会場は、那須高原ビール様出開催予定。
2007年04月22日
コメント(1)
-

矛盾を内包する真実を生きる
理性に支配された人間、理性の奴隷になっている人というのは、絶え間なく、自分と他人を比較し、人と競争し、「善悪・優劣・損得・勝ち負け・AかBか、○か×かの物差し」で評価、判断し、批判し、人を責めるか、自分を責めるかをしている。そして、結局は、自分も他人も不幸にしてしまうのである。理性は“完全性を求める能力”なので、矛盾や不完全性を許せないのである。理性は、自分と異なる考え方、感じ方、価値観を許しがたいのである。人間というのは、「不完全で矛盾に満ちた非合理な存在」なのである。欠点もある。間違いも犯す。至らないところもある。失敗もする。裏切ることもある。心ならずも嘘をつくことだってある。それが人間なのである。でも、嘘をつきたくてつく人などいない。失敗したくて失敗する人などいない。人間は不完全で、矛盾だらけの非合理な存在であることが腹の底に落ちるまでは、人は、自分を許すことも、人を許すことはできない。「矛盾を内包する真実を生きる」「愛」とは、許すこと。
2007年04月21日
コメント(1)
-

感性が問い、理性が答える
自分のいのちから理屈抜きに込み上げてくる感性の欲求・欲望・興味・関心・好奇心こそ、その人を最もイキイキと輝かせるもの。意志の強い人間というのは、自分のいのちから湧いてくる欲求・欲望の強い人間なのである。欲求・欲望を、理性を使って実現しようとした時に、それは、その人の“使命感・志”になっていく。理性というのは、“人の役に立つことかどうなのか”ということを考えられる力であり、“普遍化できる能力”だから。これが理性の長所なのである。多くの人は、“感性が自分を目的地まで導いてくれる”ことに気づかず、理性的な判断によって目標を設定し、進むべき方向を決定しようとする。しかし理性(思考)で作った、理念、目的、計画には、作為や、見栄や、焦りが働く。嘘が混じる。損得勘定のみが働く。「仏作って魂入れず」といったものになる。理性で考えた理念・目的・目標は、決して人間のいのちに真の喜びは与えない。理性で作った目的を実現しようと思うと、その瞬間から人は、その目的や結果に囚われて、どんどん自分を追い込んでしまう。自分の頭が作ったものに、自分が縛られ、支配されて、強迫観念のようになってしまうからである。感性から湧いてきたものを実現しようとすると、そこには“自由と喜び”がある。いろいろと創意工夫のアイディアが湧き上がってくる。自由と喜びがあるかどうかによって、その目的が、感性(いのち)から湧いてきた欲求なのか、理性(頭)で考えて作ったものかがわかる。「感性が問い、理性が答える」。感性はたえずちょっと違うんじゃないか?今ひとつピンとこない。これはおかしい。どうも腑に落ちない。もっとどうにかならないものかといった“現実への異和感”を発信している。その自分の内側から来る問いや異和感に理性を使って答えていくのである。どうしても納得できないことや、異和感を覚えるところが、実は自分の役割や使命があるところなのである。●第15期「感性経営問答塾」 平成19年4月20日(金)~22日(日) 東京 開催今日から、3日間、感性経営の5原則の集中講義と実践に活かすための数々の方法を学びます。特別講演:岡部明美さんの「魅力あるリーダーとは?」次回は、5月18日(金)~20日(日)栃木県那須塩原の「那須高原ビール」のホールで開催されます。
2007年04月20日
コメント(0)
-
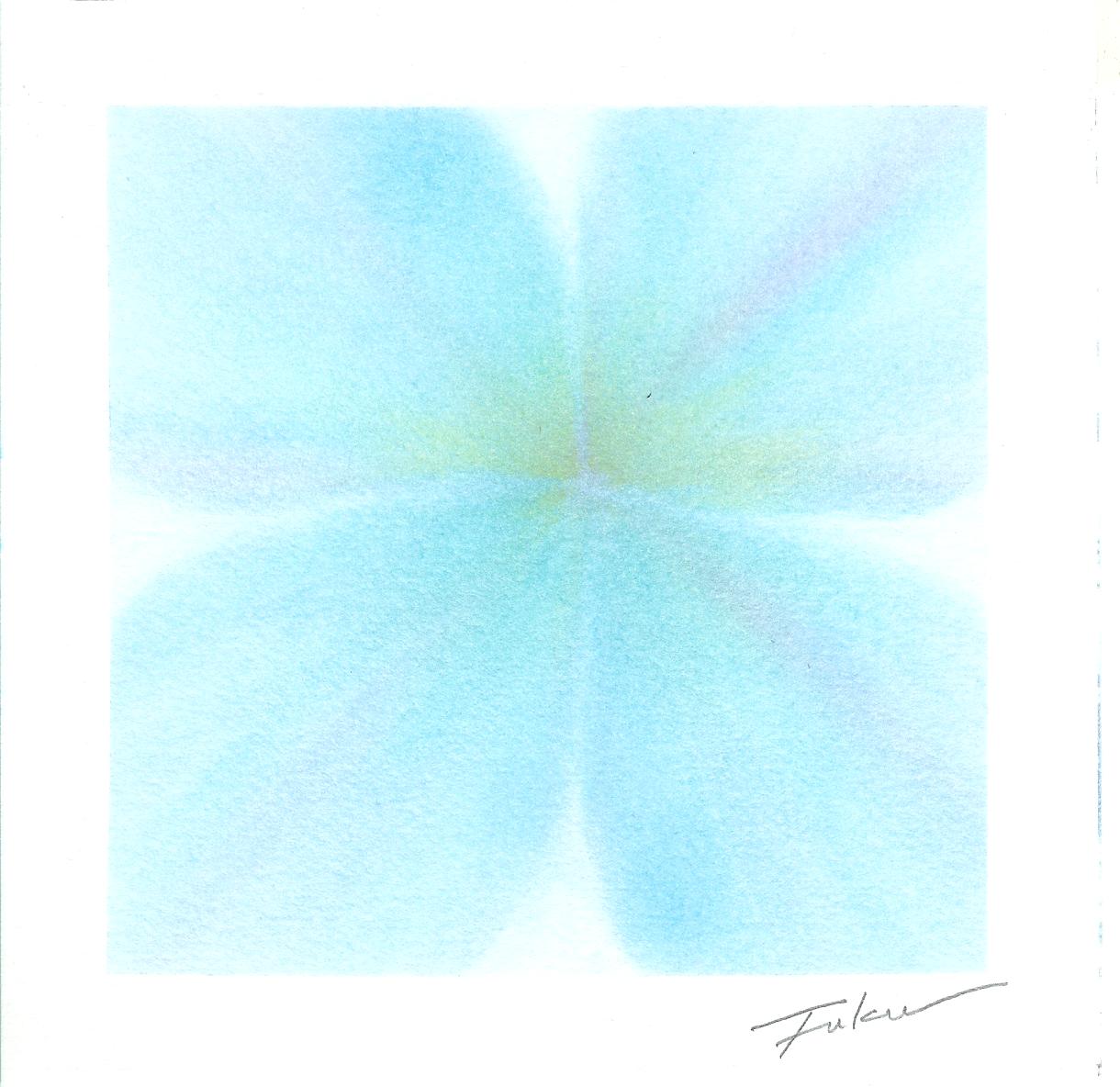
やってみなけりゃわからない
人間はみな自分だけの天分・素質(才能・役割・使命)を持って生まれてくる。その天分・素質は、“肉体と感性”を使わなければ発見できない。肉体を使うというのは体験すること。行動すること。どんなに野球が好きでも、テレビを見ているだけでは自分に野球の才能があるかどうかはわからない。やってみなければわからないのである。作家になりたかったら自分の文章を書き続けること。絵描きになりたかったら絵を描き続けること。本当にそこに自分の才能があったら、必ずそれを評価してくれる人が現れるものである。<天分・素質を発見する5つの方法> 1)やってみたら、好きになるかどうか。 2)やってみたら、興味、関心が湧くかどうか。 3)やってみたら、得手、得意と思えるかどうか。 4)やってみたら、他人よりもいつも自分の方がよくできるかどうか。 5)真剣にやってみたら、“問題意識”が湧いてくるかどうか。この5つの方法で見つけていくのです。どれが一番天分の多いところか。一番強烈な実感が湧いてくるところが天分のツボ。いのちの使いどころ。一流、オンリーワンの仕事をしている人は、みなこれらのツボを特化させて努力してきた人である。時に、この5つが全部当てはまる仕事をしている人がいるがそうなったら笑いの止まらない人生になるのである。とにかく、自分の天分・素質があるものをとことんやってみるのです。無心になって寝食を忘れて、損得を超えて。しかし、成長すればするほど、新たな限界、壁にぶちあたります。一流、本物、オンリーワンと言われる仕事をしている人というのはみな、次々にやってくる壁や限界に挑戦し続けてきた人であり、何度失敗を重ねても、常に失敗から何かを学び、教訓を得て、次に活かし続けてきた人である。成功した人というのは、成功するまで、あきらめなかった人なのである。人間の天分・素質というのは潜在能力である。ゆえに限界まで努力し、壁にぶつかった時がチャンス。「もう万策尽き果てた。もうダメだ、限界だ」とどん底でうめいて、もがいて、それでもあきらめきれずにもう一度挑戦してみた時にその人の潜在能力が突然目覚めるのである。限界を感じた時に、そこであきらめてしまうのか、もう一度挑戦してみるのかでその後の人生が大きく変わってしまうのである。多くの人は壁にぶつかった時に、これは自分の道ではなかったとあきらめてしまう。だから潜在能力としての本当の才能が開花しないのである。
2007年04月19日
コメント(0)
-
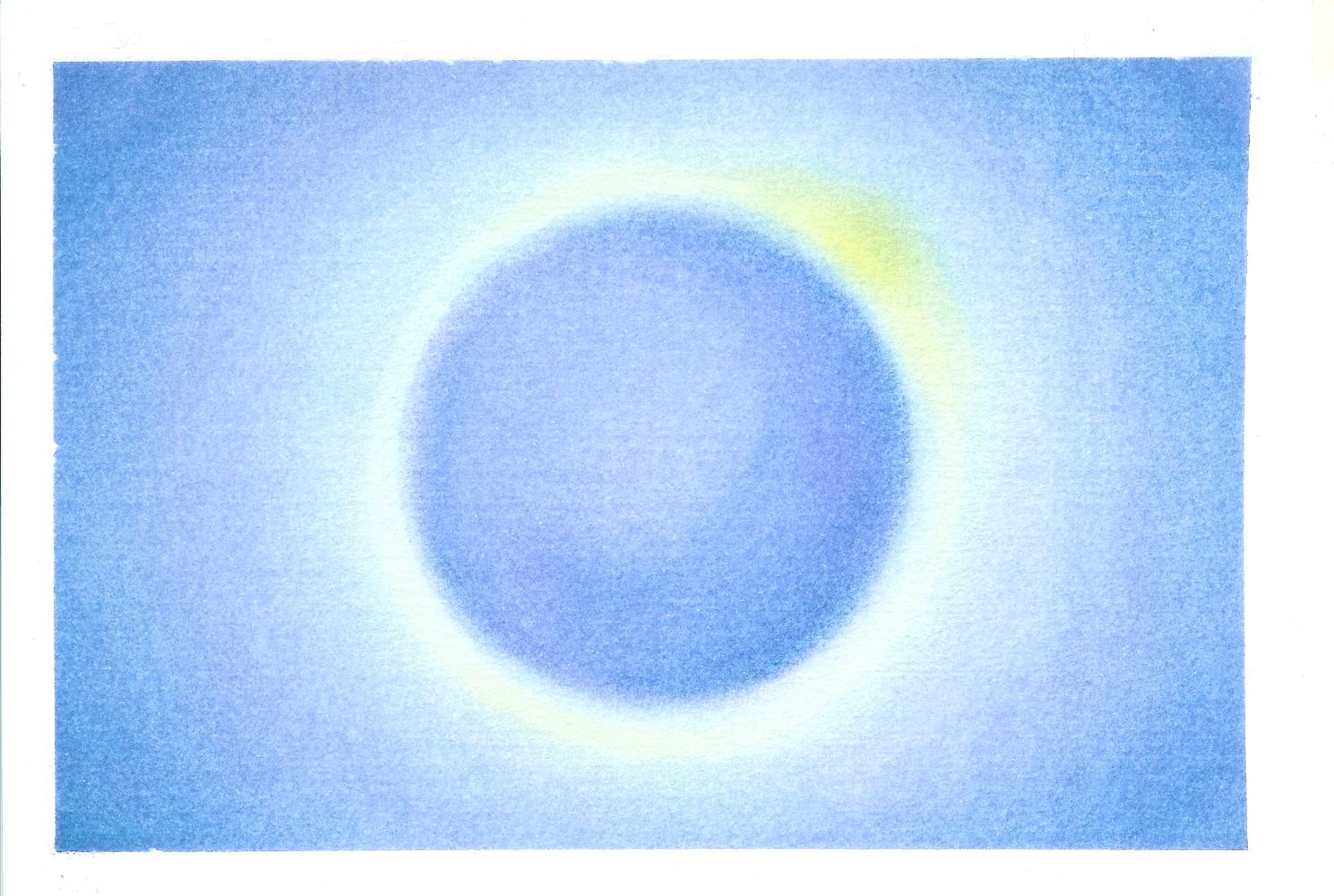
矛盾を内包した人生を生きる
「責め合ったら地獄・許しあったら天国」。天国も地獄も自分の心の中にある。自分の心が人生を創り出しているのである。相手を責めている間は、人は成長できない。自分と価値観が合う人、自分をわかってくれる人、自分を愛してくれる人、自分と気が合う人としかつきあえない人間は、自分しか愛せない人間なのである。考え方の違い、価値観の違いで、人間は対立ばかりしている。精神性の高い本物の人間は、対立する人間から、自分とは違う物の見方、考え方、感じ方を学んでさらに自分を成長させる。そういう人間こそが、真に懐の深い人間なのである。人間は矛盾を内包し、矛盾を生き切るしかない存在であることが本当にわかっている人が真に愛のある、寛容で、包容力がある人間なのである。
2007年04月18日
コメント(0)
-
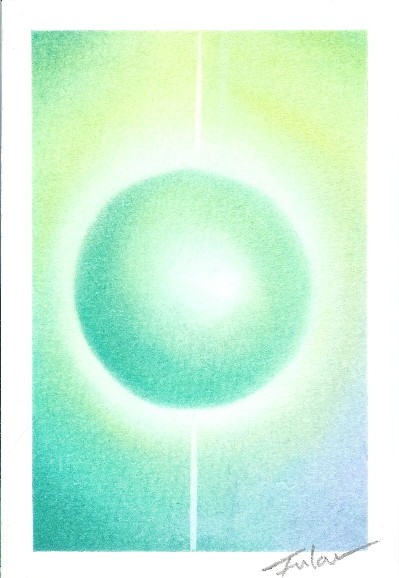
感性論哲学の目的は、全人類の“人間性の進化”である。
感性論哲学は、宇宙が人間に与えたものはすべて生かしきる哲学である。理性・感性・肉体・欲求・欲望・人生の苦悩・トラウマ・葛藤・問題。これらをどう解釈し、どう生かし切り、どう正しく使えば人間として成長し、本物の男や女になり、幸福に生きられるかを学ぶ学問である。肉体を蔑み、欲求や欲望を否定し、無欲であることを強いた宗教もまた理性による支配の呪縛から逃れられなかったのである。宇宙から与えられたものはすべて必要があって与えられているのである。それをどう使うか、それから何を学ぶのか、それをどう活かし切るかというところに人間の成長があるのである。感性論哲学の目的は、全人類の“人間性の進化”である。全人類の人間性を、もう“一次元進化”させることによって、不完全な人間同士が、共に助け合って生きてゆける本当に素晴らしい世界を創ってゆくことである。
2007年04月17日
コメント(0)
-

愛の実力意志の力
問題のない、悩みのない人生はない。人生とは問題を引き受け、悩みを乗り越え続けていくことである。人間は、問題のない悩みのない人生を望んではならない。時代は明らかに、画一性の時代から個性の時代へと移行している。しかし人類の人間性は、まだ、残念なことに、同じ考え方や同じ価値観の人間としか、いっしょに仕事をし共に生きて行くことが出来ないという段階にある。だから、ちょっとした考え方や感じ方のちがいで夫婦は離婚をしてしまう。これは問題を避け悩みから逃げているのである。宗教のちがいや思想のちがいや価値観のちがいで、人類は憎しみあい対立し戦争をして殺しあっている。問題のない人生を望むことが、かえって人間に不幸と災いをもたらすのである。こんなことでよいのか。個性の時代というのは、お互いに考え方のちがいを認めあい、考え方の異なる者が互に助けあい協力しあって生きていく時代ということである。だから個性の時代には、問題や悩みを乗り越える為に、理屈を超えた愛の力が要求されるのである。人類は、いつまでも矛盾を排除し画一性を追求する理性に支配されていてはならない。理性は人間の為にあるのであって、人間が理性の為にあるのではない。考え方のちがいで人間が戦争し殺しあってはならないのである。 『意志の力・愛の実力』芳村思風著 はじめに より。
2007年04月16日
コメント(0)
-
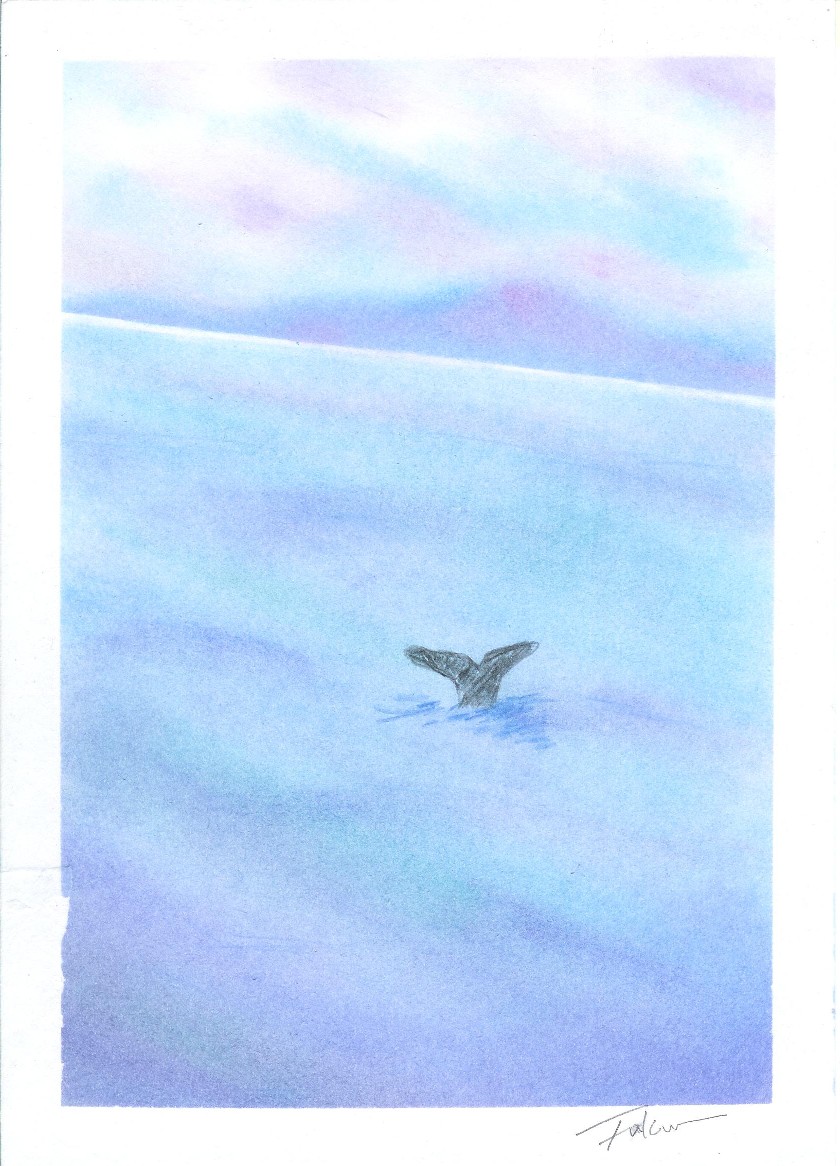
感動
「感動」こそが人を変える。人は感動した時に動く。「理動」という言葉はない。なぜなら人間の本質は感性であり、感性の実感はまぎれもない真実であり、その真実から発せられた言葉こそが人の胸に突き刺さり、人に影響を与えるからである。理性は説得の論理。感性は納得の論理である。人は深く全身で納得できたときに行動が変わっていくのである。
2007年04月14日
コメント(0)
-

問い続けること
感性論哲学には、忘れてはいけない原理原則と「問い」がたくさんあります。異和感があるところに自分の進むべき道がある。感性から湧いてくる異和感に、理性を使って「答え」をだす。答えに縛られず、さらにもっといい答えはないかと、感性で感じること。常に自分に「問い」を発し続けることが大切です。「問い」を集めてみました。「原理原則」を疑問形にすると、「問い」になります。□天分素質の発見方法 5つの問い1.やってみたら、好きになるかどうか2.やってみたら、興味関心が湧いてくるかどうか3.やってみたら、得手得意と思えるかどうか4.やってみたら、いつも人よりうまくできるかどうか5.真剣にやってみたら、問題意識が湧いてくるかどうか□人生における3つの問い1.将来どんな人間になりたいのか・・・いかに成るべきか2.将来どんな事をしたいのか・・・・・・いかに為すべきか3.将来どんな生活をしたいのか・・・・・いかに在るべきか□脱近代の人間性を作るための6つの問い1.理性を正しく理解しているか2.理性と感性の関係を正しく理解しているか3.知恵を活用しているか4.勝つことよりも力を合わせることのすばらしさを理解しているか5.人生観・生き方の変革を進めているか6.感性的な判断基準を重要視しているか時流独創の精神 6つの問い1.自分の心を本当に納得させるものを理屈ぬきに追い求めているか?2.固定観念・先入観念から自分を解放しているか?3.自分の使命は何であるかを知っているか?知ろうとしているか?4.命から湧きあがる欲求・欲望・興味・関心・好奇心を持っているか?5.現実への異和感を大切にしているか?6.有機的統合能力を磨いているか?時流独創の経営 6つの問い1.独創的技術の確立をしているか?2.独創的商品の開発をしているか?3.独創的職業領域の発見をしているか?4.独創的営業分野の開拓をしているか?5.独創的改良改革への提言をしているか?6.独創的経営システムの構築をしているか?□人生の鉄則からの5つの問い「成功への5つの階段」1.信じるに足る自己をつくっているか2.自分で自分を教育しているか3.限界に挑戦しているか4.決断に賭けているか5.意味と価値の確認しているか□本物の人間になるための3つの問い1.不完全性の自覚からにじみ出る謙虚さを持っているか2.より以上を目指して生きているか3.人の役に立つ人間になっているか
2007年04月13日
コメント(0)
-

環境の変化が命を進化させる
命の進化とは、自分の中に眠っていた潜在能力の遺伝子のスイッチがONになること。それまで出来なかったことが、できるようになる。遺伝子研究の権威である筑波大学の村上和雄先生は、「若い時にアメリカに渡ったことが今の自分を作った。日本にいたら、今の自分はなかったかもしれない」とおっしゃっています。日本からアメリカに渡るという、環境を変えることで、眠っていた遺伝子のスイッチがオンになったのです。環境の変化が少ないガラパゴスの動物たちは、太古の姿を持ち続けています。住んでいるところを変えるのも、心機一転自分を変える一つの方法。地位が人を作るということもある。自信がなかったけど、会社を立ち上げてみたらそれなりの仕事や風格ができてきたという人もいます。順調だった仕事が、社会環境の変化、流通経路の変化やインターネットの発達で、うまくいかなくなることもあります。行き詰まりを感じたとき、停滞を感じたとき、自ら環境を変えてみる。やり方をまったく変えてみることで、新しい道が見えてくることもあるのです。世の中が変化しているときこそ、進化発展するチャンスと思うことが大切です。
2007年04月12日
コメント(2)
-

信じて、信じて、信じぬく
人間は、信じられないものであることを自覚する。 ウソも言う。裏切ることもある。失敗もする。 罪も犯す。 「信じられないものを、信じると決断する」 矛盾を内包する真実を生きる。 だまされても傷つかない心を持つ。 人間だから、ウソをつくことも、 裏切ることもある。 だまされても、裏切られても、 自分ひとりだけでも信じられるかどうか。 簡単にできることではない。 だまされたら、腹が立つ。 裏切られたら、悲しい。 それでも、一度信じた人を信じぬけるかどうか。 簡単に出来ない。相当の覚悟がいる。 理屈では考えられないことをできるかどうか。 理屈では考えられない決断が、 最高の愛の世界を作る。 矛盾を内包した真実の世界を生きる。 子どもがウソをついたとき、 「お父さんが悪かった。」と 子どもに謝り、抱きしめることが出来るかどうか。 ウソをつかなければならない状況を自分が作ってしまった。 そう思えるかどうか。 「でもウソをついてはいけない」と子どもを叱るのは、 その後。 「人間は不完全である」を知る。 これを知り、実践していくとはどういうことか。 だまされたり、裏切られて相手を責めるのは、 人間に完全を求めている。 意識せずにそうなってしまうこともある。 誰が何と言おうとも自分だけは、この子のことを信じる。人間が不完全であることを認め、 不完全を許した時、 人間の最高の愛の姿がそこにある。 信じて、信じて、信じぬく力を持つ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ここからは、テレビで見た話。ビートたけしが、ある番組で話していた。「島田洋七だけは、どんなことがあってもオレは信じる。」たけしが、事件をおこして、テレビから干されているとき、取材攻勢から逃れるために沖縄の離れ島にいた。売れている時、周りに居たたくさんの人が、事件をきっかけに、ほとんどが消えていった。洋七だけは、用も無いのに、東京から飛行機を乗り継いで、何回もそこまで来てくれた。ただ顔をみるだけで、ほとんど話をせずトンボ返りで帰ることもあったらしい。いい時も悪い時も同じように接してくれる人間は、数少ない。「あいつと付き合っている」というだけで、批判されることもある。それでも友人として、損得関係なしに変わらない態度で接してくれた。こんな話をしみじみと語っていました。
2007年04月11日
コメント(1)
-
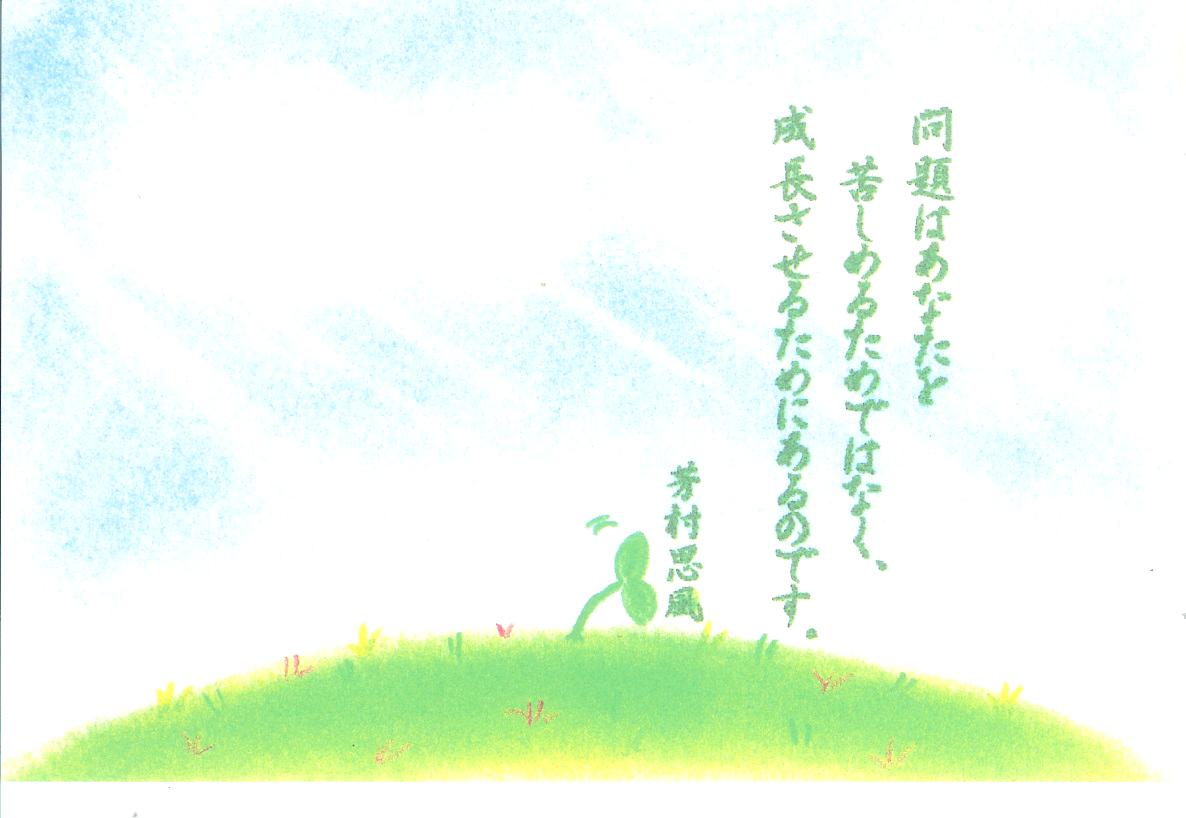
天はオレを大人物にしようってか
問題は、自分自身を成長させるために出てくる。大きな問題を乗り越えれば、それだけ大きく成長できる。大きな問題が起こったときは、「天はオレを大人物にしようってか!」と考える。命の痛みの体験を通して、命が磨かれる。プロとしての自覚が生まれてくる。人間の命を磨くのは、実業しかない。自分の感性で選んだ道が最高のものを選んだという自覚を持て!感性で選んだものに誤りはない。頭や理性で判断するから誤る。直感は意味があるから「ひらめく」。そうして決めた選択に自信を持って、捨てた選択肢のことは、きっぱり忘れる。どの道を選んでも問題はある。やっぱり別の道を選べば・・・と悔やむようでは、まだ断ち切れていない。決めたけど、断てていない。断ち切らなければ、決断ではない。「にげたらあかん!」●第15期「感性経営問答塾」 平成19年4月20日(金)~22日(日) 東京 京王プラザホテル 開催3日間で、感性経営の5原則の集中講義と実践に活かすための数々の方法を学びます。特別講演:岡部明美さんの「魅力あるリーダーとは?」ありがとうございます
2007年04月10日
コメント(0)
-

感性論哲学は、人間学
「感性論哲学」は、人間学です。これからの時代に必要ものがすべて入っています。哲学は、ヨーロッパの哲学者の言葉や業績を研究するのではなく、人間学として、実践に役立たなければ何の意味も無い。感性の本質は、同じを探す。理性は、違いを探す。理性は矛盾を無くそうとする。違いを探し、違いを無くそうとする限り、戦争はなくならない。感性と理性のバランスではない。感性だけで行動するのは、野獣と同じ。感性と理性を協力させなければならない。感じたのもを、理性を使ってどう人間らしくするか。感性型人間とは、感性を理性を使って成長させている人間のこと。理性を使わないと、感性は成長しない。この宇宙に存在する物は、すべてプラスとマイナスの両面を持っている。表・裏善・悪前・後上・下表がよくて、裏がわるいのではない。短所も長所必要。善だけの世界は無い。欠点も、犯罪もなくならない。善が、悪を作っている。これが「正しい」と決めるから、「間違い」がある。すべての基準は、時代によっても変化する。人間は罪を犯すものという事を知ったうえで、罪を犯すことはよくないこと、どうすれば罪を犯さなくなるか考える。罪を犯した人の気持ちは、罪を犯した人でなければわからない。罪を犯してもよいということではなく、その気持ちを察することが大切なこと。矛盾もなくならない。矛盾を内包した真実を生きる。感動の中に、真理を越えた真実がある。
2007年04月09日
コメント(0)
-
答えに縛られない
理性は答えを出す力感性は問う力感性が問い、理性が答える答えを持つことは大切もっと大切なのは、「これでいいのか」と問い続けること答えに縛られないこと縛られると、違う考え方の人を説得しようとする違う考え方の人と対立する感性論哲学は、どんな考え方・意見も否定はしない相手の考え方・意見のいいところ、自分の考え方にないところ、を取り入れて、自分の考え方・意見を成長させる。・・・・・・答えを出すことが一番大事だなことではない。「これでいいのか」と問い続けること。答えに縛られないこと。20世紀までは、「説得の論理」自分と違う考え方や意見を説得しようとし、相手の意見を否定し、説得・論争をし、自分の考え・意見の正しさを主張してきた。ディベートでは、常に勝ち負けを競っていた。人間関係の破綻はすべて競争意識から始まる。戦争は、自国の主張の正しさを主張することから始まる。21世紀は、「納得の論理」。勝つだけではダメ。相手を説得するのではなく、納得させること。大切な事は、勝つことよりも力を合わせること。力をあわせて、共に成長すること。人間は不完全だから、完璧なものは作れない。相手の意見・考えのいいところを取り入れ、自分の意見・考え方もよりよいものに成長させお互いに成長すること。講義の中での芳村思風先生の話。「感性論哲学もすべて受け入れなくてもいいんですよ。自分の気に入るところ、合うところだけを今の自分に必要なところだけを取り入れたらいいんですよ。すべてを取り入れたら、自分がなくなります。感性論哲学も進化・発展しています。」
2007年04月08日
コメント(1)
-
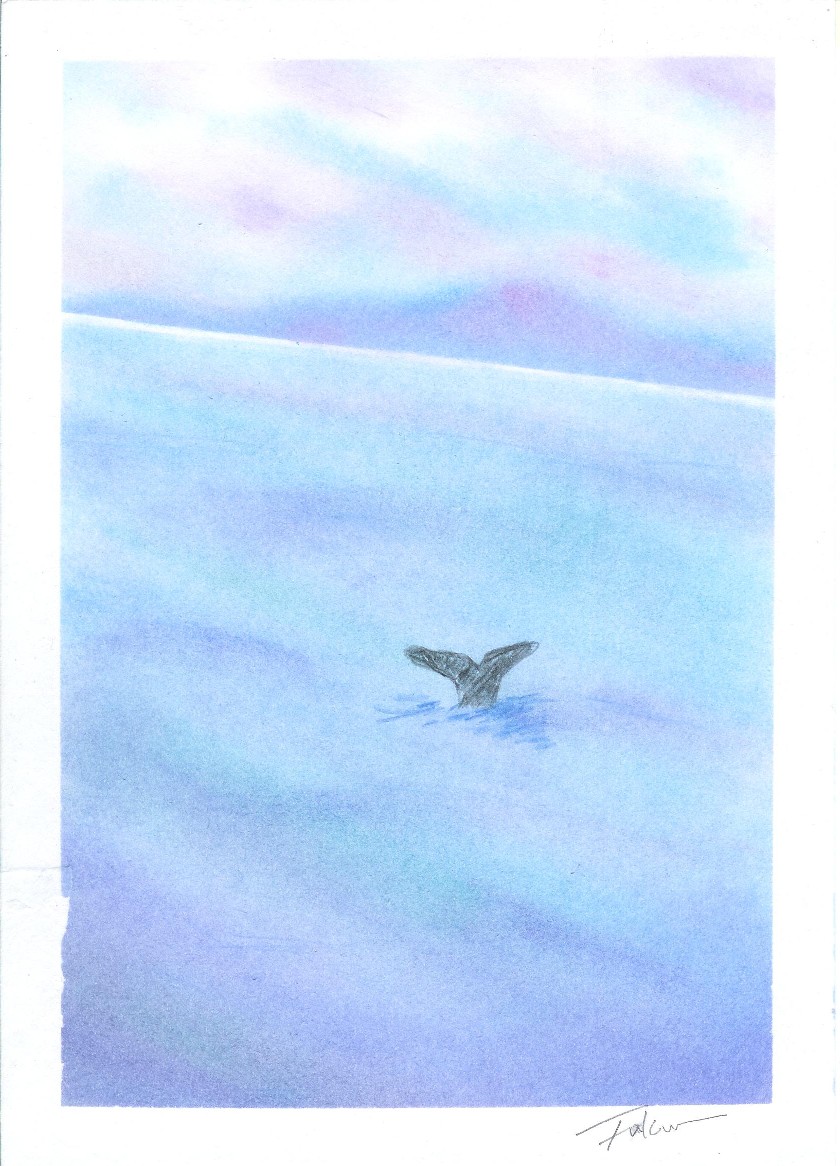
満足から感動へ
人は、感じたら動く。「感即動」とは、「感じたら、すぐに動く」という意味だけではない。「感じさせることで、人は動く」という意味がある。感じさせなければ、人は動かない。理性で説得しても、人は動かない。「理動」という言葉はない。顧客を動かそうと思ったら、感動を届ける。感動させれば、固定客になってくれる。人を紹介してくれる。これからの時代、「顧客満足」ではなく、「顧客感動」をめざす。感動させる力を持ち、感動させうる人間となる。何が人を感動させうるか1.不撓不屈の意志2.深い愛。理屈を超えた人間愛。他者中心的な愛。3.作為を超えた人間の姿。一所懸命な姿、真剣な姿。4.人間の高さ・深さ・大きさ。 高さ・・・・高貴さ 深さ・・・・より根源的、より本質的な意味や価値を感じ取る感性。 大きさ・・・人間の器、統率力5.ユーモアのセンス 状況をプラスの方向に導けるような感性。
2007年04月07日
コメント(0)
-
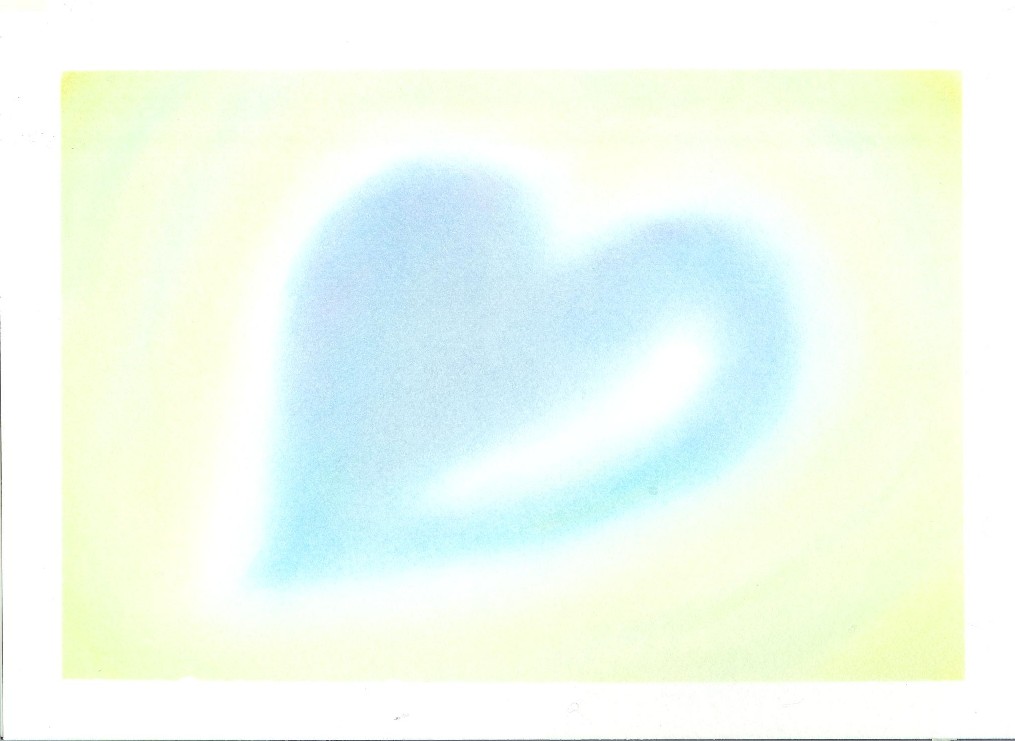
愛の実力
愛とは短所を許し補い、長所と関わる力である。古来より、「愛」は、文学の中でしか扱われていなかった。学問として体系化されていない。1000年前から、同じことを繰り返してきている。いつの時代も男女の関係・親子の関係で、人は悩み続けている。感性論哲学では、愛を能力としてとらえ、実力として成長させるものとして考えています。感性論哲学は、「愛の哲学」。争いや戦争が絶えない今の世の中に必要な学問である。「愛」の究極の目的は、「すばらしい人間関係をたくさん作ること」以下は、「愛の実力」の講義やその他の講義の中で思風先生が「愛」について話された言葉の抜粋です。愛とは感じるもの 愛とは信じること愛とは許すこと愛とは肯定すること。理屈を超えた肯定の心。愛とは認めること愛とは相手の成長を願う心情新しい精神文明の核となるもの愛は理屈を超える力。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者と共に生きる力愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛とは「どうしたらいいのだろう?」と悩む心、考える心。人間を愛するということは、不完全な存在(長所半分・短所半分)を愛するということ。短所を許すことから、人間の愛が始まる愛は人間関係の力である。人間関係の基本は愛。結婚は恋の墓場であり、愛の始まりである。人間を愛するというのは不完全な存在を愛するということ。不完全とは、どんな人間でも長所半分・短所半分。愛するとは許すこと。相手の短所を許し、長所を見つけてほめて伸ばしてますます好きになる。長所が伸びたら短所は人間の味に変わる。自分と同じ考え方の人しか愛せないのは、偽者の愛。それは自分しか愛せない愛である。愛は本来、他者を愛するために存在する。愛とは 命の能力である。命は愛によって生み出され、育まれ、満たされる。愛とは人間と人間を結びつける力。愛とは他者中心的な心の働き、思いやりである。愛は理性を使った努力。愛するとは、相手から学ぶこと。相手のために努力できるということが「愛」があるということ。相手のために努力できないのは「愛」がないということ。包容力は、愛。今、一番人類に必要とされている能力4月7日(土)の「東京思風塾」は、岡部明美さんがゲスト。13:00~1800までは、芳村思風先生の講義。18:00~20:00まで、お二人の対談です。岡部明美さんが、SQライフに芳村思風先生との出会いから、感動した言葉などを書かれています。4月7日(土) 13:00~東京思風塾※会場が狭いため、事前にお申し込み下さい。思風塾ホームページ
2007年04月06日
コメント(0)
-

「和道」と「悟道」
近代の民主主義社会は、「自由と平等」を理念に掲げて発展してきました。では、脱民主主義に続く「互敬主義社会」では、どういう理念になるのか?それは、「和道」と「悟道」というものになると考えます。現在の対立構造を乗り越えるために一番大切な理念になるのは、「平和」です。これから平和を全世界・全社会・全家庭につくっていかなければなりません。この平和を具体的な理念として掲げた言葉が、「和道」です。東洋の「道」の思想を原理として、「みんなが和して生きていく道を探る」というのが「和道」という理念です。そして「悟道」は、「人類の人間性をもっと進化させ、発展させていく」ための理念になります。人間が人格的に進化することがなければ新しい時代をつくっていくことはできません。科学技術がこれほど進歩して、物質的に豊かになったにもかかわらず、人類の人間性はまったくと言っていいほど進歩していません。これから数百年かけて、人類は自らの人間性を成長させ、発展させ、進化させていくことを大きな目標に掲げて生きなければなりません。豊かな物質文明とバランスのとれた豊かな人間性をつくっていかなければなりません。そのための理念が、「悟道」なのです。4月7日(土)の「東京思風塾」は、岡部明美さんがゲスト。13:00~1800までは、芳村思風先生の講義。18:00~20:00まで、お二人の対談です。岡部明美さんが、SQライフに芳村思風先生との出会いから、感動した言葉などを書かれています。4月7日(土) 13:00~東京思風塾※会場が狭いため、事前にお申し込み下さい。思風塾ホームページ
2007年04月05日
コメント(0)
-

問い
人生において、自分の問いを持ち、自分の言葉を持つというほど大事なことはない。人間が本物になっていくためには、誰から教えられたものでもない、誰から問われたのでもない、「自分の問い」を持つ。その問いに答えるべく、いろいろ努力していく。そのことによってしか、本当の自分には到達できません。何を問うかによって、出てくる答えは決定されてしまう。「いかに在るべきか、いかに為すべきか、いかに成るべきか」という高度な理念への問いは、実は理性によってむ高められ、高度に人間化された人間的感性からしか出てこない問いです。本質への問いが、人格の深さをつくる。理念への問いとは、「「いかに在るべきか、いかに為すべきか、いかに成るべきか」であり、「人間にとって真実の愛とは何であろうか」「人間にとって本当の勇気とは何であろうか」という問い。答えを持つことは必要である。答えはひとつではない。固定するものでもない。常に、「問い」を持ち続けること。自分自身に問い続けること。常にもっといい答えはないかと模索し続けることが大切なことである。【人生における3つの問い】1.将来どんな人間になりたいか?2.将来どんなことをやりたいか?3.将来どんな生活をしたいか?常に自分自身に問いを発すること。1.人間として、いかに成るべきか?2.人間として、いかに為すべきか?3.人間として、いかに在るべきか?「人間」のところを「父親・母親」や「経営者」「教師」などに置き換えて考える。【人生の鉄則からの5つの問い】1信じるに足る自己を作っているか?2.自分で自分を教育しているか?3.限界への挑戦をしているか?4.決断に賭けているか?5.意味と価値を確認しているか?【これからの時代の人間性をつくるための6つの問い】1.理性を正しく理解していいるか?2.理性と感性の関係を正しく理解しているか?3.知恵を活用しているか?4.勝つことよりも、力をあわせることのすばらしさを知っているか?5.人生観・生き方の変革をしているか?6.感性的な判断基準を大切にしているか?【天分を見つける5つの問い】1.やってみて、好きになれるかどうか?2.やってみて、興味関心が持てるかどうか?3.やってみて、得手・勝手と思えるかどうか?4.やってみて、他人よりうまくできるかどうか?5.真剣にやってみたら、問題意識が持てるかどうか?【人格を鍛える3つの問い】1.人格を高める努力をしているか?2.人格を広くする努力をしているか?3.人格を深める努力をしているか?【人間成長の原理からのふたつの問い】1.新しい気づきを積み重ねているか?2.潜在能力を顕現させる努力をしているか?
2007年04月04日
コメント(0)
-

激変の時代
第一の過渡期とは、古代と中世との間に横たわるギリシャ・ローマ時代第二の過渡期とは、中世と近代の間にある過渡期であるルネッサンス第三の過渡期とは、まさに今の時代現代は、「数万年単位」「数千年単位」「数百年単位」の大変化が同時進行で起きているという人類史始まって以来の大激動の時代である。それぞれにどのような変化が起きているのかを正しく理解できていないリーダーや、精神の目覚めを体験し、より高い次元から人間とこの世界を見ることのできないリーダー、人を感動させることができないリーダーは、はもはや人を導き、組織を活性化し、創造していくことはできない。☆数万年単位で起こっている3つの変化1.地球時代から宇宙時代への変化 技術の進歩により、宇宙から地球を見るという新しい視点を持つが出来た。 このことによる価値観の変化。 「地球は、ひとつ」という意識が人類共通のものと。なった2.縦型社会から横型社会への変化 人間が人間を支配するという構造が崩れ始めた。 男性が女性を支配するという構造が崩れ始めた。3.弱肉強食から適者生存への変化 競争という原理から、創造という原理へ変化してきた。 他人に勝つことを喜びとする心情は、これからの共生社会にはそぐわない。 「勝ち組み」といわれる企業は、独創的な想像力で勝っている。☆数千年単位で起こっている3つの変化1.理性原理から感性原理への変化 人間の感性から理屈ぬきに湧き上がってくる本能・欲求・興味 関心・好奇心などを、理性によって支配しようとして、 ストレスが生れ、さまざまな精神病理現象を起す。 「理性としての私」と「本能としての私」といった 二元論的な人間観を持ち続けてきた。 大事なのは、「私は二人いない。たった一人しかいない」 という意識をどこに置くか。 精神と肉体を根源的に統一している原理とは何か。 感性論哲学は、その原理こそ感性であると考えます。 「感性が肉体と精神を作り、感性が肉体と精神を根源的に統一している。」 2.地域文明から世界文明へ 地球全体がひとつの文明圏という状態へ変化しつつある。 さまざまな分野で地域文明の融合現象がでてきた。 3.二元論的人間観から一元論的人間観への変化 「人間は精神的な実体と肉体的な実体が結びついたものである」 二元論的な人間観から、「心身は一体である」という有機的な生命観となり、 「肉体は、目に見える精神である。精神とは目に見えない肉体である。」 という考え、精神と肉体は一体化した形で有機的な生命として生きており、 単に機械論的な生命観によって理解できないとした。 しかし、身体論は精神と肉体を根源的に統一する原理を見つけられなかった。 感性論哲学では、「われわれが、私といっている実体とは感性のことだ」 と論証した。 「人間の本質は感性であり、生命の本質も感性である。 感性宇宙の究極的実在も感性である。 感性が精神を作り、感性が肉体を作る」 これにより、まったく新しい一元論的人間観がつくり上げられた。☆数百年単位で起こっている3つの変化1.政党政治から脱政党政治へ、そして互敬主義社会へ2.資本主義経済から脱資本主義経済へ、そして人格主義社会へ3.理性文明から脱理性文明へ、そして感性文明へいま、世界文明の中心は、欧米から日本の真上へと来ている。日本人は、この第3の過渡期を担なえる唯一の存在である。現代の文明を完成させ、集結させる。そして、新しい時代に向かうため、それを壊していく。あらゆるの言語・宗教・文化・音楽を受け入れ、融合統合させ、さらに発展させてきた日本だからこそ出来る東洋文明と西洋文明の融合・統合。唯一の被爆国からの世界平和の発信。日本人にしか出来ないことがある。21世紀は、日本の時代。新しい時代を作るための、過渡期である「脱近代」の歴史は、日本がつくらなければいけない。その中心は、やがて中国・韓国へと引き継がれ、インドへと移っていくであろう新しい時代の礎を今、日本がつくっているのである。
2007年04月03日
コメント(0)
-

矛盾を内包する真実を生きる
理性は“完全性を求める能力”。矛盾や不完全性を許せない。理性は、自分と異なる考え方、感じ方、価値観を許しがたいのである。しかし、人間というのは、「不完全で矛盾に満ちた非合理な存在」である。欠点もある。間違いも犯す。至らないところもある。失敗もする。裏切ることもある。心ならずも嘘をつくことだってある。それが人間なのである。嘘をつきたくてつく人などいない。失敗したくて失敗する人などいない。人間は不完全で、矛盾だらけの非合理な存在であることが腹の底に落ちるまでは、人は、自分を許すことも、人を許すことはできない4月7日(土)の「東京思風塾」は、岡部明美さんがゲスト。13:00~1800までは、芳村思風先生の講義。18:00~20:00まで、お二人の対談です。岡部明美さんが、SQライフに芳村思風先生との出会いから、感動した言葉などを書かれています。4月7日(土) 13:00~東京思風塾※会場が狭いため、事前にお申し込み下さい。思風塾ホームページ
2007年04月02日
コメント(0)
-
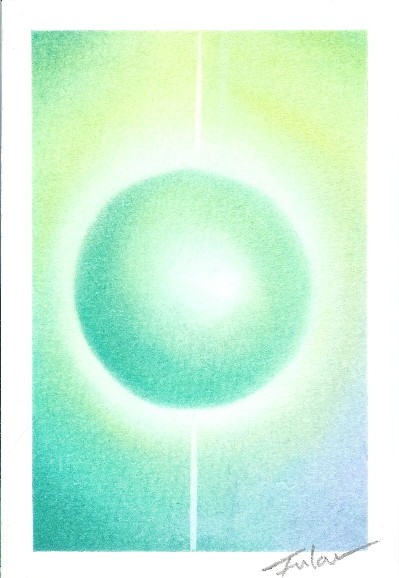
岡部明美さんとの対談
なぜ人間は肉体を持って生まれるのか。それは体験するためである。あらゆることを体験するために肉体を持って生まれたのである。真実は体験なしには語れない。体験のない学びは観念である。ゆえに、人生のどんな体験も、すべては貴重な経験であるのだから、人生には失敗などないのである。 肉体を持って生まれた人間は、人間性を成長させるために生まれたのである。神さまのような完全無欠性を求める人は、人でなしなのである。人間はみな 長所と短所を半分づつ持っている。短所はなくしてはならない。自分には半分の短所があるという自覚こそが謙虚さをつくり、他者から学ぶ姿勢を作り、人と力を合わせて生きることを学ばせてくれるからである。「I WILL フォーラム」というセミナーがある。芳村思風先生と岡部明美さんの二人の講師で5年前から、「愛の実力 意志の力」をテーマに思風先生の講義と、岡部明美さんの体験体感ワークの組み合わせで、2泊3日を2回、2ヶ月間で、実施している。3月で、通算15回。卒業生は、300名近くになっている。12年前は、岡部明美さんも受講生の一人に過ぎなかった。その後、いろいろな勉強体験を重ね、岡部明美さんは、執筆・講演・ワークショップというセミナー活動をされていました。5年前、東京思風塾の中で、『思風先生と岡部明美さんが一緒にセミナーをやれば、面白いものが出来るのではないか』という受講生の意見から生れたセミナーです。4月7日(土)の「東京思風塾」は、岡部明美さんがゲスト。13:00~1800までは、芳村思風先生の講義。18:00~20:00まで、お二人の対談です。岡部明美さんが、SQライフに芳村思風先生との出会いから、感動した言葉などを書かれています。4月7日(土) 13:00~東京思風塾※会場が狭いため、事前にお申し込み下さい。思風塾ホームページ
2007年04月01日
コメント(1)
全28件 (28件中 1-28件目)
1










