2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2007年06月の記事
全29件 (29件中 1-29件目)
1
-
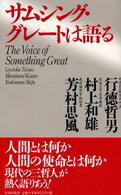
サムシンググレートは語る(致知出版)
2002年に致知出版より出された「サムシンググレートは語る」村上和雄先生・行徳哲男先生・芳村思風先生の鼎談をまとめたものです。(一部抜粋) ●思風塾ホームページ上記思風塾ホームページの「参考図書リスト」をご覧下さい。「21世紀人間の進むべき道」人間とは、素晴らしい可能性を秘めた存在である。これが3人に共通の思いである。科学、哲学、教育の分野で人間とは何かを探究し、それぞれの道を掘り下げるうちに、理性を超える何かにぶつかった。それは「サムシング・グレート」であり、あるいは「感性」と呼ばれるものだった。一道を究めた3人が語る人間賛歌と人間が進むべき道。■時流に乗れた遺伝子の研究村上 師との出会いという意味では、私は京都大学時代に、平澤興先生にお会いしたことが大きいですね。ノーベル賞の湯川秀樹さんと並び称された大学者ですが、単なる学者ではなく、大自然の不思議に頭を下げておられた。 私がサムシング・グレートというものを意識するようになったのは平澤先生にお会いしたことが大きい。私がやってきたことは生き物を科学的に研究しようということです。体の中でも最も重要なものの1つは酵素。その酵素をつくり出しているのが遺伝子であり、その中の遺伝子情報なのです。 遺伝子は研究すればするほど不思議です。ミクロの中に万巻の書物が書き込まれているのですから。人間のゲノムは大体30億の化学の文字が書かれている。そして、私たちの体の中の超ミクロの世界が一刻の休みもなく活動しているものがあります。その主体は自然です。山川の自然ではなく、目に見えない自然であり、それをサムシング・グレートと名付けたのです。 私が今一番やりたいことは、意識か心とか、つまりメンタル・ストレスによって遺伝子のスイッチをオン・オフすることがコントロールされ得るかということです。私は絶対にできると思っているんですが、証拠がまだありません。■感性論哲学で開眼行徳 私は昭和35年4月、ある財閥系の企業に入社し、いきなり労働争議の紛争整理でした。私は学生時代からイデオロギーは勉強していませんでしたから、最初は無惨に打ちのめされましまた。団体交渉の組合代表は百戦錬磨です。 当時の労働運動はイデオロギーに毒されていました。イデオロギーでは人間は救われない。それを超える世界があるはずだと模索していた時に、芳村先生の本と出会ったのです。「弁証法との決別」のタイトルに衝撃を受けました。「考え方、、すなわちイデオロギーが人間を決めるんじゃない。感じ方こそが人間を決める」というのは、まさに私の実践を裏打ちしてくれる哲学だったのです。そこから「偉大なる思想は心情より発す」の世界にたどりつきました。 人間は理性の殻、すなわち心の縛りから解き放たれた時に本来の自分に出会える。そこから自尊の念が生まれ、自制の心が生まれる。■人間とは何か芳村 結局、自分の中に生まれてから死ぬまで存在し続けるのは感性しかない。感性という感じ取る能力は我々が母親の胎内にいるころから働いている。また死んだかどうかも最終的に感性が働いているかどうかで決まる。まさに、感性こそまぎれない「オレだ」。そういう実感を持った訳です。 そして、これまで人間の本質は理性だとしてきた二元論の人間観から、人間の本質は感性だという一元的な人間観に到達しなければ、我々は近代の迷妄から脱却できないのです。 そのためにも、理性の限界を知らなければなりません。理性とは万能なものではなく、合理的にしか考えられない偏った能力だということです。行徳 理性が有限不完全な能力という考えは、哲学史にまったく無い言葉なんですよ。「人間は理性的な動物である」という人間観が圧倒的主流だったんです。ところが、私は労働争議のまっただ中で、そのイデオロギーが持つ虚構と欺瞞を思い知らされたのです。これ以上のウソはないと実感しました。芳村 理性の肯定的な面は、理性はウソを言うことができるという、非常に大事な特徴があるんですよ。 ウソが言えるということは、事実ではないことが言えるということです。事実ではない未来を語り、また夢や希望を構築するという、そういう力が理性にはあるのです。これは理性のプラス面です。村上 先ほどの芳村先生の話についてですが、肉体は3年、あるいは2年ごとに替わるのは事実です。しかし、ほとんど変わらないものがありまます。それはDNA、遺伝子なんです。他のものはすべて入れ替わっても遺伝子は入れ替わらない。そういうアイデンティティーを持っているのです。 人間をこんなに見事に動かしているのはDNAに含まれる情報です。自分を生かし、臓器を生かし、人間を生かしている情報は、遺伝子が握っている。だから、感性というと、まったく物質と離れたように見えるけれど、DNAとというのは感性と物質をつなぐようなものかもしれない。それは長い長い歴史のなかでつくられた情報であるし、まさにサムシング・グレートの思いというものも、その中に入っている訳です。■感性はサムシング・グレート村上 感性というものの基礎は何かということです。それはまったく物質と違うものと考えるのか。少なくともDNAの一部を感性と考えるのか。 例えば、泣いたり、笑ったり、怒ったりしますね。これは感性です。しかし、ここにも物質的な基礎はある。というのは、泣いたり、怒ったりすると物質が出てくるんです。快感を覚えると、快感物質が出てくる。なぜかというと、遺伝子に書き込まれているからです。つまり、サムシング・グレートはそういう情報まで書いてある。芳村 感性そのもの中に、何が自分が生きるために必要な情報なのかという、そういう働きがすでに存在する。つまり、遺伝子が持っている情報というのは感性がつくり出すものと考えることができるんじゃないかと思っているんです。行徳 中国の古典には「感性命」という教えがあって、感性は命であると教えています。感性が鈍いのは命が鈍いということです。知性や理性では命はつくれないのです。■地球上のすべての命は同じ遺伝子暗号を使っている村上 先ほどの「人間とは何か」ですが、実はわたしも遺伝子から人間を理解するために遺伝子の暗号を読み取っていておもしろいことがたくさんわかってきたんです。一番大切なのは、すべての生き物は同じ遺伝子暗号を使っているという点なんですよ。 これまで地球上に存在したすべての生き物は同じ遺伝子暗号を使っているということがわかった。私は、これは生物学における20世紀最大の発見だと思っているんです。ということは、生き物はすべてどこかでつかなっているということです。「人類皆兄弟」とどこかに書いてありますけれど、人類だけじゃない。生き物はつながっているんですよ。 私は環境問題を解く1つの鍵はここにあると考えています。人間だけが偉いのではない。サルと人間との遺伝子情報の差は、1.2~1.3%しかないのです。サムシング・グレートは、人間に何か期待して、このわずかな遺伝子情報を書き換えた。人間の心に自由を与えた。その1つが理性です。人間だけに与えたということは、サムシング・グレートの思いに、理性で近づいてくれとということではないかということです。■「地球にやさしい」は傲慢村上 ・・・それともう1つ大切なことは「地球にやさしい」とよく言いますが、これはまさに人間の傲慢です。向こうが先なんですから。地球の歴史からいったら、私らは本当に最後のところに出てきた、「地球にやさしく」なんてちゃんちゃらおかしい。そうでなくて「地球がやさしい」んです。地球は親だからこそ、子どもである人間を温かく見守るんです。地球がやさしいから人間のわがままをある程度見逃してくれているんですよ。 元素から考えましてもね。人間の体を構成する元素、水素、酸素、窒素、これらはすべて地球の元素です。その地球の元素はどこから来るかというと、宇宙から来ている。だから、私どもの体はもとは宇宙から来ているんです。 人類が誕生して五万年と言われるけれど、五万年経って初めて人類は地球を飛び出して地球を見た。外から地球を見ると人生観が変わるんですよ。こっちがアフガンだとか、アメリカだとか。ごちゃこぢゃ何をやっとるむかと。地球は1つなんです。そういう意味で、今は人間の価値観を根本的に変え得るチャンスが来たんです。行徳 外に目を向けることより、現代人に必要なのは自反です。これは孔子の言葉で、自分に返れという意味なんです。現代人は自分がバラバラになっていて、自分に返れないでいます。つまり、自壊の時代です。東洋思想には、対象と1つになった時に心自ら歓喜する、という教えがありますが、自分が自分に返った時、一番元気が噴き出すんです。そして、自分を自分に返す機能こそが感性なんです。今は前に進むのをやめて、元に帰る時代なんですね。■これから人間が掲げていくべきテーマ芳村 私はこれからの人類は2つのテーマを掲げていくべきだと思っています。1つは平和という理念。もう1つは人間性の進化です。20世紀は戦争の時代でしたが、これからは平和という大きな理念を掲げて歩まねばなりません。行徳 同感です。セルフ・カルチベーション(自分耕作)の時代です。芳村 今、時代は西洋の時代から東洋の時代へと転換しているし、また理性の時代である近代から次の新しい時代へと転換している。そういう何百年、何千年に一度という大きな転換点にある。・・・それと、今、日本の置かれている立場ですが、世界文明というのは、常に時代の中心を担う風土と国家というものを移しながら形成されていくのですが、それがだんだんとアメリカから東アジアへと移り始めている。中でも、日本は最も高度な文化水準を持っている国で、世界のリーダーシップが取れるのは、考える限り日本しかないんです。 日本の特性とというのは、あらゆるものを最も完成度の高いものに仕上げられることです。精神面で言えば、最も水準の高い仏教は日本にあります。儒教も老荘思想も、本国の中国ですら忘れ去られた状況なのに、日本にはしっかりと根付いている。西洋の科学技術にしても同様です。最高の緻密さを誇る技術は日本にあるんです。 その意味で日本は、高度な精神文明のもと、科学技術を質において完成させ総仕上げをしなければならないという使命を持っていると言えるでしょうね。芳村 ですから、日本に新しい可能性を開こうと思ったら、村上先生の遺伝子理論から言っても、環境を変えることによって新しく遺伝子がスイッチオンになって目覚めて活動を始めるのですから。そのためにも、新都造営という大きな夢を日本に掲げて、子どもたちにその夢を与え、世界に貢献するエネルギーをつくり出さなきゃなりません。村上 私も21世紀は日本の時代が来ると考えています。これからの人類は科学文明とて精神文明を調和させて、道を切り開く以外にないのです。そのためには日本の役割は欠かせません。 それと、私は人間の使命とは、生き生きと生きることだと思うのです。生き生きと生きるには各自が夢を持つことです。また、人は人に喜びを与えれば生き生きしてきます。自分の幸せだけ考えていては生き生きとしてこない。 そういうことを併せて、サムシング・グレートが1.2~1.3%に託した思いを追求する人生を生きていただきたいと思います。
2007年06月30日
コメント(1)
-
9月15日思風塾全国大会
第5回 思風塾全国大会思風塾とは、芳村思風先生の感性論哲学を勉強する会です。思風塾に参加されていない方でも、どなたでもご参加いただけます。2002年に出版された「サムシンググレートは語る」(致知出版)の鼎談者村上和雄先生・行徳哲男先生・芳村思風先生の3名に加えて今回から、土橋重隆先生(医学博士)が参加し、初めて4人でのシンポジウムとなります。【日時】平成19年9月15日(土) 1部 11:00~ 村上和雄先生・土橋重隆先生講演 2部 14:00~ 芳村思風先生講演 シンポジウム 3部 18:30~ 懇親会【会場】名古屋国際会議場 白鳥ホール 456-0002 名古屋市熱田区熱田西1-1【懇親会会場】】サイプレスガーデンホテル【参加費】1~2部 前売 5,000円 当日 6,000円 1~3部 前売 10,000円 当日12,000円 シンポジウム・パネリスト(120分) ・村上和雄先生(筑波大学名誉教授) ・行徳哲男先生(日本BE研究所) ・土橋重隆先生(医学博士) ・芳村思風先生(感性論哲学創始者) コーディネーター:岡部明美さん
2007年06月29日
コメント(1)
-

そうだよね、わかるよ
人間の本質は、こころ理屈じゃない心が欲しい。だれもがみんな心が満たされたいと願っている。「心をあげる」とはどういうことか?誰もがみな自分の気持ちをわかって欲しい。共感同苦、共感同悲、共感同喜「そうか、そんなに辛かったのか。わかってあげなくてごめんね」「そうだよな~。わかるよ」受け止めること。気持ちを理解してあげること。「頑張れ!」ではない。「そうか~。そんなに苦しかったのか~」心は、満たされきることはない。なぜなら、人間は不完全だから。お互いに「どうして私の気持ちをわかってもらえないのか?」と思っている。誰もがみな「私のことなんかだれもわかってくれない」と思っている。自分がこのように「愛されたい」と思うようには愛されることはない。親は、どんなに努力しても子どもには「父親も、母親も、オレのことをわかっていない」と子どもが思っていることを理解しておくことが大切。それは、子どもが求めるものと、父母が思っていることには、必ず差があるから。男女の関係においても同じ。男性がどれだけ、女性を愛しても女性は満たされることはない。女性がどれだけ男性のことを愛しても男性は満たされることはない。それは、男性が求めるものと女性が求めるものが違うから。「これだけしているのに・・・」と思った瞬間から、押し付けになる。「これでいいのか・・・」「こうしたら喜んでくれるかな・・・」と悩む心に「愛」がある。
2007年06月28日
コメント(1)
-
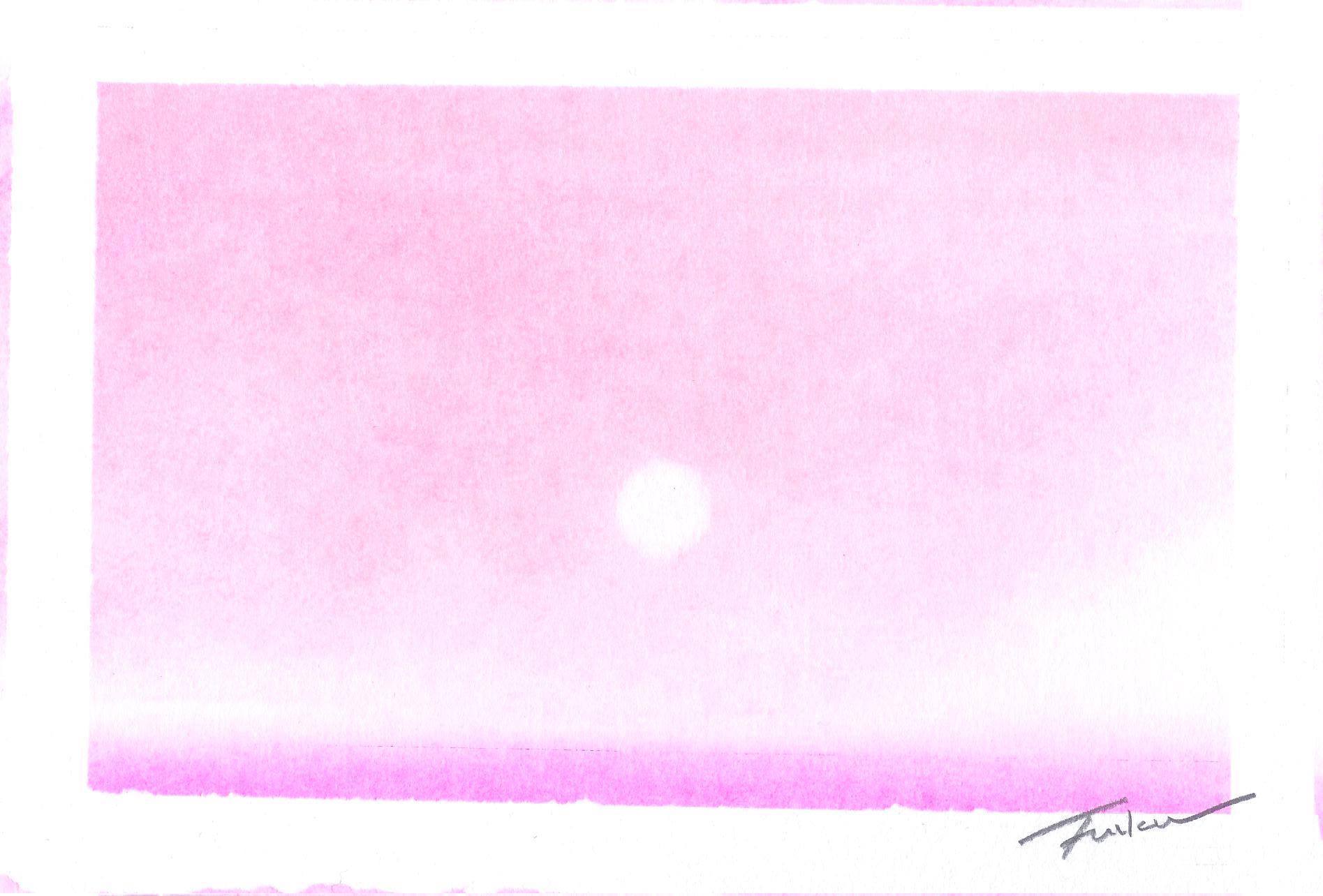
「足るを知る」と足らざるを知る」
足るを知る」と「足らざるを知る」「足らざるを知る」とは、人間は不完全であることを自覚すること。欲求・欲望は大切。欲望は強い方が良い。命の底から湧いてくる欲求・欲望が、人間を進化させる。欲求・欲望に囚われすぎると、「もっともっと」と執着してしまう。自分の器を越えた欲求は自分をつぶす。自分の能力以上の欲望に支配されてはならない。欲望だけを追い続けると、もっともっとときりがない。人に喜ばれること。人の役に立つこと。命から湧いてくる欲求・欲望は、感性。湧いてきたものを理性を使って、人間らしいにする事が大切。人間は不完全。自分にも短所や欠点があることを知り、謙虚な心を持ち続けること。感性と理性のバランスではない。感性と理性を共同作業。感性だけでは、ただの野獣。感性から湧いてくる欲求・欲望を、理性を使って人間らしいものにする。命の底から湧いてくるものの無い人間には、自分のやりたいことが見えてこない。欲求・欲望は、否定しなくても良い。人間は不完全であること=足らざるを知って、「足るを知ること」
2007年06月27日
コメント(0)
-
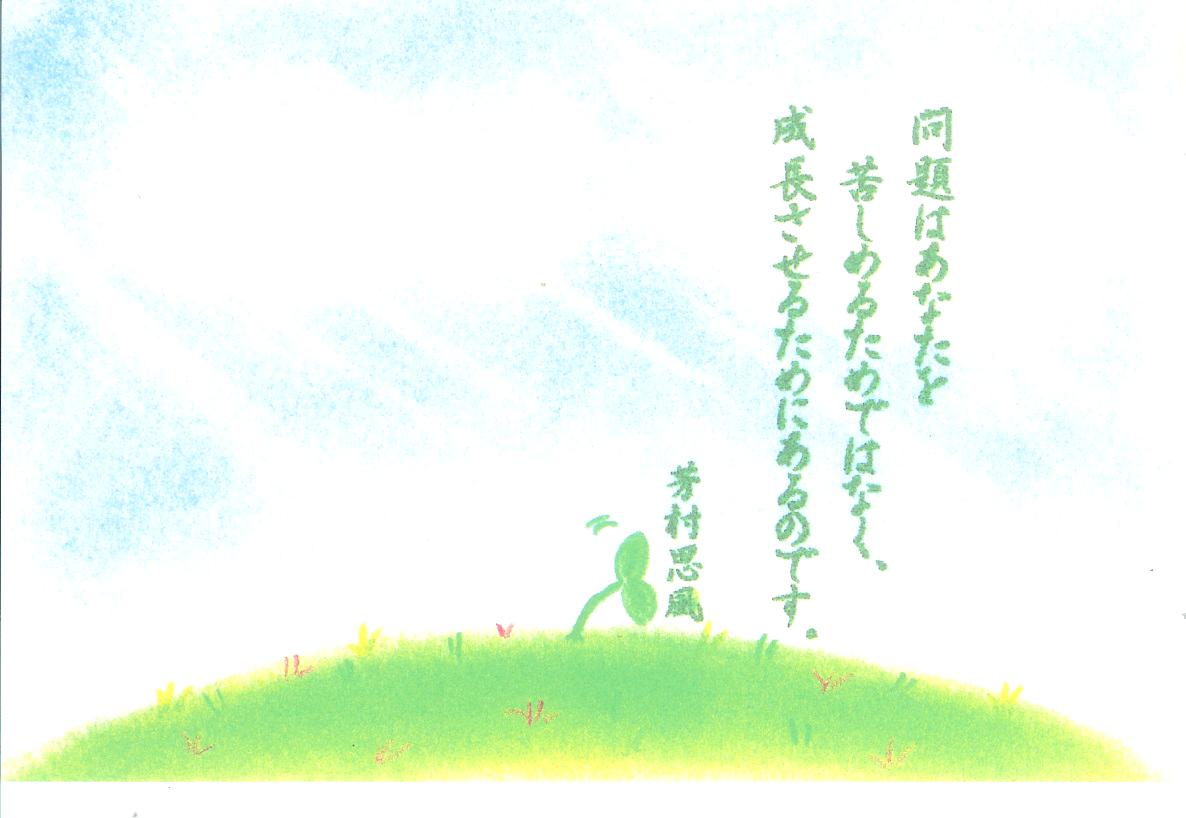
天はオレを大人物にしようってか!
問題は、自分自身を成長させるために出てくる。大きな問題を乗り越えれば、それだけ大きく成長できる。大きな問題が起こったときは、「天はオレを大人物にしようってか!」と考える。命の痛みの体験を通して、命が磨かれる。プロとしての自覚が生まれてくる。人間の命を磨くのは、実業しかない。自分の感性で選んだ道が最高のものを選んだという自覚を持て!感性で選んだものに誤りはない。頭や理性で判断するから誤る。直感は意味があるから「ひらめく」。そうして決めた選択に自信を持って、捨てた選択肢のことは、きっぱり忘れる。どの道を選んでも問題はある。やっぱり別の道を選べば・・・と悔やむようでは、まだ断ち切れていない。決めたけど、断てていない。断ち切らなければ、決断ではない。「にげたらあかん!」
2007年06月26日
コメント(0)
-

理性と使命
理性とは、客観性と普遍性の能力です。理性的に考えるとは「みんなにとってどうか」と考えることです。社会、人類、国家など、自分を包み込む、より大きなものを視野に入れながら、自分の中から湧いてくる欲求を実現しようとすることです。ここに偉大なる人間の仕事が始まるのです。単に命から湧いてくるものをそのまま自己中心的にぶつけるのではなく、湧いてくるものを理性を通して表現するところに人間的な行動があるのです。理性は客観性と普遍性の能力であるがゆえに、それを使って考えると、そこに「みんなにとってどうなのか」という社会性・人類性が芽生えることになります。理性を通して表現することによって、命から湧いてくるものは「志」となり、「使命」になるのです。「人間観の革正」芳村思風著(致知出版)
2007年06月25日
コメント(0)
-

第3の過渡と激動の時代・日本の役割
第一の過渡期とは、古代と中世との間に横たわるギリシャ・ローマ時代第二の過渡期とは、中世と近代の間にある過渡期であるルネッサンス第三の過渡期とは、まさに今の時代現代は、「数万年単位」「数千年単位」「数百年単位」の大変化が同時進行で起きているという人類史始まって以来の大激動の時代である。それぞれにどのような変化が起きているのかを正しく理解できていないリーダーや、精神の目覚めを体験し、より高い次元から人間とこの世界を見ることのできないリーダー、人を感動させることができないリーダーは、はもはや人を導き、組織を活性化し、創造していくことはできない。☆数万年単位で起こっている3つの変化1.地球時代から宇宙時代への変化 技術の進歩により、宇宙から地球を見るという新しい視点を持つが出来た。 このことによる価値観の変化。 「地球は、ひとつ」という意識が人類共通のものとなった2.縦型社会から横型社会への変化 人間が人間を支配するという構造が崩れ始めた。 男性が女性を支配するという構造が崩れ始めた。3.弱肉強食から適者生存への変化 競争という原理から、創造という原理へ変化してきた。 他人に勝つことを喜びとする心情は、これからの共生社会にはそぐわない。 「勝ち組み」といわれる企業は、独創的な想像力で勝っている。☆数千年単位で起こっている3つの変化1.理性原理から感性原理への変化 人間の感性から理屈ぬきに湧き上がってくる本能・欲求・興味 関心・好奇心などを、理性によって支配しようとして、 ストレスが生れ、さまざまな精神病理現象を起す。 「理性としての私」と「本能としての私」といった 二元論的な人間観を持ち続けてきた。 大事なのは、「私は二人いない。たった一人しかいない」 という意識をどこに置くか。 精神と肉体を根源的に統一している原理とは何か。 感性論哲学は、その原理こそ感性であると考えます。 「感性が肉体と精神を作り、感性が肉体と精神を根源的に統一している。」 2.地域文明から世界文明へ 地球全体がひとつの文明圏という状態へ変化しつつある。 さまざまな分野で地域文明の融合現象がでてきた。 3.二元論的人間観から一元論的人間観への変化 「人間は精神的な実体と肉体的な実体が結びついたものである」 二元論的な人間観から、「心身は一体である」という有機的な生命観となり、 「肉体は、目に見える精神である。精神とは目に見えない肉体である。」 という考え、精神と肉体は一体化した形で有機的な生命として生きており、 単に機械論的な生命観によって理解できないとした。 しかし、身体論は精神と肉体を根源的に統一する原理を見つけられなかった。 感性論哲学では、「われわれが、私といっている実体とは感性のことだ」 と論証した。 「人間の本質は感性であり、生命の本質も感性である。 感性宇宙の究極的実在も感性である。 感性が精神を作り、感性が肉体を作る」 これにより、まったく新しい一元論的人間観がつくり上げられた。☆数百年単位で起こっている3つの変化1.政党政治から脱政党政治へ、そして互敬主義社会へ2.資本主義経済から脱資本主義経済へ、そして人格主義社会へ3.理性文明から脱理性文明へ、そして感性文明へいま、世界文明の中心は、欧米から日本の真上へと来ている。日本人は、この第3の過渡期を担なえる唯一の存在である。現代の文明を完成させ、集結させる。そして、新しい時代に向かうため、それを壊していく。あらゆるの言語・宗教・文化・音楽を受け入れ、融合統合させ、さらに発展させてきた日本だからこそ出来る東洋文明と西洋文明の融合・統合。唯一の被爆国からの世界平和の発信。日本人にしか出来ないことがある。21世紀は、日本の時代。新しい時代を作るための、過渡期である「脱近代」の歴史は、日本がつくらなければいけない。その中心は、やがて中国・韓国へと引き継がれ、インドへと移っていくであろう新しい時代の礎を今、日本がつくっているのである。
2007年06月24日
コメント(1)
-
問い続ける
感性論哲学では、「問い」を持つことを大切に考えています。感性が「問い」、理性が「答える」。「問い」は、感性からでてくるものです。大切なことは、「問い続けること」真理は、ひとつではない。真理は、時代と共に変わる。答えに縛られると、他の答えを排除しようとする。「もっといい答え」を求めることで、進化・発展・成長する。感性論哲学のなかで話される「問い」の一部です。チェックリストとして、自分自身に問い掛けてみてください。【人生における3つの問い】1.将来どんな人間になりたいか?2.将来どんなことをやりたいか?3.将来どんな生活をしたいか?常に自分自身に問いを発すること。1.人間として、いかに成るべきか?2.人間として、いかに為すべきか?3.人間として、いかに在るべきか?「人間」のところを「父親・母親」や「経営者」「教師」などに置き換えて考える。答えを持つことは必要である。答えはひとつではない。固定するものでもない。常にもっといい答えはないかと模索し続けることが大切なことである。【人生の鉄則からの5つの問い】1信じるに足る自己を作っているか?2.自分で自分を教育しているか?3.限界への挑戦をしているか?4.決断に賭けているか?5.意味と価値を確認しているか?【これからの時代の人間性をつくるための6つの問い】1.理性を正しく理解していいるか?2.理性と感性の関係を正しく理解しているか?3.知恵を活用しているか?4.勝つことよりも、力をあわせることのすばらしさを知っているか?5.人生観・生き方の変革をしているか?6.感性的な判断基準を大切にしているか?【天分を見つける5つの問い】1.やってみて、好きになれるかどうか?2.やってみて、興味関心が持てるかどうか?3.やってみて、得手・勝手と思えるかどうか?4.やってみて、他人よりうまくできるかどうか?5.真剣にやってみたら、問題意識が持てるかどうか?【人格を鍛える3つの問い】1.人格を高める努力をしているか?2.人格を広くする努力をしているか?3.人格を深める努力をしているか?【人間成長の原理からのふたつの問い】1.新しい気づきを積み重ねているか?2.潜在能力を顕現させる努力をしているか?
2007年06月23日
コメント(0)
-

理性とは何か
理性とは何か・・・感性が良くて、理性が悪いのではない。ポイントは、「感性と理性」を協力させること。感性と理性のバランスではない。人間は、感性と理性と肉体でできている。「感じたことを、理性を使って、人の迷惑に成らない方法で、人の役に立つにはどうしたらよいかを考え、肉体を使って行動する」理性とは・・・●自分のしたいことを人に迷惑をかけない方法で、どうしたら実現できるだろうかということを考える手段能力●現実に存在するものの中の変化しないものしかつかめない能力●理性によって理解され、把握されたものは固定化され変化しなくなってしまう●理性は、生きているものを殺す力●人間が生まれてから後に、後天的につくっていく能力●現象してきたものしかつかめない能力●合理的に考えることができる能力●合理的にしか考えることができない能力●理性能力は、言葉を覚え、言葉と言葉を結びつけていく作業を通して出てくるものです。●理性能力は、人間がつくり出した言語が持っている限界。言語が持っている不完全性を背負っている。言語の制約の中でしか、理性は働き得ません。言葉の限界が理性の限界。
2007年06月22日
コメント(0)
-
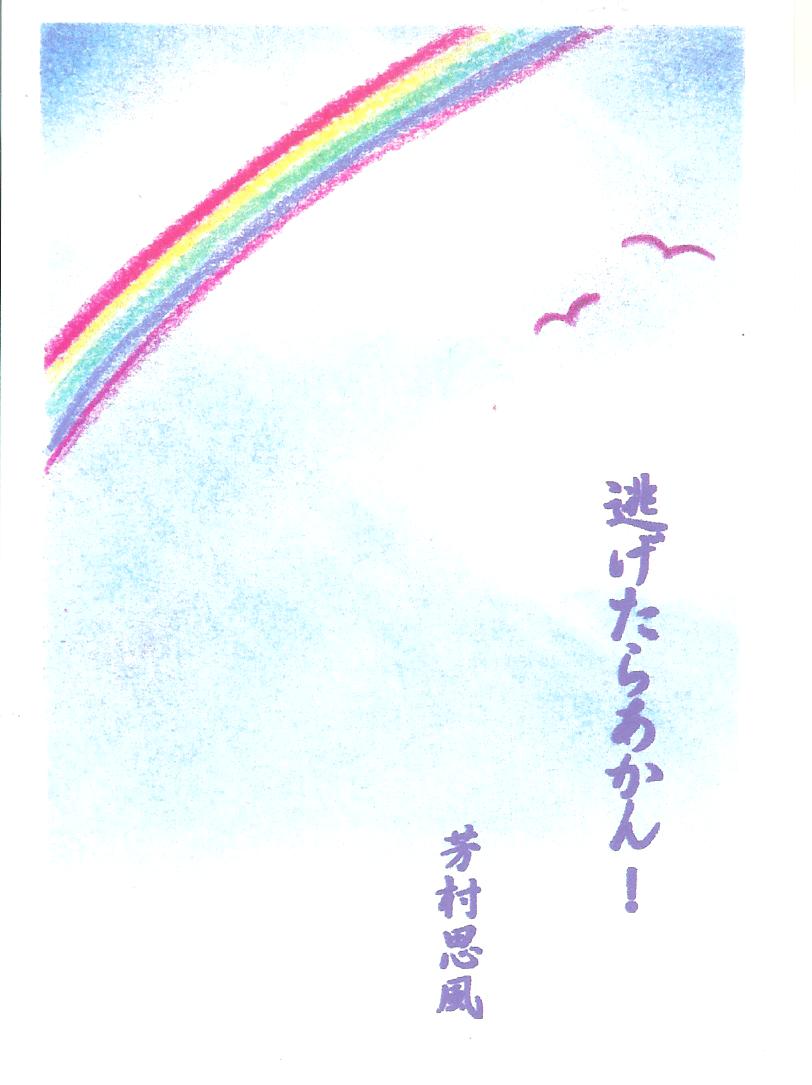
成功への5つの階段
【成功への5つの階段】1.信じるに足る自己をつくっているか?2.自分で自分を教育しているか?3.限界に挑戦しているか?4.決断にかけているか?5.今やっていることの意味と価値の確認を感じているか?
2007年06月21日
コメント(0)
-

助け合って生きるための・・・
哲学とはなにか?誰も、この苦しみを、気持ちを、わかってくれない。誰も俺の事を本当にはわかってくれない。この思いは、誰の胸にも、死ぬまで付きまとうものである。人間は、本質的に、根元的に、誰でも、皆、さみしいのである。孤独なのである。しかし、また、人間は、この誰にも理解されない心を抱えて人と共に生きて行かなければならない存在である。そこで、人間は、人と共に生きる為に人に語りかけ、話し合い、理解し合えるように努力するのである。いや、努力しなければならないのである。なぜなら、みんな同じ人間であるからだ。この、孤独である人間が互いに理解し合おうとし、その為に、全人類に共通する真実を求め、それを手がかりに助け合って生きようとする努力、これこそが他ならぬ哲学なのである。主義主張で対立する事が哲学なのではない。
2007年06月20日
コメント(0)
-

現実への異和感
異和感とは、芳村思風先生の造語。辞書では、違和感。「違う」のではなく、「異なる」だけ。現実への異和感●感性の実感●現実と深くかかわることによって、現実によって呼び出されてくる自分●現実というものと深くかかわって真剣な生き方をしていなければ出てこないもの●真剣な命の叫び●自分に問題を課する現象●自分の使命を自分に教えてくれている天の啓示●「自分はいったい何をしてこの時代を一歩前に進めたらいいのか」ということを自分に教えてくれる現象●自分に与えられた使命が何であるかということを教えてくれる現象●理性によってつくられた現実の形式と、一時の休みもなく変化し続けている歴史や時間や命や感性との間にズレがある。このズレというもの、ちゃんと歴史の動きに合うように、訂正し改めていかなければならないということを人間に語るために出てきている現象●それを本気になって何とかしようとすれば、必ずできる能力を持っているのだということも、自分に教えてくれている出来事●自分が一体何をするためにこの世に生まれてきたのかという、自分にのみ与えられた使命が一体何であるのかということを教えてくれると同時に、自分がなぜここにいるのかという存在理由も教えてくれる。そして、さらには本気になって自分がそれをやろうと思えば、自分が納得するところまでは現実を動かすことができる能力を、すでに潜在能力として与えられているのだということも自分に教えてくれているもの
2007年06月19日
コメント(0)
-

東洋の逆襲
西洋中心主義西洋から東洋への文化の流れが西洋の停滞を機に大きく変化し文化は今、東洋から西洋へと流れ始めた。いよいよ東洋の逆襲が始まったのである。そして、21世紀には、東洋の中心である日本の時代が到来し、日本民族は人類史上、第三の過渡期を担う民族として、次の二つの大事業を行う。一、近代科学技術文明を、その質において完成させて終わらせる。二、近代に代わる新しい時代を創るための原理を創造し、世界に発信する。「21世紀日本の使命」(芳村思風著)より日本は、ルネッサンス期のイタリアのような役割。東洋の時代は、中国において発展し、そのあとインドにおいて完成される。今、世界の中心は、日本の真上にきつつある。西洋の時代から、東洋の時代へ。その橋渡し役が日本。日本には、異なる文化・宗教・価値観を受け入れさらに成長させるという風土がある。お正月には神社に初詣、車には、成田山のお札クリスマスには、クリスマスパーティ大晦日には、除夜の鐘・・・宗教の違いで戦争する事もなく、すべて受け入れていく。インドで発生した仏教は、中国で発展し、日本で完成された。日本には、世界の食卓がある。世界中どこの国の料理でも食べることができる。世界中の音楽を聞くことができる。節操がないのではない。違うものを受け入れ、消化する能力が、日本人にある。
2007年06月18日
コメント(0)
-

感性論哲学は、人間学
「感性論哲学」は、人間学です。これからの時代に必要ものがすべて入っています。哲学は、ヨーロッパの哲学者の言葉や業績を研究するのではなく、人間学として、実践に役立たなければ何の意味も無い。感性の本質は、同じを探す。理性は、違いを探す。理性は矛盾を無くそうとする。違いを探し、違いを無くそうとする限り、戦争はなくならない。感性と理性のバランスではない。感性だけで行動するのは、野獣と同じ。感性と理性を協力させなければならない。感じたのもを、理性を使ってどう人間らしくするか。感性型人間とは、感性を理性を使って成長させている人間のこと。理性を使わないと、感性は成長しない。この宇宙に存在する物は、すべてプラスとマイナスの両面を持っている。表・裏善・悪前・後上・下表がよくて、裏がわるいのではない。短所も長所必要。善だけの世界は無い。欠点も、犯罪もなくならない。善が、悪を作っている。これが「正しい」と決めるから、「間違い」がある。すべての基準は、時代によっても変化する。人間は罪を犯すものという事を知ったうえで、罪を犯すことはよくないこと、どうすれば罪を犯さなくなるか考える。罪を犯した人の気持ちは、罪を犯した人でなければわからない。罪を犯してもよいということではなく、その気持ちを察することが大切なこと。矛盾もなくならない。矛盾を内包した真実を生きる。感動は、真実の世界にしかない。感動の中にだけ、真理を越えた真実がある。
2007年06月17日
コメント(0)
-
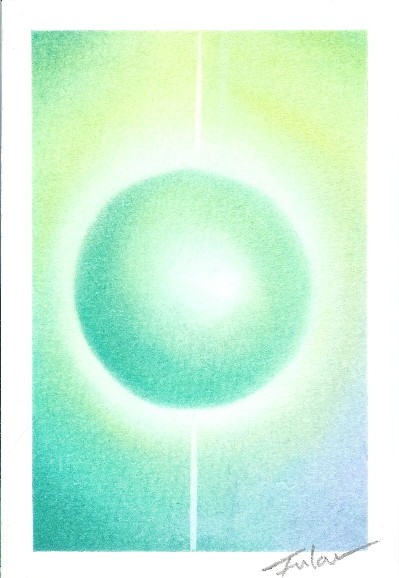
新しい時代
今、まさに一つの時代が終わろうとしている。二十世紀の理念に生きた巨星が、一人また一人とその輝かしい時代に別れを告げて去って行く。世界の文明は、あらゆる分野において危機に直面しており、深まり行く混迷の中で人々は不安に包まれている。終焉とはさみしい言葉である。喜びは短く、悲しみは長い。喜びは努力しなければ得られないが、悲しみは努力なしにやって来る。人生とは、その大半が苦から楽への、悲しみから喜びへのプロセスである。人間の価値は、このプロセスそのものにどれ程の生き甲斐を見い出し得るかにかかっている。世界は、今後、苦しい不安定な動乱期を経験しなければならないであろう。しかし、それは決して悲しむべき時代ではない。むしろ、動乱期こそ最も素晴らしい時代である。すべてのものがそこから生まれ、あらゆる新しいものがへの可能性をはらんだ生き甲斐のある時代世界中の若人が待ちに待った、夢多き時代がやってきたのである。「感性論哲学の世界」序文 芳村思風著
2007年06月16日
コメント(0)
-

愛の実力意志の力
問題のない、悩みのない人生はない。人生とは問題を引き受け、悩みを乗り越え続けていくことである。人間は、問題のない悩みのない人生を望んではならない。時代は明らかに、画一性の時代から個性の時代へと移行している。しかし人類の人間性は、まだ、残念なことに、同じ考え方や同じ価値観の人間としか、いっしょに仕事をし共に生きて行くことが出来ないという段階にある。だから、ちょっとした考え方や感じ方のちがいで夫婦は離婚をしてしまう。これは問題を避け悩みから逃げているのである。宗教のちがいや思想のちがいや価値観のちがいで、人類は憎しみあい対立し戦争をして殺しあっている。問題のない人生を望むことが、かえって人間に不幸と災いをもたらすのである。こんなことでよいのか。個性の時代というのは、お互いに考え方のちがいを認めあい、考え方の異なる者が互に助けあい協力しあって生きていく時代ということである。だから個性の時代には、問題や悩みを乗り越える為に、理屈を超えた愛の力が要求されるのである。人類は、いつまでも矛盾を排除し画一性を追求する理性に支配されていてはならない。理性は人間の為にあるのであって、人間が理性の為にあるのではない。考え方のちがいで人間が戦争し殺しあってはならないのである。 『意志の力・愛の実力』芳村思風著 はじめに より。今日から、3日間長野県上田市の女神野山で第4期のI WILL フォーラムが始まります。「意志と愛」の講座・・・経営者やリーダー・リーダーをめざす方のためのセミナー。芳村思風先生の感性論哲学の講義と、それを体で体感する岡部明美さんのワークのコラボレーションがとても絶妙な組み合わせです。今回は、25歳から○○才まで、参加者20名。再度、コクーンも参加してくれることになった。
2007年06月15日
コメント(0)
-
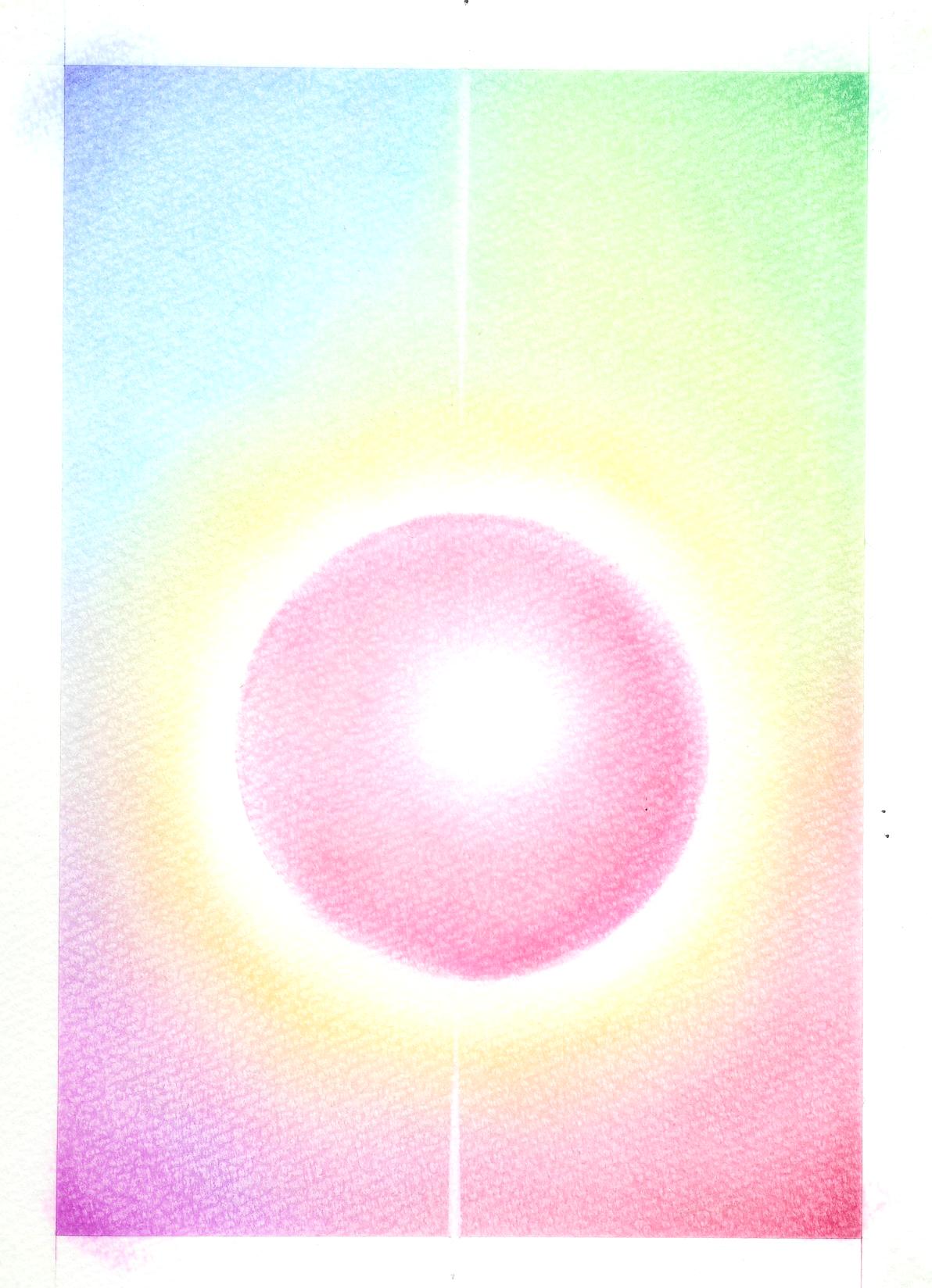
感性が問い、理性が答え、体で実現する。
感性が問い、理性が答え、体で実現する。感性論哲学では、「問い」を大切にしています。最も大事な問いは、「人生の問い」といわれます。 人生の3つの問い ・将来どんな人間になりたいか ・将来どんな事をやりたいか ・将来どんな生活をしたいか答えを持つことは、大切なこと。この3つの問いに理性できちんと答えを出す。しかし、もっと大切なことは、実行すること。行動すること。やってみて、再び問う。これでいいのか。問い続けること。「なぜ私は、生まれてきたか?」「誰もが、その人でなければ出来ない大切なお役目を持っている。そのことで時代を一歩勧めるために生まれてきたのです。新しい歴史を作るために生まれてきたのです。」歴史は、その時代に生まれてきた子供たちが作ってきた。「近頃の若い者は・・・」という言葉が出てきたら、時代の流れに沿っていないということ。明治維新もITの時代も「地がごろの若い者は・・・」と言われていた人たちが作ってきた。
2007年06月14日
コメント(0)
-

一道一徹
「一道一徹」…一つの道を貫き通す芳村思風先生が、本にサインした言葉。あまり書くことのない言葉ですが、時間があるときは、本を持ってきた人をじっくりと見て、浮んできた言葉を書かれます。書かれたサインを見て、涙を流した人を何人も見ました。「よくサインに書かれる言葉」この命なんのために使うか愛するとは、相手から学ぶこと責め合うのではなく、愛し合って生きる命には、命より大切なものがある。それは愛と志である問題は成長させるために出てくる限界への挑戦!一灯照宇の志不頼独行いつも目に愛の光を!勝つことよりももっと素晴らしいことは、力を合わせて成長することあなたは、どんなサインをいただきましたか?
2007年06月13日
コメント(0)
-
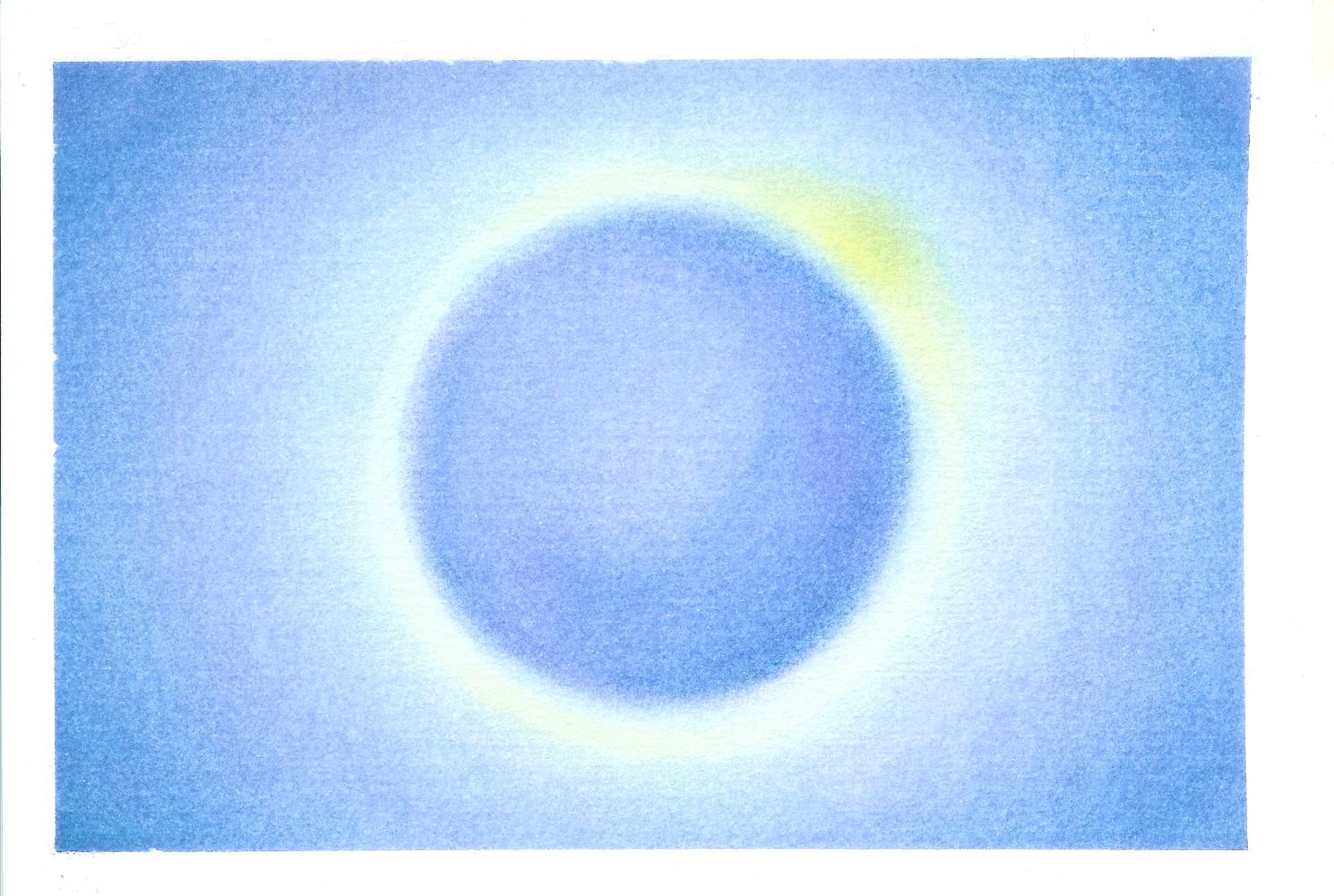
本物の人間とは
本物の人間とは、次の3つの条件を備えている。1.不完全性の自覚からにじみでる謙虚さを持つ。2.より以上をめざして生きる。3.人の役に立つ存在になる。そして、これを目的に努力することによって、人間は、本物の人間として、の格を持つことができる。これは、「問い」の形にして、常に自分自身に問いかける。1.不完全である事を自覚し、にじみ出る謙虚さを持っているか。2.より以上をめざしているか。3.人の役にたつ存在であるか。答えは、一つではない。答えを持つことは大切。もっと大切なのは、その答えに縛られないこと。縛られると他を排除しようとしてしまうから。人間は不完全だから、完璧はありえない。まだまだ努力・成長しなければいけないという気持ちが、謙虚さにつながる。個性も人の役に立たなければただのわがまま。人の役に立ってこその個性である。東京思風塾思風塾ホームページ
2007年06月12日
コメント(0)
-
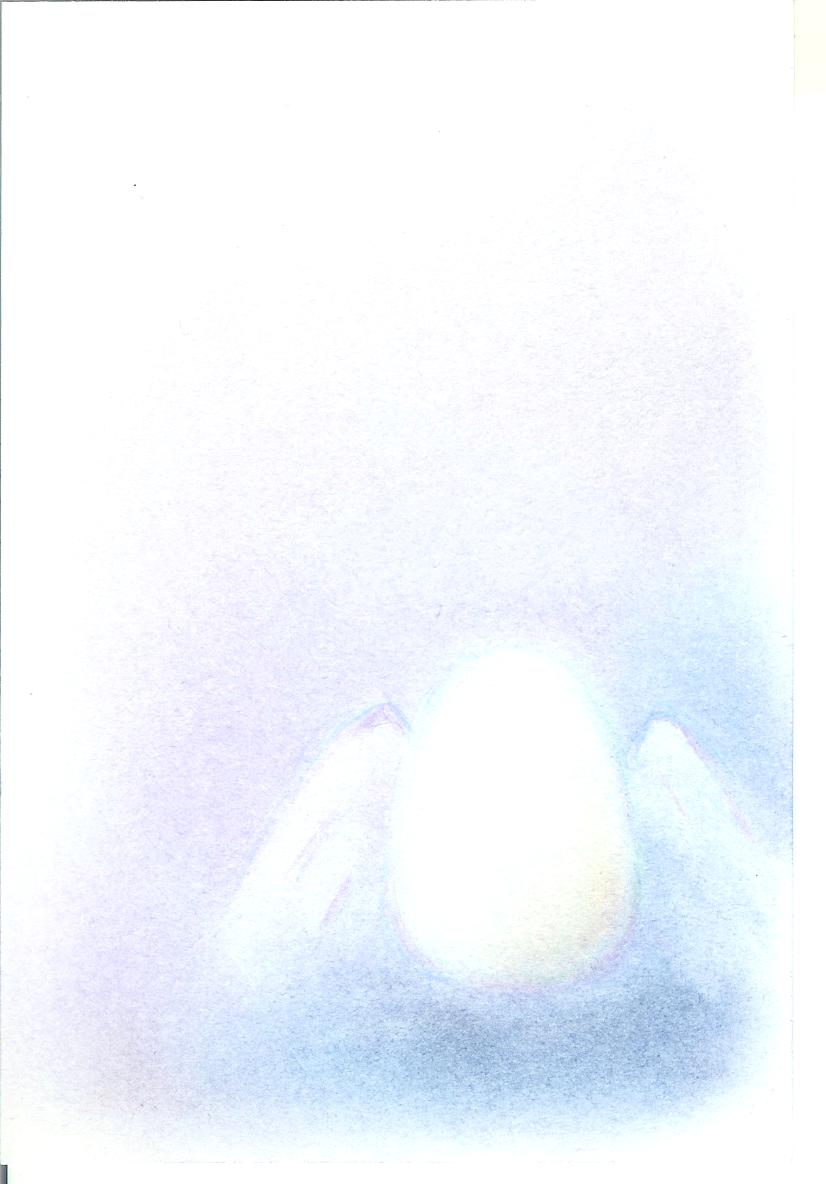
とにかくやってみる
人間はみな自分だけの天分・素質(才能・役割・使命)を持って生まれてくる。その天分・素質は、“肉体と感性”を使わなければ発見できない。肉体を使うというのは体験すること。行動すること。どんなに野球が好きでも、テレビを見ているだけでは自分に野球の才能があるかどうかはわからない。やってみなければわからないのである。作家になりたかったら自分の文章を書き続けること。絵描きになりたかったら絵を描き続けること。本当にそこに自分の才能があったら、必ずそれを評価してくれる人が現れるものである。<天分・素質を発見する5つの方法> 1)やってみたら、好きになるかどうか。 2)やってみたら、興味、関心が湧くかどうか。 3)やってみたら、得手、得意と思えるかどうか。 4)やってみたら、他人よりもいつも自分の方がよくできるかどうか。 5)真剣にやってみたら、“問題意識”が湧いてくるかどうか。この5つの方法で見つけていくのです。どれが一番天分の多いところか。一番強烈な実感が湧いてくるところが天分のツボ。いのちの使いどころ。一流、オンリーワンの仕事をしている人は、みなこれらのツボを特化させて努力してきた人である。時に、この5つが全部当てはまる仕事をしている人がいるがそうなったら笑いの止まらない人生になるのである。とにかく、自分の天分・素質があるものをとことんやってみるのです。無心になって寝食を忘れて、損得を超えて。しかし、成長すればするほど、新たな限界、壁にぶちあたります。一流、本物、オンリーワンと言われる仕事をしている人というのはみな、次々にやってくる壁や限界に挑戦し続けてきた人であり、何度失敗を重ねても、常に失敗から何かを学び、教訓を得て、次に活かし続けてきた人である。成功した人というのは、成功するまで、あきらめなかった人なのである。人間の天分・素質というのは潜在能力である。ゆえに限界まで努力し、壁にぶつかった時がチャンス。「もう万策尽き果てた。もうダメだ、限界だ」とどん底でうめいて、もがいて、それでもあきらめきれずにもう一度挑戦してみた時にその人の潜在能力が突然目覚めるのである。限界を感じた時に、そこであきらめてしまうのか、もう一度挑戦してみるのかでその後の人生が大きく変わってしまうのである。多くの人は壁にぶつかった時に、これは自分の道ではなかったとあきらめてしまう。だから潜在能力としての本当の才能が開花しないのである。
2007年06月11日
コメント(0)
-

感性と理性の協力関係
自分のいのちから理屈抜きに込み上げてくる感性の欲求・欲望・興味・関心・好奇心こそ、その人を最もイキイキと輝かせるもの。意志の強い人間というのは、自分のいのちから湧いてくる欲求・欲望の強い人間なのである。欲求・欲望を、理性を使って実現しようとした時に、それは、その人の“使命感・志”になっていく。理性というのは、“人の役に立つことかどうなのか”ということを考えられる力であり、“普遍化できる能力”だから。これが理性の長所なのである。多くの人は、“感性が自分を目的地まで導いてくれる”ことに気づかず、理性的な判断によって目標を設定し、進むべき方向を決定しようとする。しかし理性(思考)で作った、理念、目的、計画には、作為や、見栄や、焦りが働く。嘘が混じる。損得勘定のみが働く。「仏作って魂入れず」といったものになる。理性で考えた理念・目的・目標は、決して人間のいのちに真の喜びは与えない。理性で作った目的を実現しようと思うと、その瞬間から人は、その目的や結果に囚われて、どんどん自分を追い込んでしまう。自分の頭が作ったものに、自分が縛られ、支配されて、強迫観念のようになってしまうからである。感性から湧いてきたものを実現しようとすると、そこには“自由と喜び”がある。いろいろと創意工夫のアイディアが湧き上がってくる。自由と喜びがあるかどうかによって、その目的が、感性(いのち)から湧いてきた欲求なのか、理性(頭)で考えて作ったものかがわかる。「感性と理性のバランス」ではない。「感性が問い、理性が答える」。感性と理性の協力関係を作ること。感性はたえずちょっと違うんじゃないか?今ひとつピンとこない。これはおかしい。どうも腑に落ちない。もっとどうにかならないものかといった“現実への異和感”を発信している。その自分の内側から来る問いや異和感に理性を使って答えていくのである。どうしても納得できないことや、異和感を覚えるところが、実は自分の役割や使命があるところなのである。
2007年06月10日
コメント(0)
-

決断
人生は賭け!結婚も賭け、会社の経営も賭け。人生は、決断の連続。決断とは、いろいろとある選択枝の中からひとつを選び取るだけではない。決めたら、選ばなかった他のものは、すべて捨て去る。断ち切ること。決めたら、バカになれ!オレにはこの道しかないこの人しかいない誰に何と言われようとも、どう思われようともオレが決めたことどんなに真剣に選んでも、問題の出てこない道はない。そのとき自分の持てる最高の力で、全力を振り絞って決める。決めたら自信を持って、出てくる問題を全力で乗り越え続ける。問題が出てきたから、選んだ道が間違っていたではない。人間は不完全だから、問題がないことはない。問題のない道は、成長のない道。決めたら迷うな!バカになって問題に取り組み、乗り越え続ける。
2007年06月09日
コメント(0)
-
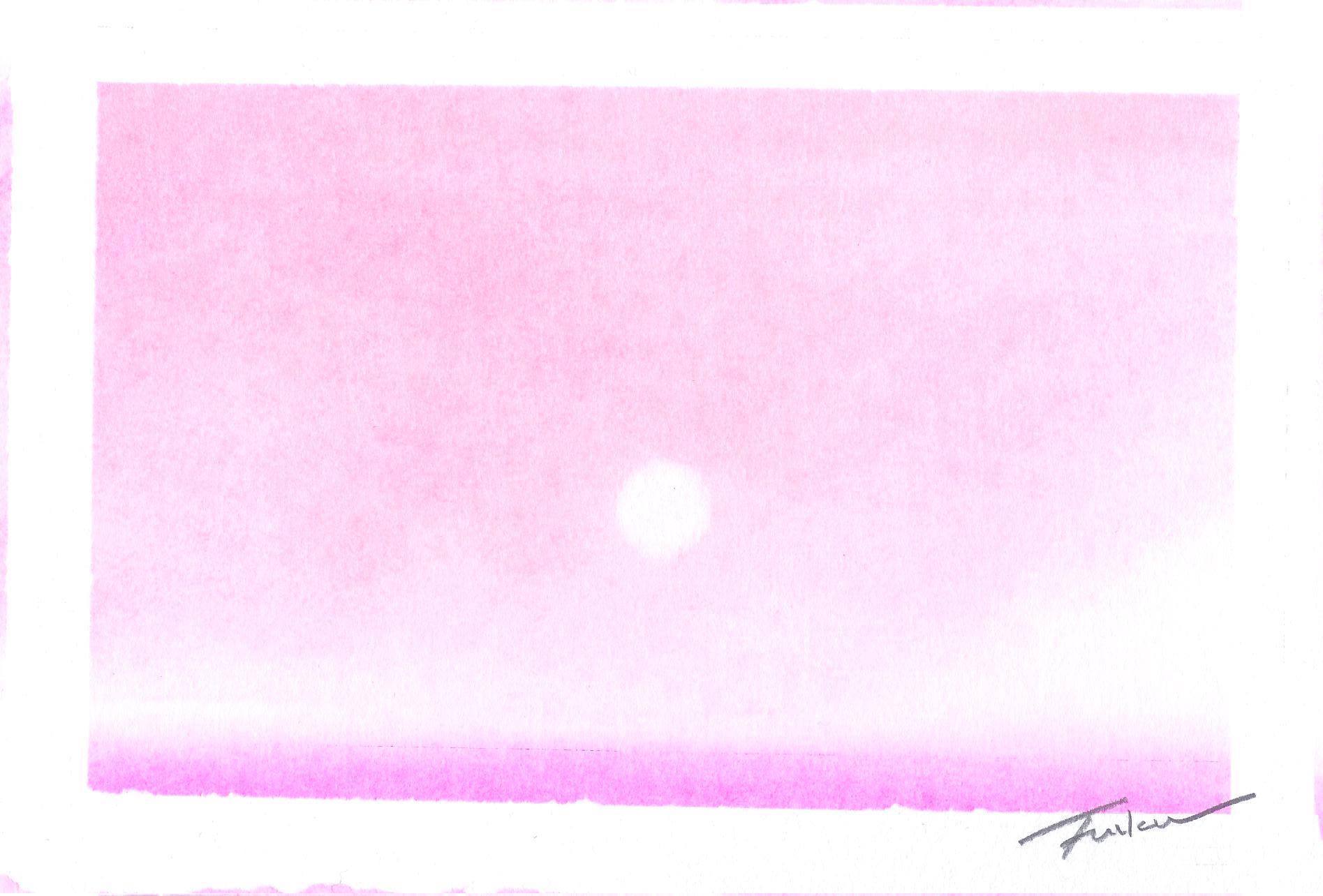
「足るを知る」と「足らざるを知る」
「足るを知る」と「足らざるを知る」「足らざるを知る」とは、人間は不完全であることを自覚すること。欲求・欲望は大切。欲望は強い方が良い。命の底から湧いてくる欲求・欲望が、人間を進化させる。欲求・欲望に囚われすぎると、「もっともっと」と執着してしまう。自分の器を越えた欲求は自分をつぶす。自分の能力以上の欲望に支配されてはならない。欲望だけを追い続けると、もっともっとときりがない。人に喜ばれること。人の役に立つこと。命から湧いてくる欲求・欲望は、感性。湧いてきたものを理性を使って、人間らしいにする事が大切。人間は不完全。自分にも短所や欠点があることを知り、謙虚な心を持ち続けること。感性と理性のバランスではない。感性と理性を共同作業。感性だけでは、ただの野獣。感性から湧いてくる欲求・欲望を、理性を使って人間らしいものにする。命の底から湧いてくるものの無い人間には、自分のやりたいことが見えてこない。欲求・欲望は、否定しなくても良い。人間は不完全であること=足らざるを知って、「足るを知ること」
2007年06月08日
コメント(0)
-
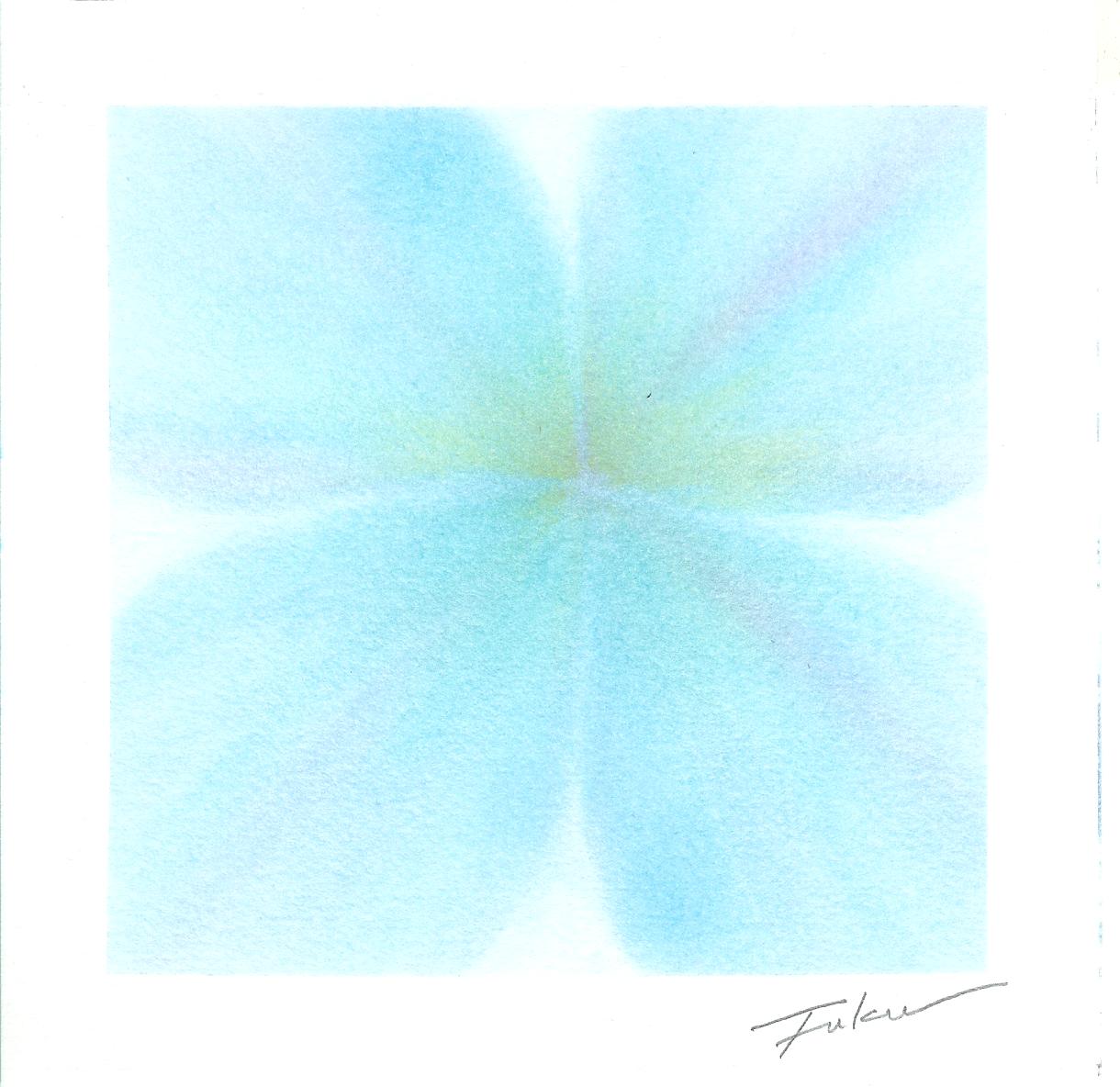
愛は感じるもの
真実の愛は、努力してつくっていくもので、その努力に愛の価値があるのです。相手のために払った努力の量と質が愛の重みを決定するのです。そして、その努力を愛と感じるのが、人間の愛であると言えるのです。愛は感じるもの。感じなかったら愛ではありません。また、愛を感じさせることによってしか、愛は存在し得ないものです。
2007年06月06日
コメント(0)
-

信じて、信じて、信じぬく
人間は、信じられないものであることを自覚する。 ウソも言う。裏切ることもある。失敗もする。 罪も犯す。 「信じられないものを、信じると決断する」 矛盾を内包する真実を生きる。 だまされても傷つかない心を持つ。 人間だから、ウソをつくことも、 裏切ることもある。 だまされても、裏切られても、 自分ひとりだけでも信じられるかどうか。 簡単にできることではない。 だまされたら、腹が立つ。 裏切られたら、悲しい。 それでも、一度信じた人を信じぬけるかどうか。 簡単に出来ない。相当の覚悟がいる。 理屈では考えられないことをできるかどうか。 理屈では考えられない決断が、 最高の愛の世界を作る。 矛盾を内包した真実の世界を生きる。 子どもがウソをついたとき、 「お父さんが悪かった。ウソをつかなければいけないような状況になっているのに気がつかなくてごめんね。許してね」と 子どもに謝り、抱きしめることが出来るかどうか。 ウソをつかなければならない状況を自分が作ってしまった。 そう思えるかどうか。 「でもウソをついてはいけない。」と子どもを叱る。叱らなければ、ただの甘やかし。 「人間は不完全である」を知る。 これを知り、実践していくとはどういうことか。 だまされたり、裏切られて相手を責めるのは、 人間に完全を求めている。 意識せずにそうなってしまうこともある。 人間が不完全であることを認め、 不完全を許した時、 人間の最高の愛の姿がそこにある。 信じて、信じて、信じぬく力を持つ。 ・・・・・・・・・・・・・・・・ここからは、テレビで見た話。ビートたけしが、ある番組で話していた。「島田洋七だけは、どんなことがあってもオレは信じる。」たけしが、事件をおこして、テレビから干されているとき、取材攻勢から逃れるために沖縄の離れ島にいた。売れている時、周りに居たたくさんの人が、事件をきっかけに、ほとんどが消えていった。洋七だけは、用も無いのに、東京から飛行機を乗り継いで、何回もそこまで来てくれた。ただ顔をみるだけで、ほとんど話をせずトンボ返りで帰ることもあったらしい。いい時も悪い時も同じように接してくれる人間は、数少ない。「あいつと付き合っている」というだけで、批判されることもある。それでも友人として、損得関係なしに変わらない態度で接してくれた。こんな話をしみじみと語っていました。
2007年06月05日
コメント(0)
-
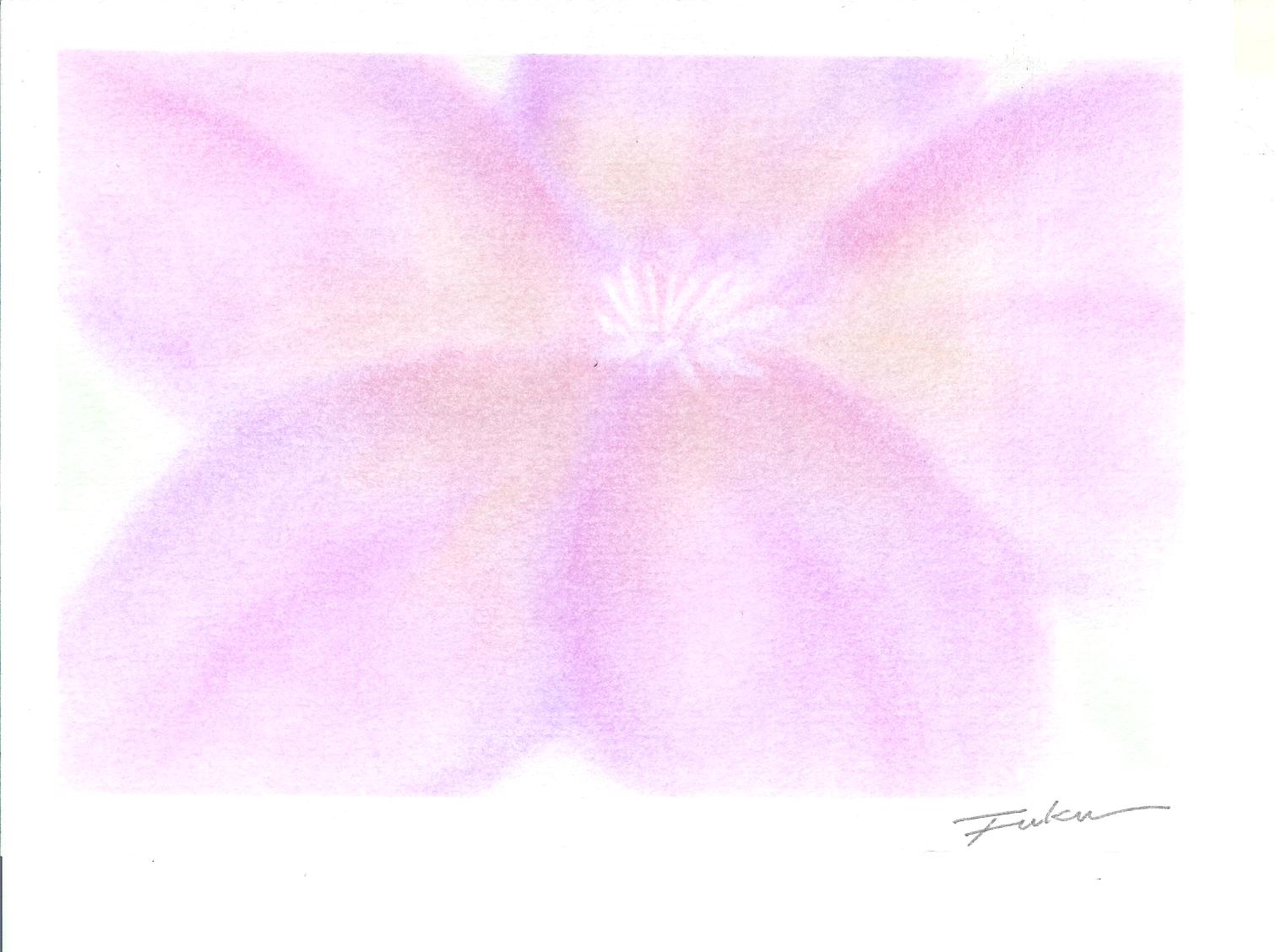
理屈じゃない
人間の本質は、こころ理屈じゃない心が欲しい。だれもがみんな心が満たされたいと願っている。「心をあげる」とはどういうことか?誰もがみな自分の気持ちをわかって欲しい。共感同苦、共感同悲、共感同喜「そうか、そんなに辛かったのか。わかってあげなくてごめんね」「そうだよな~。わかるよ」受け止めること。気持ちを理解してあげること。「頑張れ!」ではない。「そうか~。そんなに苦しかったのか~」心は、満たされきることはない。なぜなら、人間は不完全だから。お互いに「どうして私の気持ちをわかってもらえないのか?」と思っている。誰もがみな「私のことなんかだれもわかってくれない」と思っている。自分がこのように「愛されたい」と思うようには愛されることはない。親は、どんなに努力しても子どもには「父親も、母親も、オレのことをわかっていない」と子どもが思っていることを理解しておくことが大切。それは、子どもが求めるものと、父母が思っていることには、必ず差があるから。男女の関係においても同じ。男性がどれだけ、女性を愛しても女性は満たされることはない。女性がどれだけ男性のことを愛しても男性は満たされることはない。それは、男性が求めるものと女性が求めるものが違うから。「これだけしているのに・・・」と思った瞬間から、押し付けになる。「これでいいのか・・・」「こうしたら喜んでくれるかな・・・」と悩む心に「愛」がある。
2007年06月04日
コメント(0)
-

愛の実力
愛の実体は、努力である。愛とは、違った価値観・考え方を持った人と、共に生きる力である。同じ考え方の人・同じ価値観の人としか暮らせない・仕事が出来ないというのは、本物の愛ではない。それは、理性的な愛である。愛とは、社会を生き抜く力であり、理屈を越えて力である。求める愛から、与える愛へと成長させなければならない。愛は、文学の世界でしか描かれず、学問として、能力として、成長発展してきていない。夫婦・嫁姑・職場での人間関係・・・は、昔から変わっていない。今、愛を能力として、力として、成長させていかなければならない時。命は、愛より生まれ、愛によって育まれ、愛によって満たされる。愛は、命の力。理性だけが、能力ではない。愛も能力として、成長させなければならない。理性を超える能力として、成長させなければならない。能力とは、問題を解決する力。理性によって作られる問題は、理性では解決できない。理性を使って、愛の実力を成長させる。理性を使わないと、愛は生まれない。愛とは、心遣い・思いやり。「どうしたらいいのだろう」と思い悩むところに愛がある。理性と感性の統合。理性と感性のバランスではない。答えは必要。答えに縛られず、「もっといい方法はないか」と問い続けるところに愛がある。答えに縛られると、「これだけやっているのに・・・」と押し付けになってしまう。理性を使わないのは、愛ではない。恋である。恋は、自然発生的なもの。恋は、自然。愛は、努力。結婚は、恋の墓場で、愛の始まり。愛とは、人間と人間を結びつける力。人間関係の力。長く一緒にいると、それまで見えなかった嫌なところ・短所が見えてくる。どんな人間も長所半分短所半分。恋しているときは、長所しか見えない。あばたもえくぼ。結婚すると、短所が短所として見えてくる。短所は、無くならない。短所が無くなったら人間ではない。無くす努力は必要ない。自分にも半分短所があると自覚すること。少しでも出ないように努力する。短所が、人間らしい心を作る。短所こそ人間の本質を作る。愛とは、相手の短所を許し補い、長所と関わる力である。・・・・・・・・・・・・※感性論哲学は、「愛の哲学」「愛」は、文学の世界のものと考えられてきています。芳村思風先生は、愛を学問として捉え、「実力」として成長させるものと話されています。思風塾の講座の中でも人気のある講座です。I WILL フォーラムは、芳村思風先生の「愛の実力 意志の力」の講義とそれを体感・体験学習として体で学ぶ岡部明美さんのワークの組み合わせで進めるセミナーです。6/15から、I WILL フォーラム第4期が開催されます。通算16回目の開催となり、300名以上の方々にご参加いただいています。●I WILL フォーラム「意志と愛」の講座・・・経営者・リーダーのためのセミナーです。「 I WILL フォーラム 」(第4期)日程:平成19年 前期 6月15日(金)~17日(日) 後期 7月13日(金)~15日(日)会場:女神山ライフセンター
2007年06月03日
コメント(0)
-
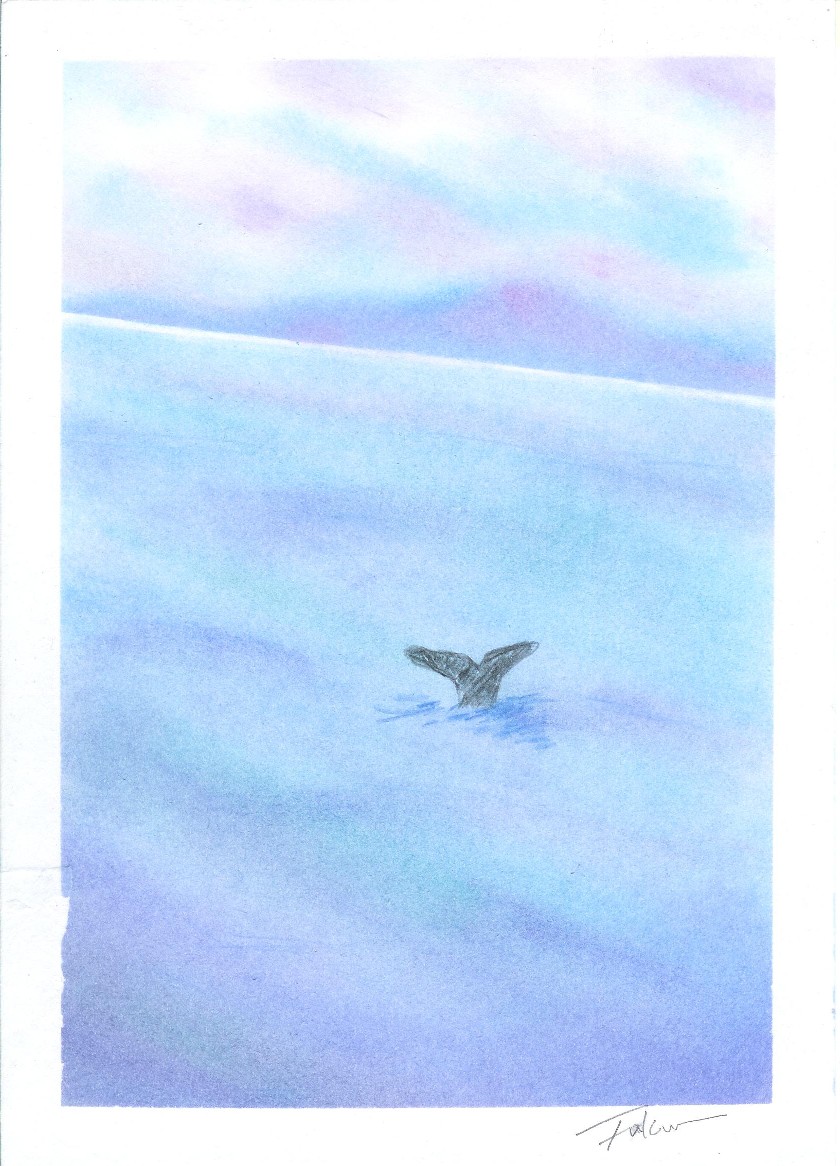
最高の出逢い
最高の出逢いとは、自分を最も輝かせてくれる人との出逢いです。人生は、出会いによって作られる。人との出会い。物との出会い。出来事との出会い。いろいろな出会いにより、道が決まっていく。学生の頃、ある教科の先生にあこがれて、その教科が好きになり、いつの間にか先生になりたいと思った人。天体望遠鏡を買ってもらったことで、毎日、星を眺めているうちに天文学の道を歩み出した人。事故や病気という出来事との出会いで、医者になった人。心の底から興味関心好奇心が湧いてきて気がついたらその道を歩んでいた。最初は興味も関心もなかったけど、縁あってある会社に入社したことにより、一所懸命仕事に取り組んでいくうち、興味関心が湧いてきて、知らず知らずにその道の専門家になることもある。縁は、自分から求めて作れるものではない。人智を超えた「計らい」によって与えられるものである。今、自分の目の前にある問題から逃げずに努力を続けることが、縁を呼び寄せます。自分のしたいことがわからない。そんな時は、今与えられている仕事に全力を尽くす。必死にやってみる。そこから、新しい道が見えてくることがある。考えているだけではダメ。とにかくやってみる。必死でやってみる。必死でやっていると、新しい出会いも生まれるもの。b>「私の言葉だけで日めくりを作ったら、誰が作っても同じです。あなたにしかできない物を作って下さい。」3年前、「先生の言葉の日めくりカレンダーを作りたい」とお願いしたときに返ってきた言葉です。それから、他からも同じようなお話があったのに、今作っていますからと断り続けていただいたそうだ。この言葉がなかったら、今の仕事はありませんでした。それまでは、趣味でやっていた事でお金がいただけるようになった。絵を描くことが仕事になってしまった。不思議なご縁です。
2007年06月02日
コメント(0)
-

生きるとは
生きるとは 人間において生きるとは、ただ単に生き永らえる事ではない。人間において生きるとは、何のためにこの命を使うか、この命をどう生かすかということである。命を生かすとは、何かに命をかけるということである。だから生きるとは命をかけるという事だ。命の最高のよろこびは、命をかけても惜しくない程の対象と出会うことにある。その時こそ、命は最も充実した生のよろこびを味わい、激しくも美しく燃え上がるのである。君は何に命をかけるか。君は何のためなら死ぬことができるか。この問いに答えることが、生きるということであり、この問いに答えることが、人生である芳村思風なんどもなんども読み返した。行き詰まったとき迷ったとき苦しいときどうしていいかわからなくなったときこれだ!これしかない!と思っても、うまくいかなくなると「ほんとうにこれでいいんだろうか?」と迷ってしまう。このためになら死ねるこの人のためなら死んでもいいそんなことに出会えたとき自分の命が震え出す。それは、一生かけて探し続けなければいけないものかもしれない。6月2日(土) 13:00~東京思風塾今回のゲストは、小田全宏さんです、対談は、18:00~受付(18:30~スタート)会場が狭いため、事前にお申し込み下さい。6月2日は、芳村思風先生の65回目の誕生日です。思風塾ホームページ
2007年06月01日
コメント(1)
全29件 (29件中 1-29件目)
1










