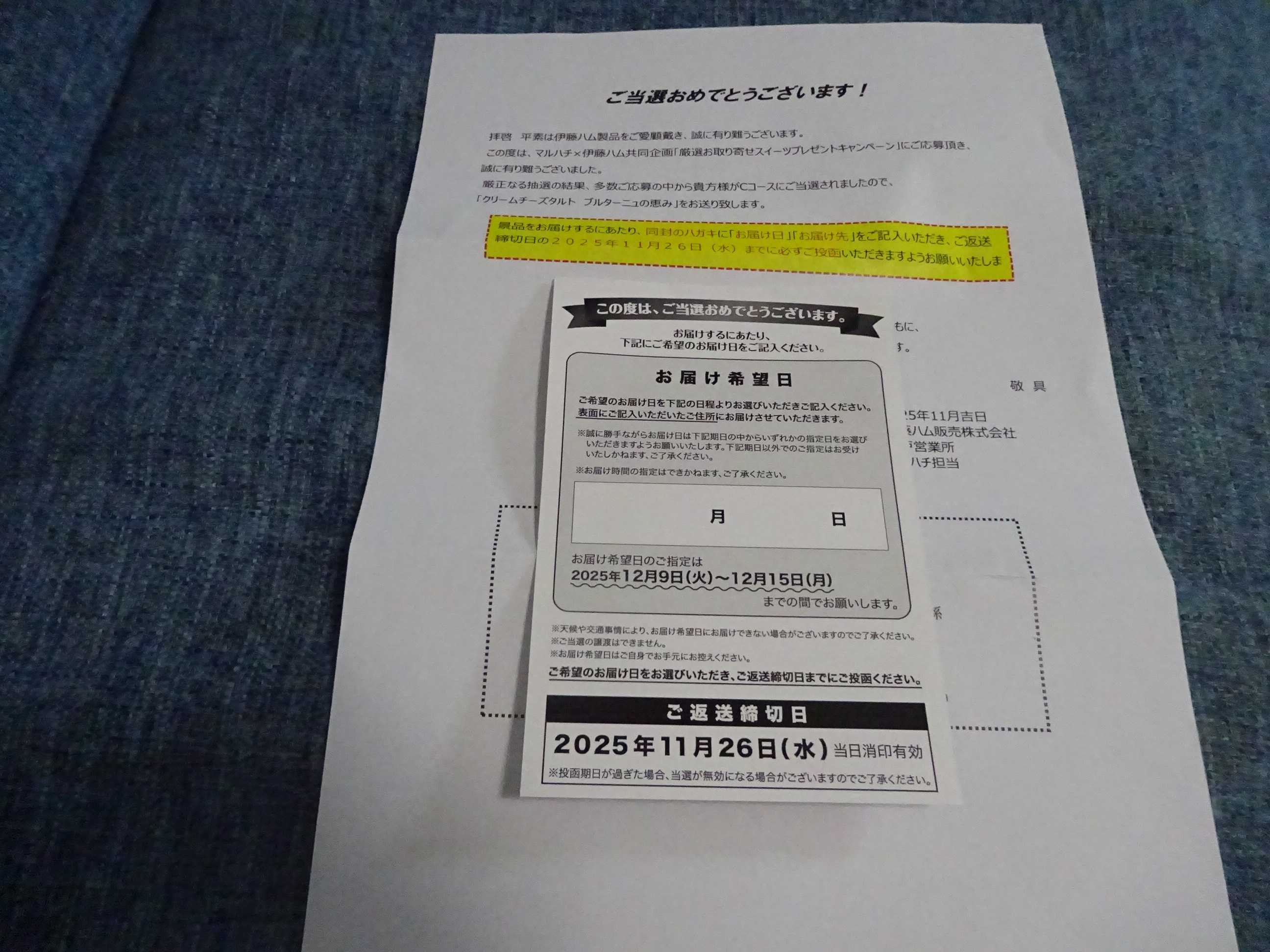2017年01月の記事
全4件 (4件中 1-4件目)
1
-

ぶらり弘前~夏の岩木山神社・奥富士出雲神社
岩木山を祀る岩木山神社です。いつもは正月の初詣ばかりなので、いつも雪で真っ白な岩木山神社しか見てなかったんですね。だから、雪のない景色は神饌。夏ならではの様々な姿を見られて感激しました。撮影は昨年の7月16日。そして今年4月24日に追加撮影。一の鳥居です。石造りの両部鳥居(りょうぶとりい)で、神社の入り口。参道に立つ鳥居の中ではもっとも新しいそうです。大きな石灯籠と、石畳の参道が見えます。「天気が良ければ、ここから岩木山が見られる!」ということで晴天だった4月24日に撮影!確かに鳥居と岩木山が一緒に見られるんですね!真っ青な空に、お山の残雪の白さが映えますね。いや、本当に、山岳信仰なんだなぁ!って実感します。石灯籠の裏には「紀元二千六百年八月一日奉献」の文字が。石灯籠の脇に、掲示板が建っていました。「祭典暦」でした。「四月 一日 月次祭 春季更衣祭 交通安全祈願祭 四日 風神祭 二十九日 昭和祭 五月 一日 月次祭 雪除祭 交通安全祈願祭 六日 花祭り 十一日 白雲祭 十五日 祈念祭」掲示板は本来どのような目的で建てられた物なのでしょう?獅子など、しっかりした彫り物がされていました。同じく石造りの二の鳥居。こちらは明神鳥居(みょうじんとりい)という形で、両柱の脇に稚児柱(ちごばしら)がついていない。素朴な造り。参道の石畳は地元産の「岩木山石(いわきやまいし)」を敷き詰めたもので、300mほど続いているのだそうです。参道の両脇には、岩木山の湧水を湛えた水路が走っています。二の鳥居の向こう右側に立つ、注連縄が巻かれた大木は「五本杉」と呼ばれる御神木。一つの株の根元から5本に別れた幹が聳え立つ、樹高約24m、幹囲7.85m、推定樹齢約500年の巨木。(「週刊日本の神社」より)弘前市の天然記念物に指定されています。こちらは三の鳥居。木製の両部鳥居(りょうぶとりい)で、濃い朱塗り。屋根がかかっています。岩木山神社の中ではもっとも古い鳥居だそうです。岩木山神社の「おみくじ結び所」は、「福を呼ぶ」とされる熊手の形をしています。うっそうと茂る木々に囲まれた参道は階段状。並木は桜、杉、松だそうです。参道脇の木々の根っこも、すごいものがあります。途中石碑がありました。参道脇に建つ石碑です。「奉祟守山三柱大神」おみくじやお守り、お札などの授与所です。丹塗り(にぬり)の楼門の手前には、朱塗りの欄干の反り橋(そりばし)「神橋(しんきょう)」があります。かつてはニジマスが泳いでいたようですが、最近はみかけません。楼門(ろうもん)「百沢寺(ひゃくたくじ)の山門として、二代藩主信枚(のぶひら)の寛永5年(1628年)に建てられた。桁行16.6メートル、梁間7.98メートル、棟高17.85メートル、丹塗り(にぬり)一色の二層の壮大な楼門は周囲を圧する趣がある。柱は総円柱で階上まで通し柱、組物は両階とも三手先詰物、上層縁廻は高欄をまわす。内部は格子戸で内陣と外陣に仕切られ、外陣は板敷、内陣は段違床板張り。百沢寺時代には上層に十一面観音、五百羅漢像を安置したが、廃寺に際して取り除かれ、階下に随神像を祀り現在に至っている。(岩木山神社拝殿・楼門 - 弘前市より)」楼門に向かって左手に控える狛犬。メスなのでツノが生えています。楼門に向かって右側に控える狛犬です。手水処へ向かう道のりには水路が走り、サラサラと流れています。御神水(ごしんすい)手水処(てみずしょ)です。「三つある龍の口からこんこんと湧き出る清水は、岩木山の伏流水。水温は年間を通して11℃前後で、飲用も持ち帰りも可能。その昔、山頂の奥宮へ向かう参拝者はここで水垢離(みずごり)をとっていたことから、「禊所(みそぎしょ)」とも呼ばれている。(「週刊日本の神社」より)」拝殿の脇に建つ「神饌所(しんせんしょ)」。「神饌」とは神様の食事のことで、その食事の支度をするための社殿だそうです。白雲神社へ行く途中からちらりと見える「本殿」は、銅板瓦葺。正面に千鳥破風と軒唐破風。「本殿には細部まで精巧な彫刻が施されており、龍や獅子、鳳凰などが至るところからご祭神を守護し、睨みを効かせている。(「週刊日本の神社」より)」拝殿です。「慶長8年(1603)に初代藩主・為信が寄進、寛永17年(1640)に完成」正面に下がる注連縄(しめなわ)は、端の飾り結びが特徴的で、駒越の愛宕神社でも同じ結び方を見かけました。「岩木山神社は山岳信仰に始まる古社で、この拝殿は元来、岩木山神社の別当寺・百沢寺(神仏分離により廃寺)の大堂(本堂)として建てられたものである。天正17年(1589年)の岩木山噴火によって百沢寺全山が焼失した後、藩祖為信が慶長8年(1603年)に起工し、三代藩主信義の寛永17年(1640年)に至って完成した。壮大な五間堂で、外部を全面丹塗り(にぬり)、内部を弁柄塗り(べんがらぬり)とするが、千鳥破風内の彫刻や蟇股(かえるまた)は極彩色で美しい。内部の構成も明快で、密教寺院本堂としての雰囲気を今に伝えている。(岩木山神社拝殿・楼門 - 弘前市より)」拝殿の千鳥破風には、弘前城から見て西にあるため、西の守り神「白虎(びゃっこ)」が彫られています。目は弘前城を見つめているとか。拝殿の内部をちょっと。元禄7年(1694)、4代藩主信政(のぶまさ)公が建立した国指定重要文化財瑞垣(みずがき)です。「瑞垣とは、玉垣(たまがき)ともいい、神社・神域の周囲にめぐらされる垣のこと。 斎垣(いみがき、いかき、いがき)、神垣(かみがき)も、すべて同じ意味を持つ。「玉」や「瑞」、「斎」という言葉はともに「神聖な」「美しい」という意味を持ち、囲いの意味である「垣」と組み合わさって「神聖なすばらしい神の為の囲い」という意味の言葉となっている。(「Wikipedia」より)」元禄7年(1694)、4代藩主信政(のぶまさ)公が建立した国指定重要文化財中門重厚な黒漆塗りの門に、見事な彫刻と、目に鮮やかな彩色。中門の金色の飾り飾りだけアップで。中門は奥の本殿と同じ時に建てられたため、よく似た豪華さがあります。中門を中から見上げたもの。どちらにも、真ん中に鳥が彫刻されています。中門の『北門鎮護』の扁額は「東郷平八郎」の揮毫(きごう)によるもので、日露戦争の折につくられたそうです。天井には、かなり色あせてきてますが、龍が描かれています。中門の天井に描かれた龍。色あせてきているものの中で、まだ鮮やかさを思わせる絵が一つありました。岩木山神社中門と、瑞垣(みずがき)と、狛犬中門の前(向かって左側)に鎮座する狛犬中門の前(向かって右側)に鎮座する狛犬神社の境内に3対ある狛犬も、参道に敷き詰められた300mの石畳も、地元産の「岩木山石(いわきやまいし)から作られているそうです。中門の手前に大きな灯籠があります。奥宮登拝道入口石碑には「岩木山神社奥宮(おくみや)登拝口(とはいぐち) 頂上迄里程(りてい)六千三百五十二米(メートル)」と刻まれています。登拝道に通じる階段です。「1,625m岩木山頂上・奥宮 二神石1,560 大倉石 1,470 鳳鳴(ほうめい)ヒュッテ・種蒔苗代左側1,502ケルン1,340 錫杖清水1,300 アラレ坂1,280 石穴(山ノ神)1,180 坊主コロバシ1,140 焼止 大沢 830 岳樺 720 姥石 680 鼻コグリ(急坂) 640 420 七曲 380 箸立 310 桜林 230 現在地 200南側百沢口登山路岩木山百沢登山道(奥宮登拝道)岩木山は、中世以降修験道の峯入り修行の場となる。山で霊魂が再生するという古い観念は、修験道や山岳仏教とつながって盛んとなった。これが次第に供養ともなり五穀豊穣祈願の山かけや、成人儀礼のお山参詣(登拝行事)に発展した。山頂まで約6kmには、七曲がり、坊主転ばし、鼻こぐり等苦行に必要な難所があり、二十六神(天然石)の巡礼を経て約四時間、奥宮(山頂)に達する。」山頂まで四時間十五分!楼門には二体の像が安置されています。「随神像」というのだそうです。「百沢寺時代には上層に十一面観音、五百羅漢像を安置したが、廃寺に際して取り除かれ」てしまったのだそうです。こちらは拝殿に向かって左側の「随神像」です。年が若く見えますね。(クリックするとフォトライブラリーで購入できます)「楼門前の石垣には、石柱にじゃれつくようなポーズの狛犬2頭が潜む。石柱とともに重さ約2tの一つの岩から削り出されたもので、元禄7年(1694)の建立。石を運んだ怪力男の半右衛門(はんうえもん)は、渾身の力を振り絞ったために目玉た飛び出したと伝えられている。(「週刊日本の神社」より)」「この狛犬と写真を撮るとさまざまなご利益をお受けできると、巷では人気のパワースポットとなっています。上を向いている狛犬と写真を撮ると、金運など喜び事の運気がアップするといわれ、下を向いている狛犬と写真を撮ると恋愛運がアップするといわれています。(「週刊日本の神社」より)」上を向く狛犬の後姿。一緒に写真を撮ると恋愛運がアップするといわれている、下を向く狛犬。下を向く狛犬の後姿。神社の帰り道、参道を見下ろした写真です。岩木山神社の境内、楼門から少し下った左側に、「社務所」が建っています。大きな萱葺きの屋根!県の重要文化財に指定されています。「木造平屋建 主部入母屋造 茅葺 玄関2箇所付 切妻造 鉄板葺(旧柾葺) 江戸時代末期の建築。座敷廻りに土縁を巡らし、「御座の間」と呼ぶ上段を中心にとり、「御次」、「御膳立」などを並べているところは、藩主の参詣を想定したものとなっている。社務所として若干の改造を受けているが、大きな入母屋造茅葺屋根の景観は圧巻である。(「岩木山神社社務所 - 弘前市」より)」もともとは、別当寺(べっとうじ)・百沢寺(ひゃくたくじ)の庫裏(くり)だった建物で、弘化4年(1847)の造営だそうです(週刊日本の神社より)。ロッカーの上には、大きな下駄が飾ってありました!座敷廻りの土縁社務所の周りに茂る木々の間からのぞむ楼門。大ぶりの長方形の石畳で、一部小さな橋がアーチ型にかかっています。庭から中が少し覗けました。龍の水墨画と素敵な布がかかっていました。社務所の内部の様子です。一部に赤いカーペットを敷き、テーブルと椅子がしつらえてあります。奥には立派な庭と池があります。ほたるでも出そうなきれいな池です。おたまじゃくしが泳いでいました。宇賀能賣神(ううがのめのかみ)を祀る末社「稲荷神社」稲荷神社に向かって左側に鎮座する狛犬。前掛けがかわいいです。そういえば、稲荷神社なのに狐様じゃなく狛犬?!池の浮島には白雲大龍神(しらくもだいりゅうじん)・多都比姫神(たつひひめのかみ)を祀る末社「白雲(しらくも)神社」です。「白蛇の池は、清らかな池です。タマゴはご神前にお供え下さいますようお願い申し上げます。岩木山神社神事課」の立て札がありました。蛇の好物である卵を奉納するのが習わしらしいです。清らかな水は、奥の山から流れてきていました。白雲神社に向かって右側の狛犬です。白雲神社に向かって左側の狛犬です。倒木には苔が生えており、大きな石の鉢がありました。白雲神社の敷地から、岩木山神社の鮮やかな本殿が少し見られました。横木が柱から突き出した部分に、彫刻を施したものを「木鼻(きばな)」という。本殿の木鼻には象や獅子、獏(ばく)などが刻まれている。(「週刊日本の神社」より)屋根の破風板に取り付ける飾り板の「懸魚(げぎょ)」には、海老などが彫り込まれている。(「週刊日本の神社」より)岩木山神社の入り口からほど近い所に建つ「奥富士出雲神社」御祭神は顕国魂神だそうです。 赤の鳥居と、石の鳥居「ノモンハン戦没勇士慰霊碑」「旧部隊長 須見新一郎書」奥富士出雲神社の拝殿です。梁にはたくさんの千社札が貼られていました。おみくじやお守りはここで買えるようです。(クリックするとフォトライブラリーの画面が開きます)拝殿の中です。左奥にはお神輿も見られます。ここの鈴は、縄にたくさん小さなかわいい鈴が結わえ付けられていました。鈴の中にはいろんな形のものがあって、探すのが楽しいですよ。「神社本庁 | 参拝の際に鳴らす鈴について 社頭に設けられた鈴は、その清々しい音色で参拝者を敬虔な気持ちにするとともに参拝者を祓い清め、神霊の発動を願うものと考えられています。」奥富士出雲神社の境内に建つ「白龍神」の祠です。石の鳥居の左側に座している「恵比寿様」の像。石の鳥居の右側に座している「大黒天様」の像。参道入口に建つ「山陽の茶屋」さん。足湯の看板も。「そば・うどん」ののれんのある、和風の佇まいの店頭足湯はここで「おはぎ国産の良質素材使用。餅米は白鳥米、小豆は北海道産を使用。濃厚でしかも後味すっきりの甘さ控え目のおはぎに仕上げております。1ケ150円。」氷みるく、かき氷、どんぶりざるそば、野菜かき揚、カレー(うどん・津軽そば)の他にも、コーヒーやHOTアップルなども
2017年01月31日
コメント(0)
-

胃がん検診の結果/ピロリ菌の除菌が始まります
胃カメラをのんで2週間。精密検査に出された胃の細胞は、3つとも正常な細胞でした!!!あー、良かった!そして医師から処方されたのが「ボノサップパック400」ヘリコバクター・ピロリ感染症に対する除菌療法に使用する薬剤です。「タケキャブ20×1錠、クラリス200×1錠、アモリン250×3カプセル」が1セットで、朝用と夕方用に色別され、ミシン目でつながった1シートになっています。1週間分の処方なので、全部で7シート。抗生物質なので腸内細菌が死んでしまうとか!?大事に育ててきたのに残念。。お腹がゆるくなることもあるので、ヨーグルトなどを食べるようにとのこと。また、1日目2日目の副作用が心配なので、病院が開いている平日に開始するようにとの指示でした。これらを服用している間は、胃薬は中止。「強力かつ持続的な酸分泌抑制作用を示すタケキャブ錠を含めた3剤を1日服用量として1シートにまとめて包装した製品です。抗生物質がピロリ菌に効果を示すためには、胃の酸性度pHを弱めなければなりません。 そのためには胃酸の分泌を抑えるプロトンポンプインヒビター(PPI)という薬が使用されます。 ボノサップとランサップはPPIと抗生物質1日分を1シートにまとめた薬です。 そのちがいは、PPIのちがいです。 ボノサップ・・・タケキャブ(ボノプラザン) ランサップ・・・タケプロン(ランソプラゾール)ボノプラザンの酸分泌抑制効果はランソプラゾールより強力で、除菌効果も大きく凌駕する結果が出ています。また、抗生物質であるクラリスロマイシン(クラリス錠)が効きにくくなっている耐性ピロリ菌に対する除菌率ではボノサップはランサップより高い除菌率を維持しました。(「ボノサップパック400と800のちがいとランサップ | YG研究会 賢く生きる」より)」
2017年01月27日
コメント(0)
-
【定期血液検査】グロブリン点滴あり/先日の胃カメラについても
白血球数3860(3500-8500)ヘモグロビン11.7(11.5-15.0)血小板数32.5万(15-35)網赤血球18.8(5-25)IgG(免疫グロブリンG)343(870-1700)IgA 26(110-410)IgM 27(46-260)フェリチン27.0(12-60)CRP(C反応性 タンパク)0.064(0.000-0.300)総蛋白(TP)5.6(6.7-8.3)アルブミン4.3(4.0-5.0)尿酸(UA)2.6(2.3-7.0)今日は予定通り、というか覚悟していた通りグロベニンの点滴がありました。点滴すると脈拍が速めになるので、ゆっくり落としたら3時間以上かかってしまいました。IgA,IgMの数値が少し高め(私なりに)なのが少し嬉しかったところです。フェリチンはまた値が下がりました。鉄剤を飲んでもなかなか貯まりません。先週、胃カメラを飲みました。かなりしんどかったです。ピロリ菌というのは胃の下部、十二指腸に近い所にまず住み着き、長い年月を経て、徐々に上部へと上がって来るのだそうです。胃酸に強く、胃を荒らしてしまうというピロリ菌。私の胃も、20数年前には綺麗とお墨付きだったのに、血管が透けるほど薄くなった壁や、もこもことひだが厚くなった壁など、荒れ放題でした。揚げ物や辛い物に弱くなったのは、そのせいでしょうね。今は画像をデジタルで撮って、パソコン管理するので、展開が簡単になってます。生検3つの検査結果は来週。何事も無いことを祈るのみです。
2017年01月19日
コメント(0)
-

ぶらり弘前~岩木山神社で初詣~「巨大絵馬」と「注連縄の端の飾り結び」
明けましておめでとうございます!今年もどうぞ宜しくお願いします。今年も初詣は岩木山神社です。混雑する三が日を避けて5日となりました。「開運招福」今年・酉年の巨大絵馬です。堂々としたニワトリと、可愛い3匹のヒヨコたち。拝殿正面に下げられた注連縄(しめなわ)は、「端の飾り結びが特徴的」ということなので撮影してみました。井形になってます。
2017年01月05日
コメント(0)
全4件 (4件中 1-4件目)
1