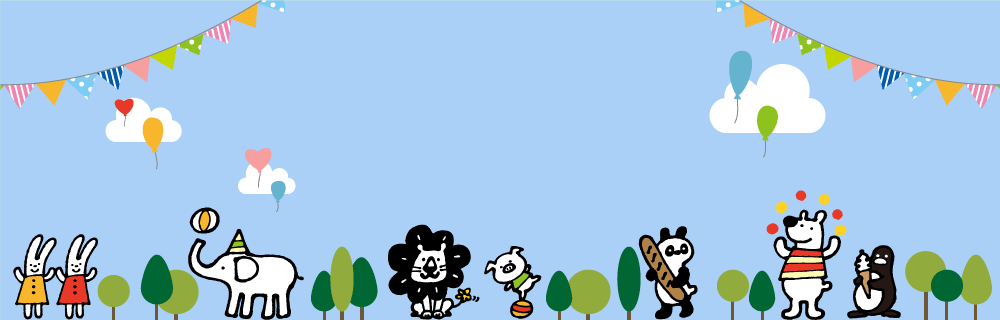カテゴリ: 反戦平和
ヒロヒト(裕仁)の始めた侵略戦争(誰も止められなかった)、驚くべき狂気の(特攻)・・・・現在は、プーチン、習近平、金正恩たちの蛮行(これも誰も止められないでいる)を見ていて、わかる人間の限界性・・・
2024-11-25 はんぺん
<学徒特攻隊 死の波紋>
NHKの(映像の世紀)は、考えさせられることが多い。
同時に(人間)の愚かさ、どうしようも無い(限界)を感じさせてくれる。
この地球を(支配)しているのは、今は(人間)かもしれないが、100年500年、1,000年先には、果たして、どうなっているのか? 我々人類は、種として存在しているのだろうか? 誰にもわからない・・・・ そういう世界観に至りつつある。
それは、この時代の
ヒロヒト(裕仁)の始めた侵略戦争(誰も止められなかった)、驚くべき狂気の(特攻)
を見れば、分かるが、
現在のプーチン、習近平、金正恩たちの蛮行(これも誰も止められないでいる)
を見ていて、なおさら、その確信を強くするに至る。
戦争という興奮状態は、作りだされた(妄想の現実化)だ。
「そのころ東京では、特攻に踏み切ったことを海軍トップの軍令部総長が昭和天皇に上奏していた。 それに対する 天皇の言葉
が残されている。
『そのようにまでせねばならなかったか。しかしよくやった』
」(本文)
ヒロヒト(裕仁)たちは、
「一撃講和」 という考えの下、
「一切の力を傾倒していっぺんだけでも勝とうじゃないか。勝ったところで手を打とう。勝った余勢を駆って講和すれば条件は必ず幾らか軽く有利になる」 と考え、 (一億特攻作戦)
は、続けられた。
軍とマスコミ(新聞・ラジオ)
は、勇ましい言葉による
(洗脳の嵐)
を繰り返す。一色に
染められた国民は、特攻の戦死者を
「軍神」
と称えながら、さらに
(特攻)を後押し
する・・・・この(悲劇)は、日本民衆の地獄への転落まで、続く・・・・・・・
今、プーチンや金正恩は、核の脅迫を隠さない言動を 繰り返している。
反核平和運動は、それなりの意義はあるだろうが、 全体主義者(独裁国家)による、核の脅迫は、全体主義国家が続く限り、絶え間なく繰り返されるだろし、今現在、それに屈服して得られるものは何もない・・・
と断言できる。
皆さんは、どう思われるか? はんぺん
―――――――――――――――――――――――
“一億特攻”への道 〜隊員4000人 生と死の記録〜
初回放送日:2024年8月17日 NHKアーカイブス
番組では 15年に及ぶ取材で特攻隊員約4000人の本籍地や経歴を徹底調査
。隊員がどのように選別されたのか、これまで謎だったその実態に迫る極秘資料も入手した。浮かび上がってきたのは、当時の日本人が特攻を希望とみなし、国のすみずみまで熱狂が支配していく様だった。
その背後には軍とメディアによるプロパガンダや、特攻を軍部内の力学に利用しようという思惑も…。隊員たちの心情も描きながら「一億特攻」の真相に迫る。
その背後には軍とメディアによるプロパガンダや、特攻を軍部内の力学に利用しようという思惑も…。隊員たちの心情も描きながら「一億特攻」の真相に迫る。
「特攻」は、 今から80年前、太平洋戦争終盤の1944年10月に始められた
。最初に命じた司令官自ら 「統率の外道」
と語った作戦。終戦当日まで10か月にわたり続けられた。隊員たちの出撃が次々と報じられる中、国民の多くも、彼らに続けと 「一億特攻」
を叫んだ。
かつて、 人々の“希望”だったという体当たり攻撃
。特攻が行われた時代を、今の私たちはどう理解したらいいのか。特攻とは、一体何だったのか。日本が突き進んだ「一億特攻」への道をたどった。
<「大君の楯」の熱狂>
2024年4月、福岡県八女市。この地域の遺族を1軒ずつ訪ねていた時、特攻の時代を覆った熱気のようなものを感じる遺品に出会った。
戦死したのは、河島鉄蔵(かわしま・てつぞう)さん。14歳で志願して少年飛行兵となり、 18歳7か月
で戦死した。
遺品の中に、当時の婦人向けの雑誌が見つかった。ページをめくると、巻頭のグラビアに鉄蔵さんら特攻隊員の特集が組まれていた。
見たことのない分厚い和紙の束が出てきた。
「特攻の 神鷲となりて 大君の 守護(まもり)つくせる 君ぞ尊き」
国民学校の教師たちが書いたもの
だった。その数 、700人以上
。18歳の若さで国に命をささげた、と河島さんをたたえていた。追悼の言葉を贈ったのは、河島さんの母校の教師だけではなかった。調べてみると、 当時の八女郡全域、50の国民学校に及んでいた。
つづりの中で、特に目を引いた言葉があった。自らを教育界の特攻隊員と呼ぶ、20代前半の教師のものだ。
「そうだ僕は歯車だ。歯車になるんだ。ぢりぢり回って特攻隊員をつくるのだ。やるぞ、やるとも、やるんだ」
自分は、歯車であるとまで書いた教師。 遺品が教えてくれたのは、 日本の隅々で戦争を支えた国民抜きには特攻は語れない、
ということだった。
<特攻の先陣を切った 予科練生
>
そもそも、特攻が始まったのは、 1944年10月、南方フィリピンでのこと
だった。
現地航空隊の司令官、 大西瀧治郎 (おおにし・たきじろう)
中将
は、爆弾を抱えたゼロ戦で、敵の空母に体当たりするよう、搭乗員に命令を下した。
太平洋戦争が、 3年目に入ったこの年、アメリカの圧倒的な航空戦力を前に、日本は敗退を重ねていた。7月には、本土防衛の要とされていたサイパンが陥落。戦闘の巻き添えとなって、民間人およそ1万人が犠牲となり、この島から大型爆撃機による本土への空襲が始まろうとしていた。そして10月、日本軍が決戦場としていたフィリピンにアメリカの大軍が押し寄せた。
10月25日、22人の隊員がフィリピンの基地を出撃した。
彼らの最期はどのようなものだったのか。航空戦史研究家の織田祐輔 (おりた・ゆうすけ)
さんは、米軍の撮影した映像と日米の報告書を突き合わせ、いつ誰の最期を捉えたものなのか、特定している。その中に、これまでないとされてきた、10月25日、最初の体当たりの映像が見つかった。
織田さん「こちらが、今まさに下にいる航空母艦に体当たりを行おうとしている日本の特攻機の零戦になります。
コマ送りにして見てみると、きりもみをしながら空母の飛行甲板目がけて急降下していっているというのが分かります」
この体当たりを行ったのは、加藤豊文 (かとう・とよふみ)
さんか、宮川正 (みやがわ・せい)
さん。加藤さんは、徳島県出身の 20歳3か月
。高知県出身の宮川さんは、 18歳1か月
だった。
そしてもう一人、映像が見つかった隊員がいた。新潟県出身の廣田幸宣 (ひろた・ゆきのぶ)
さん、 20歳4か月
。
廣田さんは、最初の特攻から5日後の10月30日、6機からなる体当たり攻撃隊の2番機として出撃。午後2時半過ぎ、1番機に続いて突撃を開始した。
空母すぐそばの海に1機目が突入し、黒煙を上げている。そこに、廣田さんの2番機が突入していく。
体当たりを行った3人の経歴を調べると、彼らは、 海軍の飛行予科練習生、「予科練」の出身という共通点
があった。
予科練は、主に10代の少年を飛行兵に鍛える養成機関。彼らは、軍人として人生を切り開こうと志願してきた。国内各地の航空隊で飛行訓練を積み、やがて、戦闘機や爆撃機などの搭乗員として太平洋の戦場へと送り込まれた。
廣田さんが戦死した10月30日まで、最初の1週間の戦死者は76人。そのうち、46人を20歳以下の予科練出身者が占めていた。なぜ、若い彼らが選ばれたのか。
廣田さんたちの出撃から突入まで、護衛機から間近で見ていたベテラン搭乗員の角田和男 (つのだ・かずお)
さんに話を聞いたことがある。
開戦以来、数々の激戦を生き抜いてきた角田さんは、当時26歳。日本軍の実情、アメリカとの戦力差を肌身で感じていた。
角田さん 「このクラス(若い予科練出身者)の人たちは、どっちみち逃げ道のない一番使いごろのクラスでしたからね」
取材スタッフ「使いごろ、というのは?」
角田さん 「みんな仲間が死んでいて、当然自分たちも死ぬのが当たり前のような状況をくぐってきた人たちですね。零戦による空戦訓練も未熟なまま 戦争をやって落とされた人の生き残りなんですよね」
廣田さんが戦死する半年前、内地から最前線に出る直前、部隊で撮影した写真。
彼らの多くが、戦況が悪化する中、訓練期間を短縮されて戦場に送り出され、命を落としていった。
廣田さんと共に戦い、特攻作戦の開始を告げられた時も一緒だった井上武 (いのうえ・たけし)
さん。ある晩、司令部の薄暗い部屋に集められた、と語った。
井上さん 「戦況が悪いから体当たりを決行しなきゃ、勝つ見込みがなくなってきたというような話
をしてね。これでもう終わりかなと思いましたよ、あの時はね。自分の命はこれで終わりかなと。みんな黙ってね、引きあげていったんですよね。いつ順番がくるのかなって、そんなことをぼそぼそ話しながら兵舎へ引きあげていった」
< 「一撃講和」
軍の冷徹な思惑
>
そのころ東京では、特攻に踏み切ったことを海軍トップの軍令部総長が 昭和天皇に上奏
していた。 それに対する 天皇の言葉
が残されている。
「そのようにまでせねばならなかったか。しかしよくやった」
特攻を否定しないこの言葉の背景には、当時、 天皇や軍首脳が抱いていた 「一撃講和」
という考えがあった。
陸軍大将で、この時首相を務めていた小磯國昭(こいそ・くにあき)が、その思惑について戦後語り残している。
・・・・・・ 「一切の力を傾倒していっぺんだけでも勝とうじゃないか。勝ったところで手を打とう。勝った余勢を駆って講和すれば条件は必ず幾らか軽く有利になる」
このまま負け続け、連合国が求める無条件降伏に追い込まれれば、天皇中心の国家体制が危うかった。しかし、軍内部には、和平を拒み、徹底抗戦を唱える強硬派が存在していた。
連合国が戦争継続をためらうような被害を与え、有利な講和を引き出すとともに強硬派を納得させる。その 「一撃講和」 の有効な手段とされたのが、特攻だった。
連合国が戦争継続をためらうような被害を与え、有利な講和を引き出すとともに強硬派を納得させる。その 「一撃講和」 の有効な手段とされたのが、特攻だった。
<予科練生たちの本音>
国家の思惑を背負わされ、特攻の先陣を切った若者たち。彼らの素顔を知るために、どうしても見ておきたい資料があった。
広島県江田島、海上自衛隊 第1術科学校の資料館に、戦後、家族から寄贈された特攻隊員の遺品が収められている。
都道府県別にまとめられた特攻隊員のファイル。全戦死者の半数近く、1,827人分に及ぶ。原則、遺族にのみ認められる閲覧を、今回、特別に許された。
軍の厳しい検閲の中、彼らは、入隊してから戦死するまで、家族に宛て多くの言葉を残していた。
その中に、逃げる空母に体当たりしたあの廣田幸宣さんの遺品が見つかった。「急報」と書かれた訓練時代の手紙。母宛てに、手作りのぼた餅を送ってほしいと絵までつけている。
廣田さんの最後の手紙は、特攻が始まる半年ほど前、前線に出る時のものだ。その後の運命を考えると、胸が痛む内容だった。
「今は命を大切にして、憎い米機を片端から撃ち落とし、日本を泰山の安きに置く迄は、尊い生命を投げすてる如き事はしません。体当りでは現在の日本は、勝つ事は出来ません」
<国内の熱狂>
一時的な命令だったはずの特攻は、軍の正式な作戦となり、継続された
。戦死した隊員のふるさとは、11月の終わりまでに248か所に増えていく。
そして、 特攻を後押しする歯車
が回り始める。 マスコミ
は、国を救う自己犠牲の美談として、特攻を報じ始めた。こちらの 「靖国隊」のニュース映像
は、全国の映画館で上映され、大きな反響を巻き起こした。
隊員たちのふるさとは、沸き立った。香川で農業を営む寺島忠正(てらしま・ただまさ)さんの家には、村人たちが石 造りの碑
を建て、 軍神
と刻んだ。
靖国隊には、朝鮮の若者もいた。印在雄 (イン・ジェウン)
さん。植民地の人々を戦争に協力させたい軍の意向で、 新聞は「半島に靖国の神鷲」
とたたえた。
この後、終戦までの間に、朝鮮半島から16人が特攻で戦死していく。
そして、福岡県八女郡。河島鉄蔵さんの遺族には、地域の教師たちから、あの「大君の楯」が贈られた。
<一億総特攻 熱狂をあおる軍>
国を覆う熱狂を更に燃え上がらせたものがある。戦争の時代に急速に普及した、 ラジオ
だ。こちらは、12月17日のある番組予告。この日の晩、日本放送協会(現・NHK)が、特攻隊員の遺言を放送するという。
遺言は、この10日前にフィリピンで戦死した護国隊という部隊の若者たちが残したものだった。彼らの自宅には、放送に合わせて報道陣が押しかけた。
大阪市出身の瀨川正俊(せがわ・まさとし)さん。母、そして兄夫婦がラジオの前に座った。
「正俊はこのたび、帝国軍人として最高の名誉を与えられました。ありがたき陛下のお言葉までいただいて、光栄に感激いたしております。母上様、お元気ですか。二十一星霜(せいそう)の御薫陶、必ず無にはしません。必ずお役に立ちます」
この放送に違和感を抱いた国民もいた。 作家の一色次郎
(いっしき・じろう)。
「暗くなってから 昨夜の放送のことを考える。ちょうど、いまごろの時間だったというふうに。 すると、なんともいえない憤りが胸にこみあげてきた。放送したということに対して。本人があわれだ」
だが、 あとに続けと叫ぶ声の方が大きかった。
伊藤忠商事の会長・伊藤忠兵衛 (いとう・ちゅうべえ)
は、隊員の言葉に感激し、放送の5日後、経営する工場の従業員に訓示を行っている。
「国民が半ば気狂にならなければ、いわゆる興奮状態にまで仕事を向上しなければ、兵隊さんに済まぬ。我々、内地勤務の者は、全く軍人と同精神で職務に当るべきであります」
(※訓示を原文のまま引用)
フィリピンで体当たり攻撃が始まって1か月余り。 「一億特攻」
という言葉が新聞に登場する。瞬く間に広がり、人々が口にするスローガンになった。
特攻と日本社会との関係を研究する一ノ瀬俊也(いちのせ・としや)さん。 「一億特攻」が広く浸透した背景には、当時の日本人がとらわれていた一つの考えがあった、と教えてくれた。
埼玉大学・教授/一ノ瀬俊也さん 「日本がアメリカに比べて国力で劣っていることは、誰でも知っていることです。当時の日本ではそれをどう覆すことになっていたのかというと、これは精神力しかないと。 物量
に対して 精神力
で対抗する。
アメリカ人は、みんな自分のことしか考えていない。民主主義国家では、国のために命を捨てるような人は現れない。アメリカには絶対にできない。日本人にしか絶対にできない。崇高な精神力の発揮である。これで戦争に勝てるかもしれない。
アメリカ人は、みんな自分のことしか考えていない。民主主義国家では、国のために命を捨てるような人は現れない。アメリカには絶対にできない。日本人にしか絶対にできない。崇高な精神力の発揮である。これで戦争に勝てるかもしれない。
そういうふうに考えたからこそ、当時の人たちは熱狂して感動したのではないか。特攻作戦というのは、指導者たちが行ってそれで終わりというわけではなく、 それを待ち望んでいた国民の世論というか、感情というか、そういうものがないとなぜあれだけの熱狂が広がっていったのか
。戦争があと数か月長々と続いていったのはなぜかを理解することはできないと思います」
<戦場の 「学徒特攻隊」
>
1945年8月の終戦の日までに4,000近い命が失われていく特攻隊員たち
。戦死した日付は、戦局の推移と密接に関係している。10月にフィリピンで始まった特攻は、12月にピークを迎え、終わっていく。
1945年1月、アメリカ軍がマニラ付近に上陸し、日本軍の航空隊はフィリピンから撤退。 特攻ではアメリカの進撃を止めることも、一撃講和の糸口をつかむこともできなかった。それにもかかわらず日本は特攻を続けていく。
そして、沖縄戦が行われる3月から6月にかけて、更に大きな山が現れる。
誰がそれを担ったのか。まずは、 予科練など少年飛行兵の出身者。もう一つは、エリート士官。海軍兵学校や陸軍士官学校などの出身で、率先して命を懸けて戦うよう教え込まれていた。そして、大学や専門学校など学徒の出身者。およそ1,000人。
沖縄戦以降、主力の一部を担っていく。
彼らが直面した「一億特攻」とは、どのようなものだったのだろう。
遺族の黒部栄子(くろべ・えいこ)さん。5歳年上の兄を戦争で亡くした。兄の力雄(りきお)さんは、短距離走の有力選手だった。太平洋戦争開戦の翌年に中央大学へ入学し、陸上部の主将として競技に打ち込んでいた。しかし、その夢が絶ち切られる。
1943年10月、出陣学徒壮行会。
行進する学徒の中に力雄さんもいた。それまで学生は、国の将来に必要な人材として、徴兵を猶予されていた。しかし、 兵力不足が深刻になる中で、文科系学生の徴兵猶予は停止された。
学徒出陣には、もう一つ狙いがあったとされる。 当時の首相・東條英機
が記者に語った言葉。
「学徒の入営はよかったね。何よりもよいことは、上下の家庭がこれでまったくひとつになったことだ。精神的にも挙国一致になってきた」
このころ、高等教育を受けられたのは、経済的に恵まれた家庭を中心に、国民の6%ほど。 大多数の国民は、徴兵で家族を兵隊に取られ、不満が高まっていた。
入隊の日、隣組に見送られる力雄さん。
この日を境に、力雄さんの運命は急変していく。2か月後には、一緒に入隊した元学徒たちと、搭乗員になるための訓練を開始。なんとか練習機を操縦できるようになった頃、フィリピンでは特攻が始まっていた。
1945年4月16日、力雄さんに沖縄への出撃が命じられる。最初の実戦が、体当たりだった。
妹・栄子さん「決心がつくまでの心の中の葛藤っていったら、並大抵ではなかったのかな。でもね、もう最後だという時は、やっぱり覚悟というか、あきらめっていうかな。そういう心境でなかったかなと思う。どうあがいても、逃れられないですからね」
<学徒を飲み込む組織の論理>
ところで、特攻隊員は、いったいどのように選ばれていったのか。実は海軍省では、主に国内で訓練中の搭乗員たちに特攻に志願するか、一人一人、意向を調べていたとされているが、実態はこれまで謎だった。
今回、その真相に迫る重要な資料が見つかった。調査に基づき、55の航空隊が海軍省に提出した搭乗員のリストだ。2,132人分に及んでいた。
一番上の欄には、志願の程度を表す文字。その下の欄には、人物評。搭乗員としての適性や技量について、上官のコメントが添えられていた。そして、詳細な家族構成まで。
このリストを踏まえ、海軍省が特攻隊員を選び、前線に送り出していたと考えられる。
この志願調査が行われた時の話を聞かせてくれた元搭乗員がいた。学徒出身だった土方敏夫 (ひじかた・としお)
さん。現在の東京理科大学に在学中、海軍に入隊した。夢は数学の教師。結婚を約束した女性もいた。
土方さんの部隊では、調査は特攻が始まった翌月の1944年11月に行われた。 「熱望」
か 「望」
か、あるいは 「否」
か。 各自が紙に書き、人のいない司令室に置きに行く仕組みだった。
土方さん「考えましたね。志願しちゃえば確実に死ぬわけですからね。やっぱり親のこととか、兄弟のこととか、そういうことが一番先に考えられましたね。 それで、嫌だったですね。敵の弾に当たってぶっ倒れるのはしょうがないけど、自分が爆弾背負ってぶつかるっていうのは、僕は嫌だったですね」
取材スタッフ 「志願について、他の同期と話をすることはあったんですか?」
土方さん 「しません。すればお互いに返答に困るわけですね。本心で俺は特攻したくないとは言えないし。特攻志願したって、でっけえ面して言うのは面映いし。
みんなそうだったと思いますね」
だが、「否」と書くのはためらわれた。学徒出身者には、士官の待遇が与えられ、部下がいた。土方さんは「熱望」と書いて提出したという。
土方さん「これは、いわゆるmust beでしょうね」
取材スタッフ「それはどういうことですか?」
土方さん「私も海軍の将校で、“部下たちが行くんだから行かねばならぬ”」
今回見つかった資料、土方さんの航空隊の最初のページには、海軍兵学校を出たエリート士官たちの名前が並んでいた。彼らは皆、「熱望」としていた。
その次が、学徒出身の搭乗員たちのページだ。右から3番目が土方さんの記録。証言の言葉どおり「熱望」と書いてある。
だが、それ以外の大多数は「望」だった。元学徒の仲間と撮った写真でも「熱望」と書いたのは、土方さんだけだった。
この資料から、何が分かるのか。300人を超える海軍関係者に取材をしてきた、戦史研究家の神立尚紀 (こうだち・なおき)
さんに読み解いてもらった。
神立さん 「『望』って書いている人は、気持ちとしては『否』に近いと思うんですよ。やはり、当時の雰囲気として『否』とは書きづらい。かといって『熱望』ではないから、『望』と小さい字で書くという人が実際いましたから」
だが、海軍省の線引きの基準は「熱望」か「望」かではなかったようだ。「熱望」と書いた土方さんを含む最初の3人は選ばれなかった。
一方、後に続く10人から特攻隊員が選ばれ、最前線へ送られた。うち8人が「望」だった。
神立さん「『望』の人が出されて、土方さんが出されないっていうのは、これはおそらく成績だと思うんですよね」
このリストは、海軍への入隊後に行われたあらゆる試験を合計した成績順に並んでいるという。特攻隊に選ばれなかった3人は、およそ5,000人いた学徒出身の同期で、トップクラスの成績だった。
神立さん「海軍としても、そこまで優秀な男を特攻の一回で死なせるのはもったいないというのがあったと思う。成績の最上位の人は残されて、上位から中の上ぐらいの人が出されて、下位の人はかえって出されていない。残酷な話ですけれども、成績で線を切ったというのが一番自然な見方だと思います」
冷徹な組織の論理。隊員の命を選別して、特攻は続けられた。
<学徒特攻隊 死の波紋>
1,000を超える元学徒のふるさと。学業に秀で、将来を嘱望された若者の死が次々と伝えられた。京都府の山間、旧須知町では、1945年1月、戦死した隊員にゆかりある人々が学校の講堂に集められ、盛大な葬儀が行われた。
戦死した隊員は、西村克己 (にしむら・かつみ)
さん。現在の京都教育大学から海軍に入り、3人乗りの爆撃機の機長として出撃した。
西村機と思われる最後の様子を米軍が捉えていた。
大きな機体は、対空機銃の的となった。空母の間近で撃墜され、爆弾は海面でさく裂した。
人々は、町で作詞・作曲された歌を葬儀の場で合唱した。
♪突き進む、里の荒鷲、ああ勇ましき、西村少尉
♪突撃す、愛機と共に、あがる火柱、見事轟沈
敵の軍艦を沈めたと、賛美する歌詞。歌の最後はこう締めくくられた。
♪いざ続け、500の学徒、澄みたてる、大地の上に
この勇ましい歌を作詞したのは、学校の教師だった細川正典 (ほそかわ・しょうてん)
さん。
旧制中学で国語を教えていた細川さんは、当時29歳。結核を患い、兵隊には行けなかったという。
娘・知子(ともこ)さん 「いざ立て、500の何とかって生徒に向けてね。戦争に行けみたいなことを書いているのでね。えっ、そんなことしていたの?と思って。それこそ、血が逆流する思いをしたんですけどね。穏やかで物静かで力とは無関係な人だったのですが、父は父で、自分が戦争にも行けずに教師をしているということ、自分がひ弱であるとか、いろいろなことについて、劣等感と言いますか、何かで自分も役に立たんといかんと思ったのかもしれません」
特攻をたたえた教師たち。調べていくと 教育現場に圧力をかけていたある組織の存在
が浮かび上がってきた。
これは、 国民学校に対して特攻隊員の慰霊顕彰に力を注ぐよう出された通達。
送り主は「地方事務所」となっている。
地方事務所とは、国の指示で各都道府県が作った出先機関で、村や町が管理下に置かれた。 この事務所を通じて、軍の要望が各町村に伝えられた。重要な使命の一つは、軍に志願する少年を集めること。
地方事務所の資料を発掘し、その機能を解明してきた木村美幸 (きむら・みゆき)
さん。
福井工業高等専門学校・助教/木村美幸さん(近現代史) 「学校長宛に陸海軍から何人あなたの学校からは集めてくださいという割り当てが、地方事務所を経由してやってきます。その人数の子どもに声をかけて、軍隊への志願を促さなければいけない。1944年、45年に向かって戦死者が増えていくのに伴って、志願兵に対する圧力も高まっていったと言えると思います」
これは、ある地方事務所が作成し、村々に配布した資料。
一番左の欄が、村ごとの志願兵の割り当て数。その右に、実際に志願した人数。
何名が合格したか、その割合までが記されている。
欄外に赤い数字が見える。資料をもらった村が、自分の村の合格率の順位を確認していたと考えられる。
木村さん「例えば、地方事務所が町村の兵事の担当者を集めて会議を開いて、その場で、あなたの村の成績はこうですよ、この学校は全員志願を出しましたよ、とか、模範的であるということが村としてのステータスになった」
<沖縄戦 果てない熱狂>
既にこのころ、日本にとって戦況は絶望的だった
。沖縄では、アメリカの艦隊が島を取り囲み、上陸作戦が始まっていた。
これに先立ち、大都市は無差別爆撃にさらされた。3月10日の東京大空襲。更に名古屋・大阪・神戸。
一方、焼け跡から目と鼻の先では、 首脳たちがなおも一撃講和を唱えていた
。海軍の作戦部長・富岡定俊 (とみおか・さだとし)
の言葉。
「沖縄は決戦です。決戦で打撃を与えれば、いろいろな工作ができるでしょう。飛行機もみんなつぎ込んで、特攻もみんなやるんだ」
しかし、特攻で戦局を挽回するという国民の“希望”には、陰りも見え始めていた。
兄が、沖縄で戦死した清水清子 (しみず・きよこ)
さん。出撃直前に連絡を受け、母・姉と飛行場に駆けつけた清子さんは、兄から特攻隊員になったと知らされる。なぜ隊員なんかになった、と詰め寄る姉に、優しかった兄が顔色を変えた。
清子さん「兄は『何を言うてる。そんなこと言うものと違う。 国賊だ。
』って言うてた」
取材スタッフ「それを言われてお姉さんは何と?」
清子さん「何も言えやしません…」
軍は、4月だけで1,500人以上を特攻に送り出していく。 そのなか国民は、隊員たちの思いに応えようと特攻を後押しし、マスコミは、勇ましい言葉を並べ続けた。
沖縄戦が始まって1か月が経過した5月4日、アメリカ軍の映像にそれまでにない特攻機が現れる。
戦闘機のガンカメラに映し出された日本軍の機体。胴体の下に下駄のような構造物が見える。この機体は、水上から飛び立つ旧式の飛行機「九四式水上偵察機」で、当時は 練習機
として使われていた。 速度の出ない機体に、重い爆弾が装着された。
織田さん「米軍側の報告書を読むと、 これらの特攻機が、超低空を低速で来た
と書かれています。特攻を行った搭乗員の方々というのは、いかにしてこの旧式の機材で沖縄に到達できるか、 彼らはレーダーに映らないようにずっと超低空で飛行してきた。
米軍の戦闘機もそれに対応して、水上機を片っ端から落としていった」
練習機による特攻だけで、300を超える命が失われていく
ことになる。
「小諸町の名誉にかけて、一家一門の名誉にかけて、必ずやりますから御安心ください」
「相馬(そうま)少尉が 死んでも生きても 天草の海 のたりのたりかな」
日本は、「一億特攻」を叫び続けたまま、終戦の日を迎えた。
一ノ瀬さん 「一億総特攻が、8月までの日本人に与えた影響というのは、 特攻さえやっていれば何とかなるかもしれない、そう思わせて、戦争に対する批判や反抗の声を抑え込んでいたこと。
これに尽きると思います。 特攻隊が出撃している限り、日本は負けない。このまま頑張っていれば何とかなるんじゃないか。
特攻隊というのは、麻薬みたいな役割を果たしていったのではないか。注射している限り、戦意を高く保つことができる。もしかしたら、何とかなるんじゃないかというふうに考えることができる。最後の最後までその希望にすがりついていた。一億総特攻という言葉にはそれを可能にする力があったのではないか」
<エピローグ 一億特攻の時代を生きて>
一億特攻を支えた人々は、どのような戦後を送ったのか。それを教えてくれた人がいた。福岡県の旧八女郡で生まれ育った、平島節郎 (ひらしま・せつろう)
さん。
河島鉄蔵さんという八女郡出身の特攻隊員が戦死した際、地域の教師が遺族に贈った「大君の楯」という追悼文集に、節郎さんの父も言葉を寄せていた。
父は戦時中、国民学校の校長をしていた。河島さんを 神鷲 とたたえ、多くの教え子を志願兵として戦地へ送った。
父は戦時中、国民学校の校長をしていた。河島さんを 神鷲 とたたえ、多くの教え子を志願兵として戦地へ送った。
平島さん「真面目一本じゃったと思う。厳しい教員じゃったらしいですよ。『あんたの親父はえすかったばい』って。怖かったって。厳しかったって」
父は、長男・俊郎 (としろう)
さんも軍に志願させていた。
海軍兵学校を卒業し、爆撃機の機長となった。 特攻が始まった直後、1944年11月に戦死
。新婚の妻・綾子(あやこ)さんが残された。
出撃前、妻の綾子さんに残した遺書が、死後、故郷に届けられた。
取材スタッフ「捨て石になるって書いてありますね。いよいよ明日は最後だって。 綾子さんは、戦後どうされたのですか?」
平島さん「死んださ。自決。自決たい…」
自決前、妻の綾子さんも言葉を残していた。
「世の中はすべて空なり、君なくてただいたずらに生きながらえんか」
息子とその妻、そして戦地に送り出した教え子の多くを亡くした父。戦後は、慣れない農業をして生計を立てた。教職に戻ることはなかった。
平島さん 「結局、何もかも組み込まれて、太平洋戦争にみんな加担したでしょ。その中で自分たちは生徒ば送り出しとるでしょ。それに対する反省でしょうね。我々の教育の誤りで、たくさんの子どもを殺したって言いよったですけん 。戦後また先生ばしようとかそういう思いはなかったでしょうね。それは反省の方が強かったですよ」
平島さん 「結局、何もかも組み込まれて、太平洋戦争にみんな加担したでしょ。その中で自分たちは生徒ば送り出しとるでしょ。それに対する反省でしょうね。我々の教育の誤りで、たくさんの子どもを殺したって言いよったですけん 。戦後また先生ばしようとかそういう思いはなかったでしょうね。それは反省の方が強かったですよ」
“一億特攻”への道。
そこには、私たちと変わらない人々が生きていた。もしまた、同じような道が生まれた時、自分ならどんな選択をするのか。隊員たちのふるさとは、そう問いかけているようだった。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[反戦平和] カテゴリの最新記事
-
<再放送> NHK「映像の世紀バタフライエ… 2024.11.26
-
マスコミの戦争責任の罪深さに驚愕する!… 2024.09.25
-
戦犯ヒロヒト(裕仁)を、なぜ糾弾しない?… 2024.09.23
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
カテゴリ
カテゴリ未分類
(1)映画
(23)日記
(31)韓国
(1342)民度
(258)北朝鮮
(1028)中国
(1737)反原発
(51)反戦平和
(315)知識
(68)健康
(99)東日本大震災
(4)反天皇制
(57)貧困
(197)社会主義
(434)慰安婦問題
(242)経済・景気
(115)環境問題
(21)拉致問題
(12)国内政治
(97)イスラム
(2)国際政治
(58)世界
(0)差別問題
(20)台湾
(84)社会問題など
(151)EU問題
(19)その他
(16)旅行
(400)主張
(45)学生運動
(83)日本共産党
(34)朝鮮総連
(3)新型コロナウイルス
(86)ギャンブル依存症
(22)死刑制度
(15)捕鯨問題
(27)教会の性的虐待
(5)僕のヰタセクスアリス
(21)コメント新着
aki@ Re:「送還された10人が処刑されるのは、間違いないと見られる。」人間を人間として扱わない地獄社会を生み出したのが、社会主義~共産主義だった。 2024-3-10 はんぺん(03/10)
この様な書込大変失礼致します。日本も当…
キーワードサーチ
▼キーワード検索
フリーページ
カレンダー
© Rakuten Group, Inc.