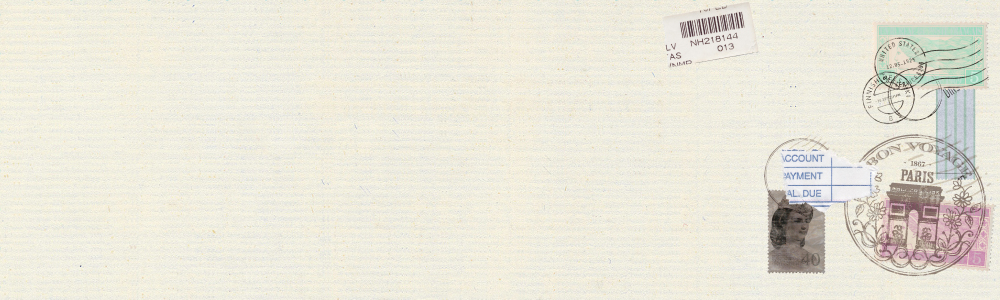2007年11月の記事
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
見つかった
■探し物、というのは、必死で探せば探すほど見つからないものだ。一般的には3連休だが、本日は休日出勤。まあわれわれの業種は365日仕事のようなものだが(^_^;)。それはさておき、研究室であっさり見つかった(^_^;)。なんともはや。
2007.11.24
コメント(0)
-
見つからない
■ドストエフスキーの『カラ兄弟』の続きを読みたいのに、本が見つかりません(>_
2007.11.24
コメント(0)
-
あへなし(あべなし)~『竹取物語』より
■寒くなったせいもあってか、妙にテンションが低い日があったり、突如、妙にテンションが下がる瞬間がある。昨日の夕方などは後者の典型だったのだけど、そこで、気を紛らわせようと思い、ちょっとした小説を読もうと、本棚を探ってみたものの、よく分からない(^_^;)。■そこで、以前まとめて購入した『日本短篇文学全集』から、第1巻を読んでみることにした。こちらの所収は、竹取物語、伊勢物語、堤中納言物語、という内容で、そのひとつめがこれ。なおいずれも現代語訳(筑摩書房)。■いまさら「かぐや姫」もあるまいとは思ったけど、実際読んでみると、案外面白い。確かに、かぐや姫ってなぜ竹の中にいたのか、なんて、覚えてなかったし、知らなかった(^_^;)。■それはさておき。『竹取物語』には、随所にダジャレが登場するが、そのひとつが「あへなし(あべなし)」である。かぐや姫の心を射止めようと、5人のチャレンジャーが現れるわけで、かぐや姫の難問に挑戦するのは、おなじみ(^_^;)。■そこに、右大臣あべのむらじ、という人物が現れる。当然ながら、彼が与えられた難問「火鼠の皮ごろも」の入手に失敗する。そして、こう書かれる。 姫は大臣と結婚なさらないのだ、と言ったので、 この話をきいて、世間では、成功しないことを、 あへなし(あべなし)といったとさ。これを読んで思い出したのが、安部前首相のことである(^_^;)。今も昔もこういうのが好きなのですね(^-^)。
2007.11.18
コメント(0)
-
『カラ兄弟』メモ07~淫蕩の問題
■ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の再々読だが、少しずつ暇をみながら進めている(新潮文庫)。通常、巷で話題となっている本などは、むしろ避けて読まないのだけど、今回だけは、ドストエフスキーを集中的に読んでいるのでタイミングとしては例外的である(^_^;)。■こうして読み進めてくると、ドストエフスキー作品の共通テーマを改めて認識することができる。すなわち、キリスト教の信仰と罪の問題、癲癇、死、子ども、ロシア的なもの、などがそれに当たるだろうが、『悪霊』のスタヴローギンをめぐって問題の留保を余儀なくされ、それが『カラマーゾフの兄弟』にもちこされたものとして、「淫蕩」の問題があると強く感じた次第。■スタヴローギンの場合、少女陵辱がそれで、フョードルの場合では、神がかり行者を孕ませたことがそれに当たる。というか、それだけではない。第二部第四編、フョードルがアリョーシャにこう言う。 なぜって俺は最後まで淫蕩にひたって 生きつづけたいからさ、 これも承知しておいてもらいたいな。 淫蕩にひたっているほうが楽しくていい。 みんなはそれを悪しざまに言うけれど、 だれだってその中で生きているのさ、 ただ、みんなはこっそりやるのに、 俺はおおっぴらにやるだけだよ。 この正直さのおかげで、 世間の醜悪な連中に攻撃されるけれどな。「俺はおおっぴらにやる」というところが凄まじい。この問題については、読み進めることで考えたい。
2007.11.16
コメント(0)
-
『カラ兄弟』メモ06~イワンの出生
■再々読をしているドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟(上)』(新潮文庫)から。興味深い箇所はすでにいくつかあるのだけど、とりあえずイワンの出生について。■フョードルが、アリョーシャ、イワンほか、家族の前で、二人目の妻の癲狂病みについて語る。フョードルがその妻から神がかりをたたきだすため、聖像に唾をひかっけても罰が当たらないことを示そうとしたというのだが、そのとき妻が全身を震わせ、気絶してしまった。それを聞いたアリョーシャにも、まったく同じ現象が起こったのである。■フョードルは あのときのこれの母親とそっくり同じだ!と言うわけだが、するとイワンが食ってかかる。 しかし、僕の母親も、これの母親と同じだと 思いますがね、どうですか?つまり、ここでのフョードルとイワンのやりとりからは、イワンの母親がアリョーシャの母親とは別人であるかのように読み取れるのである。少なくとも、フョードルはそう思っているふしがある。■前回、前々回読んだときの記憶がないので、なんともいえないが、ともあれ、このように、謎を謎めいたまま示すのが、ドストエフスキーは実にうまい。
2007.11.14
コメント(0)
-
チェーホフ:『かもめ』
■風邪をひいて寝込んだ布団の中で、なぜかチェーホフを手にする(^_^;)。まず読んだのが「かもめ」である。(チェーホフ全集第11巻、ちくま文庫)ということで、『カラ兄弟』はおあずけ…。■さて「かもめ」とは鳥のかもめのことで、戯曲の中では、自然の中で平凡に幸せに生きる存在、を象徴していると考えられる。それを打ち落としたトレープレフは、作家志望の青年なのだが、なかなかその芽が出ない。■やがて、恋人で女優志望のニーナが、優れた作家のトリゴーリンに惹かれてしまう。しかし、トリゴーリンとの間に子どもが出来ても、すぐに死んでしまうし、女優としても花開かず。手紙には自分の名前として「かもめ」と署名するまでに至る。自然の中にいたら幸せだったかもめは、結局のところ、打ち落とされる運命にある。■なお最後、トレープレフが自殺をし、注文してもいない「かもめ」の剥製がトリゴーリンのもとに届く。なぜ届いたのかについては明らかにされない。トリゴーリンは実際に注文したのに忘れたのだろうか。ぼくが読み取った感じでは、トレープレフかニーナのどちらかがトリゴーリンに贈ったのではないか。■終わり近く、一度トレープレフと別れたニーナが彼の元を訪れ、こう言う。 いまになってわかったの、 納得が行ったのよ、コースチャ、 わたしたちの仕事で大事なものは── 舞台に立つにしろ、ものを書くにしろ 同じことなのよ── 名声でも栄光でも、 わたしの夢みていたようなものでもなくて、 忍耐力だということがねえ同じ夢や目標をもちながら、明と暗を分けた二人が出会った場合の、暗の側の人間の辛さが身につまされる。■ところで、これまで戯曲を読むのが苦手で、ほとんど手にとってこなかったけれど、立場を変えれば(?)、ごくごく普通にリブレットは読むわけだから、戯曲も普通に読めばいいのだな、と思う。地の文章がないだけに、登場人物の心理を読む余地が多々あり、そこがまた面白い。
2007.11.12
コメント(0)
-
萩原朔太郎全集4冊
■ところで、今日は仕事に集中ができず、職場近くの市立図書館に出かけたあと、さらに近所の古本屋にでかけた。それも、なぜか妻も一緒に(^_^;)。■それはさておき、今日ついつい買ってしまったのが、萩原朔太郎全集(筑摩書房)の4冊(第8~11巻)。最も欲しい詩集の巻は当然なく、次に欲しかったアフォリズム集は1巻のみで、それも書き込みありなので、買わず(>_
2007.11.07
コメント(2)
-
『カラ兄弟』メモ05~ドミートリイと詩
■修道院を出たアリョーシャは、生垣の向こうの隣家の庭で兄ドミートリイが呼んでいるのを見る。やがてドミートリイはアリョーシャに長い恋物語を話すことになるのだが、その前置き(?)として、ゲーテの詩の一部を暗誦したり、シラーの詩句(「歓喜の歌」?)を暗誦する。ただし訳注によれば、シラーの詩句とはだいぶ異なっているらしいが。■ともあれ、彼がシラーの詩句を、それなりに暗誦できるほどに、愛唱してきた、ということが分かるのである。ではいつ読んだのか?それについて彼は、 よく、恥さらしな放蕩のいちばん深い どん底にはまりこむようなことがあると (もともも、俺にはそんなことしか起こらないけど)、 俺はいつもこのケレースと人間についての 詩を読んだものだ。と言う。■ドミートリイのなかにある感情は、恥辱や屈辱を受け入れつつも、神を愛し、神の愛を感じている、ということ。そして、自分は、その神から情欲を与えられた「虫けらだ」ということ。苦しむたびに詩を読む人間が、無教養とは思えないのだが、果たして・・・。
2007.11.07
コメント(0)
-
『カラ兄弟』メモ04~道化フョードル
■十何年ぶりかの『カラマーゾフの兄弟』再々読。少しずつ読んでいるが(新潮文庫)、この小説に限らずドストエフスキー作品の魅力は、やはり人物造形である。■まずはフョードルについて。もし自分の近くにこういう人物がいたならば、この上なくうざったいし、関わりたくないというのが正直なところ(^_^;)。しかしドストエフスキーが描く視点は、冷静でありながら愛情が込められており、実に魅力的に見えてくるのである。■例えば、上巻で早速、みなが修道院に集まっている。その終わり近く、その場を乱して一旦引き上げようとしたフョードルが、再び戻ってくるとき、自分のことばを思い出す。 わたしゃいつも、どこかへ行くと、 自分がだれより卑劣な人間なんだ、 みなに道化者と思われているんだ、 という気がしてならないんです。 それならいっそ、 本当に道化を演じてやろう、 なぜってあんたらは一人残らず、 このわたしより卑劣で愚かなんだから、 と思うんでさ」そして、こう結論付ける。 「今となっちゃ、どうせ名誉挽回もできないんだから、 いっそ恥知らずといわれるくらい、 やつらに唾をひっかけてやれ。」と。■確かにこのフョードルはのちに殺される。だからその意味では、人の恨みを買い、殺されるべくして殺されたのだ、という強調するために、このような人物像を提示していると、一見思えるが、そう単純ではないだろう。■フョードルがなぜこのような鬱屈した感情を抱くようになったのか、ということが重要で、単なる「カラマーゾフ的」では済まない要素が多々あるような気がしている。■スメルジャコフ誕生のエピソードも興味深い。淫蕩に淫蕩を重ねたフョードルが、リザヴェータを孕ませたというものだが、それもフョードルの人物像を形作っている。■ところで「神がかり行者」とされているリザヴェータは、ムソルグスキーの《ボリス・ゴドゥノフ》に出てくる、聖愚者を思い起こさせるのだけど、どうなのだろう。
2007.11.06
コメント(0)
-
加賀乙彦:『ドストエフスキイ』
■現在、ドストエフスキーの『カラマーゾフの兄弟』の再々読にかかっているものの、なかなか読み進むには至らず(^_^;)。で、本書をちょこちょこ読んでいるうちに、読み終わってしまった(中公新書)。■作家の加賀乙彦が、作家の目からだけでなく、精神医学者として実際に囚人に接した目からも、ドストエフスキー(本書ではドストエフスキイ)の作品を読み解いていく本である。死刑囚、癲癇、夢などが論じられるが、正直なところ、本書に対してあまり好意的な感想はもつことができなかった。■その大きな理由は、作者がドストエフスキー作品に対して、冷静で批判的な目をもっていないことにあると思う。少なくとも、そう感じてしまう書き方をしている。つまり、もう少し研究者的な、あるいは、分析的・歴史的な視点から書いて欲しいのだけど、作者の文章のテンションがかなり高くて、客観性に欠ける印象を受けてしまう。「のだ」の文末が多いのはその象徴。■もちろん、この筆者ならではのドストエフスキー作品の深い理解と愛情が感じられることは確かなのだが、だからといって、そこに圧倒的な説得力を感じるか、となると違う。もう少し冷静に書いてもらう方が好みなのだが…。
2007.11.04
コメント(0)
-

村上春樹:『若い読者のための短編小説案内』
若い読者のための短編小説案内■村上春樹がいわゆる「第三の新人」を中心に、短編小説を読み解いていく本(文春文庫)。今、ドストエフスキーのような、正統的な長編小説に惹かれる自分と、しみじみ文章を味わえるような短編小説を猛烈に読みたい自分が激しくぶつかっていて、いつもどちらを読もうか迷ってしまう(^_^;)。ともあれ、本書を読んで改めて思うのは、小説というのは読者それぞれの読み方を許容するものであって、村上春樹だって彼なりの読み方をしており、それに納得するかどうかもまた、われわれ個人的なものだ、ということだ。■で、本書の村上春樹の小説の読み方はとても面白かった。とりわけ本書の肝は、作者の創作の立場を図式化していることである。作家によっては、主人公そのもので場合もあるので、主人公のあり方を分析するには有効かもしれない。■まず作者の「セルフ(self)」を示す大きな円がある。そのなかに「エゴ(ego)」を示す小さな円があって、その小さな円では、内から外に向かって発散しようとする力が「→」で示されている。その一方で、大きな円の外側からは、外界からの力が内側に向かって加わってくる。■つまり、自分というのは、内から外に出ようとする力(ego)と外から内に加わろうとする力が等圧のとき、バランスが取れている、というわけである。で、本書で選ばれた作家たちはどうか、あるいは、作品の主人公たちはどうか、ということだが、それは本書を読んでもらうとして、ともあれ村上春樹もまた小説を、ぺろりぺろりと読んでいることがうかがえてとてもうれしくなった(^-^)。
2007.11.02
コメント(0)
全11件 (11件中 1-11件目)
1
-
-

- ★ おすすめのビジネス書は何ですか!…
- 細野真宏の数学嫌いでも「数学的思考…
- (2024-12-02 07:22:24)
-
-
-

- お勧めの本
- 「どうなってるの?どうぶつの歯」歯…
- (2024-12-04 17:50:09)
-