2015年12月の記事
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-

ベルンハルト・シュリンク『朗読者』
少年が年上の女とやりまくったり朗読したりたら、相手が蒸発してナチス関連の裁判で有罪になって恩赦間際に自殺してしまう話。●あらすじI:戦後のドイツで15歳のミヒャエルが黄疸で吐いていたところを36歳の市電の車掌のハンナ・シュミッツに介抱され、お礼を言いに行ってやりまくったり朗読したりするものの、ハンナは突然仕事を捨てて引っ越してしまう。II:ミヒャエルが大学のゼミでナチス時代の強制収容所職員の裁判に行くと、焼けた教会のドアを開けずに囚人を死なせた罪で被告になっているハンナを見つけて公判に通うようになり、ハンナが報告書を書いた首謀者扱いされて不利になっていて、ミヒャエルはハンナが文盲だと明らかにして擁護しようかと思って父に相談するものの、ハンナが文盲であることを恥じていたので結局裁判長には何も言わず、ハンナは無期懲役になる。III:裁判後、ミヒャエルはゲルトルートと結婚するものの、ハンナと過ごした時間と比べて何か違うような気がして、ユリアが5歳のときに離婚して、カセットテープに朗読を録音してハンナに送り続ける。18年の服役のあとでハンナが恩赦されることになりそうだというので刑務所に行って出所後の相談をしていると、ハンナは自殺してしまい、遺産をユダヤ人の文盲団体に寄付する。●感想一人称で、ハンナの死後10年経ってからミヒャエルが過去を回想する形式。しかしミヒャエル自身の生活や思想がほとんど書かれていないせいで、語り手役はこなしても登場人物としては存在感がなく、語りの手法としては失敗している。ミヒャエルはハンナを愛していたけれど、ハンナはナチスで、ナチスは批判しなければならないので、ハンナを批判しなければならないという認知不協和による葛藤があり、ハンナは自分が事件の首謀者ではないが文盲だとは知られたくないという認知不協和による葛藤があり、この二つの葛藤が物語の軸になっていて、I章ではミヒャエルとハンナへの愛、II章ではハンナが裁判で文盲だとは知られたくないがゆえに罪をかぶる葛藤、III章ではミヒャエルのナチス批判とハンナへの愛の葛藤が書かれる。ヒーローとヒロインの両方の認知不協和を書くので物語の構造としては複雑になるけれど、その複雑さに対して全体的に書き込み不足。I章は少年の性欲を愛として扱って、セックスを無批判に愛として美化するのは気に入らない。性欲に負けたことに罪悪感をもって愛を否定するトルストイの小説のほうが作家の感性としてはまとも。ミヒャエルが年増好みなのか、母親代わりの相手を求めていたのか、性欲発散の相手として都合よかったのか、ハンナを好きになる動機が不明。III章でミヒャエルと母親の間に問題があることをほのめかしているものの、直接の家族の問題が書かれていないあたりはプロットとしての仕込みが不十分。II章はナチスに絡んできてようやくドイツ小説らしくなるものの、前半とは別の話かのように物語の調子が変わり、ハンナの裁判が延々と続いてミヒャエル自身については書かれなくなってしまい、前半とは違う退屈さ。猿みたいにやりまくっていたミヒャエル少年の性欲はどこに行ってしまったのかというくらいの別人ぶりに違和感がある。III章はミヒャエルが長年ハンナに朗読のカセットテープを送るくせに直接会ったり手紙を書いたりしようとせず、その割にはハンナが恩赦されそうになるとホイホイ会いに行く理由がよくわからない。歳をとれば考え方も変わるだろうに、ミヒャエル自身の思考の変化を書かずに何十年もすっ飛ばしてしまっていて、語り手としての役目をサボっている。それに刑務所はたいてい自殺防止の措置があるだろうに、どうやって道具を調達して看守に見つからずに首を吊ったのかという詳細が書かれていないうえに、自殺の動機を明らかにしないまま感情に訴える終わらせ方をしたことで、最後にご都合主義を印象付けることになってしまって全体が台無しになった。著者は元判事で法学部教授のミステリー作家らしいものの、ミステリー作家の割には動機の追及が手ぬるい。肝心なところで一人称の疑問系を悪用して追及をはぐらかしてしまうのは語り手として不誠実。ぼくはどこへ行けばいいんだ?なんて聞かれても読者はしらねーよ、こっちが聞きたいくらいだよ。動機があいまいで疑問点だらけでご都合主義的な感動の押し売りに見える。もう100-200ページくらい細部を書き込んだらもっといい小説になっていたかもしれない。「心の底から涙があふれでる。「これぞ小説!」」という低俗なキャッチコピーの帯がついているけれど、泣きたかったらたまねぎでも切ったほうがましである。たまねぎに「心の底から涙があふれでる。「これぞたまねぎ!」」というキャッチコピーをつけて売ったらベストセラーたまねぎになるとおもう。★★★☆☆朗読者 [ ベルンハルト・シュリンク ]価格:594円(税込、送料込)
2015.12.30
コメント(0)
-

トルストイ『クロイツェル・ソナタ 悪魔』
結婚した男の悲劇を書いた中編小説二編。「クロイツェル・ソナタ」はわたしが列車に乗っていると乗客たちが離婚について話し出たところ、隣に座っていたポズドヌイシェフは妻を殺していて、妻が音楽家とクロイツェル・ソナタを合奏したのに嫉妬して殺したのだとわたしに話す話。「わたし」の一人称ながらわたしは聞き役にすぎず、ほとんどポズドヌイシェフの自分語りで、愛は高尚などころか恥ずかしいもので、女は快楽の道具で、性欲過剰が害悪だという性欲論や結婚論を小説形式で展開している。この結婚観は小説が書かれた当時は社会批判として意味があったのかもしれないけど、現代の読者にとっては賞味期限切れ。そのうえわたしの存在感がなく、なぜポズドヌイシェフがわたしに詳しい身の上話をする必要があるのかもよくわからない。殺人事件を犯人自身が思い出しながら語るということで心理の動揺を描いていて小説としての見所は用意されているものの、現代のミステリーやサスペンスと比べるとエンタメとしてはつまらない。「悪魔」はエヴゲーニイ・イルチェーニフ青年が父親の遺産と負債を相続して厳しい領地経営に乗り出すものの、性欲発散のために領地の女とやりたくなってヤリチン猟師のダニーラ老人に相談して亭主が留守中の主婦のステパニーダを手配してもらって不倫にはまるものの、リーザ・アンネスカヤと結婚していったんステパニーダを捨てたのに、偶然ステパニーダと会ったことで気になってやりたくなるもののリーザに知られるのを恐れていて、リーザを殺すかステパニーダを殺すかと考えて自殺する話。三人称。「クロイツェル・ソナタ」とは違う形で性欲と結婚の悲劇を書いた小説で、こちらは普通の小説としてそれなりに面白い。「だれ一人、自殺の原因を理解することも、説明することもできなかった。」と最後に書いてあるものの、エヴゲーニイはおじさんに不倫衝動を打ち明けて救ってほしいと頼んでいたので、おじさんなら自殺の原因を理解できたんじゃなかろうかというもやもや感が残る。オチに欠点や疑問点があるのはよくない。★★★☆☆クロイツェル・ソナタ/悪魔改版 [ レフ・ニコラエヴィチ・トルストイ ]価格:529円(税込、送料込)
2015.12.29
コメント(0)
-

リチャード・ドーキンス『利己的な遺伝子』
行動生物学者の著者が生物は自己複製子(DNA)を運ぶ機械でしかないという論を展開して、進化的に安定な戦略をとる様々な動物の行動について論じた本。ハト派とタカ派の戦略、母親は長男と次男のどちらに資源を分配するかという戦略、ゾウアザラシの雄がハーレムを作って雌を独占して一部のオスの遺伝子しか残らないものの雄と雌を同数産む戦略、群れに加わった雄ライオンが継子殺しをする戦略、誠実派雄雌と尻軽派雄雌の戦略、雄が派手で雌が地味な戦略、社会的昆虫のアリの戦略、人間は遺伝子とミームを残せる、囚人のジレンマ、戦争での報復行動など、例示される個々の話題は面白いものの、章立ての仕方が悪くて章全体の論旨がよくわからないうえに、例に挙げられる動物がコロコロ変わって何のためにその例が出されているのかもよくわからない。要するに様々な動物が様々な進化的に安定な戦略をとって遺伝子の複製を残すために争っているということを言いたいようである。一般人向けに専門用語を使わないで書いているので予備知識がなくても読める点はよいものの、章立てのわかりにくさゆえに結局は一般人が読みやすい本ではない。トピックごとに細かく区切っていればもっと読みやすくなっていただろうけれど、著者が書きたいことだけ書いて読み手のことをあまり考えていないような書き方。進化的に安定的な戦略がESSと略語で呼ばれるものの、evolutionarily stable strategyという元の英単語が一切書かれていないあたりは不親切で、その点も一般人への配慮が欠けている。この本では大部分が動物や昆虫についての話で人間については後半でちょっと述べる程度なものの、いじめ、浮気、継子殺し等の人間の諸問題を考えるうえでのヒントとしては役に立つかもしれない。この本での主張は既に大抵の人は知っているだろうから、動物行動学に興味がない人はいまさら読む必要はないかもしれない。★★★☆☆利己的な遺伝子増補新装版 [ リチャード・ドーキンス ]価格:3,024円(税込、送料込)
2015.12.27
コメント(0)
-
P・フルキエ『哲学講義3 行動I』
行動についての哲学をまとめた本。最初に個人は人間固有の行動ができるようになる前にまず感じることから始めるということで、第一部で行動の心理学として快楽と苦痛、感動、情念、感情、傾向、欲望、意思、自由、習慣、人格、性格と性格学、他者の再認、人と人との間の関係を論じて、第二部で人間の創造的行動である産業活動と芸術活動を論じる。講義としてトピックごとに簡潔にまとまっていて、様々な哲学者の言葉を引用するものの特殊な哲学用語を多用するわけでもなく、予備知識が必要というわけでもなく、哲学の本の割には読みやすい。ある論と反論の両方を載せていて情報が偏ってないあたりもよい。哲学を包括的に広く浅く勉強したいという人にはお勧め。欠点としては、第二部で言及される芸術が主に美術のような視覚芸術で、文学についてはほとんど言及されていない点。あとは巻末に索引がなくて学術書としては不便。私が気になったのはこの本に書かれていないエンタメが哲学的にどうなのかという点。小説や漫画やアニメといった様々なエンターテイメントやキャラクタービジネスは産業活動かつ半ば芸術活動でもあり、これらが本当に人間にとって役に立っているのかという点について哲学的な考察を書いた本があればいいのだけれど、娯楽としてのフィクションは20世紀になって産業化したので古い哲学では扱ってないし、現代の偉い哲学者はそういうくだらないことは考えてくれないし、あるいはメディア論とかに書いてあるかもしれないもののそういう本は高くて私には買えない。ということでこの本を読みながらアホなりに自分で一生懸命考えてみることにする。ロマン派が情念を神格化する一方で、ストア派やカント派は情念は正しい理性に対立するから悪とみなし、人生の理想を快楽におくエピクロス派は情念は快楽の原因よりも苦痛の原因となるので退けなければならず、情念が善であるためには、(1)善い対象を持たねばならず、(2)それは理性と意思に支配されていなければならない。そしてひとは別のことやわれわれの存在の深い希求に答えるもの(遊び、空想、芸術)に熱中することによってのみ、或る情念を棄てることができる。ということは芸術というのは作者が理性と意思で支配している情念の出現様式であり、ある情念に熱中させることで他の情念を棄てさせる効果があるといえる。芸術は真善美のうちの美に奉仕するので善でないとしても芸術のための芸術が存在しうるけれど、真や美に奉仕しないエンタメははたして善なのか、悪なのか。エンタメ作品はまず友情とか家族愛とかの善い対象を持たなければ善い作品ではありえないわけで、世間に出回っている典型的なエンタメであるエロ少女を描く少年漫画やラノベやアニメやゲーム、逆に都合のいいイケメンとの恋愛を描く少女漫画やハーレクインやBLは、善い対象ではない情念(エロや暴力)に熱中させるという点で麻薬的な精神的快楽を提供するので、エンタメは道徳的に悪いものだといえる。では悪であるエンタメがなぜこれほど社会に受け入れられて浸透しているのか。本来ならば有害なものは廃れているはずである。・仮説1:エンタメは悪ではなく善であるから社会に受け入れられている。エンタメが非日常的な情念に熱中させることで退屈な日常生活への情念を棄てさせ、人生に快楽をもたらす。もしくは単純化した情念を喚起することで子供を教育したり、複雑な社会や感情への理解を促す。作品を媒介としたコミュニケーションを活性化させて人間の社会性を充実させるための手段として産業活動として社会に貢献している。日本政府がクールジャパンとしてアニメを推進していることから、現在の日本社会はそもそもエンタメを悪だとみなしていないらしい。BL愛好者の腐女子だけは罪悪感を感じてひっそりと活動しているようだけれど、それ以外のエロ同人はおおっぴらに活動しているし、フィギュア収集やコスプレもマニアックな性癖ではなく普通の趣味として認知されるようになった。しかし幼児の教育の役には立っても、大人が知識を得たり生活を充実させたりするのに寄与しているかというと疑問である。たとえば数千時間アニメを視聴したアニメオタクが知識人扱いされることはなく、らき☆すたやまどか☆マギカの専門家として社会で役立つ知☆識を提供できるわけでもない。エンタメを積極的に享受した人がそうでない人より社会で活躍しているという根拠もない。なので仮説1は成立しない。・仮説2:エンタメは悪である。しかしエンタメが麻薬的な情念に熱中させることで現代社会の過酷な労働や退屈な生活環境に対する情念を棄てさせるとしたら、それは現実逃避の手段としての一時的な快楽といえる。戦争中のヒロポンの使用のようなもので、置かれた環境で快楽的に生きるうえでの必要悪なので社会に受け入れられている。我々はエンタメが悪だと認識した上で、現実世界を生きるために一時しのぎの快楽として意図的に悪を選択している。東日本大震災のときには援助物資として送られた漫画が喜ばれたそうだけれど、これは現実逃避だろう。redditなんかだと外人は少年時代に漫画やアニメにはまったことを黒歴史扱いしているし、大人になってアニメグッズを集めているとキモい日本オタク(weeaboo)扱いされて、現実を見ろと蔑視される。大人の社会に仲間入りする準備をするべきモラトリアム期間に現実社会に向き合わずにフィクションの世界に熱中するのは現実逃避で、大人になっても現実逃避の痕跡を引きずっているのは外人基準だとキモいようである。エンタメが悪なら、悪に染まったことを恥じるのが正常な反応だろう。他の例だとredditの翻訳スレで日本語の遺書を書いたアメリカ人の少年がいて、遺族が誰か翻訳してくれとアップロードした遺書を見てみると、けいおんが好きだけどグッズを全部買えないから自殺するということが書いてあった。人間はすべての欲望をかなえることは無理である。しかし資本主義社会は容赦なくキャラクターグッズをわんさか売り出して欲望を刺激して精神の平穏を乱すわけで、これはストア派的倫理観だと悪である。いくらキャラクターグッズをコレクションしたところで永久に現実逃避できるわけではなく、深みにはまるほど現実に適応できにくくなって余計に生きづらくなるわけで、これもまた悪である。・仮説3:エンタメは善(仮説1)と悪(仮説2)の両方の側面がある。善のほうが大きいので社会に受け入れられている。今でも教育熱心な親は子供に漫画やテレビアニメは見せず、ゲームもさせないらしい。それでもクラスメートから仲間はずれにされないように子供にゲーム機を買い与える親のほうが多いだろう。しかし子供が一日中ゲームをやっやりテレビを見ていたりした場合は叱る親が多いだろう。ということはエンタメは一時的な快楽としては許されているものの、その快楽にふけることは悪とみなされているわけだ。ということは善よりもむしろ悪のほうが大きい。クールジャパンで推進するアニメの代表的存在である宮崎駿は、映画が本当にすばらしいかはわからない、映画が好きなのはただの趣味で、多くはくだらないというようなことをドキュメンタリー映画『夢と狂気の王国』の24分頃で言っている。ジブリ映画というとエンタメアニメ映画として日本で支持されているものの、世間がエンタメを悪とみなしていないとしても創作者自身が懐疑的ということは、エンタメの社会的価値はまだ定まっていないといえる。漫画やアニメを児童ポルノと結びつけて規制しようとする左翼勢力もいて、解釈次第では『となりのトトロ』のお風呂シーンも児童ポルノになりかねず、そうなればエンタメは悪となる。「東京都青少年の健全な育成に関する条」の議論で、漫画はポルノだけれど小説は芸術だからよいというようなことを偉い人が言っていたような記憶があるけれど、これは小説が漫画よりも若干文化としての歴史が長いことによるえこひいきのようなもんだろう。フィクションが青少年の成長にどう影響するかという学問的な定説はまだ出ていないので、研究が進んで影響が明らかになればフィクションはどの媒体だろうが善にも悪にもなりうる。善のほうが悪よりも影響が大きいと言える根拠がないので、仮説3は成立しない。・仮説4:フィクションの可能世界と現実世界は違う世界なので、エンタメが悪であったとしても現実世界では悪ではない。ゆえに別世界の悪として社会に受け入れられている。たとえばGTAのゲーム世界内で強盗したり、FPSのゲーム世界中で敵兵士を射殺したりしても、それは現実世界では何の被害も起こしていない。児童の裸を描いた漫画の世界内でおじさんが児童にわいせつな行為をしていても、現実世界での被害者はいない。しかしフィクションの世界が現実世界と別の世界だとしても、作品は現実世界に存在して現実の人間に刺激を与えているわけで、これも仮説3と同様、エンタメが実際に現実社会に悪影響を及ぼすという研究結果が出た場合にはエンタメは悪として排除されうるので、仮説4は成立しない。・仮説5:現代人は生まれたときにすでに娯楽としてのエンタメが確立していてエンタメを享受して育ったので、いまさらエンタメが悪だと疑わないか、あるいは悪と知っていても既に慣習化して文化となったのでもはや社会から取り除くことはできない。国民の大半がエンタメの麻薬じみた快楽に熱中すればもはや法律でも禁止しようがない。団塊の世代は映画に熱中し、バブル世代は漫画とテレビとアーケードゲームに熱中し、団塊ジュニア世代は漫画とアニメと据え置き型ゲームに熱中し、いまどきの若者はスマホのソーシャルゲームに熱中して、娯楽の形は違っても世代ごとに何らかの娯楽に熱中していて、各世代は年上の世代からはあんなものに熱中するなんて馬鹿じゃないかと非難されている。パチンコや課金ガチャは社会的には射幸心をあおる悪いエンタメとして認識されているものの、それでも依然としてビジネスとしてまかり通っている。・仮結論:仮説2と仮説5を採用すると、エンタメは慣習化して社会に定着した悪ということになる。我々は幼少期にエンタメに囲まれた環境要因によって善悪の判断基準がないままエンタメの快楽を享受して、それが習慣化したがゆえに成人になっても過去に経験した快楽を得るためにエンタメが悪と知りつつ意図的にエンタメを求めている。未成年のときにエヴァンゲリオンを見て育った世代が、放送から15年以上経って成人してもなおエヴァンゲリオングッズを集めているのはそれが過去の快楽を継続させるための習慣になっているからだろう。大人になってもサンリオグッズを集める女性、子連れでもないのにディズニーランドに入り浸る人たち、カラオケで懐メロを歌って青春時代を懐古する人たちも同様だろう。過去に体験した快楽の欲求を自制できず、それに代わる別の快楽がないので、同じ刺激を繰り返し求める。習慣化した行為をやめるには意思が必要だけれど、たとえエンタメが悪だとしてもエンタメの快楽をやめるというのは動機を見つけにくい。エンタメが麻薬的快楽であるがゆえに、芸能界がやくざと繋がっていたり、ジャスラックのような著作権やくざがいるのはある意味必然的なのだろう。エンタメビジネスは習慣的に快楽を摂取するエンタメジャンキーを合法的に囲い込むショバ争いなのだ。私はフィクションは現実ではありえない出来事を想像しうるという点で面白いと思う反面、所詮は創作者の想像の域を出ないくだらないものだと思っている。面白さとくだらなさは両立しうる。面白さは快楽であるものの、くだらないものに熱中するのは時間の無駄である。つまりは快楽のために時間を無駄にしている。私の人生をどう無駄にしようが私の自由なので私は漫画やらゲームやら小説やら映画やらで貴重な青春時代を大いに無駄にしたのである。純文学はつまらないうえにくだらないので、今買いだめしてある分とまだ読んでない名作を読み終わったら読むのをやめようかと思う、などと悠長なことを言っているうちはやめられないんだろうな。慣習をやめるのは難しいものだ。★★★★☆
2015.12.21
コメント(0)
-

嚴歌苓『シュウシュウの季節』
映画化された表題作とその他の短編集。「シュウシュウの季節」は馬の放牧役に選ばれた少女文秀は老金のところで働くものの、中央とのコネを作るためにヤリマンになる話。三人称。20ページ弱しかなく、その分物語の構図が単純化していて遊びが乏しい。希望を絶望に変えて死で物語を終わらせるあたりは昔の典型的な短編小説という感じで目新しさはなく、もう一工夫ほしいところ。映画化されたこの短編がこの本の一番の売りなんだろうけれど、映画のほうが丁寧に作られているので、映画を見たほうが面白いかもしれない。「白蛇」はスパイ容疑をかけられて軟禁された白蛇役で人気の女性ダンサー孫麗坤を中央からきた青年徐郡山が助け出すものの、徐は実は子供のころに孫に憧れていた男っぽい女詐欺師だったという話。三人称。孫の話に政府資料やら非公開資料やらをどっちゃり挟み込む形式で、そのせいで物語が途切れ途切れで読みづらい。スパイ容疑やら政府資料やらと状況が大げさな割には内容は男っぽい女に惚れたレズの失恋話で、物語の展開方法がちぐはぐな感じ。非公開資料をどうやって作者が知りえたのかというメタ情報が読者に意識されるとフィクションくささが際立ってしまってよくない。「少尉の死」は強盗殺人をした少尉が死刑になった様子を女流作家が見たという話。三人称で、裁判中に事件の様子や恋人の思い出がシームレスに挿入される構図。この書き方は短編向きで、一行空きがないことで一連の事件と元恋人への未練を一挙に展開して技術的には成功しているけれど、タイトルでネタばれしているうえにただ事件をなぞるだけで意外性がない。少尉が死んだからなんなのか、少尉に同情したいのか、あるいは自白したら死刑にしないという約束を破って死刑にした共産党を批判したいのか、作者の意図がいまいちわからない。「リンゴ売りの盲目の少女」は人民解放軍の演出隊がチベットに行った際にリンゴ売りの盲目のチベット族の少女に甘粛人の男がつきまとって逮捕される話。わたしたちという一人称複数形で、演出隊から見た光景を書くものの、演出隊は事件や少女にはほとんど関与せず傍観者的でつまらない。「しょせん男と女しか」は雨川が婚約者の蔡曜の家に行くと、蔡曜の弟の28歳の老五は腎臓病で長生きできず家族から疎まれていて、蔡曜が出張中に老五と仲良くなるものの、老五の個展はぼろくそに批評されて、家で金がなくなったことで老五が個展を開くために金を盗んだと疑われて家を出て行ってそのまま病死する話。雨川視点の三人称。老五が痴漢の疑いをかけられたり、金を盗んだ疑いをかけられたりといった冤罪からの無実判明のパターンを二度も短編で繰り返すのは演出過剰気味。病気で芸術家気質の男に恋するパターンも少女漫画的で既視感がある。「少女小漁」はシドニーに行った22歳の女工の小漁は恋人の江偉の勧めで67歳のイタリア人の老人と偽装結婚して、老人とリタと三人で暮らすものの、リタが出て行き、小漁が部屋を出て行くときに老人が病気になる話。三人称。オラオラ系の恋人に愛想をつかして孤独な老人に同情する心情を書いた話だけれど、いつの時代の話なのか不明でその分読み応えがない。弱者に同情的な女性像は「しょせん男と女しか」とも共通するけれど、本来尽くすべき恋人以外に同情して自己満足的な悲劇に浸るあたりがワンパターン。全体的に短編ということもあって小説の構図としては平凡。著者は12歳で人民解放軍の演出隊に加わったらしく、その経験は物語のあちこちに活かされているものの、悲劇的事態を書いて性急に読者の感情を揺さぶろうとする意図が出すぎていて小説としての仕上がりはあまりよくない。1970年代の文革時代の中国に興味がある人には面白いかもしれない。★★★☆☆【楽天ブックスならいつでも送料無料】シュウシュウの季節 [ 嚴歌苓 ]価格:740円(税込、送料込)
2015.12.19
コメント(0)
-

丸山健二『まだ見ぬ書き手へ』
まだ見ぬ書き手に対して小説を書き始めてデビューする方法を指南する本。著者は大御所ぶった作家がくだらない小説を書いたり、編集者が仕事熱心とは限らないという文学業界を批判しつつ、小説を書く人を3パターンに分類して、まだ見ぬ書き手に対して小説を書いてみるように促している。1.ある作家に憧れて書き始める人→才能なし2.これくらいなら自分でも書けると思って書き始める人→やってみる価値はある3.文学を否定して文学から離れて他の分野でうまくやっているか、もしくはもっといい小説を書こうとする人→まだ見ぬ書き手この「まだ見ぬ書き手」に該当して、なおかつ小説家になるつもりがある人に向けて書かれているので、それ以外の人はこの本を読む価値がない。いきなり細部を書き込まないでアウトラインを書けとか、会話文は便利だけど頼るなとか、小説の書き方としては別に目新しいものでもなく、文学理論に基づくわけでもなく、普通のことを大まかに言っていて、技術論としてはたいして役にたちそうにない。それに著者に感化されて素直に書き始めるような人は1番目の才能のない書き手なので、結局のところこの本はまだ見ぬ書き手の発掘にはつながらないだろう。著者は文学を批判するものの、くだらない選考委員の基準に合わせた小説で新人賞をとってデビューしないと作家扱いされず、くだらない編集者が認めた小説を書かないと本が出版されないわけで、そのくだらない基準に合わせた作家デビューの仕方を指南するあたりはやり方が矛盾していて、朱に交わっても赤くなるなというような無茶な注文である。新人発掘に携わるくだらない作家や編集者と決別する方法こそ指南するべきだろう。1994年の発刊から20年経った現代に日本の文学を背負って立つような本格的な作家が出てきた様子はなく、著者が期待を寄せたまだ見ぬ書き手たちはくだらない文学になど目もくれずにどこか他の分野で活躍しているようである。★★★☆☆【はじめての方限定!一冊無料クーポンもれなくプレゼント】まだ見ぬ書き手へ【電子書籍】[ 丸...価格:356円
2015.12.14
コメント(0)
-

佐賀純一『浅草博徒一代 アウトローが見た日本の闇』
医師である著者が浅草のやくざの出羽屋の博徒だった患者の伊地知栄治の話をまとめた自伝。著者が伊地知の話を聞く形式。生い立ちから時系列順にエピソードが語られ、その一つ一つがユニークな体験なので飽きずに読める。伊地知の自伝に加えて、出会った仕事仲間や女郎たちの話なども語られるので、話題が広くて日本の雑学としても面白い。石炭の売買、サイコロの丁半博打のやり方、夜中に博打の客を送迎するもうろう船、人糞を運ぶおわい屋、銭湯のあんまの殺人事件、刑務所での拷問、徴兵、駆け落ち、傷害致死での懲役、やくざとテキヤの縄張りの違い、やくざ同士の相互扶助、敗戦後の航空廠からの泥棒、闇物資の取引など、大正時代や昭和初期の様々な出来事や社会の様子が興味深い。やくざが博打の客や女郎や近所の人とどう交流していたかという日常生活は歴史の教科書等を読むだけだとわからないものなので、同時代を生きた人の証言は一読の価値がある。具体的な仁義の作法(おひかえなすって云々)が書かれてなかったり、戦後に出羽屋がどうなったのかが書かれてなかったり、掘り下げ不足の部分もあるものの、伊地知栄治が故人になってしまったのでしょうがない。誰かが独自の体験を語れば気取ったレトリックがなくても面白い物語になりうるという物語本来の面白さがあり、これは時代を経ても色あせることのない面白さである。近頃つまらない純文学ばかり読んだせいか、リアリティのない創作よりもこういう丁寧に作られた一般人の自伝のほうが面白く思える。著者が内容をわかりやすく整理して資料で補強して編集した労力も評価したい。組織化して暴力団と呼ばれる以前の義理と面子を重んじるやくざの生活に興味がある人は買っても損はない。逆にやくざの生活に興味がない人にはあまり面白くないかもしれない。新潮文庫版だと『浅草博徒一代 アウトローが見た日本の闇』というタイトルだけれど、元は筑摩文庫版の『浅草博徒一代 伊地知栄治のはなし』というサブタイトルだったらしい。伊地知栄治という個人名を出しても有名人でないからサブタイトルを変えたのだろうけど、だからといって日本の闇みたいな仰々しいサブタイトルは合わない。あと309ページの「昔は、女を売ったり勝ったりするのを専門にしていた桂庵なんてのがいくらもいましたから」という文章は「売ったり買ったり」が正しいんじゃなかろうか。★★★★☆【楽天ブックスならいつでも送料無料】浅草博徒一代 [ 佐賀純一 ]価格:637円(税込、送料込)
2015.12.11
コメント(0)
全7件 (7件中 1-7件目)
1
-
-

- 読書日記
- 書評【ケアマネ女優の実践ノート】 …
- (2025-05-01 00:00:27)
-
-
-

- 最近買った 本・雑誌
- 購入|「ローソク足チャートで勝てる…
- (2025-04-27 21:18:15)
-
-
-
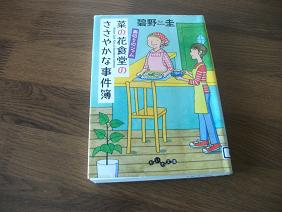
- 本のある暮らし
- 《画像》マーマレードちぎりパン&市…
- (2025-04-25 17:34:14)
-







