2024年09月の記事
全23件 (23件中 1-23件目)
1
-

喜多川泰さんの本 「株式会社タイムカプセル社」
色々と考えてしまうお話でした。未来の自分に向けて書いた手紙を、数年後に配達することを事業とする会社に働くことになった45歳の新井さんのお話。新井さんが届けることになった手紙を配達するなかで、出会う人たちの人生に触れ、自分の人生も見つめ直していきます。希望に満ちた、純粋に未来を夢みた言葉が書かれた手紙に背中をおされることもあれば、夢見た自分になれていないことに愕然とし、手紙なんて読みたくなかったという場合もでてきます。届けた手紙の意味とは‥。本の中には、たくさんのつらい思いをしてきた人たちがでてきます。自分の書いた手紙の言葉に救われる人もいれば、いろんなつらい思いをしてきた人だからこそ、でてくる言葉で、救われる人もいます。言葉の重さを改めて考えさせられるお話でした。この本で心に残った言葉は、⚫︎「来たときよりも美しく」少し要約した書き方になってしまいますが、私が生まれる前より、いい世界になっていてほしい。そんな意味がこもった言葉を、なんかいいなと、こうあれたらいいなと思いました。⚫︎「生きているってことは、きっと僕にはまだ役割があるはずだって自分に言い聞かせています。今ここに集中。今日だけを精一杯生きるしかない。」⚫︎「人生のどこかで転んだり、どん底に落ちたり、どうしていいかわからなくなってしまうようなことがあって、誰にも相談できず一人で苦しんでいるのなら、本屋にいくといい。立ち直るきっかけをくれる重さをもった言葉が詰まった本がそこにはたくさんあって、あなたに読まれるのを待っています」言葉は人を幸せにもするし、苦しめもする。重さをもった言葉をどう使っていくか。あなたはどう生きていきますか?と問われ、理想や現実や、自分の弱さと向き合う時間をくれるような本でした。ぜひ読んでみてください。おすすめです♪株式会社タイムカプセル社 新版 十年前からやってきた使者 (喜多川 泰シリーズ) [ 喜多川 泰 ]
2024.09.30
コメント(0)
-

お気に入りのりものえほん 7選
息子たちは小さい頃、車の絵本が大好きでした。特に上の子は、車のばかり読みたがるので、色々検索しては図書館で借りていました。たくさん読んできたなかで、特にこれはお気に入りだったのを、今日は書いていきたいと思います。車好きのお子さんがおられましたら、ぜひ読んでみてください✨①「なんの じゅうたい?」なんのじゅうたい? (絵本・いつでもいっしょ 42) [ オームラ トモコ ]50台もの乗り物がでてくるこの絵本。みんなが向かってる先には何があるのでしょうか?きっと好きなはず‥〇〇が待っています🤭身近な乗り物、働く乗り物、初めて見る乗り物。一つ一つ名前を言ってみたり、ただ眺めてみるだけでも楽しいが詰まってる絵本です。②「バルンくんとおたすけ3きょうだい」バルンくんとおたすけ3きょうだい。 (幼児絵本シリーズ) [ 小森誠 ]バルンくんシリーズのなかでも、この本が一番子どもたちはお気に入りでした😊道路をなおしてくれる3きょうだいの働く車が、とにかくかっこいい✨小森さんの描く車の本が、私は大好きです。③「しょうぼうじどうしゃ じぷた」しょうぼうじどうしゃ じぷた (こどものとも絵本) [ 渡辺茂男 ]古い本ですが、今でも愛され続ける名作じぷた。小さい消防自動車のじぷたは、はしご消防車や大きなポンプ車、救急車に憧れます。大きな火事の現場に呼ばれないじぷたを、はじめはみんなバカにしますが‥じぷたにしかできないことがありました。小さくても負けずにがんぱるじぷたを応援したくなる物語です。④「トミカコレクション」トミカコレクション2023 (超ひみつゲット! 118) [ (株)タカラトミー ]毎年発売されているトミカコレクション。うちにあるのは2023ですが、2024年度版も発売されています。その年にでたトミカやトミカタウンがたくさんのってあり、暇があると開いて見ています。大きさも少し小さめなので、お出かけの際や、外食のときなど、待ち時間ができそうなときには、この1冊をカバンにしのばせて出かけることが多く、少しの空き時間もこの本さえあれば、楽しく過ごせます!⑤「ゴトガタ トラック」ガタゴト ガタゴト プップー白を基調にしたスタイリッシュな絵とリズムの良い言葉たち。心地良い絵本が癖になり、何度も何度も借りた本です。トラックたちはどこへ、何を運んでいるのでしょうか?あぁ、そうなるのね!と、最後なります😊⑥「トラトラ トラクター」トラ トラ トラクター (幼児絵本ふしぎなたねシリーズ) [ 小風さち ]トララ トララ トララと、なんとも言えないこの響きと、この表紙のガッツポーズのおじさんが大好きなこの絵本。一番借りた乗り物絵本かもしれません。トラクターと台車が連結しお仕事をする物語。読んでいて楽しくなるリズムいい言葉と、見慣れない車にも興味津々になる、素敵な絵本です。⑦こうじのくるまこうじのくるま [ コヨセジュンジ ]リアルで細かい描写の、工事の車がたくさんでてくるこの絵本。ブルドーザーの中だけでもこんなに種類があるのかーとびっくりするくらい、それぞれの車の仲間たちも細かく書いてあります。クレーンの操縦席も書いてあったり、クローラーの仕組みもあったり、工事の車好きさんにはたまらない一冊かなと思います。
2024.09.28
コメント(0)
-

ヨシタケシンスケさんの対談集 「もりあがれ!タイダーン」
すっごく素敵な本でした✨ヨシタケさんの絵本は大好きで、今まで何冊も子どもたちと読んできましたが、絵本とはまた違う対談という形でのヨシタケさんの言葉も、おもしろいし、共感できることばかりで、ずっとおもしろいーって思いながらページをめくっていました。その上、大好きな作家さんたちとの対談は、絵本ファンとしてはたまらない!かこさとしさんや鈴木のりたけさんなど、いつも絵本見てますの人たちと、ヨシタケさんがお話してるーってなります笑まさか「りんごかもしれない」は、「からすのパンやさん」から影響をうけてだったとはーとか、好きな本と好き本が繋がってたなんてー!と、嬉しくなる瞬間にたくさん出会いました。また、「ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー」のブレイディみかこさんとの対談も、すごく心に響きました。イギリスの保育園で働いた経験のあるブレイディさんの言葉は、固定概念を壊してくれるものばかりでした。イギリスの保育園では、雑談しながら絵本を読むそうです。子どもたちから「なんでこんな顔してるの?」とか聞かれてなかなか読み終われなかったり、好きな姿勢で見てもいい。日本では、静かに最後まできちんと座ってきくが当たり前にありますけど、好きに楽しめる、ものが言える姿勢、関係が小さい頃からちゃんとあるんだなと思いました。今、転生ものが人気なことに関しても、「今ここにある世界を変えていくことが、別の世界をつくることだ。別に転生しなくても、今ここから変えていけるんだよ」と書かれていて、なんかすごく考えさせられました。転生ものに惹かれるのは、今を変えたいと思うことからですよね。だけど変えられないし、逃げもできない。だからそんな世界に思いを馳せるのかなって。子どもの頃は特に、変えるって難しい。そこを変えてもいいんだよ、逃げてもいいんだよって言える大人になりたいと、この対談を読んで思いました。ブレイディさんの本を読んだことがなかったのですが、これから読んでいきたいと思います。そして、この本には、ヨシタケさんや対談される作家さん方の好きな本がたくさん紹介されています。どれも、読みたくなる本ばかりで、読みたいリストがたっぷり溜まりました。似たような系統の本ばかり手にとりがちになってしまうので、こうやって新しい作家さんや絵本に出会えるのは、嬉しくて嬉しくて。これから一つずつ、読んでいきたいと思います。ヨシタケさんの絵本は、なんだか言葉にしにくいけど、どこかで感じたことのある気持ちを、あのかわいい絵と言葉で表現してくれるところが大好きなんですが、ヨシタケさん自身は「世の中がこわくて、人のことが信じられなくて、どうすれば楽しめるか、人を信じられるかの記録」として、絵本を書いているとありました。あぁ、わかるって思いました。その気持ちわかるから、そこに寄り添ってくれるから、ヨシタケさんの本が好きなんだなって、改めて思いました。ヨシタケさんファンの方はもちろん、全然知らないよの方も、いろんな方の世界観や言葉に触れることができると思います。おすすめです!もりあがれ!タイダーン ヨシタケシンスケ対談集 (MOE BOOKS) [ ヨシタケ シンスケ ]
2024.09.27
コメント(0)
-

読書感想文にいいかも(11) 「おひとよしのオオシカ」
なんか考えさせられる物語でした。気のいいオオシカのツノに、いろんな生き物が棲みついてしまうのですが、その中にはオオシカの頭の毛をむしり取って巣をつくってしまうものから、ツノに穴をあけてしまうキツツキや、重たいクマまでものってきてしまいます。重たいし、痛いと思うのに、気のいいオオシカはお客さんには親切第一と、下ろそうとはしません。そのうち、仲間からは、変わり者とされ、群れから追い出されてしまいますし、お客さんたちがいるから川も渡れず、ごはんにもありつけなくなってしまいます。そして、変わったツノをもつオオシカは、猟師さんたちの的になってしまいます。さぁ、オオシカはどうなってしまうのでしょうか?ただただ優しいオオシカですが、ずる賢い生き物たちにどんどん良いように利用されていってしまいます。そして、本文のなかでも、「もし、これが きみなら きみなら どうする?」と、投げかけられます。きっといろんな意見がでるだろう物語だなって思いました。どれも大切な気持ちだろうし、誰に重きをおくかで、気持ちは変わってくる物語。最後は、あぁよかったとほっとできる結末ですが、ひやひやはらはらとし、考えさせられてしまいます。人に優しくありたい気持ちと、自分も守らないといけない気持ち。これが正解なんてないだろうけど、どう思う?と考えることが大切なのかなと思いました。もう終わってしまった夏休みですが、もし来年以降、読書感想文でどの本にしようか迷ったときは、候補の一つにいいかもって思った本でした。おすすめです!【中古】おひとよしのオオシカ (ドクター=スースの絵本)
2024.09.26
コメント(0)
-

学校では教えてくれない大切なこと お金のこと
学校では教えてくれない大切なことシリーズ。PTAの活動で、小学校の各教室の書籍整理をした際、このシリーズの本は、どれもボロボロになるまで読まれていて、人気のある本なんだなと気になっていました。このシリーズはたくさんでているんですが、今回はお金についての本を読んでみました。登場人物は、小学3年生の子たちで、気になることを一つ一つ質問していき、アフロ先生が、漫画でわかりやすく教えてくれます。おこづかいを増やしたいお金を貸してといわれたらどうしたらいいかお年玉はなんでもらえるのかなんで消費税はかかるのか全部の商品を安くしてくれたらいいのになどの身近な疑問から、大人も答えるのに悩んでしまいそうな、社会の中でのお金の仕組みや、日本銀行やの役割など、すごく難しい分野のことなのに、親しみやすい絵と言葉で、わかりやすく説明してくれています。今はPayPayなどで、お金のやりとりをする場面を見る機会も減り、子どもたちにとって、お金について考えることも減ってしまい、よりわからないものになってきているのかなと感じていたりします。自分たちの見えないところでお金は動き、見えないとこで親は働き、働いてもらったお金だけど見えないPayPayで支払われ、それでお金を大切にしろと言われてもってなるだろなって思っていたので、この本は、その見えないとこの部分を見える化してくれているので、ぼやっとしていた視界が開けるような気持ちにさせてくれます。そして、大きく大雑把でも、世の中でのお金の仕組みや動きがわかれば、なんでお金は大切にしないといけないのかが自分の中で考え、答えに繋がれば、人に言われなくても、お金を大切に使うことができるようになっていくように思いました。この本の最初に書いてあったのですが、「世の中には、正解が一つではなかったり、何が正解かがわからないことがたくさんあります。状況によって正解が変わることもあるし、100点にも0点にもなり得る問題が世の中にはあふれています。その中で自信をもって生きていくには、自分でとことん考えて、そのときの自分にとっての正解が何かを判断していく力が必要になってきます。」とあり、その通りだなと思いました。親としてできることは、知ることや考えるきっかけを作ったり、一緒に考えていったり、私自身も考えて生きていくことかなとこの本を読んで思いました。子ども用の本だと思い手にとりましたが、知らないことばかりで、めちゃくちゃ勉強になる本でした。子どもたちがボロボロまで読む理由がわかりましたし、もっと他のシリーズも読んでみたくなりました。おすすめです!学校では教えてくれない大切なこと(3)お金のこと (学校では教えてくれない大切なこと) [ 関和之 ]
2024.09.25
コメント(0)
-

HSPの本⑤ 「HSC不登校の小学生」
今まで医師の方から見たHSPやHSCについての本は何冊か読んできましたが、実際HSCの方が書く本を読むのは初めてでした。HSPとは、生まれつき刺激に対して、とても敏感な人のことです。この敏感さは、病気でもないし、障害でもない。単に気質だと考えられており、5人に1人の割合でいると言われています。HSCは、HSPの子ども版のことで、30人クラスなら5.6人はいるんじゃないかと言われています。意外と多いですよね。。この本は、HSCの小学5年生のにんじんさんのノンフィクションの本です。どのように学校生活を送り、どのように見え感じてきたかが、とてもリアルに書かれていて、途中すごく苦しくなってしまう場面もありました。HSPは、その繊細な気質をどう受け止められてきたかで、生きやすさは大きく変わる、環境がとても大切だと、別の本で知ってはいましたが、環境が与える影響がこんなにも大きいのか‥と、痛いくらい実感させられる内容でした。自分が怒られていなくても、それ以上に、自分が怒られているように感じてしまう。怒られないようにちゃんとしないと。。どんどん怖くなり、体調を崩してしまう。その際のお医者さんの言葉が、素敵でした。「そんなにつらかったら、学校に行かなくていいよ。家で勉強しとるんやろ?そしたら大検とってから医者にでもなれよ。医者はオリンピックの選手になるよりラクやから、君が医者になったら診察してな」。そういう理解ある優しい言葉をかけることができる人もいる反面、心ない言葉をかける人もいたり、学校以外の場所には国からの支援がないことなど、今まで知らなかった現実を突きつけられた気持ちになりました。にんじんさんは、何度も何度も登校しようとがんばりますが、身体が拒否反応をだしてしまいドクターストップがかかってしまいます。いろんなことを乗り越えながら、いろんな人たちと交流を重ね、コロナ禍によりオンライン授業ができるようになるなど流れも少し変わり、その中でにんじんさんは、自分がやりたいことを見つけます。小学5年生でここまで明確にやりたいこと、やるべきことが見えている人はなかなかいないと思うくらいのことを考え実行していて、これは学校いくいかないどうこうではなく、どう毎日生きてきたかだと思いました。本気で学校へ行くとは、学ぶとは、生きるとはを考えた人だからこそだと。そして、最後にお母さんの言葉もありました。寄り添い続けてきたお母さんの言葉がどれも重く、一つ一つに大きな課題を感じました。学校へ行き渋る中、連れて行くべきかどうかの悩み。居場所を見つけることができても支援がないための金銭的な問題。保護者は、親と先生の2つの仕事をするため自分の時間は全くない状態など。けどこれは全く他人事ではなくて、もっと自分事として考えないといけないことばかりに感じました。行き渋りのあるHSCの息子の親の1人として、私も考えないといけないことばかりだし、にんじんさんが投げかけてくれたボールを受け取り、できることからやっていきたいと思いました。理解しようとしてくれる人もいれば、そうでない場合も必ずくる。いい環境でと思っていても、そんなとこばかりではないのが現実だと、この本を読んで改めて思いました。どう社会と繋がっていくか。学校が全てではないし、学校が悪いわけではない。だけど、その子たち自身が悪いわけでも絶対にない。生きづらさを感じている人たちの、生きやすい環境とは。なんかたくさんの課題を感じました。そして目の前にある行き渋る息子との向き合い方。何が正解なのかまだまだ模索中です。ですが、新たな生き方の選択肢を教えてもらえたこの本に出会えて本当によかったなと思いました。本にしてくださったことに感謝の気持ちでいっぱいになりました。たくさんの方によんでほしいなと思いました。おすすめです。HSC不登校の小学生 [ にんじんさん ]
2024.09.23
コメント(0)
-

子ども向けの投資本 「投資の心得 10歳から知っておきたいお金の育て方」
みなさんは、お子さんとお金の話とかされていますか?私は全くです💦まだ子どもが小さいのもあり、お小遣いも渡していない状況ですが、最近たまたま見たYouTubeで、子どもへのお金の教育についての話を見たのをきっかけに、興味がでて借りたのが、この本でした。私は今年に入り新NISAを始めたばかりで、去年までは投資については考えてもいなかったのですが、これからの子どもたちの時代は、働いて稼ぐ以外に、投資という選択肢も入れていかないと厳しくなるんじゃないだろうかと考えています。YouTubeで拝見した中で印象的だったのが、少額からでいいので親と一緒に投資を始めて、ニュースを見たり、応援したいと思うとこに投資をし、なんで株価が上がったり下がったりしたのかを一緒に考える。その過程がただただ投資はこわいものではなくなり、自分で考えるを育てていくという考え方でした。また長期に投資することの大切さも知っているので、早いうちから始めるほうがいいという思いもあるけど、じゃあどうやって始める?どう興味もってもらう?私自身もまだよくわかってないのにー💦って思いから、この本を読むきっかけになりました。私は投資については、YouTubeを見て勉強して始めたんですが、そのYouTubeで何度も見た、ほんとに1からの説明が10歳の子向けに書かれています。言葉の説明はもちろん、なんでお金が増えたり減ったりするのか、どうやって応援したい会社を見つけるのかなど、とても丁寧に書いてくださっています。子ども向けですが、私自身も勉強になることばっかりだったので、投資初心者さんにもおすすめだなって思いました。ですが、文字数は多めで、うちの子がもし10歳になったときに渡したとして読むだろうかと考えると、めんどくさい、興味ない、難しいで終わりだなとも思いました。お金の教育って学校ではしてもらえないし、わかりやすく、お小遣いをもらってお菓子を買うのほうでいいよになっちゃいそうで。。それも全然いいんですが、働いて稼ぐ以外に、応援したいとこに投資をし、お金に働いてもらい、社会をよりよくすることの貢献としてお金が増えるという仕組みが身につき、選択肢の一つとして生活の一部になるのとならないのとでは、将来大きくお金や時間、心の余裕を左右するんじゃないかと思いました。そんな未来になるかならないかは、親がどれだけ投資を知っていたり興味をもっていたりやっていたりなのかなと思うし、その経験こそが何より影響を与えるだろし、生活のなかで、当たり前のように投資についてやニュースについての話ができる環境がきっといいんだろなと思いました。私はまだまだなので、まずはもっと興味を持って勉強することだろなと思いました。どこか応援したい会社も見つかってないし、見つけようともしてなかったんだとこの本を読んで気づいたので、まずは子どもが大きくなるまでの間は勉強期間と思い、できることをやっていきたいなと思いました。この本は、キッズマネースクールの方々が書かれている本で、実際にご自身のお子さんにどのようなお金の教育をされているか、そして大きくなったときどうなっているかなどもリアルに書かれていて、勉強になることばかりでした。子どもに投資なんて‥の思いが変わるというか、その世界を知ってるか知らないかで、大きく人生が変わるようにも思いました。自己投資についても書かれていて、お金の投資どうこうだけでなく、そこだけでも読み物としても面白かったです。子どもとお金についての向き合い方、もっといろんな方面からの本も読んでみたくなりました。興味がある方、ぜひ読んでみてください。おすすめです!今から身につける「投資の心得」 10歳から知っておきたいお金の育て方/八木陽子/オフィス・ジータ【1000円以上送料無料】
2024.09.23
コメント(0)
-

上白石萌音さんの本 「いろいろ」
本当に大好きな本。心の中がぐちゃぐちゃになったとき、寂しい気持ちになったとき、もう無理だって思ったとき、何度も支えてもらってきた本です。たくさんご活躍をされている上白石萌音さんですが、テレビだと役柄なども影響してしまうので、どんな方なのかちゃんと知れたのは、この「いろいろ」に出会えてからでした。読めば読むほど、人柄も考え方も好きになりました。悩んだり、後悔したり、まわりはこんなにすごいのにと自信がなくなったり‥。きっとそういうところに、同じだ‥と思い、どんどん惹かれていったんだと思います。本が好きなところ、まわりの人たちを大切にされているところ、役柄との向き合い方、感謝の気持ちを忘れていないところ、そして前向きな気持ちにさせてくれる優しい穏やかな言葉たち。ぐちゃぐちゃな気持ちで読み始めるのに、読み始めると、どんどん自分の心の中も、穏やかになっていくのがわかるんです。実際の現実は何も変わらないのに、やるべきことを、萌音さんのように、誠実に、凛として、やるだけだなと思わせてくれます。そして、本に対しても、ほんとに好きなんだろなと伝わってくる言葉たちに、なんだかうれしくなってくるんです。かばんに本がないと落ちつかないとことか、他にも色々本好きさんには、あぁなんかわかるかもってとこ、きっと見つかるような気がします😊あたたかなそっと寄り添ってくれる言葉たち。なんだか疲れたなぁのとき、沁みます。おすすめです♪いろいろ [ 上白石 萌音 ]
2024.09.22
コメント(0)
-

はやく はやく!早口小学校
息子たちがハマった一冊でした!小学校に関連した、たくさんの早口言葉がでてくるこの絵本。口ずさみたくなってしまう早口言葉ばかりで、読むのも楽しい☺️「ビッグピック ピンクピッグ ビックピンクピッグ」が、個人的には大好きでした!子どもはカピバラの早口言葉がお気に入りでした✨ストーリー仕立てになっていて、最後はなんと早口言葉を使ってはいけなくなってしまいます💦早口言葉を使っちゃいけないなんて‥💦いったい最後はどうなっちゃうの?と、最後まで楽しくて、毎回読み終わったら、もう一回☝️とリクエストが入るこの絵本!読む側も、なんかテンションが上がって、楽しくなっちゃいますよ✨おすすめです!はやく はやく! 早口小学校 ~お口のたいそう 早口ことば (ことばをたのしもう 早口ことば 1) [ 間部香代 ]
2024.09.21
コメント(0)
-
熱性けいれん
熱が上がる時に、脳が急な体温の変化をうまく処理できず興奮することで起こるとされている熱性けいれん。乳幼児期に発症するタイプのけいれんの一つで、日本では10人に1人ほどの割合で、経験すると言われています。まだ私は実際にその場で立ち会ったことはないのですが、いつ目の前で起こるかわからないので、知識と対処法は頭に入れておかないとと思っています。急にけいれんが起こると焦ってしまうと思うのですが、どうすればいいのかさえおさえておけば、少し落ちついて対処できるかもと思い、簡単にですが、まとめてみたいと思います。【熱性けいれんとは】⚫︎原因は、現在まで完全には明らかになっていないとも言われてはいますが、発熱に関連して、神経ネットワークの制御がとれなくなり、けいれんが起こると推定されている。⚫︎通常6か月から5歳くらいまでにみられる。男児に多い。⚫︎1回の経験のみの場合もあれば、発熱のたびに起こる場合もある。半数くらいの割合で繰り返すが、成長に伴い、6歳前後で、ほとんど起こさなくなり、経過は良好。⚫︎親や兄弟に熱性けいれんの経験があると、発症する可能性は高いと言われている。⚫︎発熱の原因としては、突発性発疹、夏風邪、インフルエンザなど、急に高熱を出す疾患で多いが、高熱をきたす疾患は全て、けいれんのきっかけにはなる。【症状】⚫︎38度以上の高熱時で、熱が出始めてから24時間以内におこるけいれん。熱が急激に上がるのと同時におこるとされている。⚫︎急に手足をかたくし、突っ張る⚫︎手足をピクピクさせる⚫︎手足に力は入らずダラーっとして、意識だけなくなる⚫︎白目をむく⚫︎目は見開いて焦点が合わない⚫︎呼吸は不十分なため、全身の色が悪くなる⚫︎嘔吐や失禁→体全体におこったり、半身だけ、四肢の一部だけに起こるなど、症状もさまざま。この間、周囲に反応はなく、2〜3分程で自然にけいれんは治まる。けいれんが治まった後も、多くの場合は、しばらく寝ていたり、ぼーっはするが、意識は徐々に元に戻る。しかし、20〜30分と長く続くこともある。⚫︎熱性けいれんの場合は、脳に対してダメージが残ることはなく、後遺症は残すことはないと考えられている。⚠️しかし、熱性けいれん以外にも、発熱やけいれんを症状とする病気は数多くあるため、注意が必要。また、3〜5%は、てんかんに移行するとも言われている。【対応方法】①安全な体位にする⚫︎ベットや床に寝かせる⚫︎顔のみではなく、体全体を横向きに寝かせる→嘔吐すると窒息するおそれがあるため⚠️けいれん中に体をおさえる ❌口の中に手をいれる ❌→かえって悪影響であるため、控える。 ②落ちついて、けいれんの様子や体の変化を観察する⚫︎片方の手足、目だけがけいれんしていないか⚫︎けいれんが続いた時間⚫︎けいれんが治ったら、体温をはかり、38度以上あるか確認をする⚫︎可能であれば、動画撮影をし、病院で経過説明する際に医師に見せる【受診タイミング】◎救急車をよぶ⚫︎5分以上 けいれんが続く⚫︎繰り返しけいれんがおこる⚫︎意識がなかなか戻らない◎すぐに受診をしてください⚫︎初めてのけいれん→短時間であっても、熱性けいれんかどうか確かめるために⚫︎2回目以降であっても、けいれんが長く続く場合は、すぐに受診をけいれんが短時間でおさまり、意識も回復をしていれば、あわてて受診する必要はないため、落ちついて対応をしてください。【検査や治療】⚫︎検査は、熱性けいれん以外の病気が疑われる場合には必要とはなるが、必ずしも検査をするとは限らない。発熱してからけいれんが出現したタイミングやけいれんの形、家族歴など評価をし判断をするようです。⚫︎けいれんの予防として、近年ジアゼパムという座薬が使われている。
2024.09.20
コメント(0)
-

もののけしょくどう うらめしや
かわいいとおもしろいが詰まった絵本でした!真夜中にひっそりとひらく、すこし変わった食堂のお話。お家にある物たちが、今日も疲れたわーと言いながらやってくる食堂には、変わった食べ物がいっぱい😋でんちにぎりすしくつしたのてんぴぼしティッシュミルクレープほこりの出汁でできたほっこりスープきせつのふせんサンドてちょうのひらき など、どれもクスッと笑えるメニューばかり!それがなんともかわいくて美味しそうな絵で書いてあるので、子どもも大人も食い気味で見ちゃいます🤭食べたときの感想もユーモアたっぷりで、見ていてほんとに楽しくなっちゃいます!トイストーリーのような身の回りにある家具や家電や本やペンの物語。寝る前に、こんな世界も楽しいねと、ほっこりした気持ちで読める素敵な絵本です😊おすすめです!うらめしや もののけしょくどう (日本傑作絵本シリーズ) [ たにむらのりあき ]
2024.09.19
コメント(0)
-

HSPの本④ 「敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本」
これまでに、HSPについての本を「繊細さんの本」「繊細さんの知恵袋」「子どもの敏感さに困ったら読む本」と、読んできて、なんとなくHSPについてわかってきました。そして、自分や息子たちに当てはまる部分が多くあり、HSPであると自覚をし、そこからどう向き合っていこうかと本を読みながら探す日々です。HSPとは、環境や性格などによる後天的なものではなく、先天的な気質です。気質とは、感情や行動、刺激などに反応する生まれもった心のパターンと、この本には書かれていました。また、HSPが陥りがちな思考の癖は、気づくことで抜けだせることができるとも、書いてありました。今回の本でも、新たな気づきをもらえたので、忘れないでおきたいなと思ったことを書いていけたらなと思います。⚫︎なかなか眠れないというのは、HSPの多くの方に共通している悩みです。睡眠が浅く、ささいな刺激で覚醒してしまうため、脳が休まることがない。HSPが疲れやすい一因にもなっている。→うちの息子たちも、ほんとに寝るのを嫌がります。寝れないと言い、なかなか寝付くのに時間がかかり、そのうち遊びだしてしまいます。私は早く寝かさないとと思うあまり、早く寝ようって何回も言ってるよと言ってきてしまってましたけど、、この眠れないというのもHSPからきているものなのかと、寝れないでつらいと思っている息子たちに寄り添えていなかったと気づき反省しました。まずは、眠れなくても責めない。なかなか切り替えに時間がかかることも考慮し、早めから布団に入れるよう工夫したり、お風呂に浸かるタイミングを変えたり、寝る前に刺激的なものを見過ぎないでいたり、心地よい環境をちゃんと作っていかないとと気付かされました。⚫︎敏感すぎる子は、小さな時に、大人には想像もつかない刺激や変化の渦中にいて、耐えきれず固まるか、逃げるか、戦うかなどの、激しいストレス反応を起こしています。⚫︎HSPに必要なのは、安心安全な場所。「できない自分でも大丈夫なんだ」という絶対的な安心感を植えつけること。そのために親は、世間の価値観や常識にとらわれないで、敏感という個性をポジティブに捉え、愛情を子どもに伝える。→本でHSPを知るたび、あぁしんどいだろなと息子のことが頭をよぎります。上記にある、耐えきれず固まる、逃げる、戦うは、まさに息子で、保育園につくと固まり、逃げます。保育園の先生方も話をしてからは親身になり、息子の話を聞いて、息子の苦手なお着替えや水遊びは嫌ならしなくていいよと寄り添ってくれるようになり本当に感謝しているのですが、なかなか行き渋りはなくなりません。まだまだ言葉にできない何かがあるんだろなと感じます。朝になるとお腹が痛いと言い、ごはんも食べようとしない。身体的な症状がでているのかと思い、休むことにすると、お腹の痛みはなくなる。日中元気に過ごす。行けたんじゃないかと思う。。これを何度か繰り返してきました。保育園の先生や主人は、きっとお腹が痛いと言えば休めるとわかってるから言うんだと言います。無理やり連れていくこともできるんですが、絶対的な安心感からは離れる気がして、毎朝葛藤してしまいます。どこに重きをおくか‥今朝はどうなるか‥気持ちよく、行きたい場所に保育園がなるように、まだまだできること探し中です。⚫︎安心できる愛着を感じて育った敏感な子は、心の中にリソース(資源)ができ、刺激過多の中であっても大丈夫。→この状態になれるのが理想だなと思いました。そして、刺激過多の中であっても大丈夫との言葉に救われました。本の中には、たくさんのこういうときにはこんなふうにしたら生きやすくなるよと、アドバイスが書いてあります。心の中に安心できる場所をもち、その場その場では自分にあった距離の置き方などをし、少し疲れはするけれど、帰ってきたらほっとできる、そのまんまの自分でいれる。そんなふうなのを目指して行けばいいのかなとぼやっと思ったりしました。私ができることは、安心安全な場所を作ること。外でもなんとかやってみようと思えるよう背中をおすこと。まだまだその背中の押し方も加減もわからないことだらけですが、勉強しながら、たくさん話をしながら、やっていきたいと思いました。本の最後には、著者の精神科医の長沼医師がやっておられるクリニックのWEB診療についても書いてありました。近くに相談できる場所がない方は、WEB診療(保険診療、自由診療)もできますよと。気になられる方がおられましたら、「十勝むつみのクリニック」のホームページを見てみてください。敏感すぎて生きづらい人の明日からラクになれる本【電子書籍】[ 長沼睦雄 ]
2024.09.18
コメント(0)
-

中村倫也さんのエッセイ本 「THE やんごとなき雑談」
とってもあったかくて、くすって笑えるこの本が、私は大好きで、何度も読んでいるエッセイ本。言葉選びも、考えている内容もおもしろくて、どんどんページをめくっちゃうんですが、読み終わるのが惜しくて、早く続きを読みたいけど終わるのは寂しい葛藤を繰り返しながら、毎回読んでいます。明るさと影を両面持ち合わせているところ、いろんな自分と向き合いながら生きているところなど、テレビで見る華やかな姿とは別な一面を知り、すごく惹かれる俳優さんの1人になりました。そして、なんでこんな面白い表現ができるんだろうと思うくらい彩り豊かな言葉が散りばめられていて、こんな文章が書ける人になりたいと純粋に憧れてしまいます。ふわっと気楽に読める部分もあれば、人の奥深くに眠っている色々な想いに触れたりだったり、緩急ある内容に、魅了されっぱなしで読み終わっちゃう一冊です。おすすめです!THE やんごとなき雑談 [ 中村 倫也 ]
2024.09.16
コメント(0)
-

大ピンチずかん2
「大ピンチずかん」より、さらにパワーアップしている「大ピンチずかん2」。1のときにはなかった、大ピンチグラフで、どうピンチなのか分析できるようになっているとこが、よりリアルにピンチ感が伝わってきて、おもしろいです!小さい頃にやってしまったことのある先生をお母さんと呼んでしまったや、日頃大人でもあるちょっとしたピンチと、乗り越え方も書いてあったりし、あるあるーと言いながら、次はどんなピンチがくるんだ?と、ページをめくるのが待ちきれなくなっちゃいます。あと、気をつけないとと思ったのは、「お母さんがイライラしている」が大ピンチレベル94で、グラフでは不安、つらい、ドキドキ、気持ち悪いなどが枠をはみ出すくらいふりきっていて、なんかごめんってなりました。思うところがありイライラしているのですが、それを客観的に見ると、こんなにもピンチだと思わせてしまっていたんだなと知り、自分の気持ちも切り替えていったり、イライラの元を解決して、家族が気持ちよくいれるようにしないとと思いました。1のときにも、最後はなんかいいなぁってほっこりして終わったのですが、2もまたいい感じです😊大人にも響くメッセージに、ぐっときます。大ピンチなんてこわくない!自分の気持ちに向き合い、乗り越え、切り替えていく。簡単なことではないけど、この本を見ているときのように、よくあることだよねって、笑って乗り越えていける人になりたいなって思いました。最後に大人の大ピンチずかん考えてみました笑⚫︎コーヒーを入れようとしたら、暑いお湯が手にとんできた。大ピンチレベル20。分析つらい。⚫︎スープをつくろうと思って、あとコンソメいれるだけなのに、少ししか残ってなくて、味が薄いスープになった。薄すぎて子どもが食べなかった。。大ピンチレベル35。分析つらい、イライラ。⚫︎旗当番の日に寝坊してギリギリになった。大ピンチレベル65。分析ふあん、つらい。⚫︎仕事に間に合うかギリギリなのに、保育園にいきたくないと泣かれる。自転車にのってくれない。大ピンチずかん90。分析ふあん、つらい、イライラ。大ピンチずかんが好きすぎて、こんなのばっかり考えてました。。すみません💦きっとみなさんも身近にある大ピンチあると思います。あー不安度上がってるわと気づけるだけで、なんか少し気持ちが変わるように思います。いつもの毎日が、失敗に思ったりもしてしまうピンチが、なんか愛おしく感じ、前向きな気持ちにしてくれる大ピンチずかん2。おすすめです!大ピンチずかん2 [ 鈴木 のりたけ ]
2024.09.15
コメント(0)
-

ピタゴラじゃんけん装置QRブック ゴラの巻
息子たちが大っ好きなピタゴラスイッチ。特に番組おわりにあるピタゴラじゃんけんは、毎回パーにいくと思う、絶対チョキやってと、あーだこーだ予想しながらの楽しい時間です。それが本で、楽しめるなんて!本屋さんで見つけたとき、親子で、これ欲しいーってなりゲットしてからは、定期的にこの本をだしてきて、楽しんでいます。テレビでは触れられていない細かいテクニックや、どんな材料を使っているかなども書いており、ピタゴラファンにはたまらない、同じ装置を作りたい欲がどんどん出てきちゃいます!だけどどの部分をきりとっても同じようにするには難しく、すごい知識と技術がこの一つの装置に詰め込まれてるんだなって、同じように作ろうとして改めて感じます。なんでそんな動きをするのかなど、マニアック解説も書いてあるので、予想もしてなかった動きの裏側も知れて、勉強にもめちゃくちゃなります。あと貴重な、じゃんけん装置制作者さんたちの言葉ものってあります。作っておられる方々の、試行錯誤しながら作られておられる生の声は、テレビでは見られないので、読み物としても面白いです。あと、大好きなトンカッチの「さらに遠慮なく聞きました!」コーナーも、気になることを聞いてくれていて、驚くことばかりでした。じゃんけん装置の問題は、全部で16問あり、QRコードでかざすと、球の転がり方を見て、答えがわかるようになっています。この本を読みはじめると、スマホを持っていかれてしまうのは少し困ってしまいますが、見るだけでも、予想をしても楽しいピタゴラは、やっぱりいいなーってなります😊おすすめです!ピタゴラじゃんけん装置QRブック ゴラの巻 [ NHKエデュケーショナル ]
2024.09.14
コメント(0)
-
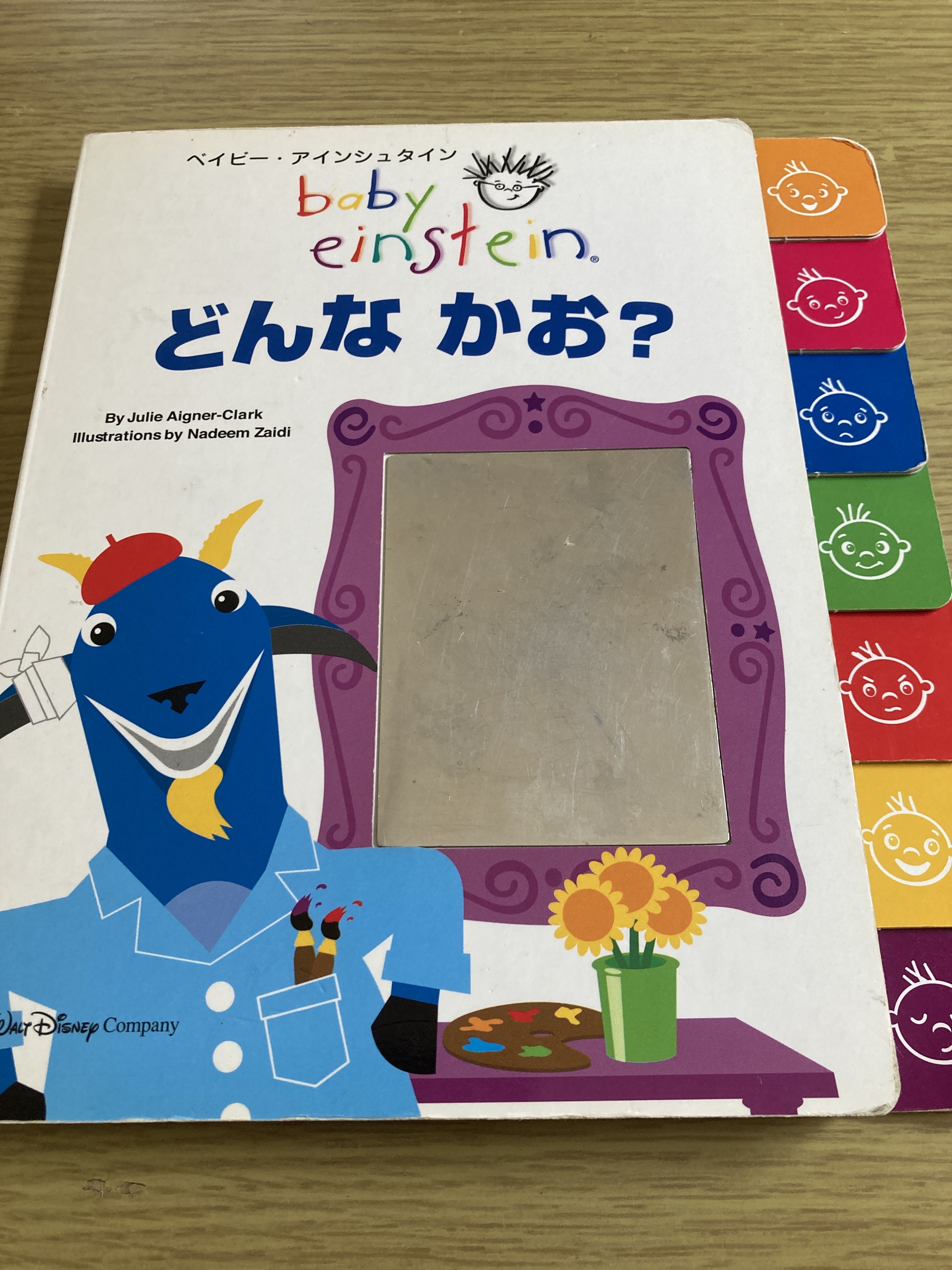
どんな かお?
絵本って読むだけが、楽しみ方じゃないんだなって教えてもらった絵本「どんな かお?」。息子たちが小さい頃からお気に入りの絵本で、全てのページに鏡がついてあります。お話には、幸せな気持ちのとき、得意な気持ちのとき、悲しい気持ちのとき、ふざけっこの気持ちのときなど、色々な感情がでてきます。その感情ごとに、得意な顔はどんな顔?や、悲しい顔はどんな顔?など、鏡を見ながら一緒に顔を作って楽しみます。絵本を読むとき、うちはお膝の上に座って読むことが多いので、あまり息子の顔って見れてないんだなって、この本に出会って気づいたんです。だけど、この絵本のときは、ずっと息子の顔も見ながら読めて、どんな顔?って聞かれる前から悲しそうな顔をしていたり、ちょっとした表情の変化も見れて、絵本を読むって、こういう感情や表情の変化を知れるから楽しいしうれしいんだよなって、しみじみ思っちゃいます。年齢と共に、表情も表現も豊かにおもしろくなってくるのもおもしろいです。一緒に絵本を読む姿って、なかなか客観的に見ることってないですよね。だけど、この本を読む時間だけは、読んでる子どもと自分の姿を見ることができます。仕事で疲れてもう寝ようよーっと思っていても、その姿を見れてしまうと、こういう時間もいいよねって気持ちにさせてくれます。いつもとは違う絵本タイムが楽しめる絵本かなって思います。おすすめです!
2024.09.13
コメント(0)
-

保育園の先生から教えてもらった本 「山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る」
わかっているけど、できていなかったなぁ。それをこれからどれだけ生活に落とし込んでいけるかだな!っと、背中が伸びる思いになる本でした。iPS細胞の山中教授と、小児科医で脳科学者でもあり、発達障害や不登校、不安障害の悩みを支える専門家でもある成田さんの対談の本。それぞれの子ども時代の話から、どんなふうに育ってきたか、家族関係から、それぞれの考える子育てに大事なことを書かれた本でした。心に残る言葉、これは実践していきたいが詰まった本でしたので、簡単にですが、まとめていきたいと思います。⚫︎「心配されるってことは信用されてないってことだから、子どもの自己肯定感はどんどん下がる。自分で選んだことを、失敗しては立ち上がって、続けて、自信をつけることが重要。」→心配、してました。朝泣いて行く息子に、夕方会ったとき、心配してたんだよと声をかけていました。仕事中も気にしていたんだよと伝えたかっただけでしたけど、自己肯定感を下げてしまっていたなんて気づいていませんでした。ちゃんと息子にはやりきる力はあるのに、まわりの先生方もたくさん助けてくださっているのに、信用できてなかったのは、息子のもっている強い部分ではなく、苦手な部分にばかり目がいっていたからだと気づきました。もう心配してたんだよは、やめます。できるって信じてたよ!に変えます。⚫︎山中教授は、なんでも自分でしなさい。自分で何をやりたいか考えるから始まり、自分で見て盗めと言われ、育ってきたそうです。あれこれ手取り足取り教えてもらうというより、レールに引かれた道を行くというより、自分で選び前に進んできた人は、失敗も人のせいにせず、身からでたさびと考え、いいことはおかげさまとまわりに感謝できると教えてもらいました。→これには、やっちゃってるなぁと反省しました。自分でできることも先回りして手をだしてしまうことも多く、やってもらって当たり前になってることたくさんあります。それは息子のことを思ってのつもりでしたけど、経験できる機会をなくし、失敗して成長できる機会も無くしてしまっていたんだと気づきました。やってみないと気付けないことたくさんありますもんね。自分でやっちゃったほうが早いと思ってしまいがちですが、本当の意味で息子のためになっているのかをよく考え、できることは自分でやろうのスタンスでいきたいなと思いました。⚫︎自立とは、なんでも自分でできることではない。自分ができないことをちゃんと理解して、誰かに「助けて」って言えること。ちょっと手を貸してくれへんかって言えて、そこをきっかけにまた成長できる。→この言葉、小さい頃に知りたかった言葉だなと思いました。私は、小さい頃から親に、人に迷惑はかけてはいけないと言われ育ちました。だから、親にも迷惑かけてはいけないと思ってましたし、人に助けてもらったりしたら、まずごめんなさいって思ってしまうのが染み込んでいました。だから、大人になり、子育てをしていても、子どもが体調不良のとき、すごく困ってしまうんです。子どものそばにはいたい。けど、仕事休んだら職場に迷惑がかかる。親にみてほしいと頼みたいけど、親にも迷惑かかる。どうしたらいいんだって‥。この悩みにもう何年取り憑かれているだろうって思います。一度染み付いてしまった、人に頼れない、この性格なのか習慣なのか、考え方は、なかなか変えられませんね。だからこそ、私は、息子達には、助けてをちゃんと言える人になってほしいなって思います。どこかの本で、人に頼っていいんです。あの人のためならいいよって、思ってもらえる人になればいいんですって言葉を知り、ちょっと泣きそうになったのを思い出しました。もしものとき、いつもよくしてもらってるあの人の頼みなら助けてやろうかって思ってもらえるには、日頃の行動の積み重ねでしかないんだと知りました。完璧に全部1人でこなそうじゃなくていいよ、もしも困っている人がいたら助ける、もしものときには助けてもらう、そんな関係ができる人になってほしいなって、そんな話も息子たちとしてみたいなと思いました。⚫︎レジリエンスとは、つらい出来事があったとしても、しなやかに対応して生き延びる力のこと。レジリエンスは生まれつき持っているものではなく、後からでも鍛えることができる。レジリエンスの鍛え方は、感謝すること。人を変えることは難しいから、自分がどうするか?どう変わるか。→この考え方は、生きていく上で忘れたくないなと思いました。レジリエンスについては、ほんとにたくさんこの本には書かれていて、ぜひ全部読んでほしいなと思う言葉ばかりでした。うまくいかないとき、相手のせいにするのではなく、どう自分を変えていけるか。毎日保育園行きたくないの息子と向き合うことが、私の毎朝の課題になっているのですが、HSCだしと思ってしまっている私に問題あるのではとまず思いました。だから心配と、信頼しきれてない私がいるからだなと。まずは心から信頼すること。そして、息子にも苦手なときは「助けて」をいえるようお話をする。息子の苦手もわかってもらえるよう、保育園の先生とも話をする。まだまだ私のやれることあるなって、思えました。⚫︎早寝早起き朝ごはん。親がしてあげれることは、どれだけ良い習慣をつけてあげれるか。眠っている時間帯が重要。夜8時から朝6時に寝ることで、セロトニンをきちんと取り込め、確実に脳が育つ。こころが壊れない。と、書かれていました。→エビデンスもしっかりでている、早寝早起き朝ごはん。わかっているのに、うまくいかない早寝早起き朝ごはん。覚悟決めないと、できませんよね。誘惑も、やらないといけないことも、てんこ盛りな毎日。本当に必要なことに優先順位をつけないと早寝早起きは難しいですし、朝ごはんも、夜ごはんに比べて、手を抜いちゃいがちです。この本には、わかりやすく必要な理由を書いてくれており、ほんとにちゃんとやらないとなって、気を引き締めました。まずは今日の夜から、早寝やっていこうと思います。すごく長くなってしまいましたが、山中教授は最後に、百の家庭があれば百通りの子育てがあって、まったく問題がなくすべて思い通り、なんて子育てはありえない。お子さんのこともご自身のことも、あんまり追い詰めすぎないでほしいと書いてくださっていました。頑張りたいことに気づかせてくれて、完璧なんかじゃなくていい、力を抜きながらねっていう優しいメッセージで終わるこの本がすごく好きになりました。何かしらの気づきをもらえる本だと思います。おすすめです!山中教授、同級生の小児脳科学者と子育てを語る 講談社+α新書 / 山中伸弥 【新書】
2024.09.12
コメント(0)
-
頭をぶつけた時に気をつけたいこと
息子が小さい時は、ソファから転げ落ちてしまったり、木から落ちたり、勢いよく壁にぶつかったりし、頭をぶつけてしまうことがありました。働いている保育園でも、お友達同士でぶつかってしまったり、転んで頭をぶつけてしまうことも‥。そんなとき、気になるのが、病院へ行くべきなのか?の判断です。どのタイミングまで様子を見ていていいのか‥取り返しのつかないことにならないのか‥色々不安になりますよね💦今回は、頭部打撲による症状や気をつけたいことなど、一つの目安になればと思い、まとめてみたいと思います。調べたり、経験上、一番大事なのは、普段からよく一緒に過ごす方の、「なんかいつもと様子が違う」この感覚だと思います。なんかおかしいなと思うようであれば、医療機関への受診をおすすめします。◎症状 (2歳未満の場合)受傷後に、⚫︎なんとなく意識がおかしい。ぼーっとしている。目が合わない。言っていることが、つじつまが合わない。⚫︎おでこ以外の部分に、こぶができている。→骨折や頭蓋内出血に関連している可能性がある。⚫︎5秒以上の意識消失⚫︎触ってわかる頭蓋骨骨折→よく頭を触ってみて、凹んでいないか、溝がないか⚫︎親から見て、いつも違うと感じる◎症状 (2才以上)⚫︎なんとなく意識がおかしい⚫︎一瞬でも意識消失があった⚫︎嘔吐がある→一度でも嘔吐があれば、CTを考慮⚫︎眼や耳のまわりが黒くなっている。透明な液体が、鼻や耳からでている。→頭蓋底に骨折がある可能性がある。⚫︎強い頭痛がある→CTを考慮他の症状として‥すぐに眠り込んでしまう体をゆすってもおきないけいれんをおこす手足に力が入らない、しびれている目が見えにくい物が二重三重に見える焦点が定まらないなどの症状もみられたら、すぐに受診をしてください。◎受診の目安上記の症状、1つも当てはまらなければ、様子をみていて大丈夫。1つでも当てはまるものがあれば、医療機関への受診を推奨されています。◎受診先脳神経外科がいいと思われます。頭蓋外傷で、十分な情報を得られる検査は、CTしかありません。単純レントゲンでは、情報量が少ない。MRIでは、頭蓋骨骨折を診断しにくく、機械の中で10分以上安静にしないといけないので、10才以下の子は麻酔をかけないと検査できない場合もあるため。◎受診のタイミング⚫︎頭を打った場合最もこわいのは、頭の中で出血をすること。24時間、特に最初の6時間は気をつけてください!何らかの症状が出るとしたら、6時間以内にでることが多いため。まれに、2〜3日後に遅発的に出血をおこすこともある。⚫︎外傷から出血をしている場合落ちついて止血を行い、受診をしてください。顔や頭は血流が豊富なため、ちょっとの傷でも出血が多いことがある。◎頭部打撲後の注意すること⚫︎できるだけ安静にする⚫︎水分(水、お茶)は、普段通りに摂取する。牛乳、炭酸飲料は、吐き気をもよおす場合があるので控える。授乳は特に制限はない。⚫︎食事は消化のよいものを、通常の半分くらいの量を摂取する。⚫︎当日の入浴は控える⚫︎就寝後も、何度か状態を確認する大人がいくら気をつけていても、思いがけずに起きてしまう打撲などの怪我はあると思います。大きな怪我になりませんように。元気でいていただきたいと願っています。
2024.09.10
コメント(0)
-

大ピンチずかん
大人気の「大ピンチずかん」。もう何ヶ月も前から図書館で予約し、やっと順番がまわってきて、やっと読むことができました!もぉ、かわいい!おもしろい!息子たちと、わかるーと何度も何度も言いながら、たくさん笑いました!子どもがしやすい失敗集って感じなんですけど、それを失敗とは捉えず、「大ピンチ」と捉え、それを大ピンチレベルや、なりやすさで表していて、ゲームのようで楽しく、しかも、その一つ一つのピンチが愛おしく思える本当に素敵な本でした。牛乳をこぼしてしまった、ポケットからすながたくさんでてきた、バックのなかですいとうがもれた、など身近なピンチから、最後には、わぁー、なんかいいなぁって、心があたたまるピンチまで‥。こう見ると、子どもたちってこんなにもピンチに囲まれているんだなって思ったんです。大人にとっては、ささいなことも、子どもにとっては、大ピンチ。やってしまったあと、大人へ伝えて、またそんなことしてーと言われるとこまでがセット。。こういうピンチを繰り返し、乗り越えて、かわし方を覚えて、大きくなっていく。がんばって大きくなるんだよ。それを失敗ととらえず、大ピンチレベル50だーとか自分で思いながら、ユーモアも忘れず、乗り越えていくんだよという、著者の方の優しさが、詰まっているように思いました。大人の私も。大ピンチレベル30。まだいける。と、自分の中で背中をおす考え方を知れた気がしました。大人も子どもも、楽しい。笑えて、あたたかい気持ちにもなれる。寝る前に読む「大ピンチずかん」は、私たちに明日もがんばるパワーをくれます。おすすめです!大ピンチずかん/鈴木のりたけ【1000円以上送料無料】
2024.09.08
コメント(0)
-
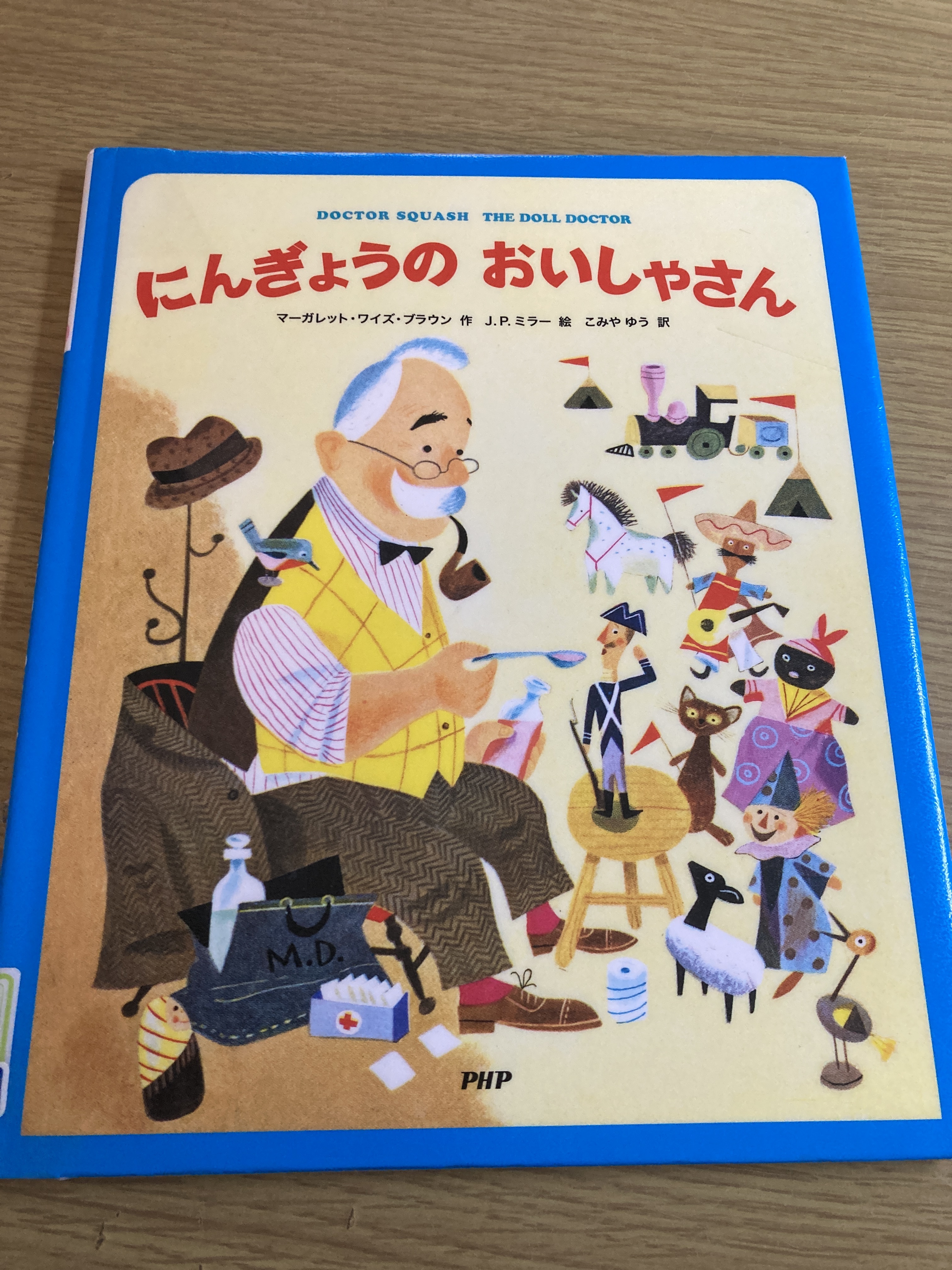
にんぎょうのおいしゃさん
「にんぎょうのおいしゃさん」心がぽっと、あたたかくなる話でした。物語は、トイストーリーのような、おもちゃの中の世界。調子が悪くなってしまったおもちゃたちは、にんぎょうのおいしゃさん、ひげせんせいを呼びます。ひげせんせいは、つらかったね。だいじょうぶだよ。すぐにつくからね。と、みんなの不安がなくなるよう言葉をかけ、適切な処置をして、手を握り、心も体もなおしてくれます。ところが最後、ひげせんせいも体調を崩してしまいます。そのとき、今まで治してもらったおもちゃたちがみんな、ひげせんせいにもらった優しさを返そうとします。みんなからの優しさで、ひげせんせいは‥看護師をしていますが、この気持ち忘れちゃいけないなと強く思わせてもらえる本でした。つらい気持ち。心細い気持ち。そばに誰かいてほしい気持ち。医学的な治療はもちろん大事だけど、それと同じだけ、寄り添う気持ちは大切にしたいなと改めて思いました。そして、優しさは返ってくるんだなと。。すごくあたたかいメッセージがこめられているお話でした。この絵本は、こみやゆうさんがえらぶおひざにおいでシリーズの第2弾。こみやさんは、『絵本を子どもと楽しむということは、その子の心に「よろこびの種」を蒔くということです。種は、いずれ木となり、実をむすびます。その子が大きくなった時、心にたくさんの実があれば、時に他人にわけ与え、時に自らを励ますことができるでしょう。きょうもあなたのおひざの上で、ひとつでも多くの「よろこびの種」が蒔かれますように。』と、書いておられました。素敵な言葉だなと思いました。いつか、この時間が、出会った言葉たちが、息子たちを励ますことに繋がるなら、、こんなうれしいことはないなと思いました。今しかない子どもたちとの絵本タイム。楽しんでいきたいですね😊寝る前に読むと、ぽわんとあたたかい気持ちで眠りにつける、そんな優しいお話でした。おすすめです!
2024.09.07
コメント(0)
-

HSPの本③ 「子どもの敏感さに困ったら読む本」(2)
先日、「子どもの敏感さに困ったら読む本」について書いたのですが、そこではあまり触れなかった親子関係について、もう少し残していけたらなと思います。児童精神科医の著者の長沼さんは、敏感な人たちが社会に適応していくことはハードルの高いことだと言います。過敏性の問題もあるし、とても疲れやすい。普通のようにはできないなど、色々問題を抱えます。その人たちを助けるには、「子どもを信じること。自己肯定感をもてるように関わること。過保護、過干渉にならないこと。親が抱えている心のわだかまりがあるなら、癒してあげること」を、あげておられました。親がHSPであるか、そうでないかによって、子どもへの影響も異なることも書いてありました。親がHSPでない場合、子どもの抱えるしんどさに気づいてあげれないため、子どもはわかってもらえないと思ってしまったり、親も理解できないために、普通を押し付けてしまう。親がHSPである場合、子どものことを心配しすぎて、過保護、過干渉になってしまうことがあり、親が一生懸命になればなるほど、かえって子どもが自力で生きようとする力が出せなくなると、ありました。私の場合は、ですが、両方理解できてしまいました。私はHSPだと思います。私の親はHSPではないと思うので、小さい頃から、親にわかってもらえないと思うことが多く、否定されてきた感も残っていますし、親の顔色ばかり見て、親の意向に合わせ、自分の感情を抑えて生きてきたなと、思っています。だからこそ、その生きづらさがわかるぶん、その反動かのように、HSCである子どもに対し、気持ちはよくわかるからと応えてあげたくなるし、私自身の境界線が弱いぶん、子どもたちの不安やストレスがどんどん入ってきてしまい、一種の共依存のような状態になり、過保護、過干渉になりつつあるなと、思いました。けど、いまのままではダメなんだとこの本を読んで気付かされました。子どもの問題なようで、親である私の抱えてるものが解決してないから、子どもへも影響がでているんだと知り、そこからは自分を見つめ直す時間になりました。今でもなお、親には本音は話せないですし、甘えれない自分がいます。親には感謝していますし、親孝行だってしたい、許したい気持ちもちゃんとあるのに、目の前にたつと、今でもまともに目を見れない自分、甘えることのできない自分に、ずっと負い目を感じていました。そんなことは、今の息子たちの問題とは関係ないと思っていましたけど、分かってもらえなかった→受け止めてあげたい甘えれなかった→甘えさせてあげたいと、反発なのか、過保護、過干渉まっしぐらになっていました。著者の方は、「子どもの弱さを受け入れるということは、自分の弱さを受け入れなければいけません。わだかまりがあるうちは、許そうと思っても許せない。憎いという気持ちを認めましょう。憎いという自分を責めなくていい。許さなくていい。そのままでいい。そういうものなんだと受け入れるだけでいい。それはもう終わったこと、もういいじゃないかという方向に気持ちをシフトしていけるとかなり楽になる。これまでよくがんばってきたんだから、少し休んでもいいんじゃないかな」と、言われており、少し気持ちが軽くなりました。ずっと、親を否定しない自分にならないとと縛っていたことにも気づきましたし、一旦全てをそのままでいいと思うことで、子どもへの見方も変わりました。過保護に、失敗しないように、人に嫌われないように、こうしたらいいんじゃないかとアドバイスのつもりでしていたことも、度を超えると、こうしないとダメに縛られ、自分で臨機応変に行動できない人、私みたいに顔色ばかり見て自分で考えれない人になると気づきました。まずは、気持ちを抑えないで、自分の意思をだせるようにし、「それでいいよ」って言っていきたいと思います。本には、「良い悪いのジャッジを手放す。いかに、それでいいんだと思えるかがカギになる」とも、書かれており、その考え方を軸に、子どもに関わっていきたいと思いました。そして、下の子の保育園問題。毎朝、行きたくないという息子に対し、応えてあげたい、守ってあげたい気持ちと、行って強くなってほしい気持ちとで、毎日葛藤しています。どこにも吐き出せる場がなければ、自分の中で溜め込んでしまうので、嫌だ行きたくないと言えることは大事なことだとは本を読んでわかったのですが、そこからどう向き合うべきかがわからず、悩んでいました。本には、「親の心配は子どもにも伝わる。親が一生懸命になるほど、子どもが自力で生きようとする力を出せなくなる。少し距離をおいたほうが、子どものためにだということもある。過保護、過干渉で育つと、どうしても社会的スキルが弱く、世の中を渡りあえず、引っ込み思案な性格になる。過剰に心配しすぎて、世話を焼きすぎない。何かあったら、いつでも支えるからという姿勢で、適度な、つかず離れずの関係になるとベスト」と、ありました。ずっと探していた答えの糸口を見つけれたような気持ちになれた言葉でした。無理やり連れていくことは、わかってもらえなかったという私と同じ気持ちを抱かせてしまうんじゃないかというのが根底にあり、ずっと一緒になって不安がっていましたけど、私が今やってみることは、子どもを信じて、保育園の先生たちを信じて、大丈夫だから行っておいでと笑顔で送り出すこと。乗り越えれる力があることを信じ、伝え、乗り越えれたときは一緒に喜び、たくさん褒める。先生たちには、苦手に思ってることは伝え、共有し、味方を増やす。そういう形での支え方もあるんだと思えました。全部1人で、守ってあげようではなく、「適度な、つかず離れず」。これからの私の目標になりました。親子関係。親である私と息子。それだけの問題ではなく、私の親との関係まで影響するとは‥育ってきた環境って、大きいですね。このまま、自分の過保護や過干渉に気づかずいたら、息子だけではなく、もしかしたら孫にまで影響していたかもと思うと、今一度、この本に出会え、立ち止まって考えれたことに、ほんとに良かったなと思えます。きっと、まだまだ直すべき点はあるだろし、気をつけていないと同じことをしちゃいそうですけど、知らないでいたときより、何かいい方向にいけそうな気持ちになれたことがうれしいなと思います。もし今、子どもさんの敏感さに困っているなと思われる方がおられましたら、きっと何かいいきっかけを見つけることができる本だと思います。おすすめです!子どもの敏感さに困ったら読む本 児童精神科医が教えるHSCとの関わり方 [ 長沼 睦雄 ]
2024.09.06
コメント(0)
-

「かんぺきなこども」
「かんぺきなこども」奥が深い、考えさせられるお話でした。お話の内容は、こどもがほしいマカロン夫婦は、こどもストアという望んでいるこどもに出会えるお店にいくところからはじまります。そして、完璧なこどもを希望し、ピエールくんと家族になります。おかしは虫歯になるから食べない。ごはんも残さず、こぼさず食べます。勉強もできるし、わがままも言わない。だけど、親であるマカロンさんたちは‥?そして、マカロンさんの間違いで、完璧なはずだったピエールくんは人前で大恥をかいてしまったことをきっかけに完璧をやめてしまいます。完璧でなくなったピエールくんは修理にだされようとしますが‥。。。客観的に見ると、こどもが完璧なんてこわいって思っちゃうんですが、日常をみると、たくさんごはんこぼして‥字はもっと丁寧に書いたら?保育園も笑顔で毎日楽しいって行ってくれたらいいのに‥など、たくさんの理想を子どもに押し付けてしまっている自分に気がつきました。どれもこれも、私の理想であって、子どもは、こぼそうと思ってこぼしてはないし、おいしく食べたいだけ。字も綺麗に書きたいなんて思ってないし、覚えるだけで精一杯だよ。保育園だって十分がんばって行ってるよ。‥きっとそんなふうに思ってるんだろなと、この本を読み、ごめんねってすごく反省しました。じゃあ、大人である私は完璧なのか?全然そんなことはなく、失敗もたくさんするし、苦手なことだってたくさんある。なのに、子どもには、できないことに口をだし、何様なんだろなって、恥ずかしくなりました。最後の裏表紙の絵は、ぐっときます。誰も完璧な人なんていないんですよね。完璧なんかじゃなくてもいいよって言っていきたい。完璧だから好きなわけではないし、完璧じゃなくても笑って一緒にいられるのが家族だよねって、思いあえる家族でありたいなと思いました。家族を見つめ直すきっかけをくれる絵本です。おすすめです!かんぺきなこども (ポプラせかいの絵本 62) [ ミカエル・エスコフィエ ]
2024.09.06
コメント(0)
-

子どもの敏感さに困ったら読む本
みなさん、夏休み、おつかれさまでした。やっと終わりましたねー。始まった2学期。子どもたちにとっても、環境が変わり、気持ちが不安定になりやすい時期かなと思います。うちの息子たちも、それぞれ新しい悩みや不安を抱えながらのスタートとなりました。以前から息子たちの悩みや繊細さが気になり、いくつか本を読み、HSPではないのかなと思うようになってきました。息子たちがぶつかってしまった壁の打破の仕方の糸口がほしくて、色々と本を読み、今回読んだこの「子どもの繊細さに困ったら読む本」は、ドンピシャに悩んでいたことに寄り添い、答えをもらえる本でした!まとめたいと思っても、全部にマーカーをつけたくなってしまうくらい、あぁこういうことが知りたかったんだ、これは覚えておこうと思うことばかりの、ギュギュっと欲しかった言葉が詰まった本でしたので、ほんの一部になってしまうんですが、本の言葉をお借りし、うちの家族はどう生活に落とし込んでいきたいかもふまえて書いていけたらなと思います。⚫︎HSPとは?5人に1人はいると言われている敏感すぎる気質をもった人のこと。HSPの子ども版のことをHSCと呼ぶそうです。HSP.HSCは、病名ではないそうで、医学的な根拠としては認められていない、あくまでも心理学的な、ひとつの見方すぎないという位置づけにあるそうです。なので、精神科や神経科、心療内科にいっても、HSPと診断されることはまずないそうです。この敏感さは、病気でもないし、障害でもない。単に生まれ持った気質。足が早い人もいれば、手先の器用な人もいるように、とても敏感な気質をもった人たちがいるだけという考え方。⚫︎HSCの特徴繊細で、気遣いができ、他者への共感力が強いうれしい、楽しい、悲しい、怖いなど、人より強く感じる。あとにも残りやすい些細な変化、刺激に気づきやすい人に合わせすぎる人との境界が薄い痛みに敏感人が怒られていたら自分も‥と思ってしまうマイナス感情を溜め込みやすいなど、他にも特徴はたくさんあるので、興味がある方は調べてみてください。⚫︎子どもがHSCかもと思ったとき、親としてどうあればいいのか?「5分の1の確率の気質の持ち主なのだから、他と違う親になる覚悟が必要。子どもがうまく対処できないとき、他の子や親と比較はしない。普通と違うことを怖れない。」→この本で一番響いた言葉です。どこかで、子どもに対し普通でいてほしいと思ってしまっていた自分に、普通の親でいたい自分がいたことに気づきました。けど普通ってなんだろうと考えるきっかけになりましたし、他の親と違う親になる覚悟って言葉に、私が足りなかったとこはこれだなって思いました。勉強をして、もっとHSPについて知って、息子たちのことを知りたいと思える言葉でした。⚫︎「生育環境において、その気質がどう受け止められてきたかで、その後の生きやすさ、生きにくさは大きく変わります。だからこそ、子どもの敏感さに目を向けることが大事」「普通の感覚の人にとっては何でもないようなことも、大きな刺激や動揺のもとになり、疲れやすく、傷つきやすく、ストレスを感じやすい。それだけに、自分のことを理解してくれる人や安心できる場所を非常に強く求めている」「敏感体質であっても、理解され、愛され、肯定され、穏やかな環境で育つと、ストレスは抑えられ、自律神経のバランスも保たれ、病的な症状が引き起こされにくくなる」→この本には、敏感さを受け止めてもらえず成長し、つらい思いをした人たちの体験談もたくさんのっていました。HSPの方は、相手の求めていることを感じとりやすいため、それに応えたいとがんばってしまう方が多いように思いました。しかしがんばりすぎてしまうと、、自律神経失調症、パニック障害、うつ、慢性疲労性症候群など、さまざまなストレス由来の病気にかかりやすくなるとのことでした。周りがどう受け止め、支えれるか、環境次第で変われるというのなら、私ができることはこれなんだなと思いました。息子の場合は、保育園に行きたくないと強く言います。理由もいくつかはあげますが、きっと言葉ではいいきれてはいない何かがあるんだと思います。ずっと前のことでも心に引っかかっていたりもしますし、直接怒られたわけではないのに、お友達が注意されたことに対し一緒につらくなる、大勢が苦手、夕方になるとお部屋が変わるなどの環境の変化にも弱かったり、色々あるのだと思います。今回この本を読んで、ちゃんと先生と話をしないといけないなと思い、息子の訴えていること、家での言動、最近困っていること、息子の特徴みたいなことをお伝えしました。先生は受け止めてくださり、保育園での関わりも、みんながこうだから一緒にとはせず、したくないなら今はいいよなど、気持ちに寄り添いながら関わってくださるようになりました。まだ行きたくないは続いてはいますが、家族だけではない味方が増えたことは、息子にとっても私にとっても、嬉しく、心強くなりました。みんなと同じようにをまず目指そうと思うと、子どもを変えようとがんばってしまいますが、そうではなく、周りの理解を深め、こうしてみてもいいかもと良い知恵をお借りしながら、私も息子も成長していけたなら、そういう道もいいかもしれないと今回思えました。長い人生。壁にぶつかりながら生きていくのはHSPの人だけではないように思います。ぶつかったときどう対処していくのか。それを一つ一つ学ぶ良い機会だと思い、いつかの何かの役に立つと思いながら、転んだ時の立ち上がり方法を、今息子と学び中です。⚫︎「敏感すぎる子は、普通に生活しているだけで、刺激に圧倒され、気をつかいすぎて疲れる。さらにたくさんの刺激を浴びさせるよりも、ひとりで静かに過ごす時間、心身を休ませる時間の確保するほうが大切」→平日がんばる息子に、がんばったからと休日は楽しみを作りたいと出かけがちになってしまってました。しかし、私が思っている以上に刺激過多になっていたんだろなと反省しました。大事なのは、心身ともに休めること。ほっとできる時間をちゃんと作ること。足りなかったところだなと思うので、平日の夕方からの時間の使い方も、休日の過ごし方も、まだまだ見直しが必要だなと思いました。⚫︎「困っているお母さんに本当に必要なのは、診断名をつけてもらうよりも、親身になって話せる相手を見つけること」→私は診断名がほしいわけではなかったのですが、HSPかもしれないと思い、調べ、当てはまることが多いことに、あぁこれだったからかと腑に落ち、少し安堵したんです。糸口が見えた気がして。なぜかわからないこの特徴とどう向き合っていけばいいのかわからない時より、本を読み、HSPを知り、みんながしてこれはよかったよを試していく、できることがあることに、スタート位置に立てたような気持ちになりました。そして、友達にHSPの話をしたところ、実はHSPに詳しくとても親身になって話をきいてもらい、本も貸してもらえることにもなりました。人に話をするのはどう思われるのかすごく身構えてしまいがちでしたが、親は親で重たいものを抱えがちになるので、どこか発散する場は絶対に必要だなと思いました。私はありがたいことに受け止めてくれる場がありましたけど、なかなかそんな場所ないですよね‥。そういう話できる場、あったらいいですよね。探してみようと思います。⚫︎「敏感さにたいして、誇りを持てるようにする。自己肯定感を持てるようにする。彼らの優しさは、共感性は、人を癒します。繊細で傷つきやすいけれど、だからこそそれが強みにできるのだということを伝えてあげる役目を、周囲にいる大人は担っている」→うまくできないところばかりに目がいきがちでしたけど、良いところいっぱいありますよね。良いところを伸ばす。生きやすい環境を作る。自分のことを好きでいられる。私の目指すべきものはこれだなと思えました。まだまだHSP、HSCについては、勉強段階です。わからないことだらけですが、手探りでも一個でも何かを見つけ、息子の笑顔に繋がるよう行動していきたいなと、この本を読んで思いました。もしかしてと思われる方がおられましたら、ぜひ読んでみてください。おすすめです!子どもの敏感さに困ったら読む本 児童精神科医が教えるHSCとの関わり方 [ 長沼 睦雄 ]
2024.09.05
コメント(0)
全23件 (23件中 1-23件目)
1









