テーマ: どんなテレビを見ました?(78146)
カテゴリ: 鬼滅の刃と日本の歴史。
NHK「歴史探偵」西遊記の回を見ました。
玄奘三蔵の地誌「大唐西域記」が、
ファンタジー小説の「西遊記」へと変貌した謎について。
あとで調べたことも含めて内容をメモしておきます。
◇
玄奘は身長180㎝もある大男だったそうです。
砂漠や山脈を超えて往復3万キロを踏破するくらいだから、
たんなる知識人じゃなくて、
冒険家・アスリート的な人でもあったんでしょうね。
京都の臨済宗興聖寺には、
世界最古の「大唐西域記」の写本があるそうです。
◇
番組を見た後にネットで確認したら、
Wikipediaに 「西遊記の成立史」 という詳細な記事がありました。
簡単にいうと、
宋の時代に生まれた都市講談が、
『大唐三蔵取経詩話』という形で刊行され、
それを原型として元の時代に雑劇などが発展し、
さらに明の時代になって、
全100回からなる小説が完成したとのこと。
これは「世徳堂本」と呼ばれるもので、
最初は南京で刊行されましたが、
現存するものは福建省南平市建陽で刊行され、
すべて日本で保管されてきたのだそうです。
番組でも、福建省南平市を取材していましたが、
ここは千年前から木版印刷が盛んだったらしい。

◇
孫悟空のルーツも、やはり福建省にあります。
ここには、もともと猿を神として祭る風習があって、
それは畑を食い荒らす猿への餌付けに由来するそうです。
Wikipediaによると、
江西省と広東省にまたがる山中には、
旅する婦人をさらう「斉天大聖」という妖猿の伝説があり、
2005年には、福建省順昌県の宝山で、
元末~明初期の頃の「斉天大聖」の墓が発見されたとのこと。
番組でも、この墓を取材していました。
さらに、
敦煌の壁画には「馬を曳く猿を連れた唐僧の像」もあり、
遼の墳墓の彫刻には「雲に乗る猴行者の像」もあるらしい。
※猴行者 こうぎょうじゃ とは、宋の時代の孫悟空の呼び名です。
◇
猪八戒のルーツは、
摩利支天の御者(御車将軍)のブタです。
これが日本ではイノシシと誤読されたため、
鎌倉時代からは摩利支天が軍神として崇められ、
上野アメ横の徳大寺にもそれが祀られています。
沙悟浄のルーツは古く、
もともとは砂漠に倒れた玄奘を水場に導いた「大神」でしたが、
これがやがて「深沙神」と呼ばれ、
元の時代には「沙和尚」と呼ばれ、
明の時代には水怪の「沙悟浄」に変わり、
それとともに弟子としての地位もどんどん下がったあげく、
日本では滝沢馬琴の翻案でカッパになってしまった。
またもや馬琴ネタ!
牛魔王のルーツは、チベット仏教の伝説の妖牛だそうです。





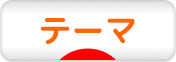
玄奘三蔵の地誌「大唐西域記」が、
ファンタジー小説の「西遊記」へと変貌した謎について。
あとで調べたことも含めて内容をメモしておきます。
◇
玄奘は身長180㎝もある大男だったそうです。
砂漠や山脈を超えて往復3万キロを踏破するくらいだから、
たんなる知識人じゃなくて、
冒険家・アスリート的な人でもあったんでしょうね。
京都の臨済宗興聖寺には、
世界最古の「大唐西域記」の写本があるそうです。
◇
番組を見た後にネットで確認したら、
Wikipediaに 「西遊記の成立史」 という詳細な記事がありました。
簡単にいうと、
宋の時代に生まれた都市講談が、
『大唐三蔵取経詩話』という形で刊行され、
それを原型として元の時代に雑劇などが発展し、
さらに明の時代になって、
全100回からなる小説が完成したとのこと。
これは「世徳堂本」と呼ばれるもので、
最初は南京で刊行されましたが、
現存するものは福建省南平市建陽で刊行され、
すべて日本で保管されてきたのだそうです。
番組でも、福建省南平市を取材していましたが、
ここは千年前から木版印刷が盛んだったらしい。

◇
孫悟空のルーツも、やはり福建省にあります。
ここには、もともと猿を神として祭る風習があって、
それは畑を食い荒らす猿への餌付けに由来するそうです。
Wikipediaによると、
江西省と広東省にまたがる山中には、
旅する婦人をさらう「斉天大聖」という妖猿の伝説があり、
2005年には、福建省順昌県の宝山で、
元末~明初期の頃の「斉天大聖」の墓が発見されたとのこと。
番組でも、この墓を取材していました。
さらに、
敦煌の壁画には「馬を曳く猿を連れた唐僧の像」もあり、
遼の墳墓の彫刻には「雲に乗る猴行者の像」もあるらしい。
※猴行者 こうぎょうじゃ とは、宋の時代の孫悟空の呼び名です。
◇
猪八戒のルーツは、
摩利支天の御者(御車将軍)のブタです。
これが日本ではイノシシと誤読されたため、
鎌倉時代からは摩利支天が軍神として崇められ、
上野アメ横の徳大寺にもそれが祀られています。
沙悟浄のルーツは古く、
もともとは砂漠に倒れた玄奘を水場に導いた「大神」でしたが、
これがやがて「深沙神」と呼ばれ、
元の時代には「沙和尚」と呼ばれ、
明の時代には水怪の「沙悟浄」に変わり、
それとともに弟子としての地位もどんどん下がったあげく、
日本では滝沢馬琴の翻案でカッパになってしまった。
またもや馬琴ネタ!
牛魔王のルーツは、チベット仏教の伝説の妖牛だそうです。




お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2023.05.26 09:42:47
[鬼滅の刃と日本の歴史。] カテゴリの最新記事
-
NHK「地球ドラマチック」ネアンデルタール… 2024.06.15
-
NHK「歴史探偵」武士の起源は東北の蝦夷だ… 2024.06.15
-
NHK「古代史ミステリー」東日本の前方後円… 2024.05.14
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
キーワードサーチ
▼キーワード検索
カテゴリ
政治
(209)ドラマレビュー!
(221)NHKよるドラ&ドラマ10
(30)NHK大河ドラマ
(24)NHK朝ドラ
(19)プレバト俳句を添削ごと査定?!
(187)メディアトピック
(37)音楽・映画・アート
(72)漫画・アニメ
(19)鬼滅の刃と日本の歴史。
(26)岸辺露伴と小泉八雲。
(20)アストリッドとラファエルの背景を考察。
(8)アンという名の少女の感想・あらすじネタバレ。
(31)東宝シンデレラ
(63)恋つづ~ボス恋~カムカム!
(48)ぎぼむす~ちむどん~パリピ孔明!
(38)わたどう~ウチカレ~らんまん!
(63)汝の名~三千円~舞いあがれ!
(16)トリリオン~ONE DAY!
(16)Dr.チョコレート~ゆりあ先生!
(15)警視庁・捜査一課長 真相ネタバレ!
(32)「エルピス」の考察と分析。
(10)「Destiny」&「最愛」ネタバレ考察。
(20)大豆田とわ子を分析・考察!
(10)大森美香の脚本作品。
(12)北斎と葛飾応為の画風。
(13)不機嫌なジーン
(13)風のハルカ
(28)純情きらりとエール
(30)宮崎あおいちゃん
(18)スポーツも見てる!
(29)逃げ恥~けもなれ!
(24)スカーレット!
(13)シロクロ!
(13)ギルティ!
(9)家政夫ナギサさん
(6)半沢直樹!
(4)探偵ドラマ!
(12)倉光泰子
(4)パワハラ
(7)ドミトリー
(37)ゴミ税
(3)その他。
(1)夢日記
(4)© Rakuten Group, Inc.









