テーマ: 暮らしを楽しむ(384707)
カテゴリ: 考古学・日本古代史

9月22日月曜日。私は自転車に乗ってある所へ向かった。それは長年探していた古墳。前日地底の森ミュージアムを案内してくれたのは、ここでボランティアをしてる我が町内会のK副会長。その彼が古墳が載った地図を見せてくれたのだ。ずっと見つからずにいた幻の古墳に、今日こそ会える。そう思うと、私の胸は知らず知らずに高鳴った。
捜し続けていた古墳の名は「王ノ壇古墳」。四角い形をした方墳らしい。かつては周濠(墓を取り囲む堀)もあったようだ。この古墳の名が、やがてこの地区の名前である「大野田」に変化したとも聞く。この周辺にはかつてかなりの古墳があった。だが埋蔵文化財調査の後はことごとく埋め戻され、その上にビルや住宅が建っている。ここは20年以上も発掘調査を続け、たった一つだけ残されたのが地区の名の元となった方墳なのだ。

それらしい場所をグルグル廻っているうちに、あるマンションで見つけたのがこれ。「王ノ壇古墳」がこの周辺にあるのは確か。だが幾ら捜してもそれらしいものはない。古くから住んでそうなお宅を訪ねたが、住人の小母さんは知らないと言う。虚しく戻る途中、2人の自転車に乗った高校生に出会った。「ダメ元」で彼女達に古墳の場所を尋ねた。すると意外や意外。そのうちの1人が知っていて、私を案内してくれたのだ。やったー!!

それがこの場所。何だ何だ~っ?これが古墳だって?ここはさっき私が通り過ぎた場所。てっきり何かの工事現場だと思ったのだ。残土をブルドーザーでかき集めたような小山。どうしてもこれが古墳とは思えない。高校生にお礼を言って、私はその「現場」に近づいてみた。看板があった。どうやら王ノ壇古墳に関する案内のようだ。とすると、この場所が古墳であることは間違いないが、なぜこんなことになったのかが謎。

これが古墳の在りし日の姿。私が捜し求めていた古墳はこんな姿だったのだ。それが開発ですっかり形を変えた。古墳の東側は新しく出来た道路に削られ、元の姿を失った。発掘調査後に周囲を再整備するため、一旦古墳を破壊したのだと思う。

こちらは発掘調査時のもの。私も何年か前、この付近での現地説明会に出たことがあった。ここは東北地方でも珍しい古墳群があった場所。それを開発の名の元にことごとく破壊した。埋蔵文化財調査なんて、言って見れば行政側の言い訳みたいなもの。私達の遠い祖先達が眠る古墳。当時の文化や歴史を伝える重要な手掛かりが、全ては闇に葬られてしまったのだから。
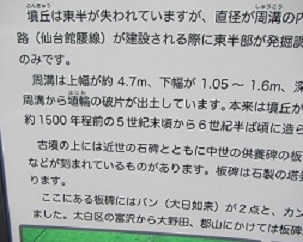
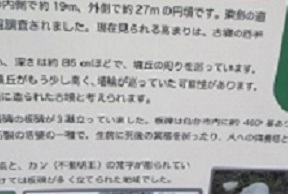
横長の説明板を撮ったが、くっつけても読めるかどうか。この古墳がこの地の名前の興りになったことなどが記されていた。その貴重な古墳が何と無残な姿だろう。恐らくは元の状態に復元するはずだが、それはもう古墳ではなく、ただの土山ではないのか。

こちらは古墳の頂上に建てられていた板碑(いたび)。恐らくは鎌倉時代の仏教遺跡だと思う。頭部に刻まれた梵字は古代インドのサンスクリット語。現在は会話では使われず、文字としてしか用いられていない。本来は薄い石に刻むのだが、これらは笊川(ざるがわ)の河原石みたい。


私は虚しい気分で再びペダルを漕いだ。帰る途中に小さな神社があった。名前は春日神社。ここにも説明板。元の神社は西北の方向150m離れた場所にあった。それが土地整備のために移転したのだ。埋蔵文化財調査を行った結果、地下に古墳があった。そこから見つかったのが右側の「隼人の革盾」(はやとのかわだて)だ。
これは宮中を警備する時に用いるもの。当時この地方を支配していた権力者はかなり大和朝廷とも親しい関係があったのか、親睦の証としてこの盾が朝廷から贈られた。盾はその後土の中で腐ったが、色と紋様が土に付着して残った。復元写真は前日博物館でKさんが見せてくれたもの。私もこの話は聞いたことがある。
隼人の革盾が発見されたのは東北地方ではここだけで、全国でも数か所しかない由。その貴重な古墳すら壊される文化行政とは一体何なのだろう。この地区は多賀城以前に国府があったとされる郡山遺跡(仙台市太白区郡山)に近く、そこに勤務した官人の住居だった由。古代東北文化の最先端の地が跡形もなく壊され、近代的な街に変貌してしまう理不尽さ。

10月12日日曜日。私はランニングの途中にここを通った。あれから19日。周囲の様子がすっかり変わり、荒々しい工事現場が公園風に治まっていた。台風が去った14日、私は再度デジカメ持参で訪れた。小山は整えられ、古墳らしく変身していた。多分これから芝生を張ったりするのだろう。


立ち入り禁止の柵を越えて中に入ると、片隅に石が転がっていた。そのうちの幾つかは、前回の写真に載っていた石。左側はその細部だ。消えかかっているが、微かに梵字が読める。右側は江戸時代の天保年間に建てられた雷神石のようだ。この地区にたった一つだけ残った古墳。周囲の様子がかつての風景とはすっかり変わってしまったが、やがて小山の頂上には石碑が戻されるはず。
さて、私の近所には長年の開発で姿を消した古墳が数多くある。そのうちの一つをかつて東京国立博物館で見たことがある。何と、石棺は雨ざらしになっていた。1500年後にまさかそんな扱いをされるとは、古代の勇者も考えてなかったはずだ。嗚呼。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事
-
いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)
-
小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.









