カテゴリ: 考古学・日本古代史
<歴史と思い出>

まだ小学生のころ、仙山線の線路脇の土手で白い貝の層を見つけた。それは私が初めて見た「貝塚」で、歴史に関心を持つきっかけになったようだ。東京に転勤して千葉の幕張に住んだことがあり、千葉市内で加曾利貝塚を見た。日本有数の貝塚はとても巨大で立派だった。宮城県内では大木囲貝塚などを見た。いずれも縄文時代を代表する貝塚だ。
五色塚古墳
高校生の時、近所の畑できれいな石を拾った。近くには東北地方で第3位の大きさを持つ前方後円墳の遠見塚古墳があった。土器の破片らしいものもたくさん落ちていた。拾った石は滑石製の「紡錘車」だったと思う。恐らくあれが考古学に興味を持つようになったきっかけだろう。
やがて私は転勤族となり、徳島勤務の時は岡山の作山古墳、造山古墳、神戸の五色塚古墳などを見た。いずれも日本を代表する巨大な前方後円墳で、五色塚古墳は築造当時の「葺石」や埴輪まで復元してあった。明石海峡を目の前にした古墳は船で通過する者が、権力のあまりの大きさに驚いたことだろう。そうそう、埼玉のさきたま古墳群では丸墓山古墳(円墳)や稲荷山古墳(前方後円墳)なども見た。
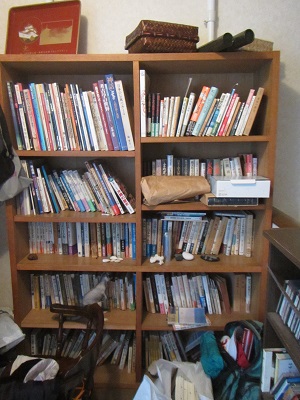 私の本箱の一つ
私の本箱の一つ
30歳を過ぎた頃から、私は「新刊ニュース」で歴史関係の専門書を選ぶようになった。対象は日本古代史や考古学関係だが、やがて神話学、文化人類学、人類学、言語学、宗教学、民俗学などにも広がり、東アジアの歴史にも関心を持つようになった。基礎知識がないため読解するには苦労したが、少しずつ読み進めた。定年後には歴史小説も読み始めた。幕末期のものが多かったが、中国の歴史小説もかなり読んだ。

沖縄勤務時には琉球史関係の本を中心に、沖縄に関する本を300冊ほど読んだ。沖縄の文化や宗教、民俗、地理、生態、文学など様々だ。また詳細な地図を持って県内の城(ぐすく)、御嶽(うたき)、拝所(うがんじゅ)、風葬墓などの聖地を40か所以上訪ねた。そのことで沖縄には原始神道はじめ、現代の日本が失った古い形が残されていることを知った。沖縄については今でも鮮烈な印象が残っている。

たまたま博物館に転勤したことから、アイヌの文化にも関心を持つようになった。「北海道マラソン」参加のついでに、アイヌ人初の国会議員となった萱野茂氏の自宅と博物館を訪ねたことがあった。氏は私が勤務していた博物館のチセ(アイヌの小屋)の祭りに毎年来られていて、顔見知りだった。風邪で臥していたのだが、わざわざ起きて来て色んな教示をいただいた。忘れられない思い出だ。
吉野ヶ里遺跡
沖縄勤務時には九州地区の会議を利用し、佐賀県の吉野ケ里遺跡を訪ねたことがあった。弥生時代を代表する遺跡だが、当時はまだ整備が始まって間もなくのこと。それでも遺跡の広さや「甕棺」などの葬制を目の当たりにして驚愕した。「邪馬台国九州説」の根拠ともなる遺跡だけに、王の絶大な権力を見せつけられた想いがした。別な機会には大宰府跡や宗像大社(福岡県)、宇佐神宮(大分県)なども訪ねた。
 真脇遺跡
真脇遺跡
チカモリ遺跡
石川勤務時には能登半島の真脇遺跡を訪ねた。ここは縄文時代の遺跡で、約5千年に亘ってイルカの追い込み漁をして来た場所。地下には累々たるイルカの死骸が眠っている。イルカの脂を燃やしたランプなどが出土し、住民はアイヌと同様に木の棒を立て、獲物の魂を「送る」儀式をしていた。
金沢市内のチカモリ遺跡では半分に割った栗の巨木を円形に立ててある。ここも縄文時代の遺跡。縄文時代にこんな巨木を切り倒して運搬し、真っ直ぐに立てる技術があったことに驚いた。
 三内丸山遺跡
三内丸山遺跡
これは青森市にある三内丸山遺跡。野球場を造る工事中に発見された日本を代表する縄文時代の遺跡で、常時500人ほどが住む巨大な集落だった。道の両脇にはずらりと墓が並び、広場には巨大な楼閣(櫓)や長さが50mにも及ぶロングハウスなどが建てられていた。楼閣の基礎には版築と呼ばれる工法が用いられている。これは粘土と砂を交互に入れて突き固め、地盤を強化する方法だ。
谷のゴミ捨て場では、貴重な遺物が発掘され、北海道から新潟まで、日本海を通じての物の交流があったことが判明している。また集落の周辺では栗など、数種類の植物が栽培され、縄文時代が単なる採集文化ではなかったことが分かった。
火焔土器
4年前の旅行では、長岡市にある新潟県立博物館で、見事な火焔土器など縄文時代の遺物をたくさん見学した。現物を見ると、本で読むだけでは得られない発見や感性が起きる。この時は縄文人のパワーを感じたものだ。この旅行では越後一宮である弥彦神社へも立ち寄った。
さらには吉備津神社、吉備津彦神社(岡山)、出雲大社(島根)、大麻比古神社(徳島)、伊勢神宮(三重)、熱田神宮(愛知)、石上神社、大神神社、春日大社(奈良)、住吉大社(大阪)、八坂神社、貴船神社(京都)、白山比め(めは口に羊)神社(石川)、出羽三山神社(山形)なども訪ねている。
 遮光器型土偶
遮光器型土偶
これは昨年青森県立郷土館で見た遮光器型土偶。ここには「松韻堂コレクション」と言う、縄文時代の遺物を中心とした優れた展示物があった。青森在住の医師親子が二代に亘って収集した逸品だ。「遮光器」とはエスキモーが使う「雪眼鏡」のこと。目の周囲がこれに似ていることからの命名だ。新潟の火焔土器もそうだが、初めて見て縄文人のパワーと宗教性、感性に驚いたものだ。
大湯環状列石
これは昨年訪れた秋田県鹿角市にある大湯環状列石(ストーンサークル)。縄文時代の巨大なお墓で、この巨大なサークルの中に、小さな円形の石組が幾つかある。また広い遺跡にはもう一つの環状列石や、幾つかの配石遺構があり、「墓」の傍には祭祀のための掘っ立て小屋が数棟建てられている。墓として使用された期間がわずか200年間だったとのことにも驚いた。
 合掌土偶(国宝)
合掌土偶(国宝)
これは今年の6月、八戸市立是川縄文館で見た「合掌土偶」。まるで宇宙人のようだが、縄文人の信仰心が分かる。縄文人の平均寿命はわずか37歳。自らの長寿と子孫の繁栄を真剣に祈る姿なのだ。膝の辺りが壊れ、アスファルトで接着した痕があることからも、大事にされていたことが分かる。土偶のほとんどが人間の代わりに破壊されることが多い。それが後世の「流し雛」に繋がって行くのだろう。
こんな風に、歴史や考古学に対する思いは尽きない。毎年の旅行も、私の趣味に合わせてのことが多いのだ。このシリーズは冒頭から長引いてしまった。いよいよ明日からは残った写真を使って、東北の歴史を訪ねる旅を紹介したいと思う。最後までお付き合いいただけたら嬉しい。<続く>

まだ小学生のころ、仙山線の線路脇の土手で白い貝の層を見つけた。それは私が初めて見た「貝塚」で、歴史に関心を持つきっかけになったようだ。東京に転勤して千葉の幕張に住んだことがあり、千葉市内で加曾利貝塚を見た。日本有数の貝塚はとても巨大で立派だった。宮城県内では大木囲貝塚などを見た。いずれも縄文時代を代表する貝塚だ。
五色塚古墳

高校生の時、近所の畑できれいな石を拾った。近くには東北地方で第3位の大きさを持つ前方後円墳の遠見塚古墳があった。土器の破片らしいものもたくさん落ちていた。拾った石は滑石製の「紡錘車」だったと思う。恐らくあれが考古学に興味を持つようになったきっかけだろう。
やがて私は転勤族となり、徳島勤務の時は岡山の作山古墳、造山古墳、神戸の五色塚古墳などを見た。いずれも日本を代表する巨大な前方後円墳で、五色塚古墳は築造当時の「葺石」や埴輪まで復元してあった。明石海峡を目の前にした古墳は船で通過する者が、権力のあまりの大きさに驚いたことだろう。そうそう、埼玉のさきたま古墳群では丸墓山古墳(円墳)や稲荷山古墳(前方後円墳)なども見た。
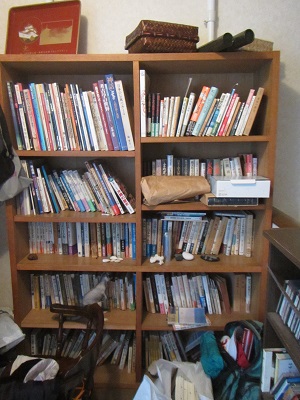 私の本箱の一つ
私の本箱の一つ30歳を過ぎた頃から、私は「新刊ニュース」で歴史関係の専門書を選ぶようになった。対象は日本古代史や考古学関係だが、やがて神話学、文化人類学、人類学、言語学、宗教学、民俗学などにも広がり、東アジアの歴史にも関心を持つようになった。基礎知識がないため読解するには苦労したが、少しずつ読み進めた。定年後には歴史小説も読み始めた。幕末期のものが多かったが、中国の歴史小説もかなり読んだ。

沖縄勤務時には琉球史関係の本を中心に、沖縄に関する本を300冊ほど読んだ。沖縄の文化や宗教、民俗、地理、生態、文学など様々だ。また詳細な地図を持って県内の城(ぐすく)、御嶽(うたき)、拝所(うがんじゅ)、風葬墓などの聖地を40か所以上訪ねた。そのことで沖縄には原始神道はじめ、現代の日本が失った古い形が残されていることを知った。沖縄については今でも鮮烈な印象が残っている。

たまたま博物館に転勤したことから、アイヌの文化にも関心を持つようになった。「北海道マラソン」参加のついでに、アイヌ人初の国会議員となった萱野茂氏の自宅と博物館を訪ねたことがあった。氏は私が勤務していた博物館のチセ(アイヌの小屋)の祭りに毎年来られていて、顔見知りだった。風邪で臥していたのだが、わざわざ起きて来て色んな教示をいただいた。忘れられない思い出だ。
吉野ヶ里遺跡

沖縄勤務時には九州地区の会議を利用し、佐賀県の吉野ケ里遺跡を訪ねたことがあった。弥生時代を代表する遺跡だが、当時はまだ整備が始まって間もなくのこと。それでも遺跡の広さや「甕棺」などの葬制を目の当たりにして驚愕した。「邪馬台国九州説」の根拠ともなる遺跡だけに、王の絶大な権力を見せつけられた想いがした。別な機会には大宰府跡や宗像大社(福岡県)、宇佐神宮(大分県)なども訪ねた。
 真脇遺跡
真脇遺跡チカモリ遺跡

石川勤務時には能登半島の真脇遺跡を訪ねた。ここは縄文時代の遺跡で、約5千年に亘ってイルカの追い込み漁をして来た場所。地下には累々たるイルカの死骸が眠っている。イルカの脂を燃やしたランプなどが出土し、住民はアイヌと同様に木の棒を立て、獲物の魂を「送る」儀式をしていた。
金沢市内のチカモリ遺跡では半分に割った栗の巨木を円形に立ててある。ここも縄文時代の遺跡。縄文時代にこんな巨木を切り倒して運搬し、真っ直ぐに立てる技術があったことに驚いた。
 三内丸山遺跡
三内丸山遺跡これは青森市にある三内丸山遺跡。野球場を造る工事中に発見された日本を代表する縄文時代の遺跡で、常時500人ほどが住む巨大な集落だった。道の両脇にはずらりと墓が並び、広場には巨大な楼閣(櫓)や長さが50mにも及ぶロングハウスなどが建てられていた。楼閣の基礎には版築と呼ばれる工法が用いられている。これは粘土と砂を交互に入れて突き固め、地盤を強化する方法だ。
谷のゴミ捨て場では、貴重な遺物が発掘され、北海道から新潟まで、日本海を通じての物の交流があったことが判明している。また集落の周辺では栗など、数種類の植物が栽培され、縄文時代が単なる採集文化ではなかったことが分かった。
火焔土器

4年前の旅行では、長岡市にある新潟県立博物館で、見事な火焔土器など縄文時代の遺物をたくさん見学した。現物を見ると、本で読むだけでは得られない発見や感性が起きる。この時は縄文人のパワーを感じたものだ。この旅行では越後一宮である弥彦神社へも立ち寄った。
さらには吉備津神社、吉備津彦神社(岡山)、出雲大社(島根)、大麻比古神社(徳島)、伊勢神宮(三重)、熱田神宮(愛知)、石上神社、大神神社、春日大社(奈良)、住吉大社(大阪)、八坂神社、貴船神社(京都)、白山比め(めは口に羊)神社(石川)、出羽三山神社(山形)なども訪ねている。
 遮光器型土偶
遮光器型土偶これは昨年青森県立郷土館で見た遮光器型土偶。ここには「松韻堂コレクション」と言う、縄文時代の遺物を中心とした優れた展示物があった。青森在住の医師親子が二代に亘って収集した逸品だ。「遮光器」とはエスキモーが使う「雪眼鏡」のこと。目の周囲がこれに似ていることからの命名だ。新潟の火焔土器もそうだが、初めて見て縄文人のパワーと宗教性、感性に驚いたものだ。
大湯環状列石

これは昨年訪れた秋田県鹿角市にある大湯環状列石(ストーンサークル)。縄文時代の巨大なお墓で、この巨大なサークルの中に、小さな円形の石組が幾つかある。また広い遺跡にはもう一つの環状列石や、幾つかの配石遺構があり、「墓」の傍には祭祀のための掘っ立て小屋が数棟建てられている。墓として使用された期間がわずか200年間だったとのことにも驚いた。
 合掌土偶(国宝)
合掌土偶(国宝)これは今年の6月、八戸市立是川縄文館で見た「合掌土偶」。まるで宇宙人のようだが、縄文人の信仰心が分かる。縄文人の平均寿命はわずか37歳。自らの長寿と子孫の繁栄を真剣に祈る姿なのだ。膝の辺りが壊れ、アスファルトで接着した痕があることからも、大事にされていたことが分かる。土偶のほとんどが人間の代わりに破壊されることが多い。それが後世の「流し雛」に繋がって行くのだろう。
こんな風に、歴史や考古学に対する思いは尽きない。毎年の旅行も、私の趣味に合わせてのことが多いのだ。このシリーズは冒頭から長引いてしまった。いよいよ明日からは残った写真を使って、東北の歴史を訪ねる旅を紹介したいと思う。最後までお付き合いいただけたら嬉しい。<続く>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[考古学・日本古代史] カテゴリの最新記事
-
いのちを生きる(3) 2022.02.15 コメント(4)
-
小さな郷土史と縄文への旅(2) 2021.07.15 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.









