テーマ: 美術館・博物館(1516)
カテゴリ: 歴史全般
~丸森町の歴史など~

ぼけているが、これは宮城県の地図。赤く塗られたところが、斎理屋敷がある丸森町だ。見て分かるように、町の半分が南隣の福島県に飛び出している。戦国時代はこの地を巡って、伊達と相馬が戦った。相馬が治めていた時は磐城国の伊達郡に編入され、伊達氏が奪還した後は陸奥国の伊具郡に入った。
さて現在は福島と県境を接しているため、東日本大震災の福島原発事故による放射能汚染問題も発生した。町の特産品であるタケノコが、あの事故以来数年間出荷停止となったのだ。除染が終了し、現在では再び出荷が可能となった。

今日は丸森町の歴史を探るため、「まるもりふるさと館」を案内したい。町立の小さな博物館で入場無料。町役場付近にあり、斎理屋敷から歩いて15分ほどだ。これは縄文時代の石器。左側と上部に見える石斧(せきふ=いしおの)は、丸太などを伐る際に使われた。右隣の石棒は男性のシンボルとも言われ、呪術的な意味合いが深い。いずれも良く磨かれ、技術性の高さが偲ばれる。

縄文土器の一部。破損したままなのが残念だが、縄文の息吹を感じることは出来るだろう。

複製品で、縄文人の勢いが感じられないのが残念。当時の東北は縄文文化の最先端地で、土器にもエネルギーが漲っていたのだが、これだと薄っぺらいものにしか見えない。

これらは土偶(どぐう)と呼ばれる土製の人形。人間に代わって穢れを祓うために破壊された。後世の流し雛(ながしびな)と全く同様の考え方だ。日本人の遠い祖先たちの長命と健康を願う気持ちが込められている。

土偶。当時の品ではなくレプリカだが、造形美と縄文人の精神性を知る上で貴重だ。

弥生式土器の複製。主に狩猟によって食料を確保した縄文時代と異なり、大陸から伝わった米を育てて食料とする弥生時代の土器は、意匠がより単純化する。生命の危険性が減ったからだろうか。東北への稲作はかなり早く伝わったものの、寒冷化によって一旦米作地が後退する。寒さに強い品種がまだ出来てなかったためだ。

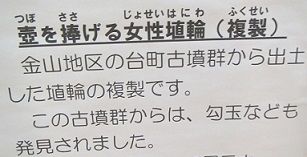
複製にせよ、県下でこれだけ見事な埴輪が出土したとは驚きだ。古墳時代の東北に、大和朝廷の影響が出始める。稲作で力を蓄えた豪族たちが、中央の墓制を取り入れるのだ。東北には従来独自の墓制があったが、中央の権力者との協力関係によってさらに自己の権威を増すためその墓制を取り入れたのだろう。ここ丸森町にも前方後円墳を含む古墳群が造られる。

緑色の真っ直ぐなのが管玉(くだたま)で、カーブしたのが勾玉(まがたま)。縄文時代から伝わる勾玉は胎児を模したとも言われ、呪術性を有する。共にメノウ製だ。首飾りだろうが、それにしては部品が少ない。貴石で作られた飾りは、権力者の象徴だった。

これは釧(くしろ)で、腕にはめるブレスレット。やはり権力を表す道具だ。なお北海道の釧路はアイヌ語の地名を漢字で充てただけで、本来の意味ではない。

これは銅製の鈴釧(すずくしろ)。釧の周囲に5つの鈴型装飾が施されている。私は今回初めて実物を見た。

<阿武隈川の流れ=上方が下流側です>
奈良時代にはこの地に伊具郡の郡衙(ぐんが)が置かれたことだろう。平安時代には奥州藤原氏が陸奥守となって東北全体を治めた。だが源頼朝の40万騎が藤原氏を滅ぼすと、この地も鎌倉幕府の支配下となった。南北朝時代は付近の霊山などで戦乱が続き、戦国時代には鎌倉武士の末裔たちが、領地の拡大に奔走して戦いに明け暮れた。


親子同士での戦いもあった。政宗の祖父稙宗(たねむね)は、実子である政宗の父照宗と戦って敗れ、この丸森の小城で余生を送った。その面倒を見たのが相馬氏に嫁いだ照宗の姉妹。稙宗の死後、娘はこの領地を相馬氏のものとし、それを照宗が戦いで奪い返した。冒頭の領地の帰属と郡名の変更の話は、これによる。

<町内の蔵>
仙台藩は、領地のほとんどを家来に分け与えた。ここ丸森を治めていたのは佐々(さっさ)氏。城は設けず、街道筋の町として賑わっていたのだろう。ここは奥州街道から逸れた脇街道だが、並行して阿武隈川が流れており、江戸時代は舟運で上流の福島(幕府の天領)から米が運ばれるなどし、河口鳥の海にあった積出港への中継地としても栄えた。斎理屋敷の主は、舟運などでも大いに稼いだのだ。

<旧郵便局>
幕末の戊辰戦争で陸羽越列藩同盟の中心となった仙台藩は、ここ丸森でも官軍と戦った由。だが最新兵器を持つ官軍に対して、仙台藩の大砲の弾丸は陶器製で威力に欠けた。結果は火を見るよりも明らかで、列藩同盟は敗北。一部は最後の挑戦のため函館の五稜郭へと敗走した。明治初期、何度か混乱があった。一時期この地を南部藩に組み入れたのは、薩長主体の新政府の報復だったのだろう。

<町章が入ったマンホールのふた>
東北を冷遇した大久保利通がやがて反省する。江戸初期に政宗が遥かヨーロッパに使節を送り、通商を試みたことが明らかになったためだ。有為な人物が東北にいたことを知って政策を変え、現在の東松島市野蒜に近代的な新港を築いた。横浜港に先立つものだったが、外洋に面していたため波で堤防が破壊されて断念。しかし、仙台に第二高等学校、東北帝大、陸軍師団を置いて重視する。

<駅から斎理屋敷へ向かう途中の橋>
盛んだった阿武隈川の舟運に代わり、やがて沿線に鉄道が敷かれた。だが国鉄の民営化に伴って丸森線は民間の「阿武隈急行」となり、目下赤字で経営難。この沿線では過疎化が進んでいる。沿線の5市町は財政援助を行って、阿武隈急行の車両更新を図るなどしている。では明日から再び斎理屋敷の紹介に戻ろうと思う。どうぞお楽しみに。なおタイトルの一部を変更した。<続く>

ぼけているが、これは宮城県の地図。赤く塗られたところが、斎理屋敷がある丸森町だ。見て分かるように、町の半分が南隣の福島県に飛び出している。戦国時代はこの地を巡って、伊達と相馬が戦った。相馬が治めていた時は磐城国の伊達郡に編入され、伊達氏が奪還した後は陸奥国の伊具郡に入った。
さて現在は福島と県境を接しているため、東日本大震災の福島原発事故による放射能汚染問題も発生した。町の特産品であるタケノコが、あの事故以来数年間出荷停止となったのだ。除染が終了し、現在では再び出荷が可能となった。

今日は丸森町の歴史を探るため、「まるもりふるさと館」を案内したい。町立の小さな博物館で入場無料。町役場付近にあり、斎理屋敷から歩いて15分ほどだ。これは縄文時代の石器。左側と上部に見える石斧(せきふ=いしおの)は、丸太などを伐る際に使われた。右隣の石棒は男性のシンボルとも言われ、呪術的な意味合いが深い。いずれも良く磨かれ、技術性の高さが偲ばれる。

縄文土器の一部。破損したままなのが残念だが、縄文の息吹を感じることは出来るだろう。

複製品で、縄文人の勢いが感じられないのが残念。当時の東北は縄文文化の最先端地で、土器にもエネルギーが漲っていたのだが、これだと薄っぺらいものにしか見えない。

これらは土偶(どぐう)と呼ばれる土製の人形。人間に代わって穢れを祓うために破壊された。後世の流し雛(ながしびな)と全く同様の考え方だ。日本人の遠い祖先たちの長命と健康を願う気持ちが込められている。

土偶。当時の品ではなくレプリカだが、造形美と縄文人の精神性を知る上で貴重だ。

弥生式土器の複製。主に狩猟によって食料を確保した縄文時代と異なり、大陸から伝わった米を育てて食料とする弥生時代の土器は、意匠がより単純化する。生命の危険性が減ったからだろうか。東北への稲作はかなり早く伝わったものの、寒冷化によって一旦米作地が後退する。寒さに強い品種がまだ出来てなかったためだ。

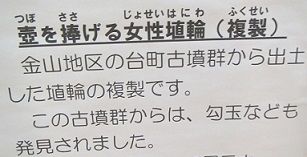
複製にせよ、県下でこれだけ見事な埴輪が出土したとは驚きだ。古墳時代の東北に、大和朝廷の影響が出始める。稲作で力を蓄えた豪族たちが、中央の墓制を取り入れるのだ。東北には従来独自の墓制があったが、中央の権力者との協力関係によってさらに自己の権威を増すためその墓制を取り入れたのだろう。ここ丸森町にも前方後円墳を含む古墳群が造られる。

緑色の真っ直ぐなのが管玉(くだたま)で、カーブしたのが勾玉(まがたま)。縄文時代から伝わる勾玉は胎児を模したとも言われ、呪術性を有する。共にメノウ製だ。首飾りだろうが、それにしては部品が少ない。貴石で作られた飾りは、権力者の象徴だった。

これは釧(くしろ)で、腕にはめるブレスレット。やはり権力を表す道具だ。なお北海道の釧路はアイヌ語の地名を漢字で充てただけで、本来の意味ではない。

これは銅製の鈴釧(すずくしろ)。釧の周囲に5つの鈴型装飾が施されている。私は今回初めて実物を見た。

<阿武隈川の流れ=上方が下流側です>
奈良時代にはこの地に伊具郡の郡衙(ぐんが)が置かれたことだろう。平安時代には奥州藤原氏が陸奥守となって東北全体を治めた。だが源頼朝の40万騎が藤原氏を滅ぼすと、この地も鎌倉幕府の支配下となった。南北朝時代は付近の霊山などで戦乱が続き、戦国時代には鎌倉武士の末裔たちが、領地の拡大に奔走して戦いに明け暮れた。


親子同士での戦いもあった。政宗の祖父稙宗(たねむね)は、実子である政宗の父照宗と戦って敗れ、この丸森の小城で余生を送った。その面倒を見たのが相馬氏に嫁いだ照宗の姉妹。稙宗の死後、娘はこの領地を相馬氏のものとし、それを照宗が戦いで奪い返した。冒頭の領地の帰属と郡名の変更の話は、これによる。

<町内の蔵>
仙台藩は、領地のほとんどを家来に分け与えた。ここ丸森を治めていたのは佐々(さっさ)氏。城は設けず、街道筋の町として賑わっていたのだろう。ここは奥州街道から逸れた脇街道だが、並行して阿武隈川が流れており、江戸時代は舟運で上流の福島(幕府の天領)から米が運ばれるなどし、河口鳥の海にあった積出港への中継地としても栄えた。斎理屋敷の主は、舟運などでも大いに稼いだのだ。

<旧郵便局>
幕末の戊辰戦争で陸羽越列藩同盟の中心となった仙台藩は、ここ丸森でも官軍と戦った由。だが最新兵器を持つ官軍に対して、仙台藩の大砲の弾丸は陶器製で威力に欠けた。結果は火を見るよりも明らかで、列藩同盟は敗北。一部は最後の挑戦のため函館の五稜郭へと敗走した。明治初期、何度か混乱があった。一時期この地を南部藩に組み入れたのは、薩長主体の新政府の報復だったのだろう。

<町章が入ったマンホールのふた>
東北を冷遇した大久保利通がやがて反省する。江戸初期に政宗が遥かヨーロッパに使節を送り、通商を試みたことが明らかになったためだ。有為な人物が東北にいたことを知って政策を変え、現在の東松島市野蒜に近代的な新港を築いた。横浜港に先立つものだったが、外洋に面していたため波で堤防が破壊されて断念。しかし、仙台に第二高等学校、東北帝大、陸軍師団を置いて重視する。

<駅から斎理屋敷へ向かう途中の橋>
盛んだった阿武隈川の舟運に代わり、やがて沿線に鉄道が敷かれた。だが国鉄の民営化に伴って丸森線は民間の「阿武隈急行」となり、目下赤字で経営難。この沿線では過疎化が進んでいる。沿線の5市町は財政援助を行って、阿武隈急行の車両更新を図るなどしている。では明日から再び斎理屋敷の紹介に戻ろうと思う。どうぞお楽しみに。なおタイトルの一部を変更した。<続く>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[歴史全般] カテゴリの最新記事
-
ウクライナの平和を祈って(17) 2022.03.18 コメント(2)
-
戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.27 コメント(4)
-
戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.26 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.









