カテゴリ: 歴史全般
<近代史への迷い道 日清戦争まで>


ここ何回か東アジアの歴史について記している。学校で何も学ばなかった身で、これを書くのは実に辛い。だが私が旅した大連と旅順は「旧満州国」に属した地域。それならどうしても満州に触れない訳には行かず、それを書くためにも東アジア史に触れざるを得ない。そんなことから迷い道にはまり込んだ次第。何か知ってることがあれば、それを手掛かりにしてネットで調べられる。そして固有名詞や歴史の事実が明らかになれば、それなりに画像を得ることも可能。今はとても便利な時代なのだ。

これは北海道の古地図。松浦武四郎が「北海道」と名付ける前は蝦夷地(えぞち)と呼ばれ、その本州に近い部分を奈良時代には渡島(わたりしま)と呼んでいた。先住民はアイヌではなく、縄文人だろう。アイヌの人がこの島へ来たのは、ずっと後になってからだ。江戸時代後半になると、伊能忠敬、間宮林蔵、松浦武四郎らが探検や測量にやって来た。それは彼らの趣味のためではなく、幕府の命令によるもの。
それだけロシアの南進政策による脅威が迫っていたのだ。彼らは不凍港を求めて東へ、より南へ目指した。そして江戸幕府に開国と開港を迫った。そこで幕府は松前藩、津軽藩、仙台藩に蝦夷地の警備を命じた。それが明治以降の北海道開拓につながった。また仙台藩では藩内の何か所かに蛮船監視所を設けて、黒船の動向を探った。それだけ、飲料水や燃料を求めて来航する黒船が多かったのだ。

嘉永6年(1853年)ペリー率いるアメリカ海軍東インド艦隊の黒船4隻が浦賀水道沖に現れた。日本の開国と燃料補給などを求めてのこと。幕府の禁止を振り切って品川沖に現れた黒船を、千葉道場を抜け出して竜馬が見物に行ったことが、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」に記されている。幕府はこれ以降各国の強い要求により開国し、箱館、横浜、下田、長崎などの開港に踏み切る。鎖国体制の終焉だった。
文久元年(1861年)ロシア海軍の軍艦が、対馬を占拠する事件が起きた。この時は幕府と対馬藩の説得では退去せず、イギリス海軍の仲介で箱館に駐在していたロシア領事を対馬に連行して説得させた。ロシア帝国の不凍港確保のための南下政策が、深刻だったための事件だ。それがその後の日露戦争の前哨戦となった。

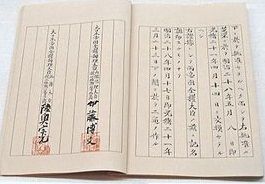
<清国北洋艦隊> <日清講和条約=下関条約>
明治27年(1894年)朝鮮半島の江華島で測量中の日本兵に対して、清国軍が発砲したことを引き金に日清戦争が勃発した。その数年前には漂着した沖縄の島民70名を台湾の蛮族が殺害し、日本兵が鎮圧したことも背景にあった。清国政府は台湾は化外の民(統治外の蛮族)として責任は取らなかった。清国海軍北洋艦隊は山東半島の基地威衛海から、遼東半島の旅順に向かわせた。
それを監視していた日本の連合艦隊発見して対戦した。これが黄海海戦で、兵力と兵備は清国が優っていたが、作戦と統率力が優った連合艦隊が圧勝して多大な損害を与えた。この結果、下関で締結された「日清講和条約」で、清国は台湾と遼東半島の永久割与、朝鮮国の独立、賠償金2億テールを支払日本に支払うこととなった。こうして約2千年間中国の支配下にあった朝鮮は独立し、後に日本への併合を自ら議決した。<続く>


ここ何回か東アジアの歴史について記している。学校で何も学ばなかった身で、これを書くのは実に辛い。だが私が旅した大連と旅順は「旧満州国」に属した地域。それならどうしても満州に触れない訳には行かず、それを書くためにも東アジア史に触れざるを得ない。そんなことから迷い道にはまり込んだ次第。何か知ってることがあれば、それを手掛かりにしてネットで調べられる。そして固有名詞や歴史の事実が明らかになれば、それなりに画像を得ることも可能。今はとても便利な時代なのだ。

これは北海道の古地図。松浦武四郎が「北海道」と名付ける前は蝦夷地(えぞち)と呼ばれ、その本州に近い部分を奈良時代には渡島(わたりしま)と呼んでいた。先住民はアイヌではなく、縄文人だろう。アイヌの人がこの島へ来たのは、ずっと後になってからだ。江戸時代後半になると、伊能忠敬、間宮林蔵、松浦武四郎らが探検や測量にやって来た。それは彼らの趣味のためではなく、幕府の命令によるもの。
それだけロシアの南進政策による脅威が迫っていたのだ。彼らは不凍港を求めて東へ、より南へ目指した。そして江戸幕府に開国と開港を迫った。そこで幕府は松前藩、津軽藩、仙台藩に蝦夷地の警備を命じた。それが明治以降の北海道開拓につながった。また仙台藩では藩内の何か所かに蛮船監視所を設けて、黒船の動向を探った。それだけ、飲料水や燃料を求めて来航する黒船が多かったのだ。

嘉永6年(1853年)ペリー率いるアメリカ海軍東インド艦隊の黒船4隻が浦賀水道沖に現れた。日本の開国と燃料補給などを求めてのこと。幕府の禁止を振り切って品川沖に現れた黒船を、千葉道場を抜け出して竜馬が見物に行ったことが、司馬遼太郎の「竜馬がゆく」に記されている。幕府はこれ以降各国の強い要求により開国し、箱館、横浜、下田、長崎などの開港に踏み切る。鎖国体制の終焉だった。
文久元年(1861年)ロシア海軍の軍艦が、対馬を占拠する事件が起きた。この時は幕府と対馬藩の説得では退去せず、イギリス海軍の仲介で箱館に駐在していたロシア領事を対馬に連行して説得させた。ロシア帝国の不凍港確保のための南下政策が、深刻だったための事件だ。それがその後の日露戦争の前哨戦となった。

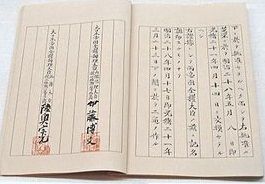
<清国北洋艦隊> <日清講和条約=下関条約>
明治27年(1894年)朝鮮半島の江華島で測量中の日本兵に対して、清国軍が発砲したことを引き金に日清戦争が勃発した。その数年前には漂着した沖縄の島民70名を台湾の蛮族が殺害し、日本兵が鎮圧したことも背景にあった。清国政府は台湾は化外の民(統治外の蛮族)として責任は取らなかった。清国海軍北洋艦隊は山東半島の基地威衛海から、遼東半島の旅順に向かわせた。
それを監視していた日本の連合艦隊発見して対戦した。これが黄海海戦で、兵力と兵備は清国が優っていたが、作戦と統率力が優った連合艦隊が圧勝して多大な損害を与えた。この結果、下関で締結された「日清講和条約」で、清国は台湾と遼東半島の永久割与、朝鮮国の独立、賠償金2億テールを支払日本に支払うこととなった。こうして約2千年間中国の支配下にあった朝鮮は独立し、後に日本への併合を自ら議決した。<続く>
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[歴史全般] カテゴリの最新記事
-
ウクライナの平和を祈って(17) 2022.03.18 コメント(2)
-
戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.27 コメント(4)
-
戦争と平和・歴史と真実・国家と民族 そ… 2021.08.26 コメント(2)
【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね!
--
/
--
PR
X
© Rakuten Group, Inc.









