2014年08月の記事
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-

ハービー・ニコルス 『ハービー・ニコルス・トリオ(Herbie Nichols Trio)』
忘却の彼方に置かれた孤高のピアニスト “不遇のミュージシャン”というのは、音楽の世界にはたまに見かけられる。そんな中でもジャズ界においてこの表現で思い浮かぶ最初の一人とも言えそうなのが、このハービー・ニコルス(Herbie Nichols)というピアニストではないだろうか。片手で数えられるほどの枚数の作品しか残すことなく、白血病により44歳で他界した(1919年生まれ、1963年に死去)。 本人はマンハッタン出身だが、両親はセントキッツおよびトリニダー、共にカリブ海の小島の出身。これと関係あるのかもしれないが、ニコルスの演奏を聴くと、ピアノとは“奏でる”ものではなく、“弾く(はじく=ひく)”ものだということがよくわかる。ピアノという楽器の“打楽器的”な要素を示してくれる奏者はと言えば、筆者にとっては、セロニアス・モンクと、そしてこのハービー・ニコルスといったところだったりする。 実際、このニコルスはミュージシャンであると同時に音楽批評家でもあったそうで、セロニアス・モンク論を雑誌に載せていたりもしたらしい。なるほど、モンクの真似では全くないにせよ、ピアノの鍵盤を“叩く”意味についてはモンクから大きな着想を得ていたのかもしれない。どこへ飛んでいくか予想がつかなさそうなアドリブもまた、モンクの影響大と言えそうだが、やはりモンクのコピーではなく、モンクの香りを持った独自性を展開している。 10年近くもブルーノートのアルフレッド・ライオンに自身の録音機会を申し入れ、断られ続けたが、やがてライオンは重い腰を上げて、彼の吹き込みを実現させる。1955年~56年に2枚の10インチ盤と本盤を吹き込むが、なぜかその後は、ブルーノートでの活動は続かなかった。ベツレヘムやサヴォイに若干の吹き込みを残すが、1963年に44歳の生涯を閉じ、その後はやがて再評価の波が押し寄せるまで忘却の彼方へと忘れ去られた。 ニコルスの演奏は上で述べたようなパーカッシブなピアノという特徴を持つけれど、全体としてはドラムスに大きな役割を与え、全体の構成をコンポーザー的に考えているように思う。誤解を恐れず少し大げさに言うと、ドラムが単なるパーカッシブな役割を超えた役割を持ち、ピアノが普通のジャズ奏者のそれに加えてよりパーカッシブになって組み合わされている、とでも言えばいいだろうか。3.「チット・チャッティング」なんかはその典型例のように思う。 収録されているのはほとんどがオリジナル曲で、曲としては流れるように進む(どこかメロディアスだったりする曲も多い)のと同時にリズムとアドリブ展開の先の読めなさが楽しい。そんな観点から特にお気に入りなのは、1.「ザ・ギグ」、4.「ザ・レディ・シングス・ザ・ブルース」、6.「スピニング・ソング」、7.「クェアリー」といった辺り。この辺の“完成された芸”(=捉え方によってはワンパターンといえなくもない)がライオンに限界を感じさせたのかと思わなくもないが、ひとつのトーンで全体としてはうまくまとまり、個々の曲についてはどこへたどり着くのか予想し難い展開の仕方をする、これが本盤の最大の魅力と言えるだろう。[収録曲]1. The Gig2. House Party Starting3. Chit-Chatting4. Lady Sings the Blues5. Terpsichore6. Spinning Song7. Query8. Wildflower9. Hangover Triangle10. Mine[パーソネル、録音]Herbie Nichols (p)Al McKibbon (b: 1.~5.,9.),Teddy Kotick (b: 6.~8.、10.)Max Roach (ds)録音:1955年8月1日(1.~4.,9.)、1955年8月7日(5.)、1956年4月19日(6.~8.、10.)下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年08月29日
コメント(0)
-
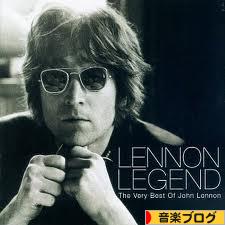
INDEXの更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順の過去記事リンク一覧)を更新しました。少し間が空きましたが、ここしばらくの記事を追加しています。 INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りの上、お好きな演奏者やシンガー、曲やアルバムなどご覧いただけると幸いです。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-L)・つづき(M-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A-E)へ → つづき(F-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へ アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング: 人気ブログランキングへ
2014年08月27日
コメント(0)
-

51万アクセス、感謝
当ブログの累計アクセス数が510000件に達しました。ご覧いただいている皆さまにあらためて感謝いたします。今後とも引き続きご愛顧のほどお願いします。 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2014年08月25日
コメント(2)
-
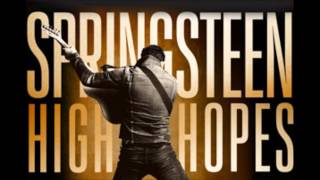
ブルース・スプリングスティーン&トム・モレロ 「ゴースト・オブ・トム・ジョード(The Ghost of Tom Joad)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その10) 50万アクセス記念と称して10回シリーズをやってきましたが、最後は今年(2014年)になってからリリースされたこのナンバーで締めくくりにします。元々はブルース・スプリングスティーン本人の曲なので、本シリーズの「その8」と同様に“セルフカバー”ということになってしまうのですが、今年になってから聴いた“名ナンバーのカバー”という意味では、ぜひとも取り上げたいと思う次第です。 元の曲(演奏)は1995年のアコースティック色の強い静かな調子の同名アルバムに収められていました。その激変ぶりをまずは比較してみてください。 表記の演奏でとにかく大きな存在感を発揮しているのが、トム・モレロ(元レイジ・アゲンスト・ザ・マシーン、元オーディオスレーヴ、現ストリート・スウィーパー・ソーシャル・クラブ)の存在です。ここ数年来、B・スプリングスティーンと共演したり、リトル・スティーヴン不在時のギタリストを務めたりしています。 そのようなわけで、最後はトム・モレロがライヴでスプリングスティーン・バンドと共演している模様で締めくくりたいと思います。 [収録アルバム]Bruce Springsteen / High Hopes(2014年)Bruce Springsteen / The Ghost of Tom Joad(1995年)←元バージョン収録 送料無料!!【CD】ハイ・ホープス/ブルース・スプリングスティーン [SICP-4070] ブルース・スプリングステイーン 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2014年08月24日
コメント(0)
-

忌野清志郎 「イマジン(Imagine)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その9) さらに調子に乗って、少々異例なカバーを取り上げたいと思います。亡き忌野清志郎によるジョン・レノンの超有名曲のカバーです。ジョンのこれほどの有名曲をカバーするには、普通に考えれば、相当の覚悟が要りそうなものですが、圧倒的な自分の世界(“清志郎ワールド”)をいとも簡単に作り上げてしまうこの人はやっぱり偉大です。 元々は、1971年にソロ作として発表した『イマジン』のタイトル・チューンですが、その数年前(1969年のゲット・バック・セッションの頃)にはその原型となる曲ができていたようです。それを忌野清志郎がカバーとして発表したのは、1988年のRCサクセションのアルバム『カバーズ(COVERS)』でした。反核や反原発といった内容からレーベル(東芝EMI)から発売中止(「素晴らしすぎて発売できない」)処分を受け、古巣の別会社(キティ・レコード)から終戦記念日の8月15日に発売されたという、いわくつきの作品発表の経緯でした(参考過去記事(1) ・(2) )。 この「イマジン」をカバーしているアーティストは星の数ほどいそうな気がしますが、RCサクセション(もしくは忌野清志郎)の利点は、“訳詞”という点にあったと思います。原曲を英語のままカバーしても、当たり前ですが、元と同じ歌詞です。それに対し、“日本語訳(和訳)”であって、しかもその訳詞が強烈な個性を反映した訳詞でした。過去の記事でも書きましたが、忌野清志郎の才能とセンスのなせる業だったということでしょうか。 映像1つで終わっては何ともあっさりなので、今回は元のジョン・レノンも取り上げようと思います。通常のヴァージョンではなく、1988年のドキュメンタリー映画『イマジン』のサウンドトラックに収録されたデモ(リハーサル)・ヴァージョンをお聴きください。 今さらながら、やはり元から名曲ですね。[収録アルバム]RCサクセション / COVERS(1989年)John Lennon / Imagine(Original Picture Soundtrack)(1988年) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】カバーズ [ RCサクセション ] 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年08月23日
コメント(2)
-

ピーター・セテラ 「愛ある別れ(If You Leave Me Now)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その8) 今回は少し変則的ですが、バンドでやった曲をソロでセルフカバーという例です。原曲は70年代後半の中期シカゴの名曲で、当時シカゴのヴォーカリストだったピーター・セテラが20年ほど後にソロで新録したというものです。セテラの『愛ある別れ~ピーター・セテラ・ベスト・コレクション』という1997年のソロ第6作(ベスト盤というよりは既発表のデュエット曲+新録を加えた作品)には、シカゴ時代のナンバー(「愛ある別れ(If You Leave Me Now)」、「朝もやの二人(Baby, What A Big Surprise)」、「君こそすべて(You’re the Inspiration)」)のソロ・ヴァージョンが含まれています。 今回はそのうち「愛ある別れ(イフ・ユー・リーブ・ミー・ナウ)」をお聴きください。 原曲でのバンドでの演奏はすっかり変化し、ソロのヴォーカリストとしてひたすら声を聴かせようという感じのアレンジです。確かに、ピーター・セテラの艶やかな声は、こういう言い方も何ですが、しょぼい曲でも名曲に変えてしまうような魅力があります。 無論、この曲そのものをけなしているわけではありません。それどころか、本ナンバーは中期シカゴの大名曲です。70年代後半から80年代にかけてのバラード系ヒットの先駆けとなった原曲もお聴きください。上のヴォーカルで聴かせるニュー・ヴァージョンと対照的に、バンド全体の演奏、コーラス、そして“雰囲気”で包み込むといった感じのナンバーです。 [収録アルバム]Peter Cetera / Inspiration(愛ある別れ~ピーター・セテラ・ベスト・コレクション)(1997年)Chicago / Chicago X(カリブの旋風)(1976年)←元バージョン収録 ↓シカゴ時代の元のアルバム↓ 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】【送料無料】シカゴX(カリブの旋風)<2003年リマスター&エクスパンデッド音源>/シカゴ[CD]【返品種別A】 ↓ソロでのヴァージョン含むベスト盤↓ 【当店専用ポイント(楽天ポイントの3倍)+メール便送料無料】ピーター・セテラPeter Cetera / Number Ones (輸入盤CD) (ピーター・セテラ) 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2014年08月22日
コメント(0)
-
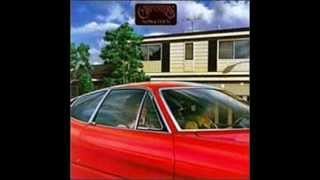
カーペンターズ/ステイタス・クオー 「ファン、ファン、ファン(Fun, Fun, Fun)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その7) だいぶ前に、カーペンターズ(Carpenters)の通算第5作『ナウ&ゼン』というアルバムについて書きました。同アルバムの後半のほとんどを費やして収められたオールディーズ・メドレーというのがあり、今回はそれを取り上げたいと思います。このメドレーの冒頭に含まれる「ファン、ファン、ファン」(元はビーチ・ボーイズの1964年のヒット曲)を思い出し、名ナンバーのカバーということで取り上げたいと考えた次第です。 カーペンターズによるこのメドレーは、代表曲として知られることになる「イエスタデイ・ワンス・モア」および「同(リプライズ)」にはさまれる形で、発売時のLPのB面に収められ、合計15分ほどの演奏となっています。 収められている曲は、「ファン、ファン、ファン」(上述の通りビーチ・ボーイズの曲で、ブライアン・ウィルソンとマイク・ラヴのペンによる)のほか、収録順に、「この世の果てまで(ジ・エンド・オブ・ザ・ワールド)」(スキータ・デイヴィス、1962~63年)、「ハイ・ロン・ロン」(ザ・クリスタルズ、1963年)、「デッドマンズ・カーブ」(ジャン&ディーン、1964年)、「ジョニー・エンジェル」(シェリー・フェブレー、1962年)、「燃ゆる瞳(ザ・ナイト・ハズ・ア・サウザンド・アイズ)」(ボビー・ヴィー、1962~63年)、「アワ・デイ・ウィル・カム」(ルビー&ザ・ロマンティックス、1963年)、「ワン・ファイン・デイ」(ザ・シフォンズ、1963年)です。 アルバムを取り上げた記事中にも書きましたが、長いのにあっという間の心地よい15分間です。ちなみに曲間のDJ風ナレーションをやっているのは、カーペンターズのリード・ギターを担当していたトニー・ペルーソ(Tony Peluso)という人で、カレンの死去でカーペンターズの活動が終焉した後はレコーディング・プロデューサーおよびエンジニアとして活躍し、2010年に亡くなっています。 さらに今回は、もう一つ。この同じ曲の滅法カッコいいカバーもお楽しみください。1996年にステイタス・クオー(Status Quo)がビーチ・ボーイズとの共演で演奏した「ファン、ファン、ファン」です。 原曲を壊すことなく、見事に“ステイタス・クオー・フレーバー”にできていると思うのですが、いかがでしょうか。[収録アルバム]Carpenters / Now & Then(1973年)Status Quo / Don’t Stop(1996年) 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】【送料無料】ナウ・アンド・ゼン/カーペンターズ[SHM-CD]【返品種別A】 [CD]STATUS QUO ステイタス・クオー/DON’T STOP + 4【輸入盤】 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2014年08月20日
コメント(0)
-

シンニード(シネイド)・オコナー 「ナッシング・コンペアーズ・トゥ・ユー(Nothing Compares 2 U)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その6) 「ナッシング・コンペアーズ・トゥ・ユー(Nothing Compares 2 U)」は、プリンス(Prince)が1980年代に発表した曲で、初出は彼の傘下にあったザ・ファミリー(The Family)によるものでした。その時点では特に注目を集めたわけではなかったのですが、しばらく後にアイルランド出身の女性シンガー、シンニード(シネイド)・オコナー(Sinéad O'Connor)がセカンド作『蒼い囁き』(1990年リリース)にこの曲を吹き込み、これがヒットを記録し、一躍ポピュラーなナンバーになりました。 この曲はいろんな人によってカバーされているうえ、プリンス自身によるバージョンも存在します。シングル・ヴァージョンおよびB面集となった作品(1993年発表)や、さらに後のライヴ盤(2002年発表)などでこの曲が取り上げられています。今回は、TVショウでの、キャンディ・ダルファー(サックス奏者)との共演をご覧ください。*リンク切れを貼りなおしましたが、音声のみです。 さらに数あるカバー・ヴァージョンの中から、比較的気に入っているものを一つだけ取り上げてみます。大阪出身の歌手、矢井田瞳(ヤイコ)の名を全国に知らしめるきっかけとなったセカンド・シングル(「my sweet darlin’」、2000年リリース)のB面にこのカバーが収められています(アルバム未収録なので、シングルB面としてのみ入手可のようです)。*残念ながらリンク切れのままです。 [収録アルバム]Sinéad O’Connor / I Do Not Want What I Haven’t Got(1990年)Prince / The Hits 1(1993年)*プリンスは他のライヴ・ヴァージョンのリリースもあり。 【輸入盤】SINEAD O’CONNOR シネイド・オコナー/I DO NOT WANT WHAT I HAVEN’T(CD) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】【輸入盤は全品ポイント5倍!】【輸入盤】Hits And B-sides Collection [ Prince ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2014年08月18日
コメント(0)
-

ニルス・ロフグレン 「ジャスト・ア・リトル(Just A Little)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その5) 今回は、永遠のロック少年、ニルス・ロフグレン(Nils Lofgren)による、60年代曲のカバーを取り上げてみます。「ジャスト・ア・リトル(Just A Little)」というナンバーで、1990年代の彼のアルバムに収められています。 まずはアルバム収録のロック調ヴァージョンからどうぞ。 一方、ライヴでは主に次のようなアコースティック・ヴァージョンで演奏しています。 この原曲は、1960年代半ばに活躍したボー・ブラメルズ(Beau Brummels)によるものです。彼らによる元々の演奏もお聴きください。 彼らは1964年デビューということですから、ちょうどビートルズのアメリカ進出と同じタイミングです。後に“フォーク・ロック”と呼ばれる雰囲気に近いものを持っていますので、“ザ・バーズの先駆者”といった感じでしょうか。追記:動画リンク切れにより、記事内容を更新しました(2019年4月)。[収録アルバム]Nils Lofgren / Crooked Line(1992年)←アルバム・ヴァージョン収録Nils Lofgren / Rare Tracks Collection(1994年、日本盤のみの未発表曲集)←シングル・エディット&アコースティック・ライヴの2ヴァージョンを含む 【中古】 クルックト・ライン /ニルス・ロフグレン 【中古】afb 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年08月17日
コメント(0)
-

ジェフ・ヒーリー 「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス(While My Guitar Gently Weeps)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その4) ここのところ、有名な曲のカバーを特集してお届けしていますが、有名曲のカバーというのは、なかなか難しいものです。下世話な体験談ですが、学生時代にビートルズのカバーをしていた時に、メンバーとよく議論した話題に、どうすれば“じゃあ、家へ帰ってビートルズのCD聴いた方がいいや”とならないようにするか、というのがありました。 一流のアーティストにとってもカバーはこれと同じ危険性を常にはらんでいるとも言えます。“元の曲を聴く方がいい…”、カバーする曲が有名であればあるほど、その危険性があります。そんなことを考えるにつけ、“これは凄い”と思う演奏を今日は取り上げようと思います。ジェフ・ヒーリー(Jeff Healey)による、「ホワイル・マイ・ギター・ジェントリー・ウィープス」です。まずは1990年の発表時のビデオクリップをどうぞ。 ご存知の方も多いでしょうが、ジェフ・ヒーリーは盲目のギタリストで、闘病生活の末、残念なことに2008年に41歳という若さで亡くなっています。膝の上に乗せたギターを鍵盤楽器のようにプレイするのが独特のスタイルです。 “なるほど、ハンディキャップを持った特殊なギタリストだったのね”程度に思った方(そんな人いないことを願いますが…)がもし仮にいたとしても、次のクリップを見ていただければ、さらにご納得いただけようかと思います。1997年、モントルーでのライヴ演奏です。 “圧倒”とか“圧巻”という言葉は(世間では乱発されるし、自分でも乱発してしまっているかもしれませんが)、まさしく、こういう演奏を形容するためにあると言えるのではないでしょうか。[収録アルバム]The Jeff Healey Band / Hell To Pay(1990年) ↓こちらは元のアルバム作品↓ 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】【送料無料】[枚数限定][限定盤]ヘル・トゥ・ペイ/ジェフ・ヒーリー[SHM-CD]【返品種別A】 ↓ベスト盤にも収録されています↓ 【当店専用ポイント(楽天ポイントの3倍)+メール便送料無料】ジェフ・ヒーリーJeff Healey / Playlist: The Very Best Of Jeff Healey (輸入盤CD)【I2013/10/15発売】(ジェフ・ヒーリー) 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2014年08月16日
コメント(0)
-

INDEX再度更新(不具合修正)
先回のINDEX更新にミスがあり、うまく更新できていなかったため、再度更新し直しました。ついでに昨日の記事もINDEXに含めてあります。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-L)・つづき(M-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A-E)へ → つづき(F-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へ アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2014年08月14日
コメント(0)
-

ジョニー・ウィンター 「追憶のハイウェイ61(Highway 61 Revisited)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その3) 続いては、先日亡くなったジョニー・ウィンター(Johnny Winter)による名曲カバーをお届けします。ボブ・ディランの「追憶のハイウェイ61(Highway 61 Revisited)」です。元のディランとはうって変わって、うねりのあるスライドギターの激しいプレイが圧巻です。 上のものは、メジャー契約後の第2作(通算第3作)の『セカンド・ウィンター』(1969年リリース)に収録された演奏ですが、今回はまだまだその後についてもご覧いただきたいと思うのです。 1976年のライヴ盤『狂乱のライヴ(Captured Live!)』に収められた、この同じ曲の演奏です。マンネリ化するどころか、ますます磨きがかかり、最高のドライヴ感と最高の技術が発揮されたお気に入りの演奏です。 さらに、今回はもう一つ。ジョニー・ウィンター追悼ということで、『ジョニー・ウィンター・アンド』を先に取り上げましたが、ここでは、比較的近年のこの曲の演奏の様子も見ていただこうと思います。2007年(だと思います)のライヴの模様です。 60歳代に入って老け込む(見かけは確かにそうなっています)どころか、この演奏! 60歳で“老人”と言うと、その世代の方に叱られてしまうでしょうが、10代の若者からすればどう見えるのだろうと、つい考えてしまいます。若いギター・キッズ目線に立ってみれば、こんなすごいスーパー爺はかっこよすぎる、といったところだったのではないでしょうか。[収録アルバム]Johnny Winter / Second Winter (1969年) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】【輸入盤】Second Winter [ Johnny Winter ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2014年08月13日
コメント(0)
-

INDEXの更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-L)・つづき(M-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A-E)へ → つづき(F-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へ アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2014年08月11日
コメント(0)
-

シンディ・ローパー 「アイコ・アイコ(Iko Iko)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その2) 第2回目は、「アイコ・アイコ(Iko Iko)」という、ニューオーリンズのトラディショナル曲を取り上げてみたいと思います。そもそもは1950年代に録音されたもの(ジェイムズ・“シュガー・ボーイ”クロフォードの「ジョック・ア・モー」)が原曲ですが、ドクター・ジョン(1972年作『ガンボ』に収録)によるものがよく知られています。 それでもって、1980年代になって、遅咲きの女性ポップ・シンガー、シンディ・ローパー(Cyndi Lauper)が名盤となったセカンド作『トゥルー・カラーズ』で熱唱を披露しました。これがまたなかなかの名唱だったのではないかと思う次第です。 続けて、今回は若い頃の(といっても以下のビデオの時には既に30歳代後半ですが)シンディをさらに、ということで、1991年の横浜でのライヴのこの曲の演奏模様をどうぞ。 それにしてもこのコスチューム(楽器)は何なのでしょうか? ニューオーリンズの音楽は、通常のパフォーマンスを超えたことをさせる魔力も持っているのかもしれません(笑)。[収録アルバム]Cyndi Lauper / True Colors (1986年) 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】【送料無料】トゥルー・カラーズ/シンディ・ローパー[Blu-specCD2]【返品種別A】 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2014年08月10日
コメント(2)
-

ジャクソン・ブラウン 「アイ・アム・ア・パトリオット(I Am A Patriot)」
50万アクセス記念~ロック&ポップスの名ナンバーをカバーで聴く(その1) 50万アクセス達成を記念して、動画つきで10回ほどお届けしたいと思います。表題にある通り、“名曲カバー選”というテーマでお付き合いいただければ幸いです。 第1回目は、過去記事で取り上げたものなのですが、ジャクソン・ブラウン(Jackson Browne)がリトル・スティーヴン(Little Steven, 本名Steve Van Zandt, B・スプリングスティーンのバンドのギタリストでソロとしても活動のほか、俳優としての活動でも知られる)をカバーしたこの曲です。 リトル・スティーヴンの原曲はいかにもレゲエ調で、本人の歌い方もある意味“濃い”のに対し、ジャクソン・ブラウンは、彼らしくさらりと(しかしこのメッセージ性にいかにも共感していそう)歌い上げています。 以下はジャクソン・ブラウンが原作者のリトル・スティーヴンと共演しているものです。2017年のライヴのキャプチャー映像です。 こういう政治的な内容のものを取り上げ、フェイヴァレットとして愛聴ならぬ愛演しているのは、ジャクソン・ブラウンのファンの側では意見が分かれるところかもしれませんが、個人的にはそもそもこの曲はよくできたナンバーで、それをうまくジャクソン・ブラウンが取り上げたということで、大成功だったのではないかと思っています。追記:リンク切れにより動画を差し替えました(2019年4月)。[収録アルバム]Jackson Browne / World In Motion(1989年) 【中古】【店頭併売品の為売り切れ御免】【中古】【CD】ジャクソン・ブラウン/ワールド・イン・モーション 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年08月09日
コメント(0)
-

50万アクセス御礼
当ブログのアクセス数が500000を超えました。この場をお借りして、日頃ご覧くださっている皆さまに御礼申し上げます。今後とも引き続きご愛顧のほど、よろしくお願いします。下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年08月08日
コメント(4)
-

トーマス・ドルビー 『光と物体(The Golden Age of Wireless)』
トーマス・ドルビーのソングライティングを再評価 トーマス・ドルビー(Thomas Dolby)は、1958年ロンドン出身のミュージシャン、プロデューサー。本名はトーマス・ロバートソンだが、ドルビー社(ドルビー・ノイズ・リダクション・システムのあのドルビー、カセットテープ世代には懐かしい単語ではないでしょうか)のドルビーをステージネームとして使い、かつては訴訟となったが、示談によって今でもこの芸名を使用し続けている。ちなみに、本名を使わなかったのは、音楽活動を始めた頃に既に名を知られていたシンガーのトム・ロバートソンとの混同を避け、キーボードとテープに向き合っていた時に仲間たちから付けられたあだ名(そのあだ名がドルビーだったとのこと)を採用して芸名にしたという。 本盤『光と物体(The Golden Age of Wireless)』は、1980年代初頭にリリースされた彼のソロ・デビュー作。当時としては時代を先取りした感のあるエレクトロ・ポップ・サウンド全開の作品というのが、全般的なイメージと言えるだろう。現在の感覚ではすでに消化された音楽かもしれないが、この当時という文脈では、“滅法新しい音楽”だった。 その代表例は、全米5位(カナダでは1位)の大きなヒットとなった1.「彼女はサイエンス(She Blinded Me With Science)」。1982年のファースト・リリース盤には未収録だったが、翌83年のセカンド・リリースでは曲順や収録曲に変更があり、この曲が含まれた(その後もCD化などの際に複数曲のヴァージョン差し替えがあった模様)。ちなみに、この当時のタイトルにはまだまだ日本語独自の邦訳タイトルがあった。アルバム表題の『光と物体』(直訳だと『ワイヤレス(無線)の黄金時代』)だし、この曲も「彼女はサイエンス」も雰囲気だけで意味不明な邦訳タイトルだけれど、直訳すれば「彼女はサイエンスで僕を眩ました」といったところ。ワイヤレス時代(いまのWi-Fi?)の到来を察知し、サイエンス=科学で幻惑する女性(●保方さん?)を連想させるのは、トーマス・ドルビーが30数年後を見据えたなんていうのは、考え過ぎだろうか(笑)。 さて、真面目な内容に話を戻して、そんな30年前の最先端サウンドのアルバムであると同時に、トーマス・ドルビーのソングライティングのよさが垣間見える作品でもある。3.「電波(Airwaves)」、5.「無重力(Weightless)」、6.「哀愁のユウローパ(Europa and the Pirate Twins)」(この邦題ももうちょっと何とかならなかったものか!)、9.「ワン・オブ・アワ・サブマリン」といったところが、個人的には好みである。その中でも3.「電波」は、このそっけない直訳では想像できないほど美しいナンバー。トーマス・ドルビーの曲作りの能力という観点で聴くなら、本盤の中でいちばんの聴きどころと言ってもよいかもしれない。 余談ながら、坂本龍一つながりということだと思うが、2.「ラジオ・サイレンス」では、矢野顕子(ちょうどこの時期に坂本龍一と結婚している)がバックヴォーカルで参加している。[収録曲]1. She Blinded Me with Science2. Radio Silence3. Airwaves4. Flying North5. Weightless6. Europa and the Pirate Twins7. Windpower8. Commercial Breakup9. One of Our Submarines10. Cloudburst at Shingle Street1982年リリース(注:上記収録内容・曲順は1983年リリース)。 【当店専用ポイント(楽天ポイントの3倍)+メール便送料無料】トーマス・ドルビーThomas Dolby / The Golden Age Of Wireless (輸入盤CD)(トーマス・ドルビー) 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2014年08月05日
コメント(2)
-

トミー・コンウェル&ザ・ヤング・ランブラーズ 『ランブル(Rumble)』
直球勝負の潔さ トミー・コンウェル(Tommy Conwell)は、フィラデルフィアを起点に活動するギタリスト。ザ・ヤング・ランブラーズ(The Young Rumblers)を率いての自主制作盤(1986年)がきっかけとなって、メジャー契約し、大手(コロンビア)から2枚のアルバムを残すも、3枚目はお蔵入りになり、メジャー・シーンからは姿を消してしまった。現在でも、地元でのライヴ活動やヤング・ランブラーズとの再会ライヴを行ったりしているという。 本盤『ランブル(Rumble)』は、大手の契約を得て1988年に発表されたメジャー・デビュー・アルバムで、大ヒットとはいかないまでの相応のリスナーからの反応を得た。シングル・カットされた1.「アイム・ノット・ユア・マン」がUSメインストリームのチャートで1位(全米では74位)、3.「ネヴァー・ミート・アゲイン」は、メインストリーム9位(全米48位)だから、駆け出しのセールスとしては悪くなかった。 本盤を一度でも通して聴けばすぐにわかるように、とにかくストレートで直球な正統派アメリカン・ロックを身上としている。程よくハードで多少のポップさも忘れない曲とギタープレイ、鍛えられたアメリカン・ロック向けの喉のヴォーカル、いずれもそうしたアメリカン・ロックにぴったりに思える。パティ・スミスのアルバムでギターソロを担当したり、ブライアン・アダムスのライヴで前座を務めた経歴からも、その演奏がイメージできるだろうか。 アルバム全体を通して、抑揚や押したり引いたりといった要素はほとんどない。上記のようなストレートなロックで押しまくって10曲、40分余りという感じ。良くも悪くも最初から最後までまっすぐなのである。その中で目立った曲を強いて挙げれば、シングル曲の上記1.と3.のほか、2.「ハーフ・ア・ハート」、5.「ワークアウト」、10.「ウォーキング・オン・ザ・ウォーター」など、どこを切り取ってもシングルにできそうな印象がある。 コンウェルおよびこのバンドのよさと、人気に火がつかなかった理由は、コインの裏表の関係にあるかもしれない。良くも悪くもまっすぐ。直球アメリカン・ロック好きな筆者にとっては、お気に入りの作品ではあるが、世間での売れ行きや人気という意味では、あまりに一本調子といえなくもない。“ああ、懐かしい”という人も、初めてこの名を耳にしたという人も、“直球好き”には一度(あるいはあらためて)楽しんでいただきたい1枚。[収録曲]1. I’m Not Your Man2. Half A Heart3. If We Never Meet Again4. Love’s On Fire5. Workout6. I Wanna Make You Happy7. Everything They Say Is True8. Gonna Breakdown9. Tell Me What You Want Me To Be10. Walkin’ On The Water1988年リリース。 【中古】 ランブル /トミー・コンウェル&ザ・ヤング・ランブラーズ 【中古】afb 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年08月04日
コメント(0)
-

トレイシー・ネルソンほか 「ダウン・ソー・ロウ(Down So Low)」
名曲「ダウン・ソー・ロウ」聴き比べ 先にシンディ・ローパーのブルース盤『メンフィス・ブルース』を取り上げた際に言及した曲を、動画つきで少し見ておきたいと思います。 「ダウン・ソー・ロウ(Down So Low)」という曲ですが、元々はトレイシー・ネルソン(Tracy Nelson)のペンによるもの。彼女はウィスコンシン出身のシンガーで(同名の女優とは別人)、60年代後半にサンフランシスコへ進出してからは、マザー・アース(The Mother Earth)を結成して活動しました。まずは、トレイシー自身によるこの曲をどうぞ。 様々なアーティストがこの曲を解釈していますが、60年代末から70年代にかけて多くのヒットを残したリンダ・ロンシュタット(Linda Ronstadt)によるカバーをご覧ください。この人は(もちろんいい意味で)いろんな人の楽曲をカバーすることに実に長けていたと思います。 さらに、続いては、思いっきりブルース側に振れた「ダウン・ソー・ロウ」をお聴きください。少し前(2012年)に亡くなった、偉大なブルース、R&Bシンガーのエタ・ジェイムズ(Etta James)による気迫のこもった歌唱です。 そして、最後は、先にアルバムを取り上げたシンディ・ローパーのヴァージョンです。アルバム収録のスタジオ録音のものではなく、その後のツアー中のフランスでのラジオ向けライヴ演奏の様子をどうぞ。 【当店専用ポイント(楽天ポイントの3倍)+メール便送料無料】シンディ・ローパーCyndi Lauper / Memphis Blues (輸入盤CD) (シンディ・ローパー) 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2014年08月02日
コメント(0)
-

シンディ・ローパー 『メンフィス・ブルース(Memphis Blues)』
“虹色の声”の歌姫によるブルースって…? あのシンディ・ローパー(Cyndi Lauper)がブルース曲のアルバムを制作すると聞いて、正直なところ、いったい何事か?、はたまたどんな作品に仕上がるのか?と発売前にはいろんな想像が頭の中を駆け巡った。結局、作品に仕上がってリリースされた盤を聴いた後の感想としては、意外なことに、よくも悪くも驚きはなかった。 メンフィス録音とのことだが、実際、演奏もさほど“もろブルース”ではない。いや、細部や各々のフレーズはブルースなのだが、上記のシンディのヴォーカルが加わると、トータルではやはり“べったりブルース”という感じはしない。想像するに、演奏する側もこの企画の主旨をよく理解していたのだろう。シンディは既成のブルースの形に合わせてアルバムを作ろうとしているのではなく、彼女にしかできない方法でそれらの題材を歌おうとしていた。演奏者もそのことをよくわかっていて、無理やりシンディを自分たちの側に引き込もうとはしていないように感じられる。 今から思えば、過去にもこうしたシンディのアプローチはあった。少なくとも、大ヒットアルバムとなった『トゥルー・カラーズ』収録の「アイコ・アイコ」はそうだったと筆者は感じている。ドクター・ジョンの解釈でよく知られるこの曲だが、シンディは“歩み寄る”というよりは“自分の側に引き込む”形で見事な解釈を提示していた。もちろん、自分側に引き寄せるといっても、その“自分側”にはその対象となる音楽もバックグラウンドとして含まれているということになるのだろうけれど、でもやはり最終的にはそれらも含めて“自分側”のものにしてしまう。いや、シンディだからこそ、見事にできてしまう、と言った方がいいかもしれない。 本盤では、しかもそれをアラン・トゥーサンやB・B・キングらを相手にそれをやっているのだから、やっぱりシンディはただ者ではないといったところか。実際、本盤を巡るシンディの発言として、これら愛してやまない曲を録音することは何年も前から考えていて、メンフィスで実際に時間を過ごした結果、“(生まれ育った)ニューヨークのクイーンズとメンフィスはそんなに離れていない”ことがわかったと述べている。これらの発言はまさしく上で述べた“自分の側に引き込んで”しまう、シンディならではという感じがする。 注目曲としては、アラン・トゥーサンおよびB・B・キングの豪華共演による3.「アーリー・イン・ザ・モーニン(Early in the Mornin’)」。シンディを含めこれら3人の芸風はまちまちな感じだが、不思議とこの曲の元にまとまっている。クリーム(E・クラプトン)で有名なロバート・ジョンソンの11.「クロスロード(Crossroads)」は、5.「ハウ・ブルー・キャン・ユー・ゲット(How Blue You Can Get)」と並んで、“ブルースの天才少年”(といっても既にこの時点で29歳だけれど)、ジョニー・ラングとの共演。この「クロスロード」においても、もろブルースのジョニー・ラングと、自分流シンディの不思議な融合が展開される。さらに、少し異色のナンバーとしてぜひ触れておきたいのが、9.「ダウン・ソー・ロウ(Down So Low)」。ブルースの影響を強く受けた白人女性シンガー、トレイシー・ネルソンの曲で、シンディにはこういう音楽もルーツになっているのかと、その消化ぶりに妙に納得させられたりする。 本アルバムには、賛否両論いろんな意見があったみたいだけれど、リリースから数か月で60万枚の売り上げを記録したという。グラミーにもノミネートされ、140本を超えるツアーも行い、シンディの健在ぶりを印象づけることになった。[収録曲]1. I'm Just Your Fool (feat. Charlie Musselwhite)2. Shattered Dreams (feat. Allen Toussaint)3. Early in the Morning (feat. Allen Toussaint & B.B. King)4. Romance In the Dark5. How Blue Can You Get (feat. Jonny Lang)6. Down Don t Bother Me (feat. Charlie Musselwhite)7. Don't Cry No More8. Rollin and Tumblin (feat. Kenny Brown and Ann Peebles)9. Down So Low10. Mother Earth (feat. Allen Toussaint)11. Crossroads (feat. Jonny Lang)12. Wild Women Don't Have the Blues*13. Don't Wanna Cry (feat. TOKU) * *12.と13.は日本盤ボーナストラック。2010年リリース。 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】【送料無料】メンフィス・ブルース/シンディ・ローパー[CD]通常盤【返品種別A】下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年08月01日
コメント(0)
全20件 (20件中 1-20件目)
1
-
-

- ギターマニアの皆さん・・・このギタ…
- 【ギター×イス軸法®︎】体軸でギター…
- (2024-08-17 21:14:58)
-
-
-

- X JAPAN!我ら運命共同体!
- 手紙~拝啓十五の君へ~(くちびるに…
- (2024-07-25 18:16:12)
-
-
-

- ☆AKB48についてあれこれ☆
- ☆乃木坂46♪NHK「Venue 101」出演集合…
- (2025-11-23 05:02:10)
-







