2014年12月の記事
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-

ジョン・コルトレーンほか 『ウィナーズ・サークル(Winner’s Circle)』
“勝者”たちの共演の楽しみ方とは? 「ウィナー(勝者)のサークル」なるよくわからぬアルバム名。その実態はと言えば、音楽誌(『ダウンビート』)が1957年に発表した批評家の投票結果を元に選んだメンバーの共演作である。オスカー・ペティフォードは、評価の確立されたプレーヤーとして、ジョン・コルトレーンやケニー・バレル、フィリー・ジョー・ジョーンズやアート・ファーマーは新たなスターの枠で選出され、企画盤としてベツレヘムがこれを録音した。 一見してわかるように(下記のパーソネル参照)、奇数曲と偶数曲でメンバーが異なる。ベースとドラムは共通だけれども、その他はメンバーや楽器編成が違う。例えば、コルトレーンは“偶数組”にのみ参加で、一方の“奇数組”はサックスは入っていなかったりする。そんなせいか、交互に違った編成の曲が現れ、聴き手としては、どうも統一感のなさに面食らうことになる。A面とB面で分けた方がすっきりしたのではないかという気さえしてしまう。 全体としては編曲できれいにまとまった感じがする。レギュラーコンボではないが、腕が保証されたミュージシャンが集まったがために、これまでのまとまりができたのだろう。とはいえ、コルトレーンの名や他のメンバーの名につられて、がっつりハードバップなんてものを期待すると、見事に肩透かしを食らうことになってしまう。 このアルバムにそのような期待を抱いてはいけない。むしろ、室内音楽的に静かに鑑賞するタイプの盤なのだという気がしている。実は筆者も最初は“不完全燃焼盤”みたいなイメージをもっていたのだけれど、このように思って聴き始めた途端、本盤は楽しいということに気がついた。特定の誰かの演奏にじっくりのめり込んで聴くタイプではなく、皆の演奏を少しづつつまみ食いして楽しむタイプの盤だということ。“あっ、コルトレーンが来た”、“このケニー・バレルのフレーズがいいよね”、“エディ・コスタのヴァイブ、いいじゃないか”。さらには、“このアンサンブルいいね”、“おお、このクラリネット(ロルフ・キューン)がはまっている”などと戯言を言いながら聴くのがいいのだと思う。 真面目にジャズを聴かないと不快感を示す愛好者もいるだろう。けれども、筆者はこういう“酒のつまみ”的にジャズ作品を聴ける可能性もあることを教えてくれたこの盤に感謝している。追伸:2014年も終わろうとしています。今年1年、ご覧くださった皆さん、本当にありがとうございました。今後とも引き続きご愛顧ください。[収録曲]1. Lazy Afternoon2. Not So Sleepy3. Seabreeze4. Love and the Weather5. She Didn't Say Yes6. If I'm Lucky (I'll Be the One)7. At Home with the Blues8. Turtle Walk[パーソネル、録音]奇数曲:Art Farmer (tp), Rolf Kühn (cl), Eddie Costa (vib), Kenny Burrell (g), Oscar Pettiford (db), Ed Thigpen (ds)1957年9月録音。偶数曲:Donald Byrd (tp), Frank Rehak (tb), Gene Quill (as, 2.のみ), John Coltrane (ts), Al Cohn (bs), Eddie Costa (p), Freddie Green (g, 2.のみ), Oscar Pettiford (db), Ed Thigpen (ds, 2.を除く), Philie Jo Jones (ds, 2.)1957年10月録音。 【楽天ブックスならいつでも送料無料】ウィナーズ・サークル [ ジョン・コルトレーン&アザーズ ]下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月31日
コメント(0)
-

ビクトル・マヌエル 「シン・メモリア(Sin memoria)」
ビクトル・マヌエルの名曲・名唱選(その3) スペインのシンガーソングライター、ビクトル・マヌエル(Víctor Manuel)の曲を取り上げる不定期更新シリーズの第3回です。 彼は主に1980年代に有名曲を多く発表していますが、シンガーとしての最盛期はどこにあるのか、などと考えるにつけ、1990年代の活躍も見過ごすことはできません。優れたライヴ盤(1994年の『ムチョ・マス・ケ・ドス』、1996年の『エル・グスト・エス・ヌエストロ』)だけでなく、ソロとして発表したアルバムにも、その進化の後がしっかりと残されていることではないかと思っています。 そんな観点から、外してはならないと思えるのが、1996年のアルバム、『シン・メモリア』です。さほど注目されたアルバムではなかったかもしれませんが、個人的にはお気に入りで、繰り返し聴いています。今回はその表題曲である「シン・メモリア(Sin memoria)」をどうぞ。 弾き語り風のギター伴奏にいくらかの楽器をかぶせたシンプルな作りで、ヴォーカルで真っ向勝負な感じがします。でもこの作りのおかげでビクトル・マヌエルらしさが実によく出ている曲ではないかと思ったりもします。 “ビクトル・マヌエルらしさ”と言いましたが、具体的には次の二点です。一つは、このヴォーカルの“色気”。男でも(別に“その気”があるわけではありません)ぞくぞくしてしまいそうなこういうヴォーカルは、どこでも簡単にお目にかかれるものではありません。もう一つは、“詩人”としての側面。ビクトル・マヌエルは、シンガーソングライターとして活躍してきましたが、その良さも存分に発揮されています。 ちなみにこの表題は「記憶なしに」という意味で、詞の内容は、“これまでの過去の記憶なしに生きることはできない”というものです。1人称で歌われていますが、人間一般の広い意味にも理解できそうな歌詞で、聴き手に広い解釈の余地を残し得る歌詞になっているように思います。この曲を聴きながら、年末を迎えたこの時期に、1年の記憶を振り返ってみるというのもいいのではないでしょうか。下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月29日
コメント(0)
-

カーティス・フラー 『ボーン&バリ(Bone & Bari)』
J.J.に続くトロンボーン奏者の第二作 何やら意味不明のタイトルに見えるが、“ボーン”はトロンボーン、“バリ”はバリトン・サックスと言われれば、なるほど納得がいく。『ボーン&バリ(Bone & Bari)』は、トロンボーン奏者のカーティス・フラー(Curtis Fuller)が、初リーダー作の『ジ・オープナー』に続いて吹き込んだ第二作である。 トロンボーンという楽器の性質上、ということかもしれないが、この2枚目の盤では、前作のテナーとは違って、バリトン・サックス奏者、テイト・ヒューストンとの組み合わせが選択されている。さらには、1曲目の「アルゴンキン」は、前作とは異なり、ゆったりしたナンバーではなく、マイナーのブルースでありながら、むしろこのトロンボーンとバリトン・サックスという組み合わせを強調するかのような演奏になっている(これがまたスリリングでカッコいい)。 少しトーンを落とした2.「ニタのワルツ」に続き、表題曲の3.「ボーン&バリ」もまた、とりわけテーマ部分が何ともカッコよく、これらの楽器の組み合わせの妙がよく出ている。なおかつ、それを支えるソニー・クラークのピアノをはじめとするリズム陣の活躍もそれぞれのソロで聴くことができる。 他にお気に入りは、同様に4.「ハート・アンド・ソウル」や6.「ピックアップ」で見られる勢いのよさ。前者はゆったりした曲調ながら、小気味よいトロンボーン演奏がミソ。後者は、文字通り勢いに溢れた緊迫感ある演奏で、さりげなくピアノのソロもなかなかいい感じの出来に仕上がっている。 というわけで、どちらかと言えば“静”の印象が強い1枚目に対し、この2枚目では動的なカーティス・フラーの演奏という色合いがより濃いように思う。前作の“柔らかさ”を引き継ぎながら、バリトンとの共演、よりシリアスなソロ演奏と、その魅力を一層増やしているという風に感じる。[収録曲]1. Algonquin2. Nita's Waltz3. Bone and Bari4. Heart and Soul5. Again6. PickupBlue Note 1572[パーソネル、録音]Curtis Fuller (tb)Tate Houston (bs)Sonny Clark (p)Paul Chambers (b)Art Taylor (ds)1957年8月4日録音。 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年12月26日
コメント(0)
-

ワム! 「ラスト・クリスマス(Last Christmas)」
2014クリスマス特集(その4) クリスマスになると、毎年必ず街のどこかで耳にする曲第1位と言えば、はやはりこの曲でしょうか。あまりに有名すぎるナンバーですので、これも過去記事(こちら)でも取り上げていますが、当時は動画がつけられませんでしたので、これを機に動画つきであらためて取り上げておきたいと思います。 80年代に絶大な人気を誇った、ジョージ・マイケルとアンドリュー・リッジリーからなるデュオ、ワム!(Wham!)の「ラスト・クリスマス(Last Christmas)」です。 おそらくこれが多くの人が耳にするワムの「ラスト・クリスマス」でしょうが、このシングル・ヴァージョンとは別に、もう少し長い、7分近いヴァージョンというのがあります。12インチ盤のシングルやアルバムに収録されていたのが、その長い方のヴァージョンで、“プディング・ミックス”という名がついています(最初に見た時、“なんでプリン?”と思ったのですが、結局なぞは解けていません…)。 そんなわけで、今年のクリスマスは4曲しか紹介できませんでしたが、最後は、個人的にもシングル・ヴァージョンよりも好みの「ラスト・クリスマス-プディング・ミックス-」で締めくくりにしたいと思います。 [収録アルバム]Wham! / Music from the Edge of Heaven(1986年)Wham! / The Final(1986年) 【楽天ブックスならいつでも送料無料】ラスト・クリスマス [ ワム! ] 【楽天ブックスならいつでも送料無料】【輸入盤】Music From The Edge Of Heaven [ Wham! ] 【楽天ブックスならいつでも送料無料】ザ・ファイナル [ ワム! ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2014年12月24日
コメント(2)
-
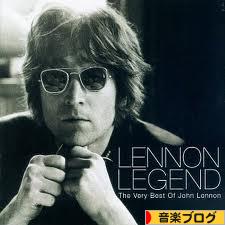
INDEXの更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ→ つづき(H-L)・つづき(M-Z)アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A-E)へ→ つづき(F-N)・つづき(O-Z)アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へアーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月23日
コメント(1)
-

ジョン・レノン&オノ・ヨーコ 「ハッピー・クリスマス(戦争は終わった)(Happy Christmas(War Is Over))」
2014クリスマス特集(その3) ジョン・レノン(最初のリリース段階では、ジョンとヨーコ、プラスティック・オノ・バンドwithハーレム・コミュニティ合唱団、という名義)の「ハッピー・クリスマス(戦争は終わった)(Happy Christmas(War Is Over))」です。この曲は、以前にも一度取り上げているのですが、その頃はブログ自体に動画リンク機能がなかったため、今回、改めて取り上げる次第です。 まずは曲をお聴きください、と言いたいところですが、以下のビデオ、苦手な方は飛ばしてください。リアルに戦争や戦場で人が亡くなったりする場面を含みますので。 前(過去記事)にも書きましたが、邦語副題が“戦争は終わった”となっているものの、実際に歌われている内容は、そうではありません。“君が望むのなら、戦争は終わりになる”というのがより正確ではないかと思います。つまり、裏を返せば、みんなが望むまで戦争はなくならない、そんなメッセージとも言えます。 そのようなわけで、英語の元の歌詞を見ながら、あらためてこの「ハッピー・クリスマス」をじっくりとお聴きいただければと思います。 *2024年11月、動画リンクを差し替えました。↓ベスト盤です↓ ジョン・レノン/レノン・レジェンド 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2014年12月22日
コメント(0)
-
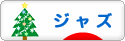
58万アクセス御礼
今日の日中にアクセス数が580000HITを超えました。いつもご覧くださっている皆様に、あらためて感謝申し上げます。今年も残り少なくなりましたが、楽しいクリスマスとよき年末をお過ごしください。下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月20日
コメント(0)
-

ナタリー・コール/ナット・キング・コール 「ザ・クリスマス・ソング(The Christmas Song)」
2014クリスマス特集(その2) 今年のクリスマス曲集、第2回目は、有名な定番曲です。「ザ・クリスマス・ソング(The Christmas Song)」という曲は、ナット・キング・コール(Nat King Cole)で知られるナンバーで、その娘であるナタリー・コール(Natalie Cole)によるこの曲は、実は昨年も取り上げています(過去記事はこちら)。 今回は、同じナタリー・コールが昨年取り上げたものの数年後に発表したクリスマス盤に収録された、一風変わった「ザ・クリスマス・ソング」を取り上げる次第です。同じく交響楽団(この時はロンドン交響楽団)の演奏での歌をお聴きください。 “何が変わっているの?”“ただのデュエットじゃないの?”と言われてしまいそうですが、“亡き父とのデュエット”であるというのが一風変わっている点です。彼女はこの曲以前にも、生前のナット・キング・コールの声とのデュエットというものをやっていて、同じくそれをクリスマス曲にでもやったというわけです。 そんなわけで、今回は、父ナット・キング・コールが歌う「ザ・クリスマス・ソング」もどうぞ。 [収録アルバム]Natalie Cole / The Magic of Christmas(1999年)Nat King Cole / The Christmas Song(1963年)↓父とのデュエットではありませんが、ナタリーによる「クリスマス・ソング」を収録↓ 【送料無料】 Natalie Cole / Mormon Tabernacle Choir / Most Wonderful Time Of The Year 輸入盤 【CD】↓こちらはナット・キング・コールの1961年ヴァージョン収録↓ 【メール便送料無料】ナット・キング・コールNat King Cole / Christmas Song (輸入盤CD)(ナット・キング・コール) 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年12月20日
コメント(2)
-

バンド・エイド30 「ドゥ・ゼイ・ノウ・イッツ・クリスマス?(Do They Know It’s Christmas?)」
2014クリスマス特集(その1) 年の瀬も迫り、気がつけばクリスマス目前…。そんなタイミングですので、数回だけで終わってしまいそうではありますが、今年もクリスマス曲をいくつか取り上げてみたいと思います。 まずは、今年新たにリリースされたこのナンバーから。バンド・エイド30による、エボラ出血熱支援のチャリティとして企画された曲です。 30周年ということでバンド・エイド30という名称なのですが、考えてみれば、生まれた赤ん坊が30歳になるだけの年月ですから大した月日が流れたものです。元々は1984年にボブ・ゲルドフがミッジ・ユーロとともに曲を書いてチャリティ参加を募ったバンド・エイドの曲です。30年前のものはエチオピアの飢餓救済という目的のチャリティでした。 30年前のものは過去(曲紹介、動画紹介)に取り上げていますが、せっかくですので、2014年ヴァージョンと並べる形で、オリジナルのヴァージョン(以前の動画とは別のエクステンデッド・ヴァージョン)もご覧ください。 こうやって比べてみると、1984年に比べ、2014年は全体的に暗いトーンになっている気がします。アレンジのせいと言えばそれまでなのですが、“遠い世界の飢餓”だったエチオピアに比べ、すっかり世界がグローバル化して狭くなって、エボラ熱はもはや対岸の火事ではない、そんな欧州側の“危機感”も思わず想像してしまいます…。 [CD]BAND AID 30 (VARIOUS) バンド・エイド30/DO THEY KNOW IT’S CHRISTMAS?【輸入盤】 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、“ぽちっと”クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2014年12月18日
コメント(0)
-

過去のクリスマス・ソング&アルバム(リンクまとめ)
早いもので、気がつけばあと1週間でクリスマスです。 今年も何回かはクリスマス曲などを取り上げようと思いつつ、まだそれもできていません。とりあえずは過去記事のリンクをまとめるということで、お時間のある方はご覧いただければと思います。 過去のクリスマス曲関連の記事をリストにしてリンクさせました。洋楽・邦楽問わずアイウエオ順(定冠詞Theを除く)にならべてあります。その先の動画などが切れている場合は、ご容赦ください。イーグルス「ふたりだけのクリスマス(Please Come Home For Christmas)」エイミー・グラント『クリスマス・アルバム』エイミー・グラント「エマニュエル」【動画】エイミー・グラント「テネシー・クリスマス」【動画】エルトン・ジョン「ロックンロールで大騒ぎ(ステップ・イントゥ・クリスマス)」・同【動画】GWINKO 「Gwinko’s Christmas Carol」【動画】グロリア・エステファン「きよしこの夜(Noche de Paz)」【動画】ケイト・ブッシュ「ディセンバー・ウィル・ビー・マジック・アゲイン」・同【動画】小林明子・永井真理子・麗美・辛島美登里 「Merry Christmas To You」【動画】佐野元春 「Christmas Time In Blue ―聖なる夜に口笛吹いて―」【動画】ジョン・ボン・ジョヴィ 「プリーズ・カム・ホーム・フォー・クリスマス(Please Come Home For Christmas)」【動画】ジョン・レノン&オノ・ヨーコ「ハッピー・クリスマス(戦争は終わった)」トム・ウェイツ 「 ミネアポリスの女からのクリスマス・カード(Christmas Card from a Hooker in Minneapolis)」【動画】トリーシャ・イヤウッド『ザ・スウィーテスト・ギフト』トリーシャ・イヤウッド「サンタが町へ来る(Santa Claus Is Back In Town)」【動画】トリーシャ・イヤウッド「光の中へ(Take A Walk Through Bethlehem)」【動画】ナタリー・コール 「ザ・クリスマス・ソング(The Christmas Song)」【動画】ザ・バンド 「今宵はクリスマス(Christmas Must Be Tonight)」【動画】バンド・エイド「ドゥ・ゼイ・ノウ・イッツ・クリスマス」・同【動画】プリテンダーズ 「メリー・リトル・クリスマス(Have Yourself a Merry Little Christmas)」【動画】ブルース・スプリングスティーン「サンタが街にやってくる」・同【動画】ボブ・シーガー&ザ・シルバー・ブレット・バンド「リトル・ドラマー・ボーイ」・同【動画】山下達郎 「クリスマス・イブ(Christmas Eve)」【動画】ラウラ・パウジーニ「きよしこの夜(Noche de Paz)」【動画】ルイス・ミゲル「きよしこの夜(Noche de Paz)」【動画】ルイス・ミゲル『ナビダーデス』麗美 「走るそよ風たちへ」【動画】ワム!「ラスト・クリスマス」 【メール便送料無料】トリーシャ・イヤーウッドTrisha Yearwood / The Sweetest Gift (輸入盤CD)(トリーシャ・イヤーウッド) 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】クリスマス・イブ(30th ANNIVERSARY EDITION)/山下達郎[CD]通常盤【返品種別A】 【CD】Cafe Bohemia/佐野元春 [MHCL-30005] サノ モトハル Very Special Christmas 輸入盤 【CD】下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月17日
コメント(0)
-

ビクトル・マヌエル 「アストゥリアス(Asturias)」
ビクトル・マヌエルの名曲・名唱選(その2) スペインのシンガーソングライター、ビクトル・マヌエル(Víctor Manuel)を取り上げる不定期シリーズ第2弾です。この人の出身地はというと、いかにもスペイン中央部(カスティーリャ・ラ・マンチャ)や、よくフランメンコのイメージで語られる南部のアンダルシアといった場所のではなく、北部のアストゥリアスという少々マイナーなところです。行ったこともないので、よくわかりませんが、個人的には“陽気なスペイン”のイメージとはちょっと違った地域なイメージを持っています。さらに余談ながら、スペインの王位継承予定者(皇太子)は、代々、アストゥリアス王子の称号を持ち、最近、スペインの王は交代したので、現在はまだ9歳の娘さん(レオノール王女)がその地位にいます。 そんな出身地アストゥリアスを真っ向からタイトルにしたのがこの「アストゥリアス(Asturias)」という曲です。ペドロ・グラフィアという人の詩にビクトル・マヌエルが曲をつけたらしいのですが、スペインではまだフランコが生きていた時代ゆえ、詩が作られた70年段階では検閲にあって、結局はフランコ没後の76年まで公にされなかったということのようです。 1934年の十月革命、第二共和政後の抑圧などが登場し、アストゥリアスを擬人化して語り掛けるような口調が印象的です。まずは若い頃(といっても30歳代の末)の映像からご覧ください。1986年のライヴ映像とのことです。 続いては、この同じ曲の、近年の演奏の様子をもう一つ。昨年(2013年)、オーケストラを従えてのビクトル・マヌエルの歌唱です。見た目は白髪の老境に入りつつありますが、この曲の雰囲気がよく伝わる好演ではないかと思ったりする次第です。 下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月14日
コメント(0)
-

スティーヴ・ウィンウッド 『ジャンクション・セヴン(Junction Seven)』
天才の変わらぬ天才ぶり スティーヴ・ウィンウッド(Steve Winwood)は、1948年英国バーミンガム出身で、60年代以降、スペンサー・デイヴィス・グループを皮切りに、トラフィック、ブラインド・フェイスなど様々なバンドやプロジェクトに参加し、その天才ぶりを発揮してきた。ヴォーカル、キーボードだけでなく、何の楽器でもこなせるマルチプレーヤーで、70年代途中からは主にソロでその才能を発揮してきた。 ソロになってからの彼のヒット作と言えば、セカンド・アルバムの『アーク・オブ・ア・ダイヴァー』や、1986年の『バック・イン・ザ・ハイ・ライフ』を思い浮かべる人も多いだろう。では、逆にあまり売れなかったりチャートアクションが少なかった作品はと言えば、1997年の本盤『ジャンクション・セヴン(Junction Seven)』か、はたまたそれに続く2003年の『アバウト・タイム』かといったあたりになるだろうか。本盤『ジャンクション・セヴン』は、英国チャートはともかく、全米ではともに最高位が100位圏外と、彼のキャリアの中では明らかに“振るわなかった”アルバムである。 では聴く価値なしかというと、決してそんなことはないように思える。面白いのは、英国チャートでは本作は32位まで上がっていて(『アバウト・タイム』の方は英国チャートでも順位はいまいちだった)、アメリカ人にはそっぽを向かれたが、イギリスではそれなりにちゃんと聴かれたということなのだろう。 実際、その内容は悪くない。というか、相変わらずの天才ぶりが着実に収められた好盤と言っていいように思う。これまで通り、ウィンウッドはマルチプレーヤーぶりを発揮していて、ヴォーカル、ギター、ハモンド・オルガン、ピアノ、クラヴィネット、パーカッションなどを担当している。必要なところに必要なミュージシャンをという、彼のソロ活動のある時点から明確になった方針も継承されていて、参加ミュージシャンの中では、レニー・クラヴィッツ(4.にギターで参加)やナラダ・マイケル・ウォルデン(複数曲でベース、パーカッション、ドラム等を担当)あたりが目を引く。 冒頭の1.「スパイ・イン・ザ・ハウス・オブ・ラヴ」は、ソロ転向後のスティーヴらしいナンバーで、ギターがさりげなくカッコいい。全体としてはゲスト・ミュージシャンを迎えながらバンド・サウンド的まとまりの曲が多いけれど、5.「リアル・ラヴ」のように、もろバラード風な曲もあって、良くも悪くも抑揚がついたアルバムになっていると思う。 少し面白いのは、ラテン・ダンス風の7.「ゲット・バック・トゥ・マイ・ベイビー」で、サルサのリズムを取り入れた異色曲となっている。この異色なナンバーがさらに面白いのは、スティーヴ・ウィンウッドが歌うと半分ヴォーカリストとしての彼の世界、もう半分が曲調によるラテンな世界という不思議な組み合わせのように聞こえる点だと思う。つまりは、これほど劇的に違うタイプの曲をやっても、残り半分の彼の歌の表現者としての世界は崩れ去らないとういのが興味深い。[収録曲]1. Spy in the House of Love2. Angel of Mercy3. Just Wanna Have Some Fun4. Let Your Love Come Down5. Real Love6. Fill Me Up7. Gotta Get Back to My Baby8. Someone Like You9. Family Affair10. Plenty Lovin'11. Lord of the Street1997年リリース。 【中古】輸入洋楽CD STEVE WINWOOD / JUNCTION SEVEN[輸入盤]【P06Dec14】【画】 【メール便送料無料】STEVE WINWOOD / JUNCTION SEVEN (輸入盤CD) 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2014年12月11日
コメント(0)
-

ザ・ビートルズ 「イエス・イット・イズ(Yes It Is)」/「カム・トゥギャザー(Come Together)」
ビートルズ時代のジョン・レノン曲(後編) 前編に続き、ビートルズ時代のジョン・レノンの曲をお届けしますが、この後編では、少々“シブめ”の選曲で、ビートルズ時代のジョンのナンバーを取り上げたいと思います。 まずは「イエス・イット・イズ(Yes It Is)」という曲です。元々は「涙の乗車券(チケット・トゥ・ライド)」(1965年)のB面曲でしたが、シングル以外では、アメリカ盤ではとあるアルバムに収録されたものの、イギリスではバンドの解散後まで正式なアルバムには収録されず、疑似ではない本当のスタジオ・バージョンは1988年の編集盤(『パスト・マスターズ』)で初めて公開されました。余談ながら、過去記事ではこんなカバーも取り上げたりしています。 さて、ジョンの曲を取り上げだすときりがなくなってしまうのですが、今回はもう1曲、定番ながらビートルズ後期の最高にカッコいいナンバーでまとめにしたいと思います。『アビー・ロード』所収の、「カム・トゥギャザー(Come Together)」です。元のアルバム・ヴァージョンではなく、ビートルズ後のソロとしてのニューヨーク市でのライヴのテイクをどうぞ。 1980年、銃弾によってジョンは40歳で亡くなってしまいました。自分自身がその歳をとっくに過ぎてしまったというのも、あらためて思い返せばそれはそれでショックなのですが、もしもジョンが存命であれば現在では74歳になっているはずでした。ありきたりながら、あらためてご冥福を祈りつつ、この12月を実感したいと思います。[収録アルバム]The Beatles / Past Masters Vol. 1(1988年)←Yes It Is収録。The Beatles / Abbey Road(1969年)←Come Together収録。 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】【送料無料】アビイ・ロード/ザ・ビートルズ[CD]【返品種別A】 【RCP】【Joshinはネット通販部門1位(アフターサービスランキング)日経ビジネス誌2013年版】【送料無料】パスト・マスターズ/ザ・ビートルズ[CD]【返品種別A】 下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月07日
コメント(4)
-

ザ・ビートルズ 「イン・マイ・ライフ(In My Life)」/「ジュリア(Julia)」
ビートルズ時代のジョン・レノン曲(前編) 12月初旬になるとジョン・レノンの曲が流れ始める…。かつてはそんなイメージがあったのですが、どうも最近そうした機会が減っているのではないかと危惧しています。10月になったら一気呵成にハロウィーンを宣伝し、それが過ぎたら次はクリスマス、12月25日を超えたら一気にお正月気分で…といった商業主義が蔓延してきたせいなのか、はたまたジョン・レノンの殺害という衝撃的ニュースから30年以上ということで、あまりに時が流れ過ぎたのか…。 もちろん、12月が来たからジョンを思い出すといった、“年間行事”を煽るつもりはありません。普段から折に触れて、ジョンの作品を聴く機会もそれなりにありますが、今回はなぜかこのタイミングで、先月半ば頃からビートルズのアルバムを立て続けに聴きたくなるという気分になり、ここ数週間は車の中でもビートルズのオンパレードといった状態でした。 そんなわけで、ジョン・レノン死去から34年となる今年は、ビートルズ時代のジョン・レノン・ナンバーをいくつか動画で取り上げようと思います。 まずは“美しい曲”というキーワードで、2曲ほど取り上げたいと思います。まずはここ数日繰り返し聴いている『ラバー・ソウル』(1965年)の収録曲で、「イン・マイ・ライフ(In My Life)」です。 さらにもう1曲、『ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)』(1968年)に収められた、ナンバーを行きたいと思います。今回、このアルバムは、上で述べた“突如聞きたい気分”の発端になったアルバムでした。その中でポールの「アイ・ウィル」と並んで忘れがたい名曲、「ジュリア(Julia)」です。 よく知られてはいますが、ジュリアというのはジョンが若い頃に亡くなった母親の名前です。とはいえ、歌詞の中にはオノ・ヨーコを思わせる語句(“オーシャン・チャイルド”=洋子)もあり、母親をテーマにしつつも、妻となった小野洋子に言及している、そんなナンバーです。 さらに続きをというところですが、長くなってきたので項を改め、もう1回おつきあいいただければと思います。(後編へ続く)[収録アルバム]The Beatles / Rubber Soul(1965年)←In My Life収録。The Beatles / The Beatles (White Album)(1968年)←Julia収録。 【送料無料】ラバー・ソウル/ザ・ビートルズ[CD]【返品種別A】 【送料無料】ザ・ビートルズ(ホワイト・アルバム)/ザ・ビートルズ[CD]【返品種別A】下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2014年12月06日
コメント(0)
-

57万アクセス御礼
先程、当ブログの累計アクセス数が570000HITに達しました。ご覧くださっている皆さまに、あらためて感謝申し上げます。今後とも引き続きご愛顧ください。 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年12月05日
コメント(0)
-

INDEX更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。 INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ右欄(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-L)・つづき(M-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A-E)へ → つづき(F-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系(ロック・ポップス)編へ アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓ にほんブログ村 : 人気ブログランキング:
2014年12月03日
コメント(0)
-

タニア・リベルター 「アルフォンシーナと海(Alfonsina y el mar)」(2/2)
海へ身を投げた女性詩人の物語(後編) 今日から12月ですが、記事内容は昨日の前編からのつづきです。引き続き、ペルー出身でメキシコを舞台に活躍する女性シンガー、タニア・リベルター(Tania Libertad)による「アルフォンシーナと海」の動画を取り上げてみます。 この曲の詞に歌われているアルフォンシーナというのは、人物名(女性の名前)です。しかも、それは実在の人物で、有名なアルゼンチンの女流詩人のアルフォンシーナ・ストルニという人です。 アルフォンシーナは1892年、両親が滞在していたスイスに生まれ、物心がつく前にはアルゼンチンに戻って、1910年代から詩人として活躍しました。しかし、若くして乳癌に侵され、1938年に46歳でマル・デル・プラタの水面に身を投げその生涯を閉じたのです。 彼女の死については、しばしばロマンチックに静かな自殺だったと言われたりします。「アルフォンシーナと海」という曲は、このストーリーが題材となっています。ひとり孤独に、静かに海に眠るアルフォンシーナ、というわけです。 こうした背後にあるストーリーを知れば、次の悲しげでかつドラマチックなヴァージョンの雰囲気も納得ということになるでしょうか。 最後にライヴのものも、ということで、比較的最近と思しきライヴの歌声をどうぞ。“アメリカの声”と呼ばれたメルセデス・ソーサ(2009年没)亡き後、「アルフォンシーナ~」を歌い継いでいくのは、この人しかいないと思ったりする次第です。 [収録アルバム]Tania Libertad / Alfonsina y el mar(1989年)その他、ベスト盤・ライヴ盤等にも収録。 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーを“ぽちっと”応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2014年12月01日
コメント(0)
全17件 (17件中 1-17件目)
1
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- サーカスパフォーマーまおのライブ
- (2025-11-23 13:17:54)
-
-
-

- 福山雅治について
- 福山雅治PayPayドームライブ参戦
- (2025-09-29 12:53:35)
-
-
-
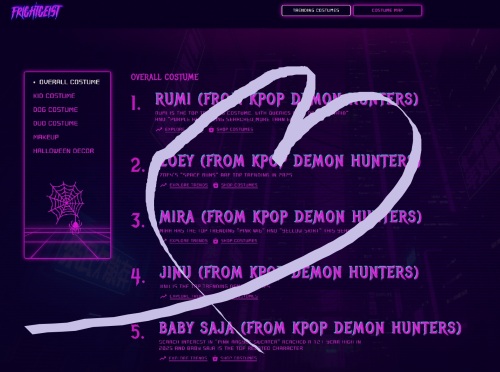
- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 영원히 깨질 수 없는
- (2025-11-11 06:13:39)
-







