全3256件 (3256件中 1-50件目)
-

ジョ・ジョ・ガン 『ジャンピング・ザ・ガン(Jumpin' the Gunne)』
玄人好みの真摯でハードなロック 1973年、セカンド作に続いて同年に発表されたのが、ジョ・ジョ・ガン(Jo Jo Gunne)のサード作となる『ジャンピング・ザ・ガン(Jumpin' the Gunne)』だった。前作に続き、ビル・シムジク(イーグルスの作品などで知られるプロデューサー)がプロデュースを担当している。 部屋に置かれた大きなベッドにメンバー4人がいて、その上を太った裸の(靴だけ履いている)女性が飛んでいるという、シュールかつ、今の時代だと“人を不快にさせる”というクレームがつきそうなジャケット(さらに、ジャケット内側では、曲目やクレジットの文字が体に書かれたこの女性がうつ伏せになって子豚?と向き合うという構図の写真で、今のどきの世の中だと受け入れられないかもしれない)。この見かけとは裏腹に、本盤の内容は真摯なロック・アルバムだったりする。前作よりもややキャッチーな部分が強くなっているように思うところもあるが、全体として骨のあるしっかりとしたハードなロックを聴かせてくれる。 筆者の好みに合致するナンバーをいくつか挙げておきたい。2.「トゥ・ジ・アイランド」は、ジョ・ジョ・ガンらしいナンバーの一つ。派手にパフォーマンスをするというよりも、真摯に、そして(もちろんいい意味で)下を向きながらこつこつと演奏してそうな雰囲気が想像されるところが個人的にはプラスの評価ポイントだったりする。 楽器音の厚み、とりわけ低音の“圧”を感じる演奏は彼らの身上である。そんな点から筆者の好みはというと、5.「ビフォー・ユア・ブレクファースト」、7.「モンキー・ミュージック」、11.「ターン・ザ・ボーイ・ルーズ」といった楽曲が挙げられる。ある程度の音量と低音を感じられる装置で聴くと、このバンドの演奏の分厚さはてきめんに浮き彫りになる。決して万人受けしそうなスタイルではないし、広く人気を得そうな派手さもない。けれども、こうした玄人受けの良質な演奏というのは、聴き継がれてもらいたいところだと思ってみたりする。[収録曲]1. I Wanna Love You2. To the Island3. Red Meat4. Getaway5. Before You Get Your Breakfast6. At the Spa7. Monkey Music8. Couldn't Love You Better9. High School Drool10. Neon City11. Turn the Boy Loose1973年リリース。 【中古】【非常に良い】Jo Jo Gunne/Bite Down Hard/Jumpin the Gun & So [CD] 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年11月25日
コメント(0)
-

ブルース・スプリングスティーン 「僕の父の家(My Father’s House)」/「生きる理由(Reason to Believe)」
『ネブラスカ』全曲紹介(最終回) ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)のアルバム『ネブラスカ(Nebraska)』の全曲紹介を目指してきましたが、この5回めがようやく最終回となります。 残る2曲のうち最初の曲は、「マイ・ファーザーズ・ハウス(My Father’s House)」です。邦盤では「僕の父の家」という日本語訳のタイトルが与えられています。この曲は、アルバム完成前に追加で録音されたナンバーとのことですが、割合いにシンプルな弾き語り形式でストーリーが語られていきます。 その詞のストーリーはというと、昨晩見た夢の中の、幼いころの父の家の記憶から始まります。目が覚めた主人公は、その場所へと向かいます。おそらくは何らかのわだかまりか何かで絶縁していたであろう父を訪ねに行くわけです。けれども、そこにはもう父はいません。その家には見知らぬ女性が住んでいて、主人公が自分の経緯を話した末にドアチェーンの向こうから“お気の毒だけれど、そんな名前の人はもうここには住んでいないわ”と告げられてしまうのです。それでも主人公にとって“父の家”は輝いて見えているという、なんとも悲しげな結末のストーリーです。 さて、アルバム最後のナンバーは、「リーズン・トゥ・ビリーヴ(Reason to Believe)」です。邦盤では「生きる理由」という日本語のタイトルがついています。直訳なら“信じる理由”なのですが、意訳されてこのような表題になっているということなのでしょう。小刻みなギター、ハーモニカの間奏とともに心情を吐露するかのような調子で歌詞が紡がれていきます。 その詞の内容を少し見てみたいと思います。辛い労働に追われる人たちが“ハードな一日の終わりに、それでも人は何がしかの信じる理由を見出そうとする”という現実が果たして妥当なのかを問いかけるものです。具体的ないくつかの人生ストーリーが語られているのですが、例えば、突然姿を消した愛するジョニーを待ち続けるメアリー・ルーの話が出てきたりします。男性の名が「ジョニー99」の“ジョニー”と重なり合いますが、もしかすると同一人物なのかもという印象を聞き手は持つかもしれません。また、別の人生模様の描写には、罪を背負った赤ん坊を川で洗うという話が出てきます。そして、これと並行して人知れず死んでいく老人の埋葬が描写されます。筆者には、誕生と死の間(つまりは人が生きている間)にある、辛い人生の苦悩というのが婉曲的に語られているというように見えるのですが、印象的なのは埋葬時の“主よ、これが何を意味するのか、お教えください”という意味深な台詞。この台詞の直後に“ハードに働いた一日の終わりに、あなたは何がしかの信じる理由を見出す”の決め文句(邦訳歌詞カードには反映されていませんが、この箇所だけはアレンジが加えられていて、“人々は”ではなく“あなた”が主語になっています)が続くというものです。 最後に、この「生きる理由」の中で、筆者がいちばん印象に残っている詞に触れておきたいと思います。それは、結婚式に新婦が現れなかったストーリーの部分に含まれています。新婦が現れなかった末に、祝福に訪れていたはずの人たちは去ってしまい、“泣いている柳”の向こうに陽が沈んでいきます。最後に呆然と立ち尽くす新郎の脇で“川は苦も無く流れ続ける”という詞が出てきます。この“苦も無く(effortlessly)”というのが、努力(effort)を払って必死に生きて、それでもなお希望を持ち続けようとしている姿と痛々しいほどの、けれどもはっきりとした対比となっているところが印象的だったりします。 以上、全5回にわたって、『ネブラスカ』の全曲を見てきました。今回のリマスター版リリースを機に改めて聴き続けられる古典的アルバムであってほしいと思っています。元アルバム過去記事: ブルース・スプリングスティーン『ネブラスカ』(1982年リリース)『ネブラスカ』全曲紹介:第1回(「ネブラスカ」)第2回(「アトランティック・シティ」、「マンション・オン・ザ・ヒル」、「ジョニー99」)第3回(「ハイウェイ・パトロールマン」、「ステイト・トルーパー」)第4回(「ユーズド・カー」、「オープン・オール・ナイト」)第5回(「僕の父の家」、「生きる理由」)(本記事) 【送料無料】[枚数限定][限定盤]NEBRASKA 82: EXPANDED EDITION (4CD+BLU-RAY)【輸入盤】▼/ブルース・スプリングスティーン[CD+Blu-ray]【返品種別A】 ネブラスカ [ ブルース・スプリングスティーン ] ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年11月22日
コメント(0)
-

ブルース・スプリングスティーン 「ユーズド・カー(Used Cars)」/「オープン・オール・ナイト(Open All Night)」
『ネブラスカ』全曲紹介(第4回) ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)のアルバム『ネブラスカ(Nebraska)』の全曲紹介の続きです。なかなか最後までたどり着きませんが、いましばらくお付き合いください。 アルバムの7曲目(LPのB面としては2曲目)は、「ユーズド・カー(Used Cars)」、要は“中古車”です。シンプルな弾き語り調の中、この曲では、語り手の子どもの頃の情景が、夢に出てきた話として語られています。しかし、その夢の中の情景は、決して穏やかな子供時代の思い出ではありません。“朝から朝まで汗水たらして同じ仕事”をする父親が新車は買えず、新しい中古車を買うシーンです。貧しさから抜け出せない状況を目の当たりにしもどかしく感じている主人公は、“宝くじに当たった日には、俺は中古車なんかには乗らない”と締めくくります。つまりは、夢で思い出した子どもの頃の体験、父親の自動車(中古車の購入)というエピソードを通じて、変えようのない社会的現実が語られるわけです。そして、この曲の主人公も、おそらくは新車を買えない境遇にいる…。そんな彼の境遇が“中古車”、“宝くじ”というキーワードで語られるわけです。これもまた、当時のアメリカの労働者階級の社会的苦悩を示唆するストーリーになっていると言えるでしょう。 続く「オープン・オール・ナイト(Open All Night)」は、『ネブラスカ』の収録曲のうち、唯一エレキギターを使用しているナンバーで、ロカビリー調の演奏です。他の曲に比べるとリズム感のあるナンバーですが、詞の内容はというと、これもまた明るいものではありません。彼女のもとへ一人で暗い夜中に車を走らせる男の心情を赤裸々に歌ったものです。最後には朝が明け、依然として車を走らせ続けている場面で曲は終わるのですが、興味深いのは最後の部分の詞です。混線するラジオを聞きながら、彼はDJに対して“最後の祈りを聞いてくれ”と訴えかけます。その祈りというのは、最後の方は掛け声と混じってわかりにくいのですが、曲をよく聴くと“このどうしようもない状態から抜け出させてくれ”というものになっています(歌詞カードでは明確にこの文言で詞は終わっています)。そう、先の「ステイト・トルーパー」という曲と同じセリフが締め括りになっているわけです。曲の配置(LPの曲順でも、「ステイト・トルーパー」はB面の最初の曲で、この曲はB面の3曲目)を考えても、おそらくスプリングスティーンは意図的に同じ言葉で語ることのできる結末を用意したのだろうと思います。 『ネブラスカ』の収録曲、見れば見るほどテーマの重たさを感じるわけですが、あと2曲については、次回の更新記事で取り上げたいと思います。元アルバム過去記事: ブルース・スプリングスティーン『ネブラスカ』(1982年リリース)『ネブラスカ』全曲紹介:第1回(「ネブラスカ」)第2回(「アトランティック・シティ」、「マンション・オン・ザ・ヒル」、「ジョニー99」)第3回(「ハイウェイ・パトロールマン」、「ステイト・トルーパー」)第4回(「ユーズド・カー」、「オープン・オール・ナイト」)(本記事)第5回(「僕の父の家」、「生きる理由」) 【送料無料】[枚数限定][限定盤]ネブラスカ '82:エクスパンデッド・エディション/ブルース・スプリングスティーン[Blu-specCD2+Blu-ray]【返品種別A】 ネブラスカ [ ブルース・スプリングスティーン ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年11月20日
コメント(0)
-

ブルース・スプリングスティーン 「ハイウェイ・パトロールマン(Highway Patrolman)」/「ステイト・トルーパー(State Trooper)」
『ネブラスカ』全曲紹介(第3回) ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)のアルバム『ネブラスカ(Nebraska)』の収録曲を順に紹介していますが、今回はその第3回です。元のアルバムの収録曲的には、A面の最後とB面の最初という、少々アンバランスな巡り合わせになってしまうのですが、それら2曲を見ていきたいと思います。 アルバムの5曲目で、LPのA面最後の曲に当たるのが、「ハイウェイ・パトロールマン(Highway Patrolman)」です。これもまた1人称の語りで進んでいく詞なのですが、表題通り、高速道路のパトロールをしているジョー・ロバーツなる人物がその語り手です。曲のテーマは、彼自身の弟で、問題児のフランキーです。フランキーの人生模様が語られ、最後は、警官をしている兄が弟の起こした事件現場に立ち会い、その弟は逃走犯となって姿を消していくというストーリーになっています。このフランキーというのは兵役から戻ってきた、つまりは帰還兵で、ヴェトナム戦争帰還者をモチーフにした「ボーン・イン・ザ・USA」と同じく、アメリカの影の部分を想起させます(実際のところ、「ボーン~」もこのアルバムの時期に書かれた楽曲でした)。 お気に入りの曲なので話が長くなってしまうのですが、この「ハイウェイ・パトロールマン」の詞で決め文句になっているのは“家族に背を向けるなんて、よくない奴だ(Man turns his back on his family, well he just ain’t no good)”という部分だと思っています。弟の過去の話を語るヴァースの最期にもこのセリフがあれば、事件の経緯が明かされた後の曲の最後の締めくくりにもこのセリフが出てきます。付属の歌詞カード(邦訳)ではあまり印象的ではないのですが、元の詞を見ると、個人的にはこのセンテンスがキーになっているように思います。ちなみに、この曲を元ネタに俳優のショーン・ペンが映画「インディアン・ライナー」の脚本を書き、監督デビューしているというエピソードもあったりします。 さて、ここからはアルバムの後半、LPではB面に収録されていた曲です。後半最初の曲は、「ステイト・トルーパー(State Trooper)」です。演奏は何ともおどろおどろしい感じなのですが、それもそのはず。詞の内容はというと、自動車の免許も登録もない男が、警官に怯えてどうか止められないようにと心で叫んでいる、その悲痛な声を歌にしたものです。下層労働者が苦しみの中、“最後の祈り”として、“このどうしようもない状態から抜け出させてくれ”という悲痛な声を発するところで曲は終わっているのが印象的です。 さて、今回はここまでということにします。続きは次の第4回で見ていくことにしたいと思います。元アルバム過去記事: ブルース・スプリングスティーン『ネブラスカ』(1982年リリース)『ネブラスカ』全曲紹介: 第1回(「ネブラスカ」)第2回(「アトランティック・シティ」、「マンション・オン・ザ・ヒル」、「ジョニー99」)第3回(「ハイウェイ・パトロールマン」、「ステイト・トルーパー」)(本記事)第4回(「ユーズド・カー」、「オープン・オール・ナイト」)第5回(「僕の父の家」、「生きる理由」) ネブラスカ '82 エクスパンデッド・エディション [ ブルース・スプリングスティーン ] 【送料無料】[枚数限定][限定盤]ネブラスカ '82:エクスパンデッド・エディション/ブルース・スプリングスティーン[Blu-specCD2+Blu-ray]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年11月19日
コメント(0)
-

ブルース・スプリングスティーン 「アトランティック・シティ(Atlantic City)」/「マンション・オン・ザ・ヒル(Mansion on the Hill)」/「ジョニー99(Johnny 99)」
『ネブラスカ』全曲紹介(第2回) ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)のアルバム『ネブラスカ(Nebraska)』の全曲紹介の2回目です。 アルバムの2曲目は「アトランティック・シティ(Atlantic City)」というナンバーです。このアトランティック・シティという町は、アメリカ東海岸随一のカジノがある観光都市で、スプリングスティーンの故郷であるニュージャージー州にあります。弾き語るというよりは確かなテンポで歌っていて、コーラスが印象的です。ハーモニカの間奏も聴き手の脳裏に残りやすいものになっています。詞の内容は、カジノにはまってしまい、返しようのない借金を抱え込んだ男が危ない世界に足を踏み入れていこうとする姿。その状況が、主人公を1人称にした形で語られていきます。当然、犯罪に手を染めるこの男(詞の中にはその恋人がいることも明示されています)が悲惨な末路を迎えるであろうことは想像に難くありません。そして、こういう境遇の男だからこそ、”ベイビー、あらゆるものは死ぬという運命なのさ”と言いつつも、”きっと、死んだものはすべて、いつか蘇るのさ”と儚い希望を口にするわけです。 続く3曲目は、「マンション・オン・ザ・ヒル(Mansion on the Hill)」です。そのまま日本語に訳せば、“丘の上の邸宅”となるでしょうか。殺人や犯罪というテーマの最初の2曲に比べれば、一見して牧歌的なナンバーです。というのも、幼い頃ないしは少年時代の情景といったようなものが詞になっているからで、トウモロコシ畑で遊ぶ姉弟の姿などはそんな印象を与えます。けれども、実のところ、その情景というのは、工場務めをする労働者階級の人とその家族が見上げる丘の上の大きな家が主題になっているのです。つまり、この階層の人たちは、永遠にそこに住むことはなく、いつもその邸宅を見上げるだけ。だからこそ、曲の最後は、現在に時間が飛び、工場から帰宅する車の渋滞の列で、自分自身が“丘の上の家の上に”輝く美しい満月を見上げるという情景描写で締めくくっています。 さて、4曲目は「ジョニー99(Johnny 99)」。表題の“ジョニー99”(99は“ナインティーナイン”と読みます)は、この曲の詞の主人公のあだ名です。職探しがうまくいかず、あげくに泥酔して店員を撃ち殺したラルフなる主人公は、懲役98年プラス1年(つまり99年)の判決を受けて服役することになり、こう呼ばれたわけです。この曲では、ラルフは、最初は3人称(“彼”)で語られている。それが次第に1人称(“私”)に変わっていき、最後は、判決をやり直せるものなら死刑にし、“俺を処刑場へ送ってくれないか”と悲痛な叫びをあげます。ファルセットの部分を含め緊迫感のあるヴォーカルが、この心情の吐露を赤裸々に伝えるという、そんな1曲に仕上がっています。 今回はここまでということで、次回(第3回)に続きます。元アルバム過去記事: ブルース・スプリングスティーン『ネブラスカ』(1982年リリース)『ネブラスカ』全曲紹介: 第1回(「ネブラスカ」)第2回(「アトランティック・シティ」、「マンション・オン・ザ・ヒル」、「ジョニー99」)(本記事)第3回(「ハイウェイ・パトロールマン」、「ステイト・トルーパー」)第4回(「ユーズド・カー」、「オープン・オール・ナイト」)第5回(「僕の父の家」、「生きる理由」) 【送料無料】[枚数限定][限定盤]ネブラスカ '82:エクスパンデッド・エディション/ブルース・スプリングスティーン[Blu-specCD2+Blu-ray]【返品種別A】 ネブラスカ [ ブルース・スプリングスティーン ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年11月17日
コメント(0)
-

ブルース・スプリングスティーン「ネブラスカ(Nebraska)」
『ネブラスカ』全曲紹介(第1回) 今年(2025年10月)、ブルース・スプリングスティーンの1982年作『ネブラスカ』(過去記事)の“エクスパンデッド・エディション”なるものが発売されました。4枚組(+ブルーレイ1枚)という内容については、またいずれ取り上げようと思うのですが、その内の1枚が“2025リマスター”(つまりは元アルバムと同じ内容のリマスター)だったということもあり、せっかくなので、何回かに分けて、この名盤の収録曲全部を順に取り上げてみたいと思った次第です。 自宅で4チャンネルのいわば“自炊録音”のようなローファイ音源のリマスターで音がどれほど改善されるのか、と思いながらリリースされたリマスター音源のCDを聴いたのですが、限界(特にヴォーカル)はあるものの、とりわけギターやハーモニカの楽器部分の音質はかなりクリアになっているという印象を受けました(と言っても、元のクリアでないこもった感じの方がいいという人もいるかもしれませんが)。ともあれ、そのリマスター版を聴きつつ、全10曲を見ていくことにしたいと思います。 アルバムの最初のナンバーはアルバム表題曲の「ネブラスカ」。物悲し気なハーモニカで始まるギターによる弾き語り調のこの曲は、米国で実際に起きた凄惨な事件を題材にしています。1957~58年、ネブラスカ州とワイオミング州で11人を殺害した19歳の少年(チャールズ・スタークウェザー)は、裁判で死刑を宣告され、1959年に死刑となりました。犯罪の過程では、付き合っている14歳の少女とも一緒だったというショッキングな事件です。 この少年を1人称にして語っていくというのが、この「ネブラスカ」の詞です。“俺は行く手にあるあらゆるものを殺していった”、“少なくともしばらくの間、俺と彼女は楽しく過ごした”といった具合に事件の経緯を語り、“俺は生きていてはいけないと宣告された”と歌う。曲の締めくくりが印象的で、“彼らはなぜ俺がそんな行為をしたのかを知りたがった”、けれども、“この世には、意味もなく卑劣な行為ってものもあるんだよ”と曲は終わります。なんとも思わせぶりというか、聴き手に考えさせる投げかけ方です。元々、ストーリーテラーとしての能力に秀でていたスプリングスティーンですが、とりわけこの盤はその側面がこれ以降の曲でも先鋭的に現れていきます。 このような感じで全10曲(残り9曲)を見ていくということで、次項に続きます。元アルバム過去記事: ブルース・スプリングスティーン 『ネブラスカ』(1982年リリース)『ネブラスカ』全曲紹介: 第1回(「ネブラスカ」)(本記事)第2回(「アトランティック・シティ」、「マンション・オン・ザ・ヒル」、「ジョニー99」)第3回(「ハイウェイ・パトロールマン」、「ステイト・トルーパー」)第4回(「ユーズド・カー」、「オープン・オール・ナイト」)第5回(「僕の父の家」、「生きる理由」) ネブラスカ '82 エクスパンデッド・エディション [ ブルース・スプリングスティーン ] ネブラスカ/ブルース・スプリングスティーン[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年11月15日
コメント(0)
-

INDEX更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事へのリンクを追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも ありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年11月14日
コメント(0)
-

ルパート・ホルムズ 『パートナーズ・イン・クライム(Partners in Crime)』
ヒット曲を含むAORシンガーとしてのピークを示す盤 ルパート・ホルムズ(またはルパート・ホームズ, Rupert Holmes)は、1947年、イギリス出身で、幼くしてニューヨークへ移り住んで育った。洒落た都会的ないわゆるAORのシンガーソングライターである。彼のソロシンガーとしての人気が最も高まることになったのが、1979年に発表された5枚目のアルバム『パートナーズ・イン・クライム(Partners in Crime)』であった。 収録曲はすべて自作で、アップテンポの現代的雰囲気のナンバーから、スケール感のあるバラードまで、アルバム全体を見渡すとバランスよく配されているという印象である。ソングライティング力の高さに加え、プロデュースにも本人が加わっていて、単なるシンガーというだけでなく、音楽を創り出す者としての力量が発揮されている(そして、その力量は、バーブラ・ストライザンドはじめ大物アーティストたちが彼の楽曲を取り上げたこと、さらには、彼が後世に他のアーティストのプロデュースや、ミュージカル制作で成功したことにも表れている)。 本盤で特に注目したい楽曲を、筆者の好みで挙げてみたい。1.「エスケイプ」は、全米(およびカナダでも)シングルチャートで1位となった楽曲。詞の中でキーワードの一つになっている“ピニャコラーダ”に因んで“ザ・ピニャコラーダ・ソング”の副題がついていて、軽妙で都会的なサウンドと曲調が特徴のナンバーである。3.「ニアサイテッド」は、近視(ルパート・ホームズは眼鏡を使用している)というテーマながら、驚くほどの美バラードで、とりわけ曲後半のギターを生かした盛り上がりがなかなか気に入っている。 6.「ヒム」は、アルバムリリースの翌年に当たる1980年になってからシングルとしてヒットし、全米6位となったナンバー。美曲を仰々しくやるのではなく、さらりと聴かせるというのは、やはりこの人の才能の為せる業なのだろう。8.「ユー・ネヴァー・ゲット・トゥ・ラヴ」は、ホルムズ自身がいちばんに気に入っている曲とのことで、実際に知り合うことのなかった運命の人だったかもしれない人について歌ったナンバー。アップテンポ系のナンバーの中では、アルバム末尾の10.「イン・ユー・アイ・トラスト」がとくに好曲と言えるように思う。[収録曲]1. Escape (The Piña Colada Song)2. Partners in Crime3. Nearsighted4. Lunch Hour5. Drop It6. Him7. Answering Machine8. The People that You Never Get to Love9. Get Outta Yourself10. In You I Trust1979年リリース。 【国内盤CD】【新品】ルパート・ホームズ / パートナーズ・イン・クライム パートナーズ・イン・クライム/ルパート・ホームズ[SHM-CD]【返品種別A】 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年11月12日
コメント(0)
-
楽天ブログの不具合
ここ4~5日ほど、楽天ブログにアクセスが難しいという状況が続きました。本ブログでも、アクセス数も驚くほど少数の日々が続きました。どうやら復旧したようです。引き続き本ブログを楽しんでいただければ幸いです。
2025年11月10日
コメント(0)
-

イングヴェイ・J・マルムスティーンズ・ライジング・フォース 『アタック!!(Attack!!)』
イングヴェイ節が冴える21世紀盤 スウェーデン、ストックホルム出身のロック・ギタリストであるイングヴェイ・マルムスティーン(Yngwie J. Malmsteen)。彼は、アルカトラスでの活躍(参考過去記事)を経て、1984年にファースト作(過去記事)を発表して以降、バンド名義でしばしば作品をリリースしてきた。とはいえ、バンド名義の下であっても、実質はイングヴェイの作品(あるいはイングヴェイのバンド)であり、メンバーは頻繁に変わっていった。21世紀に入って最初のスタジオ盤となった本作『アタック!!(Attack!!)』においても、前作の『ウォー・トゥ・エンド・オール・ウォーズ』(2000年発表)からメンバーを総入れ替えし、ヴォーカルはドゥギー・ホワイトとなっている。 ひとことで言えば、イングヴェイ節が冴えわたるといったところだろうか。ヴォーカルのホワイトとの相性も悪くないように思える。1.「レイザー・イーター」の流れるようなギターのメロディに始まり、表題曲の5.「アタック!!」でもイングヴェイ節が存分に発揮されている。インスト曲の6.「バロック&ロール」は本盤の聴きどころの一つで、「ファー・ビヨンド・ザ・サン」などインストの名演を残してきたこのギタリストの本領発揮のナンバーだと言える。 イングヴェイのギター・プレイという観点では、8.「マッド・ドッグ」、インストルメンタルの10.「マジェスティック・ブルー」といった曲も要注目である。また、上記のホワイト(ヴォーカル)との相性およびバンドとしての演奏という点では、13.「タッチ・ザ・スカイ」の出来が特によいと感じる。アルバム締めくくり(ただし日本盤ではこの後にボートラが続く)となるインスト・ナンバーの15.「エア」は、バッハの「G線上のアリア」が原曲となっている。 [収録曲]1. Razor Eator2. Rise Up3. Valley of Kings4. Ship of Fools5. Attack!!6. Baroque & Roll7. Stronghold8. Mad Dog9. In the Name of God10. Freedom Isn't Free11. Majestic Blue12. Valhalla13. Touch the Sky14. Iron Clad15. Air16. Nobody's Fool 〈日本盤ボーナストラック〉2002年リリース。 【中古】CD Yngwie J. Malmsteens Rising Force Attack!! PCCY01582 CANYON Japan /00110 【中古】CD▼アタック!! レンタル落ち 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年11月09日
コメント(0)
-

ニルス・ロフグレン 『稲妻の夜~ニルス・ライヴ!(Night After Night)』(2/2)
内容充実の初の公式ライヴ盤(後編)(前編からの続き)ニルス・ロフグレン(Nils Lofgren)の初ライヴ作『稲妻の夜~ニルス・ライヴ!』について、アルバム後半(2枚組の2枚目)の内容を見ていくことにしたい。 LP盤の2枚目前半(C面)は、クレイジー・ホース(ちなみに、ニルスはニール・ヤングのアルバムへの参加経験もある)に関連した2曲から始まる。II-1.「ベガーズ・デイ~ダニー・ウィッテンへの賛歌」は、かつてのクレイジー・ホースの中心的人物であったダニー・ウィッテン(ウィットン)に捧げられたナンバー。続くII-2.「ムーンティアーズ」は、ライヴの見せ場の一つで、実弟のトム・ロフグレンとの絡みも含め、ニルスのギターが聴きどころとなっている。II-3.「コード・オブ・ザ・ロード」は、この当時の最新作『稲妻(アイ・ケイム・トゥ・ダンス)』からのナンバーで、9分超の長い尺だが、曲の後半にかけてのギター・プレイが冴える。 LPで2枚目後半(D面)だったのが、最後の4曲。骨太のII-4.「ロックン・ロール・クルック」はファースト・ソロ作からの楽曲、歌も聴かせるタイプのII-5.「南へ(ゴーイン・サウス)」は、再び『稲妻』からの楽曲で、ギターもメロディアスな部分を含んでいるのがいい。II-6.「イッツ・オーヴァー(インシデンタリー…イッツ・オーヴァー)」は、ソロ2作目の『クライ・タフ』に収められていたものだが、ライヴ向けに盛り上げるアレンジが加わっている。アルバムを締めくくるII-7.「ロックン・ロール・ダンス(アイ・ケイム・トゥ・ダンス)」は、『稲妻』の表題曲。テンポ感のいい曲調とギターを存分に聴かせようという演奏(それゆえ、こちらも9分近い長尺)が魅力となっている。 なお、余談ながら、米国での再発CD盤では、II-2.「ムーンティアーズ」がカットされ、それ以外に複数の曲が短くされてしまっているとのことである(おそらくはそのせいで日本盤ライナーの曲目の番号も乱れている)。ちなみに、これと同じことは後の2枚組ライヴ盤『ニルス・ライヴ!~コード・オブ・ザ・ロード』でも起きいて、本来の2枚組をきちんと再現してもらいたいものだと思う。ともあれ、この盤については、日本で2014年に再発された紙ジャケ盤が2枚組をきちんと再現してくれているので、そちらを聴くことをお勧めする。[収録曲](Disc I)1. Take You to the Movies Tonight2. Back It Up 3. Keith Don't Go (Ode to the Glimmer Twin) 4. Like Rain ←ここまでLP盤のA面5. Cry Tough6. It's Not a Crime7. Goin' Back8. You're the Weight ←ここまでLP盤のB面(Disc II)1. Beggar's Day (Eulogy to Danny Whitten) 2. Moon Tears 3. Code of the Road ←ここまでLP盤のC面4. Rock & Roll Crook5. Goin' South6. Incidentally... It's Over7. I Came to Dance ←ここまでLP盤のD面1977年リリース。 ニルス・ロフグレン / 稲妻の夜〜ニルス・ライヴ! [CD] ニルス・ロフグレン / 稲妻の夜〜ニルス・ライヴ! [CD] ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年11月04日
コメント(0)
-

ニルス・ロフグレン 『稲妻の夜~ニルス・ライヴ!(Night After Night)』(1/2)
内容充実の初の公式ライヴ盤(前編) ニルス・ロフグレン(Nils Lofgren)は、1951年生まれのロック・ギタリスト。1970年代前半にグリンというバンドで活動したのち、1970年代半ばからはソロ名義で作品をリリースしていった(後にブルース・スプリングスティーンのE・ストリート・バンドに加入)。そんな彼にとって、最初のライヴアルバムとなったのが、2枚組として1977年に発表された本盤『稲妻の夜~ニルス・ライヴ!(Night After Night)』であった。ソロ・デビュー作のプロモーションのために1975年にスタジオ・ライヴ盤が制作(ただし正式リリースは30年以上経ってからだった)されていたものの、本当の意味でのライヴ盤という意味では、これが最初だった。 でもって、その内容はというと、秀逸なステージ演奏のオンパレードである。グリン時代の曲から、本ライヴ盤リリースと同年に出された最新作(『稲妻(アイ・ケイム・トゥ・ダンス)』)の曲まで幅広い選曲がなされ、完成度の高いパフォーマンスが展開されている。 最初の曲はI-1.「スターウォーズで決めよう(テイク・ユー・トゥ・ザ・ムーヴィーズ)」であるが、これはライヴのオープニングの1分半ほどの“枕”となる、エレキギターで軽く伴奏を付けた弾き語り風の演奏である。その後、勢いよくI-2.「バック・イット・アップ」が始まるところから、ライヴ本編が始まる。キース・リチャーズに捧げたI-3.「キース・ドント・ゴー」(オープニングのギターも、曲中のギター・ソロも、ギタリストとしてのニルスのよさが発揮されている)を挟み、グリン時代のバラード曲I-4.「ライク・レイン」へと続いていく。 LP時代の1枚目裏面(B面)は、前年(1976年)の『クライ・タフ』所収の2曲から始まる。I-5.「クライ・タフ」のシリアス感のあるギター・プレイは筆者のお気に入りで、I-6.「イッツ・ノット・クライム」は一転して明るい曲調。ファースト・ソロ作に収められたキャロル・キングによるナンバーのI-7.「ゴーイン・バック」は、ピアノ弾き語りの別の曲(「ビリーヴ」)から始まり、そのままニルスのピアノによるこの曲へと移っていく。続いては、同じくグリン時代の曲I-8.「きみがすべてさ(ユア・ザ・ウェイト)」。重くどちらかというとシリアスな曲調のものと明るめのポップのものを交互に配したり、ギター一辺倒にならず合間でギターを置いてピアノ演奏を挟むなど、ライヴとしても飽きさせないところも工夫が感じられる部分と言えるのかもしれない。 長くなってきたので、続きは後編に(収録曲の情報等は次回更新の後編をご覧ください)。 ニルス・ロフグレン / 稲妻の夜〜ニルス・ライヴ! [CD] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年11月03日
コメント(0)
-

スティング 『ブルー・タートルの夢(The Dream of the Blue Turtles)』
ソロ・アーティストとしてのスティングの姿勢が明確化された好作品 1984年にポリスが活動休止となり、その翌年にメンバーだったスティング(Sting)はソロとしての第一作を発表した。それが、1985年リリースの本盤『ブルー・タートルの夢(The Dream of the Blue Turtles)』である。 ポリス時代の諸作とは違い、本作ではスティング個人の音楽的志向性がはっきりと示されている。ケニー・カークランドやブランフォード・マルサリスなどのミュージシャンが参加し、ジャズ寄りのサウンド、1980年代半ば当時の華やかなロックシーンには異質の方向性の作風が展開されている。 オープニング・ナンバーの1.「セット・ゼム・フリー」は、先行シングルとして発売され、全米3位のヒットとなった。2.「ラヴ・イズ・ザ・セヴンス・ウェイヴ」もシングルとしてリリースされたナンバーで、個人的にはお気に入りのナンバー。3.「ラシアンズ」は東西冷戦体制を批判した楽曲で、こちらもシングルとして注目を集めた。 アルバム後半では、6.「黒い傷あと」や9.「バーボン・ストリートの月」が筆者の好み。特に後者の重く寂しいトーンは最初に聴いた当時から印象に残り、当初から忘れられない1曲となっている。また、アルバム表題曲の8.「ブルー・タートルの夢」が短い演奏ながら、もはや単なるロック/ポップのアルバムではないということをよく示している。 これ以降、スティングは秀でた作品をいくつも制作していくことになるわけだが、その最初となったこのアルバムもまた聴き逃がせない名盤の一つと言っていいように思う。[収録曲]1. If You Love Somebody Set Them Free 2. Love Is the Seventh Wave3. Russians 4. Children's Crusade 5. Shadows in the Rain6. We Work the Black Seam7. Consider Me Gone8. The Dream of the Blue Turtles 9. Moon Over Bourbon Street 10. Fortress Around Your Heart1985年リリース。 ブルー・タートルの夢/スティング[SHM-CD]【返品種別A】 ブルー・タートルの夢 [ スティング ] 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーをクリックして応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2025年10月31日
コメント(0)
-

ポール・デイヴィス 『アイ・ゴー・クレイジー(Singer of Songs - Teller of Tales)』
カントリー、ソウルをバックグラウンドにした西海岸的AOR盤 ポール・デイヴィス(Paul Davis)は、1948年ミシシッピ生まれのシンガーソングライター。ソウル、カントリーなどの音楽的背景を持ちながらも、西海岸的サウンド、レイドバック風のヴォーカルで成功を収めた。その代表盤とされるのが、ソロ5作目の本盤『アイ・ゴー・クレイジー(Singer of Songs - Teller of Tales)』(1977年)である。 邦盤では収録されたヒット曲をアルバム表題にしている(このやり方はチャラいものの、「商品」を売るためには鉄壁のパターンなのだろう)けれど、英語の原題は“歌の歌い手、物語の語り手(シンガー・オブ・ソングス、テラー・オブ・テイルズ)”である。つまりはシンガーソングライターとしてのこのアーティストのスタンスが示されている表題と言え、実際、収録された10曲中8曲が彼のペンによるナンバーである。 1.「アイ・ゴー・クレイジー」は、1978年にシングルとして全米7位を記録したポール・デイヴィスの代表曲で、40週という長期間にわたってトップ100入りし、アルバム自体の商業的成功にもつながった。べったりぴったりど真ん中のバラード美曲であり、ヒットにつながったのも頷ける。 これ以外にもいかにもAOR的なナンバーが並ぶ。上記1.以外に個人的に特に好曲だと筆者が感じているのは、2.「ブラインド・ニュー・ラヴ」(とにかく曲がいい)、7.「もうひとつの愛」、8.「ジャスト・ア・ローズ」、10.「エディトリアル」(ピアノをバックに歌い上げる熱唱が印象的)といった楽曲である。 ここまでの話からすると、聴衆受けを狙った大衆迎合的なナンバーばかりが並ぶのかと思ってしまうかもしれない。けれども、アルバムの随所に彼のルーツとなる音楽性が顔をのぞかせるという側面もあるように思う。6.「ハレルヤ・サンキュー・ジーザス」は、彼がカントリーのソングライターであったことがよくわかるし、9.「バッド・ドリーム」は古き良きロックンロール音楽をうまく当時風にアレンジしているという印象を受ける。[収録曲]1. I Go Crazy2. I Never Heard the Song at All3. Darlin'4. Sweet Life5. Never Want to Lose Your Love6. Hallelujah Thank You Jesus7. I Don't Want to Be Just Another Love8. You're Not Just a Rose9. Bad Dream10. Editorial1977年リリース。 アイ・ゴー・クレイジー [ ポール・デイヴィス ] 次のブログランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月27日
コメント(0)
-

テッド・カーソン 『ライヴ・アット・ラ・テト・ドゥ・ラール(Live at La Tete de L'Art)』
隠れた好ライヴ演奏盤 テッド・カーソン(Ted Curson)は、1935年フィラデルフィア生まれのジャズ・トランペット奏者で、2012年に77歳で没している。10歳でトランペットを手にしたという彼は、セシル・テイラーやチャールズ・ミンガスとの録音にも参加した経験を持つ。ワールドワイドに名が知られた演奏家というわけではなかったにせよ、フィンランドではよく知られたミュージシャンで、ポリ・ジャズ・フェスティヴァルには1966年の初回から毎年参加していたという。 この『ライヴ・アット・ラ・テト・ドゥ・ラール(Live at La Tete de L'Art)』は、カナダのモントリオールで1962年に録音されたライヴ演奏盤。テッド・カーソンのトランペットとアル・ドクターのアルトをフロントにしたクインテット編成の演奏である。決してレコーディングの音質は良好というわけではないけれども、テッド・カーソンのトランペットの魅力が存分に発揮された好演奏を楽しむことができる一枚である。 冒頭の1.「クラックリン・ブレッド」は穏やかに始まり、端正な演奏が印象的。この“端正”というのは、テッド・カーソンの形容によく使われるようだが、“ハンサム”な演奏と言い換えてもいいように筆者は思っている。とにかくいい意味で整っていてシャキッとしているのである。この特色は、2.「テッズ・テンポ」のようにモード的インプロヴィゼーションが展開されてもしっかりと維持されていて、そこがなかなか面白いところだと思う。3.「プレイハウス・マーチ」は勇壮なテーマに続き、これまた端正なトランペット演奏についつい聴き惚れてしまう。 アルバム後半(元のLP盤のB面)に入り、収録曲のうち最も尺が長い(12分半)の4.「ストレート・アイス」でも、ややもすると間延びしかねない展開の中、このシャキッとしたトランペットが聴き手の集中力を持続させるという演奏が繰り広げられる。5.「クイックサンド」はシリアスな雰囲気を醸し出している楽曲であるが、ここでもテッド・カーソンのトランペットの端正さが際立っている。決してよく知られた盤ではない(というよりほとんど知られていない盤なのだろう)が、これを聴かないのはもったいない、そんな好盤だと言えるように思う。[収録曲]1. Cracklin' Bread2. Ted's Tempo3. Playhouse March4. Straight Ice 5. Quicksand[パーソネル・録音]Ted Curson (tp, piccolo-tp), Al Doctor (as), Maury Kaye (p), Charles Biddle (b), Charles Duncan (ds)1962年録音。 テッド・カーソン / テッド・カーソン|フォー・クラシック・アルバムズ [CD] 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月24日
コメント(0)
-

ガブリエル・リバーノ 『アサード・クリオーリョ(Asado criollo)』
バンドネオン奏者による意欲作 ガブリエル・リバーノ(Gabriel Rivano)は、1958年、アルゼンチン出身のバンドネオン奏者。バンドネオン奏者というと、“ああ、タンゴね”となりがちかもしれないが、彼の音楽は、タンゴとクラシックとジャズというトライアングル(三角形)の中に成り立っているというのが適当なのかもしれない。 本盤『アサード・クリオーリョ(Asado criollo)』は2006年にリリースされたアルバム。表題の“アサード・クリオーリョ”というのは、アルゼンチン風のバーベキューのこと(地方によって肉の種類は、羊だったり、山羊だったり、豚だったりするらしい)。この“アルゼンチン的”表題からも窺えるように、本作はとくにアルゼンチン・フォルクローレからの影響を受けた作品である。 リバーノ自身が述べているところでは、本盤の着想は1997年のアサード(バーベキュー)に始まる。けれども、様々なプロジェクトで本格化できずに時が過ぎ、2000年にギターのビクトル・ビジャダンゴス(本盤の2.でギターを披露している)とともにこの作業を開始したという。結果、2005年に録音を行い、本盤の形に結実したとのことである。 フォルクローレの有名曲である1.「ラ・テレシータ」から本盤は始まる。続く2.~5.は組曲になっていて、「パタゴニア組曲」と名づけられている。その後、6.「グスターボ・デ・シンコ・ア・セイス」を挟み、再び7.~10.は組曲となっており、こちらの方は「アルゼンチン組曲」となっている。最後は、タンゴの定番曲11.「ラ・クンパルシータ」でアルバムを締めくくる(なお、ボートラとしてギタリストのリカルド・モヤーノと共演した3.の別ヴァージョンが収められている)。[収録曲]1. La Telesita《Suite Patagónica》2. Asado Criollo3. zamba de Mayo4. Ñancul5. Zamba Junina6. Gustavo de 5 a 6《Suite Argentina》7. Tren de las Nubes - Norte8. El Argentinito - Este9. La Luminosa - Oeste10. Pampa - Sur11. La cumparista 12. Zamba de Mayo [bonus track]2006年リリース。 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月21日
コメント(0)
-

ラス・フリーマン/チェット・ベイカー 『カルテット(Quartet)』
端正でメリハリの利いた爽快盤 1950年代、ラス・フリーマン(Russ Freeman)は、チェット・ベイカー(Chet Baker)との共演を何度も行った。そして、この2人が組んだ最後となり、なおかつ出色の出来の演奏を披露しているのが、この『カルテット(Quartet)』という盤である。アルバム表題の通り、演奏内容は、チェット・ベイカーのトランペットのワンホーン・カルテット。ラス・フリーマンのピアノの他は、ベースがルロイ・ヴィネガー、ドラムスがシェリー・マンという面子である。 ラス・フリーマンのピアノがしばしば小気味よく打楽器的な感性を滲ませる。シェリー・マンは持ち前の軽快かつ安定のドラミングを見せる。ベースのルロイ・ヴィネガーは、いつもながらの安定感・安心感のある演奏。そして、チェット・ベイカーのトランペットは、この人らしい軽妙さが存分に発揮されている。無論、ここの演奏が優れていても全体としてうまくいくとは限らないわけだが、本盤に関しては、4人のオリジナリティが合わさって、このメンバーでのオリジナリティに結びついていると言えるように思う。 私的な好みから注目の演奏を何曲か挙げておきたい。ベイカーのトランペットの軽快さにドラムスとピアノが見事に呼応している1.「ラヴ・ネスト」は、間違いなく本盤の聴きどころとなる演奏。4.「アン・アフタヌーン・アット・ホーム」は、このカルテットの息が合っているのがよくわかる好演奏に仕上がっている。6.「ラッシュ・ライフ」は、フリーマンのピアノとベイカーのトランペットをじっくりと堪能できる1曲である。8.「ヒューゴ・ハイウェイ(ウーゴ・ハイウェイ)」は、ベイカーのトランペットが個人的に気に入っている。[収録曲]1. Love Nest2. Fan Tan3. Summer Sketch4. An Afternoon at Home5. Say When6. Lush Life7. Amblin'8. Hugo Hurwhey[パーソネル、録音]Chet Baker (tp), Russ Freeman (p), Leroy Vinnegar (b), Shelly Manne (ds)1956年11月6日録音。 チェット・ベイカー=ラス・フリーマン・カルテット [ チェット・ベイカー/ラス・フリーマン ] 【中古】 チェット・ベイカー=ラス・フリーマン・カルテット/チェット・ベイカー,ラス・フリーマン,リロイ・ヴィネガー,シェリー・マン 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月19日
コメント(0)
-

INDEXページの更新
1か月ほど間が空いてしまいましたが、INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。最近記事へのリンクを追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも ありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月17日
コメント(0)
-
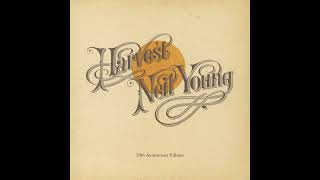
ニール・ヤング 「オールド・マン(Old Man)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その5) “秋を感じさせる”という個人的思い入れ(思い込み?)でニール・ヤング(Neil Young)の楽曲を取り上げてきましたが、今回の5曲目で一区切りです。最後は何と言ってもこの曲、「オールド・マン(Old Man)」です。初回に取り上げた「週末に(アウト・オン・ザ・ウィークエンド)」と同じアルバム(1972年の『ハーヴェスト』)に収録されています。「週末に」がアルバムのオープニング・ナンバー(A面1曲目)なら、今回の「オールド・マン」は、元来のLP盤のB面のオープニングのナンバーということになります。 イントロのギターを聴くと、何か凝った曲なのかなという印象を受けるかもしれませんが、歌が始まるとド直球の弾き語り風かつニール・ヤング節のナンバーです。 最後は、この曲のライヴでの演奏シーンです。第1回目の「週末に」と被ってはしまうのですが、その時にリンクを貼ったのと同じBBCライヴの演奏シーンです。ギターの弾き語り調がストレートに刺さってくるところ、そして何よりも若きニール・ヤングの声の伸びがお見事なライヴ演奏です。 [収録アルバム]Neil Young / Harvest(1972年) ハーヴェスト<リマスター>/ニール・ヤング[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月13日
コメント(0)
-

ニール・ヤング 「イッツ・ア・ドリーム(It's a Dream)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その4) 前回の「ザ・ペインター」が収録されているのと同じニール・ヤング(Neil Young)のアルバム(過去記事)から、もう1曲取り上げてみようと思います。「イッツ・ア・ドリーム(It's a Dream)」というのが、その楽曲です。ピアノ弾き語り風の、どちらかというと地味な曲なのですが、筆者的にはこの哀愁と寂しさの漂う感じが何とも言えない魅力になっているナンバーです。 この曲のライヴでの演奏もご覧いただきます。リリース当時の2005年、ライマン・オーディトリアムでの演奏シーンです。 鍵盤を前にしての演奏ですが、ギターを弾きながら、ピアノを弾きながら(さらにはハーモニカ演奏を披露しながらというパターンもあります)といずれも味わい深さを発揮できるのは、ニール・ヤングの魅力であり強みであるのだろうとあらためて思ってみたりします。[収録アルバム]Neil Young / Prairie Wind(2005年) 【中古】 プレーリー・ウィンド/ニール・ヤング プレーリー・ウィンド[CD] [輸入盤] / ニール・ヤング 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月12日
コメント(0)
-
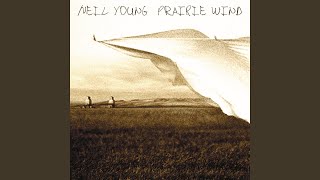
ニール・ヤング 「ザ・ペインター(The Painter)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その3) 秋という季節と絡めてのニール・ヤング(Neil Young)曲選の3回目です。前2回の曲から時は一気に進んで、2005年のアルバム『プレーリー・ウィンド』に収められた「ザ・ペインター(The Painter)」というナンバーです。 この曲が収録されたアルバムは、リリース年としては離れているものの、『ハーヴェスト・ムーン』(2005年)と並んで『ハーヴェスト』(1972年)の続編的内容と見なされる作品で、そういう意味では、楽曲の雰囲気も通底している部分があります。 続いては、発表当時(2005年)のステージの模様をご覧ください。アルバム収録のもとのヴァージョンと同様のまったりした雰囲気が魅力といったところです。 [収録アルバム]Neil Young / Prairie Wind(2005年) プレーリー・ウィンド[CD] [輸入盤] / ニール・ヤング 【中古】 【輸入盤】プレイリー・ウィンド/ニール・ヤング ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月11日
コメント(0)
-

ニール・ヤング 「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ(After the Gold Rush)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その2) 筆者の中ではなぜだか秋という季節と結びついているニール・ヤング(Neil Young)のナンバーの2曲目です。今回の楽曲は、彼の作品の中でも代表作として1,2位を争う(と筆者は思っている)名盤『アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ』に収録のナンバーです。 まずは、上記の盤に収められた表題曲「アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ(After the Gold Rush)」をお聴きください。 なぜ“秋”なのかという点については、結局のところ感覚的なものでしかないのですが、この“頼りなさげな”(もちろんいい意味で)が筆者にそう思わせるといったところなのでしょう。 今回は、後世のライヴ映像もご覧いただきたいと思います。1998年、ファーム・エイドでのステージの様子です。上記のヴォーカルの魅力(そしてハーモニカ演奏部分も実に魅力的です)が存分に発揮されています。 [収録アルバム]Neil Young / After the Gold Rush(1970年) アフター・ザ・ゴールド・ラッシュ [ ニール・ヤング ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年10月10日
コメント(0)
-
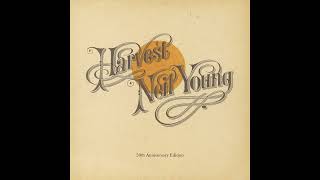
ニール・ヤング 「週末に(Out on the Weekend)」
秋の訪れとともに味わうニール・ヤングの名曲(その1) 今夏の連日の猛暑もようやく収まってきて、少しは秋が感じられる日も増えてきました。そんなわけで、“秋の風を感じるニール・ヤング曲選”をお届けしたいと思い立ちました。ニール・ヤング(Neil Young)が必ずしも秋と結びつくというわけではないのですが、個人的にはそういうアルバムがあることをこちらの過去記事(『ハーヴェスト』)にも書きました。他のいくつかのニール・ヤングのアルバムでも、なぜだか秋とシンクロするものがあって、今回はそうした中から彼の楽曲をいくつかピックアップしていこうと思い立った次第です。 最初の曲は、上記『ハーヴェスト』に収録の「週末に(Out on the Weekend)」というナンバーです。アルバムのオープニング曲にしては何とものどかというか素朴なナンバーなのですが、筆者の個人的思い入れとしては、秋風が吹く山道をドライヴするのに最適な1曲だったりします。 もう一つ、ライヴ演奏もお聴きいただきたいと思います。発表当時(というか厳密にはアルバム発表の前年)の1971年、BBCライヴでの弾き語り演奏の模様です。 [収録アルバム]Neil Young / Harvest(1972年) ハーヴェスト<リマスター>/ニール・ヤング[CD]【返品種別A】 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月08日
コメント(0)
-

アルカンヘル・ウルバーノ 『レジェンダス(Leyendas)』
“都会の天使”によるメキシコのアーバン・ロック アルカンヘル・ウルバーノ(Arkángel Urbano)は、メキシコの4人組ロック・バンド。直訳すると“都会の大天使”というのは何ともベタな名前に思えるが、その演奏スタイルもメキシコの大衆層向けのベタなロックというもの。メンバーは、ロベルト・カルロス(通称ダニーロ、ヴォーカルとリズム・ギター)、セサル・クルス(ベース)、ホアキン・ガジョソ(リード・ギター)、ダビー・アルバレス(キーボード)、ウリシス・ロサード(ドラムス、パーカッション)という5人組である。メキシコでその手の盤を多く手掛けるデンバー・レコードから2015年にリリースされたのが、本盤『レジェンダス』である。 1.「ラ・ジョローナ」は、ややヘヴィメタル寄りのシリアスな演奏がビシッと決まっている好曲だが、夜な夜な聞こえる女性の泣き声というメキシコの民間伝承を表題にしているというミスマッチが面白い。収録曲全体を見ると、ブルース/ロック・ベースのメキシカン・ロックが中心で、筆者に刺さるナンバーとしては、3.「アモール・インポシブレ」(“かなわぬ愛”の意味)、8.「フリアン」、12.「ティエンポ・デ・トリウンファール」(“勝利のとき”)といった辺りだろうか。 他の収録曲の中には、若くして母となった少女に捧げた7.「ア・ウナ・ホベン・ママ」、メキシコシティ近郊の高山を表題にした9.「イスタックシワトル(白い女性)」、イエス・キリストの名と曲調が見事なミスマッチ(?)を醸し出す10.「エル・ラメント・デ・クリスト」(“キリストの嘆き”)のような曲がある。かと思えば、日本人的にはやや仰天の11.「ゲイシャ」(“芸者”)なんて曲も含まれている。中途半端なバラード調の演奏にのせて、“月のごときゲイシャ~、白い肌、君のことが忘れられない~”といったような歌と演奏(もちろん本人たちは大真面目)。こうした部分も、“何でもあり”の面白さということで楽しめばいいのだろう。[収録曲]1. La llorona2. Recuerdos3. Amor imposible4. El blues de la verdad5. La historia de un perdedor6. Flores negras7. A una joven mamá8. Julián9. Iztaccíhuatl (mujer blanca)10. El lamento de Cristo11. Geisha12. Tiempo de triunfar (David Severo Carmona)2015年リリース。 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年10月06日
コメント(0)
-

ジョアン・マヌエル・セラ― 『エル・スール・タンビエン・エクシステ(El sur también existe)』
カタルーニャ人シンガーが“文学を歌う” スペインはカタルーニャ出身のシンガー、ジョアン・マヌエル・セラ―(Joan Manuel Serrat)の19枚目のアルバムとして1985年にリリースされたのが、本盤『エル・スール・タンビエン・エクシステ(El sur también existe)』である。セラーの有名曲の一つ「カンターレス」は、スペインの詩人アントニオ・マチャードの詩に音楽をつけたものとして知られているが、実はこの曲が収録されたアルバム(1969年の『詩人アントニオ・マチャードに捧ぐ』)そのものがそういうコンセプトであった。これと同様に、マリオ・ベネデッティを題材としたのが、本盤ということになる。 マリオ・ベネデッティは、ウルグアイ生まれの小説家、ジャーナリスト、詩人で、軍政下の祖国からアルゼンチン、ペルー、キューバ、スペインへと逃れて亡命作家生活を送った。亡命生活の最後の時期に当たるのが、ちょうど本盤の頃であった。そのベネデッティの詩を題材にして音楽にのせてセラーが歌うというのが、このアルバムのコンセプトである。 表題曲の1.「エル・スール・タンビエン・エクシステ(南もまた存在する)」は、世界におけるいわゆる南北格差が歌われており、南米出身のベネデッティならではの説得力がある。どの曲に関しても、セラーの歌唱力が生かされているが、筆者の好みでは4.「アガモス・ウン・トラート(取引をしよう)」、5.「テスタメント・デ・ミエルコレス(水曜日の遺言)」、6.「ウナ・ムヘール・デスヌーダ・イ・エン・ロ・オスクーロ(裸の暗がりの女性)」、10.「デフェンサ・デ・ラ・アレグリーア(歓喜の擁護)」なんかがいい。8.「アバネーラ」は、キューバのハバナがテーマとなっていて、これもまたベネデッティの亡命生活から生まれたテーマである。 上述のような“文学的な”盤ながら、リリース年から翌年にかけて4曲もがシングルカットされている(発売順に6., 3., 7., 4.)。文学作品がポップやロックの曲に化けるというのは、日本語では想像しにくいかもしれないが、この辺りはやはりラテン語の流れを汲む文化圏の底力なのかもしれない。それと同時に、亡命生活にある作家の声を聴衆に届けようというシンガーとしてのセラーの心意気があって誕生した盤ということであろうか。[収録曲]1. El sur también existe2. Currículum 3. De árbol a árbol4. Hagamos un trato5. Testamento de miércoles6. Una mujer desnuda y en lo oscuro7. Los formales y el frío8. Habanera9. Vas a parir felicidad10. Defensa de la alegría1985年リリース。 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年10月03日
コメント(0)
-

ポール・チェンバース 『ゴー(Go)』
ハード・バップ直球ながらオープンな雰囲気の盤 1935年、ピッツバーグ生まれでデトロイト育ちのポール・チェンバース(Paul Chambers)は、33歳と早くに亡くなったこともあり、リーダー作は決して多くはない。ブルーノート盤以外で目立ったものとして、今回取り上げるのが、1959年のヴィージェイ盤の本作『ゴー(Go)』である。 サイドマンとして数々の盤に出ているだけあって、メンツとしては、ある意味よくありそうな組み合わせ。アルト・サックスにキャノンボール・アダレイ、トランペットにフレディ・ハバード。リズム・セクションはピアノのウィントン・ケリーにドラムのジミー・コブおよびフィリー・ジョー・ジョーンズという、お馴染みの顔ぶれによる演奏である。マイルス・デイヴィス『カインド・オブ・ブルー』にメンツがそっくり?と思う向きもあるだろうが、それもそのはず。本盤の録音は1959年の2月。『カインド・オブ・ブルー』が同年の3月~4月なので、ほぼ同時期の録音ということになる。 本盤を一言で表すならば、直球のハード・バップ盤ということになるだろう。けれども、ブルーノート盤なんかに典型的なシリアスさに欠けるというのも、重要な特徴だと思う。言い換えると、弾けたりリラックスしたりという、“シリアス”の対極のような要素が演奏の随所で目立つ。それは、上記の『カインド・オブ・ブルー』と並べて聴いてみると一目瞭然だろう。 1.「オーフル・ミーン」は、冒頭からチェンバースのベースが弾け、キャノンボール・アダレイのサックスが奔放に駆ける。4.「ゼア・イズ・ノー・グレイター・ラヴ」は、上で述べた通りのオープンなリラックス感が特徴的。それに対し、5.「イーズ・イット」はもっとシリアスに迫ってくる演奏から始まるのだけれど、やはりどこかにオープンな雰囲気(途中の拍手なども含めて)を持ち合わせている。6.「アイ・ガット・リズム」も同様な特徴を持つと言えるが、個人的にはスピード感のあるこの演奏は、本盤中で特に魅かれるものだったりする。 ちなみに、筆者は通して聴いていないものの、1998年には未収録音源を含めたものが2枚組としてリイシュ―されている。[収録曲]1. Awful Mean2. Just Friends3. Julie Ann4. There Is No Greater Love5. Ease It6. I Got Rhythm[パーソネル、録音]Paul Chambers (b)Julian “Cannonball” Adderley (as)Freddie Hubbard (tp)Wynton Kelly (p)Jimmy Cobb (ds)Philly Joe Jones (ds)1959年2月2~3日録音。 【中古】 ゴー+1/ポール・チェンバース 下記のブログランキングに参加しています。応援くださる方は、 バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月29日
コメント(0)
-

オリヴァー・ネルソン 『スイス組曲(Swiss Suite)』
ネルソンがまとめあげた熱狂のライヴ演奏 1971年6月18日、スイスのモントルー・ジャズ・フェスティヴァルでの熱演は翌朝5時まで夜通し続いた。その最後を飾った演奏の収められたのが、本盤『スイス組曲(Swiss Suite)』である。この演奏をまとめあげたのは、アレンジャーでアルト・サックス奏者でもあるオリヴァー・ネルソン(Oliver Nelson)であった。 ジャケットには、上記の通りのライヴ演奏盤である旨(“Recorded Live at the Montreux Jazz Festival”)に加え、“Featuring Gato Barbieri & Eddie ‘Cleanhead’ Vinson”とあり、2人の写真も載せられている。 LPのA面全部に当たる1.「スイス組曲」では、これら2人のうち、まず前者のテナー、次いで後者のアルト・サックスが躍動する。とくにガトー・バルビエリ(ガート・バルビエ―リ)の方は、この同じ日のライヴ演奏が『エル・パンペーロ』としてライヴ盤になっており、その演奏後の熱い雰囲気の中、そのまま熱演を奮っている。およそ27分のこの演奏では、これら2人のとにかく情熱的で激しいプレイをオリヴァー・ネルソン率いるオーケストラががっちりと受け止めているのだけれど、聴く側の観点としては、そんな細かいことを忘れてとにかく熱い演奏にのめり込めるのがいい。 アルバム後半(LPのB面)は、名曲2.「ストールン・モメンツ」で幕を開け、オリヴァー・ネルソン・オーケストラによる合計3曲の演奏が収められている。これらの演奏も、総じて熱く、熱気に満ちたものである。個人的に気に入っているのは、上記の「ストールン・モメンツ」。次いで、ラストを飾る4.「ブルースの真実(ブルース&ジ・アブストラクト・トゥルース)」のキレのよさが特に印象に残る。 [収録曲]1. Swiss Suite2. Stolen Moments3. Black, Brown and Beautiful4. Blues and the Abstract Truth[パーソネル・録音]Oliver Nelson (as, arr, conductor), Gato Barbieri (ts: 1.), Eddie "Cleanhead" Vinson (as: 1.), Charles Tolliver (tp, flh), Danny Moore (tp), Rich Cole (tp), Bernt Stean (tp), Harry Beckett (tp), Buddy Baker (tb), Bertil Strandberg (tb), Donald Beightol (tb),C.J. Shibley (tb), Monte Holz (tb), John Thomas (tb), Jim Nissen (bass trombone), Jesper Thilo (as), Michael Urbaniak (ts), Bob Sydor (ts), Steve Stevenson (bs), Stanley Cowell (p), Victor Gaskin (b), Hugo Rasmussen (b), Bernard Purdie (ds), Bosko Petrovic (ds, vib, tarabooka), Na Na (berimbau), Sonny Morgan (congas)録音:1971年7月18日(*7月19日午前) スイス組曲(ライヴ・アット・モントルー・ジャズ・フェスティヴァル) [ オリヴァー・ネルソン ] 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月26日
コメント(0)
-

ウディ・ショウ 『マスター・オブ・ジ・アート(Master of the Art)』
魅力が伝わるライヴ演奏盤 ウディ・ショウ(Woody Shaw)は1944年生まれのジャズ・トランペット奏者。フレディ・ハバートと並ぶ奏者と言っていいようにも思うのだけれど、正当に評価されてこなかったミュージシャンだと言える。本盤『マスター・オブ・ジ・アート(Master of the Art)』は、1982年と比較的新しい吹き込みなのだが、彼の魅力を存分に伝える好ライヴ演奏盤だと思う。 内容としては、レギュラー・クインテット(ウディ・ショウのトランペット・フリューゲルホーンのほかにスティーヴ・ターレのトロンボーンを含むクインテット)に、ゲストとしてヴィブラフォンのボビー・ハッチャーソンを加えたメンバーでの演奏。このヴィブラフォンもなかなかいい働きをしていて、2.「ダイアン」はその効果を実感できる1曲だったりする。 本盤全体を通じての筆者のイチオシは3.「ミステリオーソ」。セロニアス・モンクの有名な楽曲で、並行して展開するメロディというややこしさを見事に創造的な演奏に変えてみせている。時にマイルス・デイヴィスを彷彿とさせるスリリングさすら感じるというと言いすぎかもしれないが、筆者的にはそのくらいに魅かれるものがある。 都合5つのトラックが収録されているが、実際の演奏は1.~4.で、最後の5.はウディ・ショウの肉声によるインタヴューである。彼は本盤の吹込みから7年後の1989年、地下鉄ホームから転落するという事故により、左腕を切断し、その後の経過もよくなく同年に44歳で死去した。通常であれば、蛇足とも言われかねないインタヴュー音声だが、生前の貴重な証言として自身の音楽観などについて語っているものとなっている。[収録曲]1. 400 Years Ago Tomorrow2. Diane3. Misterioso4. Sweet Love of Mine5. The Woody Shaw Interview[パーソネル・録音]Woody Shaw (tp, flh), Bobby Hutcherson (vib), Steve Turre (tb), Mulgrew Miller (p), Stafford James (b), Tony Reedus (ds)1982年2月25日録音。 JAZZ BEST COLLECTION 1000::マスター・オブ・ジ・アート [ ウディ・ショウ ] [枚数限定][限定盤]マスター・オブ・ジ・アート/ウディ・ショウ[CD]【返品種別A】 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月23日
コメント(0)
-

オレハ・デ・バン・ゴッホ 『ディレ・アル・ソル(Dile al sol)』
成功を収めたデビュー盤 ラ・オレハ・デ・バン・ゴッホ(La Oreja de Van Gogh, 略してLOVG)は、スペイン北部バスク地方のサン・セバスティアンで結成されたポップ/ロック・グループ。メンバーは、アマイア・モンテーロ(ヴォーカル)、パブロ・ベネーガス(ギター)、シャビ・サン・マルティン(キーボード)、アルバロ・フエンテス(ベース)、アリツ・ガルデ(ドラム)の5人から成る。なお、ヴォーカルのアマイアはソロシンガーとして独立したため、2008年からはヴォーカリストがレイレ・マルティネスに変更となっている。 1990年代の末、彼らのデビュー盤となったのが、この『ディレ・アル・ソル(Dile al sol)』である。明るくド派手なポップかというとそうでもなく、ロック調かというとそんなこともない。丁寧で安定したバンド演奏とアマイア・モンテーロの個性のあるヴォーカルが適度なポップさを伴った楽曲となって並んでいる。いい意味で、ある種の“聴きやすさ”とヴォーカルの魅力が聴衆の支持に結びついたと言えるのだろう。 1.「エル・ベインティオチョ」は、彼らの最初のシングルで、いきなりヒットを収めたナンバー。このアルバムに収録されていてシングル発売されたナンバーは8曲もあるのだけれど、そのうちで最も大きなヒットとなったのが、2.「クエンタメ・アル・オイード」。こちらの曲の方は、スペイン国内のシングル・チャートで1位を記録し、スペイン・ポップスの代表的なナンバーの一つとして定着した。 6.「ドス・クリスタレス」は、演奏もヴォーカルも聴きごたえがある注目曲の一つ。表題曲の9.「ディレ・アル・ソル」は、テンポのよさと小気味よさが光る。12.「ソニャレー」は、軽妙なリズム感とヴォーカルのよさがうまく生かされた好曲。全体として、後のアルバムと比べるとまだ荒削りな部分も残されているものの、バンドとしての演奏力の高さに加え、アマイアのヴォーカルで聴き手が魅了されるというこのバンドの特徴はすでに明確に表われている。デビュー盤ということを考えると、完成度の高さが際立っているし、上に挙げた以外にも聴き逃がせない曲が多く、おすすめの好盤と言えるように思う。[収録曲]1. El 282. Cuéntame al oído3. Pesadilla4. La estrella y la luna5. Viejo cuento6. Dos cristales7. Lloran piedras8. Qué puedo pedir9. Dile al sol10. El libro11. La carta12. Soñaré1998年リリース。 ↓ベスト盤です↓ 【中古】 La Oreja De Van Gogh ラオレハデバンゴッホ / Lovg: Grandes Exitos / La Oreja De Van Gogh / BMG Import Argentina [DVD Audio]【ネコポス発送】 ↓LP盤です↓ 【輸入盤LPレコード】【新品】La Oreja De Van Gogh / Dile Al Sol【LP2023/4/28発売】 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月20日
コメント(0)
-

INDEXページ更新
ここ1カ月ほど滞ていましたが、INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでもあり がたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年09月16日
コメント(0)
-

パブロ・ミラネス 『ディアス・デ・グロリア(Días de gloria)』
年齢を重ね、安定感と安心感に満ちた好作 パブロ・ミラネス(Pablo Milanés)は、1943年キューバ出身のミュージシャン。2022年に79歳で没している。シルビオ・ロドリゲスらとともに、キューバの新しいトローバ(ヌエバ・トローバ・クバーナ)を牽引した人物で、スペイン語圏の音楽界では実に人気の高い存在である。 1970年代以降、彼は数多くのアルバムや楽曲を世に送り出したが、2000年にリリースされた『ディアス・デ・グロリア(Días de gloria)』は、個人的にリリース直後から繰り返し聴いたこともあり、愛着のある作品の一つとなった。もう少し客観的な言い方をするならば、50歳代後半になったパブロが、以前と同様の安定感と安心感に満ちたパフォーマンスを見せた好作品ということになるだろうか。 おすすめの曲としては、まず表題曲の1.「ディアス・デ・グロリア」(“栄光の日々”の意)。この演奏は通常の弾き語り(アコースティック演奏)だが、アルバム末尾には“トリオ・ヴァージョン”(11.)なるものも収められている。2.「クアンド・ジェガス・アウセンテ・ア・ミ」(“君がいなくなってしまった時”)はテンポよく安定した演奏と歌唱がいい。5.「エン・サコ・ロト」(“破れた袋に”)はアコースティックながらラテンのリズムというキューバ人ならではの曲調が印象的である。 7.「ノスタルヒアス」(“郷愁”)は、いかにもパブロらしい回想的な詞と曲調の、個人的には気に入っているナンバーの一つ。9.「シ・エジャ・メ・ファルタラ・アルグナ・ベス」は、“もし彼女がいなくなったなら”、“もし彼女が私を愛さなくなったなら”、“もし彼女が歌うことを忘れたならば”、などと歌い、“僕がこの歌を書くことはないだろう”と締めくくるラヴソングとなっている。アルバムを締めくくるのは、上記の通り、表題曲のトリオ・ヴァージョンである11.「ディアス・デ・グロリア」。トリオと言っても、本盤全体を支配するアコースティック調を崩さない雰囲気の演奏で、こちらのバージョンも結構気に入っている。[収録曲]1. Días de gloria [acoustic versión]2. Cuando llegas ausente a mí3. Canto a victoria4. Deborah Winsky5. En saco roto6. Masa7. Nostalgias8. Éxodo9. Si ella me faltara alguna vez10. A dos manos11. Días de gloria {trio version}2000年リリース。 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月14日
コメント(0)
-

テレグラフ・アヴェニュー 『テレグラフ・アヴェニュー(Telegraph Avenue)』
サイケとラテンが融合した独自路線のロック テレグラフ・アヴェニュー(Telegraph Avenue)は、ペルーのロック・バンド。1969年、ワロ・カリーヨ(ドラムス、元ホリーズ)とボー・イチカワ(ギターとヴォーカル)の出会いに始まり、その後、ジェリー・ラム・カム(ベース)、チャチ・ルハン(ギターとコンガ)、さらにはベーシストがアレックス・ナタンソン(ベースとヴォーカル)に交代し、4人組の布陣が固まった。このメンバーで1971年にリリースされたのが、セルフ・タイトル盤の『テレグラフ・アヴェニュー(Telegraph Avenue)』である。なお、テレグラフ・アヴェニューというバンド名は、イチカワがサンフランシスコ滞在中の住処の通りの名前に由来する。 音楽的な方向性でいうと、“サイケデリック・ロック”に分類されうるのだろう。けれども、このバンドの面白いところは、ラテンのリズムが感じられるというところにある。カリフォルニアで触れたサイケを志向しているのだけれども、根はラテン。音楽を細かく分類するのは嫌いなのだけれど、“ラテン・サイケデリック・ロック”と言ってもいいような感じである。 注目の曲をいくつか触れておきたい。ラテンのリズムとサイケ音楽の融合という点では、3.「スイート・ホワットエヴァー」、5.「サンガリガリ」(←こう読むのでしょうか?)がその特徴をよく表している。他に6.「レット・ミー・スタート」は、楽曲自体もよくギターも効果的な好ナンバーで、こうした楽曲もよく聴くとリズムにラテンな部分が見え隠れするのは興味深い。アルバムを締めくくるセルフ・タイトル曲の8.「テレグラフ・アヴェニュー」は、コーラスが印象的で、どこか哀愁を漂わせるこれまた好曲である。ちなみに、CD化によって、現行の盤ではボーナス・トラックとしてもう1曲、9.「イッツ・OK」という曲が加えられている。[収録曲]1. Something Going2. Happy3. Sweet Whatever4. Lauralie5. Sungaligali6. Let Me Start7. Sometimes In Winter8. Telegraph Avenue9. It's OK [bonus track]1971年リリース。 【中古】米CD Telegraph Avenue Telegraph Avenue CD2007 Lazarus Audio Products /00110 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月11日
コメント(0)
-

ロバート・ラム 『マイ・ネイバーフッド(Life is Good in My Neighborhood)』
シカゴのオリジナル・メンバーによるソロ第二作 ロバート・ラム(Robert Lamm)は、テリー・キャスらとともに、ブラス・ロック・バンドのシカゴの創設メンバーである。彼は、1970年代のシカゴのソングライティングの重要な部分を担った。しかし、時の経過とともに、シカゴはAOR路線へと向かっていった。これによって、彼が曲を作らなくなったかというと、そんなことはなかった。バンドとしてのシカゴが“甘い”路線をとる中、彼は相変わらず自作曲を作り続けていた。そうした曲が日の目を浴びることになったのが、1993年発表のソロ・セカンド作『マイ・ネイバーフッド(Life is Good in My Neighborhood)』である。 アルバム表題の元になった1./11.「マイ・ネイバーフッド」は、シンプルかつ往年のシカゴっぽさを残す“ヴァージョンA”(トラック1.)と、少し肩の抜けた南国風な感じのする“ヴァージョンB”(トラック11.)が収められている。この表題曲のほかに前半で注目したいのは、3.「オール・ザ・イヤーズ」。往年のシカゴらしい曲調のナンバーで、シカゴのアルバムの中でも聴いてみたかったと思わせる1曲だったりする。5.「ジェシー」は、ラム節が生かされた曲で、シリアスでドラマチックな雰囲気がいい。 アルバム後半では、7.「タブラ」と9.「ホエン・ウィル・ザ・ワールド・ビー・ライク・ラヴァーズ?」が特にいい。前者は、シリアスなナンバーだが、曲の精度が高く、完成度もとりわけ高い。後者は、個人的にはアルバムいちばんの出来で、シカゴそのものといった雰囲気のナンバー。詞の内容も早い時期のシカゴを彷彿とさせるものだったりする。[収録曲]1. My Neighborhood (Version A)2. When The Rain Becomes3. All The Years4. Murder on Me5. Jesse6. Ain't No Ordinary Thing7. Tabla8. In This Country9. When Will the World Be Like Lovers10. My Neighborhood (Version B)1993年リリース。 【中古】CD ロバート・ラム マイ・ネイバーフッド WPCP5519 Reprise Records /00110 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年09月09日
コメント(0)
-

パティ・スミス・グループ 『ラジオ・エチオピア(Radio Ethiopia)』
完成度が高く、エネルギーに溢れた作品 パティ・スミス(Patti Smith)は、1945年シカゴ生まれ、ニュージャージー育ちのミュージシャン。“パンクの女王(クイーン・オブ・パンク)”と呼ばれ2007年にロックの殿堂入りしている。彼女は1975年にデビュー盤を発表し、これに続く第2作(パティ・スミス・グループの名で発表したアルバムとしては最初)となったのが、1976年の『ラジオ・エチオピア(Radio Ethiopia)』(なお、かつての邦盤タイトルは『ストリートパンクの女王』)だった。 彼女の作品の中ではロック色が濃い作品で、ジャック・ダグラスをプロデューサーに起用して商業的成功を狙ったものだったという。本盤最大の魅力は、何よりもパティのとんがり具合というか、前衛的・実験的なことも普通であるかのようにこなしていくパワフルさと実力にある。 アルバムは、ロック曲として完成度の高い1.「アスク・ジ・エンジェルス」から始まる。続く2.「エイント・イット・ストレンジ」や4.「ピッシング・イン・ア・リヴァー」に見られるうねりやアンダーグラウンド感にも、実は背後に安定感と完成度の高さが隠れているように思う。 本盤のハイライトは、アルバム表題曲の7.「ラジオ・エチオピア」。実際には「ラジオ・エチオピア」と「アビシニア」という曲のメドレーないしは組曲形式になっていて、12分超えの大作。既存の概念の打破、もしくは破壊と再構築という意味では、モダンジャズからフリージャズに行ってしまうぐらいの衝撃と吹っ飛びようである。とにかく熱く、しかし手が込んでいて、既存のスキームでは語れない“ロック”が展開されていると言えるように思う。 さて、こうしてこの人の作品を聴いていると、“パティ・スミスは女でありパンクである”という言い方は正しいのだろうか、という疑問が浮かび上がってきてしまう。彼女の音楽に耳を傾けると、“女である”ことも、“パンクである”ことも、ある種どこかで無意味化されてしまう。筆者としては、そんな気がどうしてもしてしまうのである。[収録曲]1. Ask the Angels2. Ain't It Strange3. Poppies4. Pissing in a River5. Pumping (My Heart)6. Distant Fingers7. Radio Ethiopia~Radio Ethiopia/Abyssinia1976年リリース。 ラジオ・エチオピア [ パティ・スミス・グループ ] 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年09月07日
コメント(0)
-

ソエー 『レプティレクトリック(Reptilectric)』
完成の域に達した推奨盤 21世紀に入ってから20年余年のメキシカン・ロック界でこれはというバンドを挙げるとすると、断然、筆者はソエー(Zoé)の名を挙げたい。このバンドは、1990年代に形成され、2001年のセルフ・タイトル盤でデビューした。 本盤『レプティレクトリック(Reptilectric)』は、前作(2006年)の成功に続いて制作された4枚目のスタジオ盤で、2008年にリリースされた。ソエーと言えば、2019年の『アストラン』でのグラミー受賞が知られるが、この作品と前作はラテン・グラミーにノミネートされていたし、11年のライヴ作もラテン・グラミーの受賞作となっていた。何が言いたいのかというと、この頃には既にソエーのサウンドは完成されたものになっていたということである。 実際、筆者的にも、これまでのところ上記の『アストラン』と並んで彼らの最高作と思っているのが本盤である。分野でタグづけするなら“ラテン・オルタナ・ロック”ということになるのだけれど、彼らにしかできない幻想的というか宇宙的なサウンド、ラテン系ロック独特のリズム感が演奏面の特徴になっている。そして、こうしたサウンド面の特徴だけが売りなのでなく、何よりも楽曲のよさが際立ち、この作品を特別なものにしている。 何としても聴き逃がせないナンバーとしては、まずは表題曲の1.「レプティレクトリック」。レオン・ラレーギ(ヴォーカル)がマヤの預言者の本に着想を得て思いついた造語で、古代神ケツァルコアトルを連想させる詞になっている。5.「ポリ」は初恋をテーマにした楽曲であるが、センチメンタルな感じは全然せず、浮遊感のあるサウンド、シンプルながら馴染みのいいメロディ、独白的な詞と三拍子揃った好ナンバー。なお、これら1.と5.はシングルとしてリリースされた。 長くなってきたけれど、他にどうしても外しがたい曲としては、3.「ソンブラス」、4.「ノ・アイ・ドロール」、政治批判的な7.「ネアンデルタール」、10.「ウルティモス・ディアス」。全編通じて好曲が並び、挙げだすときりがない。ソエーのアルバムとしてだけでなく、ラテン系ロックの作品としても名盤リストに入るべき作品だと言えるように思う。[収録曲]1. Reptilectric2. Nada3. Sombras4. No hay dolor5. Poli6. Resiste7. Neandertal8. Fantasma9. Luna10. Últimos días11. Babilonia2008年リリース。 下記のランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、バナーをクリックして応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2025年09月04日
コメント(0)
-

カルラ・モリソン 『アモール・スプレーモ(Amor supremo)』
成功を収めたセカンド作 2009年にシーンに登場したカルラ・モリソン(Carla Morrison, 英語読み風にカーラ・モリソンと書かれたりもするが、スペイン語の名前なのでカルラという読みが正しい)のセカンド・アルバムが、この『アモール・スプレーモ(Amor supremo)』という盤である。アルバムの表題は“至上の愛”という意味で、2015年にリリースされた。本盤には、60分を超える全13曲が収録されている。前作同様、アルバムはラテン・グラミーにノミネートされ、シングル曲がオルタナ部門で受賞を果たした。 ファースト作のところ(参考過去記事)にも書いたのだけれども、彼女の作品には、現代社会に生きる孤独感みたいなものが滲み出ている。そういう意味では、本セカンド作も同じ流れの中に位置づけられるものと言えるだろう。ファースト作と比べて変化しているのは、音作りの進歩で、作り込みの度合いが格段にアップしているように思う。 アルバムの収録順に注目したい楽曲を見ていくと、まずは、1.「ウン・ベソ」。彼女の独自の楽曲の世界が存分に発揮された1曲だと思う。3.「ベス・プリメーラ」は、ラテン・グラミーのオルタナ部門で受賞曲となったナンバー。4.「アスカル・モレーナ」は“ブラウン・シュガー”を意味する表題とは裏腹に、甘くないシリアスさが魅力。7.「デブエルベテ」は、私的にはイチオシの楽曲の一つで、いい意味でのこの“不安感”がカルラ・モリソンの魅力だと感じる。13.「トド・パサ」は、セカンド・アルバムにして堂々とした完成度が感じられる好曲だと思う。[収録曲]1. Un beso2. Flor que nunca fui 3. Vez primera4. Azúcar morena5. No vuelvo jamás6. Cercanía7. Devuélvete8. Mi secreto9. Tierra ajena10. Yo vivo para ti11. Tú atacas12. Mil años13. Todo pasa2015年リリース。 下記のブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、バナーをクリックお願いします! ↓ ↓
2025年08月31日
コメント(0)
-

ロス・ラヴキルズ 『ロス・ラヴキルズ(Los Lovekills)』
骨太のメキシコ大衆ロック・バンドによるセルフ・タイトル作 ロス・ラヴキルズ(Los Lovekills)は、2010年に結成されたメキシコのロック・バンド。詳しい情報に関しては、よくわからないことだらけなのだけれど、結成まもなく出された最初の盤が、セルフ・タイトルのこの『ロス・ラヴキルズ(Los Lovekills)』ということのようだ。バンド名の“Lovekills (Love Kills)”は、かのフレディ・マーキュリーの楽曲を思い起こさせるが、それと関係があるのかどうかもよくわからない。 メンバーは、ロべ・マルティネス(Robe Martínez,ギター&ヴォーカル)、マルセロ・メンドーサ(Marcelo Mendoza, ベース&ヴォーカル)、ラウリオ・ルイス(Raulio Ruíz, ギター)、ロッド・ビエイラ(Rod Vieyra, ドラム)という4人構成で、メキシコシティを起点に活動しているという。とはいえ、このデビュー時点では、マルティネスとメンドーサはいたものの、残る2人の名はなく、キケサン(QuiqueSan, ギター&コーラス)なるメンバーがクレジットされている。また、バンドが当初結成されたのはメキシコ北部のコアウィラ州トレオンとのことで、本盤も同地でレコーディングされている。 本盤は、デビュー作といっても、7曲入りのミニアルバムと呼べるヴォリュームのもの。プロデュースを担当したのは、マウリシオ・テラシーナ(Maurizio Terracina)というメキシコ/イタリア国籍の音楽プロデューサーである。メキシコ・ロック界では知られた人物で、独立系のバンドなどのプロデュースを積極的に行ってきたプロデューサーである。実際、1曲1曲の仕上がりの精度の高さは、このプロデューサーの力量に負う部分が大きいのではないかという気がする。 注目曲としては、1.「トゥ・シレンシオ(あなたの沈黙)」の端正で重いサウンドがいい。2.「ブスカンド・カリフォルニア(カリフォルニアを探して)」は、国境を越えてカリフォルニアでの新たな人生を目指すというベタなテーマだが、サウンド面ではベタにはならず、しっかりとした演奏に仕上がっているところに好感が持てる。4.「エウフォリカ」は1.と並んで骨太のサウンドでしっかりと聴かせる好曲。さらにハードな楽曲としては、やや実験的な6.「アウトデストルクティーバ(自爆的)」がいい。硬派な演奏とガラスの向こう側から歌っているかのようなヴォーカルの組み合わせというのは、なかなか決まっていると思うのだけれど。[収録曲]1. Tu silencio2. Buscando California3. No te olvido4. Euphorica5. Inocente6. Autodestructiva7. Zombie2010年リリース。 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月28日
コメント(0)
-

L.A.ガンズ 『“砲”(L.A. Guns)』
ロサンゼルスの熱きHR/HMシーンの立役者 ガンズ・アンド・ローゼズが2つのバンドの元メンバーの融合によって成立したということはよく知られている。その2つのバンドというのは、L.A.ガンズとハリウッド・ローズだった。ハリウッド・ローズの方は1989~90年に再結成されたものの、作品リリースはなかった。他方、L.A.ガンズの方は、早々にガンズ・アンド・ローゼズを離脱したトレイシー・ローズが中心となって再興され、アルバムを発表していくことになった。 トレイシー・ローズを中心に実力者揃いのメンバーはデビュー前から注目され、1988年に発表されたのが、ファースト作となるセルフ・タイトル盤『L.A.ガンズ(L.A. Guns)』(邦盤では『“砲”』)であった。“L.A.メタル”という括り方がなされることもあるが、文字通り“L.A.(ロサンゼルス)”の名を冠する彼らは、1980年代後半、西海岸発のHR/HMの立役者の一人といえそうな勢いを持っていた。 1.「ノー・マーシー」は、スピード感のある重くかつ軽快な演奏が魅力。2.「セックス・アクション」は、リリースされて聴いた当時から特に印象に強く残っているナンバーで、この不良っぽさも彼らの大事な持ち味の一部分である(ヒットはしなかったものの、その当時にはシングルとしてもカットされていた模様)。4.「エレクトリック・ジプシー」(こちらもシングル化された)は、たたみかけるような演奏が筆者的にはお気に入り。 7.「クライ・ノー・モア」は、小休止的なギターのアンサンブル風の小品で、じっくり聴かせる名曲の8.「ワン・ウェイ・チケット」のイントロ的な役割も果たしている。アルバム終盤をきれいにまとめようという感じではなく、勢いづいたままの10.「シュート・フォー・スリルズ」、11.「ダウン・イン・ザ・シティ」で終えているのも、若々しいと言えばそれまでかもしれないが、筆者としては好感が持てる。全体として、若さがほとばしり(そう考えると、L.A.の表記のピリオドが“ガイコツ”なのも、今となっては微笑ましい)、西海岸のメタルシーンを反映したお手本あるいはモデル的な作品。そんな風な感想を個人的には持っているアルバムだったりする。[収録曲]1. No Mercy2. Sex Action3. One More Reason4. Electric Gypsy5. Nothing to Lose6. Bitch Is Back7. Cry No More8. One Way Ticket9. Hollywood Tease10. Shoot for Thrills11. Down in the City12. Winters Fool(日本盤リイシュー時のボーナス・トラック)1988年リリース。 “砲" [ L.A.ガンズ ] 【輸入盤CD】【新品】L.A. Guns / L.A. Guns 【K2017/11/3発売】(LAガンズ) 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年08月24日
コメント(0)
-

マロ 『マロ(Malo)』
ホルヘ・サンタナのバンドによるラテン・ロックの好盤 マロ(Malo)は、カルロス・サンタナの実弟であるホルヘ・サンタナ(Jorge Santana,2020年に68歳で没)を中心とするバンドであった。前身のバンドであるマリブスのメンバーと別のバンドのメンバーを混合する形で、1970年代初頭にマロは誕生した。ホルヘ・サンタナ(ギター)のほか、アルセリオ・ガルシア(ヴォーカル、パーカッション)、パブロ・テジェス(ベース)、アベル・サラテ(ギター)ら計8人から成り、通常のロック・バンドの編成に含まれる楽器以外に、管楽器(フルート、トランペットなど)や打楽器(コンガ、ティンバルなど)がフィーチャーされているのが特徴である。1972年、このバンドの最初のアルバムとして発表されたセルフ・タイトル作が、本盤『マロ(Malo)』であった。ジャケットのデザインには、メキシコ人画家ヘスス・エルゲーラによる、アステカの擬人化された神話の作品が使われている。 メキシコ生まれのホルヘは、サンフランシスコのラテン系の多い地区(ミッション地区)で育ったという。同じく中心人物の一人アルセリオはプエルトリコ系、パブロはニカラグア生まれでティーンエージャーの時の移住者であった。まさしくそうした西海岸のラテンのストリートの雰囲気に、実兄のカルロス率いるサンタナが切り拓きつつあったジャズやラテンを含みインプロヴィゼーショナルな新たなロックのスタイルがうまく融合した成功例だったと言えるのではないだろうか。どの楽曲も短くキャッチーにというよりは、個性が強く長い尺(収録曲はいずれも6~7分を超える)で、しっかりと聴かせるナンバーが並ぶ。 本盤の収録曲のうち、最も知られているのは、5.「スアベシート」であろう。哀愁漂うメロディに軽いラテンのリズム、そして英語の詞を聴かせるというスタイルがチカーノやラテン系の人々に受け入れられたのだろう。これと同じく、ラテンの若者たちに人気を博した曲として、4.「いとしのネナ」も収められている。詞が英語とスペイン語の両方であること、音楽的には、サルサのようでもあり、ソウルのようでもあり、でもやっぱりロックであるというのが印象的なナンバーとなっている。 ほかに、個人的好みに基づいた本盤の聴きどころとしては、まず、1.「パナ」が挙げられる。ラテンの雰囲気が緊張感ある演奏とともに展開されるというのがいい。2.「さよならを言うだけ(ジャスト・セイ・グッドバイ)」は、シリアスなギター演奏が聴きどころ。6.「平和(ピース)」は、プログレッシヴな雰囲気の楽曲で、ヴォーカル、トランペット、ギターそれぞれの鬼気迫る演奏が9分を超える長尺の中でじっくりと堪能できる。[収録曲]1. Pana2. Just Say Goodbye3. Café4. Nena5. Suavecito6. Peace1972年リリース。 【中古】 マロ MALO/マロ 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月20日
コメント(0)
-
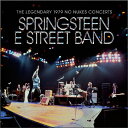
ブルース・スプリングスティーン&E・ストリート・バンド 『ノー・ニュークス・コンサート1979(The Legendary 1979 No Nukes Concerts)』(2/2)
当時の勢いと熱気が満載のライヴ盤(後編) (前編からの続き) アルバム収録曲をざっと見ていきたい。1枚目の冒頭3曲は、『闇に吠える街』を代表する楽曲が並ぶ。1.「暗闇へ突走れ」はライヴで見せ場へとなっていったレパートリーで、2.「バッドランズ」と3.「プロミスト・ランド」はそれぞれ元アルバムのA面・B面のオープニング曲である。続く2曲は、リリース直前の『ザ・リバー』からのナンバーで、表題曲4.「ザ・リバー」でじっくり聴かせ、5.「愛しのシェリー」で盛り上げる。そして、1枚目の終盤は、サード作『明日なき暴走』所収の6.「涙のサンダーロード」、ファースト作収録の7.「ジャングルランド」という、じっくり聴かせる代表的楽曲が連続する。 2枚目に移ると、最初の2曲はこの時点のレパートリーの中で特に盛り上がるナンバーが並んでいる。セカンド作収録の1.「ロザリータ」は、12分という長さを感じさせず、むしろメンバー紹介なども含めてこれだけ盛り上げて楽しませるにはこの時間が不可欠といった演奏を披露している。 2.「明日なき暴走(ボーン・トゥ・ラン)」は、若いころの彼の代名詞的ナンバーで、上記サード作のタイトル・トラック。3.「ステイ」は、モーリス・ウィリアムスとゾディアックスの1960年の全米No.1ヒット曲。続く4.「デトロイト・メドレー」と5.「クォーター・トゥ・スリー」は、ライヴでのお得意のレパートリーである。前者は「デヴィル・ウィズ・ザ・ブルー・ドレス・オン」、「グッド・ゴーリー・ミス・モーリー」、「シー・シー・ライダー」、「ジェニー・テイク・ア・ライド」という、1960年代をスプリングスティーンのバンドらしくカバーしたロック・メドレー。後者は、ゲイリー・US・ボンズの1961年の全米No.1ヒット曲のカバーである。アルバムを締めくくる6.「レイヴ・オン」は1958年のバディ・ホリーのヒットでも知られるナンバー。このように、2枚組の本作の終盤にかけての演奏は、ライヴでしか味わえないスプリングスティーンのパフォーマンスを楽しむことができる。[収録曲](Disc 1)1. Prove It All Night 2. Badlands 3. The Promised Land4. The River5. Sherry Darling6. Thunder Road 7. Jungleland(Disc 2)1. Rosalita (Come Out Tonight) 2. Born to Run 3. Stay4. Detroit Medley: Devil with the Blue Dress On~Good Golly Miss Molly~C.C. Rider~Jenny Take a Ride 5. Quarter to Three6. Rave On1979年9月21日(I: 6-7, II: 1-2, 4, 6)、同22日(1.-5, II: 3, 5)録音。2021年リリース。 【送料無料】[枚数限定][限定盤]ノー・ニュークス・コンサート 1979(完全生産限定盤/DVD付)/ブルース・スプリングスティーン&ザ・Eストリート・バンド[CD+DVD]【返品種別A】 【送料無料】[枚数限定][限定盤]THE LEGENDARY 1979 NO NUKES CONCERTS (2CD+DVD) 【輸入盤】▼/ブルース・スプリングスティーン&Eストリート・バンド[CD+DVD]【返品種別A】 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2025年08月17日
コメント(0)
-
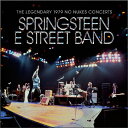
ブルース・スプリングスティーン&E・ストリート・バンド 『ノー・ニュークス・コンサート1979(The Legendary 1979 No Nukes Concerts)』(1/2)
当時の勢いと熱気が満載のライヴ盤(前編) アメリカン・ロック界の大御所、ブルース・スプリングスティーン(Bruce Springsteen)の若き日のライヴで、40年以上の歳月を経て2021年にリリースされたのが、本盤『ノー・ニュークス・コンサート1979(The Legendary 1979 No Nukes Concerts)』である。 21世紀に入った頃からだろうか、巷では、いわゆる“蔵出し”ライヴ系のリリースが溢れるようになった。そうした古い音源のリリースには、正直なところ、玉石混交という感が否めない。けれども、いざリリースされて聴いてみた時、何十年か前のライヴでこれほどに感動したのは、どちらかと言うと珍しい例だったというふうに記憶している。 収録されているのは、2枚組で全13トラック。音源には、ボブ・クリアマウンテンによる新たなリミックスが施されている。このライヴの前年(1978年)にリリースされた『闇に吠える街』と1975年の出世作『明日なき暴走』、そしてライヴのレパートリー曲が中心となっている。その一方で、リリース目前の『ザ・リバー(ザ・リヴァー)』に収録されることになるナンバーからも2曲が披露されている。 E・ストリート・バンドの息の合った絶妙の演奏は、これ以前のライヴでもよく知られているし、スタジオ作ながら『ザ・リバー』にも顕著である。また、後にリリースされた大部なライヴ作『ザ・ライヴ』(1975~85年の音源)の時期を考えると、すでに完成された演奏力が存分に発揮されていることもうかがえる。その演奏に加えて、ゲスト陣も目を引くもので、ジャクソン・ブラウンにトム・ペティ、さらにはローズマリー・バトラー(参考過去記事)なんかが参加している。 そのようなわけで、ライヴ・パフォーマンスの質が高かった(けれども1984年以降の『ボーン・イン・ザ・U.S.A.』の妙な熱狂はまだ訪れていない)時期の、優れた演奏が堪能できる盤であると、全体としては言えるだろう。 長くなってきたので、いったんここで稿を改めて、後編に続けたい(曲目等の情報は後編を参照)。 【送料無料】[枚数限定][限定盤]ノー・ニュークス・コンサート 1979(完全生産限定盤/DVD付)/ブルース・スプリングスティーン&ザ・Eストリート・バンド[CD+DVD]【返品種別A】 『ノー・ニュークス・コンサート 1979 (2CD+Blu-ray)【完全生産限定盤】 [ ブルース・スプリングスティーン&ザ・Eストリート・バンド ] 下記ランキングに参加しています。 お時間のある方、応援くださる方は、“ぽちっと”よろしくお願いいたします! ↓ ↓
2025年08月16日
コメント(0)
-

バッド・カンパニー 『ストレート・シューター(Straight Shooter)』
デビュー盤からの勢いを維持したセカンド・アルバム バッド・カンパニー(Bad Company)は、1970年代前半、フリー(参考過去記事(1) ・(2) ・(3) )での活躍を経たポール・ロジャース(ヴォーカル)、サイモン・カーク(ドラムス)らが結成したバンド。他のメンバーは、元モット・ザ・フープルミック・ラルフス(ギター)、元キング・クリムゾンボズ・バレル(ベース)という面々だった。 1974年発表に発表されたこのバンドのデビュー盤は、見事なセールスを記録し、全米チャート1位、英チャート3位を記録した。そして、続く翌年の本盤『ストレート・シューター(Straight Shooter)』もそれに劣らぬほどの成功作となり、英米ともに3位のヒット作となった。 冒頭の1.「グッド・ラヴィン」と2.「フィール・ライク・メイキン・ラヴ」はともにシングルとしてもリリースされたナンバー。前者はこのバンドらしい端正なロック・ナンバー。後者はなかなかの好曲で、全米のシングルチャートで10位となった。 他に筆者が気に入っているナンバーを少し挙げておくと、4.「シューティング・スター」は適度な肩の力の抜け具合がいい。無論、ハードな楽曲がよくないという意味ではなく、本盤の収録曲中でそうした方向性で頭一つ抜けているのが5.「ディール・ウィズ・ザ・プリーチャー」だと思う。全体として言えるのは、ハードな楽曲と少し控えめな楽曲がうまく配されている点と、ポール・ロジャースによる楽曲のよさが目立つというのが、本盤の特徴ということになるのかもしれないと感じる。[収録曲]1. Good Lovin' Gone Bad2. Feel Like Makin' Love3. Weep No More4. Shooting Star5. Deal with the Preacher6. Wild Fire Woman7. Anna8. Call on Me1975年リリース。 【中古】英LP Bad Company Straight Shooter ILPS9304 ISLAND /00260 次のブログランキングのサイトに参加しています。 時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年08月14日
コメント(0)
-

INDEX更新
INDEXページ(ジャンル別、アーティストのアルファベット順)を更新しました。ここ最近の記事を追加しています。INDEXページへは、下のリンク、もしくは本ブログのトップページ(フリーページ欄)からお入りください。 アーティスト別INDEX~ジャズ編(A-G)へ → つづき(H-M)・つづき(N-Z) アーティスト別INDEX~ロック・ポップス編(A)へ → つづき(B)・つづき(C-D)・つづき(E-I)・つづき(J-K)・つづき(L-N)・つづき(O-Q)・つづき(R-S)・つづき(T-Z) アーティスト別INDEX~ラテン系ロック・ポップス編(A-I)へ → つづき(J-N)・つづき(O-Z) アーティスト別INDEX~邦ロック・ポップス編へ 下記ランキングに参加しています。応援くださる方は、各バナー(1つでも ありがたいです)をクリックお願いします! ↓ ↓
2025年08月11日
コメント(0)
-

ロッド・テイラー 『ロッド・テイラー(Rod Taylor)』
詩人/シンガーソングライターによる幻の1枚 ロッド・テイラー(Rod Taylor)は、1947年ノース・キャロライナ州生まれのミュージシャン。1970年代に入ると西海岸に移り、ミュージシャンとして活動するだけでなく、詩集を出版したりもしている。そんな彼が唯一残した作品が、1973年発表のセルフ・タイトル盤『ロッド・テイラー(Rod Taylor)』である。 1971年に設立されたアサイラム・レコードにとって、トム・ウエイツの次に契約した13組目のアーティストが、このロッド・テイラーだったという。日本では“第2のレオン・ラッセル”の触れ込みで発売されたらしいが、日本国内どころかアメリカでもさっぱり売れなかったようである。 確かに、売れなくても仕方なかった地味さがある。失礼ながら、名前からして地味だし、アルバムもやや陰気なセルフ・ポートレート写真で、淡々と歌を伝えるシンガーソングライター然とした雰囲気が醸し出されている(とはいえ、後述のメンバーを含む演奏自体は、必ずしも地味というわけではない)。全曲が次作で、プロデュースはチャック・プロトキン(ボブ・ディランやブルース・スプリングスティーンの作品のプロデュースでも知られる)が丁寧に仕事をしている。演奏面では、ライ・クーダー(ギター、マンドリン)、ジェシー・エド・デイヴィス(ギター)、ジョニ・ミッチェル(バッキング・ヴォーカル)など、なかなか豪華なミュージシャンたちがサポートしている。 いくつかの曲をあげながら、アルバムを見渡しておきたい。オープニングの1.「アイ・オウト・トゥ・ノウ」は、ひたむきに詞を紡ぐシンガーソングライター的な楽曲。2.「クロスローズ・オブ・ザ・ワールド」は、南部風の泥臭さを伴うナンバーで、こういった曲は案外、筆者の好みだったりする。5.「メイキング・ア・ウェイ」は、どこかレオン・ラッセル風のテイストで、こういう楽曲でうまく火がついていたならば、ひょっとして売れたのかもと思わないでもない。ピアノをバックにした7.「危険な生活のブルース」も、同じくレオン・ラッセル風と言えるかもしれない。12.「ザ・ラスト・ソング」は、デビュー盤の締めくくりにこのタイトル(“最後の歌”)はどうかという気がしないでもないが、楽曲としてはなかなかの好曲。 1970年代初頭、何人ものシンガーソングライターが現れては消えていった。テイラー自身も述べているように、その中では最も成功した口だったのだろう。その後、少しの活動歴があったようだが、テイラーの名は音楽史の表舞台には残らなかった。とはいえ、アルバムという形で残された本盤は密かな1枚として聴き継がれていくことだろう。[収録曲]1. I Ought to Know2. Crossroads of the World3. Railroad Blood4. Double Life5. Making A Way6. Sweet Inspiration7. Livin' Dangerous Blues8. Something Old9. Man Who Made It Fall10. Lost Iron Man11. For Me12. The Last Song1973年リリース。 【中古】CD ロッド・テイラー ロッド・テイラー AMCY2901 ASYLUM /00110 ブログランキングに参加しています。 応援くださる方は、ぜひクリックをお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月10日
コメント(0)
-

ジョー・ペリー・プロジェクト 『熱く語れ!(Let the Music Do the Talking)』
エアロスミスのメンバーによるプロジェクト盤 ジョー・ペリー(Joe Perry)は、1950年米国出身のギタリスト。スティーヴン・タイラーの欠かせないパートナー(これら2人のコンビは“トキシック・ツインズ”と呼ばれる)で、ロック・バンド、エアロスミスを牽引してきた。そんなペリーがソロ・プロジェクトを動かしたのは、1980~83年のことだった。タイラーとの確執からエアロスミスを脱退し(後に和解してバンドに復帰)、計3枚のアルバムをジョー・ペリー・プロジェクト(Joe Perry Project)の名義で発表した。 本盤『熱く語れ!(Let the Music Do the Talking)』はその第1弾で、1980年にリリースされた。上記の3枚のアルバムの内では最も売り上げを伸ばした(全米47位)アルバムである。大部分の曲(共作も含めると全曲)がジョー・ペリーのペンによるもので、彼以外のメンバーは、ヴォーカルにラルフ・モーマン(ただし、ペリー自身がリード・ヴォーカルという曲も複数ある)、ベースにデヴィッド・ハル、ドラムにロニー・スチュワートといった布陣だった。 1.「熱く語れ!」はアルバムの表題曲。この曲名およびアルバム名の原題を直訳すると、“音楽に語らせよ”。結局のところ、音楽に語らせるのは演奏者なのだから、演奏者が“熱く語って”も一緒なのかもしれないが、実際にこの曲を聴いてみると、確かに“音楽が語りだしている”という風に思える(ちなみに、この1.はエアロスミスのアルバム『ダン・ウィズ・ミラーズ』でも演奏されている)。1.と並んで見事な演奏で音楽に語らせていると思えるのは、3.「ディスカウント・ドッグズ」。とにかくジョー・ペリーのギターがカッコよく炸裂する。 アルバムにはジョー・ペリーがヴォーカルを担当する楽曲も収められている。筆者の好みに照らしてのその中でのベストは、10弦ギターを使用しての7.「ザ・ミスト・イズ・ライジング」、次いで4.「シューティング・スター」といったところか。また、インストルメンタル・ナンバーも1曲収められている。5.「ブレイク・ソング」がそのナンバーだが、短い楽曲ながら、ジョー・ペリーがこれでもかとギターを聴かせるという演奏に仕上がっている。 アルバム終盤の8.「レディ・オン・ザ・ファイアリング・ライン」、9.「ライフ・アット・ア・グランス」まで演奏の勢いは衰えず、特に9.のリズムに乗ったスピード感は、聴いた後にスッキリした感じになる。全米チャートで47位どまりだったとのことだが、記憶の狭間に埋もれさせてしまうのはもったいないと好作だと個人的には思う。[収録曲]1. Let the Music Do the Talking2. Conflict of Interest3. Discount Dogs4. Shooting Star5. Break Song6. Rockin' Train7. The Mist Is Rising8. Ready on the Firing Line9. Life at a Glance1980年リリース。 【中古】 熱く語れ!/ジョー・ペリー・プロジェクト 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月07日
コメント(0)
-

ジャッキー・バイアード 『ハイ・フライ(Hi-Fly)』
ピアノ演奏の多彩ぶりが発揮された盤 ジャズ・ピアノ奏者のジャッキー・バイアード(ジャキ・バイアード,Jaki Byard)の3枚目のリーダー作に当たる『ハイ・フライ(Hi-Fly)』は、彼が残した吹き込みの中でもベストのものと言われたりする。このバイアードという人は、“多彩多芸なピアニスト”とも評される。さまざまなスタイルのジャズ・ピアノを取り込んだ演奏がこの人の特徴であり、しかもトランペットやサックスも演奏できるというマルチな演奏者でもあった。 本盤は、ベース(ロン・カーター)とドラムス(ピート・ラロカ)との3ピースというシンプルな構成ながら、確かにバイアードのピアノの多彩さが際立っている。そうしたピアノ演奏を可能にしているのは、残る2人の安定感というのはもちろんなのだけれど、個人的にはロン・カーターのベースがとりわけいい味を出していると感じる。以下、収録曲のうちで、特に注目したい演奏をいくつか取り上げてみたい。 まず、表題曲の1.「ハイ・フライ」はランディ・ウェストンのペンによるナンバー。ピアニストであるウェストンらしい楽曲をバイヤードらしく解釈して弾きこなしていて、派手さはないが、好演奏と言えるように思う。バイアードの自作曲は3曲(2.,4.,5.)が収められているが、なかでも意欲的で実験的なのは5.「ヒア・トゥ・ヒアー」。どういう展開の演奏になっていくのか、聴いていて飽きない。さらに注目したいのは、7.「ラウンド・ミッドナイト」。演奏そのものの幅と奥行きが感じられると言えばよいのだろうか、三次元的な深さが感じられる演奏になっている。このディメンショナルな広がりとでも言えそうなものが筆者は気に入っていて、この7.から次の8.「ブルース・イン・ザ・クローセット」への流れは本盤の聴きどころとも言えるように思う。[収録曲]1. Hi-Fly2. Tillie Butterball3. Excerpts from "Yamecraw4. There Are Many Worlds5. Here to Hear6. Lullaby of Birdland7. 'Round Midnight8. Blues in the Closet[パーソネル、録音]Jaki Byard (p), Ron Carter (b), Pete La Roca (ds)1962年1月30日録音。 【中古】 ハイ・フライ/ジャッキー・バイアード(p),ロン・カーター(b),ピート・ラロカ(ds) 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年08月04日
コメント(0)
-

エロール・ガーナー 『グレイテスト・ガーナー(The Greatest Garner)』
ガーナー初期の、控えめで味わい深いトリオ盤 左利きで、楽譜を読めず、並外れた音に対する感性を持つというエロール・ガーナー(Erroll Garner)。彼のピアノは、確かにくせがあるけれども、多くの人を魅了してきた。本盤『グレイテスト・ガーナー(The Greatest Garner)』は、1949から50年にかけてのトリオ演奏が収められたもので、時期としては、有名曲「ミスティ」(関連過去記事)や代表盤『コンサート・バイ・ザ・シー』よりも前の、彼の最初期に当たるものである。 収められた演奏は、バラード系のおとなしめの楽曲が中心。エロール・ガーナーのピアノの味わいを落ち着いてじっくり楽しむという趣の盤と言える。2つのセッションの音源となっていて、トリオの面々は過半の演奏では、ベースがレナード・ガスキン、ドラムスがチャーリー・スミス。他方、いくつかの曲では、ベースがジョン・シモンズ、ドラムスがハロルド・ウィングとなっている(詳細は下記のデータを参照)。 個人的に気になる演奏をいくつか見ておきたい。1.「今宵の君は(ザ・ウェイ・ユー・ルック・トゥナイト)」は、テンポよくガーナー節が展開される。2.「ターコイズ」は、キラキラとした幻想的な、ある種ガーナーらしいというのとは異なる雰囲気を楽しめる。これと似た方向性を持つ演奏としては、7.「スカイラーク」や9.「フラミンゴ」、さらには10.「夢(レヴェリー)」が挙げられる。他方、彼らしいピアノのリズム感を楽しめる楽曲も複数あるが、おすすめは6.「アイ・メイ・ビー・ロング」や12.「捧ぐるは愛のみ(アイ・キャント・ドゥ・エニシング・バット・ラヴ)」。“ビハインド・ザ・ビート”と表現される彼の左手の動作とその効果は、ツボにはまると中毒性がある。なお、現行のCD盤では、後から吹き込まれた方の1950年5月のセッションの未収録曲がボーナス曲として追加されており、それら4曲の演奏も本来の12曲に劣らない質の高い演奏であることがうかがえる。[収録曲]1. The Way You Look Tonight2. Turquoise3. Pavanne4. Impressions5. Confessin'6. I May Be Wrong7. Skylary8. Summertime9. Flamingo10. Reverie11. Blue and Sentimental12. I Can't Do Anything But Love[パーソネル、録音]1~4, 7, 9~12:Erroll Garner (p), Leonard Gaskin (b), Charlie Smith (ds)1949年7月20日録音。5~6, 8:Erroll Garner (p), John Simmons (b), Harold Wing (ds)1950年5月12日録音。 【中古】CD エロール・ガーナー(p) グレイテスト・ガーナー WPCR27374 ATLANTIC 未開封 /00110 以下のブログランキングに参加しています。お時間の許す方は、 クリックで応援よろしくお願いします。 ↓ ↓ ↓
2025年08月01日
コメント(0)
-

グレイト・スペックルド・バード 『グレイト・スペックルド・バード(Great Speckled Bird)』
カントリー・ロックの好盤 グレイト・スペックルド・バード(Great Speckled Bird)は1969年に結成されたカナダのカントリー・ロック・バンド。フォークないしはカントリーのデュオだったイアン(ヴォーカル、ギター)とシルヴィア(ヴォーカル、ピアノ)のタイソン夫妻(Ian & Sylvia Tyson)を中心に、エイモス・ギャレット(ギター、ヴォーカル)らが参加したバンド(メンバーは随時変化したが、本盤録音時にはエイモス・ギャレットに加えて、スティール・ギターにバディ・ケイジ、ドラムにN.D.スマート、ベースにケン・カルマスキーという布陣)だった。なお、バンド名は、カントリー歌手のロイ・エイカフの楽曲名に因む。このバンド単独の名義でリリースされた唯一の盤がこのセルフタイトル作の『グレイト・スペックルド・バード(Great Speckled Bird)』であった。権利の関係で入手困難が続いたため、“カントリー・ロックの幻の名盤”と呼ばれていた盤である。プロデュースはトッド・ラングレンで、彼にとって初めて他のアーティストのアルバム・プロデュースを担当した作品となった。 そのようなわけで、カントリー・ロックの歴史を語るうえで必ずしも王道とは言えない作品だが、カントリー・ロック作品としてかなりの好盤であることは間違いない。ザ・バーズやバッファロー・スプリングフィールドといったバンドがムーヴメントを起こしたり引っ張って行ったりしたのに対し、このグレイト・スペックルド・バードの活動は儚かった。そんな彼らの演奏は、シリアスさの一方で、どこかしらのどかさや楽しさが感じられるように思う。それは、おそらくは、このバンドがカントリー音楽の先にこの音楽をとらえていて、新たなことをやるという気負いよりも、どちらかというと各々のメンバーの特徴を出しながら楽しんで演奏するという雰囲気が強かったせいではないかと想像してみたりする。 注目曲をいくつか見ておきたい。まず、1.「ラヴ・ホワット・ユア・ドゥーイン・チャイルド」は、イアンのヴォーカルとエイモス・ギャレットのギターが中心となって醸し出すスリリングな空気感がたまらない。3.「トラッカーズ・カフェ」はシルヴィアのヴォーカルが前面に出たいかにもカントリー調のナンバーで、リイシューのCDには、ボーナストラックとして、ライヴ・ヴァージョン(13.)が収められている。 アップテンポでノリのよい6.「ブラッドショット・ビホルダー」は、イアンのナンバーで、テンポよいドラムと小気味よいギターが印象的。10.「リオ・グランデ」は、イアンとエイモス・ギャレットの共作で、楽曲そのもののよさが光る。アルバムを締めくくる12.「ウィ・セイル」はカントリー・バラードとでも呼べばいいだろうか。スローで合唱風のナンバーで、目を閉じるとメンバーたちの姿が浮かんでくるような1曲である。[収録曲]1. Love What You're Doing Child2. Calgary3. Trucker's Cafe4. Long Long Time to Get Old5. Flies in the Bottle6. Bloodshot Beholder7. Crazy Arms8. This Dream9. Smiling Wine10. Rio Grande11. Disappearing Woman12. We Sail13. New Trucker's Cafe -live-(CD追加トラック)1969年リリース。 【中古】CD グレイト・スペックルド・バード グレイト・スペックルド・バード CDSOL7194 /00110 【中古】 グレイト・スペックルド・バード/グレイト・スペックルド・バード 下記のランキングサイトに参加しています。お時間の許す方は、 バナーをクリックして応援いただけると嬉しいです! ↓ ↓
2025年07月29日
コメント(0)
-

ブラック・サバス 「パラノイド(Paranoid)」ほか
オジー・オズボーンよ、永遠なれ… つい1週間ほど前に書いた記事(過去記事はこちら)に続き、またしても訃報です。ブラック・サバスのヴォーカリストで、自身のバンドでも活躍したオジー・オズボーン(Ozzy Osbourne)が2025年7月22日に亡くなりました。パーキンソン病を公表していたものの、今月初旬に引退ライヴのステージに姿を見せたばかりだったのですが、それからわずか17日後のことで、享年76歳でした。 オジー・オズボーンといえば、まずはブラック・サバス(Black Sabbath)での活動が思い起こされます。1970年にデビューし、同年のセカンド作では大きなシングル・ヒットも残しました。まずは、彼らの代表曲の一つで、同セカンド作のタイトル・チューンでもある「パラノイド」をお聴きください。 続いては、ブラック・サバスを脱退後、ソロで自身のバンドを率いての活動期の楽曲から、個人的に印象に残っているものを一つ。1983年発表のアルバム『月に吠える』の表題曲で、同盤からの第1弾シングルとなった曲で、「月に吠える(Bark at the Moon)」です。 もう1つ、ブラック・サバスの上記のアルバム所収のナンバーで、往年のプロレス・ファンにも懐かしいナンバーです。アニマルとホークからなるザ・ロード・ウォリアーズの入場曲としても使用された「アイアン・マン(Iron Man)」です。同じタイトルということもあり、コミック作品の『アイアン・マン』の映画でも使用されました。ライヴのステージでのオジー・オズボーンの雄姿をご覧ください。 アルコール・薬物の問題や、コウモリ食いちぎり事件など世間を騒がせたり破天荒な行動が注目されたりするミュージシャンでもありましたが、いまは安らかに眠らんことをお祈りします。R.I.P.追記: 上でプロレスの話題にも触れましたが、続いてハルク・ホーガンが鬼籍に入りました。同様にご冥福を心からお祈りします。[収録アルバム]Black Sabbath / Paranoid(1970年)Ozzy Osbourne / Bark at the Moon(1983年) 【輸入盤CD】【新品】Black Sabbath / Paranoid【K2016/8/5発売】(ブラック・サバス) Ozzy Osbourne オジーオズボーン / Bark At The Moon: 月に吠える 【CD】 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年07月26日
コメント(0)
-

スティーヴィー・ニックス 『ロック・ア・リトル(Rock A Little)』
実力に裏打ちされたサード作 フリートウッド・マックへの加入によって、『ファンタスティック・マック』(1975年)以降のこのバンドの躍進を支えた重要人物が、スティーヴィー・ニックス(Stevie Nicks)だった。“歌姫”とか“妖精”とか呼ばれるものの、こうした形容は、バンドのお飾り的な“顔”という意味ではなく、ヴォーカリストとしての力量を称えるものと捉えたものと考えるべきであろう。 1985年発表の『ロック・ア・リトル(Rock A Little)』は、フリートウッド・マックが各メンバーのソロ活動を活発化させた時期の作品である。大きなヒットとなった『麗しのベラ・ドンナ』(1981年)から数えて、スティーヴィー・ニックスのソロ・アルバムとしては3作目に当たる。 ジミー・アイオヴィンら複数のプロデューサーを起用しているが、全体的に1980年代特有のきらびやかなサウンドが展開されている。聴きどころとしては、シングルとして全米4位を記録した7.「トーク・トゥ・ミー」。それから、同じくシングル・カットされて米国で16位となった1.「アイ・キャント・ウェイト」。いずれもリスナーのツボを押さえた楽曲で、スティーヴィー・ニックスのヴォーカルの魅力が全開のナンバーだと思う。 他に個人的にいいと思う曲をいくつか挙げておくと、アルバム表題になっている2.「ロック・ア・リトル」、オーストラリアのみでシングル発売された5.「インペリアル・ホテル」、8.「ザ・ナイトメアー」。あと、アルバムの最後を飾る11.「誰かあなたに(ハズ・エニワン・エヴァー・リトン・エニシング・フォー・ユー?)」。この曲は、シングル・カットされたものの、大きなヒットとはならなかったのだけれど、アルバムの中で聴くと存在感の大きいスロー・ナンバーだ実感する。[収録曲]1. I Can't Wait2. Rock a Little (Go Ahead Lily)3. Sister Honey4. I Sing for the Things5. Imperial Hotel6. Some Become Strangers7. Talk to Me8. The Nightmare9. If I Were You10. No Spoken Word11. Has Anyone Ever Written Anything for You?1985年リリース。 【中古】CD Stevie Nicks Rock A Little CP325098 EMI, Modern Records /00110 ロック・ア・リトル【CD、音楽 中古 CD】メール便可 ケース無:: レンタル落ち 【ご奉仕価格】 次のブログのランキングサイトに参加しています。 お時間の許す方は、クリックで応援をよろしくお願いします! ↓ ↓
2025年07月25日
コメント(0)
全3256件 (3256件中 1-50件目)
-
-

- クラシック、今日は何の日!?
- 鼻が詰まってるので花粉症に良いとさ…
- (2024-09-21 22:11:23)
-
-
-

- ♪♪K-POP K-POP K-POP♪♪
- 【輸入盤】ミニ・アルバム:ラッシュ…
- (2025-11-25 00:00:11)
-
-
-

- LIVEに行って来ました♪
- サーカスパフォーマーまおのライブ
- (2025-11-23 13:17:54)
-








